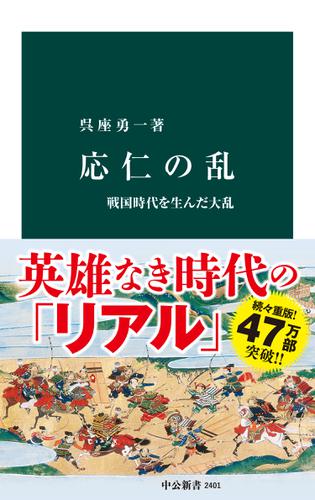
総合評価
(187件)| 30 | ||
| 67 | ||
| 51 | ||
| 15 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
評価については僕には合わなかったという意味においてなので、決して中身がないということではないことを最初に。 この本が売れている理由はなんだろうかと考えながら読んだんだけども、その理由に思い至ることはなかった。多くの人が歴史的なことを知った上でこれを読んでいるわけではないだろうけども、だとしたらなおのことわからんのよねぇ。歴史小説のように盛り上がりどころをつくっているわけではなく、淡々と語るのみ。応仁の乱の魑魅魍魎さがわかるかというと、ちょっと自信ない。ただ、こういった本を読み慣れていないので、自分の感度の問題かも知れない。 他の人の感想を読んで、どういうところがアンテナにかかったのか、ちょっと勉強してみようと思う。
0投稿日: 2017.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログヒットしたのが不思議なぐらい不親切な構成の本。戦闘があったときには、各軍の移動を説明した略図などを入れるのはもちろん、人物相関図や各章まとめのコラムような短文などがあってもいいのではないか?と読みながら何度も思った。また自著宣伝で説明をすませている箇所や、先人の研究成果を軽侮する発言の目立つ箇所も多く、それらは不快な印象を受けた。
0投稿日: 2017.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ経覚と尋尊、二人の興福寺関係者の日記を基盤に、 応仁の乱とは何か?を紐解いていく。 畠山氏の内部対立が発端とはいえ、 継承・領地・支配・・・争いの火種はあちこちにあり、 それは隣国・兄弟・親族での対立を招く。 すぐに終焉との見方は外れ、あっちをたてればこっちは不満、 ずるずると長引き、 11年、京都の地を混乱に巻き込んだ。 しかし、終焉後も大和の地に飛び火。 更に、全国のあちこちに・・・戦国時代へと歩んでゆく。 とにかく人物の多いこと! あちこちに付箋を貼って読んだので、時間がかかりました。
0投稿日: 2017.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「応仁の乱」あまりにも有名な乱だけれども何が原因で誰が勝者で何で終わったのか、よく判らない戦いを説明しようというアッパレな本。 精読しました!でもやっぱりよく判らない。 所謂「一言で言えば…。」が使えないほど複雑なのだ。此処から戦国時代が始まった…すら間違いだと言ってるし。 全然中身と関係ないが70頁に「金胎寺城」が出てくる。うちの近所なんです。標高296.4m。富田林市で一番高い山です。つい先週登った処だったんで嬉しくて。 皆んなで登りましょう!
0投稿日: 2017.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ解りにくい応仁の乱がわかりやすいと評判の1冊ですが、私には詳細すぎてわかりにくかった。。。もともとの日本史の知識が足りないからかもしれません。正直なところ、なぜベストセラーになっているのか不思議。
0投稿日: 2017.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書的記述と違い、当時の政治状況が良くわかる。 本人たちの思惑がどうあれ、行動とタイミングが合わずに果てしなく泥沼化して、終いには社会構造まで変わってしまった。
0投稿日: 2017.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017/11/02:読了 内容が濃かったが、なんとか読み終えた。 あとがき:286ページより 応仁の乱は、新時代の革命の側面がある。 ただし、それは支配階級の自滅による。 将軍や大名たちも、それなりに出口戦略は考えて、終戦に向けて様々な努力や工夫をしていたが、コミュニケーション不足やタイミングのずれで、終戦工作は失敗を重ね、戦争が無意味に続いた。 試行錯誤を重ねながら懸命に生きた人々の姿をありのままに描き、同時代人の視点で応仁の乱を読み解くという本書の試み。
0投稿日: 2017.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログホンマ疲れた。久々に苦労して読んだ。何よりも登場人物名のルビをもっと多く振って欲しかった。数日後に続きを読もうとすると名前が読めず最初に戻って調べるか、ネットで名前検索…あぁメンドクセー。正確に名前を読めないと全体をリズム良く読めないのでストレスが溜まって、もう、いや…助けて 要は将軍足利義政の優柔不断さが混乱を招いて、そこに伊勢•山名•細川の三者のバランスが崩れgdgd状態になり、追い討ちをかけて畠山家の混乱が加わり結果10年も続いた戦乱になりましたって事でオッケでしょうか。知らんけど。 ただ、これは確かに『応仁の乱』とはどんな事象だったのかって事は何となく理解できた。いや、後三回ぐらい読み返すとかなり理解出来るかもしれない。その為にも名前にルビ振ってくれ、お願いします。
0投稿日: 2017.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログあーっ!なーにやってんだよバカ〜・・・の連続。 あともうちょっとでひと段落するかと思ったら足元をすくわれたり、抜け駆けする奴が出てきたり。 もうなにも信じられないんじゃないかってくらいみんながみんな手のひらを返す。端から見てると何考えてんの!?って決断の連続なんだけど、その裏にはやはりそれぞれの抜き差しならない理由があって、各々の目的の為に別の目的を持った人と組むものだから利害関係の調整がほぼ不可能になるというジレンマの塊みたいな戦争ですね。
0投稿日: 2017.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログメディア掲載レビューほか 成功例の少ない「応仁の乱」で18万部。日本史研究に新たなスター誕生か 日本史上の大トピックとされていながらも、全体像を捉え難い「応仁の乱」。そんな題材を、既成史観の図式に頼ることなく、絶妙なバランス感覚で丁寧に整理した新書がヒットしている。NHK大河ドラマの歴代最低視聴率記録を長年保持していた『花の乱』(1994年)を始め、「応仁の乱」を扱ったものに成功例は少ないので、異例の現象だ。 「『応仁の乱』をテーマに選んだのは著者ご本人です。地味かもしれませんが名前を知らない日本人はおらず、そういう意味では歩留まりがよい。大ヒットはしないまでも絶対に失敗はしないテーマという認識でした。中公新書は『歴史ものに強い』というアドバンテージもありますし後は“著者力"で突破だ、と」(担当編集者の並木光晴さん) 古くは網野善彦さん、近年では磯田道史さんなど、日本史研究者には、時に、学識の確かさと読み物としての面白さを両立させるスター学者が登場する。36歳とまだ若い本書の著者は、次代の有望株だ。 「扱う題材の全体像をはっきりと理解し、その上で、読者に伝える情報を取捨選択できる。30代半ばでのこの筆力には、とても驚かされました」(並木さん) 中公新書の主な読者層は50代以上。しかし本書の売れ行きの初速はネットなどと親和性がある30代・40代が支え、そこから高年齢層に支持が広がった。これは、新たなスター誕生の瞬間かもしれない。 評者:前田 久 (週刊文春 2017.3.2号掲載) だらだらと続く大乱 小学校の教科書で紹介されていることもあってか、「応仁の乱」の知名度は高い。しかし、それがどのような戦乱だったのかと問われると、多くの日本人が口ごもる。室町後期に京都でおきた……戦国時代のきっかけとなった……諸大名入り乱れての……。 呉座勇一『応仁の乱』は、ほとんどの日本人が実態を知らないこの大乱を、最新の研究成果をふまえながら実証的に検証してみせる。さらには、同時代に生きた興福寺の2人の高僧(経覚と尋尊)が遺した日記を通じて、戦乱に巻きこまれた人々の生態を描いている。それらの合間に、気鋭の中世史学者ならではの自説も展開する。いたって学術的な内容なのだが、構成の巧さと呉座の筆力によって最後まで読ませる。 しかし、全体としては、やはりよくわからない。それは決して呉座の責任ではなく、この戦乱が結果的に大乱になってしまっただけで、発端の当事者(細川勝元と山名宗全)たちも、短期に決着するとふんでいたからだ。それがいつしか、両氏が多数の大名を引きこんだために、諸大名の目的が錯綜して、将軍も大将もコントロールできなくなっていき、京都だけでなく各地で戦闘がくり返され、だらだらと終結まで11年もかかってしまったのだ。しかも、戦後処理まで判然としないのだから、応仁の乱はよくわからない。 大義名分に乏しいだらだらと続いた応仁の乱は、第1次世界大戦に類似していると呉座は説く。結果的に諸国に新たなパワーバランスを生みだすことになる、地味な大乱。ひょっとしたら今、私たちもそんな混沌の時代を生きているのかもしれない。 評者:長薗安浩 (週刊朝日 掲載) 内容紹介 室町後期、京都を戦場に繰り広げられた内乱は、なぜあれほど長期化したのか。 気鋭の研究者が戦国乱世の扉を開いた大事件を読み解く。 【目次】 はじめに 第一章 畿内の火薬庫、大和 1 興福寺と大和 / 2 動乱の大和 / 3 経覚の栄光と没落 第二章 応仁の乱への道 1 戦う経覚 / 2 畠山氏の分裂 / 3 諸大名の合従連衡 第三章 大乱勃発 1 クーデターの応酬 / 2 短期決戦戦略の破綻 / 3 戦法の変化 第四章 応仁の乱と興福寺 1 寺務経覚の献身 / 2 越前の状況 / 3 経覚と尋尊 / 4 乱中の遊芸 第五章 衆徒・国民の苦闘 1 中世都市奈良 / 2 大乱の転換点 / 3 古市胤栄の悲劇 第六章 大乱終結 1 厭戦気分の蔓延 / 2 うやむやの終戦 / 3 それからの大和 第七章 乱後の室町幕府 1 幕府政治の再建 / 2 細川政元と山城国一揆 / 3 孤立する将軍 / 4 室町幕府の落日 終章 応仁の乱が残したもの 主要参考文献 あとがき 関係略年表 人名索引 内容(「BOOK」データベースより) 室町幕府はなぜ自壊したのか―室町後期、諸大名が東西両軍に分かれ、京都市街を主戦場として戦った応仁の乱(一四六七~七七)。細川勝元、山名宗全という時の実力者の対立に、将軍後継問題や管領家畠山・斯波両氏の家督争いが絡んで起きたとされる。戦国乱世の序曲とも評されるが、高い知名度とは対照的に、実態は十分知られていない。いかなる原因で勃発し、どう終結に至ったか。なぜあれほど長期化したのか―。日本史上屈指の大乱を読み解く意欲作。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 呉座勇一 1980年(昭和55年)、東京都に生まれる。東京大学文学部卒業。同大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。専攻は日本中世史。現在、国際日本文化研究センター助教。『戦争の日本中世史』で角川財団学芸賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) BLOGOSの記事『成功例の少ない「応仁の乱」で18万部。日本史研究に新たなスター誕生か 『応仁の乱』(呉座勇一 著)――ベストセラー解剖 - 前田 久』で紹介されています。 本の感想(オフィス樋口Booksより転載、http://books-officehiguchi.com/archives/4856728.html) 応仁の乱と言えば、歴史の授業で、将軍の後継者争いに管領の畠山・斯波の後継者争いが加わって長期化したと習った人が多いと思われる。応仁の乱など室町時代は人気がなく、大河ドラマ『花の乱』では当時の史上最低の視聴率を更新した。 この本では、「なぜ応仁の乱が始まったのか、教科書の説である将軍の後継者争いなのか」「なぜ応仁の乱が長引いたのか」という点に注目しているだけでなく、応仁の乱後にも注目しているのが面白いと言える。また、細川勝元や山名宗全を英雄とは言えない目立たない人物としている点も面白い。 大学受験以降、日本史の室町時代から遠ざかっている人には、日本史について復習する必要があり、何回も繰り返し読む必要があるかもしれない。室町時代の見方が変わる可能性があるので今後の研究の動向に注目したい。
0投稿日: 2017.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ1467~77年、東軍細川勝元、西軍山名宗全くらいしか知りませんでしたが、主人公もなくダラダラと続いたとされている戦争について、少しはわかったような気がしました。
0投稿日: 2017.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログよほど歴史の認識が深い人でないと読みこなすことは出来ないし、面白みを感じることも出来ない。 応仁の乱が分かりにくいのは、これと言ったヒーローも出ず、これと言った大きな戦も無く、際立った文化も無く、終わりを告げる大戦争もないからであり、いわゆる、魅力がないからである。その魅力がない時代を、面白く、魅力ある時代に描きなおしているのかと思えば、そうではなく、淡々と応仁の乱の時代を記すだけであり、面白くないのを再認識しただけである。
0投稿日: 2017.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ目を惹く広告で話題になった歴史書。噂通り前半はかなり硬めで捗らないんだが、中盤から「どこの経済小説だよ!」と突っ込みたくなるような、現代日本さながらの泥沼権力闘争が描かれ始め、あぁ、ここを読み解くための前半だったのね、となる。コーポレートガバナンスでもありがちな話がどっさり出てくるし、従来あまり評価されてこなかった人物にも平等な記述を目指す筆者の描き方からは新しい景色も見える。社内の派閥争いに疲れた人はよむといいかも。
0投稿日: 2017.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログなんなんでしょうか? この中公新書のかしこそうな感じって。 アナタたちとは違うんです、って言われてる感じ。 でも今年とても売れた新書のうちの一つということは意外とわかりやすいのかも、と淡い期待でチャレンジ… アタクシの脳ミソが世間の皆さんよりはかなり低空をフライトしていることは重々承知の上ですが、一回では誰が誰だかわからん…くやしいです!(©︎ザブングル加藤) せっかく定価で買ったのにもったいない、と人物の相関図をメモしながら再チャレンジ… わかってきたけど楽しくない… 子どものころドラクエのふっかつのじゅもんをメモってるときはとっても楽しかったぞっ。 戦国武将のみなさまへ一言。 じい様から孫の代まで同じ漢字使うなよ、誰だかさっぱりわからん…あと途中で名前変えるのは反則よ。
0投稿日: 2017.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の教科書で、名前だけは覚えた応仁の乱。 応仁の乱を幕開けに、世は戦国時代に突入していくというざっくりとした知識しかなかったが、話題の本ということで読み始めてみた。 応仁の乱の概要があまり知られていない理由がわかったような気がしました。 奈良と京都の土地勘と、なんとなく天皇の系図、将軍幕府の系図が頭に入っていなかったら、恐らく自ら地図を見、系図を確認しながらでないと読み進めるのは困難。 しかも、興福寺という要素が重要な意味を持っていることも理解でした。 新書ということで、軽い気持ちで入門編として読み始めると読みづらいと思いますが、登場人物相関図と地図を思い浮かべながら読むと複雑な面白さが伝わってくる。
1投稿日: 2017.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今売れている、応仁の乱に今の時代を見る、などの新聞記事を見、行きつけの書店で平積み、イチオシになっているのを見て思わず購入。読み始めてみるが、え~!!、本当にみんなきちんと読んでいるの? そうだとしたら買って読み込んだ人はえらい。最初20pくらいまではきちんと読んでみたがなにしろ地理や特に人物の縁戚関係がややこしくてどうにも読み進められない。研究者の研究を史料をもとに紹介しつつ自説を述べるという、歴史の専門書形式だ。なので、終章:応仁の乱の残したもの20pほどを読み終わりにした。それが1か月前。で、今なにも覚えていない・・己の歴史感覚の無さを思い知る。
0投稿日: 2017.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書の役割は学術論文を一般大衆向けにわかり易く書き直し、大衆が教養を身に着ける事に寄与するもの、トカナントカらしいが、この本は内容的にはかなり細かくて(一説によると登場人物が300人程度とか)、「大衆の教養」レベルを遥かに超えてしまっているように思う。40万部売れているそうだが、ブームなので買ってしまったのはいいが、数十ページで挫折してしまって、殆ど読まない人が半数以上いるだろう。自分は歴史はワリと好きな方だし、応仁の乱の要所は巡った事もある程度には興味はあるレベルだが、それでも、ざっと読んだだけで、細かい所までとても追いかける気にはなれない。著者も登場したNHKの『英雄たちの選択』程度深さで調度いいくらい。これをシッカリ読みこなすには大学の史学科在籍で中世を研究テーマにしようと考えている学生レベルの基礎知識と体力が必要だろう。
1投稿日: 2017.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ中公新書の「応仁の乱」が 20万部を超えるベストセラーとなったという 記事を受けて、読み始めた。 しかし、登場人物が多く、 経緯も複雑で どうも腑に落ちなかった。 読後、感じるのが、 この複雑さこそが 応仁の乱を長引かせた要因であったのではないか。 さまざまな対立要因を抱え込み、 それぞれの中心を明快に特定できず、 だからこそ、疲弊する長期戦となったのであろう。 基本構造は、細川勝元に対する 新興勢力たる山名宗全の挑戦で始まったわけだが、 そこにさまざまな対立構造が取り込まれることで 終わろうにも終われない戦いが続いたのである。 結果、終戦後には足利幕府の弱体化をもたらし 守護大名から戦国大名へと大名の変化が起き、 戦国時代を用意することになるのである。 貴族たちの次男以降が寺に入僧する構図は ヨーロッパの中世からルネサンスと 構図が類似しており、 寺社の持つ権力装置、 武装力を持った暴力装置としての側面を 見逃すことはできない。 それにしても、足利義政の朝令暮改は 目に余る。 人物に開戦の原因を求めるとすれば、 間違いなく義政だろう。
0投稿日: 2017.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログすでに多くの読者を得ていることからも分かる通り、本書は応仁の乱という複雑な歴史を筆者なりの方法により整理したものである。もちろん、それでもかなり複雑でわかりにくい面があるのは歴史自体の性格によるものであろう。 同族間の勢力争いに加えて、旧主派と新興勢力との争い、地域紛争などが戦乱に次々に取り込まれ、勝手に争いを広げていくのがこの戦乱の特徴だ。そして、それを治める役の幕府は態度が一定せず、その局面で強い方に味方するという優柔不断さが傷を深くする。すべての豪族が戦いで自己実現を試み、皮肉にもそのためにすべてが疲弊する戦国時代を招いてしまうのである。 本書は応仁の乱を近代的革命思想に解釈から開放しようとしたところに主目的をおいているように感じた。この戦いが何らかの目的意識をもって行われたとするにはあまりにも混乱が大きすぎ、大義がなさすぎる。中世という時代の人々の世界観人生観や倫理観などについて、現代とは切り離して考えなくてはならないと感じた。
0投稿日: 2017.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ評判が高いから読んでみて、途中まで人名に苦しんだけど、予想外に面白かった。いろいろ理解できたし、このへんの歴史を他の本でも読みたいと思われる。
0投稿日: 2017.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代以前の歴史をよく知らないのはあかんと思ってたところにどうも応仁の乱ブームが来たようなので乗っかって読んでみた。 興福寺の2人の僧の日記から見ているんだけど、そもそも戦国以前の大和の事情を知らなかったので興福寺の力とか筒井家がそもそもなんだったのかとかいうところで勉強になった。 あとは室町幕府の政治体制がどのようなものだったのかとか、守護代がどのような経過を経て台頭していったのかとか。 あとがきにもあるんだが、想定していなかっな自分への行為の反動でなし崩し的に誰も想像しなかった長い争いになったってのは第一次世界大戦のよう。
0投稿日: 2017.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱は日本史における大きな転換点の1つであり、歴史の授業でも必ず取り上げられるのだが、一方であまりにも複雑であるため重要性の割にはあまり時間が割かれない。本書から、応仁の乱の原因は将軍家や有力大名の後継争いといった一般に言われていることだけでなく、実はそのかなり前から伏線があったことが理解できる。
0投稿日: 2017.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの誰でも聞いたり習ったことがあるにもかかわらず、その詳細を聞かれるとあまりよくわからないという、地味な乱についてまじめに解説した本。なぜか話題になって人気ということで本屋で購入して呼んでみた。ただまじめに地味に解説してあり、一次資料を基に詳しく描かれてはいるが、全体の流れはつかみにくく、読んでいて楽しい本でもないし読みやすい本でもなかった。これを読んだら応仁の乱に興味を持つようにあるかというと、そこは疑問。
0投稿日: 2017.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ上御霊神社を「御霊神社」と書くのは誤記ではないか? 今でも下御霊神社が存在し上下揃っているのに。 応仁の乱はこのように説明されても本当に面白くない。
0投稿日: 2017.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ細川勝元、山名宗全をそれぞれ中心とした、御所を巻き込んだ戦いだが、何が原因で、なんのために行われたかがよくわからないダラダラと長期化した戦乱、て感じ。 これはかなりマジに史実を説明していて素人には難しい。なんでこういうのがベストセラーなんだ?
0投稿日: 2017.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログベストセラーだっていうので京都に行く前にと思って読み始めましたが、結局読了したのは行った後。 いやぁ。同じような人の名前がたくさん出てきて、全然頭に入りません。まんがで読む応仁の乱も売れているのがよく分かる。 応仁の乱と掲げておきながら、奈良興福寺の視点で書かれているから余計にややこしい。 とりあえず、人の世むなしい応仁の乱が一筋縄ではいかなかったということは分かった。
0投稿日: 2017.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログかなりの長期的な戦だったのでいくつもの出来事と人物で構成されてくるので登場人物を把握するだけでも容易ではない。 応仁の乱と第一次世界大戦が似ているとあとがきで書いてあったが納得できた。
0投稿日: 2017.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ評価は最高を4とする 極上のものがあれば5かな ベストセラーだけある呉座先生 面白かったです ・・・一条兼良に興味できました
0投稿日: 2017.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間のあるときにちょっとずつ読んだので,次々に出てくる登場人物がわからなくなった部分があった。 それでも,応仁の乱の具体的なところを全然知らなかったので,それが良くわかってためになった。 「守護在京制」が弱体化し,守護が在国するようになる要因となった点が勉強になった。
0投稿日: 2017.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ奈良の興福寺の別当経験者2名、経覚と尋尊の残した日記を基礎資料として、応仁の乱の経緯を追っている。京の乱というより、荘園支配を巡る争いという感。 応仁の乱ブームの中心のようにいわれる本書だが、読み解くのが大変。別の解説本で人物相関図を参照しないと、東軍、西軍が混乱してくる。
1投稿日: 2017.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終わりました.名前が途中で省略されたりしていて,誰が誰やらわかりにくく,混乱しました. 山城国一揆など,今まで思っていたことと違ったことも多く,畿内の入り乱れた権力争いも面白かったです.
1投稿日: 2017.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の帯の通り、知名度の高さの割に中身を知らない事件。読みやすく、分かりやすく書かれてはいたが、やはりややこしい。 再読が必要な本。
0投稿日: 2017.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ中央新書さんの本がこんなに騒がれたのは珍しいのではないか?(失礼) 仙台に出張した歳、知り合った地元スタッフと本の話で盛り上がり、教えてもらう。また、自分でも入手しようと調べると、なかなか好評な様子で更に期待が高まる。 読んでみた、が惨敗だなー、歴史小説が好きなのであって、歴史のことをつらつらと書かれた本は40前にもなるのに読みづらい。もう登場人物が5人以上出てきた時点で、火を自在に操るとか、ほくろから毛が生えているとか、わかりやすい特徴がないと覚えきれず、話について行けない。。。 応仁の乱の事を再勉強出来たことと、悪女富子を養護する考察に触れられた事が今回の収穫。 【学】 八代将軍足利義政に息子が居なかったので、弟の義視を後継としたが、直後に義政の妻日野富子(日本三大悪女)が男児を出産したので、富子が息子を将軍にしようと画策、細川勝元(義視)東軍と山名宗全(富子)西軍がお家騒動に介入し応仁の乱になる。 応仁の乱によって将軍の権威が失墜した「応仁の乱が終わってもめでたいことは何もない、今や将軍の命令に従う国など日本のどこにも無いのだ」とまで言われた。
0投稿日: 2017.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説ではなく、当時の知識人の日記などを基にした学術資料のような感じ。 登場人物も多く、連携と離反も多く、整理をしていかないとついて行きにくい。 人物の相関関係や地図を多用してくれると、もっと深く楽しめたと思います。
0投稿日: 2017.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ室町時代に関する本はあまり多くないが、最近、この時代の研究が盛んだそうで、室町時代の最大の出来事の一つである応仁の乱についても新しい本が出た。しかも、それが売れてるという。 どんなものだろうと思って読み始めたが、確かに面白い。奈良の興福寺の高僧二人の記録を中心に、京都だけではなく、奈良を含めた畿内という範囲で話が進み、一見複雑な人物関係も、戦局の展開も分かりやすくて、初めて応仁の乱というものが理解できた気がした。 著者の他の本も読んでみたくなった。
0投稿日: 2017.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ盛り上がりや主役が不在の為とても分かりづらい歴史的な騒乱、その後の時代の転換点です。 この本では、興福寺の経覚と尋尊の日記を通じ分かりやすく解説していていい勉強になりました。 あまり触れていないけど、やはり日野富子はラスボス感ある。
0投稿日: 2017.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
室町時代を題材とした書物を読むことは、あまりないが、本屋で並んでいるのを、つい買ってしまった。登場人物が多いし、馴染みもなくて、取っつきにくいが、相当整理されているため、案外読みやすい。 応仁の乱が、幕府の権威による支配、京都中心主義から、実力による支配、地方主義への転機だということがわかる。それが、今の日本の社会の原型になっているのだろう。 経覚、尋尊の残した記述は当時の肉声であり、世の中の動きに対する知識層の評価が伺えて面白い。
0投稿日: 2017.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人気ということで手に取る。まだ消化不良気味。とりあえず、興福寺というお寺の意味を少し考えるようになりましたが...。
0投稿日: 2017.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史上最も尊敬する人物を聞かれたとき、僕はいつも「足利義政」と答えている。和風建築、水墨画、茶道、華道といった侘び寂びを基調とする日本文化の基礎を作った人なので。 義政は政治に関心がなく無能な応仁の乱の張本人と批判されることが多いが、この本では、義政も応仁の乱を治めようと様々な努力や政治的駆け引きを行なっていたことが分かる。(ただ、あまり上手くはいかなかったが) この本自体は、決して読みやすくはない普通の歴史解説書で、この本がベストセラーとなった理由は分からなかった。(評判が評判を呼ぶというやつだろうか)
0投稿日: 2017.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきに、当時の人々のありのままの姿を描きたかった、とあるが、当時の人々はこれほどまでに生き生きとしていなかったのであろうか? などと、楽しめなかった自分は文句を言ってみます。 司馬遼太郎や塩野七生や海音寺潮五郎のような戦記物を期待してはだめ、ということ。これは新書。 この内容の分厚さは一読の価値はある。興味がある人にとっては。 近世日本史の入り口となるような生易しい代物ではない。
0投稿日: 2017.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ室町時代というのは茫洋としたイメージしかなかった。応仁の乱前後の時代を書いている本だからかもしれないが、いろいろと大変な時代だったということが見て取れた。つまり、落ち着かない世の中だったようです。 この人の前著(新潮選書の)も読んでみたくなった。
0投稿日: 2017.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
流行ってるから読んでみたけど思ったほどにはおもしろくない、けど普通の歴史の本としておもしろい。 応仁の乱のメイン部分は興味があるのでおもしろかったんだけど大和国ローカルパートはいまいち興味が持てなかった。そちらもわかった方が理解が深まるのはわかるのだけれど。
0投稿日: 2017.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
その後約100年続く戦国時代の原因と言われることもある応仁の乱。勝ち負けが判然としないことや、小説などで取り上げられることも少ないことから、細部は分かりにくい。その「解説本」が本書。 奈良の興福寺を率いたふたりの僧が残した記録などを元に、京や奈良でなにが起こっていたのかを詳述している。 しかし、ただでさえ登場人物がわんさかいるのに、足利氏、畠山氏など一族間の争いが重層的に展開される上に、一族の通字や将軍の偏諱などのせいで似たような名前も多く、ぼさーっと読んでるとすぐに、「コイツ誰だっけ?」となってページを戻る羽目になる。 それでも、さすがに読みごたえあり。「乱の全貌を知る」のは新書サイズでは現実的ではないだろうが、奈良から見た応仁の乱という視座を得たことで、(人物名以外ではw)分かった気になれる。 たまーに挟まれる戦後の唯物史観批判は、今となっては一般人にはどうでも良いことなんだけどね。
1投稿日: 2017.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ簡単な内容の本ではない。読了すれば応仁の乱が即理解できるわけでもない。けれども、ある意味で観応の擾乱の後史として、戦国争乱期の前史として楽しむことができた。そして生臭坊主達の、なんと強かなことよ……。【100文字】
0投稿日: 2017.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯文:”日本社会を変えた歴史の転換点” ”11年に及んだ泥沼の戦いの勝者は誰なのか?” ”室町幕府はなぜ自壊したのか” ”日本史上屈指の大乱を読み解く意欲作” 目次:はじめに、第一章 畿内の火薬庫、大和、第二章 応仁の乱への道、第三章 大乱勃発、第四章 応仁の乱と興福寺、第五章 衆徒・国民の苦闘、第六章 大乱終結、第七章 乱後の室町幕府、終章 応仁の乱が残したもの…他
0投稿日: 2017.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ絶対的な権力者の不在→参戦大名が増加→戦争の獲得目標増加→長期戦で犠牲増加→犠牲に見合った成果→さらに長期かするという悪循環。 第一世界大戦前夜、そして現代に通ずる共通点。
2投稿日: 2017.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白くもあり、面白くない。 詰まるところ、為政者どものグズグズ感満載の結果としての権力闘争ということだからかな。そりゃあ歴史小説の題材としてピックアップされません、これでは。 ほんと民衆からすれば堪ったものではない。何処となく現在を見ているようでもあり、余計に読み物として魅力的でもあり、うんざりでもあり。不思議な本です、はい。
2投稿日: 2017.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書でさらっと触れただけで、ほとんど良く分かっていなかった応仁の乱の原因、経過、乱後の影響が分かりやすく書いてあって良かったです。 乱の前20年ぐらいからの経緯があって、途中経過として必然的に戦争となり、最終的には勝者が存在せず、その後の下剋上の流れにつながるという点に目から鱗でした。 これは教科書の数行で理解するのは無理ですね。 本書は奈良の興福寺の二人の門跡の日記から乱を読み解いていますが、大和国の豪族の状況にこちらの知識があればもっと理解できたのかなと思いました。
1投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ20170506 何で売れてるのか?と思って買ってみた。よくまとまっているのが理由なのだと思うが全体的に華が無い時代なのだとわかった。室町時代が無ければその後の戦国時代も無かったのだがら時代を繋ぐという点でも重要なのだろうが、何か応仁の乱だけに焦点を当てるとみみっちい感じになってしまう。華が無くみみっちい所は今の時代に似てるかも知れない。
0投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本各地で同時進行的に様々な紛争が出て来るわけだけど、こちらの本のほうが、先日読んだ「応仁・文明の乱 (戦争の日本史 9)」よりまとまっていて読みやすい。 両者とも歴史的解釈は似ているので、それが今の標準的なものなんだろう。 - 義視と義尚の後継者争いが原因という従来の見方は否定的。 - 様々な紛争が発生しているが、直接な原因が畠山政長・義就の後継者争いに、細川政元・山名宗全の両雄が介入してしまったこと。 - 大和は興福寺に支配されていたが、配下の豪族たちの紛争が絶えず、混乱に油を注いだ。 - 紛争の遠因は、義教の恐怖政治、それが終わった後の赦免、義政の朝令暮改的な、大名後継への介入。 英雄はいないといいつつも、畠山義就、朝倉義景、斎藤妙椿、大内政弘あたりは中々興味深い。
0投稿日: 2017.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「東軍と西軍に分かれた大名たちが繰り広げる大乱世!」 いや~乱世乱世。 このグダグダっぷりはヒドい。 元は興福寺の大乗院、一条院が仲が悪く、それぞれ小豪族がバックに着き、小大名から大名までが小競り合い。 弱いくせに「俺のバックは幕府なんだぞ!」とちょっかい出してはボコボコにされ、幕府が調停しても同じことの繰り返し。 そして畠山の内部分裂で当事者同士の直接対決で決着を決めようとしたのに、山名が加勢して細川マジ切れで大乱勃発。 幕府をバックにした細川の東軍が圧倒的有利かと思えば、将軍の弟をネオ幕府とか言って担ぎ上げた西軍に大内の加勢が加わり長期戦へ。 以降、俺たち何のために戦ってんの?状態が続くも、最下層民の足軽さんたちは勝手に暴れて略奪し放題なので京都の荒廃がどんどん進む。 元々そんなに仲が悪くない山名と細川は本当は戦なんてやりたくなかったのに、なんかグダグダで内乱が勃発してしまった。 とても日本人らしい。 派閥を作って社内闘争勃発って、古今東西どこの国でも今の世でもある話。 あぁ、諸行無常。
2投稿日: 2017.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近よく売れているのか、どこの本屋でも ベストに入っているので手に取って読んでみました。 確かに、今まで応仁の乱自体をここまで詳細に追った 内容の書物はなかった気がします。 戦国時代前夜の室町時代の空気感というか時代背景が ある程度わかるような気がします。 戦国時代の前であるこの時代は、日本全体がもっとドラスティックに大きく動いているという感覚を持ちました。 また、応仁の乱の描写の視点として奈良の興福寺が採用 されていますが、のちの時代においてはどちらかというと 悪者にされている興福寺の影響を色濃く受ける大和の国 というところもここまで詳細に語られることもなかった ので新鮮でした。
0投稿日: 2017.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ何が原因で誰が勝ったのかがよくわからないと言われる応仁の乱。本書は史料を丹念に読み解くことで、応仁の乱の実像を明ら かにしたと言っても過言ではない。確かに複雑ではあるが、順を追っていけば理解できる範疇にあり、また、それぞれが乱の収束のために動いていたが、思い込 みや行き違い、見栄の張り合いでズルズルと続いてしまっていたということがわかる。 中心となる史料は興福寺の僧侶である経覚と尋尊、二人の遺した日記である。この二人は応仁の乱を間近で見た人物であり、特に経覚は深く関わっており、乱の中心人物ともいえる。一方、尋尊はどこか他人事の様に一歩引いたところから見ている部分がある。同じ事件を異なる視点から見た記録であり、史料として十 分に有用であると思われる。しかしこれまであまり重視されなかったらしい。偽書の可能性が高いといったことではなく、歴史学者が賞賛していた下克上やそれ による体制の変革、それを否定している――特に尋尊がその傾向が強い――ためであるという。本書でもこのことは再三触れられており、腹に据えかねているこ とが伺える。 応仁の乱は階級闘争史観に基づく歴史認識、あるいは下克上、民衆蜂起を賞賛する歴史学者にとってちょうどいい題材だったのだろう。それを否定するような二人の日記は都合が悪く、むしろ応仁の乱が幕府の自滅であって民衆蜂起でも何でもないことが明らかになることを恐れてすらいたのかもしれない。応仁の乱の わけの分からなさの原因は、実は歴史学者だった。応仁の乱を明らかにしつつ、歴史学者の本質までも暴いてしまった。
3投稿日: 2017.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログどうなんでしょう。日本史上級者には手ごたえのある内容なのかもしれないけれど、私のような一般人(以下?)にはかなり難解な内容(そもそも登場人物が多くて、その関係が覚えられない)で、応仁の乱の歴史的意義が理解できなかった。中学の勉強をし直せと云われそうだが、当時の将軍家と大名(守護)、公家族、そして寺社の関係の詳しい解説があるとありがたかったのだが。
0投稿日: 2017.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ評判なので読んでみた。 結構、時間がかかった。 なかなか読み進めなかった。 いかんせん、義政は銀閣寺を建てた程度の教養だと そういうことになりえます。 でも、完読して勉強になりました。
0投稿日: 2017.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱と言えば、無気力な将軍義政に、好戦的な弟義視、狡猾な富子・・・とわかりやすい人物が描かれるのみで、戦闘の主役たちがなぜそのような行動をとったのかの観点で語られることは余りなかった。本書は奈良興福寺のトップ経覚と義尋の記録を基に、乱前の大和争乱から乱後の明応の変あたりまで、登場人物たちの行動を克明に描いていく。何故そのような行動をとったのか、10年もだらだらと戦い続けたのか、というような何故の答えまで用意されている訳ではないが、もうちょっと考えてみると面白い。 思うに、細川勝元も山名宗全も、源平合戦以来の武士の行動原理に従っているが、現代の我々はその後訪れた戦国時代の大名の有り様を知っているから、どうしもそちら側の眼鏡で見てしまう。戦国時代の大名たちは領域を支配し、そこで軍事力と経済力を養成し、基本的に領域を拡大することで成長を遂げようとした。しかし室町中期までの武士は荘園制を前提に生きており、武士とは荘園の管理人であり、その棟梁は京都を確保することで正当性を得、守護とはその地に駐屯して荘園から軍事費や賦役を徴発する存在だった。後代の常識からすれば、京都で戦っている間に本国の方を占領してしまえば良いのに、となるのだが、そのようなことを実行したのは越前の朝倉孝景くらいで、故にこそ彼は戦国大名の先駆になった。 本書の面白さは経覚や尋尊という荘園制の旧体制にすがって生きる人々の視座で描いている点にあるのだが、荘園制から目覚めていく武士の側はあくまで客体として登場するところが限界なのかもしれない。河内の暴れん坊畠山義就のモチベーションは何か、細川勝元は幕府と細川家のどちらを大事に考えていたのか、朝倉孝景はどこをどこまで計算していたのか、など、目覚めゆく武士たちの苦悩と葛藤もまた面白かろうと思うのだが、残念ながらこのような人々のそばで記録を残した人はいないので、どうしても旧体制側から描いていくしかないのだろう。
0投稿日: 2017.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読了。 応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱 / 呉座勇一 最初に別の本を読み始め、ノリきれないのでもうひとつを読み始めるも大作なので、長引くなとおもいつつ、散歩がてら本屋に寄ってこれを見てそういえば人気あるよねこれと思い購入して、案の定先に読み終える。 応仁の乱です。 日本史の授業でもさらっと流す応仁の乱です。 どうして起きたかなんてしりませんよねこれ。 11年も長々と京都を二分して戦った大乱はいかにしてはじまったか。 そしていかに終わったか。 序章は一休さんでおなじみの足利義満さんの次の義持のときから、大乱MAX時は銀閣寺を作った義政さん 京都の戦いが終わったのは義政さん次の義尚で、最終的なのは次とその次の義稙VS義澄あたり。 長いですね。 大乱勃発の最大の原因は畠山氏でしょうかね。 君たちだけじゃないけども。 みんな乗っかかり、みんな巻き込まれる。 政治が悪いから足利将軍家が一番悪いかもしれませんね。 んで大乱が終わると、将軍さん力ないし、京都に住んでる意味ないし、偉い人たちが自分の土地で領土守ったりうばったりするべく戻っていって大名化みたいな。 でもともと守護代していた家臣が独立して大名化、元々住んでた国人衆も力を持つって感じになって、戦国時代突入! ってところでしょうか。 いやーたいへん勉強になりました。 面白かったです。
0投稿日: 2017.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあの応仁の乱を知らないはずはないのですが、実はよく知っていなかった、日本史の中でも最もよく分かっていなかった戦争という認識でした。教科書的なものを読んでもよく分からなかった。その原因が、本書を読むことで理解できたように思います。とりあえずあの応仁の乱というものは、とても複雑だし、難解なものなのだと。そのあたりを、まず感覚として持つことができたことは大きなことだったと思います。京都で発生したこの戦争を、その影響を受けながら、奈良から見ていた2人の興福寺別当の記録から紐解くことで、乱の周囲への影響も知ることができ、この戦争が大きなものだったことが実感できます。またそれにより、戦後の大名がどのように変わっていったのか、それが戦国時代にどのようにつながっていったのか、日本史の中世を知るためには、この応仁の乱を正確に知っているかどうかが重要だと思いました。 しかしながら、いつの時代も人間は芯のところは変わらず、現代人としても妙なデジャブを感じながら読ませていただきました。
0投稿日: 2017.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんだかよくわからなかった応仁の乱は、読んでもやっぱりよくわからない。でも、読んでいると読んでしまう読ませる力がある。中世というのはおっそろしくややこしいのか、単純なのか。結構違う。やれやれ。
0投稿日: 2017.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都では先の大戦というと「応仁の乱」を指すのだとか。 というくらい誰にもその名前は知られている。でもどんな戦争で誰が勝ったのかはよく分からない。英雄も生まれていないし、有名な戦闘もない。グダグダなんだな。軍事的には防御が先に進化した時代だったので、互いに決定的な勝利をおさめることもなかった。 とはいえ、中世の終焉を決定づけたことは間違いない。荘園領主制が崩壊し、下克上が始まるのもここからということは分かるんだ。
0投稿日: 2017.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代に比べてあまり一般にはなじみがないが、しかし戦国時代の口火を切った応仁の乱について述べた本。 歴史学的には、戦国時代最後の戦いである関ケ原の戦い並みに意義があるんだと思う。 関ケ原の戦いとの最大の違いは、政治的にも軍事的にも優れた指導者がいたかであり、逆にいえばそういった優れた指導者がいなかったから全国的な戦乱に陥ったのだろう。
0投稿日: 2017.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
登場人物が沢山出てきて、あまり知らない人物ばかりなので、ノートに人物名と西軍、東軍どちら側かとメモしながら、読んでいったのですが、それでも東軍だったのが、西軍に寝返ったりするので、最後はわけがわからなくなった。
0投稿日: 2017.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書としては異例の売り上げを記録しているらしいが、応仁の乱の経緯をわかりやすく説明したものではない。 興福寺の高僧の記録に多くを拠っているのが特徴で、京都よりも大和・奈良の記述が多い。また、かなり細かな事情や推移も詳細に語られるので、かえって全体像が見えにくい。だから、応仁の乱について手っ取り早く知りたいという需要ではなく、既に一定の知識があって更に詳細に理解したい読者に応えたもの。 その意味では、ここまでがっつりベストセラーになるべきべき本ではなくて、もっとニッチにだらだら売れるべき本だったんじゃないか。とはいえ、、それはそれでその硬派な感じはさすが中公新書だと思う。
0投稿日: 2017.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱のことが少しわかったが、やはり関係者がぐちゃぐちゃしてて、スカッとした 華やかさがない合戦でした。(苦笑)
0投稿日: 2017.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ近所にお墓がある人がこんなにがっつり応仁の乱に噛んでるとは知らなかった。勉強になった。またお墓参り行こう。
0投稿日: 2017.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ覚悟はしてたけど、やはり相当にややこしい。が、前半で脱落しなければ後半は相当見通しが良くなる。たしかに良書であった。
0投稿日: 2017.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ何やらバカ売れしているらしいので。史実を繋ぎ合わせている部分が多く序盤は難しかったが、最後はかなりスッキリと理解出来、興味深かった。こんなに複雑な要素を含んでいたことが驚き。やはり歴史は深い。
0投稿日: 2017.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ何だか売れているらしい。やたら登場人物が多く、その経緯を追うだけでも大変な「応仁の乱」。それをわかりやすく叙述しているのかと思いきや、前半から中盤にかけてはやはり難しかった。 しかし、乱終息後の叙述、つまり時代が「戦国時代」に入っていくあたりからすっきりと見通しがよくなってくる。途中で挫折し掛かっている方はむしろ最後をまず読んでから最初に戻ったほうが読みやすいかも。 結局、応仁の乱とは何だったのか。それを著者は守護在京制の解体と位置付ける。つまり、京都中心主義の時代が終わり、「地方の時代」(戦国大名の領国経営)の始まりである。 と、書いてしまうと身も蓋もないが、結局はそういうこと。しかし、原史料を駆使して同時代を生きた人々の生の声をできるだけ叙述に反映させようとしている。その意味で大変面白く読んだ。
0投稿日: 2017.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。高校日本史でも何となく年号覚えた程度で、知名度の割には詳細を知らなかった応仁の乱。 実態は畿内の有力な守護大名たちの家督相続や領地争いでの小競り合いがクラスター式に拡大し、それが一つの大乱に集約されたものだった。 そんな形だから、誰が主役で誰がキーパーソンかもいまいち明確でなく、リーダーシップを発揮する人がいなかったことが長期化の原因。 これは社会人になって世の中がわかったからこそ、理解ができたのではないかと思う。
0投稿日: 2017.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史の特異なトピックであり、舞台は京都を中心とした応仁の乱をテーマにしたこの本がたいへん売れているということで手にしてみた。視点としては奈良の興福寺の僧侶の日記を中心に史実を組み上げた様だ。文化都市京都の建築物が殆どが応仁の乱以後なのは特に西軍による放火戦法に寄った様だ。その戦乱は京都ばかりでなく滋賀、大阪、奈良、和歌山、岐阜、兵庫など、読む前に思ったより広がりがあった。戦国時代の方が群雄割拠のイメージがあったが、応仁の乱の頃にはもうバラバラ感が同じかそれ以上にあって、幕府も管領もお家分裂闘争してる。幕府も有名無実とまでは行かないまでもここぞで取り巻きの文人官僚すら離反する始末。足利幕府の系譜も戦による敗死や分立等こんなにややこしいとは知らなかった。
0投稿日: 2017.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ登場人物が多く身内同士の争いもあり複雑だったが、乱のきっかけやその後の戦国時代につながるきっかけがよくわかった。
0投稿日: 2017.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ名前を知らない人はいないくらい有名ながら、かなりの歴史好きの人以外「どんな内容(発端・経緯・結果)?」と聞かれて明瞭に答えられる人も少ないのが「応仁の乱」ではないだろうか。 (室町幕府の弱体化を招き、その後の「戦国時代」招来のきっかけとなった、くらいは言えるにしても、その中味は?と問われると) かくいう私もご多聞に漏れずその一人。 こちらを読んで改めて「なるほど、こういう経緯だったか…」と思うと同時に、ややこしくて読み終わった今でも自分で説明は難しいことには変わりないという…(苦笑)
0投稿日: 2017.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や,初版刊行から4か月弱で8版を数えるベストセラー。複雑な人物関係に対して付された懇切丁寧な説明もさることながら,おそらく読者の多くが長年抱いていた応仁の乱に対する「ただぼんやりとした不安」を解消しようという意気込みが,ここまでの売れ行きに繋がったような気がする。 300頁に至る本書の中で,著者が一番言いたかったのは,はたして長期化した応仁の乱の複雑なメカニズムを解明することだったのか?それならば,おそらく第6章の「大乱終結」で,まさに終結していたと思う。本書のクライマックスは,11年の歳月を費やした応仁の乱のあとに突如としてやって来る「明応の政変」にこそあろう。このクーデターで,細川政元が11代将軍足利義材(のち義稙)を廃し,清晃(のち12代将軍足利義澄)を擁立させたことが,室町幕府における「2人の将軍」化と分裂をもたらし,戦国時代の幕を開けさせた。こうした著者の主張は,フェイドアウトで終わらない平成の『応仁記』を読んでいるようで,楽しかった。 我々は普段,室町期の守護大名や国人たち,ましてや本書のストーリーテラーとなる経覚と尋尊といった門跡の門主たちの肖像画にあまり触れてこなかった。おかげで,彼らの顔となり,人となりを,非常に思い浮かべにくい。その点を,著者は文面で最大限に努力してくれたと感じる。 とくに,このような効果によって人間味を帯びた人物が,畠山義就である。大和国の守護になりたくてあれだけ暴れたのか,はたまた権威を徹底的に破壊したかった脱中世人のか,定かではないが,15世紀後半期を代表する"Best Supporting Actor"として描かれていた。もう一人挙げるとすれば,足利義視だろうか。東軍から西軍への寝返り,兄・足利義政との確執,子・足利義材の将軍就任への執着など,単なる還俗武士ではなかろう。 ただ一つだけ残念だったのは,「結果,」(212頁)という「接続詞」が使われていた点である。80年代生まれが著す宿命なのか,いずれは「接続詞」として黙認される日も来ようが,アカデミック・ノンフィクションを並べる中公新書においては,時期尚早であると言わざるをえない。
0投稿日: 2017.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ鎌倉時代もそうだろうが、この時代も戦乱が絶えなかったにも関わらず、教科書にはあっさりとしか述べられておらず、素人の私も当然ほとんど知らない内容でした。 ただ淡々と事実を述べるに留まらず、2人の僧の視点から描かれていた点が良かったです。
0投稿日: 2017.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2/3程度読んだところでタイムアウト。 応仁の乱って有名だけど内容がさっぱりわかっていなかったのでなかなか興味深かった。 やっぱり後の戦国時代に比べるとまだまだ貴族や寺社という権威が残っていたんだなぁと。主人公?もお坊さんだしね。 時代時代でたくましく生きる人々はやはり魅力。 人名の記載が名字を省かれるので、これ誰だっけか?と系統図とにらめっこしながら読まなきゃいけないので少々敷居が高かったかな? 機会があれば残りも読んでみたいと思いました。
0投稿日: 2017.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
戦国時代のきっかけにもなった長く続いた難解な大乱、応仁の乱についてわかりやすく解説した新書。 戦った当事者からではなく、興福寺の僧侶の視点から解説している所がなかなか面白い。 一見客観的視点に見えるが、当時は幕府と大名と寺社がかなり密接に結びついており、この僧侶の視点がそれぞれの派閥よりの意見になっていたりと、寺社も巻き込んでかなりどろどろのずぶずぶになっていた戦乱だったことが改めて思い知らされる。 個人的にはなかなか面白いと思っているのだが、 原因と結果をもっとはっきりと知りたいという方には、結局ずぶずぶどろどろの応仁の乱の顛末のままなのでなんか残念、となるかもなぁ。
0投稿日: 2017.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと書籍の著者はおろか私と言う双方の見識及び、出版‥並びに版元と言う四社人に誤謬(ごびゅ)を拡散する!ので、詳しい記述は避けさせて戴きます。確かに応仁の乱は?内戦では無意味の戦いでした。 「しかし、裏を返すと元々戦国時代は以外に識られてませんが(国際的には)?…蒙古襲来の恩賞を打ち切った1294年(鎌倉幕府為政者北条貞時(時頼の孫で、二度の蒙古襲来を撃破した時頼の子の時宗が…父です)、将軍は鎌倉幕府7代将軍時)の頃から、1615年(大阪夏の陣‥幕府は3(武家政権では安土桃山は含めるも、宮中での執政を選び、専制を敷いた平清盛一族は除きますと5)期目の徳川2代将軍徳川秀忠(しかし、国際的には、豊臣家との共同統治だったらしく、完全な将軍になるのは?…子供で3代将軍の家光の時代までは有りませんでした!、豊臣派の残党狩りと、彼らの再雇用及び‥転職が完遂するのも家光の時代なので尚更です)の時代)の321年(正式には?…320年と8、9ヶ月)ぐらいまでが…国際的には日本の戦国時代扱いらしいです。 唯(ただ)応仁の乱は?、一説によると?…それまで体裁で遠慮していた寝返りや、戦いが凄惨を極めつつ遭った戦いが増え始める戦いになった(要は転換期を迎えた戦いだった)とも、国際的な解釈上の扱いになったそうです」。 以上が私の愚見から述べた見識です!‥のでこれだけは記述させて戴きます。版元や出版社及び著者の3つはおろか現在は非公開の国際的な歴史記述調査関連サイトページを?…ハッキングしてません!からね?…。
0投稿日: 2017.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ〈目次〉 はじめに 第1章 畿内の火薬庫、大和 第2章 応仁の乱への道 第3章 大乱勃発 第4章 応仁の乱と興福寺 第5章 衆徒・国民の苦闘 第6章 大乱終結 第7章 乱後の室町幕府 終章 応仁の乱の残したもの 〈内容〉 室町時代の興福寺の『大乗院日記目録』『経覚私要鈔』をベースに尋尊と経覚という二人の僧侶の視点から大和と応仁の乱を詳細に描いている。応仁の乱の内容は勿論、その前後にもかなり詳しく言及されていて、山城の国一揆等についても良くわかります。高校の授業で使うには詳細すぎるが、教師はここまで知っている方がいいかな⁉室町幕府の弱体化と体面ばかり気にする将軍義政、友情とかメンツが念頭にある武士たち、となかなか面白かったです。
0投稿日: 2017.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ書店でよく平積みしているのを見かけていたのでようやく読んでみたら、確かになかなか面白かった。 著者も語っているが、応仁の乱という名前は聞いていても詳しく知っている人はあまりいない。どう始まって、どう終わったのか。僕もそうだ。(ただ今も京都人が「先の戦さ」と言うと太平洋戦争のことではなく、応仁の乱のことを意味するというのはよく聞く話) 読んでみて思ったのは、この時期、応仁の乱だけではなく、畿内は戦さばかりやっているということだ。まるで平穏な時期など一時もない。 そういう中でも荘園からの収入がなければ支配者層はやっていけないのでみないろいろと苦心している。当然といえば当然なのだが、戦乱中であっても経済活動が滞るわけにはいかない。そういう活動は通りいっぺんの歴史教科書には出てこない。歴史をクローズアップする面白さだ。 当時の京や奈良の様子、暮らしぶり、室町幕府の支配域がほぼ畿内だけっぽいこと、東幕府と西幕府、乱後の将軍並立のことなど、知らなかったことも多く興味深かった。 それにしても思うのは、人間の営みというものの変わらなさというか、普遍性というか。何時代であってもたぶん人はそんなに変わらない。いい歴史書は人間が見えてくる。そこが面白い。
0投稿日: 2017.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログどうしてもイメージが湧かない室町時代のハイライト(?)応仁の乱の概要が知りたくて手に取った。なじみの薄い登場人物が大勢出て来てとても「わかった!」とは言えないけれど入口の前には立てたような気がします。類書をもっと読みたくなった。
0投稿日: 2017.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱と言うと、戦国時代へと繋がる戦乱と言う認識しかありませんでした。 細川勝元と山名宗全の対立、奈良の興福寺の経覚、尋尊の存在感。足利将軍家のお家争い。日野富子。応仁の乱と一言で括っても、沢山の切り口があるのだなと思いました。 全国規模で起きた初めての戦乱。徳川幕府と室町幕府を比べたときに、絶対的な権力基盤を有した徳川家に対して、大名との合議制を有した感じのある足利幕府。長期政権が必ずしも良いとは限りませんが、安定した政治や平和はかけがえのないものだと思います。
0投稿日: 2017.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱という有名であるけれども、分かりにくい戦争を二人の興福寺の僧の視点から分かりやすく説明した良書。この乱は将軍家の家督相続を巡って足利義政の弟と奥さんの日野富子が争ってそれを細川勝元と山名宗全が支援して、義政は眺めていて何もしなかったとイメージされているがそうではなかったのだ。畠山家の家督争いが将軍家や他の有力武将の跡目争いに発展した事であったり、腹黒いイメージの日野富子が争いの仲介役をになったり、傍観しているだけのイメージの義政が彼らなりに一生懸命争いの調停をやったりするように意外と努力をしている事に気がつかされた。だが、そういった努力をしたとしても徒労に終わり、戦乱は11年という長い間続くことになった。原因は先生はおっしゃってはおられなかったんだが、どの家も家督争いばかりでその上戦争でしか解決できないという問題を抱え込んでいたからだと思う(主人公の興福寺の二人を含む)。いや、そもそも持明院と大覚寺という天皇家の家督争い、そして尊氏・直義の兄弟同士の家督争いの上に室町幕府という組織が成立し、3代将軍足利義満は自分の権力を揺るぎないものにするために各地の有力武将の家督争いを利用して自分側に就いた人間を重用する事で権力基盤を確立していった事を鑑みると、その家督争いという地盤がぐらぐらと揺らぎ始め、将軍自体がそれをコントロールできなくなった事で室町幕府を崩壊の道へと辿らせた状態を見れば皮肉としか言いようがない。
6投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか面白かった。 日本史有数の大乱であったにもかかわらず、その実際については戦国時代ほど知られているわけではない「応仁の乱」について、出だしを大和国の視点で説き起こすという新しい切り口で叙述した著者の野心作であると思われる。 ただ、野心作ということもあるのだが表題として『応仁の乱』というのはいささか不正確なきらいがあり、叙述内容からいって『大和国と応仁の乱』または『興福寺大乗院と応仁の乱』とでもすべきだろう。 興福寺大乗院門主にして興福寺寺務(別当)であった経覚と尋尊の目で辿る応仁の乱。それぞれの日記である『経覚私要鈔』と『大乗院寺社雑事記』を主なテキストとし、応仁の乱の前提のひとつである大和国の争乱から叙述を始めるところが目新しくとても勉強になった。 『経覚私要鈔』と『大乗院寺社雑事記』という両者の立場で比較的に応仁の乱全体を見通すことができ、また大和国という守護不設置で衆徒・国民が割拠しながらも敵対したり一揆を結んだりと混迷を繰り返す大和国の特殊事情が興味深いため著者もこの舞台背景にしたものと思われる。 尋尊の『大乗院寺社雑事記』は高校教科書にも登場するお馴染みの史料なわけだが、今回、経覚の『経覚私要鈔』と相照らしてみてそれぞれの性格からくる分析態度の相違にはなかなか興味深いものがあった。 九条家の出である経覚に対し、経覚が将軍足利義教の逆鱗に触れ更迭された後、尋尊が二条家より新門主として迎え入れられたという過去を持つ二人。著者によればその性格も対称的なものであるという。 先例にとらわれず柔軟に対処するが長期的展望に欠け、その場しのぎの対処をすることもある経覚に対し、常に冷静沈着で軽々しく判断を下さず記録を調べ先例により方針を決定しようとする尋尊。悲観的でことあるごとに「神罰が当たる」とか「仏敵」とか口汚く罵るのも尋尊である。 この辺りの視点の相違というのもなかなか面白い。 さて、「応仁の乱」であるが、著者によると東西両軍ともここまで長引くものとして争乱を起したのではないとする。 もともと畠山家の内紛により義就方と政長方に分裂したのが大乱の主要な引き金だったとするが、山名宗全が反細川連合を目的に義就を京都に呼び寄せ、放っておいても義就と政長の御霊合戦では義就が勝ったと思われるのに宗全が味方し、メンツを潰された細川勝元が宗全に対し決起したというのがそもそもの起こりで、それに将軍家、斯波といったお家騒動を持つ連中たちが次々とくっつき、大内や赤松など別の野心を持つ者なども呼び寄せた挙げ句に収拾がつかないまま11年にも及ぶ大乱になったということである。 大乱では朝倉孝景や斉藤妙椿など守護代クラスの活躍があり、それに乗じて下剋上が起こり得たと思いきや朝倉孝景のようになかなか上手く事が運ばなかったり、反面、家臣の意のままにならぬ守護に対し「主君押込」があったり、また、著者が戦国大名のはしりと評価する畠山義就の存在や、山名氏のように親子で東西に分かれたり、裏切りや寝返りがありと何でもありの様相となり、大乱はますますの混迷を深めていくことになる。 最初の頃は仲介の労をとろうとした将軍義政や日野富子ではあったが、金儲けにはしる富子や峻烈な性格であったという足利義視らの存在は混乱に何の足しにもならず、結局、東軍の経済封鎖作戦が西軍方の五月雨の降参を呼び込むことになり、義政が西軍方の諸将をそれぞれ許すことで乱が収束していったとのことである。畠山義就の存在を除外して・・・。 畠山義就はその後、河内国へ転戦し、隣国の大和国の衆徒・国民ら(筒井、越智、古市など)を巻き込みながら推移し、有名な山城国一揆をも生起させることになる。 将軍義政については優柔不断ということだが、記載箇所によってはわざと守護の力を削ぐ謀略を行ったり、戦争終結の見極めを正確に行っていたりと一見矛盾した記述のようになっているが(他の人もこういう記述がある)、そこはご愛嬌ということにしておこう。(笑) 大乱時の大和国は疎開先であったようで、一条兼良をはじめ京より多くの貴族が乱を逃れ奈良にて遊興の日を送ったとのことである。 その中で興味深かったのはやはり古市胤栄が行った「林間」(風呂付宴会)や、お盆時の念仏風流禁止令を逆手にとり、壊れた風呂釜を修理費を捻出すべく企画した風流小屋(日本最初の有料ダンス・ホールとのこと)である。動乱の時代でもなかなか乙でたくましい人物がいたものと感心した。但し、古市胤栄の末路は哀れなものであったが・・・。 また、この時代に目を引くのは僧侶が現代の感覚とは違うことであるが、特に大乱ともなると一層際立ってくる。 将軍家からして義教といい義視といい僧侶出身なのに過激で峻烈な性格を持ち大乱の大きな要素ともなっていたり、斉藤妙椿や経覚の宿敵・成身院光宣など本当に僧侶として仏事に付いていたはずが武将として活躍することになっていたりとこういった感覚の違いにもなかなか面白いものがあると改めて感じた。 大和国からの視点で語るという斬新な切り口の「応仁の乱」であったが、これはこれで面白かったと思う。 だが、「応仁の乱」そのものを網羅しているかというと・・・、どうなんだろう?(笑)
14投稿日: 2017.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ知名度の割にその内容がよく理解できていなかった応仁の乱(1467-1447)の詳細を知りたく手に取った。背景として足利将軍家の影響力低下、興福寺はじめ大和(奈良)を中心とする寺社勢力、守護勢力、管領家の内部抗争など色々な要素が絡んでいるためにわかりにくい構図となっていることがわかる。 戦乱の終結も東軍優勢のままに曖昧な終わり方で1477年に一応終結するもその後のいざこざへと続く。登場人物が多く、その時代の知識も貧相なため理解しながら読むのに少し苦労したが良書と思う。
1投稿日: 2016.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱を分かりやすく新視点で描いたと巷で評判の新書ですが、やっぱり応仁の乱は複雑でロシア文学のように訳が分からん。 南北朝といい室町時代を現代人が理解するのは無理がある。
0投稿日: 2016.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本としたい史料を設定し、それを軸に様々な先行研究や別史料も顧みながら、「知られているようで、然程知られていないかもしれない」を手際よく説く、「歴史関係の話題を扱う新書」としては「非常に“らしい”」感じなのだ。煩雑な事象について、一定の「観測する窓」のようなモノを設定した中で手際よく語られるので、少し夢中で読み進めてしまう感じだ… 「応仁の乱」の複雑な展開…本書を通じて、非常によく判った!!
0投稿日: 2016.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ室町後期、諸大名が東西両軍に分かれ、京都市街を主戦場として戦った応仁の乱(一四六七〜七七)。細川勝元、山名宗全という時の実力者の対立に、将軍後継問題や管領家畠山・斯波両氏の家督争いが絡んで起きたとされる。戦国乱世の序曲とも評されるが、高い知名度とは対照的に、実態は十分知られていない。いかなる原因で勃発し、どう終結に至ったか。なぜあれほど長期化したのか――。日本史上屈指の大乱を読み解く意欲作。
0投稿日: 2016.10.20
