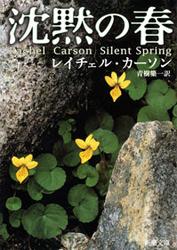
総合評価
(219件)| 51 | ||
| 64 | ||
| 57 | ||
| 17 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間のエゴはいきすぎている。すべてを便利化し、楽に生きようとすること自体が環境を破壊してるのかもしれない
0投稿日: 2025.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ殺虫剤・農薬の自然への脅威をアメリカでの数多くの事例を引いて告発した一冊。殺虫剤は対象以外にも作用し生態系を乱す。直接間接的に人間にも影響を及ぼす一方、やがては耐性を持った害虫が生まれて効かなくなる。天敵や病原菌といった天然素材を使って対処すべきだといった内容。当時は衝撃的だったのだろうが、言ってしまえば一本調子で同じような内容が続くようにも言える構成。巻末の解説で、時代が下がってくると筆者の述べる希望は必ずしも完璧なものではなく、それも自然のバランスを壊すという点では同じ、農耕を営む人類の文明が当初から抱えていたジレンマが噴出しているのが現代だ。という言には全く同感。
0投稿日: 2025.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ1962年に環境破壊の実態について書かれた本です。 読んでいて苦しくなりました。 半世紀以上経って、少しは良くなっているのか、それとも悪くなっているのか? 何方か続編を書いていただきたいと思います。
14投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ. 以前からこの本のことは、環境問題の草分け的存在であると知ってはいました。 読まないまま年月が経ってしまったのですが、先に読んだ科学系名著の紹介本でも取り上げられていたので、この機会に読むことにしました。 『これだけは読んでおきたい科学の10冊』 https://booklog.jp/users/makabe38/archives/1/4005004563 冒頭で著者は、「春になっても、鳥など生物の声が聞こえない」という、架空の土地の話を提示しています。 その原因として著者は、農薬をはじめとする化学薬品の散布を、挙げています。 具体的な薬品名を提示して、それが水や土壌にどのような影響を与えるのか、実際にどのような被害が起こったのかを、列挙していきます。 著者が強調しているのは、製造元や行政当局が「影響ない」と言うわずかな量の薬品でも、投与した地域に大きなダメージを与えてしまうということ。 また、合成してつくられた薬品の影響が長く続くことも、問題を大きくしていると言います。 そして、わずか数種の”害虫”、”雑草”を駆除するために投与していることの無益さ(効果が無い場合が多い)、理不尽さを主張している点も、印象に残りました。 著者は人間に害のある生物を駆除することそのものを、全て否定するわけではないと言います。 その上で、長く深刻な影響をもたらす化学薬品で対処するのではなく、(天敵を導入する等)野生生物間の相互作用を用いて対処すべき、と主張しています。 2020年代半ばの視点から見ると、著者が主張していることは「当たり前」のように思えます。 しかし、この本が出版されたのは、1960年代のはじめ。 この時点でこのような主張をしたということ、そしてその主張が後の世界の主流、正論になったということが、著者及びこの本の大きな功績なのだろうと、理解しました。 生物どうしの関係は複雑で、一つの種を取り除いた時に、予期しないことが起こる場合がある。 ましてや、その土地や水域に住む生物全般にダメージを与えるような化学物質を使うのは、デメリットが大きすぎるし、メリットが無い場合もある。 自然や野生生物に対する、人間の傲慢さを戒める著者の主張に、強く共感しました。 とはいえ、害虫や雑草の駆除は、現実問題として必要なことであるとも、理解しています。 科学技術が発達した現在において、どのような方法が採られているのか? 気になったので、関係する本を探して、勉強したいと思います。 .
0投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ農薬や殺虫剤といった化学薬品濫用の危険性を訴えた一冊。 読む前は専門書だと思っていたのだが、実際はかなり大衆向けの内容。 環境被害の描写が真に迫っていて、読んでいるだけで情景が浮かんでくるようだ。 当時ベストセラーになったのも納得である。 内容自体はかなり極端なので丸々信じるということはできないが(そもそも60年前の作品だが)現代にも通ずる内容が多数あり、単純に読み物としても面白いので読んでよかった。
0投稿日: 2025.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ殺虫剤が手軽でも、安易に使っちゃダメなんだってことを知った。 以前はもっと敏感に避けていたのに、最近ちょっと麻痺していたなと思う。 読めて良かった。
3投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ519.79カソン 環境保護の先駆けとなったレイチェル・カーソンのベストセラー。 自然を破壊し人体をむしばむ科学薬品。これを乱用することの恐ろしさを告白。レイチェル自身、海洋生物学者としての幅広い知識を持ち、深い洞察力から警告を発した。初版本から40年以上経っていますが今なお色あせない名著です。
1投稿日: 2025.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログかつて春は鳥のさえずりで目覚めた。だが今、沈黙が支配する。 農薬が自然界に与える静かな殺意を暴いた。便利さを追い求めた人間の手が見えぬ毒を空と大地にまいたのだ。だが彼女の警鐘は多くの心を動かし環境保護の芽を育てた。 耳を澄ませばあの春の声はまだ戻るかもしれない。守るべきは沈黙ではなく命の声だ。
0投稿日: 2025.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ沈黙の春 改版 著:レイチェル・カーソン (1907-1964) 新潮文庫 訳:青樹 簗一 出版社:新潮社 良書 農薬、殺虫剤などの化学物質が、自然に重大な影響を与えるという警告の書です。 対象となる害虫については、化学物質を用いるとより耐性をもつ個体があらわれて、目的を達成できずに失敗する 一方、想定外であった、動物、家畜、人体になどに影響をでて、 ①個体が死亡する ②個体は死亡しないが、次世代の子孫に影響がでる 子孫ができない、子孫が子供をのこせない ③染色体に異常がでて、予期しない病気になる ④特に、癌:白血病になり死に至る ⑤天敵が死亡することにより、思わぬ種が大発生し、新たに脅威となる 等々 空中散布して、その下の生物に影響を及ぼすのはもちろん、水にとけて、プランクトンや魚類に影響がでて サケの回遊がとまったり、稚魚の大量死亡によって漁に影響がでている 不可逆な進行によって、生態系が破壊されることへの警告。 人間にとっては、予期できぬ自然のプロセスの複雑さを物語っています。 人類の少子化もひょっとして、この化学物質の影響を受けているのかもしれないとおもってしまいます。 目次 まえがき 01 明日のための寓話 02 負担は耐えなければならぬ 03 死の霊薬 04 地表の水、地底の海 05 土壌の世界 06 みどりの地表 07 何のための大破壊? 08 そして、鳥は鳴かず 09 死の川 10 空からの一斉爆撃 11 ボルジア家の夢をこえて 12 人間の代価 13 狭き窓より 14 四人にひとり 15 自然は逆襲する 16 迫り来る雪崩 17 べつの道 解説 ISBN:9784102074015 判型:文庫 ページ数:400ページ 定価:750円(本体) 1974年02月20日発行 2004年06月15日62刷改版 2014年06月05日76刷
33投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ殺虫剤の乱用による自然環境への影響が統計的データを元に書かれた本。一種類の害虫を駆除する目的で殺虫剤を散布した結果他の益虫、鳥、家畜動物、魚など多くの動物も数を減らしてしまう結果となってしまう。本作が描かれたのが1960年代で殺虫剤が本格的に使用されてから間もないが作者はすでに殺虫剤の濫用の危険性を訴えていて時代を先行しているなと。殺虫剤全てが悪かと言われると実際に蚊やダニを駆除することでマラリアやチフスに対し効果があったのは事実。両面から評価することが大事。作者は批判するだけでなく、細菌やウイススを使用したり、動物を利用したりと代替案も提案していて現代においてどれくらい反映されているか気になる。虫が殺虫剤に対しどんどん抵抗を持つ様になることを考えるとただ薬の効果を強くしていくだけではジリ貧になってしまうのでどこかでやり方を変えないといけないのは事実。
0投稿日: 2025.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『センス・オブ・ワンダー』から本書に入る。著者が亡くなる2年前の1962年に米国で出版され、その後、日本でも重版された。内容はものすごく重い。農林業の生産に害をなす昆虫などを殲滅するためにばら撒かれた化学薬品だが、害虫だけにとどまらず、生態系を構成するあらゆる生物に影響し、春を告げる鳥のさえずりさえ聞こえなくなった=原題Silent Spring。ある種の化学薬品は、放射線による影響と同じく、突然変異や癌化の引き金になるという。化学薬品の使用が60年代と比べ限定的になったが、今でも我々に影響があるのでは?
0投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/webopac/BB01678208
0投稿日: 2025.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ沈黙の春、それは膨大な歴史によって紡がれ、均衡を保ってきた大自然の終わりを意味している。2025年現在、PFASという言葉を最近よく耳にする。これは農薬や工場排水、米軍基地で使われる消火剤によく含まれる化学物質で、沈黙の春に登場する化学物質と同様の性質を持つ。そしてそれは日本各地の地下水や水道水で基準値を大幅に上回る量で確認さている。言い換えれば、人体に既に被害が出ていると言うことである。岡山県吉備中央町での住民による民事裁判の事例もまだ新しい。沈黙の春はまだ私たちの近くにいる。
0投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ『三体』の主要人物の人生に大きく関わる作品だったので気になって購入。 当初学術的著書と知らずに購入し、軽い気持ちで読もうとしたら専門用語が多くいつもよりスローペースで読み進めた。 聞きなれない用語は難しかったがデータや分かりやすい論法を用いて丁寧に化学薬品の危険性を説いている。 本作を読んだことで『三体』のラストにより深い意味合いを感じることができた。
1投稿日: 2025.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生の英語の教科書で本書の存在を知り、当時は読みたいとは思わなかったが、あれから20数年が経ち、俄に読んでみたい気持ちが沸き起こった。 60年も前に出版された本だが、当時のアメリカの農業の実態に驚かされた。 次からから次へと強力な農薬を使いまくり、それが農産物内部へ蓄積することを無視し、さらに人へ発病、様々な二時汚染。 本来害虫から農産物を守るための農薬が、その成分が強すぎるあまりに農産物が耐えきれず枯れてしまうという本末転倒さ。 そして農薬にも抵抗を示す害虫たちが繁殖し、それが更に有害な農薬を生み出すことに繋がる負の連鎖。 白血病や内臓疾患、皮膚病が爆発的に増えたのは、まさしくこの農薬が原因だ。 今でこそ低農薬、無農薬農法が市民権を得てきており、私たち国民も農薬への意識をを持ちながら消費活動を行うようになってきている。 ただ、当時のアメリカの時代背景を考えると、 よくもここまで農薬のいろはを調べ上げ、世に向かって発表したなと、その勇敢さに舌を巻く。潮流に逆行する彼女の活動はいかほどセンセーショナルだっただろう。 カーソンは本書で、農薬が人体をはじめ農産物、昆虫などの生物に与える影響を指摘するだけでなく、農薬を極力使用しない具体的な方法も提案している。 P103 雑草に悩まされたら、植物を食べる昆虫の働きを注視してみる。 食物連鎖の流れをよく見てみる。 P169 アメリカでヒアリを絶滅させるために使われたヘプタクロールは、DDTに匹敵する劇薬で、水棲生物に害を及ぼす。 陸に撒かれた薬物は、最終的には流れ流れて水に行き着き、そこを汚染する。 P215 当時、アメリカの農薬に記載されていた使用方法などは文字が小さく、農夫たちはよく読まないまま適切量を無視して過剰に使用していたと。 レタス栽培現場では、一つだけで十分なのに八つも混ぜて使っていたなどの殺虫剤乱用が起きていた。 実際私たちの口に入る農産物の農薬残留量は明確に分からず、それが多種多彩なため、この程度なら安心だ!と言いきるのは難しい。 P220 昆虫の間に病気を発生させ、防除するやり方もある。 危険度の低い農薬を使い、非科学的な方法の開拓に力を入れることを、カーソンは推奨している。 最後に解説で、興味深い事柄が書かれている。 害虫Aを除去する目的である薬剤を使ったとする。それが成功し作物Bが虫害を免れた。 しかし害虫Aによって食い殺されていたC.Dという害虫が抑制因子を取り除けられて爆発的に増加し、新たな害虫となって作物Bに襲いかかる。 という例が多数あるという。 生態系の恐ろしさを痛感した事例だった。
0投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ超苦しい 古い考えで偏見も入ってるのかもしれないけど、少なくとも地球に対して優しくなれるはず 気になったなら読んでみるべき
0投稿日: 2024.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義によって作られた価値観にありとあらゆる欲望を掻き立てられ、みんなが手を伸ばしてしまって(しかも簡単に届いてしまうから)、生産性や効率性を中心に回転しているような今日が、この本(1962年出版)の中の問題を改善できたとは全く思えない、絶望。 追伸 さいきん休日に外へ出かけると、(特に都会には)〈娯楽です!〉と看板を下げているような場所がたくさんあってつかれます。そこに行くことが正解だと言われているようでとてもつかれます。 もしかしたらわたしは人生の中で、木や草や花や虫や鳥の名前も知らずに死んでいくのかもしれないと思いました。それはわたしたちにとって、もしかしたらとてもさみしいことなのではないかと思います。
1投稿日: 2024.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「除草したい草があるなら、下手に除草剤を撒くのではなく、それらを食べる虫をやるとよい。」 『生命をコントロールしようと殺虫剤のような武器に訴えるのは、まだ自然をよく知らないためだと言いたい。自然の力をうまく利用すれば、暴力などふるうまでもない。必要なのは謙虚な心であり、科学者のうぬぼれの入る余地などは、ここにはないと言ってよい。』 ブリーイエ博士 『自然のなかにこそ、頼む味方はいるのだ』 ビスケット博士 『自然環境そのもののなかに、生物の個体数を制限する道があり手段がある場合が多いことを知らなければならない。そしてそれは人間が手を下すよりもはるかにむだなく行われている。』 アルエット昆虫学者 「森の中でいとまれる自然同士の関係をきずつけないよう守り育てる」 自然は、うまくできている。だから、人がむやみやたらに手を入れるべきではない。 人間本位であってはならない。
0投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ第64回ビブリオバトルinいこまテーマ「ダブルバウト」で紹介された本です。チャンプ本。 2019.5.26
0投稿日: 2024.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログあらすじ 鳥や小動物の鳴き声が溢れ、色とりどりの自然が人々の目を楽しませる、そんな当たり前の風景に突如暗い影がしのびよってくる。 今までに経験したことのない病気が流行り出し、生き物は死滅し、草木は枯れ果てる。 もう生き物も、自然も、春を彩ってはくれない。まさしく沈黙の春である。 原因は一体何か、それは他でもない、人間が自ら招いた災禍であった。 人間は、科学技術の進歩によって、さまざまな化学薬品を作ることができるようになった。 それらは当然自然界に存在しないし、中には強力な毒性を持つものも多々存在する。 その中の農薬、殺虫剤は、害虫の駆除や雑草を根絶やしにするために、自然に向かって使われる。 そして強力な毒性により、向けられた生き物を無差別に殺戮してしまう薬だ。 使った結果、どのようなことが起きたか。 死滅させたい害虫は耐性をつけて生き残り、ターゲットでない多くの生き物は、次々と死んでいった。 そして、それだけではない。 わたしたち、人間が食べる、自然界の多くのものに、毒が残留することとなった。 人間は、長い年月をかけて構築された自然の緻密な均衡を軽視し、コントロールすることができると自惚れてきた。 しかし結果的には、コストをかけて、すぐには戻らないほど自然を痛めつけ、自分自身の首すらも締め上げようとしている。 自然の営みを利用し、自然を痛めつけすぎることなく、人間に味方するようにコントロールする、生物学的コントロールこそ、とるべき道ではないか。 感想 読み終わった時には、人間というのはなんて自分勝手な存在なのだろうか、と思うと同時に、 その恩恵を受けずに生きることはもはやできないというありふれたジレンマに苛まれました。 最後の評論家のコメントは、大変参考になりましたが、さすが評論家?問題提起ばかりな感じがして、どこか他人事感がぬぐえないものだったような気がします。(ただ、考え続けることが大切だということなのかもしれません。) その点、化学的コントロールよりも、生物学的コントロールこそ、取るべき道というカーソン氏の提案の方が、現実的だ個人的には思いました。破壊が進んでいる今、何もしないわけにはいきませんからね…。 この本を読んでいて、興味深く読み進めることができた点は、特に自然の営みを詳述しているところでした。 出発点が、殺虫剤であることが非常に残念ではありますが、その後どのように影響が出るのか、虫も、草木も、小動物も、魚も、人間まで、詳しく書いてあります。 自然とは繋がりのあるものであり、人間もその営みの恩恵を多大に受けており、切っても切れない関係であることを強く感じました。 まさしく、自然界には、単独で存在するものは何一つない、という言葉そのままでした。 自分に何ができるのかは、難しく答えは出ていませんが、人間も自然界に存在している以上は、単独で存在するものではないということです。 できる限り環境を傷つけないように日々振る舞うことはもちろん、人と接していく中でも、気をつけられることはあるかもしれません。 深い結びつきがあるのであれば、相手を傷つけることは自分を傷つけることになるかもしれないからです。 自然環境のことは勿論、読み方によっては、人に優しくなることができる本でもある、と思いました。
1投稿日: 2024.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
知ってはいたけど読んでなかった名著。『三体』での重要図書なので手に取る。 最近読む本は戦争を挟むからか、DDTが出てくることが多い。ここまで毒性があり、生態系に悪影響を及ぼすとは思っていなかった。 人間には皆殺しの欲求がある。何もかもを消してしまえという誘惑を制御できない。 選択制スプレーという手間よりも一斉散布で根絶やしにする。 落語「百年目」の赤栴檀と南縁草がふと浮かぶ。みすぼらしい雑草が、立派な木には必要だった。そういう目に見えない関係性をたやすく見落としていいとこ取りをしようとしてしまう。 事実を報告する人の信頼度の問題は解決の難しい、本質的な問題だ。真反対の意見のどちらからも信頼され信用される第三者はなかなか見つかるものじゃない。 実験室の中で、限られた動物を使って、人工的な環境下で調べた薬剤の効果は限定的な結果であるにもかかわらず、自然環境に持ち込んでも同じ結果になると断定するのは非科学的という指摘に反論の余地は無い。 またヒアリの食性一つとっても、五〜六十年経てば食性も変わるという。しかも世代交代のサイクルによって、抵抗力を持つ。常に変化するものを対象に、永続的に使える薬剤を生み出せようはずもない。 害虫に悩まされない理想の環境を目指し、製造不可能な完璧な薬剤を生み出すために膨大な労力と経費を使って、未来に蓄積する毒を撒き散らす… もう人間はダメなのか。もっと高位な生物に丸投げして滅亡するべきなのかと絶望してしまう。が、レイチェル・カーソンはそんな安易な結論は結んでいない。 細菌や天敵を使う防除は、恐らく今では別の悪影響が指摘されてるもので、積極的に選べる方法ではないはずだが「特効薬」ではなく、「生態を調べ抜いて発生数を抑える方法を探すこと」こそ、遠回りに見えて最良の近道だと著者は言いたいのだと私は了解した。 読んでよかった。 手放しで信じ込んでいた安全性の正体を明らかにする事が出来た。 あとがきは、一理あるけど、やや批判的というか身も蓋もない感がある。
2投稿日: 2024.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ農薬や除草剤や殺虫剤は人間から見て有害な生物を排除する殺すために開発された。現実は、人間にとって有害ではない生物をも殺してしまい自然界のバランスを破壊した。牧草を作るために蒔いた除草剤によって牛や羊がその除草剤の毒によって死んでしまう。一時は効果があっても、耐性を持つ蚊やハエの昆虫たち。毒は害虫だけではなく益虫いわゆる天敵をも殺してしまう。その被害は人間自身にも影響する。春になっても花が咲かず虫もいない鳥もいない「春」殺虫剤や除草剤や農薬に頼る人間に対する警告です。2024年7月7日読了。
6投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に書かれていることが当時、「センセーショナルであった」ということを知ることに価値があった。あたり前のことがあたり前ではなかったのだと
0投稿日: 2024.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
殺虫剤・除草剤の危険性や、環境を保護しながら人間の暮らしを守るためにどうすればよいかなど、米国での実例をもとにしてとりとめなく綴っている本だった。人々に危険性に気づいてもらうための内容だ。 過去に無謀なことをして、色んな失敗や意図せず失われた動植物の命や、人間の健康被害がたくさんあったことがよく分かった。空から薬剤散布するのは読んでいるだけで怖い。 農業の妨げになる虫や、場合によっては人の命を脅かす蚊など、人類が生きている限り問題として残っていくのだろうなぁ。生態や全体の環境を研究して対策が生まれていくのが興味深かった。
0投稿日: 2024.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時の考えではセンセーショナルでも、今にも通じる部分はあると思う。環境自然に興味を示したからこそ、読むとより深く考えれる話だと思います
0投稿日: 2024.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今でこそ当たり前の知識でも、1960年代当時からするとどれだけセンセーショナルな内容だっただろうと思う。
0投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログそれぞれの化学物質が、水や動物、土壌や植物、人に与える影響をはじめてファクトをベースに指摘して、今の環境問題のムーブメントを作った本。今の視点で読むと当たり前に思う、ということは、それだけこの本をきっかけに、様々な人の努力が時代を動かしたんだと改めて感じた。
0投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ環境問題を考える際に重要な本の一冊。著者はDDTと呼ばれる化学薬品に警鐘を鳴らす。なぜなら、この化学薬品を使用することで、自然本来の秩序が乱れてしまい、そこに住む生物のみならず、人間にもあらゆる面で危害を加えてしまうからである。化学薬品は確かに、効率を追求した末に誕生した発明品で、一時的には恩恵を受ける。しかし、長期的には人類に深刻なダメージを与えてしまう。そこで、著者は自然の力をうまく利用して、いかに自然環境になるべく負荷を加えないのかを考えていく。
0投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950年代のアメリカの農薬や殺虫剤の使用はこんなに大らかというか、ノーガードだったのかと改めて驚かされる。まだ環境保護や公害という概念も薄かった時代。 著者のレイチェル・カーソンのような人々の根気強い活動があって、人類の環境への意識がここまで変化してきたのだろう。
0投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1755173931877802204?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2024.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ塩化炭素系などの薬品の問題点は確かにそうなのだろうけど、自説へのバイアスが思ったよりも強い。代替え案の是非も大いに疑問があるし。 欧米の文章は多くがそうだけど、同じ事が何度も繰り返し書かれていて非常にくどいし飽きてしまう。
0投稿日: 2023.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
害虫防除のために化学薬品を使うことによる生物濃縮の恐ろしさをたくさんの実例とともに説明する前半。 後半は人間への影響の出方とその他の防除方法について。今の科学ではどう解釈されているのだろう?と思うところがいくつか。たとえば、読み間違えているかもしれないが、化学物質が染色体異常を引き起こすことから、白血病、小児がん等への影響を示唆している点。また、外来種に対して天敵を連れてくることで自然に悪影響を与えず防除することや、雄を不妊化させる薬品の使用を比較的肯定的に書いている点。現代視点での解説を読みたい。
0投稿日: 2023.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代、人類の環境に対する暴挙に対して警鐘を鳴らした歴史的名著。主に農薬濫用による生物濃縮の危険性について提唱されています。 地球の歴史の中で「環境が常に生物を変えてきた」が、この数十年の間で「生物(人間)が環境を変えている」前代未聞の事態が生じているという説明がとても印象的でした。 内容に重複感はありましたが、当時はあらゆる危機的な状況を踏まえて説明しないと政府に取り合ってもらえなかったんだなと感じました。このような時代に化学物質濫用の危険性を主張した著者には頭が上がりません。
2投稿日: 2023.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ化学物質の怖さが滔々と綴られていて、正直全ては受け止められませんでした。何かを批判する事は簡単でも、確固たる代替え案がないと納得しきれないなぁ、、とも感じます。 自然界への影響がどのように広がっていくのか学びは多かったですが、自然のサイクルがこれだけ繊細であればこそ、外来種を使用した生物学的な防除方法にも危険があるのではと思いました。 モヤモヤとした気持ちを最後の解説で解消してもらえたので、是非解説まで読み切ることをおすすめしたいです!
1投稿日: 2023.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでみたいと思いながらも、科学書であり翻訳本であることからの読みづらさ(めっちゃ読みにくかったー)で何度も断念していた本書をついに読み切った! この本を読んでいて感じていた違和感というかモヤモヤを全て解説が解消してくれた。これから読む人がいれば、是非是非解説も読んで欲しいなあ。 レイチェル・カーソンは本書で化学薬品の大量撒布の悲惨さと化学薬品に頼らない生物学的コントロールという方法を提示している。化学薬品の大量撒布が人間に全く利益を及ぼさないことは言うまでもないが、それに代わる生物学的コントロールが解決策になるという彼女の主張には違和感を感じた。彼女は化学薬品が自然の均衡を崩したために副作用が生じたにも関わらず、同様のことが生物学的コントロールではおこらないとなぜ言えるのか私にはわからなかった。(解説でこれも示唆されていた。)また、彼女は何度か「自然の征服」という考えは愚かであると述べているけれど、彼女もまだその考えから抜け出せていないように感じた。 解説では、人間の文明の歴史からの考察が書かれていて、本書で感じた私のモヤモヤは一気に解消された。まだ、レイチェル・カーソンは木を見て森を見ずのように、全体を見れていなかったのではないかと感じてしまった。それとも、これが西洋と東洋の考え方の違いなのか、、?
0投稿日: 2023.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう理系の評論めいたものを読むのは初めて。(理系なのに…!) 一冊を通してずっと「農薬など人間のエゴによる発明品がいかに自然に悪影響を及ぼすか」ということを書いているから、たまに退屈に感じる時もあったけど、興味深い話も多かった。 特にX線や放射線を照射されると、なぜがん細胞ができるのか?という話や、農薬などを使わずに害虫を防除する方法などはすごく面白かった。 X線でできるがん細胞というのは、照射によって細胞への酸素の供給が阻害され、クエン酸回路が回らず、ATP生成ができないため仕方なく原始的な代謝手段である解糖を細胞質基質で行うようになったものらしい。本来の方法でエネルギーを生産できないため、様々な不都合が生じて結局これががん細胞になるらしい…これだけで面白い…! 理系、特に生物を高校・大学で詳しくやった人には是非読んで欲しい一冊…!
10投稿日: 2023.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログDDTの危険性をいち早く告発し、世界的禁止運動と環境保護のきっかけとなった名著(平塚博子先生) 日本大学図書館生産工学部分館OPAC https://citlib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=1000245718&opkey=B169881667599219&start=1&totalnum=5&listnum=3&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00000
0投稿日: 2023.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ数の増えた害虫を排除するために農薬や殺虫剤をバラまいたことで、鳥や魚といった動植物が死に絶えた挙げ句、目的の害虫は天敵がいなくなりかえって数を増やした、というアメリカの大失敗が事細かに記されていた。 似たような記述が続いて冗長に感じる部分もあったが、それだけ当時のアメリカの薬害の被害が大きく、筆者が焦りと怒りを感じていたのかが伺える。 こういった失敗の反省をもとに今の社会が成り立っているのが分かった。
1投稿日: 2023.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ小6の理科の教科書に載ってた著者が隣のクラスの担任の先生に顔が似てると思って、図書室で借りて読んだ。こんな生意気なくそがきが読んでもめちゃめちゃ良かったし刺さったから何回も読みたいと思って本屋さんで買った。ちょうどその頃総合の授業で地球温暖化っていう言葉を知って、自分って目の前のことしか知らないんだって思った。自分の知らないところで何が起こっていた・いるのか、これから起ころうとしているのかを知ろうとすることの大切さを知った。それは自分だけじゃなくて国家レベルで起こっていることも同様 当たり前だと思っていたことがそれは回り回って未来の自分に降りかかる。今の行いは、何により起因し且つ何に影響を与えうるのか、関係ないことないで、と 読み返せば、今も崩れた生態系を取り戻すべく苦労している人は確実にいる、厳密な生態系は一度崩れるともうう難しいんだから!!地球に住んでいる限り向き合って取り組まなくちゃいけない。 SDGsという言葉がで始める何十年も前から著者は環境について喫緊の問題であることを勧告し続けたことも知ってたら今後の活動一つひとつに責任が持てるね。 読み終わったその足でセンスオブワンダー借りたよねえ
0投稿日: 2023.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA6923629X
0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスオブワンダーが好きなのと、サステナビリティに興味があり、環境問題の古典ということで読んでみた。 意識高く読んでいるつもりが、過激な化学薬品による害虫駆除により大きな問題が生じているくだりを読むにつけ、3ヶ月有効とうたわれた強力G対策スプレーを使っている身を反省させられた。 強い薬物では他の生物にも影響を及ぼすため、生物的対処をとるのが良いという。薬物対策にはお金がつくが、生物的研究や影響調査にはお金がつかないという話は、営利企業と政治の癒着が垣間見えた。 古い本だが、状況は大きくは変わっていない。 私はこれからもスプレーを使い続けてしまうだろう。 それでも、こうした話は頭の片隅に置いて意識していきたいと思う。
2投稿日: 2023.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ殺虫剤の発明によって、生態系が壊れていく世界と、その解決策を提示する。 土壌、川、動物、鳥、人体と、特定の害虫を殺したいがために蝕まれる生活圏。 かなり前の書籍だけど、読むと普段の生活意識が間違いなく変わる(かも)。 とりあえず殺虫剤と防虫剤、使わないようにしようと思った。
0投稿日: 2022.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ重い腰を上げて時間はかかりましたが読了。 60年前に書かれた本ですが考えさせられることはたくさん。生きて行く上で欠かせない水や食糧が農薬や化学物質で汚染されているというのは恐ろしいこと。花や木は枯れ、虫の羽音や鳥が鳴かない生命の失われた春が来ることがどれほど寂しいことか。 海も大地も手遅れなほどに汚染されている。けれど美しい自然に触れた時に感動したり癒されたりする気持ちを人は忘れないと思う。できるだけ後世に残したいし守りたいはず。
3投稿日: 2022.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ業務上、人々の生活と自然保護との軋轢など考えることが多いものの、正しい知識をつけるための書籍にどれを選べばいいか分からず、まずは古典に学ぼうと思い読んでみた。 有機化合物の恐ろしさに警鐘を鳴らした本書は当時としては画期的なものだったと思うし、今でも学べる内容や考えさせられる内容は多い。ただ、害虫の天敵を移入させることを肯定的に捉えた内容など、当然のことながら古い概念も散見された。生態系について考えるきっかけの書物としてはともかく、情報は新しいものを常に取り入れなければいけないなと思う。 あと、同じような内容が延々繰り返されているように思えて、少し読み進めるのが辛かった。
1投稿日: 2022.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は農薬の恐ろしさが実例を上げてつらつらと書かれている。 少し、エセ科学ものにありがちな妄想ストーリーじみているが、 一部は間違いのない事実だろう。 現在は目にすることのあまりない非常識な世界が描かれている。 ひとつ勘違いしていたが、この本はいわゆる自然保護の本ではなかった。 反・化学防除であり、天敵や病原菌を用いた自然防除はむしろ推奨していた。 現在の生態系保護の観点からいうと、後者のやり方もなかなか難しいとおもうが…。 現状はどうなんだろうか。
1投稿日: 2022.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ農薬の害の有無は、農薬の使い方次第なのだと思う。 人はより便利さを求めた結果、実際に害をもたらしたわけでもない生物を殺め、回り回って私達人間に災難が降りかかった。それを私たちは学べているだろうか? 何よりもそれが本当に正しい行いなのか?常に考え、取り扱ってる製品が何かを知るという義務があるのではないだろうか。 農薬という最終手段を行う前に、天敵や予防対策を行うということを私たちは積極的にやるべきだ。 それは農薬に限らず全てのことに当てはまる。
1投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間に都合良くなるように開発した化学物質に、結局は人間が毒されてしまう。個人が死に至るまでは想像しやすいけれど、自然界の均衡を崩してしまうと人間全体、その他の生命全体の存続の危機に至る。 下手に介入すると、得てして悪い結果になる。経済学のアダムスミスの言葉の「見えざる手」は、自然界にも通ずるのではないかと思いました。
3投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ220131*読了 Clubhouseで懇意にしていただいている方の人生を変えた3冊をお伺いし、ご紹介いただいた本。 とても有名なので知ってはいたけれど、重いテーマだろうからとなかなか手を付けられていなかった一冊。 子どもを持つ今、このタイミングで読めてよかったと思う。 1960年代に書かれた本だけれど、まったく過去の出来事ではなく、むしろ技術が進んでいる今だからこそ、より恐ろしいことになっているのではないかと、それに気づいていないだけではないかと、怖くなった。 当時もこんな恐ろしいことが起きていたのかと、震える思い。 美しい草花が、小鳥のさえずりが、動物たちの命が…そして人間の生命さえもが奪われていく。 こんな悲惨なことを繰り返してはいけない。 今こそ読むべき本だと思うし、環境への配慮が意識されつつあるからこそ、一人ひとりがどんな選択をするかが肝心だと思う。 農薬をできるだけ使わないもの、環境への負担が少ないもの、そういう商品を購入すると決めるだけでも、少しずつでも世の中の考えは変わるはずだから。
1投稿日: 2022.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学を環境専攻でいこうとおもったときに、環境に興味があるなら読むべしと言われて手に取ったことを思い出します。今回は自分を振り返るために再読。
1投稿日: 2021.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然は、人類が生まれるよりもずっと前から存在している。その自然を人間が作り上げたもので征服することは不可能である、ということをたくさんの例をあげて訴えている。
2投稿日: 2021.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログヒトによる自然への一方的な介入は、当然の帰結として自然界のバランスを掻き乱すことに繋がる。例えば一部の害虫を駆除すると、その害虫によって抑制されていた別の生物が蔓延ってしまう。また、昆虫や細菌はライフサイクルが非常に短いため、一時的に薬剤で駆除することが出来ても、一部は変異により薬剤耐性を獲得しやすい。 人間の目的に合うように改良された作物は、その分、本来の自然の中での姿から逸脱する。結果として更なる人間による介入と保護が必要になり、年々その程度は増すばかりである。人類は介入によるジレンマと一生付き合わなければならない。 まだ基礎研究が十分になされておらず、農薬利権から世論と政府ののサポートが乏しい中、化学薬品農薬の危険性を強く訴え続けたカーソン氏の尽力に感謝したい。
2投稿日: 2021.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間の快適さや農業のため、人類は除虫、除草のための化学薬品を開発した。最初は効果が上がるものの、これを上空から撒くことで、ターゲット以外の植物や水に、DDTなどの有害な化学物質が残り、その地域に生息する鳥や動物が死滅するなどの被害を及ぼす。 しかも、虫は毎年現れるため、繰り返し何度も使ううちに、目的の虫には耐性ができる上、有害物質はその地域に蓄積されていく。 今でこそ化学薬品の怖さは一般的にも知られているが、この本を1950年頃に出して、問題を指摘し、人類に警鐘をならしたレイチェル・カーソンは凄い。 一方で、化学物質の危険性は認識しつつも、今も農薬など身近なところで多用されている。個々の食品や虫除けなどの商品での使用量は基準の範囲内だとしても、日々、沢山のものを口にしたり、触れたりしている私たちの体内には、知らず知らずのうちに毒性の高い物質が蓄積されているんだろう。 個人で気をつけられる範囲を超えた問題だとは思うが、最近は無農薬農法にこだわる人も増えている。一人一人がそうしたことにもっと関心を寄せることで、危険性が少しでも減らせるのだと信じたい。
11投稿日: 2021.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ1970年代。人間の経済活動が海、森、土壌そして人々の生活をどう破壊してきたかを解説している名著。その裏には人々の認識の甘さや関係者の利害が複雑に入り組んでいる。 環境破壊から見えるのは、人間の過ちと試行錯誤の歴史だと思った。害虫駆除ひとつ取ってもただ「早く」「簡単に」解決するからといって、生態系に有害な化学品を使うよりも、生物の営みをしっかり理解した上で、自然になじむ解決策が長期的には自然を保てる、というところは納得。ただ、一般の人の日常生活の中では現実としてすぐ解決できる化学的な薬品の方が手近だったりするので、普段の生活の中でできることにも話を広げてほしかったなあと思ったりする。
1投稿日: 2021.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容がいまいちよくわからなかったけど、例がたくさんあったからわかりやすかった。自然を人間が支配する時、いろんな動物の気持ちを考えていきたいなと思いました
1投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログとりあえず殺虫剤の恐ろしさや、いま口にしているものが本当に安全かどうかを考えさせられた。外国産のものは特に怖いと感じた。国産のものがなぜ安心で、外国のものが不安があるかを明確にしてくれる本です。 ただ、全体的に同じようなことの繰り返しにしか思えなくて、科学があまり得意ではない僕は飽きてしまいました
1投稿日: 2021.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の経済活動がいかに自然環境に影響を与えているかを指摘した名著ということで購読。 日本でも、太平洋戦争後にアメリカから持ち込まれたことで有名な殺虫剤のDDTを中心に、それが土壌も水も汚染し、本来人間を守ってくれていた虫を絶滅させ(挙句、殺したかった虫は耐性を付けて大量発生したり)、人体、そこから生まれた子供たちを侵しているということを詳細に解説している。 止めた方がいいのは分かっているのに、利権やら何やらで誰も指摘しない。これも資本主義の悪しき面か…願わくば、ではどうするのかということについて著者の考えを聞きたかったというのはある。しかし、日本での初版は1964年、その時点でこれほどだから、それから人間はどれだけ自然と自分たちを痛めつけてきたかと思うとゾッとする。。
2投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、米国の生物学者レイチェル・カーソン(1907~64年)が1962年に発表し、DDTをはじめとする農薬などの危険性を、鳥たちが鳴かなくなった「沈黙の春」という象徴的出来事を通して訴えた作品『Silent Spring』の全訳である。日本語訳は、1964年に『生と死の妙薬―自然均衡の破壊者<科学薬品>』という題名で出版され、1974年に原題をそのまま訳した『沈黙の春』として文庫化された。 世界で初めて環境問題に目を向けさせたその思想は、人類の歴史を変えたものと言われ、カーソン女史は、米国誌「TIMES」が1999年に発表した「20世紀に最も影響力のあった偉大な知性」20組24人に、ライト兄弟、アインシュタイン、フロイト、天文学者ハッブル、DNAの二重らせんモデルのワトソンとクリックらとともに選ばれている。 また、本書は、米国の歴史家R.B.ダウンズが1978年に発表した「世界を変えた本」27冊に、『聖書』、ダーウィンの『進化論』、マルクスの『資本論』などとともに取り上げられている。 本書によって農薬の残留性や生物濃縮がもたらす生態系への影響が公にされ、それにより、米国はじめ各国において農薬の基準値が設けられるなど、環境保護運動が世界中に及ぶことになったが、本書発表から半世紀の間にも、人間の文明は進歩し(それ自体は良いことのはずなのだが)、そのために、生態系の破壊に限らず、地球温暖化や(バイオテクノロジーによる)生命への挑戦など、当時は想像すらしなかった新たな問題を生んでいる。 60年前に発表された本書の内容自体は、今となっては広く知られたことであるし、また、一部には後に疑問符が付けられた部分もあるのだが、今我々が本書から学ぶべきは、一部の人間しか疑問を持たなかったことに正面から取り組み、それを明らかにし、その問題を世に問うたカーソン女史の姿勢なのだと思う。
4投稿日: 2021.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ農薬、化学薬品によって無差別に虫や動物、植物等が滅びてゆく。 1970年頃の研究結果の話しだが今は? 何が良い悪いの話しではないと思った。農薬や化学薬品で助かった事もたくさんあるだろうし、この本に書かれているようにめちゃくちゃになってしまった事もある。 ただこれからは普段使用している製品を見直し環境に配慮していこうと思った。
2投稿日: 2021.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログページをめくるごとにより強い農薬が登場し、ドラゴンボール読んでるんかなと勘違いしました。 内容はアメリカに関してだが、近年は日本も農薬大国として問題になっている。最近見た記事ではADHDの原因となる農薬を日本は未だに広く使用しているという。農薬のみならず環境破壊は深刻な問題である。幼稚園児ですら自分が汚したものは綺麗に掃除に努めるが、どうも大人は汚したままでも許されるらしい。その汚染を掃除するのは今の幼稚園児だと思いますが。 この本と美味しんぼを読破すると偏ってはいると思いますが、環境破壊について学べるかと。
3投稿日: 2021.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ途中。なかなか読み進められないけれど。自然環境に対しての把握しておくべきことが書かれていると感じる
1投稿日: 2021.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ農薬や殺虫剤の悪い面は書かれているけど、反対のいい面については一言も触れていない。物事はどちらの面もみないといけないのでこの本を読んで無農薬信者にはしるのは危険だと思う。
4投稿日: 2021.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年 30冊目 『沈黙の春』 殺虫剤はその特定の害虫だけじゃなくて他の生き物や人間の生命にも影響を及ぼしてる。化学的コントロールではなく生物学的コントロールが進むべき道だっていう話。 自然の均衡を人間の欲が壊して結局ブーメランを受け自滅がかってる所はナウシカを想起させる
1投稿日: 2021.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ農薬=悪とは言っていない。自然のコントロールを壊さないことが大事。ただ農業自体が自然に手を加えるものなのだから、スタートですでにコントロールを乱していることにも注意を払わなければならないと思うのだが、そういった記載はない。
0投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ私には難しい、けれどたくさんの生き物のデータや世界中の場所から情報を集めていることがうかがえて、知的に刺激される面白い本だった。 終始、人間の作った農薬、殺虫剤の恐ろしさを説いている。 殺虫剤、除草剤は狙う虫ばかりでなく、魚や鳥、ニレの木など環境全てに強い影響を与えてしまう。なぜなら生き物は単独で存在しているのではなく、他の生き物に食べられたり影響しあって環境が作られているからだ。また減らしたい虫自体は抵抗力を持ってしまう。天敵の方が薬にやられてしまい、減らしたいはずの虫が増えてしまい効果が薄くなる。 私の家庭菜園のプランターでも毎年アカダニに悩まされていて、昨夏はじめて農薬を使った。確かに一時的には減ったが、しばらくすると復活していたし、何よりパッケージの使用方法に使用回数の制限が厳しく書かれていて怖かった。(ちなみに使用できる回数よりアカダニの方が圧倒的に強かった) 本と符合する。 この本が書かれていたのは1964年とのことだが、その後のベトナム戦争で枯葉剤が使用されて、自然環境だけでなく人間にも甚大な悪影響を与えていたことを知り、ショックだった。この本であんなに何度も何度も危険性が警告されているのに。 また悪者のDDT、戦後の日本人にシラミ駆除のため振りかけていた気がするが、それは大丈夫だったのかな。 終わりには化学薬品に頼るのではなく、別の国から天敵を取り寄せる方法などが紹介されている。 けれど今度は外来種の問題も頭をかすめるし、あとがきでは農耕での品種改良も奇形なのだ、と書かれていて難しいな!と思った。
0投稿日: 2021.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログレイチェル・カーソンにより始まり、30年前やセヴァン・スズキ、そしていまSDGsが叫ばれている。 何度も繰り返す、人間と環境問題。 60年前の本が今の地球にも言えてしまうのは、あまりにも人類が何もしなさすぎるまま過ごしてきた証拠。
1投稿日: 2021.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題 SILENT SPRING 全く動物のいない里山を想起する。稲が首を垂れているが、トンボ、カエル、鳥たち、メダカ、犬や猫、人すらもいない、静まり返った里山。 化学物質は人類に多大な恩恵をもたらしたが、その濫用は未来に静寂をもたらす——地球はずいぶんと静かになりますね。無知が故に。 こと環境に関しては、世界は足並みを揃えることがとても苦手だ。だからレイチェル・カーソンのような人が必要になってくる。 人類が他の生物と共に地球を分かち合っていることを認め、それらの生物が人類に対する利益とは関係なく存在していることを受け入れる。 (生物多様性条約が作られた時、その前文から〝削除〟された文章) 私たちの子供たちが暮らす世界に、沈黙の春が訪れませんように。
1投稿日: 2021.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の都合に合わせて製造・散布された化学物質による生態系への被害を取り上げ「分別なき化学物質利用の恐ろしさ」を世界に広く啓蒙した書籍。 有名なのでタイトルを聞いたことがある方は多いと思われます。 数多くの事例が紹介されており分量は多め。読み切るのに時間がかかりましたが、環境保護思想の先駆けといえる書籍だと思うので頑張ってチャレンジしてみました。 個人的な学びとしては ・生態系の「網」は非常に繊細かつ複雑で、外的要因によって簡単に破壊されること ・その破壊はほぼ不可逆的に起こること ・人為的に生態系へ導入された化学物質がもたらす害によって、それまでは意識されなかった生命の関係性が顕在化すること ・特定の病原体、害虫の駆除に関しては、化学防除ではなく生物防除が有効であること(日本原産マメコガネ駆除に用いられた病原菌) ・数多くの事例を調査・収集されたカーソン女史のすごさ
0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ今さらながら。 化学薬品の恐ろしさ。 マメコガネ駆除に、乳化病の胞子を使うやり方はいいよね。 初期投資かかっても、どうしてそうしないんだろう。 殺虫剤は手軽だけど刹那的。 ほかの生態系にも影響するのに。
5投稿日: 2020.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ彼女が研究して、この本を出したことで 世の中は変わったのかしら。 わからないからわかる人教えてください。
3投稿日: 2020.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「医学において、防ぐことより治すことが重視されすぎている」 ビジネスにおいても、治療することだけでなく、予防することにまで広げられれば、顧客は倍以上に拡大する。
0投稿日: 2020.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
主に、農薬や殺虫剤、除草薬が自然界にもたらす影響について書かれている。 人間が気軽な気持ちで手にするこれらの薬により、簡単に生態系を壊し、自然を破壊してしまう。 これらの薬の危険性について知ったことはもちろん、生態系のバランスを保つことの大切さにとても興味をそそられた。 また、気になったのは、例えば何かの昆虫を駆除したいときに、その昆虫を殺す化学薬品をつくる研究には国から予算がたくさん出されるが、生態系を利用した駆除方法の研究には予算がつかないこと。 生態系、自然界を守ることは、非常に重要な一方で、これらを守ることで何かお金が生み出されることはあまり想定されないと思うから、それがこの分野に予算がつかない理由でもあるからもしれないし、活動を広げることへの難しさなのかもしれない。 農薬の詳細について 生態系、自然と経済 について調べたいと思った。
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ人はどこまでも愚かになれる 科学の発展と環境とのせめぎ合い。 どう折り合いをつけていくべきなのかを考えさせられます。 きっと解説から読んだ方がいいと思う。
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ殺虫剤による化学的コントロールは環境破壊に繋がるという、農薬による殺虫は結果として人間の健康被害も引き起こす可能性があるという。
0投稿日: 2020.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ出版された当時でこれだけのことを研究分析しているのはすごい。結局、人類は地球における生態系において必要なのか不必要なのかということも考えさせられる。人類に害を与えるからとその種だけを絶滅させて良いということは無い。僅かな不均衡が、取り返しのつかないものになってしまう。環境に対する技術は進んでいるが、本来の地球の姿へ戻すことは不可能だろう。地球温暖化防止や、環境保護を叫ぶことは簡単であるが、どのような状態が良いのか深く考える必要がある。環境関係の勉強をしていたのにまだ読んでいなかったことを恥じます。
0投稿日: 2020.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログSDG, ESGへの取り組み、気候変動や環境保護を訴えるグレタさん等、今日では環境保護、気候変動への対処といったテーマが耳目を引いていることは疑いがありません。 一方、本書が著された今から60年近く前には、経済や企業活動の発展に焦点があり、環境に対する意識が今日ほど世界的な話題ではなかったことでしょう。 カーソンはこの本で主にアメリカでの化学農薬の大規模な散布が、自然に破壊的影響を与えている実例数多く紹介し、警鐘を鳴らしています。商務省、内務省での勤務で彼女自身が環境問題に関与したことから、実例は具体的な数値や、人間以外の動物、野鳥、昆虫、魚類と多岐に亘る生物への影響の具体例に裏打ちされており、大変説得力があります。 アルベルト・シュヴァイツァーの言葉が、カーソンにより引用されています。「人間の作り出した悪魔が、いつか手に負えないべつのものに姿を変えてしまった」 化学と放射能の利用により、人類は大きな利便性を手にしますが、地球規模の環境の破壊を招き入れることとなり、まさにプロメテウスの火となってしまっている感があります。 カーソンは、害虫に対して化学農薬の大規模散布ではなく、より自然の枠組みでの対処法としての、雄の不妊化や天敵の導入による対処を提唱しています。 「沈黙の春」から60年近くたった今日、化学農薬の使用は先進国で低減または横這いにあるようですが、中国など農地の拡大もあり急伸している国もまだあります。プロメテウスの火をうまく管理できる日が訪れるのでしょうか? 燎原の火のようになる前に人々の意識を高める必要性があることからも、本書は今後も読み継がれていくのではないかと思いました。
3投稿日: 2020.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今から60年近く前に書かれ、人類の環境への暴力に警鐘を鳴らし、環境運動のさきがけともなった一冊。 《ポイント》 ·化学物質、とりわけ農薬が生物、環境、人体に与える悪影響を膨大な数のエビデンスをもとに示している ·人間が自然をコントロールすることがいかに愚かか 《感想》 「自然は、人間の生活に役立つために存在する、などと思い上がっていたのだ。」 著者レイチェル・カーソンの主張は最終章の最後に端的に示されているこの一行に集約されていると思う。 この『沈黙の春』が環境問題に対して鳴らした警鐘は、多くの環境保護運動を生み、世界を変えたのは間違いないし、そのような意味においてもこの本はとても素晴らしいものだと思う。 しかし、約60年たった現在、人間は自然との向き合い方は良い方向へと向かっているのだろうか? 本書では安価な殺虫剤DDTが生物、環境、人体に与える悪影響を様々な観点から書かれているけれど、現代は加えてプラスチックゴミや温室効果ガスなど、地球に対して様々な悪影響をもたらすものが分かってきている。 そこに対して、人間はどれだけ真剣に取り組むようになっているのだろう? 近年SDGsを達成するために、様々な動きがでてきたように思える一方、今のスピード感・人々の環境への認識では2030年までに果たして達成できるのか不安も大きい。 今の人類を見たら、レイチェル・カーソンは何を思い、何を伝えるのだろうか。
1投稿日: 2020.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
レイチェルカーソルによる 化学物質の使用が環境に与える影響について 批判的に述べた1冊。 1950年代、アメリカでは害虫駆除を目的として 「農薬」が開発された。 それにより農場から害虫は減少し、「一時的に」収穫が良化する。 しかしその一方で、 自然環境が崩れ始める。 動植物の成長不全、害虫の個体の増加、場合によっては動物の死。 1945年まで続いた第二次世界大戦の影響で 農薬や飛行機の量産が可能となったアメリカでは 害虫を「減少」ではなく、「根絶」にこだわった。 過剰なまでの農薬使用により 生態系のバランスが崩れ、結局農業も衰退することを 強く訴えている。 この本で注目すべきは、 影響を示したエビデンスの数だと考えている。 およそ本の7割以上が農薬の悪影響について述べられており、 残りで改善策についての考えが書かれている。 現代、農薬を空中から降らせるなど考えもつかないが それが当たり前のように行われていた時代では 「当たり前」を批判することが いかに難しいことかを示している。 しかし結果として、レイチェル自身 化学薬品に変わる合理的な改善案は出せずに 書き終えるわけである。 1960年に決定的な解決策を見出すことが出来ずとも 農薬使用の影響を1冊の本で痛烈にまとめあげ、 世間の常識を批判した。 【学んだこと】 常に常識を多方面から見るようにすることが重要である。 農薬は農家の悩みを解決する手段という側面もあるが、 動植物への悪影響も忘れてはいけない。 このように物事を様々な面から見て、考えることが 必要である。
5投稿日: 2020.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人々はその危険性を知らずに化学薬品を多用している 化学薬品は環境や植物を汚染し、それを食べる昆虫や動物達も殺し、果ては人間も殺している 人間の身勝手な理由で生態系を破壊している事に気づき、振る舞いを改めなければならない 植物や虫の防除をする際にも、化学薬品を使う方法より、生態に合わせた生物学的方法を使った方が有効 発行当時(60年代)と現在では違いもあるが、この警鐘は今でも重要
1投稿日: 2019.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ化学物質による環境破壊の危険性を様々な例を挙げて説明している。 「放射能と同様に考える」という記述があって、そう考えると私たちも環境問題に対して積極的に考えていかないと感じた。
0投稿日: 2019.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間のエゴによる無差別テロとも呼ぶべき環境破壊活動を赤裸々にした名著。生物・植物と環境を切り離して論じてはいけないことを、この時代に発信した先見性にただただ頭が下がる。改めて出所の分からないものの見極めと、成分の分からないものを口に入れないなど、情報リテラシーと判断基準の質的向上が必要なのだと実感できた。
6投稿日: 2019.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間が自らの被害から守るために、化学的コントロールを試みることの恐ろしさ、愚かさを実証的に訴える。原著の発行が1962年、日本語訳が1964年に初版となったが、日本の高度経済成長とともに蔓延した公害に対して警鐘とはなり得なかった。死を伴う病気でもって慌てだしたのだ。企業は勝ち残り競争にあり、規制を行うには国の力がどうしても必要である。政治家までが自己の利益を優先していては、こういった課題への対応は遅れる。2019.4.30
0投稿日: 2019.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時を生きていないから衝撃のほどがきっとわかっていいが、人間には殺虫剤かけていたくらいなので、当時の常識を大きく覆したんだと思う。にしても、沈黙の春というタイトルがすごく良いと思う。 全てをコントロールできると思うことは錯覚に過ぎなかった。
0投稿日: 2019.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログレイチェルカーソンの環境問題を題材にした一冊でした。環境問題を勉強している立場の人間からするとこの一冊のように問題提起をしていくことがどれだけ大事かがわかる本でした。
0投稿日: 2019.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ定番としてであったり、名著/名文としてであったり取り上げられることが多いけれども、よく取り上げられる冒頭部分以外を読んだことがなく、たまたま見つけたので読んだ。 いまはこの本から数十年経ているので、生態系を壊さないようにしつつの害虫駆除の方法も恐らくかなり広まって改良もされているだろうけれども、こんな惨事があったとは。そして著者はアメリカの人だけど、小笠原諸島とか、日本でも起こっていたことだったのね。 利害関係が色々と絡み合ってしまって、どうしてもお金とか、目先の損得に捕らわれて考えがちだけれども、数年後、数十年後を見据えて考え、動いた方が良いという教訓。スローライフ系の話題を最近よく見るけど、あれも考え方の根っことしては同じかな、という感じがする。
0投稿日: 2019.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然の脆さ 自然的適合が自然にとってベスト 今自分たちの身体には様々な自分で分からないものが入ってきている。 人出は実験不可能なものが多く、そういったものは怖い。
0投稿日: 2019.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ環境問題を考える上でのもととなった書籍ということで拝読。 内容としては殺虫剤など、いろいろな化学物質が人間に害を及ぼしているという話。 沈黙の春の意味は、春は花が咲き、虫が出てくる季節だが、汚染によってそのような音がない沈黙という意味だとわかった。
0投稿日: 2019.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生の時に読書感想文を書こうと思って手に取りました。 しかし予想以上に難解で、夏休み中には読み終わらず感想文は読んだとこまでで何とか仕上げて提出。 その後苦戦しつつも読了しました。 今でも良く覚えているのは家庭用殺虫剤についての話。 身近にあるものだけに興味深く印象に残っています。
0投稿日: 2018.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ著名な書であり、やはり読まなければと思った。 時代背景が古く、公害や薬害に無知だった時代の葛藤が描かれているが、現代の我々はこうした事の上に成り立っているのだと自覚させられる。少しずつだが、世の中は良くなっているのだろう。
0投稿日: 2018.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ"環境問題を提起した古典的名著。殺虫剤、化学薬品を自然界にばらまき続けてきた人間。その副作用でどんなこととなったのかを示している。昆虫、魚、鳥、家畜、そして人間への計り知れない影響を告発したのが本書。 自然とのかかわり方を考えさせられる本。 農作物への害虫、害虫を殺すために殺虫剤をまき続けた1950年代。化学薬品が周辺へばらまかれ、川では魚が死に、鳥が死に、家畜が死に、人間が死んだケースある。またひとつの種類の昆虫を殺すことで生態系が破壊され、別の種が大量発生したりする。昆虫も化学薬品への耐性を強め、当初の薬品では死ななくなっていたりする。化学薬品が与える影響の大きさにおののく。 最近、近辺の田んぼでトンボを見かけなくなったとの声をきいたことがある。 何か新しい化学薬品が使われているのだろうか?"
0投稿日: 2018.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ半世紀くらい以前の話なのと、聞いた事のない化学薬品名が頻出するので、読む気がかなり削がれたが、頑張って読了。文学というよりはルポ。これと比較すると石牟礼道子の「苦海浄土」は単なるルポではなく、水俣病が舞台となった純然なる文学である事が分かる。 苦海浄土で石牟礼道子さん自身「沈黙の春」に触れている事からも、本作に少なからず影響は受けているだろう。が、それを受け、オリジナル石牟礼道子文学スタイルを完全に打ち出せているところにやはり石牟礼さんの天性の独創性をみる。 例年と志望者数は変わらずほとんどいなかったのにも関わらず、行政がヒアリ駆除のキャンペーンをアメリカで打ち出したのがアメリカの60年代頃。ヒアリが大して人間や家畜に影響ない事など昆虫学者などの証言をとって明らかにしているが、(アメリカの場合は行政と殺虫剤販売企業との癒着も問題だった)そう言えば日本でも数年前に急にヒアリ駆除キャンペーンをメディアと行政がこぞって張った。当時、あれは、日比谷公園や渋谷の公園などからホームレスを締め出す目的だったんではないかなどと言う言説が流れたが、その事を思い出し、当時は何が正しいかもよく分からなかったが、その説もあながち間違いではなかったかもしれないなぁと思った。 本書は基本的に、殺虫剤の有害性を訴えている。その当時のオルタナティブな解決策の可能性として、遺伝子組み換えなどにも期待を多少寄せているが、遺伝子組み換えなんかは手で直接触れる事での人体影響はないかもしれないが、生態系の破壊は甚だしいだろう、と筆者が虫駆除材の有害の原因に、生態系を壊し、回り回って人間がその影響を受ける事例を列挙していた為、尚の事思った。 執筆当時、どの程度遺伝子組み換えが環境や私たちに与える影響が指摘されていたか分からないが、今ほど環境へも消費者へも害があるという共通認識は無かったのかもしれない。それを考えると、2018年春、買収され会社名を消失した悪名高きモンサント社は、この半世紀ほどで大きく躍進したし、それによって人々の意識も大きく変わってきたんだろうと思った。 それから、環境破壊や人体影響という点で、第五福竜丸の事件についても触れている。当時、水爆実験や事故への恐怖が日本だけでなく世界中で一つのムードとしてあったのだろう。 水爆や原爆、環境破壊、そういうのに手を打ち、地球の人たちで手を取り合って、頑張っていこうという、流れだったのだと思うが、そういう当時の雰囲気を知らないので、時代の理解にも役立った。
0投稿日: 2018.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の都合で目先の利益の為に、虫を殺すことが、まわりまわって人間に返ってくる。 因果応報。 食物連鎖の頂点にいる人間だからこそ、他人や子供や未来の生き物や地球のことを考えて、今できることから声をあげてゆきたい。
0投稿日: 2018.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝記・小説以外に読んだ初めての本だったと思う。浅はかな私は現実社会というものは清く正しく進歩していくものだと単純に信じていたから、とても衝撃を受けた。
1投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み途中だけど途中まてでレビュー。とにかく化学薬品の恐ろしさを語った名著。この本が世に出てなければ自然破壊はもっと起きていたのではないかという気持ちにさせられる。ただ、その恐ろしさを400ページ近くまで語られるので途中から飽きる。また情報が古いのでおや?と思うところもあるし、アメリカ合衆国の話であるので日本に住む私としては少しピンとこない所もあった。しかし、化学薬品に対して一切恐れを抱いていなかった、またはぼんやりとした不安を抱えている人にとっては衝撃的な文章になっているので是非読んでほしい。野菜を食べる前には読まない方がいいかも。
0投稿日: 2017.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1974(訳底本1964、原書62)年刊。◆後年、本書と同種の内容や、進展した議論を記述した書は別に刊行されている。が、この年時の刊行は意義深い。◆本書の趣旨は①薬品(除草剤、防虫・除虫剤)の見境なき散布、②①による川、池、土壌汚染、③②の結果、植物・生物への汚染蓄積と、食物連鎖による人間への汚染蓄積、④③による生殖機能低下と細胞の癌化、⑤薬品散布に伴う生態系破壊、特に益虫・益鳥死滅と、薬品耐性生物の出現。これらは、例えば抗生物質使用に伴う多剤耐性菌の出現、内部被爆による細胞の癌化などと類似する。 しかし、1964年(東京オリンピック開催年)に刊行されている意味で、環境問題の先駆、生物工学・生態系工学の嚆矢とも言うべき書となっており、関係者・大衆の度肝を抜いたのではないかと容易に推察できる。その意味で、古典ではあるものの、読むべき一書と評しうるのではないか。 なお、「呼吸以外の方法、つまり醗酵で全エネルギーを獲得できる細胞は癌化したものである」とあるが、これは妥当な記述なのだろうか? 個人的にはアポトーシスできない細胞が癌細胞と思っていたのだが…。違うのかな…。
0投稿日: 2017.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ環境系の授業で度々紹介され、偶然本屋で見つけたので手に取ったが、読了に至らなかった一冊。300Pくらいまで読んでみたがなかなか読み進まないため断念した。内容は土壌、河川、空など様々な例を挙げつつも一貫して化学薬品の危険性と使用者側の無知に対する批判について書かれていた。この本を書くにあたってものすごい量の情報を集めたのはとても伝わった。まさしく現代の批判のように思えたがこれが1964年、40年前に書かれたものであるから驚いた。現代の様に環境問題が訴えられていないその時代にここまで気がつくことが出来たから現代もベストセラーとして紹介されるんだなと思った。 また必要とあれば読み直したい。
0投稿日: 2016.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ4 化学物質の脅威の話。現在禁止されている塩化炭化水素系のDDT等の農薬による重篤な健康被害と環境破壊の状況を訴えている。 最初は、農薬全てダメかと思っていたが、彼女の主張は、十分な安全調査をせずに大量の農薬を撒くことに対する警鐘と生物農薬など別の方法による防除。普通に読んだら化学物質全部ダメのイメージだけを残してしまいそう。「化学物質」の枕詞に「安全性が十分確認できていない」をつけないと間違う気がする。 そもそも天然非天然に関わらず人間は化学物質に接しており、化学物質を全て取り去るということではなく、リスク管理が問題。生物農薬も生態系破壊の問題は孕んでおり、化学物質が危険というイメージ先行でなく、変異原性等の毒性、土壌・水質への影響、生態系への影響、組み合わせの影響など十分な基礎データを取得し、毒性レベル・頻度・濃度・使用方法・使用する人を鑑みたリスクマネージメントをすることが求められていると感じる。
0投稿日: 2016.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ私としては珍しく、物語的でない本を読むことがてきた。今でこそ、農薬の使いすぎはよくないって自然に思えるけど、そうじゃない時代、この本の与えた衝撃はすごいものだったのだろう。そしてこの本を出版した覚悟も図り知れない。
0投稿日: 2016.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログその春、私の庭に小鳥が来ることは無かった。 ミツバチの羽音がすることもなかった。 リンゴの木は花を咲かせたけど、その花が実を結ぶことは二度となかった。 農薬や化学肥料等が、自然に及ぼす影響について、女性科学者が科学的、かつ具体的に、わかりやすく警告した本書が出版され、世に問われたのは、1962年。 それから50余年がたち、人類は化学物質だけでなく、遺伝子を操作し、自然界にはあり得ない植物や動物を造りだし、より経済的な利益、いま、目の前にある経済的利益のみを追求する道を突き進んでいる。 科学を否定するわけではない。目の前の利益だけに突き進み過度に利用するのではなく、自然と人間が許容できるゆるやかなスピードで、共生を図るべきなのではないだろうか。
0投稿日: 2016.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1964年当時の環境問題告発論文。 データとしても理論構築もその当時とし ては突出していたのかも。 ただ国家と大企業の関係性や社会構造の 弊害部分においては現代に通じる部分も 見受けられる。
0投稿日: 2016.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ残留農薬の危険性について告発した、名作レポート。取材してというドキュメンタリーというよりは、論文等をまとめたレビュー論文という形だ。 前半は、DDTおよび2,4Dなどの経皮毒性の農薬をまくことで起こった被害について、何度も繰り返し同じ内容を場所を変えて述べているだけであり、前に進む話でもないため、少々読みづらい。 後半は、論調はそのままなのだが、改善例、うまくいった例、利益相反の告発など、同じ所をぐるぐる回っているわけではないため、俄然読みやすくなる。 論の展開等については、1960年代という時代の問題もあるため、今から考えたら稚拙だし、「いずれ全てが滅ぶ」という論調を、時代が進むことによって覆されてしまったところも有り、素直に読む訳にはいかない。「メス化」なんて話も、ここが初出だったんでしょうかね。 また、これから読む人においては、世の中に存在する「カーソン教信者」にならないよう、ちゃんと疑問を常に抱きながら読む必要があろう。 さて、本作の問題点は、訳のまずさにある。 「沈黙の春といえば?」と聞けば、大概の人が「体に悪い物質は、食物連鎖の上位に向かって蓄積され濃縮される」と答えるだろう。まあ、そういうことも少しだけ書いてある。 しかし、カーソン女史は「農薬を使ってもいいが、使用量は減らせば良い」と書いているのだ。つまり、(脂質や骨などに特異的に蓄積される物質についての)生物濃縮という証拠は見ていても、その重要性は指摘していないのだ。 そういう部分を踏まえて、訳を間違ったのかなんなのだか、「自然にある物質は良い」「人が作った化学物質は全て悪い」という、大きなストーリーから出てこないはずの文章が、時々挿入される。超訳というやつかしらん? また、意図的に誤解を生むのが目的なのかどうなのか、「化学物質は」という言葉が沢山出てくる。これは原文ではおそらく "Chemicals" といった単語であろうことはわかるわけで、文脈的に「農薬」「合成農薬」などという訳語を使うべきだろう。 "Chemo" と言葉が出てきたとしても「化学物質の投与」なんて言わない「化学療法」だ。 最終的に、「マスの癌が多発している。きっとこれも…」なんて話が出てくるが、残念。自然(カビ)の作る毒が由来なのだった。 そういうわけで、結構当時から見ての、未来を見越した良いレポートでは有ると思う。これで訳が良ければ☆4なのだけどなあ。
0投稿日: 2016.03.01
