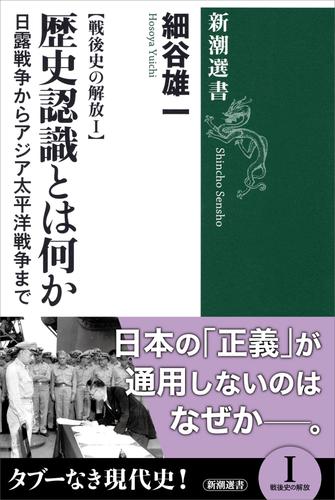
総合評価
(22件)| 9 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一次世界大戦にて特に大きな被害の無かった日本と、国土が荒廃した欧米諸国とでは、戦争に対する嫌悪感、平和への政治的情熱の熱量に大きな差があった。第一次世界大戦後も武力を背景とした権益拡大を続けようとする日本は国際社会で孤立してしまい、太平洋戦争に突入してしまった。また、日本を第二次世界大戦の際に戦略的に振る舞うイギリスのチャーチル首相と軍部に引きずられズルズル戦争に進む近衛文麿の2人が対照的。首相としての器が違う。そりゃ戦争に負けるわという印象。
0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ比較的史実に基づいて書いているように見えるが、数字的根拠は明確ではなく、基本、戦中の日本悪のナラティブである。 加えて尾張守姿勢で少し残念な書籍となっている。
1投稿日: 2023.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨今の国際情勢を受けて近現代史に改めて興味をもった社会人の学び直しに本当にピッタリでした。 このタイミングで本書に出会えたことに感謝。 外交史の視点によって、歴史がより真に迫ってきます。 浪人時代にこの本読みたかったなぁ。
0投稿日: 2023.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとタイトルから期待した内容とは違ったな。 歴史認識というよりは「国際情勢の認識」であり、しかも扱う年代の日本の指導者が、どのように国際情勢を認識していたかが検証されている。でも、それは既に先行研究により自明なこと。なぜそういう認識しか持てなかったのかが知りたいんだけどね。 それにしても太平洋戦争では東條英機が戦犯の筆頭に挙げられるけど、近衛の方が何倍も罪深いと思うけどね。そして近衛って国民に絶大な人気だった事実が開戦の原因なんだと思うんだ。
0投稿日: 2020.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは良書であるが、「歴史認識」の在り方そのものを掘り下げているというよりは、基本的には第一次大戦以降の国際政治動向を最新の研究動向を踏まえて叙述した内容。 現代に通じる多くの教訓を「戦間期」と呼ばれる時代(二つの世界大戦の間、1920-30年代)は含んでいることを改めて実感。 過去に学ぶ、ということは、「戦争反対」の平和協調主義が力の空白を生む(戦争の原因になりうる)ことの危険から目を離さないということであり、同時にそれは、当時の日本がどうにも正当化できない過ちを犯したことを正視することでもある、ということ。 文献を詳細に検討して事実(と呼びうる何か)を掘り下げる努力に右翼も左翼もない。 (以下、備忘メモ) ① 大戦の悲劇→国際協調による平和主義→大戦回避失敗→実効性のある抑止、という流れ - 欧州では第一次大戦によって1,000万人を超える死者を出した。これにおののき、各国とも真剣に国際協調による平和という仕組みを追求するようになった。1928年の「パリ不戦条約」は紛争解決に武力を用いないことを規定した「戦争放棄」条項を持つことで画期的であった(”Renunciation of war”。これは日本国憲法第9条の「戦争放棄」の訳語でもある。戦争放棄の概念は憲法9条で新しく導入されたわけではない) - 一方、わずか1,000人の死者しか出なかった日本はその切実さはなかった。満州事変で国際連盟を脱退した時、欧州を襲った「戦後秩序崩壊」への危機感を日本は共有できなかった。 ‐ 平和のために軍縮条約を締結し、それが結果的に力の空白を生みナチスの台頭を許したこと、さらにそのナチスへの宥和外交の失敗などの経験から、欧米においては一旦決められた国際ルールを軍事力で変更することへのアレルギーが強固。ちなみに、今ホットな「海洋航行の自由」は、まだ日本と開戦してもいない1941年8月、太平洋憲章という形で英米により発表された。 ② 「協調主義」に悪乗りした日本という認識 - 日露戦争のとき、日本の捕虜に対する人道的な扱いは世界の称賛を受けた。国際協調主義のおかげで、国際連盟においてアジア唯一の5大国となる名誉を得た - 一方、大国となった日本は協調を軽視するようになった。その象徴が(個人的には大変残念な新しい知識だが)当時の日本は捕虜の人道的扱いを定めるジュネーブ条約を批准しなかった、という事実。日本軍は捕虜になるのを恥としており、軍部は「ジュネーブ条約があれば、捕まっても大丈夫と思う敵軍が冒険的に本土を空襲するであろうから不利である」として反対した。太平洋戦争突入後、シンガポールで大規模な降伏を行った英国が、自国捕虜を条約に即して扱うように日本政府にもとめたとき、我々がした回答は「準適用」であった。結果的に、ドイツ軍の捕虜になった連合軍兵士の死亡率が5%だったのに対し、日本軍指揮下では20%超が死亡した。 - これも大変残念だが、第1次大戦以降、最初に一般市民を巻き込む都市爆撃を行ったのは(ゲルニカのドイツよりも前に)日本(錦州爆撃)だった。 - 例えば石橋湛山や吉野作造のように、日本の対中国政策を明らかに侵略的だと批判する人も当時からいた(「・・・鼻息ばかり荒くして、大国民の襟度を以て彼等(中国人)に接することを解せぬから・・・排日の感情を・・挑発する結果に(以下略)」)(吉野作造、P.86)。
0投稿日: 2019.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後史については、イデオロギーの偏向、時間的な誤り(1945年にいきなり戦後が始まったとする)、空間的な偏狭さ(日本一国のみで判断する)の3つの誤りが重なって、まともな議論ができない状況が続いている。 本書は、史実に基づいて、また、世界史的な視野から見て、また、戦前の歴史も視野に入れることで、まとまりのある論述になっている。 知らなかった事実も多かった。 現在が「一国平和主義」という偏狭な陥穽に陥っているのでは、という末尾の指摘に全編を通した後では深く頷かざるを得なかった。
0投稿日: 2018.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ太平洋戦争前、リベラルな天皇と富国強兵の軍隊、特に維新を守りたい海軍の猛々しさ。 本書では日本の戦争の問題点を、平和に向かうグローバルな潮流を感じ取れなかったという点に見ている。今でいうところのガラパゴス。 象徴天皇になる前は天皇はとってもリベラルだった。天皇の権力が剥奪された理由は、ファッショの危険性があったからとか独裁がダメだからとかじゃなくて、天皇を冠にすることで正当性を維持しながら色々やらかすのが日本だから。国のトップとしての戦争責任はあるかもしれないけれど、戦犯からは除外されていた。 思想が偏っていたって政治を動かせるような影響力を持つ人はほとんどいないので、正しい歴史認識が必要な理由はあまりない。実際は影響力の源泉はその偏りだったりするし。むしろまともな認識を持たない方が実行力は高まる。 国と国ではなく、私とあなたのレベルで考えた場合、思想が偏っていたってそれを口にできる人はほとんどいない。その程度にはマジョリティは臆病である。
0投稿日: 2017.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史学者が書く内容は一考に値する。国際状況のインテリジェンスが必要。思考停止 無批判の9条守れ が一番あぶない。
0投稿日: 2016.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は本書をほぼ缶詰め状態で一気に書き上げた、とあとがきに書いていますが、その通り文章にはとても勢いがあり、歴史書ながら読む者を引き込ませます。 もっとも本書によって明らかにされる新事実などはなく、先行研究のまとめが中心ですが、現時点での最新の研究動向を知るにはちょうど良いのではないでしょうか。
0投稿日: 2016.03.05歴史的事実として8月15日に終わった戦争は存在しない
教科書は現代史をやる前に時間切れそこが一番知りたいのに何でそうなっちゃうの? 「ピースとハイライト」by桑田圭祐 日本史の中では世界は語られず、また世界史の中に日本の記述はほとんどない。世界史と言いながら東洋史と西洋史は有ってもイスラムや中央アジア、東南アジアなんかも中心にはいない。分断された歴史で現代史を見ても認識のみぞは埋まらない。それは日本の外交の経験や理解が、圧倒的に国際社会のそれからずれていることがしばしばあるからだ。戦前の日本外交の失敗や誰も始めるつもりも勝てる予測もなかったアジア・太平洋戦に突入したのも、国際政治に対する日本人の想定と現実の世界とのずれが原因にある。 戦後日本の歴史は1945年8月15日に始まったと言えば多くの人に違和感はないだろう。しかし、この日は日本と朝鮮半島を除く国際社会からすれば何もなかった日だ。「そもそも歴史的事実として8月15日に終わった戦争は存在しない。」日本がポツダム宣言の受諾を回答したのは14日、国際標準としては降伏文書が調印された9月2日(中国では3日)が対日戦勝記念日であり、15日はただ多くの国民が敗戦を知った日だ。グローバルスタンダードでは「終戦」とは相手国のある行為であり、それよりも自国民向けの都合である「玉音放送」を優先することはあり得ない。 玉音放送は国民の均質的な体験とも言い切れない。沖縄では放送局が爆破されており6/23に沖縄守備隊が壊滅してからも散発的な抵抗が続き、残存兵が米軍と降伏文書を調印したのは9/7だった。千島列島では9/18、南樺太では20日にソ連軍が上陸し戦闘が始まった。 日露戦争において日本は「文明国」として国際法を遵守して戦った。捕虜になったロシア兵の死亡率は0.5%と驚くべき低い数字でありハーグ陸戦協定以上の待遇を行ったことには敵国ロシアからも謝意が表せられるほどであった。この頃日本の軍部では国際法教育が行われて下士官もジュネーブ条約などの知識を持っていた。 第一次世界大戦でドイツ権益を奪った日本では悲惨な戦地を経験したヨーロッパで生まれた人道主義と言う新たな潮流を感じることはなく、1932年には陸軍士官学校の教程から戦時国際法を除外した。日中戦争の長期化が軍紀を弛緩させ、中国蔑視に起因する捕虜虐待などが頻発した。第二次世界大戦でも欧米人捕虜に対する違法行為を繰り返した。そのきっかけとなったのが東京空襲の開始であり、泰緬鉄道建設に従事させられたイギリス兵捕虜の死亡率は25%にのぼった。全戦場でのイギリス兵死亡率5.7%、ドイツやイタリアでの捕虜の死亡率5%と比べれば日露戦争当時に比べ日本軍がどれだけ野蛮になったのか。その原因となったのが国際法教育の放棄と国際的な常識からのずれだ。 1931年10月8日、関東軍は満鉄の自衛と言う名目で150km離れた錦州を爆撃した。これが日本軍による初の都市空爆であり、戦略爆撃はゲルニカや重慶への絨毯爆撃へそしてロンドン空襲や日本への空襲、広島と長崎への原爆投下と拡大して行った。錦州爆撃以降不拡大方針を取りながら関東軍を制御できない日本政府に対する国際社会からの不信感が高まり、日本は窮地に追い込まれていくことになる。 安倍首相は戦後70周年談話で村山談話を継承した。しかし、自社連立の条件であった「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」の採決では与党自社さから70名の欠席者を生んだ。安倍首相もその一人だ。「独善的なナショナリズム」を排する決意を示した村山談話が生み出したのはその想いとは裏腹に玉虫色の決着を封じ、歴史問題を外交問題としてしまった。国内でも歴史認識は一致しない、ましてや中韓とは。著者の懸念は今の日本が平和主義と言う名の孤立主義に陥っていることだ。自国以外の安全保障に全く関心を示さない利己的な姿勢は国際主義の否定と取られかねない。
0投稿日: 2016.02.28日本と世界はつながっている。
日本で習う世界史では日本はあまり出てこない、逆に日本史では世界史の動きがあまりでてこない。 そうではなくて日本と世界はつながっていて、世界でのできごとは日本の歴史にも影響し日本の行動が世界の歴史を動かしているということ。 第一次世界大戦から第二次世界大戦までの日本の行動、それが世界にどのような影響を与えたのか。 世界の流れを読み切れず、なぜ日本は破滅へと向かってしまったのか。 大変勉強になる良書です。 おすすです。
0投稿日: 2016.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日露戦争から太平洋戦争までの通史が書かれている。太平洋戦争の開戦過程を日露戦争から記述するのは希少であると思う。 また、この本が優れているのは、国際関係と国内のアクターいずれも分析対象に入っていること。日本政治外交史の立場だけではないのは、太平洋戦争の開戦過程を探る上で良い点である。 逆に不満な点は、歴史認識という言葉をタイトルで使っている割には、歴史認識の問題に言及していない。タイトルをもう少し考えるべきであったと思う。 この本で得た教訓は、選択する政策の結末がどうなるか、楽観的にではなく、国内要因と国際関係いずれも冷静に分析する必要があるということである。決して組織内部の事情や責任回避だけでなされるべきでないということ。
0投稿日: 2016.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログサザンオールスターズが紅白歌合戦でちょび髭をつけて話題になった。その話が出てくる。 その歌(は僕は知らないが)の歌詞には、「教科書は現代史をやる前に時間切れ そこが一番知りたいのに何でそうなっちゃうの?」とある。そう、現代史は教育の過程にあるように見えて、実はない。 けれど、例え学んだとしても、普遍的に受け入れ可能な歴史的事実などには辿りつけない。辿りつけないはずだが、日本ではなぜか、そこに辿りつけるし、他国もまた同じ、という楽観的な認識がある。これが歴史問題を拗らせた一因のようだ。 それからもう一つ、わかりやすいのは「日本史」と「世界史」が分かれていて、それぞれ、日本史の中には世界は出てこないし、世界史の中には日本が出てこない、ということ。端的に日本が国際協調という姿勢を持っていないことを伺わせる。 本書はこの「歴史認識しづらい」日本において、どういうことが起こっていたのかを綴るものである。専門で学んでいれば既知のことかもしれないが、僕はそうではないから知らなかったことも多い。 日本は軍国主義だったからいけない、というよりも国際主義の欠如が問題だった、と著者は述べる。現在の日本も平和主義という名の孤立主義なのでは、とも。国際的にも平和主義と戦争放棄の理念はあるのに、憲法9条だけに存在する理念のようにノーベル平和賞を要求するのは、美しいふるまいではない、自国以外の安全保障にまったく関心を示さない利己的な姿勢も、国際主義の否定と見られかねない。 市井では歴史問題もデジタル的に賛成反対で語られることが多いが、ともかく絶対的な正義が自分にある、と思ったらやばい。平場に出たらどう見えるかってことが大事のようだ。出ないと孤立→悪、と昨日読んだ本にも出てた(って単純な話じゃないよ)。
0投稿日: 2016.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ日露戦争以降、特に第一次大戦以降の日本の国の誤り方やその原因がよくわかる。 バランスの取れた合理的な記述で、左右の立場にに関係なく、納得できるのではないか。 視野狭窄に陥り、世の中全体を見ず、希望的観測に基づいた独善的な内向きな理屈を振りかざす。 昨今の政財界の動きを見ても、戦後70年、何の進歩もないことを実感させられる。 陸海軍が自分等の国内的勢力拡大を最大の目的とした結果として、日米開戦に到ると本気で考えた当事者がいなかったというのは、驚きを超えて情けなくもある。 社会人、大学生の必読書。高校の副読本とすべき。
0投稿日: 2015.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ歴史認識の共有が難しいのか、イギリスの歴史日であるE・H・カー、歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話、 歴史に翻弄される政治、歴史的事実に基づく歴史学ではなく、自らの運動を実践するための手段として歴史が用いられる、 孫崎、戦後史の正体 秦郁彦、陰謀史観とは、特定の個人ないし組織による秘密謀議で合意されたすぎる書き通りに歴史は進行したし、進行するだろうと信じる味方 巨大な戦争の経験こそが、その後の平和を求める運動を覚醒させる最大の動機 となっていた。
0投稿日: 2015.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
氏は、日本が戦前に、対米戦争へ向けた道のりを歩み始める大きな原因を、国際情勢認識の錯誤であったと指摘しているのですが、渡辺惣樹著『日米衝突の萌芽』や『日米衝突の根源』、ジョン・ダワー著『容赦なき戦争』などを読むと、一方的に日本が悪いというわけではなく、たぶんにアメリカの日本人に対する人種差別も大きく影響していると思われます。それでも細谷氏はこれを単純な反米史観や陰謀史観と見なすのでしょうか。非はおそらく日本の方が大きいのでしょうが、日本だけが悪いのではないと思います。しかし、もちろん日本の非は悪ですが。
0投稿日: 2015.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
★★★☆☆ 細谷雄一を知ったのは、モーリー・ロバートソンのニコニコ生放送に出演していたのがきっかけ。 安保法案可決直前だったこともあって、なかなか白熱した対談で面白かった。 本書は、著者が日本における安全保障関連の議論のちぐはぐさを整理し落ち着かせるために打ったトランキライザーだ。 安全保障は世界情勢とのバランスで語られるべきものであるにもかかわらず、日本では言語の壁もあってか、どうしても国内事情が優先され、世界の潮流を見ないままで議論が進んでしまう。 著者は、本書において、英米や欧州が近代史をどう見ているか、そのステレオタイプを提示してくれる。 国際連盟の無力さを白日のもとに晒したのが日本だという指摘や、ベルギーが中立を宣言したことで逆に占領されてしまった点などは、今でも教訓として十分機能する。 英米欧の基本的な歴史認識を知ることは、彼らが話をする際に前提としている知識を知ることだ。 それを知らずにいると、ひとつひとつの言葉にどんな含意があるのかわからないので、とても表面的な話しかできないし、時に頓珍漢な間違いを犯すことにもなる。 もちろん厳密にいえば、歴史認識は個人個人によって異なるものだけれど、本書によって深い議論というトンネルの、そのとば口に立てるのだから読んでおく意味は大いにある。 ひとつ気になったのは、ソ連に関する記述がほとんどないこと。 第二次大戦は最終的にはスターリンにとって非常に都合のいい結果に落ち着いたと思うののだが、まさかそれが偶然の産物ということはないだろう。 その辺を詮索すると英米欧の人たちにとって都合が悪いから書かれなかったのだとすると、彼らのステレオタイプを理解する上ではますます都合がいいと思うのだが、それは考えすぎだろうか。
0投稿日: 2015.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ細谷雄一氏は1971年生まれ。40代前半だ。世代的に近いことは、どこか親近感が湧く。通ってきた時代背景、時事問題への認識には、共通点を見いだしうるからだ。 日露戦争からアジア太平洋戦争まで、と題され、日本史、世界史という枠組みを超えて、通史で見ていく。 氏は訴える。戦前は時代錯誤から、軍国主義という独善的な孤立主義へと走った日本人。現在は、国際情勢の理解認識の欠如から、平和主義、という偏った孤立主義へと走り、同様に世界に取り残されつつある日本人と。安保法関連法案が成立した、今だからこそ、このような氏の視点に触れ、今一度、単純な戦争反対、では無い、真の議論を進めるべきではないか。 歴史認識というのは、難しい。ましてや、目の前の事象が、正しいのか、正しくないのか、必要な改革なのか、あってはならない変更なのか、本当に理解するには時間も必要である
0投稿日: 2015.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書は現代史をやる前に時間切れそこが一番知りたいのに何でそうなっちゃうの? 「ピースとハイライト」by桑田圭祐 日本史の中では世界は語られず、また世界史の中に日本の記述はほとんどない。世界史と言いながら東洋史と西洋史は有ってもイスラムや中央アジア、東南アジアなんかも中心にはいない。分断された歴史で現代史を見ても認識のみぞは埋まらない。それは日本の外交の経験や理解が、圧倒的に国際社会のそれからずれていることがしばしばあるからだ。戦前の日本外交の失敗や誰も始めるつもりも勝てる予測もなかったアジア・太平洋戦に突入したのも、国際政治に対する日本人の想定と現実の世界とのずれが原因にある。 戦後日本の歴史は1945年8月15日に始まったと言えば多くの人に違和感はないだろう。しかし、この日は日本と朝鮮半島を除く国際社会からすれば何もなかった日だ。「そもそも歴史的事実として8月15日に終わった戦争は存在しない。」日本がポツダム宣言の受諾を回答したのは14日、国際標準としては降伏文書が調印された9月2日(中国では3日)が対日戦勝記念日であり、15日はただ多くの国民が敗戦を知った日だ。グローバルスタンダードでは「終戦」とは相手国のある行為であり、それよりも自国民向けの都合である「玉音放送」を優先することはあり得ない。 玉音放送は国民の均質的な体験とも言い切れない。沖縄では放送局が爆破されており6/23に沖縄守備隊が壊滅してからも散発的な抵抗が続き、残存兵が米軍と降伏文書を調印したのは9/7だった。千島列島では9/18、南樺太では20日にソ連軍が上陸し戦闘が始まった。 日露戦争において日本は「文明国」として国際法を遵守して戦った。捕虜になったロシア兵の死亡率は0.5%と驚くべき低い数字でありハーグ陸戦協定以上の待遇を行ったことには敵国ロシアからも謝意が表せられるほどであった。この頃日本の軍部では国際法教育が行われて下士官もジュネーブ条約などの知識を持っていた。 第一次世界大戦でドイツ権益を奪った日本では悲惨な戦地を経験したヨーロッパで生まれた人道主義と言う新たな潮流を感じることはなく、1932年には陸軍士官学校の教程から戦時国際法を除外した。日中戦争の長期化が軍紀を弛緩させ、中国蔑視に起因する捕虜虐待などが頻発した。第二次世界大戦でも欧米人捕虜に対する違法行為を繰り返した。そのきっかけとなったのが東京空襲の開始であり、泰緬鉄道建設に従事させられたイギリス兵捕虜の死亡率は25%にのぼった。全戦場でのイギリス兵死亡率5.7%、ドイツやイタリアでの捕虜の死亡率5%と比べれば日露戦争当時に比べ日本軍がどれだけ野蛮になったのか。その原因となったのが国際法教育の放棄と国際的な常識からのずれだ。 1931年10月8日、関東軍は満鉄の自衛と言う名目で150km離れた錦州を爆撃した。これが日本軍による初の都市空爆であり、戦略爆撃はゲルニカや重慶への絨毯爆撃へそしてロンドン空襲や日本への空襲、広島と長崎への原爆投下と拡大して行った。錦州爆撃以降不拡大方針を取りながら関東軍を制御できない日本政府に対する国際社会からの不信感が高まり、日本は窮地に追い込まれていくことになる。 安倍首相は戦後70周年談話で村山談話を継承した。しかし、自社連立の条件であった「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」の採決では与党自社さから70名の欠席者を生んだ。安倍首相もその一人だ。「独善的なナショナリズム」を排する決意を示した村山談話が生み出したのはその想いとは裏腹に玉虫色の決着を封じ、歴史問題を外交問題としてしまった。国内でも歴史認識は一致しない、ましてや中韓とは。著者の懸念は今の日本が平和主義と言う名の孤立主義に陥っていることだ。自国以外の安全保障に全く関心を示さない利己的な姿勢は国際主義の否定と取られかねない。
0投稿日: 2015.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、「歴史認識」に関する本を2冊読んだ。本書はその二冊目で、最初買うのに少しためらった。どういう立場の人なのか、読む価値があるのかを考えたからである。慶応の先生ということもためらった理由の一つだったかも知れない。しかし、それは杞憂だった。本書は、細谷さんの日本史と西洋史の研究成果がうまくマッチして、世界史の中で日本の近代史を見るという、とてもバランスのとれた記述になっている。日本は西洋列強に遅れて植民地競争に加わった。しかし、西洋では第一次世界大戦という大きな犠牲を踏まえ、新たな平和構築に乗り出していた。日本は最初、列強に遅れまいとしてがんばって国際法を学んだが、のちベルサイユ条約に参加したころから西洋の欺瞞性に気づき、新たな道を探ろうとした。しかし、西洋列強は欺瞞とエゴはあったとはいえ、それなりの戦争を避けるルールを探ろうとしており、日本はその流れとは逆の方向に進んでいった。アジア主義を唱え、西洋の植民地主義を批判するのはいいが、そこには朝鮮、台湾を植民地化していくことへの反省はなかった。1931年の満州事変は日本にとっては単に日中の問題のように思えたかもしれないが、それはそれまで築いてきた国際秩序を大きく崩すものであった。安部首相の答申機関であった北岡伸一氏らが、日本の侵略は満州事変から始まるというのと同趣旨の内容であろう。安部首相が日露戦争はアジアの植民地に希望を与えたと言う。それは一面の真理をものがたってはいる。しかし、そこには台湾、朝鮮を植民地化していく自らの姿は見えなかったのだろうか。また、日本がのちにアジアの解放を謳うようになるが、それもあくまで東南アジアの石油を確保するためで、マレーシアは最初その仲間に入れてもらえなかった。それはそこでの石油資源を自由に使うためには独立してもらっては困るからである。国と国との対立の中で、ソ連がドイツとくっついたり、イギリスとくっついたりと世界の首脳は頭を痛めたが、日本はほとんど脳がなかった。チャーチルなどは、反共主義でありながら、ドイツと戦うためにソ連とくっついたりした。日本と米英との戦争も、日本が仏領インドシナから撤退すれば経済封鎖にもあわなかったわけで、国際感覚のなさが目立つ。細谷さんは現在の日本のおかれている立場から、国会で論議中の安全保障法案には賛成のようだが、それは次巻ということのようだ。それにしても、これまでの歴史の総括として、とても読み応えのある本であった。
0投稿日: 2015.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの優れた研究者により蓄積されてきた個々の研究成果をもとに、世界史と日本史を統合、大きな流れの中で描く。非専門家によるイデオロギー的な歴史がベストセラーになり、国際的には通用しない論理ではなく。 確かに、わかりやすいシンプルな悪者、もしくは正義、では不十分であることはわかるけれど、歴史的にきちんとしようとすると、あっちこっちが様々、深く知らず考えずに迷走って感じ。
0投稿日: 2015.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後史を20世紀の全体像の中に位置付け直し、再構築を試みた意欲作。「世界史」と「日本史」を統合し、国際的な平和、国際的な秩序を構築しようとする潮流の破壊者として戦前期日本の行動を捉える。 日露戦争までは国際的な秩序の中に自らの行動を位置付け、それなりの国際的な信義を得ていた日本が第1次大戦以後の国際秩序構築の動きをなぜ見誤り、孤立していったのか。 例えば、第1次大戦後の国際思潮の転換を牧野伸顕はしっかりと認識していたが政府の中では少数派であり、伊東巳代治のような旧来の「帝国主義」的な思想から脱却できなかった。ベルサイユ会議に同道した若き近衛文麿も「英米本位の平和主義を排す」としたことからもわかるように、国際的協調主義を理解できなかった。 1930年代以降の日本の選択が逐一、国際情勢分析の甘さ、機会主義的な行動などによって位置付けられるのに対して、大英帝国の明確な理念に基づいて取られる政治・外交の強かさが際立つ。そして、日米開戦によって日本は益々進むべき方向を見失っていくのに対して、逆にそれによって戦争の勝利を確信したチャーチルの大局観!! 著者は最後にこう述べる。「戦前の日本が、軍国主義という名前の孤立主義に陥ったとすれば、戦後の日本はむしろ平和主義という名前の孤立主義に陥っているというべきではないか。たとえば、平和主義と戦争放棄の理念を、1928年の不戦条約や、1945年の国連憲章二条四項を参照することなく、あたかも憲法九条のみに存在する日本固有の精神であるかのように錯覚し、ノーベル平和賞を要求することは、本書で見てきたような日本の歴史に少しでも思いをいたすならば、美しいふるまいとは言えないだろう。また、自国以外の安全保障にまったく関心を示さない利己的な姿勢は、下手をすれば国際主義の精神の否定と見られる恐れもある。」(273-4ページ) 戦後70年の今、必読の一書であろう。
0投稿日: 2015.08.05
