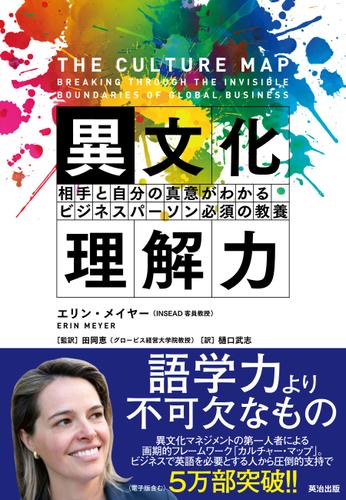
総合評価
(122件)| 62 | ||
| 40 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ・文化は相対的にとらえるもの ・異文化に対して同じようにふるまっても逆効果であることがある。同化するのではなく、意識すること 等、参考になることが多かったです。
0投稿日: 2017.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログカルチャーマップは非常に勉強になった。言語だけではカバーしきれない多様性がまとめられている。思考の違いがあることを共有し、それを前提に議論を進めていく必要があると感じた。相手の考え方の傾向を念頭に置いたうえでやらなければならない。
0投稿日: 2017.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ多様性とは何か。多様な人が活躍する会社とは何かを知りたくて読んだ。 ビジネスの場において重要な要素を8つあげている。
0投稿日: 2017.07.15読みやすく判りやすく内容が濃い
上海で異文化コミュニケーションの講師をするために、再勉強として購入。 多様な国々とのコミュニケーションについて、ギャップが生じる理由、対策などを判りやすくまとめている。 その内容は、異文化に限らず日本人の友人たちとの関係構築でも役立つものでした。 海外と業務やり取りのある人だけでなく、日本の中でも人とのコミュニケーションに悩む人にはお勧めです。
0投稿日: 2017.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログCulture mapというビジネスに特化した8つの軸を用いて、各国の文化の違いを視覚的に位置づけ、説明し、対処法を示す。 今まで仕事で漠然と感じていたことが明快に説明され、わかりやすくて面白い。 それにしても日本は極端だし、中国とは似ているようで違うところがあるし、アメリカやヨーロッパ内でも国により違うことがわかる。 海外の人と仕事をする機会がある人にはお薦め、というか必読書だと思う。20年前に読んでいたらと思ったが、初版は2015年だった。 読書メモ: イントロダクション カルチャーマップ 絶対的な位置ではなく相対的な位置が重要 1 コミュニケーション ローコンケクスト、ハイコンテクスト ハイコンテクスト文化出身の人が別のハイコンテクスト文化出身の人とコミュニケーションをとるとき、最も行き違いが生じる可能性が高い。違うコンテクストを持つから。 多文化のチームではローコンケクストなやり取りを行うこと。ただし明文化する理由を事前に説明する。 2 評価 ネガテイブフィードバック 直接的、間接的 評価の指標で自分より率直な文化を相手にするときは彼らの真似をしようとしてはいけない。 ハイコンテクストかつ間接的ネガテイブフィードバックの戦略 1.グループの前で個人のフィードバックを行わない、2.メッセージをぼかす ぼかす戦略 フィードバックはゆっくりと。食べ物や飲み物を使う。良いことを言いわるいことは言うな。 3 説得 原理優先(演繹的思考法)、応用優先(帰納的思考法) アジアは包括的思考法、西洋は特定的 水中を描いたアニメ 人物撮影での反応 4 リード 平等主義、階層主義 権力格差 権力が不平等に行使されるのを下の者がどの程度許容し期待しているか ローマ帝国、ヴァイキング、宗教(カトリック、プロテスタント) アジアは孔子(儒教) グローバルビジネス環境ではリーダーはどちらもマネージできる柔軟性が必要。 5 決断 大文字の決断 Decision(議論が長い、決まったら議論はおしまいで実行は速い)、小文字の決断 decision (議論は短い、実行しながらさらなる議論、修正) 合意志向、トップダウン式 リードで平等主義なら合意志向、階層主義ならトップダウン式、例外は三ヶ国 アメリカ、ドイツ、日本 アメリカは平等主義でトップダウン ドイツは階層主義で合意志向 日本は、階層的、ボトムアップ式、超合意志向。稟議システム、根回し 自分の文化の意思決定システムに無自覚 6 信頼 タスクベースは認知的信頼と感情的信頼を分けて考える、関係ベースは認知的信頼と感情的信頼の両方がビジネスに織り込まれる 桃 vs ココナッツ 桃は柔らかいが突然硬い種にぶつかる。ココナッツは硬い殻を破るのには時間がかかるがいったんやぶれたら友好的になる。初対面で愛想がいいからといって関係志向とは限らない。 異なる文化の人と信頼を築くには感情的信頼関係を築くのに時間を割く。 感情的信頼を築くには食事に気を払う。日本では飲みニケーション。 関係ベースの文化圏での戦略がwasta 電話やメールは相手のやり方に従う。 7 見解の相違 対立型、対立回避型 対立型の文化では相手は傷つけず意見を攻撃する。対立回避型の社会ではその二つが密接に結びついている。 見解の相違と感情表現は別 対立型で感情表現控えめと対立回避型で感情表現豊かは複雑 中国と韓国は対立回避型だがグループ内とグループ外で振る舞いが異なる。そのため信頼の構築が役立つ。 自分より対立型の文化の人と仕事をする場合、わかるまでは強い言葉の使用には注意する。 自分の行動とその理由をユーモアと謙虚をもって説明する。 8 スケジューリング 直線的な時間、柔軟な時間 インドの行列は常緑樹、ミーティングも同じ。 柔軟性 正反対の相手のことを非効率的と思ってしまう。 エピローグ 自分の文化は認識しにくい。 カルチャーマップで文化の見取り図を作ってみる。違いを理解すれば断絶を防げる。
0投稿日: 2017.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ異文化理解するための8つの軸。 コミュニケーション ローコンテクスト、ハイコンテクスト。 評価 ネガティブフィードバックの仕方。直接的、間接的。 なぜとどうやって。原理優先、応用優先。包括的。 敬意。階層主義、平等主義。 決断。トップダウン、合意。 信頼。タスクベース、関係ベース。 対立。対立型、対立回避型。 時間。直線的、柔軟。 アメリカと日本はまーちかいほうなんだな〜〜っと感じた。
0投稿日: 2017.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人って変わっているんだなということを認識させられた。 ----- p32,54,59,61,68,78,86,89,93,95,99,108,123,127,142,144,146,148,159,167,174,176,196,207,208,213,247,251,279,299
0投稿日: 2017.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ異なる文化の人と仕事をする際には、語学力に加え、相手の考え方・気質を知ることがミス・コミュニケーションを防ぐ上で大切です。世界各国の国民性を図で目に見える形で表した"Cultural Map"をこの本では紹介しています。 (Yuhiさん)
0投稿日: 2017.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に勉強になった。第1章などの、ローコンハイコンの話はよく聞くが、それ以降のフィードバック、意思決定、時間管理などの文化別の概念は知らなかった。多国籍チームで働く必要性がない人には響かないかもしれないが、何らかの形でうちの研修にも取り入れられれば
0投稿日: 2016.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログThe Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business http://www.eijipress.co.jp/book/book.php?epcode=2208
0投稿日: 2016.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分より廃コンテクストな同僚たちと仕事をするときは、より注意深く聞くことを心がけよう。「私ができる最善のアドバイスは」ディアスは言う。「何を言っているかではなくなにを意味しているかを聞くように心がけることだ。つまり相手の発言を吟味して、明確になるような質問をして、相手のボディーランゲージをより敏感に察知するよう心がけることだ」言外の手がかりを探ろうとすることによって、少しずつ正確に「空気が読める」ようになっていくのである。(p.72) 遠回しに発言する文化では「ダウングレード」の機能を持つ言葉、批判を和らげる言葉を使う傾向にある。たとえばkind of(とも言える)、sort of(多少)、a little(少し)、a bit(やや)、maybe(かもしれない)、そしてslightly(若干)といtった言葉だ。ダウングレードする人々のなかには、実際には強く抱いている感情を抑えて慎重で控えめな表現をする人もいる―たとえば「まだ解決に至っていない」と言いながら、実際は「解決には程遠い」という意味だったり、「たんなる個人的な意見です」と言いながら、実際は「この問題に関わる人なら誰しもすぐに同意するだろう」という意味だったりする。(p.90) フランスには次のような言い回しがある。Quand on connait sa maladie, on est à moitié guéri―病気が認識できれば、半分は治ったようなものである。この言葉はほとんどの異文化間のいざこざにも当てはまる。自分に対する認識を得ることで、その認識は協力関係の向上に大いに役立つ。(p.104) アジアのビジネスリーダーたちの目には、ヨーロッパやアメリカの重役たちが自身の行動の影響の大きさをあまり考慮せずに決断を行っているように映る。韓国の自動車会社キア(起亜)のペ・パクは言う。「西洋の同僚たちと仕事をするときは、彼らが他部署や、クライアントや、業者たちへの影響を考えないまま決断を下す傾向にあってよく驚かされます。彼らの決断は性急で周りへの影響を無視していると感じることが多いのです。(p.143) もしあなたが合意志向とトップダウン式文化の両方がいるグローバルチームと仕事をするおきは、連携の最初の段階で意思決定の方法をはっきりと話し合い合意をとろう。チームでの議論のあと、投票で決断するのか、上司が決断するのか決めておこう。100%の賛同を得る必要があるか、決断の期日を決める必要があるか、期日後に決断を変更する柔軟性をどの程度持たせるか確認しておこう。それから、大きな決断を下さなければならないときは、意思決定のプロセスを再び検討し、そのプロセスを全員が理解し受け入れているかを確認しよう。(p.200) もしあなたが怒り狂って「なぜ私が潜在的なクライアントとの食事や交流にこんなにも時間を割かなければならないんだ?ビジネスの話から始めて、契約書にサインするだけじゃだめなのか?」と言っている自分に気づいたら、忘れないでおこう―多くの文化では、関係こそが契約なのである。相手なしに契約はできない。(p.229) 「ちょっと挨拶をする」ためにかける時間は、次に彼らの助けが必要なビジネス上の問題が起きたときに大きな利益となって返ってくる可能性が高い。信頼とは保険のようなものだ―実際の必要が生じる前に、あらかじめ投資をしておく必要があるのである。(p.239) 私は時間への認識の違いがどれほど大きな影響を持つか気づき始めていた。スケジューリングに対するラナトと私の考えの認識の差は、「良い顧客サービス」に対する対照的な考えに現れた。仕事相手が時間に対してどのように考えているかを知り―相手に求めるものを調整することの重要性をこの話は示している。(p.275) スケジュールを効果的に扱う第一の戦略は、様々なスタイルに適応できることは今日のグローバルマネジャーにとって重要なスキルである。(p.285) 誰と働いていようが、どこの人間と働いていようが、あなたは相手にしかない特別なものを理解しようという気持ちでどんな関係も始めるべきだ。彼らの文化的背景から、相手の思考や行動の特徴を決めつけてはならない。(p.305)
0投稿日: 2016.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本のオリジナルのタイトルは、「THE CULTURE MAP」で、丸の内にある丸善で見かけたときは、確か洋書部門で1番売れていた。英語力も異文化コミュニケーションには必要だが、異文化について知らないと地雷を踏むことになる。 意外に思ったのは、フランス人のコミュニケーションはあいまいなところを好むということだ。はっきりしているのがフランスだと思っていたので、驚きを隠せない。とは言っても日本人に比べれば、はっきりしている。 アングロサクソンとひとくくりで語られることの多いアメリカとイギリスだが、アメリカ人からするとイギリス人は、はっきり言わない。その一方でイギリス人からするとアメリカ人は・・・となる。英語が通じると思っても意思の疎通がうまくいくとは限らない。 人を動かす際に、トップダウン方式がいいのか、それともボトムアップ方式がいいのかということがあるが、相手にする国や地域の文化によって変えたほうが無難だ。 「人類みな兄弟」というキャッチフレーズのCMが流れていたことがある。文化の違いがある中でどうやって異文化コミュニケーションをとっていけばいいのか。そんなときに参考になる1冊だ。
0投稿日: 2016.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に興味深く 面白い本だった。 こういうことに焦点を当てて仕事を進められればより チームが機能する。 グローバルで働く中で大切な知識を提供してくれているし 日本の企業文化をとってみても 面白く読める。
0投稿日: 2016.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「異文化交流」から「異文化マネジメント」へ。 外国人とビジネスしたり部下として使う立場でなくても、異文化交流をビジネスの観点から分析した本として非常に興味深い。国内ビジネス、コミュニケーションであっても「ハイコンテクスト・ローコンテクスト」という観点から考えることは非常にメリットがある。ことビジネスに関しては、日本国内で完結していてもローコンテクストで進めるべきだろう。 多くの章で日本の特異性(根回し、飲みニケーション)が記述されており、卑下する必要は無いが括目して読むべきである。外国の経営層はこのような分析を完了したうえで日本(人)を攻略しようとしていると肝に銘ずるべきである。 「常識やろ!」と言われることがいかにローカルな約束事であるか。作者自身、あるいは作者が見聞きした体験談はまるで小噺というか国籍ジョークの宝庫である。
0投稿日: 2016.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分個人ではこれからグローバル社会となる時代において「この国はこうだ、あの国はこうだ」という決めつけなど意味がないと思っていました。そんな浅はかな考えを一掃してくれた本です。 この本の著者であるエリン・メイヤーは言います。「他の出身地の人々と働くときは出身地によって各人の性格を決めつけるべきでない。だからといって文化的コンテクストを学ばなくても良いという事にはならない。どちらの感性も大事なのだ。」と。 この本では一つの目安として 「コンテクスト」・・・ハイコンテクストかローコンテクストか? 「評価」・・・直接的なフィードバックか間接的なフィードバックか? 「説得」・・・原理優先か応用優先か? 「リード」・・・平等主義か階層主義か? 「決断」・・・合意思考かトップダウン思考か? 「信頼」・・・タスクベースか関係ベースか? 「見解の相違」・・・対立型か対立回避型か? 「スケジューリング」・・・直線的な時間、柔軟な時間? 最近巷で見る「ここがおかしいよ、日本人」みたいなものの言い方は自虐的でしかないよね、という事がわかる。アメリカもイギリスもオランダもイスラエルも日本も全部文化的個性が違う。あるものをおかしいといった所でしょうがなく、それをお互いに学び理解することが大事なのではないだろうか。この世には色々な国があり、全ては相対的なのだ。 上記のような切り分け方は企業や個人を評価する時にも有用な切り分け方ではないかと感じた。
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段の仕事で漠然と感じていた、各国のカルチャーの違い。仕事の進め方の違い。一回では、理解しきれないけど、やっぱりと思う事が、沢山書かれていました。
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログリーダーシップ、評価、意思決定、スケジューリングといったビジネスの現場で必ず発生する8つの行為を題材に、世界各国の人々の統計調査をベースに、各国の相対的な価値観のポジショニングを見事にまとめ上げた一冊。そして凄いのは、これが学術的・ビジネスの現場における有意義性と同時に一級のリーダビリティを兼ね揃えているということ、とにかく面白くて一気に読んでしまった。 本書が優れているのは、例えばコミュニケーションに関して「ローコンテクストorハイコンテクスト」という軸で、各国の文化がどこに位置するかを明示している点にある。そしてここからの重要な示唆は、「絶対的な位置ではなく、自国と比べた際の相対的な位置関係の把握こそが異文化理解のためには重要」という視点である。 想像どおり、最もハイコンテクストな国は日本であり、ローコンテクストな国はアメリカとなる。日本のように極端なポジションの国から見ると、他の全ての国は等しくローコンテクストのように見えてしまうが、実態はそうではない。イタリアから見れば、ロシアはハイコンテクストな国だが、イギリスはローコンテクストな国であるように、ある国から相対的に見てどうか、という点を本書のポジショニングで理解することができる。 また、面白いのは、コミュニケーション(ローコンテクストorハイコンテクスト)と評価(ネガティブフィードバックは間接的or直接的)の2軸のポジショニングである。直観的に我々は、ローコンテクストな国=ネガティブフィードバックは直接的、ハイコンテクストな国=ネガティブフィードバックは間接的、と捉えてしまいやすい。しかし、この両者の関係が逆転するケースが実は存在している。この代表例は最もローコンテクストな文化を持つアメリカである。アメリカではネガティブなフィードバックを相手に直接伝えるようなイメージがあったが、実は評価におけるネガティブフィードバックは例外的に間接的に伝えるのだという。このようなイメージとは異なる事実を、ビジュアルで理解でき、我々のパブリックイメージが崩れていく面白さを本書では楽しむことができる。
2投稿日: 2016.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が推奨する8つの指標で我が日本はいつもスケールの一番端に位置しているのが目に付いた。行間を読む文化や、人を傷つける直接的な物言いを避けたり、とっても階層的な社会なのに極端な合意志向、対立回避型で、時間管理は細かい。こんな特徴的な文化背景に育った僕らが、国際交流の現場で苦労するのは当然のことなんだね。常々攻撃的と感じていたオランダやドイツでは、それが悪気ではないとはいえ、とても暮らせそうにありません。日本に暮らす外国人や、海外で暮らす邦人の勇気と苦労には頭が下がります。とっても面白い本でした。
3投稿日: 2016.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログindex 1 空気に耳を澄ます ―― 異文化間のコミュニケーション 2 様々な礼節のかたち ―― 勤務評価とネガティブ・フィードバック 3 「なぜ」VS「どうやって」 ―― 多文化世界における説得の技術 4 敬意はどれくらい必要? ―― リーダーシップ、階層、パワー 5 大文字の決断か小文字の決断か ―― 誰が、どうやって決断する? 6 頭か心か ―― 二種類の信頼とその構築法 7 ナイフではなく針を ―― 生産的に見解の相違を伝える 8 遅いってどれくらい? ―― スケジューリングと各文化の時間に対する認識 memo ■ハイコンテキストとローコンテキストと、コミュニケーション習慣の相違によって情報の受け取り方に差異が生じる。差異によって生じる問題解決のためのシチュエーション毎のケーススタディ。
0投稿日: 2015.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書では文化的背景の行き違いによる様々なエピソードが登場する。 例えば、あるブラジル人はアメリカ人の上司から食事に招かれた。 ブラジルでは約束の時間に遅れていくのがマナーだ。 時間ピッタリに行くと、相手がまだ準備できていないかもしれない。 このブラジル人は念のため、上司に配慮して35分遅れて訪問した。 上司からは(日本人でもそうするように)心配そうに「道に迷ったのか? 渋滞してたのか?」と質問され、食事の準備はすっかり整っていた、という。 本書は「カルチャーマップ」という指標と具体的な事例を用いて、各国の文化による違いを示し、そしてそれによる誤解や不要な損失を防ぐための提案をしている。 著者のエリン・メイヤーは Thinker 50で「RADAR AWARDS 2015」を受賞した。 (http://thinkers50.com/t50-awards/awards-2015/) 「RADAR」とは日本語でもそのまま「レーダー」と訳される探査装置である。 しかし「レーダー賞」では意味がよくわからない。 その意味は ・The new generation of business thinker ・most likely to shape the future of business and business thinking ・(the) work has the potential to challenge the way we think about management 「RADAR AWARDS 2015」より とある。 「未来のマネジメントに向けたチャレンジングで最も将来性のある新世代のビジネス思想家」 といった意味になるだろう。 本書は8つの指標について、各国のコミュニケーション文化を2極またはマトリクスで表現する。 1.コミュニケーション 2.評価 3.説得 4.リード(※筆者注 リーダー的な振る舞いのこと) 5.決断 6.信頼 7.見解の相違 8.スケジューリング 最初に紹介した食事に招かれたエピソードは「8.スケジューリング」についてのアメリカとブラジルの文化の違いで登場する。 本書では、日本についても多く言及されている。 例えば「KY」「稟議書」「飲みニケーション」といった日本特有の文化や価値観を紹介し、他国の人が日本人を相手に、あるいは日本人と一緒に仕事をする上でどのような点に気を付けたらよいかアドバイスがされている。 また他国の人についても、実は理解は一筋縄でいかないことが解説されている。 例えば社員としてオランダで社長と接するときと、中国で社長と接するときとでは、取るべき態度が全く異なることが分かる。 どのように異なるかは本書を読んでいただくのが良い。 本書は「多国籍のチームにおけるマネジメント」を円滑に行うために書かれた本であり、人気書評サイト「HOZ」にて「残念ながら日本人の8割にこのビジネス書はいらない」という逆説的な評価で話題となった。 もちろん本書の内容を貶めているのではなく「残念ながらこの本を活かせるような多文化チームをマネジメントするような職務についている日本人は少ない」という意味だろう。 ただ、僕としてはこれに異議を唱えたい。 「異文化」とは国と国の間だけに存在するのではない。 例えば自分が中小企業勤務で大企業を相手にビジネスを持ちかける場合や、逆に大企業からベンチャー企業に転職する場合、あるいは、ある業界から別の業界に転職する場合など、様々な場面で「異文化」に接し、戸惑う機会があると思うからだ。 そういう意味では、ビジネスマンの2割ではなく、もっと幅広く読まれるべき本だと思う。
0投稿日: 2015.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白すぎて、休みを使って一気に読んでしまった。ここで重要なのは、この面白いという感覚は居酒屋で血液型占いをするような、人間を各国のステレオタイプに当てはめて騒ぎたてる下卑たものではなく、いわば冠婚葬祭入門のように異文化理解とグローバルビジネスに対して極めて実践的基礎的な知識を学べるからである。 著者はグローバルビジネスをするにあたって各国を8つの指標- ①コミュニケーション(率直/空気を読む) ②評価(直接的/間接的) ③説得(理屈/実践) ④リード(平等/階層主義) ⑤決断(合意/トップダウン) ⑥信頼(業務/人間ベース) ⑦見解の相違(対立/回避型) ⑧スケジューリング(直線/柔軟) に分けて、異なる立ち位置の人とビジネスをする際どのようなトラブルが起きやすいか、またどのように解決するかを豊富な実例を用いて事細かに説明している。 個々人を相手にする場合もちろん更なる応用が求められるだろう。だが、某錬金術師とは違い、文化を理解する場合において全は一を内包するが、一は全には成り得ない。であれば、前もって予備知識として仕入れておくことは決して無駄ではないはずだ。 さっき述べたように、冠婚葬祭入門のグローバルビジネス版として、また単純にコミュニケーション学としてとてもとても面白かった。やっぱり自分はノンフィクションが好きだわ。
0投稿日: 2015.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとても有意義な一冊!グローバルに仕事をしてる人は必読の一冊。以下、備忘録代わりのメモ。 ハイコンテクスト文化出身の人同士(日本人と中国人など)のコミュニケーションが、最も行き違いが起きやすい。文化的背景が異なれば、読むべき空気も異なるため。よって、多文化チームではローコンテクストなやりとりをすべき。明文化、透明化、明確化など。ただし、いきなりローコンテクストで望むと、ハイコンテクストな文化の人達には信頼の欠如と映ることがあるため、事前にチーム内で説明し、同意を得ること。 欧米でも、全員が結論から議論をスタートではないということは目から鱗。そして、写真の実験は面白い。マクロからミクロ(包括的)なアジア人というのは納得。 階層的かつ合意的という、世界でも唯一無二な日本。まさか稟議システムが日本独自のものとは。 特に新興国では、書類ではなく関係こそが信頼たる契約に他ならない。 同じアジアでも日本と中国で違う点は多々ある。スケジューリングもそう。先の予定より、その瞬間重要な事項を優先する。中国人は極めて柔軟。 人はみな同じであり、みな違う。
0投稿日: 2015.10.19
