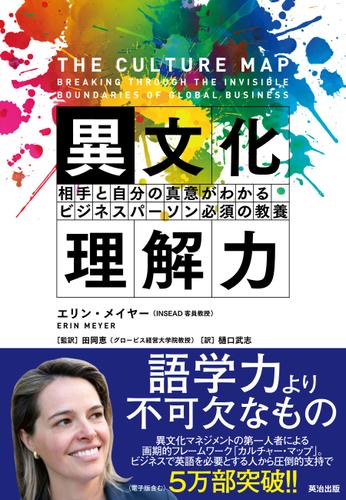
総合評価
(122件)| 62 | ||
| 40 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ<OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/G2Eac696DHcsEqyiyEmWCplXYei/description.html
0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ国ごとに性格の傾向を分類するのには抵抗があったけど、まず個々人の性格がある前提を冒頭に書いてくれていて、抵抗なく読み進められた。 この本のおかげで、ある出来事を異文化という視点で考える新たな自分に出会えたので、以下備忘。 -備忘-(日本での出来事) 先日インド人(A)とミャンマー人(S)と遊びに行く機会があった。(僕は途中集合予定) Sが10時待ち合わせと提案したため、Aは10時前に待ち合わせ場所に到着。 しかし直前にSから昼集合、場所変更連絡があり。 Aは時間を潰しつつ次の待ち合わせ場所に移動。 僕は予定があったため12時にAと合流。 その後Sは何度か時間変更を重ね、最終的に私たちは16時に合流を果たした。 Aは、冷静を保っていたものの、Sの時間のルーズさに憤慨していた。 Aは日本に適応して時間通りを意識しているという。 でもこのケースでは、AはSの文化を理解することが必要だった。かと言って僕がAの文化を意識して、少し時間にルーズでいたら、すれ違いが生じただろう(途中参加でよかった〜) とにかくこの件を通して、頭での異文化理解だけでなく、言葉を使って認識を合わせることの重要性を感じた。
0投稿日: 2025.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログINSEAD教授Erin Meyerの「The Culture Map」の翻訳版。様々な背景を持つ人々をマネージメントする上で重要な8つの領域について、文化的な背景の違いを様々なエピソードを紹介しつつ解説しています。特に優れているのは、本書のタイトルにもなっている「カルチャー・マップ」です。上記の文化的な違いを可視化し、相対的に評価することを可能にしています。かなり気づきが多かったです。これを日本人だけのチームでも、個人別に「カルチャー・マップ」を作成すれば、世代間のギャップを埋めるのにも役立ちそうです。
0投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外と一口に言っても様々な国があり、それぞれの文化や気質は異なっている。それに伴って良しとされるコミュニケーションスタイルも異なる。ローコンテクストかハイコンテクストか、ネガティブなフィードバックを直接的に行うのか、そうでないのか、合意志向かトップダウンか。それを知らずにコミュニケーションを取ると思わぬ地雷を踏むことになる。
0投稿日: 2025.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログオーストラリアのWorkawayのホストの家にあった本。 日本って結構ほとんどのspectrumでどっちかの端っこにいたのが面白かった。 いろんな考え方があるけど、それぞれそうなった理由やそれがその国ではうまく機能する理由があって、どれが間違っているとかではない。インド人が期限を守らないのに日本人がイラつくように、日本人に柔軟性がないことに対してインド人はイラつく。
1投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ豊富な具体例がエピソードとして面白いし、筆者の伝えたいことがよくわかる。文化の多様性はトラブルも生むけど豊かさを含んでいると思う。 外国人だけでなく日本人同士でもそれぞれの傾向があるので、グローバルビジネスと無縁の人でも参考になるだろう。 面白くてためになる本。
0投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語以上に文化を理解することは大切で難しい。日本で生まれ育ち当たり前な環境も世界では異端。コミュニケーション、評価、説得、リード、決断、信頼、見解の相違、スケジューリングの8つからなるカルチャーマップで日本は両極端な評価となっている。
18投稿日: 2024.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバルビジネスを行う上で、異なる文化的背景を持つ人たちとすれ違いやストレスなく上手くやるにはどうするか。具体的な実例を折り込みながら書かれており、理論がすっと腑に落ちる。 ドイツ人は真っ直ぐに質問や批判をしてきて面食らってしまう。日本人って奥ゆかしくて、でも、控えめすぎて意見がないと思われてる。そんな経験ないだろうか?フィードバック、信頼関係、議論の仕方、時間感覚など各指標でその国の文化がどこに位置し、その相対的な位置関係をみることで関係性やその文化圏の人々から受ける印象を理解する手掛かりとする。 これは異なる文化圏の国を理解するのにも役立つし、応用すれば同じ国同士でも、あの人とはちょっと合わないなぁみたいなときにもその人を理解する一助になるのではないかと思う。育った環境も文化と言えば文化であろうから。
0投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ実践的な内容が盛りだくさんで大変参考になる。この本の内容を頭に叩き込んだとしても、やはり実践で失敗しながら身につけていくものなのだろうと想像する。多国籍からなるチームで仕事をする際に最初にお互いの文化を理解し合うワークショップを実施しておくのは効果的に見えた。ぜひやってみたい。
1投稿日: 2024.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃ良書。読み終わってから日本人、外国人問わず何人に勧めたか分からないくらい。日本では、グローバルっていうと、なんかアメリカ的な習慣・考え方が海外・欧米のど真ん中だと思っている人が本当に多いように思ってて、ずっと違和感を感じてたんですが、まさにその答えを提示してくれている。日本的な価値観とアメリカ的な価値観とヨーロッパ(フランス・スペインVSドイツ・オランダ)的なものなどなど、相対的な価値観の位置関係が分析され語られています。マルチカルチュラルな環境で仕事をする可能性のある方は、是非とも読まれることを強くお勧めします!
1投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「NO RULES」の中で言及されており、グローバルにはたらくうえで必読だろうと考えて手に取った。 異なる文化的背景をもつ国の人たちの考え方について学ぼうと思って読み始めたが、日本人の振る舞い、考え方についても理解を深めることができた。自分たちの文化を客観的に捉え、他の文化圏の人からどう認識されるかを前もって理解するのは自分たちでは難しいため、このような本でその点を学べたのもよかった。 結局のところ、相手を理解しようと思う気持ち、対話し、歩み寄ろうとする気持ちというのが、コミュニケーションをとる上で重要だと感じる。本書で学べる、文化間の考え方の傾向というのは、あくまでもそのコミュニケーションをより円滑にするためのヒントのようなものかなと感じた。
1投稿日: 2024.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ多様性を学ぼうシリーズ第4弾。異文化理解力をビジネスの観点で解説してくれる。この本の面白いのは、ビジネスに必要な8つの要素について、各国の比較をしているところ。8つの要素とは、コミュニケーション、評価、説得、リード、決断、信頼、見解の相違、スケジューリング。一例としてコミュニケーションの指標では、ローコンテクスト(シンプルで明確、額面通り)とハイコンテクスト(繊細で多層的、行間を読む必要がある)の分布があり、日本(ハイコンテクストの最たる事例)から見ると、欧米人は皆同じローコンテクストに見えるが、イタリア人は、アメリカ人が大切なことだからと何度も念を押すことを、子供扱いされていると憤る。もちろん、〇〇人が皆同じなわけはなく、日本人でも青森の人と沖縄の人は違うよという主張もあるが、傾向で見ると必ず釣鐘型の分布となり、ほとんどの人が”日本人らしく”振る舞うだろう。これ、海外の方と仕事をするときなどに本当に役立つと思う。異文化理解にもってこいの一冊。
0投稿日: 2024.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#異文化理解力』 ほぼ日書評 Day748 Day744と重なる内容が多いが、こちらの方がより異文化コミュニケーションのhowに特化した内容なので、そのあたりに興味のある方にはオススメ。 https://amzn.to/48G4diW
0投稿日: 2024.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「○○人は△△だ」という考え方は主語が大きすぎるし、個人の特性を無視して偏見に繋がる良くない考え方だ。 と思っていましたが、この本での私の一番の気付きは「物の見方・考え方それ自体に、自分が属する文化圏のフィルターが反映されている」という点です。 サブタイトルに「自分の」と含まれているのも、異文化理解において大切なことだと筆者が考えているからでしょう。 自分も相手も色付きのサングラスをかけていることを自覚し、互いの文化と個性を尊重しながらコミュニケーションをとることで、良好な関係とアウトプットを生み出せる。 いつかグローバルなチームを率いる立場になったら、また必ず読み直そうと思える良本です。
0投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ国ごとに常識とされている文化の違いをジャンル別に論じている本。具体例も多く、日本の事例も数多く出ているためとても興味深く読めた。 日本人だけの職場でも、ネガティブフィードバックを出すのが得意な人/苦手な人、トップダウン式の決定を望む/合意形成を望む、など若干の差があるため、使える部分が多いです。
0投稿日: 2023.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ白百合女子大学英語英文学科 上野由佳先生お薦めの一冊です。 ~上野先生より~ 異文化理解というと、相手の文化を私たちがどれぐらい理解できるか、との点だけに意識を向けていませんか?でも実際にはそれと同じぐらい、あるいはそれ以上に、自分の意見を異なる文化の人に理解してもらうことも必要です。では、そのためにはどうすればいいのでしょう。まずは文化によるコミュニケーションスタイルの違いを把握することが第一歩となります。これをわかりやすく解説したのがこの『異文化理解力』です。文化の差を「カルチャー・マップ」を使って可視化し、文化の見取り図を解説しています。読み進めると、「なるほど!やっぱりそうか」「え、本当?」とさまざまな発見が得られます。一例を挙げると、「空気を読む」は日本固有の文化の様に思えます。でも、程度の差はありますが、「空気を読む」文化を有する国は他にもあることが同書を読むとわかります。(*原書では「空気を読む」は”listening to the air”となっています。)日本以外ではどんな国が空気を読む文化を有しているのか、あるいは、空気を読んでしまうと、全くコミュニケーションが取れない国はどこなのか、一目でわかる様になっています。 留学を希望する人、将来グローバルに働きたい人、そして日本を客観視したい人にとっても非常に面白い本です。ぜひ一読をお勧めします。
0投稿日: 2023.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい視点を提供してくれました。まずは知れました。 とはいえ、書かれているように、試して失敗して見直して慣れる、真の姿。
1投稿日: 2023.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログカルチャーマップなどいくつかのフレームワークを用いて異文化コミュニケーションの気付きを与えてくれる本。グローバルで仕事をすることが当たり前になった昨今では良く理解すべきポイントを散りばめられていると感じるが、結局は巻末にあるように「私たちはみんな同じで、みんな違う」という点に集約されるのかと思う。結局ひとりひとり違う中で生きているため、相手が何を言っているかではなく何を意味しているかを聞くように心がけることが最も重要だと思う。
0投稿日: 2023.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはすごい本です。主にビジネスにおける各国の文化の違いを8要素のパラメータを使って明確に示してくれています。海外に行くにあたって英語を勉強するのも大事ですが、この文化の違いを理解することは同じくらい重要だと思えます。それぞれの文化の特徴が生まれた歴史的背景にまで言及しているのがまた面白いです。説得のタイプの原理優先か応用優先か、の説明にイギリス経験論と大陸合理論の比較が出てくるところなんて最高です。 個人的にインド人と仕事をしているのですが、ハイコンテクスト、階層主義、柔軟な時間、関係ベースの信頼、などなど、実際に経験する身として心底納得できる説明でした。そういった外国人の文化の違いに対して、自分の文化と比較して批判したり不満をもってしまいがちです。本書の最も素晴らしい点は、そんな彼らの特徴を可視化して相対化してくれることで、優劣で語ることなく冷静に対処するマインドを持てるようになることです。 とは言っても、本書では慎重に優劣について言及しない配慮がなされていますが、その時々の状況によって文化の優劣が出てきても当然だと思えます。そこに一歩踏み込んでくれていたら良かったと思いつつ、それを語るとどうしても異文化の否定につながるので、難しいところですね。さらに、時代による文化の変化についてもあまり語られていません。ビジネスのローバル化によって、この国ごとの偏りが減り、より合理的な方向に収束していく未来もあり得るかも知れません。 改めて思うのが、外から見た時の日本人の厄介さです。ハイコンテクストであることを筆頭にあらゆる特徴が極端な方向に振れています。特に、関係ベースの信頼なのに、職場では打ち解けず、お酒の席の無礼講がないと関係を構築できないところ。私のようなあまり飲めない人には本当に厄介です。そんな日本人は、日本人だけで集められた時に最高のパフォーマンスを発揮するのではないかという仮説が頭に浮かびました。そうなると、移民政策や英語教育などが国力を低下させる、という可能性もあるなと。
1投稿日: 2023.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な国の人と付き合っていく時の、物事や言葉の捉え方の違いを、ケーススタディを使ってわかりやすく解説している。 若干単調ではあるが、仕事などで海外と付き合いがある人なら参考になるかと。
0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で海外社員の方と交流が増えたため、手に取った本。筆者が日本人でないため、少し読んでいて違和感があるが、非常に異文化についてまとまっている内容となっている。海外関連の仕事をする人にとってはマストな書籍かもしれない。国によって文化が異なるので、様々な国籍の方が集まる職場では、マネジメントに正解はない。他国の文化を理解して、モチベーションをupさせる必要がある。特に仕事に対してのフィードバックの方法には注意をする必要があると感じた。国によってフォローの方法がまるっきり異なる。 本文の抜粋で、この本を一言でまとめるなら、以下の文になるだろう。 ”グローバル環境において「気が利く」と言う事はつまり、相手と自分の文化の違いを理解して、「皆が心地よく良いパフォーマンスを出せる環境を作り出す」ことなのだ。”
0投稿日: 2022.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の上司にも勧められ、今回グローバル研修をしていただいた講師にも勧められ再読。 国によって、コミュニケーションの方法、フィードバックの方法、決定の方法などが異なり、その国の人に受け入れやすい方法が例が出され説明されている。まずは、このような違いがあることを理解し、もし他の国の人と一緒に働くこととなったら、再読し具体的な気を付けるポイントを確認してみよう。
0投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ国ごとの文化の違いによる仕事の進め方の違いについて、こんなにきれいにまとめた本は初めて読んだ。実際にこの知識を活用して仕事に生かしたいと思った。
0投稿日: 2022.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ異文化理解とはどのようなことか、ビジネスシーンをメインに、相手と交流する際の極意が書かれている。 授業の一環で読んだ。 著者の実体験など具体的な例を挙げながら、様々な観点から、異文化を理解し、適切なコミュニケーションを取るために私たちが気をつけることが事細かに書かれている。今の国際社会における必読書の一つだと思った。
0投稿日: 2022.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文化的な背景を理解した上で対応することについて。通り一辺倒とならず、文化的な傾向を知った上で対応することについて重要に思いました。 文化の違いによる期待される行動の違いについて。東南アジアにおけるボスらしくふるまうことの重要性などは、読んだ当初とても印象深く感じたのを覚えています。 とはいえここに書いてあることを実践したつもりで失敗するシチュエーションはそうていできました。①その国における集団の解像度が低い、ないしは一枚岩ととらえて雑に理解したつもりで修正することを怠る。②そもそも自分の行動をコントロールできていない、ないしは自分の行動の見え方についてある程度妥当な評価をできていない。 つまりは背景があるという一般論として同書籍の内容を把握しつつ、細かい修正や思考を怠らないことが結局は重要なのではないかという認識を改めて。
0投稿日: 2022.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ●はじめに 沈黙のボー、失聴のデュラック、インドの縦とも横とも取れぬ首振りなど。 →文化の違いで生じるビジネスコミュニケーションの難題を理解、対応するアプローチを提示する本 行き違いを避けられるように。 個性に着目することと、文化に着目することは両方重要。文化は知覚、認識、行動に影響。(何を見て何を考え何をするか) これを読み解く力をつけるのが本書の目的 カルチャーマップ、という8つの指標を用いる。 国ごとの絶対的な位置ではなく、多国間の相対的な位置が重要。 目は二つ、耳も二つ、口は一つ。数に応じて使いなさい。異文化と交流する際は、話す前に耳を傾け、行動する前に学ぼう。(個人的に、孫氏の兵法、敵を知り己を知れば百戦危うからず、とも誓いと感じた) ●read the air 空気に耳を澄ます(コミュニケーション) 良い聞き手であることが大事 ★ロー/ハイコンテクスト アメリカが最もローコンテクスト、カナダ、オーストラリア、オランダ、ドイツ、イギリスと続く ハイコンテクストなのは、日本インド中国など。 言語もその地域のスタイルを反映する。 ハイコンテクストな文化圏は長い間共有した歴史を持つことが多い。日本は単一民族の島国。数千年の歴史。アメリカは数100年の歴史。世界各国の移民で成り立つ。 →文化的多様性のある国はローコンテクスト 国の間の相対的な位置が重要。 イギリスは決まったことを最後に口頭で繰り返すのが通例。文書となりフォローされる。フランスはしなくてもわかってる。 メールも、すぐ返事できない時はいつ返事するか返しておくのが米英。仏西伊やラテン系の国はやらないハイコンテクスト。 自分よりハイコンテクストな人の場合、とりわけ話をよく聞こう。 ハイコンテクスト同士が一番誤解が生まれやすい。 ★多分かのチームではローコンテクストなやり取りを行うべき。交代制で、一人がキーポイントを口頭でまとめる。各人が各々がやることを口頭でまとめる。一人が文書にして送る。信頼の欠如と取られないようにルール化には説明が必要。 ●さまざまな礼節の形(評価) ●全体への感想 NOEの人に感じていた、疑問、そんな直接的に、ぶっきらぼうに言わなくても、というのが紐解けた。 子供の時はローコンテクストだったはず。馴染めないわけはない。
1投稿日: 2022.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ原書The Culture Map をaudible で聴いてからの日本語で再読。グローバルチームで働く人の必読書。
0投稿日: 2022.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ前職の社長が薦めていた本で、外国人だけでなく、(自分にとって)異なる文化の中で働く日本人とも関わる上で参考になると思って読んだ。 国ベースでのビジネスにおける文化の違いがメインだが、同じ文化の中でも個人差のレンジがあることにも注意しつつ、それぞれの文化を理解するうえでの項目ごとの分布(カルチャーマップ)と言っていた。 いろんな企業、また外国人の同僚・上司と働くうえで応用できそうな考え方が多く、勉強になった。 また、日本の世界における位置付けや特殊性も客観的に見ることができる。こちらも実務上で活用できそう。
0投稿日: 2022.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変面白かった。 国の文化の違い、異文化について書かれているけど、同じ国の人同士でも"異文化"を感じることはあると思う。自分のベースの考えに、この本の内容が入っていれば、円滑なコミニュケーションを図ること、またビジネスを進めることの助けになると思う。
0投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく良くまとめられてて参考になる本 こーゆー違いは国籍別だけではなくて、同じ国の人同士でもみられる いままではなぜ理解してくれないのかと思っていたことが、文化や考え方や教育方針によるものであると知り、寛容になった
0投稿日: 2022.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ…ハイコンテクストの文化圏では、学があり教養があればあるほど、話す際も聞く際も裏に秘められたメッセージを読み取る能力が高くなる。そして反対に、ローコンテクストの文化圏では、学があり教養のあるビジネスパーソンであればあるほど、明快で曖昧さのないコミュニケーションを取るのである。その結果、フランスや日本企業の会長は現場で働く社員よりもはるかにハイコンテクストである可能性が高くなり、アメリカやオーストラリアの企業の会長は新入社員よりもはるかにローコンテクストである可能性が高くなる。この点において、教育はその国の文化が持つ傾向を極端にまで体現した個人を生み出そうとするものだと言える。 ■二種類の思考法 原理優先の思考法(ときに演繹的思考とも呼ばれる)は、結論や事実を一般的原理や概念から導き出す思考法だ。たとえば、「人間はみな死ぬ」という一般原理から始めて、次に具体的な事例「ジャスティン・ビーバーは人間だ」に移る。そこで「ジャスティン・ビーバーも、やがては、死ぬ」という結論が導き出される。… 反対に、応用優先の思考法(ときに帰納的思考とも呼ばれる)は、現実世界の個別の事実を積み重ねることで普遍的な結論へと至る思考法だ。… 多くの人は原理優先と応用優先の思考法のどちらも使うことができる。しかしどちらを習慣的に使うかは、自身の文化の教育が重きを置く思考法に大きく影響されている。そのため、あなたとは反対の思考法に慣れている人と仕事をするとたちまち問題が生じてしまうのだ。 …応用優先の思考を持つ人々はまず実例をほしがる。その実例の数々から結論を導くのである。同じように、応用優先で学ぶ人々は「事例研究法」に親しんでおり、彼らはまずケース・スタディを読んで現実世界のビジネスにおける問題や解決策を学び、そこから帰納的に一般原理を引き出そうとする。 原理優先の思考を持つ人々も実例を嫌いではないが、応用へ移る前に基本的な枠組みを理解しておくのを好む。 ■権力格差 権力が不平等に行使されるのを組織の下の者がどの程度許容し期待しているか ■認知的信頼と感情的信頼 認知的信頼は相手の業績や、技術や、確実性に対する確信に基づいている。頭から来る信頼だと言っていい。この信頼の多くは、ビジネス上のやり取りを通して形成される。一緒に働くなかで、あなたは自分の仕事を全うし、その仕事を通して自分は頼りがいがあり、働きやすく、一貫性があり、知的で、裏表がないことを示す。その結果、私はあなたを信頼する。 感情的信頼は、反対に、親密さや、共感や、友情といった感情から形成される。心から来る信頼だと言っていい。共に笑い、打ち解け合い、互いに個人的なレベルで付き合うことで、あなたへの愛情や共感が生まれ、あなたもまた私にそのような感情を抱いていると感じる。その結果、私はあなたを信頼する。 ■8つの指標 1.コミュニケーション ローコンテクスト⇔ハイコンテクスト 2.評価 直接的なネガティブ・フィードバック⇔間接的なネガティブ・フィードバック 3.説得 原理優先⇔応用優先 4.リード 平等主義⇔階層主義 5.決断 合意志向⇔トップダウン式 6.信頼 タスクベース⇔関係ベース 7.見解の相違 対立型⇔対立回避型 8.スケジューリング 直接的な時間⇔柔軟な時間
0投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバル化が進んだ今日日、異文化の中で仕事をし結果を出さなければならない場面は増えている。実際、自分も長らくそうした環境において仕事をしてきたが、それは簡単ではない。典型的なのが、なぜ相手はこうなんだというフラストレーションを感じ、さらには相手が悪いという思考に陥って、双方で非難し合うという事態を何度も見てきている。 本書では、アメリカ人はどうだ、日本人はこうだ、インド人はああだ、という具合に色々なエピソードやケーススタディが豊富に挙げられているが、国民性や文化の特徴を一般化する事そのものは間違いにつながり易い。あくまで、そうした傾向があるという事であり、それらを鵜呑みにして実践に落とし込むことは思わぬ落とし穴に陥りかねないし、そうしたリスクは本書でも述べられている。また、国民性を一つ一つ覚える事も不可能であり、その国の中にも地域事に異なる文化を持つことは当然である。日本の国内でも関東と関西、さらに関西の中でも大阪と京都では人々の行動や考え方も同じでは無い。 大事なのは、まず自分の文化的背景と相手のそれが同じではないという事を前提として理解する事である。そして、違いについてコミュニケーションする機会を積極的に持ち話し合う事である。異文化環境での成功を望むのであれば、違いについて関心や興味を持ち、敬意を払い、違いを楽しむ位の気持ちが必要である。実のところ、そうした心の持ち方は特段、外国人との関係だけに於いてではなく、日本人同志であってそうであるべきであろう。多様性に対する理解が求められる21世紀の現代においては、相手に対する理解と思いやりや寛容さと、違いに直面した際にはそれを否定せず、なぜそうなんだろうかという想像力がなければならない。本書の最終章でも、結びとして、我々はそれぞれ異なる、そして我々は同じでもあると。
0投稿日: 2022.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスのおける認識の差異や齟齬は個々の性質ではなく、文化の差異によって引き起こされる。仕事上、日本対外国1ヵ国であれば良いが、対外国nカ国となった場合の振る舞い方が難しいと感じた。各国の文化を理解したうえで、それらの中間をとるような振る舞いが求められるはず。本書を読むに、カルチャーマップのどの要素もクローズかつデリケートな方に合わせるのが効果的に思える。例えば、オープンな批判がOKな国が居たとしても、そうでない国(中国など)がいれば、そちらに合わせて振る舞うなど。
0投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ国毎のステレオタイプを知ることは個人を尊重しないことではない。ということを学んだ。 グローバルな人材が集まる職場ではないし、自身も英語は全く話せない。しかし、今後日本語が堪能な外国人が同僚や顧客になるケースはあり得る。そうなった時に文化の違いを知識として持っているかいないかでは大きな違いが出るだろう。 ちなみに本書の中では日本の文化についてもいくつか触れられているが、我々の慣れ親しんだ「稟議」が文化の外側から見ると非常に奇妙なシステムに見えることについて初めて知った。 まさに金魚は水を知らない、である。
0投稿日: 2021.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスシーンの事例が多く挙げられていた 自分にはまだ経験がないためわからないことが多かった また社会人になったら読みたい
0投稿日: 2021.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ4.3 英会話に行き始めて各国の文化に興味を持ったため本書を読むことにした。この本を読むまでは、ドイツ人は真面目、アメリカ人は適当、イタリア人は陽気など一つの着眼点で各文化を一括りにしていた自分が恥ずかしい。 さまざまな異文化チームでの苦労話をあげながら何故そうなったのか、どう対応していけば解決できるかが説明されていて勉強になった。 海外赴任する重役達に赴任先の文化に基づいたリーダーシップを教えるコンサルティング事業があるなんて想像もしていなかった。自分は良くも悪くも単一民族国家の国民なんだということを凄く理解した。 面白い!
1投稿日: 2021.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログハイコンテクスト⇄ローコンテクストのものさしは有名です。 この本では8つの領域の「カルチャーマップ」で文化の違いを可視化しています 多くのマップ上で、日本が極端な位置にあることも印象的で、日本の文化的特殊性を再認識できます 海外の方と働く機会がある人におすすめ!
0投稿日: 2021.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ文化によってこれほど受け取り方が変わるのか、と驚く。お堅い日本のメーカー勤務だから、まったく異なる外資で働いてみたいな、と思ったり。 自分の当たり前が他人の当たり前ではないことはわかってるつもりだけど、なかなか意識して行動するって難しい。 思いを言葉にするってコミュニケーションの上でとても大切だけど、伝え方ってむずしいね。 伝え方が9割だって話もあるくらいだしね。 それはそうと、 本書で紹介されてた「対立に参加する時には、一刀両断するナイフではなく、縫い合わせる針を持っていけばいい」って言葉とてもステキ!!
1投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
グローバルカンパニーで働く上で、多様なバックグラウンドを持つ海外ビジネスマンとの間に潜む障壁(言語は勿論、志向性やコミュニケーション力など)を乗り越えるための方法が、分かりやすく解説されている。 また、自分自身の棚卸しもできるため、自分を客観視して強みを把握したい場合なども、一読の価値ありです。
0投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯に書いてある通り“語学力より不可欠”な異文化を理解する力が養えます。 階層性やネガティブフィードバックのスタイルなど様々な切り口で各文化の差異が相対的にマッピングされることで文化間のギャップが理解できました。 差異を知るだけでなく異なる価値観の人々とどのように接するべきか、筆者と周囲が経験したグローバルなビジネスの場での例を使いながら説明しているため実践的です。 読み進めると分かるのですが、日本は多くの軸で最端に位置しており、世界的にみてもかなり特殊なようで、それ故にエピソード例として多く登場するので日本人にオススメです。
2投稿日: 2021.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログPEGLの課題図書。 異文化でのコミュニケーション、思考の違いを具体的事例を持って教えてくれる、物凄くおもしろく、物凄く実践的で勉強になる本。 そして、国が違わなくても、完全に応用できる。日本人ばかりの企業の中でも、同じような齟齬は発生していて、まさに、みんなでこのカルチャーマップを描いて、一人一人を理解しながらコミュニケーション取っていきたい、と思う。 日本の中も、グラデーションだ。 会社の人みんなが読んだら、会議がうまく進むんじゃないか、と思うね。ほんとに。 我が社は、(もちろん相対的には日本的なのかもだが、細かく見れば)いろんなタイプの人がいて、いろんなやり方が良しとされていて、あんばいむずいよ。 私こんな考えの人!って表明できてたら、ほんと、やりやすい。 #異文化理解力 #theculturemap #エリンメイヤー #insead #読書記録
0投稿日: 2021.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外プロジェクトで苦戦しているので、池上彰の世界の見方を読み漁っていたところ、Amazonに進められたので読んでみた。 Thinkers50に選ばれたエリン・メイヤー著、8つの指標で各国の文化や思考の違いを見える化する。これはすごい、秀逸! 米国の人が、初めに良い点を述べその後悪い点を言った時、悪い点を言いたいだけの可能性がある。ドイツの人の話やメールが非常に長く、繰り返し表現が多いのは、ドイツでのプロフェッショナルな振る舞いに根ざしたもの。他にも言ったこと・書いたことしかやってくれない。。。など、ともすると、日本人の感覚では相手にネガティブな印象を持ったり、悪く評価しかねないことが、相手国では望ましい振る舞いということが起こり得る。本書ではこれを8つの指標で主要な国がどこに位置するか見える化、各国の違いを明らかに表現していて、この発想は驚きで、実用的でもある。私は早速、主な関係者の国の位置をExcelに入れ、グラフで見えるようにした。 対処方法だけでなく、どのような経緯でそのようになったのかの考察(未掲載の国を推測できる)と、両方のメンバーがいる時はどうするか、など書かれているのも素晴らしい。 指標をちゃんと理解して、各国の位置を確認するために、何度も読み返すことになると思う。 8つの指標 ・コミュニケーション: ローコンテクスト ⇔ ハイコンテクスト ・評価(ネガティブフィードバック): 直接的 ⇔ 間接的 ・説得: アジア以外は特定的で、原理優先 ⇔ 応用優先 アジアは包括的 ・リード: 平等主義 ⇔ 階層主義 ・決断: 合意志向 ⇔ トップダウン式 ・信頼: タスクベース ⇔ 関係ベース ・見解の相違: 対立型 ⇔ 対立回避型 ・スケジューリング: 直接的な時間(計画的) ⇔ 柔軟な時間 詳細 ・コミュニケーション: ローコンテクスト ⇔ ハイコンテクスト ローコンテクストでは、良いコミュニケーションとは、厳密、シンプル、明確なもの。メッセージそのままの意味で発し、そのままの意味で受け取る。 ハイコンテクストでは、良いコミュニケーションとは、繊細、含みがあり、多層的。メッセージは行間で伝え、行間で受け取る。ほのめかして伝える、はっきりと伝えないことが多い。 ・評価(ネガティブフィードバック): 直接的 ⇔ 間接的 直接的はそのままの意味だが、ポジティブな表現で包まない、他人の前でも伝える、強調することもある。 間接的は、この逆。 米国は、非常にローコンテクストだが、ネガティブフィードバックは中庸間接寄り。逆のパターンの国もある。 ・説得: アジア以外は特定的で、原理優先 ⇔ 応用優先 アジアは包括的 原理優先は原理を説明してから提案する。 応用優先は答えや事例などから説明、原理は後またはおまけ。 アジア以外は、特定のテーマにフォーカスして会話するが、アジアはテーマが全体のどこに位置づけられるか、他との関係を明らかにするのが最初。 ・リード: 平等主義 ⇔ 階層主義 リーダーや組織階層・役職を意識する度合い。 ・決断: 合意志向 ⇔ トップダウン式 そのままだが、合意志向は決断は重く簡単に変えない、変えられない、代わりに決断したあとは早い。トップダウンは、決断を変えることできる、状況に応じて変えるのが当たり前。 ・信頼: タスクベース ⇔ 関係ベース ・見解の相違: 対立型 ⇔ 対立回避型 ・スケジューリング: 直接的な時間(計画的) ⇔ 柔軟な時間
0投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東南アジアで働いた経験がある 駐在中、現地スタッフとコミュニケーショが取れず、自分の能力の低さに嫌気を感じていた。 この本に出会い、生まれた環境の違いで現地スタッフとコミュニケーショが上手くとれていなかったことがわかり、精神的に気持ちが軽くなった。 この本を読んでから、駐在したら現地スタッフとのコミュニケーショもスムーズに行えたのではないかと考えている。
1投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深いところがいくつもあった。同時に、普段15ヶ国20名以上のメンバーと仕事をしていても、ここまで顕著に違いを感じることはない、と気づいた。少なくとも仕事の場面においては、皆時間を守るし、相手を尊重する。「謙虚」という概念は日本人特有かと思っていたが、そんなこともない。もちろん、それぞれの国を訪問すると違いが目につくのかもしれないが、それぞれの国を代表して集まっている分には、多少の違いはあっても国由来ではなく人由来の個性にように思う。生まれが違うのだから、やり方が異なるのも当然、という前提でこちらも臨んでいるためかもしれないけれど。
0投稿日: 2021.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は主にビジネスコンテクストを想定して話を進めていくものだが、現在留学をしている自分にとっても非常に役に立つものだった。 異文化出身の人と過ごすことは考え方の根底が違うために、ものすごく困難を伴う。 色んな国出身の人と過ごすことで感じたさまざまな疑問や悩み、問題、本書はそれらを改めて気づかせてくれる、考えさせてくれる、あるいは説明してくれる、自分にとってこの上なく有益な本となった。 カルチャーマップという題名のように、大きく8つの観点から各国の文化的位置付けを図とともに具体例を交えて分かりやすく説明してくれる。 これから海外の人と過ごす予定のある人にとっては、本書はこの上なく助けになるなと感じた。 本書を読んで、自分は海外生活をしていた上で感じた疑問や悩み、さらには異文化に対する不和、それらがそういうことかと納得でき、異文化に対してより寛容になることができた。 まずは相手を知ることから、文化が違うということで何となく合わないなと思うことは本当にもったいない。相手を理解して、文化の違いを楽しむことは海外で過ごすのであれば、欠かせないことだと思う。これからは今まで以上に友だちに対して優しくなれるなと思うとすごくうれしくなったし、本書を読んだことで、今まで以上に相手の文化を尊重しようという姿勢で、相手に接して気持ちのいい関係が築けるだろうなと思う。 全ての異文化の人と接する人へこの本を勧めたい。 海外で生活しようと考えている自分にとって、本書はある種人生観を変える本になったことは間違いない。
0投稿日: 2021.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外で働く、外国の人とコミュニケーションを取るということが当たり前の時代にすごく重要な示唆を与えてくれる本。 多くの人が、国・地域毎の文化の差を理解したところで結局は個々人で違うのだから意味がないと考えてしまうかもしれないが、文化の差は関係ないと思って人と接すると、自然と自分の文化、価値観を通して相手を見ることが標準になってしまう。 各文化には幅があり(例えば、「率直にコミュニケーションを取る」と言っても、国や地域で幅があつ)、各個人はその幅の中で選択をする。だから、文化の違いも、個人の違いも、両方を意識する必要がある。 「違う」ということを当たり前に考え、客観的に、より多く耳、目を使うことが、異文化理解の第一歩だということが、非常によく理解できます。
0投稿日: 2021.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ人に薦められて読んだのだが、大変におもしろかった。 今年読んだ本のベスト5入り確実! 人間の考え方や行動のパターンを8つの指標から分析し、いろんな国の傾向をマッピングした本。 他国の人と一緒に働く時に、相手国と自国との位置関係により、何に気を付けるべきかが一目で理解できる。 このマッピングを見ているだけですごくおもしろい! 分かる、分かるわー、アメリカはここよね、などと思う一方で、エーッ!?日本ってこの位置なの?と驚いたり。かなり極端だと思ってた国が意外にも中央に位置していたり。 そもそも、結果よりもまず8つの指標それ自体が私にとっては驚きであった。 まず最初の指標として、「コミュニケーション」(ハイコンテクストかローコンテクストか)が挙げられる。この指標が非常に重要だということくらいはさすがに私でも分かる。 でも、その次の「評価」の仕方(ネガティブ・フィードバックをどう伝えるかなど)には驚いた。悪い評価をどのように伝えればポジティブに受け止めてもらえるか、が国によってこんなにも違うとは。全く予想していなかった。 「信頼」や「リード」、「決断」の項目については、たとえば、黒澤明の「七人の侍」はアメリカではリーダーの志村喬が圧倒的に人気だが、フランスや日本では違う、と聞いたことがあるのを思い出し、なるほどね、求められるリーダー像も良い決断もそれぞれに違うのか、と納得した。アメリカ人はやけに一方的に方針を言ってくるなぁ、と常々思っていたが、そう感じるのは私が日本人だからなのね、と、これらの項目を読んで非常に納得感があった。 そして、指標の中で思いもよらなかったのが「説得の技術」の項目。相手を説得したい時、効果的な論理の展開方法が国によって違うとは! そんなこと、今まで考えたこともなかった。 好まれる説得方法はその国の「哲学」から端を発しているという。 英語を使うようになると、「まず結論を書いて、その根拠を3つ述べ、最後に結論」という論理の展開方法をしつこいほど植え付けられるけれど、これはアングロサクソン系の人が好む説得方法であって、ゲルマン系やラテン系は違うそうである。あの手法がいつもいつも効果があるわけではない、ということを初めて知った。もう衝撃。実のところ私も、結論を最初に手短に、という展開方法にはいまだに慣れない。 最終章では、似た文化圏だと思っていた日本人と中国人が仕事の進め方でまったく相容れないことに気づいて驚くフランス人マネジャーの例が出ていたが、そこまで読んだ人にはその理由と対処法が明確に理解できるようになっている。(もちろんこの例は歴史的な確執とかそういう話ではない) 面倒くさい日本的な「察して」文化にウンザリした時などに「ああ、欧米の分かりやすいコミュニケーションの世界に生まれたかった」などと思ったりしていたが、それはあまりにも乱暴な認識だったとこの本を読んで気づかされた。近隣の国々との違いにも、一方的に「向こうが変!」なわけではないということがよく分かる。 むしろ日本はかなり変わった国だと知った。おそらく、単一民族過ぎる歴史、ホモジーニアス過ぎる歴史が世界でも稀だからなんだろうな、と思った。 私が見ている世界はあまりにも狭過ぎるので、もっと世界を股にかけている人にこの本の感想を聞いてみたいなぁ! この本、海外赴任する人へのプレゼントに良いかも。
0投稿日: 2020.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「聞き手が理解できないのは話し手のせい」という文化。良いコミュニケーションとは曖昧さのない明確なもので、メッセージを正確に伝えること。 反対に聞く側にに行間を読むことを求める文化。メッセージはほのめかして使う。 ローコンテクストとハイコンテクスト ローはシンプル、明快、曖昧さがないことが効果的。必要な背景知識や詳細の全ても伝える。共通性が少ない環境の文化圏。「まずこれから伝える内容を伝え、それから内容を伝え、最後に伝えた内容を伝える」保育所で私が使ってる話し方や。 ハイは共通点や暗黙の了解を前提にしたコミュニケーション。ハッキリ口にするのが不適切な場合もある。早々に判断してしまわず、理解できたか怪しいと思った時は確認の質問をする。 誤解によって行き詰まったり苛立った時は、自分を下の立場におき、自分自身を笑い、相手の文化をポジティブな言葉で表現すると、協力を求めることができる。 いつ何時でも、ポジティブフィードバックとネガティヴフィードバックの分量のバランスを取るようにすること。国や文化によってハッキリ言わないと全く伝わらないことも。反対に別の国や文化ではメッセージをぼかさないとわだかまりができることもある。 ココナッツ型、桃型コミュニケーション。フランス等ココナッツは初めはぎこちないし、よそよそしいが、打ち解けると友好関係が長続きする。アメリカ等、桃は初めからプライベートもオープンで、フレンドリーに話しかけてくれるが、ある時点で硬い殻に突き当たる。
0投稿日: 2020.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強になったし、目から鱗でした。自分の考え方がどれだけ文化的ルーツに根差しているか、自覚的になることが必要だと感じました。 自分と自文化との価値観の差異に気づくこともでき、あまり外国の人と仕事をしない自分にとっても有用でした。 よかれと思ってやっていることが、むしろ悪印象の要因となることすらあるのは驚きでした。
1投稿日: 2020.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさんの気付きを与えてくれる本。 異文化をOJTである程度学んだつもりでいたけれど、8つの指標でマッピングされるカルチャーマップはとても興味深いし、その背景にある歴史、教育、哲学の説明もありストンと懐に落ちる。 常々我々日本人の一般的な「普通」はグローバルスタンダードではないのだろうな、と思ってはいたけれどこうもそれぞれのマップで究極に位置にする文化だったとは。 欧州各国の違いも面白かったけれど、一番意外だったのはお隣中国のカルチャーかもしれない 2020.10.15
9投稿日: 2020.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ一緒に働くメンバーも、常日頃仕事で関わる人たちも多国籍なわたしの状況においては、 各国の人の振る舞い方や考え方の大枠とその背景を知れたことはとても面白く有意義だった! 本当の意味で色んなバックグラウンドを持つ人たちとわかり合い、信頼関係を構築するためには、知っておきたいこと!!
1投稿日: 2020.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスマンじゃなくても楽しめる本で、文化の違いと違うことの面白さを感じられる。 この違いを知ってからする海外旅行は、世界が変わるはず。 違いがあること、そしてなぜそんな違いが生まれたのかもっと詳しく学んでみたいと感じた。 僕の印象に残っているのは、日本が多くの面で「極端な位置にある文化」だということ。そして文化の差異は相対的なものであること。この詳しい内容についてはぜひ本を読んで感じてもらいたい。
1投稿日: 2020.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカに長年駐在してた尊敬する上司に勧められた本。とても面白かった。外国人と働く機会のある人全員におすすめ! 特に外国人と接する機会のない人だと「外国人=日本人よりフレンドリーで思った事を直接言って、時間にルーズ」なんてぼんやりしたイメージを持つ人が多い。 実際に外国人と働くと、確かにそんな側面もあるけれど、想像の何倍も複雑な事に気づく。 この本はその文化の違いを国別、各観点別に解説してくれる。 各観点というのは、例えばアメリカ人はもちろん日本人よりフレンドリーで、散歩やお店でも気軽に話しかけてくれるし、直接的な物言いをする事が多い。でも仕事で上司から言われた事には反論はしないし、あんなにフレンドリーに見えた同僚が辞めたら次の日から興味はない。そして評価面談等では悪い所を直接言うと「高圧的で嫌な上司」と見られる。普段のコミュニケーションと、ネガティブなフィードバックをする時の手法は違うし、仕事はトップダウン方式。フレンドリーなのは実際の仲の良さとは別。 8つの観点について、実例を使って紹介されていて楽しく学べる。実際にその国の人と働いた人にとっては「あるある」な内容。 そして、各国の文化の違いがそれぞれの歴史的背景によるもので、何百年前の出来事が現在まで根付いて影響を及ぼしているのが面白い。 この本はアメリカ人の筆者によって書かれた物だけど、日本の事が結構な頻度で紹介されていて、我が国はなかなか独特な位置にいるんだなと再認識。 日本の例は特に「そうそうそうなんだよ!」って思う事が多く、海外関係ない人でも、マネジメントする立場にある人にとっては面白いかも。 日本パートで1番共感したところ↓ 『会議で上司が「こうしたいんだけど、どう思う?」と聞いたら日本人は「上司の意見を理解できたかどうか確認してる」と受け取る。本当にメンバーの意見を聞きたいので有れば上司不在のところで意見を交わしてもらってその議事録を提出してもらったり、質問項目を事前に送ってこれについて意見を考えてくるように、と指示しておく事が必要。』 好きに意見して欲しいのに、皆全然意見出してくれないんだよね〜と悩みがちなマネジメント層、ぜひこれを意識すべき。メンバーが意見出すべきなのは勿論だけど、やり方を変えるだけでもっと意見を引き出せるはず。 最後に、この本を勧めてくれた上司が言った、好きな台詞を紹介します。 「『失敗しても恥かいても良いから意見言って』なんて言っても意見出る事はない。できる人や上司が腹を割って、素を先にださなきゃ。上から目線で言うんじゃなく同じ目線に立って先に弱みを見せて初めて相手も口を開く」
2投稿日: 2020.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文化は相対的なものであるという観点がとても印象的だった。例えば中国人のネガティブフィードバックは日本人には直接的だと感じられるが、中国人はドイツ人のネガティブフィードバックを直接的だと感じ、ドイツ人は中国人のネガティブフィードバックを間接的だと感じるという点である。 また、異なる文化の人とビジネスを行う時、単に相手側の真似をしようとすると結構失敗するという点も学びだった。 特に時間に対する考え方の違いが興味深かった。自分自身モロッコ人家庭に滞在した際、食事の時間や遊びの約束の時間などが私にとってはあまりにもルーズで、時間を無駄にしていると感じて少しストレスに感じた経験があった。しかしこれはおそらく時間の捉え方に関する文化のズレであり、彼らに合わせたり考えを明文化してよく話し合ったりすることで、試行錯誤してうまくやっていけるやり方を見つけていくべきだったのだなと反省することが出来た。 人々の具体的な経験談が豊富に盛り込まれすらすら読み進められ、内容もメッセージが非常に分かりやすく伝わった。
0投稿日: 2020.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ実例が豊富で非常に読みやすかった。 いくつかの指標に沿って各国の文化が読み解かれており、今まで非合理とさえ思うこともあった他国の文化的慣習にも合理性があるのだと得心した。 「魚は水を見ることはできない」 まさに目から鱗だった。
1投稿日: 2020.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白く読むことができた。今までの経験からなんとなく感じていた文化の違いを描写してくれたように感じる。特に自分では「日本以外」と「アメリカ」を区別できず認識していた部分について、ネガティブフィードバックの事例などを通じて、明確な差分を提示してくれたと感じる。
0投稿日: 2020.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ文化の特徴となる分野は次の8つ 1.コミュニケーション(ローコンテクストvsハイコンテクスト) 2.評価(直接的vs間接的) 3.説得(原理優先vs応用優先) 4.リード(平等主義vs階層主義) 5.決断(合意志向vsトップダウン) 6.信頼(タスクベースvs関係ベース) 7.見解の相違(対立型vs対立回避型) 8.スケジューリング(直線的な時間vs柔軟な時間) ポイントは、「自分の文化と比べて」相手がどの程度の傾向かということ。(絶対値ではない)世界の文化が互いのことをどう見ているかを理解する必要がある。 1.ローコンテクスト:良いコミュニケーションとはシンプルで明確なものだ。(アメリカ) ハイコンテクスト:良いコミュニケーションとは、繊細で含みがあり、行間で伝えるものだ。(日本) →歴史の長さと民族の多様性によって決まる ハイテクストの文化圏と付き合うためには、「何を言っているか」じゃなくて「何を意味しているか」を読み取ることが大切 ローテクストの文化圏とは、「意味を曖昧にしないため、繰り返し質問する」ことが大切 2.評価 直接的にネガティブフィードバックをする国は、ネガティブワードの前に強い言葉(まったくもって、全然)を使う 間接的にネガティブフィードバックをする国は、ネガティブワードの前に柔らかい言葉(すこし、私が思うに)を使う 何が無礼とされるのかが場所によって変わる。 3.説得 原理優先の思考法(演繹的)→なぜその結論になるのかを重視(まず実例を欲しがる) 応用優先の思考法(帰納的)→どうやって行動に移すかを重視(まず基本的な枠組みを欲しがる) のどちらの思考を使うかが、文化、宗教、思想により変わる また、この他にアジア特有の包括的な思考法→個々の事象ではなく、それを生み出す包括的な枠組みを考える(全体像を欲しがる) 4.平等主義vs階層主義 平等主義→上司と部下の距離が近い。組織はフラット。階級の違う職員とも普通にやりとりや不満をもらす 階層主義→距離が遠い。組織は多層的。階級が遠い職員とはあまりやりとりしない。 ローマ帝国の影響下にあった国(南欧州)は、他ヨーロッパと比べて階層的。逆に、ヴァイキング国家(北欧)は平等主義。また、プロテスタントはカトリックよりも平等主義。儒教国家はもっと階層的。 5.素早い決断か、じっくりとした決断か 議論を重ねてから決断する(合意に基づく文化。決断した後には実行が早い) 少しの議論で決断する(トップダウン文化。決断した後にも、情報が持ち込まれるたびに修正変更される) 日本は超階層的でありながら超合意的思考。(稟議書システムなどがそう) 6.頭で信頼するか、心で信頼するか 認知的信頼(相手を業績、技術で信頼する、タスクベース) 感情的信頼(相手を愛情、共感で信頼する、関係ベース) 7.見解の相違 対立型:見解の相違や議論を積極的に行う。 対立回避型:見解の相違や議論は組織にとってネガティヴなので、表立って行わない。 これに、 感情表現が控えめ 感情表現が豊か のy軸が加わる。 対立型なのに感情表現控えめ→意見に強く反論するものの、反論は個人的な感情の発露ではなく、貴重な知的運動として捉える。 対立回避型なのに感情表現豊か→情熱的に話すものの、傷つきやすい。意見への反論は人格攻撃だと見なされる。 8.スケジューリングの時間間隔 直接的な時間:プロジェクトは連続的なものとして、一度に一つずつ、スケジュール通りに進む 柔軟な時間:プロジェクトは流動的、同時並行し、柔軟に進む
0投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本人の特性を理解する上で大いに役立った。 「金魚は自分が水の中にいることを意識しない」とは言い得て妙で、異文化と接する機会がないといかに自分の文化的背景が特殊であるかは気付けないと思う。様々な観点で体系的に各国の特性をまとめてあるので、異文化コミュニケーションで壁にぶつかる度に読み返せる内容だと感じた。 日本は長きに渡って世界から隔絶された歴史を辿ってきた為、築かれた組織やコミュニティの中での関係性を特に重視するという説明は非常に腑に落ちた。我々のハイコンテクストで明文化を避ける姿勢は他国から見ればどっちつかずで判然としないものに映るだろう。 「ココナッツ文化」と「桃文化」という比較もとても面白かった。アメリカ人は表面的にはとても気さくで最初から友好的かもしれないが、ある一定レベルを超えて関係を深める為には相応の時間と努力を要するという示唆は心に留めておきたい。 そして、歴史的に多くの哲学者を輩出してきたヨーロッパ文化圏では、テーゼに対してアンチテーゼをぶつけていくことがより良いアイディアの創出に繋がるという信念があり、初対面であっても彼らはどんどん反論してくるというのはポジティブに捉える心構えが必要であろう。 グローバル社会で円滑に働く上では、自分の言動を率直に言語化することが重要だ。時にはユーモアを交えて自分の文化的背景を揶揄しながら、自分のコミュニケーションスタイルの特性を他者によく理解してもらうことだ。 多文化チームではメンバー間の対立や衝突がどうしても生じるだろう。しかし、それぞれの特性を活かしたマネジメントができれば、目的に応じたチーム編成により、成果の最大化を図ることも可能だ。各々の武器を理解し、適切な場面で彼らを登用することが肝要になろう。
0投稿日: 2020.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な文化背景をもつ人たちの集うチームをいかに効果的にマネジメントしていくかについて事例を交えながらわかりやすく説明されている。 各国文化が有する考え方を見える化し、対象国と比較して相対的にどこが似ており、逆にどこが異なっているかを理解した上で行動に移すことが、異文化間でコミュニケーションを取る上で重要である。
0投稿日: 2020.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ主にビジネスにおいて文化の違いのある人の集まったチームをどのように主導するかというようなリーダー側からの視点で書かれてはいますが、国際派でもなんでもない人間からしても参考になる内容でした
0投稿日: 2020.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカ人であって、フランス、シンガポールを中心に世界で活躍する異文化の女性研究者による、民族間の違いについて述べた本。いろいろな国民を、コンテクスト、ネガティブ・フィードバック、平等主義か階層主義か、トップダウンか合意志向かなど、さまざまな視点から分類し、まとめている。それぞれの項目における各国の比較は、もちろん定量的に正確に行われているわけではないが、概ね適切に行われていると思われ、説得力がある。平素から異文化交渉など、ビジネススクールにおいて教えているだけあって、わかりやすい。役に立った。 「ローコンテクスト(明確なコミュニケーション):アメリカ、オーストラリア、カナダ、オランダ、ドイツ、デンマーク、イギリス、フィンランドの順。 ハイコンテクスト(ほのめかしなど、はっきりしないコミュニケーション):日本、韓国、インドネシア、中国、ケニア、サウジ、インド、ロシアの順」p59 「ハイコンテクストな文化圏は長いあいだ共有してきた歴史を持っていることが多い。それらの文化圏は主に関係性を重視した社会であり、人とのつながりというネットワークが代々受け継がれていく中で、コミュニティのメンバー間にコンテクストがどんどん共有されていく。日本は単一民族の島国社会で数千年に及ぶ歴史を共有しており、その歴史の大部分は他の国から閉ざされた状態だった。数千年をかけて、人々は互いのメッセージを汲み取る能力に長けるようになったのである(空気を読む)」p60 「互いに全く違うルーツを持つハイコンテクスト文化出身の者同士の間で最も行き違いが生じやすい」p77 「直接的ネガティブ・フィードバック(ネガティブなメッセージを単刀直入に伝える):イスラエル、オランダ、ロシア、ドイツ、デンマーク、フランス、ノルウェー、スペイン、オーストラリア、イタリアの順。 間接的ネガティブ・フィードバック(ネガティブなフィードバックは、柔らかく、さりげなく、またはポジティブなメッセージに包み込んで伝える):日本、タイ、インドネシア、韓国、ガーナ、サウジ、中国、ケニア、インドの順」p95 「(オランダ人)アメリカ人の同僚たちはいつも「素晴らしい」点や「優れた」点からコミュニケーションを始めますが、それは誇張されすぎていて自分がおとしめられているように感じます。私たちは大人で、しっかりと仕事をしに来ているのです。同僚にチアリーダーは必要ありません」p106 「原理優先の説明:フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ドイツ、ブラジルの順。 応用優先の説明(まとめたり箇条書きにする。実践的、具体的):アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、オランダの順」p127 「ロンドンの人々やニューヨーカーに向けてプレゼンするなら、本題から入り話を逸らさないようにしよう。フランス人、スペイン人、ドイツ人にプレゼンするなら、各要素の説明に時間を割き、結論を語る前に背景を説明しよう」p131 「応用優先の思考を持つ人々はまず実例をほしがる。その実例の数々から結論を導くのである。原理優先の思考を持つ人々も実例を嫌いではないが、応用へ移る前に基本的な枠組みを理解しておくのを好む」p133 「中国人はマクロからミクロへと考えるが、西洋人はミクロからマクロへと考える。たとえば、住所を書く時も、中国人は省、市、区、地名、番地と書く。西洋人は正反対に書く。同じように、中国人は名字を先に書くが、西洋人は名前から書く。中国人は年、月、日と書くが、これも西洋人は反対に書く」p142 「平等主義的な文化では、たとえば、権威ある人間としてのオーラはチームの一員として振る舞うことで培われることが多く、反対に階層主義的な文化では、周りと一線を画すことで培われる傾向にある」p155 「平等主義的(上司はまとめ役):デンマーク、オランダ、スウェーデン、イスラエル、オーストラリア、フィンランド、カナダ、アメリカの順。 階層主義的(組織は多層的で固定的、序列に沿ってコミュニケーションが行われる。上司と部下の距離が遠い):日本、韓国、ナイジェリア、インド、中国、サウジ、ペルー、ロシアの順」p159 「(プロテスタントの平等主義)宗教改革によってカトリックから分離し、教会の伝統的な階層性を取り除いたから」p163 「平等主義的文化圏では、組織を飛び越えてコミュニケーションを取っても許容されることが多い」p169 「アメリカは階層主義的というよりは、トップダウン式である。ひとりが素早く決断を下して全員でそれに従うという価値に重きが置かれている」p184 「日本は強固な階層主義を持ちながら世界でも有数の合意志向の社会になっている。階層主義のシステムと合意志向の意思決定という一見矛盾したパターンは日本文化に深く根差している」p193 「日本の稟議システムは、集団の合意形成に全員が参加するため決断に時間を要する文化の典型例だ。しかしいったん決断が下されると、それはほとんどの場合覆らないものなので実行は非常に迅速になる。全員が同じ方向を向いているからだ」p197 「(過剰な挨拶回り)「ちょっと挨拶する」ためにかける時間は、次に彼らの助けが必要なビジネス上の問題が起きた時に大きな利益となって帰ってくる可能性が高い。信頼とは保険のようなものだ。実際の必要が生じる前に、あらかじめ投資を行っておく必要があるのである」p239
2投稿日: 2020.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ文化の機微を比較する「カルチャー・マップ」が素晴らしい。国際共同研究にも、留学生の指導にも必須の知識。
0投稿日: 2020.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ異文化理解力がないとはどういうことか…。相手の表面には見えない前提を無視して、自分の前提を相手に押し付けてしまうこと。この「態度」が問題なのであり、逆に言えば、異文化理解の大切な最初の一歩は、「苛立ちをぐっとこらえ、相手の面には見えない前提を知ろうと言動する意識を持つこと」だと感じました。
0投稿日: 2020.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.海外の人と接する機会が多くなってきたので、困らないようにする 海外の人からみた日本はどうなのかを探る 2.異文化理解力は、異なる文化で育ってきた人達と接するにあたり、相手の発言、行動の違いを理解すること。そして、自分はどうみられているのかを分析することです。 これが備わっている人は、チームの皆が心地よいパフォーマンスを出せる環境を作り出すことができます。つまり、グローバル環境下においての気が利く人を意味します。 この本では、わかりやすく、二項対立で大きな枠組みを作り、各国がどこに位置しているのかを示しています。言葉1つとっても大きな勘違いを生んでしまい、失敗してしまうこともあるので、この理論を頭に入れておくと、対処法に迷いがなくなるようになることを目指している一冊です。 3.言っていることは、普段生活していることと変わらず、相手を理解することです。ただし、日本人同士と違って、難易度が跳ね上がります。例えば、日本はやんわりとした言葉を使って、場を上手くまとめたり、なだめることが好ましいとされています。一方で、オランダは、その逆で、どんどん自分の意見を言っていきます。何も知らない状態で接していると、関係性が崩壊していくのは目に見えています。 まず、相手がどんな教育を受けてきたのかなどの成り立ちを知ることが大切だと思いました。そこから、相手の言葉遣いなどをきにしていくことでしっかりと理解できるのではないかと思いました。
1投稿日: 2020.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉の使い方 アップ/ダウングレード 類似 日本人とドイツ人 中国人とフランス人 日本 階層主義的 直線的なスケジュール(計画的) 中国 階層主義的 柔軟なスケジュール 関係ベース 列常緑樹形
0投稿日: 2020.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年のチームの目標を「インターナショナルな文化をインストールする」にした。日本特有の凝り固まった企業文化を破壊し欧米と戦えるようにするためには、同じかそれ以上の生産性を実現しなければならない。そのためには文化を理解し、変えていく必要がある。本書を読んだ背景はそんなところだ。 本書で紹介されているカルチャーマップは文化を理解するのに役立つ。とりわけ、会議のやり方やコミュニケーションに違いが表れる。異文化理解が必要だと感じた例として、アジア人の会議での口の挟み方を挙げていた。アジア人には十分な間が必要でターン制が快適だと感じる一方、欧米人は乱雑に、重ね掛けながら議論する。 ■異文化理解力 相手と自分の文化の違いを理解して、皆が心地よく良いパフォーマンスを出せる環境を作り出す。 ■カルチャーマップ 1.コミュニケーション:ローコンテクストvsハイコンテクスト 2.評価:直接的なネガティブフィードバックvs間接的なネガティブフィードバック 3.説得:原理優先vs応用優先 4.リード:平等主義vs階層主義 5.決断:合意志向vsトップダウン式 6.信頼:タスクベースvs関係ベース 7.見解の相違:対立型vs対立回避型 8.スケジューリング:直線的な時間vs柔軟な時間
0投稿日: 2020.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章の中における情報量、意思決定の仕方、時間の捉え方など、異文化間のビジネスコミュニケーションの違いや対策について言及されており、グローバルに仕事をする人は必見の一冊だと思う。ただし、ステレオタイプにならないよう、客観的に物事を分析したり、原因が文化的なものなのか個人の性格に由来するものなのかを見分けるよう意識することも必要だと思う。
0投稿日: 2020.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国人と働く機会が多くなってきた中で、国別の価値観、文化について説明。 フレームワークを用いて、日本人とどこが異なるかが分かりやすく説明されている。 参考書として活用できる。
0投稿日: 2020.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めてグローバルやダイバーシティを考えるのには良い本。相手との距離感、意思決定方法などなど。国や地域で様々な軸が異なることを理解する必要がある。
0投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログハーバード・ビジネス・レビュー、フォーブス、ハフィントン・ポストほか各メディアで話題!ビジネス現場で実践できる異文化理解ツール「カルチャーマップ」の極意をわかりやすく解説。(e-honより)
0投稿日: 2019.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際にあった話を多く紹介しながら、文化の違いによるビジネスシーンで発生しやすいすれ違いやそれに対するアドバイスが述べられており、非常に勉強になりました。 本書でも同様のことが述べられていますが、日本人の中にも色んな人がいるように、◯◯人だからこうだと決めつけることは非常に危険です。ただ、いくらインターネットを通じて簡単に世界とつながれるようになったと言っても、同じ教科書を読んで学んだり、同じテレビを見たり、同じ習慣で生活をしたりしていると、国や地域ごとに考えが似てくるのもそれはそれで自然なことでしょう。私たちも日本の社会ではこれくらいの行動や発言をしておけば無難で、これ以上やると危険だなとういのを感覚的に身につけていると思います。 同じように国や地域ごとの文化的分布特徴を把握しておくことで、外国人と仕事をすることがあっても動じず、過度に傷付いたり、傷付けたりせずにコミュニケーションが取れるのではないかと思います。これからは日本にいても外国人と働く機会は多くなると思うので、多くの人にとって一読する価値がある本だと思いました。 また、本書は訳書で日本のことが中心に書かれている訳ではないので、外国人から見た客観的な日本人の特徴も知れて面白かったです。
7投稿日: 2019.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://n3104.hatenablog.com/entry/2019/09/15/213635
0投稿日: 2019.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本にとっては「欧米」や「アジア」で一括りになるが、それぞれの国の思考や考え方の異なりを具体的に書いていてとても勉強になった。
0投稿日: 2019.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ8つの軸で文化を整理。主にビジネスシーンを想定してその違いがコミュニケーション、相互理解にどんな影響を与えるか解説。 これ、文化差はもちろん、個人差もかなりあるので、チーム内でアセスメントして共有してみた。次はチーム以外にも広げていこう。世代によっても違いそうで、昭和なマネジメントが嫌いな僕にとって、上司の昭和度を可視化して、上司にも変わってもらうことが狙いのひとつ。 解決策としてのお互いの歩み寄りを素直に促進させてくれるし、歩み寄れなくても、チームの方針開示によって、解消図るようにと。 だいぶ前に研修受けて買ったものの、ぱらぱら見た感じ、研修で疑問に思ったことがあんまり書いてないと思い、そのまま読まずに、はや2年? 前々から新しいチームでもアセスメントしないとなあと思いながら、だいぶ日が経ったけど、最近、和音だけでなく不協和音も出始めてるので、えいやとやってみた。 音に無頓着、区別つかない僕からすると、不協和音を不協和音と捉えなくて便利だと思うのだけど…文化でもなんでも、所詮は勝手に作り上げたもの。もっと楽になりたいもんです。 ま、とにかくその準備で、そういえばとこの本を取り出し、一昨日の夜中にページめくると、疑問に思うことについてもいろいろ書いてあるかもと、読み始める。 なんであの時気づかなかったんだろうなあ。
3投稿日: 2019.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事でも活用できる! 国によってのちがい。 なぜ返信が遅いのか? なぜこちらの言ったことが伝わらないのか? 同じ言い方でも国によって対応が違うのは何故か?
0投稿日: 2019.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ19/04/13読了 良著。おもしろい。相対的な概念で、個体差があることを前提としながら、各国の文化的な背景がビジネス上等現れるかを豊富な事例で教えてくれる。
0投稿日: 2019.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のスタンスを言語化することがよい方法である。その上でそれを実行することで相手にも意図が伝わり混乱しない。 ある価値観が同じでもそれをどう表現するかということが違えば見えてくるものは違う。例えば、対立はOKだとしつつも、感情表現をどのくらいOKと考えるかで実際に見える姿は変わってくる。 フィードバックには時間をかけよう。徐々に浸透させていくのだ。 新しい文化に適応しようとすると大抵は加減を間違えてミスをする。結局は程度の問題であり、0と100ではない。対立はOKだという文化があったとしてなんでもOKというわけではない。極端には走らないように。
0投稿日: 2019.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーション 婉曲的 直接的 ネガティブフィードバック オブラート 直接 説得 なぜ 原理 演繹的 どのように 実践 機能的 組織、リーダーシップ 階層的 フラット 意思決定 トップダウン 決定事項は柔軟に変更 合意 決定事項は確定項目 信頼関係 タスクベース 仕事とプライベートの区別あり 関係ベース 仕事とプライベートの関係は同一的 議論 議論ありき グループの調和重視 時間 単一的 具体的に管理するもの 確定的 多次元的 出来事に付随するもの 昼食、日没等 柔軟
0投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「文化は仕事に大きな影響を与えている」……技術一辺倒でやっていくと息を巻いていた10年前の自分にこんなことを言っても全く聞く耳を持たないであろう。しかし、実際に仕事をしていて、これを実感する機会は多い。やり取りや人間関係は仕事において本質的であり、そこでの人の動き方には文化的な背景が大きく影響している。 本書は、多国籍チームや国をまたいだビジネスにおけるやり取りや人間関係を円滑にするための知識とテクニックを伝える本である。文化的要因の強い国ごとの習慣の違いを8つのトピックに分けて議論する。各トピックで一つの大まかな指標を取り上げ、代表的な国がその指標に関して直線上にマッピングされる。例えば、最初に取り上げるのはコミュニケーションがローコンテクストかハイコンテクストか、というトピックである。ここでは、ローコンテクストな国が左に、ハイコンテクストな国が右に来るような図が示される。この図を見ることにより、コミュニケーションをする相手の国と自分の国の相対的な位置関係を理解し、本のアドバイスを活かすことができる。 例えば、面白いなと思ったのは、①ローコンテクストな国同士②ローコンテクストな国とハイコンテクストな国③ハイコンテクストな国同士、のどのパターンが一番厳しいか、というのがあった。正解は③である。文化的背景が異なるハイコンテクストなコミュニケーションは極めて意思疎通が難しい。一方で、文化的背景を共有するハイコンテクストなコミュニケーション、即ち日本人同士のようなパターンは、実はメリットもあそうだ。まず、主張を繰り返さないので、効率的である。また、意見の相違があっても、空気を読み合うので、関係性や調和を維持しやすい。自分はUSが中心となっている国際的なコミュニティへの論文投稿で、常になるべくローコンテクストに寄せるよう心がけて活動していたので、いつしかハイコンテクストなコミュニケーションは良くない物だとなんとなく思ってしまっていたが、言われてみるとその通りでメリットもあるなと思い、面白かった。 「文化」というとつい教養よりの非実用的な印象を持ちがちだが、この本はかなり具体的かつ実用的な本であると感じた。訳書なので日本を中心とした本ではないということがまた良い。例えば、2ヶ国以上が関わる多国籍なチームや社内の日本人が含まれていないようなチームに関して考えるときにも役に立つ。また、実際には日本人のみのチームを考える際にも役に立つように感じた。日本人の間でも個人差はあり、日本人同士を直線上にマップしコミュニケーションの課題を考えることもできるように思う。
1投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外で働くと、物事の受け取り方、スケジュール、メールのやり取りの仕方、電話の仕方で、自分の中との普通とは違う状況に頻繁に会う。 それは英語で伝え合っている内容以外に、感じ方や考え方が違ったり、価値観が違うから。つまりは、文化が違うからなのであると痛感している。 本書はビジネスに影響のある文化の違いを8つの視点から分析して、各国をマッピングしている。 海外の人と働く時、驚きを感じても、本書を先に読んでいればショックを受けない上に、対策が取れるかもしれない。 『金魚は水の中を泳いでいることをわかっていない』とはよく言ったものである。外に出ないと、自分の中の普通と思っていることが何なのかさえ気付かない。 日本の事例も多々紹介されている。日本がかなり特異で、(私の感覚では)非効率な企業文化をみんなで一生懸命守っているということがわかるだろう。 読んだ方がいい本。
0投稿日: 2019.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログアジア、北米、欧州での実体験に対し、本書がなるほど!な解説をしてくれた。直ぐに解決できるものではないが、異文化理解があれば、コミュニケーションが取りやすくなる事は間違いない。 日本の稟議システムは、如何にも。これからは無くなっていくかもしれず、各国でも同様の文化ダイリューションが進む事も頭に入れておきたい。 なお、一点気になったのは、ミーティング前に用意するのは、議事録ではなくてアジェンダですね。
0投稿日: 2019.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ特定の国(国々)ではなく、「異文化間」全体を扱っているので、初めは物足りなさを感じていた。 しかし、実は自分が海外で働き始めてから1年ほど経って改めて読むと、なるほど〜の連続。 実はもっとも行き違いが生じる可能性が高いのは、 ・ハイコンテクスト文化出身者が、別のハイコンテクストの人とコミュニケーションをとる場合 いまいる国もハイコンテクストの国であり、親日国だの日本人に近いメンタリティだの言われているが、実はコミュニケーションがとても難しい国であることがよく分かった。 文化の見取り図(P299)を早速やってみる。
0投稿日: 2018.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ===qte=== リーダーの本棚お茶の水女子大学学長 室伏きみ子氏 多様な文化の相互理解に 2018/12/1付日本経済新聞 朝刊 小さい頃から読書に親しんだ。 父親が元文学青年で、仕事のかたわら詩も書く人でした。家には本があふれていました。 美しい絵は、本を読む楽しみの一つです。幼稚園児のころから好きだったのが、初山滋さんです。詩集『こころのうた』は、初山さんが装画を担当しました。高村光太郎、三好達治、立原道造、八木重吉さんら、自分が大好きな詩人の詩が収められています。 いわさきちひろさんの絵にも、心ひかれてきました。余白の使い方、線の美しさなどに、初山さんの影響を感じます。命あるものに向ける優しさと悲しみが絵にあふれていて、とても心が落ち着きます。『母のまなざし、父のまなざし』は、疲れて心が萎えそうになったときに、よく見ています。 理系への関心も、早くから芽生えていたかもしれません。自分では覚えていないのですが、幼稚園のころ子ども向けのキュリー夫人のお話を読み、「キュリー夫人みたいになりたい」と母親に言っていたそうです。 『キュリー夫人伝』は中学生のころ読みました。夫人の次女が書いた本で、マリーと夫のピエールの人となりがよく分かります。徒労に終わるかもしれない、それでも何度も実験を繰り返す。その姿に感動しました。発見した元素は医療に応用され、多くの人を助けます。「自分もいつか人の役に立つ研究を」と思うようになりました。 研究者、教育者として歩むとともに、子育てもしてきた。 研究の道に進んだのは、学校の先生の影響も大きかったと思います。小学校の理科の専科の先生は、教えるよりまず「どうなるか考えてごらん」という先生でした。自分の予想を伝えると校庭で遊ばせてくれます。そして次の授業で実験し、確かめました。これこそ本当の教育ではないでしょうか。同学年から5人が研究者になりました。 中学からはお茶の水女子大附属に通い、ここでも先生方に恵まれました。大学院の博士課程で結婚し、長男が生まれてすぐに夫婦で米国に留学することになりました。米国では時間外に子どもを連れて行くと、研究室のみんながかわいがってくれ、助かりました。 かつて自分で読み、子どもとも一緒に読んだ本の一つが『星の王子さま』です。読み返すたびに、発見があります。命のはかなさと、はかなさのなかにある美しさ。愛情と純粋さ……。目に見えないものこそ大事なのだと、ずいぶんと考えさせられました。 『銀河鉄道の夜』も、繰り返し読んでいます。主人公の一人は、いじめっ子を助けるために自分の命を捨ててしまいます。あなたは人のために生きることに価値を見いだせるか。そう問いかけていると感じます。 戦争のない社会、多様性を尊重する社会の大切さを感じている。 『チボー家の人々』は、第1次世界大戦前後のフランスを舞台にした小説です。成績優秀で、医師として将来を嘱望される兄、一時は不良だったが、誰よりも平和を大切に思う弟……。懸命に生きた人たちが、愚かな戦争のなかで未来を奪われます。高校時代に読み、非常にショックを受けました。全13巻と長いですが、1冊にまとめた『チボー家のジャック』もあります。 世界にいかに多様な考え方、文化があるかを知ったのが、小田実さんの『何でも見てやろう』でした。アメリカからヨーロッパ、アジアへとまわる貧乏旅行の記録です。くすくす笑ってしまうおもしろい本ですが、突きつけてくる課題は重いものがあります。 『異文化理解力』は、最近、グローバル企業のトップだった方に薦められました。自分の価値観だけでものを言ったり判断したりすると、誤解やあつれきが生まれ、ビジネスもうまくいかなくなることが、よく分かります。 世界にはさまざまな背景を持った人々がいます。互いに理解しあい、尊重しあう。そうして初めて、社会のなかで自分の夢が実現でき、人々の夢や平和のためにも力を尽くせるようになるのではないでしょうか。ミャンマーで医療貢献活動をしている医師が書いた『死にゆく子どもを救え』を読むと、世界にはまだまだ希望があると感じます。 (聞き手は編集委員 辻本浩子) 【私の読書遍歴】 《座右の書》 『星の王子さま』(サン=テグジュペリ著、内藤濯訳、岩波書店) 『チボー家の人々』(全13巻、ロジェ・マルタン・デュ・ガール著、山内義雄訳、白水社) 《その他愛読書など》 (1)『キュリー夫人伝』(エーヴ・キュリー著、川口篤ほか訳、白水社) (2)『何でも見てやろう』(小田実著、講談社文庫ほか) (3)『<詩集>こころのうた』(八木重吉ほか著、初山滋装画、童心社) (4)『空海の風景』(司馬遼太郎著、中公文庫ほか) (5)『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、岩波文庫ほか) (6)『十代のきみたちへ―ぜひ読んでほしい憲法の本』(日野原重明著、冨山房インターナショナル) (7)『死にゆく子どもを救え』(吉岡秀人著、同) (8)『母のまなざし、父のまなざし』(ちひろ美術館編、講談社) (9)『異文化理解力』(エリン・メイヤー著、田岡恵監訳、英治出版) むろふし・きみこ 1947年埼玉県生まれ。お茶の水女子大理学部卒、東京大院博士課程修了(医学博士)。お茶大教授などを経て2015年から現職。公職も多く務める。 ===unqte===
2投稿日: 2018.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外赴任している友人に教えてもらい購入。自分自身も外国人の上司や同僚と働く環境にいるが、日々の仕事の中で感じていた色々なことに明確な説明が与えられたと思える箇所も多かった。本書で書かれている、外国の文化と比較することで初めて自国の文化の特徴が分かるというのは、その通りだと思った。日本の文化の極端さや独特の捻れ方の説明は面白かった。自国の文化を知ることで他の文化の人とうまく付き合えるようになりたい。
0投稿日: 2018.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外で働く前に読んだ。海外とは文化が違うとはよく聞く話だけど、具体的な記載があって良かった。海外で実際働いて感じたのは、日本人こそ世界でも最もユニークな働き方・マインドを持った国の1つという事。これは海外で働く日本人に向けて書かれた本じゃなくて、日本人含めユニークな人種と働く外国人に向けられた本なんだなと(笑)ただ、世界からそういう見られ方をされているということに気づく意味でも読む価値ありと思います。
0投稿日: 2018.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログまずはコミュニケーションのローコンテクストとハイコンテクストの差を知ろう。ハイコンテクストなコミュニケーションでは、そこでの会話はとにかく言外の意味や暗黙の了解が多く、少ない言葉数に多くの意味が込められて、皆が基本的な常識を知っている前提である。一方ローコンテクストなコミュニケーションでは、1つ1つの事項はとにかく細かく言葉にされ、逐一確認をしながら先に進んでいく。そう、ハイコンテクスト世界一は日本であり、ローコンテクスト世界一はアメリカだ。 さて、日本人からすると欧米人は誰をとっても論理的であり、おしゃべりであり、基本的に建前は言わず、そして時間にはルーズ、そんな印象があったりする。ところがどっこい実際には各国の民族差というのはあるもんだ。だから例えばアメリカ人とドイツ人が会議をすれば、アメリカ人側からするとドイツ人はやけに批判的に感じるし、ドイツ人からするとアメリカ人の物言いは結構回りくどい。これはドイツ人のコミュニケーションがローコンテクストであり、かつ極めて直接的なネガティブ・フィードバックを好むから。一方アメリカ人は同じくローコンテクストながら、ネガティブ・フィードバックは間接的なものを好むことによる。そう、アメリカ人ははっきり直線的というイメージだが、存外批判はオブラートの中に包んだものの言いようをする。そして日本はハイコンテクストかつ間接的なネガティブ・フィードバックの世界代表だ。そりゃあコミュニケーションの齟齬が生じるよね、と。アングロサクソンの中ではアメリカがローコンテクスト代表、イギリスはハイコンテクスト代表らしい。だからイギリス人はブラック・ユーモアを解するが、アメリカン人にはそれがジョークだという説明が必要だという。 全体になるほどねえ、という感想を抱くが、難しいのは国内では国内で相対的なハイコンテクスト、ローコンテクストな人の間における齟齬が生じるわけだ。精神科医的にはASDやADHDの人はローコンテクストな指示でないとわからないという気がするし、定型さんたちはハイコンテクストと言えよう。最近私がよく読む戦国武将たちはやたらとハイコンテクストな内容でやり取りしていますな。
1投稿日: 2018.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄く興味深い。アメリカ人が明快であるイメージでいたが、実はネガティブフィードバックは遠回しに言うに始まり、フランス人は、ドイツ人は、オランダ人は、中国人は、メキシコ人は...と、示唆に富む。ホフステードとエドワード・T・ホールの文献をさらに深掘りしたような感じ。
0投稿日: 2018.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題は 「Culture Map」です。こちらの方が内容を反映しております。何でも「~力」にすれば良いってもんじゃない。本書は基本的にはビジネス書です。グローバル社会になって、多国籍のメンバーで仕事をする機会が増えると、文化の違いによってちょっとしたコミュニケーションの齟齬が生まれがち。最近の日本でもありがちですが、単に相手の国や文化を批判するだけではビジネスが進みません。国や地域による文化の違いを事前にお互いに理解しておけば、かなり仕事がやりやすくなると思います。本書では、ビジネスで重要となる文化の違いに関して8つの軸を設定しています。例えば、組織運営が階層的なのか平等主義なのか、信頼は仕事を通じてなのか、人間関係の構築からなのか、など。それぞれに関して国がどの辺に位置しているかがマッピングされている。それが Culture Map というわけです。絶対的な位置よりも相手との相対的な位置が重要。その8つの軸に関して順番に、著者の実体験を含む多くの実例が各章で順番に解説されていて非常にわかりやすく読みやすいのが特徴。多国籍な人びととの交流する機会が少しでもあるなら、本書を読んでことをお薦めします。
1投稿日: 2018.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
複数の指標ごとに各国民の特徴がまとめられており、自分が経験したことがロジカルに分類されていて非常に参考になる。また指標が相対的ということで、どこ起点で見るかによって変わるのも面白い。日本人は欧米人と一括りにしがちがけど、欧州とアメリカ間はもちろん、欧州各国内でもかなりの相違があるとわかる。逆もまたしかりで、日中は同じアジアだけど全然違ったりするのは単純に興味深い。自分が経験したことがロジカルにまとめられてて
0投稿日: 2018.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからますますグローバル化が進む中で、タイトルのとおりビジネスパーソン必須の教養であると思う。非常に勉強になった。
0投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書。具体例に偏り、統計的な裏付けの記述はないものの、自他の違いを個性だけではなく、文化からも説明する視点は有意義。日本国内、あるいは同じ会社内でも部署が違えば文化が違うということはあり得る。ビジネスマンとしての所作・処世術を学ぶヒントにもなる一冊。
0投稿日: 2018.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯文化の違う人々の関係を測るとき、重要なのは指標における各文化の絶対的な位置ではなく、二つの文化の相対的な位置関係だということだ。(38p) ◯衝突を取り除くには気づきとオープンなコミュニケーションが大いに役立つ。(201p) ◯多くの文化では関係こそが契約なのである。相手なしには契約はできない。(239p) ◯大切なのは価値観や働き方の違いについて考え、話し始めることです。金魚が水のなかにいることを意識しないように、人間も相手と比較しない限り、自分の文化を認識するのは難しいのです。(301p)
1投稿日: 2018.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ一番初めのハイコンテクスト、ローコンテクストの違いが一番面白かった。 最もハイコンテクストな文化を持つ日本で育った自分は、会話の中で聞き手側の努力を当然の物としているが、 ローコンテクストな文化を持つ国では、できるだけ明確で曖昧さのないものが良いコミュニケーションとされる。(聞き手が理解できないのは話し手のせい)
0投稿日: 2018.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018年前半の中で読んで良かった本No.1になりそうな本。 異文化出身の人と働く上で、大事な指標を8つ提示して、その中での位置付けにより起きそうな問題とその対処法に言及されている。 日本の外からの見え方にも納得。 海外出張で苦労した身としては、もっと早くこの本に出会いたかった…。
1投稿日: 2018.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰でも自分と異なる国籍の人と働いたり活動する中での「文化の違い」を感じたことはあるのだろうけど,この書籍の中では,その文化の違いを言語化する耐えの明確な8つの軸が紹介されている. 文化は相対的なものであることや,異なる文化圏の人々が集まって仕事をするときにどう振る舞えばよいのかという問題に対する積極的なソリューションも幅広く紹介されており,組織のアレンジを考える人にとっては必携の書籍だと言える.
1投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最近の興味は「文化」で、特にホフステードのモデルに興味を持っている。という流れで、読んでみた。 ホフステードを読んだ後では、軽く読めて、そうだろうね、みたいに思ってしまった。(多文化の環境で働いたことないのにね) ホフステードが、データと先行研究を踏まえながら、結構学術的に正確な記述を目指しているのに対して、こちらはビジネスにフォーカスを絞って、わかりやすく、エピソードや事例をたくさん紹介して、具体的な行動につながるようなアドバイスをうまくまとめているな、という感じかな。 本の中でもホフステードの研究への言及もあるように、大きく違うことを言っているわけではなく、そんなに新しい何かがあるわけではない。(ホフステード的には、「文化」というほどのことではない、表層的なところをなぞっているだけ、という感じではある) 本のまとめ方に、アメリカ的なプラグマティズムな「文化」が現れている感じが面白いかも。 エピソード満載で面白い一方では、データがどこからきたのかよくわからないところに疑問は残る。こういう本では、巻末に調査の方法論とより詳細なデータをつけるのが普通だと思う。その辺の信頼性については、よくわからないところ。 これで多文化が分かったつもりにならずに、ホフステードを読むきっかけになるといいと思う。 何はともあれ、今時のビジネスは、こうやって文化の違うを考慮してコミュニケーションやリーダーシップを発揮しないといけないわけだね、とグローバルな競争の厳しさを感じた。
1投稿日: 2017.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
英語版で読了。 ものすごく勉強になった。 日本人から見た外国人や外国人から見た日本人の本はあるが、これは世界の国々がある基準に対してどういう位置にあるかという関係性を客観的に書いている。例えば、日本人から見るとアメリカ人は時間にルーズに見えるかもしれないが、フランス人からアメリカ人を見ると時間に厳しすぎるように見える。なぜなら時間にどれくらい厳しいかというのを示したとき 日本→アメリカ→フランスという立ち位置になるから。多国籍の人と働くには、自分の国からの味方だけではなく、ある国がある国よりどうかという視点も大事であると思った。 生ま育った国で人を判断するな!という批判もあるかもしれない。著者も個々人で違うことは認めているが、一方で「あの人は悪い人だ」と決めつけ、個人を責めたりしてしまうことになるかもしれないとも。「Being open to individual difference is not enough」。文化が人格や行動に影響を与える限り、違いを理解しておくことは重要。 本書では、8つの基準で文化の違いを述べている。 Communicating: low-context vs. high-context Evaluating: direct negative feedback vs. indirect negative feedback Persuading: principles-firs vs. application-first Leading: egalitarian vs. hierarchical Deciding: consensual vs. top-down Trusting: task-based vs. relationship-based Disagreeing: confrontational vs. avoids confrontation Scheduling: linear-time vs. flexible time 第1章 Communicating: low-context vs. high-context low-contextとは、全てを明確に、詳細に述べてコミュニケーションをとること。high-contextとは、行間を読む必要があるということ。 フランス人はhighでアメリカ人はlow。英語は70000語あるのに対し、フランス語は5000語しかないことからもフランスでは行間を読む必要がある。 また歴史の長い国はhigh-contextになる傾向がある。アメリカは色々な民族がいて、明確にコミュニケーションする必要があるため、low。イギリス人も日本人に比べればlowだが、イギリス人に言わせると、アメリカ人は冗談すら通じない。アメリカ人はjust kidding!と言わないと怒り出すそうだ。 第二章 Evaluating: direct negative feedback vs. indirect negative feedback 日本人から見ると、イギリス人は十分ものをはっきり言うように思っていたが、世界的に見るとオブラートに包む方のよう。オランダ人はネガティブなことをはっきり言う文化。イギリス人が言ったことをオランダ人が聞くと否定的に言ったつもりが肯定的に取られてしまう。 イギリス人「with all due respect...」 イギリス人の意図「I think you are wrong.」 オランダ人の理解「He is listening to me.」 アメリカ人もネガティブなことはオブラートに包んで言うと言うのは日本人からすると意外な感じがした。Low-contextだからと言って、direct negative feedbackをするとは限らない。 Politenessの理解は文化によって違い、オランダ人ははっきり正直に悪いことを伝えるのがPoliteと思い、イギリス人やアメリカ人は悪いことを率直に言うのは失礼だと考える。文化によって「Polite」であることの定義が違うのは注意すべき点。 第3章 Persuading: principles-firs vs. application-first 説得するときに原理から説明するか、具体的なものから話すか。ドイツ人はwhyを説明するのに対し、アメリカ人は「じゃあどうするの?」から聞きたがる。 アジア人はこの指標には載らず、「holistic approach」と言う別のアプローチが必要。アジアでは意見を求められると、延々と質問に関係ない部分まで話してやっと結論に達する。水草の生えている水の中に、魚が泳いでいる絵を見せると、アジア人はまず「水草があって、石が下にあって・・・魚が三匹います」と説明するが、アメリカ人に何の絵ですか?と聞くと「魚が三匹いる絵」と説明する。 日本人に仕事をお願いするときは、「あなたはこれをやってくだい」ではダメで、「あなたはこれ、あの人はこれ、あの人はあれをやります」と全体を説明しないと前に進まない。 そうなのかな。 第4章 Leading: egalitarian vs. hierarchical ヨーロッパの中でも平等と階層型の文化の国がある。オランダやスウェーデンは平等。イタリアやスペインは階層型。これには3つの歴史的背景がある。 ①ローマ帝国に支配されていた国は階層型。オランダはローマに支配されていなかったから平等型。 ②バイキングに支配されていた国は平等型。スウェーデンが平等型なのはそれゆえ。 ③カトリックの国はプロテスタントよりもより階層型。 求められるリーダーも違い、階層型の文化では、指示しない上司は評価されない。強いリーダーが好まれる。なるほど、プーチンが人気の理由もよくわかる。 level hoppingにも気をつけなければならない。オランダでは、平社員が上司をすっ飛ばして社長に話すことが許されるが、それを階層型の国で行うと反感を買うことがある。なぜ自分に言って来ないで、部下に言うんだ!と。 第5章 Deciding: consensual vs. top-down まずみんなで同意した上で決定を下すのがconsensual。トップが同意を得ずに決めてしまうのがtop-down。アメリカはtop-downで、ドイツはconsensual。ドイツ人から見るとアメリカ人は人の意見も聞かずに勝手に決めると思われる。非常に階層型だと思われるが、階層型とは違うことに注意。アメリカ人は「とりあえず決める、決めたあと悪ければ帰る」というスタイル。アメリカ人からするとドイツ人は決定が遅いと不満が溜まる。 日本は究極のconsensual社会。本書では、稟議書や根回し文化が紹介されている。ただdecision makingには時間がかかるが、一度決まれば実行は早い。 第6章 Trusting: task-based vs. relationship-based アメリカ人はtask-basedですが、中国人はrelationship-based。どんなに中国人にいいプレゼンをしても、個人的な繋がりがないとビジネスは上手くいかない。夜にお食事に誘い、ビジネスと関係のないことを話すと言うようなことが必要。 アメリカ人もice breakなどと言ってrelationship構築をトレーニングに組み込んでいたりするが、それはあくまでビジネスのためであって、外に出た途端、リレーションを作ろうなんて考えない。 アメリカのようなtask-basedの社会の人に、何時間もの飲み会に誘うのはあまりよくない。とりあえず一時間のランチに誘い、それから本人が望めば長くするが、もし断られたら強くプッシュしないこと。彼らにとっては飲み会は時間の無駄と考えられている。 逆に、日本の飲みニケーションを無駄と考えてもだめで、これによって、仕事が早く進むと言うこともあり、効率をむしろあげる場合もある。 第7章 Disagreeing: confrontational vs. avoids confrontation オープンな場で議論をするかどうか。 フランス人は人前で不賛成を表明し、議論を活発に行う。そうすることで、良い案にブラッシュアップされていくと考えているから。プレゼンをすると批判の嵐になって、落ち込んでいると最後には「良いプレゼンだったね」と話しかけてくると言うことがあるらしい。 逆にアメリカのようにいろんな民族がおり、confrontationを避けることっが至上命題という国では、confrontationは避けられる。 アジアもそう。このようにavoids confrontationの国では、事前に意見をまとめてくる時間を与えたり、先に上司が意見を発表せずまず部下に意見を言わせるというような工夫がないと議論は活発化しない。 第8章 Scheduling: linear-time vs. flexible time ドイツや日本は時間にストリクト。 発展途上国は日々社会が変わっていく中で、時間を守るよりもいかにフレキシブルに対応するかが重要なため、時間を守らない。 中国も時間を守らない国。だから、当日になって「今日会える?」ということもよくある。ただ逆に自分が急に時間が空いた時に「今から会える?」ということも可能。 多国籍の人がいる場合、チームの時間文化を最初に決めることが重要。このチームでは時間ぴったりにくるのが文化でルールです、破ったら罰金というようにリーダーがクリアに決めてしまう。 まとめ 他の国と仕事をしていてトラブルが発生した時には、まずそれぞれの国が8つの基準についてどういうポジションにあるのかを理解する。そして、乖離のある部分に対して、お互いに意見交換をすることが大事。
11投稿日: 2017.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終えた。 1ヶ月以上かかった。 すごく良いことが書いてあるし、勉強にもなるんだけど、なんでこんなに読み進まなかったんだろう。
0投稿日: 2017.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国人の指導を任された際、 過去の苦い経験から「今回はしっかりと準備しよう」と思って読み始めた。中国と日本は同じハイコンテキストの文化でありながら、ハイコンテキストの背景が全く異なることにより、多くの摩擦を生んでいる。その通り。また、時間軸も直線的な日本とは真逆に柔軟性に富んでいるので、感覚が合わないのは当たり前。今後、世界で仕事をしていく中で立ち帰れる本だと思う。
1投稿日: 2017.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ#fb 北阿某地周辺で約9年にわたって感じていたヤキモキとモヤモヤをスッキリさせるに足ることが全部書いてあった。INSEADはやっぱり一味違うな。Construction Businessでフランス語圏でのInternational Projectを意識するとどうしてもEcole de PontsとかGrands Ecoles中心に情報を取ろうとしてしまうけど、まずはこの本に書いてある(多分、INSEAD的な)アプローチを、早い時点で体系的に身に着ける必要が本当に高いと思う。
0投稿日: 2017.07.31
