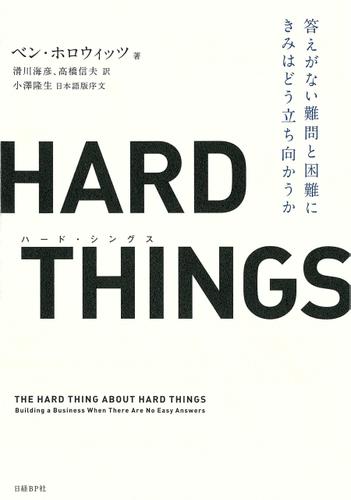
総合評価
(157件)| 44 | ||
| 59 | ||
| 31 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章が軽妙洒脱で面白い。翻訳者頑張ったなー。 他人の苦労話は愉快なものである。悲惨な過去が割と赤裸々に綴られるのだが、言い訳が少ないので読み物として面白おかしく読める。 前半は平社員にとっても含蓄があるが、後半は経営者マインドがないせいか、いまいち頭に入ってこなかった。
0投稿日: 2016.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://hinbeee.blog31.fc2.com/blog-entry-2478.html
0投稿日: 2016.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログネットベンチャーのCEOの楽しさと苦しみを書いた本。CEO以外にも管理職として生かせる部分が多く、自分の行動の指針になり得る情報も多い。 個人的にも、組織のトップを経験したことがあるので共感するところも多かった。 また、自分がいざ起業しようかという段になった時、この苦悩を味わってまで起業したいものが自分の中にあるのか?と問いかけることにしようと思った。
1投稿日: 2016.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログネットスケープの創業者マーク・アンドリーセンとの出会いから、ラウドクラウドの創業、オプスウェアの経営を経て、アンドリーセン&ホロウィッツというベンチャーキャピタルを立ち上げた著者の、苦難に満ちた企業経営史とそこから得た教訓から成り立っている。私は欧米の経営者に対して「人を簡単に解雇する」「合理的で感情に左右されずに経営判断をする」と思い込んでいたので、いい意味で裏切られた。これは、かつて日本的経営と言われていたものではないのかと思える部分も多かった。 それから、「友達の会社から採用してもよいか」という部分では、以前DeNAの南場さんが書いていたエピソードを思い出した。確か、出資してくれた企業から応援に来てくれていた社員を、その人のたっての希望でDeNAで雇い入れてしまったといった失敗談のことだ。そのように、起業し会社を大きくするうえで起こりがちなことが網羅されているようなので、ベンチャー起業家には、きっと役立つ内容だと思う。
1投稿日: 2016.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに皆さんいう通り面白い。でも、なんか、肝心なことはアンディグローブが全部書いてるよっていうんでアマゾンで調べるとあまりの中古価格の高騰ぶりにもうなんじゃこれ、そんならkindleで原書で読むよ。って思いました。それはまた簡単ではないけどね。やっぱ、献身ってことなんだよね。まあ当然だ。CEOってのは特異ノードになるってことだから、エネルギーがたいへん必要でしかもphaseがあってなきゃいけない。
1投稿日: 2016.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近読んだ本の中で何度も読み返す必要があると思った良書。 起業家を夢見ていたが、社会人になってから現実的に難しいことを再認識してやめたことが、あながち間違いではなかったことがよくわかった。よい面、悪い面の両方でバランスよく理解できた。 起業家ではなくても、リーダーであれば必ず遭遇するチャレンジとも思うので、起業家を目指していない人でも十分に楽しめる、また勉強できる一冊
0投稿日: 2016.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ物事がうまくいかなくなる時、 簡単なことはなにもなく、すべてが間違っているように感じる。 苦闘に悩む人たちが強さを身につける。 そのための つらいときに役に立つかもしれない知識。 ・ひとりで背負い込んではいけない。 ・単純なゲームではない。 ・長く戦っていれば、運をつかめるかもしれない。 ・被害者意識を持つな。 ・良い手がないときに最善の手を打つ。 「われわらは、人、製品、利益を大切にする。この順番に。」(元ネットスケープCEO ジム・バークスデール) 働きやすい場所をつくる。 なにをすべきかを伝えるだけでなく、なぜそうしてほしいかも伝えること。 ・
0投稿日: 2016.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログアンドリーセン・ホロウィッツのファンドに企業社員の職務として投資中。内容は日本の大企業経営者にはほとんど役に立たないと思われた。文化、思想、志…全く異なっており、こうした企業と同じ土俵で戦うことは避けるべき。なぜなら必ず負けるから。この国が衰退していく理由がよく分かった。かつてはこの国にもこういった精神があったのだろうが…
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・CEOかそれにもっと近い人が読めば星5はかたそう。それ以外の人にとっては理解度や共感度、役立ち度がどうしても減ってしまうので星3くらいと感じた。もしCEOになることがあればもう一回読んでみる ・社内政治の定義が目からウロコだった
1投稿日: 2016.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がシリコンバレーのスタートアップでCEOとして困難にどう立ち向かったか。その戦いの記録のような本。通常の「こうやって成功しました」というビジネス書とは違う。会社を経営するならぜひ再読したい。「人生は苦闘」という言葉が印象に残った。
1投稿日: 2016.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった。 メジャーなCEOの、ありきたりのサクセスストーリーではなく、失敗を必死に切り抜けたときの記録。 この人の場合、あるいは、多くのCEOには、次から次へと、困難が押し寄せるものなのだ。 最高責任者っていうのは、当然のことながら、責任が重い。
2投稿日: 2016.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事と私とどっちが大事なの? 人によっては簡単に答えが出る問題なのかもしれないが、 比較することはできない問題だと思う人はたくさんいるだろう。 そしてこの答えは出せるわけがないと思う人もたくさんいるだろう。 だが世の中は理不尽にできており、姿を変えながらこの問題を突きつけてくる。 無理だと思ったそこから、決断という一歩を踏み込むためには、 大事なものは何か、ということを整理しておくことかもしれない。 (以下抜粋) ○母がこの上なく辛抱強い人間でなかったら、私は学校教育を受け損なっていたに違いない。 この子供には心理療法が必要だという声が周囲では強かったそうだが、 母は私の気持ちが落ち着くまで、無限に長い時間を待ってくれた。(P.15) ○自分がしたいことではなく、何がたいせつなのかという優先順位で、 世界を見ることをこのときに初めて学んだ。(P.25) ○もし私が家へ帰れば、会社は間違いなく倒産する。 もし、ここに残れば・・・・・・(P.53) ●それは約20万ドルと安くはなかった。 その上、われわれはジョンをほとんど知らなかったし、義務も負っていなかった。 しかし、ジョンはまもなく命を失おうとしている。 私は彼の医療費を払う決断を下し、費用を工面することにした。 そうした理由はおそらく、絶望がどんなものか知っていたからだろう。(P.81) ○完全に間違っているアドバイスは、必要以上に「ビック」な人物を雇えというものだ。(P.114) ○ベン、きみとマイクが探そうとしている特効薬は悪くないが、 われわれのウェブサーバーは5倍遅いんだ。 それを直せる特効薬は存在しない。 だから、われわれは何にでも効く魔法の銀の弾丸ではなく、 鉛の弾丸を大量に使うしかない。(P.130) ○良い組織では、人々が自分の仕事に集中し、 その仕事をやり遂げれば会社にも自分自身にも良いことが起こると確信している。 こういう組織で働けることは真の喜びだ。(P.148-149) ○大きな会社と小さな会社でもっとも大きく違うのは、 経営している時間と、創造している時間の長さだ。(P.176) ○純粋に数字だけによるマネジメントは、数字通りに色を塗るぬり絵キットのようなもので、 あれはアマチュア専用だ。(P.189) ○HPでは、会社が現在と将来の両方で高い売上を求めていた。 完全に数字だけに集中している今のHPは、将来を犠牲にして成り立っている。(P.189) ●この職場で働く上で一番不愉快な点は? この会社で一番頑張って貢献しているのは誰だと思う? われわれがチャンスを逃しているとしたら、それはどんな点だろう? この会社で働くのは楽しい?(P.248) ○勇気と決意に投資するのは私にとって簡単な決断だった(P.277) ●心を静めるテクニック(P.286) 友達をつくる。 問題点を書き出す。 側壁ではなくコースに意識を集中する。 ○凡庸な製品と魔術的に素晴らしい製品との差は、往々にして、 社員にあまり厳しく責任を求める会社運営と、 社員が創創造性を発揮するためなら必要なリスクを取ることを許す経営との差にある。 社員の約束に責任を持たせることは重要だが、重要なことはほかにもたくさんある。(P.345)
1投稿日: 2016.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想は以下 http://masterka.seesaa.net/article/433519511.html
0投稿日: 2016.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいて胃がきりきりする。それくらい生々しい。市場が最悪な状態での資金枯渇と資金調達、売上のほぼすべてを占める大手顧客を失う間際の事業ピボット、競合との製品デッドヒート、友人の会社からの転職や友人そのものの降格や解雇、会社を売却するという決断、などなど。 著名なベンチャーキャピタリストでもあるベン・ホロウィッツ氏。自身もCEOとしての経験を持ち、その実体験を基にした教訓書だ。ビジネス書ではない。だから経営者や事業責任者の経験がある方が読むと目を背けたいエピソードが満載だ。もちろんこれらの「Hard Things」に答えはない。しかしある一つ、しかしとても参考になる、例示にはなるはずだ。例えば買収したタングラムのCFOジョン・ネリの脳腫瘍費用を出す、この決断はCEOとしての側面とひとりの人間としての側面を両立したベストプラクティスのように思える。 全体を通して実体験の部分は抜群に良い。指南部分は具体的なアドバイスになりすぎたようでやや汎用性に欠け退屈な感は否めない。なので★5に限りなく近い★4つとした。 これから起業される方、事業開発される方、グーグルやフェイスブックネットようなバラ色の成功はほんの一握りだ。その先に待っているのは只々ひたすら苦行のような決断の連続だ。だからこそビジネスは面白いのだ。そう感じさせてくれる一冊である。
0投稿日: 2016.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年のベストビジネス書的なやつなので、みなさんお読みだと思いますが…。特にIT系のスタートアップを大きくしていきたい方、米国スタートアップの現状を知りたい方にはとても参考になりますし、一方で経営者の物語としてもそれなりに辛く楽しく読める一冊です。 パラレルにいろいろ浮気しながら読んでいる影響か「これこれが参考になったー」とかは実はあまりありませんでしたが、流行ですし、懸命なビジネスパーソンでまだ読んでない方は話題ということでも読んだ方がよいかと(2016.01.03ごろ読了)
0投稿日: 2016.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「苦闘を愛せ」--単純な成功物語ではなく、土壇場に何度も追い込まれたスタートアップ経営者はどう行動すべきなのか、赤裸々に描いている。IIJ鈴木幸一さんの「日本インターネット書紀」と合わせて読むと、いい意味でも悪い意味でも、日米の文化の違いが浮き彫りになる。
0投稿日: 2016.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業、スタートアップから軌道に乗せていくにはさまざまな困難が立ち現れる。 CEOは率直で真実を語るのが第一だが、事業継続のためにテクニックとして知っておくべきことがある。ルールづくりや教育ということも重要になる。 これは著者自身がじっさいのCEOとしての経験から学んだものである。
0投稿日: 2016.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ●読むキッカケ ・どっかのブログで紹介されていた ・何かチャレンジングなことをする上での、その胆力的なものを感じ取りたかった ●サマリー ・実際に経営をする上での事細かなHOWが多かった印象 ・一部記載されていた著者の挑戦については、まあ飾らず淡々と記載されていた気がする。 こういうレベル感の企業をするときの、苦しさのようなものを多少経験出来てよかった気がする ・自分はこういういわゆるIT企業は目指していないんだろなあ、ということをはたと感じた。 では何か、と言われても言葉に窮してしまうのと、それ自体諦めの要素も幾分あって、必ずしもポジティブなものでも無いのだけど。 ●ネクストアクション ・また必要なタイミングで読み返してみる ●メモ ・製品づくりにおいて、顧客の声に耳を傾けることは必ずしも正ではない。 データが真実を述べているとも限らない。 では何を信じるかというと難しいけど、少なからずそう単純なものではないということには納得。 スティーブ・ジョブズもそういう発想だったように思う。 とはいえ、彼らを無視していものではなく、まあ考え抜くことが重要なのだろう。 ・「今やれていないやるべきことはあるか?」という問を投げかけること ー0ベースで何をすべきか考える上で、想像しやすいしなかなかいい問な気がする
0投稿日: 2016.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリーとしては面白いが、逆に分かり易すぎで一面的な解釈しかできない印象。so what? には明確に答えてるからAmazonでの評価は高いかも知れないが。 でも、私はもっと普遍性が高くて何度も読み返せるような内容が良いと思うな。 本書でも触れているがhow to に触れてはダメなんだと思う。 ただ、当然面白いから評価は高いんだが。
0投稿日: 2015.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、今、シリコンバレーで最もホットなベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者。今日の成功の素となる失敗について、余すことなく著した貴重な著書だと思います。ベンチャー関係者のみならず、経営を志す全ての人にとって必読の書で、2015年最高のビジネス書の1冊と言って良いと思います。
0投稿日: 2015.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ輝かしい実績ばかりが注目される起業家の、 苦闘を描いた本。 米国、IT業界の慣習を知らなければ理解に苦しむ部分もあるかもしれない。 しかし、社員に経営者意識を求める昨今、 リーダーシップを取るには如何すれば良いかの示唆が得られると感じる。 将来起業したいと考えている方のみならず、 仕事のモチベーションを上げるカンフル剤として有用だと考える。
0投稿日: 2015.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログTwitter,Facebook,Airbnbなどに投資しているベンチャーキャピタルAHの共同創業者が自らの人生の中で直面したHARD THINGSとそれらから得た教訓をまとめた本。一般的な日本人になじみのある概念のフレームワークを使って抽象化や要約をすることが困難な本だが、実際に業を起こして回していくに当たって直面する艱難辛苦を乗り越えるために必要なのは東大の授業で学ぶ手法や知識ではなく「アントレプレナーシップ」や「リーダーシップ」としか呼びようのない何かなのだと東大生に強烈に認識させる本である。(技術経営戦略学専攻) 配架場所:工3号館図書室 請求記号:335.13:H89 ◆東京大学附属図書館の所蔵情報はこちら https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2003277675&opkey=B147995498123420&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=6&cmode=0&chk_st=0&check=0
0投稿日: 2015.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業戦略本だが、一番の特徴が成功法則ではなく失敗法則であるということ。どうやって上手く言ったではなくどのように困難を乗り越えてきたのか、というストーリは非常に興味深かった。コミュニケーションの重要さはもちろんのこと、組織のトップの人間としてはさらに大事なのは「行動する」ということ。波風を立てない方法ではなく波風の立った中をどうやって進んでいくかを考えさせられる指南書。勉強になりました。
0投稿日: 2015.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ困難に直面したときのCEOのとるべき心構え、とのことで視座は高いがリーダーシップを発揮する意味で、とても示唆に富んだ良書。実体験をもとにしている話なので、シンプルだがとても心に刺さる言葉が多い。 (仕事に追われ過ぎて、家庭が崩壊しそうなのを見て、) 父は私のほうに向いてこう言った。「お前、何が安い買い物か知っているか?」 父は何を言おうとしているのか見当がつかず、私は「わからないよ。何だい。」と答えた。 「花さ。花はまったくお買い得だ。それに引き換え、恐ろしく高くつくものは何だと思う?」。 私はこれにもわからないと答えた。 「離婚だ。」と父は言った。 ★どんな人間にとっても、人生で2種類の友達が必要だ。 ひとつは、何かいいことが起きたときにその人を呼べは自分のために感動してくれる人。嫉妬を隠すための偽りの感動ではなく、本物の感動だ。必要なのは、自分が起きたこと以上に、あなたのために感動してくれる人だ。 ふたつ目は、何か悲惨な状況になったとき、例えば生死の境にいて、一度だけ電話がかけられるときに呼び出せる人。 「成功するCEOの秘訣は何か?」とよく聞かれるが、残念ながら秘訣はない。ただし、際立ったスキルが一つあるとすれば、良い手がないときに集中して最善の手を打つ能力だ。逃げたり死んだりしてしまいたいと思う瞬間こそ、CEOとして最大の違いを見せられる時である。 「つらいときに役に立つかもしれない知識」 1.ひとりで背負い込んではいけない 重荷をすべて分かち合言えないとしても、分けられる主にはすべて分けお合う。 2.単純なゲームではない 苦闘は戦略が必要だ。どんな苦しい中でも打つ手は必ずある。 3.長く戦っていれば、運をつかめるかもしれない 明日は今日とはまったく違う。明日まで生き延びれば、今日はないと思えた答えが見つかるかもしれない。 4.被害者意識を持つな 困難は、おそらくすべてあなたの責任だろう。誰でも過ちを犯す。無数の過ちを犯す。自分を評価して「不可」を付けたところで慰めにもならない。 5.良い手がないときに最善の手を打つ 偉大になりたいならこれこそが挑戦だ。 悪いニューるの扱いには自分が一番長けていると考えていた。が違った。エンジニアたちは私が一晩中眠れなかった問題を簡単に聞き流していた。結局、私は創業者でCEOなのだ。私は会社と「結婚」した人間だった。何かがひどい状況になったとき、彼らはそれを放置できるが、私はできない。その結果、社員の方がずっとうまく失敗に対処していた。 無駄に一人で悩まなければならないなんて誰が決めたのか?その問題を修正できるだけではなく、熱中して意義を感じられる人間に任せる方がずっと良い。 健全な企業文化は、悪いニュースの共有を促す。問題を隠し立てせずに自由に語れる会社は、迅速に問題を解決できる。問題があることを知らせた人を罰してはいけない。むしろ、報酬を与える文化をつくる必要がある。 「人材を解雇する(人材がイケてなかった)ときの分析」 1.役職の定義がそもそも間違っていた 欲しいものがわからなければ、それを手に入れられる可能性は低い。 2.調書ではなく、短所のなさを理由に採用した 多数決の採用プロセスにありがちなケース。採用グループは、候補者の弱点は良く見つけるが、世界に通用する実力者が欲しいとCEOが考える分野には重きを置かない。 3.拡大を急ぎ過ぎた 必要以上に行けてる人材を雇っていないか?今のステージで、今後18か月のために仕事ができる人材と取らないと、その人材は実力を発揮する前に廃れてしまう。 4.誤った野心をもっていた 会社のためではなく、個人のための野心をもっていた 5.会社になじませられなかった 入社した時に、いかに会社になじませられるかの手立てを考えておくこと 「イケていない人材に声掛けをする」 1.屈辱 世間体、これまでがんばったのに…という屈辱が伴う。 2、裏切り 自分だって人のこと言えないのに、急にそんなこと言うなんて裏切りだ、と感じる。 打ち手として、 1.言葉を選ぶ 「~と思う」、ではなく、「~だ!」と言い切る。 2.現実を受け止める イケてないと伝えるのは、自分の力量が足りないからその人材の力を活かせなかったと考えること。より経験のあるリーダーなら、その人を一人前に育てられたかもしれない。 3.貢献を認める それでも働いてほしいなら、はっきりとそう伝えるべき。これまでの仕事を評価しており、将来を見据えての今回の声掛けであることを伝える。 「打ち手がない時の心構え」 この困難を乗り越えるのに、何にでも聞く銀の弾丸はない。あるのは鉛の弾丸だけだ。 つまり、いけてない今の製品・サービスを元手に、ひたすら改善するしかない。 やるべきことに集中しろ。あなたがどれだけうまくいってなくても、それを気にかける人は誰もいないからだ。メディアも、投資家も、上司も部下も、同僚も、両親も、家族も気にしていない。気にしないでもらうことが正しいことだ。たとえ、気にかけてもらったところで素敵なサービスは提供できないし、一円にもならないからだ。 「われわれは、人、製品、利益を大切にする。この順番に。」人を大切にすることは、ずば抜けて難しいが、それができなければあとのふたつは意味を持たない。人を大切にすることは、自分の会社を働きやすい場所にするという意味だ。ほとんどの職場は、会社が大きくなるにつれ、大切な仕事は見過ごされ、熱心に仕事をする人は秀でた政治家たちに追い越され、官僚的プロセスは創造性を摘み取り、あらゆる楽しみが奪われている。 考えれば考えるほど、私はチームに「何」をすべきかは伝えていたが、「なぜ」そうしてほしいかを明確にしていなかったことに気づかされた。権威だけでは、彼らに私が望むことをやらせるには十分ではなかった。 良い組織では、自治人が自分の仕事に集中し、その仕事をやり遂げれば会社にも自分自身にも良いことが起こると確信している。こういう職場で働けることは真の喜びだ。一方で、不健全な組織では、みんなが多くの時間を組織の壁や内紛や崩壊したプロセスとの戦いに費やしている。自分の仕事は何なのかさえ明確になっていないので、自分が役割を果たしているかどうかを知る由もない。また自分たちのキャリアにとって何を意味するかも分かっていない。 社員が辞めたいと思うとき… 1.マネジャーが嫌い 自分が受けた指導、キャリア開発、FBの無さに愛想をつかしている 2.何も教えられていない 社員が新たなスキルを身に着けるため、会社は投資していなかった フィードバックがなければ、会社はあらゆる意味で最適な実績をあげるチャンスはない。修正無き方針は、曖昧かつ鈍重に見える。人は、自分が見えていない弱点を直すことはまずない。 「自分メガネ」か「チームメガネ」か 状況を「自分」に結び付けたしか考えられていない人は一人称が「私」。自分のキャリアを充実させるため、という思考が強い。 チームとしての成功を個人の成功の上に置いている「チームメガネ」の人は、自分の成功体験を語るときでさえ「私」という一人称では語らないだろう。それに、自分の待遇や昇進の見込みよりも会社を成功させる方法について興味を示す。 昇進に伴う危険-「ピーターの法則」と「ダメ社員の法則」 「ピーターの法則」では階層的組織においては、有能なメンバーは次第に昇進していく。しかし遅かれ早かれ、メンバーは自分の能力の及ばない地位に達してしまう(無能レベルに達する)。そうなるとさらなる昇進は望めなくなるのだという。 →だから、自分の限界-1の職位が一番有能であれる。 「ダメ社員の法則」では大組織においては、どの階層においても社員の能力はその職階の最低の能力の社員の能力に収斂する、というものだ。それは、その職階でも、社員あh自分の能力を測るものさしを直近上位の職階の社員の中で最低の能力の社員に求める。 「心を静めるテクニック」 1.友達をつくる 同じように困難な決断をしなければならない経験を積んだ友達を話すことは心理的に極めて有益だ。 2.問題点を書き出す 頭の整理、心の整理につながり、決断を下しやすくなる 3.側壁ではなくコースに意識を集中する 側壁に意識を向けすぎると、車は吸い込まれて衝突してしまう。会社も同様に、何十、何百とある壁、何を避けるべきかに意識を向けず、これから何をなすかに意識を集中させるべき 組織を運営するには2つのスキルが必要だ。 ひとつは、何をすべきかを知ることであり、もうひとつは、そのなすべきことを実際に会社に実行させることだ。前者を「ワン」、後者を「ツー」と呼ぶが、CEOは大抵どちらかだけに強みを持つことが多い。 真に偉大なリーダーは、周囲に「この人は自分のことより部下のことを優先して考えている」と感じさせる雰囲気を作り出すものだ。こうした雰囲気は社員に会社を「自分たちのもの」と感じさせ、それに従って行動するようになる。 大なり小なり常に社員のパフォーマンスを評価しフィードバックを与えるべきである。その時の1つのテクニックとして「小言のサンドイッチ」がある。 最初の肯定的評価が「1枚目のパン」、次に難しいメッセージ、つまり否定的な評価が来る。続いて肯定的な励ましで締めくくる「2枚目のパン」で挟み、聞く耳をもたせることが大切である。 しかし、フィードバックをするには、臆していてはいけない。 1.権威を持て 社員の感情を和らげようとする言葉に気を取られていては、伝わらない。叱る時には叱る。 2.正しい動機からのFBを与えよ FBは相手の成功を願うからであり、失敗を願うためのものではない。それを相手に感じさせ、相手に味方だと感じられれば、あなたの言葉は真剣に聞いてもらえる。 3.個人攻撃をするな 特定の個人を私心で責めるのはもってのほかだ。 4.部下を同僚の前で笑いものにしてはいけない FBは相手の頭を素通りし、相手は恥をかかせたあなたを心の底から憎むようになる 5.FBはひとつ覚えの型ではいけない ある人は批判や叱責に過敏だが、やたらに面の皮が厚く、石頭な人間も多い。FBのスタイルは自分の気分ではなく、相手の性格によって変えよ。 6.単刀直入であれ 駄目なものはダメ。水で薄めた曖昧なFBは相手を混乱させ、対処を迷わせるだけなので、いっそしないほうが良い。
0投稿日: 2015.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOのための精神安定剤と聞いていたので、関係ないかと思っていたが、会社の人たちから勧められ読破。 ベンチャー創業期を経験した誰もが共感し、 学ぶことの多い1つのストーリーでした。 その時期に合わせた人材チョイスとマネジメントが必要で、どこでも活躍する人は少ないことを感じました。 わたしはまだエグゼクティブポジションにはなれないけど、それでもベンチャー経験者にはモチベーションの上がる一冊だと思います。
0投稿日: 2015.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログベン・ホロウィッツ『HARD THINGS』(日経BP、2015.4) ITスタートアップ「ラウドクラウド」の起業から上場、そしてインテル社への売却、その都度倒産の危機をくぐり抜けた著者が困難にどのように対処したかをまとめたもの。 書評サイトなどで板倉雄一郎『社長失格』と並べて紹介されているとおり、HARD THINGSを乗り越える、困難を克服した者にしか語れぬ洞察に満ちています。 「たいていのことはうまくいかない」「ひとつの問題を解決したら次の問題がまたむくむくとわき出る」と一見後ろ向きな世界観ながら、自己の能力への過信、創業時の部下への愛着を乗り越え「いま、何をなすべきか」(そして何をやめるべきか)に集中していく姿勢はプロ経営者のそれです。 マネジメントが部下の信頼を失っていくさま(役所でもよく見られます)、部下の心理、幹部の採用。盛りだくさんの内容で個別のエピソードが読ませます。CEOとして幾多の失敗を経た上で「弱みがないことではなく、強みで選ぶ」ことが必要だと気づいた著者は、「ここ1年2年で求められる男」として無名大学卒で風采も上がらない志願者をセールスマネジャーに採用、彼は見事に売上を上げる。 そして部下の心理「どうして長時間残業してまでボスのキャリアの成功を助けねばならないのだ?」 ボスがそのまたボスにごまをすって仕事を増やすとき、手柄を求めて部下を使い潰すとき、離反の芽が兆します。 【本文より】 ◯「ベン、問題は金じゃない。」私は奇妙な安心感を覚えた。上場する必要はないのかもしれない。資金問題を重く考えすぎたのかもしれない。きっと、ほかに方法があるのだろう。再びビルが口を開いた。「並外れた金だ。」そう、われわれは上場するのだ。 ◯やればよかったと思うことには一切時間を使わず、すべての時間をこれからきみがするかもしれないことに集中しろ。結局は、誰も気にしないんだから。CEOはひたすら会社を経営するしかない。 ◯「成功するCEOの秘訣は何か」とよく聞かれるが、残念ながら秘訣はない。ただし、際立ったスキルがひとつあるとすれば、良い手がないときに集中して最善の手を打つ能力だ。 ◯忙しすぎて教育ができないというのは、腹が減りすぎて食べられないというのと同じだ。 ◯大きな会社と小さな会社でもっとも大きく違うのは、経営している時間と、創造している時間の長さだ。 ◯経験を積めば積むほど、社員一人ひとり(自分を含む)になにか重大な問題があることに気づく。完全な人間などいない。だから、弱みがないことではなく、強みが何かで人を選ぶことが絶対的に重要だ。 ◯社員Aが社員Bに対する批判を述べるときに、Bを弁護せずに黙って聞いていると、あなたはその批判に同意したと見られる危険を冒すことになる。 ◯管理職が自分のキャリアを会社の成功より上位に置くのを見れば、部下は「どうして長時間残業してまでボスのキャリアの成功を助けねばならないのだ?」と考えるようになる。
0投稿日: 2015.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ【最強のVC、ベンホロウィッツの著書】 インターネットブラウザの基礎を作ったネットスケープ社を立ち上げた一人。 その後VCとなり、SVではかなり名の知れた投資家となっているベンホロウィッツ。彼の起業家人生について、かなり具体的に、どういう感情をいだいたのか、どういう対処をしたのかまで書いてある。 本の半分は経営者が取るべき行動指針を示しており、非常に参考になる。インターネットの基礎を作った男だけに、学ぶことはそこらへんの起業家本よりもたくさんある。 経営で迷った時には非常に参考にしたい一冊である。
0投稿日: 2015.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ・どんな人間にとっても、人生で2種類の友達が必要だ。ひとつは、何かいいことが起きたときにその人を呼べば自分のために感動してくれる人。二つ目は、何か悲惨な状況になったときに、一度だけ電話がかけられるときに呼び出せる人。 ・「やっていないことは何か?」を聞くのはよいアイデアだ。 ・成功するCEOの際立ったスキルが一つあるとすれば、いい手がないときに集中して最善の手を打つ能力だ。 ・その問題を修正できるだけでなく、熱中して意義を感じられる人間に任せる方がずっとよい。 ・いい会社でいることは、それ自体が目的である ・教育はマネジャーができる最も効果的な作業のひとつだ。 ・よい製品マネジャーは、重要な問題については書面で見解を示す(競合に対する特効薬、アーキテクチャ上の困難な選択、製品に関する困難な決定、攻めるベキ市場と引くべき市場)。悪い製品マネジャーは自分の意見を江東で述べ、「権力」がその意見を通してくれないと嘆く。悪い製品マネジャーは、自分が失敗すると、失敗は予言していたと主張する。 ・よい製品マネジャーは、チームの売上と顧客に集中させる。悪い製品マネジャーはチームをライバルが開発している機能の数に集中させる ・スタートアップの幹部の場合、自分が仕掛けない限り何も起こらない ・採用時の質問:仕事について最初の一か月に何をしますか? ・定量的な目標についてばかり報告して、定性的な目標を無視していれば、定性的な目標は達成できない ・「この部門では部内の知識と社外の知識のどちらが重要か」を意識していなければならない。 ・個人面談で役に立つ質問 ・■我々がやり方を改善するとしたら、どんな点をどうすればよいと思う? ・■我々の組織で最大の問題は何だと思う?またその理由は? ・■この職場で働く上で一番不愉快な点は? ・■この会社で一番がんばって貢献しているのは誰だと思う?誰を一番尊敬する? ・■君が私だとしたらどんな改革をしたい? ・■われわれの製品で一番気に入らない点は? ・■我々がチャンスを逃しているとしたら、それはどんな点だろう? ・■我々が本来やっていなければならないのに、やっていないのはどんなことだろう? ・■この会社で働くのは楽しい? ・怖じ気づかず、投げ出さず ・会社の向かうべき方針を決めるのを得意とするCEOを「ワン」とよび、決められた方針に沿って会社のパフォーマンスを最高にするのを「ツー」と呼ぶ。 ・フィードバックは会話であり独白ではない ・CEOはストーリーによって、社員のあらゆる活動のバックボーンとなるコンテクストを与えねばならない。コンテクストとは、社員の様々な活動がどんな意味を持つのか、全体を見通せるような背景情報だ。 ・買収に関して正しい判断を下すためには、次の質問に答えねばならない。①市場の潜在的規模は現在よりも少なくとも一桁以上大きいか ②そこでナンバーワンになれるか ・苦闘を愛せ
0投稿日: 2015.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
生々しい著者のCEO経験談。 経営の教科書とは一線を画す指南書。 IT系のスタートアップのCEOとはかくも大変なモノかと 思い知った。 ITバブルがはじけたときに上場できただけでも ものすごい伝説の気がする。 印象的だったのは、平時のCEOと戦時のCEOのふたパターンの成功するCEOがあるといい、著者は戦時のCEOと 言い切っているところ。経営の教科書は平時のCEOに ついて書いていることが多いとのこと。 今の自分には到底及びがつかない内容に 少々尻込みしてしまった。
0投稿日: 2015.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ平時と戦時ではCEOに求められる資質は異なる、というのは非常にしっくりきた。 ただ、 ・日本に住んでいる ・CEOではない 身からすると共感できない、しっくりこない部分が多かったのも事実。
0投稿日: 2015.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログベン・ホロウィッツが直に体験してきたことが描かれているのでありありとその当時の情景を理解することができます。トンネルを抜けた瞬間に次のトンネルがやってくる苦闘について共感できると共に励まされる一冊です。
0投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はITベンチャーの元経営。だが者華々しいサクセスストーリーではなく、苦難に次ぐ苦難の連続であり、常にギリギリでなんとか乗り切って売却に成功した。その経験からベンチャー・キャピタルとしてベンチャー企業を支援する側に回ったという。技術には自信があったベンチャー企業でも、様々なトラブルが起こる。想像を絶する困難の中で、逃げずに立ち向かう態度には感服する。経営者の孤独と精神力が余すところなく描かれている珍しいタイプのビジネス書だと思う。
0投稿日: 2015.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1読む目的 2この本への問い 3サマリ 4感想 1視座を高めること 2スタートアップのCEOはどんなことを考えるのか 3※全部は読んでおらずかいつまんでいる ①何かを生み出す人に必要な力は2つ。一つは現状を正しく把握する力。すぐ止む雨か嵐になるか。もう一つは、嵐が起きたときに次々と手を打つ力 ②スタートアップのCEOは確率を考えてはいけない。決めるのは自分である。 ③成功するCEOは、良い手がない時に集中して最善の手を打ち続けられること。 ④戦うべき時に逃げていると感じたら、こう自分に問いかけるべきだ。「我々の会社が勝つ実力がないのなら、そもそもこの会社が存在する必要などあるのだろうか?」 ⑤何を壊してもいいから全速力で動け、リスクなしに大きなイノベーションは生まれない。 ⑥企業が大きくなるとコミュニケーションの問題が発生する。優先しなかったコミュニケーション経路を認識し、その損失を最小化することが必要 ⑦側壁ではなくコースに集中する。 ⑧勇気は他の様々な性格と同様、努力によって発達させられる。 ⑨困難だが正しい決断をするたびに、人は少しずつ勇気を得る。逆に安易な間違った決断をする度に、人は少しずつ臆病になっていく。それがCEOの決断なら、企業を勇気のあるものにも臆病にも変化させる。 4まず、スタートアップは山あり谷ありで大変だけど魅力的という印象だったが、本当に絶望的であることを認識できた。いくつかあるスタートアップを啓蒙する書籍は、何はともあれサクセスストーリーだが、本書はそうではない。困難から得た教訓、苦しいものを教えてくれる。 この本を読んで、逃げないこと・打ち手を次々と打ち続けることを仕事のこだわりにしようと決意した。 それらは自分が身につけることが困難だと思っていたが、努力によって、鍛錬によって得られる力なのでできないのは怠慢だと気付いた。常に最善を尽くしたい。それが相手への敬意であり、自己成長の唯一の手段だから、
1投稿日: 2015.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップの経営のリアルストーリー。輝かしい業績なんて氷山の一角で、経営の問題は日々あちこちで発生している。それを実話を通して学ぶことができる。まさに困難に対してどのように立ち向かうか。
0投稿日: 2015.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔懐かしいネットスケープナビゲーター開発者が書いた本。経営術だが、正直で実践的な内容をblogに書いていたのを本にしたようだ。 彼は今成功しているファンドマネージャーとして認識されているが、たとえ、現在が成功した経営者であっても、その過程は平坦ではなく、絶望し、破滅の一歩縁まで足をかけている状態を経験しているようだ。 筆者はその時の心情を赤裸々に書くと同時に、極めて実践的なアドバイスを限界を示しつつ読者に提示する。 私にとっては、これまでやってきた仲間である親友を切る、袂を分かつ、そのやり方が大いに参考になった。
0投稿日: 2015.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧巻です。アンチ経営書というか、アンチ「ビジョナリー・カンパニー」。第2章のタイトルが”I Will Survive"、そして謝辞に友人としてNasとカニエ・ウェストの名が。ロックです。毎日こんなのだったらCEOとか別に結構です、と言いたくなるほどの修羅場の連続。日本なら完全に「ブラック企業」認定。あと、本気でやってると、本気の人と出会えるってことなんだろうなあ。数年に一度のビジネス本だと言えるくらい面白かった。
0投稿日: 2015.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログネットスケープを経て、ラウドクラウドでは世界で初めてクラウドビジネスを成功させ、その後はオプスウェアを約16億ドルでHPに売却し、現在はベンチャー・キャピタルで活躍する著者が、自身の”修羅場経験”から得た教訓をまとめた一冊。 著者は「平時と戦時」や「スタートアップと大企業」では経営者に必要な資質は全く異なるとして、特に戦時のスタートアップの経営者が直面する「本当の困難」を乗り越えるためには、経営書の知識よりも、「正しい野心」や「自分の心理のコントロール」、大勢に阿ることなく決断する「勇気」、どんな時でも「人を大切にする」姿勢といった、より根元的な、いわば人間力のようなものが重要になると主張する。 また、組織拡大時のちょっとした意思決定の誤りが「経営的負債」として積み重なり、例えば社内政治等の”大企業病”を生み出す温床になるなど、ベンチャー経営者だけでなく、企業人としても学ぶことが多い。ITバブルや金融危機、或いは取引先からの裏切り行為や苦楽をともにした社員の解雇など、修羅場をくぐった者でなければ出せない言葉の数々が、圧倒的な説得力をもって響く良書。
0投稿日: 2015.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は非常に面白く、そして参考になりました。 IT業界でいくつも大きな企業を立ちあげ、様々な苦労をしたその時時の状況をつぶさに書き上げ、更にどうそれを解決したのか? 非常にわかりやすく説明されています。今は著者はベンチャーキャピタリストとしても大成功しているわけですが、自らが様々な苦労を経験しているからこそ理解できる点もたくさんあるのでしょう。 この本は良い本ですよ。。是非読んでみてください。
1投稿日: 2015.06.30苦闘する人たちへ
やたらと評判の良いこの本だがこれが本当に役に立つ人がどれだけいるのだろうと言う気がしなくもない。 本当に難しいことは、「社員を解雇すること」「既得権にあぐらをかいた優秀な人々の不当な要求に対処すること」などなど自身の経験をもとに、答えを提供するのではなく苦闘している人に何かのインスピレーションとなるようにと書かれている。 一般人が触れた最初のブラウザ「モザイク」を開発した22歳のマーク・アンドリーセンが立ち上げたネットスケープ社に押しかけたベン・ホロウィッツはウェブサーバーの開発を任された。ちょうどウインドウズ95にインターネット・エクスプローラーが無料でバンドルされたころだ。ネットスケープをAOLに売却した後マークとベンはトラフィックの増大によるトラブルを解決するサービス「クラウド」のアイデアを元にラウドクラウド社を立ち上げた。会社設立直後にITバブルの崩壊に見舞われ、IPOによる上場を目指すがこの時の運転資金は3週間分しかない。なんとか立ち上がったこの会社も顧客の倒産により資金繰りがつかなくなった。会社を分割し残った会社をなんとか生き残らせる。そうしながらベンが苦闘した出来事と、いくつかのヒントを語っている。 自分へのメモ「やってないことは何か?」を聞くのは良いアイデアだ。 「会社倒産の準備をするんだ」しかしベンはやらなかった。CEOは確率を考えてはいけない。会社の運営では、答えがあると信じなきゃいけない。答えが見つかる確率を考えてはいけない。とにかく見つけるしかない。可能性が1に9つであろうと1000にひとつであろうと、する仕事は変わらない。 幹部を解雇する第1ステップはなぜ、会社に不適切な人物を採用したかを解明することにある。 教育は、早い話が、マネージャーにできる最も効果的な作業の一つだ。 所々にこういうヒントが有るので起業する人には役に立つのだろう。 「大組織においては、どの職階においても社員の能力はその職階の最低の能力の社員の能力に収斂する」ベンが名付けた「ダメ社員」の法則によると、部下は直近の一番ダメな上司と比べ自分でもそれくらいはできると考え、同レベルの社員で占められると無能レベルに達する。だそうだ。 ツイッター創業物語ほどのドタバタ劇ではなく真面目に書かれた本なのだが役に立つかどうかは少し微妙。この本に共感する人は苦労しているのだろう。
3投稿日: 2015.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社に置いてあったので何となく読んだ一冊。 結論として今まさに読むべき一冊だった、自分がCEOになる時には改めてもう一度読みたい一冊。 本書の序文やあとがきでも触れられているが、本書は経営書によくある「ヤバかったけど私はこうして成功した」という方向ではなく「常にヤバくて、失敗しまくったし、生き残るのに必死だった」という方向から経営を語った稀有な一冊である。 実際にスタートアップの事業に触れていると大体の場合でヤバい状況であり、ぶっちゃけどうすれば良いか分からないという事が殆どだと想います。たまに良い事が起きてもせいぜい3日しか持たず、あとはヒーヒー言いながらギリギリで意思決定して実行して検証して「うわぁやっちまった!」となっている事が殆どだと思います。 著者のベン・ホロウィッツは赤裸々にそれらを語り、心の底からアンチパターンを捻り出して紹介しているのが分かります。そしてCこの本から得られる重要なポイントは、CEOはこういう場面でどのような感情になっていて、部下や会社に対してどのような想いを持つのかを、CEOでは無い人が知れる事はスタートアップの成否を分ける上で大きな意味があると感じます。 そしてポール・グレアムも良く言っている「反直観的」という言葉。この意味が生々しいアンチパターンを通して知れるのがこの本を重要な存在にしています。
1投稿日: 2015.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOの苦悩が赤裸々に語られている本。 答えがない難問と困難にどう立ち向かったか、が経験として語られています。 世の中の起業の成功本とは裏腹に起業における苦悩がこれでもかと語られます。 しかし、正直、起業に興味を持たない人にとっては、 「ふーん」「それは大変だ」 ってところにしか落ちないかも。 なぜなら、その内容があまりにも壮絶。 資金ショート 上場する直前でのごたごた 株価の急落 社員の解雇 とりわけ、人を正しく解雇する方法や さらには幹部を解雇するための準備、 一緒に立ち上げた親友を降格させるとき、 友達の会社から採用してよいか、 などなど、つらい決断を迫られ、結果どう行動したかまで語られています 一通り読み通すとほんとCEOのつらさがひしひしと感じられます。経営者ってほんと大変! そういった経営の大変さとはちょっと別に、本書で述べられていた 「つらいときに役立つかもしれない知識」 として 一人で背負い込んではいけない 単純なゲームではない 長く戦っていれば、運をつかめるかもしれない 被害者意識をもつな 良い手がないときに最善の手をうつ と紹介しています。 うん、これなら使えるかも(笑)
2投稿日: 2015.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログネットスケープの創業に始まり、ラウドクラウド、オプスウェアとCEOを勤めた著者の自伝的な経営指南書。特に困難な状況( ITバブル崩壊、顧客企業の多くが倒産、資金ショート寸前、最大顧客からの契約解除などなど)をどう切り抜けてきたかを自身の経験を題材に展開。具体的で読んでて実感がわく。
0投稿日: 2015.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙なしでは読めない。 この本を、ただふーんと読みこなす人は たぶんCEOはできない。この本にもあるが CEOになるとは武道家になるということに似ている。 武道について学ぶことはできても、あり続けなければ意味はない。 この本から深く深く学ぶことも出来るし、あっさりおわってしまう人もいるだろう。
0投稿日: 2015.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年56冊目。 「吐き気と悪寒。本書を読みながら、何度も何度も感じた症状である。」 と日本語版序文にあるように、著者のベンチャー経営における壮絶な苦難の数々が生々しく綴られている。 中盤からは、その経験を踏まえての具体的なアドバイス(人を解雇する方法、肩書きや昇進の与え方、会社を売却するか否かの判断など)が記される。 現実的でとてもシビアな話が多く、組織のトップが直面し続ける苦難を覚悟させられる1冊だった。
0投稿日: 2015.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-12032356542.html
0投稿日: 2015.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOになってからの苦労や反省をおおっ広げに書いてくれていて、もちろんレベルは違うけれども、日々の自身の仕事への学びが非常に多い。 『苦闘を愛せ』って、いい言葉だな。
0投稿日: 2015.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログシリコンバレーのベンチャーキャピタリストが書いた、CEOやマネージャー、部長職がどう困難に立ち向かうべきか、その参考になる一冊です。 著者のベン・ホロウィッツは現在はベンチャーキャピタリストですが、以前は上場会社のCEOとして厳しい環境の中でビジネスの舵を握った、事業側も経験している方。 ベン・ホロウィッツに降りかかったタイトルにある「HARD THINGS(困難)」がこの1冊にてんこ盛りに収録されいて、そのときどう立ち向かったが書かれています。 表紙にあるコピー「答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか」とありますが、この本には答えはないです、基本的に。 しかし、先人がどう立ち向かったかを知ることでとても参考になり、自分の頭で考えて行動するきっかけになると考えています。
3投稿日: 2015.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は、ハードで読み応えがある経営書です。 前半では著者がCEO(最高経営責任者)時代に経験した様々な困難、危機的状況が具体的に語られ、後半では著者の経験から培われた困難に対する対処法が記載されています。 著者は、CEOとして、日々進歩するIT業界で世界初のブラウザの販売や、Googleなどに先駆けてクラウドサービスを手がけました。 現在は、会社を売却し投資家として活動しています。 CEOによる一般的な経営書は「私は経営者として、いかに成功したか」という、シンデレラ・ストーリーが語られることが多いですが、本書では通常の経営書では語られることがない下記のような最悪の状況・困難(ハード・シングス)がリアルに語られます。 ・会社が軌道に乗った直後にバブルが破裂し、顧客が次々と倒産。資金があと3ヶ月で底を尽きることが判明する。 ・IPO(新規上場)で資金を得ようとするが、投資家への発表時に妻が病気で倒れる。 ・株価の急落と上場廃止の危機。 ・全売上の9割を依存している相手から、突如契約解除を通告される。 ・3度にわたる社員の解雇。 ・信頼していた会計事務所に買収交渉の土壇場で裏切られる。 著者は最終的に困難を切り抜け続けて、1700億円超で会社を売却するという大成功を収めています。 本書では、CEOとしてのあり方、会社の売却の仕方、企業文化の育て方、幹部の解雇の仕方、教育制度の作成の仕方、フィードバックの行い方など、CEOとして最悪の状況・困難で培われた実践的なノウハウ・アドバイスが満載です。 著者の様々な困難から培われた教訓は、CEOでなくとも学ぶことは多いです。 わたしたちも、働く上で悩みやトラブルはありますが、この著者ほどの最悪の状況に追い込まれることはないと考えると、自分の悩みは小さいものだと気が楽になります。 困難に立ち向かう勇気が得られ、耐え抜く心が鍛えられる一冊です。 著者はCEOとして自身の人生を、哲学者カール・マルクスの言葉を引用して表しています。 --------------- 人生は苦闘だ。 ---------------
1投稿日: 2015.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログベンホロウィッツが自伝的にこれまでの経営の中でぶつかった困難をものすごく具体的に語る。 経営指南書、経営学の本はあれど、このように具体的に書かれた本は他にあるのだろうな。経営者、独立したい方はとても勉強になるし、困った時に度々見返すのではないかと思う。僕は独立したいとか思わないが、それでも経営側の気持ちが分かる、ためになる本だった。とはえいベンチャーのマネージャークラスでも、人材採用やマネジメントの話が書かれているので、具体的にためになる話は結構多い。
0投稿日: 2015.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログネットスケープを経て、グーグルやアマゾンに先駆けてクラウドビジネスを立ち上げ、艱難辛苦を乗り越え見事にEXITして投資家になった著者が、前半ではその艱難辛苦を克明に描き、後半ではそこから導かれたCEOの教訓を説く。通常の成功譚や指南書では得られないリアルなCEOの越えるべき厳しい壁を具体的に提示されているのがとても良かった。
0投稿日: 2015.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログシリコンバレーのVCstであるベン・ホロウィッツによる自伝的経営本。CEOが取るべき行動や選択の際のノウハウが列挙されているが、その内容は実に生々しく、相当エグい。何しろ筆者が最も伝えたいメッセージは、「私はこの言葉こそ起業家にとって、最も役立つ教えだと思う。苦闘を愛せ。今、私は日々起業家と接しているが、一番伝えたいのはこの教えだ。」である。序文を寄せた小澤さんが「読みながら何度も吐き気と悪寒を感じた」と告白しているが、経験者であればそうなるだろう。この本で取り上げられている課題は資金であれ人事であれ、最終的には「人間」に依存する問題だからだ(個人的には銀行員時代を思い出す)。蛇足ながら、この本が人間(CEO)にフォーカスしたものだとすると、「トライブ」は組織にフォーカスしたものであり、両方読むことをお勧めします。
0投稿日: 2015.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者からみた、困難の辞典。 ビジネス書はだいたい、理想論ばかりが並ぶ。 本書は一線をかくす。 具体的すぎて、頭ん中がぐるぐるする。 私は平社員のガキンチョ。 経営者の苦悩の種類を知る、という意味で すごく有意義。
0投稿日: 2015.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織論、評価方法、採用基準だけでなく、より具体的な問題発生時の対処法が示されている。経営のマニュアルと言える。
0投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
短期間でシリコンバレーを代表するベンチャー・キャピタルの地位を確立したAndreessen Horowitz http://a16z.com/ の共同創業者であり、ネットスケープ社以来アンドリーセンの盟友であるベン・ホロウィッツ氏の、スタートアップ企業を度重なる危機を乗り越えてEXITさせた半生記と「戦時(=会社の存亡に関わる危機が差し迫った状態)のCEO」としての教訓を述べたもの。 この手の(スタートアップ企業の)戦時を語った生々しい経営書としては、氏が述べている様に 『インテル戦略転換』 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%BB%A2%E6%8F%9B-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BBS-%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%96/dp/4883043339 位しか中々類書が無く(大企業のターン・アラウンドでは⇒『巨象も踊る』http://www.amazon.co.jp/%E5%B7%A8%E8%B1%A1%E3%82%82%E8%B8%8A%E3%82%8B-%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BBV%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%BC/dp/4532310237/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1430643359&sr=1-1&keywords=%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%BC )、貴重であり非常に参考になる。翻訳も読み易い。 尚、氏の祖父母は、アメリカ共産党の正規党員であり、本書の最終ページで以下の様に述べている。 「私のマルクス主義的生い立ちが最も資本主義的な仕事のために役立った。私の祖父の墓石には、「人生は苦闘だ」というマルクスの言葉が引用してある。私はこの言葉こそ起業家にとって、最も役立つ教えだと思う。苦闘を愛せ。今、私は日々起業家と接しているが、一番伝えたいのはこの教えだ。」
0投稿日: 2015.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ洋書の起業家自伝でここまでドロドロの艱難辛苦を描いたものは初めて読んだし、著者も他にはそうあるまいと自負するレベルでアントレプレナーの苦難のストーリーが赤裸々に綴られている。 環境、文化、技術的違いがあれども、シリコンバレーで起きていることとは言え仕事に情熱を注ぐものならば激しく共感せざるを得ないエピソード満載である。 物事は大抵、順調であることのほうが稀であり、常にピンチや戦時の対応を求められる方が多い。それが新しいビジネスであれば尚更だ。 数々のHARD THINGS=困難に対峙した時に、どう行動すれば良いか、どう判断すれば良いか、そういったことへのヒントが豊富に散りばめられた至宝の一冊。 ◼︎読書メモ ・プロジェクト全体が遅れる原因は必ず一人のにんげんに帰着する。ボトルネックは一箇所ということ。 ・正しい製品を見極めるのはイノベーターの仕事であり、顧客のすることではない。顧客がわかるのは、自分が現行製品の経験に基づいてほしいと思っている機能だけだ。イノベーターは顧客の言っていることを無視しなければならないことも多い。 ・我々が今やっていないことは何か?を常に問う事。そこにこそ本来集中すべき事があるばあいがある。 ・CEOは確率を考えてはいけない、答えがあると信じなきゃいけない。可能性がどれだけ低くてもする仕事は変わらない。 ・ポジティブなフィードバック方法、サンドイッチ方式などはすぐに部下に見抜かれてしまう。 ・人、製品、利益、を大切にする。この順番で。 ・採用にはとんでもなく力を入れ、統計的に分析するのにもかかわらず、教育の価値をいとも簡単に見過ごしてしまう。 ・採用者に対して、最初の1ヶ月に何をしますかと聞いて勉強と答える人間には要注意だ。CEOが無理だというくらい新規案件を持ってくる人間をさがそう。 ・経験を積むほど、人の問題が見えてしまう。長所より短所のなさを重視してしまうがそれは間違いだ。長所が一部分でも世界レベルのじんぶつを探すべきだ。 ・MicrosoftやIntelのようなテクノロジー企業でも罵倒語が飛び交っている。 ・階層的組織においては有能な人間は次第に昇進していくが、やがて能力の及ばない地位に達する。職域に追いつかない上司を見て、しかも複数いる中で最も低い人間を見てなぜあいつが?という不満がで始める。これがピーターの法則であり、これは不可避である。 ・時として会社にはあまりにも貢献が巨大でなにをしても許容せざるを得ないような社員が存在することがある。周りへの悪影響をCEO自らがやらねばならない。デニスロッドマンはめったにいないのだ。 ・全ての組織デザインは悪い。あらゆる組織デザインは会社のある部分のコミュニケーションを改善する
0投稿日: 2015.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ハイテク業界での有名ベンチャ投資ファンドのアンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者のベン・ホロウィッツが自身の企業経験とそこから得たCEOとしての教訓を惜しげもなく披露したもの。 前半は、著者がラウドクラウド社を創業し、ITバブルなどの中で、そこからハードウェア部分を売ってソフトウェア事業だけを切り出したオプスウェア社を成長させた後に1600億円でHPに売却するまでの8年間のストーリー。後半は、著者のその経験に基づくCEO論が綴られる。そして、最後は自身の投資家としての現状で締めるという構成。 最初の起業ストーリーも、マーク・アンドリーセンなどIT界の著名人も多数登場して面白いのだが、白眉は著者のCEO論だろう。「人生は苦闘だ」- カール・マルクスの言葉を引き、「苦闘とは、そもそもなぜ会社を始めたのだろうと思うこと」という文から始まる18個の「苦闘」が並ぶ文に想いが込められており、迫力がある。苦闘は不幸で孤独で無慈悲だと書いた後、それがゆえに「苦闘は、偉大さが生まれる場所である」と諭す。 自身の経験だが、あるとき日本の中小企業の創業社長にもインタビューをすることがあった。その社長は、比較的大きな企業に所属している自分たちに対して、「悪いこと言わないから起業なんかしない方がいいぞ」と言った。そして豪快快活で比較的心も太そうなその社長は、「何もかもなくすかもしれないという恐怖で眠れないなんてことはなかっただろ」と言った。起業するということは、ある意味でそういうことなんだと思う。そのときから起業家に対してさらに敬意の念を抱くことになったことをこの本を読みながら思い出した。 起業にしても多くの人の目に入るのは、成功して残った事例だけだが、その他にうまくいかなかったがゆえに目にも入っていない多くの挑戦がある。そして挑戦のさなかにいるときには、自分がどちらの側にいるのか、わからない長いときを過ごすのだろう。 CEOの心得として著者は、解雇や降格の心得、人・製品・利益の順に大切にするという物事の守るべき優先順位、社員教育の重要性、社内政治や野心の制御、肩書きや昇進、コミュニケーションの重要性、スケーリングの準備、CEOの責任と評価、売却の判断、などたくさんの実際的で示唆に富む言葉が並ぶ。そういった中で第一に感じたことは、不確実な世界の中で大切なことは結局は誠実さであるのではということだ。ドラッカーが、マネージャーに求める資質として「真摯さ(Integrity)」を求めたが、そのことにまさに呼応していると言えるのではないかと。 原題は”HARD THINGS ABOUT HARD THINGS”。困難についての困難。よいCEOになるには、CEOになるしかないと言うけれども、この本はCEOでなくとも勉強になるところあると思うよ。苦闘する人におすすめ。
1投稿日: 2015.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャーの社長達が、非常に共感したといったコメントを書いていたので読んで見たが、 残念ながら、この本に書かれているような壮絶な経験をしてきておらず、まだまだ自分が甘い、ということだけがわかった。 冒頭に著者の経験の全体像が示され、 中盤以降は、ここのシチュエーションにおける、 対応のポイントが具体的に記載されている。
0投稿日: 2015.04.18
