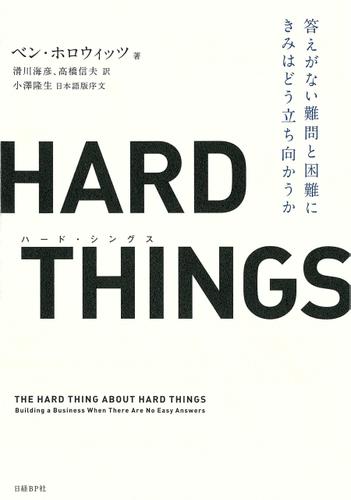
総合評価
(157件)| 44 | ||
| 59 | ||
| 31 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜベストセラーになったかわからないくらい、読むのが辛い本。 イントロダクションからして非常にハード。 本当に難しいのは、大きく大胆な目標を設定することではない。本当に難しいのは、大きな目標を達成しなかったときに社員をレイオフすることだ。 本当に難しいのは、優秀な人々を採用することではない。本当に難しいのは、優秀だと感じていた人々が既得権にあぐらをかいて、不当な悪態をつきはじめたときに対処することだ。 本当に難しいのは、大きく夢見ることではない。その夢が悪夢に変わり、冷や汗を流しながら深夜に目覚めるときが本当につらいのだ。 ▼成功するCEOの秘訣 そもそも秘訣はない。良い手がまったくないときに、それでも最善の手を打つこと。 寝れなくてもいい、吐いてもいい、困難を乗り切ることに集中すること。 どんな言い訳も必要ない。ベストメンバーが揃わない。部下が無能。市場が厳しい。 そんなことはどうでもいい。そんなことは誰も気にしてはいない。気にしているのはあなただけだ。 すべてのエネルギーを、最善の手を打つことだけに集中させること。 ▼経営幹部に求めるべきこと ・設定された目標に対する達成度 ・マネジメント ・イノベーション ・同僚との協調 ▼苦闘とは ・苦闘とは、自分自身がCEOであるべきだと思えないこと。 ・苦闘とは、社員があなたはウソを着いていると思い、あなたも彼らが多分正しいと思うこと。 ・苦闘とは、自分の能力を遥かに超えた状況だとわかっていながら、代わりが誰もいないこと。 ・苦闘とは、苦しい話ばかり聞こえて、会話していても相手の声が聞こえないこと。 ・苦闘とは、多くの人に囲まれていながら孤独なこと。 ・苦闘とは、破られた約束と壊れた夢がいっぱいの地。 苦闘は失敗ではないが、失敗を起こさせる。特にあなたが弱っているときにはそうだ。 しかし、どんな偉大な起業家も苦闘に取り組み、困難を乗り越えたきた。 ▼つらいときに役立つかもしれない知識 ・一人で背負い込んではいけない。 ・長く戦っていれば、運が掴めるかもしれない。 ・被害者意識は100害あって、1利もない。 ・良い手がなくても、最善を打つ。 ▼正しいレイオフ 1)自分のアタマをしっかりさせる。過去ではなく、未来に集中する。 2)実行を先送りしない。1秒でも遅くなるほどに、問題が連鎖して増えていく。 3)レイオフは「会社が失敗したけれど前進するために手放さないといけない。」というものであるべきだ。CEOは言い訳してはいけない。 そしてレイオフは、これまでの信頼を打ち崩す。信頼を取り戻すためには、レイオフ含めて今後とも全てに真摯で誠実であるべきだ。 4)管理職を訓練する。訓練は、黄金律を知ることから始める。「マネージャーは自分自身で部下をレイオフしなくてはならない。」 マネージャーは、そのシゴトを人事部門やサディステックな同僚、上長に任せてはいけない。 5)皆の前にいる。みんなと話すことは、なにより重要だ。 ▼マネージャーの成果を出すコツ ・なぜ部下を教育すべきなのかを話す ・教育と成果に集中させる ・ほとんどの社員は、会社が嫌いでやめない。マネージャーが嫌いか、成長させてもえらえていないことでやめる。という真実を伝える。 ・教育ブログラムを、つくらせ、洗練させる。 ▼その他 ・幹部採用は、長所よりも短所のなさを重視してしまうことに気をつける。 ・「ピーターの法則」「ダメ社員の法則」をしっておく。 ※ピーターの法則 ある仕事で成果をあげた人物が、その仕事を評価されて昇進しても、その地位において有能とは限らないため、昇進し続けるうちに能力の限界に達し、いつしか無能になる。もしくは無能な人は今の地位にとどまり、組織が無能な人が増える。 しかし、ピーターの法則が発生することは仕方がない。上げてみて、ダメならリサイクルしかない。 ※ダメ社員の法則 大組織においては、どの職階においても、社員の能力はその職階の最低の能力の社員の能力に収斂してしまう。
0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOであることは苦闘の連続だ。生まれ持ってのCEOは存在せず、みな良いCEOとなるため訓練が必要だ。 自分も、こういう仕事をする人間を目指すのだと思うを正直クラクラする。それくらいリアルな書。 途中内容がかなりITスタートアップに寄っていて、アメリカのITスタートアップの裾野の広さを感じた。きっとこれが教科書的になるくらいの市場なんだろう。
0投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025年6月25日、Yahooフリマで「高たんぱく・低糖質! rakoの美味しくてやせるおかず」のカテゴリー変更を断られた人がほかに出してた本。700円。 帯より、マーク・ザッカーバーグ推薦!でよい。
0投稿日: 2025.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログもう一度読む。線を引いて、大切なことをまとめながら。CEOのための本のように書いているが、企業人、リーダーになる人なら共通に大切なことが散りばめられていると思う。
0投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025年6月21日読了。ネットスケープ社やクラウド企業を創業・経営しネットバブル崩壊の中何度もプロダクト不備・資金調達難・レイオフなど倒産の危機を経験した著者による、マニュアルに書けないCEOとしての危機の乗り越え方指南。確かに、あまたのビジネス書は先人の自慢で合ったり「こうしたら『自分は』うまくいった」を説いているわけだが、「うまくいかないときにどうするか?」の説明はなく、また経営というのは必ずうまくいかなくなるもの、という点は納得できる。「あきらめず目の前の前提条件に縛られずあらゆる案を出す」「友人を持ち弱みを吐き出す場を持つ」など、CEOとしてのメンタルを保つ必要があるということか。人が納得感をもって昇給する仕組みの構築の重要性を説くなど、「人の感情」を抜きにして組織運営はできない、とはまさに経験者から聞きたい助言と思う。「経営は人間として不自然な行為」とは面白い。
1投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログずーっと積読していた。本当に必要な時に読むのが良いのではという謎の感覚で置いておいた。特にそんなタイミングがくることもなかったので、忙しい時期の寝る前のお供的に少しずつ読み続けた。1ページごとに吐きそうになるような事件の連続に、さすがにキツすぎwとか思いつつ、それでも乗り越えるために死力を尽くすホロウィッツの姿にはやはり勇気をもらえ、その1000分の1程度だろう今の自分の仕事に対しても頑張るエネルギーをもらえた。いっぱい線引いた。
0投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログVCアンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者ベン・ホロウィッツの著書。 ベン・ホロウィッツがラウドクラウド社のCEOであったときに直面した数々の難問と、諦めずに局面を打開していった経験が記されています。 起業家とそれを応援する人にとっての必読書と思います。
0投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOがいかに孤独な戦いを強いられているのかを感じた スタートアップのCEOへの教訓が書かれていたが、CEOでなくても学びになる内容だった ・社員の教育メソッドを作ること ・将来よりいま必要なメンバーを集めること ・考え続けて自分で結論を出すこと
0投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者としてのノウハウが実体験と共にわかりやすく述べられていた。序盤のエピソードトークは読みづらかったが、後半のノウハウは読みやすかった。
0投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いです。 まず純粋な読み物として面白い。 この手のビジネス書は中盤既視感のある事例紹介や例え話のオンパレードで飽きてしまうのですが、本書は著者が経営者として向き合い苦しんできたエピソードがベースとなっているので非常に解像度が高くシネマチックな面白さがあります。 またビジネス書としてもちゃんと学びが散りばめられており、経営者目線のみならずPMO目線でのプロジェクトマネジメントの勘所もある程度抑えられる内容になっています。 個人的には「私は交戦中だったから、戦時の将軍が必要だった」というフレーズがお気に入りです。 組織におけるマネジメントとはなにか、考え方が変わるかもしれない1冊でした。
0投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本のここがオススメ 「正しい製品を見極めるのはイノベーターの仕事であり、顧客のすることではない。顧客にわかるのは、自分が現行製品の経験に基づいて欲しいと思っている機能だけだ。イノベーターは、~顧客が真実だと信じていることを無視しなければならないこも多い」
0投稿日: 2024.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、経営の指南書でもありエンターテイメントでもある。と感じた。 一般会社員にはわからない、経営する側の気持ちを感じることができる。 前半は、筆者がスタートアップのCEOとして体験してきたドキュメンタリーだが、後半は経営者が考えるべきことが書かれている。 規模やレベルは違えど、中小企業の経営者にも響く内容だと思う。 次から次へと決断を迫られるスピード感。まさしく、ヒリヒリ伝わってきて楽しむこともできた。 上っ面だけで生きていない。それらを乗り越えた人物の言葉だけに、信用に値する。と感じた。
0投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18563467
0投稿日: 2024.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOの立場になって初めて実感する。個人も自身のCEOとなり、人財を雇用にレバレッジをかけることになれば、必要になる。
0投稿日: 2023.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログベン・ホロウィッツ氏の有名な著書。「平時のCEO」「戦時のCEO」という言葉が本の中で使われていたが、まさに戦時のような経営上の困難をいかにして乗り越えてきたかが描かれている。最後の締めくくりに「苦闘を愛せ、自身の性格、生い立ち、直感を愛せ」というメッセージがあるが、本を通じて、答えのない困難に直面してきた 著者の締めくくりとして本当に印象に残る言葉だと感じた。おそらく、この本は自身が経営者であるか否かなど、自分の置かれてる立場によってかなり感じるものが違うと思うので、立場が変わった時に再度読み直してみたい。
0投稿日: 2023.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ・苦難に関するエピソードだけでなく、そこから得られた経営技術(組織構築、人事、文化等)やマインドセット、リーダーシップ等を細かく解説している。 ・出典や言及されている人を元に以下の本も読んだことにより、より上記の理解が深まった。 -High Output -1兆ドルコーチ
0投稿日: 2023.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の起業や上場、会社運営から事業転換、売却などを通して経験した様々な「困難」が散りばめられており、それぞれに対応する知恵が記されている。本書を通して一貫して得られる教訓としては、成功するために答えのない課題に取り組む際に困難は付き物であり、困難があること前提で、その時に最善の策を打てるように胆力と意思決定力を培う必要があることだと感じた。また著者が様々な困難を克服する際に、人脈とその信頼関係が鍵となっているケースが多いところも印象的であった。
0投稿日: 2023.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 妻のフェリシア、パートナーのマーク・アンドリーセンと出会う 実はジョエルと知り合った事情は、これまで誰にも話したことがない。しかしこの事件は私の人生を形づくる上で大きな役割を果たした私は脅されて怖がったが、だからといって正しいことをする根性がなかったわけではない。私がジョエルに話しかける言葉によって、私は英雄にも臆病者にもなった。もし私がロジャーに命じられた通りに「ニガー」と罵っていたら、もちろんジョエルと私は親友になっていなかった。 この経験は何事であれ、表面で判断してはならないことを私に教えた。人でも物事でも、よく知る努力をしない限り、何も知ることはできない。知ることに近道はない。特に個人的な経験によって得られる知識に近道はない。努力なしの近道や手垢のついた常識に頼るくらいなら、何も知らないほうがよほどましだ。 第2章 生き残ってやる 第3章 直感を信じる 私の経歴の中で早くに学んだ教訓は、大企業でプロジェクト全体が遅れる原因は、必ずひとりの人間に帰着するということだった。エンジニアが決断を待って立ち往生しているかもしれないし、マネジャーが重要な購買の権限が自分にはないと思っているかもしれない。そういう小さな、一見些細なためらいが、致命的な遅れの原因になりかねない。 第4章 物事がうまくいかなくなるとき 「成功するCEOの秘訣は何か」とよく聞かれるが、残念ながら秘訣はない。ただし、際立ったスキルがひとつあるとすれば、良い手がないときに集中して最善の手を打つ能力だ。逃げた死んだりしてしまいたいと思う瞬間こそ、CEOとして最大の違いを見せられるときである。本章では、辞めたり吐いたりすることなく、困難を乗り切るための知恵をいくつか授けよう。 多くの経営書は、物事を正しく処理して失敗しないために何をすべきかに焦点を絞るが、こここでは大失敗したあとに何をすべきかについて考えよう。良いニュースは、私自身もほかのCEOも、大失敗の経験を豊富に持っていることだ。 悪戦苦闘 ■つらいときに役に立つかもしれない知識 苦闘を乗り越えるための答えはないが、私の助けになったことをいくつか紹介しょう。 ・ひとりで背負い込んではいけない。自分の困難は、仲間をもっと苦しめると思いがちだ。しかし、真実は逆だ。責任のもっともある人が、失うことをもっとも重く受け止めるものだ。重荷をすべて分かち合えないとしても、分けられる重荷はすべて分け合おう。最大数の頭脳を集めよ。オプスウェアで競合に負け続けていたとき、私は全社員を呼び、「オレたちはケツを蹴られていて、出血を止めなければ死んでいく」と話した。誰もまばたきひとつしなかった。チームは持ち直し、勝てる製品をつくって、私のあわれなケツを救ってくれた。 ・単純なゲームではない。苦闘は戦略が必要なチェスだ。ITビジネスは、とてつもなく複雑になってきた。テクノロジーが動くとライバルが動き、市場が動き、人が動く。その結果、スタートレックの3次元チェスのように常に打つ手はある。売上200万ドル、社員340人の会社を上場して、翌年7500万ドルを売り上げるという方法はどうだろうか。私の打っ手がまさにそうだった。2001年、IT企業が上場するには史上最悪の時期だと誰もが考えていたとき、私はそうした。6週間分の現金しか残っていなかった。打つ手は必ずある。 ・長く戦っていれば、運をつかめるかもしれない。テクノロジーゲームでは、明日は今日とまったく違う。明日まで生き延びれば、今日はないと思えた答えが見つかるかもしれない。 ・被害者意識を持つな。困難は、おそらくすべてあなたの責任だろう。人を雇ったのも、決断したのもあなただ。あなたは、リスクがあることを知っていた。誰でも過ちを犯す。どのCEOも、無数の過ちを犯す。自分を評価して、「不可」を付けたところで慰めにもならない。 ・良い手がないときに最善の手を打つ。偉大になりたいならこれこそが挑戦だ。偉大になりたくないのなら、あなたは会社を立ち上げるべきではなかった。 CEOはありのままを語るべき人を正しく解雇する方法/ 幹部を解雇する準備/ 親友を降格させるとき/ 敗者が口にするウソ 鉛の弾丸を大量に使う 実存する脅威に直面することほど、ビジネスで怖いものはないかもしれない。あまりの恐ろしさに、社員の多くは向かい合うことを避けるためなら何でもやるようになる。あらゆる代替案、あらゆる逃げ道、あらゆる言い訳を探して、一回の戦いに生死を賭けることを拒もうとする。私はこれを、スタートアップとの会話でよく聞く。 やるべきことに集中する 自分の惨めさを念入りに説明するために使うすべての心的エネルギーは、CEOが今の惨状から抜け出すため、一見不可能な方法を探すために使うほうがはるかに得策だ。やればよかっと思うことには一切時間を使わず、すべての時間をこれからきみがするかもしれないことに集中しろ。結局は、誰も気にしないんだから。CEOはひたすら会社を経営するしかない。 第5章 人、製品、利益を大切にする―この順番で かつてネットスケープのCEOとして私のボスだったジム・バークスデールがよくこう言っていた、「われわれは、人、製品、利益を大切にする。この順番に」。単純だが奥深い言葉だ。「人を大切にする」ことは、3つの中でも頭抜けて難しいが、それができなければあとのふたつは意味を持たない。人を大切にすることは、自分の会社を働きやすい場所にするという意味だ。ほとんどの職場は、良い場所とはかけ離れている。組織が大きくなるにつれ、大切な仕事は見過ごされるようになり、熱心に仕事をする人々は、秀でた政治家たちに追い越されていき、官僚的プロセスは創造性の芽を摘み、あらゆる楽しみを奪う。 働きやすい場所をつくる/ なぜ部下を教育すべきなのか/ 友達の会社から採用してもよいか/ 大企業の幹部が小さな会社で活躍できない理由/ 幹部の採用未経験の仕事でも適任者を見つける/ 社員がマネジャーを誤解するとき/ 経営的負債/ 経営の品質管理 第6章 事業継続に必須な要素 社内政治を最小限に 社内政治を抑えるテクニック CEO時代に私は、社内政治を抑制するためにいくつか有用なテクニックを身に着けた。 1 第一は、「正しい野心を持った人材を採用する」ことだ。会社をアメリカ上院みたいな政治の場にしたければ、間違った野心を持つ人間を雇うのがてっとり早い。長年インテルを率いたアンディ・グローブによれば、「正しい野心家」というのは「会社の勝利を第の目標とし、その副産物として自分の成功を目指す」ような人物だという。それに反して「悪い野心家」は、「会社の業績がどうあろうと自分個人の成功が第一」というタイプだ。 2 社内政治につながりそうな問題について、あらかじめ厳格なルールづくりをする。ある種の分野はどうしても社内政治につながりやすい。たとえば― ・実績評価と給与査定 ・会社組織のデザインと責任分野 ・昇進 正しい野心/ 肩書と昇進/ またザッカーバーグは、肩書は実際の職務と社内への影響力を正確に反映しなければならないと考えている。会社が急成長を続ける場合、組織がどう構成されているのかを常に明確にしておくことが非常に重要だ。ところが、副社長や最高XX責任者が何十人もいたのでは、職責が不明確になるのは避けられず、混乱が生じる。 さらにザッカーバーグは、ビジネス系社員はエンジニアリング系社員に比べて肩書がインフレ気味になることに気づいた。ザッカーバーグも対外的交渉の際にはインフレの肩書が有効な場合があることを認める。しかし彼は、エンジニアをはじめ製品を実際につくる社員こそ会社のコアと考えており、無用な管理階層はできるだけ少なくとしようと努めている。 優秀な人材が最悪の社員になる場合/ 経験ある大人/ 個人面談/ 自分自身の企業文化を構築する/ 会社を急速に拡大(スケーリング)させる秘訣/ ・組織のデザイン どんな組織化も必要悪であるから、悪が最小であるような選択肢を探す必要がある。この場合、組織デザインを社内コミュニケーションのアーキテクチャとして考えるとよい。特定の社員間のコミュニケーションをスムーズにしたいと思えば、彼らをひとりのマネジャーの下に所属させるのが、一番間違いない方法だ。逆に組織図で離れた位置にあればあるほど、そこに所属する社員間のコミュニケーションは疎遠になりがちだ。 また同時に、組織デザインは会社が外部とどのようにコミュニケーションをするかも決める。たとえば、製品ごとのセールス担当者のコミュニケーションを最大限にしようとして製品別組織にすれば確かに狙った効果は上がるかもしれない。しかし同時に、複数の製品を利用している顧客は、それぞれ別のセールス担当者とコミュニケーションをとらねばならなくなる。メリットの裏には必ずデメリットがあることを念頭に置き、組織デザインをしなければならない。 1 どの部分にもっとも強いコミュニケーションが必要か。まず一番重要な知識をリストアップし、その知識を誰が共有しなければならないかを検討する。たとえば、ある製品のアーキテクチャはエンジニアリング、品質管理、製品マネジメント、マーケティング、セールスの各部門に理解されていなければならない。 2 どんな意思決定が必要なのかを検討する。機能、アーキテクチャ、サポート方法の選定のように、繰り返し頻繁に行われる意思決定を洗い出す。関連ある問題についてはひとりの管理職がなるべく多くの意思決定を行えるように組織をデザインする。 3 最も重要度の高い意思決定とコミュニケーションの経路を優先する。製品マネジャーに重要なのは、製品アーキテクチャの理解が、マーケットの理解か。エンジニアに重要なのは、顧客の理解が、アーキテクチャの理解か。ただしこうした優先順位は、状況によってたやすく変わることを念頭に置かねばならない。状況が変われば再組織化が必要となる。 4 それぞれの部門を誰が管理するかを決める。これは4番目のステップであり、最初のステップではないことに注意する必要がある。組織づくりは実際に業務をこなす社員がもっとも効率よく働けるようにすることが目的であって、管理職が働きやすくすることが目的ではない。組織づくりで一番大きな誤りはこの点で生じやすい。組織の上のほうにいる人間の個人的な野心や都合を、組織の下にいる人間の作業実態やコミュニケーションの経路より優先させてしまうというミスだ。誰を組織の長にするかを優先順位の後のほうにすることで、マネジャー層から不満が出るかもしれないが、やがて彼らはそれに慣れる。 5 優先しなかったコミュニケーション経路を認識する。優先しなかったコミュニケーション経路がどれかを認識するのは、あるコミュニケーション経路を優先するべく選択するのと同じくらい重要だ。あるコミュニケーション経路の優先順位を下げたとしても、その経路が不要になったわけではない。もしその経路を完全に無視してしまうと、やがて必ずトラブルとなって跳ね返ってくる。 6 あるコミュニケーション経路を優先しなかったことから生じる問題を最小限とするよう手を打つ。こうした問題は部門間コミュニケーションの問題として浮上することが多い。そうした問題を処理するプロセスを事前に設定しておく。 成長期待の誤り 第7章 やるべきことに全力で集中する CEOとしてもっとも困難なスキル/ 恐怖と勇気は紙一重/ 「ワン」型CEOと「ツー」型CEO ジム・コリンズはベストセラーとなった「ビジョナリー・カンパニー2」(日経BP社)の中で、膨大なリサーチと総合的な分析の結果、CEOの後任の選択に関して、社外からの採用よりも社内からの昇進のほうが圧倒的に好成績であると結論づけている。その主たる原因は知識だ。その企業に独特のテクノロジー、それ以前の決断、企業文化、人事その他に関する知識を得るのは、CEOとして大企業を経営するスキルを学ぶよりはるかに難しい。しかしコリンズはなぜ、社外からの採用が失敗しがちなのか、本当に詳しくは説明していない。 そこで、私がこの場を借りて説明してみよう。組織を運営するには2種類の本質的に重要なスキルが必要だ。ひとつは、何をすべきかを知ることであり、もうひとつは、そのなすべきことを実際に会社に実行させることだ。偉大なCEOとなるには、このスキルが両方とも必要だ。しかしたいていのCEOは、どちらか一方を得意とする傾向がある。私は会社の向かうべき方針を決めるのを得意とするCEOを「ワン」と呼び、決められた方針に沿って会社のパフォーマンスを最高にするのを得意とするCEOを「ツー」と呼んでいる。 リーダーに続け/ 理想的なCEOのタイプというものは存在しない。スティーブ・ジョブズ、ビル・キャンベル、アンディ・グローブはいずれも偉大なCEOだが、彼らのスタイルにはほとんど共通点がない。偉大なCEOに共通して必要とされる唯一の資質は、おそらくリーダーシップだろう。それではCEOという職務においてリーダーシップとは何だろう?偉大なリーダーは生まれながらのものだろうか?それとも努力によって後天的になるものだろうか?かつて米国最高裁のポッター・スチュワート判事はポルノグラフィについて「見ればわかる」と定義した。多くの人々にとって、リーダーシップの定義もこれに近いだろう。ここではリーダーに従おうとする人々の数、質、多様性という側面から一般化してみる。人々がリーダーに従いたくなる要因にはどんなものがあるだろうか。私は次の3つの資質が重要だと考える。 ・ビジョンをいきいきと描写できる能力→スティーブ・ジョブス属性 ・正しい野心→ビル・キャンベル属性 ・ビジョンを現実化する能力→アンディ・グローブ属性 平時のCEOと戦時のCEO/ 自身をCEOとして鍛える/ CEOを評価する 第8章 起業家のための第法則―困難な問題を解決する法則はない 責任追及と創造性のパラドックス/ テクノロジー・ビジネスでは、事前に予想ができることは非常に少ない。凡庸な製品と魔術的に素晴らしい製品との差は、往々にして、社員にあまりに厳しく責任を求める会社運営と、社員が創造性を発揮するためなら必要なリスクを取ることを許す経営との差にある。社員の約束に責任を持たせることは重要だが、重要なことはほかにもたくさんある。 対立部門の責任者を入れ替える/ 最高を維持する/ 会社への忠誠心も能力も高いエグゼクティブを解雇しなければならないという状況が発生する。そのときにどう伝えたらよいのか。その幹部社員はこれまで大変な努力をしてきた。すばらしい実績も上げている。しかし市場環境は激変中で、その幹部が変化について行けないようなら、来年は解雇しなければならないかもしれない。 私は部下の幹部社員に職務評価を伝えるとき、よくこう表現した。「きみは現在いい仕事をしている。しかし計画では社員数は来年2倍になり、きみの職は今とはまったく違ったものになる。そこで今後はきみの職務評価は、新たな基準で実施される。念のために言っておくが、これはきみ個人の問題ではなく、私を含めて社員全員に新たな基準が適用される」 社員が2倍になれば、全幹部の職務内容が変わるという点を明確にすることが重要だ。全員が新たな職に就くことになるのだ。今までうまく行っていたやり方が新しい職でもうまくいくという保証はまったくない。それどころか、状況の変化に対応できず、漫然と旧来のやり方を続けることが、エグゼクティブが失敗するもっともありふれた原因だ。 会社を売却すべきか 第9章 わが人生の始まりの終わり 苦闘を愛せ 今、私は日々起業家と接しているが、一番伝えたいのはこの教えだ。自分の独特の性格を愛せ。 生い立ちを愛せ。直感を愛せ。成功の鍵はそこにしかない。私は彼らに前途に待ち受ける困難さを伝えることはできるが、困難に直面したときに何をすべきかは、彼が自ら判断する以外ない。私にできるのは、それを見出すための手助けだけだ。私はCEOでいる間、一度も心の平和を得られなかったが、運が良ければ時にはそれも得られるだろう。 しかし、世界中の助言と後知恵を集めても困難な物事は困難なままだ。最後に私は、困難に立ち向かうすべての人々に「幸多かれ、夢の実現あれ」という言葉を贈りたい。
2投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログまたステップアップしたときに巡り合うかもしれない本。 一度挫折したが、また別の本で出てきて再読して今回は読み切れた。また役職が上がると参考になるところも増えるかな。 フィードバックの項が早速参考になった。
0投稿日: 2022.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOとしての困難や苦悩、苦闘を語った本ではあるが、小さな組織のリーダーとしても深い学びを得られる。時に残酷でありながらも組織を前に進めるための考え、行動、振る舞いが凝縮されている。読んでよかった。 以下、印象的なフレーズ。 ・戦士が常に死を意識し、毎日が最後の日であるかのように生きていれば、自分のあらゆる行動を正しく実行できる。 ・何を避けるべきかに意識を向けず、これから何をなすかに意識を集中すべきなのだ。 ・苦闘を愛せ。
0投稿日: 2022.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分にはなかなかしんどい一冊でした。 翻訳がイマイチな部分あり、理解に苦しむと読み返しに疲れる、の繰り返しでした。 CEOは会社の全てを背負っているが一人では無いということも理解する必要がある。 そんな位置にはいないけど折れずに頑張っていきたい。
0投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
難しい本。社会で働いたことない僕にとっては今、どういう状況で何が問題なのかをイメージしながら読むのにはとても苦労した。ただ、経営を経験する前には読んでおくべき一冊だなと感じた。 後々企業で働くようになったら再読したい一冊。何が難しいかというと、IPOの話や株価。買収や事業の売却。マイクロソフトの話が出てきたりと、まさにIT系のビジネスが盛り上がっていく潮流の話だった。
0投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログCEO向けの視点で書かれているが、中堅社会人には誰にも学びがあると思う。ずっとこの本を読む気がしなかった。それは、熱血エリートビジネスマンにありがちな、ずっと働き詰め、熾烈な戦い、政治的駆け引きをやりやられつつ、でも俺は前に進む、のような、自分に酔ってる勘違いエリートの自慢話であり、ビジネスって厳しいんだぜ!という話かと思っていたからだ。全く違う。成功自慢やしんどさ自慢は一切ないどころか、自身の苦しみ、弱み、失敗をさらけ出し、人の採用、解雇、株主、ファンドとの向き合い方を彼の経験から得た知見を惜しみなく語る。 IT専攻し、純粋にITが世界にもたらす価値を突き詰めるための組織、会社を作った。お金儲けというより、自身の会社、製品に価値があると信じるが上での考えであり行動。これが一貫した人の言葉は重みがある。 私は良い製品マネージャ、悪い製品マネージャを完コピした。いつもこれを読み返し自分の仕事を見直し照らし合わせ、結果を出していきたい。
0投稿日: 2021.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分はまだ幹部にはなっていないが、それでも普段の仕事に役立つ金言が多数記載されていた。CEOならなおさら響くのではないだろうか。 内容としてはエピソードが多くエンタメとして面白い。 同時に苦難から学んだ著者の「経験則」が羅列されているという作りになっている。中項目、小項目とまとめられておりわかりやすい。 自分が共感できた「経験則」を備忘にて書き記す。 辛い時に役に立つかもしれない知識 ・1人で背負いこむな。 ・被害者意識を持たない。自分の責任だ。 ・良い手がなくとも最善手をうつ。 管理職、あるいはCEO ・事実は部下にありのまま伝えろ。部下にはなんだかんだ全て伝わっているのだから、隠すのは信用を失うだけだ。 なぜ部下を辞めさせることになってしまったのか ・全て企業側に資する。不必要な人材を必要であると謳って、採用したからだ。特に大きいのは、採用担当はダメな部分を見つける「ことのみ」得意である。その際CEOの求める「必要なスキル」は度外視されがちである。 ・つまり、「必要なスキルがない」が、「短所がない」という理由で採用が行われがちだ。必要なスキルに身を向けろ!そしてそれを大きく標榜し、周知するのだ。 物事の解決策 ・銀の弾丸はない。それは人月の神話でも言われているように。戦いからは逃げてはいけない。我々にできることはしなければいけないとわかりきっている鉛の弾丸を大量に撃つことだけなのだ。どこかで必ず、命がけで戦わなければいけない。 どうしてこうなったかを考えない ・失敗したかどうかなんてメディアも投資家もはたまた家族も気にしていない。理由が立派でもそうでなくても変わりはない。 どうすればよいのか?「やるべきことをやるだけだ」 人、製品、利益を順に大切にせよ ・組織が大きくなるにつれ大切な仕事は見過ごされ、熱心に仕事をする人々は秀でた政治家に追い越されていき、官僚的プロセスは創造性の芽を摘み、あらゆる楽しみを奪う ・人を大切にし、自分の会社を働きやすい場所にせよ。 良い会社でいるのはそれ自体が目的である ・なぜ会社に経営者は行くのだろう。みなが働きやすい環境で生き生きと働いていれるようにするためだ。 ・健全な組織は皆が仕事に集中し、それがどのような効果をもたらすか知っている。一方で不健全な組織は、組織の壁、内紛、崩壊したプロセスと戦っている。仕事がキャリアにどう役立つのかもわかっていない。それは部下が訴えることでようやくわかるが、あまつさえ経営陣は無視する。 ・だが、部下と常に面談しなければ上記の状態かどうかすら知り得ないのだ。 教育は必ず必要である ・マネージャー「「自身が」」教育すべきだ。義務である。そうすることで部下自身もさらに下の部下を教育することが義務になる。 ・それだけで人数×効率の生産性が上がる。 ・教育する=「何を」期待しているかがはっきりしている。同時に部下も「何が」できていないか、を理解できている。それが業績管理に伝わる ・教育無くして製品品質は上がらない。 ・「上司は何も見てくれていない」から部下は会社を去る。 大企業とスタートアップ企業の幹部は違う ・大企業では割り込み駆動型。恐ろしいほど予定が埋まる。スタートアップでは自分から動かないと何もない。 ・なぜかというと。大企業には全てが構築されている。スタートアップには組織すらない。 ・求められるスキルも違うが人材が最も重要。「創造しようとしている」人でないといけない。会社に採用してからも常に創造させてスキルを磨かせること。 社内政治 ・政治活動とは、会社の利益を向上させる以外の活動で自分の権益を獲得することである。 ・社内政治を少なくするには、昇進、昇給制度を明確にしなければならない。 正しい野心で埋めろ ・一般社員は自分のキャリアパス充実を考えて良い。ただし経営に携わる状況社員は、正しい野心をもって行動する者のみで構成されなければならない 個人面談の効果 ・個人面談は不要というのは評価のためなど上司を主体とした時の考えだ。部下を主体として考えた時、部下自身の、ひいては会社自身の不満、問題を拾い上げる場と化す。 心を鎮めるテクニック(心理的問題が起きた時) ・友達を作る。アドバイスをもらうこと ・問題点を書き出す。決断が正しい論理をそれに沿って詳細化するのだ。 ・側壁でなくコースを見ろ。問題一つ一つもしっかり見ないといけないがそれに集中してはいけない。「何を避けるべきか」の前に「何をなすべきか」という先を見据えること。 経営者のワン型ツー型 ・ワン型は情報を収集しまくり、決断を下すのが上手い。しかし日常業務には目を向けず、企業は潜在能力をいかしきれない。 ・ツー型はその逆。 ・大企業ではCEOはワン型、部下はツー型。であることを理解すること。そのため新しいCEOを見つける、育てるには労力がいるのだ。ツーをワンにしなければいけないのだから。 平時のCEO、戦時のCEO ・平時であれば、各位が創造性を発揮させることが重要だ。平時であれば。戦時であれば創造性発揮の余地はない。全員がプラン通り厳密に、正確に行動することを求める必要がある。そのために平時は企業文化を育成させる。戦時は企業文化を自ら作る。何を重要視しているのか行動で示すのだ。怒りを持って。 社員のパフォーマンスの評価とフィードバック ・権威をもて。感情を和らげるような言葉は不要。叱責として意味あるものにせよ。 ・「成長してほしいから言うのだ」と感情のせて。 ・フィードバックの仕方は「一人一人に合わせて」 ・単刀直入に言え!余計なおためごかしはいらない。 戦略とストーリー ・あらゆる仕事、活動には「なぜそれをするのか」というストーリーがある。それを常に明確で説得力のあるものにしなければいけない。でなければモラールが低下する。 CEOの評価 ・単純な目標と実績の比較ではその人の能力を測れない。過去の実績は将来の運用成績を保障しないのだから。 ただ、 ①「自分が何をすべきか明確に意識している」つまりストーリーを常に説得力あるものとし、意思決定が早い=常に必要に(なるかもしれない)情報収集を続けているか ②なすべきことを会社に実行させられているか、つまり能力のあるものを適切に配置し、すべての社員の動機付けができていて、大量の知識共有ができている。かつ社内政治に煩わされることもない状態。 責任追及と創造性のパラドクス ・創造性のためのスケジュール遅延というものがある。 遅延を詰めると創造性発揮をしようとしなくなるが、遅延を責めないと「なんであいつは」となり、周りの真面目な人のモラールが低下する。どうべきか? ①その人の役職 低ければ指導し、高ければ厳しくチェックする ②怒鳴らない。創造性を誉めよう。 ③リスクの取り方は正しかったか。結局解決された問題の遅れるリスク、機能リスクをきちんと精査していたかどうかが大事である。 常に最高を維持する ・人は衰える。であるからこそ「誰であるか」ではなく「何をなすか」で評価する。 ・環境が変われば職務内容が変わる。異動がなくとも環境や会社の体制の変更により、やり方を変えなければいけないのだ。そしてそれに適用する必要がある。
0投稿日: 2021.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めて読み直した。 普通の雇われの身の自分としては、CEOは心身ともに大変そうだなーという程度の感想にしかならないが、CEOをしてる方や経験者の方はものすごくうなづくことが多い内容だろうなと感じた。 特に自分の中に響いたのは、CEO決断するには勇気が必要だということ。 普通の社員が何かを判断する時は、理論的かに比重が置かれている気がするが、CEOは情報が不十分な中で決断しなければいけない場面が多い。 そこで必要なのは勇気、なるほどなと思うし、経験した当人しか経験できない感覚なんだろう。
0投稿日: 2021.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ生々しいヤバい人。 その中から何を学ぶか。 経営書。 CEO→ベンチャーキャピタルのブログをベースにした記事。 課題を伝えるときに解決策とあわせて持ってくるように →手に負えないモノほど持ってこない 良い会社であること ・それ自体が目的である ・物事がうまく行っている時はどうでもいいが、うまくいかないときに真価を問われる ・物事は必ずおかしくなる howどうやってを思いついて満足に浸っていてはダメ what何をすべきか、を明らかにする 新しい仕事は今の仕事と何が違うか 最初の一ヶ月、何をするか 溶け込むために何をするか(キーパーソンと交流する) どんな支援が必要か 多数は欠点が少ないほうを好む(求めている長所を重視しなくなってしまう) するとみんなが賛成するモノ、ただしうまくいかないものが出来上がる
0投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログマネジメント層じゃないんだけどうぁぁってなった。よし、今から仕事に鉛玉をありったけ打ち込んでくるわ。
0投稿日: 2021.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログベンホロウィッツの起業、経営の経験が述べられている本。 過去事例を基に、組織や文化の作り方、経営へのスタンスを学ぶことができ、読み応えがあった。 強いリーダーになる、強いリーダーを育てるという観点にも触れていて、様々な人にとって参考になると思う。
0投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle耳読で読了。 問題なく聞けた。 著者ベン・ホロウィッツの経営体験記が語られている本。 会社経営の楽しさと言うよりは、苦しさを中心に書かれている。 側から見ると大成功している人にも、苦しみはあるし、失敗もしている。 その経験が具体的に書かれており、それに対しての著者なりの対応がいくつも書かれている。 経験しないとわからないが、参考になることも大いにある。 苦しい時に読むと良いと思う。
0投稿日: 2021.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカのITベンチャーのCEO論。CEOとしての苦労話というよりも、葛藤、苦闘の物語が前半。後半はその経験を通じてのCEO向けのアドバイスの内容。前半はあまり聞けないような話で面白かった。CEO向けのアドバイスは、我々一般人には参考になるようなならないような。全体的には読んでて面白かった。、
0投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ社長かCEOになった時に大いに役に立つ本。 自分が将来そうなったら再読したいと思いました。 ならんけど(笑) 世に数多ある社長の成功本・自慢話ではなく 吐き気と戦く苦難の連続をつづった内容が良い。 一般people向けの内容として一つ上げると下記。 「つらいときに役に立つかもしれない知識」 ・ひとりで背負い込んではいけない ・長く戦っていれば、運をつかめるかもしれない ・被害者意識を持つな 管理職向けの内容として一つ上げると下記。 「個人面談で役に立つ質問」 ・この職場で働く上で一番不愉快な点は? ・この会社で一番頑張って貢献しているのは誰だと思う? ・われわれが本来やっていなければならないのに やっていないのはどんなことだろう? 作者のパートナーがMosaic/Nectscapeを作った マーク・アンドリーセンというのも感慨深いです。 学生の頃にそれらを使うともに、あのころ 研究室のhttpサーバーを独力で立ち上げたなあ、、、 と懐かしく思いました。
2投稿日: 2021.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ長年CEOを務めた著者がぶつかった様々な困難について、どのように対処してきたかが主に書かれている。 驚きと懐かしさを感じたのが、学生時代お世話になったネットスケープの関係者だった事。そして、クラウド事業の先駆けという、まさに時代の最先端を行く著者。そんなすごい経歴の裏には様々な困難があった。 恐らくCEOクラスの仕事に携わる事はないだろうから、直線参考にはならないだろうが、CEOなどの代表者の苦悩を垣間見れたのは良かった。 平時と戦時のCEOの説は状況によって対処方が違う事がよく分かる事例だと思う。
0投稿日: 2020.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOのサバイバル 経営者として、苦難に陥った時、辛い決断をしなければならない時に備え読んでおきたい本。 ■感想/評価 共感できるものが多く、手元に欲しい示唆に溢れているが、他著書でカバーできてしまうものともいえる。(会社改造・不格好経営・社長失格…) 会社改造以外はエッセイなので、体系立てて無い分、本著の方が読み返すのには良いのかもしれないが、インパクトとしては本著は弱いように感じた。 サラリーマンを続けるなら読まなくて良い、せめて 事業責任者レベルになって役に立つ内容だが、備えて読んでおくことは大切と思えた。読みやすいし、話も面白いが、登場人物の整理が大変。
0投稿日: 2020.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ◎CEO向け。難しかった。 p.160 マネージャーが社員の生産性を改善する方法は2つ。動機付けと教育のみ。 p.212 正しい野心とは。 会社の勝利を第一の目標とし、その副産物として自分の成功を目指す。
0投稿日: 2020.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこういった視点での話はなかなか書籍では得られないので、とても参考になった。 ただ、成功の基準は売却なのだろうか?そこだけが気になった。
0投稿日: 2020.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスでつらい局面に遭ったときにどうすればいいか、みたいな本。 思考がポジティブな時に読むのをお勧めします。
1投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「やっていないことは何か」 To Do Listもいいけれど、もっと何かできるのではないか、ということを確認するのも重要
1投稿日: 2020.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
企業家を待ち受ける困難の話。世にありがちな⚪︎⚪︎すればうまくいく経営、みたいな話ではまったくなくリアリティが凄かった(実話だから当たり前)。人事領域の話もでてたが、経験から来ている話が多かったので、断言している理由を自分なりに考えていこうと思う。
0投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ体験からくる経営者へのアドバイス エピソードが具体的なのと、本人が経営に関する本をいくつも読んで、それと比較して行っていることがとても良い
0投稿日: 2020.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分はただの従業員ですが、会社を作る・経営するということは本当に大変だなと再認識しました。 自社の経営者にも読んでもらいたいと感じました。 会社の問題は誰のせいでもなく、すべて自分の責任という覚悟がないとできないですね。
0投稿日: 2020.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スタートアップ企業経営という苦難に満ちた経営を手放さずにいるのは経済合理から考えてもおかしいことだ。それでも経営を続けるというのは、良い会社をつくること。それ自体がスタートアップ成功の醍醐味だと。
0投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログITベンチャーの経営書はどちらかというと煌びやかな印象があったが、この本は真逆と感じた。 経営者である作者が経験する苦難の数々が凝縮された構成となっている。 経営の難しさ、やりがい等をより感じられる作品。
0投稿日: 2020.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャー経営の指南書。困難な経営に対してどうするか、どんな苦境に対しても「何とかする力」について書かれている
0投稿日: 2020.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
HARD THINGS ベン・ホロウィッツ著 ★3.8 【シリコンバレー最強の投資家、かつ創業者による経営の修羅場と切り抜け方のヒント】 2007年オプスウェア(元ラウドクラウド)を16億ドルでHPへ売却 2009年VC アンドリーセン・ホロウィッツ創業、投資先はFacebook、Twitter、Skype、Airbnb、Foursquare他多数 ひとりで背負い込んではいけない:自分の困難は、仲間をもっと苦しめると思いがち。しかし真実は逆だ。分けられる重荷は全て分け合おう。最大数の頭脳を集めよ。 ありのままに伝えることが重要:会社の問題を隠さない方がよい主な理由は3つ。 1.信頼:物事をありのままに伝えることは、信頼を築く上で決定的に重要。 2.困難な問題に取り組む頭脳は多いほど良い:どんなに大きい脳でも知らない問題は解決できない。十分な目玉の数があれば、どんなバグも洗い出される。 3.良い企業文化、悪いニュースは早く伝わる:失敗した会社は致命的問題が会社を死に至らしめるずっと前からその問題を多くの社員が知っている。問題を知らせた社員を罰してはいけない。悪いニュースや問題を明らかにした人々に報酬が与えられる文化をつくる必要がある。 人を正しく解雇する方法:レイオフをした後に成功する会社は極めて例外的、会社の文化を壊すからだ 鉛の弾丸を大量に使う:特効薬は存在しない、魔法の銀の弾丸(M&Aや路線変更等)ではなく、鉛の弾丸(顧客ニーズである性能問題に真っ向から取り組む等)を大量に使うしかない やるべきことに集中する:外部環境の変化がどうかなんて誰も気にしちゃいない、自分のチームをコーチすること、やればよかったと思うことには一切時間を使わず、すべての時間をこれからすることに集中しろ セールス担当幹部マーク・クラニー:セールスの異才だが短所の多さから全役員反対、身元照会のための75人の紹介者のリスト、短所の無さではなく、職務遂行に必要な長所で選ぶ 働きやすい場所を作る:一対一の個人面談、なぜやるのかを十分に説明、良い会社でいるために重要 なぜ部下を教育すべきなのか: 1.生産性:マネージャーが12時間を使い講義<<<生徒10人×2,000時間/年×+1%向上=+200時間相当の利益 2.業績管理:明確な期待値を設定しておくことが重要 3.製品品質 4.社員をつなぎとめる 幹部の採用(未経験の仕事でも適任者を見つける) 社内政治を最小限に: 正しい野心を持った人材を採用すること、会社の勝利を第一の目標とし、その副産物として自分の成功を目指すような人物 給与の直接個別交渉は絶対行わない、政治性が広がる、実績評価・給与査定・昇進等は厳格なルールをづくりを 個人面談: 緊急性の高い課題以外のありとあらゆる問題を拾い上げることができる唯一のチャネル 個人面談を効果的にするカギは、その主人公は上司ではなく部下である社員だと理解するところにある、上司が話すのは10%以下、90%以上は社員 役立つ質問例:われわれがやり方を改善するとしたらどんな点をどうすればよいと思う?組織で最大の問題は?頑張って貢献しているのは誰?君が私ならどんな改革をしたい? アンディ・グローブ(インテル経営者) 「インテル経営の秘密」「インテル戦略転換」 正しい動機からフィードバックを与えよ:フィードバックを与えるのは相手の成功を助けるためであり、失敗を願うからではない。相手の成功を願っているなら、それを相手に感じさせよ。感情を伝える努力をせよ。相手があなたは味方だと感じられれば、あなたの言葉に真剣に耳を傾ける。 フィードバックは単刀直入であれ:相手の社員の感情を和らげようとする言葉を加えてはならない。叱責を別のものに誤魔化すことはできない。
0投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業家は必見 タイトルの通り、ハードシングスに見舞われた著者がその中でどのように決断をし、乗り越えたかを描いた名著。 CEOとしての葛藤や、経験からくる知恵は他の本では味わえないリアリティを持っていて、厳しい中での戦い方を伝えてくれた。
0投稿日: 2020.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップ経営者は、試練の連続で、どのように乗り越えるのかという話なのだが、ふつうに会社員をしている自分でも面白かった。経営者は、何を管理職に求めているのか、社員にどのような動きをしほしいのか、上の人の目線から自分を見つめ直すことができた。
0投稿日: 2019.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者であるベン・ホロウィッツさんが自らの経営者体験で得た知識を惜しげもなく伝えてくれた書籍です。起業、営業、人事、財務等、ホロウィッツさんがビジネスで得られた教訓はとても汎用的なものだと思います。
1投稿日: 2019.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著書のベン・ホロウィッツ氏が自身が起業した時の体験談をベースに書いた本。 成功した会社を後になって分析した本が多いが 本書は、自身がCEOとしての困難への対処法と指南に溢れているので 他の似たような本よりもリアリティが高く、参考になる部分は多い。 また、本書の中でも言及されているが、激務しながら沢山の困難にぶち当たる経験をしていないと、深みが出ない。自身にも還元したい。
0投稿日: 2019.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直なところ、序盤はつまらなかった。 色眼鏡で見ていたからだろう。これは作者の回顧録みたいなもの、回答のない困難に答えを出す方法を学ぶことを探していたからだ。 実はそんな方法はないのだと気付いてからは、読むスピードが早まった気がする。 気になったところ p88 自分へのメモ、やってないことは何か?を聞くのは良いアイデアだ。 p133 われわれの会社が勝つ実力がないのなら、そもそもこの会社が存在する必要などあるのだろうか? p248 個人面談で役に立つ質問の例 われわれがやり方を改善するとしたらどんな点をどうすればよいと思う? われわれの組織で最大の問題は何だと思う?またその理由は? この職場で働く上で一番不愉快な点は? この会社で一番頑張って貢献しているのは誰だと思う?誰を一番尊敬する? きみが私だとしたら、どんな改革をしたい? われわれの製品で一番気に入らない点は? われわれがチャンスを逃しているとしたら、それはどんな点だろう? われわれが本来やっていなければならないのに、やっていないのはどんなことだろう? この会社で働くのは楽しい? p277 私が起業家として学んだもっとも重要なことは、何を正しくやるべきかに全力を集中し、これまでに何を間違えたか、今後何がうまくいかないかもしれないかについて無駄な心配をすることをやめるという点だろう。
2投稿日: 2019.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分で本を書くような成功者のサクセスストーリーには必ずおいしいいくつかの修羅場があります。 こんな困難を切り抜けてきたと、その困難がきつければきついほど自慢できるという寸法です。 そんな成功伝からも、もちろん得るものはあるのでしょうが、本書の趣はかなり異質です。 もちろん、タイトル通りに大きな困難が待ち受けていますし、それをうまく克服もしています。 大きな違いは、自身の経験を有意義な経験則に落とせる能力でありそれを過不足なく表現できる文章力です。 文章力については翻訳者のうまさもあるのかもしれませんが、とにかく読みやすくて面白い。 内容については以下に少し印象に残った言葉や話を列挙してみます。 「ひと、製品、利益の順で大切」(P145) 「大組織においては、どの職階においても社員の能力はその職階の最低社員の能力に収れんする、これをダメ社員の法則と呼ぶ」(P226) まあ、ボトルネックの人間版ですね。 会社がつぶれそうになった時、投資家のハーブ・アレンが助け舟を出したが、テクノロジー企業には投資していなかったのになぜ我々を助けたのか?と後日彼にその理由をきいたところ、「多くのCEOは苦境になるとそこから逃げようとするが、君たちは私に会いに来て、決意をみせた。勇気と決意に投資するのが私の流儀だ(意訳あり)」(P277)などは、感動的な場面です。 会計事務所アーンスト&ヤングの裏切りのエピソード(P336)は、本書が売れれば売れるだけ会社へのネガティブキャンペーンとなりますねえ、仕方ないけど。 捨てる神あれば拾う神あり・・まさに会社経営には何があるかわかりません。 2015年に発売されて数々の受賞をしている作品だけのことはあり、読み応えばっちり、そして読めば必ず得られるものがあるはずです。 満点に近い星4つです。
1投稿日: 2019.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOが経験した困難な事象に対する対応方法を具体的にかかれた良書です。 CEOが会社や部下に対してどのように振る舞うべきなのか?を知るのであれば今まで読んだ本の中で最も良いと思いました。 一番響いたのは、社内政治について。自分が部長なら、部長は一番仕事が出来ない役員に標準をあわせて仕事をしてしまう。という点。 そうすると、全ての部長は一番仕事が出来ない役員レベルになってしまって、会社のレベルが下がってしまう。 うーん、これはまさにそうかも。自分の役職が上がってくると最も蹴落としできそうな一つうえの役職の人物を頭に思い描いた上で、その人物と自分を比較するが、これは愚の骨頂だと思った。比較するなら、一つうえの役職の『最も仕事ができる人物』と比較するべきだと実感。 そうしないと自分の成長は無いな。と感じた。
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018年ベストビジネス書。中小企業に転職する前の心の準備に最適だった。西海岸らしい明るさが一切なく、最後まで陰鬱に終わるのが良い
0投稿日: 2019.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい内容だが、それを実践しているからこその作者なのだと分かる本。 成功するCEOのスキルは、良い手がないときに集中して最善の手を打つ能力。常に死を意識し、毎日が最後であるかのように生きれば、自分のあらゆる行動を正しく実行できる。 97pからの「苦闘とは」が秀逸 苦闘は偉大さが生まれる場所である。 人、製品、利益をこの順番で大切にする。 働きやすい場所→仕事に集中して、やり遂げれば会社にも自分にも良いことが起きると確信できている。自分のする事は効率的で効果的で、組織にも個人にも変化をもたらすと分かっている。意欲が高く、満足度も高い。 教育の第1段階は、新入社員に何を期待しているかを教える〜会社の歴史的なアーキテクチャの意味合いを叩き込むまである。これを採用の条件にする。 マネジメント教育。ベテラン社員には教える側になってもらう。 個人面談の質問例 ・我々のやり方を改善するとしたらどんな点をすれば良いと思う? ・我々の組織で最大の問題は何だと思う?またその理由は? ・この会社で働く上で1番不愉快な点は? ・この会社で1番頑張って貢献しているのは誰だと思う?誰が1番尊敬する? ・君が私だとしたらどんな改革をしたい? ・我々の製品が1番気に入らない店は? ・我々がチャンスを逃しているとしたらそれはどんな点だろう? ・我々が本来やっていなければならないのにやっていないのはどんなことだろう? ・この会社で働くのは楽しい? ★上司は聞き役。社員に90%話させるつもりで ★恐怖と勇気は紙一重。英雄は自身をしっかり制御し、恐怖を跳ね除けてしなければならぬ事をする。英雄も臆病者も、感じる恐怖は同じ。臆病者は直面すべき事に直面しようとしない。 ★上に立つ者として ・原因を持って ・正しい時からフィードバックを与えよ ・ぽち個人攻撃をするな ・部下を同僚の前で笑いものにしてはならない ・フィードバックがワンパターンではいけない ・単刀直入であれ ・悪いニュースであっても部下が自由に話せる空気を持て
0投稿日: 2018.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
困難に際して何をすべきかは、自分で判断するしかない。(苦闘を愛せ、自分の性格を愛せ、生い立ちを愛せ、直観を愛せ)
0投稿日: 2018.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
シリコンバレーの何かの会社のCEOが書いたCEOはマジでこんなに大変なんだよ、という本。 以下格言 良いマネージャーは ※howだけでなくwhatが実現出来るまでを整理 ※重要な事は書面で見解を示す ※問題を要素分解する ※成功を定義する 顧客獲得と維持は全く違う。顧客満足度は定性なので数字には現れない。 正しい野心の持ち主・・・自分メガネしかない人ではなくチームで考える ピーターの法則とダメ社員の法則→緩和させるには昇進や肩書きに対する処方箋が必要。 組織のデザイン→どのコミュニケーションを優先させるか 戦略とはストーリー 会社のスケーリングは製品のスケーリングと似ている。 エグゼクティブの関連分野 ①目標に対する達成度 ②マネジメント ③イノベーション→目に見える定量的な評価を追わない事 ④同僚との協調 教育は何故大事か ①生産性 ②業績管理 ③製品品質 ④社員を繋ぎ止める
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ・幹部社員をみんなの総意で決めようとすると、議論はほぼ間違いなく、長所ではなく短所のなさへとぶれていく。孤独な作業ではあるが、誰かがやらなくてはならない ・定量的な目標についてばかり報告して、定性的な目標を無視していれば、定性的な目標は達成できない ・組織改革はひとたび決断したら、即刻実行されねばならない。時間が経てば必ず情報が漏れ、政治的な運動を引き起こすからだ ・慎重にデザインされ、厳密に運営される肩書と昇進のシステムがなければ、必ず社員の間の不公平感が蔓延する。職組織と昇進手続きがきちんと整備されていれば、多くの社員が無用な不満を抱かずに済む ・企業文化は初めから意図してシステムの中につくり込めるものではない。創業者や初期の社員たちの行動の積み重ねがやがて企業文化と呼ばれるようになっていくのだ ・平時のCEOは「市場で1位ないし2位が獲得できないならその市場からは撤退する」というようなルールを設けることができる。戦時のCEOにはそもそも市場で1位や2位になっているような事業がないので、そんな贅沢なルールに従う余裕はない ・フィードバックを与えるのは相手の成功を助けるためである。相手の成功を願っているなら、それを相手に感じさせよ。感情を伝える努力をせよ。相手があなたは味方だと感じられれば、あなたの言葉に真剣に耳を傾ける ・ビジネスでは「何もかも順調」と思った瞬間、天地が崩れるようなことが起こることがある。そんなときは「理不尽だ」と言っても始まらない。とにかく全力で対処し、しばらくはこっけいに見えても、気にしないことだ
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ●第4~7章は大いに興味深く読めた。とはいえ、CEO向けに書かれた本なので、これをそのまま自分に当てはめて活用することはできない。
0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログシリコンバレー随一のVCアンドリーセン・ホロウィッツのベン・ホロウィッツ氏が自身のラウドクラウドとオプスウェア起業から売却までの波乱万丈の経験を元に学んだ教訓をふんだんに含んだ経営に関する本。著書の中で「平時のCEOと戦時のCEOは違う」と言っているが、普通の経営について書かれたビジネス書は平時のCEOについて書かれたものばかりの中、この本は徹底して戦時のCEOのどう経営していけばよいかという内容に一貫している。 私自身は起業家でもなければ、経営者でもないけれども、人をManageする立場になった時にもう一度読みたいと強く思った。良書。
1投稿日: 2018.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半のHARD THINGSづくめの展開にはハラハラする。後半はアドバイス編。経営者にはすごく身になる内容なんだと思われる。解雇する側の話など、サラリーマンとは違う立場なので、近いようで遠い話でした。
0投稿日: 2018.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ○何を避けるべきかに意識を向けず、これから何をなすかに意識を集中すべきなのだ。(287p) ○自分の独特の性格を愛せ。生い立ちを愛せ。直感を愛せ。成功の鍵はそこにしかない。(377p) ★あなたがCEO、またはCEOを目指す人なら、この本はバイブルとなるだろう。
1投稿日: 2018.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人、製品、利益の順に大切にする。 とてもシンプルで、難しく、重要な優先順位。自分が働く会社もそうであってほしい。けど、大事にしたいと思ってもらえるような人材でい続けられるよう、最大限の努力を常にしないといけないのは当たり前のこと。自分がどこまでできているか、自分からの目線、経営層からの目線でときどき振り返る必要がある。
0投稿日: 2018.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業家が書いたビジネス書、自己啓発書はサクセスストーリーを紹介しているものが追い。本書の著者ベン・ホロウィッツ氏もITベンチャーのCEOとして成功体験を持つが、本書は起業家にとって「しんどいこと」にフォーカスしている。どちらかと言えば忘れてしまいたいようなしんどい経験を赤裸々に語り、その対処法を紹介している。日本とビジネス慣行が異なるため、直接あてはめにくい部分もあるが、起業するとはどういうことかを追体験するのに好適だろう。
0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログぐんぐん引き込まれてページを繰る手が止まらなかった。親友を降格させるとき、なんて書いてある本が他に存在するのだろうか。個人面談で役に立つ質問の例も書かれており、非常に参考になる。 以下、本書より抜粋。 「ひとりで背負い込むな。」 「単純なゲームではない。」 「長く戦っていれば、運をつかめるかもしれない。」 「被害者意識を持つな。」 「良い手がないときに最善の手を打つ。」 「何にでも効く魔法の銀の弾丸ではなく、鉛の弾丸を大量に使う。」 「やるべきことに集中する。」
0投稿日: 2018.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャーキャピタルの創業者である著者がITベンチャーを立ち上げその経営を行った際に様々な困難から得た教訓や経験を書いた一冊。 重厚な一冊で起業家CEOとしての役割を苦難に立ち向かうための心構えが書かれていました。 会社の売却や事業内容の変更など次々と押し寄せる危機からの経験はリーダーとしての立ち居振る舞いや精神というものを教わることができた また、平時と戦時や「ワン型」や「ツー型」などその時に応じて適性が変わることを本書で学ぶことができました。 精神的な部分だけでなく報酬や昇進などの社内の制度もどのように整えていくかも書かれており実践的な内容であるとも感じました。 常に困難がつきまとうこと、真実をありのまま話すこと、重要な役職の責務は1人に集約すること、人選や会社を売却する際の基準など経験に裏打ちされた活きた知識を得ることが出来ました。 そして本書は優れたリーダーについてのヒントが書かれていたと感じた一冊でした。
0投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログマネジメント部分について部分的に読んだ。起業あるある、創業者あるあるは書かれていたがマネジメントの具体論のより詳しくはhigh output managementを参照というところか。
0投稿日: 2018.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年、話題になったビジネス書。ちょっと時間が空いてしまいましたが、読んでみました。まえがきにヤフー小沢さんも書いてましたが、規模は違えどベンチャーあるあるが詰まった一冊。 成功を高らかに語っている本はたくさんあるけど、地獄を見た話しをここまで赤裸々に語った本はそんなにないと思う。会社が瀕死の状態になり、能力の問題で親友に解雇を言い渡さないくらいの状態になったら、自分なら正常な気持ちでいられるだろうか。。。 選択と集中。 何をするべきかを選んで集中すると思いがち。でも、本当は「何をしないかを選択する」ことなんだな!と。 久しぶりに読みながら、たくさん書き込みして、たくさん耳を作ったな。その部分だけを読み返すだけでも、意味がありそうだ!
0投稿日: 2018.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログSkypeやFacebookへの投資を成功させた著名なVenture Capitalistである筆者の、自らの起業経験をもとにした経営論 。巷の経営書と大きく異なるのが、①「戦時」に焦点を当てている点、②具体性。組織のリーダーの多くが直面するきわめて具体的な「困難な問題」について、ホロウィッツが自らの体験から割り出した対応のヒントが書かれており、読んでいるだけでも冷や汗をかいてしまうような場面を筆者がどう切り抜けたか、そこからどういう示唆が得られたか、が語られており、何度も読み返そうと思っている本の一つ。
0投稿日: 2018.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔にシリコンバレーで起業して、バイアウトしたのち、今はベンチャーキャピタリストをしている人のCEOだった頃のあれやこれやを自叙伝的に書いた、そしてそこから得た知己を書いた本で、起業家って本当に大変だよって言っている本です。 そして、それでもなぜ起業するのかという部分は書いてません。多分ケインズが言うアニマルスピリットってやつでしょう。人前では「事業は好調私はハッピー」と振舞っているけど、実はものすごく悩んで苦しんで臆病になっている、(私はそうだった、そして他のCEOもそう)という読むだけてしんどい本。題名のHARDTHINGはそのままの意味で「キツイこと」という意味。 英語圏の思考方法がそうだからか、翻訳するとそうなるのかよくわからないけど、英米系の本は総じてこんなことがあった→こう考えた→こうやった、と非常にロジカルに考えていることがわかる。ノンバーバルなコミュニケーションについても、これでもかという程に言語化定型化していて、このあたりのぼんやりしたものを固定化する力はいつも凄いなと思います。 最近思うことは、決定するってとっても大変だってこと。あと、金をどっから引っ張ってくるかはとても大きな要素だってこと。
1投稿日: 2017.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業時の困難な状況のときにどう立ち向かうのか、部下を解雇するときに何に注意するのか、CEOとして必要とされる能力はは何か、等ほかの本では書かれていない項目が一杯記載されていた。現状を正しく把握する力、解雇時には1理由をはっきり、2明確な言葉で3退職金の準備を、社員教育はマネジャー自身で、その職に必要とされる能力を詳しく定義、CEOをパフォーマンス1目標に対する達成度2マネジメント3イノベーション4同僚との協調、事業売却には勇気が必要、苦闘を愛せ、新規事業のTIPSが満載だと感じた。道を切り開く参考にしたい。
0投稿日: 2017.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャーのCEOを経験した著者が、様々な困難を経験した実体験をもとに書いた教訓本。解雇や資金調達などCEO視点の話も多かったが、リーダーシップ論やコミュニケーションなど一般でも為になる話も盛り込まれており面白かった。偉大なCEOは一言で言うと総じて逃げ出さなかったというのがそのものなんだと思った。考えられないプレッシャーと戦いながらよい時も苦難も両方に対応できる人は希少な存在。ベンチャーを立ち上げる気はないが面白かった。
0投稿日: 2017.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ正解のない問題や困難に直面した時,あなたはどうしますか?一人でもがくことも必要ですが,先人の経験を参考にするのも一つの手でしょう。起業家として次々と襲いくる難問に立ち向かってきた著者の経験と知恵が詰まったこの1冊が,あなたの道を開くかもしれません。
0投稿日: 2017.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業してからどのような困難にぶつかり、どう判断、解決していったかを話した内容。起業の大変さがずしんと乗りかかったような感じで読み進めた。 同じことを経験したときに、自分が乗り越えられるのか、、 CEOは常にまわりに誠実でなければならない。 信頼されなくなると何事も進まない。 p286 CEOが心を静めるテクニック ・友達をつくる ・問題点を書き出す ・側壁ではなく、コースに意識を集中する レーシングカーの運転は壁に意識を向けるとそちらに車が行ってしまう。進むべきコースに集中する p294 ワン型CEOtツー型CEO ワン型 会社の向かうべき方針を決めるのを得意とする ツー型 決められた方針に沿って会社のパフォーマンスを最高にするのを得意とする ワンは勉強、読書、思索のために週に丸一日充てるが、ツーの人はその時間の使い方では「仕事をしているような気になれない」 リーダーに従いたくなる要因 ・ビジョンをいきいきと描写する能力 スティーブジョブス ・正しい野心を持つ ビルキャンベル 「この人は自分のことより部下のことを優先して考えている」と感じさせる雰囲気をつくる ・ビジョンを実現する アンディ・グローブ 「インテル経営の秘密」著者 平時のCEOと戦時のCEOでやることが違う 戦時のCEO ジョブズとグローブ 平時のCEOは会社が現在持っている優位性をもっとも効果的に利用し、さらに拡大することが任務 経営書はアンディグローブのもの以外はすべて平時のCEO向けの内容になっている p250 独自の企業文化を構築する 従業員の満足度や会社の使命も重要だが、ここでいう企業文化は別の話。 職場でヨガができたりするのは企業文化ではない 企業文化があると、会社に望むことを実現する長期的な助けとなる
0投稿日: 2017.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社にあった本。時間かけすぎてまとまった印象がないが、成功する人は皆悩んで、苦しんでるんだなと。苦闘を愛せ。最後のこと一言が最高。
0投稿日: 2017.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・「私は数多くの取引の過程である方法を確立した。物事を進める方法、いや哲学といってもいい。その哲学の中で、私には確固たる信念がいくつかある。私は『恣意的に設定するデッドライン』の効果を信じている。私は競り合わせ効果を信じているのだ。契約のためなら、法や人の道に外れない限り、どんなことでもすべきだと私は信じている」 ・私はビル・キャンベルにEDSとの合意という良いニュースを伝えた。契約の署名が済み、月曜日にニューヨークで発表する予定だs。ところがビルは、「残念ながら、きみはニューヨークの発表会には参加できない。マークに行ってもらう」と言った。 「どういう意味です?」と私は尋ねた。 「きみは会社に残り、全員の立場を理解していることを確かめなきゃいけない。一日も待てない。いや、むしろ1分だって待てない。従業員たちは、自分がきみのために働くのか、EDSに行くのか、いまいましい職探しをするのかを知る必要がある」とビルは答えた。ビルは正しかった。 ・エンジニアたちは不安だった。彼らは、製品を市場に出す前にしておくべき作業の長いリストを私のところに持ってきた。そして、より洗練された競合製品の名前を挙げた。延々と続くエンジニアたちの反論を聞いていると、彼らが加えたがっている昨日はいずれもEDSの要求だと気付いた。たとえつらくても、正しい製品をつくる知識を得るには、もっと広い市場に出る必要があった。逆説的ではあるが、その唯一の方法は、間違った製品でもいいからまず売ってみることだった。無残に失敗する危険はあるが、生き残りに必要なことをいち早く学べるはずだ。 ・私の経歴の中で早くに学んだ教訓は、大企業でプロジェクト全体が遅れる原因は、必ずひとりの人間に帰着するということだった。エンジニアが決断を待って立往生しているかもしれないし、マネジャーが重要な購買の権限が自分にはないと思っているかもしれない。そういう小さな、一見些細なためらいが、致命的な遅れの原因になりかねない。 ・手始めに、ジョンと私はマイケル・オーヴィッツに電話でアドバイスを求めた。買い手候補のひとつ、オラクルが高値をつける可能性は低いとわれわれは考えていた。なぜなら、財務分析が恐ろしく厳重な会社だったからだs。そのことをマイケルに伝え、オラクルと交渉すべきかどうか尋ねた。彼の返答には千金の価値があった。「いいかきみたち、ドッグレースをやるつもりなら、前を走るウサギが必要だろう。オラクルは、この上なくすごいウサギだ」 ・スタートアップのCEOは確率を考えてはいけない。会社の運営では、答えがあると信じなきゃいけない。答えが見つかる確率を考えてはいけない。とにかく見つけるしかない。可能性が10に9つであろうと1000にひとつであろうと、する仕事は変わらない。 最終的に私は答えを見つけた。われわれはEDSへの事業の譲渡契約を成功させて、会社は倒産せずに済んだ。それでも、私はビルがあのとき倒産する確率が高いという真実を教えてくれたことを心から感謝している。それでも私は統計を信じない。 ・良い手がないときに最善の手を打つ。偉大になりたいのならこれこそが挑戦だ。偉大になりたくないのなら、あなたは会社を立ち上げるべきでなかった。 ・「ありのままに伝えることが重要」。すばらしいテクノロジー企業を築くには、驚くほど賢い人々を大勢集めなくてはならない。たくさんの大きな脳を最大の問題に使わないのは、大いなる無駄遣いだ。脳は、たとえどんなに大きい脳でも、知らない問題は解決できない。オープンソースコミュニティがこう言っている。「十分な数の目玉があれば、どんなバグも洗い出される」 ・CEOがレイオフするのは会社が計画を達成できなかったからだ。個人の業績が問題なら別の手段をとるはずだ。失敗したのは会社の業績だ。この区別は決定的に重要である。なぜなら、会社やレイオフされる個人に対するメッセージは、「よし、これで業績問題が片付く」であってはならないからだ。メッセージは、「会社が失敗したので、前へ進むために、優秀な人たちを手放さなくてはならない」というものであるべきだ。 ・物事がうまく運んでいる間は、良い会社かどうかはあまり重要ではないが、何かがおかしくなったときには、生死を分ける違いになることがある。 物事は必ずおかしくなる。 良い会社でいることは、それ自体が目的である。 ・マネジャーが社員の生産性を改善する方法はふたつしかない。動機づけと教育だ。よって、教育は組織のマネジャー全員にとって、もっとも基本的な要件である。この要件を強制する効果的な方法のひとつは、採用予定者向け教育プログラムを開発するまで、その部署の新規雇用を保留することだ。 ・役員報酬を考えてみよう。CEOのところには上級社員が給与の改善を要求しに面会に来る。彼らは「現在の公正な市場価格に比べて自分の給与は低すぎる」というようなことを言う。「自分はライバル企業から高級でスカウトされている」と言う社員もいる。この種の駆け引きに直面した場合、その社員の主張に合理性があると、経営者はこの問題を真剣に取り上げることになりがちだ。中には社員の主張を認めて昇給を実施する経営者もいるだろう。一見、問題なさそうな行動だが、経営者はこうすることで政治的行動への強力なインセンティブを作り出しているのだ。つまり経営者は、会社のビジネスへの貢献以外の社員の行動に、報酬を与えたことになる。 ・組織デザインで覚えておくべきルールは、すべての組織デザインは悪いということだ。あらゆる組織デザインは、会社のある部分のコミュニケーションを犠牲にすることによって、他部分のコミュニケーションを改善する。 ・私は成功したCEOに出会うたびに「どうやって成功したのか?」と尋ねてきた。凡庸なCEOは、優れた戦略的着眼点やビジネスセンスなど、自己満足的な理由を挙げた。しかし偉大なCEOたちの答えは驚くほど似通っていた。彼らは異口同音に「私は投げ出さなかった」と答えた。
1投稿日: 2017.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年のビジネス書大賞受賞作。 前年にピーター・ティール氏の『ZERO TO ONE』が大賞を受賞していて、 その翌年にこれが大賞になるというのは、なんだか不思議なかんじがします。 というのも、ZERO TO ONEの主要な主張の一つは 「競争があるところでビジネスをやるのは悲惨だよ」 ということで、この本はまさに、競争があるところでビジネスをやろうとした著者の悲惨な経験を語ったものです。 あるいは、CEOとして名選手ではなかった著者が、いかにしてベンチャーキャピタルという形で名コーチになったかを描いた一冊だといってもいい。 起業することに何かキラキラした憧れを持っている人が読むには、いい本かもしれません。 (私自身は親が自営業だったこともあり、この本に書いてあることは「スタートアップのCEOの生々しい経験談」なんていう聞こえのいいものというより、ただの「自営業あるある」といった方がしっくりくる気がしました。) 会社員が読む本というよりは起業を目指す人にとっての方が参考になる本、といえばその通りかもしれません。 ただ、会社員である私も読んだからには、この本から何かしら学んで明日からの仕事に活かしたい。 そういう観点で、気づきをもらった箇所は以下です。 「職場でヨガができたりするのは企業文化ではない」(pp.256-257) →企業文化と福利厚生をちゃんと分けろという話。 企業文化は会社がほしい能力を持った人を確実につなぎとめ、 そうじゃない人が勝手に去っていく仕組みみたいなもの。 やたらオシャレなオフィスとか、職場でヨガができるみたいなことは、 そういう意味での「企業文化」と呼ぶに値しない、 ただの「福利厚生」だという話でした。ナットク! 「組織デザインで第一に覚えておくべきルールは、すべての組織デザインは悪いということだ。」(p.262) →うちの会社の組織構造おかしいよね、って話は、 社員同士の飲み会の話題としてなかなか盛り上がりますが、 えてして愚痴大会に終わって建設的な議論にならない。 (愚痴大会をやってる本人がどう思っているかは別にして。) 組織デザインに「いいデザイン」があるなんていう幻想を捨てれば、 そういう不毛な愚痴大会とサヨナラできるかもと思いました。
0投稿日: 2017.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯の言葉にはあまり踊らされないつもりであるが、読んでおくべき最強投資家からのアドバイスだそうだ。へぇと思いながらページをめくる。前半は自叙伝。しかしそれはメインではない。メインはその後。自分がぶちあたったトラブルや究極の意思決定を下さなければならなかった事象に関しての考察の数々がある。この考察事例がCEOの教科書といわれる所以だろう。さて話は変わり、この本を読んでいて、CEOという役職は、アメリカ大統領制を企業に置き換えたものという理解が一番しっくりすると思い至ったのである。
0投稿日: 2017.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ機内でようやく読了.Hard things about hard things の訳書.翻訳よかった.
0投稿日: 2017.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の後半で述べられるように、ピンチの経営について書かた著作です。テクノロジー系のスタートアップ企業でのストーリーと訓示で構成されているため、買収や売却に関するテーマも多いようです。また、解雇に関する事項についても多くの紙面が割かれています。 私にとって、これらの教訓をそのまま適用できる場面はそう多くはないと思いますが、精神的な部分での示唆は有用だと思いました。 創業から何十年も経過し、いわゆる平時にあって継続発展を目指す日本企業でCEOの職にない者が本書をどう読むか。単に視座を高めたり視点を変えたりするだけではもったいないようですが、共感しながら読み進めることは難しかったです。 おかれた状況次第でマネジャーの役割が異なるように、必要となる資質も違うということです。それでは、平時と戦時、どちらかに対応した一本足でよいのか? それは当人のキャリアプランによって変わって来るのだと思います。しかし個人のキャリアのために働くマネジャーは不要だと本書は説きます。 「なんのために働くのか?」 はじめにこの問があって、これに対する回答が本書の入口になります。
0投稿日: 2017.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社を上場した途端、バブルが崩壊して次から次へと荒波を被るCEOの話。いろんな手を尽くして嵐を乗り越えるところがスリリングで面白い。文章に客観性があって、自分に対してシニカルな目線があるので、胃が千切れそうなほど大変な目にあっているのに、なんだかユーモラスでどんどん読み進められた。
0投稿日: 2017.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営ノウハウ本です。ただし、運営危機に陥ったときの話がメイン。9章の構成で、1~3章が著者の即死イベントまみれの体験記、4~8章が体験から得たノウハウの説明、9章がVCを作るに至った思想となっています。マニュアルには成り得ませんが、答えのない難問を解くヒントが詰まった一冊です。 銀の弾丸を探すより鉛の弾丸を撃ち続けるというのはいいと思った 人間の扱いが怖い。絶対やりたくない。 幹部社員は頭がいいので、適当なことをいうと言質取られたり拡大解釈されたりするのは怖い。
0投稿日: 2017.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社のCEOとはどういうものなのかを詳細に教えてくれる本。 精神的な強靱さを持たなければ務まらない役職だ。 タイトルのHard Thingsは、困難なことという意味以上の意味がありそうだ。
0投稿日: 2017.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップでの失敗事例とそこから学んだこと、みたいな感じがする。 ここから何かを学び取ろうとするには自分はまだ経験値が足りない。
0投稿日: 2016.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
単に企業の成功物語/CEOの自慢話、というでわけでなく、企業家/CEOにむけた真の指南書と思えた本。(いや、おれ企業家じゃないけど。)きっとすべての企業家は読むべきだと思ったけど、逆に自分はやっぱり企業家にはなれないのかなーとも思わされた本。(こんな大変な状況は乗り切れん気も。)とはいえ、普通のビジネスマンだとしても読んだらなにかしら発見はあるのではないかと。 訳者のあとがきにあるように、まさしく「フェイスブック若き天才の野望」と双璧をなす本といっていい気がします。 また、序文で小澤氏が書いているとおり「たいていの本は成功した話をあとから分析して紹介するものが多い、一方本書が素晴らしいのは、次々と深刻な困難に直面した著者が、うまくいかないときにどう考えたか/切り抜けたかを紹介しているところ」というのもその通りと感じた。 p33 きみは事態の深刻さがわかっていない。この次は自分でインタビューを受けてみろ。くそったれが。 p102 あらゆる人間のやり取りにおいて、必要なコミュニケーションの量は、信頼のレベルに反比例する。あなたを全面的に信頼していればあなたの行動について何の説明もコミュニケーションも必要ない。まったく信頼していなければ、いかなる会話・説明・推論もなんの影響も及ぼさない。なぜならあなたが真実をいっていると思っていないからだ。 p158 経済的な事情を別として人が会社を辞める理由は2つ①マネージャーが嫌い②何も教えられていない p224 なぜ肩書は重要なのか①社員が望む。次の面接に臨んだとき、「セールスのヤツ」だったとは言いたくないだろう。②やがて社員同士でも誰が誰なのか知る必要が起きてくる p226 ピーターの法則。有能なメンバーは次第に昇進していく、しかし、遅かれ早かれ、メンバーは自分の能力の及ばないちいに達してしまう。無能レベルに達する p233 性格が本質的に反乱者。⇒常に反乱をおこしていあにと満足感が得られない⇒社員よりCEOのほうが能力を発揮する p259 組織の小さいうちは問題ないが、大きくなると困難になる①組織内コミュニケーション②共通認識③意思決定 p262 組織デザインで第一に覚えておくべきルールは、すべての組織のデザインは悪いということだ。 p279 最初の問題は、CEOになるためのトレーニングが存在しないこと。CEOのトレーニングは実際にCEOになる以外ない。マネージャーディレクターその他なんであれ管理職の経験は会社運営という職務に役に立たない。役立つ唯一の経験は会社を経営すること。 p285 WFIO俺たちはやられた。この会社はおしまいだ。We're Fucked, It's Over p302 真に偉大なリーダーは、周囲に「この人は自分のことよりも部下のことを優先して考えている」と感じさせる雰囲気を作り出すものだ。 P339 私は今の今でも、アーンスト&ヤングを憎み嫌っている p373 採用は強さを伸ばすために行うべきで、弱さを補うために行うべきではない
4投稿日: 2016.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
会社員も辛いけど、起業家も辛い。っていうか、困難、困難、また困難。正面切って艱難辛苦を超えて、ギリギリで、いろんなことを押し込み、走りきった記録!しかも、困難はほぼ全て外部要因。万策尽きても、どうにかしなきゃいけないし、責任もとんないといけない。 ちょうど、大学時代にモザイクで初めてブラウザに触り、テンション上がりまくっていて、その後もシステム畑をコツコツ歩いてきた身としては、自分が使った・購入した・導入したサービスの裏側にこんなことがあったとは、興味深くて一気に読み進めてしまった。 文章もリズムがあっておもしろい。翻訳がいいのかな。
0投稿日: 2016.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国、特にアメリカの実務での経営当事者の著した書籍は、読みにくいと感じるものが多い。 翻訳の質の問題もあるのかもしれないが、この書もそのうちのひとつ。 ビジネス書大賞2016、ベスト経営書2015(HBR)の2冠とのことだがそこまで感じたものはなかった。 ただ後半は抽象的ではあるものの、ある程度引き込まれながら読んでいたので、単位自分が実際にはあまり知らない世界だから面白くなかったと言えるのかもしれない。
0投稿日: 2016.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者のあるべき姿を描いていますが、著者の背景を知っていればもっと楽しめたのかな。 知識の薄い自分には、あんまり響いてこなかったですね。
0投稿日: 2016.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログあれ、レビュー書いてなかった。。 これ読む度に、血が沸き立つ感覚を覚える。やっぱり根はスタートアップマインドなんだろうなあ
0投稿日: 2016.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログたしかに「異色の経営書」だ。「人を正しく解雇する方法」、「大企業の幹部が小さな会社で活躍できない理由」、「優秀な人材が最悪の社員になる場合」なんて、普通の経営書には書かれていない。それが読んでいてドキドキする実体験に基づく内容だけにおもしろく、説得力がある。 日米間の企業文化の差異を感じる箇所もあるが、未来の日本企業の姿だと思えなくもない。 自身、起業する予定も能力もない一方で、少なからず人の上に立ち組織で成果を出すことが求めらてれいる。 良い本に出会えた。
0投稿日: 2016.09.04経営者は何を気にし、何に悩むのか。
日本とアメリカの企業のあり方の違いはあると思いますが、経営者が思考する流れは大きく変わらないのではないかと思います。 書籍自体は、筆者のこれまでの経験を時系列で、ストーリー仕立てで見る部分と、そこから得られた教訓や、気づき、著者の考えがカテゴリーごとにまとまっている部分の二つに分かれます。 個人的には、気付きわ考えよりも、実際の流れを読むことで、追体験し、悩みを想像するものとして、すごく良い本だと思います。 ここまで、赤裸々に描かれている本は珍しいのではないかと思います。 そこから得られた気付きの部分は、ちょっとわからない部分もありましたが、経営者の思考の順番や、大切にしているものを見るにはすごくいい本だと思います。 特に、ベンチャーの経営層に近い方には、強くオススメします。
1投稿日: 2016.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ20160810 倒産しそうな会社をどのように立て直したか。時間がなく途中で図書館に返却してしまった。
0投稿日: 2016.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOの心得 主に、失敗事例を中心に学んだこと CEOを目指す人や既に渦中の人物が読むべき本。大変なんだなぁ、CEO、と思った。
0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログIT業界という非常にスピードの早い業界、アメリカ文化における企業の厳しさが生々しく知ることができる。モザイク、ネットスケープといった自分が初めてパソコンを使いだしたころには死語となっていた単語が、そちら側から語られかけていくのは非常に新鮮だった。それはITの歴史的瞬間だったのだろう この本から学べる点は様々だが、前半は物語(想像以上に面白い)、後半は経営エッセンスが語られていく。エッセンスは物語とリンクできれば面白いのだろうが、途中で少し期間が空いたからか、非常に力不足を感じた。一気に読むのがお勧め。だが、時々気になるエッセンスを読むときに、あの時のパワーがいまいち感じられない…と思うかも れない 内容としては、人、モノ、利益の順番で大切にするという点。人の採用にて、青写真と比較して欠点を洗い出すことの無意味さとリスクなどは非常に面白い (ここで利益を最後にしてるのはアメリカの場合数か月で利益を出すとか、そういうサイクルだからだろう。その数か月のために来年には会社が倒産する可能性だってある)
0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業における「旅先で起きるトラブルガイドブック」のような本。特に、採用などを始める際にまた読んでみたい。 ============================================ ・良い手がないときに集中して最善の手を打つ能力。これがCEOの才能。 ・社員がCEOを信頼していれば、基本的なコミュニケーションの能率は圧倒的に良くなる。 ・問題を持ってくるなら、答えも一緒に持って来い。 ・レイオフは絶対にNG。会社の文化を一気に崩壊させる。 ・会社が不調なときほど、CEOは会社にいるべきだ。 ・大事にすべき順は、「人→製品→利益」 ・社員に対しては、「何」をすべきかと「何故」それをすべきかを明確に伝えておくこと。 ・社員の教育は絶対にすべきだ。ここを軽視している企業は多い。 ・引き抜きはタブー。 ・何が欲しいかを知らなければ、それを得る確率は極めて小さくなる。 ・人を採用する際は、短所の少なさではなく圧倒的な調書を重視せよ。 ・同じ役職に2人以上を当ててはならない。 ・正しい野心家を採用せよ。正しい野心家とは、自分の成長よりも会社の成長を優先的に考えてくれる人のことだ。 ・給与査定には、第三者が見て納得のしうる明確な基準を設けよ。 ・社員に対して高い肩書を与えることは、低コストで社員のモチベーションを上げる良い方法だ。ただし、肩書のインフレ化も起こりやすくなるため注意が必要。また、フラットな組織を作るために、あえて全員に低い肩書を統一して与えるFacebookのような企業もある。 ・個人面談はオススメ。多くの企業でその成果が立証されている。 ・Amazonのオフィスでは、ドアの板を改造して作られたデスクがある。これは「最低のコストで最大のサービスを届ける」というAmazonの理念を表している。このように、理念を示すようなアイテムがオフィス内にあるのは良い。 ・「ゴール」を定義することは最重要。半年ごとの「ゴール」を会社として持っておくこと。 ・社員への評価は、将来性を見越した評価ではなく、今現在のパフォーマンスだけで評価せよ。 ・VCは、オールインする起業家を好む。
0投稿日: 2016.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ長期休暇からの社会復帰がてら、今一度読了。CEOという立場ではないですが、本書で言う企業の中での「戦時」も「平時」も体験してきた身としては、色々とフラッシュバックするものがあります。起業家に限らず、経営者の直面する困難やどういう生き物かを突き詰められるという意味でも、あらゆるビジネスパーソンに読んで欲しいなぁと思います。
0投稿日: 2016.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕は起業家でもなんでもないヒラ社員であるが、それでも自分の会社経験と想像力をフルに働かせて読み続け、共感に次ぐ共感から冷や汗握り締めながらエキサイティングに読破。 おそらく生ぬるい嘘なんてない、筆者の経験から学んだ経営の本質が明解な理由と共に綴られている。 会社が存続する以上、CEOは感情を捨て吐き気や悪寒と共にドライに判断や意思決定をし、問題解決のため的確に行動し続けるという連続が永遠に続く中で、逆に大切なものとは結局、感情をもつ人間なのだという感も感じた。 文章には急に音楽カルチャーなどのキーワードもでてきて、CEOや起業家たる人も我々と同じレイヤーの世界にいる人間なんだと妙に安心もするし、なかなかどおして読みやすい文体で面白かった。
2投稿日: 2016.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ[関連リンク] 祝、ビジネス書大賞「ハード・シングス」は起業家以外にもエールを送る必読の本 | Lifehacking.jp: http://lifehacking.jp/2016/07/hard-things/
0投稿日: 2016.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOを置き換えれば汎用 1.そのCEOは自分が何をすべきか明確に意識しているか? 2.そのCEOはなすべきことを会社に実行させる能力があるか? 3.そのCEOは適切に設定された目標を達成できたか?
0投稿日: 2016.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業、その後の業績低迷や株価低迷、家族の健康問題をも乗り越え、イグジットまでこぎつけた筆者の逆境にも屈しないリーダーシップを学べる1冊。
0投稿日: 2016.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ20160625 立場と苦労のレベルが違うので読んでいて追いつけない事が多かった。今後もこのような立場にはならないと思うが万一の場合は、最後まで最善を考えて行動する事という教訓は覚えて置こうと思う。
0投稿日: 2016.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログCEOの視点で書かれているが、一般社員にも得るところが多い。生々しい経験がもとになっており、説得力がある。
0投稿日: 2016.06.22
