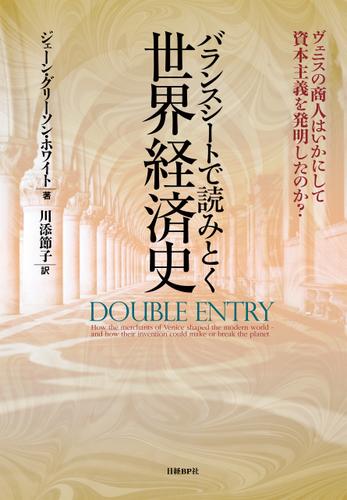
総合評価
(15件)| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ簿記が産業革命期にどのように会計に進化したかや、マル経やケインズ経済学における簿記の影響を教わり、興味深い内容でした。経理経験があるので何とか読み通せた。
0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半の複式簿記の発祥と歴史に関するところは面白く読ませてもらったが、後半のGDPや会計不祥事、グリーン経済のくだりはいかにもちょっと調べて書きましたといった感じで牽強付会にも見えてしまい蛇足気味。しかし原著刊行が2011年で、アカウンタントがグリーン経済への転換において中心的な役割を果たすことができると言っているのは、2023年現在の状況と照らし合わせると時代の流れを正しく読んでいた。 いまやすっかり電子化された複式簿記だが、もともと紙の帳簿に手で記帳する技術として開発されたことに改めて思いを馳せた。また、アカウンティングとはすなわちアカウンタビリティとも。もともとは神様というか教会・世間向けの利益追求の言い訳(?)的な説明だったとは。
0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログバランスシートでも世界経済誌でもなく、ルカ・パチョーリによる複式簿記の紹介から始まる、会計史の本。 いかにも洋書っぽいスタイル(偉人の言葉とかの人文教養で殴っていくあの形)で、複式簿記がどれだけ頑強な方式なのかを説明している。なので、多分財務会計の知識がそんなになくても、読むだけで面白い。 最後の1章は急に環境保護の話になって面食らうけど、「環境に対する負荷を財務諸表に計上する方法が無いからフリーライドになっているので、それを開発する必要がある」という話は、この手の話題で初めて納得が行くものだった。
0投稿日: 2020.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほど会計というのは思想的におもしろいのだな。フランクリンやベンサムの発想も、17〜8世紀の会計の進歩なしには存在しなかった。
0投稿日: 2020.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログややタイトル詐欺、バランシートそのものはあまり出てこないし歴史と言われるとちょっと。 会計から考える資本主義のこれからといった内容。 構成としては簿記(会計)が発生した発端ともいえる人物の活動に焦点を当てる前半と、会計では解決しない現代経済の問題提起の二つに大きく分かれていて、 前半部分は会計制度の根本部分は大昔から変わらずに今でも使用できている凄いモノだって話の補強でしかないのだけれど、後半部分は会計史が書かれたモノの中でより経済(学)について軸足が置かれてるのがこの本の特徴だと思う。 経済指標などと言ったものは会計の知識が強く影響して生まれ利用されるようになったと思われる としながらも、経済指標は経済を正確に表していないので問題があるって話なのだが、現代の会計は会計が生まれた時とは違った形になっていることには触れられず、現代も昔も変わらず会計不祥事は続いてるとだけしか記述が無かったりと、なぜ?に応えるでもなく、流れを解説してるでもないので、そのあたりは他の書籍を参考にする必要があるのがちょっともったいないなと感じた。
0投稿日: 2019.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ複式簿記が中世のイタリアから広まったということは経済学の授業で習ったが、その詳細については聞かなかったので副題の「ヴェニスの商人はいかにして資本主義を発明したのか?」に期待して選びました。 請求記号:336.91/G49
0投稿日: 2019.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史が好きなので面白く読めた。 特に興味深いのが、最初期の帳簿には十字架が記されていたということ。これはクリスチャンである彼らからすると神に誓って不正はしないということである。つまり会計をするものにとって重要な要素は誠実であることだったのだ。 僕も会計を生業とするものの1人として大事にしたい。
0投稿日: 2018.02.18簿記についてはさっぱりわかりませんので
理解できたとは言えません。 内容より文章自体がわかりにくい気もしますが、いずれにしても二、三度読んだぐらいでは私にはわからなさそうなので、何冊か他にも読んでみて出直そうと思います。 どうも難しすぎるようなので読むのをやめようかなと思いつつ、この本の事についてぼんやり考えていた時に、自分には今までに無かった物事の見方が一つ増えたんだなと、ふと思いました。 会計やら簿記やらが専門と言うと、冷静で人間味を出さないというような勝手な印象がありましたが、この本は主観が混じっているタイプの本で、時々興奮しているのかなと思う程感情も見えかくれするようなところが度々ありました。 初めは歴史を追っているようでしたが、全体的に考えると話題が多岐に渡っていたこと、また、パチョーリという人のことについて結構ページを割いていました。 最後は、気持ちはわかるけど一体どこへ行くのかなと思いながら読んでいました。 自分の全く知らない世界について本を読むことが最近楽しいです。
1投稿日: 2016.01.26簿記の歴史を知ることができる本。
数字の発明に始まり複式簿記の誕生、現在までに至る会計、経済学の発展を書いた力作である。 非常に興味深く読めたが、全く簿記の知識のない人には理解不能かもしれない。 値段は少し高かったがそれだけの価値はあるように思う。ただこの本を読んだからと言って簿記の勉強にはならないだろう、その歴史をたどることはできるけれど。
1投稿日: 2015.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
世界史の大まかな流れを理解していないと内容が頭に入ってこないな。 産業革命以降の会計士の話、環境評価の話などは興味深い。
0投稿日: 2015.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名が違う。会計の歴史。が正しい。 インドやアラビアに起源を持つ会計(複式簿記)、数学がベネチアで再発見されてヨーロッパに広まり、それが株式市場や製造業の発展共に精緻化された。 一方エンロンやワールドコムにある不正会計のいたちごっこはつづく。 GDPはケインズなどが戦時の国家統制のために作ったものがその後も使われ続けている。 最後に自然環境はオンバランスされず、使用された時のみGDPに計上される。つまり減耗すればするほどGDPは上がるが、長期的な生産能力は下がっていると思われるため、自然環境、教育、家庭内労働の再生産コストを考慮した指標が求められる。
0投稿日: 2015.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史を扱っている部分は面白い。終盤の会計スキャンダルや世界をよくするために会計にできることは何かを問う、みたいな部分は退屈だった。 ルカパチョーリとダビンチのつながり、複式簿記とウェッジウッドとダーウィンのつながり
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は会計技術を用いれば地球環境を救うことができると述べる。 会計学は言わば認識の学問ともいえよう。現状を的確に認識し、問題点改善点を洗い出す。その上で人々が問題解決の実効に移す必要があるわけだが、その実効のためには法学、哲学、政治学、経済学の知見が必要となる点で会計技術のみで地球環境を救うことはできないだろう。 とはいえ、現状認識なくして解決はないわけであるから、上記主張も大げさではない。 会計技術の起源から現代までの歴史を語ってもいるので、なぜ会計学が必要なのか知りたい人にとっても有益な書籍である。
0投稿日: 2014.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ複式簿記の発明から国民経済計算に至る会計の歴史を、数学の発展ともからめて非常に詳しく、でもわかりやすく述べてくれており、実に勉強になりました。 今日本では、官庁の非効率性は会計制度に複式簿記を導入していないことも大きいという議論から、公会計にも財務諸表を取り入れようという動きが活発ですが、この本の最終章には、世の中の価値というものは必ずしも会計数値で十全に表現できるものではないこと、会計とともに会計以外の価値の計測方法をいろいろ工夫しなければならないことが書かれており、非常に示唆に富みます。 公務員として、実に有意義な本でした。
0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11963501087.html
0投稿日: 2014.12.12
