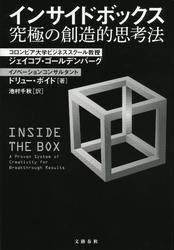
総合評価
(30件)| 4 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
インサイドボックスとは、制約の中で考え抜くことで、飛躍的に解決策がみつかる秘密の方法のこと。 各章のあとのまとめページがわかりやすくて親切。 メモ ・5つのテクニック 引き算 何かの要素を取り除く イヤホン、ipodタッチ 分割 構成要素の一部を分離 リモコン、プリンター 掛け算 一部の要素をコピー増量&変更 一石二鳥 一要素に複数機能 関数 無関係な要素を連動させ革新的なサービスを ・二つの原則 閉じた世界の原則 身近な資源に目を向ける 問題解決プロセスの固定観念を置き換える 機能は形式に従う原則 ・アウトサイドボックスなブレストは無秩序を生み、革新的な発想を妨げる。閉じた世界の方が創造的になれる! ・分割のテクニック 機能的分割、物理的分割、機能を維持した分割の3つがある。その後空間的組み替えや時間的組み替えにより新しい可能性を模索する。 ・掛け算のテクニック 要素を洗い出す、ある要素の数を増やす。コピーに全てオリジナルと異なる特徴を持たせる。ただのコピーにしないことが重要 ・一石二鳥のテクニック アウトソーシング、既存の内部資源の活用、内部要素に外部要素の役割を担わせるなど。 ・関数のテクニック 互いに関係のない2つの変数を選び出す 一方の変化に合わせて他方の性質が変わるようにする。新たな価値がうまれる。 ・矛盾を構成する三要素 利益や恩恵の要求 利益や恩恵を得るためのコスト その二つを結びつける連結要素
0投稿日: 2020.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ発想法が言語化されている! 引き算、分割、掛け算、一石二鳥、関数 実際には、このキーワードを思い浮かべながらジリジリ考えるのを続ける感じかな for創造的思考
0投稿日: 2019.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ天才や才気あふれる人による「発想」でイノベーションや独創的な発明は成し遂げられると一般的に捉えられている常識を「インサイドボックス」(=箱の中)つまりは制約の中に入れる事によって誰でもイノベーションが可能になるという主張や方法をさまざまな事例とともに紹介していく。読んでみて思ったのは確かに著者の言う通り、今までに起きた革命的な商品やサービスを著者のいう分類に分けることは可能かも知れない、だがそれが世の中にない状態から(つまり0から)発見することは幾ら発想法を知っていたとしても(幾分助けになるのかも知れないが)答えを見つけることはやはり容易ではない。もちろん著者もその事は認めているし最後の章で結局は数を作らないととサラッと事実を書いてあることは根も葉もない真実なんであろう。ただ世の中のそのほとんどの人が(何より自分自身に)自分には「センス」や「才能」がないからということを逃げ口上にしていたことはもう欺瞞であると証明されたようなものなのだ。ただ好きだから仕事が続けられるし、好きになるのはやってて面白いから、上手く出来るからということもある。自分の場合これがほとんどの理由だ。上手くやれるということは得意だったり向いているということだ。だとするとやはり得意な人が優位に仕事をすすめることが出来る=没頭してやる(量をこなす)→イノベーションを起こす可能性が高くなる→他の人はあきらめて辞めていく。という構図が出来上がる気がする。一部の才気ある人たちによるという言い方は普通の人たちの自己防衛の言葉なのかも知らないと思った。「俺がダメなんじゃない、あいつらがすごいんだ」という。ただ長年やってたらやってるだけのいびつではあるが、面白いモノが出来るという事はあると思う。オレはそれに掛けてみようと思う。そういう生き方もある。バルミューダの社長曰く自分を曲げずにやってダメなら時代のせいにすればいい。と。オレも時代のせいにしよう。(笑)
0投稿日: 2019.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログアイデア創出のテクニックを与えてくれる本。単にブレストするのではなく、その切り口を色々な方向から実例と合わせて示してくれる。背面跳びの発明、界面活性剤抜きの洗剤、キャプチャ認証が文字の読み取りに貢献していることなど、びっくりするような話もあって、興味深かった。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ・人が創造的にものを考えるプロセスの2つのパターン――?問題から出発して、それをどうやって解決すればいいかを探る方法?解決策から出発して、それによってどういいう問題を解決できるかを考える方法――人は?の方法が得意 ・インサイドボックス思考法――?引き算?分割?掛け算?一石二鳥?関数 ・創造性の本質は、限られた可能性のなかから知恵を使って解決策を見つけ出すことにある。「内側に目を向けよ!」 ・引き算のテクニック――?製品やサービスの内部の構成要素を洗い出す?不可欠な要素を一つ選び、それを取り除くとどうなるかを想像してみる。全面的削除(その要素を丸ごと取り除く)or部分的削除(その要素の一機能もしくは一側面だけを取り除く) ・分割――?機能的分割(リモコンの例)?物理的分割(潜水艦内のスペースを分割による安全性の実現)?機能を維持した分割(ハードディスクを小分けして生まれたUSBメモリ)→→空間的汲み前or時間的組み替え→→新しい視点を獲得、製品の使い方に新しい可能性が開ける ・掛け算――?要素を洗い出す?ある要素を増やす?そのコピーにすべて、オリジナルと異なる性質を持たせる(ジレット2枚刃の例) ・一石二鳥――?製品やサービス、プロセスの内部の構成要素を洗い出す?一つの構成要素を選び、(?)アウトソーシングの活用(?)既存の内部資源の活用(?)内部の要素に外部の要素の役割を担わせる、という三つの方法を検討する ・ソフトウェア企業では、製品がうまく作動しないとき、こう言う――「これはミスじゃない。そういう機能なんだ」 ・関数――?互いに関係のない2つの変数を選び出す?一方の変化に合わせて、他方の性質が変わるようにする?新たな価値が生まれる ・妥協をせず、ニセモノの矛盾を見抜きそれを打ち砕くことで、真に創造的な解決策を導き出す
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスの現場に限らずある問題が生じたとき,問題のまわりには様々な制約がセットでついてくる. そんな制約を問題解決を妨げるマイナス要因としてとらえるのではなくて,発想をガラッと変えて,制約ごと解決する(そのことを本書ではイノベーションと位置づけけいる)問題解決手法を紹介しています.
0投稿日: 2018.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ枠の中で考えればイノベーションが素早く生まれる。 ■5つの雛型 ・引き算:機能をなくし、何かで代替 →DVDプレイヤーの液晶 ・分割:機能やプロセスを分割、並べ替え →シャンプーとトリートメント、USBメモリ ・掛け算:機能をコピーして複製 →両面テープ、髭剃りの刃 ・一石二鳥: 外部要素に内部要素を担わせる →スマホアプリ 内部要素に既存要素か新規要素を担わせる →スウィーニー・トッドでの俳優の楽器演奏 内部要素に外部要素を担わせる →ロボット排斥の文字読み取り入力による書籍デジタル化 ・関数:二つの変数を選び出して連携させる →ミルクの温度で色が変わる哺乳瓶、30分デリバリーできなければ無料のドミノ・ピザ
0投稿日: 2018.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでの常識では、独創的なアイディアは発想を広げて枠の外(アウトサイドボックス)からアプローチする必要があると信じられてきた。固定概念を捨てて頭を柔らかくして発想すべきだと強調されてきたのである。しかし、本書では枠の内(インサイドボックス)、すなわち既存の範囲で、ある方程式と手順に従って創造的な発想が可能であると教えている。むしろ、制約条件下で考える方が、現実的な解決策が見出されるのだと主張する。 著者は、コロンビア大学のビジネススクールのコールデンバーグ教授(ウォールストリートジャーナル紙で「世界を変える10人」に選出された)とP&G等のメーカーでイノベーションを指導するコンサルタントであるドリュー・ボイド氏である。研究者と実践家のタッグは、400以上のイノベーションの事例を研究して、事実は従来の定説とは逆であることを突き止めた。「インサイドボックスこそが創造性を生む」こと発見したのである。そして、それらの事例の分析の結果として、次の5つのテクニックを紹介している。 1.引き算のテクニック : 製品やサービスに欠かせないとみなされている要素を取り除いてみる 2.分割のテクニック : 既存の構成要素を分割し、一部を分離してみる 3.掛け算のテクニック : 製品やサービスの一部をコピーして増量し、そこにこれまでと思われていたような変更を加える 4.一石二鳥のテクニック : 製品やサービスの一部の要素を複数の機能をもたせてみる 5.関数のテクニック : それまで無関係と思われていた要素を連動させてみる 全編に豊富な事例が紹介されている。iPhone、IKEA、ツィッター、麻酔装置、ファブリース、水準器、等々。これらの製品の開発プロセスが5つのテクニックを用いて説明されるので説得力がある。また、ボイド氏が講師を務めた企業でのワークショップの様子が何度も出てくる。どの企業でも参加者は、はじめのうちは疑心暗鬼、あるいは反発さえ見せるのだが、教えられた手順で議論を重ねるとこれまで見逃していた改良点や新製品の発見に至るのである。このワークショップから生まれた製品も多いらしい。 章ごとに「テクニックの進め方」が解説されており、実行上の注意点も添えられている。章の最後に要旨が図解されているのも使いやすい。このテーマでの書物のなかでは、群を抜いて内容豊かで実践的
0投稿日: 2017.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ制約の中にイノベーションがある 置かれた状況の中に最適な解を見つけるためには構成する要素を分解して考える 引き算、掛け算、関数、一石二鳥を考える
0投稿日: 2016.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
①なぜ、制約の中にイノベーションがあるのか? ・背面(高跳び)跳びは、はさみ跳びの延長で生まれた ・閉じた世界の中の要素を用いた経穴策の方が創造的(問題に目をそらさない) ・ブレストによる多すぎるアイデアはあまり意味がない ②引き算 ・ウォークマンは、録音機能をスピーカーを除いたマーケティング調査の結果は、散々だったが、1カ月54台→2か月5万台→全世界で5億台売れた ・Ipadはシンプルさとデザイン性(競合製品はたくさんあった) ・ファブリーズは洗剤成分を除いた ③分割 ・レコーディングで1曲を分割して、後でつなぎ合わせる ④掛け算 ・髭剃り刃を2枚に ⑤一石二鳥 ・IPHONEアプリをアウトソース ⑥関数 ・ミルクの温度で色が変わる哺乳瓶
0投稿日: 2015.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのやり方はとても参考になります。 自由に発想することが、とても不自由で、自由に発想しても大したアイディアが出ないことが、多くあります。 ワークショップでも使い勝手の良い方法です。 なるほどと思う発想が、実例でたくさん掲載してあります。 一種の強制発想法ですね。 とても参考になります。
0投稿日: 2015.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログインサイドボックス(ある制約条件の中・枠の中)で考えることでイノベーションがすばやく生まれるというもの。 引き算・分割・掛け算・一石二鳥・関数の5つのひな形をつかってまず形式を生み出してから、その「機能」を考える。 ただ、革新的なイノベーションを生み出すものではない。 成功率を確保しながら、イノベーションを考える方法としては良い方法と考える。 登録特許のほとんどが、改良によるもので革新的なイノベーションなものはごくわずかというから、特許のアイデアだしにはいいのではないか。iPhoneやiPadも本手法で考えることができる範疇に入る。
0投稿日: 2015.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【中央図書館リクエスト購入図書】☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15595503
0投稿日: 2015.05.15イノベーションを起こす法則があった!
タイトルを見て、少しでも興味を持った方は、是非一読をオススメします。 イノベーションが起こるのは、いわゆる天才と呼ばれる方々が、常人にはできない発想することが生まれたり、とことん追い詰められた末に生まれるものだと個人的には思っていました。 そもそもイノベーションの定義も、個人的には曖昧な状況ですが笑 考え方を、数パターンにまとめ、どう考えていけばいいのかをわかりやすく説明してくれます。 すぐ、実際の仕事の場で活用するには、難しいとも感じますが、言っている事は納得できます。 少しでもイノベーションを起こしたい方や、そういったことが求められている仕事をしている方は読んで損はないと思います。
0投稿日: 2015.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ創造的な発想はどうすればできるのか? 引き算、かけ算、分割、一鳥二石などの工夫をすることによりできる。 考えたことを試してみることが必要なようだ。 ダメもとの精神が大事。
0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ★4(付箋17枚/P352→割合4.83%)文字数加算+1 創造的な発想は完全な外からではなくて、その環境の中だけで工夫することで生まれる。 走り高跳びの背面跳びは、まったく新しい発想ではなくて古い型のはさみ跳びをやめられなかった選手がその方法を更に磨いて見つけたものだった。 ナインドットパズル(3×3の点を4本の直線で一筆書きで辿る。1つの点は一度しか通れない)で80%の人が点の外に直線を通すという発想ができなかったという実験を元に、発想は枠の外にあるという主張がなされた。でも実は、“空想上の正方形の外に突き出すように線を描かなければ正解にたどりつけない”と先に種明かしをしておいても、正答率は5%しか変わらない。 新しくしたい何かとその周りのものだけで考えることでしか本当に新しい発想は出てこない。その手法として著者は「引き算」「分割」「掛け算」「一石二鳥」「関数」「矛盾(を見つける)」を上げる。 実例が挙げられていて、本当に説得力がある。 パンクしてスペアタイヤ交換をしなければいけないのだが、ナットが錆ついていて、タイヤが外せない。車の中のものだけで、レンチを回すエレガントな方法とは、何だと思います? ***抜き書きは以下** ・興味深いことに、フォスベリーの背面跳びのエピソードは、「革命的な成果は枠の外(アウトサイドボックス)に出てものを考えることで生まれる」という実例として紹介されることが多い。確かに、背面跳びは、当時主流だった跳躍法であるベリーロールとは対照的だった。…この定説は素晴らしい逸話に聞こえるが、真実は少し違う。実はもっと魅力的なストーリーだったのである。 フォスベリーが走り高跳びを始めたのは、10歳のときだった。ほかの子どもたちをまねして、はさみ跳びで跳びはじめた。しかしこの跳び方は、エネルギーを跳躍力に転換する効率が悪く、時代遅れになっていた。一年後、体育の教師とコーチが子どもたち全員に、ベリーロールで跳ぶよう指導した。それでもフォスベリーは、高校に入るまではさみ跳びを続けた(上手く習得できなかった)。 (高校で一度ベリーロールに転向したものの、もっと早く転向していたライバルに追いつけず、元の方法に戻して欲しいとコーチに掛け合った) …こうして、フォスベリーはその後の競技人生を決定づける決断に踏み出した。ベリーロールの跳び方を磨くのではなく、たとえ非効率でも自分が跳びやすい方法に戻したのだ。 しかし、もっと高く跳ぶためには、跳び方を修正しなくてはならないと気づいた。はさみ跳びの最大の弱点は、お尻がバーに当たりやすいことだ。そこでフォスベリーは、バーの上を越すときに、お尻を高く持ち上げるように努めた。そのためには、おのずと肩を下に下げることになる。…そうするうちに、フォスベリーは新しい跳び方を完成させていった。バーに側面を向けて踏み切り、宙で仰向けの状態になり、まず腰を上に突き上げてお尻がバーに当たらないようにし、バーを通過した瞬間に、すぐに足を宙に蹴り上げて足がぶつからないようにし、バーを跳び越すようになったのだ。 2003年、著者と仲間たちは、世界を代表するスポーツ専門家たちにインタビューをおこない、スポーツ史上に残る大革命の重要性を採点してもらった。最も高い評価を得たのは、フォスベリーの背面跳びだった。点数は平均5点。合成樹脂製の陸上トラックや、ランニングシューズなど、ほかのイノベーションに2点以上の差をつけていた。 ※ベリーロールは体の正面をバーに向け、四つん這いのような姿勢で跳ぶ。はさみ跳びはお尻がバーに向く座ってバーをまたぐような姿勢で跳ぶ。 ・ナイン・ドット・パズル。 ギルフォードの実験の被験者は一人残らず、最初にパズルを解こうとしたとき、見えない正方形の枠の中にみずからの思考を限定してしまった(その点は、最後にはパズルを解けた被験者も例外ではない)。別にそう指示されたわけでもないのに、正方形の外に広がる空白地帯に目がいかなかったのだ。最終的に、この空想上の足枷を抜け出して正解にたどりつけた人は、被験者全体の20%に過ぎなかった。 美しく左右対称を描くシンプルな解法と、被験者の80%が空想上の正方形の枠に目をくもらされていたという事実を目の当たりにして、ギルフォードは一つの一般論的な結論に飛びついた。創造性を発揮するためには、枠の外に出てものを考えなくてはならない、という教訓を導き出したのだ。 …この理論は広く受け入れられ、直感的にも正しそうに思えたので、本当にそれが正しいか誰も検証しようとしなかった―ある二組の研究者がそれぞれ新たに実験をおこなうまでは。 両チームとも同じ手順で実験を進めた。まず、被験者を二つのグループに分け、片方のグループにはギルフォードの実験と同じ内容の指示を与える。もう片方のグループには、空想上の正方形の外に突き出すように線を描かなければ正解にたどりつけないと説明する。ようするに、最初に「種明かし」をするのだ。この二番目の被験者のグループでは、どのくらいの人が正解できたか?ヒントをもらった被験者の60~90%はやすやすとパズルを解けただろうと、ほとんどの人は予測する。しかし実際には、その割合は25%にすぎなかった。ヒントを与えても、わずか5%しか正解率が上昇しなかったのだ。 ・タイヤのパンクを車内の物だけで解決する。 スペアタイヤ交換しようとしたが、ナットがサビついていて動かない。レンチに足を乗せて体重を掛けても駄目。当時は1990年で携帯電話も普及していない。近くに棒のようなものはなく、スプレータイプのパンク修理剤も持っていなかった。 制約の中(インサイドボックス)で解決策を探してみよう。この場合で言えば、自動車の中だけに目を向けるのだ。 一つの候補としては、タイヤレンチの持ち手をタイヤの下に差し込んでから、エンジンをかけてタイヤを回転させることにより、レンチに強い力をかけてナットを緩めるというアイデアがありうる。ただし、うまくやり遂げるにはかなりの訓練が必要とされる。それより簡単なのは、ボンネットの下からオイルを抜き、ナットに数滴たらして回転しやすくするという方法だ(このようなケースでオイルを使う場合は、ブレーキオイルを用いること。ブレーキオイルは熱くなりにくく、サビに効きやすい)。 …ジェイコブは一分もせずに解決策を思いついた。答えは目の前にあった。ずっとそこで二人を待っていたのだ。その解決策とは、ジャッキだ。ジャッキを使えば、タイヤレンチを回すのは簡単だった。ジャッキは、ネジや油圧により力を増幅させられるし、とても頑丈にできている(なにしろ、そもそもは自動車を持ち上げるための器具なのだから)。 ※十字のレンチの手で持つところの上に上がる部分にジャッキを挟み、車を持ち上げる要領でジャッキを回す。 ・ブレインストーミングは、同じ人数の人たちが互いに接触せずに問題を検討する場合に比べて、どのくらい効果が大きいのか?研究を通じてわかってきた重要な発見は、以下のとおりだった。 *ブレインストーミングをおこなったグループが、同じ人数の人たちがそれぞれ一人で考えたグループより大きな成果をあげるということはない。 *ブレインストーミングをおこなったグループは、個人単位で考えたグループに比べて、生み出すアイデアの数が少ない。 *生み出されたアイデアの質や創造性は、ブレインストーミングをおこなったグループのほうが低い。 *人数が多ければ多いほど好ましいという常識に反し、ブレインストーミングに最適な人数は4人である。 こうした発見は、その後の研究でも繰り返し裏づけられてきた。もはや結論は明らかだと、研究者たちは考えるようになっている。人々を同じ部屋に集めるだけで、創造的なアイデアが次々と生み出されるなどということはないのだ。 ・コロンビア大学で創造性のクラスを受講していたジョンという学生は、自動車を製造し、世界ラリー選手権で走らせている企業で働いていた。授業で「閉じた世界」について聞かされると、ひとこと発言せずにいられなかった。ジョンいわく、世界ラリー選手権は文字どおり「閉じた世界」の原理にのっとって動いているという。競技のルールにより、レース中に問題が発生した場合は、ドライバーとコ・ドライバー(ナビゲーター)が手元にあるものだけで対処しなくてはならないのだ。世界ラリー選手権に出場する自動車の設計・製造・整備には、220人あまりの人が関わっている。しかし、3日間にわたるレースの間は、ドライバーとコ・ドライバーの二人だけですべて走りき らなくて はならない。 ex.川底の岩に激突してエンジンオイルのオイルパンに穴が開いて漏れた⇒耐火性下着オムツのように挟んで穴をふさいだ。冷却ファンの羽が一枚外れてしまっ。バランスが悪く、ファンが壊れるとオーバーヒートしかねない⇒はずれた羽の反対側の羽も取り外した。 ・J&Jの麻酔管理システム。 アムノンはまず、メンバーに試作品の主要な構成要素を挙げさせた。これは、インサイドボックス思考法のいずれのテクニックを用いるにせよ、最初におこなうべきステップだ。試作品の麻酔機器は大型のデスクトップパソコンのような外見をしており、パソコンとおなじように、モニター、キーボード、筺体、電源で構成されていた。また、政府の規制により、麻酔機器には停電時に備えた予備バッテリーの搭載が義務付けられている。チームのメンバーは、これらの要素を列挙していった。 アムノンは、次のステップに進んだ。メンバーを二人組にわけ、それぞれのペアに構成要素を一つずつ割り振った。そして、衝撃的なひとことを放った。「みなさんの課題は、その要素を取り除いたら、どうなるかを考えることです」。 …「予備バッテリーですって?麻酔機器から予備バッテリーを取り除く?そんな製品を売り出すのは、法律違反です。私たちは刑務所送りになってしまう!」と、二人は言った。 アムノンは、抵抗を受けても引きさがらなかった。「突飛な発想だと感じるのは無理もありません。でも、少しだけおつき合い下さい。試してみましょう。予備バッテリーを取り除くと、製品がどうなるかを想像してみてください。その製品に、どういう利点があるか?誰がそういう製品を欲しがるか?」 …最初にあがった意見は、製品が軽量化でき、コストを減らせ、製造が容易になるというものだった。「考えてみれば、製品のほとんどのスペースを占領しているのは予備バッテリーです」と、エンジニアの一人が述べた。「もし本当に予備バッテリーをなくせれば、製品は想像を絶するくらいシンプルなものになります」。 …アムノンは、ただちに次のステップに進んだ。「予備バッテリーの搭載をやめれば、数々の大きな利点があるとわかりました。閉じた世界の中に、予備バッテリーの機能を代替できるものはありませんか?」 第1章で述べたように、「閉じた世界」とは、その中のすべての要素(物体や人間)をすぐに利用できるスペースのことだ。本書のテクニックを用いてイノベーションをめざす場合は、そういう手の届く範囲内の要素が創造のための「材料」となる。この麻酔機器のケースでは、機器を用いる場である手術室を「閉じた世界」と位置付けた。 あるエンジニアがためらいがちに挙手した。その男性はもじもじしていたが、ようやく意を決して口を開いた。「すでに手術室に設置されている別の機器の予備バッテリーに、麻酔機器を接続すればいいのではないでしょうか?たとえば、除細動機とか?」。みんあがその人物のほうを見た。彼の声が次第に熱を帯びていった。 「長いケーブルと適切なコネクターを用意すれば、除細動機から電力を得ることができます。除細動機の予備バッテリーには、もしもの場合に両方の機器を動かすだけの電力が蓄えられています!」 …アムノンは次のペアに問いかけた。「モニターはどうでしょう?麻酔機器からモニターを取り除く利点は?」 「アムノン、忘れないでほしいのですが、私たちはモニターに関して顧客の声を集めるために何万ドルもの金を使ってきたのです。医師たちは、麻酔機器にはモニターがついているものと思っています。モニターのない麻酔機器など相手にしないのです。モニターは取り除けません」。 アムノンは、すぐにこの発言の背後にあるものを見抜いた。それは「思い込み」である。二人のエンジニアは、モニターつきの麻酔機器ばかりを見続けてきたために、モニターなしの麻酔機器など想像することもできなかったのだ。 …「続けましょう」と、アムノンが言った。「手術室の閉じた世界の中に、モニターの機能を代替できるものはありますか?」 「簡単ですよ!」と、あるメンバーが言った。「データを手術室の主モニターに転送すればいいんですよ。医師はどっちみち、主モニターを見るわけですから」。 ・既存製品の中核的機能を取り除いたことで大ヒット商品が生まれた事例を、もう一つ紹介しよう。その商品とは、モトローラの携帯電話「マンゴー」だ。モトローラのイスラエル部門のマーケティング担当副社長は、ライバル社の低価格の携帯電話に対抗したいと考えた。そこで、コストを減らすために、電話をかける機能を取り除いた。あなたの読み間違いでもなければ、誤植でもない。電話をかける機能がない携帯電話をつくったのだ。電話を受けるだけの携帯電話だ。 いったい、どういう人がそんな携帯電話を欲しがるのか?ティーンエイジャーの子どもを持つ親の気持ちになってみればいい。 …それにコスト削減により低価格にできたので、壊れたり盗まれたりしても痛手は小さい。ややこしい点がまったくない商品なので、スーパーマーケットでも売ることができた。 (他にも、子どもたちがモトローラに慣れる、企業が営業部員に利用するなどのメリットもある)。 発売から一年以内に、市場の5%がマンゴーを購入した。その年、なんとイスラエルは携帯電話普及率で世界第二位に躍り出た。 ・チリ鉱山の坑道崩落事故。 救助をめざしていた人たちはみな、行動を再び開通させることしか頭になかったが、エーベルハウト・アウという34歳の技師は別のアプローチで考えた。坑道からの救出という選択肢が引き算されたとみなしたのだ。取り除かれた要素を代替するものとして目をつけたのは、食料と水の補給のために用いていた細い穴だった。アウは補給穴を通じて地下に送り込むために、ありきたりの板金でつくれる細長いカプセルを設計した。 ・私は緊迫した状況に立たされたときの行動ルールを決めていた。それは、敵対的な空気に屈せず、しかしはったりをかましたり、弁解がましい態度を取ったりはしないというものだ。 ・あるプロセスで処理しなくてはならない課題が多すぎて、時間が足りない―そんな経験は誰もがあるだろう。そういうときは、分割のテクニックが役に立つかもしれない。 企業の社員研修を例に考えてみよう。あなたの会社は、さまざまな分野で多くの複雑な製品をつくっている。営業部員は、そうしたすべての製品について熟知していなくてはならない。しかも、それを顧客に売り込む方法も理解しておく必要がある。そこで会社は、新たに入社した営業部員に六週間の研修を義務付けている。しかし、あなたの会社は、平均して月に一つのペースで新製品を売り出している。このような製品ラインナップの急拡大に研修プログラムを対応させるためには、どうすればいいのか?研修時間を増やし続けるわけにはいかない。 (ジョンソン&ジョンソンでは人体の基礎、手術方法、製品という分割された要素の研修をしていたが、人体と手術方法の知識を細かく分け、製品に関する研修とセットにした) ・「オスがメスと交尾すれば、子が生まれる」という思い込みが、科学者たちの創造的思考を妨げていた。言い換えれば、科学者たちは、害虫根絶をめざすうえで、オスとメスの交尾を悪材料と決めつけていたのだ。 ブッシュランドとニップリングは逆転の発想をした。オスのラセンウジバエを増量したのである。このテクニックで重要なのは、増やした要素に変化を加えることだ。二人の科学者は、オスのラセンウジバエをみずからの種を根絶に追い込む手段に変えた。その解決策は、エレガントで、にわかに信じがたいくらいシンプルなものだった。オスを人工的に不妊化させたうえで自然に放ったのである。(放射線で不妊化する。メスは生涯に一度しか交尾せず、不妊化したオスと交尾すると、そのメスは繁殖できなくなる。) ・新しい試験問題をつくること自体はそう難しくない。カレッジボード(アメリカの大学進学適性試験を作成、採点する非営利団体)には、試験問題を作成する優秀な職員が大勢いる。問題は、過去の試験と比べた場合の難易度の妥当性をどうやって判断するかだ。大学は試験の難易度を毎年同程度に保ちたい。一定レベルの難易度が毎年維持されるから、SATは「標準テスト」と呼ばれるのだ。 では、カレッジボードはどうすればいいのか?もちろん、採用予定の新しい試験問題を職員に事前に解かせて、正解率をチェックしてもいいだろう。しかし、この解決策の効果は短期間しか続かない。まず、どうしても問題解答役の職員の学力が次第に向上していく。それに、解答役が仕事に飽きて退職したり、昇進したり、引退したりすれば、解答役が交代せざるをえない。 …SATの試験問題には、正答しても点数を加算されない問題が含まれている。将来の試験で問題として採用するのに適しているかを判断するために、ダミー問題として混ぜ、正解率をチェックしているのだ。どの問題がダミーかは明記されない。225分の試験時間のうち、約25分間がダミーの問題を解くために費やされている。カレッジボードは試験問題を増やし、その問題の配点をゼロに変えることにより、将来その問題を本当に試験問題として採用した場合の正解率をほぼ正確に予測できるようになった。 ・最初は2倍に増やすだけでもいいが、慣れてきたら、3倍、16倍、25.5倍という具合に、コピーする数を増やしていこう。何倍に増やすかは、あてずっぽうで決めてもいい。それによって、ヘンテコに見えるものをつくり出すことこそ、イノベーションの道だからだ。要素をいくつも増やし。その一つひとつに意外な変更を加えることによって、思考が広がり、新しい可能性が開けてくる。 ・このシステムのおかげで、ゆがんだ文字列を解読できる生身の人間だけがサイト上でチケットを買えるようになった(人気のチケットを自動プログラムで買い占めて値段を吊り上げる業者がいた)。ユーザーが文字列を読みとって、入力するために、10秒くらいの時間と手間はかかるだろう。それでも、セキュリティが向上し、人気チケットを適正な価格で買えるというメリットを知れば、ユーザーはほとんど文句を言わない。 業界関係者以外にほとんど知られていないのは、フォンアンもウェブサイト管理者やユーザーに大いに感謝しているというこだ。実は、フォンアンは1日2億回の文字解読作業を利用して、ある目的を達している。世界中の書籍をスキャンして電子化することを目指しているのである。 ・ニューヨークのある名門ホテルのCEOが一年の間に二度、ソウルに出張し、二度目も最初と同じホテルに泊まった。二度目にホテルに到着すると、フロント係が温かく迎えてくれた。「いらっしゃいませ!またお越しいただいて、ありがとうございます!」 前に泊まったことを覚えていてくれた!CEOは感激し、自分のホテルのスタッフにも同じような接客をさせたいと思った。 CEOがニューヨークに戻って専門家に相談すると、顔認識ソフトウェアを搭載したカメラを設置してはどうかと提案された。しかし、費用が250万ドルもかかるとわかった。CEOはシステムの導入を見送ることにし、次にソウルのホテルに泊まるときに、秘訣を探ってやろうと心に決めた。そして、再びソウルのホテルを訪れると、またしてもフロントで「常連客」として熱烈に歓迎された。そこで、どうやって過去に宿泊経験のある客を見分けているのかと、ぎこちなく尋ねてみた。フロント係の回答は、エレガントでシンプルなものだった。タクシーの運転手たちと話をつけてあるのだ。空港からホテルに向かう途中で、運転手が客と雑談をし、以前そのホテルに泊まったことがある かをさり げなく聞き出す。 「もし利用経験があれば、運転手はフロントにお客様の荷物を運び込むときに、デスクの右側に置くことになっています。はじめての利用であれば、左側です」と、フロント係ははにかんだようにほほ笑んで言った。「このために、運転手たちにはお客様一人につき一ドルを支払っています」。 ・有名な実験を例に説明しよう。二人の被験者にこう言い渡す。「一個のオレンジを宙に放り投げるのでキャッチしてほしい。取り損ねた場合は、相手と交渉して譲ってもらうこと」。そして一方の被験者には、相手のいない場所でこう説明する。「お子さんが重病で、その命を救うために、オレンジを絞ってジュースをつくる必要があるのです」。もう一方には、こう話す。「奥さん(ご主人)が重病で、その命を救うために、オレンジの皮でジャムをつくる必要があるのです」。お互い、相手がなにを言われたかは聞かされない。 ・あるとき、中学一年生の息子から頼まれた―学校でなにか特別授業をしてよ。堅苦しい勉強ではなく、インラインスケートの遊び方とか、クッキーの焼き方みたいに、楽しい授業にしてほしいとのことだった。そこで私は学校に電話し、「発明家になろう」という授業をすることを申し出た。私はすでに四年間、数々のイノベーションのワークショップでインサイドボックス思考法を教えていた。子どもたちのために、楽しくて役に立つ授業をする自信があった。 学校側の回答はノーだった。 私は驚いた。創造性に関するミニ講義をするというアイデアは、当然歓迎されるものと思っていたのだ。私は理由を尋ねた。発明家になる方法など教えることは不可能だ、というのが拒否の理由だった。とりわけ、子どもにそんなことを教えるのは無理だという。子どもたちに高度な要求をしすぎれば、「小さな胸を苦しめて」しまうと、学校側は考えていた。学校の上層部は、大半の人と同様、「創造性は生まれつきの才能だ」と思い込んでいたのだ。 …子どもたちの創造性に、「切る」のボタンはないのだ。ニコルたちの小さな頭脳は、授業が終わったあともフル回転し続けていた。 これ以降、私はシンシナティのワイオミングシティ学区の小学校で三年生と四年生に本書の方法論を教えている。サムという男の子は、私の教えた内容を忠実に守って、掛け算のテクニックでイノベーションに取り組んだ。この子に与えた課題は、地元のシンシナティ大学の鮮やかな赤色の傘だった。サムは定石どおり要素のコピーをおこない、取っ手が二つある傘を考案した。一つは普通の場所、もう一つは傘の先端部分についている。正しい手順にのっとって、私は尋ねた。「両端に取っ手のついた傘を欲しがるのは、どういう人だと思う?そういう傘にどういうメリットがあると思う?」 サムは一瞬考えてから、拳を店に突き上げて叫んだ。「わかったぞ!なんの役に立つかわかった!」 私は息を呑んで、次の言葉を待った。 サムは言った。「強い風が吹いて、傘がおちょこになっても、上下をひっくり返してすぐに使えるよ!」
1投稿日: 2014.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ【学び】 制約を除外するのではなくむしろ制約のの中にこそイノベーションの余地があること。また一定の雛型で考えることとその訓練をすることで誰にでもイノベーションを起こせる可能性があること。引き算、分割、かけ算、一石二鳥、関数、矛盾と連結要素。 【所感】 個人的には今年最高に面白く画期的な書籍だった。すぐに取り組めるシンプル(だけど難解なので訓練は必須)な雛型、トライしてみたいと思わせるわかりやすい事例の数々。あらゆるイノベーションがこの思考法で説明できること。一部の天才にしかなし得ないことではなく、誰にでもできる、そう思わせてくれる一冊。あとは訓練あるのみ。
0投稿日: 2014.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終わった。 通常は速読をして必要な情報をのみピックアップするのだが、この本は読みながら考えさせる箇所がいくつもあるので、その度に読むのを止めて考えた。 結論からオススメのみ本。 一般にアイデアは自分の枠を超えて考えようと言われること後多いが、この本は自分の枠組みの中に解決のヒントがある、と説く。 更に具体的な思考法(発想法)を、足し算、引き算、掛け算、等と覚えやすく説明してくれている。 しっかりと身につけるには実際に何度も実施してみることが必要。 読み返しながら試してみる。
0投稿日: 2014.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ目の前にある問題の解決に役立つというよりは、色々なアイデアを生み出してそれが解決してくれる問題を後付けで探す。 今までとは逆の順番。 実生活ではやはり最初に問題ありきの状況の方が多いと思うのだが...
0投稿日: 2014.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションを産み出すための発想法としてはとても有用で、すぐに実践で使えるのではないかと思うくらいわかりやすく、かつ具体的だ。 だが、自由ではなく制約の中に答えがある、つまりインサイドボックス、というのはちょっと違うと思う。何故なら、制約の中にあるのは方法論であって答えではないからだ。そのあたりをきちんと理解しないと間違うと思う。
0投稿日: 2014.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【制約の中でこそ、イノベーションは起こる】数々の企業でヒット商品を生んだコンサルとコロンビア大ビジネススクール教授が教える。制約の中で引き算、分割、掛算、関数を使え!
0投稿日: 2014.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ枠の外ではなく、枠の中で考える思考法。「イノベーションは制約の中にこそ潜んでいる」という考え方が面白い。この手法も試してみる価値がありそう。
0投稿日: 2014.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ制約があるからこそ創造的なアイデアが導き出せるという、妥協をせずに画期的なアイデアを出すための考え方、方法をフレームワーク化した本です。考えることをやめてはいけないな、、、と思わせる本です。
0投稿日: 2014.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「引き算」「分割」「掛け算」「一石二鳥」「関数」というフレームワークを用いることで、制約の中でも創造的なアイデアを導き出せる。企画をするときに再読したい。
0投稿日: 2014.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションは型の中にある。この発想自体がまさに画期的イノベーションと呼べる。縛りがあるからこそ問題解決へのアドレナリンが働く。逆に型の外で自由を与えられた脳は、インスピレーションは生み出すがソリューションは生み出さない。よく言う「逆転の発想」とは違う。冷静に考えれば当たり前のことである。それを気づかせてくれた本書はタダモノではない。
0投稿日: 2014.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ体系的創造思考法=インサイドボックス思考法 イノベーターが用いている5つのヒナ型とその実例 ・引き算 ・分割 ・掛け算 ・一石二鳥 ・関数 ヒナ型を使う「インサイドボックス思考法」の原則 1.身の回りの「閉じた世界」の制約の中で、アイデア を探す。 2.×形式は機能に従う←→〇機能は形式に従う
0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11885387410.html
0投稿日: 2014.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションとは妥協しないこと。 真の想像的な解決策は突飛なものであり、それは身近なものを変化させることで成し遂げらされる。
0投稿日: 2014.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ形式は機能に従う→機能は形式に従う イノベーションは制約の中にこそ潜んでいる ①引き算のテクニック ②分割のテクニック ③かけ算のテクニック ④一石二鳥のテクニック ⑤関数のテクニック 矛盾を見出せ
0投稿日: 2014.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ無限の可能性は制約の中にあるという一瞬矛盾とも言えることを主題に、うまい事例で読む人を納得させる本である。 自分の過去を振り返ると、制約の多いものほど上手くいく。もしくは、制約をドンドン見つけることで精度を上げるという事ができた時は、上手くいく。 この本を読んで改めて考えたらそれは当然だ。何故なら、新たな要素を持ってこないという事は、コストがほとんどの増えないということ。この本でも無視している暗黙の前提はコストの最小化であるがそれが自然と為されるということだ。 とは言え、思い込みの呪縛の問題はある。自分が檻に自ら入っているが、それを見ないようにすること自体が、問題解決やイノベーションを阻害している。この本を読んでやれる気になるのではなく、その呪縛に気づけるようになることの方が余程重要だ。 引き算、分割、掛け算、一石二鳥、関数、矛盾の六つは、思い込みから解き放つための重要なツールだ。使いこなす。
0投稿日: 2014.06.07
