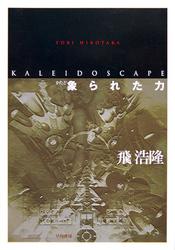
総合評価
(67件)| 20 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 1 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ飛浩隆先生。SFなんだけど、簡単にそうくくってしまうのが勿体ないような中編集。 「デュオ」主人公はピアノ調律師。チューニングハンマーを武器に闘う調律師なんているんだ…!それもジョークではなく、洗練された戦術とゆるぎない殺意をもって。音楽の描写も凄い。バイエル8番がこんなにも不穏で、読み手をざわつかせ昂らせることってある? 個人的な「癖に刺さる」という意味でも稀少な一編。 表題作「象られた力」。圧倒的。宇宙世界に生成された多層の文化と、その破壊。文章の美しさ、映像を惹起する力が凄まじい。多文化のひびきに酔い、人々と図像のふるまいに魅了され、そして善悪を超えた圧倒的な力に平伏すしかない。 きわめて映像的でありながら、じゃあ実写?アニメ?CGでなんとかなる?なんて考え始めると、見たいような、でも何を見せられても追いつかない、物足りない気がしてしまう。 主人公、クドウ圓(ヒトミ)がいい。牡鹿みたい、と恋人(も、悪くていい)に評される黒髪の男。彼に見惚れる(文字で書かれた情報なのに見惚れてしまう)そのためにだけでも読む価値はある、そんな愉しみもある小説です。
15投稿日: 2025.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ端正な文章と五感を美しく言語化した作品集。SF的仕掛けの面白さはもちろんのこと、構成のリズム感や緩急が素晴らしかった。
0投稿日: 2025.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ誌のような文章が美しく巧みで、あたかも幻想小説のようなSF中短編集。文章に想像が追いつかず、画をイメージするのがなかなか難しいのですが、独特の世界感に引き込まれます。 個人的に一番のお気に入りは「呪界のほとり」。冒険小説のようなわくわく感と、個性的で魅力あるキャラクターたちの軽妙なやりとり、想像を掻き立てられる情景描写。映画、それも実写やセル画アニメではなく、CGアニメで観てみたいなぁと不思議と思いました。
1投稿日: 2023.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には、「デュオ」と「象られた力」が好きです。 「象られた力」には『零號琴』の面影を感じました。
1投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ強大な思念の力。封印された記憶、のような実体のないものが何を伝えたいのか、装飾を丁寧に剥ぎ取って明らかにしていく。その”もの”の語る声を聴く。それが飛氏の作品に込められたテーマのように思う。 「象られた力」で惑星が秘める歴史を暴いていく過程は『零號琴』を彷彿とさせた。 『悪童日記』の双子を思い出させるような「デュオ」が最も好みだなと感じていたが、時間が経つほど表題作「象られた力」の印象が強くなって消えない。 読んだ者の心に深く印象を刻む物語、この本『象られた力』自体が、強い思念の力を持っている。
0投稿日: 2021.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ飛浩隆を読むのはこれが初めてとなる。本作は、表題作の「象られた力」を含む4篇からなる作品。レビューの評価が高く、初めて読むのには最適かとも思われた。 それぞれのエピソードの評価とジャンルを書くと以下のようになる。(ややネタバレ) デュオ(★★★★★): ミステリー、音楽、サスペンス、生と死、意識、テレパス 呪界のほとり(★★★★☆): 宇宙、バロック、冒険、ファンタジー 夜と泥の(★★★☆☆): 宇宙、宇宙連合、テラフォーミング、生物 象られた力(★★★★★): 言語、記号、宇宙、宇宙連合、超能力 「デュオ」は文句なしに面白い。きちんと物語しているし、数度のどんでん返しがある。おどろおどろしい雰囲気作りが上手いし、ちょうどいい難解さが歯ごたえを生んで心地いい。SFとしては少し変わり種だけど、万人受けしそうな内容ではある。さらに、文章に惹きつけられる。 「呪界のほとり」は、王道の宇宙系SFと言ったところ。宇宙ワープ、人造の竜族、謎の追手など、ワイドスクリーン・バロックSFを久しぶりに読んだ思い。 「夜と泥の」はテラフォーミングの話かな。自分にはあまり合わなかった。好きな人は好きかもしれない。が、作品全体のリズムを考えた時、「象られた力」の前の静けさとして上手く作用していたようにも思う。 「象られた力」はなかなか良かった。テッド・チャンの「メッセージ」のような、言語系SFかなと思わせて、実は文明崩壊SFでもあった。百合洋(ゆりうみ)文化の記号はとても魔性に映る。そして抗うすべもなく人間がおぼれていくさまは、恍惚的でもあった。 平均して面白かったし、SFとしてのジャンルは多岐にわたる。デュオは万人におすすめ。象られた力はSFファンにオススメ。ぜひ、この作者の他の作品も読みたい!そう思わされるだけの1作だった。 (書評ブログの方も宜しくお願いします) https://www.everyday-book-reviews.com/entry/%E6%96%87%E6%98%8E%E5%B4%A9%E5%A3%8A%E7%B3%BB%E8%A8%98%E5%8F%B7SF_%E8%B1%A1%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%9B_%E9%A3%9B%E6%B5%A9%E9%9A%86
19投稿日: 2020.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ80年代後半から92年までに書かれた中篇4篇を収めた作品集。 「デュオ」 交通事故で恋人を亡くし、自身で演奏する能力も失ってピアノの調律師となった緒方は、恩師からグラフェナウアー兄弟を紹介される。デネスとクラウスのシャム双生児であるグラフェナウアーは、一本ずつの腕をテレパスによって統合し完璧にピアノを奏でる天才だった。耳が聞こえず喋ることもできない兄弟の手話通訳を務めるジャクリーンと親しくなるうち、緒方は双子に“もう一人”が存在することを知る。 特にクラシックにもピアノにも詳しくない人間にも、聴力以外の感覚を喩えに使って双子が奏でる悪魔的な音楽を感じさせる表現力。「ふかふかの鍵」のくだりはピアニストの身体性を伝えていて面白かった。でもやっぱり先に「海の指」を読んじゃったからちょっと物足りなくもある。結末は絶対ジャクリーン本人が銃を握って殺すべきだったと思います。 「呪界のほとり」 追っ手から逃げるうち、呪界-地面を叩けばどこでも水が湧いてくる魔法の世界-から飛び出してしまった万丈と相棒の竜。辿り着いた辺境の星アグアス・フレスカスには、呪界に強い憧憬を抱く老人パワーズがひとりきりで暮らしていた。 ラノベというかゲームのノベライズっぽい。特殊な用語がポンポン出てくるけど、説明過多に感じさせずになんとなく察することができる情報コントロールが巧み。しおらしいのに全然言うこときかない竜のファフナーがかわいい。 「夜と泥の」 若い頃”リットン&ステインズビー協会“で共に働いた蔡に呼びだされ、とある星にやってきた「わたし」。「いいものを見せてやる」と言った蔡に案内されたのは、地球化[テラフォーミング]のために協会が使わした人工衛星たちが暴走し、夏至ごとに一人の”少女“を復活させるという沼だった。 これ好き!『タフの方舟』を思わせるような、地球人の思惑の裏をかく異星の意思が描かれ、それに取り憑かれた蔡の姿はホラー的でもある。ヒトの生みだしたものがヒトの手に負えなくなって野生化していく描写、いいよねー。 「象られた力」 〈シジック〉のイコノグラファー・クドウ圓は、“リットン&ステインズビー協会”の文化事業部に依頼され、つい先日跡形もなく消え去った隣接星〈百合洋〉の言語体系“エンブレム”の謎解明のため動きだす。エンブレムは図形によって情報を多層的に伝達できるため、同じ星系の〈シジック〉〈ムザヒーブ〉でも急速に普及しはじめていた。〈百合洋〉はなぜ滅んだのか、エンブレムに秘められた力とは。 面白かった〜!これも“文字禍”の話。エンブレムに侵食された人びとの陶然とした言葉遣いと、畳み掛けるオブセッションの艶やかさは『13』のころの古川日出男を思いださせる。〈百合洋〉出身の建築家ハバシュが生んだ現代アートの延長のような建物や、圓の恋人・錦がつくるエンブレム・タトゥーのオートマシン、あるいは極小のエンブレムがラメになったアイシャドウや、圓とシラカワが食す〈シジック〉のビーガンじみた菌類食などのディテールから星系の文化を窺いしれるのも楽しい。そんな〈シジック〉の物語をメタ化するオチは、万物から常に物語や意味を見いだそうとする人類のサガを優しく俯瞰で眺めている。この“リットン&ステインズビー協会”もの、シリーズ化してほしかったなぁ。 4作品に共通するのは、実体のないものが実体に干渉し、その精神を支配し、実体よりも実体たろうとする巨大なパワー。これは「フィクション」のメタファーでもあるだろうし、のちの『グラン・ヴァカンス』で結実したヴィジョンなのだろう。
0投稿日: 2020.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ飛さんの作品の手触りの生々しさは、SFのやや遠目な世界観を手元に引き寄せてくる。 自分が感想をうまくつかめないとき、批評というのは偉大だなと思う。
0投稿日: 2020.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めての飛浩隆作品、短中編4作全部面白い。 SFを前提にミステリ、ホラー、ファンタジーなど様々なアプローチをしてるけどどれも違和感なくしっくり収まっている。 また、情景描写の上手さはもちろんのこと五感の描き方がとてつもなく上手い。文を通して“体験”しているような感覚すらあってただただすごいなと感じた。 個人的には「夜と泥の」の設定が好みでもうちょっと読みたかった。逆に表題の「象られた力」は最後が蛇足に感じてちょっと醒めてしまった。けどそれでも面白かった。
1投稿日: 2019.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログいや〜まいったまいった。収録されている短編4作品いずれもよくできているのだが、共通するのは文字がイメージを想起させること。文字で世界がめくれ上がって裏返しになったり人が卵のように割れる感覚を味わわせる筆致の凄みがある。文字で音楽的な素晴らしさを想像させたり目の前の圧倒的な光景を想像させるような表現の妙は、自分もこんなふうに書けたらいいなと思わせられる。
1投稿日: 2019.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこういうアイディアが浮かぶって、どういう頭の作りになっているのかしら。舌を巻くというのか、とにかく痺れます。
0投稿日: 2019.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログシャム双生児として生まれた天才的ピアニストを題材にした「デュオ」や、絵や文字ではなく形・デザインが持つ力の可能性を説いた表題作など惹きつけられる設定の短編が収められた作品。だけど、オチがどれもピンと来ないものが多かったかな…。個人的にはそこまではまれなかった。
0投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『知る人ぞ知る』とか、『伝説の』とかが頭につく作家。 どういう経緯で知ったんだったか……思い出せないけど、シリーズものがドはまりで、それを執筆するまでの作品が読みたくて借りた。 この収録作を最後に10年のブランクを経て、わたしが続きを熱望しているシリーズが発売された。 やはり、すごい。 文章で、これほど視覚的に訴えてくるSFははほかにない。
0投稿日: 2019.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白かった。読んでいる途中で書かれた年を知って少し驚いた。 デュオ>象られた力>夜と泥の>呪界のほとりで、の順に好き。『デュオ』がすごく読ませる。切なさと恐ろしさが同居した読み心地。設定的にはSFなのだが、偉大なピアニストを殺すべきなのかという葛藤、殺しても死なない「名無し」の行く末、誰が死に、誰が生きるのかという展開の妙が面白い。この文学的なSFこそ本邦のSFの持ち味だと個人的には思う。 『象られた力』はもっとSFへの振り幅が大きいが、破壊や破滅の正体がSF的設定を紐解く中で徐々に明らかにされていく、という仕掛け自体は『デュオ』に似たホラーな感触がある。図形が人間の持つ本来の能力のみならず、なぜ超能力的な力まで呼び覚ますことができたのか、そのあたりの解説が無く腑に落ちた感じがしないのが惜しい。 『夜と泥の』は彼のテラフォーミングを題材にした世界観を彩る掌編と言うところか。描写の美しさに舌を巻く。『呪界のほとりで』は安易な役割語(『象られた力』でも見られるが)で話す老人に入れ込みにくく、全体的に読みづらかった。
0投稿日: 2018.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本SFの本を探していれば必ず目に入る題名なので。 思ったよりも昔(1980〜1990年代)に書かれたもの。 最初は目新しい単語と色彩で置き換えただけのSF短編集か、と思っていましたが、後半は全くそんなことなく。社会の仕組みや人間の根本を改変するSFではなく、宇宙の見方、人の感じ方と空気を変える着想と描写に力強さを感じました。 「夜と泥の」「象られた力」が素晴らしい。 宇宙に咀嚼され消化される人類、人工生物によって永遠に引き起こされる神話。視覚言語と、形に詰まったエネルギー、崩壊の文様。図形と形に満ち溢れている世界はなんて力に満ちているのだろう。満ち溢れている力に気づき感じとり、圧倒された。圧倒的な力の存在に気づいた。
0投稿日: 2018.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読んだ飛先生作品。 静かで不思議で美しいSF小説短編集。 例えると、広く暗い宇宙の片隅でいつかあった誰かの人生の一部を物語として切り取ってきたという短編が連なっている。なぜ?という質問には決して答えない。そこが逆に素晴らしい。あるがままの状況を切り取ってきて、物語として仕上げた、いわばフォークソングのような物語たち。
0投稿日: 2018.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログイメージが想起される魅力的な短編。風景と情感の描写がよく、ラストに向けて物語世界の反流に襲われる感覚となった。
0投稿日: 2018.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ三本の短編と一本の短めの中編からなる作品集。 この手の本を読んでいつも思うのは「これがSFか?」ということ。 別にSFに拘る必要もないし、読んで面白ければそれでいいのだけれど、例えば本書の冒頭の作品「デュオ」なんかは、SFのS……科学……というよりも、非科学的事象を題材にしている。 江戸川乱歩や夢野久作が書いてもおかしくない内容なのに、SFなのか……。 あるいはSFってもっと広義の意味合いが含まれているものなのか。 まぁ……いいけど(と書きつつも、どうもいつもひっかかってしまう)。 その「デュオ」なんかはブライアン・W.オールディス の「ブラザーズ・オブ・ザ・ヘッド」なんかを思い起こさせたりもした(あちらはロック・バンドだし、内容は全然違うんだけど)。 SF云々でケチをつけたような書き方をしたけれど、実はものすごく面白く読み進めることができた。 意表を突く題材に、きっちりとした伏線の張り方、その伏線の回収の仕方、読みやすい文章。 読者である僕ととても相性の良い作家のようだ。
0投稿日: 2018.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログSF。中短編集。 「デュオ」 ミステリ、ファンタジー、ホラー、どれにも分類できそうな音楽SF。個人的には怖さを感じたので、ホラーの印象が強い。 「呪界のほとり」 異世界ファンタジー風。いまいち。 「夜と泥の」 テラフォーミング。情景描写が圧巻。 「象られた力」 わからない。読みにくい。 表題作が一番苦手…。「デュオ」と「夜と泥の」が好きでした。
0投稿日: 2017.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で。 グラン何とかってのは読んだ記憶があるような… それにしても不思議な経歴をお持ちの方なのですねぇ。 デュオはピアノの話でちょっとホラーな感じ。死んでしまった3人目の意志というか意識がちゃんと勉強しているのが面白い。強い生への自我とかじゃないのねぇ。 竜と主役と老人、というスラップスティックな感じの短編は面白かった。そのうちコレシリーズになりそう。 夏至の日に機械仕掛けの妖精たちが争うってなんかシェイクスピアか神話みたいな話で面白い。ウィルス最強。 アイコンが作用しあい、一つの意志というか力を発動するというのは…なんかうん、ちょっと受け入れがたくもあり怖いなぁと素直に思ったり。百合洋をユリウミと読ませるのがカッコイイ。
0投稿日: 2017.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初の「デュオ」はSFっていうよりミステリでしょ。 シャム双生児の天才ピアニストに死産した兄弟の意識が入り込んでるって設定だけでイカす〜。 表題作はがっつりSF。 意匠や文言が感情感覚に直接作用して果てには物理的な力を持つ。。。「図形テロ」って面白いけど、だいぶ"虐殺器官"的だし、「自生の夢」と被ってない?違うネタを希望。
0投稿日: 2017.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ生徒のビブリオバトル候補本。 SFは嫌いではないと思っていたけど、この作品は観念的というか、小難しい感じがして読むのが大変でした。 個人的には苦手な部類。
0投稿日: 2016.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログSFともファンタジーともホラーともとれる短編集。文章が綺麗。映像が浮かぶ様だ。 「夜と泥の」の情景描写に感動した。
0投稿日: 2016.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログある意味、こんな表現もあることを 知ってよかったのかも… デュオは展開のしかたが ちょっとあざとい感じがしたけど 普通に読めた… でもそれ以降、読んでて、連なる語彙に 反吐が出そうなくらいな感じで 読むのを止めてしまいたくなった。 まぁ、でもいいところがあるかも って粘ってみても。 文字面だけを追ってみても。 いくら経っても気分は治まらない。 何を表現したいのかが、 ボクにはさっぱりわからず… もう二度とこの作家の作品とは 巡り会わないと思う。
0投稿日: 2015.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログどれも素敵だった。 <象られた力>は、まるで長編を読んだ後のよう。 中短篇集だからといって、休憩に読めるなんて思っちゃだめだ。 時間をかけて、音楽もかけず、ただじっくりと、飛さんの表現する世界に、ひたすら絡みつくのが最高だ。 やっぱり飛さんは素敵だ。 たぶん、飛さんの文章は過剰に映像的だし、色彩と音の描写がものすごく装飾的で、それが美しくてたまらない。 これは、テーマから考えたら目くらましかも知れないけど、これだけ美しく、そして凝りに凝って作られた設定に酔えるのが、飛さんの素敵さでしょ?と思っている。 (だいたい、こんなテーマを現実の不安として抱えたり理解する人間なんて、病的か、さもなきゃオクスリ的だと私は考えている。 少なくとも私の乏しいSF系本棚の中で、こんな思考と世界の捉え方に近くて優しくしてくれるのは、徹底的に矯正してくれようとする神林さんか、とぼけていてくれる円城さんか、美しさに溺れさせてくれる飛さんか…ってとこである。) <デュオ>は音・音楽の描き方が本当に豊かできらびやか!! それだけでも素敵だけど、「人が生きているかどうかは微妙な問題です。」 人々の記憶の合間に、情報の渦の中に、まるで誰かが存在するように振舞う何かを、感じる時のことを考える。 見えない敵と戦っている、みたいなものかもしれない。 その怖さについての話。だとおもう。 <呪界のほとり>は、大好物メタフィクション。 こんなに明るく書いてくれていいのかしら! とっても好き。 <夜と泥の> 未知の世界で、考えもしないウイルスを、知らぬ間に取り込んでいて、その世界の共感場に抗えなくなること。 人類の希釈化。 「新たな環境で、新生活で、あのヒトは変わってしまった、私は変わってしまった?」そんな陳腐な話にすり替えたって良いのかも知れない。 でもそれを良しと出来ない、自己と他者の境界で恐怖に佇む者には、こういうお話じゃなきゃ救われないのだ。 <象られた力> ちからとかたち。 私という形を保つ、内側からの力と外側からの力、内側の思考と外側の思考のぶつかり合う、この身体の表面。 わたしという形を保つ、私という形を作るために、適切適当なエネルギーと思考と他者の関わり。 その不安について。 この日常的な恐怖について。 ものすごく凝った設定で、映像的に装飾的に描いて酔わせて、最終的に消滅という退廃的な甘美さに引き連れて行ってくれる飛さんの優しさったら、とんでもないなぁと思う。 大好き。 【読後追記】 消えた星<百合洋>ユリウミの、図形言語。 そしてやはり消えたはずの星シジックから発信される“シジックの歌”。 百合洋のエンブレムが表す文脈と情動。情動は人間が環境に最適化するために作ったツール。そのツールを制御するコマンド。言語と…そして図形。 読後も頭が<象られた力>で溢れる。次になにを読むのが適切なのか、わからない。 『世界の野生ネコ』でも眺めるしかないか。
1投稿日: 2015.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログイマジネーションの奔流、理性ではなく肌で理解する物語。 鴨が飛浩隆氏の作品を初めて読んだのは、2年前に読んだ「日本SF短編50 V」に収録されていた「自生の夢」。正直言って、まったく訳が判りませんでした。でも不思議と気になって、海外での評価が高いというハロー効果もあってか、この短編集を手に取ってみました。 で、読んでみた感想ですが、正直なところ、やはりよく判らない、と思います。例えばSFを読み慣れていない友人にこの作品を判りやすく紹介せよ、と言われたら、鴨にはできないと思います。ポイントを押さえて巧いこと言語化して要約することが難しい作品だと思います。 元々言語で記述されている小説なのだから、「言語化が困難」というのは言い訳に過ぎないということはよく理解してるつもりなんですが、本当にこの世界観、言語だけでは押さえきれないんですよ。「絵になるSF」の極北、音や視覚や嗅覚といった五感を駆使して読み解くワン・アンド・オンリーな世界観です。表題作の視覚的なカタストロフィは特筆モノですね。この作品を母語で読めるということは、日本人SF者としての至福のひとときかもしれませんね。 こうした「認識のパラダイム・シフト」を前提としたSFは、実は日本SFの得意とするところなのではないか、と鴨は感じています。SFという文学フォーマットでこそ挑戦可能な分野だと思いますし、今後もより先鋭的な作品を期待しています。
1投稿日: 2015.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「デュオ」 二転三転する圧巻の展開。ゾクゾクした。名無しは今どこにいるのだろう。サスペンスホラー風味で怖かった。 「呪界のほとり」 栗本薫みたい。ファンタジーっぽいSF。他の3つと比べると微妙。 「夜と泥の」 沼の戦いの描写が引き込まれる。美しい物語。これは好きだなあ。 「象られた力」 オチは不要な気がした。これはホラ話ですよ、ってわざわざ言われなくても分かっているわけで。発現のエンブレムのアイディアが秀逸で、図形が溢れ出すイメージに圧倒された。
0投稿日: 2015.04.192-3回読まないと、腹落ちしない気がする
日本SF対象を受賞している「傑作集」とのことなので、読まなきゃ!と思ってチャレンジした。一読では「ちょっと難解」というのが率直な感想。4編それぞれが独立した世界を描く無関係の作品なので、1つでも自分なりに楽しめたらラッキーという思いで読んだが、いずれも腹落ち感は微妙。一方、それぞれの短編は100ページくらいしかないのに、その中で4編それぞれの世界観の広がりや緻密さを表現しきっているのが見事だと感じる。個人的には表題の「象られた力」の設定が一番好みで、言葉や記号が人間の深奥の何かのスイッチになるという世界は、川又千秋の「幻詩狩り」とかテッド・チャンの「あなたの人生の物語」を思い出しながら読んだ(これらの作品は読みやすいし、シンプルに面白いです)。通して美術館で作品を味わっているような感じで、ある意味「この良さが分からないのは、自分が未熟なのかも」というような気にちょっとさせられた。
3投稿日: 2014.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
WishListは「当時読みたいと思った」本が大量に入っていて、自分でもどうしてこれが読みたくなったかわからないのが多々あるのだが、これもそう。後からWikipediaで見直して「ああ、ラギッド・ガールの人だったんだな」と思いだしてようやく入っていた理由がなんとなく推測できた(ラギッド・ガールはアンソロジーで読んだので、著者名を失念していたのであった)。 本編には表題作を含めて、4つの短編がおさめられている。個人的には幻想的な雰囲気が全体を通じて漂っていて、最後にストンとおとす「夜と泥の」がお気に入り。 本書はハードSFという感じの表現もあるが、基本的にはファンタジーとSFの間ぐらいに位置していると思う。特に作者の世界の描き方が、「とても幻想的なのに、かつ写実的」という感じで、騙し絵を見ているような気持ちにさせてくれる。特に表題にもなっている「象られた力」の後半は、映像的な描写が続いて映画好きにはたまらない展開が待っている(が、映画で表したら陳腐になってしまうだろうので、たぶんそういう無茶はしないほうがいいのだろう) 全作品ともに最後の数ページでストンとおとす・・という趣向がしかけられていて、ミステリーとしても楽しむことが出来るので「SFはちょっと・・・」という人にもお勧め。
0投稿日: 2013.12.22伝説の作家、飛浩隆の初期SF作品集。
五感を刺激する作家である。眼に見えないものを表現してみ(魅)せるのがうまい。「象られた力」では、視覚。「デュオ」では、聴覚。「夜と泥の」では、そのすべて。という具合に感覚的でイメージを喚起するシンプルな言葉が散りばめられており、読んでいるとこちらが苦しくなってくるような緊張感がある。かなり推敲して書いているように思えるほど、言葉の1つ1つが際立っており非常に稀有な作家である。 ただ、「デュオ」以外は、何かシリーズ物の途中の話を1つ読んだという感じで達成感がないというのが正直な印象。物語も難解だしね(というか感覚的)。グラン・ヴァカンスもそうだったのだが、謎が謎のまま残されており、読書感が良いという人とそうでない人に分かれるかと思う。私は、本作では後者でなにかすっきりしない気持ちになってしまった。 寡作な作家であるだけに貴重な初期作品、SF好きなら読んで損なし。
5投稿日: 2013.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログおしゃれで品位ある文体で書かれていて、SFファンタジーが 盛り上がっていた頃の元気ある雰囲気を強く感じる短編作品集です。 しかし、古臭いかというとそうでもなく、 特に、表題の「象られた力」が短編ながら、面白いアイデアの作品です。 もっと状況設定を入り組ませて、長編でじっくり読んでみたいと 物足りなく思いました。 とにかく、作品のアイデアにデザインが持つ力や音がもつ力など、 身近にあるものに対して、もしかしたらある特異な力があるのではないか… という空想科学領域の漠然とした妄想思考の種を 誰もが抱えていて、それをうまくキャッチして作品 にしているなあ、と感じました。 ある一定の共感力で読者を近づけて、楽しませるという、 アイデアの新奇性だけ惹きつけるのではない、 描写力のあるSFファンタジーです。 砕けた口語調小説が好みの方には嫌煙されがちの語り口ですが、 露悪的な自伝風小説に食傷ぎみなら、 この空想科学のもつさわやかな風で 脳みそがかなり涼やかになるはずです。 脳みそミント効果ありの作品。
0投稿日: 2013.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ(デュオは未読) どうも俺には難しい。 表題作「象られた力」はのちの作品『廃園の天使』に繋がるような頽廃的・破滅的・官能的な展開を見せるが、しばしば視点の転換が行われるため話の筋を理解するのにいくらか難儀した。 時間のある時に一気読みした方が楽しめそう。 通勤通学のおともには向かないかと。 「呪界のほとり」 展開が突飛すぎてわけがわからないが登場人物が織りなすコメディのような雰囲気が印象的な一作だった。
0投稿日: 2013.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年ぶり再読。飛浩隆の80~90年代に書かれた中編集。『象られた力』は好きすぎて絶対に映像化してほしくない小説の一つ。ちょっとした描写すら美しすぎて途中からずっと泣き笑い状態。この可能性を映像なんて形に収斂させちまうのはもう犯罪ですよ。後の『グラン・ヴァカンス』にも使われるモチーフも時折見えて、ファンとしては「あれの原型はこれかあ」って遡ってみる読み方もできて嬉しい。『デュオ』のホラーテイストもいいし『呪界のほとり』もわくわくするし『夜と泥の』の雰囲気も浸れるんだけど、やっぱり表題作ががんと抜き出ている。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログSF中短編集。「デュオ」では感応をめぐる幻想を、「呪界のほとり」ではメタフィクション的な諧謔を、「夜と泥の」では記憶に馳せる思いを、「象られた力」ではかたちに対する欲望を、ひしひしと訴えかけていた。 作者の提示する世界観や情景はあまりにも豊潤すぎて、私の想像力では到底追いついていけないほど。 この美しく力に満ちたモノに、どうにかして触れたい――まさしく、そのような欲求に駆られる作品だった。 単純に完成度で見たら、少し荒削りにも感じられる。
0投稿日: 2013.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログよくよく考えてみると、SFって実はあんまり読んだことないなー。ついていけるかなー、大丈夫かなー。と思っていたのですが、なにやらエレクトロニクス的な難しい単語が飛び交ったりだとかそんなことはなく、どちらからというとファンタジー要素の強い作品だったので読みやすく、そしてなんだか懐かしい気持ちになりました。 小学生の頃、土曜日の昼下がり、ドラクエ3で友達の名前のキャラクターを作って世界を冒険していた時のことを思い出してしまうような、そんな感じ。ちょっと違うかもしれないけどまあ、大体そう。いつだって僕らは何かを懐かしんでいる。というか主にドラクエを懐かしんでいる。 「デュオ」という、結合双生児が天才ピアニストという話と、「呪界のほとり」という、ドラゴンと一緒に宇宙を旅する男の話が面白かったです。でも、「呪界のほとり」は、「俺たちの旅はこれからだ!」的な終わり方になってしまうのが残念でした。 シリーズ物にしたかったけど、結局できなかったとのこと。そんなー。私財を投げ打ってでも続編を買う覚悟は出来ていたのに。
0投稿日: 2013.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ『廃園の天使』シリーズが良かったのでこちらも購入した。 8〜90年代、『SFマガジン』に発表された中短篇集。映像的な文章はこの頃から変わっていないようだ。 音楽ものの『デュオ』、この本の中ではホラーテイストが濃い目の『夜と泥の』が好み。
0投稿日: 2013.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「デュオ」ミステリ要素たっぷり、音と匂いの描写が素晴らしい。ページを捲る手が止まらない。「呪界のほとり」コミカルなキャラとテンポの良い展開でページを捲る手が止まらない。続編希望。ジジイ最高!「夜と泥の」視覚的・聴覚的な描写が素晴らしい。全体を通しての緊張感にページを捲る手が止まらない。「象られた力」視覚的描写が美し過ぎてお腹いっぱいです!次のシーンが「見たくて」ページを捲る手が止まらない。アニメとかにならないだろうか。
0投稿日: 2012.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ後書きにも触れられていますが、どの話も感覚に訴える話で、その刺激が心地良かった。 一番お気に入りの話は「デュオ」です。<ピアノ><死>がメインで扱われていて、音感やぞっとする冷たさを、イメージを喚起する絶妙な文体を通して感じます。 実は、以前友人からこの本を借りて、「デュオ」の妖しい魅力が忘れられなくて、今回自分で購入して再読しました。 初読で味わった衝撃的な感動は得られなかったけれど、じっくりと「デュオ」の魅力を味わうことが出来たと思う。
0投稿日: 2012.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ理想の文体かもしれない。 憧れは山尾悠子氏、それはこれからも変わらないが、自分が目指すとしたら。 肉体は五感を支配しているだろうか。 あるいは、五感が肉体を支配するのだろうか。 文字を読むということが、ここまでの体験をさせてくれるのだ。 そんな満足感をもたらしてくれた一冊。 しばらくは余韻を引きずりそうだ。 五感が、騒ぎすぎて。
1投稿日: 2012.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作がとにかく好みの設定すぎた。 突如、忽然と消えてしまった星の遺産である図形言語。人の感情の動きを呼び覚ますエンブレム。その文様が数千個多重らせんに収められた高さ30センチの円柱形ダイヤモンド製の“エンブレム・ブック”。それを読み解くことで何が起こるのか… ああ、なんてときめく設定! それこそ(綴り違いだけれど)万華鏡のようにきらめく文様に翻弄されるようだった。 「デュオ」はSF的でもあるが、ミステリやホラーっぽくもあり、張りつめられた緊張感を楽しんだ。
0投稿日: 2012.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『THE FUTURE IS JAPANESE』で知った飛浩隆の初期作品短編集。 音やモノのかたちが持つ「力」がキーワード。SFらしい意匠はふんだんに出てくるが、感情表現や視覚的表現に割かれている言葉の「質量」が大変に豊富で、視覚・聴覚・味覚などの五官に訴えてくるイメージが強い。読後感はむしろ異世界ファンタジーという方がしっくりくる。 表題作の重厚な表現が炸裂する文章と、「呪界のほとり」のようなコミカルな語り口とが良いバランスでまとめられていて、緊張感とわくわく感が何ともいえない風味になっている。
0投稿日: 2012.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ飛 浩隆の短編集ということで読む。 グランヴァカンスシリーズ以前の作品でいささか違いがある。 それでも流用したギミックなどがでてくる。 「夜と泥の」と「象られた力」の2つは気に入った。めくるめく想像力と描写力に読みふけった。SFのお手本のような作品。この2つにでてくる惑星改造レンタル会社のアイデアはいくらでも続編がでてきそうなワクワク感がある。
0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ連作短編集。 他のハードSF作品と違ってエンタメ寄りの文章のため読み易い。 ただ表題作は文章は読み易いが章毎に一人称(計4人)や三人称の文章に変わったりして慌ただしく、説明も分かりづらいものが多く読み通すのは辛かった。 他の三編の中短編がそれぞれ面白かったのでこの点数に。これから読む長編も楽しみだ。
0投稿日: 2012.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりにSFものを読んだ。 本作は短編集。 状況や情景を想像するのがSFの楽しさの一つだと思うのだが、どの編もイマジネーションを刺激する作品だった。 気に行ったのは『デュオ』と『象られた力』。 前者は若干ミステリーやホラーテイストもありぐいぐい引き込まれた。 ラストのコンサートシーンはぞくぞくした。 後者は、世界観がかなり好みであった。 図形(形)が力や能力を発揮する発想や、ロフトの構造であったり、食や性的描写がとても興味深かった。 もっと早く読めば良かった~。
0投稿日: 2012.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ絶対だと思われた世界が、実はとても危ういものである、という事をまざまざと思い知らされるSF短編集。読み進めていて、アタマの中に新しいチャンネルが構築されていくような感じが、堪らない。表題作も素晴らしいが、個人的に巻頭の「デュオ」に痺れた。
0投稿日: 2012.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ堀→山本→野尻→飛っていう連鎖だ。1960年生まれで島根大学だそうな。近いなぁ。 どんでん返しが驚きの結末を彩るミステリー「デュオ」、作者の世界なのかな?けっこう凝った世界観を下地にした「呪界のほとり」、非常に風景描写が美しく筆力を感じさせる(ただし筋はイマイチの)「夜と泥の」、そして表題作「象られた力」と中編4編だ。 肝心の表題作はというと・・・・ちょっと長すぎる。あらかた筋書きが読めてからが長い。登場人物も多すぎて感情移入している暇がない。いい作品だと思うのだが残念。手が加わってるらしいので、オリジナル版を読んでみたいなぁ。
0投稿日: 2011.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭の一編「デュオ」が凄い。やけに描写のクオリティは高い上に、展開も落とし所も劇的。異様な読後感がしばらく消えないのだからこれは傑作なんだろう。 音楽SF?なのだとか。確かに双子のピアニストにまつわる話ではあるけれど。最近のSFの潮流も分からず「完璧な小説」という触れ込みだけで読んでしまったのが良かったのかどうなのか、グロテスクで確かに完璧。こんなの読んだ事無い。 他の作品の水準の高さも比類ない。間違いなく天才ですね。 その後(更に)傑作との「グラン・ヴァカンス」も危うくて。このネガな魅力には昔イタリアンロックに嵌った感を思い出した。手を出さない方がよかったかなぁ。
0投稿日: 2011.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも一気に読むのがもったいないし、短編を続けて読むと気持ちの切り替えが旨く出来ず物語があまり楽しめなくなるので、ボリューム自体はそんなにある訳でないないが、かなり時間をかけて読んだ。 どれも秀逸。 特に『デュオ』を読み終わった時はクラクラした。 『象られた力』も中盤〜最終局面の緊張感がものすごく、読み終わった時に息を大きく付くような気分。 飛浩隆は、合法で、健康に害のない、だけど依存性の高い読むドラックだと思う。
0投稿日: 2011.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「デュオ」 「そうです、私がかれをころしました。もう何年まえのことになるでしょうか」という語りから始まる悪魔的な魅力を持っている双子の天才ピアニストと調律師の物語。全体を漂う濃くドロンとした不気味さ、緊張や恐怖など情感の表現が素晴らしくラストに向け音楽とともに加速してゆくストーリーには圧巻だった。ラストのオチもまた背筋をゾッとさせてくれる。 「呪海のほとり」 まぁSFっぽいSFで面白かったと言えば面白かったがこの作品集の中では一番レベルが低いのかなと思った。作者も元々シリーズものにしようとしていたらしいのでそこまで作り込まれてはないようだ。 「夜と泥の」 年に一度夏至の夜に泥の中から生まれ、月光を浴びて舞い踊り、また腐り落ちて泥に還る少女。それを調査するために乗り出した二人の男達が経験する不思議な体験の話。この作品は特に五感を刺激してくる。泥の感触、生命の質感など読み進めるにつれ鳥肌がたった。 「象られた力」 この作品集の中で一番好きな作品だがなんと説明していいかわからない^^;そのぐらい凄い。正直一度読んだだけでは完全に理解できなかったのでまた読もうと思っている。美しく残酷な物語である。本当によかった。一切無駄のない文体に緻密な言葉の配置、その上に出来上がる世界には素晴らしく惹かれる。 どれもセンスオブワンダーを感じる作品ばかりで面白かった。やはり飛浩隆の本はいい。最高だった。飛さんの本は一冊の本を何度も読みたくなる衝動に駆られる。
0投稿日: 2011.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログきれいです。凄く綺麗。 音や形が目に見えます。まさに『象られた力』。 素晴らしい筆力。寡作にして佳作なのも肯ける。 今読むと、万丈とファフナーに笑った(名前がアニメのキャラじゃん。ファフナーはこっちが先だけど)。
0投稿日: 2010.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「デュオ」読了。不思議な話。構成としてはどんでん返し系なんだけど、それ以上に「名無し」をどう捉えるべきなのか...。音楽の知識があったら、より楽しめたのかもしれない。 「呪界のほとり」を読了。すいません、理解できませんでした。。。多元宇宙的な話なのかしら。SF的リテラシーがなくて困る。 「象られた力」読了。ミステリ的な手法で書かれているので、普通に楽しく読めた。が、この物語を理解できたのかと言われれば、全く理解できていないんだろうなぁ。エンブレムがコマンドになっている、ということはわかるのだが、エンブレム自体が意思を持つ、的なのはどういうことか分からん。。
0投稿日: 2010.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ4篇が収められたSF中・短編集。文体も描かれている世界も幻想的で美しい。聴覚や視覚などが感じる「美」を言語化しようとする描写力に五感と想像力が強烈に刺激される。表題作が特に良かったかな。
0投稿日: 2010.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ文句なしの星5つ!めちゃくちゃ面白いです。たしかにSFなので難しい部分もあったりですが(そこが格好いいのかもしれませんけど)分かんないながらにどんどん読み進めたくなるストーリーの面白さ、キャラクターの魅せ方、情景描写の美しさ。他の作品も読んでみたい!
0投稿日: 2010.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログバラエティに富んだ中短編集?でした。 作品ごとに印象が違うので、まぁ良く分からないけど、もしかすると好みかもしれない(漠然としすぎだろ
0投稿日: 2009.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ラギッド・ガール」があまりにすごかったのでかなり入れ込んで読んだのだけど、うーん、これは…。どの短編にもさほど惹きつけられなかった。 「離陸」しないのだ。SFに限らず(SFにおいて顕著だが)ある種の物語はどこかの時点で加速して宙へ駆け上っていく。そうとしか言いようのない瞬間がある。物語の力に連れ去られ、そこから世界を新しい目で見ている時の高揚した気分を求めてわたしは本を読む。言葉にしがたい飛翔の感覚がそこにある。 五感に訴えかける筆者の描写力はデビュー作から際だっている。でも、色彩あふれる世界にどうにも入っていけなかった。「廃園の天使」シリーズでは風の流れや匂いまで感じ取れると思うほど「連れ去られて」いったんだけど。 これで本になったものは全部(と言ってもたった三作)読んでしまった。ああ早く「数値海岸」の世界へ行きたい。筆者はインタビューで「当分出ない」と断言していた。何でわたしの好きな作家は寡作なんでしょう。でも気長に待つよ。原リョウも。
0投稿日: 2009.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作を含む四編の中篇集。 緻密で芸術的な表現は読んでいるとある種の酩酊感すら覚える。音楽や図形といった文字で表現する事の難しい事象を綿密に形容する本書は独特の風味を醸し出している。 表題作である「象られた力」そのもののように、まるで文字が意思を持って力となって読者を圧倒する。それが先を読みたいという思いになって、読む手を進めさせられるような感じ。読後には、独特な、爽快感とも言うべき印象を与えてくれる。
0投稿日: 2009.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ余裕がある時に再読したい感じだなあ。SFはやっぱし密度が濃いっていうか消化するのに時間がかかる。ということで星みっつ。
0投稿日: 2009.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ飛浩隆パート2。 つらい現実から逃げるためには、描写力に優れた作家の作品って、雅に良薬。 私は、それほど文章を映像化して読むタイプの読み手ってわけではないのだが、否応無しに映像が流れ込んでくる、作家という人たちがいる。 まさに希有な才能の持ち主。 秋山瑞人と、この飛浩隆は二大描写力作家。もちろん文章力も半端無い。 山尾悠子も似てるんだけど、彼女は一瞬焼き付いたような絵が浮かぶことがあるんだけど、なかなか動き出さないんだよな〜 このタイプとは別に「文章」「情報」が頭に流れ込んでくるというタイプの作家もいて、冲方丁がその筆頭だし五代ゆうもそのタイプな気がする。 どちらも好きなんだけどね〜
0投稿日: 2009.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ未知かつ良くわからないものを描くことと、単純に文章自体を「上手い」と思わせる作品。批評家気取りではないですが、技巧派っていうのはこういう作品のことでしょうか。短編の中の1つ「呪界のほとり」に登場する老人のある言葉に鳥肌が立った。
0投稿日: 2009.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクロググラン・ヴァカンス 廃園の天使 を読んでもの凄い衝撃を受けたので、購入。 グラフェナウアーズ怖いよグラフェナウアーズ。
0投稿日: 2008.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段は全く読まないSF小説。 サイエンスに興味がないからなぁ、と思ってたら そっか、SFもフィクションだよな、と気付かされました。 最初の「デュオ」が一番面白かった。 シャム双生児の神童ピアニストと調律師の話。
0投稿日: 2007.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「デュオ」はSF幻想怪奇小説とでも呼ぶべきか。私には一番しっくり来た作品で、その末尾に提示されている世界観は、やがて『グラン・ヴァカンス』を産むことになる胎盤ではないかと思われた。表題作も、いったん精緻に築き上げた世界を、圧倒的な無残さで崩壊させていくところが、『グラン・ヴァカンス』と通じるのではないかと思った。もちろん、こうした想像力の「核」のようなものこそ、作品の(作家の)力の源泉なのだろう。「夜と泥の」は、宇宙進出に伴う人類の希釈化という概念ないしテーマを据えつつ、地霊めいた沼・泥・有機体の世界が不思議な美しさを放つ。植民地主義批判という政治的な側面もあるのかもしれない(中国系の人物が主要人物であることとも、関係ありそう)。「呪界のほとり」は、そういう理屈をあまり感じさせない、ユーモラスな作。書き手にとっての息抜き、という気がして、それはそれで、のびのびした読み心地が悪くはない。
0投稿日: 2007.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ格好いいーーーーーーっ!(はぁと) どの作品もイメージ喚起力が強いヴィジュアル的な作品で、非常に視覚や味覚を刺激される物語ばかりだ。硬質かつ的確な言葉で紡がれるのは、幻想的で魅惑的な異世界ばかり。構築された世界観にうっとり耽溺してしまう。SFではあるものの、幻想小説としても堪能できるかと。今まで読まずに積んでいたことを、非常に後悔した作品です。素敵!素晴らしい!
0投稿日: 2007.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ五感を刺激する精緻で豊穣な文体を駆使して、思弁的アイデアによって構築された世界での人々の意識の変容を描く作品4編を収録。表題作と「デュオ」はオールタイムベスト級の傑作。イーガン、チャンの最高作に比肩しうるレベルに達している。
0投稿日: 2006.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ例えば大友克洋の「AKIRA」で鉄雄の力が暴走するところ、僕はそれを外側から一つの現象として見るわけです。一方で「象られた力」では、ホテル・シジックの崩壊を圓として体験することが出来る。こういうことこそが、マンガや映画とは違う活字の力であり、小説家に求められる資質なんだと僕は思う。飛さんの小説を読むと、そういうことを強く感じてしまう。 それから飛さんの小説の登場人物は見事なまでに饒舌である。これはきっと、SFであるからなんだろうと思うけど、読んでいる途中はほとんどそうである事を感じさせない、巧さなんでしょうね。 もう一つ感じるのは、面白いSFって良く出来たミステリーになっているってことですね。 今のところ「夜と泥の」が一番好きです。誰かの何かに比較したりするの良くないのだろうけど、漆原友紀「蟲師」とか、大友克洋「彼女の想いで...」などを視覚的に思い浮かべながら堪能しました。 ところで、この本を去年の秋頃に松江のある書店で買ったんですが、その日ちょうどその店で飛さんを見かけたんですね。で、声かけようかと思ったけど、手にはまだレジを通していない現物を持っているし、「今から買うところなんですよ」っていうのもマヌケだよね。なんて思っているうちに見失ってしまいました。こう見えて、小心者なんですよ、おいら。 そうだ、今、思い付いたんだけど、「面白いSFって良く出来たミステリーになっている」ではないですね。小説ってもともとがミステリーなんだよね、きっと。ミステリーっていうのは、ジャンルではない、きっぱりと言い切ってしまうのだ(何故、今?)。
0投稿日: 2006.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログSF大賞受賞ということで読んでみた。短編集。中編込み。全体として感覚がとろけて持って行かれるような興味深さがあった。文章で架空の世界を描くことで、そんな風になるというのは素晴らしい。世界の終わりを感じさせるようで、それでもまだ続く。SFってすげえなと思わされる。ひっくり返る伏線と、毎度驚いて手に汗握る自分。SFを書くべくして生まれた優れた作家の作品がここにある。あまりに面白いので、読んでいる途中ですでに他の作品も購入してしまった。
0投稿日: 2005.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこれほど文章の豊潤なSFを読んだのは初めて。饒舌ではない、むしろ無駄のない文体なのに、想像もつかない世界を言葉の力で鮮明に浮き上がらせてくれる。 言葉も、世界もとても魅力的。物語に浸る歓びがじっくり味わえる。 表題作が特に印象強かった。
0投稿日: 2005.11.24
