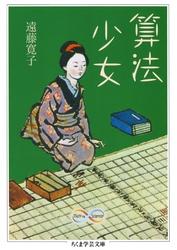
総合評価
(95件)| 14 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 5 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白かった。でてくる人物がとても優しくて愛おしい。ひらがな表記がやや読みにくい(気にするほどではないけど。)のだけど、児童文学だったところから来るのだと思うと納得。 千葉あきの優しさや算法への想いが伝わって、ラストはなんだかうるっとくる。 江戸時代やもっと万葉の時代から九九などの算法は開かれていて、秘中の口伝みたいな形でしか伝えられず滅びたのは悲しい。しかし日本ならあるあるなのかもしれない。西洋技術に負けたとはいえ、昔の人はえらかった!と感じさせる生き方を伝えてくれる素晴らしい良書。たくさんの人に読んで欲しいので、あとがきの復刊までの道のりにも感激してしまった。
21投稿日: 2025.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ壺中の天。お酒を飲む楽しみという意味だけではなく、この世とは別世界のような楽しみを持つことを現す。和算が江戸の庶民に親しまれていたことがよくわかる。今でいうクイズのような感覚かもしれない。アハ体験を楽しんでいたのだろう。算数とか数学に目を向けてみたくなった。
3投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代の和算書「算法少女」を題材とした物語ですが、作中の人物を通して著者が語った学問に対する考え方には共感を覚えました。次は算法少女の解説本に挑戦したいです。
0投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルは、実在する江戸時代の和算の本と同じもの。この物語では、町医者の父と、父に算法の手ほどきを受けた娘が一緒にその和算書を著した、その経緯が描かれている。 算法の実力があることで、町方の娘が大名家に声をかけられたり優秀な学者と交流を持ったりと、世界が広がっていく。 学ぶことを楽しみ、算法の素晴らしさを世に広めることに情熱を燃やす人々が、学生時代数学が大の苦手だった私には、なんだかまぶしく羨ましく見えた。
0投稿日: 2023.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログかわいらしく、想像をふくらませる名タイトル! 実在する「算法少女」という江戸時代の書物は、とある父と娘により書かれた和算(当時の日本の数学)の書。この「算法少女」に着想を得た著者による、同じ「算法少女」というタイトルをつけた少年少女むけの時代小説です。児童文学なのでとても読みやすく、学問に打ち込むことの豊かさを感じることが出来ます。 個人的には、作中に出てくる数式で謎をとくような、数学ミステリ的からくりがあればさらにワクワクするストーリーになったかもと思いましたが、江戸人情にあふれているとてもいい物語です。江戸の町の楽しさだけでなく、宗派によって学問が分断されることや、育ち・身分で人間が分断されることの悲しさも自然に描かれます。主人公のあきが、屋敷通いの指南役でなく市井の塾講師を選ぶことで、本当に豊かであることとは何かを教えてくれます。 文庫版あとがきに、この小説版「算法少女」復刊をめぐる経緯が書かれているのですが、そのリアルストーリーが、本編のフィクションと重なるような不思議さを感じます。江戸期代に「算法少女」をしたためた娘とその父。本編の主人公あきとその父、そして著者とその父。3組の親子が、時空とフィクションの壁を超えてひとつに重なるのです。事実は小説より奇なりと言いますが、まさに小説になるような奇跡にため息がもれました。
0投稿日: 2022.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、昔学んだ鶴亀算を思い出した。 方程式で解くのとは違い、解答に至る考え方が独特な面白さで興味深かった思い出がある。 考え方を学ぶという意味では、非効率な方法であっても今の小学生にもぜひ教えてもらいたいと思う。 さて本書だが、実在の和算本を題材としているらしい。出てくる主要な登場人物も実在の人物のようだ。 ストーリーはテンポの良い展開と多少のミステリ的要素を加えた物語で、和算に興味がなくても楽しめる小説。
2投稿日: 2021.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代に幸運な偶然と、本人の熱意で和算を習った女の子の話。 丁寧な解説もついており、江戸時代の和算流行の様子を窺い知ることが出来る。 『きりしたん算用記』とともに読むととても味わい深い。
13投稿日: 2021.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際に存在する書籍「算法少女」が書かれるまでの生い立ちを創作するという発想が非常に面白かった ストーリーもしっかりしていてもしかしたら本当にこの通り算法少女は書かれたのかな 算法に限らず何かやらなきゃと思った
1投稿日: 2021.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ『算法少女』というのは、実際に存在する和算の本である。安政4(1775)年に出版され、著者は壺中隠者・平章子とされている。現存するのは数冊という稀覯本であるが、国立国会図書館のデジタルコレクションなどで見ることができる。いかつい漢文と仮名混じりの柔らかな和文が代わる代わる出てくる。ところどころに和算の幾何問題の図が挿入されている。 この著者については、長らく謎とされてきたが、昭和の初めに数学史家の研究により、千葉桃三という医師とその娘のあきであることが判明した。漢文部分は父、和文部分は娘の書いたものと思われる。 明治維新前の和算の本としては、女性が著者に名を連ねているのはこの本のみである。 本書は、この江戸時代に出た和算の本を元に、著者・遠藤寛子が空想をふくらませ、あきがどんな風に算法に親しみ、本を書いたのかを物語仕立てにしたものである。 千葉桃三やあきについては知られていることが多くはないため、大部分は著者の想像ということになる。だが、なるほどこんな算法好きの女の子がいたのかもしれないと思わせる、生き生きとした少女の姿がそこにある。 あきは父の手ほどきで算法に慣れ親しみ、時には母が眉を顰めるほど、夢中になって問題に取り組む日々である。当時、和算の学習者は、難問を考え出し、それが解けると、問題を絵馬にして神社仏閣に納める習慣があった。算額と呼ばれるものである。あるとき、あきは友達とお寺参りに行った際、算額の解答の中に誤りを見つけてしまう。それはあるお侍が奉納したものだった。年端も行かない娘に間違いを指摘された侍はいきり立つが、確かにあきの方が正しかった。しかし、これをきっかけにあきは騒動に巻き込まれてしまう。 関孝和の流れをくむ関流と上方流の学閥の対立。江戸の出版事情。数学好きのお殿様。無学な町の子たち。 さまざまな困難と闘いながら、あきは好きなことを極めつつ、自分の進むべき道を凛と決めていく。しゅっと背筋の伸びた少女の姿が清々しい。 著者・遠藤が和算書『算法少女』を知ったのは、在野で幕末から明治の理化学書を収集していた自身の父からであったという。幼い頃に漏れ聞いたこの話を、長じて愛すべき作品に結実させた。 元々は1973年に別の版元から出版され、一度は増刷が打ち切られた。だが数学関係者らの尽力により、2006年にちくま学芸文庫として復刊が果たされた。このあたりの経緯にも著者あとがきで触れられているが、なかなか興味深い。
4投稿日: 2021.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸で出版された女性がかかわった数学の本『算法少女』を題材に作られた物語。読みやすい歴史小説の趣で引き込まれながら、実在した女性の算法家の存在を近いものとして感じられた。 身分も土地も派閥も性別も超えて、正しいか正しくないかだけ、って潔い。 なんか面白かったなー。
0投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代のリケジョの話なのだが、非常に面白い。同名の元ネタの本は、安永4年(1775)に刊行された和算書。本書は、最初に岩崎書店から1973年に出版されている。児童向けではあるが、大人が読んでも楽しめる、数学が苦手でも大丈夫。漢字にふりがながふってあるし。あと、挿絵が秀逸。
5投稿日: 2019.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「算法少女」という本は実際に江戸時代に医者の父と娘によって書かれた本で、名前もわからないその父娘をモデルに和算に取り組む少女のことを書いた小説。 著者も学校の先生とのことで、中高生向きかな。眼差しが優しい。
0投稿日: 2019.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ和算、円周率などところどころ数学要素も出てくるが、数学の話というより、数学の才能があるが、親子の話し、流派の違いによる、時代背景的な要素も物語を盛り上げるようなのだが、正直面白みを全く感じなかった。 4倍速で理解がおぼつかなかったからか。。
0投稿日: 2019.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代に実際に出版された和算書「算法少女」から物語をつむぎ出した児童書。 とある出来事から和算が得意の少女「おあき」に、大名家の息女への和算指南の話が持ち上がる。しかし、流派の違いや大人のエゴが立ちはだかり……。 学ぶことの楽しさ、一途に続けることの意義、お金のためではない志。 児童書ではありますが、大人も充分に楽しめる本です。
0投稿日: 2019.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2007/6/8 遠藤 寛子さんの 「算法少女」と言う本を読みました。 江戸時代の人というと 庶民は 寺子屋で 読み書き算盤、 侍は 孔子の教え などと思っていましたが、 算数どころか高度な 「数学」 を競い合っていたんです。 ここに登場するのは、小学高学年から中学生くらいの 女の子、だけど すごい! 大人顔負け しっかりしてる・・・。 そういえば、私も5、6年生の頃、クラスの子らと 難しい算数というか幾何の問題に 夢中になっていましたっけ もともと「算法少女」と言う題の本は、江戸時代にこの少女が書いたもの。 その話をふくらませて 遠藤 寛子さんも同じ題で 「算法少女」を書き、箕田 源二郎がステキな 挿絵を描いたものを、私は読んだわけです。 とてもよい本なのに、いちど廃刊になり このたび 復刻されたと言うことなので ぜひ 読んでみてはいかが?
0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ壷中の天(こちゅうのてん)、いい言葉ですね。俗世間とは別世界を持っていた方が精神衛生上、健全な気がします。 数学で才能ある少女の話で、家賃も払えなくなるほど数学の本を買ってしまうお父さんの話とか、πの求め方の話とか、才能あるのに屋敷に奉公に行きたがらない話とか、さらさら読めて、ちょっと面白かった。
0投稿日: 2018.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ万葉集に九九が登場する行(くだり)。 「二二」と書いて「し」と読んだり 「二十五」を「とお」、 「十六」をしし」と読むものがある。 なんともすてきな遊び心。 こどものころは、こんな文字遊びも愉しいもの。 1973年の本 舞台は江戸時代。 言葉使いが美しく、読んでいると、心地よい。 美しい日本の言葉が自然と身に着くように感じ入る。
0投稿日: 2018.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだか児童文学のような文体だと思ったら、1973年の本だった。それが復刻されるのは凄い。内容はもっと数学絡みで快刀乱麻かと思ったけどあまり盛り上がらないまま終わってしまった
0投稿日: 2017.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ父・千葉桃三から算法の手ほどきを受けていた町人のあき。ある日、その噂を聞きつけた久留米藩主・有馬候に姫君の算法指南役を申し付けられますが…。安永4(1775)年に実際に刊行された和算書『算法少女』の成立をめぐる、歴史小説です。
2投稿日: 2017.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年5月31日読了。 とても興味深かったし、面白かった。『天地明察』を読んでいたからいろいろ内容もわかって楽しかった!
0投稿日: 2016.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代の和算書に『算法少女』という書があるそうです。 平章子という女性が父親・千葉桃三の協力の下に書いた書物だそうですが、詳細は不明。 この執筆の際にどのようなやり取りがあったのか、作家の遠藤寛子さんが想像して描いた物語です。 主人公千葉あきも、その父親千葉桃三も、その他有馬頼徸も、藤田貞資も中根宇多も本多利明も鈴木彦助も山田多門も木賃宿の子どもたちも町の子どもたちも谷素外も、各々が自分に与えられた境遇の中、不満も言わずあきらめず最大限に学問を学び・楽しみ・一生懸命人生を送っています。 清く楽しく美しく。学問や人生に対する姿勢を考えさせられます。 「数学資料館」というサイトでは 「この本は小学生から大人まで、とくに高校生の時一番読んで欲しい本である」 と書かれています。 確かに、私もそうありたかったですね。 若い時は、なぜ勉強するのか、特に数学なんて何の役に立つのか、と反発するものですが、本来、和算にしろ学問にしろ楽しいものだったのです。 ただ、現在は、ゲームなどの刹那的な楽しみにあふれているので、学問の楽しさに気付きにくい時代です。 学校の先生方の教え方の工夫が必要かと思われます。 その意味で、本作品『算法少女』を高校の授業に用いたという高校の先生は素晴らしいと思います。 その先生をはじめ、色々な先生方の運動で、絶版になっていた本書が復刊されたという物語もあったようです。 この『算法少女』、1973年に岩崎書店の「少年少女歴史小説シリーズ」の一冊として出版されたそうです。 ということは、私が小学生や中学生だった頃の図書室に入っていてもおかしくはない状態です。 ところが40を越える今まで、本書『算法少女』について知る機会はありませんでした。 (そういえば進研ゼミの情報誌の「おすすめ本」コーナーでチラッと見たような気がします。) 今回、FeBeのポイントが失効する前に何か購入しようと思って探していたら、面白そうだったので購入したわけです。 オーディオブックだと読む手間が省けて気楽ですが、数式や図形・挿絵・解説などが見られないという一長一短があります。 私も中学や高校時代に本書を読んでいれば、人生に目的意識を持ってもっと良い人生を送っていたかのう。 実際は、その期間は精神を病んで好きだった学問や読書をする気力すら無くして人生から滑り落ちていたわけです。 若い時期に本書とめぐり合う機会がなかったこと自体が、私が人生に失敗した象徴なのでしょう。 http://d.hatena.ne.jp/nazegaku/20160917/p1
0投稿日: 2016.09.17中学生の頃の自分に読ませたい
40年ちょっと前のジュブナイルものですが、あとがきにもある通り、出版社に重版を断られながらも、ついにはちくま学芸文庫から出版社を変えて刊行された、というものです。 江戸時代の算術や算術書「算法少女」を題材に、学ぶこと・解くことの楽しさが伝わってくる小説です。 算術を題材にはしていますが、算術の問題ばかりが出てくるというわけではないので、算数・数学が苦手な人でも楽しめると思いますが、好きならさらに楽しめます。 作者が教師だったということもあるのか、流派や出世にこだわらずだれでも自由に学ぶこと、それ自体の楽しさが強く伝わってきました。中学生高校生くらいの読書感想文の題材によさそうな本ですね。 学生の頃にこの本を読んでおきたかったと思いました。
1投稿日: 2016.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログほのぼのする本。 ファンの支えがあっての復刻、心にしみました。 広い視野を持って、と優しく背中を押してくれます。
0投稿日: 2016.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
元々が1973年に発刊されたものとは思えないほど、読みやすくそして楽しめる小説でした。 所々に和算の問題が差し込まれているものの嫌らしいほどでなく、計算が嫌い!という人でも気にせず読めると思います。 行動力があり、そして算法が趣味となるほどの頭脳もあり、そんな主人公「あき」が終盤、競争相手の宇多と共に手まりをする姿には、本来の女の子としての姿が垣間見え、なんとなくホッとさせられました。 現在私達が普通に計算方法を学べているのは幸せなことだなぁ...としみじみ思いました。
0投稿日: 2016.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ千葉あきという実在の女性が,このような本を出していたことに驚いた.江戸の町人文化は奥が深い.生き生きとしたあきの先生ぶりや,算法にかける意気込みなど,とても面白かった.
0投稿日: 2015.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語としての面白みは少ない。けれど、この時代を数学という学問を通して感じることのできる貴重な一冊。 数学好きの父親と娘が学問に励むのを厭う母親。そして藩主やらプライドの高い士族やら。文系の私には理解し難いけれど、いつの時代にも数学の魅力にとりつかれている人ているんだな、高校時代の恩師を思い出しくすりとした。
0投稿日: 2015.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ安永4(1775)年に出版された本書は現代語訳です。 算法とは算数のこと。250年前の算数は、日本では庶民たちの遊びの道具になっていました。そんな算数を学ぶ少女あきは、久留米藩主から姫君の算法指南役を頼まれます。そこからライバル少女と算数バトルをすることになってしまい。さてその結果は!
0投稿日: 2015.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
評価は小学校高学年が読んだとしたら、で。 数学好きの私に息子がくれた誕生日プレゼント5冊のうちの1冊。少し対象年齢が違っていたかな。 実在する書物を基に創作されたらしい。なんとなく、何冊かの歴史小説に似ていると感じた。数学的な面白みは弱かったが、それは私が期待し過ぎたのだろう。 他の方のレビューも読んでみよう。
0投稿日: 2015.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログさらり と 読み通せる という要素は 面白い小説の一つの条件です まだ 「算数」という言葉も「数学」という言葉も なかった「算法」の時代の息づかいが聞こえてくるようです 四の五の難しい理屈をこねる前に 物語の中にするりと入って 「千葉あき」(主人公)さんを 初めとする さまざまな登場人物と 一緒に この時代の雰囲気を楽しむ それが この本の楽しみ方です
0投稿日: 2014.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代に出版された実在する和算書「算法少女」から想を得て書かれた小説、ということで、元来文系ながらも最近理数系に興味が出てきたので読んでみた。 児童文学の域を超えない内容だけれど、あの「天地明察」にも出てきた関和孝氏の名が出てびっくり。 (歴史上実在した人物も登場しているので) 和算の歴史を垣間見た、という点で興味深い一冊でした。
0投稿日: 2014.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み返しシリーズ。こんなんだったかなー。小説読みながら計算した覚えが・・・・ジェンダーとか身分とかが反映されていたことを実感。 和算は読み物としてはたのしい。
0投稿日: 2014.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代に実際に出版された『算法少女』という本から着想を得て書かれた子ども向け時代小説。 子ども向け時代小説というと『肥後の石工』を思い出すが(実在の人物をモデルに虚実織り交ぜて作った物語という点で似ている)、読み物としては「石工」ほど重くない。 数学が得意で、芯の強さと、優しさを持つ主人公はちょっと素晴らしすぎて共感できるというタイプではないのだが(一昔前の道徳的児童小説の系譜にある)、女子でも自立して、意思を持って世のため人のために生きるというところが(発表の1973年当時としては)新しかったのだと思う。 現在は女子でも意思を持って、特技を生かし、生きていくというのが当然だし、そういう主人公が出てくる小説もたくさんあるから、存在意義は薄くなっている気もするが、和算というものがどういうものであったか、どういう位置にあったかざっくり知ることができるし、地方藩の情勢や殿様の苦悩なども窺い知れるなど、いい点もたくさんある。 今どきの児童書みたいな個人の内面的な悩みや家族のごたごたがなくて清々しい気もする。 小学校高学年から、男女問わずおすすめできる、間違いのない作品。
0投稿日: 2014.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ実在する「算法少女」というタイトルの江戸時代の算学テキストの出自にかんして、著者がストーリーを与えた小説。小学生の高学年から中学生くらいで読み切れる内容で、展開が少し作られ過ぎているようには思う。作り話というものを一つ価値が低いものとして見てしまう嫌いがあるが、江戸ものということで手にとってみた。少し前にドラマ「仁」が人気を博したが、江戸時代の貧しくも温かいというか、そういう雰囲気を感じる。 話は、あきという算法が得意な少女をとりまく物語で、根底には学問を通しての平等性と学問(と日本)は開かれるべきという主張がある。著者とその父との思い出が時代を変えて描かれた小説とも言える。
0投稿日: 2014.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログパラパラっと飛ばし読み。数学の本というよりは江戸時代のお話。もっと和算についての詳細な解説があったらうれしかったなあ
0投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ父親に教わり、算法(いわゆる算数、算術)の得意な町娘がふとしたことから藩主に興味を持たれ、それを良しとしないものが邪魔する、といった話。この話がもともとある「算法少女」という江戸時代に刊行された本にまつわる逸話というところが面白い。どちらかと言えば小学生ぐらいに読ませて、算数の楽しさ、ひいては学問への興味を喚起するような本。歴史小説といえば、そうかもしれない。
0投稿日: 2014.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログまぁ悪くなかった、という感じ? 結構淡々とした物語でしたが。 昔の暮らし向きや、江戸時代における算数の在り方はよく分かったので、そういう意味で、面白かったかな。 考えてみたら、時期的には当たり前なのかもしれないが、江戸時代に円周率の話をしているとは、あまり考えたことがなくて、意外な感じでした。
1投稿日: 2013.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代にも一部では算数をかなりやっている人がいたんですね。学術的な意味でも興味深いです。その後、天地明察を読んで時代の雰囲気がさらにわかりましたが。
0投稿日: 2013.10.17学ぶことの楽しさが伝わってくる
江戸時代(1775年)に出版された和算書『算法少女』にインスパイアされて書かれた少年少女向け小説。ひらがなの割合が多くてちょっと読みにくい所もあったけれど、とても面白く読めました。40年前の1973年に発表された小説とは思えない新鮮さを感じました。 算法好きの父親に手ほどきを受け、和算好きになった主人公の少女千葉あきが、和算書『算法少女』を出版するお話です。少女あきの和算に向き合う姿が生き生きと描かれています。 和算に対する興味が益々強くなりました。数学に興味のある人はもちろん、興味の無い人にも十分に楽しめる作品だと思います。 学ぶことの楽しさが伝わってきます、子供たちに薦めたい一冊ですね。
2投稿日: 2013.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ蔵書整理シリーズ 以前読んだときは,具体的な問題の解き方がのっていないこともあり,学芸文庫として出版するのはどうかなと思っていました。それもあり,あまり評価していなかったのですが,今回再読して,印象が変わりました。 読み物としては,おもしろかったです。
0投稿日: 2013.10.15『天地明察』で和算に興味をもったら
和算(日本独自の数学)に夢中になって「算法少女」という和算書を書いた女の子・あきの物語です。 40年近く前に書かれた本とあって、文体が古かったり説教くさいところはありますが、数学がわかること・問題が解けることの楽しさを伝えてくれる一冊です。小中学生ぐらいのときにこの本に出会ってたらもっと算数・数学を好きになってたのかなぁと思わせられます。 『天地明察』の頃より時代が下りますが、和算そのものに興味をもったらこちらの本がオススメです。
6投稿日: 2013.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ児童書でとても読みやすかったです。 算数って数字にしても記号にしても「和」を感じないので、私の中で算学が昔の日本で学ばれていたことにピンときていなかったのです、恥ずかしいことに^^; 関孝和の名は『天地明察』にもでてきましたが、その頃よりも今の時代は高度な算学を学ぶことが出来るはずだと思うと、進んで学んでこなかったことが勿体ないです…。
0投稿日: 2013.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代、あきという少女が、和算を好きで取り組んでいる様子が生き生きと描かれている。数学の魅力も伝わってくる。
0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ一度絶版になるも復刊ドットコムの投票を得て2006年ちくま学芸文庫から復刊された本です。 私も早速、書店で買い求めて読みました。 感想。 面白かった!!! です。 実に素直に伸び伸びと書かれているのですね、全体が。 算数好きの少女の物語と言えば、そうなのですが、 それ以上に人への思いやりとか、学問への真摯な情熱が描かれている本です。 読み終えた後の爽やかな読後感、たまりません。 まだ読まれたいない方は、是非読んでみては、とお奨めです。 すぐに読めます。
3投稿日: 2013.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸神田の町人、木賃宿で暮らす人々、お武家様、お大名、そして算法学者、といった登場人物たちの暮らしや関係性が描かれ、読み物として楽しい。司馬遼太郎などがよく言う、江戸時代町人の持つ合理主義を尊ぶ精神、その一方で流派の面目争いにとらわれて視野狭窄に陥る人々の姿、先進的で西洋の数学もどん欲に研究する人、などなどエッセンスはじゅうぶん。もともと少年少女向けの物語ということもあり平易な文章でさくっと読める。
6投稿日: 2013.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「父から算法の手ほどきを受けていた町娘あきは、ある日観音さまに奉納された算額に誤りを見つけた。その出来事を聞いた久留米藩主・有馬侯は、あきを姫君の算法指南役にしようとするが…。」 物語なのでとても読みやすいです。そして物語だけでも十分満足できます(笑)そのなかで江戸数学の面白さを感じてもらえると思います。
0投稿日: 2013.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代の文化が感じられる作品でした。 もう少し、算法について出てくるのかなと、思ったが、これはこれでアリです。
0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公である十三歳の少女あきは父の教えにより算法に優れている。その算法の才能が大名に認められ姫君たちに教えてほしいといわれるが、様々な困難が立ちはだかったる。その中で少女が自分が数学を学ぶ本当の目的を見付け出す物語。少女の純粋さ真っ直ぐな算法(数学)への想いが清々しい。 江戸時代に実際に出版された数学書「算法少女」からインスピレーション得て1973年に書かれた児童小説。 日本の数学が江戸時代の時点でかなり進んでいたということが理解できて、とても面白かった。一番感心したのは万葉集に九九が出てくるというもの。「ニニ」と書いて「し」と読んだり、「ニ五」を「とお」、「十六」を「ししと読むものがある。洒落てるよね。 凄く面白い設定だから、もっと面白く、盛り上がったような気がするが、そこは作者のしとやかさなんだろうかなー。 この本はすぐにでも映画化出来そうだと思いました。
0投稿日: 2012.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
江戸時代に、本を出すほど和算に精通した少女が実在したということに驚きましたが、それ以上に、関孝和の功績を後世の算法家たちが、関流として排他的に門徒を閉ざして秘匿している姿に驚きました。 「天地明察」で関孝和によいイメージがつきすぎたのでしょうか? そんなことは兎も角、優しい文章で描かれた、お武家様より市井の町民に算法を教える道を選ぶという心意気が粋なお話は、読んでいて大変心地良かったです。
0投稿日: 2012.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ95点。おもしろい! 文庫じゃなくて児童書の形をしていたら小学校から読めるし、小学校の図書館にも置きたい。 あとがきにその辺りの岩崎書店への恨み辛み?が書いてあって、大人は楽しめる。 中学生には絶対すすめたい本で、「万葉集に九九が載っている」とか「「絵馬」に数学の問題と解き方を書いた「算額」というのがあった」とか「江戸時代にも円周率を解いていた」とか誘い口もいろいろ。 なんといっても、主人公の町医者の娘のあきが、まっすぐで広い心を持っていて、読後感がすがすがしい。 魅力的な登場人物も多くて大人も子どもも楽しめる本。
1投稿日: 2012.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ34年前に書かれた児童文学の復刊版。今大人が読んでも十分楽しめます。今から300年前の江戸で、算法(数学)が好きな町娘が、その頭脳ひとつで性別や身分を越えて世間と渡り合い、また才能におぼれる事なく身の丈にあった人生を送ろうとする姿が、 とても爽やかで小気味良い。 ちなみに「算法少女」という書籍は、本当に江戸時代に出版されたもの。
0投稿日: 2012.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
江戸時代。算法好きな町医者の娘が、ある日、観音様に奉納された算額(算法の問題が書かれた絵馬)に誤りを見つけたところから話が始まります。 頭脳明晰でありながら素直な主人公の少女には好感が持てるし、その他の登場人物の描写も丁寧です。(算法好きな町医者の父親が、ちょっと浮世離れして頼りなかったり) ストーリーは、久留米藩主のお姫様の算法指南役をめぐって、主人公ともう一人の少女の算法対決が中心にあり、その背景には彼女たちを取り巻く大人たちの思惑や権謀術数が垣間見えます。しかし、特に後半のプロット(ライバルの少女との決着や、本の出版など)は自然ではあるもののご都合主義的にも感じられ、結果として、子ども向けとしても、大人向けとしても、ちょっと中途半端な読後感が残りました。大人のほうが楽しめるかも。
0投稿日: 2012.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ前に読んだ本を久しぶりに借りてきて読む。また読んでもおもしろい。実際に江戸で出された「算法少女」をもとに書かれた、数学好きの少女のはなし。 父から算法の手ほどきを受けていた町娘のあき。あきが算法の勉強に夢中になることを、母は「女が算法をやってなんになる」と言い、「いくらやったって、くらしの足しにならないのに」と嘆く。母にそう言われることは、あきにとってつらい。(おかあさんは、算法のすばらしさをすこしもわかってくださらない)とさびしい気持ちになる。 ある日あきが観音様に奉納された算額の誤りをみつけ、それを指摘したことを聞き及んだ藩主から、姫の算法指南役にとあきに声がかかる。貧しい人の泊まる木賃宿で病人が出ると親切にみてやるあきの父は、お礼の金銭にはあまり頓着せず、あきの母は家賃を払うのにも事欠くことが多くて困っていた。大名のお屋敷へあがるなんて、そんなきゅうくつなことはごめんだと思っていたあきだったが、扶持が入れば暮らしのたすけにもなると思い、その話をひきうけようとする。 しかし、あきに算額の誤りを指摘された少年の師匠が、関流の実力者であったことから、あきの登用に難色を示し、あきが学んだ上方算法と、江戸の関流算法を学んだ同じ年頃の娘と、力試しをという話になっていく。この娘同士の算法腕くらべの話もおもしろいのだが、今回読みなおして、あきが、木賃宿に泊まる者の子どもらを集めて、算法など手習いをみてやるところが印象に残った。 木賃宿・松葉屋の主人は、あきに子どもらのことをこう語る。 「お嬢さん、ここの子は、みんな文吉とにたようなものですよ。手習いにも、そろばんにも縁がないまま、奉公へでることになります」 「行儀も悪いのですが、だれもかまってやるものがありませんのでな。ここへ泊まっている客は、みな遠国からだいじな用をもって出てきているものですから、子をつれてきても、めんどうはみてやれぬのです。ちょっと大きくなれば、しごとを見つけてはたらきにいきます。小さい子が遊んでいるあいだに、せめて、読み書き、そろばんなど、少しは習わせたいとおもいますが、ただで教えてくださる奇特な人はありませんし…」(pp.92-93) その話を聞いて、父にも相談し、あきは子どもらの勉強をみてやることにした。松葉屋の主人も、あいている座敷をかたづけて、ふるい机をならべてくれた。あきが算法をみてやるほか、あきの友だちのけいや千代も、ひらがなの読み書きをおしえる役をひきうけた。 子どもたちが熱心に勉強するようすを読んでいて、震災後に、郡山の避難所で勉強会を始めたという坂内智之さんの話と重なるようだった。 同じちくま学芸文庫から『和算書「算法少女」を読む』が出てるのを発見。今度はこれを読んでみたい。 (8/24了)
0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ書名の『算法少女』というのは、江戸時代・安永4年(1775年)に千葉あきという女性が著した和算の本の書名。この本は、その千葉あきの少女時代の物語。 あきは江戸時代の町医者の娘。算法好きの父の薫陶よろしきを得て、なかなかの算法使い。母からは、算法などという役に立たないものを女だてらに学ぶことを反対されているが、それを明るく受け流すおおらかさと賢さがある。 あきの評判を聞いて、算法家でもある久留米藩主の有馬頼徸(よりゆき)が、娘の学友としてあきに白羽の矢を立てるが、頼徸に使える算法家の藤田貞資(さだすけ)が、身分の違いや算法の流派の違いを理由に別の娘を推したために、頼徸の出題で2人の娘の算法比べが行なわれることになる。 物語はその算法比べをめぐって進むが、党派的利害という狭い了見の愚かさ、算法は身分や職業にかかわらず必要であるということ、真理に心を開くことの大切さといったメッセージが、算法少女のゆれる心を通して読む者に伝わってくる。 善良な町医者の父、娘の将来を案じる母、あきの才能を認めてメジャーデビューの手伝いをしようとする俳人、あきに勝ってほしいと応援する友だち、あきの算法教室に集う子どもたちなど、多彩な登場人物の描写からうかがえる江戸の町民のスローな暮らしぶりも心地よい。 ちなみに、物語『算法少女』の著者は中学校や養護学校で教えた女性教師。父親は工業化学技術者の娘で、幕末から明治初期の日本の理化学について研究していた趣味の科学史家。その父から和算書『算法少女』の書名を聞いたことがきっかけで、物語『算法少女』を書いた。時代を超えて2組の父娘が重なっているようでもある。
1投稿日: 2012.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」のず~っと子供向け版。でもこの「算法少女」の題名が200年も前につけられたとはビックリ。桃三さんのセンスに拍手。
0投稿日: 2012.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ少年少女向けの歴史小説で、一気に短時間で読み終わるボリュームですが、かなり楽しめます。 なにより、「算法少女」という同じ題名の和算書が安永四年(1775年)に実際に出版されていたこと、そして著者が町医者とその娘であることを知ることができたのは大きな喜びです。日本では、明治維新前にも女性が数学を学び、本まで出していたのです! 幕末に日本を訪れた西洋人が、日本女性の学識の高さに驚いて「中国女性よりも進んでいる」と言っていたことを思い出しました。 コピー機のない時代に、国立国会図書館で原書の復刻版を薄紙に書き写した著者の情熱と思い入れ。物語りも、読む人にわかりやすく書かれている温かさを感じました。 また、素敵な挿絵が豊富に、ほぼ4ページに一枚の割合で入っていて、イマジネーションが生き生きとできます。 欲を言えば、後半の話の盛り上がりがもう少しあってもよいのでは、と感じました。せっかく魅力的なキャラクターがそろっているので、もう少しからみがあったほうが良いのでは・・・。たとえば、武家と町方の和算勝負がもうちょっとあったら・・・。 でも、総評として、読後感がさわやかで、すてきな本です。
1投稿日: 2012.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2012.05.24読了)( 2012.02.03購入) この本の単行本が刊行されたのは、1973年10月です。1974年に、サンケイ児童出版文化賞を受賞しています。その後品切れとなり、復刊が待たれたのですが、なかなか果たせず、2006年になってやっと文庫で出版され、話題となり、よく読まれたようです。 文庫で1000円弱もするのに、すごいことです。 『算法少女』というのは、もともと江戸時代に出版された「和算」の本の題名とのことです。その本の作者は、長い間不明だったのですが、数学史を研究した三上義夫さんによって、千葉桃三という医師とその娘アキではないか、ということに落ち着いた、とのことです。 遠藤寛子さんの『算法少女』は、この千葉アキさんを主人公にした小説です。子供向けに書かれた本ですので、どんどん読めます。 和算についての難しい話も出てきませんので、算数や数学が嫌いな人でも大丈夫です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「おあきちゃん、算額だってさ」 「ねえ、こんなへんてこな絵でも、おあきちゃんにわかるの。あたいたちにおしえて」 子どもたちは、仲間のうしろにたった「あき」とよばれる少女を、まえへおしだした。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【目次】 はじめに 花御堂 壺中の天 手まりうた 九九をしらぬ子 雨の日 縁台ばなし わざくらべ まね オランダの本 わたしの本 決心 あたらしい道 江戸だより ちくま学芸文庫版あとがき ●男女・身分を超えて(195頁) 女であれ、男であれ、優れた才を持っている人は、だれでも同じように重んじられなければならない。―それを、どうです。今この国では、どんなに優れた才を持っている人でも、身分が低かったり、自分たちの仲間に入っていないと、その才能を認めようとしない人が多いのです。女の人を一段低く見て、男にはとてもかなわないという考え方も、同じことです。 ●算法の世界(196頁) いったい、算法の世界ほど、厳しく正しいものはありますまい。どのように高貴な身分の人の研究でも、正しくない答えは正しくない。実にさわやかな学問です。断じて遊びなどではない。それを、この国では、一方では算法を金銭を数える道につながるとして卑しむかと思えば、また、単なる遊び、実利のないものとして、軽んずる風がある。 ☆関連図書(既読) 「円周率を計算した男」鳴海風著、新人物往来社、1998.08.30 「算聖伝 関孝和の生涯」鳴海風著、新人物往来社、2000.10.30 「『塵劫記』初版本」吉田光由著・佐藤健一訳、研成社、2006.04.20 「和算を楽しむ」佐藤健一著、ちくまプリマー新書、2006.10.10 「天地明察」冲方丁著、角川書店、2009.11.30 (2012年6月5日・記)
0投稿日: 2012.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった! 『算法少女』は、実際に江戸時代(安永4年:1775年)に出版された算法の本の題名。長い間、この本の著者が誰なのかは分からなかったが、昭和初期の研究で、作者は千葉桃三という医師らしいこと、そして娘のあきが父を手伝ったのではないかということが分かってくる。それでも、なお多くの部分が謎として残されている。200年前に出版された『算法少女』を底本として、著者の遠藤寛子さんが謎の部分を想像力豊に埋めるように児童文学に仕上げた。 著者の遠藤寛子さんは三重県出身の児童文学作家。小さい頃にお父様から『算法少女』の話しを聞いたことがきっかけとなり、この本を書くことに至っている。そういう意味で、お父様への気持ちもこの本には込められているのだろう。 九九の歴史を紐解くと万葉集の時代にまで遡ることことか、「長者の米粒の問題」や、円周率を無限級数で求めていたことなどが登場し、日本の算術の歴史も感じられて興味深い。
0投稿日: 2012.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ算法について詳しい解説などが載っていると思いきや、算法好き父娘の和やかストーリー。 個人的には思いがけず、いいお話でした。 なんだかんだ算法云々より、主人公の あき は出来た娘だね。
0投稿日: 2012.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん。なんとなく面白さがピンとこないな。当時の算学に対する世間の認知度みたいなものは非常によくわかりましたが、その分主人公であるあきの心情みたいなものはえらくさっぱりとしている気がする。 あとがきで知ったんですが実際にあった史実を下敷きにしていたんですね。「算法少女」という本も実際にあった、と。 無理に史実に沿わせようとしているのかちょっと話が無理や知なところがちょっと気になったなあ・・・
0投稿日: 2012.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ将軍家治時代の江戸を舞台に、和算を巡って少女が活躍する児童文学。 とりあえずタイトルにキュンときますね。そして、随所に挿入されるイラストもまたキュートで好し。 もちろん普通に小説としても面白いですよ。
0投稿日: 2012.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ児童向けの本なのだろうけど、面白く読めた。 こういう本を読むと、和算のことをいろいろと知りたくなる。
0投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルがイケてないんとちゃうかと思ったが、実在の江戸時代の文書とその著者の一人である少女を題材に書かれた小説とのこと。 今では算数•数学と一括りにしてる教科だが、かつてはいくつもの流派にわかれていた立派な学問だった。 考えてみれば、アルファベットや記号を用いた数式が日本に昔からあるはずがないんだよな。 いつの世にも人が考えつかない事を突き詰める人がいて、まだ日本にもたらされていない数式を日本人なりの表現で解明していた人たちもいた。 正解のない問題に挑み続けるようなものだったのかなと想像してみる。 文体は児童向けだが決して幼稚な内容ではなく、楽しめた。 2012年2月29日
0投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者は元教師で児童向け文学作家、というだけあって スラスラと読みすすめられる、やさしい文体です。 江戸時代が舞台となっていますが、 文章にはひらがなが多く、難しい言葉は算数用語だけ。 小学生でも分かりやすい作品だと思います。 挿絵がなんとも味があってかわいらしいなぁと思っていたら 挿絵を描いた箕田 源二郎さんは いわさきちひろさんと縁のある方でした。 ストーリーがとりたててすばらしい、ということはないのですが 江戸時代に「算法少女」という数学の本を出版した女の子がいた、 という事実に基づく話であることが驚きです。 あとがきでは、一度絶版となってしまったこの作品を 復刊させるにあたってのご苦労が述べられています。 数学関係者から、復刊を望む声が多くあったにもかかわらず 当時、出版社がなかなか復刊にGOサインを出さなかったそうですが・・・ 私が購入したもので十八刷。 当時の担当者は今頃くやしい思いをしているでしょうね。
0投稿日: 2012.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ永和時代に実際に発刊されていたらしい算術の本に着想を得て書かれた、時代物の小説、というか小話くらいのボリューム。 算術が得意な町娘が、ひょんなことからその噂がお殿様の耳に入って、、、っていう筋なのだけど、 考えると深いなってこととか、素直な目線とかが、新鮮に真っ直ぐ存在していて、嫌味が無く、素直。
0投稿日: 2012.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「町娘あきは、ある日観音様に奉納された算額に誤りを見つけ声をあげた・・」、書店レジ前に平積みにされるような一般向けの本ではないだろうと思い、目を疑いながら手にとった。 江戸時代、日本人の算数への意欲とレベルは世界一を争うほどの実績だった。子供たちが目にする本の表紙には、「一、十、百、千、・・・京、垓、・・・無量大数」の単位が書かれ、算法の本は多数出回り、算木を用いて、Xの8乗からXを求める難解な計算なども行っていた。そして、難しい問題が解けると、神社にその解答を算額として奉納するという熱狂ぶりだったのだ。この事実はほとんど知られていない。私がこのことを桜井進先生から伺った時には本当に驚き、そして感心してしまった。が、まさか、その算額を扱った本があるとは思わなかった。 本書では、江戸時代に盛んであった和算の話を背景にストーリーが展開される。あきが子どもたちに九九を教えている途中、こんな質問をするシーンがある。「ある長者が下男になんでも望むものを申せといった。下男は米1つぶをついたちからおおみそかまで毎日2ばいにして、くださいといった。これを聞いた長者はおおいにわらった」。---子どもたちも、1つぶ、という響きに笑うが、やがてそろばんをはじいて20日目には524288つぶ!と驚き、「数って、こわいんだねえ」と気づくのである! おそらく現在、多くの日本の小学校教育ではこの計算は扱わないだろうと思う。電卓なしでは答えが出ないからだ。しかし、「数ってこわいんだねえ」という驚きが出たこんな授業を、ぜひ現在の小学校の教科書にも取り入れてほしいものだとも思ったりするのだ。江戸時代の和算は、どれもパズルのように豊かで柔軟で面白いのだ。日本の重要な歴史遺産である。 本書は、数学の教師などの大いなる声によって絶版から復刻された。算数本のブームもあるだろうが、この思いが、広く日本に届くことを期待する。
0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代の数学のデキる少女の物語。数学嫌いでも問題なく読め、行間が広くあっという間に読めてしまう児童書。物足りない読後感。もっとこの数学少女を堪能したかった。
1投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
児童向けなのかな?もう少し江戸時代の数学について触れられても良かったなーと思いつつ、とても面白かったです。
0投稿日: 2011.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日、テレビで「和算」を外国人に紹介する番組があった。和算は江戸期に発達した日本の数学。テレビによれば、今で言う、懸賞クイズのようなものもたくさんあり、巷では算術指南の看板を掲げるところもたくさんあったようだ。また、新たな問題を創った際には、算額という大きな絵馬のようにして、寺社に奉納することも良く行われていた。勉学の成果を神仏に感謝する、と言うわけだが、実際には「どうだ、スゴイだろう」という自慢だったらしい。 この「算法少女」もこの算額奉納の場面から始まる。 同名の、安永4年に刊行され、今では国会図書館などに僅かに残るだけになってしまった和算書「算法少女」をモチーフにした児童書であるが、当時の様子が生き生きと描かれており、思わず、算額探しの旅に出たくなってしまった。 また、この本は、絶版になったものを、読者と関係者の努力で版元を変えて出版されたもの。そういう成立過程にも感じるところが多々ある、良書です。
0投稿日: 2011.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ文体は少々古臭いが、江戸時代に算数のすばらしいセンスと才能をもつ少女を描いた視点が、他の時代小説と異なり面白かった。ルビがふってあるので小学校高学年なら充分読める。
0投稿日: 2011.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの時代の女性は奥ゆかしくて魅力がある。 数学が好きだから引かれたが、知らない人にも楽しめると思う。
1投稿日: 2011.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代に実際に出された『算法少女』をもとに、遠藤さんが書いてくれました。千葉あきという少女は、観音絵馬の問題の答えが間違っていることを発見。算法を通じて、大人の心の狭さの恥ずかしさ、算法の楽しみ、江戸っ子の人柄など、とても楽しく読めた。
0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「Q.E.D. 証明終了」という漫画で和算・算額についての物語を読み、和算について楽しくとっつきやすく知ることができる本を探していてたどりつきました。和算を題材に、和算が得意な女の子の成長を見せてくれるおはなし。素敵な児童文学だなと思いました。
1投稿日: 2011.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ問題を解こうとしなければ、2〜3時間でさらっと楽しめる子供向け時代小説。具体的に登場する算法問題は数も少なく、解き方があるわけでもないので、元になった同名の算法書にもあたってみたくなった。
1投稿日: 2011.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルの『算法少女』というのは江戸時代に13歳の女の子が書いた実在した和算書。 その『算法少女』の成立をめぐる史実を下書きに、江戸の生活や学ぶ喜びがイキイキと描かれている。 13歳の少女ながらも自分で決断し行動する勇気は男前。 漢数字しかなかった時代の数学の本は難しそうで読めるか自信はないが、国会図書館に原本があるらしいので一度見に行きたい。
1投稿日: 2010.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ算法がマイナーだった時代に、算法に惹かれた少女。 日本では算法を学ぶ意味がなかなか理解されずにいた時代に、 なにか心惹かれ、子供たちに九九を教え始めた少女がとても魅力的。
0投稿日: 2010.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ“「算法の勉強なの?そんなら、おあきちゃんのやってる勉強だね。おあきちゃん、こんなむずかしい勉強してるの。うわあ、えらいんだなあ」 おさない子は、むじゃきに大声をあげた。 算法とは、今日でいう算数、数学のことである。 「いやよ、おみっちゃん。はずかしいわ」 あきは、みつをたしなめて、なおも問題をみつめていたが、説明文のある箇所に、しきりに首をかしげた。なんども読みなおしたが、やはりなっとくできないあきは、 「どうもへんだわ」 と、つい声になった。 「なにがへんなのさ」 そばからけいがききとがめた。 「あのね、どうもこの答えがまちがっているようなんだけど」” 母の本棚から。 時代は昔だけど、そんな難しいことばもなく結構すらすらと読めて内容もよかった。 “「おあきちゃん、お屋敷に行くことにきめてきたんじゃないの」 「あたいに算法をおしえるの、どうなるの」 「おれ、せっかく九九をおぼえかけたんだ。よそへ行っちゃいやだ」 「ええ。わたし、もうどこへも行かない。あんたたちといっしょに算法を勉強するわ。さあ、いっしょにかえりましょう」 あきは子どもたちにこたえてから、 「素外のおじさん、町の算法塾のお師匠さん――これがわたしに、いちばんにあうでしょう」 と、晴ればれとわらった。”
0投稿日: 2010.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログまず読み物として非常におもしろい。それだけでなく、物語を読むうちに算法(数学)というもののおもしろさ、奥深さに自然と気づくようにできており子供向けの小説として良書といえるだろう。もちろん大人が読んでもおもしろい。学問は実生活に役立てお金を儲ける助けにもなるが、それはあくまでも付帯的結果である。人間は本来、真理を追い求め、少しでもそれに迫りたいと希求する存在である。人は常に真理に飢え学問を修める。その一番根源的な姿がこの本に描かれている。つまり、知的好奇心を満たすことは「この世とは別世界のような楽しみを持つこと」すなわち「壺中の天」(こちゅうのてん)なのだと。 主人公が一介の町医者の子供であること、それも封建時代における女であることがこの物語を面白くしているといえるだろう。身分が低く、取るに足りないものとして扱われる市井の者が、身分の高い武士や権威を振りかざす学者の鼻をあかす。それも物事の中心は江戸だとふんぞり返り、上方のものを歯牙にもかけない態度の江戸人を上方の学問が打ち負かす痛快さは『王将』の坂田三吉にも似たものがあり、私のような庶民はやんややんやの拍手を送るのである。
0投稿日: 2010.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生から読める本。 さらっと読めて楽しいです。 算法、今の算数・数学を何のために勉強するのか。 なかなか認められないけれど、あきちゃんの考えは素敵です。
1投稿日: 2010.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ算数は苦手!という人も大丈夫です~ 江戸の町の活気ある生活のようすや 真摯に「学びたい!」と考える少女を縦糸に また 武家の面目ばかりを考える大人たちや 算法の流派の確執を横糸に 活き活きと物語が進み、 実在の「おあき」ちゃんの姿勢にこちらまで 居住まいを正すような気持ちになります。 中に出てくる 有名な和算の問題もちょっと楽しい。 著者である遠藤寛子さんとその父親、 「おあき」ちゃんとその父親との関係が 偶然にも重なり合い その不思議な縁に 心温まり、また羨ましくもなりました。
1投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだかかわいい話だった。子供向けってせいもあるだろうけど。 いくつか問題があったけど今の私には理解不能でした。 まだ算数やってるときに呼んでたらもっとちゃんと勉強したのに・・・たぶん。 数学嫌いにならなかったのに・・・たぶん。
0投稿日: 2009.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ何年だっけ173?年…解体新書が出された頃に、江戸の町医者とその娘共著の和算書『算法少女』が発刊され、その史実に基づいて書かれた、算法少女ができるまでのちょいと脚色もされた歴史小説。少年少女向けだからかなり読みやすい。パラパラめくった時の印象より面白い。刺激はないけど、へーって感じです。
0投稿日: 2009.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル買いしました。なんてチャーミングな題名なんだー!と。 江戸時代を舞台に、算数好きであること以外はごくごく平凡な、町人の女の子を主人公にした物語です。武士の子がこれみよがしに掲げた数学の問題について、「答えが違う」とうっかりつぶやいたことで評判になってしまった、主人公・あき。お殿様に、「お姫様の算術の家庭教師に」と望まれますが、例の武士の子の先生一派がそれを阻止しようと、同じような数学自慢の少女(こっちは武家の子)を出してくるのです。二人の算術対決の行方は… ってのが大筋ですが、対決自体はそんなに盛り上がりません。 メインは、算術マニアの父親の影響を受けていた主人公が、だんだん自分で篭って数学を究める楽しみから、他人に教えて知識を共有していく楽しみを見出す成長物語。素直な性格の女の子なので、非常にほのぼの心温まる小説です。 式でなく言葉で説明される数学の問題は、何が何やらさっぱりわかりませんでしたが(^^;
0投稿日: 2009.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ和算の達者な娘さんを主人公にした、古い児童書であります。 「役に立つから」じゃない動機で学問に励む姿というのがとても好きなので。
0投稿日: 2009.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際に出版されていた本だとは知りませんでした。 おあきの心がまわりの大人の心を動かしていく 江戸時代の暮らしを垣間見て、学びたくても学べなかった子供たちが たくさんいた時代に比べ、ほんま贅沢やなあと今を思いました。
0投稿日: 2009.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ和算は流派の垣根を越えられるのか。 江戸時代、 儲ける手段、または趣味の遊びと捉えられていた和算(数学) 和算に優れた町娘の『あき』が、 『師匠』でもある父の考えに違和感を抱きながら、 本来の『数学(科学)』の有り方に気づくまでの話。 江戸の町民たちの暮らし振りも新鮮で楽しく、 江戸(時代)の生活と、和算について知りたくなりました。
0投稿日: 2009.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生の時代にこの方の本を読めば、きっと数学を嫌いにならずに済んだ筈。 「数学ほど公正な学問はない」 という言葉が印象的です。
0投稿日: 2009.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ役に立つかどうかという観点を持たず,数学するということ自体を目的にするのが大事ですね。 個人的には「壷中の天」でもいいと思いますけど。
0投稿日: 2008.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ算数(数学)に関する小説は初めてだったので面白かった。元々嫌いではなかったけど、これを読んだ後だとさらに算数、数学に興味が出てくるなぁ。
0投稿日: 2008.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ華恵ちゃんが本の中で紹介していたので読んでみた。あきの13歳にしては、しっかりしたすじのある生き方に驚いた。またあきの父親の生き方、算法に対しての思い入れが粋だなと思った。遠藤さんのことばがすごく好き。華恵ちゃんの言った、”すがすがしいのです”という表現が、まさにこの物語にぴったりの言葉だと思う。
0投稿日: 2008.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分にはわからない世界ながら、熱を入れる人々の様がよくわかる良書。「国書総目録」で思わず確認してしまった。 20080119
0投稿日: 2008.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ先に紹介した数学ガールのタイトルは この本にインスパイアーされたにちがいないwしかし、この本のオリジナルは実在の算法少女が父親の手伝いでその才も本物 でもこの本 昭和のライトノベルなんだよね、それにしては、しっかりした作りです 浅草観音様の前で江戸の町人と武士を巻き込んだ 斬九郎でも出てきそうな雰囲気ではじまる でも、あまり数学的な話はでこない いいたい事は小さい流派争いなんかしてるから、せっかくの学問が西洋に負けるという結果 ご用心ということですな。 若い人達にぜひお勧め
0投稿日: 2008.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ1973年に岩崎書店から発行された本の復刻版らしいです。算数ができる女の子の話。江戸時代にこれだけ数学が発達していたとは知りませんでした。物語としても面白かったです。
0投稿日: 2007.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代の算数が得意だった少女の話。 事の起こりから締めまでの展開が見事に決まっている。 忘れかけていた学問の本質を思い出させてくれる良書。
0投稿日: 2007.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠藤寛子の算法少女を読みました。江戸時代に存在したという算数の得意な少女のお話でした。医者の父親の手伝いをしながら算数の勉強をしているうちに、和算の心得のある大名の目に止まって、と物語は進んでいきます。ジュブナイルですが、大人でも楽しめます。江戸時代の日本は欧米に負けないくらい数学の研究も盛んだったのですが、派閥などにこだわってしまい、また他の学問との交流をしなかったため、それ以上の発展はなかった、ということが主張されています。
0投稿日: 2007.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログかねてから読みたいと思っていた絶版本がちくまで文庫になった。江戸時代、「和算」の天才少女の話(小説)。
0投稿日: 2006.10.17
