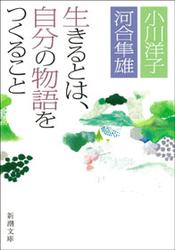
総合評価
(131件)| 40 | ||
| 43 | ||
| 24 | ||
| 5 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ敬愛する御二方の対談は、読めども読めども、自分自身の未熟さばかりを思い知らされるものだった。どのように生きれば、人とこのような対話を交わせるようになるのか。。。10年後の自分よ、その片鱗でも分かるようになっていて欲しい...! とりわけ小川洋子先生のあとがきからは、小川先生のお人柄が文章からこれでもかと伝わり、随所でうっとりとしてしまう。 内容もさることながら、まるで水面にしとしとと降る静かな雨のように、優しく、美しく、やわらかな日本語が、体に染み渡っていく。
0投稿日: 2025.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ『小川洋子のつくり方』の中の全作品紹介を読んで興味を持った一冊。 大学で心理学を専攻した身として、河合隼雄はもちろん知っていたけれども、なぜかどうしても著書を読む気持ちにならず、当時周りがみんな読んでいたのに、何となく話を合わせて読まなかったわたし。 今この本に出会えて良かった。 ''人間は矛盾しているから生きている、整合性のあるものは生き物ではなく機械です'' 矛盾を意識し、折り合いをつける。その折り合いの付け方が個性であり、物語だ、と。2人がそこで共感していて、共感し合えることが素晴らしいと思った。 その物語を小説にして見せてくれる小川洋子さんの作品は、だから心に響くのか。 「傍にいること」の章では、''苦しみ、悲しみを受け止め、一緒に苦しむけど、望みを失わずにピッタリ傍にいれればもう完璧''だ、と。 娘に対しても、仕事上でも、常に心に留めて行動すべき金言だと思った。 必要な時に必要な本に出会えるんだなぁ。
6投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「生きるとは、自分の物語をつくること」 物語は、既にそこにある。 なんか、分かりそうな言葉だなと、最近感じる。自分の視野で見えているものは一時的で、その瞬間瞬間に過ぎないけれど、人が生きてるだけで、それは全く瞬間的でない。そこには間違いなく過去があって、歴史があって、今までとの繋がりがあって、多様な偶然が折り合った果てに、今の自分がここにいる。 何となく毎日を生きてると、すぐに忘れてしまうし、今この感想を書いている間も、自分が「そういった意味」で現実を見れているかと問われると、見たいように認知している部分があるし、確かとは言えないよなと感じる。 近代化学の発展から、合理的で効率的であることが求められる社会だけど、個人的には、そういう「物語」とか、その人がそこに存在してる理由,意味みたいなものが魅力的だと最近感じるし、それを社会の渦に巻取られて忘れてしまわないようにありたいと、思う。でも、自分は能力値が高い訳では無いし、中々難しいだろうなと感じてもいる。 だから、今を大事にしたい。最近、思い出に支えられていると感じることがある。それは全部事実だけど、母の愛だったり、家族の愛だったり、誰かの労りとか,「思い」であることが多くて、思いが形には見えないけれども、確かに存在するのだから、今を大事にしたいかな、とか考える。 うっちーにこの前言われた、「逃げてる」ってのもそうだと感じるし、相変わらず常時焦ってばっかな感じは拭えないし、「浅はか」なのだなと論理的に思うことも多々あるが、それでも、生きていけたらなぁと、思う、感じる。
1投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みながら、第六感(?)みたいな、普段とは別の、心の深いところにある感覚がゆっくり目を覚ますような感じがしました。「黙っていられるかどうか」という章が特に印象に残っています。誰かにに寄り添うこと、心を通い合わせることは、シンプルでいて、でもとても繊細で、分かりにくい、「あわい」ということ。簡単ではない。それを本当に分かっているお二人だと思いました。
0投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ対談の柔らかくあたたかい雰囲気が良い。 カウンセリングと物語の話もとても興味深いが、個人的には、河合隼雄さんの著書や対談を通して小川洋子さんが「なぜ小説を書くのか」という、若い頃には答えるのが苦痛だった問いに対して、「誰もが物語を作っているのだ」という気づきを得て答えを見つけていった、というあとがきの文章がとても素敵だった。
5投稿日: 2025.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて。金言だらけだった。人間はつらいときにその人なりの物語として落とし込んでいる。「個」は自分の知ってる範囲内。人間は矛盾しているから生きている。
1投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて購入したけど、お二人の対談でこんなに心温まるとは、、人生に正解を求められる世の中だけどそんなことないと改めて。生きるのがしんどい時や、「こう生きなきゃ」と縛られる人に読んでほしい。答えは書かれてないから、自分に問いかけながら読み進めていくのが◎肩の力を抜くヒントになります。他者との関わりの中で人生(物語)は変わるし、人生=物語って言葉が大好きです。
1投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ#生きるとは自分の物語をつくること #小川洋子 #河合隼雄 #読了 二人の対談。難しいけど難しくない。難しくないけど難しい。思考力のいる文章だった。 望みのないときにどうするか 望みをもってただそばにいる 人に寄り添うとはそういうこと。 小川さんの物語を書く意味についての語りが好きだ。
5投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容を全く予想していなかったが、とんでもなく良き出会いとなった一冊。どのページをとっても河合隼雄先生の温かさ、目の前の一人の人間にぶつかる真剣さ、そしてプロフェッショナルに触れる事ができた。
1投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ気付きが色々と。もっと長くお二人の会話を読んでいたかったな〜。河合さんが亡くなっちゃったので仕方ないけれど。
0投稿日: 2024.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ博士の愛した数式の執筆秘話みたいなのも あってよかった。 先生と家政婦さんの恋愛関係に至らないところからのプロとしての話が良かった。
3投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉の端々にお二人の優しいメッセージが伝わってくる。人生で何かを成し遂げるよりも自分の物語をつくるほうが幸せなのかもしれない。短い本だったが、安堵と幸福感を感じられるような素敵なお二人の掛け合いが心地良かった。
1投稿日: 2024.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「生きるとは、自分の物語をつくること」 読み終えたあと、このタイトル通りであることが分かる。物語の作り手である小川洋子さんと、人々が作る物語=生き方を聞き続ける河合隼雄先生との対談。 読んでいると共感できる部分や、気づきが多く、その箇所に付箋を貼っていたらたくさんになった。 「死」について語られることが多いような気がしたけれど、これは私がそれについて意識しているからかな? 物語を作ること、物語に寄り添うこと(聞くこと)の大切さについて知った。また、小川洋子さんや河合隼雄先生の著作をこれからいろいろ読んでいきたいと思った。
1投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ優しい、柔らかい言葉の中に散りばめられたメッセージ。 分けられないものを分けてしまうと、大事なものを飛ばしてしまうことになる 噛み締める。
2投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄さんが入院する2ヶ月前の対談で、最後の対談と言われている。 相手が作家の小川洋子さんだからかもしれないが、河合さんがリラックスして喋っている。 以下の小川さんの追悼の話が、どうも私の頭から離れません。 『対談の途中、先生は一度、深い悲しみの表情を見せられました。御巣鷹山に 墜落した日航機に、九つの男の子を一人で乗せたお母さんの話が出た時でした。 心弾む一人旅になるはずが、あんな悲劇に巻き込まれ、お母さんは一生拭えな い罪悪感を背負うことになったのです。その瞬間、先生の顔に浮かんだ表情、 思わず漏れた声、 宙の一点に絞られた視線、それらに接した私は、失礼にも「先生は本物だ」と確信しました。』 という小川さんの話です。 河合さんは、いろんな著書で「ほんとうの父性を日本の父親は持たなければいけない」と啓蒙している張本人なのに、やってること(カウンセリング)はまったくの日本人的対応でやさしすぎるということが、わかるエピソードですよね。西欧の父性的理論は熟知していても「三つ子の魂、百まで」ということでしょうか。
1投稿日: 2024.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログとても良い。常々思っていた疑問の答えがここにあった。 小川洋子氏との対話形式なのでストンと心に落ち着く。 もっともっと対談して欲しかった。小川洋子氏の長いあとがきが良い。繰り返し読んでいこうと思う。
0投稿日: 2024.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合さんの本を読むのは2冊目ですが、このおじさん好きだわ。大人が失った、子どものときに持っている力に着目されているところとか、深くお聞きしてみたい。それとか、相手の存在を受けとめる力も見習いたい。 この方のそういう人間力の根っこに、文学とか人文学的な関心とか経験が大いにあるんだなと実感する。まさに、生きることは、自分の物語をつくること であると、自分に対しても他人に対しても思いながら人と関わっておられるのだなと思った。 「博士の愛した数式」は映画で観たのみですが、そういう河合さん的な、子どもの力に着目するような読み方をしたら面白そうだと思った。
0投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
そう。「個」というものは、実は無限な広がりを持ってるのに、人間は自分の知ってる範囲内で個に執着するからね。私はこういう人間やからこうだとか、あれが欲しいとか。「個」というのは、本当はそんな単純なものじゃないのに、そんなところを基にして、限定された中で合理的に考えるからろくなことがないんです。前提が間違ってるんですから笑 日常の中で、何気なく人を励ましてるつもりでも全然励ましたことにはなってなくて、むしろ中途半端に放り出してるってことがあるんでしょうね。 それはつまり切ってるということです。切る時は、励ましの言葉で切ると一番カッコええわけね。「頑張れよ」っていうのは、つまり「さよなら」ということです笑
0投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私がその域に達していないのか、 なんだかあんまりしっくりこず。 宗教や日本のルーツがお二人の経験談と絡み合う。 様々な信仰対象や歴史的背景があって 今の我々が形成されているんだから しっくりこなければいけない気がするんだけど、 言語化できぬ。。 河合先生の「望みを失わず傍におれたら、もう完璧」がよかった。
1投稿日: 2024.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「博士の愛した数式」の小川洋子先生と、臨床心理学者 河合隼雄先生の対談集。 人と人との関係は、寄り添い合うこと。人を助けようとする人は使命感に燃える強い人が多いけれど、そこに力関係があってはいけない。どんな人に対しても、スッと相手と同じ力になることで生まれる繋がりがある。 一神教の世界では、神様の存在が大きいから、人間は神の創りたもうた世界を物語を生きている。日本のような多神教の世界はたくさんの物語が生まれる。 「源氏物語」の光源氏は、女性に光を当てる役。 【厳密さと曖昧さの共存】 日本は境界が曖昧。一流企業の並ぶ街に、ガード下の飲み屋など、街の境界も曖昧な国。 機械は整合性のあるもので、矛盾する世界の中で折り合いをつけて生きていくのが人間。その折り合いの付け方、物語の描き方にこそ人の個性が現れる。生と死、身体と精神、意識と無意識を結びつけるのが物語。生きるとは、自分にふさわしい、自分の物語を作り上げてゆくこと。 【やさしさの根本は死ぬ自覚】 お互い限りある人生なんだ、という意識を共有することが、魂同士の人間関係構築には大切。その自覚があればお互いを尊重しあえる、相手のマイナスを受け入れられる。
1投稿日: 2024.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ充実の対談集。 「博士の愛した数式」の逸話と「源氏物語」の解釈が新鮮。 日本の曖昧さと西洋の厳密さが興味深い。 私はアースされているから大丈夫という河合先生の心構えを見習いたい。
0投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語とは、自分自身に現実にあるものを受け入れるもの。小説は現実に即した物語として、読み手や書き手に、そこにあるものを感じさせる。規則から生まれる合理性だけで世界は成り立っているわけではなく、そこにある偶然も含めて、その現実や矛盾をどう取り込むか、大きな流れの中で個性が現れる。(大樹)
0投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語とは、自分自身に現実にあるものを受け入れるもの。小説は現実に即した物語として、読み手や書き手に、そこにあるものを感じさせる。規則から生まれる合理性だけで世界は成り立っているわけではなく、そこにある偶然も含めて、その現実や矛盾をどう取り込むか、大きな流れの中で個性が現れる。
0投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子さんの本を読んでよかったのでこちらに。 河合先生の、カウンセリングの話ははっとさせられた。相談や迷いの声を聞くと、わたしは答えらしきものが知りたくて、⚫︎⚫︎ということ?と問うてしまう。もしくは、こう捉えたらいいんだよと解釈を与えてしまう。 相手に寄り添い、相手の世界の中で話をする態度を自分はとりたいけど、現実的にはそうもいってられないことも。自分の考えのよらないことに、ああそうかとただ受け止めるようになりたいし、まだ自分がわかってないこともあるかもと思っていたいと感じた。
0投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間というのは物事を了承出来ると安心する。了承不可なことは人間を不安にさせる。下手な人はそういう時自分が早く了承して安心したくなる。質問する側が納得したくてなにか言ってしまう。質問する側が物語を作ってしまうのでそうならないように心がけるべし。
0投稿日: 2023.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログNo.19/2023 『生きるとは自分の物語を作るということ』 河合隼雄・小川洋子 博士の愛した数式を読んだことがあり 印象深かったので名前を見て手に取りました 河合さんの名前は大学の時に一度聞いており 有名な人くらいは知っていました 対談は上質で 言葉の1つ1つに重みを感じました 「アースしている」 「相手の意識を共有する」 今の仕事に活かせることがたくさんあり 勉強になりました
1投稿日: 2023.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子と河合隼雄のキャッチボールが見事だ。河合隼雄のダジャレやわかりやすい例えが実に効果的だ。聞くことを専門にしている河合隼雄の手法が、ツッコミを入れて楽しんでいる。小川洋子は『博士の愛した数式』を読んで、なんとステキな文章と体温のある物語を書くのだろうと感心した。それ以降、あまり注目していなかったが、最近の小川洋子の言っていることが興味深いので、読み始めた。 「生きるとは自分の物語を作ること」という言葉がいい。 小説家は、いろいろと妄想を働かせることが仕事。河合隼雄は、「小説家と私の仕事で一番違うのは、現実の危険性を伴う。作品の中なら父親を殺すこともできるが、現実に患者さんが殺すと大変です」河合隼雄はいう『若きウエルテル』は、死ぬけれど、ゲーテは長生きする。一流の選手ほど選択肢をたくさん持っている。つまり、死ぬより生きていたほうがいいだろうときちんといえるかにある。 現実の中には、偶然があって、本当にいいことが起こったりする。小説以上の展開がある。問題は、そんな偶然を気がつかないことが多い。 小川洋子はいう。小説が全く何も書けない真っ白な状態というのが続くことがあります。一生懸命何か書こうとして考える。思いもしないところから、カミオカカンデにニュートリノが飛び込んでくるみたいに、パーっと何かが動き出して描けるようになる。 博士に対する人間的な交流がなんとも言えないものがあり、それがさらに人の痛みに共感することでより深い人間関係を日常の中で掘り起こしている。篠田節子のようにホラーに持っていかないで、日常感をあぶり出す。平凡な中に、きらりと光るものがあるのがステキだ。そこには、作者の確かな視座が必要だと思う。 第1章の魂のあるところは『博士の愛した数式』についての河合隼雄の意見が、作者である小川洋子の想定外のところに広がっていくのが、面白い。 河合隼雄は数学の教師もしたことがあり、数学の美しさについて理解する人であり、江夏の背番号28は阪神タイガース時代だけで、南海17、広島26、日ハム26、西武18だった。阪神の時だけ江夏は完全だったという。博士は阪神の江夏しか知らない。数字は数字だけでない意味を持っているものがある。それは、素数、完全数、友愛数などだ。8は、2の2の2倍で、倍倍倍だから、多いことを示す。八百屋、八百万となる。河合隼雄は、「男性と女性、大人と子供、それに障害のあるものとない者とか、みんな友情が成立する」と言っていたが、『博士の愛した数式』はその見本のような作品だという。 源氏物語は、最古の文学であり、女性が描いた。ほとんどが失恋と出家の物語。出家が身近にあった。つまり、それだけ死の世界が日常生活にものすごく近くて、一歩踏み出せば行けるという感覚だった。「人間はどうして死ぬのか」「死んだらどうなるんだろう」という恐怖が物語を生み出している。死が間近になっていた現在はいろいろな面白いことがあって、死が遠くにあるような錯覚に陥っている。 戦争で生き残ったり、震災で生き残ったり、身近な人が死んだりしたら、「自分が悪いのではないか」と生き残った自分を責めてしまう。 小川洋子はいう「人間が困難な現実を、自分の心に合うように組み立て直して受け入れる」。生き残った自分を責めるというのは、原罪とは違う。 この問題意識から、小川洋子は、アウシュビッツ収容所で生き残った人へのインタビューやアンネの日記に関わる人たちを拾い上げていく。自分に責任がないのに自分が悪いのではないかと自分を問い詰めてしまうあり方を、もっと深く取り下げて、生きていることがいいんだといえる小説を書こうとしている。 なるほど、この問題意識は、かなり重要なテーマでもある。 非言語的世界が、1万年前に長くあり、そして言語的物語が、神話、聖書、昔話となった。それは人間の悩み、死と向き合うことなどが題材となっている。人間の共通の課題が昔からあった。日本は、厳密さと曖昧さが入り混じった社会となっている。一神教ではないことが大きな要因。論理的に矛盾することがあったまま科学の進歩がある。科学は曖昧を容認しない。その矛盾を生きていることが日本人のありようがある。こういう矛盾を生きることが、個性ともなる。弱さがわかることと強くあること。強くあることが、難問をくぐり抜けることができる。 いろいろな苦しみや悲しみ、それを受け入れるために自分の物語を作るなのだ。なんか、いい対談に巡り会えた。
0投稿日: 2023.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログことばを大事にすることを生業にしている2人の対談 人は誰しも物語を作らねば生きていけない 小説家はそれを拾い上げ、 カウンセリングはそれを手助けする
0投稿日: 2023.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄先生との対談、が大部分を占める内容ですが。 そうか、河合先生は教育学者であり、心理学者であり、数学者でもあったのか…。 そのご縁となった「博士の愛した数式」からの、おはなし。
0投稿日: 2023.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ何となく手に取り読んだ本。 何となく、ではあったけれども、 「人の話を聴くこと」や「物語を書くこと」、 そこにあるものに気付き、とらえることのお話など、 惹き込まれてあっという間に読み終えました。 『博士の愛した数式』を読み返したくなりました。
0投稿日: 2023.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ決して上からでなく、対等の人として接する河合先生だからこそ、悩める人たちを多く治されているのだろうと思うけれど、ご本人は決して私はただ聴くだけ、そこにいるだけで、ご本人がご自身でと治されると言われる。小説と思うほどの奇跡も沢山経験されていて、人間の治癒力の可能性を信じられている。それは人を信じているこそなんだなぁ。
0投稿日: 2023.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ理と文が混ざって境が溶ける時、一段深いおもしろさがある。物語と現実が溶ける時もある。もっとたくさん、このお二人のお話を聴きたかった。
2投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨床心理学者 河合隼雄先生と小川洋子さんの間で2005年と2006年に行われた対談。河合さんは2007年に死去され、氏にとって最後の対談となった。小川さんの長い後書きによると、本当は続きがあるはずだったらしく残念。 箱庭療法、源氏物語など、いろいろな話題から物語とは何かを語っている。カウンセリングで患者と対峙する場面についての河合さんの話からは、一筋縄ではいかない優しさが伝わってきて感動した。読んでいると温かい気持ちになれる一冊。 最も印象に残ったのは、長年、「なぜ小説を書くのか」色々な人から問われ続けてうまく説明できなかった小川さんが、”内面の深い部分にある混沌は論理的な言葉では表現できない。それを言葉にできるのが物語である”と、そういう解釈に触れて心底納得できたという話。文学者などではなく、心理学者から気づきを得たという点も面白い。2012年頃にとあるエッセイ集で小川さんが、人生を築き上げるとは、事実を自分なりにアレンジし、バランスをとっていくことで、それを”自分で物語を作る”というふうに表現していたのが好きで覚えていたが(さらに、それが出来なくなったときが”挫折”だとも述べていた)、それはこのときの対話がきっかけで考え得たことが窺える。
3投稿日: 2023.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
他者理解に必要なことが河合先生のお話にたくさん詰まっていた。 私はどこまでも待てないんだけれど、他人と物語を共有しようとすればいいのかもしれない。
0投稿日: 2022.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログポール・オースターの小説内で語られる物語の捉え方と、小川洋子の物語の捉え方に共通点が多くて驚いたが、後書きにポール・オースターを敬愛してると書いてあったので納得。 113 それはつまり切っているということです。切る時は、励ましの言葉で切ると一番カッコええわけね。「頑張れよ」っていうのは、つまり「さよなら」ということです(笑)。
0投稿日: 2022.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子さんと、臨床心理学者の河合隼雄さんとの対談本。 心理学的な話が主なのかと思いきや、数学や宗教に絡んだお話も多いです。 「原罪」「原悲」や、西欧一神教の人生観についての話はとても興味深かったです。もう少し深く考えたいので、そのうちまた読み返したい。 河合氏は、2007年に亡くなったそうで、もっとこのお二人の対談を読んでみたかったので残念です。この方の本もそのうち読んでみたい。
3投稿日: 2022.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて手に取った本。つくづく、寒雲セラーさん、臨床心理士さんとは大変な仕事だ、、と痛切に感じさせられる。そして、きついと感じている人たちに、何もアドバイスせず、ジャッジせず、上も下もなく、ただ、一緒にいる、そこにいる、ということをする。そのことの偉大さは、実際にクライアントとして河合さんのもとでお話しした方にしかわからないだろうが、でも、とても救われるんだと思う。 博士の愛した数式を切り口に話が進むので、読んだ方はかなり楽しめると思う。
0投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ井戸を掘る際に、相手を強く牽引してはいけない。強者であってはいけない。相手と同等でなければならない。屈んで目線を合わす。良き聞き手でなければ。
0投稿日: 2022.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度も読み返したい良本。 図書館で借りて読んだので、我が家の本棚用に一札購入したいと思います。 最も印象に残った言葉は 佐野・・・布の修理をする時に、後から新しい布を足す場合、その新しい布が古い布より強いと却って傷つけることになる。修繕するものとされるものの力関係に差があるといけない 河合・・・そうです。それは非常に大事なことで、だいたい人を助けに行く人はね、強い人が多いんです。そうするとね、助けられる方はたまったもんじゃないんです。そういう時にスッと相手と同じ力になるというのは、やっぱり専門的に訓練されないと無理ですね。我々のような仕事は、どんな人が来られても、その人と同じ強さでこっちも座ってなきゃいかんわけですよ。 読後に起きた思い ・箱庭療法用の箱庭が欲しい熱再燃(用途は、心理療法用ではなく、自分のお遊び用) ・博士の愛した数式を再読したい ・博士の愛した数式の映画を見たい ・河合隼雄さんの本を読みたい
7投稿日: 2022.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログちくまプリマーの「物語の役割」と同じタイミングで読めてよかった〜 お二人の暖かく優しい人柄が伝わってきた、癒された。辛いときにまた読みたいな ・河合隼雄さんは現代文の評論くらいでしかお名前を知らなかったけど、他の著書も読んでみたくなった。臨床心理士をされていたのも知らなかった。「僕は大丈夫、アースされてるから」って言葉は胸に沁みた。私はすぐ溜め込んでいっぱいいっぱいになってしまうから。 ・修復するときには、修復するものは元のものより強いとだめ、物語も人生においてそういった役割を担っているんじゃないかというエピソードに関して、占いとか宗教とかって少しそういう役割を持っているのかなとか思ってしまった ・本編はお二人の対談を第三者として覗かせてもらうみたいな感じだけど、あとがきで述べられていた小川さんの想いも感動した〜河合さんがご存命でないの本当に残念だな 「物語の役割」の感想の方にも書いちゃったけど、内容が思い出されたTED talkのメモ https://www.youtube.com/watch?v=y9Trdafp83U https://www.youtube.com/watch?v=XgRlrBl-7Yg&list=PL6QbRcFJo4tsyytRZs0LkGQ_C3HCjuTZ8&index=13
1投稿日: 2022.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「物語は既にそこにある」ーー『博士の愛した数式』ひとつのフィクションをとっかかりに、小説家・小川洋子さんと臨床心理学社・河合隼雄さんが紡いでいく“物語”をめぐる対話。現実のフィクション性や人間に内在する矛盾に、物語という枠組みだけが説明を与えてくれる。
0投稿日: 2022.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ似たような悩み、同じ病状、同じ類型であっても、そこに至るルートには独自性があって。 その解決に一定のパターンがあっても、至る思考ルートには独自性がある。 どこの視座に立つか。マクロに見ればどんなこともパターン化する。ミクロに見れば独自性はある。物語とはミクロなものです。「人間」が主語の物語が面白いだろうか? 必ず個別な物語を人は楽しむでしょう。そして個性というのはミクロに見れば誰にでも見つけられるものだから、価値が無いようで有るかもしれない矛盾とどう生きていくかが物語になるのでしょう。
0投稿日: 2021.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄という人物に触れなかった人生が恥ずかしい…。文化界の大家であると、経歴を見ずとも実感させられた。"おひさまにあててポカポカふくらんだ座布団のよう"な人。 対話集なので軽やかにさらさら読めるが、さらさら素通りすることはできない言葉が詰まっていた。 小川洋子、河合隼雄ともに、本当に厚みのある人だと思う。 やさしくてたおやかな物言いでも、芯と実感が通っている。 この本の良さを伝えられる語彙が自分にはなくて嫌になるなあ。 ちょうど、フルHDのテレビ画面では4KテレビのCMが意味をなさないのと似ている。 本当に、出会えてよかった本。それに尽きる。
3投稿日: 2021.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
心理学者で文化庁長官の河合さんと、優しい小説を書く小説家の小川さんの対談。 河合さんの死去で、もっと読めなかったのが残念。 一神教のキリスト教圏と、多神教の日本との、厳密さと曖昧さの違いについて語られていたのが面白かった。 キリスト教圏の人は、厳密さ、厳格さの中で生きていて、例えばポルノを見ない、と決めている人は、その国だけでなく外国に行っても絶対に見ない。見たら人格が崩壊してしまう。 日本は曖昧さの中で生きていて、日本ではポルノを見ない教育者が、パリに行ったときに一度見たからって人格崩壊はしない。 無責任さ、曖昧さを良しとして生きる文化。 街の中にも境界がない。 科学が進歩して世界が厳密になっていく中で、日本には科学の厳密さと多神教の曖昧さ、矛盾したものがある。それを共存させる人生観、世界観はないだろうか。 生命はもともと矛盾を孕んでいるもので、それを受け入れて、ごまかさずに生きていくより仕方ない。 「その矛盾を私はこう生きました」というところが「個性」となる。 理屈のつかない曖昧さ、矛盾を愛しながら生きられたら、人間らしく美しい生き方ができるのだろうな。
0投稿日: 2021.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
河合隼雄の対談集を読むのはこの本が初めて。読みやすくてスラスラと読めていってしまうが、大事な言葉を取りこぼさないようにと時々ゆっくり読んでは想像も広げていた。 心に残った言葉。 ・新しい布が古い布より強いとかえって傷つけてしまう。相手と同じ力になる。 ・意味ないけど、その子の世界にはまだいる。その子のいる世界の内側にとどまる。 ・つくらないけど、その世界に入っている。
0投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人に目を向けられる程、余裕がないこと多々。 だけど、こんな事が自然とできるようになりたいとの希望を込めて。意識してみてこ •意味はないけど、その子の世界にいる。 意味のあることをやり取りするのが重要ではなく、その子のいる世界の内側にとどまる。 心がそこにいてだまっているなら、なんぼ黙っていていたもいい。その人の世界から出ない。 •望みを失わずにピッタリ傍におれたら、もう完璧なんです。 何気なく人を励ましてるつもりでも全然励ましたことにはなってなくて、むしろ中途半端に放り出してる。
0投稿日: 2021.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨床心理学者の河合隼雄先生と人の心を描き続ける小説家小川洋子が『博士の愛した数式』を皮切りに様々なテーマについて語った対談集。 各ページのやり取りに心がポッと温かくなります。 長い本ではないので、割とすぐに読めます。 要約やかいつまんでの書評はできない内容ですが、自分の人生を物語として捉えるのっていいですね。 特に様々な人生と苦悩に向き合ってきた河合隼雄先生が言うと説得力がある。 特に最後の欧州と日本の違いは面白かった。 日本人は意志を曲げたり、間違いを認めることは何とも思わないが、西洋の文化からすると、どうしても認めらないようなことになる。 それは西洋には確固たる主体の自分がいるから、そしてそれは一神教をベースにしているからではないか。 あと西洋宗教は原罪であり、日本宗教は原悲であるというのもなるほどと思った。
4投稿日: 2021.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の人生の教科書がまたひとつ増えました。 大切な、大切な本になると思います。 あとがきで泣いてしまったのは初めてです。
6投稿日: 2021.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ正確には読むの断念しました。 「博士の愛した数式」は読んだけど、既に忘れてて二人の対談についていけませんでした。残念。 けれど、タイトル「生きるとは、自分の物語をつくること」、これ素敵な言葉だなと思った。
1投稿日: 2021.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時、文化庁長官もつとめていた心理学者で心理療法家の河合隼雄と、小説家である小川洋子の対談が主な内容です。2005年と2006年に行われた二回分の対談が約100ページ、対談の翌年に亡くなった河合氏に向けた小川氏による追悼文が約30ページです。 第一回は2005年の雑誌・週刊新潮における対談で、映画化作品も含めて小川氏の小説『博士の愛した数式』を主要な話題としています。これを受けて翌年に行われた第二回は、カウンセリング、箱庭療法、『源氏物語』、宗教(小川氏の両親・祖父母が信仰していた金光教についてを含む)、日本と西洋の価値観の比較など、扱うトピックは様々ですが、大きくは物語とは何であるかを巡る対話となっています。全般に、どちらかといえば小川氏が河合氏から知見を引き出す傾向が強かったように思います。河合氏がときおりダジャレを発すのは、村上春樹との対談同様でした。 二回目の対談の終わり方を見る限り、継続的な対談が企画されていたように見受けられます。文字サイズも大きく一冊の書籍としてはボリュームが不自然に少ないのは、対談から二か月後に河合氏が倒れて翌年に亡くなったために計画が頓挫した影響でしょう。自然と小川氏による追悼文は、二回の対談を振り返る意味合いが色濃くなっています。 以下、印象に残った言葉を私なりに箇条書きで要約して残します。 ・友情は属性を超える ・良い作品(仕事)は作り手の意図を超えて生まれる ・分けられないものを明確に分けた途端に消えるものが魂 ・やさしさの根本は死ぬ自覚 ・魂だけで生きようとする人は挫折する ・カウンセラーには感激する才能が必須 ・一流のプレイヤーほど選択肢が多い ・奇跡のような都合のよい偶然は、それを否定している人には起こらない ・物語を必要としなかった民族は歴史上、存在しない ・小さい個に執着すると行き詰まる ・人間は矛盾しているから生きている ・矛盾との折り合いにこそ個性が発揮され、そこで個人を支えるのが物語 ・望みを持ってずっと傍にいることが大事
13投稿日: 2020.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きることは物語であり、他者との繋がりもまた物語である。身近で大切な誰かの喪失を受け止め乗り越えるのためにもまた物語が必要である。
5投稿日: 2020.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きることが表現であり、物語ることであるならば、物語は生きるとともにあるのだろう。見えない物語に触れる手は、誰かの者ではなく誰の者にもならない、その手が物語を誰かに伝えるならば、その物語はきっと形になるのだと思う。
0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019.9月。 河合隼雄さんと小川洋子さんの対談。素晴らしい。河合隼雄さんの懐の大きさ。人間力。包容力。すごいなあ。こんな方がいるんだなあ。もっともっと生きて、今の時代にいて欲しかったなあ。大切なお話。手元に置いておく。 人を助けに行く時はずっと相手と同じ強さになる必要がある。 キャッチボール。 自分の意図を超えたおもしろさ、自分の手に負えないこと、思いがけないことがおこる。プロ。 わけられないものをわけてしまうと何か大事なものを飛ばしてしまう。その一番大事なものが魂。分けられないものを明確に分けた途端に消えるものを魂という。区別を全部消してものを見る。 優しさの根本は死ぬ自覚、 魂の世界で繋げていくのは子ども。子どもは本当にすごいもの。 命に関わる仕事。 昔話はホラだけどある意味本当。真理。 自分の物語を発見し自分の物語を生きていく。 苦しみを経ずに出てきた作品は患者には魅力がない。 患者の深い悩みに付き添ってどこまでも下へ降りていく。 常識は忘れていないけど縛られたらダメ。 一流ほど選択肢をたくさんもっていてその中きらパッと最善の方法を選ぶ。下手な人ほど選択肢や答えが一つしかない。同じ言葉でもたくさんの中から選ばれた言葉か、唯一それしかもってない人の言葉かで受け止められ方が違う。 それしかないは駄目。 都合のいい偶然が起こりそうな時にそんなこと絶対起こらんと先に否定してる人には起こらない。気づく。 治る場に必要な空気や水を患者さんに供給。患者さんが治している。自分が治そうとしてしまうが、そういう時も必要。それがあって今がある。最初から適切なものを選択して供給できるというわけにはいかず無駄と思える迷いの時が必要。 下手な人ほど質問する側が勝手に物語を作ってしまう。相手を置き去りにして自分が了解して安心したい。 患者の世界の内側にとどまる。黙ってて心がよそに行きかけた時もその人の世界から出ない一言をかける。大事にして、変なものを付け加えないように、変に触らないように、ただそこにいる。 ごまかせるのが普通の人。大きい問題を持ってる人はごまかしようがない。解釈をしないで鑑賞する。 砂場遊びはもなすごく大事。形なきものに形を与える天地創造。 鍛えられて教えられてを繰り返してだんだん訓練される。 罪の意識に対してあなたは悪くないというのではなく、そこを追求して追求してその人の人生ができていく。罪を根っこにしてまた果実が実る。荷物を礎にする。頭の上にのっけるのではなく、生きていくために踏ん張る足を支えるものに変える。 生きることに心を奪われすぎて死ぬことを忘れているから変なことが起きる。 個は無限な広がりを持っているのに人間は自分の知っている範囲内で個に執着するから行き詰まる。個を大きな流れの中で見る。 矛盾したものを持つ。厳密さと曖昧さの共存。 矛盾との折り合いの付け方にこそ個性が出る。そこで個人を支えるのが物語。 最後は地球にお任せしてる。アースされている。 望みを失わない。まだ大丈夫という望み。一緒に苦しんでるけど望みは失わずピッタリそばにいる。強くいなければならないし弱さも分からなくてはいけない。根本的にすごく強くないと駄目。共倒れにならないように。
0投稿日: 2020.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前に読んだときはピンと来なかった2人の会話が染み込んできた。 曖昧を持ち合わせたまま生きてよいのだということ励まされた。合理性を過剰に求めなくていいことにも。なぜ小説が、物語が人間に必要なのかがよくわかります。とても癒される。
4投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子さんも河合隼雄さんも、お話を聞くのが抜群にお上手なのだなと感じる。ひと文ひと文が心にしみて、癒される。
4投稿日: 2020.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 クライアント自身のもつ力を信じて ただ、寄り添いアースとして存在する。 そんな存在に近づいていきたいです。
4投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔、ユングに興味があった時、河合さんの講演を聴きに行ったことがある。 ユーモアに溢れたとても面白い公演だった。 一番最後に、質問を受け付けていて、手を挙げた人がいた。 「どうしてこの道に入ろうかと思ったのか」という問いだった。 著作を読むと、動機について、教師をしていた時期に生徒の悩みを聞き、それを何とかしたいと思ったと、よく書かれてあった。 しかし、その時の答えはちょっと違っていた。 「何かこういう研究をしないと、自分がおかしくなってしまうのではないかと思った」と吐き出すように言われたのだった。 私もこんな闊達で明るい人が、どうして重く苦しい心の研究をしているのだろうと不思議に感じていたので、何となく得心がいったのをよく覚えている。 ご自分の中にも患者さんの抱えているものに匹敵する重い何かがあったのだろう。何かは知らないけど。 恐らく仕事を通してそれは浄化されるのだろう。 小川洋子さんの小説の世界を題材に、和やか、かつ刺激的。河合さんの最後の対談。 西洋人と日本人の倫理観の違いが興味深い。
6投稿日: 2019.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子と河合隼雄との対談。 カウンセリングは必ずしも優しく接するのではなく、人間として接すると言う内容に、その方が信頼できるのかと新たな発見。 小川さんはどちらかというと感情面で、河合さんは建設的な話をするなといった印象。 例えば、日本人がたくましいからという小川さんに対し、河合さんは文化から逃れられていないと。 生きている人には必ずストーリーがある。
0投稿日: 2019.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ悲しい出来事を受け入れるには、その事実だけでなく 物語が必要とのこと。 なるほどなぁ。 大切な人が病気で亡くなった事実だけでは受け付けない。 こんなタイミングだったから、とか これだけ頑張ってた人だから、とか それぞれの物語をつけたくなる衝動を言語化してもらった。
5投稿日: 2019.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄さん、最後の対談集。小川洋子さんも素敵な物語を書く方。もっともっもお二人のお話聞きたかったなあ。
4投稿日: 2019.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小説家・小川洋子さんと心理療法家・河合隼雄氏との対談。 河合先生は本当に様々な人と対談されている。先日読んだ、松岡和子さんとのシェークピア対談のときは、登場人物を心理分析するといった対談だったけれども、今回の小川洋子さんとの対談は、どちらかというと「小説家」と「心理療法家」の共通点を発見する対談だったように思う。 二部構成の最初は、小川さんの代表作「博士の愛した数式」をめぐっての語り合いだ。河合先生がもともと数学科の出身で、数学の教師もされてたというから、河合先生は、博士の立場やその教え子ルート君の立場になって、この小説を語っている部分も多い。 第二部は、まさにこの本のタイトルどおり「生きるとは、自分の物語をつくること」ということについて両者は意見が一致している。 生きることに意味を見出すことができなくなったクライアントが河合先生の箱庭療法で、自分の生を表現したり、クライアントが箱庭をつくっていく過程で、人生をを蘇生していく様子が語られている。箱庭づくりは、自分の物語をつくることと言える。 一方、小川さんは「自分は小説家だから小説を書いているのではない」とあとがきで独白している。「誰もが生きながら物語を作っているのだとしたら、私は人間であるがゆえに小説を書いている。」と語り、「世界中にあふれている物語を書き写すのが自分の役割」とも語っている。 二人の対談者の共通点は、「生きる」ことを支える人であるということだろうか。 この二部の対談の直後に、河合先生がお亡くなりになられたようで、小川さんのあとがきは、河合先生を忍びやや長めの内容となっている。共通点のあるお二人の対談をもっと深めてほしかったような気がする。
2投稿日: 2019.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログvol.141 あなたの物語はいま、何ページ目くらいでしょうか? http://www.shirayu.com/letter/2012/000280.html
0投稿日: 2018.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去の事象は単なる点であり、無数の点を繋ぎ線にし、面にしていくのが歴史(HISTORY)だとどこかで読んだ。物語(STORY)も、これと同じことなのかな、と、この本を読んで思った。とりわけ印象的だったのは引用個所のとおり。 同様に、河合隼雄も自分の仕事について「来られた人が自分の物語を発見し、自分の物語を生きていけるような「場」を提供している」(p.48)と語る。 小説が自分の心を映す鏡だとするならば、自分は様々な物語を読んで様々な面で自分を映し出すことで、単なる安心のための物語ではない、曖昧さも含んだ真実(というものがあるとするならば)に限りなく近い自分の物語をつくろうとしているのかも知れない。
0投稿日: 2018.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ブクログ談話室でオススメしていただいて読了。 恥ずかしながら河合隼雄さんの存在を初めて知ったのですが、こんなにも真の意味で人は暖かくなれるのかと、その功績に触れてみたいと思う。ご存命でないのが非常に残念。 ありのままに、死をも受け入れて生きていけば人はもっと優しくなれる。あなたも死ぬし、わたしも死ぬ。当たり前のことなのに、改めてその事実を受け入れて生きていきたいと願う。 何かにつまづいている時にゆっくり読みたい本。
6投稿日: 2018.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むだけで、カウンセリングを受けてるような気分になる。悪いものを悪いまま受け入れる「原罪」の話は、河合隼雄先生の包容力を感じると同時に、ポジティブ思考だけではかえって自分を見失うんじゃないかという、私の違和感への答えになった。不思議な物語を生み出す小川洋子さんとの対談は、期待通り、面白かったのだけど、それよりも「あとがき」が素晴らしくて。 長いあとがきを読むことで、少しずつ、読むことの叶わなかった対談の続きの物語が、別の形で昇華されて行く気がした。 それにしても、河合隼雄先生の遺作が小説であったことと、この対談のタイトルとの間に不思議な符合を感じるのは、考えすぎだろうか。
5投稿日: 2018.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川さんの『アンネ・フランクの記憶』の後に読むと、なおさら心に入って来る。小説家とカウンセラー、職業は違えど、「物語について、これほど柔軟で、どんな人の心にも寄り添える解釈を示したのが、作家でも文芸評論家でも文学博士でもなく、臨床心理学の専門家であったというのは興味深い事実」と小川さんも記している。人の物語に寄り添う河合先生の姿が、とてもよく伝わってきた。
4投稿日: 2018.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄さんの「こころの子育て」がビビッとき来たので、タイトルに惹かれて読みました。 「博士の愛した数式」に沿った内容だったので、読んだことない状態では、共感度が弱まったかも。小説を読んだら、再読したい。
0投稿日: 2018.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ混沌の中に生きるということ。物語そのものの類型と、それとはべつに、自分のものとして生きるうえでのよすがになる力とを思う。梨木香歩さんや荻原規子さんのエッセイも思い起こして、偶然のちからということを、考える。
4投稿日: 2017.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感できる内容。これを自然と言語化できるような人になりたいと思う。温かい。 ▼概要 ・臨床心理学者の河合隼雄(ユング心理学の第一人者)と、 作家の小川洋子(代表作「博士の愛した数式」)の対談を本にしたもの。 ・人それぞれの人生を物語として捉える2人が、 「生きるとは何か」「物語の存在意義とは何か」「日本の宗教観から現れる特徴」などを心理学、哲学、文学に基づいて語り合っていく。 ▼内容 ◯物語について ・人はしばしば、生きていくうえで難しい現実をどうやって受け入れていくかということに直面する。そんな時、自分の心の形に合うように、その人なりに現実を物語化して記憶にしていく。 ・その物語作成を患者に促すのが臨床心理学者であり、その物語を実際に作り出すのが小説家。 ・人は、自分とは異なる物語(現実、架空を含む)と接することによって、それに反したり、それを受け入れたりして、自分の物語を作っていく。 ・そういう意味では、心理学と文学は近しい部分がある。 ◯源氏物語について ・「源氏物語」は、多神教の日本だからこそ、世界でも初期に生まれた物語。 ・一神教では神の力が強いため、人間が作る物語は神の創ったものに基づいていく(神話など)。 ・日本の宗教観、かつ女性という出世ストーリーに携わらない立場の人(定められた物語を持たない人)だからこそ、書かれた作品。 ◯その他 ・日本語に主語がない理由 →日本人特有の、自然、他者、場の空間との境界の薄さ。曖昧さ。 →日本の謝罪文化は、人格の柔軟性が一因。謝っている時の人はその人ではなく「謝るべきペルソナ」であると捉えている。 ・やさしさの根本は死ぬ自覚
0投稿日: 2017.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。序章の「魂のあるところ」は、博士の愛した公式の解説と分析でした。後半の「生きることはー」につながります。箱庭の解説もあり、興味深い。
0投稿日: 2017.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて読む。 誰かと比べて落ち込んだり、優越感に浸ったり、その瞬間での喜怒哀楽はあっても、振り返れば、それは全部物語の一つだ。 そう思うと全てに意味があるように感じるし、楽しくなる。
0投稿日: 2017.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ混沌とした心を肯定する温かくてありがたい眼差しに溢れた本だった。物語を聴く人と物語を書く人、神さまのような視点から話される言葉に、じわじわとこころが動く。インタビューをして文章を書く仕事をする人の端くれの端くれとして、刻んでおきたい言葉がたくさん。
0投稿日: 2017.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「生きるとは、自分の物語をつくること」(2008.8刊行、2011.3文庫化)、作家小川洋子さん(1962~)と臨床心理学者河合隼雄さん(1928~2007)お二人の対談集です。読んで、数(字)の面白さとカウンセリングはとても難しいものだということが少しだけわかりました。基本的に、私にはとても難解な対談内容でした!
0投稿日: 2017.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ息の合った対談、分量も多くはないし、すぐに読めます。さらっと読めるわりに内容は深く、掘り下げるのもきりがない感じ。 河合氏のカウンセリングの際の「聴く」姿勢は、個人的にこう聴いて欲しいと思っている内容とぴったり一致していた。
0投稿日: 2017.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ裏表紙にある通り河合隼雄さんの最後の対談なのだと認識して読み始めたはずなのに、終わりに差し掛かる頃にはすっかり頭の隅っこの方に追いやってしまっていたようです。「また今度」と手を振った直後に死を思い出した(?)とでも言えばいいのか、強烈な余韻の中に取り残された気分です。ハリーポッターのシリウスかダンブルドア先生かが死ぬ場面か、最終巻で夢か現か分からない状態でプラットホームで先生と話していたはずがホワイトアウトする場面か、辺りと似たような感覚かもしれません。要するに「もっと話を聞きたいのに!」「教えて下さい、どうしたらいいのか!」という気持ちの問題です。心を落ち着かせてくれる、ときにはクスッとさせてくれる、絶妙な話を展開してくれただけに。 二人の対談の中で今の自分の心にビビッと来たのが、昔の人は死ぬことを考えていたけれど、今では生きている時間が長くなって生きることを考えるようになった、というようなくだりです。学生の間はテキトウな間隔で社会的な区切り目があったのが、大人になったら還暦辺りまではしばらくノンストップな感じがあって、イマドキお年寄りと呼ばれるようになっても大病をしない限り寿命が分からない具合になっていて、そういうことを考えてたまに広場恐怖症のような感覚に苛まれることがあります。それと同じ位、人間どれだけスケジュールが未定でも、最後の一日に死ぬことだけは決まっているという事実を唐突に考えて背筋が凍るような気分になることもあります。ただし極端に気持ちが沈んでいるというわけでもなく。でも、どちらも割と人として普通なことで、そこに伴う恐怖心が物語を生んでいるということ、そして死んでからの方が長いという表現。別に新しい言葉だったわけではないような気もするけれど、悶々としていたこのタイミングで欲しい言葉に会えた感じがして嬉しかったのです。 後は西欧一神教の世界観の話。日本人もキッパリしている人はキッパリしているけれど、ケースごとに細かったり、自覚無く軸が曖昧だったりして、一神教の世界の人からみたときに全く一貫していないと思われてもおかしくないのでしょう。私はキリスト教に触れざるを得ない生活をしてきたからか、一時その点で馬鹿みたいに葛藤したことがありました。細々としたところにおける自己矛盾に対する罪悪感みたいなものです。変なベクトルの真面目さはもう捨てよう、とどこかで思ったもので、今では若干思考を放棄していますが。でも、とにかく言わんとすることがよく分かった分、印象に残る話でした。尻つぼみ気味に終わっておきます。いくらでも対談に混ざり込んで傍で勝手に適当に雑談する感じで、ペラペラ話せそうですが。
11投稿日: 2017.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「博士の愛した数式」を軸に。 心理学者河合隼雄氏と小説家の小川洋子による対談エッセイ。生きること、書くこと、カウンセリング、いろいろな視点から語られる対談だが、絶筆?ではないのか、対談の途中で河合隼雄氏が亡くなられているため、対談の続きがない。それでも、小川洋子が、博士に惹かれた家政婦さんのように河合さんのあたたかな眼差しや深い洞察に惹かれていることが強く感じられて、読みやすく面白い本だった。
0投稿日: 2017.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ故・河合隼雄さんと、小川洋子さんの対談集。河合さんが亡くなられたことで、完結しなかったものだ。人は、目の前の現実を、物語にしていく。言い方を変えれば、意味を与えていく。そのことで、科学や論理では決して解決ができない、矛盾や運命を乗り越える力を人は持ち合わせている。震災復興はまさにそうだが、社会課題の多くは、論理だけで解決することはない。社会にかかわる団体は、物語や意味の力を理解しておく必要がある。
0投稿日: 2016.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログつらいことも語る事で、自分の中で昇華できるんだろうな。 それを人間は神話の時代から行ってきた。 河合さんと小川さんの素敵な対談集。
0投稿日: 2016.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄さんと小川洋子さんの対談集+小川さんによる長いあとがき。 というのも、本来はもう少し対談の章が続くはずだったのが、それが実現しないうちに河合先生が亡くなってしまい、最後が追悼文的あとがきになったのだとか。 河合隼雄さんはユング分析心理学の第一人者で、臨床心理学者。著書や色んなジャンルの人との対談集も数多く出していて、私は20代半ばくらいまでのとても深く悩んで病んでいた時期に、河合先生の本にものすごく救われた。 元気になるにつれて本を開くことは減っていって、この対談集は本当に久しぶりに読んだ河合先生の言葉だったけれど、心がそれなりに元気なときに読んでも自分の中に深く残るものはたくさんあった。 小川洋子さんの著書「博士の愛した数式」にまつわる対話も多く、この小説を読んだ人なら楽しく読めると思う。 人間は、辛いこと悲しいことも経験しながら生きていく。そこにはなかなか乗り越えられない出来事もあるし、思いを引きずったまま生きていくこともある。 そうだからこそ、人は自分の人生を物語化して、整合性をつけようとする。 「ああいうことがあったから、今の自分がある」と思ったりする。人生のひとつひとつが分離したものと考える人は少なく、多くの人はすべて繋がっているものと捉える。 「どうして小説を書くのか」と問われたときしっくりくる答えを出せなかった小川さんが、物語を紡ぐ意味に気づいた瞬間の話がとても興味深かった。 素人でただ趣味で物を書いているような私でさえ、とりわけ長い文章を書いてそれを人に読んでもらって、その人に言われたことで物語の中で起きている偶然の奇跡に気づかされることがある。 意識ではなく、何かに導かれたような偶然。 だからこそプロの物書きである小川さんがそういう偶然に触れることはたくさんあるはずで、理屈では説明できないところに物語の面白さがあるのだと思った。 ユング心理療法の「箱庭」、実は私も中学時代の不登校だったときにやったことがある。その時は、こんなもので何が分かるんだろう、と思っていたけど、きちんと意味があって見方があることを、つくづく知る。 昔読んだ河合先生の著書を、今一度読んでみようかと思った。
3投稿日: 2016.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『心音を聴きながら』 少し前に私は小川洋子を病室で昔話を聞かせてくれるとおばあさんのようだと言い表したことがあった。言葉少なくでも芯のある声で、見たこともない世界の話をたくさんしてくれる、死を間近にしたおばあさん。私はその時いつも5、6歳の幼い少女で、長い長い坂を登ってそのおばあさんに会いに行っていた。 その小川さんが私のように5、6歳の少女になって会いに行っていたのが河合隼雄さんなのだと思った。河合さんの前にいる小川さんは幼くてなにも知らない、無垢な少女だった。今日あったことを一生懸命話して、興味のあることを突然話して、おじいさんを困らせたり。そんな風に感じた。 決して、わかった気にはなっていない。だけど、小川洋子という人について少しだけ深めることができた。ああやっぱり、この人は宗教に近しい人だった。人のたくさんの人の死に関心がある人だった。そして、他人の背中に悲しみを分かち合える人だった。私の中で、染み込んでいくようにたくさんのああという理解が綺麗に落ちていった。
1投稿日: 2016.06.12タイトルがすべてをあらわしている
小さく、弱い存在へと寄り添う物語をつくりつづけてきた小説家の小川洋子と 他人が物語を見つける/回復する手伝いをしてきた臨床心理士の河合隼雄。 人が生きていくうえで、難しい現実とどう折り合いをつけていかなくてはいけない。 そのとき、ありのままでは受け入れられず、心のかたちに合うように、 その人なりに現実を物語化して記憶していっているはずだと小川はいう。 小説でひとりの人間を描く時、作家はことばやお話しという形で取り出して、 それぞれの積み重ねてきた記憶を再確認するのだと。 一方で臨床心理におけるカウンセリングは、 カウンセリングに来た人が、悩み迷い失いつつある自分の物語を発見し、 その物語を生きていけるような「場」を提供することだと河合はいう。 結局どちらもひとりの人間がことばと物語でもって、 いかに生きるのか、生きてきたのかを見つめることなのだ。
1投稿日: 2016.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きていたら、不条理なことに出会う。時には、自分の心がとんでもない方へ飛んでいってしまいそうになったりもする。 そんな時、ただただ伴走者のように、そこにいてくれるのが「物語」。一呼吸したら、また、一歩、一歩、歩き出せるように・・・。 自分で自分の「物語」が作れなくなった時、物語を作るお手伝いをするのが、臨床心理士のお仕事で、個人の「物語」を普遍的なものにして、多くの人に伝えるのが作家のお仕事。 自分の魂に語りかけてくる「物語」の生まれるところ。
0投稿日: 2016.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄氏が病に倒れる前に、『博士の愛した数式』の作者小川洋子さんとの間で実現した最後の対談。生きることがいとしくなります。
0投稿日: 2015.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと長生きしてほしかったな河合隼雄さん。 手元に置いて定期的に読み返したい。 「のぞみのない時はひかりです」 「あっ、のぞみの次はひかりだ」 「こだまが帰って来た」 とかさ、ぐっとくる。深い。 少し長すぎるあとがきも良い。
0投稿日: 2015.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ“個人が内面の混沌を物語の形で受け入れるのと同じように、国家や社会もまた、その集団の根底に横たわる不安や不満や傷や憂いを言葉で表現することにより、対立する相手集団と歩み寄れるのでは? そのような社会的役割を物語が果たす可能性について” (P150)
0投稿日: 2015.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログお二人の著書をあまりちゃんと読んだことが無いのにタイトルに惹かれてよんでしまった。 いつでも傍に置いてペラペラめくりたい軽快なやりとり。 こんなふうにお茶しながら会話したら楽しいだろうなと思わせてくれる一冊。
0投稿日: 2015.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ対談。河合先生が逝く前に実現して良かった。そしてその内容が世に出て良かった。カウンセリングの難しさと、人生を述べられる先生は宗教家のようにも映った。「やさしさの根本は死ぬ自覚。」「あなたも死ぬ、わたしも死ぬ、ということを日々共有していられれば、お互いが尊重しあえる。相手のマイナス面も含めて受け入れられる。」2015.3.18
0投稿日: 2015.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
作家、小川洋子と河合隼雄の対談集。 対談は終わっても終わりではなく、また次に会うときに二人の会話はまた始まるんじゃないかと思う。 次は会えないこともあることを人は知っていながら、忘れてしまう。この本を読んで、河合隼雄さんはもうこの世にいないことを想った。人が死ぬということは、その人からもう言葉や物語が生まれないということなのだと思った。 その人の言葉、物語が自分の手の中に重さを持って存在している本もその人の物語と一緒に生きていくもの。 ネットの中にあれば、ものとしての本はいらないのではないか、そして場はいらないのではないか・・そうした問いへの合理的な答えは分からないし、説明したいとも思わない。 自分の手の中にある本が存在していることの意味を自分が感じるだけ、ただそれだけでよいのではないかと思う。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 印象に残った言葉 ・『臨床心理のお仕事は、自分なりの物語をつくれない人を作れるように手助けすること。小説家が書けなくなった時に、どうしたら書けるのかともだえ苦しむのと、人が「どうやって生きていったらいいのかわからない」と言って苦しむのとはどこかで通じあうものがある。』(小川洋子) ・やさしさの根本は死ぬ自覚(河合隼雄) 私も死ぬし、目の前の人も死ぬ。 明日がその終わりかもしれない。そうした当たり前のことを自覚しているだけで、かかわり方は変わるんだと思う。
1投稿日: 2015.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログカウンセリングの傾聴の話を聞いていて、沈黙でもいいから、相手の世界にいつづけることの大変さ難しさ大切さを感じた。
0投稿日: 2015.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本の内容】 人々の悩みに寄り添い、個人の物語に耳を澄まし続けた臨床心理学者と静謐でひそやかな小説世界を紡ぎ続ける作家。 二人が出会った時、『博士の愛した数式』の主人公たちのように、「魂のルート」が開かれた。 子供の力、ホラ話の効能、箱庭のこと、偶然について、原罪と原悲、個人の物語の発見…。 それぞれの「物語の魂」が温かく響き合う、奇跡のような河合隼雄の最後の対話。 [ 目次 ] 1 魂のあるところ(友情が生まれるとき;数字にみちびかれて;永遠につながる時間;子供の力;ホラ話の効能) 2 生きるとは、自分の物語をつくること(自分の物語の発見;「偶然」に気づくこと;黙っていられるかどうか;箱庭を作る;原罪と物語の誕生;多神教の日本に生まれた『源氏物語』;「死」への思い、「個」への執着;「原罪」と「原悲」;西欧一神教の人生観;厳密さと曖昧さの共存;忘れていたことが出て来る;傍にいること) [ POP ] 「『若きウェルテル』は死ぬけれど、ゲーテは長生きする」。 人は生きるために物語を必要とする。 作家と臨床心理学者の対談。 共感に満ちたやりとりの中で語られる物語の不思議。 対談本は多いが、これほどの面白さは稀。 河合の死による中断が惜しまれる。 [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2014.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合さんの、カウンセラーとしての人への接し方にはだいぶ学ぶことがある気がした。助ける者が強すぎてはいけない、結論をだすのを急がずに寄り添うという在り方。 また、物語とは、人が矛盾との折り合いをつけるときに人の支えとなるもの、という話が興味深かった。 20180913再読 物語とは、こうだったらいいなとか、こういうつらいことにもこんな意味があるかもしれないとか、こういう考え方や対処もあるとか、こんなことを信じたいとか、色々な思いを重ねうるものかなあ、と思った。
1投稿日: 2014.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合先生の最後の対談本 残念なことに途中で亡くなられ後半は小川さんの文章 源氏物語のことに触れていた わたしはきちんとすべてを読んでいないので 今年の夏は源氏物語を読んで過ごそうかと思ったり・・ 恋に疲れた女が尼さんになる・・・という印象が強い しかし女性が使う平仮名により人の心の機微が表現され始めたのが紫式部や清少納言・・ どの作家さんの源氏物語を読もうか悩むのも楽しい。
0投稿日: 2014.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ良いにつけ悪いにつけ、必然になる偶然を呼び寄せられていく。 意図をしないと何もかわらないが、意図をして何かしても、思ったようには進まない。しかし、考え尽くした挙句に直感で選んだものには、選んだ当人が気づこうと気づかまいと、思いがけないつながりや次への道しるべとなるヒントがたくさん詰まっている。
0投稿日: 2014.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子による追悼文で涙しそうになった。リアルタイムで知ったときには、そんな気持ちにはならなかったのに。対談部分ではそんなに…って感じだったのに、後半の作家の筆致に感動した。
0投稿日: 2014.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログほろほろ、いい言葉が散りばめられている本。 読み終わって印象に残っているのは、河合先生の話していた、寄り添うお話。 人を励ます時に、人の話を聞く時に、なにも面白い反応はしなくていい。 大事なのは気の利いたことを言うのではなく、相手に寄り添うこと。相手のいるところまで降りていくこと。うんうん、そうなんだね、って言うこと。 そうすることで話し手は、自分で解決の道を見つけていくんだって。 そうなんだーって知ったら、らくーな気持ちになった。
0投稿日: 2014.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014年52冊目。 『博士の愛した数式』著者の小川洋子さんと、ユング派心理学や箱庭療法の日本での第一人者・故河合隼雄さんの対談。 人間の深層に降りていくことの意味を分かっている人同士で、絡み合いが絶妙。 「人は生きていくうえで難しい現実をどうやって受け入れていくかということに直面した時に、それをありのままの形では到底受け入れがたいので、自分の心の形に合うように、その人なりに現実を物語化して記憶にしていくという作業を、必ずやっていると思うんです。」 物語は過去に対してだけ効果のあるものではないと思う。 人間誰しもにある暴力性を、物語を書く・読む中で実現させることで、現実世界をやり過ごすことができる、そういう未来性もあるのだと。 「物語」、この言葉をまだまだ追求していきたい。
1投稿日: 2014.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生を再構築しようとする心を病んだ患者が、奇跡と言えるような偶然を契機にしながら立ち直っていくということが興味深かった。前向きに捉えるようになれば、人生には面白いことがたくさんあるということだとおもいます。
0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子と臨床心理学者河合隼雄との対談2編と、河合氏の死によりもうやってこない次回以降を埋める小川さんの長いあとがきで構成されている。 ふたりの会話は非常に軽やかでさっぱりしている。 高尚なこと、哲学的なこと、デリケートなこと、様々な話題が出ても、どこか優しくて穏やかな普通さが漂っている。 臨床心理学者として心の病を抱えたひとと向き合う中でのエピソード、『博士の愛した数式』にまつわる内容が特に示唆に富んでいる。 小川さんが書かれている通り、もっともっとふたりの話を聞きたいのに、もう二度と叶わないのが残念である。 http://www.horizon-t.net/?p=1105
0投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄は何度でも戻っていかなければならない、と思う。後からつくられたものであろうが自分の原点の一つ。人と関わるのが好き、というのではなく、その裏にあるもの、物語が開花していくダイナミズムへの優しさ、見守ることの喜びとでも言うのか。 沈黙の大切さについても語られていた。黙っている、しかし関心を絶対に外に向けず相手と同じ世界にいる。そういう関わり方の中で確実に変化が起こる、というあり方の記述。 小川洋子の小説を書く動機についての率直な述懐も心を打つ。河合隼雄の話は面白い細部に溢れている。充実した読書であった。
0投稿日: 2013.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ読み始めなのですが、心理学に憧れていた私が本格的な入門書に挫折して巡り合ったのが河合先生の著書でした。お亡くなりになってしまったことがとても残念です。 「博士の愛した数式」も好きな作品のひとつです。その著者である小川洋子さんとの対談!そして、「自分の物語をつくる」というタイトルに心惹かれて読んでいます。また、読み終わったら編集するつもりのレビューです。ただ、みなさんにぜひ読んでほしい、ということは今から変わらない感想になると思います。
0投稿日: 2013.10.26
