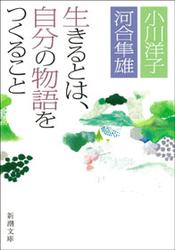
総合評価
(131件)| 40 | ||
| 43 | ||
| 24 | ||
| 5 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子、村上春樹といってること一緒すぎるけども大丈夫?って思っちゃった。コピーとは言わないけれども、それに準ずるような、なんか聞き覚えのあるかんじで、でも一段低くて、なんだか心配になってしまった。心の底からそう思っているのだとは思うけれども、本当にそのスタンスで大丈夫?無理してない?ってかんじ。特に人間にとっての物語の存在についての意見が。なんだか読むにつけ、本当に村上春樹のオリジナリティーみたいなものをひしひしと感じてしまう。対談自体はとても魅力的で、最近わたしが忘れ去っていたあらゆる物事、要素を思い起こさせてゆさぶられる、ああ忘れていた、こういうかんじだったと懐かしませる、そんな感じだった。
0投稿日: 2013.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄先生との対談をまとめた本書。河合先生が亡くなられたことで未完に終わっているのが唯一残念だが、タイトル通り「物語」が持つ意味や力、日本とキリスト教世界での生きることの意味など深く広い知識と、臨床心理の現場の経験から生み出される言葉は、学ぶことがとても多かった。 また、小川洋子氏の小説を河合先生が読み解くところでは、小川氏の知らないところで様々な偶然が小説の中で起こり、彼女の意図を超えたところで物語が勝手に動いていることも面白い。作家の意図を超える解釈の自由は許されるのだ!これがユングの集合的無意識というものなのか。無意識から汲み取られる物語。
1投稿日: 2013.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ魂、という言葉を、何らの衒いもなく使うことは可能だろうか。 小説家の小川洋子が、臨床心理士の河合隼雄に問い掛ける。 そして、その問いの中に、既に、答えの一部は含まれている。 分けられないものを分けてはならない。 つながりあった、というよりもむしろ、元々一つだった世界の中から、各人が各人にとって必要な物語を取り出すこと。 小説家は、その世界の中から、目に見える形で物語を取り出す仕事であり、臨床心理士は、その世界の中から、各人が物語を見出すのを手助けする仕事である。 生きていくために必要な物語を、自分の中に積み重ねていく。 小説家でも、臨床心理士でもない我々にとって、必要なのは、読むべき幾つかの本と、語らうべき何人かの友人だと。 「その恐怖や悲しみを受け入れるために、物語が必要になってくる。死に続く生、無の中の有を思い描くこと、つまり物語ることによってようやく、死の存在と折り合いをつけられる。物語を持つことによって初めて人間は、身体と精神、外界と内界、意識と無意識を結びつけ、自分を一つに統合できる」(P. 126)
0投稿日: 2013.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構軽い気持ちで読み始めましたが、最期の「少し長すぎるあとがき」にやられました。小川さんの作品は好きでよく読むのですが、その理由がわかりました。小説家とは、なんとも素敵な役割なんだなと実感です。
0投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログとても深い意味のタイトルだが、とても穏やかで、和やかな会話の中で、大切な言葉の端はしが読み取れる対談集。 「やさしさの根本は死ぬ自覚にある。あなたも死ぬ、私も死ぬ、ということを日々共有していられれば、お互いが尊重しあえる。相手のマイナス面も含めて受け入れられる。」 いつか誰でも死ぬとはいえ、自分が死ぬなんてこと、まだ考えたこともなかった。ゴールは誰でも死。そのゴールに向かって、自分なりの物語をつくるべく、一日一日生きている。そう思えば、楽しいこと、悲しいこと、辛いことなどいろんなことが自分の物語に彩りを添えている、と客観的に見ることができるのかもしれない。じわじわと生きる勇気を与えてくれる本。
0投稿日: 2013.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の中で人生に役立つ言葉が一つでもあれば読んで良かったと思う。 でもこの本は雑談しているような優しい雰囲気の中に、これでもかってくらい役立つ言葉が詰まってる。
0投稿日: 2013.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもと向き合う時の心構え、とても勉強になりました。人に寄り添うことは難しいですが、その先に希望の光がみえ、読了後、温かい余韻に浸れました(o^^o)
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ村上春樹氏も会いに行った、臨床心理学者・河合隼雄氏と、作家・小川洋子さんとの対談集。 お互いの立場から、いろんなテーマを語り合う。特に子供の心に関するものと、宗教によって神の立場が異なる話が印象に残った。
0投稿日: 2013.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
やっぱり彼女の書いた文章は、小説ではなくても静謐でその中に優しさがあるように感じる。佐藤多佳子も同時に読んでいたから余計にそう思う。 饒舌な文章ではないけれど、読む者をぐいぐいと引っ張っていくわけではないけれど、その言葉達は優しく響く。 この作品は河合隼雄との対談をまとめたもの。 ただ、途中で河合隼雄が亡くなったことで計画半ばで終わってしまう。彼女の「少し長すぎるあとがき」で、対談を待ち望んでいたこと、彼の言う偶然の導き、自分が小説を書くことについて述べている。 以前に、彼女の講演会に出席したとき、彼女は言っていた。 「小説とは、死者との会話。作家は、死への行進の最後尾を集めるのだ」と。この考えがまとまったのも、河合隼雄との対談で言語化されていたのかもしれない、と思う。 物語とは; 内面の深いところにある混沌は論理的な言語では表現できない。それを表出させ、表層の意識をつなげて心を一つの全体とし、さらに他人ともつながってゆく、そのために必要なのが物語である。物語に託せば、言葉にできない混沌を言葉にする、という不条理が可能になる。生きるとは、自分にふさわしい、自分の物語を作り上げてゆくことに他ならない。(126)
0投稿日: 2013.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子と河合隼雄との対談集。 妊娠カレンダーからときどき、読むようにしている小川洋子。 独特の視点をもっていて、表現法も女性らしい感性です。 河合先生は、言わずと知れた方。 ものの見方は優しいし、経験に基づく言葉は、含蓄にあふれている。 南伸坊との対談は、伸坊さんが苦手意識満載でしたが、 今回は、割ときちんとキャッチボールされていて、 読んでよかったと思いました。
0投稿日: 2012.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄と小川洋子の対談。 ブクログで「生きざまが描かれている本でのお勧め」を質問して教えてもらった中の一冊です。 夫も昔読んだことがあるらしい。 中でも箱庭療法の話が印象的でした。 箱庭の底に砂が敷き詰めてあるとは知らなかったんですが、それでぴんときたことがありました。 大学時代の心理学の授業で箱庭のビデオを見たんです。 そのときに虐待を受けた子のカウンセリング前と後の箱庭が紹介されてました。 その子がカウンセリング前に作った箱庭は、動物たちを戦わせていたんです。 そのときカサカサ言ってたのが砂だったのか、と10年以上前の授業のことを思い出しました。 ちなみにカウンセリングを受けた後は、箱庭の中で動物を遊ばせていました。 そんなことを思い出した本でした。 河合さんのカウンセリングをするときの姿勢、小川さんの小説が書けなくなった時の話。 共通する思いが繋がっていて深かったです。 箱庭の本、読んでみようかな。
0投稿日: 2012.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨床心理学の河合氏と作家の小川氏の対談2篇(初出は2006年、2008年に雑誌に掲載)を収録。長い「あとがき」を含めても、160ページに満たない。だから、買って手元に置くというよりも、待合室などに置いてあるのを手にとって、ぱらぱらとめくって目にとまったところから読み始めるような、そんな手軽な造りの本です。(文庫本ではなく、単行本で読みました) でも、生き方や哲学に通じる内容が込められていて、じんわりと心にしみてくる場面もあります。 臨床心理の専門家は、人が「物語」をつくりながら生きていることに気づき、その「物語」を大切にして治療していきます。 小説家は、「誰もが生きながら物語を作っているのだとしたら、私は人間であるがゆえに小説を書いている」ことに気づきます。 寄り添うことの難しさ、大切さに気づかされる、一冊です。
1投稿日: 2012.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の心に寄り添うという事がどれだけ難しく、忍耐の居ることか。 そして、それが『正しく』できた時に、人は『人』と『自分』の物語を共有出来るのだと理解し、それがどれほど『嬉しく』『楽しく』『尊い』事だろうか。と想像しました。 小川洋子さんの作品が好きな私は、彼女の作品を読む度に、どれだけ作者の意図に反した『うまいこと』を思い、考え、感想を抱いているだろうか。とそこにも少なからず興味を持ちました。 『生きるとは、自分にふさわしい、自分の物語を作り上げてゆくことに他ならない』 この言葉を読み、その自分の物語を振り返る際に、『うん。良い物語りを歩んだな』と、笑顔で居られる自分でいよう。とも思いました。
0投稿日: 2012.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「傍にいるということ」がどういうことなのか、わかったように思う。難しいことではあるけれど、それができるように努めたい。今の私には、光だ。
0投稿日: 2012.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨床心理学者の河合隼雄と作家の小川洋子の対談集。生きるということは自分の物語を作ること。物語が持つ力。読んでいて思うことは多く溢れそうなんだけれど、言葉に言い表すのが難しい。もっと何度も読んで、自分の中できちんと咀嚼したい。そう思わされました。 作家として物語を紡ぐことに、どういう意味があるのか。それを問われていましたが、それは読み手としてどう物語に向かうのかという問題でもあるでしょう。物語というものが必要とされる意味、それに向かい合いたい。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄さんと小川洋子さんの対談集。 河合隼雄さんの言葉には、優しさやらユーモアやら、いい尽くせないほどのスケールを感じます。 一度、大阪フィルの大植さんの企画で天下茶屋にある大フィルの練習場で河合隼雄さんのフルートを含めた演奏会が有ったのに行って来たんです。もうその頃には、文化庁長官をなさっており多忙だったはずです。しかしプロの人たちと演奏をするという事で、気合いの入った様子を感じました。 演奏が終わり、最後に大植さんが河合隼雄さんにインタビューをしていたのですが、締めくくりに大植さんが向けていたマイクをさっと奪い取り、シャレを言って会場がドッと笑うと同時に、何とも言えない柔らかな空気に包まれたんです。 その空気感は、河合隼雄さんが全ての人に好かれる根本だと思うのです。 この本の中にはそんな空気感と小川洋子さんの優しさがつまっていて、とても良い本になっています。 最後の長いあとがき、おそらく同じ様な感覚になる人も多いのでは。 この本と村上春樹さん、吉本ばななさんとの対談集もまた、読み直したいと思いました。
0投稿日: 2012.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子と河合隼雄の対談集。 群馬県の御巣鷹山に墜落した日航機に息子を一人乗せて見送った母親の話があまりに悲しい。 子供のためにとプレゼントした野球観戦がこんな悲劇をもたらすとは、、、
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ臨床心理学者の河合隼雄さんと小説家小川洋子さんの対話。 人は皆、それぞれの物語を綴りながら生きている。 「生きる」ということを、臨床心理学者と小説家が優しく語り合う作品。 長いあとがきの中の一場面が印象的。 科学がいくら発達して、死の原因を論理的に説明できるようになったからと言って、自分の身近な人の死を受け入れる解決策にはならない。なぜ死んだのかと問われ、出血多量と回答したとしても、その死を感情的に受け入れられるかというと別物。受け入れるには、物語が必要。 人間って本当に不思議。
0投稿日: 2011.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きるとは、自分の物語をつくること。 はっとさせられるタイトルに導かれて読んでみた河合隼雄さんと小川洋子さんの対談集。 一人ひとりが自分の物語を紡いでいく。それは小説家が小説を書くことに似ている。 たったひとつの自分の物語。 ころころと上手い方向に転がってハッピーエンドになればいいけれど、そんなわけにはいかないわけで。 どうしても先に進めないことや、まずい展開に陥ることも数知れず。 河合さんは、臨床心理士の仕事はそういう人に、自分なりの物語を作れるように手助けをすることだといい、カウンセリングの秘密を教えてくる。 その道の第一人者の秘伝の技。。。なるほどなあ、すごい、とうならされる。 でも、これはすごい、もっと、もっと、と読み進めていたのだけど、対談は突然に終わってしまった。河合さんの死によって。 もっと、もっと秘密を教えてほしかった。
0投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なぜ死んだか」と問われ、「出血多量です」と答えても無意味なのである。その恐怖や悲しみを受け入れるために、物語が必要になってくる。死に続く生、無の中の有を思い描くこと、つまり物語ことによってようやく、死の存在と折り合いをつけられる。物語を持つことによって初めて人間は、身体と精神、下界と内界、意識と無意識とを結びつけ、自分を一つに統合できる。人間は表層の悩みによって、深層世界に落ち込んでいる悩みを感じないようにして生きている。表面的な部分は理性によって強化できるが、内面の深いところにある混沌は論理的な言葉では表現できない。それを表出させ、表層の意識とつなげて心を一つの全体とし、更に他人ともつながっていく、そのために必要なのが物語である。物語に託せば、言葉にできない混沌を言葉にする、という不条理が可能になる。生きるとは、自分にふさわしい、自分の物語を作り上げていくことに他ならない
0投稿日: 2011.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄臨床心理学者との対談集。数学者だった河合氏が臨床心理学者となりカウンセリングの世界へ。カウンセリングはキャッチボール、自分の物語を作るお手伝い、など興味深い話がありました。小川さんの「博士が愛した数式」への、もと数学者であった河合氏の解釈も面白かったです。
0投稿日: 2011.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ユング心理学の先生でもあり、人格者としても高名な故河合隼雄さんですが、どうも引っかからないのです。箱庭療法の本とか5、6冊は読んでいるのですが、ピンとくるところがなくて…… 今回もチャレンジしたのですが、気持ちが離れてしまいました。 縁がないのかなー。興味を抱いているポイントは先生に近いものがあると思うのだが……
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きることは物語をつくること。 小川さんがなぜ物語を紡ぎ出すか。 人のこころに寄り添うことの難しさと偉大さ。 じぶん自身のの未熟さを、空回りしてしまう焦りを、ぐるりと回って愛おしく感じられるような本でした。
0投稿日: 2011.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ小川洋子・河合隼雄対談集。 言葉の端々から、河合さんの人柄が伝わってきます。 お二人の対談、もっともっと読みたかったです。 「道に物なんか落ちていないと思ってる人は、前ばっかり見て歩いているから、いい物がいっぱい落ちとっても拾えないわけでしょ。ところが、落ちてるかもわからんと思って歩いてる人は、見つけるわけですね」
0投稿日: 2011.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログやわらかくて温かい対談集。のぞみとひかりの小話がすき。お二人とも、本当に魅力的です。生きるためには物語が必要なんだよ。
0投稿日: 2011.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人一人物語がある。作っている。作っていく。 日本、日本の文化、宗教、言語、思考、文化差、歴史、あらゆることを考えさせられる。 おもしろくてうなりっぱなしだった。 「人間は矛盾しているから生きている」 自分が作る物語なんだから、矛盾したっていいし思い切りやればいい。
0投稿日: 2011.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「のぞみがないときはどうするんですか。」 「のぞみがないときはひかりです。」 「あっ。のぞみの次はひかりだ。」 「こだまが帰ってきた。」 深いなぁ。
1投稿日: 2011.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ対談集。読んでいると気持ちがほぐれてきます。左脳傾向な僕のアタマにもすっと入ってくるのは、河合隼雄さんの真剣さ、取り扱った臨床の数がすごく多いこと、言葉の端々にあふれるユーモアのミクスチュアのなせる業なんだなあと。
0投稿日: 2011.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的に小川洋子さんの小説『博士の愛した数式』の内容を取り上げてお話されているので、未読のひとにはわかりづらいかもしれませんが。 臨床心理学者の河合隼雄(かわい はやお)さんが語る、古来から多神教のもとで形成されてきた日本人の柔軟性や、”死”というものを初めて物語として書き表した『源氏物語』の独自性についてのお話などは、目からウロコでした。 タイトルの『生きるとは、自分の物語をつくること』についての核心は、巻末の”少し長すぎるあとがき”の中で小川さんが語っています。 2007年に亡くなられた河合さんのお人柄が偲ばれる対談集です。
0投稿日: 2011.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ河合隼雄先生を舐めてましたすみません。 何このお方、素晴らしすぎる。 なんでもっと早くに読まなかったんだろう。
0投稿日: 2011.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「物語に託せば、言葉にできない混沌を言葉にする、という不条理が可能になる。生きるとは、自分にふさわしい、自分の物語を作りあげてゆくことに他ならない。」 物凄く良かったなぁ。 前、よしもとさんと河合さんの対談は、ダメだったのだけれど、 今回のこの対談は非常に有意義のものに感じた。 人生とは、物語であるという考え方は、 私も持っていたのもので、その点でもとても共感させられたし、 どうしてそう思うのか、という点についてまでは、 私自身まだ考えていた部分もあったからとても有益だった。 そして、もう河合先生がこの世界にいないというのも、 とても残念な気にさせてくれる内容だった。 小川さんの河合先生に対する文章が、とても良かった。 どうしても、対談では、話がそれて行ってしまうものの、 最後の、小川さんのパートは物凄く読み応えがあり、 小川さんの重いがダイレクトに伝わってきて胸がいっぱいになったのだった。 いい本でした。 【4/5読了・初読・私の本】
0投稿日: 2011.04.17
