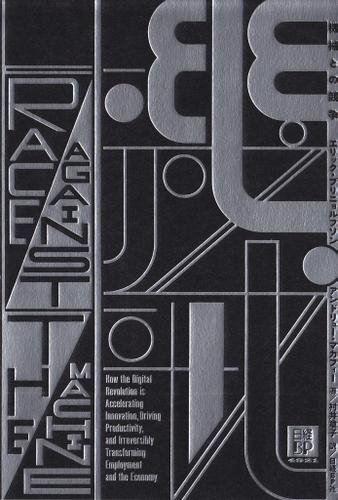
総合評価
(127件)| 14 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 8 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年の出版なので少し古く、かつそこからの未来想定を含む内容なので、「答え合わせ」ができるのだが、何よりAIに関する考察がやや物足りない。面白かったのは、下記のような発想。 ー 産業革命の初期までは、立派に雇用されていた職が、20世紀の初めにほぼ消滅すると言う事態が起きた。役馬だ。325万頭が労役に使われていたが、鉄道に変わられたり、蒸気機関にとって変わられた。馬に賃金が支払われていた。 馬が大量鶴首された。馬は、労働者ではなく、よりアナログな機械として考えるべきでは無いのか。失業者の損失は、生活保護コストや消費の減少にあるが、馬にはそれらが無い。冷酷な言い方をするなら、過剰な馬は美味しい馬肉として、飼育コストを換金する事さえできる。 CEOの報酬と平均的社員の報酬を比べると、1990年には70倍だったが、2005年には300倍だという。このデータはやはり古いが、しかし、ここで考えるべきは、将来、CEOだけが人間でロボットやAIがワーカーになる場合、この差は極限まで広がり、CEOは残りの失業者への生活保護を支払いながら、しかし、他のCEOが提供する商品を、失業者以上に獲得するモチベーションを制度設計として保たねばならない事だ。 ー 今まで誰も思いつかないことを想像することはコンピューターにはできない。創造的なビジネスのアイディアを出す経営者や、感動的な歌を作る作曲家は、コンピューターには置き換えることができない。肉体労働も置き変わらない。 今や、居酒屋でロボットが客の注文に答えて料理を運んでいる。歌やイラストもAIが作る。本著の見立ては既に古い。本源的な人間の価値について、問い直すべきだが、答えが出ない。人間が作ったという「情報」があれば、錯視だとしても成立してしまう気がするからだ。
30投稿日: 2024.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ約10年前に書かれた本ということを前提に。 発展による未来予想系の本だが、予想と現実が違うことがよくわかる。 正確な未来は予想できないが、近い形では実現していく。 その中で自分はどうするか。 そんなことを考えた。
0投稿日: 2022.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械との競争によって失業者が世に溢れるディストピアを描く…訳ではなく、意外にも筆者はデジタル社会の将来に楽観的。ただし、的確な政策が講じられれば…と説く。 トランプ政権の4年間でこの理想とは反対に進んでしまったように思える。
0投稿日: 2021.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ装丁が面白い。色あせたように見える黄色い紙を使用。紙が厚くページ数が少ない。内容は見た目ほどのインパクトはなかった。
0投稿日: 2019.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「イノベーションのジレンマ」の言葉を借りると、 人間自体が「持続的技術」で、機械が「破壊的技術」と言えるかもしれません。 テクノロジーの急速な進歩によって、雇用が減り、クリエーターと肉体労働者に二極化するという話です。 1.この本をひと言でまとめると 「機械との競争」に人は負けている。機械を味方につけよ。 2.お気に入りコンテンツとその理由を3から5個程度 ・eディスカバリーが弁護士の仕事を肩代わりしたように、高度なスキルもコンピュータに浸食される恐れなしとしない。(p101) →ちょうど昨日、「弁護士収入:2割が年収100万円以下」というニュースを見た。ネットで調べれは大抵のことはわかるからかも。 ・ソフトなスキルの中でも、リーダーシップ、チーム作り、創造性などの重要性は高まる一方である。これらは機械による自動化が最もむずかしく、しかも起業家精神にあふれたダイナミックな経済では最も需要が高いスキルだ。大学を出たら毎日上司にやることを指示されるような従来型の仕事に就こうなどと考えていると、いつの間にか機械との競争に巻き込まれていることに気付くだろう。(p.127) →働き方について従来の考え方を見直さないといけない。 ・著者からの提言(p131) →基本的には「小さな政府」のような考え方で、納得できる。 3.突っ込みどころ ・「解説」で指摘していたが、著者が具体的な対応策として述べていることが「アメリカでは十分やっているではないか」という指摘はその通りだと思う。 ・5章の「人類も世界もデジタルフロンティアでゆたかになると私たちは確信している」はあまりにも楽観すぎないか。楽観の根拠も抽象的。 ・看護師を肉体労働者と分類するのはちょっとちがうのでは? ・技術の進化が指数関数的としているが、そこまで急激といえる根拠がわからなかった。 4.自分語り ・本が硬くて読みにくかった。 ・極論を言えば、人間にしか出来ない仕事(肉体労働)をするか、新しい仕事を創出するしかない
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ景気が良くなっても雇用環境が良くならないのは、テクノロジーの進歩による「雇用の喪失」だと。 産業革命を牽引したのは「蒸気機関」、次が「電気」、そして現在進行中のコンピュータとネットワーク。 「文明がこれまで成し遂げた最も偉大な功績は、機械を人間の主人ではなく奴隷にしたことである」 しかし、人間側のスキルや組織制度が技術の早い変化に追いついていない。 それには「組織改新の強化」と「人的資本への投資」だと。 教育には改善の余地が極めて大きいと。 「教育のデジタル化」 アメリカの状況がこうである。 日本は?
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログたとえばチェスは人間と機械の連合軍が最も強いなんてのは今となっては古い情報だし、だから彼らの予測もどこまで信じられるのかなあとちょっと疑問を持ちながら読み進める。 まあ、うまく機械と人間が融合できる世の中であってほしいなあと今の僕は祈るのみである。
0投稿日: 2018.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーの進歩は人から雇用を奪っているだろうかという問いに、YESと答えた上で、この後の展望や提案などがなされている。面白い記述は、この書の段階ではチェス最強が、コンピューターでもなく、人間でもなく、コンピューターを効率良く使う人間であるというくだり。はやすぎる技術革新に社会の体制がついていってないという指摘。イヤな展望を払拭するほどではないが、明るい展望も書かれている。
0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーは雇用を破壊する。 コンピューターは雇用に影響を与えず、近年低迷しているのではないか、と言われていたが、むしろ逆だ。発展が早すぎて人類が進化に追いつけていない。 コンピューターの発展は雇用体系を大きく変え、失業を起こしている。 労働力を節約する手段が、その労働力の新たな活用先を見つけるペースを上回ることで、失業率が高くなっている。 技術の発展の恩恵は存在がするが、誰もが技術の恩恵にあずかれるという保証はどこにもない。むしろ大半の人が恩恵を得られるかどうかという法則すら存在しない。 現にアメリカの平均賃金に変化はなくとも、中央値は下がっている。テクノロジーの発展により格差が広がり、富めるものは富み、貧しきものはより貧しくなる。 富めるものと貧しきものの差は何かが言及されている。 ・スキルの高い労働者 ↔︎ スキルの低い労働者 これからの時代を生きぬくにはSTEAM ( Science , Technology , Engineering, Art , Mathematics )らしい。 仕事を奪われると嘆く人は、コンピューターにもできる仕事しかしていない。 ・スーパースター ↔︎ 一般人 コンピューターの発展により誰でも世界に発信できることや、様々なもののコピー可能なことが大きな影響を与えている。 現在 ( 2007) の アメリカの0.01%の人間が、アメリカの6%の資産を持っている。 ・投資家 ↔︎ 労働者 労働者は機械に変わるが、投資家は変わらない。投資家は労働者の賃金ではなく機械に投資するようになる。 これから我々はどうするべきか、筆者は提案している ・教育 1.とりあえず先生の報酬を増やし、よりよい人材にとって訴求力の高いものとす2.る。 2.教師の終身在職権を剥奪し、裁量制とする。 3.学生の指導と、試験・資格認定を切り離す。学校は学生の募集や評判や社会的地位向上を考えるのでなく、教育を重視するべき。 4.義務教育の時間を増やす。(そして経営学やプログラミングなどを学ぶ) 5.スキルを持つ移民の積極的な受け入れ行う。 ・企業家精神 6.全ての高等機関で企業と経営の基礎を教え、起業家層を育成する 7.起業家ビザを作り、企業家精神の発展に努める 8.起業の手間を簡略化。意見交換の場も揃える。 投資 9.通信、輸送インフラの強化に投資する(アメリカはインフラが弱いらしい) 10.基礎研究や、政府の重要な研究機関への予算を増やし、無形資産や組織改革を新たな研究対象に設置する。 法規制 11.労働市場の流動性を保つ。解雇が処罰されるとなれば、企業にとっては雇うことがリスクになる。 12.技術の導入より人間の雇用の方が相対的な魅力になるような状況を作り出す(これは雇用の観点なので、僕としては懐疑的である) 13.福利厚生と企業を切り離し、市場の流動性を高める。医療保険やその他の福利厚生が雇用に義務付けられていると、転職や起業がしづらくなる。企業を考えていても、医療保険がなくなるかと思うと踏み切れないように。 14.新しいネットワークの規制はゆっくり行う。実験段階の、とりわけ新しいプラットフォーム作りに関しては、最大限試行錯誤や実験ができるようにするべき。 16.金融サービスに対して供給されている補助金を削減する。「金融機関が大きすぎて潰せない」と政府に存続を保障されることで、金融サービスに多くの優秀な人材とテクノロジーが吸われてしまう。 17.特許制度を改革し、審査官を増やす。 18.著作権の保護期間は伸ばすべきではない。新しいアイディアは既存のアイディアの掛け合わせで生まれるから。 日本はアメリカを目指してすらいないが 日本より教育が進んでるとされているアメリカでも、教育に関して問われているのだ。今こそ改革の時、ということなのだろう。
1投稿日: 2017.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械が人間の労働に置き換わるかという議論は産業革命の頃から尽きない議論である。 機械、コンピュータの普及により人間がやるべき仕事の領域が大きく狭まり、人間が本来すべき仕事にリソースが集中することになるだろう。
0投稿日: 2016.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「アメリカの景気はなぜ回復しないのか。GDPは増大するが失業率は改善されないのはなぜなのか。指数関数的に進歩したコンピュータがこれまで一般労働者が行っていた労働を侵食しているからだ」という内容です。 1時間以内に読み終えることができるうえ、非常に平易な文章で書かれて(訳されて)いるので、ぜひ読んでみてください。 ところで、この本は単純な労働者の仕事を機械が代替することを中心に書いてありますが、今やコンピュータはもっと創造的なこともできてしまいます。『アルゴリズムが世界を支配する (角川EPUB選書)』と併せて読むことをお勧めします。
0投稿日: 2015.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ『とくに注目すべきは、従来人間にしかできないとされてきた知的な仕事をデジタル技術がこなし始めたことである。 汎用コンピューターは、労働人口のうち情報処理的な仕事に携わる60%に直接的影響をおよぼすだけでなく、残りの40%も次第に侵食しつつある。 チェス盤の残り半分を進むにつれて、テクノロジーのパワーは倍々ゲームで強化され、その用途は飛躍的に拡大し、職業や雇用に影響を与えずにはおかない。 したがって、スキルの面でも、社会制度や産業の面でも、遅れを取り戻すべく努力しなければならない。さもないと、この先もっと多くの労働者がテクノロジー失業に直面することになるだろう。』 簡潔で分かりやすい問題提起的な作品。 我々としては、機械で出来ることは最大限機械で行って、機械では出来ない部分をいかに強みとして人間に働いてもらうのかを真剣に考えることが大事なんだろうなぁ〜。 』
0投稿日: 2015.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく面白い内容で、出典など調べながら読むのが楽しかった。出典がほぼネット上の論文やYouTubeなので、まさにテクノロジーが大活躍。 うちの従業員たちにシェアした部分もありました。 ただ、なんでこういう装丁なんだろう・・読みにくいったらありません。
0投稿日: 2015.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカで失業率が改善しない理由(仮説)。p12 ①景気循環。つまり、景気回復が不十分で、新規雇用に至らない。 ②停滞。経済を進歩させるような新しい強力な発想の生まれるペースが鈍化した。また、中国やインドなどが成長し、相対的に、進歩が遅くなっている。 ③停滞の逆。つまり、技術の進歩が早すぎる。 ※本書では、③の考えを支持している。 労働者が陳腐化するのではなく、人間のある種のスキルはこれまで以上に、価値が高まる。ただし、それ以外のスキルは価値がなくなる。p21 世界最強のチェスプレーヤーは、コンピューターではなく、コンピューターを使った人間。p110 つまり、コンピューターを使いこなすことが、重要。 テクノロジーは、特にスーパースターを(スーパースターだけでなく、普通の人も)より自由にする。p86 歌手は、劇場でしか、歌声を届けられなかったが、レコードやCDによって、低コストで、消費者の好きなタイミングで届けられるようになった。
0投稿日: 2015.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログMIT教授らによる、IT革命がもたらした"影"の部分、すなわち雇用喪失や格差拡大といった、社会に対する「負の影響」のマクロ経済的な分析と、それらの課題に対する提言をまとめた一冊。 過去の産業革命では、蒸気機関等の革命的技術が衰退産業を上回る規模の雇用を創出したため、失業が社会問題化することはなかったが、「ムーアの法則」に象徴される今日の技術革新スピードは速すぎて人や組織が着いていけず、「雇用喪失>雇用創出」の状態に陥っており、格差を助長する要因にもなっているという。 この状況を打開するには「技術を味方につける」ための組織革新や人的投資が不可欠であるとして、「新たな組み合わせによるイノベーション」を、足し算ではなく"かけ算"で行うことができる組織・人材開発の必要性を主張する後半は「フリー」以降の文脈にも通じており、「ITによって仕事が奪われる」という危機感を逆に原動力にして、前向きに未来を切り開こうという"楽観論"は納得感が高い。
0投稿日: 2015.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ雇用の減少を引き起こしている要因はAIだとする説を提唱した本。具体的にAIがどのようにして雇用を奪っていくかと現在急速に起こりつつある変化を説明し、今後の問題と対応策を述べている。AI問題を取り上げている本の中ではかなり有名かつわかりやすいものであるが、本書内に記されている解決策が有用だとは思えなかった。大前提としてアメリカで実行可能な解決策だというのもあるし例えそれを考慮したとしてもこれらの案にあまり期待はできないと感じる。 だが問題提起と現状分析は詳細で優れている。AIにまつわる諸問題を知り心構えをする上では必読ではないだろうか。
0投稿日: 2015.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆3.5 失業はしたくないぞ。でも、産業大改革進行中の変化が激しい面白い時代にちょうど良く生きていることを、とても嬉しく思う。AIには苦手で私に得意な部分の力をつけられるように仕事をしていこうと思ったよ。 関連書籍を読むための取りかかりの本として、主張が明確なよい本だよ。
0投稿日: 2015.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「テクノロジー失業」 テクノロジーの進化の早さは指数関数的に伸びており、人間が調整可能な範囲を超えているため、人間の雇用を奪っていく。 自動運転、翻訳。 複雑なパターン認識での進化のスピードも加速している。 人間が機械と共存するには、 組織革新と人的資源への投資。 組み合わせによる新規市場・ビジネスモデルの創出、人的資源を育てる教育の革新が求められる。 " 分散するのは時間や場所など特定の状況に関する知識である。十分に活用されていない機械を見つけて利用すること、もっとうまく活用できる人材やスキルを発掘して生かすこと、供給が途絶えたときに使える余剰在庫の存在を知っておくことなどは、優れた新技術に関する知識と同じくらい、社会にとって役立つものである。 「組み合わせ爆発」は指数関数的な上回る数少ない数学関数の一つである。このことから、組み合わせによるイノベーションは、創意工夫によって人間が競争にとどまる最高の方法だと言えよう。 生産性の向上に教育は飛び抜けて重要な貢献を果たすにもかかわらず、教育そのものの生産性を計測する系統的な試みはほとんど行われていない。 "
0投稿日: 2015.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログMITスローン・スクール教授による、短いが衝撃的な本。 ITの加速度的な進歩により従来人間だけができた仕事が侵食されつつあり、機械に人間の雇用が奪われてゆく。 この変化を理解するうえで提示される二つの法則が分かりやすい。一つは半導体の集積度が18ヶ月毎に2倍となるムーアの法則。もう一つは米粒が倍々に増える「チェス盤の法則」。指数関数的な変化は気づいた時には想像を絶する大きさになり、まさにITのインパクトはこれに当てはまると著者は主張する。 「ワーク・シフト」と並び、未来の社会と働き方を考える上で面白い。
0投稿日: 2015.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログリーマンショック後のアメリカで設備投資が回復しているにも関わらず雇用が回復していない状況から、テクノロジーが人間の雇用機会を奪っていることを指摘している本。 「ホンシェルジュ」に記事を寄稿しました。 http://honcierge.jp/users/646/shelf_stories/25
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械というかテクノロジーの進歩により雇用が減ってこの先大変よ、でも多分大丈夫ってな話でした。 大多数の人々は大丈夫だと思えないけれど… とりあえずぼーっとしてたらダメだってこたぁわかりましたよ(ってかわかってましたよ) しかし読みづらい本でした。なんでこんな硬い紙使うのかなぁ。未だに電子書籍より紙の本がいいと思ってるけどこの本に関しては内容含め電子書籍のがいいかもね。
0投稿日: 2015.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ米国商務省経済分析局が設備投資の対象に「情報技術」を加えたのが1958年。この年をIT元年だと考え、ムーアの法則により、集積密度の倍増ペースが18ヶ月毎だと仮定すると、32回倍増したのは2006年。すなわち、つまりその年にチェス盤の32マス目に到達している。2015年は38マス目。指数関数的な進化が我々を驚愕させるのはまさにこれから。 未来のコンピューターは、パターン認識能力、問題解決能力から人類の脳そのものの感情や、知性までカバーするようになる。 統計は平均値ではなく、中央値で見ること。 1983年から2009年にアメリカで創造された富の100%”以上”が世帯の上位20%で生じており、残り80%の世帯では富が”減って”いる。それも、富の正味増加分の80%以上が上位5%の世帯に、40%以上が上位1%に集中している。つまり、「GDPが増えても国民の大部分は貧しくなっている。」 2000年以降、雇用が激減しているが、それは解雇の増加ではなく、雇用の喪失。欠員1件あたりの募集頻度がこの10年で激減した。つまり、雇用主は労働者を必要としていない。 オークンの法則が通用しなくなっている。デジタル技術の高性能化と普及に伴い、GDPが回復しても雇用が回復しなくなった。テクノロジーが雇用に与えるインパクトはとても大きい。 オークンの法則: 雇用されて生産活動に貢献する労働者が増えれば実質GDPが高まり、逆に失業率が高まり生産活動に従事しない労働者が増えると実質GDPは低下するので、両者の間に負の相関関係が生じる 産業革命の”初期"までは立派に雇用されていた者の数が、20世紀初めにはほぼ消滅した。それは「馬」である。役馬の数がイングランドでピークに達したのは産業革命からしばらく経った1901年で、325万頭が使われていた。 2002年以降の経済成長の65%を世帯の上位1%が手にしている。 GDPに占める企業収益の比率は過去50年で最高水準に達した一方、労働者に対する報酬は賃金と福利厚生を足した総額で見ても過去50年で最低の水準となっている。パイの取り分は資本家が大きく、労働者が小さくなっている。 モラベックのパラドックス 35年に及ぶAI研究で判明したのは、難しい問題が容易で容易な問題が難しいということである。我々が当然なものとみなしている4歳児の心的能力、すなわち顔を識別したり、鉛筆を持ち上げたり、部屋を歩き回ったり、質問に答えたりといったこと(をAIで実現すること)は、かつてないほど難しい工学上の問題を解決することになる。…新世代の知的機械が登場したとき、職を失う危険があるのは証券アナリストや石油化学技師や仮釈放決定委員会のメンバーなどになるだろう。庭師や受付係や料理人といった職業は当分の間安泰である。最も解明が難しい人間のスキルは「無意識」。 現時点で世界最強のチェスプレーヤーは、人間でもマシーンでもなく、「マシーンを使った人間」。そして、「弱い人間+マシーン+よりよいプロセス」の方が「強い人間+マシーン+お粗末なプロセス」よりも強い。 十分に活用されていない機械を見つけて活用すること、もっと上手く活用出来る人材やスキルを発掘して活かすこと、供給が途絶えた時に使える余剰在庫の存在を知っておくことなどは、優れた新技術に関する知識と同じくらい社会にとって役立つ。 イノベーション力を高めるには、これからは「STEM(科学、技術、工学、数学)」ではなく、「STEAM(+アート)」である。 1992年、クリントン大統領が全米から最高の頭脳を集めて将来の経済について議論させた時、インターネットに言及する者は誰一人いなかった。 貧困国における携帯電話の普及は、産業を様変わりさせるだけではなく、世界を変える。 雇用の二極分化が進む。どうしてもコンピューターに置き換えるのが難しい雇用は2タイプ。 1. 創造的な仕事。今まで誰も考えつかなかった事を想像する事。 2. 肉体労働。 21世紀に成功するのは、組織革新とスキル開発を最適な形で実現できる経済。 組織革新を推進し、人的資本の形成を促進する事。
0投稿日: 2015.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械に雇用を奪われているという産業革命後のような状況が 近年のアメリカ経済の停滞から推測出来ると筆者は主張する。 こうしたテクノロジーの発展により雇用を奪われるのは ブルーカラーではなく、ホワイトカラーの可能性が高いと警鐘を鳴らす。 ロボットの運動能力は未だきわめて原始的で、2足歩行ロボットも階段の登り降りにも一苦労している段階だ。 ウェイターや看護士、配管工などの仕事は高度な問題解決能力を必要とし、機械はこの作業を苦手とする。 IT技術は指数関数的に発達する(ムーアの法則)ので、油断ならない。 IT技術が駆逐する領域を見極めることが大切。
0投稿日: 2015.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械に仕事を奪われる。昔からよく言われることだが、これまでは機械化による産業全体の効率化のおかげもあって、新規事業が生まれ、そこが雇用を吸収するという流れがあった。しかし現在のテクノロジーの発展はあまりに速いため、全体最適化の前に雇用が失われる事象が発生する。 本書の指摘はそれほど新しいものではないが、具体的に機械に祖語とを奪われない職種が、実は肉体労働だというのは面白かった。
0投稿日: 2014.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ産業革命以降、人間にしかできなかった仕事の多くが機械に取って代わられ、その結果として多くの人間が失業した。 経済は発展して、世の中は便利になっているのに雇用は増えない。増えた富の大部分はごく一部の人に集中しており、多数派は貧しくなっている…… 内容はそこそこ。ただ装丁が良くない。読みにくい。 -- memo: 49 コンピュータは、パターン認識や複雑なコミュニケーションなど、これまで人間が独占してきた領域を侵食しつつある。 54 (NASAの報告書より)「人間は非線形処理のできる最も安価な汎用コンピュータ・システムである。しかも重量な70キロ程度しかなく、未熟練の状態から量産することができる」 99 スキルと賃金の関係が、最近になってU字曲線を描き始めたという。つまりここ10年間、需要が最も落ち込んでいるのは、スキル分布の中間層なのである。 111 幸いなことに、人間はまさにコンピュータが弱いところに強い。 147 情報は、消費されてもすり減ることはない。(中略)エリックは、読み終わった本をアンディに貸してあげることができる。この時、本の中身は少しも減っていない。いやそれどころか、エリックが読み終わった本はアンディにとってもっと貴重だと考えられる。なぜなら2人はその本に書かれていることを共有し、それをもとにして新しいアイデアを共同で生み出せるかもしれないからだ。 171 著者によれば、どうしてもコンピュータに置き換えることが難しい雇用には2つのタイプがあると言う。1つは、創造的な仕事で、(中略)もう一つは肉体労働なのだと言う。 高所得を得られる創造的な職場と、低賃金の肉体労働に二極化するということだ。
0投稿日: 2014.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ[並走から、追い抜きへ]企業が莫大な利益を得る中で、雇用者数の改善が一向に見られない状況に目をつけた著者は、経済と技術の相関に目をつける。そして、雇用者数の改善が見られない理由を、技術のあまりにも急速すぎる発展にあるとし、多くの労働が機械にとって代えられるという事態が既に起こりつつあることに気づく......。ディストピアのような話が現実に生じていることを鋭く指摘した警句の書です。著者は、米国のマサチューセッツ工科大学に務めるエリック・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィー。訳者は、経済関係の著書の翻訳に定評のある村井章子。原題は、「Race against the Machine」。 機械が人間の労働にとって代わる事態が起きているという指摘に、「ホントかよ?」と疑問符つきで読み始めたのですが、読み進めていくうちに「ホントかよ!」と驚かされずにはいられませんでした。実証的なデータを示していますので、極端ながらも説得力のある帰結に読者は真剣にならざるを得なくなるはず。大著ではありませんが、その分研ぎすまされているようで、惹き付けられるものがありました。 その一方で、著者の二人があくまでテクノロジーは良いものであるという立場を崩していない点が印象的。大胆に途方もない現実を突きつけておきながら、その現実を凛々しく越えていこうとする研究者の態度に、知的な強さを感じることもできた作品でした。 〜言い換えれば、多くの労働者がテクノロジーとの競争に負けているのである。〜 将来のことはよくわかりませんが☆5つ
0投稿日: 2014.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ早過ぎるテクノロジーの進歩によって、労働力の削減が新たな雇用創出を上回るペースで進むことで生じる失業をケインズは「テクノロジー失業」と呼んだそうな。今、アメリカで起きている雇用なき景気回復はその現れ。所得の二極化は総需要の減少をもたらす。著者はテクノロジー失業の処方箋として、組織革新と教育を挙げている。
0投稿日: 2014.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ざっくり言うと、機械はものすごいスピードで進化しているので、機械と人間が競争するのはよして、機械を上手に活用していきましょうという内容でした。
0投稿日: 2014.07.31この競争はお釈迦様の手のひらを飛び回る孫悟空の運命に似ている
現代版ラッダイト運動の思想的根拠を示す本かと思っていたので、いまから予測不能なほど指数関数的に進むテクノロジーの進歩に対し、片方では憂慮を表明しながらも、そのデジタルフロンティアが約束する未来に希望を寄せるという著者の矛盾する立場に少しガッカリさせられた。 デジタル技術の進展が「驚天動地の結果をもたらす」ほど甚大かつハイペースなものであるなら、著者が提言する教育や法規制の改革などやる前から手遅れで実効性がどこまであるのか疑問だろう。 それでもテクノロジーが雇用に与えるインパクトの大きさは再認識できたので読んで良かった。
0投稿日: 2014.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ機会が人の仕事を奪っていくので、人はより付加価値をつけていかないといけないということ 技術的特異点ですね
0投稿日: 2014.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報通信技術の指数関数的な発展に人々がついていけす、経済的な利益が生まれても雇用の喪失が生じるという話です。コンピューターが代わりにやってくれるような仕事の多く失われていき、企業経営の意思決定あるいは人にしかできないような肉体労働だけが残り、経済的な格差も大きくなっていくといいます。 いまは有効でお金を生む技量を持っていたとしてもわずか数年で全くお払い箱になってしまうかもしれないという現実は怖いです。 著者はいたって楽観的であるが、やはり教育が重要であると説きます。情報通信技術との競争ではなく共闘するのが良いということですね。 装丁が無駄にオシャレです。
0投稿日: 2014.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
不景気から回復しても、以前のように就業率は上がらない。それは、人間の仕事を機械が代わりに行うようになったから、というお話。 将来、人間の仕事は二極化していく。一つは、何かを創造する仕事。もう一つは、肉体労働を伴う仕事。 自分の将来の仕事は大丈夫だろうか、と心配する前に、自分の価値を高めていく方法を考えていこう。
0投稿日: 2014.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1次産業革命や第2次産業革命と同様に、現在のコンピュータの発展によってコンピュータが人の仕事を盗むかというとその通りで、とは言ってもその代わりコンピュータにはできない複雑な仕事は増えるので問題はない。なのだけど、情報技術に対して順応するのが遅くまだまだ仕事が整っていないというのが現状の問題のよう。 技術者の中で雇用の機会が多いのは低レベル、高レベルの人材で、中レベルの技術者は雇用が減っていくらしいが、何かを生み出すコストは減っていっているのでチャンスはどこにでもあるとも。
0投稿日: 2014.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コンピューターの発展は人間の仕事を奪い、人間の仕事(雇用)を二極化[高所得と低所得]すると、その処方箋として、教育、起業家精神、インフラ投資、法制度などをあげる。 教育への投資とインフラ投資は、そのとおりだと思った(特にアメリカは軍事に金を使うのでインフラ投資の割合は低いと聞く)が、雇用の二極化は避けられないかも知れない、高度成長期のように、所得の中央値をあげる社会情勢・状態が世間的には幸福感を醸し出すと思うのだが、自分の子供達の時代を思うと、そんなハッピーな時代がもう来ないかもしれないと思うと、少し暗くなる。
0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ産業革命期のラッダイト運動が現代でも起こりうるのか。リテラシーの高まった日本ではきっと起こらない。チェス盤の法則から紐解く機械と労働者のこれからについてオススメの一冊。
0投稿日: 2014.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジー失業に関するお話。指数関数的な情報通新技術の進歩に、新たな雇用の創出が追い付いていない現状。人件費削減が進む社会で、創造的職業と肉体的職業以外は早々に駆逐される可能性があるという。最後は楽観論で締め括っているが、勝者総取りの社会を是正するには、新たな雇用をどのように産み出すのか、考えていかなくてはいけないと思う。
0投稿日: 2014.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
機械が発展していっても、人の職はそれに応じて増えていく。機械に代われない仕事もいっぱいある。ちょっと希望が持てた。
0投稿日: 2014.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「チェス盤の法則」によって指数関数的に進む技術革新のスピードから、機械化、自動化が進むと今まで以上に一部の仕事が人からコンピューターへ置き換わるスピードはアメリカで起きている現実よりもっと加速していくのかも知れない。ただ、「弱い人間xマシンxよいプロセス」のほうが、「強い人間xマシンxお粗末なプロセス」より勝っていることも事実。今でさえ生産の現場で人間が高度に自動化された機械やコンピューターを本当に使いこなせているかは疑問だし、移民政策などがなかなか進みづらい、人手不足の日本のような国こそスキルの向上を徹底的に行って、生産性をあげていくしか道はないのでは。 チェス盤の法則は、ローマクラブの「成長の限界」とよく似たメタファー。色んなリスクマネジメントをしていかないと。。
0投稿日: 2014.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械に置き換えられた大量の失業に対処することが今世紀の最も急を要するに社会問題に。機械と共存する社会とビジネスの再構築を。
0投稿日: 2014.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆かなり浅めの読了。 ◆景気が回復しても雇用が回復しないアメリカ社会。その理由は、人間がおこなっていた労働が高度な技術に代替されているからではないか。この本が提起する問題はいたってシンプルで、ラダイド運動が象徴するようにそれまでも語られてきた問題でした。著者によれば、かつては楽観的にみられていたこの説明(雇用喪失説)が、コンピュータとインターネットの時代となったいまになって、にわかに危機的な課題として浮かび上がりつつあるといいます。 * 感想 * ◆問題提起の本と著者が語っているように、雇用喪失の問題と技術発展の問題にどれだけ関係しているのか(解説にあるように、のちにならないと分からない)、そして対策・解決の点ではそれぞれ疑問が残るかもしれません。たとえば、教育をとおした人材育成という解決策が提示されるいっぽうで、いま機械との競争に負けつつある人びと(つまり労働が機械に代替されつつあるか、その可能性が高い人びと)に対してはどのような対策が可能なのでしょうか。 ◆衝撃的な問題提起から、読者がそれぞれの答えを考えながら読んでゆくと面白い本だと思います。
0投稿日: 2014.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログITによる進歩が速いので、新しいことによる雇用の増加が起こる前に、雇用の減少が進んでしまう。 これからは、教育への投資増や、新しいテクノロジ利用への規制をしない、といった考慮が必要に。 原書はアメリカの話だが、それでも日本から見るとアメリカは良くやっているように見える。ということは、日本はさらに数歩遅れているということ。
0投稿日: 2014.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ140322 中央図書館 ICTの進化は、指数関数的である。(チェスの盤面の残り半分に入った・・との比喩) これにより通常の仕事は機械に急速に奪われていくため失業が社会問題となるだろう。そのために教育投資、自由闊達なアイデアを促しイノベーションを励起する政策が必要だ。。というあたりまえの主張。 確かに、機械が仕事をしてくれてしまうことによって、「経済」「社会」がどうなるか、を明確に教えてくれるミクロ経済学者が思い当たらない?
0投稿日: 2014.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ産業革命が進展していた頃、機械に職を奪われるという危機感を頂いた労働者が織物機を破壊した事件(ラッダイト運動)については歴史の授業で習ったが、いまやICTが職を代替する時代になっているということを各種分析を根拠に解説している。「平均的な人間の大多数が従事している仕事については機械がこなせるようになるだろう。そしてその人達は新たな職を見つけることはできまい」「この時代は大不況でも大停滞でもない。大再構築である」 一方、機械ができない仕事は、クリエイティブな仕事とプロフェッショナルな仕事。起業家が作り出す新たな付加価値によって新たな雇用が生まれるということであり、そのための教育や制度作りを一層加速するべきという主張。これが米国の学者の書籍であることに驚く。米国に於けるこういう仕組みは最先端と思っていたがその米国でさえ危機感を頂いている。いわんや日本においておや・・・。
0投稿日: 2014.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログとても短く、深くない。 コンピュータの発達の速度が速いので、雇用調整が取れず、中間層の仕事が奪われてるよ、という本。
0投稿日: 2014.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にちぐはぐな印象を受ける。 機械が雇用を奪うこと、富裕層がますます豊かになることと、著者の提言に関連性を見出せない。 テクノロジーが生活を便利にし、雇用が無くなるのではなく労働から解放される、という視点で、社会・経済システムに斬り込んでいくべきところを、近視眼的な論調で終わった。
0投稿日: 2014.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログパターン認識力の向上 グーグルに自動運転、ワトソン研究所のワトソン ムーアの法則とチェス盤の残り半分 18ヶ月ごとに倍増する。指数関数的に増加する。(倍々ゲーム)。 文書のレビューもコンピュータが行える。 販売職は、14%近い減少(1995年から2002年) 創造性にはまだ能力がない。 テクノロジー失業は、ケインズの時代にもあった。 労働力を活用する新たな道が見つかる前に、節約する手段が見つかっている。 生産性の増加によって価値が増えているのに経済的に困窮する人がいるのはなぜか。技術の進化が加速しているのに、所得が一向に増えないのはなぜか。 人々が一生懸命働くから成長するのではなく、よりスマートに働くから成長する。 生産性の向上とは裏腹に、所得の中央値は下がっている。 以前ほど人出が要らない。 スキルの高い労働者と低い労働者。スーパースターと普通の人。CDなどのテクノロジーによって、スーパースターに集中した。資本家対労働者。 所得の格差は経済全体の規模にも影響する。=所得の限界効用は減少する。機会の平等も奪われる。格差は社会不安を呼ぶ。所得の急激な変化は総需要の落ち込みを招く。 単純労働は需要が減少していない。肉体労働、庭師、見ようし、介護ヘルパーなど。肉体運動は、自動化が難しい。 チェスは今は、よりよいプロセスを持つものが勝つ。テクノロジーを味方につけることが、勝つ方法。 組織改革を推進する。人に投資、スキルを身につける。 テクノロジーによって生み出される製品が、次の製品のネタになる。ネタは枯渇しない。 スーパースターの人数に限界はない。 デジタル教育など。 とはいえ、だれもが起業家になれるわけではない。起業家が多くいても、雇用創出には限界がある。テクノロジーを見方につけても、勝ち組と負け組はいる。経済全体が成長しても、ある職は消えていく運命にある。 福利厚生と雇用を切り離す。雇用の自由化。 デンマーク、オランダの例。 3回の産業革命。蒸気機関。電気。コンピュータとネットワーク。
0投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械が雇用を奪う。コンピュータの発展は、新たな職を生んではいるが、一方、「人間しかできない」という仕事をどんどん狭めつつある。筆者は、この課題を解決するには、雇用の流動性を高めなければととく。 機械と人間が上手に共存出来ればと期待する。
0投稿日: 2014.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと、機械に人間の労働力は取って代わられるのではないか、という危機感は持っていた。それは避けられないことで、いずれ世界はGoogleに支配される(Googleのコンピュータ)と言う人さえいる。 この本でも、アメリカの実情に従って、コンピュータとインターネットの発達はあまり雇用を生み出していないこと、その結果失業率が減らないこと、また貧富の差が大きく広がっていること、中間スキルを持つ労働者の需要が減っていることなどが語られる。 だが最終的に、悲観では終わらない。コンピュータと人間の直感などの組み合わせが最も素晴らしい力を発揮し、これまでの産業革命の歴史から見ても、イノベーションによって新たな市場が出来上がるチャンスだと述べている。 僕は、この本ほど楽観的な態度は取れなかった。だが避けられないことなので、それを見据えて歩むしかない。 薄くて内容は読みやすいが、装丁がどうも読みづらく仕上がっている。
0投稿日: 2014.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械との競争はすでに想像以上の結果となっている。これからはいかに機械と共存し、人としての価値をつけていくかを念頭にスキルアップに励まないといけない。特に直感と創造性を機械は備えておらず、人間の強みを伸ばしていけば、十分共存できる。 著者は組織革新と人的資本の投資を提言しており、今後創造的な仕事を生みだす起業家と労働者に二分されると記している。起業家を産むために教育の重要性を説いているが、やはりスキルアップに励むしかない。これからチェス盤の法則によると、機械は更に進化する。そこに対して悲観せず、人としての価値を作り続けるしかない。
0投稿日: 2014.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーによって雇用が奪われるかがテーマの本です。 数年前に書かれた本なので、期待はそこまでしていなかったのですが非常に面白く読めました。 ただし、紙質がわら半紙みたいでこれで1,680円とるとかヒドいと思い、☆4に抑えさせて頂きました。 結局は雇用や収入について、二極化していくお話だと思います。 (IT分野のスキル教育を受けてるかとか代用の聞かないスキルを持っている点で) そのテクノロジーの進化が早すぎる中で、人間にしかできないソフトスキル面を延ばすことや、コンピュータを奴隷にするスキルが高い人が残って行くのかなと思いました。 (一部テクノロジー関係ない職種もありますが、IT分野に従事する身として)
0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログコンピュータが我々に与える影響と、我々がコンピュータに施す工夫の結果として比較的コンピュータで解きやすいものを中心にヒトの出番が減少するという話だと理解した。 競争なのか、切っても切れない間柄になるということだと、後者なのでタイトルは煽りすぎだと思う。 現在チェスではフリースタイルというルールがあり、ヒトと機械がチームを組めるそうだ。そのルールでの勝者はもはやコンピュータではなく、ヒトとのチームであると言う。 アニメの制作ではコンピュータはもはや不可欠である。作業者はセルや絵の具の代わりにコンピュータを操作する。役割分担が最適化された系が生き残るということだ。 ヒトの仕事が無くなったのではなく、役割が大きく変化しただけである。
0投稿日: 2013.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーの発展はものすごく早く、コンピュータは、人間の領域を侵食し、雇用は減る。しかも、減った雇用は、創造性を求められる高所得の仕事と、肉体労働に二極化されていく。富の分配は、平等には行われない。といった主張。 本の装丁は奇抜で、紙は色付きの厚紙。はっきり言って読みにくかった。
1投稿日: 2013.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人の労働者一人あたりの所得はこの15年で毎年下がり続け、100万円以上も下がっている。 その中で史上最長の好景気の期間が入っていることと矛盾している。 これは物まね工業の限界と少子高齢化による高度成長の行き詰まりという日本独自の事情によるものかと思ったが、どうも米国でも同様らしい。 GDPは増え続けているのに、所得に格差が大きくなって、中央値はむしろ下がっている、という。 本書ではその原因は、IT等による仕事の効率化に人間がついていけなくなっているため、と説く。 2000年までは、機械化がされて、人が余ってくると、その元になった技術で新分野が開拓され、それに余った人が労力として吸収されて、全体の生産(GDP)も増え、個人あたりの生産性も向上して所得も向上する、という循環だった。 それが、今世紀になってから、主にIT技術によって、例えば、一般小売りがAmazon.comに取って代わられる等で、小売業の余剰人員が他の新しい業種へ移行するのが間に合っていない。 僕がうすうすそうではないか、と思っていたことが、本書で裏を取って示された。 本書ではその対策として、やはり新規事業を立ち上げることを優先し、その支援を行政が行うべき、としている。また、スキル開発を進める組織改革と規制緩和が重要と行っている。 でも、僕はほんとうに、そんなことで、対応できるのか疑問を感じる。本書末の法政大学の教授の解説でも同様なことを述べていて、結局、抜本的な対策は不明、という印象を受けた。 数パーセントのほんの一握りの人が所得のほとんどを持って行ってしまうしまう格差社会は今後、世界的な大問題になっていくと思う。
0投稿日: 2013.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ19個の提言とSTEAM(➕アート)の発想は説得力があった。 機会との競争において、あくまでもオプティミスティックな発想が印象的な一方で、むしろ人間側の価値に可及的速やかな転換を求める内容は、自分自身への戒めになった。
0投稿日: 2013.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログコンピュータが人間の領域を浸食する事により、雇用は減り、その減った雇用は、高所得を得られる創造的な職場と、低賃金の肉体労働に二極化する。 これに対して、著者は組織革新を推進し、人的資本の形成を促進すれば良いのだと述べ、さらに、教育、起業家精神、投資などについての十九項目の具体的な提言を行っている。 そして結果的に「人類も世界もデジタル・フロンティアで豊かになる 」と述べている。
0投稿日: 2013.10.26量の割に高いし目新しい部分もない
紙量をわざと増やして(しかも紙の質が悪い)稼ごうという考えが見え見えだった。 まあ電子書籍だからこれはあまり関係ないが、内容的にも特に目新しい部分もなかった。作者はEラーニング神話を信じているようだが、私は逆効果ではないかと考えている。
0投稿日: 2013.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コンピュータが労働力を置き換える不安を考える本。技術の発展する速度が速すぎて、新たに生まれた雇用の数よりもコンピュータが人間の仕事を奪った数の方が大きい。過去の出来事を振り返ると、蒸気機関や電気の普及などの革命的な技術が生み出されたときは、今と同様に労働者達は不安を抱えていた。でも実際には雇用の数は増えたし生活は良くなった。現代のインターネットの普及やコンピュータ技術の革新も、これまでの技術革新と同様に新たな雇用を生み出すのか。また、どういう仕事ならコンピュータに置き換えられないか。どうすれば機械と人間は共存できるのか。こういう議論が興味深く読める。 法政大学の小峰教授が書いた最後の解説が上手くまとまっていてかなり読みやすい。 メモ:労働者が失業の不安から機械を壊したラッダイト運動と同じような運動が今もあってそれはネオ・ラッダイト運動ていうらしい。
0投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ一部で話題の本。途中まで読んでいたのをやっと読了。 著者は昨今失業率が回復しないのは、デジタル技術の進化に人間がついていけなくなった結果、職を失っているからであるというショッキングな仮説をデータとともに突きつける。 指数関数的に進化する技術によって、従来人間しかできないと思っていたことが機械によって可能になってきているので(車の運転や翻訳など)、パターン認識などのコンピュータが得意とする分野では雇用が減っていく。 ただ、人が勝っている、クリエイティブな分野、何かを創ったりすることと、肉体的な労働においては、当分コンピュータが追いつけないので、雇用も残るだろうと。 著者は悲観しているわけではなく、組織革新の推進と人的資本への投資が対応策であると言い、また、これからに向けての教育や投資等19の提言も示している。 結局のところ、技術を使いこなす側になる、すなわち努力や工夫によって自己の成長を促すことを継続しないと、付加価値を高められず、低所得や失業という事態を招くということ。 いつの時代もそうなのだろうけど、指数関数的に技術が進化するということは従来よりも増々スピードがあがり、今後更に早くなるということ。(ムーアの法則が続けば、、、だけどね) アニメ「ウォーリー」に出てくるような未来で人間が楽してる社会は決して訪れなそうだなぁ。。。
0投稿日: 2013.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ割と軽めの本。一日で一気に読めます。主張は割と単純で、これからコンピューターがさらに急速に発達して、人間の仕事を奪う、というものです。確かに、これまでコンピューターがどれだけ発達しても、いわゆる判断を伴う業務は苦手とされていましたが、そのかなりの部分をコンピューターが担うことになるということです。確かに、とにかく目的地に行く、とか必ず一定の結論に帰結するような、トラックの運転手や、弁護士、医師の仕事のかなりの部分がコンピューターが置き換わりそうですね。言わんや薬剤師なんて今でも不要な訳で。これからは、いかにもコンピューターに置き換わりそうな仕事をいかに避けるか、という社会になりそうですね。とにかくマニュアルに沿ってやりなさい、みたいのが一番危ない。いかにコンピューターにできなそうな付加価値というか、柔軟性というか、創造性といったものが求められそうです。
1投稿日: 2013.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フラット化する世界」を読んだ時点で到来が予想できた デジタルによる経済・産業の革命による労働生産性向上が 賃金や雇用に反映されず、資本や技術に重きがおかれることを 書いている。所得再分配機能も機能しないと。 でも前向きに技術を使う人は今後もあかるいと!! チェスにコンピュータに勝てなくてもコンピュータと人間 チームは実際に勝てているようにと。
0投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログRACE AGAINST THE MACHINE・・・ 機械に! そう、コンピュータに! 雇用が!! 奪われる!! という恐怖の本・・・ 2008年に発生した大不況・・・ とは言っても企業は回復した・・・ のに・・・ 雇用が回復しない・・・ 失業率がなかなか下がらない・・・ なぜか? それだけハイパーな落ち込みだったのさ・・・ いや、そうではなくて、イノベーションやら生産性を高める能力、技術の進歩がついに停滞しちゃったのさ・・・ いやいや、そうではなくて、新興国との競争が激しすぎるのさ・・・ いやいやいや、そうではなくて、技術の進歩が速すぎて、人間とコンピュータが置き換わっていくのに、対応しきれてないからさ!!との説を主張するのがこの本・・・ 機械が人間の仕事を奪い去る、職がなくなるという恐怖は実はそんなに新しいものじゃなく・・・ 自動織機を壊しまくったラッダイト運動という、1811年まで遡ることができる・・・ でも、その恐怖は杞憂に終わってきた・・・ もちろん無くなった職もあるけれども、機械化が進み、生産性が上がり、新しい産業が生まれ、逆に新しい職(雇用)が生み出され、経済が拡大し、所得も伸び、多くの人たちがその恩恵を受けてきたのに・・・ 今回は・・・ 今まで人間にしかできないと思われていた多くのことをコンピュータがこなせるようになってきている・・・ そのスピードたるやハンパない・・・ ムーアの法則とチェス盤の法則を考えると末恐ろしい・・・ ドンドン加速していく!! 速すぎて、人間が新しいスキルを身につける前に、コンピュータがドンドン進歩していって追いつけない!! 実際、アメリカは経済成長を着実にしてきたのに、生産性はシッカリ伸びて、なのでGDPはずっと拡大してきているのに・・・ 所得が伸びない!! 世帯所得が伸びない!! 富はものすごく増えた・・・ が、ごく一部の人に集まっている・・・ 中間層の富は減っている!! 中間層の労働者がコンピュータとの競争に負けつつある・・・ スキルの高い労働者は富を増やす・・・ スーパースターは富を増やす・・・ 資本家は富を増やす・・・ 普通の人は職や富を失っていく・・・ こういう図式が出来上がりつつある・・・ 一方で、庭師とか美容師とか、配管工とか看護士とか、ヘルパーだとかレストランのウェイターだとか、肉体労働系は機械になかなか置き換えられないので、労働需要を減らしていない・・・ しかし、いずれにせよ中間層が溶けていく・・・ 途方もなく強力で高度なデジタル技術の時代が到来しても、人間のある種のスキルはこれまで以上に価値が高まるだろう・・・ ただし、それ以外のスキルは価値が無くなるだろう・・・ では、どうしたらイイか? その対応策が書かれているし、著者は意外に楽観的である・・・ けども、対応策読んでみても・・・ 正直・・・ ・・・ さて、人間の未来は・・・? この恐怖の本はオススメ・・・
0投稿日: 2013.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログジャケ買いしたけど、いざ開いてみたら紙質やデザインが凝り過ぎてて読みづらい。。。 中身はアメリカ中心にテクノロジー失業について。
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
技術革新が雇用に与える影響についてまとめられたシンプルな内容。 機械が雇用を奪ってしまうのではないかという憂慮に対し、「新たな雇用機会が生まれるから大丈夫」とする楽観的な考えに待ったをかける。 爆発的な勢いで加速する技術進歩に、雇用創出が追いついていないというのだ。 高度なスキルを持つ者や肉体労働者の仕事は未だ機械に浸食されていないが、賃金中央値の仕事は厳しい状況。 所得格差はある意味自然な流れだったのかもしれない。 ただ、解決策は見えている。 …組織革新とスキル開発だ。 まさに「人間」の底力が問われているというべきか。
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いつ読み終わったんだっけなぁ? 次なるラダイト運動は起こるか?起こしようもないのか?? 機械の登場による産業構造の変化は三次産業へのシフトだった。だから結局、労働集約の場が変わっただけ。 今度の産業の変化は三次産業の労働力も奪うものである。次なる4次産業なんてできるのかな?? と思ったら4次産業・5次産業はあるんだと。 「4次産業…ソフトウエア産業とか、情報通信産業、技術開発など、物質やエネルギーなどの大量消費を伴わない産業。マスコミや芸能界なども含まれる。」 つまり、とりあえずクリエイティヴな仕事ってこと。 「5次産業…第1次から第4次までの産業形態を自由に融合、分化させて、これまでになかった一種の不定形な産業を生み出す産業」 つまり、4次産業で生まれたクリエィティヴな事業を一つの産業にまで格を上げる仕事ってこと??コンサルト的な?? 結局、仕事は人の力を使わないようなっていく。それもものすごい速さで。ということは分かった。 でもさ、そうなると、アナログな技術って価値が下がるようで、価値が高くなると思う。 この時代の流れで、アナログ技術の価値が洗練されて、本当に美しい技術が何かって言うのがわかるようになるんだろうなぁ。 例えば、農業でも、トラクターとかビニールハウスは廃れても、里山と共存していくような農業は意外と伸びるかもね。 だって、そんな非効率的なことはコンピュータにはまだ早いでしょww ただ一つ結論できるのは、人口の減少は必至だな。
0投稿日: 2013.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーが雇用を奪うということを述べた一冊。タイラー・コーエン『大停滞』とセットで読んでイノベーションと失業の関連に興味が持てた。 筆者は現代のテクノロジーの進歩が速すぎて人間が追いつかない状態であるから失業が生まれると主張。そこで鍵となるのが、「ムーアの法則」と「チェス盤の法則」である。特に「チェス盤」の法則が興味深い。イノベーションの進歩は指数関数的に上昇するというもの。最初は緩やかな直線だが、時間が経つにつれて、一気に加速度的に上昇するというものである。現代において、ITがまさにそうである。インターネットが普及し、加速度的にイノベーションが発生し、かつて人の手で行っていたような作業がコンピュータに置き換えられるようになった。さらに、急速なイノベーションにより、かつてコンピュータに置き換えられないと考えられてきた仕事までもコンピュータに置き換えられるようになった。そのため、人間にイノベーションが先行し、どの分野で人間の役割を果たすべきか答えを導く前に雇用がコンピュータに奪われる現象が発生している。それが、不況につながると筆者は主張する。 現代において、人間にしかできない能力を備えることが生き残る手段である。それが発想力などになる。どの分野が人間にしかできないのか、しっかりと考え、機械、コンピュータに負けないようにしなければならない。 イノベーションが速すぎて、失業を生み出す。イノベーションはいいものと考えていた自分にとって、衝撃を感じさせてくれた。同時に、今自分の付加価値を高め、代替手段を置き換えられないような人間にならなければ生き残れない時代であると感じた。イノベーションは人間を豊かにする側面と苦しめる側面両方を持つのだとこの本を読んで感じた。 ここで疑問と感じたこと ・かつてのイノベーションの形態としては、テクノロジーが人間に先行することはなかったのか?例えば、産業革命期、高度経済成長期はどうであったのか? ・もう少し、テクノロジーと失業に関する文献を読みあさろうと思う。
0投稿日: 2013.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学者がついに技術革新による失業率の上昇を認めた!という一点で評価に値する書かと思いきや、実は全くのぬか喜びであった。確かに、IT(あるいはICT)革命の特殊性として、労働市場における需給ギャップの存在すること、技術の発展が早すぎたために、労働力を取り込むための新市場の成長が間に合わなかったことを認めてはいる。しかし、結果としては、それらの問題は時間によって解決され、生産性の向上をもたらすであろうという予測に落ち着き、従来の理論を保持するというなんとも味気ない内容であった。生産性概念について再考することもなく、理論枠組みについても新たな提案は何一つない。先日読んだ広井良典の著書においても、生産性概念の見直しの必要性は説かれていたし、マル経においてはそもそも生産性の向上は、剰余価値の搾取以外の何者でもない。経済状況の根本的変化と認識しながらも、あまりに中身のない議論であった。 そして極めつけは、後半のアメリカ人向けのビジネス書的内容である。曲がりなりにも経済学者が、アメリカ人がいかに儲けるかという内容を著書にしたため、アメリカ人の企業家精神を焚き付けるようなことがあってよいものだろうか。そして、そんなしようもないものを日本語に翻訳して流通させる日本人もどうかしている。
0投稿日: 2013.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「機械が人間の労働を駆逐する。」今、若手の人からすると他人事とは思えないテーマを経済学の事例を用いて述べている。コンピュータでもできる仕事をするか、人ならではの価値を提供するか。今後の働き方を考えさせられる一冊。
0投稿日: 2013.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログいっこうに回復する気配のない景気。その理由をITの技術の進化に人間がついて行けていないことだとする主張を展開している、MITの方が書いた本の日本語訳。 この本のいっていることは、ほぼ正しいと思う。この20年で、人間が手作業でやっていた仕事のかなりの量がコンピュータに取って代わられていることを思うと、確かにコンピュータができることだけをやっていてはいずれ自分の仕事を失いかねない。 ただ、だからといって「コンピュータ導入反対!」などと言っていてはいつまでも生産性は上がらないし、そうなると生存競争に敗れてしまう。コンピュータによる社会の進化は必然のものととらえ、それに人間が適合していく方法を見つける必要があるというのは非常に納得。 過去の産業革命の時とも比較して、今回のパラダイム・シフトだって乗り越えられるはずとする主張は、未来志向で非常に好感が持てた。 まあただ、最後に提言として、いますぐやるべきことの19項目を上げているんだけど、ちょっとありきたりすぎて、本当にこのような大きな変化に適合していくのに最適なのかどうかは疑問。
0投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログITの進歩が早すぎるので、人間の雇用が脅かされている。提起されている課題は今後考えて行くことの種になりそうです。 ただ、メインの対策は結局教育、に落ち着くことに何と無く違和感。どんなことでも、スーパー人間が教育できるようになれば解決できるもの…。どんな人材を育てるべきかのデザインが大きな課題なのでは。進歩が早すぎてどんな世の中になるか分からないのにそんなデザインできるのかな。
1投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的には、現在の失業率の高止まりと技術進歩が与える影響との関係についての考え方だけで一冊の本になっている。 ちょっと期待ハズレであった感は否めない。 実際には、いろいろな論文やウェブサイトで説明されている内容に対しての、Link集のような役割にはなりそう。(と言っても、図書館に返却してしまったけど。) 何度も出てくる、チェス盤の後半に入りつつあるという感覚は参考になったのだが、ちょうど読み始めた、ブライアン・デイビッド・ジョンソンのSF プロトタイピングの本で、今後の技術進歩が与える影響を考えるという方が個人的には興味深いかな。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ分からん。どこにこの本がそんなに売れるだけの要素があったのか、分からん。ちゃんと当時買えばよかったなと少し後悔した。 そのくらい、「まぁそうよね」って感覚くらいしかなかったなぁ。文量が少ないし、主張も視点も特別目新しいわけではない。変わった点といえば、装丁が面白いことくらいなんでなかろうか。
1投稿日: 2013.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログそれなりに説得力があるように思えた。若い人には、これからどのようなスキルが必要なのか考えてもらいたい。
0投稿日: 2013.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ主張は、 「これまでの技術革新では、それによって失われた雇用は、新たに雇用が作られ補われた。しかし、今後は雇用は減り続けるだろう。なぜなら、機械の技術革新の速度が早すぎるからである」 というもの。 その事自体にそれほど新鮮味はない。 どちらかというと、第3章の「勝ち組負け組」の煽りに反応する人が多いのではないか。 1.スキルの高い人と低い人 2.スーパースターと凡人 3.資本家と労働者 が、「技術革新がもたらす三通りの勝ち組と負け組」だそうだ。 しかし、ここに拘泥しても、あまり得るものは無さそうな気がする。 「次にどう行動するのか」がよく見えない本だった。
1投稿日: 2013.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーが雇用と経済に与える影響について論じた一冊。近年のコンピュータを中心とする情報技術の発展は技術の進歩が速すぎた結果、雇用を奪っていること、雇用の二極化が進んでいるとまとめている。以下メモ。(1)雇用の二極化とは、創造的な仕事、創造的なビジネスのアイデアを出す経営者、感動的な歌を唄を創る作曲家、肉体労働は置き換えることは困難であり、中間層の没落という事態に陥っている(2)希少性の経済学から豊かさの経済学に根本が変わっている(3)アイデアを組み合わせる為の組織改革の推進、人的資本の形成が必要。
1投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械が人の雇用を奪って行く。失業率の悪化は不景気ではなく、機械との競争によるもの。 いずれ人間の知能は機械に抜かれる。その時の人間の価値は何か? 仕事はますますオペレーションが機械化されていく。人間はその機械をコントロールできるように成長する必要があり、それができない人は生き残っていけない。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械に仕事を奪われるこの本をみて怖くなった。 まだ自分は機会に使われている立場なのかもしれない。 奴隷として扱うといいうのは言い過ぎとして、パートナーとして生きていくことが今後は必須になる。パートナーとして生きるには、相手のことを知らなくては、、、
0投稿日: 2013.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでの経済理論では古い産業が新しい産業に駆逐されると古い産業に従事していた人は新しい産業に吸収されるので、最終的には失業者は増えないことになっていたが、現在のIT革命では新しい産業の変化のスピードが早すぎて、新しい産業に吸収されず、失業者が増えているという。 その対策として著者が提言している内容は、それほど目新しいものではないが、日本には足りない部分だ。
0投稿日: 2013.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ不況や労働市場を新たな視点でみることができるようになる良書であると感じた。 人間の雇用をテクノロジーの過剰で調整のとれていない発達によって奪われるという内容であるが、本書の帯に書かれているほど衝撃的ではない。SF世界にある機械との戦争も起こりえない。 体感的に欧米の研究者が書いた書籍には読者をわくわくされる要素が詰まっていると常々思う。それが、絵に書いた餅なのか、良質な未来予測なのか両方の視点を心に留めて健全な批判的精神を以て読むことをおすすめする。
0投稿日: 2013.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーが雇用を奪う。 身近でも機械化によるコスト低減の話はよくあり、 そういったことにあまり違和感は感じなかったが、 経済全体に及ぼしている影響を知り驚いた。 また、テクノロジーの急速な発展を改めて考えると、 その伸びを脅威に感じる。 5年後、10年後、今やっている仕事の何割かは、 機械に任せているのだろう。 機械が得意なこと、人が得意なこと、その違いをよく理解し、 上手にパートナーとして付き合っていかなければならない。 自分も機械に取って代わられ無いよう、 人が得意とする分野を、もっと磨かねば!
2投稿日: 2013.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械との競争は、テクノロジーの進歩が雇用を狭める、駆逐する、という内容で、過去、実地に体験してきただけに、何を今更感も、多少ありました。。 インターネット接続が、33.6kbpsや56kbpsの音声モデムから、ISDNになり、ADSLになって光になり、テクニカルコールの内容が接続不具合トラブルシュートから、アプリケーションの設定や使い方程度になったり、とか。 ブログツールの登場で、ホームページ制作会社の淘汰が進んだとか。 ガラケーがなくなってスマホばかりになって、ガラケーテストチームは不要になったとか。 あ、切なくなってきた(笑) 知的にみえたとしても、範囲限定の繰り返しは早めに卒業すべし、ということなんでしょうね。わかってても抜け出せない負のスパイラルが、非正規雇用にはあるのです。難しい。
0投稿日: 2013.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ技術の進歩が必ずしも雇用を増やすわけではない。いまはITの進歩に社会が適応しきれてない。という本だけど、本当にそのうち適応できるのか疑問。ITができない仕事をできない人はずっと一定の割合でいるんじゃないか。って思った
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
工業・IT・金融等々全ての業界においてテクノロジーが進歩してきたことで、今まで人にしかできないことを機械がより効率的にできるようになったが、それは果たして雇用や景気や人の暮らしにどのような影響を与えるのか、という内容。 なんとなく読む前に想像した主旨としては、「単純作業は機械に取って代わられるが, 創造性やコミュニケーション能力や直感を含む作業は人しかできないものであり、代わられることはないから大丈夫!」くらいの内容かな、と思った。まぁ当たらずとも遠からず。 本書は、機械の影響を受けて勝ち・負け組になった人たちをそれぞれ スキルの高い/低い労働者 才能のあるスター/普通の人 資本家・起業家/労働者 の3通りに分けている。全てに共通する勝ち組の特徴は、「機械に取って代わられるのではなく使いこなして豊かになる立場である」ということ。実際、チェスの現世界チャンピオンはスパコンではなく「アマチュア+機械+優秀なチェスソフト」の組み合わせで、これは「プロ+機械+まあまあのソフト」よりも優れている、と。そういった使いこなし、機械を良き隣人として共に発展していくのがベストな方法だというのが著者の楽観的主張だと思う。 機械はブルーカラーとホワイトカラーの中間にあって、高度にプログラムされた単純作業を大量に速くこなして生産効率を上げるが、それは上流の人間にしかできない創造性ある仕事と、下流の人間にしかできない複雑な肉体労働を繋ぐサポートする為のものであり、最終的に豊かさをもたらす…らしい。 この主張を僕含めて大半の読者が「なるほどそうだよなぁ、いい分析だ。自分の頑張るべき場所は確かにここにあるのだ!」と思って読むことができるのは、心のどこかで自分は機械を使ってクリエイティブな仕事を自分の業種でいつかやり遂げることができると信じているからだと思うwww こういう今の僕みたいな考えの人が増えるのが、一番経済によって良くないな(‘A`)良い本でした。初版をそのまま持っていて、数十年後により機械によって発達した世界で過ごしながら改めて読み、その展望について色々レビューしたいと思えるくらいには良い本だった。装丁も豪華だしねw十分満足。 ちなみにタイトルはrace against the machineだけど、これはどう考えてもロックバンドのrage against the machineのオマージュっていうw機械に対して怒りではなく、反抗ではなく、協力(race with)の関係を保つようにしていきたい。
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
テクノロジーの進化による人間の役割の変化を構造的に論じた良著。 数字による裏付けも比較的しっかりしており、起こる変化とそれに応じて人が(先進国の社会が)どう変わるか、どう変わるべきかまで網羅的にかかれている。 ただし、個人がどう行動すべきか、というところまでは落ちていない。
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在の高失業率を招いている要因として、技術革新を指摘している本。つまり、技術の進歩により、今まで人間が行っていた仕事を機械が行うようになっているために、失業率が上がっていると指摘している。筆者は、これを憂う必要はなく、技術革新により新たな雇用を生むこともありうると主張している。また、そうなるために、高度な義務教育や高等教育を行うべきだなどと主張している。 技術革新により高失業率を招いているという指摘は、盲点であったため、新鮮であった。具体例や論理展開も明快であるため、読みやすいと思う。 しかしながら、実際に機械によって駆逐されてしまった人々をどう救うか、という視点は欠けているように思われる。恐らく、この本にとって先の視点は埒外にあると思われるが、触れて欲しい論点であった。
1投稿日: 2013.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ技術の発展がどう人間の雇用に影響を与えるのかを分析している。単純作業はどんどん機械に置き換えられているが、危機的なものは中間層のホワイトカラー労働者。体の動きと知覚を組み合わせることは難しいというのは、言われてみるともっとも指摘。うまく機械を味方につけるようにしていきたいものだ。
0投稿日: 2013.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーの進化は、果たして雇用を奪うのか。過去の歴史から紐解くに、経済学者はそんなことはない、と話すが、実際のところ、アメリカでは新たな雇用が生まれていないという現実があり、また富める者はなお富み、そうでないものはさらに貧しくなる傾向が見られる。その要因にはここ数年の主にIT関連のテクノロジーの、爆発的な、指数関数的な(本のなかではムーアの法則、チェス盤の法則)進化によるものだと主張する。 で、著者はイギリス産業革命時ののラッタイド運動のように、人はテクノロジーを打ち壊さなくてはならない!ではなく、現状はテクノロジーの急速な発展に人間が追いつけていないので、そのギャップが埋まれば大丈夫、という結論に至る。 確かに今更昔に戻る気はしないし、かと言って仕事が奪われるのは困るし、というなかで、国家も個人も適応していかないといけない…それは今までの国家だったり個人だったりの在り方とは違うかもしれない(内田樹なんかがギャーギャー言ってるのはそれが気に食わんのやろなぁ)。しないといけない、と思うのか、すれば大丈夫!と思うのかの差はあれども。著者のようにポジティブになるほどバイタリティはなく、かと言って悲観しても仕方ないしなぁ、やれやれ、というのが素直な気持ちかも。
0投稿日: 2013.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカを中心に話題になっている本です。「雇用問題」をテクノロジーの進化との関わりという文脈の中で議論しています。 本書において著者たちは、「コンピュータが人間の領域を侵食することにより雇用は減り、その減った雇用は、高所得を得られる創造的な職場と低賃金の肉体労働に二極化する」との見通しを示しその状況に警鐘を鳴らしています。しかしながら、彼らの最終的なスタンスは楽観的です。 結論はそのとおりになるかもしれませんが、全体を通して論考が甘く、正直なところ物足りなさが大いに残る内容でした。
1投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・サマリ テクノロジーの伸長によりコンピュータが置き換えられる仕事が増えていく。現時点でもこれは怒っており、企業業績の伸長に比して雇用の伸びは停滞している。 さらに、コンピュータの能力の伸長は指数関数的であるため雇用に対する悪影響は今後大幅に大きくなる。これによりスーパースターと負け組の格差が広がり社会に悪影響が及ぶ、あるいはすでに及んでいる。 これに対して社会的、個人的な対応策が必要である。社会的に所得の再分配は安易な手段であるが、労働の対価が金銭だけでないことを考えるとそれだけで十分とは言えない。教育を拡充して行くことが必要である。個人としてはテクノロジーと敵対するのではなくテクノロジーを活用していくことが必要である。チェスにおいて世界チャンピオンがコンピュータに敗れたのは10年以上前のことであるが、現在最強のチェスチームは人間とコンピュータの混合チームである。人間とコンピュータは相互補完的に働きうる。 著者はテクノロジの伸長が社会に及ぼす影響について上記のような歪みがあるとしても一方で楽観的である。過去の二度の産業革命と同じように人類の生活をよりよい方向に向かわせることを確信している。 ・感想 - 総論としてAgree。現在起こっていることとしても、近未来の予測としても腑に落ちるところが大きい。先日の将棋の電脳戦もタイムリーに象徴的な出来事。 - では、どうすれば?というところは社会的な対策はともかくとして個人的には現実感が乏しい。じゃあこれからどうしよう? - 貪欲な改善意識と日本との差。教育分野や起業意識といったところに改善提案がされているが、より遅れていると思われる日本の環境からすると一歩も二歩も先をいかれている感覚。
1投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
E・ブニョルソン、A・マカフィー『機械との競争』日経BP社、読了。本書は「技術の進歩によって人間の労働力がいらなくなり、失業が増えるのではないか」というラッダイト運動以来、繰り返された疑問に応える一冊。コンピュータの加速的な進歩は、機械が人間が駆逐する現在と言っても過言ではない。 経済学者はこの問題に「杞憂」と答えてきた。それは技術の進歩によって新しい仕事が生まれ新たな雇用機会となってきたから。労働力や資本の存在量が同じでも、技術革新は、より多くの生産物を生み出すから長期的な成長率を高くする。 しかし本書はこうした主張を一蹴する。著者は近年の情報技術の発展は雇用を奪っていると主張、技術の進歩が速すぎるからだ。これまでの調整メカニズムうまく機能しない。著者は「ムーアの法則」と「チェス盤の法則」からそれを説明する。 指数関数的に進むコンピュータの進歩は、雇用の減少のほか、置き換え不可能な領域における雇用の二極分化をもたらす。作曲家のような高所得を得られる「創造的な仕事」と低賃金の「肉体労働」。がそれである。 自動車は人間だけが動かしたが、グーグルの自動車は公道走行実験に成功したという。果たしてコンピュータは人間を凌駕するのか。本書の議論は説得的で、著者は楽観的提言を最後に付す。ただし疑問も残る。行く末を追跡したい。
0投稿日: 2013.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「コンピュータの性能の向上、進化が人間の雇用を奪っていく。」…生産性を追求することで自分達の首を絞めているような感覚は、産業革命の時と同じかもしれないけど、その時と同様に過去を上回る新しい雇用が発生するかは難しい気もする。機械にできない仕事を探すのがどんどん難しくなってくるかも。
0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ散々と煽っておきながら、終わり方がそれかい!って感じも否めないが、著者がいうアイディアの組合せ、というのは合点がいく。 ビッグデータの時代と言われて久しいが、結局のところビッグデータも、組合せをどうデータから抽出するか、が鍵となる。 人間が新たな組合せ=イノベーションを常日頃模索しないと、いつテクノロジーにとって変わられるかは、時間の問題。 最後の法政大学の先生によるあとがきは頂けないね。
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報技術は新しい仕事を生み出すが,過渡期は従来の仕事に従事していた人の仕事を奪い失業者が増える. 特に情報技術は進歩が凄まじいため,仕事を奪う側面が強調されて見える. 過渡期に生きるには(過渡期じゃなくとも言えるが)結局新しく必要になるスキルを勉強し続けるしかない.
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『どれほど富裕な国でも、人的資源を無駄遣いするゆとりはない。大量の失業に伴う士気の低下は国家にとって最大の無駄であり、社会秩序を脅かす最大の敵である。』 --フランクリン・ルーズベルト
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械が得意なことは機械化される。 その結果、人の労働が2極化する。 新しみは感じなかったが、わかりやすく整理されていた。
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログデータサイエンティストによる学問のすゝめ。 個人のスキルが中庸な人はシステムに仕事とられる、ってこと考えると、自分の業界のことをかんがえてしまうよ。 デザイン最高なんで手にとって欲しい。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰をライバルと思うかで、世界の見え方がガラリと変わる。 職場の同僚をライバルと思えば出世競争を勝ち抜く術が必要だし、同業他社をライバルと思えば業界内シェアやランキングが重要だし、広くエンタメ業界で可処分所得や可処分時間を奪い合ってると思えば、お小遣い争奪戦+時間争奪戦に勝利する必要がある。いや、ライバルは世界中にいると思えば、グローバル競争を勝ち抜かないといけないし、ライバルはアップルやグーグルやアマゾンだと思えば、打つべき手はいまとはまったく変える必要があるだろう。 だけど、ライバルが機械だったら? 自動翻訳、自動ライティング、自動編集……。そういう世界で、ボクらはこれから戦っていかなければいけない。そして、ヤツらの進化のスピードは速すぎる。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械(特にIT)がどんどん進化してきて、人間の仕事を奪ってきている。しかも、今までの機械の進化より、これから先のITの進化は、今より人間に近い柔軟な仕事ができるようになり、ますます人間の仕事を奪っていく可能性がある。 そうなっていくのはもう逃げようがない。そうなった時に、人間がやるべき仕事とは。世界はどうなる、貧富の差は。考えれば考えるほど結論は出ませんが、先を見据え、一つの仕事に拘らず、本業以外のスキルを持っておき、複合的に仕事ができることが、機会に打ち勝つ、唯一の手段のように思います。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ【機械とどのように付き合っていくのか?】 人間の職が機械によって侵食されていき、最終的には一部の知識階級者と大部分の肉体労働者に二分されて、格差社会がより進行するのではないか?とふと感じて、この本を読み始めた。 本書によれば、コンピュータの進化のスピードは極めて速く、「ムーアの法則」(集積回路上のトランジスタ数は18ヶ月ごとに倍になる)に則り、確実に前に進んでいる。人は未だそのスピードに危機感をいだいていないが、「チェス盤の法則」にもあるように、中盤を超えたあたりでそのスピードに恐怖感さえ覚えるようになるだろう。 人間にしかできない仕事。それは2つあると本書は説く。 1.創造性・リーダーシップを必要とするもの 2.人間にしかできない複雑な動きの持つ肉体労働 前者は高給取り、後者は低賃金となり、賃金に対する格差はさらに広がっていく可能性はある。ただし、将来的に機械が上記2つもできるようになる可能性もあるので、気にかける必要はある。(ドラえもんの映画、ブリキのラビリンスのような世界観) 我々がすべきことは、機械といかに共存していくかであり、また自分をどのように成長させるかである。前者は、全世界的には政治的な面も踏まえて議論されるべきである。一方の後者は、そうはいっても機械の進化のスピードを弱めることはできない中で、自分がどのように対応していくのかをしっかりと考えることだ。 機械が人間にしかできないと思われていたことを、やってのける日もそう遠くはない。
0投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ機械に労働機会を奪われる、という現代の状況を分析。 乗数的に機械技術が進化したがゆえに、そのスピードに人間の側がついていけなくなっている、これはまさにその通り。不景気で雇用が無いのではなく、そうして爆発的に進歩した機械に仕事をとって代わられた事によって雇用が減っているのだと。 確かに会社で働いていて、何でも自動化したりすると人の手数が余る、という状況は経験があるだけに、著者の言う状況は容易に理解が出来た。 ただ、この事態を著者は楽観的にとらえている、と自ら述べている。 つまり、機械がどれだけ進歩しようとも機械単独では最善の仕事は出来ない、逆に人間とペアを組み、機械を活かすことがベストなのだという。 そのために、人はもっと教育を受ける、スキルを高める機会を持つべきだと。 しかしこの主張の根拠がなんだかよく分からない。別に対機械を意識しなくても、既に教育への重点投資は行われている国が多いのではないだろうか。今まで通りで問題ない、と言っているような気がしたが、だったら機械との競争なんてそもそも意識しなくてよいはず。前半の「雇用は機械が占めていく」という世界になる可能性に現実味があるだけに、もっと違う対処策があるように思うのだが。。。
0投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業の豪華な受付にポツンとおかれた自動応答システムを見たとき、ここにいた綺麗なお姉さんたちはどこに行ったのだろうと思ったことがある。この本は機械化によって人間の単純作業、それも資格や微妙な感性が必要とされない単純作業がどんどん駆逐されて行く可能性を記している。確かにガテン系職業への需要があまり変わらない一方で、世間から「きれいな仕事」と思われがちの事務系の中途半端にスキルが必要な仕事は確かに機械化の恐怖だ。この辺は昨今の薬のネット販売解禁をめぐる議論にも共通しているようにも思う。この事態への著者が示す処方箋については大雑把な印象もあるが、今後の世界を想像するトレーニングとしては良書だった。
0投稿日: 2013.04.28
