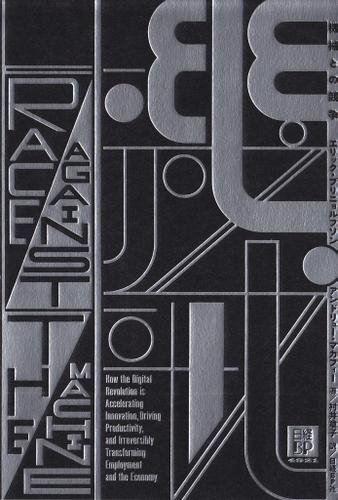
総合評価
(127件)| 14 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 8 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログある意味衝撃的。機械は人間を労働から駆逐するかということを、肯定しているという事。 そして、「1985年を」IT元年とし、ムーアの法則による集積密度の倍増ペースが18か月ごとだと仮定する。すると、32回倍増した年、すなわちチェス盤の32マス目に到達した年は2006年ということになる」にあるように、機械の進歩のスピードが飛躍のレベルになっているという事。
0投稿日: 2013.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーの急速な発展がいかに人間の雇用に変化を及ぼしているかという議論であって、決して仕事を奪っているとは言っていません。しかしなんでこんな読みにくい装幀にしたんでしょう。日経BPだし内容から言ったら電子書籍で出すべきだと思いますが、
0投稿日: 2013.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、ITが既存業種を駆逐する、というタイプの議論が花盛りであり、本書もそのようなものの1つ。これから駆逐される業種とされにくい業種に関して、目新しい内容はあまり書かれていない。ただ、本書は主にアメリカの雇用情勢を踏まえて書かれているので、日本人が書いた本とは視点が少し異なっている気がする。将来、ITによって労働力が現在ほど必要なくなるとして、日本は人口も自然減少するからまだマシだけど、アメリカは移民のせいで人口が増えるからますます失業率が上がってしまう。「自由と正義の国」も大変だね。
0投稿日: 2013.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーの進化は雇用を減少させ所得格差を拡大させている。そしてその指数関数的な進化は今後、良い面、悪い面を含めてより一層の大きな変化をもたらすと説き未来への警鐘を鳴らす。 米国での対応としては教育への投資、移民の受け入れ、起業家精神の育成、通信・輸送インフラへの投資など19のステップを提言として挙げている。 テクノロジーの進化についての未来への展望はとても面白く興味深いが、提言は米国らしい月並みな感が否めない。「機械との競争」で弾き出された人々は「機械への怒り」で拳を握り締めるしかないのだろうか。。。
0投稿日: 2013.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中で飽きてしまった。 装丁はデザイン良く中身も黄色の用紙に青い字でインパクトはあるのだが、 集中して読めず内容が頭に入ってこない。 頭に残っているのは……(以下、意図と大きくずれていないと思うが自身なし) ・IT革命は雇用を奪うだけになっている 産業革命は従来の雇用を奪うように思えるが実際は新しい雇用を生み出している しかしIT革命は指数的に発展しており人間のスキルや組織制度が追い付いていない ・雇用が減少しているのはスキル分布の中間層 創造的なことはコンピュータに出来ない 事務は自動化しやすい 肉体労働は自動化しにくい、ただし今後も人間の独壇場とは限らない ・機会を味方につけることが大事 近年のチェスの優勝者は最高の人間でも最強のコンピュータでもない 人間とコンピュータの組み合わせが優勝している 「弱い人間+マシン+よりよいプロセス」が「強い人間+マシン+お粗末なプロセス」を打ち負かす ・創出する市場に上限はない イノベーションは他のイノベーションを組み合わせた結果が多い いろんな組み合わせを試して新しいイノベーションを起こそうぜ
0投稿日: 2013.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館の返却コーナーに置いてあった本で、タイトル(機械との競争)に惹かれて手に取ってみました。この本の著者である米国の方が、なぜアメリカの失業率は、景気が良くなったにもかかわらず低迷し続けているのかについて解説及び将来への提言をしています。 印象に残った点は、技術の進歩がいよいよ人間を労働力として必要としなくなってきたということです。進歩のスピードは、過去2回の革命(蒸気機関、電気)と現在進行中のコンピュータとネットワークによって加速度的(2の階乗のスピード)に速まってきていて(p155)、現在はチェス盤(64升目)の半分を通過した辺りであろうとしています。つまり、これからスピードは更に上昇することを暗示しています。 このスピードが、身分の格差や、スーパーエリートと一般人の格差を大きくしているようです。技術の進歩により、生産性が上がるのは喜ばしいことですが、そのために失業者が増えるというシステムは、「人間の社会」として理想的な姿であるのかどうかを考えさせられた本でした。 以下は気になったポイントです。 ・米国の国際総生産は 2009.6の大不況終結以来、7・四半期の間に年率換算で平均2.6%の成長率を記録、これは1948-2007の長期平均を上回る数字、アメリカの企業収益も史上最高、設備・ソフトウェアの投資はピークの95%まで回復、なのに新規雇用は控えられたまま(p11) ・機械による雇用なき景気回復は、1980,1990年代、21世紀の最初の7年間の失業率が低かったので、雇用喪失説は信用されなかった(p19) ・コンピュータが更にパワフル、高度化するにつれて、仕事・スキル・経済全体にこれまで以上に大きなインパクトを与える、問題の根本原因は、大不況ではなく、人々が「大再構築」の産みの苦しみに投げ込まれていること(p23) ・グーグルの自動運転車、ライオンブリッジの機械翻訳ソフトは、デジタル技術によるパターン認識能力、複雑なコミュニケーション面での能力が向上したことを証明した(p36 ・1988-2003年の15年間で、処理速度が4300万倍の高速化を達成したのは、プロセッサの能力向上(1000倍程度)より、アルゴリズムが4.3万倍に高性能化したことが大きい(p40) ・1958年をIT元年、ムーアの法則による集積密度倍増ペースを18か月とすると、チェス盤の32マス目に到達したのは、2006年になる(p43) ・人間の能力でコンピュータに犯されない領域は、いまのところ肉体労働の分野、体の動きと知覚をうまく組み合わせる必要があるため(p53、99) ・生産性の伸びが1990年代から大きくなっている(1960年代と同等)のは、情報技術が原動力である(p65) ・現在の失業の説明としては、解雇の増加ではなく、雇用の喪失である、雇用主は以前ほど労働者を必要としなくなった(p72) ・技術革新がもたらす3種類の勝ち組、負け組の定義、1)スキルの高低による労働者、2)スーパースターと普通の人、3)資本家対労働者、これらが重なり合っているのが重要(p78) ・経済の拡大をもたらした相次ぐ技術革新は、機械を敵に回しての競争ではなく、機械を味方につけた競争から生まれた(p109) ・世界最強のチェスプレーヤーは、二人のアマチュアプレーヤーと3台のコンピュータからなるチームで、弱い人間+マシン+よりよいプロセスが勝者となっている(p110) ・提言の1つとして、特許制度の改革(訴訟が大量におきるため、特許取得を煙たがる風潮あり)、著作権の保護期間は伸ばすべきでない、がある(p139) ・指数関数的に進むコンピュータは雇用に大きな変化をもたらす、1)雇用の総量が減る、2)雇用の二極化が進む(p171) 2013年4月6日作成
1投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
知人に借りて読了。 機械との競争ということで古くはチェス。今ではニコニコで将棋の対決など、機械VS人間の枠組みで捉えられる問題の話。 文字も大きく、非常にライトな内容なので、サクッと読むことが出来る。 僕がこの本で興味深かったのが、2つ。 1つは、過去の歴史を紐解き、最初は「ラッダイト運動」にまで遡るということ。 もう1つはジョン・メイナード・ケインズの「テクノロジー不況」を持ち出したことだ。 歴史は回帰する。愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶというが、歴史の教訓は非常に重要だろう。たとえ、そのまま適用できなくても比喩的に用いれるからだ。 ただ、僕は過去に似た内容を読了している。 『コンピュータが仕事を奪う』だ。 レビュー:http://booklog.jp/users/tetito/archives/1/4532316707 こちらの方が、より詳細に記載されているような気がする。 昔にも書いているが、フリードマンのフラット化する社会の件も想起した。 今で言えばワーク・シフトも似たようなことが書いてあるのだろう。教養として、何かしら読んでおくべきと個人的には思うところだ。 目次 第1章 テクノロジーが雇用と経済に与える影響 第2章 チェス盤の残り半分にさしかかった技術と人間 第3章 創造的破壊ーー加速するテクノロジー、消えていく仕事 第4章 では、どうすればいいか 第5章 結論ーーデジタルフロンティア 解説 小峰隆夫・法政大学大学院教授
0投稿日: 2013.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか考えさせられる本でした。 これからコンピュータはどうなっていくのか、それに人が対応できるのか・・・ 一体、どうなってしまうのでしょうね。
0投稿日: 2013.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ■機械との競争 A.米国企業の業績は回復しているが、新規雇用は手控えられたままである。その説明として、次の3 つの説がある。 1.景気循環説:今回の大不況のように、需要の落ち込みが激しい場合、回復に時間がかかる。ゆえに失業率が高い。 2.停滞説:イノベーションを生み出す能力が伸び悩んでいるため、経済は不振から抜け出せていない。 3.雇用喪失説:技術が急速に進歩した結果、必要とされる労働者の数が減っている。 B.米国の現況を見ると、雇用喪失説が妥当といえる。すなわち、技術革新のペースが速すぎて、人間が取り残されている。換言すれば、多くの労働者がテクノロジーとの競争に負けている。
0投稿日: 2013.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ3/20読了。飛行機移動中に8割方読破。米国では人口が増加してるにも関わらず、雇用機会の喪失の方が大きいそうです。本書では、その原因をデジタル技術での技術革新などに求め、人間の労働が機械に取って替わられ、その進歩の速度に人間が追い付けていないことを指摘しております。人間が機械に勝つのは、肉体労働と創造力が必要な労働に二極化しているとの分析は印象的。雇用と事業価値創造、そしてその目的達成手段としての教育について深く考えさせられます。装丁もSF小説ぽくてスタイリッシュ。
0投稿日: 2013.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ産業革命が起こる度に一部の人間の仕事は奪われてきた。現在の第3の革命はコンピューターの発展により、指数関数的に拡大していくと考えられている。つまり人間の仕事はどんどんコンピューターに奪われていく。これは止まらないと考えられているが、筆者はコンピューターにも苦手なところがあり、これを活用し共存することで人間の仕事はなくならないという。一方で、生き残るための仕事の方法を身につけなければ仕事がなくなるのは時間の問題かも知れない。 現在気づいていなくても自分自身の仕事が将来的に奪われる可能性はかなり高いので、その中で生き残るための準備をする上でも本書を一読し学ぶべきポイントを具体的に考えていく必要があるのではないかと思う。
0投稿日: 2013.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネットが当たり前の時代になって20年近くたちました。 その間のITの発展は目覚ましく、それによる社会の変化も大きなものです。 蒸気機関、電気による産業革命に続く第3の産業革命とも言われるIT 本書はこれによる雇用への影響を論じた一冊です。 全5章からなる短い(しかし内容は充実している)本ですので、忙しくて余り時間がないと言う方にもおすすめです。 では前置きはこの位にして以下で内容を簡単にご紹介。 上記の通り全5章からなり、それぞれ 1章:テクノロジーが雇用と経済に与える影響 リーマンショック以降、回復傾向を見せるアメリカ経済にも関わらず、同国の雇用状況は厳しいまま。 この状況を説明する以下3つの理論を解説し、最後の「雇用の喪失説」が現実だと主張 ・景気循環説 今の状況はこれまでにもあったありふれたもの。 雇用状況が厳しいのは単純に景気の回復が不十分なだけ。 ・大停滞説 イノベーションを産み出す能力や生産性を高める能力が長期的に失われてきており、現在の雇用状況はそれが目に見えるようになって来たものである。 ・雇用の喪失説 技術の進歩により、従来の人間の仕事を機械が行うようになった。 その結果、雇用自体が減少してきている。 2章:チェス盤の残り半分にさしかかった技術と人間 3章:創造的破壊ー加速するテクノロジー、消えていく仕事 以下の様なテクノロジーの発展を指摘。ムーアの法則に基づき、これからその発展速度は想像を絶するものとなると主張。 ・2004年に出版された経済学者フランク・レビーとリチャード・マーネンの著作「新しい分業」では自動車の運転は機械には無理だと主張されたが、6年後にはグーグルカーが完全自動運転を実現した。 ・コンピューターのパターン認識能力を活用した証拠文書解析により、弁護士1人で500人分の仕事が出来るようになった。 4章:では、どうすればよいか テクノロジーの急激な発展の一方、人間社会の変化は遅い。 その結果、テクノロジーへの個人や社会の対応の遅れが生じ、それが雇用の喪失につながっている。 しかし、機械と対立をするのではなく、それと協調すれば生産性はこれまで以上に上がる。 例)チェスの現チャンピオンはコンピュータではなく、コンピューターの使い方に秀でたチェスのアマチュア2人組+コンピュータの組み合わせ ebayやアマゾンマーケットプレイ、Appstore、知的仕事を依頼できるMechanical Turk など様々な形態の新ビジネスが誕生。 これらによって直接的に作られた雇用は数百万。 そして、急激に変化する技術に対応するため、人材育成の重視や様々な規制の撤廃による社会の柔軟性の確保などを目的とする19ヶ条の提案を提示。 5章:デジタルフロンティア これまでの2つの産業革命同様に、今回の革命に社会が対応し終わるまで数十年の時間がかかる。 しかし、人と人との繋がり、政府の透明性の向上や説明責任の強化など革命の先には豊穣な未来が待ち構えている。 未来は明るい。 産業革命は価値の抜本的な変化を生んできました。 本書でも紹介されているラッダイト運動(1811年から1817年頃、イギリスで起きた機械破壊運動。機械に職を奪われた人々が機械を破壊)など、その変化の過程において社会に大きな痛みをもたらしてきました。 しかし、その後の歴史を見ても分かるようにラッダイト運動はこの変化を止める力を持ちません。 従って、その変化を拒むのではなく、逆にそれに積極的に対応していく事が求められます。 著者らはその対応力の要として教育の重要性を指摘しており、革命後の世界では、もしかしたら現在の大国ではなく、教育制度が優秀な国家が主導的立場にたっているのかも知れませんね。 上記の通り、短い本ですので忙しくても十分読みきれる一冊となっています。 興味をお感じになられれば一読されてみては如何でしょうか。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本来、技術の進歩は、生産性を高めることによって長期的な成長を促すものであったが、昨今のIT技術の進歩が速すぎるがゆえに、その成長の果実を掴むことができず取り残される失業者が増えていっていると主張。 人間でしかできないだろうと思われてきたことが、次々とコンピューターによって置き換えられていく状況。 では、どうすれば良いか。 本書では19項目の解決策を提言している。 どれもすばらしい内容ではあるが、教育や投資、法規制など、社会システムを変えていくことが中心で、個人としてどうしたらよいかは書かれてはいない。 いままさに取り残されようとしている人が読んだら憂鬱な気持ちになるだろう。 しかしながら、技術に奪われるのではなく、技術をパートナーとして使いこなすことによって富を産み出す事も可能であるとプラス面の示唆も与えてくれる。 現状を把握するには十分に説得力のある話が短くまとめられているので、目を通しておいて損は無い本だと思う。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11484248440.html
0投稿日: 2013.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ装丁が格好いいけれども、ちょっとどぎつい。プロレタリア風のデザイン。紙質がボール紙のような黄色でめくりにくい。ちょっと昔懐かしい感じのポップさ。Amazonでポチったけど書店だったら買わなかったかも。意外と小さくて薄い本。字も大きい。 機械は人の雇用を奪うだろうか。人間にできて、機械にできないことはなんだろう。創造的な仕事、肉体的な仕事。なにもないところから、作曲をしたり絵を描いたり、笑顔で食事を運んできたりすることが機械にできないのであれば人間の行動の意味はそのへんにあるのではないか。
0投稿日: 2013.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ“機械の登場による事務職のコストの低下、しかし日本はそれをそのまま人がやっているので、できたあとのサービスやものの値段が高い(=デフレ)。このデフレを脱却するには、事務職の機会への移転と、それであまった人材の創造的職と肉体労働への最分配と、それに伴う組織変更である、という本 3・11見た感じ、高すぎる”
0投稿日: 2013.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ原著は紙で97ページの分量だったので、読むのに時間は掛かりませんでした。サマリーについては以下がかなり詳細なので参照のこと。 http://getnews.jp/archives/286612 本書は「機械が雇用を奪うか」という問いについて、報告と提言をしています。画期的なのは、それについて楽観視していること。いずれにしても誰しもがどの道巻き込まれていく問題なので、この本なり前掲のサマリーなりを読んで考えて備えると良いでしょう。 しかし4章で挙げられた19の提言については疑問があります。どれも政府が政策として行なう行動なのですが、そしたらその目的は国富なり国民所得の中央値向上にあるのでしょうが、それこそテクノロジーとグローバリゼーションの恩恵により他国民がフリーライド出来てしまうと思われるけど、それで良いんでしょうか?そう考えると、小さな政府志向者の言うように、適切な政策というのは、人的資本の形成(主に教育)と規制緩和位しかなくなるように思います。
0投稿日: 2013.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本のある層は、電気料金が高くなると空洞化する、というのだけれど、それはそれで電気の比率が高い産業はそうなのだろうと思うけど、人件費のことはあんまりいわないなあ、と思っていました。この本は、日本と外国の人件費の競争、ではなくて、コンピュータがあんたの仕事をどんどん奪うぜ、ヤツらこんなことまで出来るようになっているんだぜ、という本。 僕はそっち方面に興味があるので、いまさらびっくりするようなネタもなかったのだけど、むしろ驚いたのは、解決策。教育に力を入れろ、持ち家に補助金を出すな。さあこれをどう捉えるか。流動化を高めることは、コンピュータとより近い土俵に行っちゃうんじゃないかなあと思っていたのですが。地元で商売、じゃ駄目なんか。それにしても、紙の色や左下の数字など、ずいぶん読みづらい本なのだけど、機械なら正確に読み取るよ、という皮肉なのだろうか。
0投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
以下の解説だけでも良かった ----- 10年後、税理士や事務、営業などはなくなる? デジタル失業の時代が到来(ビジネスジャーナル) - 経済 - livedoor ニュース http://news.livedoor.com/article/detail/7464298/ 10年後になくなってそうな職種 - ネットゲリラ http://blog.shadowcity.jp/my/2013/03/10-5.html コンピュータ技術やロボットの飛躍的な発展は、雇用の二極化をもたらすようになる。 今までにない新しいビジネスを創ったり、感動的な音楽や文学を生み出すような直感的で創造的な仕事の領域と、高度な問題解決能力をも必要とする看護師や美容師、配管工といった反復作業ではない肉体労働はコンピュータやロボットには苦手な領域だ。 雇用はこれらの高所得を得られる創造的な職場と低賃金の肉体労働に二極化され、それ以外の中間層の仕事は急速にコンピュータに置きかえられる。それが、現在の総雇用減少の一因になっているというのだ。つまりデジタル失業の時代だ。 『機械との競争』の共著者の1人、アンドリュー・マカフィー(MITスローンスクール リサーチサイエンティスト)がインタビューに答えている。 IT革命の影響で恩恵を受けているのは高度スキルの人材だ。コンピュータ科学者やデータ科学者、プログラマーなどのハイテク分野の仕事で、アマゾンやアップル、フェイスブック、グーグルの社員は学歴もスキルも非常に高い。 一方で、コンピュータのおかげで文書事務が減ったことが一因で、事務や秘書、営業といったホワイトカラーの仕事が減っている。また、計算ソフトのおかげで、ソフト開発会社は儲かるが、会計士、税理士の需要はこの数年で8万人も減っている。 これまでは「テクノロジーは起業と雇用を生む」と考えられてきたが、テクノロジーは起業を生み出すものの、雇用は生み出さないどころか、奪おうとしてしまうのだ。
0投稿日: 2013.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本を見た時の感想は「何だ、この装丁は」だった。何しろ一風変わった装丁で、目立つなあと思ったと同時に、このジャンルの本にしては、アバンギャルドな表紙なので、どんなものか手にとって読んでみた。 内容は、機械が人間の仕事にとって代わる、あるいは人手が少なくなるという事が書かれている。その原因は、テクノロジーの発達のおかげで、オフィスの所在している場所は関係なくなり、専門にしていない人でも利用できるようになっていることが挙げられている。 カスタマーセンターは、アメリカの場合、同じ英語圏のインドやフィリピンに移して人件費の削減をしている。アメリカ英語やアメリカの文化を教えて、アメリカの顧客に違和感を持たせないようにしているという文章を読んだことがある。 語学の教師にしても、フィリピンの大学生とスカイプで英会話のレッスンなんて言う時代になっている。日本で語学学校の教員をしている外国人は、脅威に感じているだろうなあ。 法律の世界でも、テクノロジーの威力が発揮されている。E-discoveryと言う、訴訟があった場合、アメリカの司法省に対して必要な書類を提出するために、紙のものならPDF化してサーパーに入れ、パソコンのデータを必要と思われるキーワード検索をかけて振り分けるものがある。まあ、トレジャーハンティングと言ってもいいかな。イーディスカバリーと言っても、訴訟を起こされる企業にとっては「よい発掘作業」ではない。紙で発掘作業を行っていた時は、人件費と時間がかかり依頼する企業側には負担になっていた。テクノロジーを使うと手間がかなり省ける。法律事務所にとっては、人件費削減が出来てウハウハといったところか。著者は、ニューヨーク・タイムズでディスカバリーに関する記事を引用している。 ほかの分野でも、人間の雇用が機械に脅かされてきている。今回の本は、「これからがデジタル革命の後半戦。飛躍的に能力を拡大していくコンピュータに人間はますます仕事を奪われる」と言う観点から2人の著者が書いた。学校で得た知識1.0のまま、社会人として過ごしていると、機械にバッサリ仕分けされましたとなりかねないので、知識2.0にアップロードする必要があるなあと実感した。 ニューヨーク・タイムズのディスカバリーに関する記事 http://www.nytimes.com/2011/03/05/science/05legal.html?pagewanted=all&_r=1& 東洋経済のサイト http://toyokeizai.net/
0投稿日: 2013.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログコンピュータとネットワークの指数関数的な発展に人間が追いつかず、雇用がどんどん減っていくのが大変だという本。切り口と最新事例の紹介は面白かったけど、打ち手の教育への投資というのはもう少し深掘って欲しかったな。 教育へ投資してもコンピュータの発展には追いつけない気がするし、本書で語られている所得格差は埋まらない気がする。(当然、大事だけど。) スーパースターの成果に対する報酬を一部が独占するのではなく、社会全体でシェアできる仕組みが必要と思う。雇用が無いなら働かなければ良い社会って現実的じゃないのかな。狩猟時代から農耕時代になった時に生まれた人的な余剰によって文化や技術が大きく進歩したように、労働以外の領域での発展につなげられるのが理想なのでは?
0投稿日: 2013.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
薄くて大きい字なのですぐ読める。 主張も平易で、頭に入ってきやすい。 ・技術の進歩はあまりに速すぎる。特に、ムーアの法則に代表されるように指数関数的なPCの性能向上はもはや人智の及ばないレベルにまで達している(著者らはこれを、ご褒美の麦をチェス盤の升目一つごとに倍にしてもらうように頼んだ逸話になぞらえる。最初のうちはその増え方はゆるやかだが、チェス版の半分を超えたあたりからは想像もつかないレベルで増えて行く) ・コンピュータの進歩はもちろん、経済全体のパイを大きくする。しかし、物質と違い、再生産のコストが0の情報化社会においては勝者の総取りが起こりやすく、増えたパイの恩恵は勝ち組の一部にしか行き渡らない。 ・今後、雇用は二極分化して行くだろう。報われる仕事はきわめて高い教育を受けた者だけに可能なクリエイティブな仕事と、介護のような肉体労働、の両極端な仕事のみが機械に取ってかわられない領域として残るだろう。 ・今後、機械と競争するのではなく、機械を使い、協調していくことが求められるだろう(このへんは具体性に乏しい) ・勝者総取りの世界では二番手戦略というものは存在しない。マイクロマルチナショナルともいうべき、ニッチの王様として地位を確立していく企業が生き残る
0投稿日: 2013.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ短いが重要な論点を提示している。 ICTの進化が非常に早いためで、雇用の調整が間に合わず、多くの仕事がコンピュータに奪われているという指摘。 テクノロジー失業という言葉はケインズの昔からあるのだが、それが加速している。 自動車運転のような複雑なパターン認識をともなう作業はコンピュータにはまだ無理と2004年にはいわれていたが、2010年にはGoogleがほぼ実用になりそうな自動運転を実現した。しかもそれは、トリッキーな方法ではなく、力技でまっこうからパターン認識をやってのけてのことだった。(20万キロ自動走行して一度だけ事故を起こした。それは信号待ちで停車中に人の運転するクルマに追突されたのだった、という話には笑った。) コンピュータとの役割分担において、人間は何をするのか。 創造的な仕事、人をよろこばせる仕事、は「まだ」人にしかできない。 その方向を伸ばすための具体的な19の提言も含まれている。アメリカを前提としているが、アメリカですらこうした方向性へむけた行動が不十分だと認識されているとき、日本の現状はどうかと考えると、これは相当に厳しいといわざるをえない。 日本人はロボットや自動機械による対人サービスへの違和感が少ないという文化的な「優位性」があるのだから、そこを活かして、人にしかできないことをやる社会をめざすのがよいのではないか。 マシンエイジを彷彿とさせる金のかかった立派な装丁。紙が厚いので、束の割には早く読める。
0投稿日: 2013.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2011年に出たキンドル版を翻訳したもの。すぐ読めます。本の紙が厚紙で不便。値段もやや高すぎ。 リーマンショック後失業率が回復しない説として、①景気循環説(クルーグマン)、②停滞説(コーエン、フェルプス)、③「雇用の喪失」説を挙げ、③を主張。 ③は停滞説の逆で技術進歩が速すぎ、中間層の職が「機械」(コンピュータ)で代替され、雇用の総量が減り(「テクノロジー失業」by ケインズ)、「スーパー・スター」と「肉体労働者」の「雇用の2極化」が進行しつつある、という説。 対策としては、「組織革新の強化」と「人的資本の投資」であり、著者から19の提言が挙げられております。 小峰先生が「日本が世界に伍して戦うには」と解説を付けておられますが、米国は更に先を進もうとしている時に、日本はやばいんちゃう?、と警鐘を鳴らしておられます。 日経ビジネスオンラインで、第1章が読めます。 雇用と所得は「誰が」奪ったのか 『機械との競争』第1章を公開 テクノロジーが雇用と経済に与える影響(上) http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130205/243298/ 雇用を奪ったのは業務の海外委託でも規制でもない 『機械との競争』第1章を公開 テクノロジーが雇用と経済に与える影響(下) http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130205/243327/ <書評> 『機械との競争』 産業革命によって馬が使用されなくなったようにスキルの低い労働者は代替される http://d.hatena.ne.jp/travelbookcafe/20130220/1361312547 良書悪書 機械との競争 池尾 和人(@kazikeo) http://agora-web.jp/archives/1404263.html 機械との競争: 技術革新による失業の第3波を人類は乗り越えられるか http://jein.jp/jifs/discussion/scientific-topics/1075-topic37.html 『機械との競争』テクノロジー失業の時代が迫っている http://honz.jp/22073 マシンが同僚になる時代に備えるために――『機械との競争』 http://blogs.itmedia.co.jp/akihito/2013/02/post-ef27.html
0投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 テクノロジーが雇用と経済に与える影響 第2章 チェス盤の残り半分にさしかかった技術と人間 第3章 創造的破壊ー加速するテクノロジー、消えてゆく仕事 第4章 では、どうすればいいか 第5章 結論ーデジタルフロンティア
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーの進歩が「速すぎた」ため、雇用が奪われているという視点は面白い。が、そもそもたいていのテクノロジーは機械による労働の置き換えが目的なのに、それに奪われたという表現は少し引っかかる。 それはともかく、今後の展望として人と機械との協調によりイノベーションを生み出し、新事業の起ち上げを進めていくべきだとの主張はイマイチ。著者によれば、教育の拡充(学校は宿題をする場所にするという発想はかなりいいと思う)により将来の起業家を量産すべきらしいが、現状のベンチャーの成功率を見ると、その未来はとても楽観視できるものでは無さそうだが。
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ日経ビジネスのWebサイトでこの本の冒頭部分が紹介されており、非常に興味深かったので購入して読んでみました。 短くて1日で読み終えられる本ですが、内容にはいろいろと考えさせられるところがあり、いい本だったと思います。 コンピュータの発達が想像以上であり、従来は人間でないとできないと思われていたような高度の分析、判断、コミュニケーションまでこなせるようになってきており、多くの雇用が機械に置き換わってしまった結果、失業が増えているというのは、実際その通りだと思います。 それを克服する方策は、コンピュータやネットワークを使って自らのアイデアで改善・改革を行えるスキルを身につけた人を増やし、労働のミスマッチをなくすこと、そういう教育システムや労働市場の流動性が極めて重要になってくるという解決策も、まさにその通りでしょう。 自分自身のこれからのスキルアップや、子供たちへのアドバイスを行う上で、必ず念頭に置いておく必要があると思いました。
1投稿日: 2013.02.11
