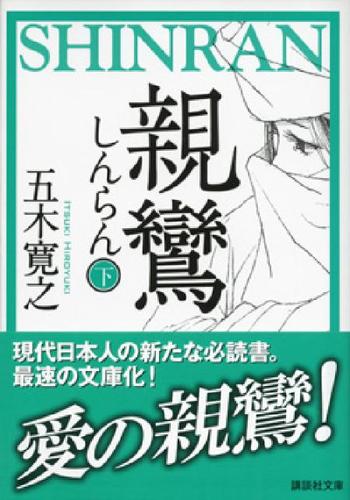
総合評価
(88件)| 18 | ||
| 39 | ||
| 17 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞を読み始めて、東本願寺の朝のお勤めに参加。さすがに比叡山で音覚法印に読経と声明を修業しただけはある美しい読経だった。おまけに渉成園で朝ごはんをいただく。真宗が日本の歴史に、特に武士の時代に果たす役割は大きかったんだろうなぁと思い至った。
15投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の決して平坦ではない修行を通じての生き様と、法然上人と易行念仏に行きつく過程が、常に迫力を持って描かれていて、とてもリアルに飽きることなく読み進めることができた。弥七がかっこよく、ファンになってしまった笑
1投稿日: 2025.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2010/7/10) 五木親鸞の下巻、上巻からちょっと間をおいて、ようやく読んだ。相変わらず一気に読める。 法然の説く念仏教の意味をついに理解して弟子となり、かねてから愛する女性と再会し妻とする。いわゆる破戒。 世俗にもまれながら、本当の念仏教を極め、広めてていく親鸞、、、ではなく、範宴、棹空、善信、親鸞!あら棚成長段階を迎えるごとに名を変える。 仏教でもキリスト教でも、元の教えはシンプルなはず。釈尊(仏陀)もイエスキリストも民衆とともにあり、教えをたれていたはず。それがいつしか階層化する。修行したものだけが教えを理解できるような形にして、民衆を下におき、僧侶が、牧師が、神父がなんらか権限を持つ。政治に係わる。 何で、虎の威を借る狐かな担ってしまうのだろう、人間って。 人の上にたちたがるんだろ。 親鸞はそれに真っ向から戦った。 無論法然もそうだった。民衆に念仏だけでいいと教えながら、法然自身は戒律を敗れなかった。叡山にとらわれていた。 親鸞はそうではなかった。妻帯し、肉を食い、世俗にまみれる。そして、どんな善人にも悪がある、だからみな南無阿弥陀仏と唱えることで極楽にいけると説く。 地に足のついた宗教家だ。 親鸞と法然は互いを信じあっていたというのがいい。その上で、法然の教えを自ら体現し伝える親鸞。 かくありたい! いま一度吉川英治親鸞を読むべきだろうと思う。
3投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ法然の弟子になり、綽空、善信となり、自分の道を進むことを決心した。 念仏道は、既存の仏教の教えを選択して、念仏を唱えるだけで救われると言う危うい教え。 既得権益の集団から狙われることに。黒面法師の最後が意外にあっけなかった。 豪胆な法然と親鸞にびっくり。
5投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞となるまでの幼年から青年期までの葛藤が人間らしく、歴史上の人物にとても興味を持つきっかけになりました
0投稿日: 2024.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ後の親鸞が範宴と名乗り、六角堂に百日参籠することを決めるところから始まる。 そして、流罪によって越後へ旅立つ。この時親鸞と自称する。とこの本はそこまでのお話。 (範宴29歳〜親鸞34、5歳) 絶体絶命のピンチに見舞われても、親鸞は周りの人々に守られ、窮地を脱す。 どんなオーラを纏った人物だったのかなと実際に見てみたい気持ちが湧いた。
0投稿日: 2024.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は、他人の悲しみの上にしか 自分の幸せをおくことができないのか 信じると言うのは、物事ではなく、人です。 この二言が印象的であった。
1投稿日: 2022.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞として改名して越後に流罪として流されるまでが描かれている青春篇。面白くて一気に読んでしまいました。
1投稿日: 2021.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之の小説は面白いのであるが、長編は間延びがある。わずか2巻なのに随分かかってしまった。この次の編も読もうと思うが、全部読み終わるのはいつになるやら…
2投稿日: 2021.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞は名前を変えていく。生まれ変わって名前を変えていく。最後は新潟に出発するまでの話。親鸞に名前を変えるまで。法勝寺の八角九重塔って本当にあったんだな。見てみたかった。法然も親鸞も叡山で修行して今は叡山にも飾られていて、時の流れを感じるとともに叡山の人材輩出振りに改めて関心する。激動篇も楽しみ。
1投稿日: 2020.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「他力の念仏。情けない愚か者には、二度、三度と呼びかけられるのが仏の慈悲。呼ばれるたびに愚直に答える者が、どうして救われないことがあろうか。」「われらは末世の凡夫である。罪悪の軽重をとわず、煩悩の大小によらず、ただ仏の本願による念仏によってのみ救われるのだ。」あみ、だんぶ、なも、あみ、だんぶ、なも。
1投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻に続けての一気読みでした。 どこまでが史実に則しているのかはわかりません。 でも、読み終えてそこに間違いなく親鸞が生きた時代を垣間見ることが出来た。 続編も楽しみに読み進めていきたい。 説明 内容紹介 親鸞は比叡山での命がけの修行にも悟りを得られず、六角堂へ百日参籠を決意する。そこで待っていたのは美しい謎の女人、紫野との出会いだった。彼が全てを捨て山をおりる決意をした頃、都には陰謀と弾圧の嵐が吹き荒れていた。そして親鸞の命を狙う黒面法師。法然とともに流罪となった彼は越後へ旅立つ。 内容(「BOOK」データベースより) 親鸞は比叡山での命がけの修行にも悟りを得られず、六角堂へ百日参篭を決意する。そこで待っていたのは美しい謎の女人、紫野との出会いだった。彼が全てを捨て山をおりる決意をした頃、都には陰謀と弾圧の嵐が吹き荒れていた。そして親鸞の命を狙う黒面法師。法然とともに流罪となった彼は越後へ旅立つ。 著者について 五木 寛之 1932年福岡県生まれ。朝鮮半島より引き揚げたのち、早稲田大学露文科に学ぶ。PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て、66年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、76年『青春の門』(筑豊篇ほか)で吉川英治文学賞を受賞。81年より一時休筆して京都の龍谷大学に学んだが、のち文壇に復帰。2002年にはそれまでの執筆活動に対して菊池寛賞を、英語版『TARIKI』が2002年度ブック・オブ・ザ・イヤースピリチュアル部門を、04年には仏教伝道文化賞を、09年にはNHK放送文化賞を受賞する。2010年に刊行された本書は第64回毎日出版文化賞を受賞し、ベストセラーとなった。代表作に『戒厳令の夜』、『風の王国』、『風に吹かれて』、『百寺巡礼』(日本版 全十巻)など。小説のほか、音楽、美術、歴史、仏教など多岐にわたる活動が注目されている。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 五木/寛之 1932年福岡県生まれ。朝鮮半島より引き揚げたのち、早稲田大学露文科に学ぶ。PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て、’66年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、’67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、’76年『青春の門』(筑豊篇ほか)で吉川英治文学賞を受賞。’81年より一時休筆して京都の龍谷大学に学んだが、のち文壇に復帰。2002年にはそれまでの執筆活動に対して菊池寛賞を、英語版『TARIKI』が2002年度ブック・オブ・ザ・イヤースピリチュアル部門を、’04年には仏教伝道文化賞を、’09年にはNHK放送文化賞を受賞する。2010年に刊行された「親鸞」は第64回毎日出版文化賞を受賞し、ベストセラーとなった。小説のほか、音楽、美術、歴史、仏教など多岐にわたる活動が注目されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
5投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019年12月8日読了。 ●P95 サヨから綽空への論 ●P110 真実の教えというのは常に危ういものだ。 新しい考えも、そうだ。 その危うさを避けては、真実の新しい道は開けない。 しかし、危うさをもたぬ安全な考えにあまんずるのなら 法然上人も比叡山を降りられなかっただろう。 そして、法然上人の真の新しさとは、古い仏典をこえて 十悪五逆の悪人でさえも救われる、と初めて堂々と説か れたことだ。 〜 念仏ひとつによって悪人なお往生す、とおっしゃったか たは天竺にも、唐にも、おられない。 法然上人は、唐の善導というかたを心の師と呼ばれてい る。 ●釈尊にはじまり、道綽、善導、源信と続く浄土教の教説 の徹底的な検証の中から導き出された究極の正論であ る。その確信によって選択された唯一の行が易行念仏 だ。 ●人は他の人の悲しみの上にしか、自分の幸せを築くこと ができないのだろうか。この自分もまた、無明の世に生 きる悪人なのだろうか、と恵信は思った。 ●念仏門をひらいた法然上人から選択本願寺念仏集の書写 を許されたということは釈尊にはじまり、世親、 どう鸞、道綽、善導、とつづく浄土の教えの弟子の 一人としてはっきりと認められたことになる。 ●わたしが求めているのは、よく死ぬことではない。 思い闇を抱えて、それでもなお歓びにあふれる生き方 だ。 ●仮借… ●帰依…
1投稿日: 2019.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ貴族から庶民のための宗教に移り変わり始めている時の話。 庶民にもわかりやすく、念仏を唱えればどんな人も救われる。そういう教えなのに、いつの間にか、何をしても念仏さえ唱えればなんとかなるという間違った教えが広まることに。 新しい事は、いつの時代もなかなか権力のある人には受け入れられず、いつの時代も苦労しますね。
2投稿日: 2019.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ忠範、範宴、綽空、善信と親鸞の名前は変わってきた。下巻最後にようやく親鸞が出てきた。越後に旅立つ巻末は情景が目に浮かぶ、作者の表現の素晴らしさが垣間見えた。この先も楽しみである。
1投稿日: 2019.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ詳細は、あとりえ「パ・そ・ぼ」の本棚とノート もご覧ください。 → http://pasobo2010.blog.fc2.com/blog-entry-1777.html 五木 寛之の 親鸞(上) を読んだので、早く続きを読みたい。 上に引き続き 下も読破! これまで全く興味のなかった親鸞のこと。 もっと知りたくなりました! 本の続きは、親鸞 激動篇(上) (講談社文庫) 2013/7/11 予約 7/15 借りる。 7/18 読み始める。9/6 読み終わる。 内容と著者は 内容 : 親鸞は比叡山での命がけの修行にも悟りを得られず、六角堂へ百日参籠を決意する。 そこで待っていたのは美しい謎の女人、紫野との出会いだった。 彼が全てを捨て山をおりる決意をした頃、都には陰謀と弾圧の嵐が吹き荒れていた。 そして親鸞の命を狙う黒面法師。法然とともに流罪となった彼は越後へ旅立つ。 著者 : 五木 寛之
1投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ越後に流罪となり、親鸞の名乗るまでの下巻。叡山から吉水に下り、法然上人に学ぶ中、政治的な弾圧を受けるなか、師の教えを信じ信念を突き通す真摯な姿勢は仏門に限らず、矜持を持つ生き方として畏敬と憧れを感じる。恵信との結婚や鹿野を巻き込んだ同門の遵西、そして黒面法師との対決など見どころも多く、遵西の処刑、親鸞の旅立ちの場面が最大の見せ場ですね。 方苦しくなくとても読みやすい文体と感じました。 続編も読みたいと思います。
1投稿日: 2018.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半にも増して仏教感や精神論も深くなって来たが、決して難しくもなく、次々といろんなことが起こりエンターテイメント性が強くなって歴史小説と思えないほど。 ドラマにしてほしいくらい。 最後にやっと親鸞誕生で、これまでの諸々の素地があって親鸞は生まれたのか、、と納得。 まだまだ続きが楽しみです。
1投稿日: 2018.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之の親鸞(下)読了。求道に至るエピソードを交えながら、世の流れに翻弄される親鸞の姿を読み進める。次は激動編。完結まで読み終えたら梅原著に手を出そうか悩み中。純粋な思想として、日本の仏教の面白みを味わってみたい
1投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログぬおおお、親鸞誕生!ドラマチック、ドラマチックです。その分、史実通りじゃない部分もあるのかもしれないけど、ドラマチックです。激動編が楽しみ。
1投稿日: 2018.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞が越後に流されるまで。上下巻を通じ、テンポ良くストーリーが展開していき楽しめた。ただ浄土真宗の開祖が主人公なので、もっと荘厳な哲学風のものを想像していたが、悪との闘い、死地からの脱出と、かなりエンターテイメント色が強かった。吉川英次の作品も読んで比べてみたい。2017.12.21
1投稿日: 2017.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞は比叡山で修行しても悟りを得られません。 山を下りた親鸞は、専修念仏の法然のもとへ。 法然のところで念仏の道に入りますが、その頃都には陰謀と弾圧の嵐が吹き荒れていました。 親鸞の命を狙う黒面法師、阻止すべく活躍する仲間たち。 念仏に対する弾圧は、ついに親鸞を法然とともに流罪としてしまいます。 親鸞は妻とともに、妻の故郷である越後へ旅立ちます。 史実とフィクションが織り交ざり、どんどん読み進んでいきます。
1投稿日: 2017.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ怒濤の展開の下巻。凝縮されすぎていて感想を書くのが難しいくらいおもしろい。当時の宗教観や死生観は、心の支えでありながら、自らを律する鎖でもあったのだろうと思う。現代人には少し欠けてる部分なのかも。 めちゃくちゃするやつももそれなりに出てくるのだが、皆真っ直ぐなので嫌いになれない。
1投稿日: 2016.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ範宴が法然上人のいる吉水に通い始めてから、親鸞となって吉水を去るまで。 この話の中でこの人はまた何回も名前が変わった。 範宴から法然の弟子となった綽空 この名前の時、恵信(紫乃)と結婚。 選択本願念仏集の書写を終えて善信 信州へ流罪となり、親鸞へ。 ようやく知っとる名前になった!!!
1投稿日: 2016.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞、いや綽空・善信の物語。 時空を超えて人生に苦悩する若者は、いつの世も同じ。 教科書で目にする坊さんも昔は若者。 親しみをもちました。 とりあえず念仏を唱えてみたくなります。 あみ、だんぶ、なも。
1投稿日: 2016.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ範宴は比叡山を降り、綽空と改名し、さらに法然から秘伝書である選択集を授かったときに、善信と改名し、越後に遠流の刑となったときに、親鸞と改名した。 恋あり、チャンバラあり、政争ありの俗世間にまみれた僧の話。 仏道のみならず文化全体の最高学府としての叡山
1投稿日: 2016.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ浄土宗の開祖が法然で、法然の弟子の親鸞は浄土真宗の開祖である。違いは浄土宗を継承発展させたのが浄土真宗なのだとか、浄土真宗も後年には東本願寺・西本願寺・大谷派と分派する。同じ念仏仏教の雄、日蓮宗の開祖、日蓮について気になるので調べてみると、日蓮が親鸞より49歳年下で同じ時代を生きていた。ネットで調べるとお互い知ってはいたがあったことはないらいしい、いろいろと興味は尽きない。
1投稿日: 2016.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰もが抱える心の闇を、ほんの少しでも照らす光明を信じて生きて行きたい。 マジでそう思わせてくれる。
1投稿日: 2015.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どんな内容だか気になってはいたが、意外とドンパチものもあって、エンタメ的に仕上がってはいる。 深くしようとするといくらでも深くできそうな気はする題材のため、これはこれでいいかも。 本書は親鸞になって終わる。 この話にはやはり続きがあるとのこと。その後、どう浄土真宗を開いたかまでやはり読まないといけないか。
1投稿日: 2015.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻に続いて下巻も変わらずテンポよくワクワクしながら読んだ。そして気付いたのは私自身煩悩まみれであるという事(笑) でも親鸞自身もそんな感じで最高の伴侶を得たりしてて人間味を感じた。そこから見えてくるものだってあると思う。何も無駄じゃないんだなと勝手な解釈(笑)
1投稿日: 2015.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ続きだが、彼が求めてきたものが少しずつ形になる。 やはり普通というよりはどこか異端児なところがある。 かつ一つのことを貫き通す。 そういう人が記憶に残り、また人々から愛されていくのだろう。
1投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ信仰の自由など到底考えられず、国家による介入が当たり前だった時代、いわゆる鎌倉新仏教が立ち上がるに至る、激動の物語。法然とのかかわりを中心に綴られる本下巻。内部での人間模様も魅力的に描かれていて、単なる仏教話ではない、小説としての面白さも担保されている。やっと”親鸞”の名前に落ち着いたところで、いったん物語は完結。でも既に続きも刊行されているようで、そちらも楽しんでいきたいと思います。
1投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ比叡山を飛び出し、法然のもとへと走った範宴は、綽空と名を改めることになります。彼は、弁才とともに病人の治療に当たっていたときの彼に手巾を渡してくれた紫野という女性に惹かれていきます。 しかし、やがて紫野は病を得て故郷へと帰ってしまい、彼女の代わりに紫野の妹の鹿野という女性が彼のもとへとやってきます。範宴は、鹿野が彼に寄せる想いに気づきながらも、紫野への思慕を断ち切ることはできません。そんな範宴の態度に傷つけられた鹿野は、彼の兄弟子である安楽坊遵西という僧のもとへと走ることになります。 範宴は、やがて法然の厚い信頼を得るようになりますが、兄弟弟子の間には、そんな範宴に対する妬みがくすぶっていきます。そんなある日、範宴は遵西から、一つの提案を持ちかけられます。彼は、法然の教えを広く世の中に伝えるため、事件を引き起こして、法然の態度をもはや旧仏教徒の対決が避けられないところに追い込もうと画策していたのです。彼は、かつて「六波羅王子」と呼ばれ、現在は「黒面法師」と名乗っている伏見平四郎と手を組み、寺に火を放ち禁裏に攻め入る作戦を立てます。 綽空は、遵西と行動を共にすることはできないと彼の誘いを退けますが、遵西は鹿野を人質にとって、綽空に決断を迫ります。彼は紫野とともに鹿野のもとへ向かいながら、黒面法師のような五逆十悪の者たちに呼びかけるためには、法然の教えをいっそう突き詰めていくことによるほかないと考えます。 後巻もドラマティックな展開を孕みつつ、法然の教えから親鸞が何を受け止め、それをどのように突き詰めていったのかが解き明かされています。「生」についての教えに偏り、「浄土」の持つ意義が薄くなっているのではないかという疑問もありますが、歴史小説という枠組みの中で親鸞という人物を見事に造形化した作品だと思います。
1投稿日: 2014.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ山陰中央新報で読む。六波羅童の頭目を悪の権化に据え、そして河原坊浄寛に法螺坊弁才、さらにツブテの弥七を師として仲間として、それどころか信仰の羅針役として据えている。それによって小説としての魅力を与えられるけれど、所詮はすべて架空の人物だろう。彼らとの関わりが物語の柱だと、親鸞という著名な歴史上の人物を題材にした単なる娯楽小説になってしまう。
1投稿日: 2014.05.05親鸞の 苦悩と名前の変遷
親鸞の前の名前が 何回か変わる。最後が親鸞。変わるたびに生まれ変わる。 恵信と 妹 との 三角関係の苦悩などは、夏目漱石っぽくて良い。 ただ、悪者の登場と 仲直りが ドラゴンボールの最後の方のなんかなー感 漂い、題材の良さと 後半のこの部分が 吉川英治の武蔵とかぶる。
0投稿日: 2014.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の持つ善と悪について深く考えさせられた。親鸞でさえも善だけを持った人間でなかったことで安心させられた気もする。たぶん完璧な人間が教えを説いてもそれは人の心に響かないのではないかと思う。 深く、重いお話だった。
1投稿日: 2014.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ浄土真宗の開祖,親鸞の物語. 親鸞は,自分に正直に生きた,自分に正直に生きることを大事にした.そう感じる.憧れだったお山(比叡山)での厳しい修行.しかし,旧来の修行は,彼にとっての真なることをもたらさなかった.市井に交わり,師となる法然に出会い,彼は成長していく.自分は,河原の礫(つぶて)に過ぎないものであること根っ子としつつ,信じる力を信じ,師を超えることが知命と考えるに至り,自分の道を拓いてゆく.(激動編につづく)
1投稿日: 2014.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞自身が なかなか 悟りを開くことができないことを 自分の業が深いと思っている。 また、女性に対する想いが強く 煩悩を断ち切ることが できないことも、親鸞をなやませる。 『放埒の血』になやむ。 じつに 人間臭い のである。 仏に つかえる身 であり、仏に 解脱することが 修業であるが 苦行を通じてしか生まれない。 一種の狂信的な行為が 必要なんだね。 基本もしくは 原点で素直に悩む。 『仏とは?』 この問いかけが 親鸞の原動力となる。 範宴は、釈尊に出会うのではなく 聖徳太子に 出会うことが 面白いな。 鹿野に対する 態度に対して サヨが手酷く しかる ところは、 さすが オンナの目が したたかでもある。 お経とは 声を出して 読むもので 良い声,悪い声というものがあるものだ。 安楽房遵西は、イケメンであり、声がいい。 詠い方は独特で女子を引きつける。 今様、和讃。 ワクをはみ出て はじめて 新しいものの創造が可能である。 親鸞は 自分が満足しなかった故に、 自分を窮地に追い込むことで 切り開いていく。 先人である 法然が すごいんだね。 忠範 範宴 善心 そして 親鸞への 4度名前がかわる。 紫野が 労咳 となり、信心して なおし 恵信 となる。 そして,再び会うことで 範宴は こころの安寧をえる。 法然上人から 善心は 若くして 信頼を得る。 そして、後鳥羽上皇の怒りにより 法然上人 親鸞とも流刑に。 法然上人は 土佐へ 親鸞は 恵信の故郷 越後に 流刑になる。 親鸞の物語も こうやって 小説になると親しみやすいものだ。 親鸞の人となりが 人間臭いが それでも 前に進もうとする 決意が 尊いのだろう。
1投稿日: 2014.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後に「完」とあるものの、その直前ようやく「親鸞」を名乗ることになり越後に着いたところで終わるという、序章がやっと終わっただけという感じ。浄土真宗はまだ気配すらありません。引き続き「激動編」が楽しみ。まだ新聞連載中の「完結編」も早く本当に完結してくれたらなと思います。 ともあれ、真宗の「一念義」や「悪人正機」でこれまで疑問に思っていたところが実にわかりやすく説明されていて、非常に勉強になりました。
1投稿日: 2013.11.23面白かったけどちょっと..
上巻の頃は親鸞がどう成長していくだろうという期待感もありわくわくと読ましていただきました。 下巻になるとなんだか、下手な時代劇のチャンバラみたいな展開がが入ってくるのはどうなんでしょうか。 もっと念仏を中心とした精神的な世界を書いてもらった方が私には楽しめたかも。
2投稿日: 2013.10.26五木文学の最高傑作
「青春の門」からの五木寛之ファンですが、「親鸞」は五木文学の最高傑作ではないでしょうか。 まるで親鸞が現代に生きているような面白いストーリーで、とても読みやすい。それでいて、奥の深い内容で、読みごたえがあります。 宗教にまったく興味のない方にもおすすめです。
1投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ“悪人でさえ念仏を唱えれば成仏できる”と言う教えとなれば、悪の限りを尽くしてもいいと曲解・誤解は必至。親鸞が犬麻呂に名前を呼びかけ答える場面で、何となく自力本願・他力本願の事は分かったような気がしますが、むむむ、やっぱり本質は掴めない。それとは別に、「範宴」→「綽空」→「善信」→「親鸞」へと名前を変えていく過程は、それぞれ納得の出来事があって面白かったです。
1投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の幼少から越後への流刑までの物語として、歴史上の人物を面白く膨らませ、小説らしく楽しく読める。また、親鸞の人生を知る上でも貴重な小説になっている。印象深いのは、法然が親鸞に撰択本願念仏集の書写を許したとき、親鸞がそれを釈尊の最後の言葉「わが教えをよりどころとして、おのれの道を往け」と解して、自立し旅立つところ。「往生するのは善人か、悪人か」と問われて、「善人・悪人の区別をつけない。みな、深い闇を抱いている」と応えているところは、親鸞の言葉でもあり、著者の言葉でもあり、なるほどと思う。面白かったが、この本を読む人たちには、親鸞の他力にすがりたいという想いがあると思う。それに応えるインパクトは不足している気がする。
1投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログお堅い本かと思い覚悟を決めて手に取ったが、読み始めると一気に最後まで読了。法然上人・親鸞上人の強さに感銘。こういった生き方に憧れます。
1投稿日: 2013.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞が越後に流されるまでを描いている。 あくまで小説だが、親鸞“上人”でなく人間・親鸞が描かれており面白い。 ここで描かれる親鸞は煩悩をもつ凡夫であり、聖人ではない。人間として悩み、葛藤し、そしてようやく念仏という道にたどりつく。 激動編で今後の親鸞がどのように描かれるか楽しみ。
1投稿日: 2013.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「親鸞」が9才で比叡山に入り20年に及ぶ修業を積むが限界を感じて下山、「法然」の門下に入り、朝廷による「専修念仏」の停止から越後へ流刑となるところまでを描く。 司馬遼太郎の「空海の風景」的な小説や伝記かと思いきや、エンターテイメント小説。伝記を想像して読むとがっかりするが、エンタメとすれば100万部を超えるというが分かる。 「親鸞」としての布教や7子を設けた話はない青春記。
1投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞が恵信尼と出会ったり、法然上人に弟子入りして念仏に目覚めたりする。聖典とされる選択本願念仏集について、登場人物に語らせて説明してくれるので勉強になる。 親鸞は「妻帯肉食」を公にした人物だが、やはり宗教的には若干のタブー感がある。これを小説にするのは難しい気がするが、本作は、その辺サラッと書いているので、読み手にはあまり負担がかからない。 五木寛之って、相当色気たっぷりな人だけど、妙にダンディな抑制感が前頭葉の発達ぶりを感じさせる。こんなオジサンになりたいものだ。 読んで初めて知ったのだが、実は本作品で扱われているのは越後配流まで。そのあとは、激動編やら完結篇と続くようです。むう。
1投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ名前しか知らなかった親鸞さんが、すごく身近な存在に感じられて、仏教に関する興味がわいてきた。 人生の中で本当に心から尊敬、信頼できる人に出会うとは、なんと幸せなことか。 親鸞が師法然に出会ってからの目覚まし変化。 信じることのすごさがよくわかる。 まだまだ続くようなので、早く文庫化になってほしい。
3投稿日: 2013.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「他力の計らいに身をまかせるお覚悟が定まっていた」「その念仏は釈尊の心であり、無限無量の大宇宙からさしてくる無碍の光」という箇所が気に入った。他力、釈尊の心、宇宙からの光...何と呼ぼうと、その力に抵抗せずに、無心になって寄り添う、信じきって安心して完全に身を任せるという事 ... 不思議と私が読んできた本が繋がっていき... それも、宇宙の力の計らいか、と思ったり。 物語としても、とても面白かった。共感出来る箇所もたくさんある。途中、血なまぐさい箇所もあるが、最後まで読んだら、とても穏やかな気持ちになった。
1投稿日: 2013.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教的な雰囲気でなく、私の好きな歴史的背景がよくわかるようにできているので、とてもおもしろい。 親鸞のような人物も、若い頃は苦悩の日々だったのですね。
1投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教を極めんと修行し続ける主人公だが、知識と難行に限界を感じ、全てを捨て始める。その先に到達する思想とは何かを追い求める後編
1投稿日: 2013.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
親鸞が法然上人とはわかれて、流刑にされるまでの話、てっきり、そのあとに浄土真宗を開くところまで描かれているのかと思いきや残念。 また、お坊さんの話の割に、女性が多く登場し、色欲とはなかなかに強いものであることを再確認した。 全体としてはエンターテイメント色が強くもう少し史実に近い内容が読みたかったようには思う。
1投稿日: 2013.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「親鸞」という人物が形成されるまでのプロセスの物語。 徹底的に自分という人間の内面性と向き合い自覚し、仏教のパラダイム転換に至ったお話。 悩み続けながらも前に進み続けること。 今の時代こそ大切な姿勢の気がします。
1投稿日: 2013.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ法然との師弟関係を見ていると、自分の先生を思い出してほろりときます。 優しいけれど、心には厳しいものをもっている法然上人に惹かれました。 「信じる」ということがどれほどお互いの心を支えていることか。 二人の会話はさほど多くない印象ですが、どれも味わい深く、悩み苦しまれている法然上人の心が感じられます。 法然も親鸞も、真実を探しあてようとし、考え続けることで孤独になっていくよう。 それでも自分自身の信じたものを貫き通す姿はカッコいい。
1投稿日: 2012.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 宗教ではなんでもそうだけど、一人歩きした教えは時に危険。解釈、見たいものしか見ない。 それでもそれなりに思いがあってのことだったり、実直に向き合う強情さと、強情だからこそ向き合う大変さだったりと、面倒な性格はどうしようもなかったりと、げに人間とは。。
1投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞と名乗るようになるまでの話ですが、このあとの親鸞はどういう人生を歩んでいったのか、興味があります。 自分の信じるところを、迷いながらも少しずつすすむ。偉い偉いお坊さん?という認識しかなかったので、意外な感じと親近感を覚えました。
1投稿日: 2012.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学だか高校だかの歴史の授業のときに、ちらっと出てきた人物『親鸞』。 本書を読むことで、ただただ暗記をした歴史上の人の名前、でしかなかったモノが、 その時代を確かに生きた人物として私の中に鮮やかに刻まれることになった。
1投稿日: 2012.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「善人なおもて往生を遂ぐ、況や悪人をや」以外に何も知らなかったが、平清盛、後白河法皇時代から、比叡山、法然との関係、恵信との関係などまずは時代背景がよくわかったことでかなりすっきり。加えて、念仏を選択(せんぢゃく)する過程がなんとなく腹におちたような気がします。僧として相応しくないのではないかという煩悩について悩む先に易行念仏に到達した経緯が、大胆に描写されている。親鸞についての入門として良書かと思います。
1投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いや~激動。 すごいです、まじ。 後半がやばい。 範宴・綽空から善信と名前が変わってきたわけですが 道々のものと一緒に南無阿弥陀仏を唱えるとこが こー、なんというか。 正直巷のお坊さんに読め!と言いたい。 いや、お坊さんだけでなく 宗教に全く関心がないわたくしも読んでるわけで。 一番心に残ったのは 「選択というのは2つの中からどちらかを選び出すことではない。それは片方を捨て、片方に身命をかけること」 ん~深い。 そうやって人間生きてるんだなぁ、と。ふと。
1投稿日: 2012.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞、越後に配流になるまで。 なんかわかっていたような、わかっていなかったような、念仏とは、とか他力とは、ということも考えつつ。話としてはフィクションも多いんだろうけど、そもそも法然とか親鸞とかよく知らんかった。
1投稿日: 2012.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名を見るとお堅いイメージですが、全く予想外でした。厳しい修行、それに対する苦悩、色恋、人との出会い。いろんな出来事を経て、『親鸞』 誕生。読み応えありました。こういう本を読むと歴史に興味がわいてきますね。続編もあるということなのでぜひ読んでみようと思います。
1投稿日: 2012.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の教科書ではほとんど記憶に残らないくらいにしか出てきていなかった親鸞の姿が、活き活きと描写されています。親鸞になってからのことも知りたくなりました。
1投稿日: 2012.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の教科書では念仏を唱えると誰でも極楽浄土に行けるという法然、その弟子の親鸞ってわずか一頁にもならないくらいだったように覚えてる。比叡山での修行では悟りは得られないと町に降りて俗社会に暮らし、そこで法然との出会い。ブッダが苦行では悟れないと、苦行をやめていく様に似ている。面白く、法然、親鸞、念仏について知れた。なかなか読み応えがあった。
1投稿日: 2012.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局冒険活劇は続くのですね。読後感は爽やかです。上下巻合わせて三点でしょうか。ただし、続編を読む気にはなりませんでした。もう少しかためが読みたいと思ったので。
1投稿日: 2012.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞連載時に最初のほうは読みのがしたので、やっと全部読めた。弱さや欠点を持った人間としての親鸞を生き生きと描いていて、一気に読ませる。「激動編」の文庫化が待ち遠しい。
1投稿日: 2012.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログスピード感がある。仏教界のこともよく描けている。 しかし,悪役との対峙,恵信尼とのラブロマンスのあたりは,小説につきもののパターンに収まってしまっている感を拭えなかった。そこそこ面白いが,没頭はできない。
1投稿日: 2012.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ念仏の解釈の違いや、比叡山との確執などめまぐるしく動く情勢の中で、煩悩に左右されながらも次第にぶれなくなっていく親鸞。ひと時の紫野との幸せや、黒面法師の思惑、後鳥羽上皇の狂乱など見せ場が次から次へとやってくる。ラスト、越後に着く頃の親鸞の心構えは全てを受け入れていて、既に生き仏のようだが話はまだ続く。仏教の話だからと身構えていた自分はもういなくて、早く続きが読みたいと気が高ぶっている。続編はまだハードしか出てないけど、買うしかない。
1投稿日: 2012.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻から引き続きのドラマ仕立てで、大変おもしろかった。 その分、少し軽く浅いが、親鸞という、現代の一般庶民にはあまり馴染みのない宗教家を、ここまで親しみを感じさせ、興味を抱かせる手法は、まさに親鸞的(な気がする)。 下巻でもまだ序章。続きが気になります。
1投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年70冊目。(再読) やはり面白い。 激動編で親鸞がどのような行動を起こすか楽しみ。 ==================== 2012年29冊目。(2012年3月25日) 高貴な人たちを対象とする比叡山。 卑しい身分の大衆に「念仏だけで救われる」とする法然。 そして高貴な人も卑しい身分の人も心に闇を抱える「凡夫」であるとする親鸞。 トレンドの移り変わりとそれに伴う弾圧の様子が小説として描かれとても馴染みやすい。 続篇である激動篇も早く読んでみたいです。
1投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ和丸和尚に聞かされていた、親鸞上人のことばを思い出しながら読んだ。 親鸞の基本は、「すべての人に」。釈迦も「すべての人に」だったという。 仏を信じることと、仏を利用することは違うのだ。改めて「信じる」とはどういうことなのだろうかと思った。
1投稿日: 2012.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
叡山から範宴が六角堂での百日参籠を行い、夢うつつのところで吉水へ行くことを救世観音からの声を聞いて決意する。 法然の教えを聞き、その教えに傾倒して行く。とうとう法然の弟子入りを果たし、名前を綽空、善信、親鸞と替え、法然の説く教えを自分で理解をして、広めようとする。ただその頃の今日の権力者からは念仏教は叡山を含む他の仏教からも危険な宗教としてとうとう禁止弾圧を受けてしまう。これは信長の頃の浄土真宗の弾圧にもやはり似ているが、念仏にて浄土に行けるという思想はともすると叡山とともに政治の道具となりかねない。しかしその創始者のときは本当に純粋な思いからの宗教であった。これは誇って良いことだと思う。 始まりは素直な心からきた宗教であり、人として素晴らしい行き方だとお思いますね。
1投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログそういえば歴史で習ったけど…くらいの感覚だったが、ストーリーが面白くて一気に引き込まれた。何度も目頭が熱くなったし、仏教に関しても理解が深まった。でも、ドキドキワクワクする感じで読みすすめられたのは幼少期、上巻の方だったなぁ。
1投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ重いテーマ・人物を扱ってるはずが楽しく読めてしまいます。 劇画的。アニメ化したら良いのではないか。 史実に忠実な本を期待している方は別の本を読んだほうが良いでしょう。
2投稿日: 2012.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログえええまだ浄土真宗開かないの!?に集約されているのではないか。数々の名前の変遷を経て、ようやく親鸞と名乗るところまで。いや、物足りないが上手い戦略とも言える…。読みやすく楽しいのでついつい続きが気になるからだ。 軽い歴史小説にはありがちなように、やはり歴史的な出来事との相互関係の描写が浅い。歴史小説よりも時代小説よりになってしまっている気がする。
1投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ平安末期から鎌倉初めにかけての混乱した京の様子が伝わる。大河ドラマ「平清盛」の画像が汚いと、どこかの知事が批判して話題になったが、もう少し後の時代とはいえ、当時の世相からすればそんなものだったのだろう。 上巻の親鸞の少年時代(忠範)が出会う河原者たちの猥雑でかつ活力に満ちた描写がいい。親鸞を名乗るまでの青年期までのお話だが、青春活劇としての楽しませ方は流石だと思った。宗教者としての足跡を期待すると戸惑うかもしれない。史実とどうなのかは別にして、小説としては十分に楽しめる。 続く「激動篇」にも期待。
1投稿日: 2012.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「仏様より呼びかけられてする返事だから、仏よりいただいた念仏、というのですね」 「そう思う」 綽空は自分で自分の言葉を確かめるように、二、三度うなずいた。 「それが他力の念仏だ。自力の念仏とは、仏たすけたまえ、とこちらから呼びかける念仏。これまで範宴のころ、比叡のお山までわたしがずっととなえておったのは、その自力の念仏であった。いまはちがう。よばれれば何度でも、はい、と返事をする。一度の呼びかけできっぱり信心がさだまる幸せ者は、いちどの念仏でよかろう。だが迷い多く、煩悩深き悪人のわれらは、呼ばれた声をすぐ忘れたり、とかく逆らったりしがちなものだ。そんな情けない愚か者には、二度、三度と呼びかけられるのが仏の慈悲。だから一度念仏しただけでも往生できる。まして、呼ばれるたびに何度でもはいと愚直に答える者が、どうして救われないことがあろうか。念仏は一度がよいか、それとも多く念仏するのがよいか、などと議論するのは、そもそもおかしいと私は思う。一念なお往生す、いわんや多念においてをや、と法然さまがおっしゃねのを聞いたことがあるのだよ」 法然の弟子になった直後の綽空のころは、一念と多念についてはこのように明確に答えていた親鸞であるが、「でも、悪人が救われるなら悪事はやり放題、というもの達には、なんと申しましょう」という問いには明確に答えることができない。 悪人正機説の当然出てくるこの問いに対して明確に答えるのは、「激動編」を待たねばならない。しかし、最終決着をつけるのは現在連載中の最終の巻きなのだろうと思う。 下巻では親鸞が法然の弟子になり、やがて法然と同時に京の都を追われるまでを描く。
3投稿日: 2012.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこれだけ馴染みの深い偉人なのに、その生涯や偉業に関して、恥ずかしながらあまりよくは知らなかった親鸞さん。この本はその半生までのお話。末法の世と言われた平安末期から鎌倉初期の描写はナマナマしく、その中で法然、親鸞らが広めた念仏というのがいかにすごいことだったのを初めて知りました。フィクションなので全てが史実通りではないでしょうが、念仏により仏教が為政者のものから万民のものになる過程はまさにパラダイムシフト。日本人の心の中の革命だったのかも…残りの半生を描いた続編が待ち遠しいです。
1投稿日: 2012.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ厳しい修行を重ねつつも、真の仏の姿に触れることのできない親鸞の苦悩が描かれ、あっという間に読み進められると思います。巻末が近づくに連れ、どんな結末になるのだろう、このまま終わってしまうのだろうかと不安になりましたが、続編があることを知ってほっとしました。年明けに続編が単行本で出版されましたが、また文庫になるまでしばらく待とうと思っています。
1投稿日: 2012.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
親鸞が親鸞となるまでの人間ドラマ、末法の世の混乱ぶり、その中で醸造されてゆく思想体系などが盛り込まれ、とても密度の濃い作品。しかしこの2冊ではもの足りなくなるのでやはり続きが楽しみ。
1投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログいやいや、面白いっつーの。 という上巻と同じ感想が書けるのはそれを上回ったからで、 なにしろ最後まで中だるみなく読まされてしまった。 下巻もやはりエンターテイメントとして 仏教の考えをひも解くわけですけど、 案外深いところまでえぐってきます。 この内容をこのテンションで描き切るのはすごいなあ。 富も、名声も、戦うための武器も持たず、 なんらかの姑息な悪事に手を染めずには生きられない 何百、何千という貧しい人々が、 一斉に腹の底から念仏を叫ぶ。 それは自らの罪の意識や死への不安だけでなく、 不当な体制や押し寄せる理不尽に対する抗議など、 いろんな思いをないまぜにして、地響きを起こして絶叫する。 その先頭にいるのが親鸞だ。 彼は巨大な悪意に迫られても一歩も引かずに 目を据え、地面を踏みしめてひたすらに念仏を唱え続ける。 そら格好良いわけです。 途中までは、こいつ能書きばっかりで結局なにもできないじゃん。 と思ってたんですが、まあ立派になったというかなんというか。 いや、何もできないのはできないんですけど。 念仏を唱えるっていうと お葬式のイメージが出てきてどうにも辛気くさい感じがするんですけど 仏教は当時もっと生活に根付いたものだったんですね。 それは医学であり、哲学であり、建築であり、 歌であり、娯楽であり、生きる術そのものだった。 念仏は、修行を積んだ高僧や お布施を納めることができる一部の貴族のためのものではなく、 罪を重ねざるをえない平民のためにこそある。 彼らは救われなければならないのだ。という強烈な意志が 色々な経験をへて、主人公の中に次第に固まっていきます。 いいぞいいぞ。それそれー。 登場するキャラクターの数は決して少なくないのですが それぞれが抜かりなく丁寧に描かれていて読みやすいです。 全員が大事な役割を持った魅力的な人物達。悪役含め。 それだけに最後まで頭の片隅で 上巻冒頭に出てきた河原坊浄寛に もう一度会いたいなーと思いながら読んでました。 だってあの人嫌いな人いる?
1投稿日: 2011.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「聖の戒は,,無戒。これがおきてじゃ。無戒であるということは,仏法の常識や世間の常識など,それらすべてにとらわれず自由に生きることをいう。」 「なむあみだぶつ,とは,南無,すなわち帰命する,ということでございます。帰命するとは,すべてを捨てて仏の前にひれふすこと。なにもかも,すべておまかせして信じ,決して迷わない。その誓いを南無というのです。そして,あみだぶつ,とは,阿弥陀如来という仏様をお呼びする声」 「わたしはついに出会ったのじゃ。真の母のような仏様に。それが阿弥陀仏じゃ。多くの世の母親の中から,ただ一人の自分の母と出会う幸せを,選択(せんちゃく)という。そしてこの世のあわれな者を一人残らず救うぞという阿弥陀仏の誓いを,本願という。そのみ仏の本願を信じて,思わず体の奥から漏れ出る声,それが念仏というもの」 「この世に生まれて,これほどまでに信じる人と出会えるということは,何という幸せなことだろう。」 「本願をほこる,しかしそれしかほかにほこるものなき人びとのことを思えば,私の胸はひどく痛むのだ。母親に愛されていることにはじめて気付いた子が,度を超して甘えたとしても叱るわけにはいくまい。だから私は,遵西らを念仏門の悪として切り捨てることをしないできた」 「選択(せんちゃく)というのは,二つの中からどちらかを選び出すことではない。それは片方を捨て,片方に身命をかけることで,魂が二つに引き裂かれる恐ろしい行為でもある。その引き裂かれた魂からしたたる血が念仏なのではないか」 「もしも生涯の師弟というものがあるとすれば,師,高弟,弟子,門下といったつながりではなく,易行念仏を説きつつ人びとの暮らしの底にはそれぞれはいっていくところにあるのかもしれぬ。旅立つことが真の師との出会いなのだ」 「法然は,区別なく,という立場で人びとに念仏を説いております。…しかしそれは法然のたてまえではないか,とわたくしは疑っております。強き者,富める者,身分の高き者たちを区別して,世間の大多数の貧しき者,弱き者たちを念仏ひとつで救おうというのが法然の真意ではありますまいか。悪人ですら往生できるのだ,いわんや善人はもちろんのこと救われる,と法然はいったと聞きますが,本心はその逆かも知れませぬ」「善人なおもって往生す,いわんや悪人をや,ということか。そこをつきつめていけば,親は病の重き子をこそ愛しく思う,という論になる」 「善信は師の法然の示した道を,さらに一歩ふみだすことで,もっとも忠実な弟子となろうとしているのではないでしょうか。…悪人,善人の区別さえつけないという考えのように見えます」 「わたしは浄土にはいったことがありません。ですから,師の言葉を信じるしかないでしょう。信じるというのは,はっきりした証拠を見せられて納得することではない。信じるのは物事ではなく,人です」 予想以上に面白かった。全く知らなかった親鸞の人生,考え方について少しだけ理解した。次の激動篇も読みたい。
1投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞が比叡山をおりて法然上人に師事し、易行念仏の真実に迫っていく物語。 厳しい修行を重ねても悟りを得られず、振り払うことのできない煩悩に悩みに悩む。生死をかけた修行の後に法然上人という真の師にめぐりあい、そこで真の念仏と出会う。 実は法然上人のこころにも大きな迷い、悩み、苦しみがありそのために念仏を日に何度も唱えるという。親鸞や法然にさえ克服できない煩悩があるのに、いわんや凡人の自分をや。 いにしえよりかわることのない人の苦しみ。人々をその苦しみから救い出すために念仏に命を賭ける様は美しい。
1投稿日: 2011.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史モノながらかなり読みやすい。 展開がドラマチック過ぎてうそっぽ過ぎる(一部フィクションなんだが)のが 少し気になったが、そこで引き込まれてもいた。 自分の中のいやらしい部分だとか、ものごとの真理だとかを 追求して追求し尽くす、その過程でズレない、ブレないということ。 仏教にちょっと興味を持った。
1投稿日: 2011.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は親鸞という方を名前くらいしか知らない。 多分教科書などで目にしたくらいだろう。 この作品は忠範から、範宴、綽空、、善信、そして親鸞となるまでの生きてきた有様。 常に自分に厳しく、自分に正直に行動をする決して器用ではないが、誰もが愛してしまう性格。 親鸞という人物の本を今まで読んだことがないんでよくわからないけど、とても考えさせられたし、活劇のような面白さもあって、のめり込むように読んでしまった。 病室にて読了
1投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教を扱った小説だが、かなり読みやすかった。物語性にも富んでいて、入門編には最適かも知れないと感じた。 ただ、読みやすい分、思想的背景が薄い気もしたので、もう少し仏教うんちくを入れてもらってもよかったと感じた。
1投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み込みが足りないのか?読解力が足りないのか?悪人も救われる、という理由や、「人はどうすれば救われるのか?」という、文庫の帯に書いてあった問いに対する答えなど、自分が知りたかったことがすんなり心に入ってこなくて、読み終わった後はもやもやした感じが残った。ストーリーも面白くなかったし…。
1投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の少年期から「親鸞」と名乗るまでの間の揺れる心情が描かれている。親鸞が親鸞と名乗る前に3つも名前があり、人生の節目に、生き方を変え、それにあわせて名前も変えていたとは。日本仏教の歴史の一端が見え、面白い。
1投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の追放まで描くが、決して悲劇ではなく、ハッピーエンドといった結末。堅苦しい本ではなく、楽しめる本だ。
1投稿日: 2011.10.30
