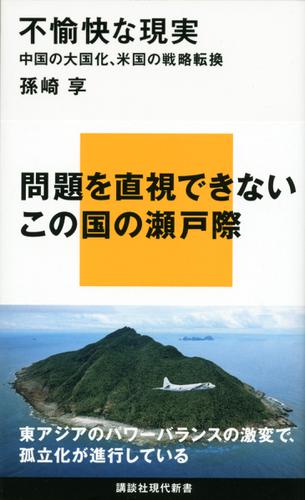
総合評価
(37件)| 9 | ||
| 14 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国は必ず発展する、というかもうしつつある。中国を軽んじたら痛い目にあうよ。そして、中国と米国が二大国となる可能性が高いけど、その過程で考えなしに米国について行ったら、対中国のかませ犬にされちゃうよ。不愉快な現実とは中国の発展であり、日本の没落ということ。簡単にまとめるとこういうことかな。 ただ、これを不愉快な現実と捉えるのか、まぁ現実ってそういうものでしょと捉えるのかは、近代日本をどう考えるのかに依るのでしょう。私は不愉快に思わないし。その意味で、日本のような小国がですよ、中国のような大国に対して(一時期は欧米に対しても)上から目線ができたって、19世紀半ばから20世紀後半にかけて敗戦を挟みつつ、日本の発展はあまりにもすごかったということです。それを実力と捉えるか、運が良かったととらえるのか、ですね。となると、なんか非正規雇用の話みたい。
0投稿日: 2024.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に論理的な持論の組み立てだが、すべては中国が米国に比肩する経済大国になることが前提になっている。日本人がこれを認めたがらないとのことだが、その前提はこれまでの成長トレンドと米国人へのアンケートがベースになっている。が、ちょっと待って欲しい。本当に過去のトレンドがこの先も続くのか? 経済成長率は生産年齢人口の増加率に大きな影響を受けるが、一人っ子政策によるdemographyの歪により2013年には中国のそれは減少に転じたと言われている。またこの数年間の高度経済成長は、経済原理を無視した無理な設備投資に支えられており、全成長率7%の内4%がそうした過剰な投資効果によるとの推計もある。これ以上の無理な投資はさすがの独裁国家でも不可能だ。更に中国には知財の蓄積がほとんどないため、成長鈍化と労務費増加によって外国企業が逃げだせば独自路線での経済成長は困難だ。一方で米国はイノベーションと戦略的外交で益々その影響力を増している。 こういった疑念は不都合な現実から目をそらしているだけなのだろうか?自分にはそうは思えない。
0投稿日: 2015.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ気になった言葉のメモ 中国は大国化する アメリカは日本よりも中国を重視する それを見極め日本としてどうするかを考えるのがこの本の目的。 日本の課題は日本人が厳しさを認識できるか。 日本の最も適切な戦略とは。 国際情勢への関心の低さ。 自身への関心が高く 他者への関心が低い 2011年末に書かれた本書の予言は、2015年の今も生きているように見える。 中国のバブル崩壊などと煽っていたメディアの論調もすでに見られない。むしろ、中国経済は大きく成長し続けている。 日本は経済も人口もジリ貧状態。 こういう中で中国とどう付き合っていくか。 戦略的な思考が必要なことは不愉快なほどによーくわかった。 あとは、教育にどう活かしていくべきなのか?
0投稿日: 2015.01.02中国よりと言うより反米感情があるかも
元々ドイツの文化圏だったアルザス・ロレーヌ地方はドイツ、フランス間で長年領土紛争が行われて来たが第二次大戦後の後その原因となった資源石炭、鉄鋼を共同管理する欧州石炭鉄鋼共同体を作り後にEUへと発展した。日本も大国化する中国との付き合い方でお互いの利益となるような体制を作ると言うのが本書の主張のようだ。 前半では日米関係、日中関係、中米関係に関する分析がなされている。 冷戦下でアメリカの方針として対ロシアの防御線として日本の復興を後押ししたアメリカは80年代以降は経済的な脅威として日本を捉え逆に弱体化をはかる。それが銀行のBIS規制で当時世界の銀行の内ベスト10に7行あったのがBIS規制がもとで置いて行かれたと言う。しかしこれは元々資産バブルで膨らんだ価値だったので過大評価されていただけだったと思うのだが・・・とは言え日米貿易戦争でアメリカが日本を脅威として捉えていたのは事実。 現在のアメリカがアジアで最も重視しているのは日本ではなくて中国であり、中国が強くなりすぎないように日本を対抗させると言うのがアメリカでは一つの常識的な考え方だと言う。まあそれは有るかもね、筆者も書いてるがリチャード・アーミテージ、マイケル・グリーン、ジョセフ・ナイは日米同盟強化路線で裏には軍産複合体がいて日本にF−35なんかを売りつけようとしていると。一方金融、産業を代表するグループは中国との関係を重視し、またG2米中が国際問題を協議、解決すると言うことを目標とする勢力も有る。(個人的にはGゼロ説に1票w)筆者は日米関係強化路線にはむしろ反対の立場のようだが多くの日本人の感覚としては日米関係の強化は対中関係でアメリカのパワーを当てにしていると言うことだとの理解で日米関係さえ安泰なら何もかも大丈夫と言うほどのんきな人はあまりいないと思うのだが。 中国と尖閣で軍事対立が起こったらどうなるかについても中国軍事力が部分的には日本を圧倒し、米軍は日本が前にたたない限り全面にはたたない。中国のミサイルは日本の米軍基地を破壊する能力が有る。などなど列挙しているがさすがに米軍基地が攻撃されたらアメリカは反撃すると思うよ。尖閣諸島の帰属についてアメリカはノーコメントなのは事実なのですがやや意図的にミスリードしているように見える。 尖閣諸島が中国領であると言う根拠をいくつか示しているが、同様に尖閣諸島が日本領であると中国が認めた根拠もいくつかあるのにそちらには全く触れていない。北方4島についても日本が放棄した根拠のみを述べロシアが条約に参加していない部分は触れていないなど、相手方の見方はこうだという説明をするのはいいとしてもかなり一方的な主張に見える。 他にも中国は2002年にアセアンとの間で南シナ海の行動宣言で「現在占領されていない島や岩礁上への居住などの行為を控え、領有権争いを紛糾、拡大させる行為を自制する」の項目が有ることを元に中国は武力的な解決を行わないだろうとしているが、元々島を勝手に占領したのは中国でこの宣言はある意味やっちゃったのは仕方ないがもうしません、だから取り返しにくるなと言ってる様な物なのでそう素直に信じられないと言うのが普通の感覚だと思う。 紛争を避けて経済的にお互いに利益のある関係を作りましょうと言う主張は理解できるのだが、やったもん勝ちの中国の行為を責めずに日本政府の対応のみを問題視し平和的な解決をしましょうと言ってもねえ。最後は中国をどれだけ信用できるかと言う話になるし、それこそ中国人だってそれほど中国政府を信用していない。まあ経済的な結びつきを強くすることからですかね、EUの例に習うのであれば。
0投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の要旨は終章で次のように書かれている… 1 日本の隣国中国は、経済・軍事両面で米国と並ぶ大国になる。 2 この変化の中、米国は中国を東アジアで最も重要な国と位置づける。 3 2020年頃、中国は米国に経済的に追いつくことが予想される。 4 軍事力で米中が接近する状況で、米国が日本を守るために中国と軍事的対決することはない。 では、そうした中、日本はどうあるべきか… それは選択肢のある問題ではない。本書では次のように書く。 ―日本には軍事的解決の選択肢はない。 平和的解決の手段しかない。 …であるならば、従来の対米追随のありかたは、見直されて 然るべきなのだろう…残念ながら現在の日本の政治に、 その萌芽はない。本書で述べられる「東アジア共同体」は、 非現実な理想としても、ボクらは、どこへ向かうべきか考える時だ。
0投稿日: 2013.12.21未来のためには何が正しいのか…
こういう考え方もあるんだ、という一つとして興味深く読みました。全く正反対のことを主張する人もいますので、あれこれ読んで比較すると良いと思います。
0投稿日: 2013.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国の台頭、アメリカとの二極化はわかるがアジア共同体というのは少し違和感あり。EUの現状を見ると緩やかな統合も場合によっては危機的状況を脱出できない。むしろ今の日本が経済力を再生し大国とのバランスゲームを演じるほうを志向したくなる。
0投稿日: 2013.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログようは最近、米国さんが日本より中国を重視してるよ〜。という警鐘 本書の主旨ではないが、95ページにある最近20年間の世界金融機関ベスト20の入れ替わり具合が興味深かった。
0投稿日: 2013.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ主張のブレ無さが逆に気になるというか、中国農村部、チベットの状況を聞いて何故そこまで信頼を寄せられるのか。 自分が実際に係ったところに近くなるほど近視眼的になるのはよくある現象。 アメリカが首位を脅かされる恐怖で、80年代の日本にしたように中国に噛み付くのを期待して待つしかないのか。
0投稿日: 2013.10.03タイトルで損してますが…。
どうしてこんなタイトルにしたのかわかりませんが、著者の言いたいことは、このタイトルからは絶対読み取れません。私が読み取ったことは、戦後アメリカ主軸の外交政策と政治を一旦180度ひっくり返してみよう、ということです。実際、この国は戦後の落とし前を未だにつけていないかもしれないという漠然として落ち着かなさの原因と、この先、どんな政策で近隣諸国と付き合っていくのが得策かを理解することができました。うーん、やっぱりこのタイトルはおかしいです。
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ孫崎氏の著書は明快な記述のものが多いが、この本もその1冊。日本の立ち位置について、ASEAN諸国のあり方は参考になることが多いと思う。武力はいくら持ったところで安心が得られるものではないのだから、著者の主張する「複合的相互依存関係」を構築することは解になりうると私も思う。課題は何を、どうやってというところだ。悲しいことに、今の私はノーアイデア…というわけでもないか。
0投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
中国がアメリカをしのぐ超大国となり,アメリカも日本より中国を重視する状況が近づきつつあるという現状認識のもとに,今後の日本外交の進むべき方向を論じる。 TVやネットで著者の言動を目にして,唯我独尊な思い込みに基づくように感じていたが,本を読むと,まことにもっとも。 勉強になったし,説得もされた。
0投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治以降150年間で経験しなかった中国の大国化に日本はどう向き合うか。2020年には中国のGDPはアメリカを越えるという情況の中で、米国のオバマ政権は同盟国重視からG2戦略へ転換するのか? 中国の戦略等々を踏まえた分析、提言は傾聴に値する。 反米傾向が強いと言われる著者だが、この本ではかなり冷静な分析、提言をしている。
0投稿日: 2013.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ孫崎の日頃の主張通り。ただツイッターを最近フォローし始めてTPP反対とか東アジア共同体についていろいろ言ってる背景を初めて知れたかも。 中国が大国化するなかで米国も東アジアで日本より中国を優先していくだろう、その中で日本はどうやって生き抜くかを考えるとゆう本。 地政学において軍事力の重要性が弱まっていること、今までは金、技術を欲しがっていた中国がマネジメントを欲しがっていること、中国にとってEUや米国との関係が重要であるほど、日本との問題が悪い影響を与えないようにと日本にとっても都合がよくなること、逼迫する財政で手が回らないところを日本の自衛隊との共同を深めていくことで補おうとする米国、中国との関係を強化しつつ、中国との関係が悪化したときに備えて日本やインドとの同盟を強化するザカリアの「ヘッジ戦略」、BIS規制で起こった日本経済への悪影響、どうしようもなくなる日中の軍事バランス、リアリズムより複合的相互依存関係へとゆう主張、中国や韓国が領土問題についてどうゆう認識を持っているか知らない日本人、実質的な複合的依存関係を中韓と深め、EUやASEANのように段階的に東アジア共同体をつくっていこうとゆう主張など、TPP反対や経済についてはともかく、孫崎さんの国家戦略論にはいつも納得させられます。
0投稿日: 2013.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログキッシンジャー 日本人を戦略的にものを考えられない人たちと蔑視 米国の戦略的資産としての日本 マイケルグリーン 1 伝統的な日米関係を重視 2 米中二大大国が世界を調整する 3 米国は部分的撤退を図るがその分を同盟国で穴埋めさせ共通の敵として当たらせる オフショア・バランシンス 4 関係国で国際的枠組みを作っている 米国は日米同盟強化ししか動かないと錯覚している 日本の多くの人は十分に認識していないが、尖閣諸島近辺で日中間の軍事衝突が起こった時に、日本が勝つシナリオはない 棚上げとは現状を容認し、その変更を武力でもっておこなわないことである 新疆ウイグル地方 イスラム教 カトリック、プロテスタント間での宗教戦争 ドイツでは人口の10−15%減少 戦争における膨大な犠牲を避けるため、「国家の主権を認め、互いに干渉しない」ことを原則とするウエストファリア条約が結ばれた ロシアの国別輸出額 日本は14番目 重要度低い サンフランシスコ講和条約 日本国は千島列島に対するすべての権利、請求権を放棄する 吉田茂 千島南部の択捉、国後両国が放棄の千島に含まれている 望ましい対応 歯舞色丹は1956の日ソ間の合意にもとづき日本に返還すること 国後、択捉は歴史的事実を踏まえ日本ロシアは解決を図ること 北朝鮮 相互依存がいいが、実際は輸出輸入ともへっている 一方中国との相互依存は上がっている 孫子 十なれば、則ちこれを囲みこれと戦い、五なれば、則ちこれを攻め、倍すれば、則ちこれを分かち、敵すれば、則ちこれとよく戦い、少なければ、則ちこれをよく逃れ、若からざれば、則ちおくこれを避く。故に小敵の堅は、大敵のきんなり 戦争の原則としては、味方が10倍であれば敵軍を包囲し、5倍であれば敵軍を攻撃し、倍であれば敵軍を分裂させ、等しければ戦い、少なければ退却し、力が及ばなければ隠れる、だから少勢なのに強気ばかりでいるのは、大部隊の捕虜になるだけである ナッシュ均衡 我々が考える最善の戦略は、自らのあるべき姿を考えて出てくるのではなく、相手国の動きによって最適な戦略が変わる 日本が抱える火種は領土問題である。ここで顕著なのは日本側が領土問題について相手方の主張をほとんど知らないことである 米国の軍事思考の根幹にはトゥキュディデスの戦史がある。ここでは、アテネの滅亡は、アテネの国益に密着していない同盟国を助けたことにある 望ましい戦略は、相手と我の力関係を冷静に判断し、最も適切な戦略を選択することである。「こうしたい」では望ましい戦略は出ない。相手と関係なく「戦う」という選択をすれば、破れ、滅びる運命が待っている 阿部信行首相 1939/8-1940/1 無謀な戦争をやめようとした それを回避するためには互いに平和的解決を志向する者同士の連携を図る。これが国際政治で強く望まれることである 欧州共同体も、はじめは欧州石炭鉄鋼共同体からスタートした いま日本人に求められているのは、「日本の隣国中国は、経済・軍事両面で米国と肩を並べる大国になる」という事態を直視できるか否かである。そして米国との協調のみを求めれば日本の繁栄があるという時代は終わったという事態を直視できるか否かである
0投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ元々ドイツの文化圏だったアルザス・ロレーヌ地方はドイツ、フランス間で長年領土紛争が行われて来たが第二次大戦後の後その原因となった資源石炭、鉄鋼を共同管理する欧州石炭鉄鋼共同体を作り後にEUへと発展した。日本も大国化する中国との付き合い方でお互いの利益となるような体制を作ると言うのが本書の主張のようだ。 前半では日米関係、日中関係、中米関係に関する分析がなされている。 冷戦下でアメリカの方針として対ロシアの防御線として日本の復興を後押ししたアメリカは80年代以降は経済的な脅威として日本を捉え逆に弱体化をはかる。それが銀行のBIS規制で当時世界の銀行の内ベスト10に7行あったのがBIS規制がもとで置いて行かれたと言う。しかしこれは元々資産バブルで膨らんだ価値だったので過大評価されていただけだったと思うのだが・・・とは言え日米貿易戦争でアメリカが日本を脅威として捉えていたのは事実。 現在のアメリカがアジアで最も重視しているのは日本ではなくて中国であり、中国が強くなりすぎないように日本を対抗させると言うのがアメリカでは一つの常識的な考え方だと言う。まあそれは有るかもね、筆者も書いてるがリチャード・アーミテージ、マイケル・グリーン、ジョセフ・ナイは日米同盟強化路線で裏には軍産複合体がいて日本にF−35なんかを売りつけようとしていると。一方金融、産業を代表するグループは中国との関係を重視し、またG2米中が国際問題を協議、解決すると言うことを目標とする勢力も有る。(個人的にはGゼロ説に1票w)筆者は日米関係強化路線にはむしろ反対の立場のようだが多くの日本人の感覚としては日米関係の強化は対中関係でアメリカのパワーを当てにしていると言うことだとの理解で日米関係さえ安泰なら何もかも大丈夫と言うほどのんきな人はあまり以内と思うのだが。 中国と尖閣で軍事対立が起こったらどうなるかについても中国軍事力が部分的には日本を圧倒し、米軍は日本が前にたたない限り全面にはたたない。中国のミサイルは日本の米軍基地を破壊する能力が有る。などなど列挙しているがさすがに米軍基地が攻撃されたらアメリカは反撃すると思うよ。尖閣諸島の帰属についてアメリカはノーコメントなのは事実なのですがやや意図的にミスリードしているように見える。 尖閣諸島が中国領であると言う根拠をいくつか示しているが、同様に尖閣諸島が日本領であると中国が認めた根拠もいくつかあるのにそちらには全く触れていない。北方4島についても日本が放棄した根拠のみを述べロシアが条約に参加していない部分は触れていないなど、相手方の見方はこうだという説明をするのはいいとしてもかなり一方的な主張に見える。 他にも中国は2002年にアセアンとの間で南シナ海の行動宣言で「現在占領されていない島や岩礁上への居住などの行為を控え、領有権争いを紛糾、拡大させる行為を自制する」の項目が有ることを元に中国は武力的な解決を行わないだろうとしているが、元々島を勝手に占領したのは中国でこの宣言はある意味やっちゃったのは仕方ないがもうしません、だから取り返しにくるなと言ってる様な物なのでそう素直に信じられないと言うのが普通の感覚だと思う。 紛争を避けて経済的にお互いに利益のある関係を作りましょうと言う主張は理解できるのだが、やったもん勝ちの中国の行為を責めずに日本政府の対応のみを問題視し平和的な解決をしましょうと言ってもねえ。最後は中国をどれだけ信用できるかと言う話になるし、それこそ中国人だってそれほど中国政府を信用していない。まあ経済的な結びつきを強くすることからですかね、EUの例に習うのであれば。
0投稿日: 2013.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ孫崎享さんに対しては、最近、著書『戦後史の正体』が「陰謀史観に過ぎる」というような批判も少なくないようだが、少なくともこの本で書かれていることは至極真っ当な指摘であり論であると感じる。 曰く「不愉快な現実」とは、 1. 日本の隣国中国は、経済・軍事両面で米国と肩を並べる大国になる。 2. この中、米国は中国を東アジアで最も重要な国と位置づける。 3. 日中の国防費支出の差は拡大し、日本が中国に軍事的に対抗することは出来ない。 4. 軍事力が米中接近した中で、米国が日本を守るために中国と軍事的に対決することはない。 という「現実」である。 (「来るべき現実」という意味も含めて) この現実の中で日本はどういう道を取るべきか?を論じたのが本書であるが、リアリズムに基づいた論だけに、根拠の無い単に威勢のいいだけの論とは異なり、非常に傾聴に値すると思う。 中でも白眉は第8章の「戦略論で東アジアを考える」だ。紛争解決とは「ゼロサムゲームではなく、非ゼロサムの思考が必要だ」という指摘はまさにその通りであり、著者が引用されているラムズボサムの「紛争への5つのアプローチ」のフレームワークは大変に参考になる。曰く、「自身への関心」が高く「他者への関心」が低い場合は「競争・対立」的アプローチをとりやすくなる。(上に書いた、単に威勢のいい論者はこのパターンが多い) 賢者のアプローチは「自身への関心」だけでなく「他者への関心」も高い、「問題解決」の姿勢だ。 「不愉快な現実」を前にして日本人は「米国に追従していれば安心」という"思考停止"状態から抜け出す必要があるという筆者の主張の根底にある姿勢に強く共感する。
0投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
我々日本人は「アメリカは日本の同盟国として中国に対峙してくれる」と、無邪気に信じ込んでいないだろうか。「アメリカが中国とのパートナーシップを選ぶ」という可能性について、真面目に考えたことがないのではないだろうか。そもそも歴史的に見てアメリカは中国寄りだった時期も多いわけで、いつまでも東西冷戦の枠組みの中でしか考えようとしない我々は非常に危うい。ロシア、北朝鮮、そして韓国といった「決して穏やかでない」隣国に囲まれた我が国は、どのように生きのびていくべきなのかを真剣に考える必要がある。60年前には殺し合っていた独仏に、多様な宗教、政治体制を乗り越えて連帯するASEANに学ぶべきところは多い。
0投稿日: 2013.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、出版物が多い元外務官僚で、戦略論の著書もある孫崎氏の本。 これまでの著書は、日米同盟や日本の領土問題などの問題を扱ってきたが、この本では中国の経済的・軍事的な台頭、中国に対してアメリカはどのような関係を今、築こうとしているか、またロシアなどの国々はどのような意図を持ってきているのかなどを取り上げながら、感情論やナショナリズムではない、現実的な対処法の検討を行っている。 ドイツとフランスの戦争後の関係の築き方など、まだまだ歴史に学ぶ点は多い。脱亜論を説いた福沢諭吉の考えに私たちは非常に多く染まっているが、中国の新の狙いや国益を考えながら、来るべき時代(新しいパラダイム)でどのように振る舞うべきかを考えるべきかを強く思った。
0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこの手の本を読むと、提言は分かったけど、個人としてどうすりゃいいの?と思ったりするわけで、この本も例外に漏れなかったりします。 ただ、この本の価値は、「ゼロサムの結果と非ゼロサムの結果」の図に尽きると思う。 あの島は我が国の領土的な白黒はっきりさせるのではなく、こっちの主張に加え、相手の主張もよく聞くことで、対立を避け、妥協や問題解決に導くことができる、という考え方は広く応用できると思う。 まあね、領土問題とか、そんな冷静に話せることじゃないんだろうけどね。
0投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ尖閣諸島の防衛に関する第5章は様々な論点が議論されている.「棚上げ」という一見不可解な政策の重要性が認識できた.
0投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログデータを色んな角度から見て、将来の国のあり方を模索し、現実的に政策を実践していく。 予断と偏見はなしだ。 アメリカと中国の位置関係、そして、その狭間における日本の立ち位置。 世界の歴史に学ぶところはいくらでもある。 日本人だけが考える希望的観測、こんなものは何の役にも立たない。 日本国を滅亡に導くだけだ。 そんなことを考えさせられる、元外務官僚の国際的な視点に立った著作だ。 冷静に読み解かなければならない。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
領土問題は複雑だ。 確かに各国それぞれにその領土に対しての認識や主張は違う。 それぞれの国の認識や歴史事実を踏まえて外交は進めないと戦争になる。 特に日本は中国に対して、アメリカが助けてくれると信じているが、実際のアメリカがどのようなスタンスで接しているかを理解していないと放り出されることになる。 それが、不愉快な現実なのだから。
0投稿日: 2012.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ福沢諭吉が「脱亜論」において、「支韓両国は数年以内に亡国となり、諸外国に分割されることは疑いの余地がない。よって、支韓と伍するのを脱して西洋の文明国と進退を共にするべきである」と喝破して以来150年もの間、戦前は軍事力において、戦後は経済力において、日本の国力はずっと中国を上回っていた。けれども、近い将来中国の経済力は米国をも追い越し、超大国として君臨することになる。軍事的にも、もはや日本が中国に対抗するという選択肢はありえない。このような状況の中で、米国は東アジアにおいて、日本よりも中国を重視するようになってきている。一方の日本はといえば、経済は停滞したままであり、少子高齢化には歯止めがかからず、国力は衰える一方である。明るい話題はなにもない。まずはそれを認めた上で、では日本はどのような道を進むべきなのだろうか? ASEANは、イスラム教、仏教、キリスト教国を含み、多様な民族・価値観を内包する共同体である。それにもかかわらず、今やASEAN諸国間で軍事衝突が起きる可能性は極めて低い。著者は、ASEANの叡智に倣って、日中韓で「東アジア共同体」を形成すべきだと説く。 中国は経済的に日本を追い越したとはいえ、それは単純に人口が多いためだ。一人あたりで考えれば、依然として貧しいままである。(一人あたりGDPがブルガリア、トルコ、メキシコ並みになれば、中国の経済力は米国を追い抜くことができる。)貧富の差・地域格差は拡大し、環境破壊は甚だしく、共産党の独裁が続く。そして国内には、政府が「核心的利益」と主張するチベット、東トルキスタンという大きな民族問題がくすぶる。そんな中国の覇権は長くは続かず、きっとどこかで破綻するに違いないと思ってしまう。 けれども、中国では伝統的に権威を重んじ、権力は「天」から授かったものとみなす。したがって、(善政を行っている限りにおいては)民主主義体制でないことは中国民衆にとって問題ではないのかもしれない。共産党が国内の不満を抑え込むためには経済成長を続けるしかなく、そのためには外国との経済的結びつきを強めるしかない。そうすると、中国は外国に対して宥和政策を取らざるを得ない。ということは、意外に中国はずっとこのままなのかもしれない。それがまさに、「不愉快な現実」なのである。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ孫崎 享 (著) 日本人が国内で「願望」を語っている間、周りの状況は刻一刻変化している。しかも我々が望まない方向に…。将来必ず起こる「中国が超大国として米国を抜く」事態を前提として、日本の生きる道を探る。
0投稿日: 2012.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ台頭する中国と、それによる日米関係の変化についての本。 タイトルになっている「不愉快な現実」とは、アメリカが日本よりも中国を重視し、日本だけが一方的に取り残されるという事態を指している。 外交やパワーバランスについて、専門書を引用しながら書かれていて、日本を取り巻くアジア問題の入門書としてオススメ。
0投稿日: 2012.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ日米関係はソ連を封じ込めるために始まり、今日においては中国との距離感でその価値が語られるのもやむを得ない。米国から見れば、2010年代においては日米よりも米中かもしれないし、 日本はオフショアバランシングの駒の一つに過ぎないのかもしれない。日米同盟を金科玉条と奉じる人々に対し、筆者はそんな不愉快な現実を突きつける。 もう一つの不愉快な現実、それは日本には中国との軍事紛争を戦う力はないということ。福沢諭吉以来の脱亜入欧の時代はもう終わり、しかし日本人の心の底に残る中国蔑視感。それでも経済でも国際政治でも軍事力でも、最早中国には敵わない。そんな中領土問題で一方的に敵がい心を燃やす危うさ。 筆者は言う、相手の主張に知ろうとしない姿勢は危険である、と。 中国にも自国の中核的利益を東シナ海や北朝鮮でなく対米軍事プレゼンスでもなく、国内治安や経済建設にあると考える勢力はある。そういう人々と手を結び、という発想も、領土問題にも平和的な解決手段があるという知恵も、従来の日本には欠けていた要素だけに興味深く読むことができた。 まぁ、筆者は筋金入りの懐米論者とお見受けするので、そうと知って読む必要はあるけれども。
0投稿日: 2012.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ知ろうとせずお人好しからの脱皮を。ウィン・ルーズからウィン・ウィンへ、リアリズムから複合的相互依存の関係へ。客観的事実、現実直視。
0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ左寄りの、日中、日ロ、日韓共存論。 アメリカがすでに、日本を緩衝材としての中国政策をオフショアバランシングとしているというのはままあることだと思う。 中国の軍事力、GDPを冷静に直視した時に、日本が考えられる行動を客観的に分析し、かつ、最も有用な策を練る。 そんな行動ができないのは、WW2から一向に進歩してないということか。 ただ、だからといって、手放しで中国やロシアと友好関係と行くとも思えない。 両国民の間にある不信感や敵愾心を超えて、Win-Winの関係にするのは並大抵ではないと思うので、その対応策なども論じて欲しかった。 読後、右から中道右派ぐらいには振り戻ったかな。
0投稿日: 2012.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
特に8,9章が星5。 外交は単純なものではない。 白黒つければ良いというものでもない。 紛争を起こさないために、グレーのままにしておくのも一つの方法。 尖閣諸島を東京都で買うことに何か戦略があるのだろうか。 この本にあるように、領土問題はこのまま棚上げして、 この地域を両国間で有効に活用するのが、よりよい対策に思う。
0投稿日: 2012.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカしかみていない外交をはじめ、国際問題をどう見るべきなのか、筆者の思いと現実社会との落差を強く感じました。 アメリカ絶対主義的なところを打破していくために、私も努力していきたいと思いました。
0投稿日: 2012.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ『日米同盟の正体』を読んで、孫崎さんの考え・意見に興味を持ったので2冊目。昨今の中国の大国化とそれに対応する米国の政策転換、そしてこれからの日本の生きる道について。この本でも孫崎さんは日本の政治政策に危惧を抱いている。『日米同盟の正体』同様、孫崎さんの考えには納得できてしまう。ただ、『日米同盟の正体』より少し読みづらかったように感じた。
0投稿日: 2012.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに、タイムリーな一冊。多くの日本国民が、たとえ賛成はしなくとも、著者の提示する事実と主張を読んだうえで日本の外交戦略を考えてほしい。
0投稿日: 2012.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「スーパー301条」という言葉を覚えているだろうか? 戦後アメリカ追随で進んできた日本だったが、アメリカから制裁を受ける事態を日本人はどのようにうけとめようとしていただろうか?自分を守ってくれる親でもあり、親友でもあるアメリカが日本を敵視する事実に動転して慌ててすり寄ってしまった。 多くの日本人が疑問をもたずに思い込んでいることがある。 「民主主義国アメリカは共産主義国の中国よりも同じ民主主義の日本の仲間」 「これまでのやりかたでこれからもうまく行く。今の不調はこれまでのやり方が正しい路線からずれているため。」 著者の孫崎亨氏これらが幻想であることから話をひもといてゆく。 「中国がアメリカを抜く大国になる」 「核の傘はもう存在しない」 「アメリカは日本を守らない」 「日本は中国には勝てない」 「北方2島や尖閣諸島、竹島の領有を主張する日本の根拠は薄弱」 等、すでに明白な事実が日本人の多くにはまだ見えていない。 アメリカは日本の友達であると信じたい気持と、そうである保証などなくなっている事実の間で、ひたすら集団で現実逃避に走る日本人。日本人の常識は単なる思い込みにすぎず、不愉快な現実がより事態を直視できなくしていることを伝えることがこの本の主題である。 著者はこう述べている。「単純な話、今日、日中でどちらの政治指導者が、それぞれの環境を前提にした中で、それぞれの国を正しい方向に導く能力を有しているか。残念ながら、筆者はとても『日本の政策が中国よりも国益に合致した政策である』と言えない。」(P166) またこう問いかける。「『中国は民主主義体制でない』と批判する人々は、日本と中国のどちらの政策が『公共の利益のために行使されているか』を問えばよい。」(P168) 私が思うに、第三国の人から見ればこの問いの答えは明らかなのだが、多くの日本人にはにわかには理解できない、また受け入れたくない「不愉快な現実」なのである。
1投稿日: 2012.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年の日本の安全保障事情の解説と分析。基本書的位置づけ。 日本の一般大衆が抱く日米同盟の「誤認識」を指摘し、米国のアジア戦略における日本の位置づけが、中国の軍事的経済的台頭によって変わっていることを、日本の安全保障事情の歴史的な背景と変遷を含め様々な情報を駆使して詳しく解説・分析している。また、日本の今後の安全保障戦略を考える上で、企業戦略の視点を導入しているところが面白い。 残念なのが、今後日本が取るべき安全保障戦略内容の具体性に欠ける点だ。伝統的な日米同盟関係維持から脱却し、東・東南アジア諸国との関係改善に努めるという方針は賛成だ。だが、それを示しただけでは日本の今後の安全保障戦略について分析したことにはならない。次はこの点を深めた孫崎先生の見解を、是非、出版して頂きたい。
0投稿日: 2012.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的に軍事や外交関係の理論を構築する際に、孫崎氏の主張は大変参考にしている。 以前読んだ『日米同盟の正体』とも合わせ、日本がこれから構築すべき外交戦略をしっかりと道筋立てて述べている。 結論を先に述べると、日本は中国や北朝鮮、ロシアなどの隣国と過度な敵対的態度を取らず、相手側の主張や言い分も理解したうえで、建設的に外交努力を目指すべきとしている。そして、最終的には米国追従一辺倒だけでなく、東アジア経済圏の中でプレゼンスを発揮すべきと主張する。 米国追従では、日本は極めて危険な状態に置かれる理由は複数ある。 (1)日本の経済の将来性は、対米から対中へと一層シフトし、外交で対立しても全くメリットがない。 (2)同様に米国もアジアの貿易の中心国を中国とし、安全保障の面では警戒しつつも、次第に貿易の依存度を高めている中、中国に対しては友好な態度をとる戦略に変わっている。 (3)中国の軍事力は圧倒的に強く、ここで日本の軍事力を高めても意味がない。一番重要なのは、お互いに譲歩を引き出しながら、中国との友好な関係を樹立することだ。 領土問題、経済問題、色々あるけれども、もっと普段のメディアで報道される問題に対し、冷静な判断材料を与えてくれる孫崎氏は、あらためて貴重な存在だと思っています。
0投稿日: 2012.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ孫崎さんは外交官OBで、するどい分析だなと思っていた。 職場の本屋の棚から新刊を購入。 不愉快な現実。 (1)米国はアジアの交渉の中心を日本から中国に移した。 (2)アメリカは、日本のために本土がやられるため、日本に核の傘をかけることはない。 (3)自衛隊だけでは現時点ですでに中国軍に対抗できない。 この不愉快な現実の中で、日米同盟でアメリカの尻にくっついていた日本は、外交戦略を練り直さなければならない。 まず、自分にできることとしては、中国だけでなく、地政学上重要なベトナム、タイ、インドネシア、オーストリアなどの太平洋諸国との連携を強めていくことだと思う。
1投稿日: 2012.03.20
