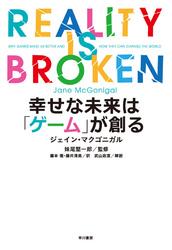
総合評価
(54件)| 19 | ||
| 17 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームの効用に関する大規模な詳細な研究の訳本。 ゲームの教育的利用などについて多くの事例から学ぶことができる。現実を変えるパワーをもった驚きの「ゲーム」がすでにいくつもある!
0投稿日: 2023.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログざっくりとした自分なりの解釈として 現実にゲームの要素を取り入れれば、もっと世の中が良くなるじゃない?って内容。 ゲーム固有の四つ特徴として ・ゴール プレイヤーが達成すべき具体的な成果のこと。 プレイヤーの注意を引きつけ、ゲームへの参加を促し続ける。 ゴールとは、プレイヤーに目的意識を与えるもの。 ・ルール プレイヤーのゴールに達するうえでの制約をもたらす。 ゴールに達するために1番わかりやすい方法を奪うか制限を加えることで、プレイヤーはまだ発見できていない方法を模索せざるを得なくなる。 ルールは創造性を解き放ち、戦略的な思考を促す。 ・フィードバックシステム プレイヤーがどこまでゴールに近づいているかを示すもの。 得点、レベル、合計点、進捗表示バーなどの形で示される。 あるいは、もっと簡単なかたちとしては、「このゲームは、…になったら終了です」と、単に具体的な成果として知らせるだけのフィードバックシステムもある。 フィードバックが常時示されることで、プレイヤーはゴールに必ず到達できるという気持ちを保ち、プレイし続ける力を得る。 ・自発的な参加 ゲームをプレイする誰もがそのルール、フィードバックを理解したうえで、進んで受け入れることを意味する。 それにより、共にプレイする複数の人々が共通認識を持つことができる。 自分の意思で参加、または脱退できる自由があることは、ストレスが多くて難しい課題でも安全で楽しめる活動として経験できることを保証する。 があるらしい。 つまりゲームをプレイとは 取り組む必要のない障壁を自発的にこえようとする取り組みである。 そして、ゴールが魅力的で、フィードバックが十分に意欲をそそるものであるとき、私たちはゲームの限界に(創造的に、誠意を持って、熱心に)長い時間挑戦し付ける。 こういった、ゲームの要素を現実の生活にも応用させていくことでより魅力的で幸福な社会を築き上げて行けるのでは? とのこと。 感想 ゲームってかなり人間的な活動なのかなと思った。 無理矢理な制限、目的意識、ルールの共有などは頭が良くないとできないかなー。 その考える脳みそがあるゆえに、こうした、ゲームの要素を駆使しないと幸福になれないなんて、皮肉なもんだなと思った。
0投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームがなぜみんなハマるのか、ゲームを今後実生活で役に立つものとしてどう活用出来るのかを理解出来た ゲーマーのリソースを使えば、なにか世の中の課題解決に使えるのではないかと思った また、日常の仕事などにもゲーム要素を取り入れて生産性、モチベーションを上げるような工夫が入ると良いと思った
0投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームと比べて現実は不完全である、というコンセプトでスタートして、ゲームの考え方で世界を変える方法を実践交えて書いてある。 ゲームを「反逃避」と位置づけて、ゲームの考え方や、ゲーマーたちの能力、そして未解決の巨大な課題を解決するにはゲームの力しかない、という説得力を感じる。 自分も数十年にわたりゲームをやり、現在小規模ながらもゲームを作っている身として、ゲームのデザインで現実世界に影響を及ぼすことができればいいなと強く感じた。 また、10年前の本なので現状で動いているプロジェクトは少ないかもしれないが、参加型のゲームについてはいくつかやってみたいと感じたので、早速調べてみよう。 こういう取り組みが、ゲームを数多く生み出している日本という国で根付かないのはちょっと悲しい。まあ、某県で禁止条約が発行されるくらいなので、世間的に見たゲームの印象は現実逃避の時間の無駄としか思われていないんだろうなと思うと同時に、過度の収益重視が良くないのかなと。どこもかしこも課金→ガチャの収益モデルで荒稼ぎだもんなぁ… マグロクエスト作る際のモチベーションや参考として、何度も開きたい本であった。
0投稿日: 2021.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに「幸せな未来はゲームがつくる」理由と事例をたくさん学べる。もう少し外発的動機づけと内発的動機づけの議論が丁寧に欲しかった、、、
0投稿日: 2021.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めに説かれる「ゲーム開発者によるノーベル平和賞の受賞」という予想は、本書を読み進めるにつれて現実味をおびた。 ゲームは操作者がいて初めて成り立つインタラクティブなメディアだからこそ、強く没入できる。そこがゲームならではの強みで、使いようによって社会を変える潜在力があると思っていたが、それはほんの一部だと知った。なぜ能動的にゲームに挑み、熱狂するのか、仮想世界にも関わらず没頭するのか、そこにはゲームクリエイターが長年開発してきたノウハウがあり、そのノウハウこそが世界を変えるヒントを与えてくれた。 14個の現実修復法はそれぞれにいくつもの実例があり、どれも画期的。特に、医療、学校教育は遊び心が介入しにくい分野であるにもかかわらず、ここまで成果を出すゲームが存在していたとは驚き。このゲームが大規模に展開されたらと考えるとゾクゾクする(ただ、強制参加的にならなければ)。 本来、自分はゲーミフィケーションについて学ぶために読んでいたけど、本書はARG(alternate reality game)という言葉で書かれている。なぜARGという言葉で語られているかは重要で、(解説でも言っているように)本来の目的から逸れてしまうことのリスクを考えるべきという配慮は、これからゲーミフィケーションを考えるにあたって必須になると思う。 542ページと読み返すのは中々大変だけど、ゲームが世界を変えることを示す重要な研究本として大切にしたい。
0投稿日: 2020.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ★ゲーマーはなぜゲームに熱中するのか 世の中には、週に数十時間以上ゲームに熱中しているゲーマーが多く存在している。 人々をそこまで熱中させるゲームの魅力って何だろう?という疑問を、科学的に解析してくれています。 ◆ゲームの要素を現実社会に取り入れる ゲームの魅力を、現実社会にどう取り入れたらよいか?を説明してくれています。 本書で紹介されているゲームは知らないものばかりでしたが、興味深く読むことができました。 仕事を楽しくするにはどうしたらいいか?と考えるヒントになります。
0投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ講座に行った際、講師の先生に勧められて買った本である。ゲームと言うと、マイナスのイメージが強いが、いかに有効であるかと言うことを述べられていた。 ヘロドトスが記した歴史で、飢餓に当たって食事する日を1日おきとし、その間の日はサイコロゲームをして過ごしたと言うことで18年続いた飢餓を乗り越えたと言う事実がすごい。まだ古い考えの自分は、ゲームの有効性をもっと知るべきだと思った。
0投稿日: 2020.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事とか勉強とかゲームっぽい感じで取り組めたら熱中するし幸福度も増すのかなぁと思った。 ゲームには以下の4つの特徴がある ゴール ルール フィードバックシステム 自発的な参加 いろんな種類のゲームがあるけどたしかにこの4つはベースになっている気がする(スポーツ、ギャンブル?とかでも同じかも) たまに仕事がおもんない時は次のことが原因なんだろう。ここは印象的だった。 ・満足のいく仕事には明確なゴールとゴールに向けた次の具体的な行動のステップがある。 ・明確なゴールがあっても次に何をすれば良いかわからない時は仕事ではなく問題となる。問題自体に没頭することは悪くないが、問題解決へのやる気だけでは実際に成果を出すには十分ではない。 →本来の目的を忘れてしまうパターンに近いと思った。 ・よくデザインされた仕事は着実に成果を出せるように練られている。 →このようなデザインは一企業としては誰の役割なのだろうか。上司(仕事を持ってくる人)なのか、自分自身なのか。まぁすり合わせられたらいいのだけれど。 最後に 最初に世の中のことがゲームっぽくなれば良い(ゲーミフィケーション)と書いたけど訳者が後書きでレベルをあげたり能力を上げることそのものが目的になってはいけないのではないかと問うていた。 ゲーミフィケーションの本質はその先にある、個人の幸福度を上げること、人類全体の発展だと思う。 よく読めました。読解力 +200
2投稿日: 2020.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界に広がるオンラインゲーム。人生に全く意味のないものとされているにも関わらず、多くの人を熱中させている。なぜゲームはそこまで人を熱中させるのか、なぜ現実世界はゲームのようにワクワクしないのか、ゲームの役割を考察しながら、解説している図書。ゲームの仕組みを活用すれば現実世界はよりよくなるらしい。 ゲームには固有の4つの特徴、「ゴール」「ルール」「フィードバックシステム」「自発的な参加」がある。また人間は、金、権力、容姿では幸福状態は続かず、内発的報酬が重要である。内発的報酬は「満足のいく仕事」「成功体験、成功への希望」「社会的なつながり」「意味」がある。ゲームにはこれらが含まれていることが多い。ゲームの仕組みを理解して現実世界も再構築すれば、なんかうまくいきそうな気がしてきた。さて、世界を救いますか…
0投稿日: 2020.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011年に書かれたこの本は、今、改めて読むと重要な指摘をしていたのだと感じる。特にゲームのもつ特徴は、今のアイデアソンやハッカソンにうまく導入され、現実の課題を楽しく新たな観点で解決に導く取り組みに活かされている。 時代がARやMRを活用し、電脳コイルのように、OMOの世界としてリアルをデジタルが包み込むような時代になると、こうしたゲーム性の社会への活用がもっと進むのではないだろうか。
0投稿日: 2020.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ1章は、ゲームのなかの世界にこそ生きる価値があることについて。2章はNike+のような「現実と密接に同期させたゲーム」の登場の背景と展開について。「現実の出来事をゲームによって意味付ける」ということの奥深さを知った。 3章は「ゲームが現実を救う」というお話。現実は不完全であり、それは受け入れがたいことを前提としている。ゲームを通して現実社会への学びを進めることによって、困難なタスクに取り組んで「成し遂げる」という結果につなげていくという考え。 全体を通して読んだ感想としては、ゲームのネガティブな面にはあまり触れずに「今ゲームに何ができるのか」という問いへの著者なりの回答としてたのしく読めたと思う。
0投稿日: 2019.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は相当にエキサイティング!大学生の時,ゲームの経験をいかに現実に活きるのかについてあれこれ考えていたんだけど,この本はまさに,そこを丁寧に説明していていい。翻訳本なので事例が海外でややとっつきにくいけど,わからなくはない。こういう本が日本でも書かれていてほしいし,今のスマホゲームにも志を継いてほしいと思う。
0投稿日: 2019.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語訳が直訳的なのか、原文が論文調なのか、読むのに集中力と時間を要する。はじめの部分しか読めず。 ゲームによって、能力が伸びたり開発される、という面もあることは確か。著者がその理想を掲げることには異論はないし、そういうゲームが生まれていることも確か。しかし、みんながゲームをやるべきだというのは、少し違うと感じるし、現実に刺激が足りないから、達成感を味わえないから、現実の問題を解決できないからゲームをする、という論点には疑問を感じる。 昔のインベーダーゲームのように、習熟度は反射性がほとんどのゲームは、いくらやっても時間を浪費するだけだと。そして、人間の脳の反応として、ある種の気持ちよさを感じられることから、中毒性があり、こういうゲームに大量の時間を使うのは、負の面しかないのでは?
0投稿日: 2018.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・ 【期待したもの】 ・とりあえずどんな内容か図書館で目を通す 【要約】 ・ 【ノート】 ・HGでサラリ読み。早い話、ARGってのがあって、それが現実世界を(ある意味)歪曲させるマインドセット。 ・あのケリー・マクゴニガルの妹だって。 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログゲーミフィケーションと幸福研究を混ぜたような内容の話。某編集者に勧めていただいた。しかし、余白が狭くて読みにくいな…
0投稿日: 2018.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔からゲームは楽しくて仕事や勉強はなぜ面白くないのか、不思議で仕方がなかった。 この本はなぜ人々がゲームに熱中するのかを科学的に検証した本。 日本だとなんとなく[ゲーム=悪]みたいな風潮なので、もっとゲームをいろいろな分野に応用する研究が進んでほしい。
0投稿日: 2018.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームについて興味のない人だと「今はそんなことになってるのか」と感心することも多いのでは。 現実とゲームとの関わりを複数の事例を挙げて解説しているが、その事例を参考にして生活に活かすという使い方はできないかな。 読み物としてそれなりにおもしろかった。
0投稿日: 2017.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現実世界はゲームに比べると複雑で、自らの行為に対して明確なフィードバックが得られなかったりすることから、現実世界はゲームよりも退屈になものになってしまった(ゲームのが現実世界よりも魅力的である)。 その中で、ゲームの効果を再確認し活用していくことで、現実世界をより良く変えることができるのではないか。 というのがこの本の論旨。 ■ゲームの特徴 ①ゴール プレイヤーが達成すべき具体的な項目。プレイヤーに目的意識を与える。 ②ルール ゴールに到達する上での制約をもたらすもの。プレイヤーに創造性を求める。 ③フィードバックシステム ゴールにどこまで近づいているのか示すもの。 ④自発的な参加 誰もがゴール、ルール、フィードバックシステムを理解した上で、進んで受け入れること。 ■ゲームの有効性 「ゲームは悪影響」の言説が未だに世に蔓延っているが、ゲームは人間に良い影響を与える。 ゲームがなぜ重要なのか、 それはゲームが全世界に広がる広大なプラットフォームであるからである。 例えば、21歳までにゲームをする時間は約1万時間(勉強時間よりも長い) →1万時間の法則から、この時間は活用次第で大きな財産になる。 —— ■ゲームは現実世界を変えうるキーになる 1) 取り組む必要のない問題や課題に自発的に取り組むようになる 2) 感情の活性化 3) より満足のいく仕事 4) より良い成功への希望 5) より強力な社会的つながり 6) 壮大なスケール 7) 心から参加すること 8) 意味のある報酬を、それがもっとも必要なときに得られるようにする 9) 見知らぬ人々ともっと楽しむ 10)幸せハッキング 11)持続可能なエンゲージメントエコノミー 12)より多くのエピックウィン 13)一万時間の協働 14)大規模多人数参加型未来予想 --- 上記の14項目がこの本に於けるポイントなのだが、中でも重要だと思うのが、 1) 取り組む必要のない問題や課題に自発的に取り組むようになる テトリスは進めは進む程どんどん難しくなるのに、プレイヤーはそれを進んで受け入れプレーし続ける。 2) 感情の活性化 フィードバックにより、自分がどれだけ上達したのかという報酬を受け取ることができる。 それが繰り返されることで、どんなに難しい課題でもやればできると楽観的な状態になる。 9) 見知らぬ人々ともっと楽しむ 共通の関心を育み、それを元にした交流する機会を手段を提供することで、見知らぬ人同士でも楽しむことができる。 例えば、オンラインゲームとそのwikiなど。 11)持続可能なエンゲージメントエコノミー ゲームの自発性と広大なプラットフォームにより、魅力的なリソース持つエコノミーが出来上がる。 例えば、 ガーディアン紙が取り組んだ「地元選出議員の経費を調べよう」ゲーム http://tracpath.com/works/story/gamification/ プレイステーション3のネットワークを使いたんぱく質の折りたたみを解析しようとした「Folding@home™」 http://www.jp.playstation.com/info/release/nr_20070315_ps3_folding.html など --- これからの社会課題を解決する上で、特にソーシャルビジネスなどに於いてゲームの重要性と有効性は増してくるのではないだろうか。 社会課題をわかりやすくゲーム化で解決しつつマネタイズ&利益をNPOなどに投資、みたいな流れが一貫してできると面白いと思う。 あとはファンベースに考え方にゲームを取り入れて、既存ファンの囲い込みをゲームで行うと、より強力なコミュニティとプラットフォームができるのではないか。
1投稿日: 2017.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームの効用や社会問題への応用可能性を論じた本。 翻訳がとても良い。ゲームのタイトルもきちんと邦題に合わせているし、細部まで注意が払われている。
0投稿日: 2016.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログゲーミング、ゲーム性について深く熱量を持って考えた内容に満ちている。アメリカのゲーム業界での隆盛の背後にはこういったアカデミックな研究あってこそだったのではと感じられる。 また、代替現実、ゲーミフィケーションへのゲームの活用の視点も豊富。
0投稿日: 2016.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームの定義が良いです。 ジェインマクゴナガル著のreality is broken 読んで再確認出来たのですが、受動的な余暇より能動的でFBのある余暇の方がその後のパフォームも良い感覚はあり、その割合を増やしていきたいなと思えました。 彼女が掲げるゲームの要素は4つで、ルールがある、ゴールがある、フィードバックシステムがある、自発的参加である事で、確かにこれらを満たす余暇はモチベーションを上げる方向に作用すると思った。身体疲労の面からその後のパフォーマンスに対しては投入時間の制約があるという指摘もまさに。 多くの人にとって現実社会や仕事は、ルールがなく(理解に時間がかかる)、ゴールがなく(自覚的には設定されない)、フィードバックシステムがなく(成果や賞賛、成長が実感できない)、自発的参加ではない(仕事はやらされているもの)からこそツマラナイのだが、ゲームはその全てを満たしている。 だからこそ、ゲームは多くの人を惹きつける。そうなのならば、現実社会にもゲームを活かして生きましょうと、自分には、そう捉えられた。 宣伝?をしておきますと、併せてこちらを読んで頂けると大変示唆深いと思います 一流の経営者は、根っからのゲーマーが多い ゲームが社会をより良いものにしていく | 読書 - 東洋経済オンライン http://toyokeizai.net/articles/-/94528 @Toyokeizaiさんから 述べられているように、たぶん(現実社会での生活という観点で見た時には)暇つぶしにはソシャゲより普通のゲームが良いのは間違いないのだが、それ以上に先程の4条件を満たす活動の方がもっと良いと思うんだ。
0投稿日: 2016.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館にて。 ゲームが現実に影響を与えうる実例と考え方を論じる本。 常にゲームと現実という軸で豊富な実例が解説される。 著者の経歴や語り口からそれぞれのゲームに対し興味が湧くこと必至。 ただ、ここでいうゲームはテレビゲームではなくARGという現実でプレイするゲームに主眼が置かれている。既存のゲームはゲームの特性等を語られる際に引用される程度なのでゲームに詳しくない人でも読んでいて関心を持てないということはないと思う。 巻末のゲームリストを転載。 バウンス(BOUNCE) チョアウォーズ(CHORE WARS) カムアウトアンドプレイフェスティバル(COME OUT & PLAY FESTIVAL) ザコンフォートオブストレンジャーズ(THE COMFORT OF STRANGERS) クルーエル2Bカインド(CRUEL 2 B KIND) デイインザクラウド(DAY IN THE CLOUD) イヴォーク(EVOKE) ジ・エクストラオーディナリーズ(THE EXTRAORDINARIES) フォールドイット!(FOLD IT!) フォースクエア(FOURSQUARE) フリーライス(FREE RICE) ゴースツオブアチャンス(GHOSTS OF A CHANCE) グラウンドクルー(GROUNDCREW) ハイド&シーク・フェスティバルとサンドピット(HIDE & SEEK FESTIVAL AND SANDPIT) 地元選出議員の経費を調べよう(INVESTIGATE YOUR MP'S EXPENSES) ジェットセット(JETSET) ロストジュールズ(LOST JOULES) ザ・ロストリング(THE LOST RING) ナイキプラス(NIKE+) プラスワンミー(PLUSONEME) クエストトゥラーン(QUEST TO LEARN) スポアクリーチャークリエイター(SPORE CREATURE CREATOR) スーパーベター(SUPERBETTER) スーパーストラクト(SUPERSTRUCT) トゥームストーンホールデム(TOMBSTONE HOLD'EM) トップシークレットダンスオフ(TOP SECRET DANCE-OFF) ワールドウィズアウトオイル(WORLD WITHOUT OIL)
0投稿日: 2015.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームには人を夢中にさせる力がある。この力を使って、人のスキル習得や望ましい行動を促進する取組みは、ゲーミフィケーションとしてよく知られるようになった。本書はタイトルから、ゲーミフィケーションの本かと思うが、実は、本書はもっと深いところを目指している。現実世界の不完全さをゲームで変革するというビジョンである。 ・ゲームで時間つぶしをすると後から空しくなる ・ゲーマーは不真面目で堕落した人間だ と思っている人は、本書を読むと ・ゲームはただの暇つぶしでなく、人生を楽しむこと ・ゲーマーは新しい世界を知っている先駆者 となるかもしれない。
0投稿日: 2015.10.02ゲーム好きの人にも、そうでない人にも
ゲームは、暇つぶしの、人生の浪費や現実逃避ではない。人間の能力を高め、目的に向かって課題を解決し、世界を変革することのできる道具である。 フィクションばかりで、こういった「啓蒙書」?的な本はほとんど読まないのだけれど、上の主張を、「ゲーム好きの言い訳」に終わらせない、説得力のある理論と実践に引っ張られ、最後まで読み通すことができた。 いわゆるネットゲームから縁遠い自分には、想像できていなかった世界。こういう思想が「学問」として成立していることに驚き。実践がネットワーク(ソーシャル、集合知)偏重と感じることもあったが、「むすび」にある、3000年前のリディア人との違いを読んで納得。ゲームによる未来の変革の可能性とともに、自分の生活、生き方に、何かこういった動きを取り入れたい、と感じさせられた。 ただ、どことなく引っかかり、手放しで頷けないと感じる点も。 ・「言語圏によるコミュニケーションの広がりの限定」 あくまでも、言語を主としたコミュニケーションによる進行である以上、異なる言語圏の間での広がりは難しいのではないか?全世界的な課題の解決に対し、どの程度この手法が有効なのか。 ・「悪意のあるプレイヤーの存在」 前向きな参加者による、建設的な進行が前提のように思える。対立する思想を持つ参加者による、ゲームシステムの破壊に対して、どう対抗するのか。 ・「ゲームデザインの難しさ」 近年の、「教養」としてのゲームプレイヤースキルの社会的な向上については述べられているが、この手法の肝はゲームデザインではないか。ゲームデザインのスキルが向上しないことには、有効な手法を打ち出せないのでは。 とは言え、こういった課題ですら、ゲームの手法で解決できるのでは、と思わせてしまうところが本書の真骨頂。ぜひ一読し、こういった考え方を共有する仲間が増えることを願ってやまない。
1投稿日: 2014.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームは、暇つぶしの、人生の浪費や現実逃避ではない。人間の能力を高め、目的に向かって課題を解決し、世界を変革することのできる道具である。 フィクションばかりで、こういった「啓蒙書」?的な本はほとんど読まないのだけれど、上の主張を、「ゲーム好きの言い訳」に終わらせない、説得力のある理論と実践に引っ張られ、最後まで読み通すことができた。 いわゆるネットゲームから縁遠い自分には、想像できていなかった世界。こういう思想が「学問」として成立していることに驚き。実践がネットワーク(ソーシャル、集合知)偏重と感じることもあったが、「むすび」にある、3000年前のリディア人との違いを読んで納得。ゲームによる未来の変革の可能性とともに、自分の生活、生き方に、何かこういった動きを取り入れたい、と感じさせられた。 ただ、どことなく引っかかり、手放しで頷けないと感じる点も。 ・「言語圏によるコミュニケーションの広がりの限定」 あくまでも、言語を主としたコミュニケーションによる進行である以上、異なる言語圏の間での広がりは難しいのではないか?全世界的な課題の解決に対し、どの程度この手法が有効なのか。 ・「悪意のあるプレイヤーの存在」 前向きな参加者による、建設的な進行が前提のように思える。対立する思想を持つ参加者による、ゲームシステムの破壊に対して、どう対抗するのか。 ・「ゲームデザインの難しさ」 近年の、「教養」としてのゲームプレイヤースキルの社会的な向上については述べられているが、この手法の肝はゲームデザインではないか。ゲームデザインのスキルが向上しないことには、有効な手法を打ち出せないのでは。 とは言え、こういった課題ですら、ゲームの手法で解決できるのでは、と思わせてしまうところが本書の真骨頂。ぜひ一読し、こういった考え方を共有する仲間が増えることを願ってやまない。
0投稿日: 2014.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言で言うと、この本を読んで、ゲームに対する見方が変わった。 コンピュータゲームというと、『引きこもり』と結びつけて捉えてしまっていたが、もっと能動的な能力を発揮しているとも捉えられるという。 電車の中で、ヒマつぶしにゲームしている人達の、あの時間、あの浪費されている空き能力を使うビジネスが思いつけないかなと、常日頃思っていたが、もっと先を走っている人、人達がいた。既に、実験をはじめている。 そこで、学んだこと。お金をあげるのは、必ずしもよくないということ。外的報酬の効果は、すぐに薄れるということ。言われれば当たり前だが、カネというアイデアから離れられなかった。
0投稿日: 2014.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームと人間との史実(リディア人がなぜ飢えを凌ぐことができたかの考察)や現代の様々なゲームが現実世界に貢献している事例まで、Jane氏の取り組みや考察が非常に興味深いです。
0投稿日: 2014.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログどう取り込んでいこうかと考える。うまくすれば、個人や組織のモチベーションをあげることができると思う。
0投稿日: 2014.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ所有欲、権力欲などはゲーム世界で満たし、現実世界に持ち込まない。 ゲーム的思考、枠組みを現実世界に当てはめ、楽しくより良くしていく方向を探る。 ゲームがくだらないと思う人間はまだ私たちの世代にも少なからず残っているが、もう数世代で絶滅するだろう。世界を楽しみながら良く出来るか、共産主義に匹敵する社会実験が始まっているのかもしれない。
0投稿日: 2013.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フォトリ12冊め。ゲーム=現実逃避と認め、ゲームが現実社会より魅力的な理由を探る。それを利用して、現実世界を魅力的に変えていく。リアル世界から仮想現実を見るのでなく、仮想現実に軸足をおいて現実世界を見るというスタンスは、ゲームにはまっていない私にはかなり衝撃的。でもゲームネイティブ世代にとっては至極当然な感覚。子供達の世界観と私の世界観には大きなギャップがあるということですね。子供達がゲームにはまるのを理解するよすがになりました。
1投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームを定義する4つの要素とそれに付加するいくつかのポイントがそろうと、人は能動的に動けたり、本来の目的以上の目的を見出したりするよ、というようなお話と事例。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログアーケードゲームではない、ソーシャルゲームとして、さらに援助行動や平和、協働としてのゲームを描いたものである。日本ではマスコミがほとんど取り上げないゲーム(マスコミの利益とは無関係だからか)についてなので、あらためてやってみることに意義があると思われる。この本でソーシャルゲームの実態がよくわかるであろう。
0投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログソーシャルゲームを体験したことのない人間にとって、本書で述べられているゲームで多くの人や社会と繋がるという感覚は新鮮に感じられた。 ARG、現実代替ゲームの話は面白い。 様々な分野に応用が可能だろう。 自分の身の回りで使えないか考えてみたい。 しかし第3章で述べられていた現実代替ゲームの多くは、プレイヤーを選ぶように思えた。 自ら考え意見を述べる、写真や作品を投稿する、など一般的なゲームとは一線を画している。 すべてのゲームを今現在楽しんでいる人、またゲームに馴染みのない人を惹きつけるような現実代替ゲームの登場に期待したい。
0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログゲーミフィケーションの本の中では一番面白く感じた。 ゲームデザイナーでもある著者が、ゲームから一般社会を見た本。 ゲーミフィケーションとよばれる、現実世界での行為をゲーム化することでモチベーション向上や生産性向上につなげる分野の内容では、最もゲーマー(ゲームをする人)向けだと思う。 特にMMOのような大規模オンラインゲーム経験者だと共感できる部分も多いように感じる。 最近のソーシャルゲームは、ゲーム化の精度を上げる事で「お金」を使わせる事に非常に成功していると思うが、「時間」を使わせる事に成功したMMORPGよりはまだましだと個人的に考えていて、 ゲームが「時間」→「お金」と続く個人を駆り立てるものの向かう先が気になる。
0投稿日: 2013.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログゲーミフィケーションの可能性を最大限活用し社会に還元することについて書かれている。事例豊富だが論文的でもあるため広く読まれるにはエッセンシャル版があってもよい。
0投稿日: 2013.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログゲームリテラシーをもっている人々は、自分自身でご褒美回路を作り出し、ものごとを楽しんで達成することができる。それを人は”才能”と呼ぶ。
0投稿日: 2012.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ120626presentation.onETV2300美人fmCaoiforniaDr. for peace !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --- はじめに リアリティ・イズ・ブロークン 第1部 なぜゲームは人を幸せにするのか(ゲームとは? 「幸せエンジニア」の登場 より満足できる仕事 楽しい失敗とより高い成功への期待 より強力な社会的つながり 自分の存在よりも大きな何かの一部になる) 第2部 現実を作り変える(代替現実の効用 現実生活でレベルアップする 見知らぬ人と楽しむ 幸せハッキング) 第3部 大規模ゲームはどのように世界を変えられるか(エンゲージメントエコノミー 実行不可能なミッション 協働のスーパーパワー みんなで現実世界を救おう) むすび リアリティ・イズ・ベター --- 脳と魂を揺さぶる本書は、あなたの「ゲーム」観のみならず、価値観をも一変させる! ――ダニエル・ピンク(『モチベーション3.0』著者) マクゴニガル以外に、世界をよりよくするようなゲームを開発できるデザイナーは存在しない。 本書は世界を変えたいと思うすべての人々の必読書だ! ――ジミー・ウェールズ(Wikipedia創設者) ユニークなアイデアを思いつくだけでなく、それを実際に世界に影響を与える形で利用できる人物はほとんどいない。 マクゴニガルはその貴重な一人である。本書が説くように、 生活やビジネスや教育の場でゲームを活用できれば、 世界は想像超えた変化を遂げるはずだ。 ――トニー・シェー(ザッポスCEO) 近年、世界のオンラインゲーマーのコミュニティは数億人に達し、莫大な時間と労力がヴァーチャルな世界で費やされている。これは現実に不満を持つ人々による「大脱出」にほかならない。 なぜ人々は「ゲーム」に惹かれるのか? それは現実があまりに不完全なせいだ。現実においては、ルールやゴールがわかりづらく、成功への希望は膨らまず、人々のやる気はますますそがれていく。 そんな現実を修復すべく、ゲームデザイナーの著者は、「ゲーム」のポジティブな利用と最先端ゲームデザイン技術の現実への応用を説く。コミュニケーション、教育、政治、環境破壊、資源枯渇などの諸問題は、「ゲーム」の手法で解決できるのだ。 世界最高のイノベーターと評されるゲーム界のカリスマによる刺激的社会改革論。 世界最高、最先鋭のゲームデザイナーによる刺激的社会改革論。
0投稿日: 2012.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ私のブログ http://pub.ne.jp/TakeTatsu/?entry_id=4380333
0投稿日: 2012.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ***** ゲームとは、取り組む必要のない障壁に主体的に取り組むこと。 そのプロセスにおいて自らの能力を精一杯に発揮することが フロー状態を作る。 ***** ゲームに取り組むことで得られるのは、 より満足のいく仕事、 より高い成功への希望、 より強い社会的なつながり、 より大きな存在の一部になること。 いずれもが根源的な欲求に根ざしている。 ***** 自らの活動を「ゲームとして構成する力」が身に付けば、 ものすごく生産的に自分の行動をコントロールできるように なるのではないか。 内発的に動機づけられ、 ゴールが明確になっており、 実現のためのプロセスが明確になっている。 *****
0投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これまで考えたことの無いテーマで、非常に興味深く面白かった。 自分に役立つことが在るだろかと考えて読み始めたけれど、「ひとり」っていう感覚では書かれてない気がする。また、読んでいる中で、もっとお金になることを考えなくちゃ続かないんじゃないのか?と思うこともあったけれど、そこは著者はきちんと否定している。むしろNPO的な活動をいかに成功させうるかという観点のような気はする。 ゲーミフィケーションのこれからに関しては、より関心を持ってみていきたいです。 あと、憶えておきたい引用をメモ・・・ 「何かを強制的にやらされているとしたら、もしくはしぶしぶやっているとしたら、本当の参加ではありません。 結果がどうなるかに関心を持っていないとしたら、それは本当の参加ではありません。 何かが終わるのを受動的にただまっているとしたら、それは本当の参加ではありません」 ・・・まったくです。反省。 「現実の問題を自主的に取り組む障害に変えることで、私たちは義務として取り組むときより純粋な関心、好奇心、動機、努力、楽観主義を始動させた。架空のゲームの文脈で現実生活の行動を変えられるのは、変えようという決意を取り巻くネガティブなプレッシャーがまったく無いからだ。ポジティブな緊張感と、より満足感や達成感が得られ、社会的で意味のある形でゲームに参加したいという自分自身の欲求だけで動いているからだ」 ・・・うん、興味深い!
0投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ゲームや集合知の力を色々な角度から書いた分厚い本。 ゲームを使うことで日常生活がより幸せになり、大切な人達ととより強いつながりを維持し、がんばったことに対してより大きな見返りを手にし、現実世界を変える新しい方法をゲームは持っているとの事。 下記、本書で上げられた14の項目 1.取り組む必要のない障壁に取り組む 2.感情の活性化 3.より満足のいく仕事 4.よりよい成功への希望 5.より強力な社会的つながり 6.壮大なスケール 7.心から参加すること 8.意味のある報酬を、それがもっとも必要なときに得られるようにする 9.見知らぬ人々ともっと楽しむ 10.幸せハッキングをしよう 11.接続可能なエンゲージメントエコノミー 12.より多くのエピックウィン 13.一万時間の協働 14.大規模多人数参加型未来予想
0投稿日: 2012.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終えた。500p以上の本で、翻訳が読みづらくてわかりにくい。読み進む速度も遅くなる。何とて長い。 内容は、総じて面白いと思います。ゲームが未来を創るという発想はありかなと思いますが。。事業化についてもうすこし論述がほしいかなとおもいました。
0投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の時からゲームが好きで、『新ネットワーク思考』や『シェア』、『シンク』、『スモールネットワーク』辺りの創発系や最近はやってるゲーミフィケーションから、ポジティブ心理学を通ってから本書を読んだので、完全に自分の考えをまとめられた感覚。 これからの未来に期待ができるしそんな未来を作りたいと感じさせる本。 そこらへんのゲーミフィケーションの本よりかなり刺激的な経験を提供してくれます。
0投稿日: 2012.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ退屈で憂鬱な現実世界をよりよくするのに役立つゲーム。短時間で安価に、しかも劇的に問題を解決する。人々が従来ほど苦痛を感じずに現実世界をもっと楽しむ手助けし、ある経験が私たちとって難しいとき、挑戦しがいのある目標を与え、ポイントやレベルや実績を記録し、バーチャルな報酬を提供することによって、その経験をより容易にすることができる。こうした内発的報酬を生み出すゲームの効用を事例を挙げて解説。 参加型ネットワークを利用した、エンゲージメントエコノミー(関わりの経済)圏の中で、参加者の満足度を上げる仕組みにも言及している。そのため、SNSやコミュニティーサイトを企画・運営する時の参考として読んでみるのはよいだろう。 ただ、全体を通して冗長的な印象があり、個別事由に関しては示唆に富む箇所も多いものの、、500ページを超えるハードカバーを読んだ充実感は得られなかった。 事例を絞りエッセンスをまとめた新書サイズの本があるとよいのでは。
0投稿日: 2012.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログp441「ゲーム開発者がやがてノーベル賞を受賞するようになる」...!!!確かにその可能性をみせてくれたプロジェクトがあった。
0投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく「一般意志2.0」の描いていた、 未来像の有用な手立てがあるんではなかろうかという予感のもと読んだ。 そしたらすげー面白い。 「モチベーション3.0」にも通じる、 「やる気」をどう引き出し持続させるか、 というテーゼにゲームからの回答を出している感じ。 特にWOW(World of Warcraft)の「フェージング」という視覚効果の話が面白い。 達成度に応じて同じ場所でも見え方が異なるシステムらしいのだが、 これって、 「○○の影響(○○の部分は適宜入れてください)で世界の見え方(考え方)が変わった」 というような劇的な人生経験での変化をわかりやすく視覚的に表しているってことで、 わたしでいうところの「いい本」を読んだ時の快感を、 クエストを達成するごとに味わえるわけである。 こういうシステムがあることをこの本で初めて知ったけれど、 よくよく考えてみると昔からRPGで、 隠された宝箱が見えるようになるとか、 街の人のセリフが変わるとかあったから、 その起源は案外古いのかもわからない。 少々気になったのが、 フィードバックをすぐに返すようにする、 というのが効果的なのはわかるのだけれど、 そういう傾向が、 「我慢出来ない」最近の無時間モデル的消費者思考からくるのか、 それとも元々人間は「そういうふうにできている」のか、 どっちなのかなぁ、と。 最後のほうで、 今現在の様々な問題のソリューションを、 ゲームのプラットフォームを用いて導き出しましょう、 てなことが書いてあるのだけれど、 うーん。 ちょっと得心いかないんだよなー。 なんなんだろ、このモヤモヤ。 ただのルサンチマンかしら。 地球を管理するという、 傲慢な姿勢が気に入らないのかしら。 あとは、 最後のほうで気づいたけれど、 どうやら文章があまりお上手でないのではないだろうか。 非常に単調に感じられる。 この本を読んでふと、 そういえば昔はゲームデザイナーになりたかったなぁ、 てなことを思い出した。 しこりの残る本。 とりあえずはペンディングしとこう。
0投稿日: 2012.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「万国のゲーマーよ、集結せよ! 世界を変えるのは君たちだ」と、なかなかの煽りの言葉が帯に綴られている。ゲームにおける人の行動原理を現実世界へ適用して、世界を変えてしまおうとする野心的な内容で、かなり興味深いものがあった。実は期待していた内容とはかなり違った。表紙のカラーセンスがソーシャルゲーム関係の本と似ていたので、てっきりその仲間だと思ったのだが、大きく裏切られた。 "World of Warcraft" などのゲーマーの話から始まり、最後は地球が抱える問題すらも解決してしまおうというのだから、ケータイの中でポチポチやってる話とはスケールが違う!! ただ、ちと長いので、読了するのにけっこう労力がかかってしまった。正直、「くどい! (^^; 」とも思うのだが、書かれていることはとても大切なことだ。旧来の (生産性を下げるばかりでおもしろくない) 管理モデルに辟易しているオレとしては、人が能動的に行動するモデルを、ゲームシステムから学んで社会に組み込みたいと考えている。そのためには、本書のような内容が一般に認知されるようになるのが手っ取り早いので、ぜひ、一読されたい。 ゲーマーは膨大な時間をゲームに費やす。今や世界中で週に 30 億時間がゲームに費やされているという。誰に強制されたのでもなく、自らの能動的な行動としてだ。「そりゃぁ、ゲームだからだろう。」では思考停止だ。人々の能動的な行動を促すために、現実をゲームのようにデザインするにはどうしたらいいか? …を考えれば、社会はもっと良いものに、そして面白いものになるではないか。原題は "Reality is broken" で、おそらく現実と仮想 (ゲーム) とを区別する意味が薄れていることを込めたタイトルなのだろう。実際に著者のジェイン・マクゴニガルはそのようなゲームデザインをいくつも手がけていて、本書に事例も登場する。ジェインがデザインしたゲームは、簡単で楽しく、そして遊んでいるだけなのに、大きな効用をもたらしているようだ。「注目すべきトップ 10 イノベーター」に選出された彼女の活躍が、これからも楽しみだ。 ふっと気付けば、スクラムに代表されるアジャイル開発は、ゲーミフィケーション理論を活用した開発手法だ。アジャイル開発の本質を理解するためには、実は本書が近道かもしれない。
1投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ゲームの社会貢献的な側面に注目して書かれた本。ゲームの持つ社会的価値、力を肯定。全てのゲームファンに読んで欲しいおすすめの本。 ゲームは現実よりはるかに楽しい、現実はゲームに比べたらつまらないと思ったのなら、これはチャンス。現実はゲームのようにすばらしくなる可能性を持っている。いかに現実の世界を魅力的にするか? 優れたゲームに現実改革のヒントがある。 ・ゲームに対する批判、差別的な意見は多い。しかし、私達はゲームからたくさんのことを学べる。 ・優れたゲームにはプレイヤーの注意、好奇心をひきつけ続ける仕掛けがある。モチベーション維持の方法論は、現実の仕事、生活改善にも役立てることができる。 ・ゲームは、現実では満たせない人間のニーズを満たすことができる。 ・ゲームを長時間していると無駄なことをしたという気分によくなる。けれど、ゲームには現実に役立つアイデアがたくさん詰まっている。 ・ゲームは失敗を楽しさに変え、私達に明確で、達成可能な目標を次々与えてくれる。もっと努力してレベルを上げようというやる気を引き出してくれる。 ・ゲームは古代ギリシアの時代より、現実生活をよりよくするという機能を持っていた。ゲームでストレスを軽減することプラス、ゲームのアイデアを現実に応用することも可能。人類が直面している社会問題、環境問題、国際問題の解決にゲームのアイデアを応用可能。 とにかく福音的な本。ゲームにはまってもったいないと思った後悔を、あれは学ぶ場だったんだと逆転的に解釈できるようになる。
1投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログゲーマーでありゲームデザイナーである作者が、ゲームの効用について力を込めて賛美している本ですが、単に定性的な効用や可能性を説くのではなく、これまでにヒットしたゲームや、作者が意図的にデザインしたゲームが、実際にどのようにプレイヤーの社会性を高め、問題解決能力の向上に貢献してきたかを、豊富で具体的な例を挙げながら論を進めていることで、非常に説得力を感じました。 面白いゲームは確かに非常に中毒性があるため、それをやりこむことでそのゲームを解くためのスキルは短期間で飛躍的に向上することは間違いないのですが、しょせんゲーム作者がコンピュータプログラムに盛り込んだ制約のある条件の下でしかそのスキルは成り立つものではなく、現実世界のきわめて複雑な問題解決への適用・応用には限界があるのではないかと思っていましたが、この本で作者が取り上げている例の多くは、ゲームで一番ポピュラーな単純1人対コンピュータ対戦型ではなく、人間同士の対戦型あるいはプレイヤー協働でのコンピュータ対戦型のものであり、また、モニタ画面の中だけで完結するものでさえなく、他人とのリアルなコミュニケーションによってそのゲームの解決を図らなければならないものであり、なるほどこれなら先ほどの「限界」は大きく超えているなと納得させられました。 広告やマーケティングにゲーム的手法を導入して効果を高めるというのなら、これまでも広く行われてきたことで特別の目新しさはありませんが、作者の考えていることはそれをはるかに超え、エネルギー不足や貧困や気候変動対策といった、本物の巨大で長期の社会問題の解決に、ゲームの手法がなぜ、どのように役立つのかを真剣に検討しているところで、読んで本当に驚かされました。 僕自身もゲームは好きで、シングルプレイヤータイプのものは気軽に楽しめるエンターテイメントとして今までいろいろやってきましたが、作者がこれから増えてくると予言する「社会参加型ゲーム」といったものの存在には、その発生にすら全く意識はいっていませんでした。今後は気をつけて注目してみたいと思います。
1投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終える、ほぼ1ヶ月。いわゆる読んでみたら相性が悪い本というのもあるが、これはその1つか。正直、全体500頁のうち最後の100頁強は斜め読み。 本題に関係ないところでは、21歳までに1万時間を熱中したものから天才が生まれるということ(マルコム・グラッドコム。この人がどういうレベルのヒトか知らないが、そのフレーズが引用されていた)。それで言えば、私は中学高校のバスケットボールが天才に最も近かったか(ちょっと苦笑)。 さて、この本に戻ると最後の章は「みんなで現実世界を救おう」というタイトルで、その中でworld without oilというゲームの例があったが、「もし〜だったら」というのをリアルの世界でやったのはまさに2011年の日本人だったような気がして(もし、とんでもない震災が起こったら、もし、電気が使えない世の中になったら)、それを現実で実行していった実績を前に、そんなことをゲームと結びつけて語って欲しくないな、とも感じる一方で、確かにスマートホームやスマートシティーというコンセプトってとってもゲームちっくな気もして微妙な読後感でした。 私としては、もっとヴァーチャルワールドとは何かを突き詰めて欲しかった(中途半端にバーチャルワールドを語っている点。最後はリアルに持ってきたか、、という感じ)。
0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になっているゲーミフィケーションという考え方をビジネスのみに利用するのではなく、社会問題に取り組むことや個人の問題を解決するために用いたりするなど、様々な事例を紹介してくれている。ゲームをつくるときに用いられる考え方をもっと広い範囲で応用していこうというのがこの本の基本的な考え方である。現実社会はゲームの社会と比べ、かなり攻略しにくい。達成感が得られにくい。そういった問題をどうにか解決していこうという著者の姿勢にかなり共感できる。これほどまでに体系的にゲームと現実社会を結びつけている本はないと思うので、一読をおすすめする。
0投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中をゲーム化(ゲーム・システム良い部分を利用)することで世界を変えられる。 ARG(代替現実ゲーム:ゲーム開発ノウハウとネットやメディアを利用し、現実世界でコミュニケーションを促したり、行動させたり、協力させたりするゲーム)によって社会を変えていけるのでは…と著者は考える。 つまるところ、ゲームのエンジニアたちによるゲーマーのモチベーションをくすぐる手法、著者からみたゲーマー達の「力」とそれをどう生かせるかということ、そして実際に行われたARG(もしくはそれに準ずるもの)の紹介が本書の中心。 興味深いゲーム事例と、何故人々がゲームにはまるのか、その特性はなにでどう生かせるのかということをわかりやすく、そして応用もしやすく紹介しており、多くの可能性を感じさせる。 ただ、個人的には最終章の事例はただのブレインストーミングに陥ってしまっており、また目的の壮大さと成果事例のアンバランスさで尻すぼみになってしまった感があるのが残念。 またいくら現代世代に有効とはいえモチベーションを保ってあげる仕組みを準備しなければならない社会とすることは正直どうなのかと感じた。それゆえ「社会を変える」のではなく「人を利用する・動かす」為のゲームノウハウと考えるほうがしっくりとくる部分もある。
0投稿日: 2011.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログここ4,5年で一番よかった本。 脳が刺激される。僕もやってみたいと思ってしまう。ゲームを使えば本当に現在の人類の抱えている問題を解決できるかも知れない。より沢山の幸せを生み出すかも知れない。 かもしれないという表現を使っているが、ほぼ確実にできると思っている。 この本を読めばそう思えるのではないでしょうか。 ゲームといってもビデオゲームだけを指すわけではない。 この本ではネットゲームのそれを主に指し、 壮大なゲームの世界を大規模な人数で協力プレイしたり競争したり。 「ゲームなぜこうも人の心をつかむのか。」 それを研究してきた著者が、心をつかむゲーム構築のノウハウを使って現実世界を良くしよう。良く出来る! いくつものゲームが紹介されているが、どれも興味をそそられるし成果も残している。 ゲームで未来をつくるのは ゲーム業界の人の妄言でも希望でもなく、実現可能でかなり確実な方法なんじゃないかと思う。
1投稿日: 2011.11.07
