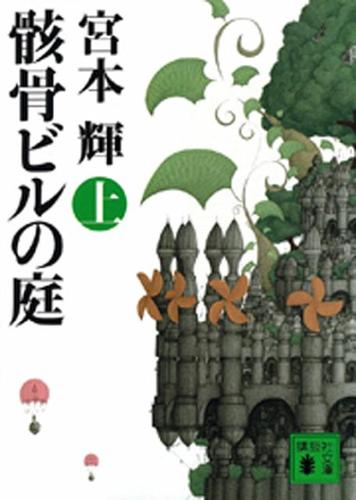
総合評価
(32件)| 13 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本輝さんで大阪が舞台、もちろん会話も大阪弁。 期待せずにはいれない、のだが何か物足りない。 エピソードごとは良いがウネリにはならない。 ハードルを上げすぎてるのかな。とりま、下巻を読んでみるか。
0投稿日: 2025.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが宮本輝の作品。ユーモアに富んだ登場人物、それらの難しい人間関係の様子をうまく表現してて、どんどんストーリーに引き込まれていく。 そして相変わらず、美しい日本語(大阪弁)が秀逸すぎる。 この勢いで下巻も一気に読んでしまいます。
0投稿日: 2024.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ大阪や日本中に骸骨ビルというものが実在していたのかもしれない。戦災孤児の証言を元に話が進められている。詳しい感想は下巻にて。
5投稿日: 2023.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ孤児たちが住み着いた「骸骨ビル」、そこの住人を立ち退かせるため、主人公の八木沢三郎がやって来た。八木沢で三人目であるが、他の二人は何故、住人の立ち退きが出来なかったのか。上巻ではそこの住人と八木沢との出会い、住人の自分史などを混ぜながら物語は下巻へと続く。★閑話休題★阪急電車の十三(じゅうそう)駅は京都線、神戸線。高塚線の三線が交わる駅。小生がサラリーマン時代に神戸方面、大阪方面など日帰り出張時には、この十三駅で途中下車し、駅前の飲み屋で同僚と時間を潰した懐かしい場所。書き出しの風景で思い出した。
1投稿日: 2022.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦前に建てられた英国調のビルはGHQに接収され、屋上にアンテナを張り巡らした姿が骸骨に見えると、いつしか骸骨ビルと呼ばれるようになった。 この建物をマンションに建て替えようという話が持ち上がるが、ほぼ孤児院としてそこで育った人々は今も居座っており、主人公の八木沢が彼らを立ち退かせるために送り込まれる。けれどごくごく一般人の八木沢は、その住民たちの生い立ちを聞くうちに次第に感化されただ骸骨ビルで住むだけの人になる。 戦後日本の光と闇が綯い交ぜとなった生活史が興味深くもっと知りたくなる。まだ続きがあるのが嬉しい。 ジャンルはなんなんだろう?他ではあまり経験できない読み心地。犯人がわからない人物から脅されたりとミステリーの要素もある。 ただ、建物の持ち主が語学学校に作り替えようとした夢を諦め、子供たちの生活のためにビルとその庭を改変した話が基礎にあり、暖かい結末が約束されているようで、かなり悲惨な話でも安心して読んでいけるような。
0投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は何のために生まれてくるのか?明確に答えられるものでないと承知していたが、パパちゃんは即答し、断言したのだ。自分と縁する人たちに歓びや幸福をもたらすために生まれてきたのだ、と。 なるほど。宮本輝の小説には、金言があります。
0投稿日: 2020.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦災孤児たちの半生とそれを支えた復員兵の不思議な関係性。 主人公は元メーカーの営業マンで、彼の日記の書き方や行動、考え方は私が見習いたいと思う部分が多々あった。 大阪弁が人間らしさというか、登場人物の性格をよく表現していると思う。 不思議な筋書きなのに、あまり違和感なくどんどん読み進めてしまうのは、文体のなせる技か。
1投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ四十七歳でサラリーマンをやめ、第二の人生に向けてある仕事に就いた八木沢省三郎。その仕事は土地開発会社で、大阪に戦前からあるビルに住んでいる人々を荒立てず、穏やかに転居をさせると言うものであった。 そのビルは、妻のある男が建てその夫婦の死後、男の愛人の子・杉山轍正が相続したものであった。彼がフィリピン群島にて戦争を生き延び、ビルで住み始めた時、そこには戦争により孤児となった姉弟が入り込み、何とかその生を繋ぐように日々を生きていた。彼はパパちゃんと呼ばれながら、長短ありながらも四十人以上もの孤児を、病気で生家からでざるをえなかった茂木と共に育てていった。 だが、一人の孤児の裏切りにより、世間に批判される中で心筋梗塞で死亡する。パパちゃんにかけられた冤罪をとき、世間に知ってもらうべく、茂木やかつての孤児たちは動き、ビルに居住や仕事場を設けているのだった。彼らに対し、八木沢は…。 主人公が大学で師事した、中国古典文学の老教授の言葉。 「優れた師を持たない人生には無為な徒労が待っている。なぜなら、絶えず揺れ動く我儘で横着で臆病で倣慢な我が心を師とするしかないからだ。」 先生だけじゃなく、先輩とか友達、同僚にも当てはめられるなあと。様々な師によって、良い人生に導かれている。 骸骨ビルに住むナナちゃん(本名小田勇策、男、でも心は女の美人、43歳)が、おかまバーのママに言われた言葉。 「自分を磨け、磨くのは、見映えと脳味噌だ、…私たちお化けは頭を磨かなきゃどうにもならない。見映えってのは、目鼻のつき具合とは別の問題だ。」 私も感じ入る言葉でした。 パパちゃんが、孤児だった高校生の、人間は何のために生まれてきたのかと言う質問に対して即答・断言した言葉。 「自分と縁する人たちに歓びや幸福をもたらすために生まれてきたのだ」 ここに書いた文だけだと、ありふれたものだけど、そこまでの物語で描かれたパパちゃんや孤児を思うと、あらためて考えさせられる。 心に響く言葉や人物の生きざまが描かれていて、引き込まれる作品。 まだ、下巻が残っている。最後どうなるのか、楽しみ。
2投稿日: 2017.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大阪の十三というところに戦前から建っていた堅牢でイワクありげな建物「骸骨ビル」の除却という業務に、ひょんなことから関わった主人公が、様々な人間模様、それも戦前戦後のどさくさで、好むと好まざるに関わらず、悲壮的な宿命を負った戦災孤児の人間模様を絡めながら、話は、読者を引き込んでしまいます。 人間置かれた環境で、様々な職業につかざるを得ない、インフォーマルな世界を作者独特のタッチで書き進む。 主要な登場人物がこのビルの歴史的に背負った背景を語っていくというスタイルだ。 そして、除却を請け負った主人公の心の動くも同時進行で描かれていく。 そして、下巻へと続いていこのである。
1投稿日: 2017.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ広い意味での戦災孤児と、それを育てた二人の男を巻き込んだ事件を、平成の世にヤギショウの聞き語りで進む物語は、初っ端から怪しい雰囲気を醸し出しながら進んでいく。ヤギショウは標準語、骸骨ビルの住人は大阪弁。彼らの語りを慣れない関西弁のイントネーションで読み進めるのは大変だ(笑)さて、ヤギショウと彼の親族は無事でいられるのか? 下巻へ突入だ!
1投稿日: 2017.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだか哲学的な内容やら、ひやひやする内容やらありつつも、魅力的な人達ばっかり出てくる。 それと美味しそうな食べ物が沢山出てきてお腹空く。
1投稿日: 2017.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
内容(「BOOK」データベースより) 大阪・十三に戦前からある通称「骸骨ビル」。戦後の混乱期に住み着いて、オーナーの阿部轍正と茂木泰造に育てられた孤児たちを立ち退かせるために三人目の担当者として送り出まれた八木沢省三郎は、一筋縄ではいかなそうに見える彼らの話に耳を傾けるうちに、困難だったであろう日々を思い描くようになる。 評価は下巻にて
1投稿日: 2016.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日記形式。 骸骨ビルの管理人として過ごした数カ月間。 そこに住む人たち、そこで育った人たちと関わりながら、退居させることが求められている私。 さてさて、どうなるものか。 元々ことビルを所有していたオヤジが子供(戦災孤児)に伝えた言葉、人間は何のために生まれてきたのかの質問に、自分と縁する人達に歓びや幸福をもたらすために生まれてきたのだ。 こういう質問に、明確に答えることができる人間になる。
1投稿日: 2016.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ大阪・十三にあるビルに戦後の混乱期に住み着いた孤児たちの立ち退きにまつわる話。 そのなかに、料理の話あり、農業の話あり、本筋よりもそちらの方に興味が行ってしまった。京都のおいしい七味とごま油と醤油で食べるおうどんがなんとも 美味しそう。
1投稿日: 2014.01.15悲しいけれど温かい本
宮本さんが「にぎやかな天地」でちょこっと触れていた人物が、主人公になったのかなあと感じました。 彼の作品には、「他人の子を育てる」というシチュエーションがよく登場しますが、これはその際たるものでした。終戦後、巷にあふれた孤児たちを育てた一人の男性の物語で、彼に育てられた子供たちが大人になってからのお話です。その一人ひとりが非常に個性的で、彼らが話す大阪弁と、主人公の東京言葉が優しく絡む感じでした。 悲しみがあふれているけれど、なぜかじわーんと胸が熱くなる本でした。
1投稿日: 2013.12.27生きる力が湧いてくる良作
「骸骨ビル」と呼ばれるビルに集い、戦後の激動期を生き抜いた子どもたち、そして彼らを守った大人たち。 ビルの立退き担当となった主人公の目を通して、彼らの生き様が徐々に明らかになっていく。 さすが宮本輝、と感じずにはいられない、深く人間を描いた、重厚な物語。
0投稿日: 2013.10.10猥雑と静謐
20代のころに、よく宮本輝さんの小説をよく手にしていましたが、いつしか読まなくなっていました。 電子化されて、手軽になったので、読んでみました。たくさんの人物が出てきて、その人たちの語られる人生にひきつけられました。 戦争から続く、それぞれがたどってきた人生は猥雑なのに、読み終えると静謐さが感じられます。 それは、聴き手であり、物語の書き手でもある主人公の態度が影響しているのだと感じます。
0投稿日: 2013.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ純文学と大衆文学の明確な違いもよく分からないし、そもそも分ける自体がナンセンスなのかも知れないが本作品は純文学よりな気がする。損得を超えた無償の愛、使命感、嫉妬、生への執念等 人間臭さが滲み出ておりジワジワくる。終わりもスッキリ、すっと入ってくる。もう少し人生の経験を積んでから再読したい。
1投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本輝、予備校生だった二十年前に出会った作家。模試の国語で『星々の悲しみ』が出題されて以来の付き合い。大学二年くらいまでの間に、当時出版されていた作品の、ほぼすべてを読んだと思う。 それからは数年に一冊、なんとなく手に取り、毎度のようにしっくりと身体に染み込んでくる感覚を味わってきた。 たぶん、森の中の海かなんかを数年前に読んだ、次がこれになった。
1投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「わたしが畑仕事で知ったことは、どんなものでも手間暇をかけていないものはたちまちメッキが剥げるってことと、一日は二十四時間がたたないと一日にならないってことよ。その一日が十回重なって十日になり、十日が十回重なって百日になる。これだけは、どんなことをしても早めることができない。」ナナちゃんの話
1投稿日: 2013.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
屋上に何本もの物干し竿が突き出していて、それが人間の骨みたいだったので、骸骨ビルと呼ばれている建物に子供の頃から住み続けている人たちの物語です。 宮本輝さんの作品は、いつも初めはとっつきづらいけど、徐々に世界に入り込んで抜けられなくなります。
1投稿日: 2013.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ教訓的であり、人が誰かのために生きることの尊厳を改めて考えさせられた作品だった。2度読んで2回ともおもしろかった
1投稿日: 2012.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ日曜朝のFM、小川洋子さんのメロディアスライブラリーでこの本を取り上げていた。表紙のバロック風というか不気味なイメージにも惹かれ手に取った。 表紙のイメージとは違って、大阪十三のゴテゴテしたような、侘しいようなビル。かつての孤児達の職業は猥雑さが満載だが、スッキリ書かれているので、いやらしさが無い。そのシーンを想像すると、かなり珍妙な風景も多く、笑ってしまう。女性にはこの本お勧めし辛いな。 戦後捨てられた子供達と子供達を育てた2人の男の物語。主人公はビルの明け渡しのために乗り込んだ中年。肝が据わっているのか、いないのか、良く判らない。彼ら一人ひとりが語りだす話を聴きことが小説の眼目になっている。だから、物語は全然動かない。にもかかわらずジワジワ沁みてくる。 料理を作ったり、庭仕事をすることが、如何にも地に着いた仕事のようで、物語に深みを与えている。 この物語はどう収斂するのかと思いながら読み進める。何か起こったようでもあり、何もなかったような気もする。それでも深い満足を感じながら本を閉じた。 何が言いたいのか判らないレビューになったが、今年一番良かった本になると思う。 これから、茂木が何を求めていたのか、ゆっくり考えてみようと思う。
1投稿日: 2012.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本輝さんの小説。輝さんの小説は古めかしいが、安心して読める。『骸骨ビルの庭』も上下だが、けっこう読みやすく、それほど長く感じない。 これは十三が舞台。輝さんは阪神電車や阪急電車の沿線あたりを舞台にするイメージがある。スポーツ新聞を読むおっちゃんがいつもでてきそうである。競馬場や競艇場の雰囲気もいつも思い出される。『幻の光』で阪神の杭瀬や大物のあたりが描かれていたのを過去に読んで、そのイメージがいつもかぶるようである。 この小説の語り手であるヤギショウさんは名作を読みつつ、人生を考えている。例えば『史記』とか。こういうところもいい。 古いビルが醸し出す雰囲気がなぜか昔から好きで、「骸骨ビル」もいいなと思ったのでした。
1投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ余計な言葉はひとつもない うつくしくないものはたくさんある それでもうつくしい それから ごはんがとてもおいしそう
1投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
母からの課題図書。 私にとっては、初「宮本輝」である。文章や組み立て、とてもうまくて引き込まれ読んだ。 舞台は阪急十三界隈で、たぶん今は無き北予備の付近と、阪急沿線出身者にとっては馴染みのある雰囲気が懐かしい。北予備には夏期講習とかでお世話になったなぁ… 話は、骸骨ビルを買った会社からそこに住み着く住人/孤児たちを退去させる役目をおった主人公がなぜ彼らがそこにいつづけるのかを調べる過程で、戦争で孤児となった子供を引き取り育てたパパちゃんこと阿部と茂木と孤児達の関わりを知っていくことになり… パパちゃんの戦場での不思議な体験と「光」には、宗教的なというより、すべての人の心の奥底にある「善なるもの」というような、もっと単純ででも暖かいもののように感じる。不思議と唐突な感じを受けないのも話に引き込まれているからだろう。 損得ではなく、しなくてはいけないと思ってしまったこと、をやり抜く、それを達成した時のある種の高揚感が胸に残った。やらないとダメなんだなぁ、と思いつつ。
1投稿日: 2012.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ通称「骸骨ビル」戦後の混乱期に住み着いてオーナーの阿部轍正と茂木泰三に育てられた戦争孤児たちを立ち退かせるために担当者として八木沢省三は送り込まれる。 阿部轍正の汚名をはらすまではでていかない。という茂木と子供たち。 終戦後、大人一人でも生きていくのが大変な時代に血のつながらない子供、それも一人や二人ではない子たちを育てる決意。 自分の人生より子供たちを育てることがなぜできたのか。 阿部と茂木、そして子供たちの絆が読んでいて胸にぐっとくる。
4投稿日: 2012.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ立ち退きを完了させるために、戦争孤児たちが集まるビルにやってきた男が、住人たちとの交流の中で主の慈愛を再確認して行く話
1投稿日: 2012.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後の日本に溢れた孤児たちと、その孤児たちの、それぞれ「父親」と「母親」の担ってくれた二人の男の物語を主人公の目を通して辿っていく物語。大人になった孤児たちの個性が強くてすごく面白く、また心温まります。
2投稿日: 2012.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログうむ。 じわじわくるな。 なんだろう、特にうわぁとかおおっとか激しく気持ちが動く訳じゃないんだけど、じわじわっときいてくるんだよね… 下巻まで読んでしまった後なので、内容がかぶってるかもだけど、主人公がキャベツ刻むのプロ並みで免許皆伝レベルだったり、オムレツのトロトロ加減が絶妙だったり、ひろこさんの教えてくれる料理をカンペキにマスターしたりってのが、村上さんの登場人物的でなんだかなーって思った(苦笑) 要は私が、お料理上手な男性がムリなのかもしれん… (自分が料理苦手だからって)
1投稿日: 2012.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ心に響くお話でした。 すべての登場人物に奥行があって、引き込まれました。 戦争によって、孤児とならざるを得なかった子供たち、 戦地での体験に、心縛られる大人たち、 誰もが必死で生きねばならなかった終戦直後の暮らし。 ただ生きるのではなく、人として崇高に生きる事の大切さ。 魂魄…魂は心だけではなく体にも宿るもの。 自分を変えようと思ったら、何度も何度も挫折を繰り返しながら、それでもなりたい自分を目指して、続けて行く事。 色んな事を考えさせられました。
2投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり旅には宮本輝と決まっている。 文章がうまいので、心乱されずすっと本の中に入っていける。 本作はすっと読める。三時間かからず上巻は読了。 そこまで盛り上がるものはないが、じわじわくるのが宮本輝だから、下巻が楽しみだ。 ボディーブローのように、じわじわと、読み終わってから考えたり、何か胸に残ってしまって人生に問いを投げかけてきたりするのが、宮本輝のいいところ。
1投稿日: 2012.01.07
