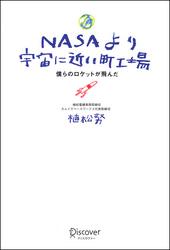
総合評価
(148件)| 72 | ||
| 43 | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、北海道の赤平という片田舎にある町工場の社長の実体験がもとになっている。当初、誰にも期待されなかったロケット開発が幾多の困難を乗り越えて、米国のNASAにも注目される事業となったさまは感動的である。
2投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ終始響きっぱなしだった。 最近読んだ中でも一番良かった。 「夢」って実現しなきゃいけないものなのか。という言葉にハッとさせられた。 夢はあるのに「金がない」「時間がない」「子育てがあって」「仕事が忙しい」とか勝手に諦めてて、勝手に【どうせ無理】を作り上げていた自分がいた。 奥さんと二人で10年以内にドイツのクリスマスマーケットに行く。 一般サラリーマンの自分がそんな夢を実現したいと思っている。 子供の学校はどうするのか、親の介護の可能性はないかとか考えてしまうと、行けるかは分からないけど、そのためには何ができるのかを考えてみよう。 きっとできることはあるハズ。 そう思うと何だか楽しみになって、フッ切れた気持ちになれた。 ここ近年の中で1番の良書だった。
0投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログロケットを作っている北海道の社員20名の小さな会社の社長さんの本 どうせ無理という言葉をこの世からなくすために頑張っている 普通のロケットは火薬を使っているので危険物 管理コストが必要 植松さんのロケットは燃えにくい 燃料を使っているので危険物 管理コストが不要 前までは 人工衛星はすごく大きかったけど今はデジタル化が進んで人工衛星 も小さくなった なので そこまで大きいロケットも入らなくて 今は小さいロケットでも需要がある ぶどうを育てている友達がワインを作りたいけどワインを作るためには ステンレスでできた ドイツ製の素晴らしい装置が必要だと言って悩んでいた その人にワインはいつからあったか尋ねた すると 紀元前からあるよ と帰ってきた 紀元前はドイツも ステンレスもないよね と言った 最新の設備だけを見ていたら自分ではできないような気がする けれど 例えば自動車も飛行機も最初は手作りで作られた
1投稿日: 2024.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ暇を暇と捉えるか、チャンスと捉えるか。 給与に似合う仕事をするか、仕事に似合った休養をもらう努力をするか。 興味の芽は摘まない。
1投稿日: 2024.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログどうせ無理という言葉をなくし、だったらこうしたらという言葉に変えたいと。 息子がこの方の講演を聞いて感動し、私もYouTubeで講演を聞いた上で、本書を読んだ。 赤点ばかりの子供時代でも、大好きな紙飛行機や工作が支えとなり、植松電気の社長になって、金属の仕分けをする重機の磁石の開発、夢見ていたロケットの開発。 作者のこれまでの人生を踏まえた重みのある言葉。 本書で、息子に少しでも灯りを灯してやりたい。
5投稿日: 2023.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どうせ無理」をこの世から無くす。 そのために宇宙に、チャレンジする。 感動しました。 植松さんだけでなく、多くの企業家が、新しいチャレンジを日夜続けています。 日本中で、数々のドラマが繰り広げられています。 そのひとつひとつにスポットライトが当たってほしいです。
2投稿日: 2023.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもが植松さんのロケット教室を受けたことがあり、この本を手に取りました。 とても心に残るフレーズが沢山あります。 是非一度読んでいただきたい本です。
1投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年以上前の本なのに、今の時代に向けて書かれたかのような。あまり変わってないんだな。 後半は熱いメッセージの連続。できないことなんて、ない!
2投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ北海道の町工場から、自腹でロケット開発に取り組む植松さんによる自伝的ビジネス書。丁寧で穏やかな語り口調の中にも、仕事や夢に対するとてつもないパワーが感じ取れます。子ども向けの講演会もしておられ、経営やビジネスだけで無く、親として教育の観点からも参考にしたいと感じました。自分の夢や可能性を信じて実践したくなる良著です。
2投稿日: 2021.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が子供の頃からの夢や目標を叶えた経験を元にした、教育論に近い内容。 アツい想いが伝わってきて、自分はいつもどう考え行動しているか考えさせられる。こういうふうに、子供の持つ能力が国の教育システムによって失われているのかもしれない… 読んでよかった。
0投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020.9.10 85 ものの始まり図鑑、ワインの最初はステンレスでなく足踏み 0から1 幼児は諦めることを知らない 夢を叶えるプランbがあれば目的になる。一つしかプランがないと夢が手段になる。 よかった。、
0投稿日: 2020.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログどうせ無理をなくす だったら、こうしてみたらと考え続ける 憧れが努力を生む 憧れと優しさが夢を叶える 夢はたくさんあったほうがいい 全体的に読みやすい文書で、感情に訴えつつ論理的にもなっていて、植松さんの真っ直ぐした情熱が伝わってきた。 後半のロケット教室のエピソードいいなぁ
1投稿日: 2019.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「前向きになれる本。私もどうせ無理って言わないようにします」 すごい本に出会ったな・・と思いました。 植松さんの今まで感じてきた社会への違和感をブレずに仕事に生かしているところが心に響きました。 この本では、自分が逆の立場だったら「もうだめだ、やめよう」と感じてしまうような出来事が紹介されます。 でも、「あきらめないで工夫」しつづけるとこんなことが起こるよ、だから「どうせ無理」って思ってはいけないというメッセージが何回も表現や具体例を変えて紹介されます。私はこの本を読みすすめるうちに、今「無理」って思えていることを工夫して進められないかなという気持ちになりました。 また、この会社は「女性役員比率」や、「給料の高さランキング」等に入ってくる会社ではないと思います。(そもそもそれを目指していないと思いますが) しかし、この会社に関わった人(見学者までも)がみんな成長を感じられる会社であることがわかり、とても魅力的に感じました。魅力的な会社=ランキングにある会社 とは必ずしもないのかもしれないなということを、よく考えなくても当たり前なのですが、再認識できました。 昔はいろいろな条件が揃っていたから(無理していたのかもしれないですが)いい学校、いい会社、お金に心配のない人生がセットになって「勝ち組」といったような価値観が作られました。 しかし、時代は変わったのに、その価値観に沿って人生を進められなくて苦しんでいる人がたくさんいる現状があります。 これからは、「工夫する人」「あきらめない人」「『どうせ無理』といわない人」がお金のためではなく、夢や憧れに向かって自由に表現していくような方向性が教育や自分の人生を考える上で重要になってくることを気付かさせてもらいました。
4投稿日: 2019.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログTED talkを観て植松さんのファンになって、すぐにこの本を読みました。 簡単な言葉だけど、そこに植松さんの想いが詰まっていて、心に直接響いてくる。 前向きになれる。頑張る力をくれる。夢を持つ大切さを教えてくれる。 今まで読んだ本の中で、一番パワーをくれた本でした。 今後の人生、道に迷ったり躓くことがあったら読み返そうと思います。 "成功するための秘訣とは、成功するまでやるということです。" "100パーセントできることは夢ではなくて、今できることをやらないでいるだけです。" "夢とは、好きなこと、やってみたいことです。そして仕事とは、社会や人のために役に立つことです。"
2投稿日: 2019.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ夢の実現に希望が持てるようになる。 内容は平易なので中学生くらいに是非とも読んでほしいとおもう。 北海道に民間でロケット開発をしている会社があるというのは知っていたので、その会社のロケット開発に関する本だと思って読んでみたんだけど、そう言う話ではなかったが、別の面でとてもいい本だった。 著者の植松努氏はそんなことは無理と言われてしまいそうな、民間企業による宇宙開発を通して、どうせ無理、という言葉をなくしてしまいたいという思いで活動されている。 たしかに国に頼らず、従業員20人ほどの中小企業がロケットから開発して宇宙開発する、なんて普通に考えれば無理としかいいようないのだが、それを実現させている著者に、無理なんてことはない努力と工夫でなんでもできる、と言われてしまえばこれほどの説得力もない。 本業はリサイクルに使用されるマグネットを製造している植松電機で、そこでの儲をロケット開発につぎ込んでいるらしい。 その植松電機の経営方針も独特で、「稼働率を下げる、なるべく売らない、なるべくつくらない」という経営方針で会社を運営している。 一見奇妙な経営方針だが、著者ならではの着目点からそういう経営方針を持つに至ったらしい。 全ての企業や仕事に適用できるわけではもちろんないが、その考え方の基本は極めて普遍的なものがあり、そこはとても参考になる。 植松氏のやっているカムイスペースワークス(http://www.camuispaceworks.com/)は到達高度10Kmのロケットまで成功している(http://hermes-me.eng.hokudai.ac.jp/vsrl/library/HSC-pre_CAMUI%E6%89%93%E4%B8%8A%E3%81%92%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf) 平成19年以降のプレスリリースがないのが気になるが、その他にもホリエモンの行っている宇宙開発事業のSNS inc.(http://www.snskk.com/index.html)が目指している有人ロケット開発にも協力しているらしい。 現在国が行っているロケット開発は種子島での発射がメインになっているが、10年後、20年後における日本の民間ロケット開発の中心は北海道になっていることは間違いなく、その中心にはおそらく植松氏がいるのではないかと思う。 自分もいろいろとやりたいと思ったことを、無理だろうとあきらめていたことがたくさんあるが、あきらめるまえに「だったらこうしてみたら」といことを考えてみるようにしたいと思った。
0投稿日: 2018.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どうせ無理」という言葉をこの世からなくしたい、 そのために宇宙開発に取り組んでいるという 会社の社長さんが書いた話。 読んでよかった。元気をもらった。 ワタシは、常々宇宙飛行士という人達は、子ども の頃の純粋な心をいつまでも持っている人達だ と思っている。「宇宙に行きたい」という子どもの 頃の夢を捨てないで持ち続け、そのまま大人に なって宇宙に行った人達。 彼らが宇宙の話をするとき、まるで子どもの ように目をきらきらさせているのがその証拠。 この本を書いた植松さんからも、これと同じ ものを感じる。 宇宙には、人をつき動かす何かがあるんじゃ ないか…そんなことを考えた。
1投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログとある本のレビューにその本よりこちらの方がお奨めと書かれていて読んでみました。 成功体験本かなと思いつつ読み始めたのですが、刺さる文章が連発。 とても良い本です。お奨め。 言葉そのものは出てきませんが、コンフォートゾーンとか、ドリームキラーといった概念に通じる話も出てきて、そういう意味でも興味深かったです。
1投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ"これは、すばらしい本だ。甥っ子にプレゼントしようと思っている。 元気がもらえるし、自らの可能性含めた人間一人ひとりの可能性を信じてとても前向きになる。一度植松さんにも会いたくなること間違いなし。"
0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ【文章】 とても読み易い 【気付き】 ★★★★・ 【ハマり】 ★★★★・ 【共感度】 ★★★★★ この世から「どうせ無理」を無くす。 投資したお金は、経験と知恵と人脈で回収する。 消費者迎合という表面的な対応が、成長の機会を奪う。 好きという気持ちが無ければ、問題意識を持つ事も無く、指示待ち人間になってしまう。 夢とはやってみたい事、仕事とは人の役に立つ事。 理想とは北極星のようなもの、自分の位置を確認し、進むべき方向を知るためには、必要不可欠。到達できるかできないかが重要なのでは無い。
0投稿日: 2017.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に作られたものは手作り 新しいものは誰も教えてくれないし、本にも書いてない 憶測の評論に負けないこと、これってすごく重要だし難しいことだと思う
0投稿日: 2017.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
若いパパとママに読んでいただきたいと思います。子供の夢を摘まないように…子供の可能性を伸ばせるように…パパやママも、一度はあきらめた夢を取り戻すために、自分たちの可能性にも再チャレンジできるように… 植松氏は北海道赤平市で(株)植松電機を経営し、バッテリー式マグネット装置を製造する傍ら、ロケットの製造をしています。池井戸潤さんの『下町ロケット』のように、ロケットの部品を造っているのかと思ったら、ロケットそのものを造っているそうです。ロケットって、国を挙げて開発するモノじゃないの?って思いますよね?植松氏は、自分の価値観に従って興味が持てることを突き詰めていたら、志の高い人と出会い、追求すべき信念に到達し、行動し続けていたら、夢が叶ったという話です。先人の知恵をまとめた啓発本とは一線を画する内容です。 この本は、上司から借りた本で、既に他のメンバーにリレーしてしまったので、手元にないのですが、身近に置いておきたいので、Getしたいと思います。文字も大きく、とても平易な言葉で書かれており、内容も分かりやすいので、読書に慣れていない方にもお薦めできます。「世の中から“どうせ無理…”という言葉を廃絶したい」という植松努さんの思いを伝える一人になりたいと思います。 植松努さんは「自信が大切だ」と何度も繰り返し書いています。自分の夢を叶えられなかった大人(親や教師)の言葉は、全ての子供たちが持っている夢の芽を摘んでしまいます。大人たちは古い価値観を子供たちに押し付け、既成の価値観の中で得する人(親にとって都合の良い子供)になることが人生の目的になるように指導しようとします。その結果、新しい価値観を創造したり、未知を切り拓くことが出来るような子供たちがいなくなってしまうのです。 この本は、まだ子供が小さい、若いパパとママに読んでいただきたいと思います。子供の夢を摘まないように…子供の可能性を伸ばせるように…パパやママも、一度はあきらめた夢を取り戻すために、自分たちの可能性にも再チャレンジできるように…
0投稿日: 2017.08.27やるまえから諦めるなんてもったいない
夢を目指して邁進する北海道の小さなマチの工場の話。 物語ではなく実話である。 ついつい日頃、「いやこれは無理だろう」と諦めてしまいがちな夢も、「本当に無理なのか?」をきちんと考えていかなければいけない。 子ども達は夢を見なくなった、という言葉を聞くけれど、夢を本気で見られなくなったのは、本当は誰なんだろう。 自分たちが信じられないものは、子ども達だって信じられなくなってしまう。
0投稿日: 2017.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログいままで考えて、話して、落ち込んで、それでも捨てきれなかったこと。全部この本に書いてあった。とても勇気が出たし、なによりも諦めないで頑張ろうと、前向きになれた。 ありきたりな感想になったけど、この本は人生を変えると思う。
1投稿日: 2017.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わったー\(^o^)/ 独自に宇宙開発をしている北海道の田舎の小さい企業の社長の書籍。 「どうせ無理」を払拭することが大切。
0投稿日: 2017.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どうせ無理」をなくし、「だったらこうしてみたら」で世界を変える。 夢を夢で終わらせないためにもずーっと手段を考え続けなきゃね。
0投稿日: 2016.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログI share this youtube with you. https://youtu.be/gBumdOWWMhY
0投稿日: 2016.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は北海道の町工場の経営者。小さな町工場だが宇宙ロケット開発に取り組んでいる。すごい技術力を持っている会社だとは思う。本文は日記調で感情的な叙述が多いので、読んでいて好き嫌いが出るかも。気になったフレーズ。「どうせ無理だ」というセリフに対して「だったら、こうしてみては」を考えてみる。同じことをやり続けてみるのではなく、プランA,プランB,プランCと次の手を考え続ける。
0投稿日: 2016.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログすぅっと入って来るわかり易い表現で、目からウロコな言葉がぎっしりと詰まった一冊。 前向きになれて、やる気が溢れ出て来る宝物のような本!
0投稿日: 2016.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学から高校くらいの子供に読んでほしい本。どこを見ても否定形の言葉があふれてる中で「どうせ無理」をなくすための考え方が詰まっている。 言い過ぎな部分もあるようには思いましたが、著者が帰ってきてからの売り上げの伸びが全てを物語ってるように思う。 結局すべては、やるかやらないか。自分の中の成功者の共通点を補強できた。 読みやすいので、もっと若い人に勧めたい。
0投稿日: 2016.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
他人に勧めたい本で個人的No1に推薦したいのがこの本。現代社会を生きていると、様々な理想と現実のギャップに悩むことがあるが、この本はそうした悩みに対して明確なアドバイスをくれる本だ。 今世界中の人が、労働の意義や企業の存在価値について疑問を抱いていると感じる。その疑問とは、終わることのない大量生産・大量消費社会のについてである。似たような商品やサービスを次々に提供し、膨大な広告宣伝によって購買を勧める社会のあり方だ。次々と登場する商品やサービスを買うために人生の大半を労働に費やし、ローンを払う暮らし。 定期的に利益を出し続けるために、メーカーはわざと壊れやすい製品を作る。商品やサービスを買わせるために、心理的効果の強い広告宣伝で消費者を煽る。価格競争に勝つために人件費を削り、一人当たりの労働量を増やし、ブラック化していく企業。枯渇する資源。 こんな世の中に辟易している人たちが増えているように感じるのだ。「草食系」や「ミニマリスト」などの言葉がそれを象徴している。元ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカ氏のスピーチや本がヒットしたのも、氏の主張がこうした疑問に1つのヒントを示すものだったからだろう。 本書もこうした疑問にヒントをくれるものだ。著者の植松努さんは故郷の北海道の小さな町で宇宙開発の会社を運営している。過疎化が進み、雇用も少ない地域で敢えて宇宙開発をすることで「どうせ無理」という言葉を世の中からなくしたいというのが筆者の主張だ。 しかも、国の補助金や外部からの援助に頼らず、リサイクル事業で稼いだ利益を主な原資として宇宙開発を行っている。これも、「国に頼らずとも、民間の力で宇宙開発は出来る」ことを示したいからだと言う。その結果、無重力実験施設を独自に作ったりしてしまった。 植松さんは「誰もやったことがないこと」に挑戦するべきだと主張する。たとえ失敗したとしても「だったら次はこうしてみよう」と考えてやり直せばいいだけだと。その過程で分からないことがあったら調べればいいし、知らないことは「本」から人類の積み上げてきた叡智をいくらでも学べると言う。確かに、その通りだ! 誰かと同じことばかりやっているから価格競争に陥るのであって、それなら真似のできないものを作れば良い。 もちろん「それは理想論に過ぎない」「ヒト・モノ・カネのある大手に勝てるわけがない」という意見もあるだろう。そこで自分達が宇宙開発を進めることで、そうした「どうせ無理」という意見をなくしていくことが、植松さんの目標だ。 本書を読んで、これからの社会もそうあるべきだと感じた。すなわち、アイデアのある個人や小規模組織が前例のない価値のある商品やサービスを次々に作り出していく世の中。そしてその中から環境に優しい商品やサービスが現れ、社会を良い方向に変えていく。 現状そうなっていないのは「他社の模倣」や「二匹目のドジョウ」でリスクを冒さず利益を得たいという企業が多すぎるからだと思う。未踏の領域に踏み出すことは確かにリスクも伴うが、それをやることこそが社会的な労働の意義であり、企業の価値ではないだろうか。本書を読んでいるとつくづくそう感じる。
0投稿日: 2016.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ最新の装備だけを見ていたら、自分ではできないような気になるでしょうが、最初の自動車は手づくりでつくられています。最初の飛行機だって手作りなんです。だから、いろいろなものの歴史を知ると、なんでも出来そうな気がします。
0投稿日: 2016.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年1月25日に開催されたビブリオバトルinいこまで発表された本です。テーマは「ギャップ」。チャンプ本!
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がTEDで発表している「どうせ無理」をなくし「だったらこうしてみれば」と言い合える世界にしたいという話をyou tubeに見て是非読みたいと思った。 You tubeの発表もよかったが、本も最近読んだ本の中で一番心が動かされる本だった。 是非家族全員に読んで欲しい。と思った。 「どうせ無理」と言う人は実際にやっていない人の発言、しかしその人が、そういう憶測で評論する人がどんな人かと言うと。 1.知らないことが恥ずかしいと思っている人。知ったかぶりの憶測をして、知らないものと出会った時それはくだらないと言って知ろうとすることさえもしない。 2.間違える事が恥ずかしいことだと思っている人。間違えを認めず、「自分が正しいんだ」と決めつけてしまう。 しかし知らなかったら調べればいいし、間違ったらやり直せばいいだけの話と言う言葉を聞いて、たったそれだけの事をしない出来ない自分がいる事を反省した。 楽をすると他人がする経験をさせて通ることで、経験しなくては身に着けられない能力が身につかないため結果「無能」にしかならない。 恐ろしい不幸の連続のスタート地点は「楽をする」。苦労する中努力する中に「面白い」と思う事を見つける、すなわち「楽しむ」。「楽」をしてはいけない。「楽しむ」のです。→楽をしないで努力しよう 諦めなければ状態がほんの少し良くなる。状態がほんの少し良くなるまで辞めずにやり続ける事が出来る事が大切。工夫し続ける。諦めるとどんなに素敵な幸運も公開の対象にしかなりません。 自分が今持っているものが手段なのか夢なのかを判断する簡単な方法は、その夢をかなえるためのプランBがあるかどうかです。プランBがない夢はきっと手段です。 人と仲良くなるために一番大切な秘訣はそういう人が困っている事を見つけて助ける事です。そうすると人から必要とされるんです。
0投稿日: 2016.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆6 僕は、宇宙開発はあることを実現するための手段だと考えています。 それは「どうせ無理」という言葉をこの世からなくすことです 「よりよく」を求めなくなったとき、社会はダメになる 顧客満足というものは、お客さんを「いやあ、すごいな」とうならせることにあります。お客さんをさらに成長させることにあります。 お客さんをチヤホヤすることは、お客さんの能力を低下させます 幼児というものは、やったことのないことをやりたがります。そして、あきらめません アニメーションなんかくだらないと言う人がいますが、今、日本で、二本足で歩くロボットの開発が世界のどこよりも進んでいる理由は、 ひとえに『鉄腕アトム』があったからです 僕たちはもしかすると、自分の愛する子どもたちの将来のことを思うあまり「あんたのためなんだから、この位牌を買いなさい」という霊感商法のような勢いで大学進学を無理やり勧めてはいないでしょうか。そして、子どもの大学進学の費用を稼ぐために、子どもとのコミュニケーションも犠牲にして働いているんじゃないでしょうか ばあちゃんは教えてくれました。お金はくだらないよ、一晩で価値が変わっちゃうからね、と。お金があったら本を買いなさい、頭に入れてしまえば誰にも取られないし、その知識が必ず新しいことを生みだすと教えてくれたんです 国家の総力というものは、そこで暮らした人たちの流した血と汗と涙の蓄積です。それを文明という形で蓄積する方法もあるというのに、日本はゴミ捨て場や埋め立て地に蓄積しているのではないでしょうか 人生、最後に勝つのはどれだけ「やったか」です。どれだけ「もらったか」ではありません 誰かが信じてくれることを期待していてはいけません。信じるというのは、自分自身の覚悟のはずです 僕はアポロの着陸そのものを覚えてはいません。僕が覚えているのはじいちゃんのあぐらの中の温もりです。じいちゃんのあぐらの中に座った僕にテレビを見せながら、「人が月を歩いているぞ。すごい時代になったぞ。おまえもきっと月に行けるぞ」とじいちゃんは言っていました。自分が大好きだったじいちゃんの、今まで見たこともない喜びぶりが僕の中に記憶されました。だから、僕は飛行機やロケットが好きになったんです
0投稿日: 2016.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・ニッチを狙えとよく言われますが、ニッチは見つけるものではなく自分で作るもの。 ・0から1を生み出す仕事する人たちは「やったことのないことをやりたがる人」、「あきらめない人」「工夫をする人」。キーワードは「だったらこうしてみたら?」。 ・いろんな夢をもった時、周りの人から「それはダメかもしれないよ」と言われることがありますが、「ダメかもしれない」と「できるかもしれない」は確率は同じ。だったら「できるかもしれない」と思う人を増やしたい。
0投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログTEDのスピーチは話し方もあってあまり心に届かなかったんだけど、この本読んで見直した。植松さん素晴らしい。そして、思考力に感服。
0投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ銀行員の立場からすると過剰投資だけど、一方でこんな会社と一緒に成長したい。 困難だからこそやってみる。そのとおりだ。
0投稿日: 2015.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログTEDのプレゼンを見て筆者の持論、考えに引き込まれました。 私にとって、子育て中の今だからこそ響くものがたくさんありました。 何度も読み返したい本です。
0投稿日: 2015.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログすごくよかった。スペースデブリを回収するロケットを目指しているってすごい。子育てにもとても役に立つと思った。また読み直したい。
0投稿日: 2015.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯によると、講演の書き起こしのようです。 だから同じ話が何回か繰り返し出てきますが、それだけに熱いのです。 著者(?)の植松努さんは、北海道にある赤平市という、小さな市で会社を経営しています。 炭鉱がさびれてから景気が悪くなり、財政再建団体目前の市ですが、そこで社員20人の会社をやっています。 リサイクルに使うパワーショベルにつけるマグネットを製造するのが仕事です。 そしてもう一つ。 宇宙開発をしています。 植松さんは小学校6年生の時に卒業文集の「ぼくの夢、わたしの夢」というところに「自分の作った潜水艦で世界の海を旅したい」と書いて、先生に呼び出しを食らいます。 ほかの子どもはちゃんと職業のことを書いているのに、こんな、できもしない、かなわない夢を書いていていいのか? 中学校の進路相談の時間に、先生から「将来どうするんだ?」と聞かれたので、「飛行機、ロケットの仕事がしたいです」と胸を張って答えたら、「芦別に生まれた段階で無理だ」と言われたそうです。 飛行機やロケットの仕事をするためには東大に入らなければいけない。おまえの頭では入れるわけがない。芦別という街から東大へ行った人間は一人もいない。 自分の興味のあることを、独学で一生懸命学んでいた植松さんは、どうしても学校の成績の方に支障をきたしていたんですね。 次々と否定的なことを言われますが、国立の大学に入ります。 そうしたら、今まで独自に勉強してきたことが全部大学の勉強に結び付いたんですね。 そして。 大学の先生たちにかわいがられたようですが、やっぱり「お前はこの大学に来た段階で、残念だけど飛行機の仕事は無理だ」と言われてしまいます。 その大学は国立の工業系大学の中で、当時偏差値が一番低かったからです。 けれど植松さんは、名古屋で飛行機を作る仕事に就きました。 「風立ちぬ」の堀越治郎さんがいた会社です。 これだけでも元気が出ませんか? いろいろあって地元に戻り、父の経営する植松電機で働き始めますが、取引先の一言で株式会社にします。 経営方針は「稼働率を下げる。なるべく売らない。なるべくつくらない」 そのためには、どんなことがあっても壊れない製品を作る。 そして、時間を余らせて、新しいことに使う。 で、宇宙開発です。 ロケットを作ります。 材料はホームセンターや通信販売で簡単に手に入るのだそうです。 液体燃料を使わない、爆発しない(しにくい)ロケットなので、家の隣で実験ができます。 今、地球の周りには人工衛星の残骸などの宇宙ゴミがたくさん散乱しています。 それを回収するロケットがいつかは必要になります。 それには、人工衛星のような技術も必要になります。 だから人工衛星も作りました。 実際に宇宙に行ったその人工衛星は、世界で初めて宇宙にごみを残さなかった人工衛星になりました。 国内ではニュースになりませんでしたが、世界的に高く評価されているそうです。 宇宙で動くかどうかの実験をするために、真空施設が必要ということになりました。 国の施設のレンタル料は、1日600万円もします。 なので、廃材を利用して自分で作ったら20万円でできました。 世界で3つ目の無重力の実験施設もここにあります。 あとの二か所はドイツと岐阜県にあるんですって。 ほかの二か所は試験をするたびに費用がかかりますが、ここはただで使わせてくれます。 だから世界中から知識や技術を持った人たちが、ここに実験に来ます。 それが植松電機の財産になるのです。 どうしよう。 こんなに描いても全然面白さが伝えられない。 成功の秘訣は成功するまで続けること。 楽をすると「無能」になる。楽をしないで努力しよう。 失敗を生かして改良する。 植松さんの行動を通した大切なことが、たくさん書いてあります。 ひとりでも多くの人に読んでほしいなあと思います。←いや、力入り過ぎ
1投稿日: 2015.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログTEDプレゼンが素敵すぎる!と話題の植松さんの著書。TEDを見て凄い人だ!と思っていましたが、当書を読んで、改めて植松さんのファンになってしまいました。どう人生を生きるかという指南書は数多くありますが、どう生きるかという考え方の整理だけでなく、それを実際に実践し続けているからこそ、文中に出てくる数々の言葉が重く、且つ説得力があるんだと思います。 以下、参考になった点。引用、自己解釈含む。 ・「どうせ無理」という言葉は恐ろしい言葉。その言葉をしたり顔で口にするだけで、チャレンジしない自分を正当化してしまうだけでなく、人のやる気さへも奪ってしまう。こんなに無責任な言葉は無い。 ・楽をしたら成長は出来ない。苦労することが生きた経験を生み、その経験が次の扉を開く。苦労を避けている限り、経験値は積みあがらない。 ・当然、何もしなければ、自信は芽生えない。自信が無い人はどうするかというと、他人を評論することで、自分を大きく見せようとするる。そして、なんとか自己充足感を得ようとする。 ・この身勝手な自己充足感の為に、またその人の周りの人の自身が奪われていく。こうして「どうせ無理」の負の連鎖が進んでいく。 ・この負の連鎖を断ち切る為には、一人一人が「どうせ無理」という言葉をステ、「こうしてみれば」という考えを持ち、新しいことにチャレンジすること。 ・「楽」という言葉を「らく」と読むのではなく「たのしい」と読むようにする。らくした先には何も生まれないが、楽しんだ先には次のステージが待っている。 ・1つのことを一生懸命やるというのは一見良いように見えるが、他のことにチャレンジしないことを肯定する逃げの言葉として使っている場合が多々ある。1つのことだけをやっていても、次の成長に繋がらないことは皆わかっているのに、そのことを認めたがらない。 ・消費者迎合は顧客満足では無い。真の顧客満足とは、お客様に「いやーすごい!」とうならせること。そして、お客様の成長に役立つこと。消費者迎合は、お客様満足どころか、却ってお客様の能力を下げることになる。 ・本当にやりたいことであれば、教えられなくても、自分で調べてやれることはたくさんあるはずです。なのに「教わってない」という一言で自分のやるべきチャレンジを先延ばしにする人がなんて多いことか。こんな勿体ないこてゃない。やりたいことであれば、出来ることから調べ、学んで、やればいい。それだけのこと。 ・「CAN DO」は『カンドウ』と読める。カンドウ≒情熱をもって行えば、必ず出来るという意味だと思っている。言葉遊びだがとても大事な考え方。
0投稿日: 2015.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
僕は、宇宙開発はあることを実現するための手段だと考えています。 それは「どうせ無理」という言葉をこの世からなくすことです。(p.14) 「消費者迎合」を「顧客満足」と勘違いしている企業がたくさんあります。でも、これは顧客満足ではありません。顧客満足というものは、お客さんを「いやあ、すごいな」とうならせることにあります。お客さんをさらに成長させることにあります。お客さんをチヤホヤすることは、お客さんの能力を低下させます。(p.37) でも、こういうことができるようになったのは、僕たちが偉かったからではありません。ロケットをつくるための材料も、人工衛星をつくるための材料も、最先端素材といわれたものが、今ではホームセンターや通信販売で簡単に手に入るからつくれるんです。「できる」と思ったらできます。「できない」と思ったらできません。それが宇宙開発です。(p.45) 歴史の本を読むのは、とても大事です。最初につくられたものは全部、自分でもつくれるような気がするからです。できるかもしれないと思えるのはいいことです。(p.53) 僕たちが「普通」をつくりだしているわけです。僕たちは周りの人から影響を受け、そして周りの人に影響を与えています。普通というもののレベルは、いくらでも変えることが可能です。自分が子どもたちにどんな人になってほしいかを考え、それを助けるような「普通」というもののをつくりだす必要があるのではないでしょうか。(p.69) この歌には致命的な欠点があると思います。花屋さんの店先に並ぶ前に、どれだけ多くの花が間引かれて捨てられているのかということを忘れているからです。店頭に並ぶのも、すごい努力の結果です。こんな歌を信じてしまうと、努力に気づくことができなくなってしまいます。 オンリーワンになるのにも努力が必要なのです。(p.110) 自信のない人間は、他の人間の自信を奪います。自信を少し持つだけで、他人の自信を奪わなくなります。優しくなってしまうんです。(p.184)
0投稿日: 2015.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ全ての制約だと思い込んでるものを見直すきっかけになる良書!全ての人に! 植松努氏のTEDスピーチの内容をもっと知りたい人にもオススメです!
0投稿日: 2015.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ判断用に借りた。 そんなに期待してなかったからか、すごく面白かった気が する。こりゃ、購入&おすすめだわ。
0投稿日: 2015.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読む価値あり。植松努さんのTED(プレゼン)を見てから興味がわき読みました。本当に読み応えがありますし、植松さんが言う「だったら、こうしてみたら」という考え方が世の中に浸透すると世の中が良い方向に変わるのではないでしょうか。「どーせ無理」という言葉に出会ったら、「だったら、こうしてみたら」と言い返せるようにします。
2投稿日: 2014.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログTEDxトークを見て感動したので(http://youtu.be/gBumdOWWMhY)本も読んでみた。とっても分かりやすくて心に響いてくるメッセージ。「よりよく」を求める社会をつくろう。「どうせ無理」じゃなくて「だったら、こうしてみたら」と考えよう。人が可能性を信じられるように、儲けにならなくても、ロケット開発を進めてきた植松さんの熱い思いは、ほんとうにすごい。
0投稿日: 2014.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはみんなに読んで欲しい。 子どもに語りかけるように平易な言葉で大切なことをシンプルに力強く伝えてくれます。 読んだだけで、希望と勇気が湧いてくる。 どうせ無理、という言葉をなくすという夢の手段がロケット。 絶対無理だと言われた夢を叶えることによって、身近な問題の解決を無理と言わせない大胆な展開ですが、 もう、素晴らしいとしか言いようがないです。 学ぶということ、よりよい暮らし、幸せとは、働くことなどなど。 多岐に渡るけど、核はひとつ。諦めないこと。 自信のある人は優しい。 自信のない人は他人から自信を奪う。 能力とは、過去の実績ではなく未来の可能性。 アドラー心理学の本とリンクする部分がたくさんあった。
0投稿日: 2014.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB00119988
0投稿日: 2014.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログロケットを開発している北海道の町工場の社長さんが著者。 「どうせ無理」結構よく聞く言葉。「だったら、こうしてみたら」自分にも周りにも大事な言葉。 今仕事が煮詰まっているところで読んでよかった。自然とやる気が湧いてくる、背中を押してくれる一冊でした。
0投稿日: 2014.08.13失敗から立ち直る力
人は、挑戦と失敗の繰り返しで、学び成長して行く。学校の成績は悪くても、関心を持った紙飛行機を研究していくうちに、自作ロケットを打ち上げるといった、北海道の中小企業の社長の講話である。行き詰ってもあきらめないこと、失敗したら次はどうするかを考える、より良いものを作るためには利益に走らない、社長の方針に従業員が付いて行きアメリカのNASAとの取引を持つまでになった。地元では子供たちにロケットを作らせ感動を与えている。ふつうではない生き方だが、挫折感を味わった時に参考になる図書である。
3投稿日: 2014.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、何度か講演をお聴きした事のある、北海の雄・植松さんの著書です。彼は「どうせ無理・・・」という言葉を、この世からなくそうとしています。どこか身近に感じる植松さん、彼の体系づけられた言葉は、すんなりと入ってきます。
0投稿日: 2014.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログプロジェクトXに出てくるような企業の本かと思いきや、思いっきり哲学の本でした。従業員20人ほどの小さな工場が本業とはほとんど関係のない「宇宙開発」に取り組み始め、本当にロケットを飛ばしたり、無重力実験装置を作ったりしてしまうという面白い会社。本業が立ち行かなくなることを見越しての開発かと思ったら、大義名分は「世の中からどうせ無理という言葉をなくしたい」とのこと。要するに宇宙について学歴も知識も経験もない会社でも、ただできるんだという一心でロケットを飛ばせるんだから、「どうせ自分には無理」と夢をあきらめずに「どうしたらできるのか」を考えなさい、というメッセージがこめられた内容になっています。 著者は小さい頃飛行機やロケットに興味を持ちますが、進路指導の先生に東大にいかなきゃ無理だといわれてしまいます。著者はこれらに興味を持つことで、逆に学校の勉強をしなくなってしまい、それで成績が悪くなったのですが、その後、先生の思惑通りにはならず飛行機関連の仕事に就くことができます。学校の勉強よりも好きで始めた飛行機の勉強が結局に役にたったのです。そして今や人工衛星まで作ってしまい実際に宇宙に飛ばしています。 好きなことなら努力を惜しまないという気持ちが非常によく分かるので共感する部分が多く、ここで働きたいと思いました(笑)。 経験ある方もいると思いますが自分が「できる」と思っていても誰かに「いや無理やろう」と言われたら「あ、無理なんか」と思ってしまうこと。このように流されない意思を持つには自分ができるという経験を積まないといけない。本書にまさにそのことを示す一文がありました。 「出来ると思ったらできる。出来ないと思ったら出来ない」
0投稿日: 2014.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書。夢を追うためにどんなことを大事にすればいいか書いてある。若い人や、何かを頑張って心が折れそうになった時に読む本。
0投稿日: 2014.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログきわめてラディカルで、きわめてシンプルな社会批判、社会改革の本だ。 大人だからこそ、あきらめを身につけてしまっている。子どもはそれを模倣する。 しかし、どんなハイテクももともとは手作りだったのだ。さかのぼれば、この手が実現できるのだ。 プランBが無い夢は手段。きつい一言だが、この辺の勘違いを認識することから始めよう。
0投稿日: 2014.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ北海道赤平市という地で、町工場を営みながら宇宙ロケット開発にも情熱を注ぐ著者による仕事論。自身の宇宙ロケット開発に携わるまでの経緯やそこに至るまでの考えなどを通して、子供そして大人に『広く夢を持つこと』を伝えている。 「自信がない人は評論として他人の自信を奪う」ように、何事も初めてのことに対しては根拠なしに「どうせ出来ない」「無理に決まってる」という意見を言う人はいる。そういう責任が一切ない意見に振り回され、せっかくの希望やチャンスを自ら失うのは損なだけ。いつか子供をもった時に「普通」という枠に当てはめることなく、たくさんの経験させて広く興味を持てる子に育てていきたい。危険なことでない限り「無理だ」「止めろ」という言葉は使わず色々なことに挑戦させ、可能性を後押しできるような大人でありたいと思った。 繰り返し出てくる『よりよく』の精神には、万人に当てはまる生きていく上で大切な姿勢が詰まっている。シンプルに『好き』を突き詰めていくと、こんなにも大きなことが成し遂げられる。 真っすぐな言葉の数々が、素直に心に響きます。 ~memo~ ・アイデアを生み出すのは学歴でも偏差値でもなく「工夫する人」。 ・顧客満足とはお客様を唸らせること。チヤホヤさせることは顧客能力の低下につながる。 ・はじめてのことに対して、周囲は未知というだけで苦言を言う。でも何事も始まりはあるので、信じた道を突き進む。気づけば周りが自分の後ろをついて歩くことになっているかもしれない。 ・大学は好きという気持ちを掘り下げられる場所。 ・できない諦めようではなく、だったらこうしてみたら? ・夢はたくさんあったほうがいい。
0投稿日: 2014.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ町工場でロケットができた!? 安全で安価で宇宙から戻ってくるロケットができたのは、小さな町工場で考え努力し、お金がないなか いろんな知恵を絞っての結果。 「どうせ無理。。。」そんな言葉を廃絶するぞ、という作者の決め具合が伝わる!! 「努力というものは我慢ではありません。いやいやすることでもありません。憧れた結果、してしまうものです。憧れがなければ努力はできないんです。」
0投稿日: 2014.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み始めてまず思ったのは、ハウツー本や自己啓発に近い本だということ。もっと町工場がいかにしてロケットを制作するようになったのかの経緯や技術が詳しく書いてあるのかと思っていた。 が、読み進めるうち、作者の植松さんが言いたいのはそこではなく、夢を諦めない、「どうせ無理」という言葉は未来を殺すというメッセージを、大人だけではなく子供達に向けても強く発信するための本だということ。 やったことがないから、知らないから、やらない、出来ないと言うのは罪である、というのが根性論ではなく、実際に限りなく困難な状況からの社会的な成功例を持って書かれている。 諦めがちな自分としては読んでいて心がちくちく痛む。夢と手段を取り違えてはならない、という言葉も印象に残った。
0投稿日: 2014.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功するまで続けることで、それまで積み重ねた時間が輝く。諦めたら、その同じ時間も暗いものになる。 過去の同じ時間、労力も成果をあげるか否かで、捉え方が変わる。 確かに途中で投げたものって変な苦手意識がつきまとう気がする。成功なんて大それたものでなくとも、少しでも結果を出せるまでは、愚直でも粘り強く続けたいと勇気付けられました。 サッカーをやっていた身として、PKでミスっても勝てば笑い話になる感覚と重ね合わせて読んでしまった。 また筆者はメカニック好きで、幼少期からものづくりが好きだった。 何かを作る時のコツは「全てのものが第一号は手作りだったこと」を思い出し、シンプルに考えることとおっしゃっていて、何事も複雑に捉えがちな自分には響いた。
0投稿日: 2014.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいて、 鳥肌立つくらいワクワクして、 ページをめくる度に自分自身の経験を回想して、 常に共感しっぱなしの本だった。 世間から「どうせ無理…」という言葉を無くすために、 北海道の従業員20人規模の小さな町工場が、 宇宙開発を目指している。 世界で3つしか無い無重力試験場の内、 1つを所有し、ポリエチレンを燃料とする世界初のロケットエンジンを 開発、NASAからも見学者がくるという。 僕たちはやっても見ないのに、 「どうせ無理…」という。そこで道を閉ざしてしまう。 本当にやりたいのであれば、「だったらこうしてみる…」という感じで アプローチを変えればいい。 成功する秘訣は… 成功するまで諦めないこと。 人にとって一番辛いのは… 可能性を失うこと、だから、複数のプランが必要。
0投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすい。 ものは人からうまれる限り何でもできる。 すべてのものは最初は手づくり 確かに理想論かもしれないけど植松氏が身をもって証明してくれている。 自分で学ぶ。 楽をしないで努力を楽しむ お金よりも知恵と経験 暇な分学ぶ 成功するまでやる しんどいからビジネスがうまれる ニッチは自分でつくるもの だったら、こうしてみたら
1投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
常識にとらわれないで『どうせ無理』と言ってあきらめない大切さ。 夢を持つ青年や若者。あきらめてしまっている人に勇気を与えてくれる良書。 『しんどいことやつらいことを克服したり改善したりするのは、みんな立派なビジネスになる』
0投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ(投稿例) 「○○○だからどうせ無理」と言いそうなときにはこの本を☆ 著者の体験から「そんなことないよ!」と答えを教えてくれます。前向きな言葉が並んでいて自然とやる気がでてきます! 九州大学:いーもん
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年、職場の講演会に来た植松努さんの著作。 読んでいると、講演の内容がそのまま文字化されているように思えた。話術のある方なので、それならテンポの良い講演を聞いている方がいいじゃん!とも思ったが、読み進めていくうちに講演時間内では収まりきらなかったであろう彼の会社経営の具体的方針について述べられているところは興味深い。 とくに、「稼働率を下げる、なるべく売らない、なるべく作らない」というくだりは一見目を疑うが、なかなか理にかなっていて面白かった。 彼の講演を聞いたことがある人には、ぜひ読んでほしい一冊。 「だったらこうしてみよう」がキーワード。「どうせ無理」はNGワード。
0投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人にとって自信を持つことはどても大切で、それが夢(と仕事)にとって大きな力になるんだという考えが著者の経験に沿って率直に書かれています。 【ものづくり】に関わる上で持ち続けたい考えに触れられた気がします。
0投稿日: 2013.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇宙への憧れ、チャレンジ精神を持ち続け、小さな町工場でもロケット開発ができるということを実践し続けている工場の話。 子ども達が抱いた夢や憧れの芽を潰さないような姿勢を、周りの教師や大人たちに持ってほしいという想いや、努力を続けることの大切さについても厚く書かれています。 文体としては子どもでも読めるよう、分かりやすい表現で書かれています。
0投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者は自児童養護施設のボランティアの体験から、児童虐待をどうすれば減らせるのか考えた末、大人があきらめるのが悪いとの結論に至る。皆があきらめないためには「どうせ無理」という言葉をなくさなければいけない。誰もがあきらめる宇宙への夢を現実にしてしまえば「どうせ無理」などという言い訳は出来なくなるのだと。 (印象に残ったエピソード~ロケット教室で子供に自信を) ・0.3秒で時速200kmまで加速、高度100mまで到達してパラシュートで戻ってくるロケットを自作する教材を使う。説明書は英語。 ・このロケットは作る過程においてやったことがないから出来ないということを吹き飛ばし、そして飛ばす過程において「どうせぼくのはダメだろう」を吹き飛ばす。 ・子供たちは自分が作ったものがとんでもない勢いで飛んでいったのを見て、自分でも作れたと自信をもつ。その自信が人を優しくする。 ・自信のない人間は、他人の自信を奪う。自信を少し持つだけで他人の自信を奪わない優しい人になる。 (宇宙開発プロジェクト) ・地球の周りには人工衛星の残骸などデブリと呼ばれているゴミが二万個以上あり、これがマッハ25の速度で地球を回っている。 これを片付けるにはゴミに追いすがって、捕まえてブレーキをかける。すると引力に引かれて落ち大気圏で燃え尽きる。 ・北海道大学大学院 永田晴紀教授との出会い。非常に安全なロケットエンジン。燃えにくいポリエチレン(プラスチック)を上手に燃やす技術。3kgのポリエチレンで25,000馬力の出力。家でも作れる? ・無重力の研究成果・小型ロケットの技術・小型人工衛星の技術。 ・NASAから次世代スペースシャトルの開発委託を受けているロケットプレーン社と仲良くなった。
0投稿日: 2013.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ北海道の民間の会社で宇宙にロケットを飛ばす為に、どうすべきか?と試行錯誤をしながら夢を追いかけて、今ではNASAの実験など、凄いことをしている企業の話。 ロケットを題材としているが、どうすればいいのか?まず、やってみればいいじゃんと考えさせられる。 何事においてもチャレンジスピリッツは大切だなと思いました。
0投稿日: 2013.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に読んでよかった!もっと早く読んでおけばよかったと思った! 「どうせ、無理」 このマイナス言葉をなくすために、著者の植松さんは戦っておられる。 でもそれが嫌々かっていうと、むしろそれが生きがいで人生が成立しちゃってる。 「どうせ、無理」を「無理」とするためには、いろんな諦めと戦う。人が考えそうな批判は、すでにこの人が可能にしちゃっているから、結果、何も言えなくなる。そんで、これは書いてなかったけど、たぶん批判する人たちは、「どうせ、無理」が成立するような人に矛先をチェンジする。自分たちの価値観が成立する人を求めて。 これって馬鹿馬鹿しい。植松さんの生き方を知ると、自分が知らぬ間に「どうせ、無理」人間になっちゃっていたことに気づかされる。何も難しいことはない。自分のことなんだよね。植松さんの人生凄いけど、じゃあ植松さんしかできないかっていうと、そういう感じもしない。やっぱり、今の「僕、自身」がどうするかなんだ。 とっても勉強になった!これは、すごくおすすめです!!!!
1投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルから感じた印象よりも、自己啓発の要素が強い。 モノを創る、産み出すということをヒトが持つ唯一の価値とおいた時、最も頼れるのがこの著者なのだろう。 実ビジネスの上でも、評論家と化す上司への危惧はリアリティがあった。
0投稿日: 2013.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあきらめないこと努力することの大切を実体験から語ってくれている。 また、小さい会社だからこそ可能だと思うが、本業のマグネットでは「値引きしない」「納期短縮しない」ことで利益を確保し、さらに製品は「壊れない」そうすることで、業務に余裕をつくり、できた時間で新規開発や宇宙開発につぎ込む。この余裕こそが今の日本に大事なのではないかと思う。
0投稿日: 2013.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇宙開発でたまった宇宙のゴミを片付けるのに最適なポリエチレン燃料ロケット。 全長3280mm。 火薬を使ってないから危険物管理コストがかからない。 ポリエチレンは燃えにくいから、安全。 「どうせ無理」と言う言葉をこの世からなくすためにやっている。商売のためではない。 成功するための秘訣は、成功するまでやること。 あらゆる方向から、さまざまな試みを行う。 リサイクル用分別にパワーショベルに付ける電磁石のシェアはほぼ100%。 壊れなくして、作り過ぎない。値下げ要求をする会社には売らない。 楽をしようとすると無能になる。 夢がないと奇跡は起きない。 最低限やらないといけない仕事だけを全力でやってしまうと、 最低限の人間にしかなれない。 誰かが信じてくれることに期待してはダメ。 信じるということは自分の覚悟。 ロケット打ち上げに適したエリアは意外に少ない。 自転を利用すると、東に他国のない場所。 アメリカ東海岸。オーストラリア。南アメリカ。日本。
0投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇宙開発関係の難しい本かと思っていたが、内容はとても読みやすくて面白かった。不可能を可能にすることを目指す著者の志がかっこいい。
0投稿日: 2012.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
考え方がとても参考になる。なんでも自分で作っちゃえばいいのですね。普通は考え方によって変えられる。これは自分が子供を将来育てる事になったら、意識することの一つにしたい。他にも手元のメモに多々。
1投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ全て自腹で宇宙ロケット開発に取り組む北海道の町工場の話。 友人がこの本を紹介していて初めて知ったのですが、こんな会社があるのですねー知らなかった。 本業は工業用のマグネットの会社なのだそうですが、自社の資金で宇宙ロケット開発に取り組んでいるのだとか。 宇宙ロケット。。ってそれ無理でしょ?といいたくなるのですが、その「どうせ無理」という言葉をなくしたいという思いで実際飛ばしているそうです。 シンプルで強い思いが伝わる本でした。 一番印象に残ったところ 夢とは大好きなこと、やってみたいこと。 仕事おとは社会や人のために役に立つこと。 どちらもひとつだけとは決められていない、どちらもいくら儲からなければダメとは決められていない。 お金を払ってしてもらうことはサービスでそれは趣味じゃない。趣味とは自分でやることだよ。 著者の植松さん、きっと少年のような人なんじゃないかな。。 一度お会いしてみたいな。 ロケット教室、機会があったら参加してみたいです(私が)
0投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ北海道の町工場で宇宙開発を手がける植松電機社長の仕事論。 宇宙開発を通じてできると思ったらできるし、できないと思ったらできないということを感じたという。 「あきらめるのはいつでもできるから、最後までとっておくといい」など、仕事のみならず生きていく上で大切にしたい言葉がたくさん詰まっている。 どんな人でも一度読んでみると活力がもらえる良書。
0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・成功するための秘訣は、成功するまでやるということ。 ・「ニッチを狙え」というがニッチは探すものではなく、自分で作るもの ・顧客満足とは「すごいね」と御客様と唸らせ/成長させること。御客様のチヤホヤすることではない。 ・これから必要なのは「諦めない人」「工夫する人」。口癖は「だったらこうしてみたら」 ・間違ったらやり直す、わからなければ調べる。それが問題解決能力。 ・自信剥奪は連鎖する。心の優しい人に濃縮される。 ・楽しんで努力する。「楽」と「楽しい」は全く違う。 ・「一生懸命」という言葉で正当化される。「全力を尽くすこと」。楽をしないこと。 ・人生最後に勝つのは「どれだけやったか」。「どれだけもらったか」ではない。 ・全ての人には世界を変える可能性を持っている。人の役に立つ可能性がある ・夢とは大好きなこと、やってみたいこと。仕事とは社会や人のために役立つこと
1投稿日: 2012.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ北海道の小さな会社で、NASAに対抗してる社長! ●人間、好きなことにのめり込むのが一番!好きこそものの上手なれ。 ●フル稼働=多忙だと、忙しそうで素晴らしく見えるけど、創造・発見が生まれない。だから、余裕や暇な時間をたっぷりと予定して仕事してる。
0投稿日: 2012.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ夢と希望に溢れてる! 行動に移せば夢は叶う! やるかやらないか。 どうやるか! ものごとは0から始まる!
0投稿日: 2012.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「だったら、こうしてみたら」 尖った才能を持ったひとが、優しい言葉で書いた本。 突出したものを規格外として評価せず、均して出荷する、農作物の出荷のような教育がまかり通ってきた我が国で、苦しむ子供達に生きることの良さと価値を導ける内容だと思います。 「海底少年マリン」や「海のトリトン」を見てイルカの潜水艦を夢想するとか、、「良く飛ぶ紙飛行機集」で紙ヒコーキにはまるとか、プラモデルを禁止されてたことや、図鑑に出ていたゴダードのロケット。 どれもこれも、わたしが触れていたもの。夢をたぐり寄せた人と、川の流れに流されたRiver Peopleたるわたしとの差か。 氏に訪れる出会いがまた素晴らしい。好きなものを一生懸命知って、知見を深くしておくと、いつか同好の士と出会ったときに信頼の基になること。 この時代に生きている子供たちが、自分の夢を見つけて邁進し、幸せをつかめることを願います。決して甘いことを書いているわけではなく、楽をしないで努力をしようと語りかけてきます。 夢と仕事の定義が好きです。 子供達へやる気を出させるヒントが詰まっています。
0投稿日: 2012.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で少し行き詰まっていた時になにげなく手に取った本です。 本書とは関係ない仕事ですが、諦めずに努力する事や出来ると思えば出来る‼などなど前向きになれる言葉があり、 私には元気とやる気をくれた一冊です。
0投稿日: 2012.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館 すげー面白い。 読んでいてテンションあがる。 何か自分でもやらなきゃという思いが募る。 行動を起こそう。 後で買う。
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功する秘訣は成功するまでやること 今の社会は「よりよく」ではなく「安い」と「早い」しか求めない社会ですから、企業は「安い」と「早い」という消費者への迎合しかできなくなった たくさん消費しないと成り立たない大量生産社会から、節約して法が豊かになる社会に変わっていく最中が今なんじゃないかなと、僕は思っています 「21世紀こども百科 もののはじまり館」
0投稿日: 2012.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本業ではなく副業で宇宙開発をしている北海道の小さな町工場の話。 工場は小さくでもそこで働く人の器はどのビジネス書に出てくる人よりも大きいかもしれない。 この本に書かれていることは宇宙とか工場とかに興味なくても呼んで感動できます。 仕事していなくても、 夢を持っていなくても、 好きな事を探しいても、 もちろん上記のことを全て今実行している人にも読んでほしい。 理想論といえば理想なんだけれども 今の時代こういう夢を持っていなくてどう生きる? 【ココメモポイント】 ・成功するための秘訣とは、成功するまでやる ・1のことを10にするより、0から1を生み出そう ・お金は自分の知恵と経験の為に使えば減ることはなく、必ず元はとれる ・自分を変えたいと思ったら、人と会って本を読む
0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「どーせ無理」というのは,教育の現場にいるとさんざん聞かされる言葉である.自分たちも無意識のうちに彼ら/彼女らに使っているかもしれない.この言葉がいかに重く,人生を悪い方向に変えてしまうか. この本はロケット開発などで話題になっている植松努さんの著書である.先日機会があって,植松さんの講演を聞くことができた.それは教育に携わっているものにとってすごいインパクトであり,反省し,考えていかなければならないことが山のように含まれている.本書の内容はその講演を含んでいるので,あの時の気持ちが戻ってくる.学生から自信がなくなり,社会が暗くなっている中で,どうするか? この本で興味を持ったら,植松さんご本人のナマの講演を聞いてみることをお勧め.よりリアリティを持ってこの話の中身が響いてくると思う.
0投稿日: 2012.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どうせ無理」夢は諦めたら夢のまま。実現するまで頑張ればそれは夢現になる。多くの偉人や先達も言うように、失敗してもなんども重ねていけば何がダメだったかわかる。そうして一つずつ積み重ねていけば成功するんだよ。途中で諦めたらそこで失敗。あきらめない心が大切。 「ニッチは探すものじゃない。見つけるものなんだ」という言葉にグッときた。
0投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ"どうせ無理…"を根絶するために利益にならないロケットを作る著者の植松さんに憧れる。こういう人をかっこいいって言うんだぜ。
0投稿日: 2012.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
もうけ目当てではなく町工場で宇宙開発をする話が語られます。しかし、この本はいかに町工場が人工衛星を完成させるまでに至ったかを示すドキュメンタリーではありません。戦後、経済成長の名の下におかしくなってしまった日本の社会のあり方に抗い、夢という無限の可能性を失わないようにしようという、子供たちを幸せにし、まっとうな社会で暮らしていけるようにしようという決意表明の本です。 町工場の専務にそんなこと出来るわけがない。と言わせないための本です。
0投稿日: 2012.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログリサイクル用パワーショベルに取り付けるマグネットを製造している、北海道にある植松電機という従業員20人の会社が、なんとロケットを作って打ち上げに成功させる。しかも、それは本業ではなく、ボランティアというか趣味に近い。しかも「素人がロケットを打ち上げることで、この世から「どうせ無理」という言葉をなくす」ために大金をはたいて活動しているといいう・・・ 機械系のエンジニアならば、誰もが憧れるであろうその活動と、熱いハートに心を打たれること間違いなし。しかし特筆すべきは、著者の植松専務が、これらの活動にしっかりと骨格とビジョンを持たせている点です。それは、1.この活動により従業員の技術レベルを上げ、やればできるという自信をもたせる、2.そのモデルを世間一般に還元することで、社会を良くする、というもの。しかも、技術の目利きともいうべき植松氏は、大学の研究者と組んで、世界初のポリエチレン燃料による小型で安全なロケットを開発し、ビジネスとして成り立つ将来性を持たせています。 成功の秘訣は、「成功するまでやり続けること」だそうです。すべての人に響く金言ではないでしょうか。
0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
北海道の赤平という片田舎で自社でロケットや人工衛星を開発してしまった植松電機の社長のムネアツな本。とにかく自分でやってみる、失敗しても工夫をし続けて成功するまで挑戦しつづける。 強烈な熱意に胸うたれる本です。 世界に3カ所しかない無重量実験施設の1つも なんとこの会社にあるそうです。
0投稿日: 2012.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ北海道にあるリサイクルのパワーショベル用のマグネットを作っている町工場が最先端の宇宙開発をしている話。宇宙開発を始めた理由は、この世から「どうせ無理」という言葉を廃絶するためだという。最終章には更なる素晴らしい野望も。 これまでの私の人生は、夢を実現するために必要な助走期間だったのだと信じられた。 みんなに読んでほしいなあ。
0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「NASAより宇宙に近い町工場」植松 努 夢を忘れた大人のための激励本。スカイブルー。 @電子書籍 51 冊目。 GARAPAGOSストアでピックアップしたときはてっきりドキュメンタリー的な読み物かと思ったんですが、意外にも自伝・啓蒙本の類でした。 北海道赤松町というところでリサイクルプラント用の工業用マグネットを作っている小さな会社が、ロケットを作って、人工衛星を作って、無重力施設を作って、、 夢は追い求めれば実現出来る!ということを、著者が実体験をもって語っています。 これだけ聞くといかにも、な感じの成功体験、良い話だなーって印象ですが、あの手この手でビジネスパーソンに売り込もうとしてる教養書と違って、とにかく直球真っ勝負。 難しいことは言ってないし、文章も素直に読めるし、そうだよ、諦めないで追い求め続ければいいんじゃん!と単純に思わされます。 仕事は社会や人の役に立つこと。夢は自分の大好きなこと、やりたいこと。 どっちも、お金のためにする、とか、嫌々する、とかではないんですね。 とってもいい!良書でした。(5)
0投稿日: 2012.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供に読ませてあげたい本。子供いないんですけどね。 そして、毎日我慢して仕事をしているような大人に、もっと読んでもらいたい本。自分は何でも出来る気がしてきた!
0投稿日: 2011.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
知人に勧めてもらい買う。成功者目線かなと思う部分もなくもなかったが、それも作品に通して流れる原作者の植松さんの前向きなパワー故の「ことば」だとも理解でき、生きていく上での「人のあり方、心の持ち方」を作品に感じる。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕たちが「普通」を作り出している。僕たちは周りの人から影響を受け、そして周りの人に影響を与えています。普通というもののレベルは、いくらでも変えることが可能です。自分が子供たちにどんな人になってほしいかを考え、それを助けるような「普通」というものをつくりだす必要があるのではないでしょうか。(p69) 努力というものは我慢ではありません。いやいやすることでもありません。憧れた結果、してしまうものです。憧れがなければ努力はできないんです。(p167) 明日のために、今日の屈辱に耐えるんだ。(p190) 子供たちにあきらめ方さえ教えなければ、彼らは勝手に未来を切り開きます。どんなことでも、できる理由を考えればできるんです。できない理由を思いついたときは、それをひっくり返してください。それはできる理由になるんです。 どんな夢も、「どうせ無理だ」ではなくて、「だったら、こうしてみたら」といったら必ずかないます。(p198)
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「NASAより宇宙に近い町工場」の名前は株式会社植松電気。 産業廃棄物作業用のマグネットを開発・製作しているこの会社は、 パワーショベルに取付けるマグネットのシェアがほぼ100%という会社。 従業員17名の会社ながら素晴らしい業績を上げている会社です。 さらにこの会社の凄いところは自費でロケット開発を行っているというところ。 人工衛星も作り既にJAXAのロケットで宇宙に送り出していて、 NASAも使うという世界でも数少ない無重力実験棟まで有しています。 小さな町の小さな町工場がどうしてそういった躍進を続けているのか。 その秘密は「お金で得られない物を得る」という姿勢であり、 「出来ないことは無い」という前向きの姿勢であり、 「成功する秘訣は成功するまでやること」というアグレッシブな姿勢にあります。 読むだけで元気が出る一冊です。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからの新しい価値観の仕事のヒントが詰まっている本です。この本の作者のような考えが広まれば世の中が変わると思う。
0投稿日: 2011.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生、中学生に読んで欲しい本。親子で読むのもいいと思います。自分の夢について前向きに考えることができるはず。
0投稿日: 2011.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログローカルでグローバル、という自分のキーワードに引っかかって購入。 この世の中から「どうせ無理」という言葉をなくすために宇宙開発をはじめた著者。 好きなものを追い求めるためには、目の前の仕事をこなした上でいかに時間をつくって自分を磨くか。これも言うは易しであり、人間のダークサイドと向き合い、それでもなお実行して結果を残している著者に勇気づけられた。
0投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を書いた植松努さんは、とても発想がおもしろくて、少し変わった考えをもっています。でも、確かにそうだなと納得できることが多くて、気に入っています。植松さんが、失敗してしまって、上司に「反省の色が見えない」と言われてしまったそうです。その時植松さんは、「反省の色って何色なんだろう」と思ったのだと書いてありました。私は大笑いしてしまいました。でも本当に何色なのかなと思います。 この本を読むと、疑問に思うことがたくさん出てきました。 ぜひ読んでみてください。
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はきっとすごいと思って読んでみたら、 やっぱりすごかった。 「どうせ無理」よあきらめずに、 「だったら、こうしてみたら」と夢を追いかける大切さを説く本。 感動です。
2投稿日: 2011.08.21
