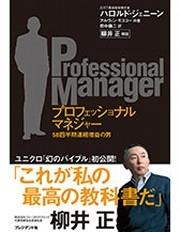
総合評価
(138件)| 29 | ||
| 49 | ||
| 36 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ不純な動機というかミーハーというか、ユニクロの柳井正が擦り切れるくらい読んだ本だというので興味を持って手に取った。別に柳井氏に憧れているわけでもないのに。そんなモチベーションだったので、物見遊山みたいな読書。少し古い本というのもあって最新の研究というよりも経営論なのか精神論なのかその両方の基本編という印象。 経営とは目標から逆算するものである。自分は何をやりたいのかをしっかり見定め、それをやり始めよ。そして数値化して計測し、体制を整え、責任を与えて任せよ。 最高経営者を中心としたトップ・マネジメント・チームの性格の反映として、どんな企業の中にもあって、それぞれの会社の個性をつくり出している。リーダーシップの質こそ、企業の成功をもたらす処方に含まれる最も重要な成分である。リーダーシップは学ぶことができる。他の人びとを導き、奮い立たせる能力は、計画的というより本能的なものであり、各人の日常の経験を通じて身に付き、そのリーダーシップの究極的な性質と特色は、リーダー自身の内奥の人格と個性から出てくるものだと。 ― ビジネスマンとして成功するにはどうすればいいかという質問を受けた。その時、私は学生たちに、それには若いうちは動きまわってさまざまな経験を積み、三〇か三五歳ぐらいになったらひとつの職業を選んで落着くことだと答えた。そうすればその人は三〇年から三五年を、その職業に身を捧げることができる。その間に、会社のトップ・マネジメントは三、四回以上交替するのが普通だ。だから、良いマネジャーには常に機会がある。若い人たちがすべきことは、ただ仕事を選び、それにむかって努力しはじめることだ。自分の人生の経営をも含めて、あらゆる経営について私が前に述べたように、自分は何をやりたいのかを見きわめ、それをやりはじめることだ・・・。 この本を読んでわかったのは、確かに柳井氏の精神性に本書が根付いている事。“当たり前”の事にも見える。この“当たり前”を根付かせるのが難しいのだという事も分かるが、恐らく私は、本書を繰り返し読んで身体化させるようなことはしないと思う。
84投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・若いうちは働き回ってさまざまな経験を積み、30か35歳ぐらいにやったらひとつの職業を選んで落ち着くこと。そうすれば、30年〜35年間はその職業に身を捧げる事ができる。その間に会社のトップは3,4回交代する。だから、良いマネージャーにはチャンスがある →37で転職経験がない人間を例に考える。今から色々な経験を積む事が出来るか? →YES!副業として経験を積んでいく事が出来る。転職だけが全てではない →総じて、プロフェッショナルとは何かを自問させられる書籍である。自分が掲げる目標は低くないか、高い視座を持って、言ったことをなにがなんでもやり抜く。グリットやり抜く力って感じ ・実績は実在であり、実績のみが実在である →痺れる心理ですな、含蓄が色々あるが、実績のみがその人を語るって事だね。お化粧はいくらでも出来るが、実績はお化粧出来ない。 人間の性格と同じだね。見た目可愛くても性格くそは結構いるもんな。実績が実在していない→存在しない存在なのか?
0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ理念や戦略など、ハロルド・ジェニーンの知恵と意識がキュッと詰まった本である。彼が活躍したのは1960-1970年代。時代が異なるとは言え、彼の訴えていることのなかにまだ実現されていないこともあるし、逆行してしまったこともあると思う。巻末の柳井さんの言葉も含蓄がある。沢山の経営本を読むよりも、こういう本を繰り返し読もうと思った。ハウツーものはそれこそ、瞬読(私の造語)すればよし。同書はじっくり心と身体に落とし込む本かなあ。
9投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログゴールから考えて行動する考え方、健康診断する様に会社の数字の意味を捉えて対処する話、会社には人事組織図に書かれている組織と血の通った人間関係の組織がある事を理解したマネジメントの話などなど参考になる話が沢山あり興味深く読んだ
0投稿日: 2025.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「58四半期連続増益の男」との副題からアグレッシブでバイタリティに満ち溢れた人物像を思い浮かべた。実際はかなりクレバーで分析力高く何より数字のロジックをもとに人々の意識の深いところへ訴えかけていくものだった。 最高の経営者像とは 自ら決断し目標、やるべきことを明言し失敗リスクを100%背負える 何をしたいのかを定め行動に移す 自らの行為と日常の態度により心から支持していることで人々を鼓舞する 最高の経営者に必要な資質とは 事実を客観的にとらえ、情報とノイズをはっきり区別し知的好奇心や根性も必要 事業計画と予算を定め達成の願望だけでなくやりきる推進力 論理だけでなく深いところの情緒により行動できる 今後の自分の行動に参考にしたいこと 多くの数字の報告とともにその質を上げる財務的アプローチ トップの思いを行き渡らせるサポートとしてパーパスの見える化 前始末の意識でリスクを最小限に、ノーサプライズこそ最高の状態 本書から経営に対する熱い思いとプロはこうあるものと迫力があった。 特に失敗リスクを100%背負うとあるがこれができる方はどれだけいるだろうか。 覚悟があるから強く、そして魅力的で人がついてくるのだろう。 やはり人間力、どれだけ信頼されまた周囲を動かす、鼓舞することができるか。
7投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ割と古そうな本ですが、きらり光る言葉が結構ありました。リーダーはクールな知能派じゃなく、戦線に立ち実績で語る者であるべしと感じさせられた。
0投稿日: 2025.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功者の回顧録かと思ったが、そうではなかった。これから先起こるであろう会社内での出来事が書かれた予言の書のように感じた。現代でも十二分に活用できる一冊だと思う。特にエゴチズムに関しては気をつけようと感じた。この先も自分が行き詰まったら本書を開いて学び直したい。若干冗長に感じたので星四つです。
0投稿日: 2025.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経営者=マネージャーとは…ということを説き、 MBAなどの机上知識ではなく実業に基づいた現場に根差した仕事をせよという強烈なメッセージ 仕事のための仕事…それが自己実現 現場まで降りていって最前線の情報を掴み、数字を抑えて判断していくことが肝要 そんな奴はクビにしろ、報酬は定時に対してではなく全時間に対しての報酬である…など M & Aについては足元のUSスチールの議論も彷彿とさせる
0投稿日: 2025.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログマッチョな経営論。 セオリー通り経営されて成功している企業はないと喝破。 軍隊ですらプラグマティックな動きをする。キャッシュカウ等各セグメントの社員のやる気を削ぐとする考えが、形式論に終始する組織論とは一線を画する。 ・過失は恥でも不面目でもない。ビジネスにつきものの一面であり、重要なのは自己の過失に立ち向かい、それらを吟味し、それから学び、自己のなすべきことをすることだ。唯一の本当の間違いは、間違いを犯すことを恐れることである。 ・経営とはかまどで料理をすること。鍋から目を離さない。 ・本を読む時は初めから終わりへと読む。事業の経営はそれとは逆だ。終わるから始めて、そのボトムラインに到達するためになさねばならぬあらゆることをするのだ。 ・予期しなかったものを獲得した時に得るものーそれが経験だ。 ・経営者は経営をしなくてはならない。自らが定めた条件を満たすためになんでもする。 ・人に何かをするなと命じるのはかまわない。しかし、本人が納得しないことをさせたかったら、納得するまで説得しなければならない。 ・それでも納得しない場合は、まず当事者である彼/彼女の考えで進め、進捗報告を受け、助言をした上で取捨選択させ、判断つきかねることがあれば相談する、主導権は当事者に置く、敬意を持った態度を取る。重要なのは誰が正しいかではなく、何が正しいか。 ・リーダーシップは経営と分かち難いが、客観的な管理とは異なる。人から学ぶことができない。自身の人生、経験のみから学ぶ。
0投稿日: 2024.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログマネージャーだけでなく、全てのメンバーが持つべき視座・視点! ①「唯一の本当の間違いは、間違いを犯すことを恐れること」 ②チームを組むには「努力に値する」目標と情熱の共有が必要。 高い目標を示さない限り、誰も熱狂的に仕事をしない。 ③ビジネスはかまどで作る料理のようなもの。 重要な決定はマニュアルではなく、決定は人物の内部から出てこなくてはいけない。 ④「ビジネスは誰もが二通りの通貨-金銭と経験-で報酬を支払われる。金は後回しにして、まず経験を取れ」 ⑤良いセールスマンであるためには良い人間たれ。 肉体も頭脳も精神も清潔そのもので、正直で率直であること。 ⑥階層に関係なくだれもが直接に意見を述べ合い、いかなる状況に関しても現実の事実に基づいて検討がおこなわれるような場をつくる。 ⑦マネジメントの良否はそれがみずから設定した目標を達成するかどうかによって判定され、その目標が高ければ高いほど良いマネジメントだといえる。 ex.マラソン選手 ⑧事業はスポーツに似ている。 サッカーでは監督はゴールへのルールと戦略を示し、ポジションを割り振る。 しかし、「ここでキックしろ」の命令はできない。 ⑨「経営者は経営をしなくてはならない」
9投稿日: 2024.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログファーストリテイリングの柳井会長のお勧めマネジメント本。内容は可もなく不可もなく。自分に有益だと思う箇所のみメモに書き留めれば良いと思います。
0投稿日: 2023.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉は言葉、説明は説明、約束は約束…何もとりたてて言うべき事はない。だが実績は実在であり、実績のみが実在である。ITT社を58四半期連続増益に導いたハロルド・ジェニーン氏の名著です。
0投稿日: 2023.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#プロフェッショナルマネジャー』 ほぼ日書評 Day631 ユニクロ創業者である柳井正氏が、本書の翻訳版初版に出会い「経営の教科書」とまで惚れ込んだのは、1985年、ユニクロの1号店を出し、その翌年に2店舗目を出した時分である。 評者が手に取ったのは2004年初版のバージョンのため、若干の改訳もなされていると思うが、それでもかなり読みづらいものを、当時の柳井氏はやはり志が高かったのだろうと恐れ入る。 それから40年近くが経ち、米国流経営に関する知識や、MBA的な知見も一般的になった今、冒頭と巻末の柳井氏の解説を読んでおけば十分という話もあるが、本文の斜め読みだけでも、真に実績を上げた経営者の発想法(と同時にストレスフルさ加減)を垣間見ることができる。 https://amzn.to/3Rzk63n
0投稿日: 2023.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者の中の経営者が書いてるなって本だった。 一介の従業員である自分にとっては、視点がなかなか付いていけない内容が多く読むのが難しかったが、経営者の立場にある人は納得できるところが多いのかなとも感じた。 だから、柳井氏にとっては最高の教科書と言わしめるような内容になっているのかなと。 「本を読む時は、はじめから終わりへと読む。ビジネスの経営はそれとは逆だ。終わりからはじめて、それへ到達するためにできる限りのことをするのだ」 これは経営者でま従業員でも、なるほどと思える内容。 目の前のことを一生懸命やり積み上げるのももちろん必要だが、将来を創造してバックキャストすること、その重要性を改めて認識できた。 巻末の柳井氏の言葉はグサッと刺さってきた。 ここだけを読むのもありだと思う。
0投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ柳井正さん推薦ということで手に取ったけど、自分にとっては柳井正さんの本のほうが参考になると思いました。米国と日本では企業文化も違うし、2004年という時代もまた、今とは違う。
2投稿日: 2021.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営とかマネジメントとかって、つまりお金の出入りをともなう組織運営なのだろうな、なんてのが漠然とした印象だった。俺自身は心理学科卒だからさぁ、経営とか経営学といわれてもピンとこないところはあったんだよね。「世界標準の経営理論」とか読んでみたけれど、マーケティングをいうのか、アカウンティングをいうのか、はたまた経済学とどうちがうのか、漠然とした印象しかつかめなくてね。 本書を読んで、「あぁ」と腑に落ちるところがあったと思う。へぇ、じゃあなんだったの?と自分に問い返してみると、いや、お金の出入りをともなう組織運営のことなんだけどね、と同じことの繰り返しになってしまうんだけど、それでも自分の中の納得感は違うのだ。 「本を読むときは、はじめからおわりへと読む。 ビジネスの経営はそれとは逆だ。 終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ。」 とは、至言だ。経営、マネジメントのノウハウといったって、こうすればよいというやり方があるのとはちがう。ただ「できる限りのことをする」のだ。 「経営者は経営しなくてはならぬ!」 あはは。そうだよね。でも、現実に何をすればいいのかわかんないから、ふんぞりかえって終わる人が多いのではないだろうか。結果、官僚主義、つまり前例の踏襲で終わってしまう。 エゴチズムの部分とか、自分をふりかえって、そんなつもりはなかったけど、俺自身エゴチズムの毒に侵されている部分はないか?なんてイタかった。 90年代前後のアメリカに向けて書かれた本ではあるが、今の日本の企業や組織運営にかかわる人が読んで、大きくためになるものだと思う。 何度も読み返すべき本だろうな。
0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ楠教授とユニクロの柳井さんがおすすめということで読む。 もう少し経ってからまた読み返したい。 誰だって初めは経験不足で、それから段々経験を積んでいくんだ。ただ、十分な経験を積むまでに、大抵歳を取り過ぎてしまう。 2022/11/14 簡単に読み返す。 ゴールを決めて、そこから逆算するということを実践したい。 経営とは目標を達成すること。
0投稿日: 2021.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ柳井さんの付録が秀逸。そこにすべてが書かれている。 この本で書かれたことをユニクロで取り組んだと書いてある。 ユニクロを知っているだけに、わかりやすかった。 1,まずは目標を設定し「逆算」せよ 2, 部下の報告ー「5つの事実」をどう見分けるかー 「揺るがすことができない事実」「表面的な事実(一見事実と見えること)」「仮定的事実(事実とみなされていること」「報告された事実(事実として報告されたこと)」「希望的事実(願わくば事実であってほしい事柄)」 3,リーダーシップー現場と「緊張感ある対等関係」をつくれ 目標と戦略と方法論は示すが、あとは個々に考えて、一緒にやりましょう 一番いい会社は社長の言っていることがその通り行われない会社 会社を統率する人間は、その会社の人々が本当は彼のために働いているのではないということを認識しなくてはいけない。彼らは彼と一緒に自分自身のために働いているのだ。彼らはそれぞれに自分の夢を、自己達成への欲求を持っている。 4,意思決定ーロジカルシンキングの限界を知れ 社長の机がきれいなら、副社長以下が仕事を抱えている 経営者は経営しなければならぬ 5,部下指導法ーオレオレ社員の台頭を許すな ミドルマネジメントでもトップマネジメントでも、ほしいままに放任されたエゴチスムは、周囲の現実をその本人に見えなくさせる。彼はしだいに自分自身の幻想の世界に生きるようになり、しかも自分は絶対に誤りを起こさないと本気で信じているために、下で働く人々を困らせる 成功は失敗よりずっと扱いにくい 6,数字は握力ーデータの背後にあるものを読み解け 数字の含蓄を成就するには、数字が持つ意味の絶えざる暴露、絶えざる反復、過去に読んだものの保持、そして数字が代表する実際の活動への親近によるほかない 7,後継ぎ育成法ー「社員FC制度」が究極の形だ 企業の給与水準は、会社の従業員、マネジャー、役員のすべてを満足させ、幸福にし、もっとたくさんもらえるようになろうと努力させ続けると同時に、会社自体の利益をも確保できるように考案された、微妙な価値体系である
0投稿日: 2021.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ机の上が散らかっているかいないかの視点は、他の人の考え方と違い、新たな知見を得た。 物事を多角的に見るって大事。
0投稿日: 2021.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【要点】 ①経営の秘訣 本を読む順番と、経営の順番は逆。 →本を読むときは初めから終わりへと 読む。一方で、経営は未来から現在 にかけて遡って行動する。 ※逆算思考が大事。ゴールを明確にする 事でやるべきアクションプランを整理 でき、適時・的確な判断を下すことが できる。 ②二つの組織 ビジネス上の(ロジカルな)組織とプラ イベート上の(エモーショナルな)組織 のことをいう。 自分の欠点を補うため「チーム」が大事 であるが、チームを信頼してよいかどう かの判断材料はエモーショナルな部分も 一因となる。 ③数字は会社の体温計 現状把握をするには数字(事実)が大事。 数字を把握できてないと計画・対策を立 てられない。 数字がわからなければ逆転の発想ができ ない。 ④経営者の条件 ・自ら定めた目標を達成する又はやり きる力が必要となる。 (情熱・忍耐力・謙虚さが必要となる) ・リーダーシップは最も重要な一要素 である。 【感想】 本書は、経営者から見た組織論並びに リーダーシップ論等の内容が記されて いるものの、一会社におけるコンピテ ンシー(行動規範)にあたる内容で あり、本書の内容を実践していけば、 いわゆる「デキるビジネスパーソン」 に近づくことができると感じた。 特にマジージャー層のビジネスパー ソンに一読してほしい内容となって いる。
1投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログファストリの柳井さんも監修?の書籍です 13の経営に関わる内容、真髄が書かれている本となります 正しくは14(全14章構成) 個人的に勉強になったのは ・帯にも書かれている第二章 三行の経営論 本を読むときは初めからおわりへと読む ビジネスの経営はそれとは逆だ 終わりから始めてそこへと到達するためにできる限りのことをするのだ ・三章 ニューヨーク大学の教授が言っていた 成功したいのであれば、みずから選んだにせよ巡り合わせだとしても 自分が属する場所て上位20%のグループに入ることが必要 ・五章 マネジャーは、 結果を達成したいと思うだけでは不十分 達成すると誓ったことを成し遂げること ・5章 ビジネスにおいては 競争相手よりまさればいいという点 ・9章 数字が示すこと 数字のみでは、何をなすべきか教えてくれないが 指標となること
0投稿日: 2020.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営のプロフェッショナルの方達が、どのような考え、想いを持って経営をしているのか、色々なエッセンスがつまった本だなと思います。 中間管理職の今の自分の立ち位置からは普段見えていない取締役会のあり方も参考になりましたし、数字をきちんと追いかけることの大事さなどマネジメントとして絶対に外せないことも改めて実感しました。 巻末に改めて柳井さんのコメントがあり、振り返りができました。きっと繰り返し読むことでもっと新たな気づきがあると思うので、現時点では(自分がその良さに気づけていないので)星4つです。
0投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、ユニクロCEOの柳井氏が「はじめに」を書いて解説している。その解説が面白くて読み始めた。 柳井氏は父親から事業を受け継ぎ、ユニクロを広島でオープンし、次いで岡山に2店をオープンしたころにこの本に出会ったという。 「山口県宇部市の書店にたった一冊置かれていた」この本を、柳井氏は山口県で唯一の読者と(思い込んで)読み、三行の経営論に衝撃を受けた。 『本を読む時は、初めから終わりへと読む。 ビジネスの経営はそれとは逆だ。 終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ。』 この本の著者、ハロルド・ジェニーン氏は経営者として、58四半期連続増益を出し結果を残しているが、本書を読むと、バリバリの厳しい経営者の姿というより、人間らしさがにじみ出ていて親しみを感じる。 企業家は常に正しい考えを持ち、ルールに従い正しい行いをしなければならない。 近道はない。見せかけやごまかしはすぐばれる。 そして、設定した目標に必ず到達しなければならない。 一人であれば自分だけのマネージメントをすればよい。 しかし、何千人、何万人も従業員のいる大企業では、どうやってその人たちに同じ目標に向かって力を出してもらうか。 いろいろな成功した経営者がいるが、この本を読むと、この人の下で働きたいと思わせられる。
0投稿日: 2020.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログファーストリテイリングの柳井正会長が「最高の教科書」と勧める本。 経営はまず結論ありきという、終わりから始める経営を実践するためのノウハウや対処法、心構えが具体的に記されている。 過失は恥でも不面目でもない。ビジネスにつきものの一面であり、重要なのは自己の過失に立ち向かい、それらを吟味し、学び、自己のなすべきをすることだ。唯一の本当の間違いは、間違いを犯すことを恐れることである。
0投稿日: 2019.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ終わりから始めて、到達するためにできる限りのことをする。ただし長期計画を当てにして短期を疎かにせず、短期であらゆる手を打つ。 マネジメントとは結果を達成すること。実績のみが実在であり、上手くいくまで試行錯誤する。 揺るがすことができない事実、をチェックする。 成功から学べるか?
0投稿日: 2019.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロの柳井さんは、人材育成に自分の時間を3割を割き、今後は5割以上にしたいらしい。その柳井さんが経営の教科書と高く評価するのが本書。「経営者は経営すべし」という身も蓋もない宣言であるが、スポーツマンや職人のように、「経営道を極める」ために努力に努力を重ねる経営者がどれくらいいるかと言われれば、確かに心許ない。最初から最後まで読むのが良いが、忙しい人は、巻末の柳井さんの解説を読むだけでも十分勉強になる
0投稿日: 2019.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ中間管理職になってしまった俺。 組織のマネジメントを考えたくて読んでみた。 説得力のある力強い言葉が、心に響く…
0投稿日: 2019.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の苦手な経営者の一人、柳井正氏の推薦という点もあり、なかなか読まなかった1冊でした。が、これは素晴らしい本です。 特に、共著として名を連ねているアルヴィン・モスコー氏というベストセラー作家の筆のさえもあり、読み物としても面白く仕上がっています。 経営者としてはまさにたたき上げのジェニー氏の体験談からくるエピソードは説得力があり示唆に富む。 例えば、事実にも種類がある・・ 表面的な事実(一見事実のようにみえる)、仮定的事実(事実とみなされている)、報告された事実(事実として報告された)、希望的事実(願わくば事実であってほしい)などはほとんど事実ではない。(P108) 第6章の「リーダーシップ」、第7章「エグゼクティブの机」、第8章「エゴチスム」などは現場を知り尽くした知恵とでもいうべきものでとても得るところが多い。 第12章「取締役会」は1985年の初版以来、本書で指摘された問題は35年間未だに解決されないままで、多くの経営者には耳の痛い話だと思われる。 「取締役会のメンバーに支払われる報酬額も再検討されるべきかもしれない。もし彼らがその報酬に依存しているのであれば、どうして自主的にふるまえよう。たいていの取締役の報酬は、それを得るためになされる働きに対しては高すぎ、なされるべき働きに対するものとしては低すぎるように思われる」(P274) 第13章「結びとして」でのまとめ(P297)も必読です。 そして、本書のはじめにとあとがき(付録)で、柳井氏の解説が展開されるわけですが、その文章には「僕は今、売上高1兆円構想の設計図を描いている」という言葉がある。2004年発行から15年たった今、売り上げ高は2兆円に迫ろうとしています。本書を教科書にした経営を愚直に行った結果ですので、これほど頼もしい宣伝効果はないでしょう。 とはいえ、故人となったジェニーン氏の人柄は知る由もありませんが、なぜかジェニーン氏となら一緒に働きたいと思うが、柳井氏とはちょっと無理というのも読後の正直な気持ちです。
1投稿日: 2019.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営とは逆算。目標から逆算して何をやるか決め、実行すること ビジネスの対価は報酬か経験。まず経験をとれ 目標に達するまで挑み続ける事が経営 達成しなければ経営でない ビジネスは競争相手に勝てればよい リーダーシップは学ぶ事は出来るが、ほとんどが自身の経験でしか学べない。 ビジネスの成功がリーダーをエゴチスムに追いやり、組織を衰退に追いやる。 数字は行動へのシグナル、思考の引き金。 肝心なのは数字の背後で何が起きているか突き止めること マネジメントの良否は自ら設定した目標を達成するかどうかで判定され、目標が高ければ高いほど良いマネジメント。 あまりに低い目標は誰でも達成できるからマネジメントと呼ばない リーダーシップの力の源泉は論理ではなく、深い情緒 なすべき事をしようとする原動力は論理ではなく、深い所に内在する情緒
0投稿日: 2019.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ遨阪s隱ュ迥カ諷九〒縺励◆縺後?√d縺」縺ィ隱ュ縺ソ邨ゅo繧翫∪縺励◆縲ょョ滄圀縺ョ讌ュ蜍吶↓豢サ縺九○繧九°縺ゥ縺?°縺ッ縺輔※縺翫″縲∬ェュ縺ソ迚ゥ縺ィ縺励※髱「逋ス縺?〒縺吶?ら樟蝣エ縺ァ襍キ縺阪※縺?k蝠城。後?縲∝クク縺ォ莠コ髢薙′髢「菫ゅ@縺ヲ縺?k縺ョ縺ァ縺吶?ゆシ∵・ュ縺ョ隕乗ィ。縺ッ蝠上o縺壹?∝撫鬘後?譛ャ雉ェ縺ッ縺昴%縺ォ縺ゅk繧医≧縺ァ縺吶?
0投稿日: 2019.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・購入背景 ある本(確かストーリーとしての競争戦略)で引用されていたのをきっかけに知る。 58四半期連続増収を成し遂げた男ハロルド・ジェニーンの社長としての日々を通して経営者としての重要なマインド・スタンスが、具体的な事例を伴って書かれている。 ファーストリテイリング代表柳井正さんが「私の最高の教科書」と絶賛していることもあり、購入した。 ・この本を読んで自分がどう変わったか? ビジネスにとどまらず人生を歩んでき上で持つべきマインドのヒントを得た。まだ働いていないため具体的にイメージしにくい部分もあったので、社会人になってから読み返すことでより一層理解を深められると感じる。手元に常においておきたい一冊。 ・内容 ビジネスで結果を残すにあたって持つべきマインドを教えてくれた一冊であった。ハロルド・ジェニーン本人の体験談も面白いが、巻末の柳井さんの解説がよくまとまっていると思う。本文は少し冗長であるため、時間がない人や要点だけをサクッと知りたい人は、巻末だけを読む、あるいは『超訳・速習・図解 プロフェッショナルマネジャー・ノート』を手にするのもありかもしれない。ただ、その場合、ジェニーン氏の言葉が「ろ過されて要約されて概略しか届かなくなり、本当を知ることができなく」なるかもしれないので、その点にはご注意を。 ・個人的に印象的だった箇所 1.三行経営論とボトムライン 2.金は後回しだ、まず経験を取れ。 3.5つの事実 ここでは特に3について深く触れたい。 3.5つの事実 5つの事実は、ジェニーン氏が実際にITTの社長として働く中で全社のマネージャーに宛てたメモの中で登場している。彼曰く、事実は5種類存在する。 ①本当の事実(揺るがすことのできない客観的な事柄) ②表面的な事実(一見事実と見える事柄) ③仮定的事実(事実とみなされている事柄) ④報告された事(事実として報告された事柄) ⑤希望的事実(願わくば事実であってほしい事柄) 経営判断するにあたっての貴重な判断材料となる事実といのは1番目だけだであって、2番目以降は逆に誤った経営判断を導かねない間違いを含んだ事実なのである。私達にも覚えがあるのではないだろうか。「〇〇さんから聞いた話です」「一般的に△△だとされている」「このことから◻◻と(好意的に)解釈できます」などなど。人間は人からよく見られたい、評価されたいという心理が働くため、少し盛った事柄を報告をしてしまうこともある。ただ、それらは、全然事実でない事実なのであり、これにより「計り知れない金と時間と士気のロス」がもたらされているということが述べられている。そこでプロフェッショナル・マネージャーに求められるのが「本当の事実を嗅ぎ分ける能力」なのである。それでここからが重用なのだが、ジェニーン氏はその嗅ぎ分けるための方法としてメモに付言を残している。 一見してどんな印象を受けようとも、念のため、必ずそれを”揺すって”みること。 常識や一般論を疑えと最近よく言われているが、やはり一度揺さぶってみることの重要性は大きいようである。
0投稿日: 2019.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ成長を実現する経営者には、色々な考え方がある。十人の人間がいれば、十人の考え方、特徴があるように。誰一人として同じ考え方で行動している人はいない。 要は、徹底できるかどうか。 それに尽きるのではないか。 「経営の鬼神」 ハロルド・ジェニーン。 徹底度合いが強烈。猛烈。ワーカホリック。仕事に全身全霊。 キモは、それだけ思い入れられることに出会うか。もしくは、目の前にあることに1000%の思いを込められるか。
0投稿日: 2019.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分は経営者ではありませんが、経営管理に携わるものとして、心に留めておきたい心構えがたくさん書かれている良著でした。 特に、「経営とは最初に決めた目標を達成するまでできる限りの手を尽くすことであり、手を尽くさずに不十分な結果を受け入れて理由をつけて弁解してはならない」というところは、心に刻んでおこうと思いました。
0投稿日: 2019.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経営者は経営しなくてはならぬ 本を読むのとは逆にゴールを設定しその目標に対して達成する為に行動する 柳井さんが考えていることや学びになっていることも記載されていて勉強になった。 リーダーシップを発揮し、言い訳せずにチームをまとめて事業に集中させる 今後の仕事で大切にしたいと思う。
0投稿日: 2019.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ●ユニクロの柳井正氏が「これが私の最強の教科書だ」と紹介しており、それで興味を持ち読み始めた。「第9章 数字が意味するもの」がとりわけ興味深かった。
0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「経営者は、経営しなければならない」、「本は前から読み、ビジネスは後ろから行う」等、一見理解しがたい短文が、この本全体に流れるエッセンスである。経営とは?・マネージャとは?・ビジネスとは?等を考える前にぜひ読むべき。深い考察のためのヒントになるでしょう。
0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディオブックにて視聴。 著者はかつて巨大コングロマリットとして知られた米ITTの社長兼CEOとして、14年半に及ぶ連続増益を遂げた伝説的な経営者。 聴き始めて少しして「うーん、引退した経営者の自分語りか。」と感じたのも束の間、どんどんと内容に引き込まれていく。骨の髄まで経営者の著者が「理論だとこうなんだけど、実際はそんなうまくいかないよね」と、理論を引き合いに出して経験則を述べる辺りはかなり興味深い。 著者なりの組織論、リーダーシップ論、経営者論(マネジャー論)、アントレプレナーシップ論は、経営学科出身の自分、則ち学問的なこれらの理論を学んだ自分としては正直耳に痛い。セオリーX、セオリーYは流石に僕らも”そんなものがある”程度にしか教えられなかったが、PPMなんて未だに”現役”なのだ。 経営に興味がある、将来は企業経営に携わりたいと思う人であれば、一度は読んでおくことをお奨めしたい。本書に美しい理論など書かれていないが、生粋の経営者の生き様それ自体が大変大きな学びとなること請け合いである。
0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ米巨大コングロマリットITTを1959年から率い58四半期連続増益を成し遂げた著者の経営論、哲学。ファーストリテイリング柳井会長が教科書とまで言う宣伝は全くの虚飾無しと読了して確認した。コングロマリットのCEOではあるがミドルマネジメントにとっても付加価値は大きい。毎年読み返そう。 「本を読む時は、初めから終わりへと読む。ビジネスの経営はそれとは逆だ。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをする」「経営者は経営しなくてはならない」
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ楠木建の「戦略読書日記」で紹介されていた本。名経営者の著書はだいたい外れがないので、相当期待して読んだが、「真面目かっ!」と突っ込んでしまいたくなるほどまじめすぎる内容で、正直面白くなかった。 尋常ない勤勉な人で驚くほかない。 唯一、面白いなあと思ったのは、エグゼクティブの机は汚い、と言い切っていること。これは楠木氏も解説者の柳井氏も触れていた。 「私が反対するのは、きれいな机のエグゼクティブのオフィスの様子とか机の上の状態よりむしろ、彼の心的態度に対してである。きれいな机は科学的経営への、ビジネス・スクール仕立ての方式への、データ整理保存への、過度に厳格な時間配分への、機構化した権限委譲への、そしてまた未来が自分のプラン通りのものを生み出すという当てにならない確信に基づいた無保証の自信と独りよがりへの固執を象徴している。そんなものを、夢にも信じてはならない。」
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025-01-02 二度目の読書 2018-10-06 米国の経営者の自伝。ユニクロ柳井社長推薦。経営者の教科書として最良の書籍。経営の秘訣は終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをすること
0投稿日: 2018.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログAmazonで上位にランクされていたので読んでみた。 相変わらず、和訳の本は読みにくいと思う。 外国人の名前は頭に入らないし、「彼」とは誰のことなのか読み返さないとわからない。 「マネジャー」「エグゼクティブ」「リーダー」が何なのかを理解してから読むべきだった。 経営の基本も知らない私が読む本ではなかった。
0投稿日: 2018.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業経営者の心構えを書いた本。原題は「MANAGING」で、邦題は中間管理職狙いでしょうか。。 無知で大変恐縮ながら、著者が長年CEOを務めたアメリカのITTって、コングロマリットの元祖的な存在で、シェラトンホテルやエイビスレンタカーが傘下にあったんですね。NTT似の何かかと思ったら、全然通信事業者じゃない(笑 コングロマリットって、今でこそ「選択と集中」やら「シナジー効果が!」とか言われて時代遅れな感がありますが、ポートフォリオを適切に選択し、経営改善をやっていくという意味では悪くないのかも。恐ろしく乱暴な表現では、投資ファンド(アクティビスト?)のちょっと持分も口出しも多いバージョン? 読んでみると、時代の差を凄く感じます。 本著で「ガッツのある」と表現される働き方は「成果が出るまで根性でやるんだよ!」的な印象だし、テレックスとか紙とかアルコール中毒とか、時代を感じます。。 とは言え、企業経営には情緒的態度、やり遂げる根性が重要とする著者の論が間違いだとも思わないので、読んでみて損ではないのかも。 全体的に、間違ってはいないけど、日本企業でも既にある程度取り入れられているんじゃないかな…?という感じの内容でした。一部はまぁうちの会社には無理かなと思っちゃうところもありましたが。。 ファストリの柳井社長が愛読されているようで、まえがきと解説を書かれています。 なお、翻訳は超読みやすい訳ではないですが、概ね良好でした。「季員会」というめずらしい誤植があったけど。
1投稿日: 2018.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそもITTなる会社を知らないので、ハロルド・ジェニーンなる人がどれだけすごいことをしたのか皆目検討がつかず、この人の言葉に従うべきかがわからない。柳井正の座右の書のようなことだったので買ってみたが、先のとおり今は存在しないITTなる会社を成功させた人の本らしいが、今は存在しない会社なのだし結果論としては大した経営をしていなかったとも言えると思う。ジャックウェルチにしても結局今のGEの体たらくを招いた責任はあるだろうし、企業経営などというのはその時だけで判断できる訳ではないと思う。内容の点から言うと、経営者たるもの24時間365日働かなくてはダメだというもっともなことと、マイクロマネージメントが大事だといういかにもアングロサクソン的なことが書いてある。チームワークももちろん大事だし、しかしながら人事評価はとにかく冷徹にするということで、とても日本企業には向かないような内容。この本の内容とは真逆の日本的経営がもてはやされた時代もあったことを考えると、結局は経営に答えなどないのだと思う(本書でもそのようなことは言っているが。。。)。とにかく、この本を読むと自分は経営者にはなりたくないし、向いていないと思うし、またこのような人の下では息もできないので働きたくもないと思う。柳井正が信奉しているらしいので、ユニクロもそんな会社なのだろうか?
1投稿日: 2018.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「経営とは、ゴールを決めてそれに向かってやるべきことをやることである。」 元ITT最高責任者で、58期連続増益をあげたハロルド・ジェニーンの経営論。柳井さんがおすすめしているので読んだことがある人も多いだろう。 彼の経験を元に、経営論が書かれた本。マネージャーになる前に読んでおくと良い。
1投稿日: 2017.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2年ほど前に「読め」と言って渡されていたんですが、ようやく読みました。 至極まっとうな内容だとは思いますが、読むことになった経緯が経緯なだけに、複雑な思いをしながら、読み進めました。 さて、どうやって自分の中で折り合いをつけていきましょうか。 ちなみに、最後に、ユニクロの柳井さんの文章が載っていますが、こちらは、この本のエッセンスを知る上で最適だと思います。 時間がない方は、まずこちらから読んでもいいかもしれません。
0投稿日: 2017.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ・本を読むときは、 はじめから終わりへと読む。ビジネスの経営はその逆。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ ・リーダーシップが発揮されるのは、言葉より態度と行為においてである ・経験とは、なにか新しいことを発見し、学び、能力の成長をもたらすプロセスである
0投稿日: 2017.01.09再読したらどうなるか?
ユニクロの柳井さんが「最高の教科書」ってお勧めしているのは知ってたけど、それほど興味もなく。。。で、ちょっと電子書籍版が安くなっているタイミングがあったのでとりあえず購入。(^^; 内容的にはなるほど!、ってところも一部あるのですが、結構大半がやってきたことをつらつらと書き連ねる感じで、何とも微妙な本だったという印象。 つまらなさそうなところは思いっきり斜め読みしたので、どこかで再読したらまた評価は変わるかな?
0投稿日: 2016.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ・⭐️本を読む時は始めから終わりへと読む、ビジネスの経営はそれとは逆だ、終わりから始めてそこへ 到達するためにできる限りのことをするのだ ハロルド ジェニーン ・⭐️「経営はまず結論ありき」、結論に至る方法を考えられる限り考え、いいと思う順からまず実行する。 ・⭐️ビジネスは結果でしか評価されない ・実地により学習する
0投稿日: 2016.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログしぶい。 極太の気骨と覇気が伝わってきてシビれる。 「経営する、とはマネージャーなり、チームなりが努力に値することとして始めたことを達成することである」
0投稿日: 2016.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から読んでみたいと思っていた本。夏休みで少し時間ができたので読んでみた。 柳井氏はじめネット等で言われているように、確かに究極のビジネス書。納得させられることが多い。汚い机の話は、私自身、多忙さからオフィスの机を片付ける時間がなく散らかっているのでこれはなるほど、と思った。 ただ一つ、ジェニーンにはブランドを育てる、という視点が欠けている。
0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書はITTというコングロマリットの最高経営責任者であったハロルド・ジェニーン氏の経験に基づいた経営のあるべき姿について語られている。きわめて実践的な、飾り気がないが、厳しい、地に足のついたメッセージが伝えられている。全体としてきわめて基本的だが、多くの経営者が陥りやすそうな罠に警告を与えている印象を持った。 印象に残ったのは「本を読むときは初めから終わりへと読む。ビジネスの経営はそれとは逆だ。終わりから始めて、そこえ到達するためにできる限りのことをするのだ」という彼の経営論だ。彼は経験を重視しMBAに代表される机上の理論に偏重した経営を批判する。 経営者は自分で事業の内容を理解し自分で経営をしなくてはならない。理屈ではなく目標を達成するために何とかして必ず達成してみせるという力を持たなくてはならないし、経営は人間相手のことであることも忘れてはならない。組織は表面的な組織図とは別の実際の人の血の通ったもう一つの組織図が存在することをしっかり見抜く必要がある。彼はまた数字の背後で起こっていくことを見抜くことも強調している。彼の経験で当初放置されていたヨーロッパの現地法人に毎月実際に出向いて各事業の責任者からの月次報告をFace to Faceで議論するようになった経緯が紹介されている。また組織の最悪の病はエゴチスムとしており、過去の成功を盾に全体最適を考えず自己最適に走る社員にはしかるべき対処をすべきことを強調している。
0投稿日: 2016.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ米国のコングロマリット(多国籍企業)であるITT(インターナショナル・テレフォン・アンド・テレグラフ・カンパニー、一九七七年以後グループは解体へ)の元最高経営責任者、ハロルド・ジェニーン氏の経営回想録 「過失は恥でも不面目でもない。ビジネスにつきものの一面であり、重要なのは自己の過失に立ち向かい、それらを吟味し、それから学び、自己のなすべきことをすることだ。唯一の本当の間違いは、間違いを犯すことを恐れることである」 僕はずっと失敗してきた。今までのビジネスも一勝九敗ぐらいである。唯一成功したのがユニクロだ。 僕はもともと商売はうまくいかないものだと思っているが、「失敗しなければ成功はない」とも信じている。大事なことは、その失敗で会社を潰さないことだ。同時に、失敗の問題点を摘出し、失敗する前に対処するように心がけている。 高い目標を示さない限り、誰も熱狂的に仕事をしない。 経営スタッフと生産ライン 農工商 商が儲かる 農がないと成り立たない われわれは常になにかの種類の妙薬、誇大なうたい文句とともに売り出される特効薬を求めてやまない。ビジネスの世界ですら、この事情は変わらず、そこではそうした妙薬は新理論と呼ばれる。というのは、われわれは常に複雑な問題を解いてくれる単純な公式を求めているからである。こぎれいに包装され、魅力的なラベルが貼られているものならほとんど何でも、効能への期待をこめて糖衣錠のように嚥みくだされる。ビジネス理論というものは、おおむねそうしたものだ。 マサチューセッツ工科大学のダグラス・マグレガー教授によって編み出された“セオリーX”と“セオリーY”があった。セオリーXとYのすばらしさは、企業経営のすべてを適用範囲の中にとりこんでいることだ。 どっちみち時間動作分析は、そうした科学まがいの大騒ぎをしなくても、有能な職長あるいは監督なら、それぞれの仕事の現場で、もっとずっと簡単に能率を上げさせることができる、低いレベルの反復的な作業にしか適用できないものだった もし“キャッシュ・カウ”の方式にまだ誘惑を感じる人があるなら、その人はこう自分にたずねてみるといい。 ビジネスは科学ではないというだけのことだ 各自の道を切り開いていく助けとなることはいうまでもない。それらは、実際への応用が適切とされる時、縦横に駆使されるべき経営の道具である。ただ、人びとは経営決定への安易な、組織化されたアプローチを求めて、理論や固定した方式に寄りかかりすぎる傾向がある なぜならビジネスは人生と同様に、どんなチェックリストにも方式にも理論にも完全にはおさめきれない、活力にあふれた流動的なものだからである。 私は一人か二人、あるいは何人かの人間にたずねることを常とした。「きみはどう思う?」と。そうして手もとにある事実に基づいた考えとひらめきを交換し合った後に、よかれあしかれ、われわれは決定をくだした。われわれは進んで行きながら学んだ。経験の貯蔵はしだいに豊かになり、前より複雑な問題を前より早く、前より上手に処理できるようになった。自分の能力に、前より自信がもてるようになった。しかし、経営の技術をひとつの方式にまとめようという気にならなかった。たったひとつの、どんな決定に関しても、自分たちは正しいことをしたと完全に確信できたことはなかった。 ある程度まで調理法にしたがうだろうが、なにか自分自身の特別なものを付け足すだろう。調味料やスパイスを入れるのに、いちいち計量しはしない。適当に振りこんだり、注いだりする。それから料理ができていくのを見守る。鍋から目を離さない。時どき出来具合を見る。においを嗅ぐ。指をつっこんで味見をする。自分の好みに合うように、またすこし何かを添加するかもしれない。そしてそれが全体の中にとけこむのを待って、また味見をする。それから同じことをもう一度。もし何かが気に入らなければ、それを修正する。 業績とは、ある四半期または一年の損益計算書についてあげつらわれるものではない。業績とは、長期にわたって会社に組みこまれたものである。 に終わりから始めることのすばらしい点は、それ自体が、その目的に達するためになすべきことを示してくれ始めるところにある。 コンサルタント会社のマッキンゼー社が給与基準とボーナスと、自社株購入権による報奨制度の立案に当たることになった。 ヨーロッパでの競争には──とりわけフィリップスとジーメンス 初めのころのわれわれの会議は、持てる国々と持たざる国々との国際連合の会議のようだった。 ニューヨークでは、文書になった要求を読んで、ノーと言うかもしれない。しかし、もしヨーロッパにいたら、私はその男の顔を見、声を聞いて、彼の信念の固さを理解し、同じ問いに対してイエスと答えるかもしれない。 私は一七年のあいだ、夏季休暇とクリスマスという差し障りのある八月と一二月を除いて、毎月一週間、しかるべきスタッフを帯同してヨーロッパへ行って、そうして一事が万事、問題は現場で、顔と顔を突き合わせて処理するのがわれわれの会社の基本方針となった。 最初の四半期に目標を達成できなかったら、けっして年間の目標を達成することはできない 、と私はみんなに言った。──まず、とにかく最初の四半期に予定された収益目標を達成するのだ。それから第2、つぎに第3の四半期の目標を。そうしたら、もしかしたら第4四半期は、あまり努力しなくても計画通りにいくかもしれない、と。 もっと単純かもしれない別の言い方をすればこうなる。──自分は何をやりたいのかをしっかり見定め、それをやり始めよ。 しかし、言うは易く、おこなうは難しだ。肝心なのはおこなうことである。 ビジネスの世界では、だれもが二通りの通貨──金銭と経験──で報酬を支払われる。金は後回しにして、まず経験を取れ。 「諸君がビジネスで成功したかったら、みずから選んだにせよ、めぐり合わせで身を置くようになったにせよ、自分が属する場所で上位二〇%のグループに入ることが必要だ」 反復的な仕事をしているだけではフーピンガーナー教授が言った“経験”にはならない。経験とはなにか新しいことを発見し、学び、能力の成長と蓄積をもたらすプロセスである 「予期しなかったものを獲得した時に得るもの──それが経験だ」。 以来、創造的経験としての仕事に対するこの態度は、私に深く染みこんだ考え方となり、それは私のためになっていた。私はいつでも、物事を前にやったよりうまくやる方法を見つけようと試み、それは私を、ほとんどあらゆる物事に対して熱意をもってのぞむようにさせてくれた。 恐ろしかった高い崖は、ずっと低く感じられた。長い年月に私が経験してきたことも同じだ。新しい仕事、新たに引き受けたことはどれも、初めは高い危険な崖のように思われた。──それを登り越えるまでは。しかし、登り終えてから振り返ると、もうそんなにけわしいとは感じられなくなっていた。 むろん、それで自分の将来が開けるはずはないことは承知で、夜はもう疲れきって、ただ寝床にもぐりこむばかりだった。それでも暗い気持ちはならなかった。私は若く健康で、やる気と希望に満ちていた。 ●いきなり商談を切り出すな。顧客にタバコを勧め、腰を下ろし、きみが売ろうとしている商品の利点を説明するのだ。 ●相手の言うことを傾聴せよ。そして言いたいだけ言わせ、途中でさえぎるな(これが私には難し かった)。 ●相手の主たる反対または疑惑を拾い出し、説得の力点をそこに集中せよ。 ●最後に、いとまを告げる前に、注文をもらうのを忘れるな。 この本よりはるかに大きな影響を私に与えたのは、セールスについてのもう一冊の本だった。というのは、それはセールスを超えたビジネス一般の領域で私を導いてくれたからだ。フォード・モーター社の最初のセールス・マネジャー、ノーヴァル・ホーキンズによって一九一八年に書かれたその本の題名は、『セールスマン必携──販売のプロセス』というものだった。それは私に長く心に残る印象を与えた。彼の説くところによれば、良いセールスマンであるためには、何よりもまず、良い人間でなくてはならない。良いセールスマンの条件は身なりでも、売りこみの口上でもない。それは顧客の信頼を勝ち取るに足る人間性そのものである。セールスマンとして成功するには、肉体も頭脳も精神も清潔そのものでなくてはならない。正直で率直でなくてはならない。 全員を豪勢なカクテルパーティに招待するのだった。われわれはみんなわめいたり歌ったりしていい気分になり、翌日はまた仲間への連帯感をもって働く意欲に燃えて仕事に戻って行った。しかし、仕事の緊張とストレスで、やさしい気持ちと共同意識は日ごとに薄れ、二週間もたたないうちにまた殺伐としてくる。 ブラック社長から、アメリカン・キャンのような偉大な会社をやめるのは間違いだということ、それによって大きな機会を取り逃がすことになるだろうということその他について、二〇分にわたる説諭をされた。私は終わりまで聞いてから、ありがたいお話に対して礼を言い、こう付け加えた。「しかし、今のようなお話は、会社をやめようとしている人間にではなく、入ってくる人間になさったほうが有益でしょう」 問題は同じだった。それらは──すべての会社の経営を良くも悪くもさせる、どの会社にも共通した要素──人間や勤労意欲やチームワークや生産性コストに関するものだった。 私は各事業部からの月次報告書の全部に漏れなく目を通すとともに、五人の執行副社長にも、各自がITTの全事業について包括的な深い知識を持つために、私と同じようにすることを求めた。つまり社長室のわれわれは、どんな問題と対峙するにしても、六つの頭はひとつの頭よりましだという単純な前提を拠りどころとして、ひとつのチームとして働いたのだ。 会社が最高経営者によって定められたゴールに向かって突進するひとつのチームとして行動するように、組織図に含まれるすべての人びとを、共同一致して機能させ、何よりも肝要な、緊密な人間関係によって結束させた時に、初めて真の経営は始まる。 われわれはいつでも困っている仲間を助けようと身がまえていた。われわれ全員はひとつのチーム、ひとつの会社であり、私の関心があるのは、責任者を譴責することではなくて、当面の問題を解決することだった。初めのころ、巨大規模の子会社を支配し、独立に慣らされていた代表取締役たちは、本社からの“部外者”が自分たちの領域にでしゃばってくるのをいやがった。 たとえば、あるマネジャーはこんな言い方をした。「いいですか、私は長年この会社を経営してきて、なすべきことは心得ています。私のことは放っといてください。自分の責任でやりますから。失敗したらクビになさればいい。しかし、私の思うようにやらせてください」。 「それは満足な答えじゃありませんね」と私は答える。「もしあなたが失敗し、あなたをクビにせざるを得なくなった場合、どんなことをしてもあなたの解雇手当から二〇〇〇万ドルの損失を弁済することはできません。一方、もしあなたがこの問題を解決すれば、どれだけの助けを借りようとあなたはそれを解決したことになり、年末には予算目標を達成した功績に対してボーナスを手に入れることになるでしょう」。 このポリシーが効果を表し、ITTの子会社の代表取締役たちにそれが受けいれられるまでには時間が──何年も──かかった。 中には自分の能力への攻撃と考えられるものに我慢がならず、会社を やめていった人たちもいる 報告書の冒頭に、以下のことを以下の順に、具体的かつ直截に述べた摘要を付することを要求する。 1 提案要領。 2 問題となっていることの摘要。 3 必要な場合には、その提案に到達した論拠を明らかにするための、思考過程の明快な説明と、判断を助ける展望を提供してくれる数字。 4 右以外の、起案者の個人的意見と、確信の度合いと、取り上げられた事柄に関する疑問点等を述べた、短いステートメント。 間違いをしたり、たまに過失を犯したりするのは恥でも不面目でもないと私は本気で言っているのだということを、マネジャーたちに納得させるのにはしばらく時間がかかった。過失はビジネスにつきものの一面であり、そのように扱われるべきものである。重要なのは自己の過失に立ち向かい、それらを吟味し、それから学び、自己のなすべきことをすることだ。唯一の本当の間違いは、間違いを犯すことを恐れることである。 自分のやることに確信をもち、けっして職業的な過ちを犯さないのがプロフェッショナルマネジャーだとする誤った考えである。 事実を客観的に眺めることは、経営に成功を収める最も重要な条件のひとつだと私は考えるようになった。人びとが意思決定を誤るのは、その決定が、入手した事実についての不適切な知識に基づいたものである場合が最も多い。 たったひとつの“事実ではない事実”のために、マネジメント全体の物事や意思決定の流れが間違った方向に向けられて、計り知れぬ金と時間と士気のロスをもたらす危険性があるのだ。 プロフェッショナル・マネジメントという最高の芸術は、“本当の事実”をそれ以外のものから“嗅ぎ分ける”能力と、さらには現在自分の手もとにあるものが、“揺るがすことができない事実”であることを確認するひたむきさと、知的好奇心と、根性と、必要な場合には無作法さをもそなえていることを要求する。 命令では人を訓練することはできない。しかし、年を経るあいだに、しだいしだいに 客観的事実に即して問題を処理する訓練ができてきた。そしてそこから、ITTで働いていることにプライドを持たせる知的誠実という気風が生まれた。 どこでも物事は起こっている。しかし、きみがそれらの物事を起こらせているのではない。きみはそれらを経営していない。といっても、なにもきみがウスノロだとか、だめなマネジャーだと言うつもりはない。良いとか悪いとかでなく、とにかくマネジャーではないということだ ビジネス・スクールに行きつく前からマネジャーだった。彼は本能的に企業経営の本質をつかんでいた。それは彼が勉強にはげんだからではなく、ひとつの対応がうまくいかなかったらつぎの対応を、そしてまたつぎの対応を……目標に達成するまで試み続けたからである。それが“経営する”ということなのだ。 「必要なら私は会社で徹夜でもしよう。しかし、この問題はかならず解決してみせるぞ」という態度でいなくてはならない。 私はしばしばそうしたし、時折、他人にそうするように勧めることもあるが、重要なのは会社で徹夜することではなくて、問題を解決することだ。経営において重要なのは結果である。 目標の八〇%を達成すれば勘弁してもらえるということを知っており、それだけのことしかしない。実際、八〇%以上を達成した時は、オーバーした分を、またノルマが増やされるに決まっている翌年に回せるように、隠しておくことさえある。そうしたことがしょっちゅうおこなわれている 一人の死者も出してはならぬ、と。事故死ゼロが目標となった。そして、見よ、それらの作業はアッセンブリー・ラインでの疲労あるいは過失による死がゼロとなるまで、改善が重ねられた。人間的な過誤をいかにして避けるかを教える制度も設けられた。 生産ラインで製品の品質管理をするほうが、あとで、使用されているそれを修理するより安くつくことを、コスト分析によって会社のライン・マネジャーたちに説明してくれた。彼の論点は、品質管理すなわち高品質を意味するものではない、というものだった。あくまでそれは品質の管理を意味する、というのだ。だから、一〇〇ドルの機械に四〇〇ドルの機械の性能を持たせるわけにはいかない。しかし品質の基準を定めて、それを満たさないものは絶対に許容しないことだ、と。 品質管理とは、マイナス面の管理である。いくつの欠陥、いくつのマイナスまでなら許容できるという態度をもってのぞむことだ。生産のプラス面を管理することは、マネジメントの仕事の一部分にすぎない。売上げや収益も、これとまったく同じように扱われるべきだ。 この程度なら許されるだろうと思われるエラーの枠を自分に与えてしまう。しかし、その枠は自分で事業を経営している企業家のそれに比べると、通例、ずっと大きい。しかも、そのエラーの枠は受けいれられてしまうのだ! なにかがうまくいっていないのを見つけたら、原因がわかるまで究明し、ひとつの解決法が効果を挙げなければ別の、また別の、さらにまた別の方法を試みるのだ。経営とは経営することである。 良いマネジャーは経験から学び、ひとつの会社なり事業部を統率するようになった時には、やって効果のあることと、ないことを嗅ぎ分ける一種の第六感を身につけていなくてはならない。さまざまな選択の中から最善のコースを選ぶことができるように、状況と問題と人間的要素を分析する能力をそなえていなくてはならない。そして用心深い人間であれば、最初のやり方が失敗したら、つぎに打つ手を準備していなくてはならない。それが“宿題をやる”ということだ。 子供のころ、貨幣の上にかぶせた紙を鉛筆でこすって、その貨幣に印刻されている像を浮き出させる遊びをした時のように、鉛筆でこする回数が多くなればなるほど、鮮明な画像が浮き出てくる。それと同じように、“事実”について多くの異なった出所からの報告が重なれば重なるほど、真の状況(もしくは、可能な限りそれに近いもの)が見えてくる。 時には像がぼやけていて、十分な事実が入手できず、それでも行動しなくてはならないこともある。しかし、その場合には、事実の全部をつかんではいないことを自覚し、状況が急激に変わるかもしれないことを念頭に置いて、用心しながら行動するだろう。だが、用心するばかりが能ではなく、とにかく行動して、はずみをつけることのほうが重要な場合がしばしばある。 経験から私は“正確度に対する時間の逆比の法則”とでも呼ぶべきものを学んだ 「経営者は経営しなくてはならぬ」とは、経営者はすべての問題を解き、すべての目標に到達し、すべてのベンチャーを見事に成功させる全能者でなくてはならぬというのではない。スポーツの場合でも、どんなに強いチームでも全部のゲームに勝つことはできない。ただ、大部分のゲームに勝てなくてはならない。ビジネスにあっては、ただ競争相手よりまさりさえすればいい。競争相手よりどれだけまさるかは、きみが定める基準による。しかし、きみはその基準によって定まった結果を達成しなくてはならない。それは不可能だとわかったら、それもまた受けいれられる答えだ。もしそうだったら、環境を変えればいい。その事業を売り払って、なにかほかのことに身を入れるのだ。しかし、おなじ売り払うにしても、たとえそれがきみの基準には届かないにせよ、当然達成するはずの基準で売りつけなくてはならない。それが経営というものだ。きみがしてはならないのは、不十分な結果を受けいれて、それを弁解することだ。 どれほど論理的で理屈にかなっていようと、決定的にテストされるのは“説明”ではない。テストされるのは、きみがマネジャーとしてやれる限りのことをやり尽くさずに、不満な結果を満足なもの として受け入れるかどうかだ。 いつでも私は仕事をするのが楽しかった。実際、私はそれを仕事だと思ったことはなかった。それは生活の一部、私が住んで呼吸している環境の一部だった。私はしばしば同僚たちに、仕事はゴルフやテニスやヨット乗りやダンスや、その他どんなものにでも引けをとらないぐらいおもしろい、と言ったものだ。それから得られる喜びは、もちろんアイスクリームを食べる喜びとは違う。仕事は思考を刺激し、その慈養となる知的挑戦を提供してくれる。それは一噛みごとに、デザートのアイスクリームをむさぼり食うのに劣らぬ、それなりの味わいがあるばかりか、もっと長続きする。その甘い味わいは、より長く持続する。ビジネスはすばらしい冒険、おもしろさにあふれた、毎日待望すべきものたり得るのみか、それから得られる報酬はサラリーやボーナスをはるかに超えたものである。 彼らが自己顕示のためではなく、より大きなチームワークの一部としてそれをやり、その中で各自がチームへの自分の貢献というものを認識し、自分が必要とされ認めら れていることを知り、ゲームに勝つようにプレーすることに誇りと満足を覚えるようにさせたかった。そして最高経営者としての私の仕事は、それらの人びとを不安のくさりで縛りつけている抑圧や恐怖から解き放つことだった。私はITTに成長と機会の機運を──各人が責任を分担したがり、私がせきたてるからではなく、仲間の圧力と誇りのために向上へと駆り立てられるような空気を──つくり出したかった。 私は一日に一二時間あるいは一六時間働くこともあり、たびたびヨーロッパへ往復し、週末はいつも仕事の書類の詰まったブリーフケースをさげて家へ帰った。しかし、それは模範を示すためではなかった。私がそうしたのは、自分の仕事を十分に果たすにはそうせざるを得なかったからだ。しかし、それはしぜんに模範を──ごまかしのない模範を──示す結果になり、それはマネジメントの各階層に伝わって、全社の仕事に対する態度の基準を確立するためにもある程度役立った。なぜといって、私にそれができるのなら、ほかの人間にだってできるはずではないか。──自分の能力にすこしでも誇りをもつ人間なら。 われわれはそれらの人びとに、彼らの収益を毎年一〇~一五%増やせと命令していたのではないということだ。それをみんなで一緒にやろう、そして彼らがその目標を達成するのを、最高経営者を含む本社のマネジメント・チームが手助けしよう、と言っていたのだ。一口に言うなら、沈むにせよ生き延びるにせよ、われわれは同じボートに乗りこんで、今から必死に漕がなくてはならないが、最後にはきっと、全員にとってやるだけの価値があったことが証明されるだろう、ということだ。 お互いに、いつでも率直な意見を述べる義務があるという明確な諒解があった。人びとは私にでも、他のだれにでも反対することができた。彼らは私でも他のだれでも批判することができ、だれもその結果として迫害されることはなかった。批判を歓迎しようと私も努力した。当然のことだが、批判されるのが好きな人間はいない。批判を受けた場合、最初の反応は防御と反撃の衝動だ。しかし、それは各自がつとめて自制すべき種類の衝動である。だれかが私と意見が合わない場合、私はキッとなるのを避けるために、意識 的に後ろにもたれる姿勢をとるようにつとめた。私は自分が間違いを犯そうとしているかもしれない時には、だれかがそれを指摘してくれることをいつでも望んでいた。そうした人間を頭からしりぞけたことは一度もない。私は相手の言うことを聞き、見解を交換した。私が明らかな誤りを犯していたこともあれば、相手が間違っていることもあった。まれにではなく、両方が少しずつ間違っていたこともあった。しかし、ほとんどいつでも、新しい事実や新しい考えが湧いて出て、両者の応酬からどちらにも思いがけない、より良い進路が現れた。 人を解雇するのに明快な公式というものはない。どんな方式を考案しても、かならず例外にぶつかるだろうし、例外があるのが当然だ。しかし、前記のようなケースをどう扱うかによって、彼がどんな種類のリーダーであるか、仲間からどれだけの尊敬を集め、またどれだけの尊敬を集めるにふさわしいかが決まり、そして究極的に彼が統率する会社の性格と個性もそれによって決定される。彼はそれらのケースに対処しなくてはならない。彼が定めた基準を達成するようにつとめ、おそらくはそうする能力あるいは熱意のない人間のおかげで余力の荷を担がされている人びとのために、邪魔を取り除いてやらなくてはならない。みんな、それを彼に期待しているのだ。 最高経営者がある人間を解雇するなり昇進させるなり、また、その人物にとって有利または不利な、なんらかの処置をとると、社内の全体にわたって反応が起こる。反動は単にボスと、彼が 最高経営者がある人間を解雇するなり昇進させるなり、また、その人物にとって有利または不利な、なんらかの処置をとると、社内の全体にわたって反応が起こる。反動は単にボスと、彼が対処している相手とのあいだにだけ起こるのではない。彼の処理の仕方の結果は、二人のあいだでの動と反動だけでは収まらない。それはラインに属する他の全員に余波を及ぼし、彼らはボスがやったことと、そのやり方に判定をくだし、それに基 づいて反応する。 良いリーダーのやることは紳士的でなくてはならない。紳士的とはどういうことか、彼は知っていなくてはならない。ほかの者はみんな知っている。むろん、だれも自分のリーダーが、無知、不決断あるいは弱さから、無能を甘やかすことを望みはしない。弱いリーダーについていきたいとはだれも思わない。リーダーとして、弱いことは最低である。そんなリーダーの判断は頼りにできない。なぜなら、困難な状況にぶつかったら、どう変わるかもわからないからだ。困難で、不評判ですらある決断をすることを恐れない強いリーダーのほうが──ただ、目下の人間を扱うのに紳士的で公正で信頼できるということが知れわたっている限りにおいて──ずっと多くの尊敬と忠誠を得られる。 皮肉や個人攻撃はいかなるレベルでも慎むべきものとされた。論理的、啓発的な批判より、利口ぶった皮肉な言葉が、想像力に富む良い考えの芽を摘みとってしまうことが多い。開放的なコミュニケーションとは、だれもが言いたいことを言う資格を与えられることを意味する。私はみんなに、あらん限りの想像力と創造性を発揮してほしかった。なにかのことで、私がだれかを叱責する必要があると思った時は、他人のいないところでそうした。私がどう思っているかを知らせたのはその人間に対してであり、ほかの人たちではなかったからだ。 本人が納得できないことをせよとはけっして命令しないという基本方針を守った 「オーケー、ジョン、(本社の)われわれはきみが間違っていると思う」と言い、その理由を説明する。「しかし、われわれのほうが誤りで、きみのほうが正しいという考えがまだ変わらないのなら、きみのやり方でやってみたまえ」。 そして彼のほうが間違っていたとわかった場合、きみとしては、そのことから彼がなにかを学んだことを期待する。それからまた同じようなことが起こって、彼が依然として頑固だったら、こんなふ うに言ってやるのだ。「よかろう、当事者はきみなんだから、きみの思うようにやりたまえ。しかし、きみはその進行状況を絶えず(本社の)われわれに知らせるようにし、われわれもよく気をつけていて、気がついたことがあったらそのつどきみに助言するようにしよう。そしたら、きみはものがよくわかった人なんだから、われわれの言うことの中から、正しいと思うことと間違いだと思うことを取捨選択してくれたまえ。そしてどちらとも判断がつきかねる場合は、われわれに相談してくれたまえ。もしそれが五分五分の可能性をもったことで、われわれのどちらもがどうとも決めかねる場合は、きみが主導権をとりたまえ。当事者はきみで、われわれよりよく実際の事情を知ってるんだから。われわれはきみに、こうせよとは命令しないし、きみを裏切るようなことはしない。しかし、きみの思い通りにやるなら、日夜よく研究して、自分が何をやっているかを自覚してやりたまえ。けっして、やみくもに何かをやったりしないように。きみが困った立場になるのは、きみが状況に関する事実を十分に探求しなかったために物事がおかしくなったのだとわかった時だ。そういう諒解のもとで、やりたいようにやりたまえ」。敬意をもって人を遇するというのはそういうことだ。 彼が間違っていると思っていても、なお彼が正しいことを願う。重要なのは、だれが正しいかではなくて何が正しいかだ。 問題のエグゼクティブの近くにいる人びとは、各自の見解を裏づけるもっと多くの事実を知ってはいるが、見解そのものはラインの上下を通じて同じなのが普通だ。そしてそうした意見の集積が会社の風潮、雰囲気、意気を形づくるのである。それはまた、業績にも表れる。尊敬し崇拝しているだれかのために働くのは楽しく、くそいまいましい野郎のために働くのは最低だというこ だれがなんといおうと、どんな会社でもだれかが頭脳を独占する(したがってその一人の考えだけが正しい)などということはあり得ないのだ。 恐怖にとらわれた人びとが会社の中で自己の生存のために競争するジャングルに変えてしまった。長い目で見ると、それは反生産的なことだと私は確信する。まず第一に、脅えた人たちは社内政略に走る。彼らは問題がまだ解決可能な早期に、進み出てそれを認めることをしないだろう。最も有能で自立心のある人びとは、そうした状態のもとで働くことを不本意として去る。良い人びとはそうした会社には入らないだろう。初めはそれとわからないぐらいだが、やがてそうしたマイナス効果をもつ状態と態度は、互いに他をこやしにして増殖して、ついには最高経営者司令官とそ の取締役会が測ろうとしても測れないほど深い淵をつくり、会社はその中に沈没していってしまうだろう。 その性格の顕現たる毎日の何百という小さなおこないにかかっている。どんな会社の体制にも徴妙なバランスというものが存在し、そのバランスはよかれあしかれ最高経営者が本能的に、直覚的に、自発的に、あるいは経験からするあらゆる小さなことによって動揺する。リーダーシップというものは、人生と同様、歩みながら学ぶほかはないのだ。 会社を経営する責任を、そこに何が含まれているかをよく知らずに委譲してしまうエグゼクティブは、自分を無用化するという大きな危険を犯しているのだ。彼は私が“マークシート・マネジャー”と呼ぶものに成り下がってしまうかもしれない。 その逆のやり方はマネジメントへの単調で義務的なアプローチを招き、結果を生むのが仕事のマネジメントが、千篇一律の繰り返しを生むだけにとどまってしまう。 未知の将来を予測する間違いようのない戦略を編み出す方式とされているものに、あまりにも依存しすぎたことにある。それはよくありがちなことだ。そうしたやり方は功を奏さない。 多くのビジネス戦略家がしばしば見過ごしがちなのは、くず物置場が稼ぎ出す一ドルも、石油会社やコンピュータ会社が稼ぐ一ドルとまったく違いがないということだ。 私が反対するのは、きれいな机のエグゼクティブのオフィスの様子とか机の上の状態よりむしろ、彼の心的態度に対してである。きれいな机は科学的経営への、ビジネス・スクール仕立ての 方式への、データの整理保存への、過度に厳格な時間の配分への、機構化した権限委譲への、そしてまた未来が自分のプラン通りのものを生み出すという当てにならない確信に基づいた無保証の自信と独りよがりへの固執を象徴している。そんなものを、夢にも信じてはならない。 オムレツを管理することはできない。できるのは一時に一個の卵を管理することである。 ※結果は管理できない。結果になる前の要因は管理できる。 すべての数字を綿密に検討し始める。その探求が進むにつれて、ほとんど感知できないほど徐々に、会社を良い経営がおこなわれている企業に変える物事の流れが起こる。彼はそれを休まずに続けなくてはならない。さもなければ、物事はまたスリップし始めるだろう。会社を経営するのは雪の上に字を書くようなものだ。書いた字が消えないようにするには、新しい雪が降り積もるたびに何度でも根気よく書き直さなくてはならない。しかし、その報酬として、同じ過程を繰り返すたびに、そのやり方に上達していく。 一般的にいって、会社はなるべく自己資本に対する負債の割合を三〇%ないし四〇%にとどめようと努める。三〇%の負債比率の企業は、他の条件がすべて同等の会社の中で、最高のAAAの信用格づけが得られる。四〇%となると格づけAAに落ちる。借入金に対する利率は、その企業への信用格づけの高さに反比例する。もちろん、負債比率をもっと低く抑えようとする会社もあれば、たとえ妥当な利率でも借金は絶対にしないという主義の会社もある。しかし、それはビジネスに対する非常に保守的な態度である。成長が必然的に制限されるだろう。 いかなる企業も完全には免れることができないショックの回数と程度を最小限にとどめるだろう。彼はキャッシュが尽きるような状態は招かないだろう。彼は会社の団結を保ち、良い経営をおこなうだろう。 しかし、そのためには支払わなくてはならない代価がある。数字に注意を払うことは単調で退屈な、決まりきったことの繰り返し──苦行である。会社のことをもっとよく知りたければ、それだけ多くの数字を相手にしなくてはならない。それらの数字の上澄みだけをすくい取るわけにはいかない。それらは読まれ、理解され、考えられ、その日、その週、あるいはその年のもっと前に読んだ他の数字の集合と比較されなくてはならない。そしてプロフェッショナルマネジャーはそれを一人で、それ以外ならほとんどどんなことでもずっと刺激的だとわかっていても、まったく一人きりでやらなくてはならない。もし会社がうまく経営されていれば、たいていの数字は予期した通りのものだ。そのこと はそれらをいっそうありふれた退屈なものにする。それでも飛ばしたり、集中力を緩めることを自分に許すわけにはいかない 含蓄は浸透の過程によって頭脳に染みわたり、彼は徐々に数字とそれらが真に代表するものの相手をすることが苦痛でなくなる。数字と事実で自分を飽和状態にすることは、初めのうちはどれほど迂遠に感じられようとも、かならず含蓄の理解をもたらす。なぜともなく、ばらばらだった断片がひとつに組み合わさり始める。それは彼がビジネスの世界でだれよりも賢い人間であることを意味するものではない。ただ、反復こそ含蓄の理解の秘訣だというだけのことだ。 それぞれの会社がそなえている合理的条件を検討した。──それは消費者が必然的に買い、将来も買い続ける製品またはサービスを提供しているか? それは良い製品か? その生産に注ぎこまれる労力に対して、収益は良好で安定しているか? その会社の将来の可能性はどうか? その市場は成長に向かっているか、それとも衰える傾向にあるか? そして最後に、ITTのわれわれは自分たちの経営技術と、より大きな資金力によって、その会社に相当ななにかをプラスすることができるか? 買収した後、われわれはその会社が成長するのを助けることができるか? ある会社がITTの経営システムに適合するかどうかの見きわめをつけさせてくれたのは、そうした単純な問いの積み重ねだった。 科学的なところはぜんぜんなかった。買収は主として直観と経験と、そしてITTのわれわれはその会社を前よりうまく経営するのを助けることができるという自信に基づくものだったと思う。 これらの巨額の損失に対して、技術者たちを咎めるべきではない。彼らは自分の専門の立場から、コンピュータが生活と市場に及ぼすに違いないインパクトをきわめて正しく予想しただけだ。誤りを犯したのは、自分を偉大な戦略家と見なしたトップ・マネジメントの人びとである。自分は部屋の中に居ながらにして、二〇年先に何が起こるかを予見できると思うことができる人びとだ。それはすばらしいビジョンだった。その知識と戦略的思索によって、彼らは未来のコンピュータ市場のシェアをつかむ計画を立てることができた。難点はただ、大作戦にはいつもつきもののことだが、他のだれもが彼らと同じものを見、まったく同一の戦略を思いつくことだった。その結果として、彼らはみな、その巨大市場のシェアをめぐって、トップメーカーのIBMと戦うことになるだろう。これまで生き残ってきた会社は、今なおその市場で利益が出るだけのシェアを求めてIBMと戦っており、長い間にはほんの二、三の会社しか生き残れないだろう。 コングロマリットは大きすぎて経営しにくいという考えを曲げない人が業界財界に多くいるのに対して、政界では主としてリベラルに属する人びとの間から、コングロマリットは大きいから、より小さい企業との競争に絶対有利だという非難が起こった。 通例、新しい製品の発売を伴う高度な冒険的な事業としてスタートし、成功を収めて成長した多くの会社が、いったん一般の投資対象となるような規模に達すると、企業家的な熱気をなくしてしまうのは、皮肉でもあり寂しくもある。最初の乾式複写方式を開発したゼロックス社はその好例である。 大企業は革新的、冒険的ではあり得ないという法則には、例外もある。その中できわだった印象を私に与えたのはクライスラー社のリー・アイアコッカである。 取締役会は外部の人間または機関によるマネジメントの監査を、額面通りに受けとる必要はないだろうし、受けとるべきでもない。会社のマネジメントは、あらゆる論評、攻撃、非難に対して、十分な答弁の機会を与えられることはいうまでもない。また、取締役会がことさら敵意をもってマネジメントに対することはない。 適切かつ正確な事実を入手するには、マネジャーは適切な質問をすることができなくてはならず、そのためには家での休息の時間を縮めてでも、自分が遭遇している物事を深く見きわめ 機械的要素(構造や方式)に重点が置かれすぎ、良い企業経営における情緒的な要素の価値に十分な関心が払われていない。 自分にたずねてみるのもいい。──自分自身を、成功するに違いないマネジャーに仕立て上げるために、人生の多くの快適な面を放棄する決意と高邁な職業意識が自分にはあるだろうか? 名声を得られるだけのすぐれた結果を達成するために、社交生活の大部分を返上して、長時間、夜遅くまで働くことを厭わないだろうか? と。そして自分はそれほど熱心にやる気はないし、そんなにあくせく働くつもりはないと思うなら、真のマネジャーになることはあきらめたほうがいい。なぜなら、そんなことではトップのレースの途中で、だれかに追い越されてしまうにきまっているからだ。逆に、もしそうした個人的犠牲を払う気があるなら、そうするがいいし、不平は言わないことだ。それを望んだのは自分であり、だれからも強制されたわけではないのだから。 努力すれば成果はついてくると単純に思われている方、一つずつ課題を解決する努力を積み上げていけば結論が出ると言われる方が非常に多い。 “本当の事実”をそれ以外のものから“嗅ぎ分ける”能力と、さらには現在自分の手もとにあるものが、“揺るがすことができない事実”であることを確認するひたむきさと、知的好奇心と、根性と、必要な場合には無作法さもそなえていることを要求する 働くことのやりがいは、正当に評価され、認められることにある。僕は経営者として、店をつくったり、潰したりをゲームのように楽しんだ時期があったことを否定しない。しかし、真の経営はチームワークと正当な人事評価だと今も昔も思っている。 エゴチスムは過度の確信や失敗への恐れから生まれると指摘する 人脈」といっても、その人が自分を信頼してくれるという状況にならない限り、人脈があるとはいえない。人脈をつくるには、自分の本業に専念することで信頼してもらうしかない。本業で結果を出せば、全然知らない人でも、訪ねれば会ってもらえるし、どんな質問にも答えてくれるものだ。 このあたり一帯にエゴチスムの良い考察★★★ ジェニーン氏は、「数字には個性がある」と言う。 「数字には数そのものと同じぐらい重要な個性がある。数字には正確なものとあまり正確でないもの、精密なものとおおよそのもの、詳細なものや平均的なものや漠然としたものがある。数字が持つそうした性質は、通常、その会社の最高経営者と、彼が部下たちから何を期待しているかによって決まる」 数字ほど確実な事実はないと思っている人は多い。だが、数字も人間との関わりの中で独特な変容を遂げるということなのだ。 今日のわれわれの大企業は、なぜ、みずからのつくりなしたビューロクラシー(官僚主義)にがんじがらめになり、一時代前のような大胆なベンチャーを封刹する規則や慣習の檻に、自由な精神をとじこめて 日本でも、株式公開した途端に成長力に陰りが生じる会社もある。それは経営者の責任だ。経営トップがその地位に安住し、社員が喜んで働くような目標も処遇も報酬も与えないからだ。 プロフェッショナルマネージャー 辞めないようなギリギリの報奨 嫌な顔で渋々金を払う金額
0投稿日: 2015.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログファーストリテーリング柳井社長のバイブル。 No Surpriseを標語に、徹底的に生の情報を社内から吸い上げる方法論を追求したITT社長による一冊。 本当に継続する企業が良い企業なのか、一人のカリスマにフィットし、その命運を共にすることも一興とするのか。 そんな題材にまで迫ってしまうマネジメント論は初見。
0投稿日: 2015.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ当書のメッセージは「経営とは、終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをする」ことというシンプルな言葉に収斂される。 そのために人を選ぶ。能力ではなく、アウトプットで見極める。ストレッチした仕事をさせて、経験を積ませる。しかも、できるだけ早い段階で。そうでないと年を取りすぎてしまう。 そのために数字をきちんと把握する。上っ面ではなく、数字の意味合い、どうしてそういう数字になるのか、どうしたら改善できるのかを考える。数字は経営における最高のコミュニケーションである。数字が分からない者に経営は務まらない。 そのために、業績目標を立てたら、最初の四半期の目標達成に拘る。そうしないと、年間も中期計画も達成することはできない。四半期ごとの目標設定にも拘るべきである。 そのために、PDCAをひたすら回す。計画を実行に移し、モニタリングする。結果を踏まえて次の行動を考える。試行錯誤の連続であり、それに飽きたり、時間を掛けることを疎んだりしてはならない。経営者たる者、経営に時間を注ぎ込まなくてはならない。結果として、それが自らの人生の満足度にもつながるだろう。 儲からない事業を切り捨てるのではなく、儲かるようにするのが仕事。そうしないと儲からない事業に関わっている人間も、儲かっている事業(資金を搾り出す事業)に関わっている人間も、ともに不幸になる。 経営者としての能力が高いのであれば、財界活動・社会貢献活動に精を出すのではなく、得意である経営により社会貢献をすべき。それができないと、別の活動に注力してしまうのかもしれない。比較優位論である。 気をつけるべきはエゴ。論理的な経営者が、いつの間にかエゴの塊になってしまうことがある。成功を重ねる経営者ほどそうなりがちなのかもしれない。ワンマンにならず、客観的に自らの言動を振り返る仕組みが必要。それが取締役会なのかもしれないし、従業員とのコミュニケーションなのかもしれない。どの会社の組織図も大きくは違わないが、その組織におけるコミュニケーションの質と濃度が差別化につながるのだろう。 ユニクロの柳井さんが解説を寄せているが、「社長の言ってることがその通りに行われない会社」というコンセプトは面白い。社長が全知全能であるはずもなく、本質を理解して、より高いレベルのアウトプットを出すように考えを尽くす組織こそが、高い業績を生み出すのだろう。 少し時代は遡るが、普遍的な内容が多く盛り込まれている良書であり、経営を志す者にとって必読の書だと思う。
0投稿日: 2015.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ『言葉は言葉、説明は説明、約束は約束……なにもとりたてて言うべきことはない。だが、実績は実在であり、実績のみが実在である。 これがビジネスの不易の大原則だと私は思う。実績のみが、きみの自信、能力、そして勇気の最良の尺度だ。実績のみが、きみ自身として成長する自由をきみに与えてくれる。 覚えておきたまえ。ー実績こそきみの実在だ。ほかのことはどうでもいい。マネージャーとは、“実績をもたらす人間”だと私が定義するのはこの理由による。 他人あるいは自分自身に対してどんな言い抜けを考案しようと、この事実を変えることはできない。そしてきみが立派な実績を挙げたら、ほかのことはすべて忘れられた時になっても、世界はそれを覚えているだろう。そして何より重いのは、きみもそれを覚えているだろうということだ。』 素晴らしい! すべての章が勉強になった。
0投稿日: 2015.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営の実態を忌憚なく書かれている。 会社の有り方や、考え方など、ストレートに書かれていて、おもしろかった。
0投稿日: 2015.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ黒い装丁とUNIQLO柳井さんの推薦帯が印象的な本。経営に関しマクロな学術書とは異なり、ミクロな経営現場のかなり泥臭い話が満載。すごみを感じる。
0投稿日: 2015.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファーストリテイリング柳井氏が推薦ということで手に取りました。 『経営者は「経営せよ」』というメッセージが幾度となく現れ、本書の趣旨はこの言葉に集約されると思います。 また数年経って読み返したい。
0投稿日: 2014.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営の厳しさとは何かを感じさせてくれる類い稀な本。柳井氏の教科書というだけにパワーをそこかしこに感じた。まるでハロルドジェニーン氏の後ろ姿を追っているような柳井氏。付録に柳井氏がどれほどハロルドジェニーン氏の仕事観を崇拝してるかが伺える。
0投稿日: 2014.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者になりたい。そのために必要なことは何か。それを身につけるための行動計画を立てよう。そう思い手に取った。 わかったようでわからないフレーズが沢山あった。その一番の理由は、経営者経験が無いことだろう。してみたい。その過程で再読し、わかったきた自分に出会いたい。 今から確実にできることは、何としても成果を出すこと。そして、一番足りないことは、成果を出すための執念。
0投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロ、柳井さんがよくわかるような気がしてくる。 日本のよい会社とも共通点が見受けられ、なるほどなと思った。 自分が経営者になった時にまた読みたい
0投稿日: 2014.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログプロフェッショナルマネージャーノートの方がエッセンスが集約されていて読みやすい印象を受けました。本編では柳井さんの解説が最後に載っており、本の内容をどのように活かされているか紹介されているので、読む価値がある箇所かと感じます。
0投稿日: 2014.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ITTで最高経営責任者として、14年半連続増益を出したハロルド・ジェーンが経営について記した本。 3行の経営論について繰り返し強調されている。 「本を読むときははじめから終りへと読む。 ビジネスの経営はそれとは逆だ。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ。」 また、ITTで取り組んだ方針や戦略、経営哲学が紹介されている。 それは、 No Suprise 4半期ごとの収益 『本当の事実』/事実を伝える者の信頼度 経営者は経営をしなくてはならぬ 人は失敗から物事を学ぶ 最高経営者に報告される数字の「質」の重要性 株主の利益を代表するべき取締役会の独立性 である。 ボリュームのある本の中で、最後に記された短い文章が印象に残りました。 「言葉は言葉、説明は説明、約束は約束。なにもとりたてて言うべきことはない。だが、実績は実在であり実績のみが実在である。実績のみが、きみの自信、能力、そして勇気の最良の尺度だ。 覚えておきたまえ。・・・実績こそきみの実在だ。」 「経営の鬼人」と呼ばれた著者だけに、厳しい経営哲学に基づいた考え方で、勉強になります。一方で、短期志向であり、人を排除する部分について、賛成できない部分もあります。 ユニクロの社長である柳井氏の書評は参考になりました。
0投稿日: 2014.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ユニクロの柳井氏が「バイブル」としている一冊。 「経営とは」の真髄がつまっており、また柳井氏の解説もついており、2倍おいしい。
0投稿日: 2014.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログKindleで300円だったのでつい。まあ言ってることはわかるけど、そこまで自分がしたいかというところがまず一点。一株あたり収益拡大のために(大企業であることがいきやすい資本集約産業が中心であるとはいえ)M&Aをひたすらに節操なく行うのはどうなのか。そして、ユニクロ柳井はここから何を学んだのか。最高の教科書と言いながら彼の行動が批判されてるように読める箇所はちょくちょくあった。
1投稿日: 2014.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ20090207追記 久しぶりに読み直しました。理論や理性ではなく、情緒や感情を含めた人間の本質への理解が重要性が書いてあるように思いました。数多ある経営書の中でも非常に深い本の一冊だと思います。またいつか読み直したいと思います。 ------ ユニクロの柳井氏が宣伝に使われているので、買ってしまいました。アメリカで経営の第一線に身をおいた当事者が書いた本なので、言っていることは非常にいいことが書いてありますが、壮絶だなぁと思いました。僕も頑張らねば。と思いました。柳井さんが書き下ろしているところも面白いです。
0投稿日: 2014.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログかつての巨大コングロマリット米ITTの社長兼CEO(最高経営責任者)として58四半期連続増益を遂げたハロルド・ジェニーン氏の経営論。1985年刊行のものを復刊した。経営の教科書にしている柳井正ファーストリテイリング会長兼CEOが解説を加える。(Amazon.co.jpより) 前回の記事、NHKスペシャル「成長か、死か~ユニクロ 40億人市場への賭け~」の続きになるのですが、柳井社長が経営の教科書として推薦されていたので、興味を持って読み進めてみました。 著者のハロルド・ジェニーン氏を知らなかったので調べてみたのですが、1959年にITTの社長に就任すると“14年半連続増益”という当時のアメリカ企業史上空前の記録を打ち立てた方だそうです。そして、17年間の在任中には積極的に企業の買収・合併を行い、世界80ヶ国に350社に及ぶコングロマリット(複合企業)をつくり上げた伝説の経営者でした。 さっそく読後の感想ですが、著者の人生を振り返る自叙伝でもあり、経営哲学書でもあります。ボリュームがある内容かつ、著者の経営思考を理解しながら読んだので、かなりのエネルギーを費やしました。以下に目次をご紹介。 はじめに 「これが私の最高の教科書だ」柳井正 第01章 経営に関するセオリーG 第02章 経営の秘訣 第03章 経験と金銭的報酬 第04章 二つの組織 第05章 経営者の条件 第06章 リーダーシップ 第07章 エグゼクティブの机 第08章 最悪の病ーエゴチスム 第09章 数字が意味するもの 第10章 買収と成長 第11章 企業家精神 第12章 取締役会 第13章 気になることー結びとして 第14章 やろう! 付録 「創意」と「結果」7つの法則 柳井正 目次を見ても分かる通り、本著は大企業(もしくは目指している)経営者に向けた指南書なのですが、中小企業の経営者も参考になる部分は随所にあったと思います。また、ハロルド・ジェニーン氏が貧しい家に生まれてから、どのような方法でステップアップし、ITTという巨大企業を発展させたのかという内容は、物語としても非常にオモシロかったです。驚いたのは、1985年に刊行されたにも関わらず、現在のビジネスシーンとほとんど変わっていなかったこと。手段やツールが進化しても、経営の原理原則は普遍なんだと実感できます。 そして、一番のクライマックスは、柳井社長が書き下ろした「創意」と「結果」7つの法則。本著を推薦するだけではなく、どのように落とし込んで、自分の経営に活かしてきたのかが、7つの法則に基づいてしっかり書かれています。個人的にはこの付録を読んだだけでも、購入する価値があると思います。それぐらい読み応え十分だったし、経営に対する経験や哲学を出し惜しみせず、解説されてたことに感激しました。興味のある方は、この7つの法則だけでもぜひ読んでみてください。
0投稿日: 2014.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ①とにかく第1、第2、第3四半期の目標を達成することを ②上位20%にいること ③経験を積むなら急いで行う ④経営するとは、やり遂げること ⑤余分に働くことの価値 この辺が身につくように取り組みたい。
0投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロ創始者柳井氏の経営に影響を与えた本です。 アメリカのコングロマリットITT社の社長ハロルド・ジェニーンが経営の極意についての書いています。 経営の本質は、次の3行で表現できるそうです。 「本は初めから終わりへと読むけど、ビジネス経営はそれと逆だ。 終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをすることだ。」 「リーダーシップは教えることはできない。自らが学ぶものだ。」 「経営者は、経営しなければならない。業績がすべてだ。」 「経営者は、自分で決断し、目標を明言し失敗のリスクを100%背負う人。」 「数字を意識すること。その裏の意味を理解すること。」 「社長の最悪の病は、エゴイズム。」
0投稿日: 2013.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業家は、これを読んで覚悟を決められるなら、起業していいと思う。 リスクを背負って、負荷を背負えるか。
0投稿日: 2013.11.24経営とは何かを考えさせられます
経営とは、「自社が達成するべきゴール」を定め、そのゴールに向かっていま何をすべきか考えて実行すること。 経営者の最大かつ唯一の任務は、「経営する」こと。 本書の骨子は、個人の目標達成にも応用できる考え方です。状況に流され、その場その場の思いつきで行動してしまう自分には経営は向かないようですが。 長い書籍ですが、本書の後半にも注目するところがありました。 《企業内企業家》、つまり常に革新を求めて挑戦し続ける人間は、大企業にはいなくなります。これは他人(=株主)の資産で企業を運営する以上、リスクを抑えた安定的な成長を求められることから考えても当然だということです。 そして経営者(CEO)と株主(取締役)の理想の関係を、両者を明確に分離し、両者がよい緊張感を保って会社の成長に貢献すること、CEOは取締役会に雇われる立場であることなどとして、日本では想像も実践も難しそうな構想を持っています。 自分の中では、いわゆる「ものいう株主」は目先の自分たちの利益しか見ておらず、長期的な企業の成長を軽視、ないしは無用としているように思われるので、本書が彼らが投資先の企業経営に求めるものを見直すきっかけになってくれることも希望しています。
1投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ30代になって、マネージャーがみえてきたときに再度読みたい本。 以下、メモ ■3行の経営論 ビジネスの経営は、終りからはじめてそこへ到達するためにできる限りのことをすること。 ■2つの組織 ひとつは組織図にかけるもの。 もう1つは、その会社に所属する男女の、日常の、血のかよった関係 ■リーダーシップ リーダーシップは伝授することは、できない。 それは、各自がみずから学ぶものである。 人生と同様歩みながら学ぶほかないのである。 リーダーシップが発揮されるのは、言葉より行動や行為である。 最終的にリーダーのやるべきことは紳士的でなくてはならない。 リーダーとして弱いことは最低である。 困難で、不評判ですらある決断をすることを恐れないリーダーのほうがずっと多くの尊敬と忠誠を得られる。 ■数字について 数字の意味は、言葉のそれと同様、相互の関係において初めて理解される。 数字は、企業の健康状態を測る一種の体温計の役である。 それは何が起こっているかをマネジメントに知らせる第一次情報伝達ラインとして機能し、それらの数字が精密であればあるほど、揺るがすことができない事実に、基づいていればいるほど情報は明確に伝わる。 数字を知っているおかげて、恐れずに前に進める。 以下、柳井社長コメント ①経営の秘訣-まず、目標を設定し、逆算する ②リーダーシップ-現場と緊張感ある対等関係をつくること ③意思決定-ロジカルシンキングの限界を知れ ロジカルシンキングだけでは、人間が見えてこないということだ。 新任のリーダーに抜擢されると、自分には権力があると錯覚する人がいる。 そういう人の多くは、「管理者になったらこういう行動や発言の仕方をしなくてはならない」といったステレオタイプを信じている人が多い。 ④数字把握能力-データの背後にあるものを読み解け
0投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロの柳井さんが推薦していることで有名な、ITTのジェニーン氏の経営書。 魔法のほうなきれいな経営理論が解説されているビジネス書とは確かに異なる。経営者は、具体的な目標を設定して逆算して経営を考えること、組織図には現れない生々しい人間関係を重視すること、数字を読み解くことなど、当たり前のように聞こえて、実は非常に困難を伴うものばかり。 経営者は情緒的になり、経営に全身全霊をささげなければならないという氏の指摘には背筋が伸びる思い。。自分には難しいかな(苦笑) 最後に柳井さんによる解説が載っていて、本書の要約と同時に柳井さんの厳しい経営哲学を垣間見ることができる。ここだけでも本書は十分に読む価値がある。
0投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代と文化の違いがあり、どうもすんなり頭に入らない。ユニクロ柳井さんの経営の教科書ということだが、経営に関する書籍なら、もう少し読みやすい本はあると思うので、あまり人にオススメはできないかなと。
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ著書はニューヨーク証券取引所のボーイから、図書の訪問販売、新聞の広告営業、会計事務等を経て、ジョーンズ・アンド・ラフリン社、レイシオン社で企業の経営に参加参画。アメリカ企業史上空前の記録、「58四半期連続増益」という金字塔を打ち立てた。 ユニクロの柳井正氏が「この本こそが、私の人生で最高の経営の教科書だ」と絶賛しボロボロになるまで読んだ「幻の経営書」である本書。 著者が実践で知力を使い、数々の修羅場をくぐり抜けて掴み取った経営の実体験が惜しげも無く以下の10章からなっている。それは経営理論ではなく、生の経験。 ①セオリーだけでは経営なんかできない ②経営の秘訣 ③大不況の中で手に入れた金銭以外の報酬 ④2つの組織 ⑤経営者の条件 ⑥リーダーシップ ⑦エグゼクティブの机 ⑧最悪の病 ⑨数字が意味するもの 10起業家精神 経営者必読ならず、私のような一般社員ももちろん必読の一冊。経営のことはやはり経営者だけが知っておくというのはやはりナンセンス。今の時代誰もが経営を意識してそのポジションにおいてその力を発揮することが求められている。 本書は経営者ならではの苦悩やそれに対して著者が実際にどのように考えその行動をとったかという事が鮮明に描かれている。自分ならこうしたこうすべきという意見・考えを持ち読み進めていけば自ずとその物語に引込まれていくようであった。
0投稿日: 2012.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ・本を読むときは初めから終わりへと読む。ビジネスの経営はそれとは逆だ。終りから初めて、そこに到達するためにできる限りのことをする。 ・戦略家たちは皆同じ教育を受け、同じ情報を研究し、同じ結論に同時に到達する。彼らの勧告は一種の流行のようなものをもたらす。それに従って航空会社が競ってホテルを買収し、巨大通信会社が競って書籍出版社を買い、書籍出版社が競ってペーパーバックの出版社を買い、誰もが競ってコンピュータ会社を買おうとするといった事が起こる。 ・物事を行うには会社の機構を通し、ルールに従ってやらねばならない。しかし、ルールに従って考える必要は無い。 ・本来の自分でないもののふりをするな。 ・紙に書かれた事実は人々から直接に伝えられる事実と同一では無い事を銘記せよ。事実はめったに事実でないが、人びとが考える事は憶測を強く加味した事実である。 ・本当に重要な事は全て自分で発見しなくてはならない。 ・物事の核心を突く質問をされるのを嫌がるのはインチキな人間であり、それを見分けて厄介払いするのはマネジャーの仕事である。
2投稿日: 2012.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてある内容はマネジメントや経営についての基本事項に感じる。内容はやや冗長。 もう少しすっきりシンプルにまとめてもらえるともっと頭に入ってくるように思う。
1投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の種類や内容はかなりちがうけど、成功したグリーという印象を受けた。 本書で繰り返されるメッセージは経営陣(含む管理職)はやるべきことがまだあるはずで、もっときちんと経営する(働く)べきだ!なのだけども、その表層の一部であるワーカホリックな部分だけクローズアップされて安易な精神論に誤読されることが多そうな予感 そして、解説のユニクロの柳井社長の文書もそれを助長しそうな気が。。。柳井社長が誤読してるわけではなさそうなんだけど なお、あえて誤読して全ての社員はもっと働くべき!とか言い始める経営者がいればそれはスーパーブラックです。 。。。と、若干否定的なことを書いたけど、誤読しなければ十分面白い内容だと思う。加えて、終わりから考えよう、といった個々のメッセージは興味深かった。 また、当時のアメリカの経済状況も興味深い。今のIT界隈もスピードの違いはあれど構造はあまり変わらんよね、と思った次第。過去に学ぶことは意外と多いもんだなぁ。
0投稿日: 2012.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者は「経営せよ」! 経営は科学ではない。セオリーもない。 目標を決め、人びとを従わせ、決めた目標のために、できることをやるだけだ。やり遂げないマネージャーは、ダメなマネージャーとか悪いマネージャーではない。マネージャーではないのだ。 と、こういう感じです。
0投稿日: 2012.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ十数年に渡って増益を成し遂げた経営者の、経営とはかくあるべきの書。分厚いけど章ごとに分かれてて読みやすい。言葉に力がこもってる。
0投稿日: 2012.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ"この本はユニクロの柳井氏が解説を行っています。 彼自身の経営指南書として読んでいるそうです。 経営者は必読の1冊だと思います。 会社の中で、マネージャー、管理者を目指す方にも必読の1冊です。 本の中、そこかしこでうなずかされる点が多い1冊です。 何度も繰り返し読むべき本だと思いますね。"
1投稿日: 2012.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ米ITT社の最高経営責任者を務めたハロルド・ジェニーン氏の著書であり、ユニクロ柳井会長に経営の教科書と言わしめたのが本書。 経営について客観的に語るとはこういうことかと知らしめられた。なんとも分析的で、なんともアナリスト畑の出身らしい経営理論。経営理論を語る本の語り口ってかなりエモーショナル寄りなものも少なくない一方で分析的な本書が自分のバランス感覚を整えてくれる、読んでいてそんな感覚でした。
0投稿日: 2012.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログITTのCEOだったハロルド・ジェニーン氏の経営論である。この本は訳書で2004年5月出版の本だが、一度日本で1985年に出版されていていて、ユニクロの柳井会長がこの本を読んだのがこの年だ。柳井会長の前書きと、あとがきを加えて再出版されたものだ。 前書きを読んで柳井会長が1985年に訳書を読んだとあり、奥付に©1985Haruko Tanakaとあるため日本での出版年がわかったが、この原書がいつ出版されたものなのか原書タイトルの欄を見てもほかのところを見ても記載が無く、少し苦労した。検索してようやくアメリカでは1984年の10月に出版されたものらしいとわかった。 ドラッカーもそうだし、昨年読んだ「世界一シンプルな経済学」もそうだが、何十年も前に書かれた本が私たちの営みに対しても正鵠を得ている。これは人や組織の問題が時代が変わっても本質が変わらないということを意味しているのでもあろうし、また実践者たちが過去に学んで行いを進化させていないということでもあろう。 「セオリーなんかで経営できるものではない」 ジェニーン氏は1980年代に日本メーカーが米国メーカーを圧倒した要因の分析をしているが、きわめて自然な結論である。賃金が安く良く働く人が、政府の援助を得て、最新鋭の生産性の高い設備を使っていたのが日本であるから結果は当然だったのだ。 産業心理学をかじったことのある人でなくても、X理論、Y理論は聞いたことがあるだろう。80年代に日本企業の成功を分析して「Z理論」という本を書いた人がいた。今でもその残滓があるが、ビジネスの方法論を理論や体系にすることが流行るようになり、おりからコンピュータメーカーの営業戦略に合流して、コンサルが幅を利かす時代が本格化したわけだが、本書のなかでジェニーン氏はそういった風潮の誤りをすでに喝破している。私が1985年にこの本を読んだら、本書の第一章のこの部分を読んでどのような印象をもっただろうか。それは今の私のそれとはだいぶ違ったものだっただろう。当時の私はジェニーン氏や柳井氏のように、人間の集団を率いるリーダーではなく、才気走った大企業の一企画スタッフでしかなかったから。 「終わりからはじめて、そこへ到達するためのできるだけのことをするのだ」 今やっていることは重要ではなくそれに囚われる必要は無い。われわれは「よいやりかた」を競っているわけではないし、よい結果を求めているのだ。 「だれもが二通りの通貨ー金銭と経験で報酬を支払われる」 ジェニーン氏はまず経験を取れという。エリートではなかったジェニーン氏の経歴の紆余曲折が語られている。氏はMBAについても触れているが、方法論はあくまでも道具にすぎないという視点は当時のアメリカ人の発言としては、日本ではうけなかっただろう。日本企業がこぞって社員をアメリカのMBAコースに社員を送り出し、学生もMBAを目指す流行が盛り上がった時期であったから。 MBAで学ぶ理論は別にIVY leageで学位をとらなくても、習得できることがすぐにわかってしまったし、ケースステディやディベートは実務にいくらでもスキルを磨く場があったから、MBAたちが差別化できる余地は実戦ではすくなかったのだ。コンサルがオペレーション企業を指導するというビジネスモデルが人々の意識にMBAの独自性を成立させていたのだ。 「どの会社にも二つの組織がある」 新しい職場に来てまず必要なことは、誰がどのような位置にいるのかということだ。世界のどこにいってもこれは共通だ。 「経営者は経営しなくてはならね」 日本の会社でも通常は部長以上は、なんらかの産出と投入に責任をもつ経営が仕事のはずだが、トップも含めて経営していない経営者と名のついただけのボスが多いのである。 「リーダーシップは伝授することはできない」 氏は「それは自ら学ぶものである」と書いている。 「机をみれば人がわかる」 ジェニーン氏はいつも机がきれいな経営者と管理者は、自分は何もせず人に頼っているだけであるのという趣旨のことをここで述べている。 私は混乱をオーガナイズするのがリーダーの仕事だと思う。だから管理者に投入される数々の問題は混沌としていて、机の上はその通りの姿となると思う。私の机の上は昼間は本当に混乱している。帰る時にそれをいかに組織化して事務所をあとにできるか。これにつきると思う。 「エゴチズム」 経営者の陥る最大の病はエゴチズムであると述べている。 世の中を見渡せば例にことかかかない。だれもがかかる病だ。この病は必ずかかる病だが軽症にとどめることができるのは自分である。私は家族や友人がとても重要だと思うし、また常に現場の難局に自分から飛び込んでいくことが慢心とエゴチズム防止に役立つと思う。 「数字が強いる苦行は自由への過程である」 人の行動に対する論が多い本だが、やはり数字を大切にすることも述べている。 人間の思い込みと錯覚を牽制することができるのはやはり数字であるということを改めて認識させられる。 「コングロマリットってなんだ」 わたしもコングロマリットについては、とおりいっぺんの知識しか無かった。多角化とか本業集中とか方法論が問題ではないのだが、買収を重ねてどの事業も10%以上の利益を上げていたITTは、コングロマリットでもあり、また専門企業でもあったということだ。氏とITTの幹部はどの企業にも共通するマネジメントスキルを持っていたのだ。 「企業内企業家はどこにいるのか」 それが存在しない理由がこの第11章に書いてある。読んでみるべし。 「取締役会のありかたは、もう少しなんとかならないものだろうか」 よく米国企業の取締役会と日本企業の取締役会の違いが話題になるが、この章を読むと大同小異であることがわかる。取締役が取り締まることはできないのである。 「良い経営の基本的要素は、情緒的な態度である」 「会社ではルールにしがたって物事をおこなわなければならないが、ルールに従って考える必要は無い。」「リーダーシップは物事を遂行するように人々を駆り立て・・・満足できる結果を得るまでやめないよう駆り立てる情念の力である。」 最後の第14章はとても短い。タイトルは「やろう」だ。 「事業はスポーツに似ていると思う」と氏は述べる。教育よりも訓練が、バックオフィスの検討と指示よりも現場の状況把握判断と反応が実戦の勝敗を決める点で、私もまったくその通りだと思う。 この本を読むと、アメリカの経営者も日本人の経営者とまったく変わらないという感想を持つだろう。また、数十年程度の時の流れも経営者のあるべき姿に、大きな変化をもたらしていないこともわかるだろう。30年たって、私たちはもとの場所に帰ってきたようである。
0投稿日: 2012.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログカーネギーやドラッガーと同じ匂いがした。 その日暮らしをするアルバイターに過ぎなかった著者が苦労して会計を学び、転職を機に立場を強めていき、最終的にITTの最高経営責任者として同社を長期的な成長に導いたサクセスストーリー。 読者はその過程で発生した試行錯誤から経営の本質を学びたまえ。 という本。 どこがカーネギーやドラッガーと同じかと言うと、非常に冗長なんだけど、経験に裏打ちされている分、確かに学べることはたくさんありそうで、ただし一回では吸収しきれないというようなところだ。 立場が変わってから読むとまた違うことを学べるに、違いない。
0投稿日: 2012.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先ず柳井さんのすごさに感動 最高の教科書と言っている意味が分かる 内容は人生がつらつら書かれているので、すべてを読み解くとなると大変 ポイントをしっかり読み事が大切 ①ビジネスは終わりから始める。ゴールを決めることが重要 ②2つの組織。組織図の組織と、血の通った組織。通じ合っていると解釈 ③経営者は経営しなくてはならない。この意味が心もそこからわかった。数字の重要さ。目標達成の重要性。社運が掛かっている
0投稿日: 2012.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読んで必要とされる内容は読む人や時期に左右されるものではあると思いますが、今の私には必要な要素が多く含まれておりとても参考になる本でした。ユニクロの柳井氏も共感されていた「本は初めから終わりに向かって読むが、経営はその逆で終わりから初めてそこへ到達するために出来る限りの事をするべきだ」の記載は、これまでの私の発想にはないものでした。 またこの筆者は次々発生する問題にうんざりするのではなく、企業経営とは問題を解決しつづけることと言わんばかりに問題解決に取り組む姿勢は、優秀な経営者といえどやっていることが全てうまくいっているわけではないことを改めて思い知らされました。 本書の冒頭にありました「困難な決定は、先頭を立って他を導く自信のある男女によってなされる」の言葉を胸に前を進んでみたくなる本でした。
0投稿日: 2012.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログというわけでユニクロ柳井氏がバイブルと仰ぐ、かつての巨大コングロマリットCEOとして58四半期連続増益を遂げた経営者の著作。 ・ビジネスにおいては、4という数字はプラス12とマイナス8の和を表していることがしばしばある。(中略)マイナス8のほうに注意を集中し、それがプラス5とマイナス13から成り立っていることを発見する。それから彼はマイナス13を掘り下げて、(中略)一連の製品の生産を中止することで彼は13の損失をセーブすることができ、その結果をその事業部の総和の4という数字に適用すると、新しい総和は17となり、それは新しい体制の健全な利得となる。つまり彼は数字の背後にあるものを変えたのである。 ・実のところ、企業家精神は大きな公開会社の哲学とは相反するものだ。 ・人に何かをするなと命じるのは構わない。本人が納得できないことをせよとは決して命令しない。「オーケー、われわれは君が間違っていると思う。しかし、われわれのほうが誤りで君の方が正しいという考えがまだ変わらないのなら、きにのやり方でやってみたまえ。しかし、きみはその進行状況を絶えず我々に知らせるようにし、われわれもよく気をつけていて、気が付いたことがあったらそのつどきみに助言するようにしよう。そしたら、きみはものがよくわかった人なんだから、我々の言うことの中から、正しいと思うことと間違いだと思うことを取捨選択してくれたまえ。(以下略)」
0投稿日: 2012.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
企業の中で何のために働くのかを模索しながら読んだ。 マネジメントをしている訳でないが、企業という組織を統括するマネジャーがどうすべきかを読むことで、おのずとヒントが見えてくるのではないかという仮説で。 会社のためか、自分のためか、社会のためかわからなくなることがある。本書にも「組織のために働くのではなく、働くために組織がある」などと書かれていたが、解釈は難しい。 周りにはトップの決めたことに従順な人間が多く、仕事もどんどんクリエイティブではなくなっていく中で、モチベーションをどう維持していくべきか? そういう意味で、組織のどの立場にいても、自分の頭を使って考え、自分の足で動いた結果を糧にすべきだと感じた。その場合も、人に自立を望むのであれば、柳井氏も解説で書いているように、スターマネジャーを評価する仕組みが必要なのだ。
0投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロの柳井さんが教科書と読んでいる本。 私は一読しただけでは、なかなか内容が頭に入らずモヤモヤしたまま終わってしまった。 内容がとても深く何度も読み直さないと理解できない。 最後の付録で柳井さんがポイントを解説しており、分かりやすいものになっているので、それを読んでから再読すると理解が増すと思う。
0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1.報告書 向後、私はすべての報告書の冒頭に以下のことを順に、具体的かつ直截に述べた摘要を付すことを要求する。 ・提案要領 ・問題となっていることの摘要 ・必要な場合にはその提案に到達した論拠を明らかにするための、思考過程の明快な説明と、判断を助ける展望を提供してくれる数字。 ・上記以外の、起案者の個人的意見と、確信の度合いと、取り上げられた事柄に関する疑問点等を述べた、短いステートメント 2.ひとつの対応がうまくいかなかったら次の対応を、そしてまた次の対応を・・・・目標に達成するまで試み続けること。それが経営するということなのだ。 3.ルックスや家柄の良さをせいぜい利用している、チャーミングで屈託のない人々は敬遠した。あまりにも賢すぎて、われわれ凡人とはうまくやっていけない天才も欲しくなかった。熱意があり、物事を達成し、自分の人生をなにものからしめたいと欲求し、自分が求めるもののためには苦労することを恐れない、有能で経験を積んだ人物。 4.企業の成否の最も重要な要素となるのは会社の労働環境である。環境管理は最高経営者の手中にある。その場所の温度と空気の質を決めるのは彼だ。会社の個性を決定するのは最高経営者。彼の下にいる人々は彼の命令を遂行し、彼のスタイルを模倣する傾向がある。彼のやることとそのやり方は、一種のファッションとなって下の階層の人々に模倣される。 5.なすべきことをしようとする衝動の原動力となるのは、論理ではなく、深いところに内在する情緒である。 6.本来の自分でないものの振りをするな。見せかけのために物事を遂行することは自分に跳ね返り、やることのすべてを鼻持ちならないものにしてしまう。自己顕示のための旅行、社内政治その他、真の自分でない役を演じることを避けよ。 7.紙に書かれた事実は人々から直截に伝えられる事実と同一でないことを銘記せよ。事実そのものと同じくらい重要なのは、事実を伝える人間の信頼度である。事実はめったに事実ではないが、人びとが考えることは憶測を強く加味した事実であることに留意せよ。 8.組織の中の良い連中はマネジャーから質問されるのを待ち受けている。なぜなら、彼らにはそれに答えることができ、答えたいと思っているからだ。それから初めて両者は一緒に前進することができる。
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロの柳井会長も経営の教科書と崇め、自らもこの翻訳書の中に付録解説として寄稿しているが、こちらも非常に読み応えがある。なにしろ、この「経営教科書」のどの部分をどう運用して、あれだけの成果をあげたのか、を詳細に記しているため、スケールは違えど「実行する」とはこのことなのだ、と実感、自分でも「実行」してみたくなる、というのがこの書の読みどころ。 また、こ難しいテーマでも解りやすい「例え話」が理解を容易にしており、あまり身構えることなく、その「講義」に入っていける、という感覚で読み進めていくことができる。
0投稿日: 2012.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ実績を残したひとの実績に基づく自信に満ちた言葉。 経営者の評価はただ会社の業績で判断される。 マネジャーも同じ。 参考にしたい。 ただし、読み返すのは「ノート」にする。読みやすくわかりやすいので。
0投稿日: 2012.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいると経営とは何かということに真摯に向き合えるんですが、著者のワーカホリックっぷりにちょっと引いてしまいました。 経営者は経営しなくてはならぬ!×3 机が片付いている人は現実から隔離されてほかの誰かに仕事をしてもらっているのだ。など。 ユニクロの柳井社長の熱い序文は伊達じゃない。
0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『日本では、労働コストはアメリカよりずっと安い。』 『日本の工場は、われわれの工場より新式で、ずっと高性能だ』 『日本の企業は政府からあらん限りの援助を受けている。』 我々が現在中国に抱いているような状況が背景にある。 『危機や破局は一夜にして生ずるものではない。それは、問題が長い間放置され、症状が悪化するまで放置されてきた結果である。』 『原則として私は長期計画というものを信用しない。目の前の一年間の計画を立てるだけで、マネジメントにはなすべきことが山ほどある。』 『報告書』 1 提案要領 2 問題となっていることの摘要 3 必要な場合には、その提案に到達した論拠を明らかにするための、思考過程の明確な説明と、判断を助ける展望を提供してくれる数字。 4 起案者の個人的意見と、確信の度合いと、取り上げられた事柄に関する疑問点などを述べた短いステートメント 『重要なのは自己の過失に立ち向かい、それらを吟味し、それから学び、自己のなすべきことをすることだ。唯一の本当の間違いは、間違いを犯すことを恐れることである。』 『プロフェッショナル・マネジメントという最高の芸術は、”本当の真実”をそれ以外のものから”嗅ぎ分ける”能力と、さらには現在自分の手元にあるものが、”揺るがすことができない事実”であることを確認するひたむきさと、知的好奇心と、根性と、必要な場合には無作法さをもそなえていることを要求する。』 『批判されるのが好きな人間はいない。批判を受けた場合、最初の反応は防御と反撃の衝動だ。』 『批判に対して開放的であることには、通例、予期せぬ配当がついてくる。』 『成功は失敗よりずっと扱いにくいもののように思える。』 『経済の変化が自分たちを助けてくれるのをただ待つことは、解決策として受け入れがたかった。』 『合衆国ないでの収入を増やす必要があった。ITTの年間の収入の-当時の15%でなく-50%が国内の売り上げから生じるようにしなくてはならない。国外からの収益に頼ることは、とにかく不安定要素がありすぎた。』 『最高経営者は取締役会のメンバーになっている。それどころか、大企業の3/4以上の会社で最高経営者は取締役会長を兼ねている。最高経営者兼取締役会長、それはなんの犯罪でもない。しかし、株主の利益という見地からは公正ではない。』 『社内のメンバーの一人を会長とする、情報収集機能をそなえた取締役会を設けることによって、取締役会の会議の質と密度は、近年見たことがなかったレベルまで高まるだろう。』
0投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログユニクロ柳井会長の推薦の書ということで手に取った。今回は2回目の読破。リーダーとして事実に基づいた意思決定、予測を行い、努力に値する目標をチームと共有する。
0投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ優れた経営者の本というのは、結局のところ、本を読んでその知識・ノウハウを仕入れるだけではダメ、行動して自ら、躓きながらも会得していくしかない、ということをわからせてくれる。
0投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年前の本なのに、古さを感じなかった。 仕事中毒ぽいところを感じたが経営者としての考え方、数字についての意識は参考になった。
0投稿日: 2011.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう本を読むたび、「プロフェッショナル」という標語を掲げ、ブラックな環境でもいい感じにみせる。 前職のマネージャーさんが、「コンサルなんて、client firstとか言ったって、結局はクライアントの奴隷だよ」とか言ってたのもそれに近いと思う。 でも、個人的には仕事人間なので、なるほどそんな風に経営してるのね、あなたがた。。。というのがよく理解できた本。 一方で、現場からの事実をとにかく正確にその目で確かめるという執念、悪いことでもレポートする風土をマネージャーに理解させ、実行させるための制度をつくってきたことには驚きました。 事実を4種類(表面的な事実、仮定的事実、報告された事実、希望的事実)に分類し、これらはたいていの場合、「事実」でないと断言しているあたり、経営するうえで、いかに「事実」を経営者が自分で把握することが重要かを示しているようで、興味深かった。 監査人としても同じ考えで職務に臨まねばなりません。
0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ[読書メモ] ■本を読む時は、初めから終わりへと読む。 ビジネスの経営はそれとは逆だ。 終わりから始めて、そこへ到達するためにで きる限りのことをするのだ。 ■最初の四半期に⽬標を達成できなかったら、 けっして年間の⽬標を達成することはできない ■製品系列マネージャー 競争を眼⽬にして競 争⼒を監視 現業のセールスマンやマネージャーや技術者 やオペレーション・チームのメンバーは、いず れも⾃分たちの製品をひいき⽬に⾒ることに慣 らされていて、競争者を⾒る場合、ともすれば その⽋点にばかり⽬がいくものだ。 ■マネジメントの基本的な仕事は経営すること である。 そしてマネジメントがそれに成功する唯⼀の 道は、会社の福利に影響を及ぼすあらゆる状況 に関する事実を完全に把握することだ。 ■マネージャーたちは問題をすべて、⽉次報告 書の"⾚信号"ページに書き出し、その問題が解 決されるまで"⾚信号"をつけて毎⽉報告し続け なくてはならない。 ■報告書の冒頭 1 提案要領 2 問題となっていることの摘要 3 必要な場合には、その提案に到達した論拠 を明らかにするための、思考過程の明確な説明 と、判断を助ける展望を提供してくれる数字 4 上記以外の、起案者の個⼈的意⾒と、確信の 度合いと、取り上げられた事柄に関する疑問点 等を述べた、短いステートメント ■今すぐに、それは事実か?と、そして忘れず に、それは揺るがすことができない事実か?と たずねる習慣を⾝につけようではないか ■経営するとは、いったんその事業計画と予算 を定めたら、売上やら市場占拠率やら、その他 何であれ、それを達成すると誓ったことをなし 遂げなくてはならぬことを意味する。 ■リーダーは⼈々を指導し、司令官は⼈に命令 する。 ■会社を統率する⼈間は、その会社の⼈々が本 当は彼のために働いているのでは無いと⾔うこ とを認識しなくてはならない。彼らは彼と⼀緒 に⾃分⾃⾝のために働いているのだ。 ■私が知っているたいていの会社員は、会社が 与えてくれる挑戦と報酬に満⾜し、沈むか泳ぐ かの企業家の環境に⼀⼈で乗り出したいとは 思っていない。 ■企業の中には真の企業家は、⻑期にわたって は存在せず、また存在し得ないのが実相であ る。企業家は⼗分な経験を⾝につけるまで⼤企 業の中にとどまる。それからキャッシュを⼿に ⼊れるために出て⾏ってしまう。 ■本当に重要なことはすべて、⾃分で発⾒しな くてはならない。 ■5つの事実 ・揺るがすことができない事実 ・表⾯的な事実 ・仮定的事実 ・報告された事実 ・希望的事実 ■「創意」と「結果」7つの法則(柳井正) ・経営の秘訣 -まず⽬標を設定し「逆算」せよ ・部下の報告 -「5つの事実」をどう⾒分ける か ・リーダーシップ -現場と「緊張感ある対等関 係」をつくれ ・意志決定 -ロジカルシンキングの限界を知れ ・部下指導法 -オレオレ社員の台頭を許すな ・数字把握⼒ -データの背後にあるものを読み 解け ・後継ぎ育成法-社員FC制度が究極の形だ
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のジェニーン氏は公認会計士である。レイシオン社を経てITT社長にスカウトされ、チリ政権にも介入し物議を醸した人と記憶している。彼はコングロマリットと言う経営形態を作った人である。詰り、展開する事業は相互に深い関係はないが、財務的・会計的には統合されているのだ。日本のサラ金を物色した事もある。著者が会計士だから発想し、出来たのかも知れない。この本には彼の哲学が述べられている。曰く「私のやっている事は人類悠久の歴史からみれば取るに足らない事だろう。しかし、他に私は何をするだろうか?<中略>我が社打ち建てるべき記念碑は、株主に還元されるべき一株当たりの利益の数字以外にはないのだ!」云々。やや洗脳された人にも見える。
0投稿日: 2011.10.10
