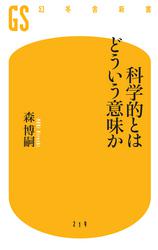
総合評価
(197件)| 35 | ||
| 68 | ||
| 51 | ||
| 10 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の新書に比べるといつもの森さん節が控えめな印象。私は文系大学行っていたけれど、ここに書かれる文系の科学とかの苦手意識は皆無なので森さんの話はよくわかる。数字を過信するのはよくないけれど、数字より感情論出してくる方がもっとやばい。そして今この感情論が蔓延りすぎていて日本大丈夫か‥?となっているのであえて今読んだ方がいい一冊だと思う。
0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログいわゆる「理系」の自分にとって、すごく大切なことが書かれていると感じた。特に、数字とか量とかのイメージを確かに持っておくべきという主張に共感する。計算ミスによる重大なミスに気づくためにも必要だと思う。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学を忌み嫌う人間(半ば私も含まれるだろう)に対して、忌憚のない忠告をした本であった。途中耳が痛くなることもあった。印象に残った箇所は、「科学は非情ではない」という点だ。科学に対して、どこか「人間味のなさ」を訴え、それが理由で排斥されることもしばしばだとか。兎にも角にも、科学に対する認識を改める方がよいと感じた。そして、曖昧にしていた「科学」とは何か?ということも、自分の中で定義を覚えておきたい。(他者によって再現可能な方法を積み上げるシステム≒客観的)
27投稿日: 2025.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識も大切だが、方法を学ぶことも大切。科学的な考え方は方法を理解すること。誰もが再現できること。再現性!まさか、ここでこのキーワードと再び巡り合うとは(若い頃、仕事のFBで知った単語)。仕事だけではなく、生活にも取り入れたら?と言われた気分。 生物としての直感も好きだが、人類が発見した数々の方法を理解し、生きやすい人生にしていきたいと思う。
6投稿日: 2024.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
p37 九九ができることが、数字を取り扱う頭脳にはマイナスになる、と僕は考える。 p39-40 最初は小さな「損」でも、積み重なれば大きくなる。小さなチャンスを見逃し続ければ、きっと経済的な損をするだろうし、もっと重大なことでいえば、自分の健康や、危険から身を守ることにも関わってくる。 p75 科学とは「誰にでも再現できるもの」である。 p90-91 たしかに、18世紀頃の科学は、もっと急進的で、いろいろなものを破壊する大胆さがあったかもしれないが、今はそうではない。 p91 カリスマ的な指導者の発言が国民を動かしたりするようなことは、科学にはない。また、科学は、一部の特権階級にだけ、その恩恵をもたらすものでもない。科学は、経済のように暴走しないし、利潤追求にも走らない。自然環境を破壊しているのは、科学ではなく、経済ではないか。 面白かった。 結構熱めの熱量を感じたり感じなかったり。震災の影響で書くことは変化したように思うし、良くも悪くもそれがドライヴさせる結果になっているような気も。また新書とはいえ10数日で本作を書き上げていることも、著者の仕事人としての凄みを勝手に垣間見ました。
1投稿日: 2024.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系小説家の森氏による、あらゆる世代へ向けた「科学を毛嫌いしていると損するぞ」というメッセージに貫かれた一冊です。 ともすればあいまいになる日々の言葉の把握ですが、己の尻を叩くためにも、折りに触れ再読したいと思いました。
1投稿日: 2024.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的に考えるのは面倒くさいなぁと思った。 でも科学的に考えないと、煽動されるかもしれない。 科学的に考えるのが好きじゃないと大変だなぁと思う。
1投稿日: 2023.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「科学」について考察したエッセイ。 物事の理論を解明し、再現性を重視するのが科学の役割だが、近年の風潮として原因と結果だけを求める傾向があるため、科学は敬遠されやすい。著者は、作家で建築分野の研究者でもある。その観点から科学的な考えや文系人間について、自身の見解を述べる。 この本が書かれたのは東日本大震災が発生した時期で、日本の世論が地震や原発問題で揺れていた。メディアでは、普段聞き慣れない単位(ベクレルやシーベルト)を使って被害状況を伝えたり、原発について理解していない文系コメンテータが感情論に訴えたりしていたが、科学をよく理解していれば、メディアに踊らされることは無いはずと言う。理系は過程を重視するが、文系は結果だけを鵜呑みにする傾向がある。自分で判断する根拠として、また論理的に推理する方法として科学がある。 メディアに溢れる識者のコメントの信憑性を判断するために、科学の正しい知識を持つ事が重要。科学知識も常にアップデートされるので、日頃から情報に接しておくことも必要だと思った。
0投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学って素晴らしいよ!というような、説明ではなく、あくまで淡々と、科学とはどういうものなのか?を説明してました。 算数や数学は、ものを考える「方法」を教える科目、ってのには成る程ねぇと目から鱗。 高校で理系を断念した文系の人にこそ、読んで貰いたい。
0投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ○多くの人が科学を敬遠するのは、自分で考えること、感じることが面倒でしたくないから ○しかし、科学を避けるとむしろ損で危険な方向に進む可能性がある ○科学とは「誰にでも再現ができるもの」 ○科学的とは「誰にでも再現できるステップを踏むシステム」 ○ただ、数や実験があるから科学というわけではない ○実験によって確かめることが「科学的」なのではない。実験では条件の設定でいくらでも変わり、不正もある ○子供に対しての注意 子供は超自然的なものを信じやすいので、きちんと説明してあげること。 好奇心をつぶさないように。外で遊ぶイメージを持たせてしまうが、科学館などもよい。 特に父親は押し付けてしまう。 自由さから科学を発展させる独創性や発想力はうまれる。
0投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自分にはわからないから」と決めつけて考えないということはよくある。「神の御業」とか「バチが当たった」と考えるのも同じで、「神」を作ることによって人々は深く考えなくても良くなった。 数値で示すことは正確な情報であるのに、人々は「わからない」と言う。人々は、数値が意味することを考えたくないので「自分にどういう影響があるのか」を言葉で聞きたがる。 それでもいいけど、「考えることを避けてしまったな」「数値に疎いな」というのは認識しておいた方がいいと思った。
0投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ消化しきれない多くの情報が溢れている現代だからこそ、自ら分析し考えて消化する思考を身に付けておく必要がある。扇動的な情報に踊らされない為に。
0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学を正しく、そして前向きにとらえた本です。 「科学では説明できない〇〇」「理屈で考えない」みたいな話は、大衆が飛びつきやすい話題なのかよくありますが、それってどうなの?と考えさせてくれます。 正しい判断力を付けられる本だと思います。
0投稿日: 2022.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ非科学的なこと(占いとか)が好きな自分にはグサッとくるところもあったけど、確かに科学を必要以上に敵視したり、少しの理屈も知ろうともしない態度は、たくさんの科学で成り立っている今の世の中を生きる上では危険なことなのかも、と思った。 あと、子育て中なので、幼少期のテストだけで、この子は文系なのね…と早々と決めつけることだけはしないでおこうと思えた。
0投稿日: 2021.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的とは、「誰にでも再現できるもの」で、再現する方法として実験がある。 文系と理系で分類することはナンセンスであることや、理系や数学に拒否反応を起こしてしまう人に対して、嫌いにならなくていいよと説明している内容であった。言葉での感想ではなく、客観的に説明できる数字が重要ということが分かった。ただ、注意すべきなのが、実験や自分の目で見たことが全てが正しい訳では無いということ。客観的に、定量的に判断する思考を大事にしていきたいと感じた。
1投稿日: 2021.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学とは? ということを理解するのに最適な入門書。身近で、もはや誰もかかわらずに生きていけない科学。科学について、一般の人間が理解しておくべき視点について簡潔に示してくれている。 非科学的なものを非難するのではなく、何が科学と異なっているのか、また、科学を理解しておくことの重要性が示されている。 とてもドライな姿勢が気持ちがいい。 内田麻理香氏の『科学との正しい付き合い方』も併せて読みたい。
1投稿日: 2021.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「科学的」の捉え方が自分の中で変わった。 面倒を避けない、メソッドを重視する、データと慎重にお付き合いする、などなど。 震災直後に執筆された本とあって、当時の原発事故に対する人々の反応に向けた批判が背骨になっている。けれど、これはそのまま今年のコロナの話として読み替え可能だ。 そういえば、そんな話を朝日新聞の特集で見たような。論者は誰だっけな? 私たちはどんな悲惨な出来事からも、基本的には、何も学ばないらしい。 ……いやいや、こういうペシミスティックな態度も、科学的じゃないんだった。 あくまでもデータと向き合い、現実的かつ慎重に、前向きに処していく態度。それが、科学的、という言葉の意味するところだと諒解した。そうなれるかどうかは、これからの行動次第だけれど。 これを読んだ後は、池内了さんの『疑似科学入門』あたりがよさそう。
1投稿日: 2020.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ名古屋大学で建築学を学んだ工学博士である一方で、推理小説で作家デビューを飾り、作品に科学関係の専門的な描写や数学の謎解きなどが多く登場することから「理系ミステリー作家」と評される著者が「科学と非科学」の違いを明らかにして、科学的な知識とか考え方について自身の意見を述べる。科学とは一言で言えば「誰にでも再現と観察が出来る現象」のことであり、それを確かなものとする手段が数字や実験であるというもの。読書やスポーツと同じように「科学」を好きになって欲しいという内容の本ではなく、科学を避けて現代を生きる事はもはや不可能であり、科学から目を背ける事は個人にとって「不利益」で、社会にとっては「危険」であるとさえ論じている。ちょっとお堅いテーマでありながら、小説家らしく興味をそそるタッチで書かれた「科学論」は大変に面白く、科学アレルギーになってしまった文系人間にもぜひ呼んで欲しい。
1投稿日: 2020.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログとても読みやすく分かりやすい表現で書かれていたのでさらさらと読めた。 理系としては知っていることの再確認なので、こうすれば伝わりやすいのだなということが確認できた程度でした
1投稿日: 2020.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログシンプルにまとまっていて読みやすいと思ったら最後に12時間で書き上げた本だということでビックリした。
1投稿日: 2020.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ★その通り、だが誰に届くのか悩ましい★いろいろなところで言われるように、科学的とは方法論で、再現可能なこと。「だから結局なに?」という早急な問いかけや思考停止をやめて、きちんと過程を考えよう、その方が面白いし役に立つ、というのは至極もっとも。理系の人が理屈っぽいといわれるのは、丁寧で慎重なだけ、というのもまさにそのとおりだと思う。津波は単なる波ではなく、大量の水の移動なので堤防の高さに応じて津波の高さも変わるという説明も分かりやすい。 ただ、著者の言う通り、科学的であることが好きでない人にどう届けるのかは本当に難しい。美術やスポーツが好きな人が関心のない人にいくら熱を込めて語ってもなかなか伝わらないのと同じだ。著者のエッセーを読む人はどちらかといえば、科学的なことが嫌いではない人だろうし。 しかし震災後の3月に、本書を3日間12時間で書いたという。小説を含めて書くスピードがすごいのは、書くことに迷いがないからなのか。
1投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「文系」人間が出来上がる仕組みはまさに自分のことを言われているようだった。 考えるより丸暗記する方が楽だと判断して得るものもあったが、その分失ったものも大きいだろう。 著者の言う文系的な特徴は、社会が複雑化し情報が溢れ思考停止している大衆社会の特徴とも重なる気がした。 まずは中学数学からやり直したくなった。
1投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学に興味のある一人として、いろいろな気づきを得られました。ただ、題名に科学とあるけれど、そういう方面が苦手な人ほど手にしてほしい一冊です。
0投稿日: 2020.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
分かりやすいだけでなく、本質的です。 科学的とは「データ(情報)」ではなく「メソッド(方法)」である? ・森博嗣先生の言い回しを借りれば、この本が示しているのは、「データ(情報)」ではなく「メソッド(方法)」である。だから、この本に書かれている内容を憶えるために、書棚の一等地に置き、7回読む必要はない。「メソッド(方法)」を腑に落としたら、後は、実践あるのみである。何か、疑問に思った時、文学的!?に理解しようとするのではなく、データを比較し、科学的に理解しようと努めよう。そうすることで、私のような文科系?も、少しだけ真の理科系!?に近づけるかもしれない。但し、参照するデータがどのように測定されたか確認しよう。 ・私の周囲にも、科学的に理解しなければならないことを、観念的に理解しようとする人が少なくありません。そのような人たちによる伝言ゲームによって事実は間違って伝わるのです。 ・意思決定するためには、課題の相関関係を把握し、目的に適合するバランスを見つけ出さなければなりませんが、そのためには、科学的にデータを読む力が必要ですね。 ・この本は、ちくまプリマ―新書のような、中高生向けのブランドから刊行されても良いような内容です。分かりやすいだけでなく、本質的だからです。
0投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ途中なんですが、文系ディスり過ぎじゃね…?文系人間はこうだからダメだ、てな決めつけが多くてヘキエキしてきました。そしてその文系理系の二項対立過ぎてな…うーん。 ちなみに私は文系自負してるけど、フィクション、ノンフィクション、読む割合は1:2ぐらいかなぁ。
0投稿日: 2019.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ天邪鬼な森氏の新書。他の新書と方向性のブレはない。国民を感情だけで誘導しようとするマスコミ、政治に懐疑的だ。ただ、世の中が科学的な思考を持つ人ばかりになったら、それはそれで生きづらいようにも思える。 何に関しても常に疑問を感じながら、めんどくさがらずに思考し続けることも大事なのだろう。
0投稿日: 2019.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分なりに理系よりだからか、言っていることは非常に共感できる。 ただ、著者の優しさというか押し付けない感じがあまりに、冗長な感じ。
0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学によって得られるものとは人間の自由(^o^)/科学の存在理由、科学の目標とは人間の幸せである\(^_^)/
0投稿日: 2019.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学エッセイ。 難しいことは全く書かれていなくて読みやすい。 思い当たることが、誰でもひとつくらいはあるのでは?
0投稿日: 2019.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「科学的とはどういう意味か?」というタイトルだが、文系理系論の本? 自分自身文系で、科学という学問の体系について学べると期待して読んだ。 実際は作者のエッセイ。そして「要は文系は~」という考えというか偏見で構成されていた気がする。 引用文献の数より自分の考えの方が大事とか、文系は小説ばかり読んでいるとか、作者を信頼していいのかと思ってしまう考えや印象が書かれていて戸惑う記述もいくつか。個人的には、持論を支える論証は多いにこしたことはないと思うし、小説しか読まないというのはそれこそ科学的ではなく偏見でしかないと思うのだが…。 筆者は理系が文系よりも優位にあると書いている。私自身文系で、文化について大学で勉強していただけに、文系学問を否定するような書き方は残念。 事実を積み上げて世界を理解する学問が理系なら、それを研究していく私たち人間について理解する学問が文系だと思う。人間はどう感じるのか(感じてきたのか)、それをどう表現しているか(表現してきたか)等など。 お互いの領域の違いがあるだけで、そこに優劣を持ち込むと、結局はお互いの学問の隔たりを深くしてしまうだけだと思う。「トロッコ問題」のように科学が思考しない領域や問題が実際にあり、それを哲学などの文系学問が思考・研究しているという部分にも筆者は目を向けたほうが良い気がする。 災害の被害の規模などを感情で語ってもしょうがないとか、最低限の科学や数字に対するリテラシーは必要という意見には頷けた。しかし、それを拡大して「だから感情・共感よりも科学というモノの見方が上」という態度になってしまうと疑問を持つ。 最後に。あとがきの12時間で書きましたーというのは、読んでいて気が抜けるというか…。
0投稿日: 2019.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中の算数嫌いの人に贈りたい本。如何に思考停止して、危うい世界に行きかけているのに気づいて欲しい。 以下の言葉を心に留めて、生きていきたい。 「好きになる」ということは本当に大きな「力」になる。人の能力を発揮するための動力として、素晴らしいエネルギィだ。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「すべてがFになる」以降学生時代にどハマりした森博嗣さん、こういう本も手掛けてなんだなあ。自身文系だけど、理数系への苦手意識は無いので、すんなり読めた。力作ではなく世間話感覚でさっと読むと良い感じ。
0投稿日: 2018.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ上司の勧め。 「かけっこも計算も一緒で、走るのが遅い人も計算が速い人も、ゴールできない訳ではない。なのに計算は「数式無理!」っていうアレルギー反応を起こしちゃうのはもったいない。」 この部分はすごく好き。というか勇気が出た。 わたしは本当に計算が遅いのだけど、バリバリ理系の職業にしがみついているから。 「数字が一番わかりやすいのに、わざわざ東京ドーム何個分ていうのが無駄」 ここは、頑固な理系って感じ。 数字は専門用語と一緒で、わかる人にはこれ以上ないストレートな表現だけど、わからない人にとってはイメージできないから理解する気になれない。 わかりやすくかみくだく、これが苦手なんだよねー理系はって証明しちゃってると感じた。 タイトルがよく中身を表してるいい新書だと思う いろんな人の考え方を知れるから、こういうのも読むと面白い!
0投稿日: 2017.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学(というか理系学問)を敬遠する人たちに科学の良さを説く本の一種。言っていることはいちいちもっともで異論はないが、この本が誰に向けて書かれたものかよくわからなかった。いわゆる理系の人であれば当然感じていることを文章にしたに過ぎず、あえて読む意味もないだろう。 しかし文系の人がこの本を読んでみる気になるかどうか怪しい。なぜなら、文系の人を惹きつける要素がどこにもないからだ。帯に書かれている宣伝文句は「科学的無知、思考停止ほど、危険なものはない!」だ。これは文系の人から見たら説教されているように感じられるのではないだろうか。 著者が有名な理系作家ということもあるため話題にはなるだろう。しかし、あとがきの最後にはこう書かれているのだ:「3月末になり、ようやく少し余裕ができた。本書は、そのとき、3日間、計12時間で執筆したものである。」・・・はあ、そうですか。確かに書きなぐったような文章ですね、としか思えない。
0投稿日: 2017.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログそうだ、森博嗣は科学者であったのだな、と改めて思った一冊。この一冊を読んで、彼の小説を読む直すと、また、違った感想をもつのであろう。ただし、近日中に読み直す暇は見つからないのが残念だけれども。 つまり、ここ2~30年、なぜ、科学的な態度、というか、科学的な見方が失われてきたのか、ということが分かりやすく書いてありました。それは、社会全体の危うさでもあり、それを一身に受け止めている若者たちの危うさでもあったのですねえ。 一気に読める本であり、一気に読むべき本でもあると思う。読み始めてから読み終わるまで、いささか時間をかけすぎた。少なくとも筆者が一気に書き終えた速度には負けないように読むべきであったと反省した。その方が、きっと感銘と理解が深かったのではないかと思っています。
1投稿日: 2017.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人はどのようにして冷静でいられるのか 人は得てして間違った判断を行う事がある。それは、人と人との事であれば、ホルモンの異常分泌などで説明が付くのかもしれないが(最近の科学ではどうもその点も解明されそうであるが)、適切な情報を収集せずに判断をする事がある。 それが、一生懸命に集めた情報が判断に足りなかったというのであれば、残念ということであろうが、十分な情報ではない事を知っていながら、それ以上の情報は何故か不要と判断して、間違った判断をしてしまう。 そんな光景を、ここ数年よく目にするようになってきていた(そのような仮説を持つようになってきたためでしょう)ので、日本人はこの先大丈夫なのだろうか?とまで思ってしまっていたときに、このタイトルに出会った。 内容は非常に分かりやすい。 目に見えないものについて、人は判断を間違えやすいが、実は目に見えないものは数多く有り、子供の頃から慣れ親しんでいるものであれば、判断を間違えない。 理系と、文系と分けてしまっているが、文系に進んだ人は理系科目の試験が時間内に回答できなかっただけで、不得手であると認識してしまった可能性があるのでは?逆に私は、文系科目については、全くお手上げで、記憶についてはコンピューターに任せれば大丈夫と高をくくってしまった。従って、文学の繊細さについてはさっぱり分からず、本を読むのが凄く遅くて、未だに困っている。 文系、理系を問わず、科学的に考えることとはどういうことか。 実は、そこに世界をフラットにする考えがあるのではないかと考えている。 科学者は単に探究心にあふれている人が多く、自分の発見を世界に広め、人類の幸せのために使ってもらおうと思っている人が多いと考えている。ただ、それでは飯が食えないので、飯を食える仕組みを考えるパートナーと一緒に仕事をするか、自分で飯が食えるようにしていく事になる。 ただ、その中でその技術の使い道を誤った方向に使ってしまうことが有り、それが大きな事故を発生させることがあるのである。 科学とは再現が可能であるわけだから、Aさんが考えた技術は、Bさん、Cさんも再現できなければならない。となると、世界中であっという間に複製されるのである。 はさみは使いよう。とはよく言ったものである。 殺人を意図した毒物を除けば、ダイナマイト、自動車も有用な利用を考えて作られた技術であるが、それでも時代の中で大きな犠牲を伴ったことも事実である。 最近見た映画で、第二次世界大戦中にドイツ軍が使っていた暗号機エニグマを解読したイギリス人数学者を描いた、イミテーション・ゲームでも描かれていたが、大枠を数字から判断することは極めて重要だと考えている。 もちろん、数字には人の機微は描かれていないことは知っている。 http://imitationgame.gaga.ne.jp/ http://amzn.to/2lHV9qe
0投稿日: 2017.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2011年刊行。「科学的」の意味内容を功利主義的視点から解明し、非科学的な言動を止める処方箋を提示。「科学的」の意味内容は至極真っ当で何ら異論を挟むものではなく、著者の「非科学的態度は損だよ」との指摘も頷くところ大。ただ、非科学的言動を止めさせたいとする著者の意図が、本書で成功するかは??。①著者が真にターゲットとすべき相手は、本書を読まないような人々だし、②「非科学的言動は妄想」的な著者の叙述は、指摘として正しく(個人的には著者と同感)とも、読者が感情的に本書を忌避し、説得行動としては上手くないからだ。 善意から生じ、かつ正確なことを言えば相手に必ず伝わると考えておられるのだろうが、まさに理系の弱点を図らずも露呈してしまった感がある。ともかく、簡明な文章だし、内容は正鵠を射た正しいものなので、本書は長女には読ませてみたい。
1投稿日: 2017.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが、元理系大学(建築系)の助教授をされていた方らしく、科学的思考について述べられています。 ご本人曰く、”理系の中では非常に文系より”(p.8)とのことで、小説家でもありますので科学的思考に関しては、きわめて伝わりやすい文章で説明されている印象を受けました。 最近、放射線、感染症、ワクチンなどに関するセンセーショナルな報道を目にする機会が多いですが、それらを適切に読み解き冷静に理解するためのきっかけを得ることができる一冊だと感じました。 いわゆる情報リテラシーを向上させるには適した一冊です。 付箋は13枚付きました。
0投稿日: 2016.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ気になっていてやっと読めた一冊。新書も高いから。電書で割引されていたので購入(*´∀`)俺も理系だけど科学って何と言われても科学とは論理的に考えられ、それが当てはまるもの的な認識しかなかった。タイトルが気になる人は是非どうぞ。
0投稿日: 2016.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「言葉とは単純化であり、ディテールを損ないかねない」という主張が、自分が最近考えていたこととピッタリ一致していた。 テーマがはっきりしていて、すんなり理解できた。 森博嗣はものの見方が鋭いというか、まさに科学的だなあ。
0投稿日: 2016.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ数字を拒否しがちという点において、典型的「文系」のわたしには耳が痛い。ものの仕組みや道理がなぜ重要なのか、著者の意見が平易に綴られていて受け入れやすかった。 合理的であること、即ち冷静であること。
0投稿日: 2016.02.16”科学的”とは自分のメジャーを持つこと
内容として、特に難解な数式は出てこない。だが、現在に生きる我々が持つに足る科学的スタンスを示唆してくれる。まるで根拠の無い効能を謳った健康商品や医療行為、曖昧な安全性で誤魔化されてしまう、津波・放射能情報など・・・。数値化されることで見えてくるモノ、科学的メジャーでモノを見る習慣をつけることで、表層的”科学万能主義”に惑わされない思考法を教えてくれる一冊。
1投稿日: 2016.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログスカイクロラの森博嗣による科学的とはという根本的なものを、東日本大震災の影響ですが考え直すべきという主旨の本。科学的にとはを考えることで、事象を感想やイメージだけで捉える危険を感じさせてくれる。 科学を敬遠する人は自分で考えることから逃げる人だ。科学とは、だれでも再現ができるものである。実験が科学では無い。数字や実験により、再現可能なものに近くなるということ。知ってるか知らないかは大したことはない。 文系と理系の違い。省略、ジャンプで結論にいきたくなるが、それが気持ち悪くて、一つ一つ確認するのが理系、科学的であるということ。鳥はどうして飛ぶことができるのか?翼があるから。しかし、翼があっても飛べない動物もいる。 科学は、神とか信じること、単純にすることでわかった気にすることができる。支配しやすい。科学は、理論によって、人間味のあるものを排除できる。思い込みから脱却し、慎重に事実を確認すべきだと。 津波は5メートル。これは高さであり、5メートルの堤防があれば防げる。これは間違い。波が押し寄せることで、力量は5メートル以上。波は押し上げられ、より高くなる。感情ではない、確認が必要だ。 科学の存在意義は、人を幸せにすること。祈ってますではなく、それはそれで人を救うけど、科学で本当に救うことも大切だ。理系の人にとって、世界はこんな風に見えている。
0投稿日: 2015.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学の大切さについて、なるべくニュートラルな立場でわかりやすく説明してくれる内容。 ●文系と理系と二つにすっぱりと自分を分けてしまうのはもったいない。 ●科学を敬遠することは、他の分野に比べて日本人が日本語を知らないくらいに致命的なこと。 ●学生の時に学んだ学問のほとんどは暗記ができれば良いが、数学はメソッド(方法)を学ぶので、他の学問とは少し違う。 ●幽霊はなぜ、壁をすり抜けたり宙に浮けるのか。つまり空気と同じ質量だから、風に飛ばされもするし、拡散もする。空気は密閉されていればガラスなどもすり抜けることはできない。であるとすれば一体何なのか? ●身近にある物の数字を知ることが大事。質量なども。 ●科学のおかげで宇宙にある法則は地球に即した法則で想定できる。今の所、あてはまらない法則はない。 ●科学とは誰がやっても再現できること。 などなど、とても為になりました。 それにしても、知らないことばかり…。
0投稿日: 2015.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学を楽しいと感じるかどうかは人それぞれだけど、科学は人を幸せにするためにあるのだし、危険から身を守るのは科学だし、科学を毛嫌いして耳を塞ぐといろいろ損をするので、聞く耳を持つことを推奨するような本。
0投稿日: 2015.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学は楽しいよ,面白いよ,といっても押しつけにしかなんなくて,楽しいとか面白いとかでなく知ってないと損するから,ていう言い方は非常に端的だと思う。そういう言い方だと脅迫っぽくなるし欠如モデル的に見える(知らなきゃだめよみたいな)から科学コミュニケーション界隈ではあんまり声を大にしては言ってないような印象があるけど(リテラシーの涵養とかは言ってるけど),もうちょっとこういう言い方出してもいいような気もしなくはない。ただ,じゃあどこまでが最低限知っておくべきリテラシーかというと,提案されているものはあるものの,どうなのだろうなあ。
0投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ驚く程読みやすくてびっくりしました。文系と理系のくだりに納得しすぎて気付けば読了していました。うん、今まで勉強しなかった分、勉強しよう……。
0投稿日: 2015.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきによればこの本は12時間で書き上げられたものらしい。東日本大震災の直後に擱筆したようで、災後の緊張感がところどころに表れている。いやむしろ、あの放射能汚染をめぐる報道の混乱の中で本書の方向性が決まったのではないかと思われる。 世の中に多く存在する科学嫌いを筆者は思考停止と考え、その不利益を述べていく。表層的な印象や、個人的な感想を中心に報道するメディアや、それを鵜呑みして自分で判断することなく結論だけを求めようとする多くの人々を痛烈に批判している。 正直言って文系と理系に人を大別したり、人間の行動を図式的に捉えすぎている感がしないではない。結論を急ぐあまりに詳細を省略した感がある。また、多少内容的重複が気になる。それは新書という器にしては仕方ないのかもしれない。 学習が「情報」の多さに偏重せず、「方法」の獲得に力点を置くべきだという考え方は、新しい学力観とも関係する注目点である。科学論を考える前の準備として読んでおくべきだろう。
0投稿日: 2015.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ世間でいわれる理系人への誤解を解く。 3.11関連の記載はここに書かれていたのか。 理系にすすみ周りにも理系人が多かったが、世間的にみたら理系はマイナーであることに最近気がついた。
0投稿日: 2015.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りた。 タイトル通りの内容を述べている。3.11直後に執筆されたらしく震災の例が多い。 文系・理系と分けることは相対的なもので、理系と呼ばれる分野の中でも互いに、あちらは文系よりだ、理系よりだと話をすることがあるようだった。 著者が問題だと感じていることに、理屈はいいから結論だけ教えてくれ、という態度があった。現象を理解して、対策を自分で考えるのではなく、危険かどうかだけをしらされて避難するかどうかを指示してもらう態度は非常に危ないと同意できた。正直、そのような態度を取る人間はどうして相手をそこまで信用できるのか理解に苦しむ。 著者のスタンスとして、科学の楽しさとか、科学に興味を持って欲しい、のではなく、知らないと不利益を被ることを伝えようとしている。 よくスポーツの楽しさとか読書の楽しさとか、自分のやっていることを相手にも押し付けようとする人たちがいるけれど、楽しさは個々人で異なるのだから大きなお世話だと思っている。むしろ知らないといけないこと、困ることを何とか身につけさせるようにする方が大切な態度だと考えるため著者のスタンスに共感する。
0投稿日: 2014.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「感情的」なニュースに辟易している最中、この本を手にした。科学のことだけでなく、マスコミの流す情報に対する意見も書いてあり、同感だと思うことが多々。 「物語ではなく、情報や意見により耳を傾けるべきである」とのこと。小説が大半を占める私には耳が痛い。 鵜呑みにするのではなく、疑うことや厳密性の追求、白黒はっきりつけようとしないこと(しかも何となくで)。 今さら科学者になれる訳ではないが、少しでも科学的であるスタンスでいたい(生きにくそうだけど)
0投稿日: 2014.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系を毛嫌いするのはなぜか?分からないものを避ける。科学は分からないものを分かろうとする手段であり,絶対的なものではない。そのために他者による再現性を重視しており,他者でも扱えるように他者と共通認識をもてるように数量化したり,制限をつけた記述をしたりする。感覚的に表現するメリットはあるが,他者と事実を共有するには感覚はあまりにも主観的すぎる。その感覚をいかに数値化するかがまた科学であったりする。
0投稿日: 2014.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ文字通り科学について書いてあって、「科学離れ」について触れている。すでにタイトルで科学嫌いにとってはハードルになってるんだけど、読んでみたら人にとっても科学者にとっても優しい言葉が書かれてあった。 科学は人をしあわせにするためにある、という言葉は響きがもうしあわせだった。科学は慎重に時間をかけて実証していくことだというのも優しさを感じる。 「実験をすれば科学的だと勘違いしている人がかなりいる」と書かれててそこにも興味がわいた。何度も再現性を確かめて、「正しい」と思える状態に近づくプロセスが科学なんだって言われてちょっとわくわくした。 「科学を遠ざけることは損だし危険すらあるのだから、もう嫌いと言っていられる状況ではない」という主張も、今まで誰からも言われたことなかったことで素直に聞き入れてみたくなった。おとなってすぐ「科学って面白いよ」って科学実験ショーなんか見せて子供を喜ばせることばかり考えるんだけど、そういう科学が見たいわけじゃなかったぼくは損得とか言われたほうが面白かった。 科学って聞くと数式とか思い浮かべて降参しちゃうんだけど、考えたら社会科学も科学のうちだし。社会や人間はより複雑な気がするけどそっちの科学には興味がないわけじゃなかったわけで、結局科学嫌いというより数式についていけないと思ってただけなんだろなって思った。 科学が嫌いって自分で思い込んでたところあるけど、別にそんな「思い込み」にこだわることもないんだなって思えた。 難しい数式はわからないけど、日々の人とのやりとりを数字に置き換えて計測したことがある。いつ会ったとか、何日ごとにメールを書いたとかだけど、それだけでも、やってみたら、目の前の出来事が少しだけ以前より理解できた(気がする)。それだけでも科学に寄り添ってるということかもしれない。
3投稿日: 2014.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ前書きに書かれているとおり、本書の主張は次の2つ。科学から目を背けることは自分自身にとって不利益、そういう人が多いことは社会にとって不利益。主張も内容も明確でわかりやすいがそれ以上の興味深さはない。
0投稿日: 2014.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ141p。"一般の人たちが目にする...「○○発見!」のようなニュースは、ほとんど眉唾状態のもの...であると理解して良いだろう。" 完全にSTAP細胞問題のことを予言しているとしか思えなかった。
0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は「科学的とはどういう意味か?」というタイトルではあるが、この点を深く追及するというよりは、この問いを起点として水平的に問いをずらして展開し、「文系と理系」「科学と非科学」と言った具合に対立構造を強調しつつ、科学の優位性を強調する仕上がりとなっている。 「科学的とはどういう意味か」という問いについては、その結論もその過程もこの本の数分の一程度のボリュームで済むと思われる扱いになっており、タイトルを見直した方が良いと感じる。中身も重複している部分があったり、順序がバラバラだったりで、体系的にまとまっているとは言えない。正直言って書きあがったエッセイがあまり編集されることなくそのまま書籍化された印象すら受けてしまったのは残念だ。事実筆者自身が後書きにて「本書は3日間、計12時間で執筆した」と認めている。 その他具体的に疑問に思われた点は幾つもあったが、例えば、 1.理系と文系というように二項対立で捉えることの非科学性を指摘しながら、理系が文系より如何に優位であるかにかなりのページが割かれている。(理系は文系を避けないが、文系は理系を理解できないため理系の人を「人間としての心が欠けている」と批判する、文系は理系に醜いコンプレックを抱えている、など) 2.科学の優位性、万能性を強調しすぎているきらいがある。非科学の例として、「神を信じている人」を挙げ、科学は「神の支配からの卒業」と捉えている。発展途上国ならともかく、科学の普及した先進国でさえ神を信じている人が多いことに疑問を呈している。しかし、そもそも科学と宗教はどちらを信じるかといった二項対立的なものではないはずである。筆者の論理でいけば、神を信じるという非科学的な思考をもつ人が多い国ほど、国家レベルでは科学の進歩は停滞し、個人レベルでは不利益を被り、最悪の場合生命の危機に脅かされるはずである。しかし、現在最も科学技術研究の先端をいく国はどこなのか?宗教のような非科学的なものを信じている国は困窮しているのか?神の存在を信じている、有能な科学者の存在はどう捉えればよいのか? つまりは「科学」と「非科学」という2つのカテゴリで括ってこれらの問題を捉えようとすることに無理があると思うのだ。 科学は、「印象や直感をできるだけ排除し、可能な限り客観的に現実を捉えようとする」。その厳格さが「他者による再現」を可能とし、その信頼性を担保する。 だが、あくまで個人的な意見ではあるが、その厳格さによりそぎ落とされたもの、定量化できないもの、印象や直感、その部分にこそ今後の時代を生き抜く上での重要なファクターがあると個人的には思える。科学的な考え方はもちろん重要だが、だからといって厳格な科学的思考にそぐわない考えを「非科学的」とみなし、それを見下して軽視してしまうようでは、それこそ狭量で危険な考え方なのではないか。 今回は思想的な部分での主張が強く、なかなか腑に落ちない所が多かったため、かなり辛口の批評となった。しかし、何かと考えさせられた一冊でもあるし、得たところも非常に多かった。森さんの今後の著作にも期待したい。
2投稿日: 2014.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ物事は単純化しないと処理しきれないからそんなに悪い事でもないとは思うが、その度が過ぎると事実と異なる思い込みや偏見になるわけで、ある程度は論理的や数字で考える事の必要性を説いている。言葉は使いようである。 但し、定義もよくわからないし文系とか理系とかはあまり意味ある分類だとは思わない。著者はこの辺に非科学的な比較を持ち込み、言葉による単純化をしている気はする。なら各試験科目の偏差値という数字で比較した方がスッキリするだろう。東大の文系とFランの理系ではどちらが論理的に数字で考えるかは明らかである。 著者は原発賛成派のようであり、本書も311後の日本を意識して書かれているが、結構批判されたようだ。人間は感情の生き物である。そこを見誤り、科学・論理に突き進むと結局自分の身が守れなくなるというのもまた事実ではある。 「科学とは方法であり、その方法は他者によって再現できる事が条件である」は311後よりも再現できないコピペ論文で話題になった昨今こそ響くフレーズではある。
0投稿日: 2014.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系か文系かと聞かれれば、私の場合、理系ということになるのでしょうか。よく妻と話していても、数字にこだわりすぎるところがあるようで、はっきり言っていやがられます。しかし、世の中、数字で考えた方が分かりやすいことの方が多いように思うのですが。 この本の著者は、もともと科学的に考えることの大切さ、あるいは非科学的に考えることの危うさについて、機会あるごとに主張してきたようです。この本を書こうとしているとき、あの大震災が起こり、原発事故が日々報道されるのを見て、さらにその思いを強くしたのではないでしょうか。 さて、この本は大きく4つの章に分かれています。第1章「何故、科学から逃げようとするのか」では、現代人が、科学的なものの見方を避けようとしていることを指摘しています。それどころか、科学的に考えようとすると、具体的には数字で表現しようとすると、数字じゃ分からん、数字なんてものは当てにならんとまで言われる始末です。 第2章、第3章では、「科学的というのはどういう方法か」「科学的であるにはどうすれば良いのか」が、分かりやすい例を交えながら紹介されます。p.121では、科学的に答えてみよう、「鳥はどうして飛ぶことができるのか?」という話題が展開します。確かに、こんな身近なことも私はよく知らないんだなあと反省させられました。 p.89のある技術者の返答も考えさせられました。「AとBはだいたい比例していると考えて良いか?」という質問に対して、技術者らしい実直な回答をします。なるほど、こういう姿勢が大切なのだなと思いました。 第4章では、「科学とともにあるという認識の大切さ」になります。ここでは、子供に対して、大人がどう接するべきかが書かれています。その中で私が引っかかったのは、p.184「僕たちが科学少年だった時代のように、これからの子供が科学に魅了されることは、おそくら無理だろう。」という部分です。なぜかというのが、どこにも詳しく書いてないように思うのですが、本当だったらさびしいですね。私の息子にも、いろいろなことに好奇心を持ってもらいたいです。
0投稿日: 2014.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ同じ理系にいた人間として、共感できる部分がとても多いなと感じる作家です。 今回も、自分ではうまく言葉にできないことをうまく表現してくれていると感じる部分もあって、読後感はよい。 ただ、この長さが必要かというとそうでもない。 もっと、短く端的にできる気がいたしました。
0投稿日: 2014.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の目的については著者が明確に記載しているので理解できたが、ではその目的を果たしているのかどうか、ということには少し疑問。非科学的なものを鵜呑みにしてしまうことの危うさは充分理解できるけれど、では科学的とは、という命題に対しては答えきれていないのではないか、と感じた。勿論、書いてあることは正しいと思うのだが、人が何故非科学的なものに惹かれていくのかということへの考察がもう少し必要なのではないかと思う。例えば、あの某宗教団体へ何故理系人間が多く参画してしまったのか、等々。この辺への言及があれば説得力があがると思うのだが。
1投稿日: 2014.02.16ものの考え方
情報が多々ある現代、流されないためこういう考え方を身につけておくのは大切だなと思った。 タイトルで取っ付き辛いかもですが、思ったより読みやすいです。
3投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ学会で,理論と実践や研究のあり方が議論となり,その直後にお勧めがあって手に取った。 「誰かが考えたことを大勢で吟味し,そしてその効用を共有する仕組みが,科学の基本である。(p.91)」 「まず,科学というのは『方法』である。そして,その方法とは,『他者によって再現できる』ことを条件として,組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには,数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また,再現の一つの方法として実験がある。ただ,数や実験があるから科学というわけではない。 個人ではなく,みんなで築き上げていく,その方法ことが科学そのものといって良い。(p.107)」 人を対象として研究する場合(教育,言語習得),難しいと思いつつ,この基本については忘れてはならないな,と。
1投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次 第1章 何故、科学から逃げようとするのか(いつから避けるようになったのか 向いていないと思い込む ほか) 第2章 科学的というのはどういう方法か(科学と非科学 非科学的な習慣 ほか) 第3章 科学的であるにはどうすれば良いのか(「割り切り」という単純化 科学は常に安全を求める ほか) 第4章 科学とともにあるという認識の大切さ(ごく普通に接すれば良い 数字にもう少し目を留めてみよう ほか) 本の内容 科学—誰もが知る言葉だが、それが何かを明確に答えられる人は少ない。しばしば「自然の猛威の前で人間は無力だ」という。これは油断への訓誡としては正しい。しかし自然の猛威から生命を守ることは可能だし、それができるのは科学や技術しかない。また「発展しすぎた科学が環境を破壊し、人間は真の幸せを見失った」ともいう。だが環境破壊の原因は科学でなく経済である。俗説や占い、オカルトなど非科学が横行し、理数離れが進む中、もはや科学は好き嫌いでは語れない。個人レベルの「身を守る力」としての科学的な知識や考え方と何か—。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ前に本屋で見かけて気になっていたものの、そのときは買わず。最近になって購入。 工学博士たる著者が『科学的』とはどういう状態を表すのか、科学的に考える思考力は発想力がないと、どのような問題が発生するのか、といったことを書いたもの。 僕自身も、工学修士を持っているので、科学的という考え方はそれなりに持っていると思っている。『科学的』ってのは一言で言うと『再現性があるかどうか』ということにつきる。 もう少し言うと、同じ条件下で誰が行っても同じ結果が得られるかどうか、というところがポイントで、それを満たさない限り科学的ではない、という判断になると考えている。 おおよそ、著者とは同じような考えだったな、と思う。まあ当たり前の話と言えばそうだ。理系学部で勉強をした人間にしてみれば、知らなきゃおかしいレベルだよなぁ、と思う。 そういう意味で、本書ではそれほど目新しい話があったわけじゃない。だけど改めて自分の日々の考えを見直すのには、とても有用だったと思う。 そもそも、文系と理系、と区別すること自体が、(著者も近しいことを書いているが)ナンセンスだと僕は思っている。人は誰も文系的な要素と理系的な要素を持っていて、どちらかと言うと強いほうがある「かもしれない」けど、おおよそは変わらなくて、どっちの勉強をしたか、どっちに興味を持ったか、というだけでしかないと思ってんだよね。 だから世の中の文系理系議論には、僕は興味ないし、どーでもいいじゃん、と思う。そんな所で自分自身を貶めなくてもいいよね、とも思うし。苦手、と思った時点で苦手になるからねぇ。 秀逸だったのは、最初の方に書かれていた以下の文章。 「文系には、数学や物理から逃避するという特徴(あるいは傾向)があるけれど、理系にはそういった特徴は顕著ではない。理系の人間は、特に国語や社会から逃避しているわけではない。ここを、文系の多くはたぶん誤解しているだろう」 これはそうだと思う。というか、サンプルが殆ど無いのであくまで僕自身のことで考えざるを得ないが、僕はまさにそうだった。正確には、国語も社会も得意だった。地理や漢字みたいに「覚えるしかない」ものは苦手だったけど、読解問題であるとか、個人的に好きだった歴史などは全然得意だった。そんなもんである。 それを文系(と自分を定義している)の人たちは、「お前らは文系学科が苦手、俺達は理系学科が苦手、おあいこでしょ」と平気でおっしゃいますが、じゃああなた方は理系と言われている人たちが理解している物理程度に古文を理解しているのでしょうかね、と質問もしたくなる。 おっと、話がそれてしまった。 ともあれ、本書は『文系と理系』と分けることの無意味さ、科学的に考えることの重要性、科学的に考える方法論、といったことがわかりやすく親切に書かれている。科学が苦手だ、数字は難しい、なんて考えている人は、ぜひ手にとって読んでみるべきだと思う。 と書いたが、そういう人はまず間違いなくタイトルで敬遠するんだよな。。もったいない。。
0投稿日: 2013.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「文系」を自認する人に。数字や論理に基づく説明を敬遠し,結論だけを求めることの不利を説く。こんこんと。さすが小説家だけあってさらさら読める。独特の外来語表記にはちょっと違和感も。
0投稿日: 2013.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログすごくしっくりときた。日常的に感じる「なんか違うなー」が形になったような感じ。 私自身、科学的な感覚の一番肝要な部分は、大学でそれなりの訓練を受けて身につけたという経緯があるから、これを読んで、その感覚がない人がどこまでついてこられるかは若干疑問。
0投稿日: 2013.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【動機】森博嗣なので。 【内容】「観測された数字を自分で解釈すること」や「詩的・包括的な言葉で思考停止せずに原理を問いつづけること」で落ち着いて判断することの重要性を説いている。 【感想】ちゃんと考えることは、めんどくささと向き合うつらさを負う一方で、好奇心をじゃましないという前向きな面も見出せることに気づいた。
0投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ***** 題名の通りの内容。 人生の中で一度でも「科学とは何か」を考える機会を持てたことをとても嬉しく思った。先生に感謝。 ***** 数字に向き合うスタンスを考える上でもとても示唆に富んでいる。 人は難しいことはなるべく考えたくない生き物である。 ファスト&スローで言っていたシステム2(合理的な思考)は怠惰で怠け癖があるので考えることは避けるし、システム1(直感的な思考)は手元にある情報から最も確からしいものをばさっとつかむ。いずれにせよ、相当に意識しない限りは目の前のことに対して熟考するような「めんどくさいこと」はしない。 *****
0投稿日: 2013.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語を調べると文系は Humanities、理系は Science なのか。学問分野としてはもちろん別だが、それを学ぶ人にとって二律背反ではないはず。この本での描き方だと、ともすれば「理系はエリート、文系はバカ」みたいなステレオタイプな思い込みを増長させやしないか。日本人はただでさえカテゴライズ化が大好きだ。昭和生まれ平成生まれ・血液型・長男次男・関東関西…。年代・地域・個人特性についてどこの国でも多かれ少なかれそんな遊び(?)はあるだろうが、少なくとも自分は文系だ理系だと主張しあうのは日本だけじゃないのかな。 (続きはブログで)http://syousanokioku.at.webry.info/201212/article_17.html
0投稿日: 2012.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学や数学とか、もちろん他のものにたいしても安直な思考停止はよくないなと、思う。 そして協調することがよいとはいけませんよ、といつものことが書かれている。 頭のなかのことをそのまま文字にしたような本。わかりやすくてよかった。 科学的に考えようとは言わないけれど、科学的に考えないと損をする、だってさ。
0投稿日: 2012.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ選挙前のこのタイミングで読んだのが最適だったような気がする書籍。 工学博士にして小説家、エッセイストである森博嗣さんが、東日本大震災の直後に、「科学的に思考しなければ損をする」という視点で、科学から自ら離れてしまっている一般人のために記した一冊です。 非常に分かりやすく書かれてありますが、科学を絶賛するというものではありません。自身自身が科学的に考えて行動するためのきっかけにできるのではないかと思います。 "カリスマ的な指導者の発言が国民を動かしたりするようなことは、科学にはない。また、科学は、一部の特権階級にだけ、その恩恵をもたらすものでもない。科学は、経済のように暴走しないし、利益追求にも走らない。自然環境を破壊しているのは、科学ではなく、経済ではないのか。" という言葉が私が今感じている気持ち悪さの説明として一番腑に落ちます。 政治家が作ったマニフェストや公約集、経済学者が記した著作、TVや新聞の解説を読む前に、まずこの一冊を読んで普段の生活から「理由もなく直感的な印象だけで判断しない」ようにしたいものです。
0投稿日: 2012.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学を好きになって欲しい、ではなく、科学的に思考しなければ損をする、という点から書かれている。科学が宗教・呪文になっている、という指摘。個人的には、科学は結果ではなく、コミュニケーションで作り上げていくプロセス、というのが興味深かった。
0投稿日: 2012.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
天文学者と物理学者と数学者の3人が、スコットランドで鉄道に乗っていた。すると、窓から草原にいる1匹の黒い羊が見えた。 天文学者がこう呟く。「スコットランドの羊は黒いのか」 それを聞いて、物理学者が言った。「スコットランドには、少なくても1匹の黒い羊がいる」 すると、数学者がこう言った。「スコットランドには、少なくとも羊がいて、その羊は少なくとも片面は黒い」 僕なら、ここに、子供を1人登場させ、最後にこう言わせたいところだ。 子供「あれは本当に羊なの?」 人間は単純化を無意識に好むものであり、概念に名前をつけ、言葉によって理解したつもりになる。 つるかめ算という名前を知っていることで、オームの法則という名前を覚えたことで、それが理解できたと思い込んでしまえる。 つまり、「神」という言葉を信じれば、人間のこと、社会のこと、自然のことを理解したつもりになれる。 少し変な例を挙げてみよう。 駐車場の9番に車を駐めたら係員が駆けつけてきて、「そこに駐めちゃ駄目だ!」と怒られた。どうしてかと尋ねると、「車はキュウにとまれない」と答える。そのジョークはわかる。だから、笑っていると、「とにかくすぐに車を退けてくれ」と要求された。貴方はどう思うだろう? 腹が立たないだろうか?駄洒落という「言葉遊び」と、現実のルールを混同してはいけない、という常識的な理屈がたぶん貴方にあるはずだ。面白さは認めるが、やはり「理不尽だな」と感じるのではないか。 けれども、神を信じ、神に支配されていた時代には、これと同レベルのことが罷り通っていた。現代の日本でも、「縁起が悪い」といって大勢が反対するようなものがある。 自分だけのことならば勝手であるけれど、ときどき摩擦が起こるだろう。
0投稿日: 2012.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ工学博士で小説家の著者が「科学的とはどうい意味か」に答える本 文系への偏見や非合理的な物事の意味を軽んじている部分は多少あったけど、「科学的」であることはどういうことがは分かりやすく説明されていたと思う 以下抜粋 「学科で教わることは…『データ(情報)』と『メソッド(方法)』だ」(p35) 「『10メートルの津波が来る」という情報がもたらされたとき、…今自分がいる場所と、自分の体力と、周囲の状況から、『自分にとって危険か安全か』を判断すること…それが『科学』なのである」(p45) 「マスコミが…真の情報を伝えない理由は、大衆が…ドラマ(物語)を求めているからにほかならない。どうして、そういったものを求めるのかというと、それは、自分では考えたくないからだ」(p56) 「科学とは『誰にでも再現ができるもの』である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが『科学的』という意味だ」(p71) 「どうして人間は、その『再現性のある科学』というものを発展させてきたのだろう。それは、再現される事象を見極めれば、これから起こること、つまり未来が予測できるからだ」(p84) 「数というのは『順番』という上限関係だけでなく、『量』というものを示す性質を持っている」(p93) 「科学というのは『方法』である。そして、その方法とは、『他者によって再現できる』ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある」(p107) 「『新幹線が速いのは何故か』という問いに対して、『ひかり号だからでしょう』というのが、単純化による言葉だけの理解である」(p132)
0投稿日: 2012.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリやスカイ・クロラを書いた人という認識だったけど、工学博士。こっちの科学本のほうが本職に近い。 科学者だけど、科学嫌いの文系人間の心理をよくわかっていらっしゃるw かなりわかりやすく的確に、普通の人(非理系)が科学にどう対処すべきかを書いた本。 なぜか2012年度高校入試で森博嗣は大人気で、この本以外に「自分探し…」や「自由をつくる…」からも引用あり。森さんは試験問題としての引用をどう思ってるんだろ……気になる。
0投稿日: 2012.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学について、科学に興味のあるない関係なしにすべての人に向けて書かれている。 少し深く考える、疑問を持つだけで変わるところは多い。 科学の嫌いな人(主に文系)に伝えていきたい内容である。
0投稿日: 2012.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ森博嗣の本はたくさんあるけど、初の新書。 理系を敬遠することがどれだけ自分のマイナスになるのか、というテーマから、氏の独特の口調で社会問題へ切り込んでいく。 人は楽をしたい。 だから結果だけを求めて、感情や感想までも相手に求めてしまう。 自分の思考を停止してしまう。 少しだけ考えてみる。 自分の中に量的な基準を持つ。 イメージする。 これだけで社会をうまく乗りこなせる。 少しだけ村上龍と通じることがある。 要するに日本人はバカで、未来はかなり絶望的でもっとしっかりしろ!ということ。
0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ"科学的"と言う言葉をキーに、著者の持論が展開されている。文系・理系の分類など、世間的に理系と言われる側から見た意見には、肯くばかり。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ『科学とは、民主的にみんなで確認をするシステム、つまり、他者と共有できることが基本となる』 タイトルにあるように、『科学的』とは何を意味するのかということを、色眼鏡をかけずにかつわかりやすく語りかけてくれる。
0投稿日: 2012.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「数学が得意であること」と「数字で量を見積もれること」と「科学的であること」というのは少し違うことであるような気もしてわたしにはちょっと理解しにくい本でした。数学のもう一つの面である「論理整合性」をあまり考えていなくて、「文系」だから「数学が苦手」という話で進めてしまったのはちょっともやもやします。理系の私からすると最も「文系」的な分野の一つである「法学」こそが数学との親和性が高いと感じているのでちょっと残念な本でした。
1投稿日: 2012.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本のタイトルで損しているな感じました。この本で語られていることはタイトルよりも深いです。(著者がタイトルに悩んだことを書いていましたが) 以下の内容が強く印象に残りました。 ⑴科目で学ぶことは「データ(情報)」、「メソッド(方法)」の2種類。数学や物理は主にメソッド中心。 ⑵科学を敬遠するのは、自分で考えること、感じることが面倒でしたくないからである。
0投稿日: 2012.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
”科学の存在理由、科学の目標とは、人間の幸せである。” ということを前提に、”科学的”といっているのは、どういう意味でいっているのかという、見方について、書かれた本.”理系”、”文系”にこだわっている人は一度読むとよいかもしれない.
0投稿日: 2012.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半はかなり納得。 「科学」という言葉にほとんどの人が拒否反応をしていると思う。 ただ普通になぜ?どうして?を気にして、理解するだけなのに。と思ってしまうのは、私が理系だからなのでしようか。 後半に関しては、超能力や占いを完全否定しているように感じ、科学が一番大事であり、超能力やういの基である「精神」や「心理」は不要というふうに受けとりました。(一応、両方大事とは記載されてますが、個人的に受けとりました) 科学が社会や経済に間違った使われ方をしているのに似て、「精神」や「心理」といった分野を異なった使い方をしているだけでは。(使い方が間違っているかどうかはおいといて)
0投稿日: 2012.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこれだけ科学技術が発展した現代において、科学離れ(科学的無知、無関心)が顕著になっている。 特に文系と称される人々は、数学が苦手だからといった些細なことで自ら考えることを放棄している。 科学とは、自ら理性的に考えることであり、また現代に生きるには必要不可欠なものである。 是非とも自称文系の人々にこの本を読んでもらいたい。 僕自身文系学部に属しているが、自分はより理系的な人間だと自負しているし、数学等を切り捨てて文系に進んだ人を哀れに思ったりもする。 そんな視点からこの本を読ませていだだくと、すごく納得できました。 しかし、こういうタイトルの本を手に取らないのもまた文系人間の特徴だとも思う。 森さんは理系、文系と二つに分類すること自体に否定的であるようですがねw 現代日本はお上(特にマスコミ)の言うがままに生きる人が多いように思う。 常に正しく必要なことだけが報道されていると思い込み、自ら考えることを放棄している。 その方が楽だし、他人との協調性も取れるのだろうけど、果たしてそれが正しいことなのだろうか? そもそも何が正しいなんていう普遍的な心理は存在しない、ならば自分が思うように、ある意味自己中心的に生きることが人生において大事なのでは無いだろうか。 もちろん社会で生きていく上で自己中心的であってはまずいが、だからと言ってイエスマンよろしく何でもかんでも鵜呑みにして従うのは間違っている。 我思う故に我ありとは良く言ったもので、考えることこそが人生だと思う。 理性的に考えることを放棄した時点で、人生をやめたに等しいといっても過言ではない。 思考しない人生はそういうのが得意な機械に任せておけばいい。僕は人間らしく生きる。
1投稿日: 2012.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学を理解していてかつ表現力も傑出している こういう本が増えれば擬似科学も減っていくのではないかと思う
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的であるとはどういうことか(第三者によって再現できる、数字で測定できる、など)、科学的な思考をすると(しなかったときと比べて)どのようなメリットがあるのか、科学的な思考を生活の中でどのように役立てればいいのか、などなど。 それなりに面白かったです。 想定読者は科学にアレルギのある文系なんだろうけど、そういうひとはそもそもこの本を読まないんじゃないかという噂。
0投稿日: 2012.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「科学を無闇矢鱈に否定して目を背けるのは、あなたにとって不利益ですよ」というのが一番言いたいことだそうだ。すごく良く解る。 でもこの本では、いわゆる「文系」が「理系」科目に対して反発することが多い、という内容が扱われていたけれど、逆も然りだよね。理系は文系科目に対してそう苦手意識を持っている訳ではない、と書いてあったけれど、少なくともわたしの身の回りではそうではないな。 理系というか、研究もそんなに力を入れてやる訳でもない薬系だからそう感じるのかも?必要ないから英語はやらない、本も読まない、歴史なんて興味ない、というひとがすごーく多いように感じるんだよなあ。それってとても勿体ない。 まあ結論を言うと、自分にこれは必要ないとか、こんなものは信じられないって妄信的に切り捨ててしまうのではなく、自分が生きて行く上で何が必要になるのか、何がプラスになるのかを冷静に、自分だけの物差しで計るべきっていう、ごく単純なことになってしまうのだろうけど。
0投稿日: 2012.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 科学の考え方について、大きく賛同。 言葉だけでは何も解決できない。事実に基づき行動を起こす。
0投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「科学的」とは?と問われると、返事に困ってしまいます。分かっているようで、実は全く分かっていない。森さんの思考をトレースしてみようと思います。
0投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学から逃げて文系に走った自分としてはほんとにイタイ内容。大学に入ってから一般教養の理系科目の面白さを知り、就職氷河期の洗礼を受けて安易な文系選択をすこーし後悔した。数学イコール科学ではないのに。 「科学から目を背けることは、あなた自身にとって不利益ですよ」これにつきますね。。 放射能汚染の問題も、「難しいことわからないから結果だけ教えて。何ベクレルが危ないの?」なんて受身では社会が損をする。 原発事故直後に元素や単位や、なんやかんやを勉強し、「なんで一般市民がこんなことに詳しくならなくいちゃいけないの、こんな世の中ヘン」と思っていたけど、それこそが大間違いだったんだなあ。
0投稿日: 2012.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的とはどういうことなのか。 森博嗣さんの小説を読んでいても感じたことだが、自分とは明らかに違う気がする。それは考え方であったり、感じ方、表現方法など、たとえ同じ風景や物体を見ていてもおそらく違うことを思っているのだろうと思う。だから面白い。だからもっと読みたくなる。 この本の中で、科学や理系という言葉だけで目を瞑ってしまう人は不利益を被ることになるという旨が書いてあるが、これは科学に限ったことではないと思う。 ある要素が絡んだだけで頭ごなしに理解できないモノとし、他人に聞きもしなければ、自分で調べようともしない。こういうことをしていると、結局は自分の不利益に繋がってしまうのだろうなと思う。
0投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
偶然図書室で発見したので読みました。小説を大して読んでないくせに名前だけ知ってる森博嗣に惹かれただけなんですけど、これがまた面白いことばかり書いてあります。 文系とは何か、理系とは何か、という話題を中心に広がっていく考え方には同意するところが多々あります。御身文系というレッテルを自分で貼り付けた身なのでこういった文理の差別化の所以たるものがなんであるか、という旨の文章は非常に興味をそそられる。 わたくし個人としてはもっと昔に読んでおけばな、と思いましたが、出版が最近の著書のようでしたので、時期的には今であっても差し支えない、これから考えていけばいい、と思えるような内容だとも感じました。 読了してみて、文理二分するのは自分にも、またそうされる人間にもあまり聞こえのいいものではないということに今さらながら気付かされました。 そうやって区分して「自分は関係ないし、難しいから」というのは単なる逃げであったことを痛烈に思い知らされたのはかえってよかったと思いました。さりげない文章でそういう私の心理をつついてくる何か不思議な力を感じました。
0投稿日: 2012.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学とは「誰にでも再現ができるもの」である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが、「科学的」という意味だ。 と、本書にあるように再現がキーワードである。また自分の考えを、相手の頭の中で再現できるよう伝えることが、科学的に伝えることになるのだろう。 いかにして科学的に伝えられるか。そのことを考えながら、日々の生活をおくっていきたいと思う。
0投稿日: 2012.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログとてもわかりやすかった! 今まで幾度となく、自分に理系の頭があったならこっちの分野に進みたかった…と思うことがあった 昔につまずいてしまってからは、文盲や色盲があるように 自分は数盲なのだ!とレッテルを貼ってしまったからだ またそうしないと、自分のプライドや心が守れなかった(現に受験ノイローゼ気味だった時は、数学の問題が解けなくて泣きさえした…) そんな風に悪い方に割り切って拒絶してしまうことの 生きていく上での損失を、本書は説いている 理系の呪文のような用語の数々を見て イーッ!!とはなるものの まだ自分にはその分野に対する興味までは失われていないと、本書を読んで再認識する いつだってわかりあいたいと、 思っているんだ… ちょっとずつ、時間はかかってもいいからちょっとずつ 気になる気持ちを大切に 最低でも自分が今生きている世界についてくらいは 理解していたいと、思った
0投稿日: 2012.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、ずっと私が感じていた「サイエンスコミュニケーション」への違和感がようやく分かった。 サイエンスカフェなどにおいて「科学はすばらしい」「科学は楽しい」と謳うのは、個人(主催者側)の感想であって、この世の中を生きていくのに科学が本当に必要なものなのかを示すものではなかった。 「科学的な知識や考え方を身につけること」は、科学技術であふれた今の世界を何者かに騙されることなく生きていくために、必要なのだ。 とても読みやすいので、一読おすすめ。
0投稿日: 2012.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学が苦手となる経過や数学と他の教科との違い、も語られている。 科学的とは誰にでも再現できること、という事柄を知っておくことは有益。
0投稿日: 2012.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識量に価値があるのではない。名称をたくさん覚えている事に価値はあまりない。知識というものは知っているものは知っている、知らないものは知らないというだけの話である。一方、方法を習得したものは、同種の他のレベルの問題まで任せる事ができる。子どもの時に自分は文系と定義する事は、言葉だけの知識を理解だと勘違いしている事に等しい。学科で教わる事は大別すればデータ(情報)とメソッド(方法)に分けられる。科学とは方法であり、他者によって再現可能な事を条件に組み上げていくシステムである。
0投稿日: 2012.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログもちろん、すべては『F』から始まったのだけれど、私はもしかしたら、彼の非小説の方が好きなのかもしれない。 1995年から2001年までの日記に見られたようなエッジィさは、少しなりを潜めたような気がする。それはもちろん、いなくなったわけではなくて、他の方法をもって表面に現れているからだろうけれど、そうやって、絶えず、変化していくことを良しとする彼の姿は、尊敬に値する。 言葉でしかできないことがあって、言葉でもできないことがある。ふわふわと目に見えず、変化し続ける、人間の精神を言葉で表すのは、本当に難しい。だからこそのディスカッションだとは思うけれど、その単語の定義すらもややこしい。 私は、森博嗣という人間が好きすぎて、冷静に彼をみられない。そういう私の精神状態であるからして、万人に等しくこういった効果が得られるとは思わないけれど、彼の非小説は、かなりの確率で、涙する。今回も、ふと気を緩めていると、ぐさりと涙腺を攻撃された。最早、何故涙しているのかも分からない涙。 分からない理由などはおいておいて、「考える」という意味をもう一度考えさせてくれる本だと思う。それはつまり、「自分」の定義を今一度、「自分に」問い直すことだと思うし、はりぼてでない「明日」を見つめ直すきっかけになると思う。
0投稿日: 2012.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中に大勢いる「科学嫌い」の人達に警鐘を鳴らす本。日頃から「理屈はいいから結論だけ教えて」「説明は3分以内で」などと言われることを不思議&不快に思っている私にとって、正に自分の気持ちにぴったりの事が書かれていると、深く共感できる内容である。 『科学は「好き嫌い」ではなく、「身を守る力」として、その知識や考え方を身に付けるべきものである。人を幸せにするのは科学の力である。』同感!
0投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学とは「方法」である。そしてその方法とは「他者によって再現できる」事を条件として組み上げていくシステムのことである。 自分がこれを読むまでは、他者によって再現できるということまでは理解できていた。なので実験してその結果を数値で説明できれば科学的だと思っていたので、多くの勘違いしている一人だったということだろう。 また正しいかを疑う精神はSEと仕事をしているにである程度慣れているが、こうやって文章で読むと非常にめんどくさい。と感じてしまう。
0投稿日: 2012.01.09
