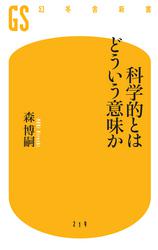
総合評価
(197件)| 35 | ||
| 68 | ||
| 51 | ||
| 10 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系の方が暗記メインとかいうのは受験の弊害であって、本来、例えば歴史ならその時に起こった出来事を豊かに想像したり紐解いていくのが学ぶってことではないんでしょうかね? それと、最近思考停止するなっていう本多いけど、そういう人は本読まなそうだったり… と、そんなことを考えさせる本。
0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ記憶系文系がこれ読んだらどんな反応するんだろうか? 非記憶系理系が読んでも新鮮味はあんましないので★★★。 日本の報道に対する意見には激しく同意する。 こないだのNHKのJobsの番組に対する違和感は、 文章にするとこういうことなんだろうな~ とこの本読んで納得した。
0投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家である著者が理系および科学への世間の無理解と無関心を嘆き,啓蒙を目指した本とでも言えば良いだろうか.全編にこの無理解,無関心へのいらつきが出ている.私も同じように感じることはあるが,著者の言葉はより直接的で,私からすれば,刺激的,過激である.普通の科学者がこの題名で本を書いても全く売れない(買うのは科学に関心のある人だけ)が,著者が書けばある程度売れて,メッセージが伝わる部分があると考えれば本書の意義は十分ある. しかし,科学の意味の考察は一般的なレベルにとどまっていて,目新しさはほとんどないし,科学の限界についても無視しているのが私には物足りない.科学について書く人が宗教を科学の対立物とみることも私は気に入らないが,本書もこれをやっている. ブログを通じて考えてきたこととは言っても,多忙な人が三日間で書いたものには限界があるということだろう.
0投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログいつも通り。 特に新しい主張はないけれど、今まで森博嗣の本を読んだ事のない人にとっては読みやすい。
0投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には、文系理系という分類の仕方は好きじゃない。筆者は文系の人はこう考える。とかいう書き方をしているが、いわゆる文系の世界に生きている人たちの中にも科学的な思考をできる人はたくさんいる。ここまでは本書の内容とは関係ない。 科学的とは数や実験を利用した再現ができること、個人ではなくみんなで築き上げて行くもの。科学的であるには、思い込みを捨て、常に疑問を持ち続ける必要がある。科学の目標とは人間の幸福である。 しかし、科学の目標とは、真理を求めることではないかと思う。そして真理を求める事は人間の性だ。
0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉で説明出来る結論だけを求めるのではなく、基づくデータや過程を繰り返し検証する考えて方を今一度見直さなければならない。 結論だけを求める考え方の危険性を考えさせられた。 科学的=他者による再現性 つまり、同じ条件下でいつでも誰にでも再現出来る現象が科学現象。
1投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学――誰もが知る言葉だが、それが何かを明確に答えられる人は少ない。しばしば「自然の猛威の前で人間は無力だ」という。これは油断への訓誡としては正しい。しかし自然の猛威から生命を守ることは可能だし、それができるのは科学や技術しかない。また「発展しすぎた科学が環境を破壊し、人間は真の幸せを見失った」ともいう。だが環境破壊の原因は科学でなく経済である。俗説や占い、オカルトなど非科学が横行し、理数離れが進む中、もはや科学は好き嫌いでは語れない。個人レベルの「身を守る力」としての科学的な知識や考え方と何か――。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ飲み屋で語っていたら、結構共感できたような気がします。特に「教育と科学」については、気にしている点のひとつでもあります。 ただ、本という形ではなく、ブログのようなメディアで読みたかったように思います。個人的には、「科学的の意味」について、体系づけられ、完結したように感じられなかったのでしょうか。 また、放射能の話と結びつけた議論については、私個人的には受け止める方に迷いました。自分の身を守る・未来を作るために知っていなければならないことは、政治・経済・法律といういわゆる文系と呼ばれる分野においても重要と思います。
0投稿日: 2011.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学とは、誰にでも再現できるものだ。 なるへそ。宗教じみたことで科学や数学を毛嫌いしている人に言いたいんだろう。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書は読むまでは興味を引かれても、読んでみると堂々巡りの著者の自説に辟易することが多く、結局なんだかよくわからない…で残念ながら私には何の教養にもならないことが多いんだけど、これはもう、全編通じて平伏!自戒の意味も込めて御守りにしなきゃ。 のっけから身につまされる。 苦手が高じて自らを文系だと決めつけ、理系をわからないもんだと避けてきた…そうですとも! 数字を量でイメージできません。 難しいことはわからないので結論だけお願いします。 …でもこれじゃあいけない。はっと気づかされた。 そしてこんな私にもわかりやすい親切な本。最高
0投稿日: 2011.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ震災後、最初に書かれた森博嗣の著書。 記憶型学習への批判を基礎部分に置きながら、それによって生じる「科学的な理解を忌避する態度」が、現代生活での危険をもたらすことを指摘している。 「科学的な理解を忌避する態度」とは、プロセスを把握せずに、結果だけを知ろうとすることだ。 本文中でも、東日本大震災における原発事故において、○ベクレル、○シーベルトと数値が公表されているにも関わらず、その数字の意味するところを調べずに「安全かどうかだけを知りたい」という人が多くいた点を指摘している。 例えば、高さが○メートルと示されれば、落ちても安全かどうか、命に関わるかどうかは個人で判断できる。 むしろ「○メートルから落ちると命に関わる」なんていう明確なラインは存在せず、個人の状況によると言っても良い。 例えば、頭から落ちるのか脚から落ちるのか、落下地点は硬いか柔らかいか、体重は何kgか、既にどこか怪我しているのか、などといった要因だ。 なぜそういった複雑な要因があるにも関わらず個人で判断できるかというと、これまでの落下した体験から衝撃を予想できるからだ。 一方、放射線被曝のように普段体験していない(正確には、体験しているが気にしていなかった)ことは、体験からは類推できない。 そこで、自分以外の人が体験したり調査したことの積み重ねから、確からしいと認められている情報=科学的情報から類推することになる。 つまり、科学とは全人類の体験の共有および一般化でもある。 一般化とは、誰でもできるということだ。 情報の多くは本やネットに書かれているので誰でも調べられる。 しかし、科学を忌避すると、そもそも調べようとしないので、こういった類推が出来ない。 そこで、誰かが判断してくれるのを待つしかなくなる。 しかし誰かから「安全ですよ」と言われても、それが正しいとは限らないことは明白だ。 なぜなら「利害」という科学的でない要因が介入するからだ。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し極端な表現も感じますが、誰かの感想を鵜呑みにする怖さが伝?わってきます。 「的確に定量的に状況を把握・理解すること」、「疑いを?持つこと」、「そのための手間を惜しまないこと」を大事にしないといけません。 ?しかしながら、本書でいうところの「文系」の人、周囲に結構多い?ような気がしますね。
0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小説家の森博嗣の新書。実はエンジニアリングの研究者。 ・再現可能性があり、みんなで民主的に検証ができるモノを科学的なものという。 ・科学的であるもの(たとえば数学・数字)の食わず嫌いは損するからやめよう。 ・科学的であろうという気持ちくらいはもっておこう。 という至極あたりまえ(なはず)の内容も、一部の文系人は発狂しかねないくらいちょっと攻撃的すぎる気も。。。。
0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系vs理系というような話は私にとって大事(というか好き)なテーマで、横浜大阪間の新幹線で一気読み。 文系出身でありながら就活のときに「SEもいいかも」と思った瞬間に考えたことのひとつに、これだけITの恩恵を身近に受けながら暮らしているのにその仕組みに対して「私知らない」って態度でい続けていいのか?と感じたことがある。それって私の「知的好奇心」的なものなのかなと思っていたけど、森さんのいう「思考停止」への危機感だったのだとしたら、私賢い(笑) 森博嗣は犀川&萌絵シリーズしか読んだことがないのだけど、科学を語る本文を読んでいると犀川先生が話しているかのような錯覚があって、犀川先生好きとしても楽しい。 理系人間は文系人間ほどもう片方の分野へのコンプレックスを持っていないというのが、目からうろこ。 これから少しずつ数字と仲良くなろうと思いました。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕は科学的ではない表現が結構嫌いです。残念ながら身の回りにはそういう表現がたくさんあります。そういうことにズバズバと文句をつける。まさに我が意を得たり、という本でした。 文系理系という分け方はともかくとして、自分のわからないことを、プライドのために「〇〇系はこれだから…」みたいな逃げを打ってはならないと。 一方で、「覚える」と「理解する」の違い、などは身につまされる思いでした。 中身は難しくないので、科学アレルギーの人も、「事実とは何なのか」と読みかえて読んでみることをお勧めします。
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ数式を見ただけで思考停止する、スルーする。私も中学の時に数学に躓いて以来、苦手=向いてないとなった。本当、著者のいうとおり。でも、理系の道を閉ざして困るのは自分。大人になってから統計や経済の本を読んでも、数字や計算が頭に入ってこない。そのページを読み飛ばすし、金融関係のはなしもさっぱり理解しきれない。社会に出てから、あらゆるところで数学がやくにたつ。それは数式ではなく、暗記でもなく、数学で使った考え方。 子どもの頃に挫折して理系の道を閉ざし、「自分は理系は苦手」と思い込んで理系科目を避け、消極的文系人間になってしまった人はとても多いと思う…。
0投稿日: 2011.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的な思考は現代社会においては必須な能力。 学ぶということの中にはデータとして蓄積するものとメソッドとして理解することがある。 英語や国語のわからないはそのことを『知らない』という事実。 科学のわからないはどうやればいいか『わからない』ということ。 わからない、理解できないと切り捨ててしまうことで自ら情報を遮断している。 これは科学嫌いの人だけにあてはまることではないと思う。 震災に関しての内容も織り交ぜているのでわかりやすい内容だと思う。 本書は科学嫌いの人に向けて書かれたものだそう。 『運勢って、何なの?』ってかいてあったのは笑った。
0投稿日: 2011.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的というか非科学的なことはどれだけ曖昧模糊として危険であるかが書かれている。 科学数学嫌いな自称文系人にこそある本。かくいう自分も学生時代は数字を遠ざけてきた人なので、ギクッとする箇所は少なくない。 TVのコメンテーターの的外れな受け答えだとか、アナウンサーの大きなお世話的な指摘には、自分も憤ることがあるので大いに納得。 科学的とは論理的なこと。 難しいことではなく、むしろシンプル簡単なことを言っているのだが、なかなかに実践している人はいないのではなかろうか。 森博嗣という人は自分の目で世界を観ている人だ。誰もがこの視線で物事を捉えられるわけでは決してないが、だからこそ言っていることもまた決して間違ってはいない。近年出版した本では同じことが繰り返し述べられていると思う。すなわち一貫した意見があるということだ。
0投稿日: 2011.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んで、これからは考え方を変えていってみようと思った。 文系/理系との区別はどのようなものか 『文系』の傾向……… 私自身は文系だが、この本の中には『確かに』というように思い当たることが多々あった。 特に、『結論のみ聞きたがる』。これは大いに思い当たった。 これからは自ら『損』をする道をわざわざ選ぶことがないように、『過程』もしっかり見ていきたいと、考えさせられた作品だった。
0投稿日: 2011.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ皆さんの素直なキモチを聞いてみたい! 自分で言うのもなんだが、これまですべての本に対して、真剣にレビューを書いてきたつもりである。しかしこの本に限っては、自分の想いをそのまま綴ってしまうと、「誹謗中傷」と判断されかねないので止めておく。規約を守って楽しむ、これがブックアサヒコムでのルールだからだ。 この本はかなりの売れ行きだと聞く。私もそれゆえ期待して読んでみたのだが、「まえがき」から「あとがき」まで、開いてしまった口が塞がることは無かった。科学の重要性や非科学の危険性、理系を異端者扱いする文系など、独特の切り口については別に構わない。だが、これは本なのだから文章を丁寧に書いて欲しい。ただそれだけだ。 最後に、「宗教の能動的布教活動は非科学の布教」というような、あとがきの記載に関連して一言。この本の売れ行きの良さは、著者のあまりに偏った主観と軽率すぎる偏見の反復記述が、一部の読者を啓蒙していることによるものではないかと思われる。一方で、メフィスト賞のような「面白ければ何でもあり」が、如何なる本でも罷り通るとは思いたくない。
0投稿日: 2011.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログBOOK TV「科学入門書特集」にて、企画のきっかけになった本だと紹介されていたので。 科学を毛嫌いする文系に対して、「科学的」な生活を提案。 文系の中で異端なポジションだったであろう自分が、高校時代から感じていたモヤモヤした何かが、確かに存在したんだと、思わせてくれた。 数学に代表される科学から逃避は、方法・思考の運用からの逃避である。 文系が行う「暗記」と言う学習方法は、知識の蓄積と同時に思考の停止、さらには解法の省略・正解の共有、感情的な判断・信じこみを招く危険があるという。 数学は社会で役に立たないと言われるが、それは「微分積分が」であり、「方法を学び運用する」と言う学習方法は、それはそれは役に立つのだそうだ。 科学分野における、現象を冷静に分析する姿勢、客観的な他者の意見への評価を、ほんの少し実践してみることで、マスコミ・ビジネス・大衆に惑わされず、自分で感じ、考え、判断する力がつくというお話。 “文系/理系”の定義は、文系が作ったものであり、正しくは“文系/文系以外”ではないか、という話...納得!!これなら自信を持って言える、「私は文系ではない!!(`・ω・´)」
0投稿日: 2011.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的と言う言葉を定義し、現在の科学なしでは生きていけない世界において科学とうまく付きあうことを提案してる本。 普段から科学を相手にしてる人にとっては当たり前なことも多いため、僕は当たり前のことを再確認した。
0投稿日: 2011.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログTVとかのお涙頂戴なレポートとかにはうんざりするけれど、森先生の言うような態度で臨めるかと言えばなかなか難しい。けれど、少しでも心に留めておくかおかないかで違うんだろうとも思う。
0投稿日: 2011.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学に対する姿勢。 科学とはどういうことか。 科学はなんのためにあるのか。 個人的な視点で書かれているが、 共感するところが多い。
0投稿日: 2011.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
理系、科学者、技術者的な考え方がよくわかる。森さんにはこういう新書どんどん出してほしい。”一番のパワーストーンは石炭だと思う”っていうくだりがツボ。こういう屁理屈的なとこが好き。
0投稿日: 2011.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「森博嗣」本はこれが初めてです。どんな小説を書かれているのか,全く知りません(今後読む予定はありません)。「鉄腕アトムを作ったお茶の水博士」という間違った情報を含むまえがきから始まるこの本は,「科学嫌いに由来する視野狭窄だと損することが多いよ!」と,科学の表面的な楽しさに訴えるというありがちな方向に向くことなく論じたものです(震災の後に書かれたものなので,震災に関することを含んだエッセイという側面が多いが)。実質的な内容は,新書にもならないと思うぐらいだけど,結構クリティカルな指摘も点在していると思います。ある意味,僕の確証バイアスもあるのだろうけど,理論あっての科学だということが確認できます。僕と話してたら実験できなくなる!と言われたことが幾度となくありましたが,“実験をすれば科学的だと勘違いしている人 (p.76)”という記述内容と自身の(素朴な)科学観とを対峙させるべきだと思います。
0投稿日: 2011.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
カテゴリを森博嗣にしようか新書にしようか悩んだ。 著者いわく、科学とは「方法」であり、「他者により再現できる」ことを条件とする。つまり、みんなが同じ現象を再現できるから、その現象は”どうやら確かなようだ”、というプロセスおよび結果を『科学』と名付けたわけです、と。(合ってるか?) だから、実験は、科学の一手法であって科学そのものではないと。 さらに、自分だけが理解していてもそれは科学ではない。科学が成立するには「他者」がどうしても必要で、複数の「他者」がOKを出さないと成立しない、なにやら民主主義のようなもの、と。 なぁーーるほど!これは納得! この本には、「理系の人は・・・、文系の人は・・・」という括りが出てきます。たしかに「理系っぽい、文系っぽい」というのは周囲環境をどう区切るかで相対的に変わるものだけど、まぁそれは置いておいて、世間的にどちらかというと私は理系に属していて、さらに著者の専門と近い分野の理系ですが、著者の「理系の人」像にはえええ!!!って感じる部分も多いので、誤解しないで欲しいといいますか。 たとえば、理系の人は「知識が多いからといって、尊敬はしない」らしいですが、んなこたーないと、思うんですが。 それから、生徒から「幽霊はいると思いますか」という質問に「幽霊がどういうものか知らないから、その質問には答えられない」と言ったそうで。笑 著者は理系の人から見ても相当変わり者だと思うので、冗談みたいなとこは冗談だと思ってください。
0投稿日: 2011.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「難しいことはわからないから結論だけ教えて」 東日本大震災を機に科学に対する不信感が世間では 大きくなりつつあるように感じるが、そもそもからして科学は「信じる」ものではなく「理解する」ものであり、科学を妄信する態度こそが非科学的な態度だった。本書の中で非科学的であることの象徴のようにでてくる「難しいことはわからないから結論だけ教えて」というのはつい取りがちな態度だと思う。科学的に生きることは面倒かもしれないが、「ちょっとよく考えてみよう」と立ち止まる機会を持ちつつ、時に「自覚的に」割り切りつつ、というのが
0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ森博嗣さんの本にある本質は、この本に書かれている事だなぁと思います。理系の側に一応いる身としては、社会に出てから「何で?」と思う様なコトが多くありましたが、まさしくこの本に書かれていることが当てはまります。 テレビを観ていても、コメンテーターの感情的な発言が多く見られますが、それを言った所で何になるのかと首をひねらざるを得ない事ばかり。具体的に物事を考えるためには、感情に流されて思考停止状態ではあかんのですよね。 一人でも多くの人が理系的な思考があればいいなぁと思います。
0投稿日: 2011.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログやや誇張もあるが、科学的に考えるということが整理されて書かれていて、すごい共感できて、自分の考えを吐き出せたみたいでスッキリする。これをぜひ「科学的に考えられない人たち」に読んで欲しいのだけれど、もし読んでも今まで通り拒否感を示すだけなのかもしれない。難しい。。。 -- 理系っぽい、文系っぽいは相対的 多くの場合で「科学の楽しさを知ってもらいたい」というがそれは楽しさを押し付けているに過ぎない 科学は現代で不可避。日本語が苦手だから日本語をしゃべらない、と同レベル 学校で教わることは「データ」と「メソッド」に大別される 国語もメソッドを教えるべき 津波を水量でなく高さで表現することに無理がある 閾値の話。例えば、高さ何mから落ちたら安全でそれ以上は危険だ、みたいのないでしょ。 数学、科学は積み重ねなので、早い段階で諦めてしまうと取り返しが付かない わからない子にわからせるのが教育なのだが、今の教育はわからなくても点が取れることに重心がある 小中学生くらいは=じゃなくて≒を問えばいいんじゃないか 人の「意見」でなく「感想」を聞きたがるのは文系の傾向かも 科学とは「誰でも再現できるもの」 白黒をはっきり決める必要はない 科学は慎重 自然を破壊しているのは科学ではなく経済ではないのか クイズ、名称をたくさん覚えていることに価値を見出すのがすでに文系的発想 奥さん(あえて敬称):妻は身内なのか他人なのか、みたいなことなのかな
0投稿日: 2011.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ミステリー作家でもあり、元大学教授がササッと頭の中にあることを311震災後に書いた本。 あとがきにも上のように書いてあるけど、本当にささっと書いたな~という感じの本で、逆にいえば読みやすい。 科学とは方法を身につけていく学問であり 特に数学を拒絶する文系を自称する人が多いけど それでは損をすることがあるよ、ということが書いてありました。 21世紀アマゾンで売れた作家上位20人に入ったそうです。
0投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだか始終共感しながら読んでました。 だから★5つ。 まー、単に森博嗣ファンってのも大きいけど(笑) これは是非、文系の人・中高時代に勉強が嫌いだった人に読んでもらいたい。 タイトルだけ見ると、『拒絶反応が……』とか言い出す人もいるかもしれないけど、内容は存外ソフトな感じです。森さんの言いたいことはよく分かるし、文体はわかりやすくて(というか、私が好きな文体)、さら~っと読める一冊なのですよ、実は。(読み出す前は私も身構えてた口なので) 新書だからって敬遠しないで欲しい一冊。 ちなみに話題も割とタイムリー。
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで私自身変わったことは、物事に疑問を持って考える習慣ができたこと。新書らしい荒々しい内容で極論も多々見受けられたけれど、学ぶことも多かった。
0投稿日: 2011.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ数字をイメージできること。 物事を科学的に疑う(認識する)ことが肝要。 科学的とは再現性がとれること
0投稿日: 2011.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ森さんのエッセンスがきゅっとまとまった、やわらかコンパクトながらお得な本。各章にまとめまでつけるなんて、優しすぎるんじゃ…、これも読者が増えた影響か。
0投稿日: 2011.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭から"科学を敬遠するのは、自分で考えること、感じることが面倒でしたくないからである。"今の私に足りないことをズバリ言われたなぁと反省しきり。。でも、読み進めていくうちに、「科学」に対する誤解がどんどん解けていき、もしかしたら、私が今行き詰まって悩んでいることの理由のヒントを与えてくれたような気がした。そんな行き詰まりを察してか、この本を貸してくださった方へ感謝です。
0投稿日: 2011.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
科学とは「誰にでも再現できるもの」である。(P.75) まさにその通りでもある。 再現性がなければ、科学ではない。 寧ろ、この再現性によって 科学というものは誰に対しても普遍的である ということができる。 どの人間に対しても科学は等しく、平等であり 「科学とは人を幸せにするものである」 という認識を持つべきだと感じさせる文章だった。
0投稿日: 2011.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系かつ森ファン相手なら半ページで伝わる内容を新書一冊かけて説明する森先生の優しさを感じる一冊。肝心の文系の読者に読まれているのか、ちょっと心配。
1投稿日: 2011.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ森博嗣の新書は小説だと思っているわけだけど,それでも割とこの本はストレートに彼の価値観が出ているのではないだろうか.昔みたいに. 文系と理系という単語がこの本には出てくる.だけれど,科学を拒絶する人間として文系という言葉を使っている所が,少し危険思想っぽいけれどあまりに心当たりがありすぎる.こんなに,そうなんだよく言ってくれた!と言語にしてくれたことに感謝する.まさに言語による単純化の始まりは気がしないでもないが. ところで,帯の「科学的無知,思考停止ほど危険なものはない!」と「横行する非科学に騙されるな!」は少し不自然な感じ(笑,本中ではどちらかと言えば危険側と言っているだけ.
0投稿日: 2011.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的とはどういう意味か。科学とは方法である。そして、その方法とは、「他者によって再現できる」ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある。ただ、数や実験があるから科学というわけではない。 個人ではなく、みんなで築き上げていく、その方法こそが科学そのものといって良い。(p107) 著者のいうように、この再現性こそが科学の肝なのだ。宇宙ではある一定の法則が存在しているということが確からしいということを前提としているからである。もし朝目覚めたら重力の定数が変わっていたなどということが起これば、人が秩序という名の楽園を開拓することは不可能となるだろう。 科学は発展しすぎた、科学が環境を破壊し、人間は本当の幸せを見失っている、という指摘はよくきかれるところである。しかし、この場合の「科学」とは、そのまま「社会」や「経済」と言い換えてもほぼ同じ意味であり、単に風刺的姿勢で警告を発している気になっているだけの物言いである。言葉は何とでもいえる。しかし、言葉では何一つ解決しない。(p186) 科学なしで、今日の文明を維持するのはもはや誰にも想像できないだろう。ということは同時に、科学という方法を利用しなければ、今の社会では不利益を被ることになるであろうことが容易に導き出せるはずである。科学、数字、数学といった通俗的な意味での理系分野に拒絶反応を示す人は少なくないが、自分の身を守るためにも周囲の人間を守るためにも科学的な方法を実践していくべきなのだ。
0投稿日: 2011.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、表題こそ科学的という言葉がある。しかし真意は、外から与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、提供されるデータを元に自分の頭で考えて判断できるようにということではないかと思う。その時に数字を食わず嫌いしてしまうのはもったいないし、大きさや量についての感覚もあった方がいい。よくも悪くも科学技術が話題になる現在、誰でも理科の知識や数字への感覚を身に付けた方がよいのではと思った。
0投稿日: 2011.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学はメソッドを中心とした学問、そこが文系と違う。科学的とは情報の取捨を自分で制御できる、思い込みが少ない、正確な表現ができることではないか。著者の主観である理系・文系論はともかくとして、理系の小生にとっては自身の思考整理の助けとなり、とても満足した本でした。
0投稿日: 2011.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「科学的とはどういう意味か」という標題が示すところは、「現代人の多くは、科学的であることの本質を理解していない」ということである。森博嗣は、世の「文系」と呼ばれる人の多くが、”理系から逃げた結果として”文系に進学している現状を憂いている。それどころか、科学的な思考法を解せない人々に向けて、ほとんど憐みに近い感情を抱きている。本書の目的は、何とかその非科学の暗闇から彼らを救い出すことであり、科学の面白さを説くのではもはや不足と感じたのか、非科学的であることの損を何度にもわたって説いている。恐らくその方法論自体は正しいし、ある程度の科学的リテラシーは、現代に生きる上で必要不可欠であるのも間違いない。その意味では、現代日本は、高度経済長期に比べて、むしろ科学的思考力が退化した社会になっているという彼の指摘も正しい。 本書は、主に文系の人間に向けて書かれているが、実際のところ、彼の標榜するレベルの科学的思考力は、理系人の多くにとっても到達するのが非常に難しい水準にあると思われる。社会は昔からそんなに頭よくないです、というのが第一の感想であった。
0投稿日: 2011.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、物の考え方、捉え方について述べた本です。 世の多くの人が曖昧な情報を鵜呑みにしがちだけど、 そういうのはすごく損しますよ、ということを言っています。 自分は職業的には理系ですが、 数があまり得意でない実際は文系なのでつい主観的になりがちです。 ただ、苦手なりにもそれなりに理系生活をしてきているので、 少しは客観的に考えられるようになっているはず(そう信じたい)。 この本を読むと、 苦手でも数値の示す意味について よく考えることの大切さが身にしみてよく分かります。 これは、なにも学問や仕事上に限ったことではなく、 日常生活でも言えることです。 故にうちを「科学的」に考える家庭にしたいんですが、 大学の教員をしている旦那ですら 曖昧な表現で適当なことを言ってることがあるので なかなか難しいよねーと思いました。
0投稿日: 2011.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ【特記事項】 ・言葉のイメージで割り切ってしまい、思考停止に陥っている。 ・科学に親しむことは楽しいというより、そうしないと損である、危険である。 ・「津波」という言葉にだまされ、とらわれ、普通の波のように思っている人があまりにも多い。 ・放射線の恐さとか、自分で調べればいい。お上の情報をどうして信頼するのか。 ・分からない子に分からせるのが教育。分からなくても点を採れる子を作るのがいまの教育。 ・6M×4M=24M²となるのに、6個×4個=24個²とならないのはなぜか。 ・東京ドーム何個分という言い方をするが、東京ドームの大きさなんて知ってるのか。それよりもきちんと数字でいったほうが適切。 ・非科学的なものを楽しむのもいいが、ちゃんと非科学的と知っていることが重要。 ・科学とは、他者による再現可能性があるもの。 ・実験が科学ではない。 ・数値がコミュニケーションの基盤となる。 ・コンクリートの比重はアルミより軽い。 ・科学的であるには、割り切りによる単純化には慎重に。 ・天文学者と物理学者と数学者がすこっとらんどを鉄道旅行していると、窓から黒い羊が1匹草原にいるのを見た。それを見て、天文学者は「スコットランドの羊は黒いのか」とつぶやき、物理学者は「スコットランドには少なくとも1匹の羊がいる」、数学者は「スコットランドには、少なくとも1匹の羊がいて、其少なくとも一方の面が黒い」と言う。 という例えがあるが、ひっしゃはこれに子どもを加えて「そもそもあれは羊なの」と言わせたい。 観察からジャンプして結論に至ることがあるが、割り切っているという自覚が必要。 ・ジャイロモノレール
0投稿日: 2011.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ思ったより地震関連の内容が多かった。 自分には合っているけれど、ダメな人はダメかも…という内容。 いっしょに紹介されている本のラインナップを見ると、世間はこれを「過激」と分類しているのかな...と思う。
0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・津波の高さは結果論、どんな状況で何に当たったか ・ドーム換算するような数値をビール換算したところで、どちらにせよ途方も無い量という認識しかできないのではなかろうか。 ・物語を求めるのが考えたくないからというのは暴論だと思う。感情に引っ張られるのがそもそもの人間の性向。 ・「道さえ決まれば、あとは単に登るだけだ」 ・思い込みと単純化を避け、広く情報を求めること。しかし何に対してもこれだとパンクする。大事なのは割り切っていることの自覚を持つこと。 ・防水仕様の自動車はかっこいい ・発展した科学は魔法と見分けがつかないというが、科学は無視すると現実的な不利益が大きいという点で魔法と異なる。
0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系に対する観察内容が偏向的すぎるな〜と苦笑する点も多々ありましたが、森先生の統計ではこういう極端なサンプルしか取れなかったってことなんでしょうか…。それともこれが本当に多勢なら、文系ヤバい\(^o^)/ピャー 「言葉だけの知識=理解」って勘違いしてる文系人間、多分ほとんどいないんじゃないかなあ。理系コンプレックスな人は「言葉を知っててもそれだけよね…」って分かってて自虐する人が(私を含め)大多数だと思うけど…どうだろ。 それでも図星をグサグサ刺してくる洞察も随所にあるのは流石です。 皆の意見をまとめて自分の意見を構築しようとするっていうのは特にグサッと…(笑)。 森博嗣が現代の科学的思考離れに鳴らした警鐘。科学から目を背けることで被りうる損と不利益。 何故、我々は「科学」を遠ざけるようになったのか。
0投稿日: 2011.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログおすすめ。 是非とも文系・理系を問わず多くの人に読んでもらいたい。 テレビなどの報道を鵜呑みにせず自分で考える癖をつけなくてはと再認識した。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリ作家の森博嗣の本。小説もだが、この人の怜悧で冷徹な文体が心地よくて好き。この本では科学的とは、「再現性」と述べられている。つまり誰がやっても同様の結果が得られる事。なるほどなぁ。ちょっとモヤモヤがスッキリした。普段がイメージ先行型なので、これからは多少科学的に考えるように努力してみよう。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系出身で文化系のコミュニティーの中で仕事をしていると感じるもどかしさの意味が少しわかった気がする。難しいことはいいから・・というようなことは本当によくいわれる。キーワードで理解したような気になっても全く本質はわかっていないのに・・と思いながら、適当にごまかしながら対応しているが、それではいけないと思いなおした。つい先日も「わかりやすさ」の感覚の違いに愕然とする事件があった。一朝一夕にはいかないが、粘り強く対応していきたいと思う。
0投稿日: 2011.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、作者の作品を読む機会が多いが、同意できる内容が多く面白い。主観ではなく、科学的である重要さもわかった。これを12時間で書いてしまうとは、すばらしい。
0投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログさらりと読める。 科学的ってどんなことで、それを避ける傾向の人が多くいること そして、科学を避けてしまうことによって起きるマイナスについて書いてある。 個人の思考なので、偏りも感じるが そういった啓発的なことは 科学者であり小説家である森博嗣が書くからこそ広まりやすいのかもしれない。 ただ、これを読んで文系(の定義も曖昧だけど)の人が同調、納得するかは難しいかもしれない。
0投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「文系寄りの理系」を自称する著者が、「科学を疎んじる人に、好きにならなくてもよいが、避けることで損や危険が生じる」と警告する内容。文系の人を上目線から捉えている感は否めないが、理系の私としては共鳴する部分も多く、特に「数字の重要性」には納得の思い。
0投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学は専門家だけのものではない。科学が嫌いな人に向けられた本。もちろん、科学が好きな人が読んでも得るものはある。
0投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ工学博士と小説家という二足のわらじを履く、自称「文系よりの理系」である著者による科学的思考入門。理系的=客観的、文系的=主観的というのはやや決めつけすぎのような気もするが、確かに「数字」をことさらに忌み嫌ったり、人の感想ばかりを気にしたりする傾向が社会全体に於いて強すぎる気もする。おそらく「文系」出身の人間が多いマスコミが世論を形成する役割を担っているせいではないだろうか。結論は当たり前だけれど、常識を疑い、自分で感じたり考えたりする事が大切、ということだろう。
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログもちろんその意見の全てに賛同するわけではないが、かね同意する内容だった。 ただ、ここまで文系を(ひとくくりにした上で)非難しているサマをみると相当鬱憤がたまってるんだなぁ…警告よりも、腹立たしさといった感情から筆をとったのではと想像してしまう。まぁどっちでもいいが。 数学や理科は得意だったなぁ~理解出来ていたかと問われれば閉口するが… 応用力のなさを感じて文系になったわけだけど、大学で学んだことは、筆者の主張する科学に近い考え方だった。 そして、社会人になって痛感することは、その「科学的な考え」が仕事をするうえで欠かせないということ。 最近になって、理解すること、答えを導き出すことの楽しさをあらためて感じている。これはいい傾向かもしれん。 手始めに数学でも勉強し直そうかの。今度は実のある理解を目指して。
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログうなずけることばかり。 自分が理系なんだなということを感じさせられた。 #しかし、こんな話を嫁にしたら逆切れされるんだろうなー ただ、最後の章の薬や子育てや宗教の話にはちょっと??? 自分のことは棚にあげて、「経験不足では?」とか思ってしまいました。。。 あと、どこで思ったか忘れましたが、あまりスポーツ(特に団体)をしたことないのかなーという印象を受けました。
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011年08月 01/050 物事を感情や感覚だけで捉えるのではなく、「科学的」に再現性を持った情報や数値をもとにした考え方の大切さを訴える本。 スピリチュアルや占い、宗教を信じやすい人は一度読むべき。つか、本気で信じている人の多さには驚きを隠せません。 そのあたりのことは気を落ちつけたりするのにはとても大事なことだとは思うのですけどね。ただ、あくどい商売とすぐに結びついて、人の弱いところをつくみたいになっちゃうのが嫌い。 松尾貴史の著作などとも合わせて読むのがおすすめ。
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ数字と向き合い自分で考える姿勢は参考になる。 ただ文系と理系の例えが極端。 筆者が文中でこき下ろす程の非科学人間に出会ったことがない。
0投稿日: 2011.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ森博嗣氏の著書。 科学的とはどういう意味か、というより、科学的であるためにはどうあればいいのか、といったことを中心に主張している。 やはり著者の思想は興味深い。
0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
元名古屋大の建築学科で教授で小説家でもある著者だから、言える意見であると思う。 高校の時点で大多数の人は理系や文系に分けられ、それにより人生の方向性が結構決まってしまう。なのに、文理分けの基準は数学や物理の出来不出来の割合が大きい気がする。したがって、文系の人は数学などにコンプレックスを持ち、科学的ということに身構えてしまっているという話だ。 今回の震災の報道でも、被災者のインタビゥーなど、感情的な報道が目立っていたりと、数字で示してほしいことが示されていなかったり、或いは視聴者もそういうものに関心が薄いとの意見でした。 科学的な視点を持つことは、損が少なくなりますってことが主題で、感情論ばかりでなく、論理的に根拠のある意見を持とうって話でした。
0投稿日: 2011.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧知の編集者が新書に移り,日記の続きの積もりで書こうとしていたら,311の震災で俄に忙しくなり,2011年3月31日までの3日間計12時間で書いたのだって~科学を敬遠するのは,自分で考えること,感じることが面倒でしたくないからである。科学を恐れ,避けることは損で,危険だ。科学というのは「方法」で「他者によって再現できる」を条件として,組み上げていくシステムだ。そのためには数を用いた精確なコミュニケーションが重要になる。言葉だけで理解している気にならず,思い込みを極力避ける。そのためには,いつも疑い続け,情報を広く求め,吟味したうえでも,きっぱり割り切るような結論を出さない。科学の存在理由,目標は,人間の幸せである~科学を好きになれ・とか,科学は面白いんだぞ・とかは云わない,科学という方法を知らないと損をするぞ・というのの「損をするぞ」は,一時自分もよく使った。子ども達が一番反応するのが損得という尺度だったからだが,それに迎合するのが嫌で次第に使わなくなった。文字を読むのが遅かった,英語が苦手だったが必要に応じて次第にスピードアップし英語で考えられるようになったと森さんは言うが,書くのがこれだけ速ければ十分。大して考えもせず,3時間程度で余り噛み砕かず読み終えたが,考えていることを論理立てて文字を連ね,それを読んで矛盾しないよう吟味し校正して,もう一度読み直して・・・2度読むだけで6時間は掛かる。執筆1時間とは・・・生産性の高い仕事をしている。全体の流れを作り,章立てして,各章に項目を並べるという準備作業があって,その項目に相応しい具体例を挙げていくのだろう。1何故,科学から逃げようとするのか2科学的というのはどういう方法か3科学的であるためにはどうすれば良いか4科学とともにあるという認識の大切さ・・・以上が章だ。各項目も時間があるから挙げておこう。1-1いつから避けるようになったのか1-2向いていないと思い込む1-3文系と理系1-4理系科目は何が違うのか1-5覚えるものと理解するもの1-6名称を覚えることの弊害1-7思い込みによる思考停止1-8津波という名称はいかがなものか1-9言葉だけの認識の危険性1-10自分も言葉だけで評価してしまう1-11わからないのには理由がある1-12教育の責任1-13社会の集団の中でも1-14数字をイメージできるか1-15感想ばかりが溢れ智得る1-16個人の感想ではなく客観的情報を1-17客観性が社会を落ち着かせる1-18科学の方法2-1科学と非科学2-2非科学的な習慣2-3幽霊を信じますか?12-4見れば信じられる?2-5科学とは2-6事件をするのが科学?2-7実験が科学ではない2-8数値によるコミュニケーション2-9数字による認識2-10科学的予測が支えるもの2-11ある技術者の返答2-12科学は人間の幸せのためにある2-13定着的な把握2-14数字による把握とは2-15それでも耳を塞いでしまう2-16知識量に価値があるのではない2-17理系と文系の認識2-18お互いに認め合うこと2-19物語だけが読み物ではない3-1「割り切り」という単純化3-2科学は常に安全を求める3-3厳密であるために疑う3-4割り切っているという自覚が必要3-5面倒なことに慣れる3-6問題を見つけることの重要性3-7科学的に答えてみよう3-8科学の歴史は浅い3-9案外知らない科学的理由3-10問いつづけると根元的な疑問に至る3-11言葉の信仰による支配3-12実験結果は必ずしも真実ではない3-13ある小さな研究の成果3-14秘伝は科学ではない3-15科学の慎重さ3-16科学の公平さ4-1ごく普通に接すればよい4-2数字にもう少し目を留めてみよう4-3数字による評価4-4数字はあてにならないものか?4-5ほっきりと示してほしい?4-6少し勉強すれば・・・4-7言葉を鵜呑みにしない4-8大まかでも良いから把握する4-9技術者として一言4-10科学者は非常なのではない4-11歩調を合わせて信じてしまう4-12科学的に否定されていない?4-13少し科学的に考えてみれば4-14若者の方が危ない4-15微笑ましいレベルの非科学4-16健康に関しては自分が基準4-17子供に対しての注意点4-18好奇心を潰さないように4-19自由さが科学を育む4-20人間の幸せのために。10mの津波を5mの堤防で防ぐことはできないのは当然。鉄とアルミではアルミの比重が小さいが,アルミとコンクリートではコンクリートの比重は小さい。地震による被害が25兆円だとすると,国民一人あたり25万円の資産が失われたことになる。私も数字の桁を捉えるのに慣れていなくて,すぐ間違える。25兆を1億で割ると2500と直感で考えるのが危険・・・0が二つ足らない・・・あーあ。もう少し桁の扱いに慣れたいものだ。人を理系・文系に分けたがるのは科学嫌いになってしまった人のコンプレックスの成せる業。自分を理系・文系に分類するのは嫌だが,この段階で理系に分類したがる人の集合もあるってことも嫌。「月までの距離」と書いてあって,「37万kmだったよな?」と思い起こしたが検索の結果『38万km!』,桁が合っていて良かったぁ。「地球の直径」はと聞かれて「6400km」と考え,月と地球の間に60個の地球が入ると答えを出したが,「6400km」は半径だと後で気が付いた。ねえ,円周4万で1万以下はあり得ません! そう正解は30個だ。うわ,何だかグダグダしてきた。あとちょっ続けよう。地表から10km上がるのは自力では叶わず,ちょっとした経済的出費と仕事を休みにする算段をつけ,非日常への期待から興奮して,わくわくしながら科学の成果である航空機の力を借りなくてはならないのに,ものの5分と掛からないのだけど,ちょっとした感動だよね。月まで空気があって航空機で行けるとしたら(この設定自体が無茶),37000×5=175000(分)≒180000=18000÷6(時)=3000(時)=3000÷24(日)→100日以上掛かるのかぁ。変な計算!前提条件がおかしいものね。航空機の巡航高度まで5分というのが怪しい・・・最たるもの。おしまい
0投稿日: 2011.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/8/2 メトロ書店御影クラッセ店にて購入 2011/9/1〜9/6 デビュー当時、"理系作家"と言われた森氏による科学論。書かれてある通り、科学とは何か、について書かれた本はあまり無かった。私も以前から、文系、理系の枠組みは全く意味の無いものだとおもっていたが、森氏の見解と同じで、枠にはまることによる思考停止が一番問題なのであろう。震災報道で見られる非科学的な論評から自分の身を守るのは、科学的な思考力を身につけることなのだ。科学的思考力には文理の違いは本来無いはずなのだ。
0投稿日: 2011.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学好きの人が抱える 科学嫌いの人に対する思いを 端的に書いた本。 そうそうとうなずけることも多々。 興味をもって話をしても 誰からも興味を持たれないっていう切なさ。 わからないと一言で話をシャットダウンされる切なさ。 もっと科学好きが溢れればいいのにな、と心から。
0投稿日: 2011.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系の人間は文系科目を「やればできる」と捉えているのに対して、 文系の人間は理系科目を極端に毛嫌いする・・・ 書かれている通り、私もそんな文系人間です。 本書の主張は、 『結果だけを見て過程を理解しようとしないのは思考停止である』ということ。 理系科目が理解できないからと、過程を省いて結論を迫るのは思考の成長の機会を失っているというわけです。 盲目的に情報を受け取るのでは振りまわされる側の人間になります。 自分で思考力を高めて正しい見識を持ちたいと思わせてくれた本でした!
0投稿日: 2011.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリ作家にして某国立大学工学部の研究者であった著者が、科学的に物事を捉えることの意義を説いた一冊。 現在のマスコミや多くの人達は物事を「印象」や「感傷」によって捉え、事象の要因を自ら考えることを避けているのではないか、というのが著者の見方。 科学というのは、他者によって再現できることを条件として組み上げられた「方法」であり、人々の生活をより豊に暮らしやすくすることを目的とした「システム」。多くの人々が科学的な思考をすることによって、より社会を望ましい方向に導くことができる。 科学的な思考をするには、どうすれば良いか? まずは、マスコミ等が発表する事実に疑問をもち、情報を広く集めて、自身で吟味すること。そこから問題意識が芽生え、より深く自身で考えようとする。 自分自身は理系であり、物事の原理的に捉えようとする姿勢は常に意識しているつもりであるが、つい深く追求することが疎かになり、抽象的な言葉だけで解ったような気持ちとなってしまう。 まず、何か疑問をもった事があれば、マスコミ報道を鵜呑みにせず、 自分で情報を収集して考えることを、少しずつでも始めたいと思う。 ----------------------- ・一部の専門家がすべてを決めることはできない。だとすると、大勢の人が非科学的な思考をすれば、それが明らかに間違っていても、社会はその方向へ向ってしまう。 ・「科学から目を背けることは、貴方自身にとって不利益ですよ」そして「そういう人が多いことが、社会にとっても危険だ」ということである。 ・名称を知っていることと、それを理解していることは同義ではない、という認識を常に持たなければならない。 ・マスコミの報道を見ていると、この「印象」「主観」情報の比率がどんどん高くなっているのではないかと感じる。 ・多くの人は、そこにある対象を見て、どう感じれば良いのか、どう考えれば良いのか、どう対処すれば良いのかということを考えたくないのだ。 ・答えをごく簡単にいえば、科学とは「誰にでも再現できるもの」である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが「科学的」という意味だ。 ・自然環境を破壊しているものは、科学ではなく、経済ではないのか。 ・一方、方法を習得した者は、同種の他の問題を解決する能力を持っている、と理系の人は評価する。 ・したがって、個人においても、科学的であるためには、あらゆるものを疑い、常に「本当にそうなのか?」と自問することが大切である。 ・どんな分野であっても、何が問題なのかを常に知ろうとしなかればならない。その姿勢が、ものごとを全身させるといっても良い。
0投稿日: 2011.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「理屈はいいから」「文系だから詳しいことは分かりません」「科学が環境を破壊した」「技術者(科学者)は理屈ばかりで人間味に欠ける」などと言ってしまう方に読んでもらいたい1冊。 震災の後に書かれたということで、震災絡みで具体的な例が挙がっているのでイメージしやすい。 書いてることは全く難しくなく、優しく誠実に書かれてる。
0投稿日: 2011.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログマスコミや権威者の言うことを鵜呑みにすることなく 自ら常に疑問に持ち、考えることが人生における リスクを避けることになる。ついつい、「言葉」を 知ることで満足してしまっている自分にとって 良い警鐘になった。
0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系の人がこれを読んで納得するか微妙ですが,理系の人が読む本ではないですね。 研究室に配属になったばかりの大学生が読むと良い本かも。
0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学的思考が現代に生きる人々にとって、もはや生きるために必要なものであるという主張には頷くし、科学が再現性のある現象を取り扱って多くの人々によって検証して問題を解決するための方法であるという定義にも異議はない。 しかし、私には第1章「なぜ科学から逃げようとするのか」という章での教育問題の記述がどうしても許容できないため、基本的な内容には賛同しつつも星3にした。 なぜ科学から逃げる子供の心理を確たる証拠も示さずに決めつけようとするのか。児童生徒の学習の意欲というのも教育学の見地から研究される立派な研究課題であり、科学的な思考で原因を追及して解決していかなければならない。刈谷剛彦などが代表的な例だろう。 著者は建築、特に流体工学が専門であるから、教育学の領域にあるトピックをうまく説明できないのは当然である。しかしそれならばいっそ断言を避けるか内容を削るべきだ。思いこみを捨てるべきだと筆者本人も記述している。 本書が科学から逃げてきた人々のために書かれた書籍だとしたら、当の読者たちのことを非科学的にとりあつかって果たして良いものだろうか。私には、この章があるために本書の主張そのものの説得力が失われてしまったように感じた。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「文系だから」聞くだけでイラっとする。 その背後にあるのは理解を諦めた思考停止。 それに対して「科学は楽しいよ」「それは間違っている」などの方法ではなくて、「知らないと損をするよ」と説く。 3月11日の震災後に書かれたので、影響を多分に受けているが、その際にも知らないと命を落とす、という例が出されている。 津波のメカニズムを知っているだろうか。 今まで知らなかったが、通常の波とは全く異なる。 「堤防があるから大丈夫」は本当なのか? その一点のみでも、「津波のメカニズムは知っている人が対策をしてくれればよい」とは考えることが出来ないことがわかる。 「結論は?」「大丈夫か大丈夫じゃないかだけ教えて」など、過程を知らなくても結論だけわかれば良いと考える傾向がある人にこそ読んでほしい。 本書は厳しいわけではない。 どれだけ損をするかがわかるだけなのだから。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ森氏の作品を読んで理系人間に憧れて、数学の本を読み始めるようになったのですが、それこそが理系コンプレックスの現れてだったんですね。 けれど、この著書的に言えば、自分の物事の捉え方、考え方が理系の思考と同一だと分かったのが嬉しかった。 少しは憧れていた理系人間に近づけたのかも。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「他者による再現可能性」、これに尽きると思う。 他者から批判されたり、覆されたりするのをおそれて、隠し立てするのはまさに「科学的」の正反対にあることなのですね。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログごくごく当たり前のことが書かれているだけ。分からない人、分かろうとしない人がたくさんいて、悪いことにそういう人達がマスメディアなどで一定の影響力をもっている、と。 記者会見場で、分かるように説明して、と曰う記者さんは分かろうとするつもりなどさらさらない、と。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とても面白かった。 理系出身者としては納得。(意識してないと、ついつい安易に非科学的に流れる自分がいます。) 津波は超高潮だというのは言われてみればその通り。(対策を認識し直さないと・・・) こちらのこの本に対する書評も一読の価値あり。 (科学が人の幸せのため、というところは小飼 弾 氏に一票。 http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51708664.html
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学についてわかってるようで何も分かっていないことに気づいた。人は、苦手なものに対しての考えるのが面倒で、思考停止してしまい、使えればいいかと考え、本質について深く考えようとしない。数値で表したときに、それではわかりにくいので何かに例えて考えようとするが、数値の意味についてもっと考える必要がある。
0投稿日: 2011.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の科学的な思考プロセスがいろいろな日常の場面を借りて語られてて興味深い。まったく科学的でない母親や妻にも読ませたい。
0投稿日: 2011.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学の定義を明らかにし、同時に科学に目を向けないことの危険性を丁寧におった本。 ただ持論を論理的に主張しすぎるあまり、極端に走りすぎる記述が随所にみられるところがマイナス点。
0投稿日: 2011.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51708664.html
0投稿日: 2011.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は何か説明のつかない事象や理解のできない事象と接すると、思考をとめ、それを「神の仕業」であったり、「そういうものだ」と割り切ってしまう。 今回の東日本大震災を例にしても、放射能の測定値は毎日のように発表されているし、調べようと思えばすぐに調べられるのに、「はっきりと示してほしい」とテレビの司会者は政府に対して怒りをあらわにする。 それについて説明を受けても(科学的な)「結局のところどうなの?」と個人の感想を聞かれることが多い。 これは明らかに、思考の停止であり、このように科学から逃げることは損である。 自分は典型的な文系であり、かなりの物事を自分にとって意味の無いものとか、割り切って考えてしまたり、結果だけを知りたいと思ってたりする。 ただし、これが悪ではなくて、大事なのは割り切ることを正しく取捨選択できること、理解できないことすべてを割り切ってしまわまいことだと感じた。
0投稿日: 2011.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ『「やる気」や「心意気」よりも数字の方がずっと信頼できる。数字は人を裏切らないし、数字は調子が悪くなることもない。』 科学的な知識や考え方とは何か、身近な事例を用いて主張が展開されている。比較的、教育方面の話題が多い。そういう意味では、科学的とは何か、ではなく、科学的であるためにはどうすればいいか、という点に主眼が置かれている。それはつまり、科学的になりたい人が読むわけではなく、自身が科学的だと思っている人が読むということ。 概ね良かったけど、小説の抽象度の行がちょっとどうなのかなと思った。
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ震災後のマスコミ(特にテレビ)の報道に接して感じていた不安、不満の正体を的確に捉えていただいたという印象。
0投稿日: 2011.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者の言う,文系の人の理系コンプレックス,のようなものが実際にあるのかは理系の僕にはわからないが,科学技術を過剰に否定したり,オカルトに没頭するなど,非科学的な思考を持つ人は実際によく目にする. 本人がそれでいいなら別に構わないが,そんなのはあなたに不利益なだけですよ,科学的に考えて…,という本. なのでそれ以外の人にとっては得ることは少ないように感じたが,さっくり読めるので頭の整理にはなると思う. まあでも実際に読む必要がある人は,この本を手に取らないんだろう….
0投稿日: 2011.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ森さんが日記や小説でいってることでした。日々森さんが言ってることをまた再確認して、もっと知りたい!という気持ちになりました。
0投稿日: 2011.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
科学的の意味を説明しているというよりは、現象に対してもっと疑問を持つべきと言っている本です。 ただでさえ日本語はあいまいなところに、言葉の持つ意味合いは個人の経験などで微妙に異なっている。そこで言われたことをうのみにするな、ということですね。 文系、理系という言葉でくくらなくていいですし、あえて科学的と構える必要もないと思います。 期待したほどの読みごたえはありませんでした。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「科学的な態度」とは、実は非常にはっきりしない態度なのである。「文系」の人間から見るとそう見える。簡単そうにみえることでもいろいろ条件をつけて決して断言しない。 あるいは、「科学的な態度」とは非常に非人間的な態度である。「文系」の人間から見るとそう見える。人の気持ちなんかおかまいなしに、データで判断する。 しかし、そういった「文系」人間の主観を中心とした判断は実は大変危険なものなのだ。「単純化」「割り切り」といった方法で、思考停止してしまう。判断を他人に預けてしまう。 私も数学が苦手な文系人間であるが、なるべく数字から逃げずに、科学的な態度をとるようにしていきたいと思った。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くは語るまい…。 頷くところは多分にあるけれども、情緒に欠けやしませんか。分かりやすさのための作為的なものだろうけど。期待値高かっただけに残念。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ近頃はネットで色々と見るものが増えたけど、 その大半は誰かの「感想」だったりする。 感想の洪水に飲み込まれて無難な腺で落ち着いたり、 不特定多数のみんなと同じであることに無意識に安心していたり。 本当、気をつけなきゃいけないな。 あと、「数値をイメージする」ってのは確かにそのとおりで。 桁が多くなるとすぐ諦めてしまうのは自覚があっただけに胸が痛い。 少しずつ気をつけていきたいと思います。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学とは第三者による再現性のあるものであり、そうなるようにするたための態度が科学的な態度という。著者の危惧するように今の日本人は過度にそして意識的に非科学的な態度をとっているように思えてならない。
0投稿日: 2011.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/7/9読了。 科学的ということをもっと深い部分(哲学の範疇に属するような)で考察する内容を期待していただけに、"文系"(文中では理系科目を毛嫌いする人の意)の人に対して理系的な物の見方を説明する議論の中に新鮮味は感じられなかった。 しかし、理系の人間であれば大概の人が感じている(であろう)ことを、イメージしやすい例えと言葉で伝えられるということから、著者が文系に近い理系であるという言葉は的を得ているのであろうと感じた。
0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学が苦手でも、物理が苦手でも、ただ自覚的であれば問題は無い。 「言葉」のイメージだけでわかったような気になってしまう「文系」の弱点を思い切り指摘されて、痛い痛い。科学とは「方法」であるという説明がとても腑に落ちた。
0投稿日: 2011.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログいつもの森先生の話。文系、理系だとか。 震災、というより、それに対する在り方についての言及を含んでいるのが意外でした。時事問題を減らしてより抽象的・一般的な記述にするかと想像していたため。 ある質問に関する、技術者の誠実な回答に関するエピソードが印象的。性急に答えを求めてしまうことへの戒めとして、心に刻もう。
0投稿日: 2011.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
科学とは、普遍性を維持するための仕組みである。そのため、誰にでも再現ができ、誰もが観察できるものである。 科学を通じて、一般的に理系と呼ばれる人と、文系と呼ばれる人の事象に対する反応について述べている。 また、東日本大震災が生じたときの人々の反応から、人々の科学に対しての無知を憂いている、ように書いている。 http://unreconstructed.dtiblog.com/blog-entry-18.html
0投稿日: 2011.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
要するにもっと数字を意識せんといかんってことと、自分で考えろってことを言っとります。主観と感情先行の報道は改めて、客観的な数値を示せとも。震災中に書かれたみたいだからよりイメージしやすい。小説家だけあって比較的読みやすい。ノベライズの一角でよく見るから名前は知ってたけど小説は読んだことない。
0投稿日: 2011.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
久々に森先生の本を読んで、懐かしかった。 現代社会の複雑さに目をそむけて、楽をするために状況を鵜呑みにすることの危険さ。森先生は昔からそういうことを書かれていたなあと思い出しました。 津波のエピソードにものすごく納得しました。 波というとサーフィンとか、すぐに引いていくような印象だけど、超高潮になると、引かないイメージがする。 言葉・名詞によって思考が制限されてしまうんですよね。 毎日少しでも、自分の頭で考える時間を持ちたいなと思いました。
0投稿日: 2011.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ森先生、新書をもっと書いていただきたいなと思ったけれど、そう思うことがもう考えるのを面倒がっているのだろうな。とりあえず、どうして携帯電話で通話ができるのか、自分で調べて理解したいと思います。
0投稿日: 2011.06.29
