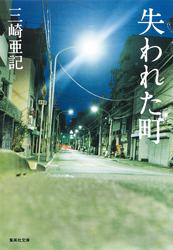
総合評価
(129件)| 27 | ||
| 40 | ||
| 33 | ||
| 17 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ全然ハマらなかった。これはSF?終わり方は突然で、そこも拍車をかけて「?」となってしまった。 街がなくなるということを誰にも話せずただただ受け入れるというお話。後から登場してきた人物が知った感じで振る舞っていたり、常識では考えられないことが普通として描かれているので、理解力が乏しい自分は置いてけぼり。 初の三崎亜記作品。他の著書もこんな感じなのかなー。
0投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かやっと読み終わったという気持ちがする 失われる町との対決や登場人物など魅力的なんですが、何故か語られない所が多々ある為、そこが気になってイマイチストーリーにのめり込めなかった 舞台は日本ぽいけど日本じゃないの?居留地は中国のこと?高射砲って何のためにあるの?分離って普通なの? ハイポーションて何?て感じでキリが無いほど謎設定が多すぎる 茜が回収員時代から最期に関係者が勢揃いする所までストーリーが連なるところは非常に感心しましたが、他のことがいちいち気になり没入できずに頁がなかなか進まず勿体無い作品と思います
0投稿日: 2024.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ何らかの影響で、町の住民が消える。月ヶ瀬町もその一つであり、消滅後に月ヶ瀬町の記録としての痕跡を消す回収業を行う人々の物語。 明らかに眉村卓を意識したようなタイトルだが、内容はいつもの三崎亜記である。しかし、印象は悪い1冊だ。 良いところは、読みやすい。複雑なはずのストーリーだが、わからないならわからないなりに読み進めることが出来る。わからない状態でも、なんとなく誰がどうしたのかはつかめるというところはこの本の利点だろう。 しかし、悪いところはたくさん有る。まず「町の記憶」だったり「澪引き」などの、作者の作ったテクニカルタームをカッコ付けで表現されるのだが、悪い意味で中二病の作者が、自分の中の世界に酔っているようにしか思えない。また、町が消えるメカニズムや、境界がどうなっているのかといったような読者の一番気になる部分については、登場人物はすべて理解しているのに対して、全く説明がなされない。 さらに、「別体」などと、ただでさえよくわからない世界観に、さらによくわからないものを混ぜ込んだのも印象が悪い。それはそれで別の作品にすればよいのではないのか。 作者の他の本も読んでいるが、すべての作品で不満なのが、SFとして描かれているにも関わらず、何がどうなるというメカニズムの部分にはノータッチで、不思議なことが起こってしまったからしゃーないやんという諦めのようなものを感じる。 SF(とホラー)の要は、メカニズムである。町のどの部分から起こっているのか、消滅した人はどうなったのか、ペットは?植木は?というところが、なんとなくでも描かれる必要が有る。一方で、いつか自分も消えてしまうかもという恐怖が、登場人物にわからないものでなければ読んでいて緊迫感を感じないために面白くない。 ワタシが最も嫌う作品に、SFのように書かれていて、最後に純文学として逃げるというものが有る。三崎亜記という作家はそのギリギリのところにいる。しかし、この作品はダメだろう。SFにも純文学にもなっていない。もうちょっと何とかならなかったのか。読むのなら他の作品を手に取るべきである。
0投稿日: 2024.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失われた町 30年に一度、ある町の住民が突然失われるという現象に巻き込まれた人々の物語です。 「となり町戦争」と同様に、無機質で冷たい官僚機構の中に情緒ある物語が展開されるので、物語が引き立っています。 この物語には何人もの主人公がおり、それぞれの体験から町が失われるという現象に否応なく巻き込まれたり、進んで対峙したりしていきます。冒頭で次の消失を防ごうとする様子が大きなインパクトを持って語られますが、続く各章で、大円団に向かって収束していく主人公達の軌跡が丁寧に語られていきます。語られるにつれて登場人物同士の関わり合いがだんだんとわかってくるという構成はとてもわくわくしながら読むことができました。 主題は「思いの継承」でしょうか?町の消失という現象に立ち向かっていく間に多くの人が亡くなっていきます。それでも、そういった人々の思いを受け継ぎ、それを「生きる力」に変えていく。そういった繋がりによる明日への希望。とても、感銘をうけた竹蔵でした。 竹蔵
0投稿日: 2024.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「こんなに美しく、哀しい作品を書ける人がいるのか。」 これが読んでいる途中で何度も思った感想。実際電車の中で読んでいて何度も目を潤ませることになった。 人々に忌み嫌われながらも町の消滅を解明し、止めようとする人たちは、みな心に傷を負っていて、それでも自分の身を犠牲にしてでも消滅を止めようと奮闘する。 登場する名前のある人物にはすべてに役割があって、ちょい役のようでも伏線のように後で効いてきたりする。そういう上手さもある。 悲壮な努力の結果は報われたのか、新たな問題を生み出したのかはわからないし、今回使えた手は次回使えない(消失した双子はいないし、属体のひびきはおそらく戻ってこられない。消滅耐性をもったのぞみも次回は高齢になってくるし、そもそも今回無事帰還できるのかも不明)。次につながるのかわからない方法だが、それまで無力だった人類からすれば大きな一歩でもある。”新しい方法”ではなく、理不尽な現象を克服しようとする人間の”努力”にスポットが当てられた作品だと思う。だから美しい。 作者は(名前から)女性だと思って買ったのだが、扉の部分で男性だと分かった。内容を読むと、確かに男性っぽい。 続編(?)があるらしいので、そのうち買って読んでみようと思う。
0投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり多くを説明せずに作者が創造した世界に読者を引きずり込むのは難しい。 「失われた町」というコンセプトそのものは面白い。そこに関する部分は比較的楽しく読めた。 ただ、それ以外の、「居留地」や「澪引き」、「古奏器」、「強化誘引剤」、「分離者」…とにかくいろんなオリジナル要素が詰め込まれすぎていて、さらにそれらについてほとんど説明もないままストーリーが進行するので、ついていけなくなった。 あまり説明をしすぎても野暮ったくなるし、かといってここまであっさりしていると読者として戸惑う。難しいところ
0投稿日: 2024.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「町」を生きているものとして取り扱っているところが面白かった。その分定義やルールづけもされており、理解しながら読み進めることができた。
0投稿日: 2023.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一つの町が失われるということは、単に地名や場所としての町が失われるという意味だけでなく、その町で生活していた人々の暮らしそのものが失われるという事実を突きつけられました。その時まで普通にあった町が突然失われる…という不条理の中で、残された人々の抱える大事な人々を失った静かな悲しみに胸を打たれます。 消滅の連鎖が起こってしまうために大々的に悲しむことすら許されない中で、失われた大事な人の遺志を継ぎ「消滅」と戦う方法を模索する人々の姿は、絶望の中にある希望の光のようで私も勇気づけられました。
0投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み物として、世界観を作り出す中で語られる固有名詞、特に地名・人名ではないキーワードとして使われる用語・概念の解説が淡白なので、没入してこないと賛否両論分かれる作品だと思った。映像化はうまくやれば効果的に表現できるのではないかと思った。かなり一気に読み切れる作品だった。分割された登場人物のエピソードが、最後に一気に結合していく感じは良かった。
0投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごく好みの設定だった。SF物としても十分面白いし、自己啓発本的な生き方について考えさせられる部分もあり、とても満足度の高い一冊だった。
0投稿日: 2021.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ発売当時、単行本を読んでから 数年ぶりに再読 ある日、町から人々が消えた。 「消失」現象が定期的に起こる世界 家族や友人を失った人たちと、消失に対抗すべく活動する「管理局」に属する者達の日々 消失の現象自体、消失に関する管理局の人間たちの持つ能力、キーアイテムで出てくる古奏器とその再魂(調律)、 同一性障害の治療として人が 本体、別体に分離する現象、など 三崎さんが1アイデアで短編一作 いけるような要素(テーマとしてはすでに扱っている)が散りばめられていて濃い。 数章にわたって、立ち位置の違う人物達の視点で消失に触れ、繋がっていく。 描かれてない消失を経験した人達もいるのだろうけど、次の別の消失に向けて希望を繋げていく線(人のつながり)が描かれている。 悲しみがあり、全体的に静かな話かと思いきや章によって動きがあり、別の話を読んでいるような気分になる。 今のコロナの状況と照らし合わせることも出来る(死ではなく、二度と会えなくなること)だけど、亡くなった親族や突然引っ越して誰もいなくなった友の家とか、今ここから見える場所、建物にある思い出のことを考える。 前に読んだ時より、沁みた。 追記: 読んでいる最中に「ニセモノの妻」を購入 「失われた町」の中にも妻の本体、別体と生活する夫が出てきたりする。 「古奏器」は別の話に出てくる職人を思い起こす。
16投稿日: 2021.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログある日、突然にひとつの町から住民が消失した―三十年ごとに起きるといわれる、町の「消滅」。不可解なこの現象は、悲しみを察知してさらにその範囲を広げていく。そのため、人々は悲しむことを禁じられ、失われた町の痕跡は国家によって抹消されていった…。残された者たちは何を想って「今」を生きるのか。消滅という理不尽な悲劇の中でも、決して失われることのない希望を描く傑作長編。
1投稿日: 2021.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと終わった 三十年ごとに町が失われるという世界で 生きる人々のお話でした そんな世界で、失われないように戦ってる人たちもいました 「刻まれない明日」にも登場する人たちも本作に いました 町が失われる他に、人が分離するっていう設定も 気になりました
1投稿日: 2020.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年に一度、突如としてどこかの“町”は失われる。 その町の住民だけを飲み込んで。 新たな町の消滅を防ぐため、人々は失われた町を悲しむことを禁止され、その町の名も世間から消される。 作者独特の世界観が表現された一冊。町の消失を止めようとするもの、失われた人々への悲しみをこらえる残されたなど、町を中心にしてさまざまな登場人物が登場する。その人物たちがだんだんとつながり始めるのが面白い。 最初の『プロローグ、そしてエピローグ』だけを読むと意味が全く分からないが、その題名通りすべてを読み終わった後に読み返すと驚くほどすっきりした気分になる。 もし、これが現実に起きたら・・・と考えてしまいます。
1投稿日: 2020.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公達にとって 作者にとって 「町」とは何なのか。 考え続けても分からないまま読み進めたけど 何かすごく大切なものなんだろうかな。 カタカナが多いシーンは苦手だったけど ファンタジー強すぎる作品なのに 現実みたいに捉えられた。 市川拓司さん並みに有り得ないファンタジーなのに。
2投稿日: 2020.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ気になるところはあるものの、絶望か分かりやすい希望が好きなので久しぶりに読み返して楽しかった。曖昧なところは匂わせたり、造語でやりくりしているところが好きです
0投稿日: 2020.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログファンタジーもので、かなり練られた作品。こんなに何度も戻っては読み、戻っては読み、を繰り返した本はないだろう。 ハリーポッター以来かな。 まだまだサイドストーリーもあるはずだし、それも書けば相当な長編になったであろう内容を、このサイズに収めることで作品の魅力をより引き立たせている。 沢山の登場人物をとても丁寧に、大事に描き、きちんと伏線を回収する、、、 とても好きな本になった。 この著者、三崎亜記さん、すごいなー。天才。
1投稿日: 2019.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
独特の世界観だけれど、細かく設定されていて説得力がある。 初めは理解できなくても後から繋がってくるので引き込まれる。 消滅に直接立ち向かう人も、それを支える人も、意思がとても強い。 その一方で、自分が失われると分かっているのに何もできない、月ヶ瀬など「失われる町」の住人や管理局職員のやるせなさはいかばかりかと思う。 いつ自分の元にかえってきてくれるのか分からない人を、傷つきながらも待ち続ける茜や勇治の姿は切なかったが、それだけ人を信じて待てるのは素敵なことだと感じた。 統監と中西さんが本体と別体の関係だったとは、最後まで驚かされた。
1投稿日: 2018.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ突然一つの町から住民が消失する不可解な現象に違った立場、違った角度から関わった人たちを通して、やわやわと外堀を埋めるように見えて来る筈の全体像が、最後までいまいち掴み切れず厚さを持て余した。ペンション風待ち亭の存在が爽やか。一人が二人に分離したり消滅耐性を持つ存在等には薄ぼんやりと興味を引かれた。
0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったです。 三十年ごとに、町が「消滅」し、そこに住む人々は失われる。町に住む人々は、自分達が消滅することを知っていても抗えないし、町が消滅したあとに、消滅に関心をもったり、消滅した人達を悲しむことも「余滅」を引き起こすとして禁じられている世界。 序盤の、消滅した町での回収作業は、小川洋子さんの「密やかな結晶」を少し思ったりしました。 そんな理不尽な世界でも、「町」に抗おうとする人々に希望が持てます。消滅耐性を持つ特別汚染対象者、分離者、管理局。 「居留地」「西域」「ハイ・ポジション」など、三崎ワールドだ、と思います。 後半になるにつれて、登場人物たちが関わり合ってきて物語がひとつになっていくのも良いです。 おしまいの「エピローグ、そしてプロローグ」を読んで、最初の「プロローグ、そしてエピローグ」に戻るとじーんとします。 人との別れは、この物語のような形でなくても、思いがけずに訪れます。悲しみを抱えながら、でも前に進んでいく、という気持ちをもらえました。「刻まれない明日」も読みます。
0投稿日: 2018.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログある日 突然に一つの町から住人が消失した・・・ そんな裏表紙に心を奪われて手にした本。 SF映画を観ているような ハラハラドキドキする場面も多く 登場する人物への繋がりが儚く一気に読み終えてしまった。
0投稿日: 2018.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読。連作短編集のような長編。各章に素敵なタイトルがついていて主人公となる人がそれぞれの章で入れ替わる。登場する女性が幼い女の子から年を重ねた女性までみんな魅力的。三崎さん女性を描くのがうまいんだよなあ。人の力ではどうしようもない喪失に立ち向かっていく勇気と人のつながりに、時に涙し癒された。『となり町戦争』でワードしか出てこなかった世界が緻密にに構築されていて、この世界が『コロヨシ』にもしっかりとつながっている。
1投稿日: 2018.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログバスジャックやとなり町戦争の三崎亜紀さんの作品。 この二つは昔読んだことがあったので、きっと面白いだろうと思って読んでみました。 最初の方は、つかみどころがないというか なかなか世界に入れなくて読み進めるのがしんどかった。。 後半になるにつれて面白くなったけど! たぶん難しい言葉を使おう使おうと思って使ってるから あんまり内容が入ってこなかったのかも。 設定としては、これぞ三崎亜紀作品!っていう感じの日常+非日常。 そこで暮らす人も巻き込んだ町の喪失に 立ち向かったり、巻き込まれたり、残されたりする人々の話。 ずっと東日本大震災を思い浮かべながら読んでいたんだけど これって2006年の作品なんですね。震災の5年も前とは。 登場人物はとても多くて、 立場によって考えも思いも違っていて しかもそれがどんどんと繋がっていくのは面白かった。 不幸な部分も多いけど、 人々が全然不幸そうじゃないのもよかった。 実際こんな風に大きな出来事と向き合うと人ってこうなのかなってリアルでもあり、 現実はそんな甘くなかろうにって気もする。 続編はその後の話なのか、それとも次の町の喪失の話なのか… すでに買ってあるので読もうと思います!
0投稿日: 2017.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
30年に一度、どこかの町が丸ごと人ごと消滅するという世の中。 そして町に関することは忌み嫌われて差別されるという・・ そんな町に関わる人たち同士の出会い、交錯する想い。 いろんな人たちが最終的につながっていき、この人とこの人が・・!という仕掛けがとてもよかった。
0投稿日: 2017.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ三崎さんワールド全開な話 最近は歳のせいか涙腺が脆くて困る。 そんな話 人って素晴らしい
0投稿日: 2017.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ構成は面白いもしれないが、難解で文字を追うことに疲れる本。 途中で離脱しようと思ったことがしばしば 疲れた
0投稿日: 2017.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ前提がぶっ飛んでるわけで。思いっきりファンタジーの世界なら割とすっと受け入れられるのに、現代の世界観に似ているのに、なんかちょっと違う!みたいな時に感じる違和感はモヤモヤしてたまらん。 でもそのモヤモヤが次第に癖になってくるというか。クラブでテクノをかける時にはじわーっと音程をずらしてくんだとかなんとか言ってた気がするけど、そういう感覚だろうか。
2投稿日: 2017.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ理不尽に大切な何かを奪われていく人々。 これは喪失の物語だ。 原因を突き止めるために生き残った人たちは監視下におかれる。 生きていくためには「管理局」に協力するしかない。 さまざまな実験が繰り返されデータが集められる。 その犠牲が報われる日は来るのだろうか。 三崎さんが作り上げた独自の架空世界。 けれど、その世界にだって哀しみもあるし喜びもある。 「消失」という抗えない現実に直面したとき、人々には選択の余地は残されていない。 消え去ることを知らせることも出来ず、別れを言うことも叶わない。 消失後、国家によってすべてはなかったことにされていく。 今はまだ、それだけが被害を拡大させないための方法だから。 地図からは抹消され、土地の名前を別のものに変えられる。 個人の持ち物からも写真や書籍、場所が特定できるようなものはすべて処分されていく。 消滅した人たちを想う心。 消滅した町にはせる思い。 大切な何かを「喪失」した心はどうなるのだろう。 きっと少しずつ慣れていくんだろう、と思う。 でも、慣れることはできても「喪失」によって空いた心の穴はけっして埋まることはないような気がする。 たとえ異世界であっても、喜怒哀楽の感情に共感はすることはできる。 どうすることも出来ない理不尽さに負けない希望。 明日へ、もっと先の未来へとつながる希望のカケラ。 わずかな可能性でも諦めない人間の強さが、結局は解決への糸口になるのでは?と思ったりもした。
0投稿日: 2017.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編連作。 ある日、街の人々が一斉に失われてしまう世界。 そして、そのことを悲しむ人は汚染されてしまう。 街の消滅を阻止しようとする人たちの、過去のできごとが短編になっている。 でも、肝心の街の消滅を防げたのかとか、決定的なものは何もわからないまま終わっていて、消化不良。 さんざん引っ張って終わりかよ……って気持ちになった。
0投稿日: 2016.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読んだ作家さんでした。 教えてもらって読み始めたのですが、とても良かったです。引き込まれるものがありました。
0投稿日: 2016.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年に一度、何処かの町が失われる。 正確には30年の周期で何処かの町の住人が全て消滅してしまう。 それを悲しんではいけない。 何故なら悲しむことでその人も消滅してしまう可能性があるから。 この小説の世界観を掴むまでに時間が掛かります。 ジグソーパズルのように1ピースづつ嵌めていく感じです。 それと、泣けます! 町に捕らえられそうです。 となり町戦争の時にも思いましたが、近未来でもなく異世界でもない日本? というか、そもそも日本なのか?と、思っちゃいますが、この小説を受け入れられるかどうかは、この世界を無防備に受け入れられるかどうか?ではないでしょうか?
0投稿日: 2015.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログある日、突然にひとつの町から住民が消失した―三十年ごとに起きるといわれる、町の「消滅」。不可解なこの現象は、悲しみを察知してさらにその範囲を広げていく。そのため、人々は悲しむことを禁じられ、失われた町の痕跡は国家によって抹消されていった……。残された者たちは何を想って「今」を生きるのか。消滅という理不尽な悲劇のなかでも、決して失われることのない希望を描く傑作長編。 紹介文より
0投稿日: 2015.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ序盤はまるでゲームの話みたいで、正直つまらないと思いながら読んでいたけど、あるとき突然すべての伏線がはっきりと意味を持ち始め、ジェットコースターのように話が面白くなり結果最後まで一気読み。 本を読んでてこんな体験をしたのは初めてで記憶に残る一冊になりました。
0投稿日: 2015.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2007年本屋大賞9位 ある日突然町の人々が消えてしまうSF世界で、その消失に抗う人たちのお話。 町の描写は映画でいうと"ブレードランナー"や"トータルリコール"のようだし、人間模様は"宇宙戦艦ヤマト"くらいキャラクターの役割分担が決まっているようだし、世界観の設定がビシッと定められていて非常に面白いのだが… ん~、何だろう? 突飛な世界の中でさらに(蔑まれる)特殊な人たちの話なので、対比できる「この世界での常識・美徳」が表に出てないからなのか、いまいちしっくりと来ない。 恐らく対比は読者自身に委ねられているのだろうが、感情面を除き、突飛な世界観のみを把握しようとするのが精いっぱいって感じなのかなぁ。 差別発言を「この--め!」と放送禁止用語みたいに書いてあるのは笑えたw きっと読者が持っている言葉の一番汚い単語を入れるんだろうねw エピローグから始まりプロローグで終わるので、読了後はもちろんもう一回エピローグを読み返しましたw
0投稿日: 2015.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋大賞2007年度9位。SFかファンタジーか。設定がイマイチぴんとこないのと、文章もすぱっとした切れがなくって、全体的にもったいぶってるというか、冗長というか、すごく読みにくい。キャラもぼやけてるし。まあ、好みなんでしょうが。何年か眠り続けるって話もつい最近他の本で読んだ気が。
0投稿日: 2015.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きか嫌いかでいうと、この作品ものすごく好き。 5段階評価でいうと、星五つ。 ただ、欠点も色々ある。 まず第1に会話文が下手。 会話だけを取り出して読むと、話し手の年齢も性別もまったく違った風に読めてしまうことが多々あった。 20代の彼女。40代の彼女。50代の彼女。 全く同じで、どれも私には40代のガサツなおばちゃんにしか読めなかった。 園田さんに至っては、おじさんでしょ? 最終章を読むまでは、勝手におじさんに脳内変換して読んでいた。 最終章で、園田さんは女性でなければならないと気づき、女性に戻してみたものの、会話文はやっぱりおじさんで。 30年に一度、町から人々が消失する。 どこの町が消滅するかはわからない。それは町の意志なのだという。 大切な人を消失しても、悲しむことは許されない。 悲しむと、町に付け込まれるから。消滅した町に追いかけられるから。 しかし許されないからと言って、悲しまないでいられるわけがない。 町に悟られないよう、喪失感を抱えながらそっと偲ぶ人たち。 町の消滅を食い止めるために、身を削って働く人たちがいる。 消滅した町に関わると、汚染されてしまうのだ、 人体が珪質化するという。 少しずつ汚染の毒を体内に蓄積させながら、消滅の連鎖を食い止めるために働く人たちがいる。 なぜ町は消滅するのか。 消失した人々はどうなっているのか。 説明は、ない。 なくていいと思う。 この世界を書きたかったわけではないのだろう。 この世界に生きる人たちを書きたかったのだと思う。 けれど、人々の行動に説得力を持たせるためにはある程度の世界の構築は必要で。 妙に詳しく書きすぎていたり、その割に矛盾があったり土台がぜい弱だったりして、もう少し整理したほうがいいと思った。 もっと時間をかけて練り直せば、もっと読みやすく、伝わりやすい作品になったのではないか。 それができる力量のある作家なのではないか。 そこが少し残念なところではある。 でも。 好きだ。この作品。 善人しかいない、人の生死を取り扱って感動を作ろうとしている小説なんて、大嫌いなんだけど。 痛みや哀しみを抱えながら、それでも自分の意志で誰かのために何かを成す。 甘い。甘いよ。 普段だったらそう思うはずの私が、ずっと、何か懐かしいものに包まれたように、幸せにこの本を読んだ。 読み終わって思い出したのは、高校生の時に大好きだった森下一仁の作品たち。 人の心の繊細さと冷徹な現実の按配が、多分とても似ているのだと思う。 そして、この配分が、私はめっぽう好きなのだと。 ちょっと間違えると甘々で、数値化も言語化すらもできない人の想い。 町を消滅から救うのは、人が消えた後もどこかに残る、人の想い。 消えてしまったけれど、思い出すことはできないけれど、無くなりはしない人の想い。 それをつないでいくことの意味。 “人には決して癒されえぬ悲しみや苦しみがあることを知る音だった。それらを抱えたまま、それでも進んでいかなければならないという貫くような意志と想いが託されていた。” “人は失われても望みは受け継がれてゆく。決して失われないものもあるのだ。” 物語は、ハッピーエンドとは言えないかもしれない。 けれど私はこの世界、閉じた環ではなく、上昇していく螺旋と信じたい。 少しずつでも。 3.11より前に書かれた作品。 読む人によっては拒否反応を起こすかもしれない。 それでもいつか、時が充ちたら、この作品を読んでほしいと思うのだけれど。
0投稿日: 2015.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログループするかのような構成で何度読んでも泣ける。 始まりも終わりもない中での主人公たちの奮闘や強く生きるさまが伝わってきてとても良い。
0投稿日: 2014.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
抗うというのが、テーマになっている小説だと思った。 自分の町が汚染地域と呼ばれる苦痛という表現に、いま日本に存在するそういわれてしまっている地域に人の苦痛を思った。 震災をテーマにした本ではないけれど、震災でも山の噴火でも、原子力発電所があったりマグマがあったりする以上、完全に安全ではないことを織り込み済みで、居住しているんだと思う。大人は。 町が意志をもって町を失おうとしている小説の入りでぎょっとしてしまうけど、それは小説の設定で内容の中心ではなくて、冒頭に述べたように、どう抗うかというのが、この小説のテーマだと思った。
0投稿日: 2014.10.05喪失と再生の物語
具体的に書かれているけれども、全く訳が分からない世界、という三崎さんの小説は絶対に他人にはお勧めできない作品ですが、個人的には大好きで堪りません(笑)「喪失」と「再生」という曖昧模糊としてはかない「感情」をこれほどユニークに表現出来る人はなかなかいないのではないでしょうか。自分にどれだけ引き寄せて読めるのか、といつも考えながらの三崎さんの小説との格闘をこれからも続けられればと思います。
2投稿日: 2014.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログSF苦手なので読むのにものすごい時間かかった。 感動できるけど、世界を想像できないからなかなか大変。
0投稿日: 2014.05.05摩訶不思議な三崎ワールド
少しずれた世界で起こる「町消滅」に翻弄される人々。何故起こるかなどの説明がないので相変わらずの不親切な設定ではありますが、唐突に愛する人を失った人々が理不尽な運命に抗い再生しようとする物語を作者は描きたいのだろう。「町消滅=自然災害」に置き換えてもぜんぜん読めるしね。しかしどんどん広がる三崎ワールド、この奇妙なる世界が今後どこまで広がるのか楽しみだ。
1投稿日: 2014.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議の不思議。 読み始めて、どんどん読んでいける、引き込まれる。 でも、はっきりとわからない。バラバラの話。 特に私は最初に出た登場人物の名前を覚えないので不思議に輪がかかる。 でも、最後にすべてが繋がる。そして一番最初の章を読み返す。 すべてが納得! 不思議、そして面白い本。 私は好きだ!
1投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ町から人だけが突然消えてしまう。 それに抗おうとする人々。 見えないけれども確かに存在する大きな力。それに立ち向かおうとする人。そのドライビングフォースは、突然人が消えてしまうという悲しみの連鎖を止めたいと思う気持ち。 自分の存在の小ささを嘆きつつ、何かをあきらめることもできない。でも向かうべき方向が見つからない。
0投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「まち」には意志がある、という観点から広がっていく物語。1つの町を中心に年代も場所も境遇も異なる人達が成長し、最後にはとある場所に集い、思い新たにする。
1投稿日: 2013.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ決して嫌いな話ではないが、長くて時間がかかった。かなり細かい創造設定が盛り込まれている。(消滅/消滅耐性/分離/別体/汚染/音/珪化/消滅順化/澪引き/管理局/感情抑制/居留地/回収員/余滅/残光etc.)「となり町戦争」を途中で断念した経験があるけれど、どんな本なのかを少し想像できる材料になった。丁寧な文を書く人で、丁寧な文は嫌いではないのだけど何だか疲れてしまう。ゆっくりゆっくり読まれるべき本なのかもしれない。私が一番この話で寂しくなったのは、失われる人々より、章が進むにつれ時の経過によって自然に亡くなる人がいるというところだった。舞台が一緒の小説があるらしいので機を見てそちらの方も読もうと思う。情景がよく浮かぶ。灰色とか、青とか、硬質な薄水色の。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年に一度、どこかの町で住人の消滅が発生する世界のお話。 短編が7話で同じ世界で登場人物も繋がっています。 消滅を阻止しようと奔走する人々のお話ですが、三崎作品らしく、「消滅阻止」が話のメインではない。 登場人物たちの葛藤や後悔、そこから未来へと進んでいく姿が細やかに描かれています。 いきなりエピローグで本体やら汚染やら書かれていてなんのこっちゃでしたが、読み進めてこの人エピローグに出てきたな!と戻って確認するもの楽しかった。 最後の?プロローグもあーここも繋がっていたのねとちょっと切なくなりました。 「消滅阻止」がメインではないとはいえ、月ヶ瀬の次の消滅は防げたのかな。気になる。 2013/07/29-08/04
0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「もしも町の人間が一瞬で消滅する現象が存在するなら」を とことん突き詰めて創造されたような群像劇。 失われた町の情報が含まれる活字や、 消滅から免れた人々は 「汚染」の発信源となり(もしくはそう噂され)、 残された人々を苦しめる。 町の消滅現象は1回きりではなく、 数十年のスパンで国内のどこかで発生する。 残された人々は消滅の再発を防ぐため、 次回の消滅のときに備える。 同じ作者の作品、「刻まれない明日」も 同じ世界観で同様のテーマを扱っている。 今度は両作品を読み比べて時系列の整理や 登場人物や地名などの共通点を 見つけていくのも面白いに違いない。 「艫取りの呼び音」は三崎作品の世界観を知るのに 格好の話だった。
0投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ設定、描写が難しく理解しにくい部分はある。でも人の想いがとても丁寧に描かれており、琴線に触れる箇所が多々ある。
0投稿日: 2013.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
エピローグで始まるのはやめてほしい。登場人物も背景もわからないので、まったく頭に入らない。結局、後から読み直して初めてわかる。まあ、数ページだからどうでもいいけど。 数十年に一度ある町の中に住む人が消滅する世界で、町の消滅を調べ、できればその消滅を回避しようとする管理局と、その周りの人たちの話。世界の終りとハードボイルドワンダーランドのような印象をもった。
0投稿日: 2013.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いんだと思う。 けど わからないことが多すぎて消化不良。 もっとじっくり集中して読めばよかったのかも。 【再読】 消失した町の傍で生きる人たちの話。 『刻まれない明日』を読んだから再読。 どうせならこっちを先に読んでおきたかったかな。 2冊あってようやくそれなりに理解できたような気がする。 強化誘引剤とかハンドルマスターとかって他の本でも出てきたかな? 読んだ端から忘れていくのってなんだかな。。
0投稿日: 2013.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ突飛な設定に思えるが、現代社会にもどこか通じるものがある。なぜかエヴァンゲリオンを思い出した。評価が難しいけれど嫌いじゃない。残された人のエピソードは3/11の地震に繋がるものを感じて、心が痛くなった。
0投稿日: 2013.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログプロローグそしてエピローグで始まる。わけもわからず全然未消化のまま突き進む。結果的にはこれが良かった。朧で曖昧なままでイイのである。章が進むほどに全貌が明らかになっていく。つれてエピローグを読み返す楽しみもますます膨らんでいく。人が替わり舞台が替わり時間も変わる目まぐるしさが目を釘付けにする。息詰まる静かで熾烈な戦い。最後まで飽きることなく楽しんだ。理由もなく命が奪われることも世の中にはある。理不尽を感じながらも人は欠落した断面の手触りを日々確かめながら、それを日常として歩き続けなければならない。定めとか運命ではなく自ら選び自ら切り拓いていくことこそ大事。何があっても現実を肯定し生き続けること。たとえ明日なくなる命であっても、その直前まで自分の為すべきことをして生き続ける。犬死などというものはなく、信念をもって当たればきっと誰かが意志を繋げてくれる。自らを信じて生きていきたい。それぞれの役割を真摯に貫く登場人物の姿を見ながら改めてそんなことを思った。
0投稿日: 2013.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだかよくわからないんだけど、ストーリーの中の規律に縛られていく。 思想に追われていく。 なんとなく引き込まれる作品。 --- ある日、突然に一つの町から住民が消失した--三十年ごとに起きるといわれる、町の「消滅」。不可解なこの現象は、悲しみを察知してさらにその範囲を広げていく。そのため、人々は悲しむことを禁じられ、失われた町の痕跡は国家によって抹消されていった……。残された者たちは何を想って「今」を生きるのか。消滅という理不尽な悲劇の中でも、決して失われることのない希望を描く傑作長編。
0投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この作者って男だったのね~! 「あき」なんて女の名前だから、固定観念で女だと思ってしまった。 まず、それに驚き! でも読んでみて、「あ~、これは男の人が書いた本だな~」って感じた。 これは、とっても濃厚なSFファンタジーです。 でもミステリっぽくて、ドラマであって、SFなのに現実的なところもあって、とっても不思議な感じがする設定。 なのに、なぜかしっくりいってしまう。。。 『町が消える』という超非現実な設定なのに、その構成がちゃんと出来ていて、何故か読んでて納得してしまうの。 そして、最後、登場人物が一つの線でつながったときは、何かが頭の中で弾けたような感覚。 この著者の頭の中はどうなってるんだろう。と思う。 町の消滅を阻止するために、汚染されながらも実験台にされながらも感情を抑制しながらも、消えた町と格闘する人たちのお話。 なんか、こんなこと絶対に起こるはずないのに、「自分がもしその状況におかれたらどうするかな~?」ってついつい考えてしまう。 一人一人の儚い思いがひしひしと伝わってきて、じーんときた。 でも、一つだけひっかかるところが。。。 のぞみが、 「障害者や老人を「不幸な人」と決め付けて、『幸せ』な自分が施しを与えるような感覚がきらいだった」 って部分。 わかるよ~、こういう気持ち。 でも、これが全てじゃないと思うんだよね。 最後のほうで、 「誰かのために生きるなんてまっぴら」 て書かれてて、「自分のために生きなくちゃ」みたいな終わり方だったんだけど、でもそれはちょっと違うような~。 「誰かのために何かをすること」それはとってもいいことだと思う。 そして、「自分のためにも人生を生き抜くこと」も必要だ。 みたいに肯定してもらいたかったな。 ちょっと最後のエピローグでガクってきてしまった。。。。
0投稿日: 2012.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ文体なのか 森博嗣氏の「スカイクロラ」シリーズに似た匂いを感じた 淡々と少ない言葉の描写だからこそ 登場人物の行動の裏の切なさが滲み出ていて良かった アニメ化したら ハマりそうな作品
1投稿日: 2012.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構厚みもあって、物理的にはボリュームのある本だと思うけど、内容的にはそんなにボリューミーには感じなかったです。 ひとつの町から住民が突然消えてしまうという、町の「消滅」。 その仕組みを解き明かそうと、次なる「消滅」に抗うため、立ち向かってゆく人々。 残された人々は、どう生きてゆくのか…。 世界観や物語の設定は、なかなか奇抜でおもしろいと思います。 多くの登場人物が、その語り手を変えながら次々とクロスしてゆくのもいいし、 最初にエピローグ、最後にプロローグへと繋がってゆくのもおもしろい。 実はプロローグで既にすべてが詰まっていたんだと、読み終えて気づきます。 きっと2回目に読んだときにもっといろんな発見が出来そうな本だろうな。 ただ、なんとなく文章の語り方が、自分と合わない気がしてしまい、なかなか入り込めませんでした…。 「となり町戦争」を読んだときは、そんなに思わなかったんだけどな。 ちょっと残念。
0投稿日: 2012.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し難しかったけど、たくさんの登場人物が出会いで繋げていく感じがすごかった^^ 町に汚染されるとか発想がすごい。 そしてこの人が書く女性はなんかセクシーだな…
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ町が突然消える。 その虚構に基づき忠実に書き上げた一冊。 あなたは町が消えた、となるとどんな障害を予想しますか? それ以上の障害がこの本には書いてあります。 私が保証します。絶対。まあ、読んでみてください。 ちょっと(ってかかなり)気分暗くなりますが面白いですよ。
0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ町が失われる?設定が難しい。急に消失してしまう理不尽さ、愛する人を失う喪失感、しかし、悲しみの感情は出してはいけない。人はどんな心で生きて行けばいいのだろうか。
0投稿日: 2012.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ始めは、硬い難しい言葉が続き、スムーズに読み進められず、苦労したが、次第に独特の世界観に飲み込まれていきました。エピローグに到達する頃には、プロローグの内容は、すっかり抜け落ち、再度プロローグを読み返し、改めて納得。なんだ!初めから到達する先を知ってたんだって、思わず苦笑い。でも、嫌いじゃなくて、好きな感じ。
0投稿日: 2012.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
30年に一度、とある町から住民が一度に消えてしまう町の「消滅」。これがいつどこで起こるのかまでは解明できたものの、国家も研究者も、誰もこの消滅を止めることは出来なかった。 一瞬にして消えた月ヶ瀬の町。 町に愛する人がいた人。 偶然にも消えずに残されてしまった人。 生きている人たちは不可解な町の消滅に恐れ慄き、話題にすることすら避けるような空気があった。 その消えた月ヶ瀬にまつわる7つのエピソードが語られる。 最後まで読んでからもう一度最初に戻って「プロローグ、そしてエピローグ」を読むと、おお~!!となるのでぜひ。 逆に、最後の「エピローグ、そしてプロローグ」は 月ヶ瀬が失われる直前の様子が描かれている。
1投稿日: 2012.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ町の消滅とそれに関わる人たちのお話し。 著者の他の物語と同じくバラレルワールドな舞台設定。完全に異世界なのに説明なしで進行するから、一歩間違うと意味不明な前衛になってしまうが、今回もギリギリ踏みとどまった。 だけど今回は本当にギリギリ。西域の描写のあたりからそっち向きの描写が楽しくなってしまった様子。 まぁ量もあるからそれぐらいのアクセントが必要だったのかも。
0投稿日: 2012.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと気合の入りすぎた感じ。 文句なく面白いのだが、設定が複雑で、入っていくのが困難。 文体も硬いので、馴染むのに苦労する上、このボリューム。 詰め込み過ぎの感。 とはいえ、喪失感は心地よかった。
0投稿日: 2012.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
となり町戦争を読んで、三崎さんの書く設定が面白いと思って、続いて読んだ本。 30年に一度、町に住んでいる人が失われる。 消えた町に関する「人の思い」は全て回収して、いなくなった人の事を悲しむ事も禁じられる世界。 暗い、重たい、設定ではあるけど、独創的で面白い。 それに、町の消滅と奮闘する人たちの、お互いを思いやる気持ちが暖かくて素敵。 ------ 2度目の読了 久しぶりに読んでみたけど、日常の中に実際にはあり得ない現象を描いていて、それを想像するのはなかなか難しい。 設定に入り込むのがなかなか困難。 特に最初が、プロローグ、そしてエピローグというだけあり、この章だけでは理解出来なくて世界に入り込めない。 個人的にはエピローグ6からが、人々の繋がりも増えて俄然面白くなる。 読みきったらまた最初に戻って、その章がようやく理解出来る。 最終的に、町の消滅を食い留める事が出来たのか?それ自体は分からないけど、もし出来たとして。 その次の消滅を食い留める手立てはあるのか、思いをつなぐ人達は?と疑問も浮かんだ。
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとなり町戦争やバスジャックよりこちらの方が好みだった。 相変わらず独特な世界観と設定で、前に上げた二冊よりそれが確立しているように思う。
0投稿日: 2012.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い設定なんだけど、わかりにくく感じます。登場人物の心理描写が、繊細に描かれてました。 でも、僕にはあわないかな。
0投稿日: 2012.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年ごとに起きる「町の消滅」に関わる人々の物語。町の消滅って何?とか、失われた人を悲しんではいけないとか、「失われた」は「喪われた」ではないの?とか、そういうことにおろおろしながら、その「おろおろ」を楽しめる本。 この作家さんの作品を読むのは、『となり町戦争』以来。結構な厚みがあるのについついページが進むのは、淡々とした語り口でスムーズに読めるのと、先を知りたいという気持ちにさせられるせいだろう。 読みやすく、しなやかで肌触りの良い作品だと思った。
0投稿日: 2012.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年に一度、突如1つの町の人々が消失する。意志をもった「町」と消失を食い止めようとする残された人々の戦いを描いた1作。
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログヒロインの性格の描写が好き。世界観が良い。一方で、序盤の説明がかったるいのと、終わった後も疑問に思う描写が残る。コンテンツよりもデリバリーの悪さが作品の完成度に足を引っ張っているような気がした作品。世界観は良い。
0投稿日: 2012.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログだんだん三崎亜記の世界にはまってきた。重ねられたエピソードが、町の消滅への静かな戦いと、それに立ち向かう人々の思いを積み上げる。人によって好みはあるだろうが、自分は「終の響い」が好き。泣けるよ。
1投稿日: 2012.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ突如人だけが消えた町に関する、それに関係していく人達の 『記録』と言った方がしっくりくる気がします。 その町に関係するものは片づけられ、その町に住んでいて その『時』に居なかった人達は、町の『人達』の記憶がなくなり…。 そうなった場合、どうするのでしょうか? 大事な人の記憶がなくなる、というのも嫌ですが それすらも分からなくなる、というのも辛いです。 それに関係する差別、その仕事をするにあたっての辛さ。 そして、それに対抗する事ができる人。 どれもこれも、そうだね、と頷く事が出来るもの…という事は すごく共感できる状態、なのかと。 関わり合いになる人が狭い範囲でいるためか、あちらこちらに 同じ人が出てきます。 エピローグでありプロローグ、プロローグでありエピローグ。 確かに、でした。
1投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ設定はおもしろいのになー。 バスジャックみたいな、短編の方がおもしろかった。 エピソード5がひどく浮いてる。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ初、三崎亜記。 小難しくて、繋がりを理解するのに時間かかって、 それでもこの世界観は好きだと思えた本。 意味わからないまま読み進めた部分もあったけど。 失われた人を悲しんではいけないって、無理。 写真も全部没収って、無理。 悲しい世界だった。 もう一度読みたいと思う。
0投稿日: 2011.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ作品の全体の雰囲気は暗く落ち着いているのに、展開やセリフまわしが非常にベタで痒かったかと思えばどうにも脈絡のない展開になったりと、全体の雰囲気がチグハグしている。題材は面白いのに勿体無い。
0投稿日: 2011.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ深い。限りなく深い。 想像力を限界まで駆使させる話だ。 人の想いを紡いでいく沢山の登場人物達。連鎖する様々な想いが複雑で深遠なる物語を構成していく。 エピローグまで読み終え、改めてプロローグを読み理解が深まるエッシャーの騙し絵のような話の構造。 正直、理解出来ない部分も多々あったが、いつの間にかその世界観にズブズブと引き込まれていった。 不思議と心地よい小説だ。。
0投稿日: 2011.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の評価基準 ☆☆☆☆☆ 最高 すごくおもしろい ぜひおすすめ 保存版 ☆☆☆☆ すごくおもしろい おすすめ 再読するかも ☆☆☆ おもしろい 気が向いたらどうぞ ☆☆ 普通 時間があれば ☆ つまらない もしくは趣味が合わない 2011.7.29読了 あまり面白くなかった。 面白くないのは、趣味が合わないからだが、登場人物の関係性の構成に矛盾があり、そこも売りのひとつと思われるが、これでは、成立しない。それも、町の力だ、と言われると、そうですかと言うしかないが。 何か、作者も無理して書いている様に思えるのは、気のせいか。 となり町戦争はすごく面白かったのに、ちょっと残念。 なお、自費で文庫本を購入したので、ちょっと辛めでした。
0投稿日: 2011.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログある日突然、ひとつの町から住民たちが姿を消す。大切な人を失った人々が、何を思い、何をするのか。 ありえない設定からどんなふうに話が展開していくのか、興味深く読み進んだのだけど、ありえなさすぎて途中でチョット疲れちゃった
0投稿日: 2011.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと長い本読んでみよーと思い立って本屋を探したら三崎サンの本が… 「となり町戦争」がおもしろかったのでここでも購入。 ちょっと難しくて理解に苦しんだけど最後までしっかり読み切ればおもしろさがわかる本。やはり現実と非現実を交差させるのが相変わらずお上手です。今回のがミステリー要素満載でした。 次作に早くも期待です。
0投稿日: 2011.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ切なさの中にある温かみを感じられる作品であると思う。そして、これからの小説の世界を想像できる作品。 暗い雰囲気ではあるが悲壮感は不思議と感じなかった。暗い雰囲気であるが故に、暖かな雰囲気の場面が引き立っているのかも。 この作品に出てくる登場人物は羨ましいほどに皆強い。
0投稿日: 2011.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログそれぞれの胸に様々な思いを抱いて、「町の消滅」をくいとめるために戦い続ける彼らに、「心安らぐ日々が訪れますように。」と祈らずにはいられない。 冒頭から、その戦いの真っ只中が描かれ、最初は訳もわからないまま読みすすめていった。 長編というより、連作短編(もしくは中編)の形式で描かれる、長い長い戦いの記録を読んでいくうちに、だんだんと今の状況や各人物の相関関係が明らかになってくる。彼らの熱い思いも。 最初は我慢が必要かもしれないが、個人的には、エピソード1の途中からどんどん話に引き込まれ、読み終えることができた。 他の方のレビューにもあったが、直後にもう一度読み返したくなった。もどかしさが残る点もあるものの、それも含めていい物語だと思う。
0投稿日: 2011.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろい。 だからもう少しこの世界の話が読みたいと思いました。 過去に失われた町とこれから消滅を防ぐ町のことと2篇。 読みたいなぁ(((o(*゚▽゚*)o)))
0投稿日: 2011.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ■先週の千葉出張で読了。特に状況設定や環境設定がかなり抽象的な表現だったり、時に強引と感じる(というか説明なしでいきなり..という)ような展開も多く、なんかモヤモヤしたまま読み進めていくことになるんだけど、ストーリそのものがとても魅力的なのでついつい読み耽ってしまう作品。って書くと否定的なコメントが先行して聞こえるかもだけど、ぶっちゃけ相当面白い。読み始めると他のことができなくなる危険性大。いや、マジで。 ■三崎作品は『となり町戦争』『バスジャック』とシリアスなストーリでもどこかほのぼのとしたホっとさせるようなところがとても好みなんだけれど、この『失われた町』はそれらとはかなり毛色の違う作品になっている。あえて例えるなら少し恩田ワールドにも繋がっているようなベクトルかも。
0投稿日: 2011.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
世界観は良かった。しかし、詰め切れていない感は否めなかった。町の消滅で生き残った人が受ける扱いは今の放射能に対する反応と酷似していた。
0投稿日: 2011.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ喜怒哀楽は確かにあって、でも静かで、全体的に冷たい雰囲気を纏いながらも温かい思いが忘れられません。読み終えた今でもこの独特すぎる世界全てを把握できる気がしませんが、でもそれでいいような気もします。どこで知ったのかも忘れて正しい使い方である自信もないのですが、「不在の在」という言葉がぴったりの作品だと思います。
0投稿日: 2011.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の特徴である「あり得ない設定の日常の中で生活する普通の人たち」という構成は健在であるものの、「あり得なさ」が他の作品より頭抜けており、SF的な内容となっています。人物描写が魅力的で、かつ細部まで細かく配慮された設定など素晴らしいと思いますが、私が読んだ三崎作品の中では最も長編であったことも手伝ってか、少し疲れる読了感でした。初めて読むのが本作品ならもっと評価が高かったかも知れません。
0投稿日: 2011.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログややたいくつ。 話が集合してくる最終章あたりは読みやすいけど、なんというか登場人物が重なりすぎていて、閉塞感を覚えずにはいられない。登場人物が絡み合うということを適切に扱えていない。加納朋子を髣髴とさせられる。 本の構成のように、エピローグとプロローグだけに力が入っていて、それ以外が疎かになっている感じがする。読み終わってみれば、少しもったいないようにも思われる。 となり町戦争よりパワーダウンしてないか?
0投稿日: 2011.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ三崎亜記sanは初めて読みました。裏表紙のあらすじで一目惚れだったのですが・・・期待をしすぎてしまったのか、人物の関係性や会話が複雑すぎて少し疲れてしまいました;;【2007年本屋大賞9位】
0投稿日: 2011.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今朝から読み始めたけれど、まず暗い物語の始まり方が今朝のさわやかな朝日に全くそぐわない。読み進めてみよう。
1投稿日: 2011.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログある日、突然にひとつの町から住民が消失した─三十年ごとに起きるといわれる、町の「消滅」。不可解なこの現象は、悲しみを察知してさらにその範囲を広げていく。そのため、人々は悲しむことを禁じられ、失われた町の痕跡は国家によって抹消されていった…。残された者たちは何を想って「今」を生きるのか。消滅という理不尽な悲劇の中でも、決して失われることのない希望を描く傑作長編。
0投稿日: 2011.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ町が突然、消滅する話。 最初は、何がなんだかさっぱり。 読み進めるうちに、何となくわかって、最後は一気に読める。 最後まで読んでもう一度、最初を読むといいかも。
0投稿日: 2011.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解ができるまでは「???」だったが、理解できてからは一気に読み終わった。読み終わった後、改めてプロローグ、エピローグを読むと、胸に響くものがあります。
0投稿日: 2011.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に恐ろしい本だと感じた。 あえて恐ろしいと表現しよう。 無条件に無差別に、失われていく自分の存在。失われる大切な人。 それに対し何もすることができない。あまりにも理不尽な「消滅」 そこに、希望はあるのか? 最初はいきなり説明もなく物語が始まるので、戸惑うが、読み進めていくうちに止まらなくなってしまった。 そもそもこの物語は、設定について完全に理解して読み進める必要のないタイプのもの。 設定世界観が素晴らしいので充分楽しめると思う。 圧倒的な世界観がこの作者の、この本の魅力だ。 しかし、何故人々が失われるのか、その理由は最後まで明らかにされず、自分で読み解くしかない。 様々に張り巡らされた伏線、そして希望からの、何やら不穏なラスト。 まさに、ご想像にお任せします状態。 それがこの本のもう一つの魅力である。 とりあえず、もう一度今度は自分で購入して読むことにする。 まだ全て理解できたわけではないし、初めて読んだときとは違う世界に浸れるに違いない。
1投稿日: 2011.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『となり町戦争』『バスジャック』と読み進め『失われた町』を読み終える。わりと好き、たぶん好きなんだろう、著者、三崎亜記の不思議な世界観が良い。☆4つじゃないのは、これから出るであろう著者の新刊に更なる期待をしているからだ。これからも読み続ける作家だと思う。 ふと頭によぎるのは、2006年有川浩の『図書館戦争』に感じが似てるってこと、それで『となり町戦争』を調べると2005年1月5日発行日となっているので、三崎亜記が、この手のお話しの元祖なのだと一人納得する。有川浩については、一作しか知らないし、それもアニメを観ただけなのではっきりとは言い切れない。なので、有川浩の自衛隊三部作を読まなければいけない。この様に読書の楽しみは尽きることはない。
0投稿日: 2010.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ三冊目の三崎 亜紀作品。 この人の書く話はストーリーの根幹をなす 大前提がかなり「異常」(^ ^; 前二作を見ても「となり町と戦争が始まった」だの 「バスジャックがレジャーとして定着している」だの(^ ^; 今回は「ある日突然町の人が消滅する」というもの。 町並みは残っている。道路も建物も信号も無傷。 ただその町に住んでいた人たちだけが 何の痕跡も残さず忽然と消え失せる。 何十年かに一度のペースで起こる町の「消滅」。 消えた町は、放置しておくと近隣にまで「汚染」が進み、 消滅の「連鎖」が起きるとされている。 その連鎖を断ち切るため、消えた町の名や住民の痕跡は 跡形もなくなるまで「回収」され、地図からも消される。 が、ごくまれに消滅を免れる人が現れる。 また「消滅の日」に町の外に出ていて 消滅を免れる人もいる。 残された者たちは、失った者を思い出すことはできるが、 決して悲しんではいけない。悲しみの気持ちは 町の「汚染」を許してしまうから。 ...と、ざっと話の大筋を説明するだけでこんな字数が必要(^ ^; さらに、いつの時代ともどこの国とも分からない独特の世界。 三崎氏独特の造語による、分かったような分からんような説明(^ ^; も、ね、最初のうちは何書いてんだかさっぱり(^ ^; 訳分からん設定の中で、訳分からん言葉が解説無しに使われ、 もの凄い「取り残された感」から始まる(^ ^; 物語は、色々な形で町の消滅に「関わっている」人を中心に、 登場人物ごとのエピソードを紹介する形で進む。 愛する家族を消滅で失ってしまった人。 町の消滅を事前に予知し、食い止めようとする人。 消滅した町の中で、ただ一人生き残った「消滅耐性」の子。 それぞれが、それぞれの思いを抱いて、日々を生きている。 喜び、悲しみ、決意し、諦め、怒り、赦し...と言った感情は 我々と少しも変わることはない。たとえ異常な設定の中でも。 だから読み手は、素直に物語として感情移入できる。 これはもしや、かなり良質な「人間物語」なのかも。 町の消滅を、字義通りに受け止めると荒唐無稽だが、 例えば政治的な思惑によって国が南北に分断されたとすると、 境界線の向こう側は「消滅した」と同じような状況なのでは。 また町一つ、何万人も一度に消えるというのはSFでも、 突然で理不尽な別れというのは、現実世界でも、ある。 戦争、天災、事故、無差別殺人... 近しい人を「失って」、やり場のない思いを抱きつつ、 「日常」を送っていかなければならない人は、少なくなかろう。 三崎氏は書く。 「その音色は、単なる『癒し』ではなかった。 人には決して癒されえぬ悲しみや苦しみがあることを知る音だった。 それらを抱えたまま、それでも進んでいかなければならないという 貫くような意志と思いが託されていた。」 「町の汚染」によって言葉と記憶を失った男性が、 古奏器(古楽器のことらしい)を奏でるシーンだが、 正にこの「苦しくても悲しくても、生きていかなければ」 ということがこの本のテーマなのではなかろうか。 ...ってなことを、ついうっかり真面目に考えてしまう(^ ^; もしかしたら、当人は「壮大な悪ふざけ」のつもりで 書いたのかも知れませんが(^ ^;
0投稿日: 2010.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年に一度、街が人を消す。街に汚染される。その街の名前を見てはいけない。失われた人を悲しんではいけない。 ...という斬新なストーリー。発想は面白かったんですけど登場人物や用語や設定がちょっと漫画っぽいかなーと。エヴァンゲリオンの世界観が好きな方にはオススメです。
0投稿日: 2010.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ【10/11/03】 町が町に関連する全てを消滅させるという内容はとても新鮮でした。想いを繋げて後世に繋げていく。それは全ての人が出来る訳ではなく、意志の強い人間だけが実行できるようなもの。となり町戦争同様、独特な世界観のお話だったように思います。
0投稿日: 2010.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ抗えない運命と悲しみの中でも、力強く未来に向って生きようとする人々の美しさに感動。カミュの「ペスト」に描かれた不条理な世界、宮崎駿の漫画「風の谷のナウシカ」のナウシカが物語の最後につぶやく「生きねば・・・」というセリフが頭に浮かんできた。
0投稿日: 2010.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログP109 雑誌を開くのも忘れ、魅入られたように写真から目を離すことが できなかった。決して心地よくはない、かといって不快というわけ でもない、形容しがたい奇妙な感覚に支配される。 何かのオブジェか彫像を写した写真のようだった。審判の時を 待つような孤高な荘厳さがあり、同時に、慈悲深きものの懐に 包まれるかのような安寧も感じられた。 ハッとして窓の外に顔を向ける。そう、それは目の前の公園 からの見慣れた風景を、まったく違う視点で P223 「私を好きになってもかまわないの。でもね、あくまであの子の 『代わり』として好きになってほしいの」 P411~P412 「脇坂さん。俺、一応女性経験豊富なつもりだったけど、何で好きに なった奴とは分かり合えないんだろう?」 「人と人とが分かり合えるわけがないだろう」 ・・・ 「確かなことなんか何もないんだ、人と人との間には。たとえ好きに なった者同士でもな。いや、分かり合いたい相手ほど、より多くを 求めてしまい、結果、分かり合えない部分はより一層増えていくもんだ」 「じゃあ、どうすりゃいいんですか?」 「信じ合える部分、求め合える部分を見つけることだよ。それが一つ でもあるならば、何があっても心が離れることはない」 P436 「 ☆きっかけは八方美人な書評を読んで。 読了日:2010/11/01
0投稿日: 2010.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ相変わらず三崎さんの世界観は解りにくい。 でも、最後にそれぞれの希望と絆が確認できて救われた。 どんなところにも、幸せはみつけられるんだね。
0投稿日: 2010.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編集かと思いきや、全てが繋がっている。 時間が前後しているので、人名だけは確実に把握しておこう。 30年に一度(だったかな)ある日突然町単位で住民が消滅するという事象が置き、その町の住人に関係する人たちが、突然の家族の、恋人の、知り合いの消滅に戸惑い悲しむ。 そんな関係者達がつながって、お互いに気持ちを乗り越える道を見つける。
0投稿日: 2010.08.24
