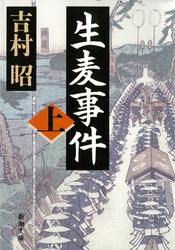
生麦事件(上)
吉村昭
新潮社
開国か、攘夷か。揺れる幕末を直撃した、世紀の殺傷事件!
生麦事件。 歴史の教科書では、幕末に起きた一事件としてあっさりとした記述で触れられる程度の 出来事に、当時の国内の政治状況を未曾有の大混乱に陥れた経緯があった事に驚かされる。 日本の作法を遵守すべく、外国人を処断した薩摩藩。 慎重の上にも慎重を重ね、外国を刺激しないように配慮していた江戸幕府。 この事件を契機に、薩摩-江戸の亀裂は深まり、やがてそのうねりは、 倒幕、明治維新へと繋がっていく。 その序章は、この事件ですでに始まっていた事を思い知る。 国家の威信を保ちつつ、諸外国と渡り合って いくには、どうすべきか。今に変わらぬ、この難問に、苦心惨憺した 当時のすべての先人達に、尊崇の念をいだかせる。 坂本龍馬、だけが幕末ではない、と勉強させて頂いた一冊。
1投稿日: 2013.11.24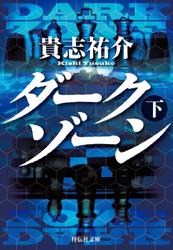
ダークゾーン(下)
貴志祐介
祥伝社文庫
運命の第七戦、勝利を手にするのは?!
上巻を読まれた方へ。 突然、理不尽な異空間へ投げ出され、王として戦いを指揮する事になった主人公。 初戦の敗退に動揺するも、体制を立て直し、冷静な判断力で敵と互角に渡り合い、 戦いは最終局を迎える。 将棋世界が具現化された、奇妙な極限状態で、最終的に勝利するためにはなにを成すべきか。 味方に多大な犠牲を払ってでも、敵の王を討ち取ればよし、 最小限の犠牲でも、自分が討ち取られれば 即、敗北。戦闘に興奮し、また逡巡し、苦悩する主人公から目がそらせない展開が続くなか、ついにこの世界の謎が明かされる、、、。 この種明かしに対する批判もあるようだが、それは、枝葉末節であろう。 本作は素直に、このような状況になったら、自分は勝利できるのか?!、 とハラハラしながら楽しく読み進めるのが、作法であろう。
0投稿日: 2013.11.13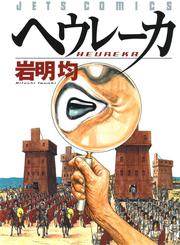
ヘウレーカ 1巻
岩明均
ヤングアニマル
見たことのない歴史漫画、を読む楽しみ。
かの有名な寄生獣、そして現在連載中のヒストリエでご存じの方も多いと思われる岩明均氏の 古代ギリシア・アテネの世界を描いた、読み切り歴史漫画。 歴史好き以外には、あまり馴染みのない時代、世界観でありながら、 戦記モノとしての魅力、群像劇としての魅力を存分に内包し、一気に読ませる 作品となっているのはさすが、である。 そして、このような濃厚な人間ドラマがあった彼の地は、現在 草に覆われた地中海の遺跡として、ひっそりと佇む、という描写で 締めくくられるあたりに、なんとも言えない、人の世の無常観、切なさが漂う。 それでも、どんな時代でも、おかれた環境で人々はそれぞれ精一杯生きてきている訳であり、 現在の視点から、彼らの判断に善悪の裁きを加えるのは、大変に僭越な事と知るべき。 氏の本作は、歴史に対してあくまで中立の立場で、登場人物への分け隔てない やさしい眼差しで、いきいきと人物が描かれている。今どきの言葉遣い、の会話も テンポ良く読ませるための、工夫であろう。このあたりもさすが、である。 歴史漫画、かくあるべし。 愚かしくも、愛おしい、そして切ない・・・人間ドラマ。氏の筆致が冴え渡る。
3投稿日: 2013.11.10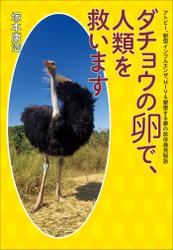
ダチョウの卵で、人類を救います アトピー、新型インフルエンザ、HIVも撃墜する夢の抗体発見秘話
塚本康浩
小学館
溢れる、ダチョウへの愛!
人類を救います、という大層なタイトルに眉をしかめつつも、 抗体開発なるテーマを扱う科学本という事で、食指を動かされて 手に取った一冊。 なぜ、ダチョウなのか。幼少時から、鳥が大好きで、鳥の研究に 邁進する事を決めた著者にとって、ダチョウによる抗体研究は ライフワークとするにふさわしい、ある意味天職であったと 思われる。 一時期、大学院生として免疫学の研究に携わった身である自分に とって、研究の世界の悲喜こもごも、に深く共感できた次第。 もちろん、物語としても、十二分に楽しめる展開で、ダチョウの 卵由来の抗体の更なる可能性に胸躍らせながら、一気に読了 できる事、請け合い。 全編を通して、溢れるダチョウへの愛、研究の成功への使命感、 など著者の誠実な人柄が忍ばれ、さわやかな読後感に包まれる。
2投稿日: 2013.11.08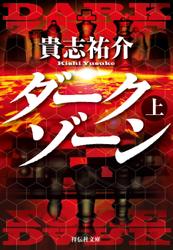
ダークゾーン(上)
貴志祐介
祥伝社文庫
貴志祐介、待望の新刊!!
お前は、赤い軍団の王だ。味方の戦士を指揮して、戦いに勝利せよ。 唐突な始まりから、一気にこの特異な世界観に引き込まれる。 最近では、人気俳優が主演した悪の教典、の作者として有名な 貴志祐介氏であるが、こうした不思議な舞台装置での活劇は、 名作クリムゾンの迷宮(未読の方はこちらも必見)以来、おそらく 氏の最も得意とする分野であろうと推察する。 本作は将棋世界を具現化し、将棋のコマを異形の生命体に置換した、閉鎖空間での予断を許さないリアルタイムの戦闘に描き起こしたもので、 この辺りにゾクゾクできる向きには、非常に満足感の高い作品と言える。互いの軍に、それぞれ非常に攻撃力の高い駒・生命体が 配備されており、これらは将棋の飛車、角を連想させる。また雑兵 でありながら、一定時間の戦闘に耐えると昇格する(歩の成り) など、細かいルールもなかなかに面白い。 戦闘開始時は、戦力はまったく互角なのに、時に一方的な 展開になったり、劣勢であっても、一気に王を討ち取れば、 それで勝利になったり。将棋は、指す人の棋力で決まる、という 当たり前の世界が本作によってゲーム感覚で、すんなり理解できる。 上巻では、敵味方、手探りの緒戦における混乱が描かれる。 もっとも大切なのは、現在の状況、敵味方の戦力、その展開、について 限られた手段で、”情報収集”する事、というメッセージが感じられる。 これは、現実社会でもまったくその通り、と実感できる。 新社会人にとっては、まさに異空間な環境、組織で、なにを目標に、 どんな手段で、誰と連携して、働くのか(戦うのか)これを組み立てるには、 正確な”情報”こそ命。 現実世界も、またダーク・ゾーン。
7投稿日: 2013.11.05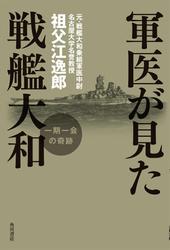
軍医が見た戦艦大和 一期一会の奇跡
祖父江逸郎
角川書店単行本
先達として、医師として心よりご尊敬申し上げます。
祖父江逸郎先生、そのご子息もまた医師・大学教授としてご活躍中。ご子息と一面識ある、いち勤務医として、また戦記・戦史に興味ある いち読者として、タイトルに心をわしづかみにされ、手にとった一冊。 壮絶で、圧倒的な戦争体験。そのただ中にあって、負傷兵である患者さんのために、医師として誠実に、常に最善を尽くしてこられた逸郎先生。 蒸し暑い戦艦のなかでの、外科的治療、疫病治療。それでも、淡々と職責を全うしようと奮闘された姿勢に、同じ医師として打ちのめされる。 患者さんを選んでいる暇などなかった、と。更には、そうした経験も一期一会のかけがえのない体験であったと感謝さえ述べられる氏の語り口に、 感動する。もちろん、戦艦大和で過ごされた日々も詳細に綴られており、大和にある種、畏敬の念を抱いているであろう 読者層をも揺さぶる内容である事間違いなし。 逸郎先生の希有な人生経験を共有させて頂くという、この上ない贅沢な時間を、是非ひとりでも多くの方に。
6投稿日: 2013.11.02
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数19
