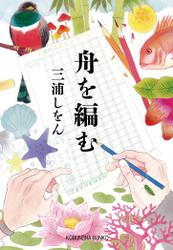
舟を編む
三浦しをん
光文社文庫
やっぱり、じーんときた
三浦しをんの本を読んだのは『風が強く吹いている』に続き2冊目。その本同様にじーんときた。不器用だけど何かに一心不乱に打ち込む愛すべき人。その人に周囲も感化され、目標に向かって一丸となって突き進んでいく。今の自分の仕事は、コミュニケーションをしっかりとるために曖昧さを排し、言葉の意味を大切に考えていかなければならない。なんとなく“辞書編纂”にも通じる部分があるせいか、「うんうん、そうだよなぁ」と共感することが多かった。『風が強く吹いている』もそうだったけど、この本も読み返したくなる1冊。
4投稿日: 2014.05.31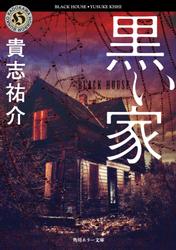
黒い家
貴志祐介
KADOKAWA
本当に怖いのは自分かも
保険金殺人がテーマ。怖かった。面白かった。妖怪の類は出てこないけど、妖怪のような人間に主人公が襲われる後半は読むのが止まらなくなる。そしてなぜ怖いのか、を考えさせられた。妖怪の怖さの根本的な要因は自分に理解できないものに対する不安だと思うけど、妖怪はありえないと思っているから、本当は怖くない。しかし、妖怪のような人間ならいるかもしれない。そして、自分の無意識の中には、妖怪になってしまうような要素があるのだ、と気付かされてしまう。あー、怖い。
0投稿日: 2014.05.23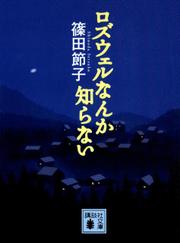
ロズウェルなんか知らない
篠田節子
講談社文庫
読む価値大
UFOで村おこしする物語。よそ者が来てひょんなことから村おこしが始まり、ある程度まで盛り上がったところで問題が発生。大きな挫折を経て、希望を感じさせるエンディング。定番とも言える流れだけど、ディテールがしっかりしていることもあり、読みごたえがある。そして、「人間が生きるって、こういうことなのだろうなあ」と考えさせてくれる。自分にとっては、読む価値が大きかったエンタテインメント小説。
0投稿日: 2014.05.17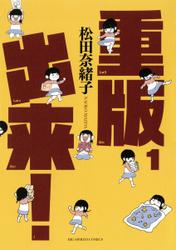
重版出来!(1)
松田奈緒子
ビッグスピリッツ
謎がひとつ解けた
「なんでこんなマンガが売れたのかわからない」--。こういう感じることはマンガに限らずある。「何でこの芸人が売れたのかわからない」とか。 自分の感性に問題があるのだろう、年をとって自分はそういう感受性が鈍くなっているのだろう、と思っていた。もちろん、そういう面もあるだろうけど、そうじゃないかもしれない。 このマンガは、「何故、売れたのか」という謎に、ひとつの答えを与えてくれた。その部分1巻のハイライトのひとつのような気がするから、読んでいただければ…と。 たまたま見ていたテレビ番組で、新刊の移り変わりは非常に激しくて、本に出会うこと自体が奇跡、というようなことを話してた。だから、本は売る人の努力が必要なのだと。 また、同じテレビ番組で、自分のお店である本を売りまくって、ブームに火をつけた地方書店のカリスマ書店員さんが、「そもそも必要のない本なんてない。売れないのではなく、売ってないだけ」というようなことを話していた。 本が売れなくなることについて、誰のことかよくわからない“一般市民“が本を読まなくなっているから、とすることがよくあると思う。しかし、売る方は、本と出会う機会を増やす努力を、怠らずにしているのだろうか? そんな問いかけをしている、ような気がする。
6投稿日: 2014.01.18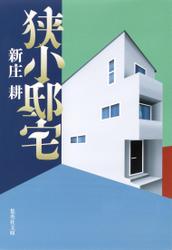
狭小邸宅
新庄耕
集英社文庫
妙にリアル
この本に出てくるような、都会の狭小地に立つペンシルハウスである「狭小邸宅」に住んでいる自分。作者は何かのインタビューで、「奇妙な形のペンシルハウスには、人間の欲望や滑稽さ、むなしさが象徴されているように思える」と答えていたけど、そのように指摘されると、そう自覚せざるを得ない。 その“象徴”が意味するところは、買う側だけでなく、売る側にも当てはまる。「狭小邸宅」にかかわる人を通じて、人間の「欲望や滑稽さ、むなしさ」を描いている。そんな感じの本。 不動産販売の実態と顧客との駆け引きも見所で、多少の誇張はあるにせよ、リアリティを感じる。だけど、よりリアリティを感じるのは、仕事を通じて変わってく主人公の心情。そして、成長していくかに思えた主人公は、最後に…。 スッキリする終わり方ではないけど、妙にリアル。多くのサラリーマンが、こういう感じを飲み込んで、ヨレヨレになりながらも生きている、と思う。だから、「あー、あるある、そういうこと」って、なんだか共感してしまった。スカッとする、痛快な本も好きだけど、こういう本も好き。
1投稿日: 2014.01.18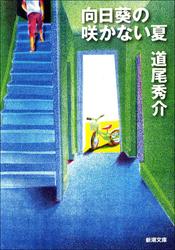
向日葵の咲かない夏
道尾秀介
新潮社
「自分にはあわなかったけど記憶に残る本」、暫定1位
ミステリーって、面白く読んでも、記憶に残っていない本って、結構ある気がする。もっとも、それはミステリーに限らないかもしれないけど。 しかし、この本は、記憶に残る一冊。「自分にはあわなかったけど記憶に残る本」、暫定1位かもしれない。ちなみに2位が、『イニシエーションラブ』、3位が『桜葉の季節に君を思うということ』。 とにかく設定が凄い。しかし、その設定を受け入れることができるのであれば、よくできた物語、という気がする。 ミステリーって、誰かが殺されて、こいつが犯人だろうと考えて、それが、エーッ、そうだったの? なるほどなぁ、騙されたなあ、という気持ちを期待している自分だから、「あわなかった」と思うのだけれど、そういう固定観念をとっぱらって読めば、楽しめた、かな?
2投稿日: 2014.01.13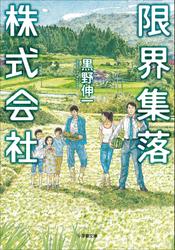
限界集落株式会社
黒野伸一
小学館
キャラクターに感情移入できなかたったかも
さくっと読めた。個性的なキャラクターがぶつかり合っていくうちに打ち解け、力を発揮し、困難を一丸となって克服していく。青春スポーツものにもありがちな展開が、限界集落を立て直すという舞台で描かれる。なかなか面白い。 しかし、読後感は、物足りない感じがした。何故だろう。多分、キャラクターに感情移入できなかったからかもしれない。フィクションは、現象自体、常識を超えたことがあっても良いのだけれど、そのキャラクターの気持ちが、理解できないというのは、自分は、気持ちが悪いらしい。 主人公は、億円単位の資産を持つ、いわゆる勝ち組。そんな人が何故、限界集落立て直しにのめり込むのか、理解できない。ハッピーエンドもどこか腑に落ちない。この点は自分のひがみが入っているのではないかと。 また、ツンデレのお父さんも、ちょっとなぁ。最後の行動を読むと、何であそこまでツンデレだったの? という気がしてしまう。全くの別人格のように感じてしまい、この点もスッキリしなかった。 爽快さがあっても良さそうな展開なのに、それが感じられないのは、自分の感性の問題かもしれないけど、やはり物語の舞台が、生活のためにある程度の打算も飲み込んで行動する大人の世界だからかもしれない。それがきれいにまとまることに対して違和感というか、居心地の悪さを感じるのかもしれない。 この手のストーリー展開は、高校生とか、せいぜい大学生を中心にしたものが限界ではないかしらと。
1投稿日: 2014.01.04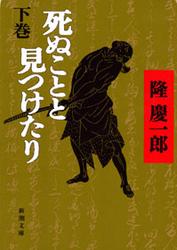
死ぬことと見つけたり(下)
隆慶一郎
新潮社
<死ぬことと見つけた>ことで学んだこと
「死ぬ気になれば何でもできる」とは人生において、何度か聞かれさた言葉ではあるけれども、「死ぬ気になる」なんてことに現実味はない。しかし、過去、武士という人の中には、「死ぬ気になる」ことができた人がいたらしい。 <所詮失うもののある方が負けなのである。失うべき何物も持たない死人の方には負けはないのだ。彼等は勝つことさえ望んではいない。勝っても負けても、やるべきことはやる。それだけのことだった。> この物語で学んだことは、死ぬ気になれる人は最強であるということ、そして、何か事を為そうとする人は、死ぬ気にならなければならないということ。 後の部分は、筆者が亡くなったことによって、描き切られなかったような気がするけど、編集部が記した「結末の行方」でなんとなく知ることができる。<(略)わが身を投げて藩を救った。武士道とは、死ぬことと見つけたり--。> 最後まで描ききってもらいたかったけど、未完でも真髄は十分に伝わる、ような気がする。 死ぬ覚悟の重要性はわかった。後は、何のために、死ぬ覚悟を持って生きるかだけど、これがなかなかわからない、武士ではない、残念な自分を再確認。
0投稿日: 2014.01.02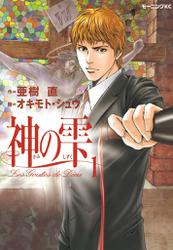
神の雫(1)
亜樹直,オキモト・シュウ
モーニング
“大人の『リンかけ』”
ワインって、興味あるけど、何を飲んだら良いかよくわからん。ワインって、興味あるけど、酸っぱくてボトル1本飲めない。そんなこんなで、アルコールを飲み始めて20年間、ワインを敬遠していた自分。そんな自分をワインの世界に引き込むきっかけとなった本。 ワインっていうと、色々なうんちくとか、聞きなれない表現とかが鼻につくのも、ちょっと近寄りがたくなる理由のひとつだと思うけど、そこはマンガの良いところ。大げさな表現でも、マンガ世界の中では、すんなり受け入れられるから不思議。 ワインを飲んで、マンガのような気持ちになるのか、マンガで描かれている画が見えてくるのか、現実の世界で試したくなる。そして、飲んでみると、意外と酸っぱくなく、美味しかったりするから、いろいろなワインを飲んでみたくなる。 昔、『リングにかけろ』を読んで、パワーリストを買っちゃったとか、“ブーメランフック“とか“ローリングサンダー”とかの練習をしたというのと同じような気がする。自分にとって、この本は、“大人の『リンかけ』”ですな。 結局、この本の魅力って、ワインの魅力なんだろうけど、それを自分みたいな素人にも、上手く伝えることができているのだろうと思う。昔、マンガを読んで、ヒーローの技を試してみたことのある人は是非。ただし、未成年は、マンガは読んでもワインを試しちゃダメよ。
0投稿日: 2014.01.02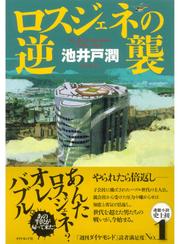
ロスジェネの逆襲
池井戸潤
ダイヤモンド社
情けは人の為ならず
勧善懲悪というか、主人公に理不尽な思いを徹底的にさせ、最後に敵をやっつけることでスッキリした気分にさせてくれる池井戸作品。『空飛ぶタイヤ』が一番好きだけど、テレビで有名になった半沢直樹シリーズは、ズバリそのものですな。 サラリーマンの物語ゆえ、共感できる、シビレルセリフも魅力のひとつ。この本では、<仕事は客のためにするもんだ。ひいては世の中のためにする。その大原則を忘れたとき、人は自分のためだけに仕事をするようになる。自分のためにした仕事は内向きで、卑屈で、身勝手な都合で歪んでいく。そういう連中が増えれば、当然組織も腐っていく。組織が腐れば、世の中も腐る。わかるか?>がイイ! 「わかりました、半沢部長!」って感じ。 "情けは人の為ならず"(人に対して情けを掛けておけば、巡り巡って自分に良い報いが返ってくるという意味ね)という言葉は、バブル世代である自分がいつも心にとめている言葉だけど、ロスジェネ世代の人は<もっと的確な答える見つけるはず>ですよね、きっと。
1投稿日: 2013.12.29
β1さんのレビュー
いいね!された数17
