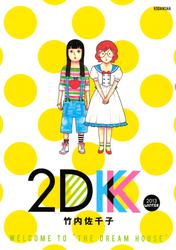
2DK(1) 2013WINTER
竹内佐千子
モアイ
「ジュノンボーイになってからにしな!」
アイドルの追っかけなどをする女子の生態が第三者的に楽しめる。自分の愛するものを愚直に追及するひたむきさは,(その対象物に対する愛情は共有できないとしても)見ていてすがすがしい。まじめで内気,良識派のこむぎ(キレると播州弁になる)と,芸術方面のお仕事をしていると思しいボヘミアン気質のきなり(顔面を取り外せる),主人公二人を中心に,登場人物はそれぞれどこか抜けているところがありつつみな善良でありほほえましく,読んでいてほのぼのする。こういう漫画を楽しむのは,スポーツでも音楽でも,生で鑑賞するのでなく評論を楽しんで読むというのに近いのだろうか。そう考えると高度な精神活動のような気配すら漂ってくるが,気の迷いかもしれない。きなり役が綾瀬はるかでの実写化を妄想中。
0投稿日: 2016.09.05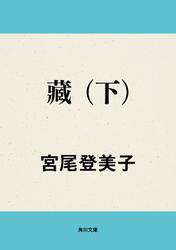
藏 (下)
宮尾登美子
角川文庫
「烈だってしあわせらことはいっぺことある。/そのいっち大(でつ)けもんはね,十四の年までは昼間,見(め)えてたことらぜね。」
新潟の旧家,田ノ内家の当主である意造,一人娘の烈,列の母の妹である佐穂を中心に描かれる物語は,烈の眼病からの失明という事件を軸にいろいろな出来事を重ねながら進行していく。よくも悪くも旧家の跡取りとしての良識や世間体に縛られがちな意造に対し,常に自分の心にまっすぐでひたむきな烈の心が際立ち,その必死さが心を打つ。「鳥の声は,いつも瞼の外側がうす明るくなってのち聞こえて来,それを聞くと何かしら心はずむ思いがあるのに,今朝に限って外はまだ明るい。/何故かしら,と,そっと目を開くと夜の続きのような目の前はまだ黒いとばりがおろされている。/へんな鳥,まだ夜も明けないのに,と再び目をつむろうとして烈はどきん,とした。・・・・・・」に始まる烈の目からついに光が失われた朝の描写,烈の心に訪れる恐怖が静かに読み手にも伝わってくる。「おとっつあま,烈は,この黒(くう)れマントの切れを,鋏で切りてあん。包丁でもいい。突き破って切り裂いたら,そっから明(あかあ)れ明れお陽さまがさし込んでくると思わんさね(思うのよ)」新潟の方言で語られることが烈の心がより生なましく感じさせる効果を生んで印象深い。物語は烈の婚礼で終わり,その後に田ノ内家のその後を作者がかいつまんで述べる後記がついている。烈が自らの困難をある意味克服した時点で物語の主題は終わっており,そこで終わりとすることが良いする一方,その後の烈や田ノ内家について語らずにいられなかった作者の思い入れが感じられる。
0投稿日: 2016.09.05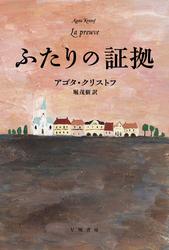
ふたりの証拠
アゴタ・クリストフ,堀茂樹
ハヤカワepi文庫
痛切な,孤独
『悪童日記』の続編。前作では,主人公の二人は自らの感情を一切記さず,あらゆる事柄を冷静に見つめ,冷戦下の世界の中で翻弄される人々の姿をいわば超越者の目で見つめていた。母や父の死も含めて人の死はショッキングなまで軽く淡々と扱われた。本作では主人公の二人は別れ別れになっており,別の孤児とのかかわりから,超越者の座から地上に降りたように感じられた。孤児の死を通じて描かれる,救いのない孤独。人間の孤独ということをこれほどむき出しに,痛切に描いた作品を評者は知らない。『第三の嘘』も購入したが,読み終わるのがもったいなく,まだ読み始めていない。
1投稿日: 2016.08.23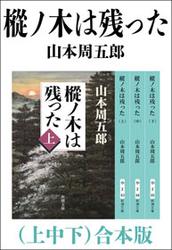
樅ノ木は残った(上中下) 合本版
山本周五郎
新潮文庫
人間らしく,生きる。
この著者の作品を初めて読んだ。上巻のあたりは登場人物が多くてそれぞれに複数の呼び方が混在するので混乱してしまい,何より主人公である原田甲斐の内面を表現するような部分が全くないので何やら読みづらいままで進む。話としては「伊達騒動」に関わる一連の出来事を原田甲斐を中心に据えて追っており,10数年の時間経過があるはずなのだが,主人公の動きがなかなか見えてこないこともあり,物語の進行しているという感じがない。甲斐はひたすら自分を韜晦しつくし,伊達藩を転覆させる陰謀を阻止すべく耐え続けるのだが,その過程で親しかった人々から見放され,あるいは責められあるいは別れ,その中でも感情の動きを表に現さない甲斐の姿は,読者にも何やら得体のしれないものに思われる。そんな甲斐が心を通わせるのは樅の木や鹿,鯉であり,人間とはおよそ心を通じ合えないように見える。甲斐は主家の存続のために周囲の人間の苦しみまでも受け入れて耐えながら,一方では孤独そのものの山での時間を愛するように武家社会の倫理に縛られない生き様こそが本来の人間らしい生き方であると考えているように思われ,陰謀に巻き込まれて縁者を失った宇乃,あるいは宮本新八への接し方にそれが表れている。しかし武士としての生き方を自ら捨てることはできず,自らの心を誰にも明かせないすさまじい孤独の中で10数年生きる甲斐の姿は,なんとも言い表しようがない。物語の中盤から終わりにかけて,わずかに甲斐の心情が漏れだすように述べられる。歴史の真実は不明であるが,孤独に耐えて自らの使命を貫く男の姿は,無言の中に存在感をもって読者の心に残るものと思う。
0投稿日: 2016.08.23
白い巨塔(一~五) 合本版
山崎豊子
新潮文庫
人は何に生きるか
言わずと知れた名作。特に理由はなく敬遠していたがふと思い立って、同じ作者の「不毛地帯」に続き購入。ラスト3冊は一晩で読んでしまった。元来3巻までで執筆されたものが、あまりの反響に続編として作成されて計5巻となったとのこと。続編部分である意味勧善懲悪的な結末が補われたことには賛否両論あるのかもしれないが、財前五郎という人物を最後まで描き切ったものとして個人的には納得。財前五郎は憑かれたように外科医としての頂点を目指すが、自らの傲慢さが招いた陥穽に陥り、非業の死を遂げる。「財前は、自分が一番信頼している人間は里見で、女として愛しているのはケイ子だと思った。」の一文は財前の孤独を示すとともに、死に臨んで初めて澄んだ目で自らを見つめる財前の姿を浮かび上がらせ心を打った。
0投稿日: 2016.08.14
不毛地帯(一~五) 合本版
山崎豊子
新潮文庫
巻を措く能わず
非常におもしろくて,一気に最後まで本を読んでしまうことを表現した言葉だそうだが,まさにそのような感じで全五巻を読破してしまった。とにかく続きが読みたくて,通勤時間はReaderで,トイレに入っているときはスマホアプリでひたすらに読み続けた。今まで特に理由もなく敬遠していたことを反省。ストーリーとしては陸軍の参謀を努めた主人公が,シベリア抑留を経て帰国し,心ならずも商社マンとして就職し,大きな課題に取り組みながら出世していく,,,と書くとなんとなくありがちな話のようではあるが,おそらくは徹底的な取材に基づいた細部の積み重ねと全体の緊密な構成が,この小説を凡百の企業小説と一線を画したものにしているように思う。まず圧倒されるのが,初めに1巻を丸々費やしたシベリア抑留の部分。この部分だけでも作品として成立する,気迫のこもった内容であり,ぜひ多くの日本人にシベリア抑留がどのようなものであったかを感じる意味でも読んでもらいたいと思う。終戦時に大本営の参謀でありシベリア抑留を経験したことがのちのストーリーに明らかに目に見える形でかかわってくる度合いというのはそんなにないのだけれど,終戦から高度成長に向けて立ち上がった日本の一つの象徴というか,典型として主人公である壹岐が描かれたのだろうか,とぼんやり考えた。主人公を見出した大門社長やライバル社の鮫島など,脇役・敵役もそれぞれに個性的で非常に魅力的。主人公がプライベートではなかなかうまく立ち回れなかったり,息子と衝突したり,恋人ともどかしい関係を延々続けたりと,仕事でのスーパーマンぶりとの対比も主人公の人間的な欠点を見せてくれて,親しみが持てる。この作者の長編をこれから順番に読んでいくのが楽しみである。
0投稿日: 2016.08.05
真っ赤なウソ
養老孟司
PHP文庫
現代日本のあたりまえの日常が当たり前に見えなくなるあたりまえの本。
「バカの壁」でベストセラーとなった著者の,続編のような書らしい。「バカの壁」を読もうかと思って某サイトのレビューで本書を先に読むことを進めていたので購入。読みやすい文章であるが,内容は決して浅くない。自分の中でもやもやしていた感覚に一部形を与えられたと思った。一神教の論理が現代日本人の心性にどれだけ影響しているか,また仏教の現代的な価値についても言及している。個人的にわが意を得たりと感じたのは『「頭に個性がある」と困る』という章。昔の日本人は成長とともに名前が変わり,自分という人間も時間とともに変わるという感覚が普通だったが,現在の日本人には『変わらない私」なんていう前提がある』。それが末期の延命治療などとも関連しているという指摘は,個人的にはかなり興味深かった。現代の日本のいろいろな問題の根本には,日本人特有の心性の問題があるという視点はかなり刺激的である。憲法9条に関するコメントも,思わずにやりとさせられた。 作者の考えは,ごく平易で,複雑な論理や極端な飛躍はなく淡々と進む(ように思う)。あたりまえでないのは,自分を含めた現代日本の大多数なのかも,と思わせられる。平易な文章に込められた知的刺激。古くて新しい仏教が再び,日本人にとってもっと身近なものになればよいと思う。
1投稿日: 2015.07.14![ユリウス・カエサル ルビコン以後──ローマ人の物語[電子版]V](https://ebookstore.sony.jp/photo/BT00003156/BT000031565400500501_LARGE.jpg)
ユリウス・カエサル ルビコン以後──ローマ人の物語[電子版]V
塩野七生
新潮社
共和制ローマの極点
作者にとって一番愛着のある人物がユリウス・カエサルであり,カエサルを描いた前巻と本巻はいわば作者からカエサルへのラブレターのようにも思える。実際以上に美化されているのかどうかは評者にはわからないが,確かにここで描かれるカエサルはカッコいい。ここに至る共和制ローマを支えた人-多くは名もなき一人ひとりが,個々の能力は別として,共同体を重んじつつ,常に粘り強く前進し続けてきた,ある意味精華がカエサルという一人の人間であるとも感じられる。自分に反対するものを決して排斥せず,むしろ自由な意見を尊重するそのありようは,広く現代人も範とすべきである。凶刃の前に倒れる際の描写は思い出すだけで涙。暗殺者たちはカエサルを葬ったことで自らが恐れていた未来を開いてしまった。それはローマの転換点ではあるが,歴史の必然でもあったのだろう。 圧倒的な歴史の前に,その重みを知るものはけして饒舌にはならない。この作者の抑制された筆致でこそ描き出されたローマ人の,人間の物語。1巻だけで放り出してしまった人には,途中からでも是非おすすめしたい。
0投稿日: 2015.07.09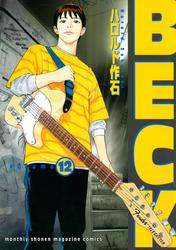
BECK(12)
ハロルド作石
月刊少年マガジン
ロックのレジェンドに導かれて
本巻の1話目の扉は『ヨシュア・ツリー/Joshua Tree』。全米チャートでNo.1を獲得し,U2を一躍ビッグ・バンドに押し上げたこの記念碑的なアルバムと,そのツアーを追ったドキュメンタリー『魂の叫び/Rattle and Hum』(と同名のアルバム)でU2はアメリカン・ルーツミュージックへの傾倒を示し,B・B・キングと共演したり,プレスリーの墓参りをしたりしている。 グレイトフル・サウンドで傷だらけになりながら「最後の」ライブ・パフォーマンスを行い,そのまま分解してしまっていたBECKのメンバーも,竜介という水先案内人を欠いたまま,よちよち歩きの再出発を果たし,本巻からアメリカ・ツアーへ旅立つことになる。 U2が上述の2作品を経てまったく違う形に生まれ変わったように,この世を去ったロックのレジェンドたちの夢に導かれて,アメリカ・ツアーはいくつもの意味でBECKにとって再生の旅となる。 漫画という表現手段でここまで音楽を表現できるものか。どれだけ頑張って実写映画化しても,原作で心揺さぶられた読者の魂の中で鳴り響く自由なサウンドは表現できないと思ってしまう。毎回の名盤のパロディ扉絵にも現れる作者のロックへの愛情と深い造詣,そして何より漫画家としての力量によって生まれた,音楽を使わずに音楽を表現することが無限の自由を生む,稀有なシリーズ。
0投稿日: 2015.07.09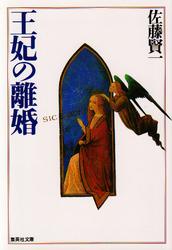
王妃の離婚
佐藤賢一
集英社文庫
時代は変わっても;男と女と愛と結婚。
佐藤賢一の著作を初めて読んだ。これまでの本のタイトルだけを見て,雰囲気で重厚な歴史小説を書く人なのかしらと漠然と思って頭の片隅に入れつつ,これまで読む機会がなかった。海外出張の機内で読む本を探していて,ふと思い立って購入。読みはじめ,モノローグの多い,悪く言うと言い訳がましいような女々しいような文体がやたらに鼻について,失敗かと思った。個人的にはもう少し自分語りの少ない文体が好きだなと。ただ読み進めるうちに文体はあまり気にならなく,内容にそれなりに入り込むことができた。ストーリーは,ブルボン王朝時代のフランスを舞台に,かつて天才学生の名をほしいままにしたひねくれ者の弁護士が,国王ルイ12世から離婚の訴えを起こされた王妃の弁護に立ち上がり,権力に華々しく立ち向かう法廷ドラマ・・・・・・というところ。合間合間に主人公の過去が少しづつ明かされ,最後には不思議な運命のめぐりあわせも明かされ(でもなんとなく予想がついた),という感じで,難をつけるなら話がそつなくまとまりすぎている感じがあること。上述の文体の問題は,主人公の姿勢(当初はひねくれて無気力だが,中盤から自分のプライドと王妃のために立ち上がり生き生きと法廷で闘う)と照応しているよう・・・・・・でもあるが,違うかも。著者の他の作品を読んで,結論は出そうと思う。
0投稿日: 2015.05.21
おでんbmさんのレビュー
いいね!された数4
