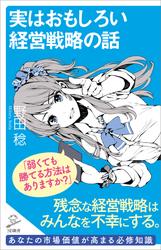
実はおもしろい経営戦略の話
野田稔
SB新書
なぜ、社長があんなことを言うのか、が分かった
恥ずかしながら、経営戦略の本は初めて読んだが、一つ一つのワードを丁寧に説明していて分かりやすく、よく理解できた。 そもそも戦略(ストラテジー)の語源は、ギリシャ語の軍隊(ストラス)と統率(アゴー)を合わせたものだそう。ケーススタディと統計学による学問なので、7〜8割は使えると思うけど、想定外のことも現実では起こるよ、と最初に前置きしてくれたのが良かった。 そういうわけで、前半は歴史の授業にも出てくるような軍の戦略を紹介、経営に置き換えての解説が入る。今更ながら「ああ、学生の頃歴史の授業で習った君主論はこういうことが書かれていたのか」など、点と点がつながる場面も私は多くあった。戦略を中心に見ると世界史はこうも面白かったらしい。(私の学生時代の授業は、とにかく語句の羅列ばかりだった…。) 戦の指南書の神様、孫子には特にページが割かれていた印象だ。 後半は、実際の企業のケーススタディが多く紹介されている。有名企業が取り上げられているので、身近で想像しやすい。 終盤にいくにつれ、では自分たちの企業はどうか、とどんどん自分ごとになっていく私がいた。また同時に、自分の会社の社長が節目や朝礼で言っていることの意味が、より深い意味で分かったように思う(私の会社の経営陣はきちんと勉強しているんだなぁ、と改めて思った)。経営陣と対話するときの教養に、というか共通言語に、読んでおいて良かったと思う。 最後に、この本の最初の方で、企業の目的は顧客の創造、すなわち新たな価値の創造(これが欲しかったんだよね?を生み出す)というドラッカーの考え方が呈示されていた。私はこれを忘れずにいたいと思う。 私がやっているのは、小さな仕事かもしれない。でも、目的は「お金」じゃない、「自分の成長」じゃない。「世界をちょっとよくするため」なのだと。 (「お金」と「成長」は手段!って言い切れるとカッコいいんだけど……なかなか難しい…)
0投稿日: 2020.07.09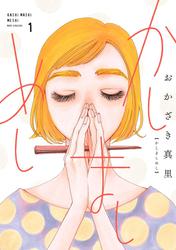
かしましめし(1)
おかざき真里
FEEL YOUNG
食べるってセクシー。
同級生が自死し、その葬式で会った3人の美大生。 パワハラで会社を辞めた千春。 会社で男に裏切られた上、お局扱いを受けるナカムラ。 恋人に明るく振る舞いすぎてしまって、どうも関係が上手くいかない英治。 リアルな悩みに共感してしまう27歳の3人が、美味しいごはんを食べるシーンを中心に、小さな幸せとやさしい友情が紡がれる。 もう死んでしまいたい、そう思ったときの生きる方法が「ごはんを食べる」っていうのが良い。 私たち色々と悩みはあるけれど、本当はごはんを食べるってだけで幸せになれるんだよな、って思い出させられる。 食事には、それだけの力があるよね。 人間の三大欲求の一つに食欲があるというけれど、セクシーにさえ見える美味しそうな食事シーンが、そう思わせるのだ。 一方で、ただ美味しそうに食べるマンガにとどまらず、おかざき先生らしい人間ドラマにも読みごたえを感じる。こんな世の中だけど、生きてやる!という登場人物たちの生命力が爽快だ。 最後の流れを含めて、清々しい気持ちになれて、よし頑張ろうって自分も思う1巻だった。
0投稿日: 2020.02.20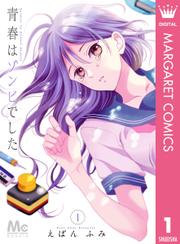
青春はゾンビでした 1
えばんふみ
Cookie
私も、青春ゾンビ
恋愛をしてこず、青春に心残りがある「青春ゾンビ」。主人公の雪村梓は、まさに青春ゾンビの22歳で恋愛マンガが上手く描けず困っているところだが、ちょっとずつ、自身が恋のようなものを体験していくことで、マンガが描けるようになっていく。 これを読みながら、私もこんなマンガを読んじゃって、キュンとしちゃって、青春ゾンビなのかもしれない、と思った。 既に結婚もしている身だが、少女マンガは読みたくなるし、それでキュンとしたいし、なんなら読後は「私ももっとトキメキながら生きよう」と思っている。 恋愛マンガって心を潤しますよね。 良いんですよきっと青春ゾンビで。ずっと青春しながら生きていきましょ。
0投稿日: 2019.09.23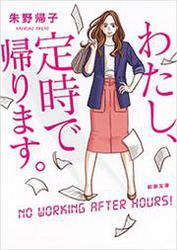
わたし、定時で帰ります。(新潮文庫)
朱野帰子
新潮文庫
残業なんか、やめちゃおう
私たち、平成世代の気持ちを代弁しているよう。 「働き方改革というが、そうそう簡単に残業を減らすのは難しい。」そんな意見をよく聞くし、無理矢理減らした残業は、どこかにしわ寄せがいっているかもしれないことも確かだ。 一方で私は、『クリエイティブな仕事を続けていくためには、日頃のインプットを継続すること、またそれによって自分の引き出しを増やしていくことが大事。』そう考えて仕事をしているので、「仕事を定時で終えて帰る」のは優先的なことで、毎日定時で帰ろうと、特急で仕事をしている。(もちろん、帰れない日もたくさんあるのだが。) 「わたし、定時で帰ります」は、タイトルが私の気持ちをそのまま言ってくれていて、書店に並んだときからワクワクした本だ。 主人公の結衣は、仕事中毒だった父親を反面教師に、毎日定時で帰ることを信条としている。結衣が教育係として指導している新卒の新人・来栖も同じく『定時で帰る』価値観を持っているのだが、そのほかの社員は『残業するのは当たり前』の仕事スタイルが定着していて、定時に帰る二人をよく思っていない。 そんなときに、『残業しなければ絶対に片付かない』と言われる大きな緊急案件が入ってくる。周囲は、「残業して乗り越えよう」というやる気に満ちた雰囲気。「そもそも残業前提なのはおかしいのでは」と格闘する結衣。果たして、結衣は残業しない仕事スタイルを貫けるのか…、この職場の意識を変えることができるのか。という話。 職場としては、定時で帰ってOK。でも、残業をする人はたくさん。これは、職場あるあるではないだろうか。 もちろん、仕事量が多過ぎて、残業するしかないという人は多くいると思う。 しかし、それでも。残業しない工夫をしているか、終わらせようという確固たる意思を持っているか、その仕事量を客観的に分析して上に掛け合っているか。そして、上に立つ人間は、皆が残業しなくていいように考えて管理する責任があるのではないか。 残業の多い職場ほど、仕方ない、と諦めが蔓延しているように思う。感覚が麻痺している職場だってありそうだ。 就活をする人はブラック企業ではないか、ということを極度に気にする。どこの職場だって変わらなければいけない部分なのだ。 自分はどうゆうふうに働くか、を問うてくる。 そして、また同時に、自分の仕事への努力(仕事を早く終えるための方法の一つは、処理速度をあげることですよね)、スキルアップについても、問う一作だ。
0投稿日: 2019.04.28
20代にしておきたい17のこと
本田健
だいわ文庫
迷いも多い20代に、力を与えてくれる一冊
著書に大ヒット作「ユダヤ人大富豪の教え」を持つ著者、本田健さんが自分の考えだけでなく、実際に「経済的にも社会的にも成功して、いま幸せな人たち」に聞いたという『20代のうちにやっておきたいこと』をまとめた内容。30代より上のあらゆる世代に「後悔していること」を聞き、さらに人生が順調にいっていない人にも話を聞いたということで、多くの人が考える『20代でやっておきたいこと』がそろっています。 目次になっている、その17は 1人生最大の失敗をする 2大好きなことを見つける 3一流のものに触れる 4人生を100パーセント楽しむ 5死ぬほどの恋をする 6一生つき合える親友を見つける 7両親と和解する 8自分のルーツを知る 9才能のかたちを知る 10専門分野を持つ 11メンターを探す 12人生が変わる本と出合う 13質問力を鍛える 14お金と時間の管理を学ぶ 15没頭できる趣味を持つ 16異文化に触れる旅に出る 17運について学ぶ とどれも、バイタイリティを感じるポジティブなものばかり。 20代ならできる、ちょっと思い切ったことも、やっちゃいましょう!と背中を押してくれます。 「7両親と和解する」では、著者が学んだ最新の心理学を例に「父親と和解できていると、キャリアを積んだり、人生でさあ何かをやろうというときに、感情的な抵抗が少なくなります。」「母親と和解できていると、いまの自分を受け入れることが楽になります。創造性を育んだり、人生を味わう、楽しむということが自然にできるようになるのです。」とあります。私の胸にとても刺さった部分でした。本当に親と和解するということは、なかなか難しいことです。でも、順風な人生を送るためには、根本の部分で、それが大切なことなのだ、と思えるエピソードも紹介されていました。 悩んでいるとき、迷っているとき、読みたい1冊です。
0投稿日: 2018.08.16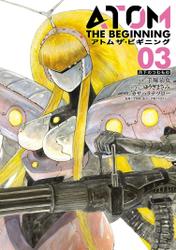
アトム ザ・ビギニング3(ヒーローズコミックス)
手塚治虫,ゆうきまさみ,カサハラテツロー,手塚眞
月刊ヒーローズ
「学習する」ロボット
この話が進む5年前のこと。 日本では、未曾有の大災害が起こっていた。 各地で発生した爆発災害。一晩で、死者は数万とも数十万とも言われたという。 しかし、この災害には不思議な点がある。それは、政府が調査隊を出したにも関わらず、一切その結果が報告されなかったのだ。その秘密が隠された島を調べてしまったがために、謎の集団に追われるようになってしまった、天馬くんとお茶の水くん。1巻から小出しにされていた大きな事件が一気に存在感を出していく。 その一方で、天馬くんとお茶の水くんの方向性の違いは溝を深めていく。天馬くんが目指すロボットは、「自分で瞬時に判断までくだせる、人間を超越した、神のような存在」。お茶の水くんが目指すのは「心を持った、優しい友達」。 二人の思いがある中で、A106は壊れたロボットを自分と接続し、そのデータを自分の中に取り込んで知識を増やすという芸当を行ってしまう。 知識を増やす方法は、天馬くんたちから教えてもらったものだが、自分でそれを行ったのである。 人工知能を持つロボットは自分で学習する。これは、おそらく私たちにとっても身近なことだと思う。予測変換が出る、自分好みの商品を勧めてくる……。画面の中でなら便利だが、実際に動きを伴う、決定を伴う、と現実世界に影響を持ち始めたら、それはお茶の水くんの言うとおり、確かに不気味なのかもしれない。予測不能なものに対して人間は恐怖を覚えるものだし、天馬くんがいうレベルのロボットができれば、人間が制御できなくなることだってありえるかもしれないのだ。 こう考えると、アトムレベルまではいかずとも、現実世界でも「人間の代わりになる」ロボットは研究開発が進められているはずだ。それらは、どういう方針が立てられているのだろう、と少し気になってくる。 そんな私に、まずは今までの人工知能の歴史から知ろうね、と言わんばかりに分かりやすい変遷の付録が巻末に付いていた。 ますます楽しい……が、不安も渦巻いてくる3巻です。
2投稿日: 2017.01.09
アトム ザ・ビギニング2(ヒーローズコミックス)
手塚治虫,ゆうきまさみ,カサハラテツロー,手塚眞
月刊ヒーローズ
ロボットの声は、聞こえた方が良いのか
前回から引き続き、ロボットレスリング決勝戦で戦うA106。 以前、日常生活中に襲われた経緯から、A106は襲ってきた理由を、戦いながら対戦相手のマルスに問い続けます。しかし、返答はなし。遂には、物理的に追い詰められてしまいます。 絶対絶命か、と思われたところでA106がポツリ。ロボットにしか分からない発信で言ったのが「ひとりぼっちのまま、壊れてしまうんだな」。その呟きは、まるで人間。 伝馬さんもお茶の水さんもA106の自我システムはできそこないだから、感情もない、と思っています。が、以上のことから分かるのは、A106のAIは人間に近いレベルまで成長しているということ。 ストーリーの後半では、襲ってくるロボットと戦いながら、うれしいのか、悲しいのか、A106自身も自分の感情に戸惑いを覚えるようになる場面も。 科学に何を求めるか。人間と同じように動く、人間の代わりを求めていくのであれば、「感情を持たせること」はキーワードとなる。でも、それなら、人間とロボットとの区切りはどこに作るか。 ロボットの心の声が表面に出てきたときに、この問題も表面化するはずです。ロボットに心を持たせる、それは好奇心的にはくすぐられるところですが、科学の倫理としてはやるべきではないのかもしれない。ロボットの声は、多分聞こえない方が良い。そう思いました。 ぜひ、A106の切ない声を、この巻で聞いてほしいと思います。
3投稿日: 2016.12.12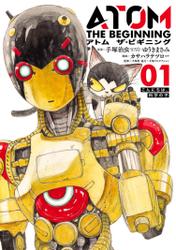
アトム ザ・ビギニング1(ヒーローズコミックス)
手塚治虫,ゆうきまさみ,カサハラテツロー,手塚眞
月刊ヒーローズ
彼のコンセプトは「心やさしき科学の子」
知っている度合いは違えど、誰もが知っているロボット「鉄腕アトム」。この作品では、その「アトム」が生まれるまでの道のりを、生みの親・天馬博士、育ての親・お茶の水博士の学生時代とともに描いています。 え、手塚治虫さんは亡くなってるのに誰が作ってるの?と、私は思いましたが、企画監修にあたっているのが、ビジュアリストとして映画監督、映像クリエイターを務める手塚眞さん。手塚治虫さんの息子さんです。視点を変えて、親子二世代で物語を紡いでいく、おもしろい企画と感じました。 目に見えてロボット作りの才能をもつ天馬くんと、地味に見えて良い気付きが強みのお茶の水くん。二人は、日々人工知能を持つロボットA106の開発に励みます。 それは、まだ、人工知能を搭載したロボットが登場したばかりの頃のこと。機械に人の仕事を任せるなんて……と思う人もいる世の中で、二人は自分たちの作る「人の気持ちを分かる、心を持つロボット」をいろいろなところで試します。 仕事をさせる、ロボットレスリングという格闘大会に出してみる。A106はどう動くのか、何を思うのか。 読みすすめながら、こちらもロボットの作り手の気持ちになってみてしまう。所々で、私たちのアトム像にリンクする部分も出てきて、ノスタルジックな部分も持ち合わせた話です。(時間軸的には、こちらの方が昔の話になりますが) ここから、どうA106が生まれ変わっていくのか、仲良し2人の関係はどう変わっていくのか(アトムでは、二人は敵対しています)。続きが楽しみな1巻でした。
3投稿日: 2016.11.13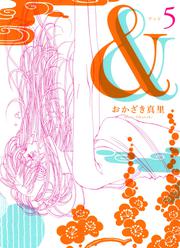
&(5)
おかざき真里
FEEL YOUNG
矢飼先生が、薫にときめく
矢飼先生との恋愛に胸を踊らせながらも、仕事に精を出す薫ちゃん。 医療事務の仕事はレベルアップし医師事務になるが、一方で自分が本当にやりたいと願っているネイルの仕事は中途半端なまま。その中途半端である、という痛いところをシロにつかれ、自分の気持ちを確かめる作業に入る。 自分の気持ちを再確認した後、薫ちゃんはシロに言う。「中途半端なのは分かっている」と。そして、「でも、両立させたい」と。 身に染みた。 将来が不安だ。自分のやりたいことでは、自立できない。だから、両立してでも続けたい、と願う。きっと、一本道で自立している人から見るともどかしいだろう。でも、いろいろな生き方があっていい。今は、これでいい。自分の納得できる「今」という選択を、みんな続けていくんだと思う。
0投稿日: 2016.11.07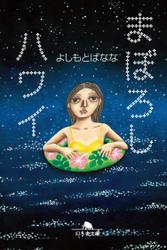
まぼろしハワイ
よしもとばなな
幻冬舎
美しい装丁と、やさしい香りの物語
その美しい装丁に一気に惹かれた。「まぼろしハワイ」。広がる星空。海に浮かぶ女性…。キリキリとしていた気持ちの糸が、ゆるんだ。この本に、会いたかったのだ。 なんとなく、とっつきにくくて私はよしもとばななさんの作品を読んだことがなかった。初のばなな作品に少し構える。本を開くと、ハワイの香りが溢れだした気がした。ハワイの空気感が良く出ているのだ。ホノルル空港に着いた瞬間に香る甘ったるい空気。それを確かに感じた。 この本は三本の短編が入っている。「まぼろしハワイ」「姉さんと僕」「銀の月の下で」。どの話も、少し事情のある家族たちの話だ。登場人物たちは皆、誰かと深いところで繋がっていたいと思っていて、傷つきながらも一生懸命生きている。ハワイでは、時間が不思議な流れをしていて、主人公はそれぞれ傷を癒やしていった。前に進む運命的な出逢いもある。 私は、偶然出会った2人の夜の散歩が魅力的な「銀の月の下で」が一番好きだ。なんて、美しいのだろう。 この本の始まりは 「ハワイ行きたい、どうしようもなく行きたいよ、ねぇ、いっしょに行かない?」であるが、今の私はまさにハワイに行きたい。そういう気持ちになるのだ。もしも失くしてしまったものがあるのならば、ハワイに行くことで取り戻すことができる。今、私はそう思えてならない。 全体的に流れる空気が心地よい作品だった。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■ 「なんで時間は過ぎてしまうんだろう、 どうして愛する人はみな逝ってしまうんだろう。」 まぼろしハワイ ■□■□■□■□■□■□■□■□■
0投稿日: 2016.09.26
さとみさんのレビュー
いいね!された数14
