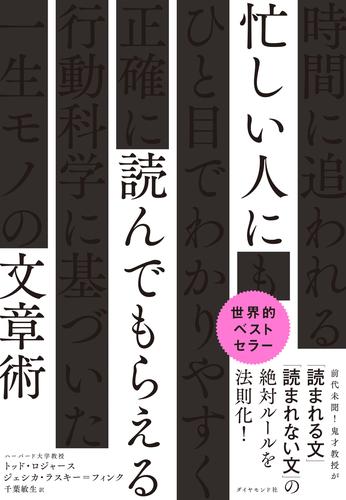
総合評価
(4件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
まず装丁が素晴らしい。図書館で見かけて借りた。 内容としては”短く簡潔に”に終始。新しい知見が得られた感じはしないが、出典も明記されまとまっているので今後も気をつけて文章を磨いていきたい。 - 頭のなかに同時に保持できる情報の個数には明確な上限がある。具体的には、およそ7個±2個 - 無関係な情報を無視する脳の能力。1999年、ハーバード大学の有名な研究 - 被験者に1分間のバスケットボールの動画を見せ、パスの回数をかぞえさせる。動画の途中で、ゴリラの着ぐるみが画面を堂々と横切るのだが、半数近くがゴリラの存在に気づかなかった - 脳の報酬関連の領域は、”いますぐ”望ましい結果が得られる選択肢について考えたときには活性化するが、”あとで”望ましい結果が得られる選択肢について考えた時には活性化しない - 「効果的な文章を書く」能力を磨けば、「明確に考える」能力まで磨くことにつながる - 簡潔さこそが命 - 2010年の平易記載法(Plain Writing Act of 2010) - 国民が「理解して使用できる」ような「平易」な言葉で書くよう連邦機関に義務づける法律だ - 効果的な文章を書きたければ、見栄を捨て、長くて珍しい言葉の代わりに短くて一般的な言葉を使うべきなのだ。 - 読み手が1回読んだだけですんなりと意味を理解できる文章を書くこと - 書き手視点の件名「ロック・ザ・ボートでボランティアをしよう」 - 読み手視点の件名「無料イベントに参加しませんか?」 - ボランティア登録率は、読み手視点が4倍近くにも及んだ - 読み手自身の利益に訴えかけることが目的達成に役立った - 「どういう人に読んでほしいか」を強調する - 書き手視点「重要な製品改修情報」 - 読み手視点「6月にXYZスープを購入されたお客様に、商品回収のお願いです」 - 読み手に必要な情報がすべて1か所で手に入るようにすること - 事前に選択された年金プランと自発的に選択しなければならないプロセス - 事前に選択されたプランの登録率は10〜20パーセントポイント向上した - 2000年のアメリカ大統領選挙 - 投票用紙に穴を開ける方式だが、ごあにとうひょうしようとして誤ってブキャナンに投票してしまった人が2000人以上いたという`
0投稿日: 2025.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
忙しい人に読んでもらえる文章の6つの原則 この本では、忙しい人が文章をどのように処理するかを科学的に理解し、その特性に合わせた効果的な文章を作成するための「6つの原則」を提示している。 1. 第一の原則:少ないほどよい(Less is More) 短く、簡潔にまとめることの重要性を説く。 忙しい読み手は、情報処理コストが高い文章を避けるため、内容を極限まで削ぎ落とす必要がある。 すべての単語、一文、段落には、存在すべき明確な理由が求められる。 冗長な表現や重複を排除し、必要な情報のみに絞り込む。 2. 第二の原則:読みやすくする(Make it Easy to Read) 文章の分かりやすさを高めることで、読み手の負担を減らす。 簡潔な言葉を使い、専門用語や難解な表現を避ける。 短い文で構成し、一文に複数の情報を詰め込みすぎないようにする。 受動態よりも能動態を多用し、主語と動詞を明確にする。 3. 第三の原則:見やすくする(Make it Easy to See) 文章の視覚的な構造を工夫し、素早い情報の把握を可能にする。 段落を短くし、頻繁に改行して「視覚的な休憩」を提供する。 箇条書きやリスト形式を積極的に使い、情報を整理する。 空白(余白)を適切に利用し、圧迫感のないレイアウトを心がける。 4. 第四の原則:書式を生かす(Use Formatting to Your Advantage) 書式(フォント、太字、色など)を戦略的に用い、重要な部分を際立たせる。 太字や下線は、最も重要なキーワードやフレーズに限定して使用する。 見出しやサブタイトルを活用し、文章の構造を分かりやすく示す。 **「箇条書き」や「番号付きリスト」**は、情報の整理と優先順位付けに役立てる。 5. 第五の原則:読むべき理由を示す(Tell Them Why They Should Read It) 文章の冒頭で、読み手にとって読むメリットや重要性を明確に伝える。 忙しい読み手の注意を引きつけ、「これは自分に関係がある」と思わせる工夫が必要。 核心的なメッセージや結論を最初に提示する「結論先出し」の構成が有効。 読み手が何を得られるか(時間節約、問題解決など)を明示する。 6. 第六の原則:行動しやすくする(Make it Easy to Act) 文章を読んだ後に、読み手に何をすべきかを明確かつ容易にする。 「行動の呼びかけ(Call to Action)」を具体的に示し、曖昧さを排除する。 行動に必要な情報(リンク、期限、連絡先など)をすぐに参照できる場所にまとめる。 一つの文章につき、一つの行動に焦点を絞る。 実践的なアドバイス 最も大事なことは、「どうすればこの文章は相手にとってもっと読みやすくなるか?」を常に自問自答することである。 効果的な文章は、推敲によって生まれる。送信前に読み手の視点で徹底的に削り、順序を整えることが、やり取りの回数を減らし、自分の時間の節約にもつながる。 これらの原則は、メール、SNS、提案書、プレゼンテーションなど、あらゆるビジネスコミュニケーションに効果を発揮する。
0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆◆◆◆◆(先生の勉強)司書の仕事をしていると、先生や子どもたち、おうちの方向けに「書く」ことがよくある。せっかく書いたなら読んでもらいたいし、理解してもらいたい。でも、自分の文章はそれを実現できているだろうかという不安もある。そんな自分にとって役立つ本だった。 この本は、効果的な書き方の6つの原則を教えてくれる。ここでいう「効果的」とは、 ①読み手に読んでもらえる ②メッセージを理解してもらえる ③行動してもらえる ということ。 〈効果的な文章の6つの原則〉 1 少ないほどよい 2 読みやすくする 3 見やすくする 4 書式を生かす 5 読むべき理由を示す 6 行動しやすくする すでに意識してることも多かったけど、足りていない点もまだまだあった。 ◆少ないほどよい 書く目的を見定めて、不要な内容は削る。そのほうが読み手に届くし理解してもらえる。自分はついついあれもこれも伝えたくなるし、長く書けばがんばった気にもなる。でも、大事なのはそこじゃない。意志を強くもって言葉や内容をへらそう。 ◆読みやすくする つい難しい言葉を使って知的な雰囲気をまとおうとするクセが自分にはあるかも。できるだけ一般的な言葉を使おう。一文を短くしよう。 ◆読むべき理由を示す 忙しい読み手は「読むべき」と感じないとそもそも読んでくれない。自分の書いた文章を「読むべきだ」とアピールするのは気が引けるけど、メッセージを届けたいならやるべきだなあ。これは今までほとんどやっていなかったかも。 6つの原則は、書くときだけではなく、授業などで話すときにも通用すると感じた。これらの原則を参考に、自分の表現を見直していこう。
2投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでもらえる文章の6原則 ❶少ないほどよい ❷読みやすくする ❸見やすくする ❹書式を生かす ❺読むべき理由を示す ❻行動しやすくする ❶〜❹は無意識にでもやっていたけど、❺❻は意識してなかったので勉強になりました! ❶から❺で読んでもらえたとしても、その文章が読み手の行動を促すものだとしたら、❻ができていないと行動に移してもらえない。とても汎用性の高い考え方だと感じました!
2投稿日: 2025.09.14
