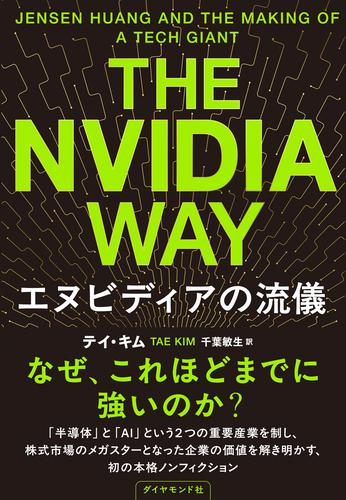
総合評価
(7件)| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログエヌビディアの思想だけでなく、テック業界における、半年で技術が陳腐化してしまう苛烈な競争環境や、上場企業でも一発の開発意思決定のミスで経営が傾くような猛烈な技術開発投資の勢いをかんじられて興味深く感じた。
0投稿日: 2025.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『The NVIDIA Way エヌヴィディアの流儀』を読み終え、率直に感じたのは「表面的な成功物語ではなく、逆境と信念の積み重ねがここまでの企業を築いた」という重みである。以前に読んだ『エヌビディア 半導体の覇者が作り出す2040年の世界』に比べれば、本書の厚みとリアリティは桁違いだ。やはり創業者ジェンスン・フアンをはじめ、多くの関係者の肉声を拾い上げているだけに、企業の内側に流れるダイナミズムがこれでもかと伝わってくる。 印象に残ったのは、NVIDIAが「GPU」というカテゴリそのものを発明した過程である。単なる半導体メーカーではなく、GeForce3やCUDAを通じて「プログラム可能なコンピューティングの未来」を描き出した姿勢は、2020年代のAI爆発につながる布石だった。10年以上前の挑戦が今日の成功を導いている事実に、戦略とは「長期の信念の持続」であると痛感させられる。 また、GPUの用途をゲームにとどめず、バイオテクノロジーや医療へと拡張していった点も象徴的だ。ロス・ウォーカー教授との協働によって、AMBERのGPU版が登場し、世界中の研究者が自宅で最先端のシミュレーションを走らせることが可能になった。このエピソードは、技術が産業や社会に波及していく瞬間、つまりイノベーションを鮮やかに描き出しており、「NVIDIAはゲーム企業」などという短絡的なレッテルを鮮やかに打ち破る。 人材戦略もまた過激なほどに徹底している。買収できないならその会社から人を引き抜く、そこにいても負けるだけなのだから勝ち組に入れと説得する、そして入社した人材には株式付与で強力に報いる。その結果、離職率はわずか3%。「使命こそが究極のボス」というジェンスンの言葉どおり、組織は計画表ではなくビジョンと実利の両輪で動いている。多くの日本企業が「定年まで安定」や「横並びの報酬」にとらわれている姿と比較すると、発想のスケールと合理性の違いに驚かされる。 とりわけ心に残ったのは、ジェンスン自身の生き方である。成功への近道はなく、むしろ困難な道を選ぶことを信条とし、逆境を最高の教師とする姿勢。株式を「自分の血液同然」と語る成長への執念。これらは単なる経営者の名言ではなく、NVIDIAそのものの文化を形づくっている。 本書を通じて私が得た最大の気づきは、「テクノロジー企業の本質はハードではなく信念にある」ということだ。GPUの発明、CUDAの推進、AIへの果敢な賭け・・・どれも短期的には無謀に見えながら、結果として世界の産業構造を変える決定打となった。企業が未来を切り拓くとは、こういうことなのだろう。 『The NVIDIA Way』は、単なる企業研究を超えて、「不確実な時代に何を信じて突き進むべきか」を考えるための一冊だと感じた。読み終えて、自分自身のキャリアにおいても「困難な道を選ぶ勇気」を持てるかどうか、問われているような気がした。
0投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログボリュームは凄いけど、これまでの関係者へのインタビューに基づく時系列の物語風(?)になっていて、歴史と文化の両方を知ることができて、割と一気に読み終えれる。これは読む価値ありありかと
0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとジェンセンファンを持ち上げすぎな気もするけどNvidiaの強さの理由は感じられた。 Appleの創業からのストーリーもそうだけど幸運を確実に掴んで自分の強いフィールドでビジネスで勝っていくのは現代の冒険譚。昔DOS/V自作をやっていた世代からするとNvidiaの覇権の前のS3,3dfx,matroxといった名前で昔を懐かしむこともできる。
0投稿日: 2025.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ半導体、GPUの品質が良いとか、技術力が高いとかだけではなく、自社のGPUを購入、活用してもらう、し続ける仕組み=エコシステムが秀逸。 ちなみに、日本の半導体の最後の砦と言われる ラピダスのことを本質的に理解できていないが、戦略とかエコシステムとして、競争優位性を維持するためのものなのかは疑問が残る。
0投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ一日25時間週8日で働く文化。 優秀な人材を競合から引き抜いてくる力。 それを30年以上続けられることがまたすごい。 とても冗長な本
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、半導体設計大手NVIDIAの驚異的な成長の軌跡と、その成功を支える独特の経営哲学、企業文化、そして創業者兼CEOであるジェンスン・フアンの強烈なリーダーシップ、すなわち「NVIDIA Way(エヌビディアの流儀)」を、創業期の苦闘からAI時代の覇者となるまでの具体的なエピソードを交えながら解き明かす一冊です。(※提供された情報に基づく要約です) 創業と初期の苦難: 1993年、ジェンスン・フアンはサン・マイクロシステムズの同僚だったクリス・マラコウスキー、カーティス・プリエムと共にNVIDIAを設立。当初はPC向け高性能グラフィックスチップ市場での成功を目指しました。 ジェンスンはHPでの製造経験、共同創業者は技術設計の専門知識を持ち寄りましたが、最初のチップ「NV1」は、独自規格が業界標準と合わず商業的に失敗。会社は深刻な資金難に陥ります。 この時期、デニーズでのアルバイト経験(皿洗い、トイレ掃除)が、仕事への取り組み方やコミュニケーション能力の基礎を築いたとジェンスンは語っています。 起死回生と危機乗り越え: NV1の失敗を受け、社運を賭けて開発されたのが「RIVA 128」。開発は困難を極め、エミュレータでのテスト段階でもトラブルが続出。発売直前のベンチマークテスト結果も芳しくなく、会社は再び資金枯渇の危機に瀕します。 ジェンスンは全社員を集め、会社の預金残高をセント単位まで読み上げて危機感を共有。一方で、後に注文が入り財政状況が好転した際には、社員一人ひとりに1ドル札を手渡し、祝賀ムードを抑えつつも感謝と希望を示しました。これらの行動は、彼の率直さと危機管理能力を示しています。 NVIDIA Way - 独特の企業文化: ホワイトボード文化: 会議ではパワーポイントではなくホワイトボードを多用。リアルタイムで思考プロセスを共有し、深い理解と活発な議論を促します。厳密さと透明性が求められる、NVIDIAの社風を象徴するツールです。 フラットな組織: ピラミッド型を排し、社員の自律性を重視。管理職は部下のキャリア指導より専門家としての役割を期待されます。官僚主義や社内政治を嫌い、迅速な意思決定を目指します。 率直なコミュニケーション: ジェンスンのメールは短く要点を突き、会議では徹底的な論証が求められます。曖昧さや言い訳は許されません(LUA - Look Up and Act)。 「トップ5」プロセス: 現場の社員が感じている課題やアイデアを経営層に直接伝える仕組み。弱いシグナルを早期に捉えることを重視します。 失敗を恐れない: 失敗は避けられないものと捉え、挑戦を奨励し、社員に能力証明の機会を与えます。ただし同じ失敗は許されません。 現状維持の否定: 「今までこうやってきた」は通用せず、常に改善と革新を求めます。「人真似をせず、もっとうまくやる」が基本姿勢です。 技術革新と市場転換: CUDAの登場: グラフィックス処理用だったGPUの強力な並列処理能力を、科学技術計算やAIなど他の分野に応用可能にするプラットフォーム「CUDA」を開発。ハードウェアとソフトウェアを統合的に設計し、当初は高価なプロ向けGPU限定だったものを、安価なGeForceシリーズでも利用可能にしたことが普及の鍵となりました。 AIへのシフト: GPUがAI(特にディープラーニング)の計算に最適であることを見抜き、AI分野へ大胆にリソースを投入。研究者コミュニティとの連携や、関連スタートアップの買収(レイ・トレーシング技術など)も積極的に行いました。DLSSのような技術で既存製品の価値も高めました。Googleが開発したTransformerアーキテクチャの登場も、高性能AI開発におけるNVIDIA製GPUの需要を加速させました。 ジェンスン・フアンのリーダーシップ: 技術とビジネス戦略への深い理解、市場の先を読む洞察力、大胆な決断力、そして社員への高い要求水準と細やかな配慮(末端社員の経歴まで把握)が特徴です。負けず嫌いな性格も、組織を成功へ駆り立てる要因となっています。 競争と提携、未来: 製造を委託するTSMCとは長期的なパートナーシップを構築。 アクティビスト投資家との対峙など、外部からの圧力にも冷静に対応。 競合他社に先んじて優秀な人材を積極的に獲得。社員を大切にする文化が低い離職率に繋がっています。 低価格競争を避け、常に技術革新を追求し、高品質な製品で競争優位性を維持。「イノベーションのジレンマ」を乗り越え、AI創薬など新分野への展開も進めています。 NVIDIAの成功は、単なる技術力だけでなく、ジェンスン・フアンの強力なリーダーシップと、それを支える「NVIDIA Way」という独自の企業文化によってもたらされたことが、本書から読み取れます。変化の激しいテクノロジー業界において、常に革新を続け、未来を切り拓こうとする姿勢が貫かれています。
1投稿日: 2025.04.20
