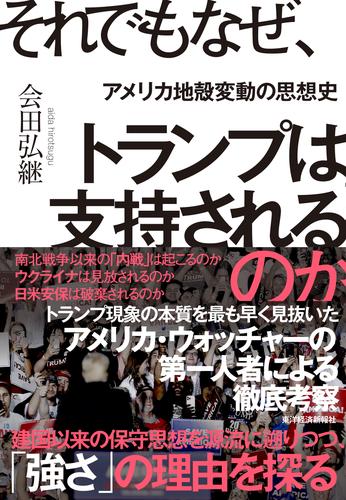
総合評価
(19件)| 1 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜトランプがこんなに支持され続けるのか、その答えと思われるのもが提示されている。 民主党の政策による中間層の没落と、ネオコンの覇権主義の失敗、伝統的なアメリカ第一主義の復活。
0投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく興味を持って読み始めたけど、私には難しく、リタイヤしました。でも、もう一度 チャレンジしたいと思います。
0投稿日: 2025.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「アメリカ政治は左右の分断ではなく上下の分断であり、文化戦争が上下の分断の偽装の道具につかわれている」 アメリカでトランプが再選したのは、アメリカ国民のリベラル疲れと言われていた。そうなのか、程度に思っていたが、本書でアメリカの状況を知ると、想像以上にリベラル的状況になっていた。例えば、ポリコレによるキャンセルカルチャーが一流メディアが白と言っていたものを黒に変えさせたりしていた。これは、反対勢力に対する攻撃ではなく、リベラルの内部統制のような行いであった。 ニューヨークタイムズの自己批判である白を黒に変えさせた経緯は公になっており、その経緯を見た人がポリコレに嫌悪感を感じたのも民主党が負けた理由なのかもしれない。これじゃたしかに揺り戻しがきてもおかしく無いなと感じた。例えば、一昔前までは裏で圧力をかけて差別用語を無くせばよかったけれど、情報の民主化が進んだ現在では変更の経緯も透明化しており、側だけ変えればよかった時代とは違うんだなと思った。 トランプ現象を分析した結果、トランプ支持層と絶望死が多発していた地域が重なっていた。アメリカで他の階層の寿命は伸びているにもかかわらず、白人低所得者層の寿命が縮んでおり、死因は「絶望死」といえる自殺や薬物中毒であった。これは、価値観をアップデートできず民主党政府から見放されたようになった階層が、民主主義の権利である投票によって政治に意見を表明したといえ、大変健全な政治活動である。日本で参政党が躍進したときに、「投票するだけではダメになった」とか「一票の質が」などと言い出す日本とは違うと感じた。 アメリカ以外の先進国でも、極右政党の躍進があるらしいので、これは一時的な転回ではなく、しばらくは続く、とうかリベラリズムの次の思想となりそうだ。
0投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は元共同通信の編集委員。 題名となった問いに対しては、断定をする表現を避けこれまで見たことがない現象が現在進行系だとする。 その現象、すなわちトランプ現象はトランプ自身が作り上げたものではない。アメリカの根底にある新自由主義(ネオリベラリズム)、つまり資本主義が途方もない経済的格差を生み出したことが今起きていると説く。 民主党vs共和党の政権構図も実際には横並びではなく、富める者vs貧しい者の構図になっており、エリートへの反発のマグマが沸点を迎えるところにトランプが出現したと解説する。大分端折ってしまったが、文中ではアメリカの政治思想史を丹念に記す。 現政権にあるのは冷えたポリシーではなくて、熱いモメンタムといったところであろうか。
0投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと右寄りな本。でも日本では破茶滅茶無鉄砲としか報道されてないトランプの裏側?(表側?)の思想とか、アメリカの政治と思想の歴史的な移り変わりとかとても新鮮で楽しかった。何よりアメリカの政治ニュースを見るのが面白くなった。
0投稿日: 2025.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログとてもよくわかった。面白い。しかし深すぎる。バーナムの生い立ちまでくるとなんだかすごすぎ。オバマさん批判。しにくい人だから、米国内でされていることをしっかり書くのは良いこと。オバマさんが外国人とか言い出したのは、トランプさんじゃなくてヒラリーさんなの!ニューヨークタイムズの1619プロジェクト?そんなものがあったのか。だからトランプさんは新聞社を攻撃してたのか。1619プロジェクトのこと日本ではあまり知られてない。日本ではトランプさん新聞を攻撃する悪者扱いだったけど。
1投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ米国の政治はしばしば振り子のように揺れる。理想や多様性を掲げるリベラルが進めばその反動として保守が勢いづく。トランプ氏の言動は過激で分断を招くと批判されるがそれでもなお支持は根強い。 背景には置き去りにされたと感じる人々の怒りと不安がある。グローバル化やIT化が進む中で失業や格差に直面した彼らは「アメリカを再び偉大に」と訴える声にすがった。良識を重んじる声があれど感情に訴える言葉は時に理を超える。民主主義とは耳を傾けるべき声の多様さを映す鏡なのかもしれない。
2投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログトランプ大統領は、原因ではなく結果なのだ。トランプ関税やウクライナ・イスラエル等への外交姿勢、マイノリティに対する差別やヘイトスピーチなど、世界中に大混乱をもたらすトランプ政権が誕生した歴史的経緯を紐解いた内容となっている。 いまのアメリカ合衆国では、絶望的なまでの経済的格差が党派による分断を深くしている。単なる泡沫候補だったトランプは、民主党から共和党に鞍替えして白人労働者の中間層の代弁者となっていく。それまでの共和党は、WASPに代表される東海岸の資本家によって支えられてきた保守政党であったが、産業構造が変わって金融やITが台頭してくる中で、党勢が脅かされていく。 一方の民主党は、クリントン・オバマという環境や人種差別といった部分での政治的正しさ(ポリティカル・コレクトネス)を重視しながらも、その実は金融業界におもねった政策を採ってきた政権によって、リーマン・ショックやイラク・アフガン戦争の泥沼化といった国民に負担を強いる状況が続いてきた。庶民はインフレや増税、社会保障不安に悩まされ、少数の金持ちがこの国の方向を決めるやり方に嫌気が差していたのだった。 そこに現れたのがトランプであり、従来の(資本家向け保守政党=共和党)・(労働者層向けリベラル政党=民主党)という区分けは完全に逆転していく。ポリコレ糞食らえと暴言を吐き、海外の戦争に軍隊や金を出すのではなく国内に投資して移民を排斥しろといったポピュリズムによって白人労働者を岩盤支持層としてさらに無党派層を動員していった。このトランプという怪物を生み出したMAGAという存在こそが、アメリカ第一主義の原動力となっている。 ベストセラー『ヒルビリー・エレジー』を記したヴァンス副大統領や、白人貧困層から史上最年少で入閣したレヴィット報道官など、トランプに続く人材が現れてきている。そしてアメリカ合衆国という世界秩序を制してきた存在が内向きになる時代こそ、パクス・アメリカーナの終焉が近づいていると考えるべきであろう。
3投稿日: 2025.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想、国破れて山河あり。 元の杜甫の春望よりも、やはり芭蕉の感覚の方が、気持ちは近い。どこか旅先の余韻が、ピッタリだ。それでいて戦った自覚は全くないのに、負けていたと、感じてしまった。 冷戦終結時、我々近代国家の数十億人は、負けたのだ、と。アメリカ人も含めて。 世紀末に大転換が来るかと思っていたその十年前に、そう思っていたその時、既に負けていたか。小次郎負けたりって感じだったんかな。 外部性、その圧縮率の比率が、全く質の転換を起こしたのだろうかな。前後の履き違えからくる、チグハグさは、これからもかなり続くのだろうな。
1投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログトランプ大統領は、今米国で起きている分断、民主主義の危機の原因ではなく、その結果だ。 その通りだと思う。 意識高い、あるいは、思惑のある左側エリートさん中心に大騒ぎしているが、要は、そう言う人たちの綺麗事にまとわりつく利権、権力構造への嫌悪が、トランプ大統領という核に集まって溢れ出てしまった。 ちょっと怪獣8号みたい。 金持ちと貧乏人ばかり優遇されて、中間層はそのために搾取されている。 それはいいんだが、同じことばかり言葉変えて言っとるなあ、と思ったら、やはり過去の論説集という体裁だった。ガチの論証だと思うんだが、そこまで固い文章を長く読みたいわけではないので、本気で分析したい方はじっくり読めば良かろう。 ま、日本も同じだけど、依代、いねえしな。 特級呪物ばかり外からも内からも集まって、どうすんだろうね。ほんとに嫌。
2投稿日: 2025.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はあとがきで、トランプ支持者が多数派の今のアメリカについて、 ー 一種の言葉の意味の転倒が起きているのだ。それによって、これまでの常識が通じなくなっている。そのような事態を普通、「革命」と呼ぶ。 と、言っている。 そういうことなのだ。 日本でも、たぶん「革命」は静かに進行している。
35投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログトランプが最初に大統領に選ばれたときは、彼がどういう政策をやるのか、みんながわかっているわけではなかった。だが、彼の4年間をみて、さらに支持者が国会に傾れ込む姿を見て、これでトランプは終わったかと思ったら、再び大統領として復活した。 となるとトランプは、なぜ選ばれたのかをちゃんと理解しないわけにはいかない。 トランプは、これまでの共和党の基本戦略、キリスト教的な伝統的な価値観を社会政策的にアピールしつつ、経済的には新自由主義的な政策を推進するという大きなパターンの中にあるものと考えていた。この社会政策と経済政策の組み合わせは一見変なのだが、アメリカの基本理念やプロテスタント的な価値観で一人一人の自立性というところでなんとか繋ぎ止められているものだったと思う。 以前のトランプは、オバマケアへの批判などから、経済政策的には小さな政府支持なので、基本、新自由主義的な政策をベースとしつつ、一部の産業については保護主義的な方向に向かうのかと思っていた。つまり、保守的な白人の利益を保護しつつ、基本、新自由主義的で金持ちが儲かる世界を作ろうという話しだと思っていた。 が、最近の政策だと一気に保護主義的な政策が全開で、もはや新自由主義とはいえない。小さな政府的なことを言っているが、実は結果的には大きな政府になる方向にある気もしている。 などなど、思いながら、読んだのだが、この本はそういうレベルの話を超えた政治思想、哲学の話しがメインなのだ。 で、これまで全く知らなかった政治思想家の話しがたくさん出てきて、驚いた。そうか、アメリカの保守主義の思想にはここまで深さがあったんだなと。 そして、トランプが選ばれるというのは、世間のムード、不満や彼のキャラクターということもあるのだが、それを支える、正当化する政治の理論、思想があるんだと思った。 一見、そうした思想は、政治に直接関係しないように思えるのだが、やはり深いところで、理論はある政治的な立場を正当化し、一見、破茶滅茶な政策を裏付けしていくということになるのだなと思った。 これまでにない視点をもらった。
2投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#それでもなぜ、トランプは支持されるのか』 ほぼ日書評 Day843 全編を通して、雑誌等への寄稿論文の寄せ集め形式のため、論調に重複が極めて多く読みづらい。 こと前半は、米国社会思想史の系譜にトランプの思想を当てはめることがテーマのため、大元となっている米国思想史に馴染みがないと、大きな文脈を追うことすら難しい(副題に『思想史』と付いているが、むしろそちらをメインタイトルとすべきだろう)。 また、寄稿された時々の文脈で書かれるため、もはやそんなこともあったかなぁ(サンダース大統領候補が一躍時の人になった等)的な内容が多いのも、なかなか入り込みづらい要素。 主タイトルに合致する論考は、ほぼ以下の内容。「これは初耳!」というような内容にも乏しく、数ページのレジュメ的な記述で足りるのではないかと感じた。 ジェフベゾス、ビル、ゲイツ、ウォーレンバフェットというたった3人の資産額の合計が、アメリカ国民の皆50%の合計資産額に並ぶという事実(今なら、これがイーロンマスクに入れ替わるだろうが、基本的な構造は同じだ)。 学歴が高卒以下に相当する白人中年層においては、心臓病などでの死亡は減っているのに、自殺、薬物中毒、アルコール性肝疾患による死亡者数が増えている。中でも、薬物中毒による死亡者数は急上昇中とのこと。 「絶望死」と名付けられた、こうした死者数は、2017年1年間で15万8千人に上る。 この30年ほどで、アメリカ経済は年平均2.5%成長しているが、酵素、水以下の白人男性の平均賃金は年平均0.2%低下した。 つまり、高卒以下の白人は、全く成長の恩恵に預かれないばかりかも貧しくなっている。 さらに、そうした人々を食い物にするように薬物中毒に誘い込み、大手製薬会社が莫大な利益を手にした一方で、高額すぎてそうした人たちには、手が届かない医療制度が背景にあるという。 一般のイメージとは異なり、この貧富格差は(その前のブッシュJr政権の時よりも)オバマ政権時に加速度的に急拡大した。 ポリティカルコレクトネスやキャンセルカルチャーの行き過ぎも酷い。 ある中学で採用された「特権チェック表」には、「白人」「キリスト教徒」「異性愛者」「健常者」といった単語が「特権」として記載されているらしい。 最終章は夏目漱石の『こころ』について。トランプの「ト」の字も出てこない。ここまで来ると単なるページ稼ぎか。 https://amzn.to/4js2PHf
3投稿日: 2025.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログトランプは病因ではない、病状なのだ。原因ではない、結果なのだという。 時代がトランプ大統領を生んだのか。 何が真実かわからなくなっている現代、もしかしたら日本の報道が、トランプを悪人に仕立て上げているのかもしれない。
6投稿日: 2025.01.28民主党の方が立ち後れているのが現状か
2025/01/20の就任前に気になっていた本を読んだ。表面的にしか知らなかった諸々、特にトランプ登場に伴う米国保守思想の革命的変遷とその意味合いが、様々な角度から照らし出されてよく分かる。ずっと不思議だった「露骨な分断と呉越同舟の両立」が、アメリカ特有の「信教の自由」→「宗教の自由市場」からくる二分法のレトリックを基礎にしているという分析には空恐ろしいものを感じた。
0投稿日: 2025.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの保守層は、従来「小さい政府」と規制緩和を主張してきたが、このコロナ禍で「大きな政府」に傾き出している。「政府は解決をもたらすものではない。政府こそ問題だ」(レーガン大統領)「大きな政府の時代は終わった」(クリントン大統領)。共和・民主両党で近年最も人気がある二人の大統領の言葉にも象徴される「小さな政府」を掲げる時代は、いよいよ終わりを迎える気配だ。 トランプは自由貿易と対外軍事介入を否定し、一方で「大きな政府」によって社会保障の維持を約束する、まさにレーガン主義を反転させた選挙公約を打ち出した。こうした公約は特に高校卒業以下の低学歴の白人男性を引きつけ、これが中西部の「ラストベルト」などの接戦州を制する力となった。
9投稿日: 2024.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ雑誌論文を集めた本.章立となっているが,体系的な記載ではなく,同じ人物と思想について,繰り返される記述がとても多い.
1投稿日: 2024.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログトランプ以前の米国政治は民主共和両党の政策は大差なく、支配階層にとってはどちらの政権でも構わなかった。そして支配階層の望み通りに格差拡大していった。白人労働者階級は平均寿命が低下するほど困窮し、自暴自棄になっていた。 そうした白人労働者階級の不満に応えたのがトランプであり、若者の支持を集めたのがサンダースだった。 つまり、トランプとサンダースは支配階層へ反乱者の受け皿。日本では長らく米国支配階層視点のメディアによる米国政治解説がなされてきたので、トランプ政権誕生時にはトランプ支持者への理解が不十分だったが、陰謀論にハマる愚か者が有権者の半分も占めるわけもない。 米国社会の格差と絶望がトランプを登場させた。 つまり、トランプが米国政治と米国社会を壊したのではなく、米国政治と米国社会が壊れているからトランプが登場した。 トランプ登場が当然であることを米国政治の歴史と米国社会の現在地を踏まえて解説してくれるのが本書。なので米国政治の歴史を知るためにも本書は役立つ。 なお、他のレビューアーも指摘していたことだが、著者の雑誌への寄稿文を寄せ集めいるので重複する内容が多い。
1投稿日: 2024.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容としては、タイトルのテーマに沿ったまとまりのある論評·分析ではなく、この数年の間に書かれた論文(評論)を寄せ集めたものなので、重複も多く、中にはトランプと無関係のものもあった。しかし、アメリカの二大政党の変遷と施策について、多くのことを知ることができ、大変興味深く読んだ。まさに自分が、「トランプの奇矯な行動ばかりに気をとられると、その底流で起きている現象を見落としてしまいがちだ」という状況に陥っていたことを認識し、「幸福な国はトランプを大統領に選んだりしない。絶望している国だから選んだのだ」という説明に、深く納得した。
2投稿日: 2024.08.29
