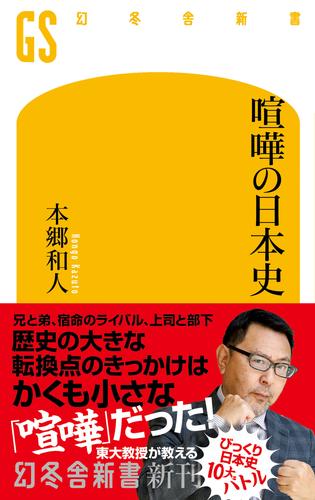
総合評価
(7件)| 0 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「あいつが気に食わない」という理由だけでは、歴史の「喧嘩」は起きない。そういう理由も多少はある場合もあるが、そこには戦略的な理由が存在する。頼朝vs義経、源氏vs北条、鎌倉幕府vs地方武士、尊氏vs直義、謙信vs信玄、信長vs光秀、家康vs秀頼、吉良上野介vs赤穂浪士、井伊直弼vs水戸藩。どれも権威の維持、戦略の違い、理想の現実などを目指した理由があったのだろう。日本は和の国と言われているが、やはり譲れないものがあれば、話し合いでは解決できないのか⁈
54投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいきなり余談だが『花の慶次』でよく前田慶次が「喧嘩」と言っているが実際には殺し合いもしくは戦である事が多い。当時の慣習からするとそれが正しい認識なのだろう。で、本書だが頼朝vs義経を始め事の発端は喧嘩でも最終的には命のやり取りであり多数を巻き込む戦になっているところで本質は変わらないのだろう。 著者の新書は読みやすいのが多いが本書はテーマも面白いし人間の対立軸から歴史を捉えていて人物史が好きな自分としては当たりの本だった。
6投稿日: 2025.05.27日本史上最大の兄弟喧嘩の影響
日本史上の喧嘩の達人たちによる巧みな戦略の数々。 1)小さな火種を大騒動にまで発展させる。 源頼朝は、朝敵となった義経の捜索・探査を理由に、朝廷から全国に守護、荘園に地頭を置く許可を取りつけることに成功する。 義経追討を理由に心の底から欲しかったものを手に入れるという頼朝の見事な戦略で、これにより鎌倉幕府を成立させている。 2)権力簒奪の第一歩は合議制の提案から。 北条時政は、将軍家の権力を無力化させる目的から合議体制への移行を目論む。 一見、専横を生まない民主的な体制のようにも思えるが、すでに権力を手にしている者からすれば、合議制など必要ない。 源氏将軍家の権力を奪うため、自らが権力を振るおうとした北条氏だからこそ合議制を必要とした。 3)すぐに派閥間対立に突入するのではなく、最初は敵対勢力間の仲間割れを誘う。 13人の合議制のメンバーのうち、北条時政の最初の標的となったのは、頼朝の一番の家臣だった梶原景時。 いってみれば秀吉亡き後の石田三成状態で、嫌われ者。 不満を一身に集め、反北条派からすれば仲間なのに、弾劾されてしまう。 敵対勢力は、わざわざ自分らにとって都合のよいはずの勢力を削ぐことに協力させられているのがわからない。 図に乗った時政が嫌われ者の次に標的としたのが、一番の人気者だった。 武士の鑑と評され、御家人たちからも人気の高い畠山重忠を亡きものしようと、陰謀を巡らす。 これが失敗だった。 「彼が謀反などするはずがない。軽率に誅殺すればきっと後悔する」という息子・義時の諌言も聞かず突っ走った結果、逆に鎌倉から追放される憂き目に遭ってしまう。 4)権力差がついてきたら、火種を煽って敵を倒す。 挑発を繰り返し暴発させたり、堂々と喧嘩をふっかけライバルを蹴落としていったのは、北条だけでなく家康もそうだった。 単なる個人間の喧嘩を軸に日本史上で起こった重要な対立を読み解いていくなど無理があるだろうと思わなくもないが、足利尊氏・直義の兄弟喧嘩のように、日本史上に絶大な影響を残した対立もあった。 尊氏と直義の兄弟喧嘩に端を発する路線対立は、その後の室町幕府の歴史を通じてずっと続いていき、ひいては江戸時代にまで影響を及ぼしている。 「西国の京都を中心に政権を構想する足利尊氏派と、東国の鎌倉で政権を構想する足利直義派の対立は、室町幕府の歴史を通じて、射程の長い対立の原理となってきました」 最初は、「京都へ行くか、鎌倉へ戻るか」の行軍の進路の問題だったのが、国家観や理念の違いとなって先鋭化する。 直義の思想は、頼朝以来の「朝幕分離」路線。 「武士の政権は東国に、貴族の朝廷は京都に」という棲み分けである。 それは徳川家康の江戸幕府へと受け継がれていく。 この理念の根底には、「京都のことなんてどうでもいい、関東は関東で好きにやればいい、関東のことだけを考えよう」という東国武士に共通する思想がある。 ようは直義は鎌倉幕府の続きをやろうとしたのだ。 武家は武家で、公家は公家であり、幕府と朝廷は違うものと考えた。 朝廷の争いに武士が関わるとろくなことにならない。 その反対に、武士の政治には朝廷に口を挟ませない。 そのためには、朝廷には近づかずに、鎌倉に戻り、政権を固めるべきだという立場だった。 しかし尊氏の考えは違った。 京都に拠点を置く路線をとり、朝廷と関わり合うことを恐れず、あくまでも武士の政権にイニシアティブがある状態を目指そうとした。 これは常に朝廷の承諾を前提にしながら、自分たちの政権の権益を確立していった頼朝にも通じる思想だが、鎌倉時代とは異なる時代の要請もあった。 つまり、京都とは距離を取ろうという勢力と、貨幣経済の観点から財政基盤を無視して東国に政権を置くわけにはいかないという立場の対立だったのだ。 京都を押さえるということは、商品流通を押さえることであり、経済の中枢を押さえることでもあった。 このように尊氏と直義の対立には、根本的な国家観・政権観の違いがあった。 面白いのはここから。 尊氏と直義といったトップ同士には明確な思想・路線の違いがあっても、家来レベルではそこまで明瞭な違いはなく、単純に「あいつが気に食わねえ」「許せん」といった気持ちだけで対立が継承されていったと言う点。 時代が経るごとに思想や理念は失われ、応仁の乱の頃にはただ代々引き継がれてきた「憎き細川」「憎き山名」という恨みのみで、両陣営分かれて戦さとなっていたということ。 そんなものだろうと思う。
0投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史の大喧嘩を個人の関係にフォーカスして説明していて、しかもその喧嘩が歴史的にどう重要なのか、高い視点からの解説もあって日本史の見方が深まる。 頼朝と義経、源氏将軍と北条氏、鎌倉幕府と地方武士、尊氏と直義、尊氏派と直義派、謙信と信玄、信長と光秀、家康と秀頼、吉良上野介と赤穂浪士、井伊直弼と水戸・薩摩藩という章立て。 日本史上親殺しはあまりないけど兄弟殺しが結構あったり、西上せず鎌倉に留まった頼朝は読み書きもできない武士たちの利益を貴族や寺社から守る棟梁として朝廷から距離を置いて政権を作ったとか、頼朝や秀吉など最高権力者が生きている時の不満が梶原景時や石田三成に向かったんだとか、フビライは日本を攻めるつもりはなく挨拶に来いという使いを何度も無視した時宗の無策、経済活動に課税するため京都に幕府を開いた尊氏と東国にこだわった直義、朝廷を呑み込んだ義満、尊氏派と直義派の対立が応仁の乱まで打て継がれていたこと、室町幕府が関東、東北を切り離していたこと、戦略目標を達成したのは信玄だから川中島の戦いは信玄の勝ちとする考えや晩年に北陸侵略マシンとなったことから謙信が義の人とする説への疑義、徹底した能力主義ゆえに裏切られまくった信長、家康としては豊臣家を相手にした喧嘩だった関ヶ原の戦い、仇討ちは赤穂事件まで家族に限られていたこと、実はまだそんなに死んでいない安政の大獄などなど。 全体の教訓として、喧嘩の火種が生まれたら大きくなる前に対処し、逆に小泉劇場のように喧嘩を利用して利をとるということもあるよと。
2投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史での有名な騒乱、戦いを「とっかかりは喧嘩」という観点から話す。話すと書いたが、読んでいると講演をきいているようでとてもすんなり入ってくる。ある程度流れを知っていることが前提で書いているか、という感じだが、史料を出して、ここにこうあるからこうだ、という書き方ではなく、本郷氏の中で咀嚼されたものを、一般読者向けにポイントを話してくれている。過去の大河ドラマを思い浮かべながら読む。 1.源頼朝VS弟・義経 ~弟は最大の脅威 2.源氏将軍VS北条氏 ~戦いが王をつくる 3.鎌倉幕府VS地方武士 ~ケチな出し惜しみが滅亡を招く 元寇のあと、北条氏が身銭を切って、北条得宗家の領地を少し褒美にやっていればちがったのかも。そもそもフビライは日本を支配下におくつもりはなく、挨拶せよ、という要求だった。それを朝廷、北条氏をも理解していなかった。「挨拶のために使者を派遣します」と返事を出しておけばフビライは怒らなかった、というのが東洋史研究者たちのなかでの定説となっている。フビライの使者・趙良弼は1年ほど日本に滞在して報告書を出している。そこには「日本は肥沃でもなく農産物も豊かでなく掘っても何も出ず特産物もない。戦争はおやめなさい」とある。 ※中国の「冊封体制」、中国の「朝貢国」となり、貢物をもって挨拶に行く。帰りは貢物の10倍ものおみやげをもたせてもらえる。 4.足利尊氏VS弟・直義 ~西か東か、日本は真っ二つ 2人の国家観の違い。弟は鎌倉幕府の形態を継承し京都とは距離を置く。尊氏は京都に腰をすえ、一応土地に対する税といっているが、内実は物資の流通網に対して税をかける。貨幣経済の成長に目をつけていた。三代義満の頃には朝廷を飲み込んでしまう。尊氏は政治、直義は軍事が得意。関東は直義の任せ、鎌倉公方とした。 5.尊氏派VS直義派 ~応仁の乱と関東騒乱の理念なき「喧嘩」 6.上杉謙信VS武田信玄 ~何が何でも「〇〇〇」が欲しかった。 川中島の戦い。攻める側は上杉謙信。守る側は武田信玄。謙信は北信濃の領有権が欲しかった。武田はとにかく北信濃を奪われなければいい。北信濃に残ったのは武田軍なので武田の勝ちといえる。武田軍は海の交易の拠点として「直江津」が欲しかったので北信濃に進軍したが、だめだった。が第4回の川中島の戦いの前年1560に桶狭間の戦いが起き今川義元が破れ、「甲相駿三国同盟」を反故にし、駿河国へ侵攻、海に近い江尻に拠点を構えることができ、武田水軍なども創設。もはや直江津にこだわる必要はなくなった。 7.織田信長VS明智光秀 ~能力主義と抜擢人事の落とし穴 8.徳川家康VS豊臣秀頼 ~関ケ原の「喧嘩相手」は光成にあらず 戦いの根本は「誰と誰が戦ったのか」「戦いの目的は何か」「勝利したのはどちらか」の三つを考える。 家康にとっての目的は「秀頼の首をとる事」。関ケ原時点では、秀頼をいつでも殺すことができる状態にしておくこと。大阪城を支配下に置き秀頼を意のままにする。秀頼が戦場に出て来ていれば、戦況は違った。 9.吉良上野介VS赤穂浪士 ~もしもあのとき、六秒ガマンしていれば 10.井伊直弼VS水戸・薩摩藩 ~桜田門外の変、敵の敵は「敵」 2024.5.30第1刷 図書館
9投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「喧嘩の日本史」とは面白いタイトルですね、数年前から追いかけている本郷氏による今年(2024)5月に発刊された新書です。本屋で見つけた時にはすぐ購入しましたが、最近読みたい本が多くて先日読み終えました。 この本で取り扱っているのは、歴史上の有名な事件ですが、私が歴史の授業で習った「その後の日本の方向性」を決めてしまうような事件も、元を辿れば、人間同士が起こしたものなので「喧嘩」に行き着くとのことです。 喧嘩を起こす前の「感情の高まり」を抑えることができれば、大事件に繋がることが防げたケースもあれば、個人で努力しても、個人についているグループ(派閥等)の影響で、どうしようも無かったケースもあったようです。それらを数々の歴史書を分析して、このような本にわかりやすく解説してくれているのは、私にとっては嬉しい限りです。当分、本郷氏の本は追いかけていきたいですね。 以下は気になったポイントです。 ・平治の乱は、源氏と平氏の直接的な対決というよりも、代理戦争に過ぎない。後白河上皇と信西一派(平氏方)と藤原信頼(源義朝)一派の権力争いのための、それぞれの重要な武力として用いられただけで、源氏と兵士がライバル同士というわけでない。(p27) ・治承・寿水の乱は、源氏と平氏の喧嘩などではなく、調停を中心とする中央政権と、朝廷の影響力から脱したい在地の武士たちの戦い、言い換えれば中央対地方のケンカだった(p33)源頼朝は自覚していたので、東国武士が頼朝を担いだ、反対に木曾義仲は上洛の誘惑に負けて平氏の軍勢を打ち破ったのちに、京都まで軍勢を進めてしまって、後白河上皇と対立を深めて、頼朝に吉中追討の命令が下った(p35) 源義経の最大の誤算は、後白河上皇から頼朝追討の宣旨が降りて大義名分を得たにもかかわらず、彼の挙兵に呼応するものが全く現れなかった(p43) ・頼朝の優れた点は、武士たちの真意を見抜いて、朝廷や西国と一定の距離を取り、東国で力を蓄えたところにある。平氏も、木曾義仲も朝廷に近づき過ぎて墓穴を掘った(p47) ・鎌倉時代の13人の合議制は、北条派と反北条派に二分される、将軍家の権力を無力化させようとする北条時政の思惑から合議制は生まれ、逆に頼家の外戚として力を振る舞いたい比企能院は、自分の息のかかった人間を合議制に入れることで、北条氏の専横に待ったをかけようとした(p62) ・北条泰時は、武士が中心の鎌倉幕府においても、武力だけではく法の支配も需要になると考えて、御成敗式目を制定した、これば鎌倉幕府が150年ほど存続したことに寄与した(p80) ・源平の戦いでは、平家を滅ぼした源頼朝は、平家が全国に持っていた500もの所領を全て鎌倉幕府のものにした、これが幕府の財政基盤となった。承久の乱においては、長鯨に加担した、貴族・寺社・武士の所領が全国に3000箇所あり、全て幕府が没収することができがが、元寇においてはそれがなかった(p94) ・時致の跡を継いで9代執権となった、北条貞時によって制定された「英人の徳性令」は、御家人が自分の土地を御家人でない人間に譲った際、後からその土地を無償で返却してもらえるというもの、御家人間同士でも、売買から20年経過していれば返してもらえた。御家人でない人間に土地を売った場合には、20年間は適用されず無条件で取り返すことができた。これは、御家人ファースト、であり、鎌倉幕府が終わるまで有効な法律であった(p101)これに対して、その法律を取り消すことを要求したのが「悪党=反社会的な人々」とみなされた(p101) ・源氏一門でトップは、平賀氏であったが、北条氏によって潰された、鎌倉幕府を打倒した時、源氏一門のトップであ李、幕府内では北条氏に次ぐ地位にあった、足利氏が反旗を翻したので、初めて御家人たちが動いた(p109) ・足利尊氏は、弟である直義の主張(鎌倉に止まる)とは逆に京都へ進軍した、これは尊氏と直義の国家間の違いであった。尊氏は、武士政権が京都へ進出することを考え、直義は、鎌倉幕府以来の「武士政権は東国に、貴族の朝廷は京都に」という点にこだわった(p117)尊氏は土地以外に、物資の流通網に対して税をかけている、つまり経済活動に対する課税である。国外から宋銭が大量に輸入するようになり、貨幣経済が根付いていたのが、鎌倉幕府設立時との違いである(p119) ・細川頼之は山名氏を討った後、足利義満が室町王権を作り上げていった、その仕上げが南北朝の統一である。南朝の後亀山天皇に、持明院統と大覚寺統が交互に天皇になる両統更迭立などの条件を提示し、これを受託させると、三種の神器を後小松天皇に譲渡し、南朝は終焉を迎えた。その後に、両統迭立は守られず、北朝の系統だけが続いていく(p138) ・応仁の乱は、教科書的には、管領の畠山氏、斯波氏の家督争いと、足利将軍家の家督争いに、細川勝元と山名宗全が介入したことで引き起こされたとされるが、本質は、足利義満の時代における勝ち組である細川氏(とその一族である、赤松氏、京極氏)が東軍に、負け組である山名氏(とその一派である大内氏、土岐氏)が西軍となって時代を超えて幕府の主導権をめぐり対立したと、筆者は考える(p144) ・侍所の長官にあたる所司になれるのが、赤松氏・一色氏・山名氏・京極氏・土岐氏、土岐氏が途中で外されて、4家となったので「4職」と呼ぶ(p148) ・明徳3(1393)年の時点で、足利義満は、関東(鎌倉公方がすでに設置)だけでなく東北も切り離しを行う、これに九種探題が置かれた九州も幕府の直轄統治の対象外となった(p155) ・鎌倉は守りにくいことが新田義貞の攻撃(集団戦に変わっていたので)により明らかになっていたので、足利政和は鎌倉ではなく堀越にとどまり、これが堀越公方となる。ここは北条氏のかつての故郷なので、それなりに整備された土地柄であった、北条公方と言った方がピンとくる。足利持氏の遺児である足利成氏は、下総の古河に本拠を置き、これが古河公方となる(p163) ・本能寺の変は色々と説があるが、歴史学説でかろうじて成り立つのは、四国説である(p198) ・赤穂事件(忠臣蔵)で特異なのは、日本で行われ初めての家臣による主君の仇討ちであった、親の仇討ちは届出をすれば認められていた(p231) 2024年7月13日読破 2024年7月14日作成
1投稿日: 2024.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> 第1章 源頼朝vs弟・義経~弟は最大の脅威 第2章 源氏将軍vs北条氏~戦いが王を作る 第3章 鎌倉幕府vs地方武士~ケチな出し惜しみが滅亡を招く 第4章 足利尊氏vs弟・直義~西か東か、日本が真っ二つ 第5章 尊氏派vs直義派~応仁の乱と関東争乱の理念なき「喧嘩」 第6章 上杉謙信vs武田信玄~何が何でも「○○○」が欲しかった 第7章 織田信長vs明智光秀~?能力主義と抜擢人事の落とし穴 第8章 徳川家康vs豊臣秀頼~関ヶ原の「喧嘩相手」は三成にあらず 第9章 吉良上野介vs赤穂浪士~もしもあのとき、六秒ガマンしていれば… 第10章 井伊直弼vs水戸・薩摩藩~桜田門外の変、敵の敵は「敵」 <内容> いつものごとき、なんでこんなに本を書くのか?の本郷先生。今回は「喧嘩」がテーマ。第5章あたりまでは本職に近い時代だが、第8章以降はどうなの?歴史学者にあるまじき直感勝負。実証性はないかな?第4、5章あたりは確かにそうだなと。視点をちょっと変えることの大事さはあると思う。
0投稿日: 2024.06.16
