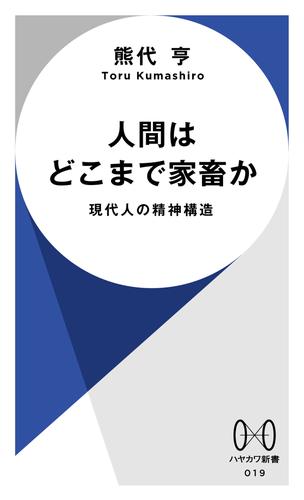
総合評価
(25件)| 4 | ||
| 11 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
熊代亨「人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造」 ◎序章 「自己の家畜化」とは、進化生物学で、哺乳類が進化の過程でより群れやすく、より協力しやすく、より人懐こくなるような性質に変わっていったことをさします。 家畜化(脳内セロトニン分泌の増大など )は人間が社会を築くうえで欠くことのできない要素だといえる。 高密度な集団を保つため増えていくルールや、所属流動性の高さにたいして攻撃性や不安を抑える働きは、セロトニンが担っています。 進化心理学者のスティーブン・ピンカーの著書『暴力の人類史』によれば、太古から現代にいたるまでに人間のふるう暴力は少なくなりつづけているそうです。 家畜といえば動物です。動物園のなかで、ゲージに囲われている動物たち。彼らは、ゲージのなかでは退屈ではあるけれど、野生状態よりずっと安全に管理され、おおむねリラックスして過ごしています。 食物があり長生きで、病気なれば治療される反面、彼らは繁殖期を迎えてもなかなか子孫をつくれません。動物園という人工的な環境では、子どもをもうけられない、育てられない動物も多いのです。 それは現代の日本人にとって子育てがむずかしく、少子化が解決されないことと全く無関係にはおもえません。社会や制度にすっかり囲まわれ、保護され、生かされている点では動物園の動物と私たちの境遇は遠くない…と私には思えるのです。 生物学的な家畜化の進化はかなりスローペースです。なので私は文化や環境の変化が速まれば速まるほど、心を病み、社会不適応をおこし、治療や支援を必要とする人の数は増えるのだと思います。 私は精神科医として働いていると、そうした人間の文化的な決まりごとと動物的な側面の両方を否応なく意識させられます。 従来こうした問題にたいしては人文社会科学領域とされ、盛んに議論されていました。ですが人間は法的主体や経済的主体であるだけでなく、生物学的なメカニズムに基づいて行動するホモ・サピエンスという動物です。 本書を書く際に頼りにした分野があるので少し紹介します。それは歴史学の一派にあたる「アナール学派」です。アナール学派は庶民の暮らし、常識やルール、そこについてまわる感情や感性の移り変わりなどに注目しています。研究対象は主にヨーロッパの中世から近代です。 ◎第1章 進化生物学では時間的経過による世代から世代へ受け継がれる「渡り鳥が長距離を移動する」「クラゲが満月の夜に産卵する」といった進化のことを行動形質と呼びます。 細菌やウイルスのように世代交代が速ければ短時間で進化し、形質を変えていきます。病原菌が抗生物質への耐性を身につけていくのはそのためです。 20世紀中頃、遺伝学者ベリャーエフはソ連の追及をまぬがれるため、ソ連経済のためにも毛皮目的でギンギツネの養殖実験をはじめました。 そしてより人懐こい個体を選別し世代交代を繰り返し、肉食性のあるギンギツネを、100%の確率で人を噛むことのないギンギツネとして生まれるように進化させることに成功します。 形質を変えたギンギツネは、恐怖や攻撃性といった感情や情動的反応の基礎をなす、ストレスに対して分泌されるホルモン(コルチゾールやノルアドレナリン、アドレナリン)を司るHPA系が発達していませんでした。 このギンギツネはすでに家畜とされている、ほかの哺乳類(ウシ、ヒトコブラクダ、ウマ)と同じ身体的特徴を持つことが分かり、それは「家畜化症候群」と名付けられました。 ウマなどに「家畜化症候群」が表れた時期は、おおよそ15000〜5500年前だと推測されます。「家畜化症候群」を通じて家畜たちはより小型に、よりおだやかな気性になりました。生涯を人間社会の保護下におかれることで、野生環境に適応したそれまでの生物学的メカニズムは不用になったのです。 さらに言えばこうした「家畜化症候群」に類似する特徴は人間の体にも起こっています。はるか昔の人類の化石は古いほど頭蓋骨が大きく、現代人はより小顔で若い顔つきになっていきます。脳の容量を増やしてきた人類ですが、ホモ・サピエンスの脳は縮小化をしています。人類史も時代を経るほど安全性のある都市化が進みました。 進化生物学者のジョセフ・ヘンリックは著書『文化がヒトを進化させた』で、「人間は文化を開花させただけでなく、その開花させた文化をとおして進化もしてきた」といいました。 ◎第2章 進化生物学者のリチャード・ランガムは著書『善と悪のパラドックス』のなかで、セロトニンには「カッとなって壊した」「気に入らないから捨てる」といった「反応的攻撃性」を抑えることしかできないといいます。感情によらない「能動的攻撃性」、チームワークや計画性がある組織的大規模殺戮 ジェノサイドは減らしません。 人類史はその大半で、数百人程度の部族で狩猟採集社会を営んでいました。ランガムは、そのため人間はより争いを避け調和的になったり、高密度な集団を維持することでよりしたたかに共同体という社会集団を築くことになったといいます。教わった道徳を守り、ルールを尊重したり、ルールを違反した者に厳しくあたるという気質は人間に共通するものです。 ピンカーによれば、ジェノサイドは国家の統治、すなわち処刑や追放という制度によって減っています。 法や統治機構に基づいて個人の自由な活動を保証する思想は社会契約と呼ばれ、アンシャン・レジーム期にいわれるフランス革命前の時期に議論され始めました。 社会が法によって治められること、そのためにも個人間のやりとりは法に基づくべきとされ、警察や国家による暴力の独占、法治に基づく中央集権化の進んだ状態を想定しています。 社会契約が思想家の夢想から社会の常識に変わるためには、それを支える強力な統治機構が必要でした。 資本主義そのものは、政治的枠組みを提供できません。資本主義が成立するためには、社会契約を成立させられる中央集権国家の介在が必要です。 社会契約や、資本主義や個人主義といった思想は私たちの内面だけでなく、住まいや都市にも、思想が実践され、文化が形をなしたものとして存在します。 明治維新以降、日本でも社会契約の思想は浸透していきました。 それは昭和から平成にかけてなお変化の途上にあったように回想されます。たとえば私有地である空き地は、昭和時代には地域の子どもの遊び場として黙認され、個人所有の家の庭に地域の子どもが入ってくることさえありました。ですが今日では、そうしたことは田舎でもすっかり少なくなりました。 人間は血縁や地縁に基づいたまとまりをなし、集団主義的な性質も持ち合わせています。今日でもそうした心性はナショナリズムや郷土愛、アイドルの推しやスポーツチームの応援などをとおして垣間見ることができます。 たとえば戦後の日本企業は、それに基づいた年功序列の体制で高度経済成長を支えました。 それでも戦後以降、個人主義的なライフスタイルも定着していきます。上司や企業や地域は社会契約に基づく関係か、せいぜいwin-winの関係を期待すべき対象であって、集団主義において美徳とみなされていた「忠誠」、御恩と奉公の関係を期待できる対象ではありません。 精神科医である私には、都市空間の典型である東京が超巨大な精神科病院のようにも見えます。というのも、精神科病院はモニタリングやマネジメントに適した設計になっていると同時に、間取りをとおして患者の行動を変容させたり症状の出現頻度を減らしたりするよう、工夫が凝らされているものだからです。 数百年前のキリスト教の大聖堂と比べても東京という空間は、はるかに大規模で間断なく私たちを啓蒙し、誘導し、諸思想の信徒らしく行動するよう機能しています。 昔から都市は人口を吸い上げる焦点として機能し、常に外側からの人口供給(世代再生産の外部化、人口的搾取)を必要としてきました。 都市はそれ単体では人口学的に成り立たず、動物としての人間がおのずと世代再生産しづらく、人口をすり減らす空間としてあり続けてきました。 そんな都市への人口集中は全世界的にはすでに半ばを越え、世界人口は2064年には減少に転じると予測されています。 生物学的な自己家畜化を超えて、文化や環境に飼い馴らされる生を、あなたは満喫していますか。もし満喫していて、そうした社会と生のありように疑問を感じないなら、そう悪くはないでしょう。ですがもし、この文化や環境に生きづらさを感じているなら? 私たちが生物学的に身に付けている自己家畜化の水準と、"文化的な自己家畜化"のニーズがどこまでも乖離していくことさえ肯定できるでしょうか。 ◎第3章 精神医療の体裁が整ってきた時期は近世以降です。 はじめはヨーロッパ各地で犯罪者や浮浪者とも区別しないまま社会からはみ出している人を施設に収容してきた側面があります。それは、はみ出している人から社会を防衛するシステムとして機能するという社会的側面でもあります。 同じことは東アジアである日本社会にも言えます。"文化的な自己家畜化"を成すことができない人は、ホワイトな職場の功利主義を損ねてしまうかもしれず、生産性や効率性を毀損するかもしれず、権利や雇用契約を侵してしまうかもしれないリスクファクターなのです。 患者が家族や行政や国の干渉を受けると同時に、家族や行政や国は患者を保護したり世話したりしなければならないという社会は、いわば家長制です。 (補足:Google AIによる概要 儒教の家長制度とヨーロッパの家父長制は、家族内の権威構造という点で共通していますが、その起源、特徴、影響は異なります。儒教は、道徳的な秩序を重視するのに対し、ヨーロッパの家父長制は、法的な権力や財産を基盤とする傾向があります。また、儒教的な家族は、伝統的な価値観を重視するのに対し、ヨーロッパの家父長制は、より多様な家族形態を許容する傾向があります。) 精神疾患はその社会の文化や環境によって、病気と判定されるかどうかが変わるところがあります。文化や環境が期待する能力や行動が変わっても適応することのできなかった人が精神疾患と認定され、治療や支援の対象になるのです。 きっと自己家畜化する(HPA系がより穏やかでセロトニンがより豊富な脳をもつ)ことのできた人は少なくないでしょうが、多くもないのでしょう。 アメリカでは1980年代から、日本でも1999年からSSRI(脳内で利用可能なセロトニンを増やす抗うつ剤の一種)が発売されました。それまでの抗うつ剤より安全で副作用の少ないこの薬が軽症〜中等症の治療に果たした役割は大きく、多くの神経症性障害などの治療にも使われています。 発達障害のひとつADHDについてパイオニア的な啓蒙活動をした精神科医の司馬理英子は、1967年出版の著書『のび太・ジャイアン症候群』で、「高血圧がいろいろな成人病を引き起こすように、のび太・ジャイアン症候群は将来の深刻な問題の萌芽になり得る。 そしてこれは治療可能な、治療の必要な医学的な状態である」といいました。 発達障害が他の精神疾患を二次的に併発しやすいことを思えば、司馬の指摘は妥当なものです。それでもかなり先進的な主張だったと推測します。たとえば私の小学生時代を思い出しても、当時の普通学級にはADHD的な子が珍しくなく、ASD的な子や汚言症の子、盗みを働く子すらいました。20世紀の環境では、ジャイアンがのび太を殴るような喧嘩は日常の一部だったようにおもいます。 2007年以降、昭和時代にはそのまま普通学級にいたであろう、さまざまな障害特性を持つ子どもを対象に含めた特別支援教育が実践され始めました。 在籍者数は2010年で約14万人で、2020年には30万人を超えるようになりました。その半数は自閉症・情緒障害で発達障害の子どもたちです。 (補足: それまでの特殊教育では、視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱虚弱の5つの障害をもつ児童生徒だけが対象だった。) 日本の学校教育は財界の意向が反映され、中央集権的な管理教育が推し進められてきたといわれます。その環境に対する何らかの"救済措置"が、発達障害の診断と治療、あるいは特別支援教育だったのではないかと考えられます。 文部科学省は平成18年度 2006年にいじめをより広く定義し、さらに平成25年度 2013年からはいじめ防止対策推進法に基づき、より一層のいじめ撲滅に乗り出しています。 より安全かつ効率的で、よりコンプライアンスに適った教室運営がなされるためには、昭和時代には許容・黙認されていた児童生徒のあやまちやはみ出し、たとえば悪戯や拳骨も、問題行動や校内暴力として認知されなければなりません。 今日の管理教育は、他の子どもに危害を加えず、迷惑をかけず、他人の財産を侵害することのないような、功利主義に基づいたルールを子どもたちに守らせ、馴染ませるものです。資本主義の論理に晒される最前線で育つ子どもはよりしっかりと社会契約や個人主義を内面化し、身につけていくことでしょう。 2022年障害者権利条約の国連審査の際、委員会は障害のあるなしによらない、すべての子どもたちにインクルーシブ(包括的)教育を受ける権利があることを認識するよう要請しました。 おなじ社会のなかに暮らしていても、障害によって選別や排除をしたうえで、それ以外の人々の快適さや効率性が追求されているのではないかという危惧です。 ◎第5章 私は、発達障害と同じことがゲーム症やネット依存に起こってもおかしくない、と考えています。 ゲームやネットが、私たちの日常に結びつけば結びつくほど、それらとうまく付き合えるかどうかが問われ、私たちの社会適応も左右されるように思われるからです。あらゆる営みがオンライン化し、IoT化されたツールとインフラに包囲された環境が到来した時、それらを適切に利用できるか否かがより重大な、人生を左右する課題としてクローズアップされるのは間違いありません。 エンハンスメントとは、本来病気や障害の治療のために開発された医学的技術を、能力向上の手段として用いることを指します。 すでにアメリカではコロナ禍以降、遠隔診療サービスをとおして精神刺激薬であるアデノール(アンフェタミン)が大量に処方されるようになり、供給不足であると報じられました。 エンハンスメントに用いられる薬の安全性は、発売の段階では十分にはわかりません。 たとえばナチスドイツが栄えた20世紀には、ベンゾジアゼピン系抗不安薬が広まっていましたが、依存性や副作用による弊害が表面化するにつれ、国も軍も指導者もぼろぼろになり、崩壊に至りました。 ある社会集団のなかで人々に望まれボトルアップ的に広まったドラッグは、はじめは生産性に寄与し、組織に貢献します。 進歩する文化や環境に適応するためにエンハンスメントを用いること自体は否定できないように思われます。そのとき精神科医は、病者を治すというより社会適応を包括的にメンテナンスしコーディネートする職業と位置づけられるのかもしれません。 しかし肝臓にはSSRIの代謝を司っている酵素があるのですが、性能にバラつきがあり、白色人種ではあまり問題にならないものの、黄色人種、特に東アジア圏では問題が生じる人が少なくありません。 将来的にSSRIが必須の文化では、SSRIの代謝に問題があることも病気たり得るでしょう。 フランスの思想家ミシェル・フーコーは、(処刑や死刑にまつわる)専制君主や国家からのトップダウン的な命令やマネジメントでなく、よりボトムアップで行政的な、庶民や有権者の願いが寄り集まって人間の行動や生き方のマネジメントが起こっていく権力のはたらきかたを生政治と呼びました。 生政治は統計的エビデンスに基づいて人々をモニタリングし、制度やシステムをとおしてマネジメントし、環境に介入し、間接的に影響を与え、生産性や安全性を向上させるものです。 そして家庭や学校で過ごす生活習慣などで身に付ける規律型の権力をあわせ、生権力と呼びます。 フーコーのいう生権力は、精神医療にも、管理教育にも、出生前から臨終までの健康マネジメントにも、ホワイトな職場のウェルビーイングにも、IoT化していく社会全体にも当てはまります。 それは私たちを"文化的な自己家畜化"へと引っ張っていく力、思想に根付いた正当性を伴いながら暮らしに浸透し尽くしているために認識すら難しく、抵抗もしづらい力です。 文化や環境はますます社会契約や資本主義や個人主義に妥当するかたちへ、より良く生きたいニーズに応えるかたちへ変わっていくでしょう。 それらを悪いことだと言うのは難しいことです。なぜなら今日の快適で安全な生活が成立し、たとえば東京のような街も、それなしには成立不可能なのですから。 文化や環境は人間の行動を変え、世代から世代へ受け継がれ内面化されながら洗練の度合いを高めてきました。 しかしあたらしく生まれてくる子どもは必ず、生物学的な自己家畜化以上のものは身に付けていません。 資本主義の思想が浸透し、それを内面化した私たちにとって、資本主義の思想は生物学的な要素よりも強い行動原理になっていて、子孫を残すのにふさわしい暮らしは、資本主義にふさわしい暮らしに上書きされています。 本来資本主義に基づいていなかった領域までコスパやタイパで考えすぎれば、資本主義にそぐわないもの、遠回りかもしれないもの、効率的でないもの、リスクを伴うものが選びにくくなります。 エドワード・ショーターの1987年出版の著書『近代家族の形成』には、地域社会に組み込まれた家族が、プライバシーの内側で家族愛を育みつつ、核家族に変わっていくプロセスが記されています。 急激な経済発展は、ジェネレーションギャップを生み、若者を古い家族観と新しい現実と板挟みに直面させます。そのうえ雇用情勢が流動化し、教育費や住宅費が高騰しているのですから、リスクやコスパの考え方を内面化した若者たちが家族や子育てにまつわるリスクを回避するのは無理からぬことです。 なら、最終的には、配偶や子育ては個人のものから社会のものになるしかないのではないでしょうか。 核家族化するまえの配偶や子育ては、血縁や地縁による共同体を維持するという目的がありました。それは社会契約とそれを可能にする中央集権的国家とは違います。 現代社会は動物としての女性の生物学的特徴を顧慮した進歩をほとんどみせていません。女性の生物学的特徴を踏まえた社会参加の可能性やキャリアにしかるべき尊敬と社会的地位が伴う社会であるべきでしょう。
0投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人間は唯一の耐火種である」 焚火を見て暖かい気持ちになるのは耐火種の末裔だから 現代の狩猟採集民は"平和的で平等主義"(に進化した)→道徳を守りたがりルールを尊重したがる→逸脱した者に厳しくあたる→処刑、追放 つまり人間はチンパンより危険…て全然"平和的で平等主義"じゃないやん 医療保護入院の廃止とか絶対やめて? 閉鎖病棟にぶち込む、治験の実験台、移植用臓器 ●75歳以上医療費負担5割/90歳以上は全額自己負担 ●喫煙、飲酒、登山、海水浴、ジャンクフードなど健康リスクを伴う娯楽にはそのリスクに応じて課税 ●安楽死(DDD=Deign Death with Dignity)の合法化 これめっちゃいいじゃん! 2060年といわず来年から施行しよう!
0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. 自己家畜化の概念 - 人間が自身で家畜化するプロセスを「自己家畜化」と定義。 - 例として、オオカミやヤマネコが人間と共生し、犬や猫に進化した事例を挙げる。 - 進化生物学が自己家畜化の重要性を指摘し、文明社会の形成に寄与したと論じる。 2. 高密度社会とルールの遵守 - 自己家畜化により、人間は高密度な社会でルールを守る能力を得た。 - 攻撃性や不安を抑えることで、交易や都市文明の発展が可能となった。 3. 自己家畜化の進行と自由の懸念 - 自己家畜化が進むことで、文明社会において人間の自由が制約される可能性。 - 精神科医として、ルール遵守が強要されることで不適応を起こす人が増える懸念。 4. 現代の精神疾患の増加 - アメリカの診断基準によると、社会不安症やうつ病などの精神疾患の有病率は高まっている。 - セロトニンの増加は自己家畜化の特性だが、すべての人がそれを持っているわけではない。 5. 現代社会における適応の難しさ - 精神的な適応が難しい人々が増加している現状。 - 発達障害やゲーム依存など、現代のコミュニケーション能力や環境にうまく適応できない人々の問題提起。 6. 文化的な自己家畜化 - 中世から現代にかけて、文化が進化し、より穏やかで合理的な社会が形成されてきた。 - その過程で、攻撃性や衝動性を抑えることが求められるようになり、個人の自由が制約されている。 7. 未来の展望 - 進化と文化のはざまで立ち往生する現代人の姿を描写。 - 医療や福祉、社会制度の発展が進む中で、自己家畜化の度合いが進むことによる未来の不安。 8. 社会契約と個人主義 - 日本の社会契約や個人主義が進化する中で、文化的自己家畜化が進行。 - 現代の人々が自己家畜化の思想に基づき行動することで、より安全で効率的な社会が実現している。 9. 生物学的な自己家畜化と文化的な自己家畜化の乖離 - 生物学的な進化が文化的な期待に追いつけないことが、人間の生きづらさを生んでいる。 - 自己家畜化の概念が現代の文化や環境にどう影響を与えているかを考察。 10. 結論 - 現代人は文化的な自己家畜化に適応しきれず、精神的な問題が増加している。 - 未来の社会において、自己家畜化のニーズと生物学的な特性の乖離がどのような影響をもたらすかを探求する重要性。
0投稿日: 2025.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ家畜化によるメリットとデメリットを考えさせられます。このままでいいのか、人間は何かを手放さなければならないのか、読了後も正しい答えはあるのか謎です。
0投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ我々、現代人は資本主義の家畜なのかもしれない。ボクたちは、一見すると、自由主義に乗っ取った生活様式を取っているが、はたして本当に自由と言えるのだろうか。毎日学校や職場に行かなければならないという生活は、はたして自由といえるのだろうか。現代社会を丸ごとメタ認知させてくれる良書です。
0投稿日: 2025.01.10家畜になれない者たちの今後
昭和、平成、令和と学校における生徒の問題行動は質的に変化している。 学校環境の変化を如実に表わす2つの矛盾する統計結果からそれがわかる。 一つは文科省が出した小学生の暴力件数・いじめの発生件数の調査結果で、平成25年以降の急増が示されている。 もう一つは警察庁の犯罪白書で示される校内暴力で検挙・補導された人数の統計データで、昭和から平成、令和と減少を続けている事がグラブでわかる。 この大きく異なる調査から著者は、教室がかつてなく穏やかに変わってきている一方で、暴力や逸脱に対してより敏感になっていることを指摘する。 かつては教師に食ってかかり、激しく物品を損壊するなど激しい荒れだったものが、注意力が散漫になって授業中に勝手に動き回り、SNSで友だちの悪口が交わされる静かな荒れへ、学級崩壊の質が変化している。 おとなしく従順な子が増えたと見える一方で、表面上では良い子を演じられる生徒の割合が増えたとも言え、結果として落ち着きのない、昔ながらの問題児はより目立ちやすく、異質化しやすくなる。 いじめの定義も、国の方針により、より広く定義されるようになった一面もあるが、より許しがたいものという認識が共有化される一方で、それだけ隠蔽されやすく陰湿化しやすいものに変わった。 著者が強調しているのは、過去と現代で子供に求められている必須の能力が異なってきていて、「より素早く、より厳格に“文化的な自己家畜化〟に沿った行動」を身に付けなければならなくなったと語る。 それができない子どもは排除され、支援や治療の対象となっている。 発達障害を示すADHDも、最初は重度の男の子の患者に限定して治療の対象になっていたのが、治療薬の誕生によって対象範囲は拡大され、それまでグレーだった子供たちも積極的に診断されるようになっている。 注意欠如や多動性障害の子供の増加が話題に上っていた時、こうした医療や製薬会社の思惑や、圧倒的なマジョリティーとなりつつある真・家畜人だらけの教室を想像したことがあっただろうか。 文化や環境から求められる社会適応に直面しているのは子供たちばかりではない。 大人も社会人として、負の感情がマネジメントされコンプライアンスが遵守されたホワイトな職場環境を創出せねばならない。 アンガーマネジメントは言うに及ばず、感情は常に安定していなければならいし、自己抑制も強く働かせた、穏やかで物わかりのよい人間でなければいけない。 勇敢で猛々しく、時に衝動的な感情表出や行動は、かつては美徳とされた時代もあったがいまはそうではない。 侮辱に耐え、冷静沈着、合理的・効率的な行動や抑制した情感の持ち主は、かつては臆病者や卑怯者、落伍者と見なされ、それこそ中世であれば修道院行きであったがいまはそうではない。 すべては逆転した。 HPA系に由来した衝動性は矯正の対象となり、セロトニン分泌量の多い人間は、協力したり教えたりできる必須の人材として持ち上げられる。 ようは「家畜」になれない者たちに待っているのは、肩身の狭い現実なのである。 他人を不快にさせず、安全であることを証明しなければならない世の中は、そうしたくてもできない精神疾患を持つ人々にとっては堪らない時代である。 IoT化が進み生活の隅々までオンライン化した未来には、発達障害と同じ足切り対象の拡大が待っている。 ゲームやネットに没頭できない者、バーチャル空間に馴染めない者、スマートグラスやVR端末に酔う者、監視カメラだらけに違和感を覚える者など、発達障害と似た形で隔離され、治療や支援の対象となるかもしれない。
0投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会からの押し付けに生きづらさを感じつつも、社会によって生きやすくもなっている。生きやすさに傾斜しすぎて生きづらくならない観点を持ちたい。また思考停止のまま社会からの押し付けに流されないよう個人も考えていく必要がある。
0投稿日: 2024.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ第四章 「家畜になれないものたち」が面白かった。発達障害という言葉は現在当たり前のようになっているが、現在の家畜化(著者はフーコーの生政治を解説として用いる)についていけない人でないのかという考察。しかし、Dv加害者や、ジャイアンのような子供も、昔はそういう人はありふれていた、だから彼らも家畜化されにくい人であり今は管理する対象となっているという考察は、やっと現在声を上げられたハラスメントの被害者に対するバックラッシュではないかと感じる(著者のいう、「昔」はそのような被害者自体ないものとされ、中には自殺に追い込まれた人もいるだろう)adhdのような疾患の考察と、権力の勾配がある話とは別に考えた方が良いかと思う。 著者は最後にすこしだけ、「女性に優しい社会を目指そう」と提言するのだが、「家畜化」が男性中心主義であることが、問題の根っこの本質ではないか。他の章でももう少しジェンダーの視点を持って考察してほしかった。
0投稿日: 2024.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった 最近気を使えない奴が増えたなとか思っていたが、そうではなくて社会のルールが厳しくなっているのか 考えてみれば電車のマナーとかは喫煙OKな時代のことを考えると厳しくなっているわ 社会不適合者的な人も増えたと思っていたがこれも同じ理由かもしれない 快適な社会のためには厳しいルールは必要であるが同時についてこれない人間も増えるという意味で微妙なのか
0投稿日: 2024.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ進化生物学や近年の精神医療の現場の状況がまとまっていて、興味深い内容だった。 西暦2060年近未来Aのシナリオが妙に具体的で面白い。逆に2160年の近未来Bはオルダス・ハクスリーのすばらしい新世界を彷彿とさせる感じで、遠くのことを語ろうとすると何かに似てしまい、かえって凡庸になると感じてしまった。
3投稿日: 2024.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ウシやブタ、イヌやネコが家畜化したのと同じように、人間もまた家畜化が進んでいる。それは、ウシやブタのような人為的家畜化ではなく、イヌやネコが人間の生活環境に自ら適応し、生物学的な性質を穏やかで協力的な方向へ変えてきた、自己家畜化であるといえる。 自己家畜化とは何か、その歴史から始まり、現代社会が家畜化と言われる所以、それに適応できない人について、最後に未来はユートピアかディストピアかについて語られている。 現代を生きる人間は自己家畜化を経てきた、それは現在進行形であると言い切るなんて野蛮な、という第一印象をタイトルから抱いていてとても興味がある本でした。 家畜というとウシやブタのことを指し、それが人間に当てはまるなんてと思っていましたが、確かに人間の歴史を紐解き、現代社会の構造について読み進めていくと家畜化されていると思えました。 取り分け最も私の見解をガラリと変えたのは、現代社会は出産も死も医療化されそれが習慣となっているという部分でした。そんな今では当たり前のことと捉えている医療の進歩が人間の文化的な自己家畜化の一因を担っているという考え方は目から鱗でした。 本作では、過去を美化したり現代社会を批判したりすることを主旨とは決してしておらず、文化的な自己家畜化の恩恵を受けるその陰には生物学的な自己家畜化が追いついておらず、社会の変化についていけない人がいる、それを踏まえた上でこの先どうやっていくのかを語られていて、思想や感情的でないところがとても良かったです。 私としては、筆者が提示した近未来はやむなしと思いますし、超未来はSF漫画などで見た未来は現在と地続きで起こりうることだと捉え、そこまで悲観的、ディストピアとも思わなかったです。
2投稿日: 2024.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこれかなり面白かった! 自分は社会不適合だからダメだ…と思ってる人にぜひ読んでほしい。あなたはきっと悪くない。 内容としては、生物学的な自己家畜化が、文化や環境の変化スピードに追いついてない人が医療や支援の対象となっているのではないのか、このままで良いのか、という話だったように思う。 前半は、そもそも自己家畜化ってなんぞ?という話で、ここがめっぽう面白い。動物の自己家畜化の事例や、人間が進化のうえで穏やかにより社会的な人間になってきたことが明かされている。ここが面白すぎて、読みたい本がめちゃくちゃ増えた。笑 そして後半は現代の話にうつる。他人を不快にさせない、長寿で、健康で、効率的であるべき…など、文化や環境が人間に求める能力や行動は変わっていき、生物学的な自己家畜化が追いついていない、そこに適合しない人間は精神疾患と看做される。昔より安全に暮らせるが、本当にこれでいいのだろうか?と著者は警鐘を鳴らす。 これは大きい問題で、かつ解決が非常に難しい問題だと思う。文化が変化するスピードは変えられない。著者は人間にやさしい文化や環境へと舵を切り直すための知恵と勇気が必要と記しているが、人間にやさしい文化ってなんだろう?とも思える。でも多くの人間が自己家畜化という言葉を認識し、現状を理解していったならば、少しずつ何かが変わるのかもしれない。
1投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は動物である 加速度的に発展していく現代、これからも人間的に幸せに生きることができるのか。 ユートピアはなんなのか。 考えさせられる一冊でした。
0投稿日: 2024.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログYouTubeのPIVOTというチャンネルで、著者の説明を聞いて、無茶苦茶面白い!と思い手にした本。読書により更に理解が深まった。我々は家畜であり、飼い主である。それが悪いことかどうかを動画では少し議論していたが、概ね良いこと、というのが結論だろうか。 自己家畜化が起こったさまざまな動物たち。有名なのは実際に家畜化を試みたベリャーエフのギンギツネ。小型化する。のちに大型の品種がつくられる動物でも、最初は野生種から小型化する。野生種よりも顔が平面的になり、前方への突出が小さくなる(=彫りの深い顔から平たい顔になる)。犬歯をはじめ、歯が小さくなり、顎も小さくなる。野生種に比べて性差が小さくなる。雄が強さをディスプレイする度合いが小さくなり、ウシやヒッジなどは雄の角が小さくなる。体重に対する脳の容量が小さくなる、などの特徴をもつ。 また、たとえば野生のキツネやオオカミでも、子どものうちは人間との接触を嫌がらなくなる。その理由は、ストレスに対して分泌されるホルモンを司っているHPA系が機能低下し、コルチゾールやノルアドレナリンといったホルモンが分泌されなくなるから。これらのホルモンはさまざまな臓器に影響し、血糖値や血圧や心拍数などを上昇させ、ストレスの源と対峙できるよう心身を整える効果があり、たとえば敵と戦ったり逃げたりする際にはこれらのホルモンが分泌されるもの。野生のキツネでは、大人になるとこのHPA系が十分に成熟するため、人間に接すると身体がいわば戦闘モードに切り替わり、恐怖や攻撃性を示す。 こうした特徴がまさに人間的。だから、人間が家畜的、という事である(日本語が変だが)。 人間は古い祖先たちと比較して、テストステロンやコルチゾールが減少し、セロトニンが増加したために、穏やかになっている。しかし、注意しなければならないのは、それで減少したのは「ついカッとなって人を殺した」「通行人の目つきが気に入らないから喧嘩を売った」といった、その場の感情に根差した、まさに反応的な殺人や争いであって、計画的な殺人や争いはこの限りではないという事。理性的な殺人は、やれてしまうと。 飼われた豚になるなら飢えた狼に。しかし、そうもなりきれないのは、既に社会全体が相互に飼い主化していて、人は一人では生きられない事の裏付けでもあるのだろう。
55投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科医でありながら人文社会学の視点からみた人類学。 進化生物学的には自己家畜として繁栄してきた人間であるが、中世以降の文化による自己家畜化の加速により、それが恩恵であり人間疎外をもたらすという視点として現代社会を分析していて興味深く刺激的であった。 人間は生物的な進化はゆっくりなのに、急速な文化に適応を求められている。中世と現代人では、別人種ともいうべき位の差があるだろうことに気がつかされた。 過去の流れから推測されるSFも説得力がある。
1投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は文化によって進歩し、豊かな暮らしを実現させたが、その“文化的な自己家畜化”の過程は、ゆっくり進化してきた生物学的な自己家畜化をはるかに上回るスピードで変化しているため、それに適応できない人々が増え続けている。文化的な自己家畜化は、常々身体性から逃れる方向に未来を夢見てきたが、「人に優しい未来」を考えた時に、身体性を顧慮しないのは果たして優しいと言えるのか。
2投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログホモ・サピエンスのビッグヒストリーの中で「自己家畜化」をキーワードの現代社会の成立過程とその影について、哲学、精神医療に触れながら述べられている。本書は自己家畜化というワードに対して善悪の断罪を行うことなく、これまでの影響とこの先の未来について描いていた。
0投稿日: 2024.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『人間はどこまで家畜か』もうタイトルにぎょっとする ここでいう人間の家畜化というのは、現代の人間はより穏やかで安全な文化に適応して生活しているのだけれど、 この文化がより高度なもの、より礼儀正しく感情を荒げることなく他者と協力的なコミュニケーションを取れることを人間に求めるようになってくると 不適応を起こし、文明からこぼれ落ちていく人間が増えていくばかりではないかという懸念ともっと動物としての人間にやさしい未来を考えるべきではないかという警鐘を鳴らす本であった。 たしかに現時点で精神疾患が学生だと不登校、発達障害なんかも増えており、そういった判断や治療が行き届くこと自体は喜ばしいことだけれど、 結果的にふるい落とされた人を排除していることにならないかという指摘には頷いたし、こういった生産性を希求する姿勢そのものがもう限界にきていると思った 熊代氏の言うように高度な文明に生きる人間というよりも、もっと動物的な部分にフォーカスする未来のほうが大人も子どもものびのびと過ごせるのではないかなと思う
2投稿日: 2024.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は生物学的な進化の過程で家畜化してきたが、文化・文明的な意味でも自らを家畜化してきた。しかし今に至って、現代社会が人間を家畜化しようとする圧力は、動物としての人間の首を絞め始めたのではないか?という考察をした一冊。 一章では、人間の生物学的な家畜化がどのようなものかを説明し、二章では近代までの文化による家畜化を、三章では現代文化による家畜化を、四章では現代社会の家畜化圧力による弊害を説明している。最終章である五章では、現代社会の家畜化圧力から導き出される未来像を描いて、その未来を憂慮している。 脳科学者や心理学者、精神科医のおもしろい話には気を付けなければならない。胡散臭い人の顔も思い浮かぶ。この本にしても、引用している文献を恣意的に解釈しているのではないか?という疑いを持つ必要はある。 という警戒は必要だが、著者の見方には概ね同意する。日頃、著者のツイッターやブログは見ているし、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて」も既読なので、このような内容になることの予想はついていた。著者も言及している通り「健康的で清潔で・・・」を踏まえた上で、自己家畜化というキーワードによって考察を深めた一冊だろう。 些末なことだが、猫が家畜化された動物だという話に違和感がある。あいつらは本当に家畜なのだろうか?犬は家畜だと思うが、猫は簡単に野生に戻れるイメージがある。野生のヤマネコと見た目も大して違わない。その点、犬はチワワからブルドックまでめちゃくちゃだ。 平たい顔族の一員としては、家畜化された種は野生種より小型化して顔が平面的になる、という話には思うところがあった。東アジアの人間は動物的特性が弱いのだろうか。 この本では触れられていないが、文化や社会が人間の家畜化を進めた要因として、死刑は大きいと思う。死刑は、野生の狂暴な遺伝子を持った個体が遺伝子を子孫に残すことを難しくしたに違いない。 ところで、私が本書を読む前に密かに期待していたことがある。それはリベラル・ポリコレ批判のための外堀を埋めることだ。リベラル・ポリコレはそろそろ生物学的な人間の対応できる一線を越えようとしている気がする。リベラル原理主義者は人間が動物であることを認めないのではないか。自分自身は15年前だったら、リベラルですよ、と言えた。しかし今は口ごもってしまう。そろそろついて行けなくなっている。なんならマイルドな保守かもしれない。自分はおそらく昭和のリベラルなのだ。真・家畜人失格だ。 だが、リベラルは基本的に、理性的で論理的で倫理的に正しい。そこに異議を唱えるのは難しい。なぜか。その異議は、非理性的で非倫理的で非論理的な動物的な正しさに基づいているからだろう。動物的な正しさは、理性や倫理や論理とは関係がない。論理的な「言語」を舞台に両者が相対した場合、リベラルが勝利するのは当然だ。ただ著者はバランス感覚に優れているらしく、リベラル批判という言質を取られそうなことは書いていない。 急進的なリベラル・ポリコレの動きにブレーキをかけるという意味では、ネトウヨや陰謀論者にも果たす役割があるのかもしれない。彼らはリベラルである真・家畜人より動物的特性が強いのだと思う。ただやはり言論という場に立つと、理性的で倫理的で論理的なリベラルには勝てない。 五章に書かれた未来予測はSFで描かれるディストピアのように感じた。ある程度リアリティもある。しかし本当にそのようになるのだろうか?生物学的にも内面的にも家畜的特性を備えた真・家畜人は、あまり子供を産まないだろう。その一方で、生物学的にも内面的にも家畜的でない特性を持った人々、動物的特性の強い人々、雑にいうとヤンキー素養のある人々は子供を産むだろう。その結果、家畜的特性の強い真・家畜人は絶滅するのではなかろうか? 経済的な側面からも似たようなことを考えてしまう。これから日本は更に没落していくことが予想される。その世界でお行儀の良い真・家畜人は生き残れるだろうか?戦後間もない頃、ヤミ米に手を付けずに死んだ裁判官がいたことを思い出す。健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会は社会的経済的に安定していることが前提だ。それが崩れた時、真・家畜人は葛藤に引き裂かれるだろう。法や倫理の隙を突くチートだのハックだのが一部で支持されているのはその萌芽ではないのか?それでも真・家畜人でいられるだろうか?その時生き残るのは、すぐ怒鳴る、殴る、約束を守らない、略奪する動物的な特性を備えたヤンキーではないか?それはそれで嫌なディストピアだが。
1投稿日: 2024.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログSNSで目に入った書評を見てきっとおもしろいと思って、さっそく入手。 人はこれまでにいろいろな動物を家畜化してきたというのはわかっていたが、自らも家畜化しているという視点はなかった。でもたしかに、自然から切り離された、清潔で計画的で道徳的な生き方は"家畜化"なのだなぁ…。「社畜」のような表現もなかなか的を射ているということか。 この本では、自己家畜化を必ずしも悪いこととはきめつけず、ゆるやかな進化の過程としてはある意味当然の変化だととらえつつ、社会や文化の設計・変化がこのゆっくりした変容がおいつかないほど急なことで生じる問題などを検討してほどよい落とし所を探る必要を伝えている。 少し前のドラマ「不適切にもほどがある!」が、いまから振り返った昭和は雑な部分も多かったけれどいいところもなかったか、昭和の人から見たら目を見張る技術やコンプライアンスに囲まれた現在はユートピアなのかディストピアなのか考えさせる作品だったことを思い出した。 薬によるエンハンスメントの問題はアスリートのドーピングの話と同様に、さまざまな問題をはらんでいるし(ナチス・ドイツがエンハンスメント(向精神薬)を奨励していたとは初めて知ったが、その行き着いたところを知っているのだから、エンハンスメントはやはりあやういとしか言えない)、真・家畜人たれない人が治療を要する対象とされていくことのあやうさはディストピア小説さながらの未来予想図からよく理解できた。最近よくきく行動経済学の「ナッジ」なども、いい面もあるけれど、使い方に気をつけないと危うい気がする。 読んでいますぐどうこうできることもないのがつらいが、こういう流れの中で生きているのだと知ることは無駄にはならないと思う。 そこらに置いといたら、教育実習のため帰ってきている大学四年生の娘が興味を持ち、ざっと最後まで読み終えた、おもしろかったとのこと。
4投稿日: 2024.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
犬や猫は自己家畜化した動物。自ら家畜になった。人間も同じ。 動物園の動物に似ている。動物園の動物は繁殖ができない。ホッキョクグマは、半年以上生きられたのは122頭中16頭。 自己家畜化とは、人工的な環境でより穏やかで協力的な性質に自らを変化させること。 『暴力の人類史』によれば、人間の暴力性や衝動性が減ってきている。 現代人は理性的で合理的、感情が安定しているように強制されている。それができない人が精神病になるのではないか。 アナール学派=社会が変わるとルールや生活習慣だけでなく感情や感性まで変わる。 家畜化したギンギツネの実験。攻撃性が少ないキツネを交配することで、13代でペットとして買えるほどになった。 その特徴は、小型化する、顔が平面的になり前面への突出が小さくなる、犬歯など歯は小さくなり顎が小さくなる。性差が小さくなる。角が小さくなる、脳が小さくなる、繁殖周期の変化。 ホルモンの変化で攻撃性が少なくなる。白い斑点ができるのはホルモンのせい。色素を作るメラノサイトが端まで移動できず、尾の先端や足の体毛が白くなる。副腎の大きさも機能も小さくなり、感情的情動的反応が穏やかになる。象牙芽細胞が少なくなり歯が小さくなる。脳の成長が遅れて小さくなる。性ホルモンが変化し、発情期や生殖サイクルが変わる。 人間にも自己家畜化が進んだ。歯、口、顎のサイズが時代とともに小さくなる。人類は火をあやつることで大きな脳を持てるようになった。消化率がよくなった。ホモサピエンスはネアンデルタール人より脳が小さくなった。脳の使い方が変化した。攻撃性が減って野生動物としての感情的な反応が低下した=穏やかな感情を身につけた。野性的な脳から家畜的な脳へ変わった。文化がヒトを進化させた。動物と穀物を養うと同時に人間も家畜化されたのではないか。 人類は唯一の耐火種である=火を見て温かい気持ちになるおは人間だけ。 攻撃性は反応的攻撃性と能動的攻撃性がある。セロトニンのおかげで、反応性は減ったが、能動性は減っていないため戦争はなくならない。 子どもは「7つ前までは神のうち」死亡率が高い。 かつてはいつ死ぬかわからないという死生観を持つしかなかった。飼いならされた死。 資本主義の定着で、社会契約の遵守が重要になった。 いつ死ぬかわからない死生観では、資本主義は成り立たない。社会契約の中で資本主義や個人主義という思想通りに生きることを余儀なくされている=新自己家畜化。 現代の精神を病む人たちは中世では英雄だったのではないか。 ADHDやASDはスペクトラム的な疾患概念なのため、境目ははっきりしない。有病率は3%、4%とされている。 文化的な自己家畜化についていけない人が精神医療にかかる。 ナチスドイツは、向精神薬で恩恵を受けて、最後は弊害とともに崩壊した。 成功同意書は、性行為の領域に功利主義や社会契約のロジックを導入するツール。自由を尊重するようにみえて、自由を管理させるものではないか。 自己家畜化はゆっくりした変化だったが、文化的な自己家畜化は急速で、恩恵のほかに疎外を生み出している。
0投稿日: 2024.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類は自己家畜化を図ることで社会の豊かさや清潔さを求めてきたが、それに伴い動物的な側面は切り捨てられている。 例えるなら、ドラえもんでいうのび太(授業に集中できない子供)やジャイアン(暴力をはたらく子供)は治療や排他の対象になった。 過剰な自己家畜化とそれに取り残される人々という現状把握。 更にそこからの未来予測。
1投稿日: 2024.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間が衝動的な暴力を集団的な暴力によって排除抑圧し秩序を保つことで、統計学的な生存率を高めるという生存戦略を取ってきたとする進化生物学の自己家畜化の議論から始まる。しかし、本書の中心的なテーマは生物学的自己家畜化ではなく、文化的な自己家畜化と筆者が呼ぶものだ。生権力の議論を自己家畜化という言葉で語り直していると言える。
0投稿日: 2024.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024-03-30 思っていたのとは逆に、家畜になれないものを家畜にならず主体的である方向の議論が読みたかった。どうすれば家畜になれるか、を模索した内容。たぶん家畜という言葉のイメージ(使役者がいる)のせいで、どうもスッキリしない。提示される未来予想図も両極端。 どうせなら、自己家畜化をおしすすめてなお
0投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ一緒に読むとよさげ 過防備都市 (中公新書ラクレ 140) https://amzn.asia/d/i0pqTqY
0投稿日: 2024.03.08
