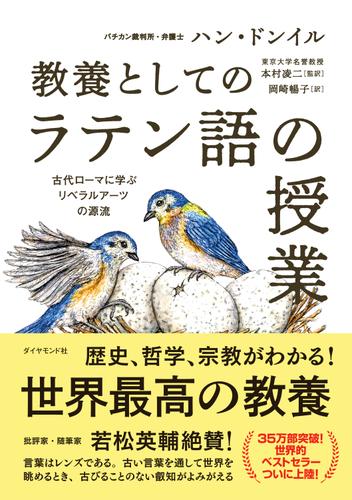
総合評価
(30件)| 4 | ||
| 13 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ東アジア初のロタ・ロマーナの弁護士であるハン・ドンイル教授の初級ラテン語の授業を書籍化したもの。ラテン語の文法や名句だけでなく、関連するローマの生活とか歴史とか英語の語源など幅広い教養が語られている。さらに言えば半分くらいは人生訓だったり、学生への励ましだったり、自分の体験談だったり、学生に伝えたい人生哲学みたいなものが熱く語られていた。結局人に傷つけられたのではなくて、人から受け取った言葉を解釈して自分で自分を傷つけてるんだよなぁとか、耳が痛いのは自分の弱点をつかれているからで、それを前向きに受け止めるのが大事だよなぁとか、自分の心の持ち方や辛い人生に希望を持つ心のあり方を熱く語っている感じ。自分で自分を認めて褒めて微笑みかけてあげないと、みたいな。 そこまで押し付けがましい感じでもないし、優しく静かですっと受け入れられる感じもあるけど、もっともっとラテン語の話も聞きたい。 Do ut des 「あなたが私に施したから私もあなたに与えよう」というのはローマ法の債権契約の項に出てくる法律的概念で、西欧の相互主義という対話の基本原理になったそうだ。たしかに今自国ファーストの極右が世界中で幅を利かす中で、相互主義は揺らいでいる。他者に何を与えられるか、与えられるものがあるよう準備しておくことが大事。
1投稿日: 2025.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語の授業というより、人生哲学の授業。ラテン語やその文化や歴史を題材にとりながら、懐深く、かつ、心に染みる人生の応援歌。ラテン語を学ぶとは、難解な文法を少しずつ読み解き、理解しながら前に進む忍耐力を鍛えることに似たり。まさに人生そのものである。
0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログずいぶん前に読んで感想を書かないままだったが、爽やかな印象だったような。ただし、基本的に日本人にはあまり好意は持ってはなさげな、なんとはなしの印象がある。
0投稿日: 2025.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語を学習すると言うよりは、ラテン語に関する歴史や時代背景を学びながら、「日常生活をどう満足できるものにしていけるのか」みたいな哲学的思考を考える作品だった。著者とは考え方や物事の感じ受け取り方が同じという訳では無いが、自身とは違った考え方を聞ける良い作品だと思う
10投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ韓国の大学でのラテン語の授業を再現している。ラテン語や古代ローマの文化を通して、「生きること」、「学ぶこと」を見つめなおさせてくれる。各セクションが読者への問いかけで終わっていて、ただ読むだけではなくて、読書に一度たちどまって考えさせる仕組みがあって良いなと思った。
0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学の授業のようでスラスラ読めた。 ラテン語を本格的に教えてくれる訳では無いが、ローマの時代の歴史などと絡めた説明がとても面白かった。
0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
語学書ではなく、ラテン語を軸とした随筆。古代ローマからキリスト教、著者のイタリア留学など幅広い。 ラテン語は難しい! 古代ローマでは「男性間の淫乱罪」があり、紀元前149年「スカンティニア法」により金貨100枚の罰金刑に処せられていた。 一口に古代ローマといっても、古代ローマは長いので、年代によって法や習慣が変わってしまうことが、私にとって学ぶ上での難点だ。 古代ローマは同性愛に寛容だと思っていたし、罰金刑は初めて知った。 女性間でも罰則はあったのだろうか。
0投稿日: 2024.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士をしている著者が、自国の韓国の大学でおこなったラテン語の講義の記録をもとにした書。今の時代、教会の裁判所とはどんな役割を担っているのか、ちょっと想像できないがそれはさておき。ラテン語の文法の話も出てくるが、それ以上にラテン語のさまざまな言葉を通じて、歴史、宗教、哲学、そして人生について考える書と言った方がよいだろう。宗教者として学生たちに語りかけている言葉が、静かに心のうちに流れてゆく。日常の些細なことでざわついた心を落ち着かせるように静かに語りかけてくる。 歴史的なラテン語の格言なども多く引用され、ラテン語の入門書としても面白い。ただ、文法上の説明については、疑問を呈するSNSがあるので、若干の注意が必要であろう。しかしそれを差し引いても読むに値する。
2投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語について学びたかったのに、人生教訓本というか、豆知識本というか……自分が求めていたものとは違った。語学をしたい人向けではない。
1投稿日: 2024.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この先生の授業を生で受けてみたいと思わせる一冊だった。少し経ってからもまた読みたいと思った。 中身はラテン語の単語やフレーズから、その背後にある文化的な意味や歴史、宗教のことなどを解説していた。 また、最後の方はラテン語を通じて哲学を学んでいるように感じた。より良い人生にするための哲学をラテン語を通じて教授してくれる一冊だった。
14投稿日: 2024.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りた。 著者は韓国人で初のロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士にまで登りつめた方。語学書ではなく、あくまで教養を学ぶ本と考えてもらった方がいい。著者のイタリアでの留学経験を踏まえ、ラテン語という側面からさまざまな教養を学べる授業だ。実際韓国でも人気の授業となっているらしい。 たしかに、人文・社会科学的な教養を感じられるが、「ラテン語を学ぶ」という側面が弱すぎた印象も否めない。私はその点で物足りなかったかな。
0投稿日: 2023.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養本というか哲学書だった。 ラテン語とキリスト教は切り離せないからきっとそうなる。 ミッション系の母校でキリスト教の授業があり、当時は「イエス様、たとえ話またキターー!」とかおちょくっていたのだが、世界の教養を学んでいたと思うと有り難い時間だった。 言語にはその国の歴史や国民性が滲み出ている。それが学ぶ人にも意識的・無意識問わずゆるりと染み渡っていくのが面白い。 英語にはもう、その文化を煮詰めたような旨味はないかもしれないがその根底にもラテン語が潜んでいて、私たちは知らず知らずに古代ローマの滴を啜っている。 あぁカエサル!2000年も経った今、私が極東の地であなたの言葉を味わっていますよ! 何と尊く喜ばしいことか。 著者はとても勤勉で前向きで愛に溢れていて、その講義に時折涙が出そうだった。 隣国であるにも関わらず韓国にあまり興味を持っていなかったのだが、最近良い出逢いがいくつかありこの先生との出逢いもその一つ。 自分の世界の広がっていく感覚がいくつになっても訪れるのは嬉しいことだ。 人生とは、読書とはかくも素晴らしい。
2投稿日: 2023.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスペイン語やフランス語をかじっているのですが、ラテン語系と漠然と一括りにしていて、活用の「格」が複雑…と思ってた、それらがラテン語から来ているらしい!と教えてもらいました。 そもそも惣領冬実先生の「チェーザレ」を読んでいる最中で、話の中に若いチェーザレがラテン語を理解し、きれいな発音で相手に返す、というようなシーンがあり、ラテン語って!?と思っていたところで読み始めました。 ラテン語の文法だけを学ぶ本ではないですが、ラテン語が、特にキリスト教に関わってきた歴史を、かすかに知ることができました。 かすったので、もっと知りたくなる…(笑)死ぬまでにもう少し知ることができますように… 実は、語学の勉強も、テキスト代がかかるし、将来何の役にもたたないかも…とやめようかと思っていたのですが、この本を読んで、やっぱり続けよう!とあらためて思いました。 「昨日の自分より成長すること」 勉強できる機会があるなら、活かそう!と思ったのです。 リベラルアーツの意味もようやくわかり…「教養」のことなんですね。知識ではなく教養… 読後感としては、ラテン語そのものよりも副題と思われる「古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流」を知る本でした。過去に思いを馳せながら、できることをやっていこう!と思いました。 そして、柔らかく生きていきたいと思いました。
4投稿日: 2023.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語の名句が各章で取り上げられるのだが、その名句に含まれる一つ一つの単語が丁寧に解説されている。英語、スペイン語を学んでいる自分には、ラテン語が語源となっている英語、スペイン語の単語をいくつも知ることができて、言語の奥深さを感じることができた。 著者はキリスト教だけでなく仏教、儒教をはじめとした様々な宗教に造詣が深く、ヨーロッパの様々な言語、世界史や法学にも精通している。真に学問を追究してきた人が紡いだ言葉には、重みがあった。 その一方、韓国ではやはり日本人による征服の歴史が根を張っていることをこの本から感じた。歴史と、日本人に対して複雑な感情を抱く人も韓国には少なくないという事実を、我々も忘れてはいけないだろう。 勉学に悩んでいる私の心に響く言葉が多くあった。本に書かれていたことを、深く考えていこうと思う。著者の人生に対する姿勢を見習いたい。
1投稿日: 2023.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログL’étymologiste non omnia finit. 死がすべてのことを終わらせるわけではない この本にはいろいろなラテン語の名句が出てくるが、この言葉が1番心に残った。私がすべてを終わらせるわけではない、生きている限り希望があるのだ。 ラテン語の授業の話なのかな?という興味で読み始めてみたが、授業は授業だが、ラテン語というよりは、ラテン語を通じた人生の話だった。また、ラテン語がヨーロッパ、英語の元になっていることはしっていたが、ここまで多岐にわたっているとは、言語に興味を持つきっかけにもなる。 作者自身の考え方や物の見方の変化の話もあり、心のありようを考えさせられた。 素晴らしい。
1投稿日: 2023.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ところどころ説教っぽいところもあったが、全体的には興味深い語源や面白いエピソードが散りばめられていて楽しめた。ラテン語にはスペイン語やフランス語と共通している/似ている部分が多くあることがわかって同じラテン系言語だということを改めて感じたと同時に英語に借用されている言葉も多くあってラテン語のヨーロッパ言語に与えた影響力の大きさを感じた。 ラテン語で綴られる格言は高尚な感じがしてかっこいい。日常会話などで言ってみたいと思った
0投稿日: 2023.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 “語学として”のラテン語教本ではなく、ラテン語格言・名言などを通して、様々な価値観、生き方の教訓を学んでゆく本。「教養」とは、ラテン語格言に込められた欧州的価値観……否、そうした地域を限定するものを超えるものを紐解いていく感じの本だった。 そこから見えてくるのは、欧州の「古代ギリシャ・ローマの現文明こそ自分たちの根源である」というプライド。 ラテン語から紐解かれるルーツには、欧米の歴史やリベラル・アーツの話、さらにさかのぼってインド・ヨーロッパ語族に至る。 既にネイティブが存在しない言語なので、発音はどのようなものなのか、ローマ式発音(スコラ発音)、古典式発音(復元発音)があるという。 そうした前提知識から、人生の教訓に至ってゆく。 ラテン語から垣間見る、自己のルーツ(アイデンティティ)を明確化すること、人生観などに至る。 先人たちが遺した様々な言葉と共に。
1投稿日: 2023.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語は自分を表現するための手段であり、世界を理解するための枠組み その通りだが、ラテン語と思って手に取ったら、 自己啓発本みたいな感じで説教っぽく かなりイマイチだった 立ち読みで済ませてよかった
1投稿日: 2023.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語をなぜ学ぶか、興味深く読めた。古代ローマに思いをはせながら、ラテン語の少しかじれて良かった。
0投稿日: 2023.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ○市立図書館より。 ○本屋で見てずっと気になっていた。読んでみるとラテン語の本というよりはラテン語の名言等を通してローマの歴史や文化を語り、さらにそこから現代社会の息苦しさやせわしなさに対する批判や心配、受講生である大学生たち若者世代への思いなどが中心に語られる。 ○平易でわかりやすい語り口で、できるだけ話し言葉をそのままおこしたような文体だからか、読み進めているとまるで自分もこの穏やかで知的な先生の講義を、大学の講義室で学生たちと一緒に聴いているような、そんな心持になった。 ○全体的に感動的で、優しい気持ちになれる本であるのは間違いないのだが、どのセクションでも大体終わりはちょっと浪花節が入るので、だんだん食傷気味になってしまったのも事実である。 *** ○モメンタム=瞬間 ○本格的な勉強の前に、30分くらいのウォーミングアップを入れる(好きな科目など)
1投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代ローマでの価値観や生活をラテン語を踏まえて語っている。韓国の様子も垣間見ることができて面白いが、ラテン語を学べる本ではない。あくまで「ラテン語の授業」の本だと思う。
1投稿日: 2023.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語の名句に学ぶ「捨てる勇気」「川を渡り終えたら、舟は川に置いていかなければならない。」「本来の長所であったものが短所になった時点で、思い切って手放すことが大事なのかもしれません。」(62頁)長所を捨てる、学びを捨てる、持っていること、固執していることが、短所になったら捨てる。あとはこの時点が自分に到来していると気付けるかどうかが問題です。
0投稿日: 2023.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ今からもう40年程前の話となってしまいますが、高校生の頃に「百万人の英語」といラジオ講座を聞いていました。毎日担当の先生が変わるのですが、木曜日のコーナーの先生の授業は殆どが英語でなされて殆ど言っている内容が分からないのに聞いていたのを記憶しています。日本人の先生なので時々日本語を喋るのですが、一番印象に残っているフレーズが、英語のラジオ講座なのに「ラテン語を勉強しなさい」というものでした。 あれ以来、その意味をずっと考えてきましたが、いまだにその解答は掴めていません。現在答えるとすれば、「欧州言語の基礎となったラテン語は他の言語を勉強するときに役立つ、若しくは、難しい文法や3文節以上の単語は教養があるように見える?」でしょうか。そのように思っていた私が、先週品川駅でこの本を見つけました。 教養のあると思われる英単語は、おそらくラテン語によるものだろうと思っていたのですが、この本を読んでその思いを強くしました。また、大学受験のために必死に覚えた「試験に出る英単語」は個人的には大学入試にあまり役に立ったとは思えませんが、大学を卒業して社会人になって、それもビジネスの場ではなく、それ以外の外国人との会話の中で「よくこんな単語を知っているね」と感心されたことがありました、これが「教養のある単語」なのかもしれないと、この本を読み終えて感じました。 この本にはラテン語の解説はそれほど多く載っていませんが、それでも格変化も多く、それぞれの品詞に3種類の性別があり、とても複雑だなと思いました。これからラテン語を克服しようという気にはなりませんが、ラテン語の触りだけでも機会があれば勉強してみたいなと思った次第でした。 以下は気になったポイントです。 ・私のラテン語クラスの最終目標は、ラテン語を使いこなすことではなく、学生たちにラテン語への興味を植え付け、ラテン語を通じて思考体系の新たな枠組みを構築してもらいたい、学生の頭の中に本棚をひとつ作ってあげようというのが私の授業の目指すところです(p26) ・自分の心の中に幼稚な(勉強を始める)動機を発見したとしても、それを否定したり恥ずかしがったりせずに、その学びによって今後何ができるか、どんな面白いものが生み出せるのか想像してみてはいかがでしょうか(p29) ・西ローマ帝国の滅亡により学校が閉鎖されると、ローマ・カトリック教会が公教育を司る。司教座附設学校では、三学(文法学、修辞学、論理学)と四科(音楽、算術、幾何学、天文学)、聖書と司教神学を教えていた、学生は18歳になると司教または司祭の前で、聖職に従事するか結婚するかのどちらかを選択しなければならなかった(p34)命題を作る訓練を第一段階、次に、論理を介してその命題にアプローチすることを問題解決への第二段階だと教育した(p77) ・ラテン語は、インドヨーロッパ語族の影響を受け、中でも、ギリシア語・ケルト語・古代ゲルマン語に加え、ヨーロッパ圏の言語を形成する、イタリック語派の影響を受けた言語に該当する(p42) ・ラテン語に陰りが見え始めたのは、マルティンルターの登場に先駆けて、ローマ・カトリック教会を強く批判する人々が現れてからのことである。この頃にはすでに「ラテン語で語られることは何事も交渉に見える」という概念は時代遅れのものになっていた。(p45) ・ラテン語辞典で動詞を調べる場合は、動詞の「直接法、現在、単数、一人称」で引くようにする(p52)英米ドイツ系の学者たちは、古典式発音を、イタリア・スペインの学者たちは、スコラ発音(ローマ式発音)を使っているが、お互いの話はきちんと聞き取れている。ラテンの国々は自分たちの文化は、その歴史の流れの中にあるという自負心があるため、ローマ式発音を重視している(p53) ・知識を得る行為そのものが学問の目的になってはいけません、学問とは、知るだけにとどまらず、その和の窓から人間と人生を見つめ、より良い観点と代案を提示するものである、人生のために学ぶのが勉強のあり方である(p56)知識を人々のために支えなければ知性人とは言い難い(p57) ・本来の長所であったものが短所になった時点で、思い切って手放すことが大事なのかもしれない(p62)何が長所で短所かではなく、どんな環境であっても省察を通して自分の可能性を発見し、そこから枝葉を広げていくこと、人生とは絶えず長所と短所を自問し、選択をする過程なのではないか(p64) ・学生が自発的に勉強を進める中で最も大切なことは、学生自身の成長であり、他人と比べることではない(p70) ・成功した経験がある人こそ、こうすれば成功できるとか、またはこうすれば失敗を克服できると語れる、そうでない人の言葉には耳を傾けることもない(p127) ・ローマ人は相手が受け取った手紙を読んだ時点でようやく自分の考えが伝達されたと考えたため、受取日に合わせて時制を作成した。現在なら過去分詞、過去なら現在完了分詞、未来は能動未来分詞で表現した。(p132) ・ローマは当時としては最先端の通信システムを構築(駅:馬の交換、馬の世話役の管理、獣医師の管理監督など)し、他の古代社会では見られらない、整備された道路網という社会的インフラを通じて支配していた(p133) ・ローマ法によれば、少年は14歳以上、少女は12歳以上で結婚できた、中世では16歳、14歳であった。一般市民としての法的効力は25歳から適用となるので、結婚はできてもローマ法上は未成年であるため、未成年としての規則を順守することが原則であった(p166) ・学びとは、頭の中を知識で満たすことではなく、自分だけの歩き方・動き方を学ぶことではないか(p168) ・ティラミスとは、ティラレの2人称命令形である「ティラ」に、直接目的語「ミ」が結合、ここに方向を示す「上に」という意味の前置詞「ス」がついたもの、このケーキを食べれば、憂鬱な気分が晴れて元気になれる、という意味が含まれている(p171)難して死んだ日である金曜日に、悔い改める気持ちで肉ではなく魚を食べる習慣である(p172) ・本棚に並べられた本を見れば、持ち主の人となり、がわかると言われる。本以外にも、その人を知る手がかりがある。「40歳を過ぎたら人は自分の顔に責任を持たなければならない」とリンカーンは言ったが、その人のそれまでの性格や表情が積み重なって、40歳を過ぎる頃には顔に現れているという意味である(p250) ・朝一番に鏡の中の自分に微笑みかけることは、自分に対するねぎらいと励まし、となる(p251) 2023年2月9日読了 2023年2月11日作成
3投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「教養としてのラテン語の授業」というタイトルだが、この本でラテン語を学ぶことはできない。ラテン語の幾つかの単語や、名句を手掛かりに、ローマや、それに続くヨーロッパ文化を(つまみ食い的に)紹介しているが、ローマの文化や人々、暮らしぶりについて知りたければ、「古代ローマの24時間」や「古代ローマ帝国1万5000キロの旅」を読んだ方が良い。テルマエロマエという手もある。 この本は、ラテン語の言葉、文句で想起される著者自身の思い出や、人生訓を、大学生ぐらいの年齢の生徒に向かって語るもの、ざっくり言えば雑談、おそらく、大学の講義中の脱線部分を集めたものである。著者が学生に伝えたかったことの本質は雑談部分にあるとも言えるし、人生訓に価値を見出す人はいるであろうが、これを読んだらリベラルアーツの源流についてひとくさり蘊蓄を傾けられるようになるなどと思ってはいけない。 著者は韓国人で、しばしば韓国の現代社会に対する批判が出てくるが、日本と似ているところもあり、多少違うかなというところもあり興味深い。現在の日本の元気のなさに比べて、元気いっぱいに見える韓国だが、若者は結構生きづらいと感じているのだろうか。 最近では、ドラマ、音楽、化粧品/術、料理まで、すっかり韓国に席巻されている感があるが、教養書の類まで、韓国産のものが取り入れられるようになったのは興味深い。 ところどころに、翻訳のおかしいと思われる箇所がある。
1投稿日: 2023.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語を材料にした人生訓の本だった。 外国で暮らす際の心の対応力は、参考になった。 (若い時に知っておきたかった) 面白かったのは、ヨーロッパ言語は水平型の言語なので、ある程度の年月を過ごせばため口で話すことができる、韓国語はそうではない、という指摘。 日本語も同じで、どんなに親しくなっても年長者にはですますで話す。 だから日本社会は年功序列型でジョブ型雇用がなじまないのかな、と思考が飛んだ。
1投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ解剖学の授業で初めて触れたラテン語の響きと気高さに,何となく魅力を感じて,独学でちょっとだけ齧った経験もあり,興味深く読んだ. 途中からややキリスト教の教義的な内容が深まっていき,これは「ラテン語の授業」じゃなくていいな.とも.
1投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語を通じた人生論。韓国で人気の講義、ベストセラー。名句から考察する人生。 難解なラテン語を、学ぶことを通じて人生を考察する。教養が人生を味わい深くしてくれることを教えてくれる一冊。
1投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語にまつわるエッセイ集みたいな感じ。 ラテン語の文法の説明も少しは出てくるけど、ラテン語の解説書では全くないので要注意。
1投稿日: 2022.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今ヨーロッパで使われている言語の母語であるラテン語はアジアを起源とするインドヨーロッパ語族に属しているって面白かった インドでうまれた仏教の経典もサンスクリット語だしそこが繋がってるってのは面白い 行動してその後どう感じるかを経験しないと自分がどうしたいかは分からない ラテン語から人生を考える構成で学ぶってそういうことかって感じられた
1投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログラテン語の有名なフレーズを取り上げて時代背景が紹介されていたり、そこから理解できる当時の人々の考え方から現代の私たちの生きづらさへの処方箋となるような示唆が与えられたりしてページをめくる手が止まらなかった。構えずに読める読み物として面白い!
1投稿日: 2022.10.10
