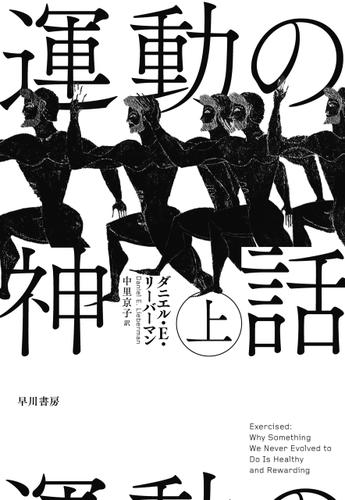
総合評価
(13件)| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/iwjs0027opc/BB04013535 西図書館2階・開架 780.19/L-62/上
0投稿日: 2025.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代に生きる人類が、敢えてスポーツジムでただひたすら歩いたり(トレッドミル)、運搬する訳でもなく重いダンベルを持ち上げる、トレーニングがなぜ現代に必要に至ったのかを、人類学的視点から、新たな知見や興味が、そそられるのを期待して読んでみたが、特に目新しい内容は見当たらず。哺乳類との比較や人類の進化の過程で、今に至ったのかを復習出来るに留まった。運動嫌い、出来るなら体に楽をしたい根拠探しに注力している著者の描き方は面白い。下巻に期待。
29投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類は運動するために進化してきたわけではないが、運動は体にいいのはなぜか。運動にまつわる近代の神話を紐解く。 タイトルから勝手に運動は別に健康によくない的な話かと思い込んでいたら流石にそんなことはなく、やっぱり健康にいいらしい。ランニングのモチベーションアップに活用する。
1投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ健康になるために運動をするという固定概念を持っていたのだけれど、この考え方はひどく現代的なんだなと思った。 本書の後半で出てくる「反応的攻撃性」と「能動的攻撃性」という概念は非常に面白く示唆に富むものだった。 武器が身体の延長線上にあるため、武器を前提としている我々の身体は祖先と比べて弱体化しているというのが上巻の結論なので、下巻でどう話が進むのか非常に楽しみ。
2投稿日: 2024.10.29ピッチャーができるのは人間だけ
「私たちは運動をしたがって当然だ」というのは思い込みであり、神話にすぎない。 我々の祖先を振り返っても、健康のために何キロも走ったり歩いたりするような者はいなかった。 私たちは運動するように進化してきたわけでもなければ、何だったら怠けるために生まれてきたのではと思えるほどの十分な証拠がある。 しかし今では、十分に運動しない人は怠け者とのレッテルが貼られてしまう。 だからといって著者は、運動にまつわるものは全て神話なんだから、体を動かす必要なんてないと言ってるわけではない。 運動は確かに健康を増進する。 著者が指摘しているのは、逆説的なのだが、運動というのは現代的なものでありながら健康的な行為であると言いたいのである。 昔の狩猟採集民たちはよく体を動かしていたが、現代人は十分運動していないという思い込みも人類学的視点に立てば、一日の身体運動を比較するとほとんど変わらないことがわかる。 また自然選択の観点に立てば、繁殖の成功を最大化するには必要のない身体活動にエネルギーを振り向けることは無駄以外の何ものでもなく、何だったら人間は極力体を動かさないように進化してきたとも言えるのだ。 古代の本能から言えば、不必要なエネルギーの浪費を避けるため体を極力動かさずいることは完全に理にかなった振る舞いである。 だがこれが、奇妙にも反転したのは現代になってからであり、健康のために自発的に体を動かすエクササイズが特権階級の特権となったのもここ最近のことなのだ。 それでも狩猟採集民は、現代のオフィスワーカーに比べれば活発だ。 面白いのは、現代人と同じくらい不活発なのは、我々のはるかな祖先である類人猿であるという事実。 それは大部分の哺乳類と比べても、これほど座りがちなのは例外的だと言えるほどなのだ。 なぜなら彼らは、森の中の移動に費やすエネルギーをできるだけ少なくして、可能な限り多くのエネルギーを、繁殖に充てられるように仕向けたためで、その意味で類人猿はカウチポテトになるように適応してきたのだ。 人間がこのカウチポテト族の類人猿から進化したにもかかわらず、それではなぜ狩猟採集民はあれほど活発なのか? 毎日8キロから16キロも歩き、食料や乳幼児を運び、何時間も掘り続け、ときには走るまでに進化した要因は、爆発的な繁殖の成功により、より大きなカロリーの消費とエネルギー生成といった正のスパイラルが働いたため。 それに応じてより脳は大きくなり、社会ネットワークも広がって、ますます繁殖成功度にプラスに働いた。 それでも長時間動かず座り続ける状態は異常。 これにほとんど運動しない状態が組み合わさるなに、さらに問題だ。 私たちの祖先は、腰を下ろす際にも、どっしりと座るより、しゃがんだり、膝をつくなど多様な座り方をしていた。 和式便所が駆逐され、しゃがむことができなかったり、蹲踞の姿勢を維持できない子供が増えていると聞くと、太ももやふくらはぎの筋肉は衰えていく一方に違いない。 人間はその祖先よりますます身体的に弱くなっているが、それは退化したためではなく進化したためだと著者は指摘する。 協調行動が増え平和になり戦わなくてもよいためか? 違う。 スポーツや武器など異なる形で戦うように進化してきたからだ。 まず人類史に起きた自己家畜化について。 この現象は二段階のプロセスで進行し、まず狩猟採集の開始に伴う協力関係の強化という選択圧によって、そしてホモ・サピエンスにおいて女性が攻撃性の少ない男性を選択したことによって生じた。 狩猟採集社会において、男女間の協力関係が増加すれば、女性の役割が増していく。 それに伴い、体格における性的二形性が減少していき、攻撃性が失われていく。 攻撃性は二種類あり、反応的攻撃性と能動的攻撃性がある。 我々は「反応的攻撃性が高く、能動的攻撃性が低い、強くて危険なサルのような動物から、反応的攻撃性が低く、能動的攻撃性が高い、弱くて協力的で遊び好きな人間」へと進化していった。 その裏にあったのは、人類が直立し二足歩行への移行が契機としてあった。 700万年前の運命の分岐点を境に、われわれは四本脚を手放したがために、ずっとのろまな動物として過ごす羽目に。 しかしそのトレードオフとして、直立して武器を使って戦うことができるようになった。 腕を盾として使ったり、棒を振り回すだけではない。 我々は肩を投石機のように使える初めての動物だ。 すなわち人間は、物を力を込めて正確に投げることに適応したのだ。 投擲武器の進化は、体が大きくて反応的攻撃性を持つことの優位性を減らし、自己家畜化を加速させた。
0投稿日: 2024.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ# 運動がヒトとしての文化かどうか、考えさせられた一冊 ## 面白かったところ - 「運動」 == 「ヒトにとってよいこと」に切り込みを挿れるあたりのセンスがもう面白い - 座ることや睡眠、エネルギーのライフサイクルを含めた、人間の分析が面白い ## 微妙だったところ - 特になし ## 感想 食料や領土に命を差し出す必要がなくなって、たかだか数百年を生きる我々にとって、運動という記号が必要になってしまった。 かつては、「生きるために必要だから動く」というシンプルな答えが、今は産業・商業化されたスポーツであったり、エクササイズでありふれている。 動物としてのヒトに求められた運動とは、カロリーを燃やすためではなくカロリーを得るための運動だったはずだ。明日生きるために必要だった運動が、明日死なないようにするために必要になった。 なかなかいい皮肉じゃないか。 運動の統計データの多くは、じつに現代的で食料に困らない欧米人が対象になっていたり、統計学問によりスポーツの数値を向上させるためのプロが参加していたりと、データのバイアスが高いことも1つの見方としていい示唆を与えてくれる。 まだ前半戦だがすごく楽しめた。後半戦も期待したい。
1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ動物は無駄なエネルギーを保持しておくことを最善策として取るのに、人間はなぜエネルギーを意図的に消費する(無駄な)運動をするのか?との着眼点から話が進んでいく興味深い内容。
0投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 感想は下巻にまとめた。 https://booklog.jp/users/suibyoalche/archives/1/B0BDF7S2SL 【まとめ】 1 運動は万能薬ではない 私たちは運動するように進化してきたわけではない。 今日、運動のもっとも一般的な定義は、「健康やフィットネスのための自発的な身体活動」ということになっている。だがそれは最近の現象だ。狩猟採集や農耕にいそしんでいた、さほど遠くない私たちの祖先は、十分な食料を得るために毎日何時間も体を動かさなければならなかった。 健康のために運動するという概念は現代のものである。同時に、運動とは逆説的なものだ。健康的でありながら異常に身体を消耗させ、本来無料でありながら高度に商品化され、喜びと健康の源でありながら、不快感、罪悪感、反感を抱かせる。 運動に関して私たちが抱いている信念や態度の多くは神話にすぎない。誤解のないように付け加えると、私は運動が有益でないとか、あなたがこれまでに読んできた運動に関する話がすべて間違っているとか言っているわけではない。とはいえ、現代の産業化された運動に対するアプローチは、身体活動に関する進化論的・人類学的な視点を無視あるいは誤って解釈しており、誤解、過大評価、誤った論理、散見する誤り、そして許しがたい責任転嫁により損なわれている。 最も問題なのが、「人間は運動をするために生まれてきた」「運動するのは正常なことだ」という思い込みであり、これが運動をしない人を不当に非難し、混乱や疑念を広める原因となっている。 2 私たちは運動するように進化してはいない 進化的に「正常な」人間の運動習慣についてほんとうに知りたいのであれば、現代の欧米人だけに焦点を当てるのではなく、狩猟採集民について学ぶべきだ。 狩猟採集民のハッザ族のもとに筆者が訪れて印象に残ったのは、皆が座ってばかりいたことである。ハッザ族の男女は野営地にいるときは、ほとんどの場合、地べたに座って話をしたり子供の世話をしたりしながら軽い雑用をこなしているか、ただブラブラしている。もちろん、ハッザ族の人々は、男性も女性も毎日のように狩りや食料調達のために灌木地帯に出かけてゆく。ハッザ族の平均的な成人は、1日に合計3時間40分を軽い活動に、合計2時間14分を中程度から激しい活動に費やしていた。この1日数時間の慌ただしさは、平均的な欧米人の約12倍の活動量になるものの、その労働量は、どんなに想像力をたくましくしても骨の折れる肉体労働とは言い難い。 狩猟採集民の行動こそが進化的に「正常な」のだと仮定した場合、アフリカ、アジア、アメリカ大陸の現代の採集集団を対象とした包括的な研究によると、かつての人間の典型的な労働時間は約7時間であり、その多くは軽度の活動に費やされ、活発な活動はせいぜい1時間程度だったということになる。ほとんどの狩猟採集民は適度なレベルの身体活動を行なっており、その多くは座ったままで行なわれている。 人々のエネルギー消費量を測定する指標である「身体活動レベル(PAL)」を用いた研究では、狩猟採集民のPALは男性平均1.9、女性平均1.8で、先進国の工場労働者や農民のPAL (1.8) とほぼ同じで、先進国のデスクワークの人々のPAL(1.6)より約15%高いことが分かった。言い換えれば、ほとんど運動をしない一般の人でも、1日1~2時間歩くだけで、狩猟採集民と同じくらいの身体活動ができることになるのだ。 3 怠惰に過ごすのは不自然か? 人間と同じ類人猿のゴリラが1日に移動する距離は、わずか1.6キロ程度にすぎない。チンパンジーの歩行距離も3〜5キロほどだ。人間は、仲間と比べてもはるかに多くのエネルギーを獲得して消費するよう進化した。 人が「安静」でいるためにはかなりコストがかかる。体重が82キロの男性の場合、安静でいるだけで1日約1700キロカロリーを消費する。活動的なひとでもインドアな人でも狩猟採集民でも、除脂肪体重1キログラムあたり毎日約30キロカロリーを消費している。一言でいうと、活動的な人でも、体を動かすよりも体を維持することにより多くのエネルギーを使っているのだ。 カロリーを消費する方法は5つしかない。体を成長させる、体を維持する、エネルギーを脂肪として蓄積する、体を動かす、繁殖する、だ。人類はこの5つの消費行動を前提に、より繁殖成功度が高くなるよう遺伝子を進化させてきた。自然選択の観点からすると、カロリーが限られている場合、必要のない身体活動から、繁殖またはその成功を最大化する機能にエネルギーを振り向けることは、たとえそのトレードオフにより健康が害されたり寿命が縮まったりするとしても、常に理にかなうことなのだ。 つまり一言で言えば、私たちは極力体を動かさないように進化してきたわけだ。より正確に言うと、私たちの体は、身体活動を含む非生産的な機能に対して、エネルギーを十分にではあるが過度には振り向けないように選択されてきたのである。貴重なエネルギーを、自由裁量である「運動」に浪費しないよう慎重になることは理にかなっているのだ。 4 座ることは不健康ではない 当然だが、座っている方が立っているよりも疲れにくく、よりエネルギーを消費しない。 平均的なアメリカ人が座って過ごしている時間は目覚めている時間の55〜75%を占める。睡眠時間を考慮すれば、1日9〜13時間ほどは体を動かさずに過ごしている。1965年から2009年の間に、アメリカ人が座って過ごす時間は43%増加したとの研究がある。 長時間座ったままでいることが健康に及ぼすと危惧されている影響は、大きく分けて三つある。まず一つ目は、座っているがために、やらないことが問題だ。つまり、椅子に座って快適に過ごす1時間は、運動やほかの何かを積極的に行なっていない1時間なのである。二つ目は、長時間座りっぱなしでいると、血液中の糖や脂肪が増えて、体に害を与えることだ。そして三つ目の、最も懸念される影響は、何時間も座り続けると、「炎症」として知られるプロセスにより、免疫系が体を攻撃しかねないことである。 大部分の脂肪は健康的なものだが、内臓脂肪細胞が膨張すると、炎症を誘発する大量のタンパク質が血液中に滲み出してくる。長時間座り続けることは活動不足を招き、血液中の脂肪や糖を細胞に蓄えてしまう。また、長時間座ったままだと筋肉の活動が停止したままになり、慢性炎症が引き起こされる可能性がある。 実のところ、脂肪細胞の肥大化、血液中の過剰な脂肪や糖、ストレス、そして不活発な筋肉という炎症を引き起こすメカニズムは、いずれも座ること自体が原因なのではない。むしろ、体を十分に動かさないことが原因なのである。だが通常それは、座っている時間が長いことを意味するため、両者が関連付けて語られるのは避けられない。 残念なことに、週に7時間以上の中強度または激しい運動をしている人でも、それ以外のときに座っていることが多いと、心血管疾患で死亡するリスクが50%高くなっていることが分かっている。座り過ぎはジム通いを打ち消すのだ。 では、良い座り方はなにか?コツは定期的に立ち上がることだ。30分に1回、ほんの短時間だけでも座りっぱなしを中断するだけで、糖、脂肪、悪玉コレステロールの血中濃度が低下する。座りながらもぞもぞ動くのもよく、たまに立ち上がってストレッチするのはかなり効果的だ。 注意点は、座るに比べて「立つ」のが健康とは言えないことだ。立つことは運動ではないし、立ち机に大きな健康的メリットがあるとお墨付きを与える研究は存在しない。さらに、12時間以上座っている人は、座っていない人に比べて死亡率が高い傾向にあることは多くの疫学調査で明らかになっているものの、仕事で座る時間(職業的座位行動)が長い人の死亡率が高いことを示す前向き研究はまだ行なわれていないことにも注意が必要だ。つまり、座っていることに関する恐ろしい統計は、仕事中ではなく余暇時間における座り方に基づくものなのだ。
26投稿日: 2023.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログなんでわざわざお金払ってジムで運動するかな?それってほんとに楽しい?みたいな疑問に向き合ってくれた本。
1投稿日: 2023.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読んでから時間が経ったので、 かなりデフォルメして覚えているが、 初期の人類がまだ火を 使えていなかった頃、 集団で生きていた彼らは 肉食獣(最高速度40キロ時) に怯えていたはずだが、 生き延びるために どれくらい速く走って逃げることを目指せば よかったのか、のクイズが 超面白かった。 こたえ: 同時に逃げている 隣の人間より速ければok これには笑った(^^)
6投稿日: 2023.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人間は運動するように進化してきたわけではない。むしろ逆に、運動に費やされるリソースをなるべく節約し、生殖や個体維持のために取り置くように進化してきたはずだ。それなのに、運動が健康のため推奨されるのは一体なぜなのか」。毎日のように何かしらの運動をしている僕だが、言われてみれば確かに不思議な話に思える。我々は盲目的に「運動は体によい」と信じ込んでいるが、もし本当に運動が自然選択上有利な戦略だというなら、なぜ世界がアスリートで溢れないのだろうか。 本書では、ランニング界に革命をもたらした著名本「ボーン・トゥ・ラン」にも登場する著者が、この意外な逆説を各種エビデンスを用いて小気味良く解きほぐしていく。自身のフィールドワークによる直の体験談も各所に散りばめられており、またユーモアたっぷりの文体も魅力的で飽きさせない。上下巻の構成で少々冗長ではあるが、冒頭で謎かけのように掲げられる「マントラ」──「『運動の生理学』は進化に、『行動としての運動』は人類学に、それぞれ照らして見なければ筋が通らない」が徐々に解き明かされていく過程はなかなかに読み応えがある。 パートⅠは「身体的に不活発な状態」がどのようなものかを考察する。著者によれば、「不活発=不健康」というドグマの背後にはジャン=ジャック・ルソー以来の「自然人理論」がある。これは、自然の「野蛮な」状態で暮らすことこそが人間本来の姿である、と主張するもので、西欧社会で運動不足を諸病の根源とみなす態度はこれに起源するという。しかし、現代の「野蛮な」狩猟民族たちの多くをみると、むしろ一日の大半を我々と同じように不活発な状態で過ごしている。この矛盾を説明するのが自然選択上の「トレードオフ」、すなわち限られたエネルギーを生殖や個体維持などのための生産活動と、不必要な身体活動とのどちらに振り向けた方が生存上有利か、と言う問題だ。当然ながら前者により多くのエネルギーを取り置いた方が優遇されるため、本来人間は運動を避けるように進化してきたのだという。 そして、座ること自体に問題があるのではなく、sedentaryなライフスタイルが伴いやすい別の問題、すなわち肥満やそれに伴う慢性炎症、筋肉の減少こそが問題なのだと指摘する。 睡眠については、短いながらも最新の科学的知見がコンパクトにまとめられている。主に運動と睡眠の質に関するトピックが多いが、個人的には世界中の非工業化社会の人々が、我々が通常そうするのとは逆に、周囲の騒音や光などを全く遮断することなく睡眠をとることが多いという事実に目を開かされた。最近、焚き火や波、雨の音などを睡眠導入時に流すアプリ等を目にするが、そういった刺激がむしろストレスのない睡眠に繋がるという事実が裏付けになっているということだろう。 パートⅡは身体活動のうち主にスピードとパワーにフォーカスが当てられる。スピードと持久力のトレードオフを、細胞レベルの代謝機構で説明する部分はやや入り組んでいるが、運動開始からの時間経過で稼働する代謝機構が交代することがよくわかる説明になっている。また、筋肉増強による力強さとスピードのパワーオフから、過去の人類にとては筋肉が必ずしも長所でなかったことの指摘も面白い。 なお、人間の成体が他の霊長類に比べ非攻撃的に進化したことの説明として、リチャード・ランガムの「反応的攻撃性/能動的攻撃性」の概念を持ち出しているが、これは個人的には説得力あるもののようには思えなかった。現代人は前者が弱く後者が強いとしているが、行動経済学者のダニエル・カーネマンによれば、脊髄反射的・短絡的・近視眼的な思考様式「システム1」は我々現代人の脳にも根強く残っている。また集団内での協力姿勢を強めるため「自己家畜化」により自ら能動的攻撃性を弱めるよう進化した、というが、協力姿勢がそこまでの選択圧として本当に機能したかは検討の余地がありそうだし、「遊び」を覚えた人類がスポーツで攻撃性を抑えたというのもやや出来すぎた説明に思えた。
4投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「運動は健康に役立つのか」 「そもそも人間に運動は必要なのか」 人類の歴史からみる運動との関りを紐解く考察はとても刺激的で面白い。
2投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、運動にまつわる神話や思い込みについて、実際はどうなのか、著者の専門である進化生物学の見地から検証したものだ。 まず大前提として、「人間は運動するように進化してきた」という神話があるが、実際は、不必要な運動は避けるように進化してきたのだそうだ。 パートⅠでは、「座ることは不健康である」「8時間以上の睡眠は不健康である」といった神話に対して検証している。 パートⅡではスピード、力強さ、パワーについて、人間がいかに弱い存在か、ウエイトトレーニングの必要性、人間にとってスポーツとは?が書いてある。 下巻へ続く
23投稿日: 2022.10.16
