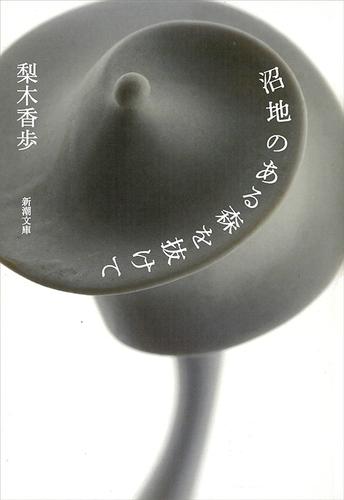
総合評価
(193件)| 34 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 15 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解できるところと理解できないところが極端にわかれた。 合間に挟まる「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」がなんなのか考えるのが楽しかった。 5年後くらいにまた読んでみたい。
1投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は面白かったけど途中からよくわからず、読み飛ばしてしまった。うーん、今は頭が足りないみたいなので、また読み返してみたい。
0投稿日: 2025.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ(借.新宿区立図書館) ぬか床にまつわる因縁ものかと思ったら、最後は最初の生物というか細胞に至るちとめんどくさいお話に。
0投稿日: 2025.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログはじまりは、「ぬかどこ」だった。先祖伝来のぬか床が、うめくのだ――「ぬかどこ」に由来する奇妙な出来事に導かれ、久美は故郷の島、森の沼地へと進み入る。そこで何が起きたのか。濃厚な緑の気息。厚い苔に覆われ寄生植物が繁茂する生命みなぎる森。久美が感じた命の秘密とは。光のように生まれ来る、すべての命に仕込まれた可能性への夢。連綿と続く命の繋がりを伝える長編小説。 「新潮社」内容紹介より 読後に残る欠片は、「原初の望み」みたいなもの. 結局はそれをプログラムされているんだ. 人間がそれをまねて組織を作るのも、絵として表現するのも、すべてそこにつながるんだ. そして人として生まれてきたからにはそこからは誰も逃れられない. 人が作り上げてきたと幻想している家の格式とか、集落のしきたりとかといったものが、外部からの働きかけにより壊れていく様は、現在の様子に重なる. ただ壊れるだけではなく、それは新しいものへの変容とか、再生といったものにつながっているところが、細胞と重なって面白いと思った.
12投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に想像してたストーリーとは全然違った結末というか途中から予想してなかった話になってきて、 途中からどういうことや?となりながらでも読む手は止まらず。だいぶ専門的な感じがエッセイしか読んだことなかったけどそこで感じた梨木さんらしくてこんなに小説に特徴が表れるんだなぁと。 結局どうなったの?と言われれば全然わからないけど、すごく興味惹かれる内容ではあった。
0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中までは軽快に次はどうなるかと想像しながら読み進めましたが がらりと変わってからはむずかしかった。 ちょっとついて行けなくなりましたが 命の始まりのことが最初からずっと繋がってたのかと思いあまりにも壮大すぎて きっとどんどんはまっていくと面白いのだと思いましたがやっぱり私にはむずかしいテーマでした。 島に着いてからはテンポ良く読みましたがなんとなく胸にひっかかりが残ってしまった 最後の詩はよかった。
0投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ先祖から伝わる「ぬかどこ」をめぐって奇妙な出来事が起こる。その「ぬかどこ」から自分のルーツを探しに行くんだけど予想の付かない出来事の連続で夢をみているようだった。 ただ、主人公を大事にしてくれた叔母さんの愛情が心に響いた。「血」の繋がりはどんなことがあっても切っては切れないものなのだなあと、ふと自分の家族の事を思い出してしまった。
0投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんとゆうか、これは、語彙力を試されているかのような話だった。 あらすじをゆうと、主人公の叔母が亡くなり、一族の故郷の島にある、沼の成分が入った家宝の「ぬか床」を受け継いだところから話が始まります。 ぬか床って、わたしもかつて世話をしていましたが、毎日手を入れて底からかき混ぜて空気を入れないといけない、けっこう手間のかかるものです。 それを引き取るかわりに叔母のマンションも譲り受けるのですが、そのぬか床の手入れを怠ると、ぬか床から文句を言われたり酷い匂いがしてきたり、昨日まではなかったはずの卵がぬか床の中から生まれて、卵からは人が生まれて、それが子供の頃亡くなった同級生の男の子に見えたり、親友に見えたり、両目だけがあちこち浮遊している、「カッサンドラ」というのっぺらぼうな女の人が出てきたりと、奇妙なお話が続きます。 物語がぐっと動き出すきっかけは、主人公の両親は事故で亡くなったと聞かされていたけど、実は叔母とおなじ心臓麻痺だったということを知り、真相を確かめるために、男性の体だけど男性という性別を捨てた風野さんという人と一緒に故郷の島にいくところから。 そこで、沼の秘密とは。 自己とは何か。 自分と他者との境界についてや、生物が一つのものが二つに分裂していくことを繰り返す無性生殖から、二つのものが一つになる有性生殖が始まった起源を辿るような、まるで神話を読んでいるかのような壮大な物語と様変わりしていきます。 他の梨木さんの作品でも生きることや死ぬこと、などのテーマを扱ったものがいくつかあると思いますが、この話はその根源的なルーツにも思えるような感じがして、読み終わった後はしばらく呆然としてしまうようなお話でした。 なんとも奇天烈な話ですが、ずっと心に残る作品です。
0投稿日: 2025.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読、なのにはじめて読んだような感じです。最初に読んだときは、この物語を受け入れる準備が自分にはなかったのかな?と思う。たぶん三度目の再読があると思う。
79投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな物語に出会えて嬉しい。 生物としての喜び、幸せを斬新な切り口で伝えてくれる。自分の存在まで背中を押された気分になった。幸せになろうと思える話、ちょっと忘れちゃった。また読みたい
1投稿日: 2025.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
梨木さんの本は何冊か読んできたけど、中でも少しハードな題材の物語だったという印象。 自己、生殖、性、生命、循環…。 幻想的ではありながらも、SF的な要素もあって新鮮な読み心地だった。 風野さんの「性別への嫌悪感」みたいなものがすごくリアルで共感した。私自身も「男の子になりたい」というより「女の子をやめたい」と思ったことが何度もあったし、「みーんな細菌になって無性別になればいいのに」って思っていたこともあったので、風野さんの考えを馬鹿らしいとは思えなかった。 特に印象的だったのは、最後の沼地での富士さんのセリフ。 『沼地は、もう、前のような方法では生殖を行わないから、彼らはこの種の、最後の人たちとして、ここで平和に滅びてゆくんだ。』 何故か分からないけれど、地域猫のことが頭に思い浮かんだ。 ずっと古代の頃は野生で、人間の事情でともに生きるようになって、ここ数年で人間の事情で野良猫は許されない存在になった。地域猫たちは避妊・去勢手術をされていることが多く、彼らの命は1代限り。いろいろな事情で昔のままではいられないからしかたがない変化ということはわかっている。ただ、彼らの最後も平和であってほしいと町で見かけるたびに思う。
7投稿日: 2025.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終えるのに3、4ヶ月かかってしまった。 更に感想書き終えるのに数ヶ月? ぬか床から卵が出てきたり、そこからひとが孵ったり。人に説明しようとすると、ついこのようにセンセーショナル?な感じで言ってしまってましたが、不思議ではあるけど嫌いじゃないんです。だけど伝わらない自分の語彙力。いや語彙じゃない。よりによって場面一部切り取ってそこしか言わんのがあかんのですよ、自分。とわかっちゃいるが、余りにインパクトがありまして。 ぬか床、酵母、菌。生命の根源から未来まで。 何言ってるんだか。でも相変わらず梨木さんの本は読んでいて気持ち良いのです。 カッサンドラの目がパタパタしてるのは気持ち悪いような、でも可愛いらしさも感じるような…まさに文章ならではの面白みだなあと。 島のイメージは青ヶ島とか勝手にそんな感じをイメージしたけど、もっと沖縄の離島な感じなのかな? 自分が行ったことあるのは父島の森だからなあ。 大東島とかそんなイメージもあったり。 途中で挟まれた僕たちの物語も嫌いじゃなかった。 しかし読み手を選ぶ本ですね。
2投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語の始まりは糠床。 亡くなった叔母から不思議な糠床を引き継いだ上淵九美。 そしてその糠床からは不思議な現象が。 人(沼の人たち)が現れるのだ。 第三章で突然視点が変わった時、一瞬ついていけなかったが、ああ、「僕たち」とはもっとミクロな存在の何かかしら? と思い至る。 これは多分、かつて、まだ島の沼地が機能していたころの菌類たち目線のお話なんだね…。 う~ん…こ、これは……苦手だった~⤵⤵ 奇をてらって…と言ってはいけないよね。 でも九美が主軸の章における糠床の異変や、フリオのキャラクターにしろ、「僕たち」の章の異色の目線にしろ、最後までどうしても馴染めず…。 不思議現象をすっと受け入れることが出来ず、この作品が本当に伝えたかったことを真っ直ぐ受け取れなかった。 山場と思われる島を訪れてからのストーリーも…う~ん…。 要はこの不思議現象に気を取られ過ぎた。 ざっくり、“脈々と続く細胞レベルでの自分探し旅”のような物語だとは思ったのだが。 好きな作家さんであっても、全作品が好きとは限らないもんね。 いや、少し前に読み終えた『ぐるりのこと』に通じるような内容でもあったのだけれど…。 ちゃんと読み込めなかった自分が残念。 こりゃぁいつか読み直しだな。
33投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ先祖伝来のぬか床に由来した奇妙な出来事。その謎を追っていくうちに明かされる家族のこと。そして主人公はぬか床を故郷に返すべく、一族が生まれた島の生命みなぎる森の沼にたどり着く。 生物って、生命って。圧倒された。濃厚で壮大。濃ゆい梨木さんの物語、好きよ。
1投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
沼地のある森を抜けて 先祖がぬか床を持って駆け落ちして以来、ずっと守られてきたぬか床。叔母の死をきっかけに、叔母のマンションと共にそのぬか床を継いだ主人公の物語と、ぬか床の中の酵母やら細菌やらから見た物語とが交錯しながら話が進んでいきます。 自分のアイデンティティ、命のはじまり、何故有性生殖か?、そして命は何を目指してどこにいくのか? こういった問いが詰まった(結局結論は出ませんが)難しい話を、ある程度の難しさを残してはいますが、エンターテイメントにしてしまう著者の力量はたいしたものだなあと思います。 ぬか床が呻いたり、ぬか床の卵から人が出てきたりと幻想小説っぽいところもありますが、「家守奇譚」のようにそちらが主ではないので、さらりと現実的に描かれていて、その点も面白いなと思いました。 ちょっと残念だったのが、「おおーこの構造は、”世界の終わりとハードボイルドワンダーランド”(村上春樹)だー」とものすごく期待したのですが、2つの物語の絡み方や収斂の仕方が今ひとつだったのが、期待が大きかっただけに残念です。 もうすぐお盆なので、自らの自出やご先祖さんのことを、無い頭で考えてみている竹蔵でした。 竹蔵
1投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ親族から相続したのはぬか床。そのぬか床から現れるものは。久美と風野さんはぬか床の秘密を求めて「島」へと旅する。 ずっと以前に読んでいたのだけど、何か消化不良で心にひっかかっていた本。再読です。 梨木さんは、今のモノ・コトについて、その記録のページを一枚一枚めくるように思索を掘り下げていくのが得意な作家さんで、けっこうなナチュラリストでもあると思います。この本ではその科学的知識と命の進化から、生命とは何か、生命はどこから来るのか、という根源的な問いを深める作品でした。 確か前に読んだ時は「結局そこに落ち着くのか」みたいな、ちょっとしたガッカリ感を感じたのではなかったかと思いますが、まあ今回も、そこまで広げておきながら結論はそこかあ。という感想にはなりました。ただ、最後の誕生を言祝ぐ詩にはすごくグッときたのですが、これは多分このストーリー(落とし所)だったからこその効果だったんだろうなあ、と感じました。 しかし改めて読み返して感じたこととしては、梨木さんがすごく真剣に命はどこから来るのか、どこへいくのかについて向き合いながら書いたんだな、ということでした。共生説や受精になぞらえたサブストーリーなんかをみても、その思索のあしあとは迫力がありました。 同じく生命のゆくえについては「ピスタチオ」でもテーマにしていたと思うので、こちらも再読してみようと思いました。
24投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
沼地のある森を抜けて 梨木香歩 ぬか床から人がってのでファンタジー?と思ってたら人が死んでるってのでホラー?そこからトラウマとかルーツ探し?と読み進めると、最後壮大な生命と再生の物語 この最後を読む為に今までの鬱々としたのがあったのね、と 言葉にできないほどにカタルシス凄い "解き放たれてあれ 母の繰り返しでも、父の繰り返しでもない。先祖の誰でもない、まったく世界でただ一つの、存在なのだから、と" もういないのに傷つけられた記憶と対人恐怖症だけ残ってる私には この本はとてもよかった この壮大な再生を言葉で表現して本で主人公と一緒に体験できるのがすごい ひっそりととても良い本ですと 万人向けではないかもしれないけど、こじらせてる大人にはオススメです
3投稿日: 2023.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
そうかこの人裏庭書いた人だった 最近怪談よく聞いてるから結構怪談っぽい話で嬉しい 梨木香歩さんは最初はとっつきやすくて引き込まれるけど最後何の話?!ってなるんだよな全般的に… 分かる人すごいわ…大学院とか行ってんだろな…
0投稿日: 2023.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
梨木香歩「沼地のある森を抜けて」、2005.8刊行、2008.12文庫。全510頁。ぬか床を毎朝かき混ぜていると、卵ができ、やがて人間が誕生する。誕生し、そして消えていく。酵母、微生物・・・。種の起源といいますか、生き物とはを問うた作品でしょうか。4日間かけて何とか読了、ふぅ!鴻巣友季子さんの解説を読むと、自己とは何かを探す物語とか? 梨木ワールド全開でしょうか・・・? 私には理解不能な作品でした。でも、ぬか床の記憶は残りそうですし、糠漬けを食べるたびに思い出しそうです。毎朝食べています(^-^)
0投稿日: 2023.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ『西の魔女が死んだ』『家守奇譚』などからしっとり系ファンタジーを予想していた。しかし、これははっきり言ってハード系SFだと思った。 植物に詳しい作者が、その嗜好全開で書いた作品と聞いていた。植物うんちくなどというものではなく、生物のありようを哲学する壮大な、思想というべきかというテーマを描いている。 時代も場所も現実幻想の境界をまたぐ目まぐるしい展開で、主義主張も随所に散りばめられている。面白いけれども、なかなか理解・共感ともに難しく、ハードな読み物であった。
1投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまたなんとも不思議な…ぬか床から出てくる人(?)たちとの交流を書いた作品。ミツヒコが出てるところまでは微笑ましかったけど、その後はちょっとダラダラしていた気がする。家に昔あったぬか床、あれにも何かあったのだろうか…
0投稿日: 2023.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ何書いても余計になる気がするけど、書いてみたいから書く。 読み進めていくと、綺麗な情景や人間との関わり(個人的にそう感じた)と相対するように生物の底なしの存続への渇望が醜く表現されすごく絶妙な話だと思った。 最後、風野さんと久美ちゃんはどういう結末を迎えたんだろうか。 きっとしばらく経ってから読み返すべき話だ。 私には少し早すぎたのかもしれない。
2投稿日: 2023.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ生生しく体をかき回されるような描写に取り込まれて、官能小説のようだなと思った。 ぬか床をかき回したくなる。
2投稿日: 2023.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ぬか床から始まる日常物かと思いきや、どんどん話が膨らんでいき、最終的には生命の深淵をのぞき、そして読者にも問いかけるような内容となっている。 後半から挿入される「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」はかなり抽象的だが細胞壁=ウォールを持つ生き物とそこに入り込んできた似て非なる生命のお話で(だと思っている)同じテーマをあつかっている。 もとはひとつの生命が生まれ、壁を作り、それを壊し、そしてまたひとつになることの不可思議さと奇跡、または呪いや祈り。 自分が何者かの定義の曖昧さもあれば、確固たる 自分の意思もあるような気がするその線引きの危うさと自由さ。 そういったものを深く考えさせられた。 誰もが良いと思う作品ではないと思うが、個人的に 忘れられない作品となった。
2投稿日: 2023.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
うむむむむ、難解・・いやいや、私の読解力や知識が不足しているだけ・・・ 初めの、フリオの話は面白くて一気に読んでしまった。 梨木さんってこんな物語も書くんだ?と思いつつ、 久美の自問自答がちょっとおもしろいところもあって、 クスッと笑ってしまった。 いやー面白い、と思いながら読み進めると、一気にトーンというか景色というか、物語の色みたいなものが変わる。 カッサンドラの話は、口だけの三味線女がでてくるなんてホラーでしかないんだけど、叔母だけでなく両親の死までさかのぼって真相を、となると、もはやミステリーのようにもなってきて、心がかき乱される。後々わかったけれど、カッサンドラが久美にとってジョーカーで、ジョーカーを消したことで、ぬか床やその元の沼に変化が起きたってわけなのだな(と、書いておきながら、本当にその解釈でよいか、自信がない)。 カッサンドラがそんな感じだったのに、次のシマの話。 え?村上春樹?違うな。カズオ・イシグロ?(←ひと作品しか読んでないのに)小川洋子?と読書家の皆様から激怒されそうな的外れなとまどいを覚えつつも、そうか梨木さんには「裏庭」という長編ファンタジーもあったな、と思い出して、少し心が落ち着いた。 クスッと笑えたフリオの話から、菌類、無性生物と有性生物、全宇宙のはじまり、最初の細胞の孤独、などなど、どんどん壮大な話へと広がっていき、「これは何のこと?何を表現しようとしているの?」と自問することをやめ、そのまま、文章通りに受け取ることにした。 あらゆる生命体は、意図せずとも「孤独」を感じ、それゆえに繁栄へ向かっていくものであり、その過程で必ずやそのもの自身やまわりの環境に変化というものは訪れ、それはどうにも止めようのないもので、いずれは死、無に終着する。「生」の期間、自分と他者をどう区別しているのか。自分と他者を隔てるものは何なのか。 などなど考えながら読み進めたけれど、やっぱり深くは理解できなかったと思う。 ただ、読んで面白かったか、面白くなかったかと言われれば、面白かった。 いつも思うけれど、梨木さんの頭の中の思考はどうなっているのだろう。
6投稿日: 2022.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの作品。 受け継いできた糠床。その糠床との生活は想像すると面白いがなんだか恐ろしい。そして、その糠床をなんとかしようとしたであろう両親や叔母は命を落としていて、どうやったら解決できるんだろうと思いながら読み進めていた。 最後の方、なかなか世界の理解が難しかった。
1投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語としては、「ぬかどこ」から始まる不思議なお話ではあるのだが、読んでいくうちに、現実の生命現象がすでに不思議な存在であることを再認識することになる。 生命とは、性とは、個とは。現代の生物学的知識を踏まえた上でも、語り切れるものではない。では、その先、我々はどう考えたらよいのだろうか? その問いに対して、本書は、ひとつの方向性を示してくれるだろう。
4投稿日: 2022.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆5じゃ足りないです 読み終わって世界の見え方が少し変わるような 自分の心や体の様子とともに周囲に五感を働かせてみよう 読後、ぬか床に挑戦したくなる!?
3投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・動きや感触の表現が、読み返したくなるくらい綺麗だった。 ・何について語っているのかはっきりと示されていない章もあり、色々想像しながら読み進めていくのが楽しかった。 ・自分の意思がしっかりあって、冷静に適切な言葉で相手に伝えられる久美ちゃんのような大人になりたい。 ・久美ちゃんと風野さんのその後がすごく気になる〜気になる〜 ・めちゃくちゃ現実の中にあるありふれた物にファンタジー要素を落とし込んでいるのが最高。
1投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ中盤から終盤までは、物語の根源風景がなかなか見えず、 少々読みあぐねたが、 文章自体はグングンと飛翔していくので、とにかく追いかけた。 終盤に「ぬか床」や「沼地」についてやっとこ入り込み、 「解き放たれてあれ」という名言に光を感じながら、 森を歩き、抜けていけた。 最終的に、自分の中でこの物語の世界観が心に定着したので安心した。 生命に問いかけ、根源を悟り、孤独と他者を知り、また始まっていく。 解説の一文 「個を超えた反復であり、同時にその場にしか生まれえないオリジナルでもある。」 のように生命の二律背反を感じつつ、時にそれを飛び越えていく物語だった。 にしても、このような物語を成立させる「言語」という機能は不思議で凄いなと感じる。人間の前頭葉のなせる技だろうか。 言語は人間から生まれたものであるならば、生命の型を持っているのだろう。 言語もそれだけでは「孤独」だから「他の言葉」を探し繋げ、 意味という膜、ウォールを作り、 他者に伝えていくのだろう。
1投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
始まりはぬか床、ぬか床が生み育むのは美味しいぬか漬けや発酵菌だけではなかった。そこは豊穣たる命が宿り、生み出す世界。 …お漬物マニアなら、こんなこと考えたりするし言うだろうけど、まさかこんな惹句が400Pを超える長編小説になりうるとは…梨木ファンタジーさすがである。 時々引用される、男の子の物語とオーラス50Pほどについていけなかったのが残念。ここは完全に好み、で、俺がえらばれなかっただけ。及び腰になってしまったこの2つにがっちり嵌れたら、この小説は手放せなくなること間違いなしだと思う。
2投稿日: 2022.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮大なスケールの話を、淡々と書いた小説。 表紙の螺旋状の何かの様に、現実から、想像へ、一歩ずつ、気づかないうちに踏み込んで行って、今がどちら側なのか、わからなくなっていくような。(境目なんてないのかもしれないけど) 生と死と、それはごく普通で、当たり前のこと。
2投稿日: 2021.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ家宝のぬか床の世話をしなければいけない主人公のゆったり日常かと思いきや、ぬか床にいれた覚えのない卵が出現、それがひび割れたと思ったら、見知らぬ人が現れる。ファンタジーかと思っていると自分のルーツ辿り、そして壮大な命の物語となり、最終的に、ほう、とため息が漏れてしまう。 梨木さんのこの独特の世界観が心地よくてたまらない。読みながら、あぁ好きだなぁ、しみじみしてしまう。
1投稿日: 2021.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの世界。 はじまりは「ぬかどこ」。 世界に一つしかない細菌叢の世界。 しかも時間とともに変化し続ける。 一つの細胞から細胞膜、細胞壁、細菌、麹菌、動物、人。 脈々と続く時間の流れ。 境界のない世界。 とても大きな世界感。 人と人の結合がこのように語られるのか と驚き。 「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」もすごい伏線だと思う。 子どもの頃は100年なんて想像もできなかったけれど、梨木さんの世界に触れることで、今は1000年単位でも理解が出来るような気がします。 この本も大切な一冊になりました。 老若男女におすすめです。 で、読み終わってすぐですが、もう一度読み返しています。。
64投稿日: 2021.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
職場の先輩から教えてもらって読んだ物語。 読んでる途中から 不思議な雰囲気やなあと思ってたけど 最後に「西の魔女が死んだ」「裏庭」の 梨木香歩さんの本やとわかって納得。 「自分は自分でしかない」ことなんてなく、 自分が生きてる間に出会った人たちや環境の影響を受けて自分が形成されているということ。 生命は絶えず生と死を循環しているということ。 物語のメインテーマはここかなあと思うけど、 ぐぐっと入り込んで読むことができなかったから あれこれ深読みも出来なかった…。
1投稿日: 2021.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ代々受け継がれてきた「ぬか床」が来たら、変なことが…、って、それが「ぬか床」という、おおよそ物語のテーマになることがないものだけに、かえって興味を引くんだけど、読んでいて、どーもイマイチ。 というのも、「ぬか床」の話だからか、登場人物がなんだか妙にベチャベチャしていて。 そのベチャベチャ人たちのベチャっとした人間関係に、たぶんうんざりしちゃったんだろう。 と言っても、主人公はサバサバ、さらっとした性格なのだ。 でもさ。なんだろ? 女性作家の小説って、なぜかこういう性格の女性が多くない?(^^ゞ それって、作家みたいに知性を価値観におく女性が思う理想の女性像みたいな気がしちゃって(そうなのかは知らないw)、結局、なんだかそれもベチョベチョした話だなぁーって感じちゃったって言ったらいいのかな?w 前に読んだ『村田エフェンディ滞土録』は、すごく骨太な話だなーという印象だっただけに、この著者もこういう話を書くんだなーと、ちょっとシラケちゃったんだと思う。 もっとも、「2.カッサンドラの瞳」の中の“家庭という不可思議なぬか床は醸成されていくのだろう。その曖昧さは、考えただけに窒息しそうなほどだ”の言い得て妙さには、一瞬、呆気に取られてしまって。 人って、家庭でもいいし、職場でもいいし。学校だったら、クラスとか部活とか。あと、今はSNSがあるか。 そういう囲われた他者の目が入らない中で、独自の価値観やルールをプツプツ音をたてて醸成されていくんだろうなーと思ったら、ニヤニヤと、厭ぁーな笑みを浮かべてしまったくらい感心してしまったんだけどね(^^; でも、つづく、「3.かつて白銀に靡く草原があったシマの話-1」は、変に説明くさくてつまらないし。 「4.風の由来」は、さらにベチャベチャしてきたこともあって、これは他の本を読んだ方がいいかなーと思いつつ。 つづけて、「5.時子叔母の日記」辺りを読んでいた時だったのかなぁー。 ふっと、あ、ベチャベチャしてる話だけど、この話も『村田エフェンディ滞土録』から全然ブレてないなんだなーと感じてから、急に面白くなってきた。 たぶん、“「決断力に溢れた男らしい」人間であったとしても、それは「自分の側の論理を振りかざすだけの傲慢さ」と同じこと。自分のナルシシズムに溺れきっているからこそ、他人がナルシスティックなることが許せないのよ”という文を読んだ辺りかなぁー。 そういえば、「4.風の由来」でも同じようなこと書いてたなぁー、と戻ってみると。 “いわゆる、常識とか、普通って、言葉はもう使わないようにしましょうよ” “〇〇さんの今とった分析的な態度は、とても男性的なの。何人か集まれば、誰かがそういう役割をとらなければならない”とあって、あー、あー、これこれと。 『村田エフェンディ滞土録』を読んだ時にも思ったのだけれど、この著者の小説(著者の価値観?)の面白さは、 この「女性の」感覚、論理的知識的思考による感覚(思考による感覚って、なんか変だけどw)でなく、(女性の)肌感覚で、我々が思っている“常識”の、あるいは“普通”の世の中や世界に疑問を投げかけている所にあるように思う。 いや、“「決断力に溢れた男らしい」人間であったとしても、それは「自分の側の論理を振りかざすだけの傲慢さ」と同じ”と言われても、人は、自分の論理で決断をしなきゃならないのは確かだ。 また、“〇〇さんの今とった分析的な態度は、とても男性的”であったとしても、著者も書いているように、“何人か集まれば、誰かがそういう役割をとらなければならない”わけだ。 著者は、それは重々わかりつつ。でも、だからこそ、現在の人の世の習い的な“常識”や“普通”に反対を言いたいのだろう。 だって、その“常識”や“普通”というのは、“「決断力に溢れた男らしい」人間”や“自分の側の論理を振りかざすだけの傲慢”がつくった“常識”や“普通”にすぎないのだから、という、(慣用句的な意味での)「女性らしい」視点で著者は終始一貫しているのだろう。 そこは、男である自分も、というか、自分が男だからこそ感心するものがある。 人間は男と女、2種類なのだ(と言うと、今は怒りだす人もいるけどw、あくまで慣用としての話)。 それは、同じようで絶対違う。違うのは、違うことが生物として必要だったからで、その必要を満たしたからこそ、人は(たぶん)生き残れたわけだ。 男には、男なりの思いや考えがあって。女には、女なりの思いや考えがある。 それは、どちらも生物としての人間の役割なんだと思うのだ。 『村田エフェンディ滞土録』では、その二つの違いを「西洋と東洋」という慣用句(あくまで慣用句だ)で分けて、小説にした。 一方、これは「男と女」という慣用句(これもあくまで慣用句だ)を二つの違いにして、小説にしたのだろう。 例えば、今のミャンマーの状況下、軍事クーデターへの反対デモを決行することは「決断」しなきゃしょうがない。 というか、それは間違った政権にNo!を突き付けるのは、国民一人一人が負っている義務であり責任でもあるわけだ。 ただ、例えばデモで軍事政権が倒れたとしても、新政権の人たちが、もし、“自分の側の論理を振りかざすだけの傲慢”な政治をしたら、国民の暮らしは軍事政権下と同じになってしまう。 悪政を倒した人たちが、前政権の悪政の原因だった利権の独占をしてしまうことで、同じ悪政をしくことは普通にあるわけだ。 つまり、間違った政権を正す“自分の側の論理”による「決断」を、著者は(慣用句としての)「男性」の視点(行動原則)とし。 その新政権が前政権のような“自分の側の論理を振りかざすだけの傲慢”な政治をしないように戒めることを、著者は(慣用句としての)「女性」の視点(行動原則)としている。 そういう男性の視点、女性の視点が両輪がないと。人は、社会は歪んで、壊れてしまう。 『村田エフェンディ滞土録』では、それを西洋の視点と東洋の視点にした。 そういうことなんじゃないだろうか? その後の面白さは圧倒的なのだが、圧倒的すぎて、正直、著者の言いたいことを理解しきれてないように思う。 ただ、いわゆる「利己的な遺伝子」論的な、“生物が目指しているのは進化ではなく、ただただ、その細胞の遺伝子を生きながらえさせること”、“細胞が死ぬほど願っているのは、ただ一つ、増殖、なんだ”というようなことが結論?ネタ?オチ?なのかなーと思った。 だとすると、フリオが“自分って、しっかり、これが自分だって確信できる? 普通の人ってそうなの?”と言うのがよくわかる。 人って、普段はあまり意識しないけど、でも、ふとある時、呆れるくらい自分が親や兄弟と似ていることに気づいたりするものだ。 もちろんそれは、「似ている」で。フリオが言う、自分だって確信できないほどではないのだが、でも、それは人という生物が個の意識を過剰に持つがゆえに人であるからであって。 遺伝子からしたらそれは違いではなく、コピーでしかないのかもしれない(爆) つまり、「自分探し」なんて、遺伝子からしたらヘソが茶を沸かすようなことなのだ(^^; でも、人は、遺伝子からしたらコピーにすぎないわずかな自分と他人の違いを認識するorしたいと思うからこそ、人なのだ。 自分と他人の違いを認識するorしたい「自我」があるからこそ、人の遺伝子はここまで増えることが出来た、とも言えるんじゃないだろうか? というかー、もし、人がコピーだったら、著者の小説(『村田エフェンディ滞土録』)が成立しなくなっちゃうわけでー(^^; そんなわけで、遺伝子からしたらコピーにすぎない違いを認識したい自分からすると、この小説をホラーに作り替えたらどんなに面白いだろうって(爆) この話だけで『リング』~『らせん』、あるいは『ループ』まで包括出来ちゃうんじゃないかって、すっごくワクワクする(^^ゞ
1投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ緊急事態宣言の出た日、明日から仕事も休みというときに、長期の休みに備えてなぜか無印の『ぬか床』を買ったのだけど、それを話したらおすすめされたのがこの本。 すぐに図書館で予約してみたけれど、図書館が休館になってしまって届いたのは2ヵ月後。ぬか床が出てきたところで、ああ、そういえばそんな話をしていたんだったと思い出しました。 ところがこれが簡単なぬか床の話ではなく、ぬか床から変なものが次々と出てくるという話。怖くなって慌ててうちのぬか床かき回してみましたよ。 ここでの「ぬか床」は「家族」を象徴するものでもあり、代々手をかけてきた女性たちの念もこもっているので、主人公は自分が家族だと思っていたものはいったいなんだったのか、結婚もせず子供も産まずここまで生きてきた人生について考えざる得なくなります。いろんな意味でなかなか怖い。 幕間に挿入される「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」は幻想的な生き物や壁で囲まれた世界観などが村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と重なります。 家に不幸があると「物忌み」として不幸が出歩かないように扉を閉めるという話が出てくるのですが、今でも地方ではドアの鍵を閉めなかったりするのはその名残だったりするのでしょうか。不幸が出歩くという発想が遠野物語。 後半は民俗学と発酵と微生物がからむ壮大な展開になるのでついていくのが大変ですが、ぬか床の世話がめんどうになったらこの物語を思い出してかき回そうと思います。 以下、引用。 ー愛がないから、漬け物だってうまくいかないんだよ。主婦に愛がないときの、ぬか床の、意地の悪さったら。 老舗の蔵には、壁や柱や天井なんかに何十年何百年というその蔵独自の菌が住み着いていて、空気中に漂うそれが酒造りに働くの。 蔵には女を入れない、とか、神聖視されるのも、偶然の要素が大きく作用する、神の領域のものと思われていたからなんでしょう。 家庭を営める、ということは、選ばれた特殊な人々の特権のような気がする。論理で動いているのではない、家族の成員のそれぞれの生理がぶつかり合う場なだけに、どこか力が抜けた、ある種の感度の鈍さ、感受性の低さが求められる。鋭すぎる感性はそのミクロフローラを生き抜けない。家庭という、世間とは隔絶された暗黙のルールで支配された世界を醸成して行くためには、異分子は早めに排除される運命なのだ。 青灰色の円錐形のスカートが、橙色の夕暮れの光を浴び、淡い薔薇色に染まる。数十ものそれが動くたび、微妙に輝きが波をつくってさざめいてゆく。僕はそれを見るのが好きだった。単調な生活の中に美がある。 ー気を付けていないと、雨期には簡単に消えてしまう。よほどね、心持ちをしっかりして。 それにしても「沼の人」とはいえ、家の中に家族と違う人間がいるのに気づかないなんて。そういうと、佳子姉さんは、だから家族には違いないのよ、その時々で違った姿をするだけなのよ、という。 新しい制服の、スカーフの結び方をいろいろ試した。出来上がりは全く同じなのに、結び方の様々あることといったら。ユキはどうせ同じなら一番簡単なのがいいっていうけど、結び方が違うってことは、見えないところの構造が違うってことで、結果的には同じとしても、折り畳まれてゆく空気の手順が違うってことで、私はもう少し込み入った結び方にすることにした。 この島では大抵の家は石積みの塀の出入り口部分を戸を立てずに空けている。本土のように冠木門にして木製の戸を立てているのは地主の家ぐらいだ。その地主の家も普段は戸を開けっ放しにしている。だが家に不幸があったときは、その戸を閉ざし、その家で端を発した不幸が門を出て、島を練り歩かないようにする。 「おじいさま、浜というのは、陸と海との境で、両方を繋いでいるのですね」
1投稿日: 2020.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログシュールでも、もう少しユーモアで突き進むのかと思いきや、壮大な結末に至って少し驚いた。結末付近の風野さんとのくだりはいらなかったのではないかな。
2投稿日: 2020.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ叔母が亡くなって先祖伝来の「ぬかどこ」をマンション込みで 受け継ぐことになった主人公:久美 ぬかどこが呻いたり、卵が出来て、子供が出た?(゚ロ゚;)エェッ!? そして亡くなった叔母の日記を見つけて、 久美は先祖が育った島に向かうことになる。 命を繋ぐための進化・・・色んな解釈があるんでしょうが 種を守るための壮大な物語。これは楽しい。っていうか面白い。 そして久しぶりにフジテレビで放送されていた グレートジャーニーを思い出しました。
1投稿日: 2020.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初めはワクワクした。中盤以降に挿入される物語の世界観は村上春樹を思い出した。後半は、それまでの現実主義的な分析はいったい何だったのかと思ってしまい、あまり盛り上がらずに読了。
1投稿日: 2019.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床から始まった物語は,酵母や菌類の成長と発展?につながり,ぬか床からクローンのように現れる人たちの不思議さに驚いているうちに,生命とは死と再生の力だと大潮の日に収斂していく.特殊な島の奥深い沼地の不気味さもあって,少しホラー的な要素もある.本編に差し込まれた3つの挿話「かって風に靡く白銀の草原があったシマの話」は意味深で謎に満ちた細胞の美しい物語だ.
1投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先祖代々伝わる"ぬか床"を受け継いだ久美は、毎日朝晩ひたすらに"ぬか"を掻き回す。 ある日、いつものように"ぬか"を掻き回していた久美は、正体不明の卵を"ぬか"の中で見つけてしまう…。 まさか"ぬか床"の話から壮大な生物誕生の神秘へ発展するとは思わなかった。 確かに"ぬか床"は生きている、とよく聞く。 温度や湿度、掻き回す人によって全く味が変わるらしい。 だから同じ"ぬか床"は二つとない。 代々の掻き回す人の手を通して、一族の歴史も染み込み醸成されていくのだろう。 そう思うとぬか漬けを軽々しく食べれなくなりそうだ。 "ぬか床"を譲り受けたばっかりに、掻き回す手を止められなくなった久美は、"ぬか床"の呪縛から逃れようと自身のルーツを辿る旅に出る。 世界は最初、たった一つの細胞から始まった。 その一つから無数の生物の系統へと拡がり、やがて次の新しい命へと希望が解き放たれる。 「生」の神秘と受け継がれる「命」について、静かに思いを寄せる物語だった。
8投稿日: 2019.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読。命が生まれることの不思議と喜び。命がつながっていくことの奇跡と驚き。ぬか床から生まれてくるファンタジーも含め、命の力強さがまぶしい。複雑な話なんだけど、爽やかさがあふれている。
1投稿日: 2019.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとも言えない空気感。知らず知らずのうちに、物語の空気感に絡み取られていくような。うまく言葉がまとまってくれない。
1投稿日: 2018.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作品をきっかけにぬか床を始めた。笑 「自分」の境界をめぐる話。 からくりからくさ、ピスタチオなどと繋がる、自己の在り方、在り様と、世界との繋がり。 読後、消化不良になったり壮大さにクラクラしてしまう人は上記の二冊から入れば分かりやすいかな、と思う。 他の梨木作品に比べて「いや〜な」人物も出てくるけれど、きちんと作用してゆく。 酵母の嫌気性の話は自分の中のものすごく深いところに入っていった。
1投稿日: 2018.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ消化不良。上手く自分の中に取り込みきれない。南方の島の中、土俗的な風習など作者お得意な領域という気はする。
1投稿日: 2018.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年2月16日~17日。 ミクロが作りだすマクロな世界って感じか。 とても壮大な物語を読んだ気がする。 誕生と死、圧倒的な孤独、細胞の夢。 抽象的でもあり、非常に科学的でもある。 ぬか床なんて庶民的な小道具を持ちだしてきて、こんな世界を作ってしまうんだからなぁ。 ついでに言ってしまうと、僕が最近興味を持っているもの、性、存在、始まり、なんてものとリンクしている。 リンクしているなんてもんじゃない。 読んでいてビックリするほどに符合する。 まさにシンクロニシティ。 まぁ、これなんかは完全に個人的な感想なんだけど。 正直、難しかった。 いずれもう一度読み返すことになると思う。 難しかったが、いや、難しかったが故にたまらなく面白かった。
1投稿日: 2018.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初はラジオドラマ「フリオのために」を聴いた。 それが序章に過ぎないとは。 生命の連続性に立ち会うのは、一度は性を放棄した男女。 この男女の設定があるからこそ、生命が奇跡のように感じられる。 ジェンダーを越えてセックスを越えて生命そのものがエロスであるような。 結局は性交と出産かよ、と興ざめしないように、意外と巧妙な構成。 (ハコちゃんこと岩下尚史さんを連想) ぬか床からクローン? え、ホラー? いやミステリ? という序盤からは思いもよらない壮大な終盤。 これは「開かれている」終結。 とはいえ、序盤のフリオがまるで自分かと思ってしまっただけに、フリオのその後が気になる。 「シマ」のパート。 細菌の存在をファンタジー仕立てにした話(タモツくんやアヤノちゃんの)かと思いきや、 単性生殖から有性生殖への初めての移行(「シ」=「死」=「雌」=「子」) でもある、という難解さ。 (初めての細胞の孤独、という発想を下地にして再読必要。孤独が源流にあるからこそ、暴力的に生物を増殖のための乗り物に仕立ててしまう。) まあ、「村田エフェンディ」や「家守」のほうが好み。
3投稿日: 2017.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床である。恐らくほとんどの日本人なら言葉くらいは聞いたことがあって、でも今や一家に一個あるんだかないんだか、てか普通ないわー、的な存在なんだけども、まだ過去の遺物になりきってもいない、微妙なスタンス。そのぬか床から生まれるなんだか奇妙なファンタジー、かと思ったら驚くほどにSFチックというか、なんというか、読み始めた時に感じたのと、思ってたのと違う感が!ちと残念だったのでした。 しかし浅漬けよりはやっぱりぬか床で漬けたほうがうまいよねぇ。
1投稿日: 2017.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ夏になると読みたくなる梨木香歩。 長年なんとなく読む機会を伺っており、とうとう読んだのですが、その甲斐がありました。 島、とあったので、からくりからくさと何か関係が、と思ってたのですが、島違いだったのかな。
1投稿日: 2017.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでも感じること、表現することは許されているのだなと思いました。 自由な発想の中でも、いわゆる日常的なシーンもたくさんあるから、ストーリーはしっかり進んでいるのがすごいなと思います。 本来あるべき姿、何が必要で何が必要でないのかはとらえる枠が変われば、その線引きもやはり変わるわけで、全ては緩やかに1つなのかと大いに納得。 今一度転がしながら読みたいです。
1投稿日: 2017.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常と非日常、科学と詩的ロマンが、分離しながらも溶け合おうとするような、奇妙で危ういバランスの世界観。序盤からもう只事じゃない。 菌類のミクロの宇宙を久美たちと覗くうちに、一個の生命体としてここにあることの「不思議さ」に向かって目が開かれていく......。心にガツンとインパクトを食らわせてくれる、どでかい質量を抱えた物語でした。
1投稿日: 2017.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」のような、ほんの少し影があるやわらかな森の中のような話を予想して読み始めたけれど、内容はもっと、濃いものであった。個体としての境界や性別、生殖について。わたしに響くものがあった。これから何度も読むことになるように思う。
1投稿日: 2016.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮大な物語だった・・・ 生と死。 それも細胞レベルでの生と死、形を変えながらも永遠とめぐっていく命がテーマなのかなと思いました。 途中で入ってくる『かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話』。 最初は正直、良く分からないしこれいるのかな?と思っていたのですが最終章を読んで、何となく繋がったような気がしました。 それまでは本編とサイドストーリーという感じだったのが、最後の最後にしてきれいに合わさったという感じ。 うまく言葉にできないですが、パズルの最後のピースがパッチっとはまった時の喜びとも快感ともつかないような感覚を覚えました。 そして、登場人物の人が主人公に問う、「自分って、しっかり、これが自分って、確信できる?」のセリフ。 個性とは、自分とは何なのか。 考えさせられるものがありました。 最初の1日で1章・2章を読んで、えっ?!ホラー?と思い、読みすすめようかどうしようかと思ったのですが、しっかり最後まで読んで良かったと思います。
1投稿日: 2016.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ有り得ない設定にビックリしてドンドン読み進めてしまいました。 最後は、やらしさがないのになんだか官能的かつ神秘的でした。 フリオの子どもはどうなるんだろう… それだけ、なんだか取り残されたような気持ちです。
1投稿日: 2016.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ第16回(2006年) 紫式部文学賞、第5回(2005年度)センス・オブ・ジェンダー賞大賞受賞。 梨木香歩さん初めて読みました。『西の魔女が死んだ』『裏庭』で児童文学系の受賞してるんで子供向けファンタジーかと思ってましたが、途中からの剛速球にびっくり。
1投稿日: 2015.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこれほど「シ」を美しく描かれることはあるだろうか。 代々受け継がれてきた「ぬか床」という「ダサい」ものを囲んで次々と現れる「命」。この根源のある「沼」に辿り着くまでに、様々な人や歴史をたどっていく。 これほど古臭いものが美しいラストを描けるって素敵。 私は恋愛に「褪めて」しまった人が振り回される話がとても好きみたい。
2投稿日: 2015.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか漬けが恋しくなる初夏の頃に読みました。 自己はどこまで自己か他者の介入が本当にないと言えるか…レイヤーの様に他者が重なった自己は自己か?竹藪の竹の様に見えてる部分は一本一本だけれども根は一つなのではないか? 象徴的なものが繰り返し出てくるのでそれが何かはわかるんだけど。うーん。 相変わらずこの方の文章は家の中に集約していく様で外を向いてる。そして人間以外の気配が多いなと。この雰囲気は好きなので楽しめました。
2投稿日: 2015.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログぬかどこから始まる命と愛の物語。 さあ、困った、という小説だった。梨木香歩の小説は、『西の魔女が死んだ』はまだすっと入りやすいけれど、『裏庭』『家守奇譚』みたいに、物語を掴んでうまく入れるまで時間がかかるものがある。現実(今)と不思議(とか昔とか)の層が混ざってしまっているのが理由。小説を読みなれていない人が挑戦したら挫折しそうな、何重構造。それが梨木香歩の魅力でもあるけれど。 今回も戸惑った。特に三回挟まれている「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」は。これを解釈して正解を出すことはナンセンスだな、と最後まで読んで思った。これが未来なのか過去なのか別次元なのか、考えてもわからない。本編(久美の話)とどんなつながりがあるのか、考えてもわからない。でも、イメージは浮かぶ。とても繊細な絵。 最初はジェンダー的な話かと思った。そういう解釈をしてもいいかもしれない。でも違う。男がどうだとか、女がどうだとか、性とか命とか愛とか、なんだかそういう現実世界のぐだぐだしたものを超えたところに結末が行ってしまったので、ジェンダー的視点で読もうとするとぽかーんとしてしまう。とにかく不思議だ。単純な「命の大切さ」を訴える話とも言えない。命はかけがえのないもの、そんなことは導けない。むしろ、「私」というものが揺らいでいく話。 他の誰とも違う「私」は、なぜ「私」なのか。そもそも「私」なのか。私は「私」をすべてコントロールしているのか。私はどこから「私」なのか。ルーツとか自分探しとか、アイデンティティを考える時期があるけれど、本当は、誰も確信を持って「私」なんてつかめていないのではないかと思う。揺らぎない「私」のふりをしているだけで。 絵本で『ぼくのニセモノをつくるには』というのがあるけれど、自分を定義するには、かなり細かい情報が色々あって、でも、それをすべて並べたとしてもまだ「自分」を作ることはできない、そう思いたいのだ。私がどこかの「私」のコピーだなんて、思いたくないけど、「私」がここにしかいない、唯一絶対のもの、自分で作り上げた「私」でしかない、という証明はできない。ただ証拠もなく、私は唯一絶対の「私」なんだ、と信じていくしかない。だって、それを突き詰めようとしたら、受け止めきれない。だから、この小説も消化しきれなかった。 消化しきれないことが、この小説の魅力だと、今は思う。歳をとって、結婚したり、子どもを持ったりして、自分の状況が変わればまた違う感想が生まれてきそうなので、いつかまた読みたい。
3投稿日: 2015.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言で言えば、「感動〜!」 じ〜んと心に染みる物語でした。 実は、一度読みかけた事があったのですが、図書館からお借りしていたので期限が来て返すハメに。その時に読みかけていた所が物語の伏線部分に入った所でいまいち、パズルのピースがずれかけた感覚から抜け出せず、すごく読みたいーーーーという衝動にも駆られなかったのでとりあえず、ピリオド。 でもずっとずっと気になっていて、数ヶ月ぶりに目に飛び込んできました! 今度は、一気読みです!!伏線部分から難しくなるような覚悟(?!)を持って読み始めた為か、すべてがすんなり入って来ました! 日本人にしかわからないだろうなぁ〜、「ぬか床」。 ここがキーポイントで、すっごく良かった!!
1投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「ぬか床」に支配されるということが古い日本社会のドロドロした部分の象徴であり、それを断罪していく話なのかと思いきや、そう単純ではない。後半、ストーリーは急展開して壮大な生物の歩みというテーマにまで突っ込んでいく。そこに戸惑う人もいるかもしれないが私は作者がテーマに正面から立ち向かった結果として肯定したい。
1投稿日: 2014.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ代々受け継がれてきた「ぬか床」を譲り受けたときから始まった奇妙な出来事。いるはずのない人が現れ、奇妙な出来事がつづき、そしてついに彼女は先祖の土地へそのぬか床へ返しに行くことを決意してゆく。 ぬか床、という鍵そのものから独自性を感じますが、奇妙な成り行きな話はユーモア交じりの描写も含みつつ穏やかに丁寧につづられていきます。その静かな説得力にほだされてか、いつの間にかしっくりとその「非現実」を受け入れて読み込めるようになります。 ぬか床が抱えていた自分たちのいわれの深遠さは、くらりとするほど生命の根源にも迫るとてもダイナミックなものです。それに相対する終盤の場面ではこんな根源の問題にこれだけ真摯にアプローチするのか、という感銘を覚えました。 形のみえないもの、今現在ここにないものにたいして、これだけの想像力を発揮してそして面白く読ませるという描写力を思い知った物語でした。
2投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
糠床と新生命体の話し。 りかさんから読み始めて梨木ワールドも、はやついていけなくなった。早期離脱。
1投稿日: 2014.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとか最後までは読み切ったのだが…2つの世界が並行して描かれるあたりからは、もはやすべてを咀嚼することは諦めてしまった。 奇天烈な設定は楽しめたのだが、この作品を理解できるだけのものが私には備わっていないようだ。それが何なのかは特定できないけれど。 またいつか、もっとほかの梨木作品を読んでから戻ってみようと思う。それまでは可もなく不可もなくの3つ星で。
1投稿日: 2014.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論→ぬか床は偉大。 「ぬか床」からこんなに壮大な話になるとは思ってなかった。菌の名称頻出に数学に対する苦手意識がアレルギー反応。自然科学わからない。やっぱ中学〜高校初級くらいの知識は一般常識として必要だな。…がんばろう。 閑話休題。 理解できていないが、それで良いとする。時折挿入される「シマ」と「僕」の話は、解釈が幾通りもあるだろう。私は真っ先に久美の故郷の神話または祖先の物語を想起したが、その後も色々な可能性が連想され、どれが正しいとかいう結論はは出ない。とにかくスケールが大きい。生きていることが異常事態ならば、それが異常事態でなくなったとき、世界はその事態を受容できるのか。生命は、どうにかして当たり前に存在することを、やめたくなるに違いない。そして、自ら異常を起こすことで再び「異常な」生命としての価値を求めるのではないか。一度はこの道を辿ったものの、最終的には滅びを選んだ「沼」は、「異常」であることを捨てた。その先にまつのは「シ」なのか。「異常」を貪欲に求める生物とは対象的な「沼」の結末は何かを暗示しているようでならない。考えすぎか。
1投稿日: 2014.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかった。 ぬか床から謎な人が出てくる前半はわりとサクサク読めたのだけど、後半話が壮大になり、難しかった。難しかったけれど、読みやすかった。 時子おばさんの日記や安世さんの手記など、謎がどんどんと解けていく感じは爽快。 何代にもわたって受け継がれてきた不思議なぬか床。また別の形でどこかで再生しそうなそんな感じをうけた。 難しいけど、読むのをやめれない。そんなお話?
1投稿日: 2014.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々…でもないけと梨木さん読んだ! からくりからくさ、とか裏庭と通じるものがある話でした。 それと風の谷のナウシカのこともちろっと頭をよぎった。あの粘菌たちのこと。さみしいから、こわいから、他を融合?合体?しようとする。大きくなろうとする。変化しようとする。 ものごとには始まる場所があってそれが終わる場所でもあって、常に変化してて、なるほどって思うけどやっぱり難しい。
1投稿日: 2014.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとわかりにくくてあまりサクサクは読めなかった。後半は少し読むスピードも上がったけどまた読みたいとは思わなかった。 ぬか漬けが食べたくなった。
1投稿日: 2014.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めてこの人の作品を読む。おどろく程すんなりと入ってきた。ここ数年、ずっと考えてきたこととリンクして、登場人物たちに共感を覚える。人々(人外も含む)の交流がとても丁寧に描かれていて愛おしい。生物学、哲学、神話や伝説、ファンタジーにSF、あらゆる要素がぎゅっと詰め込まれ、それぞれがつながっている。ぐいぐいと引っぱられ、まるで最後の打ち上げ花火があがった後に感じる圧巻と充足感、心地よい寂しさに、読了後しばらくこちらに戻って来れなくなった。でも思うに、この話に入り込めたのは、自分が今に至るまでの色々があったからで、数年前の自分が読んでいたらまた違った感想を持ったかもしれない。 何度も読み返したくなる宝物のような作品。
1投稿日: 2014.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の個性的な死生観を表現するには、これくらい大胆な展開を用いなければ叶わないことが知れてくる。命の源とは、繁殖とは、自己とは。
1投稿日: 2014.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ糠床から始まるファンタジー。 合間に入ってくる異世界(?)の物語も 面白かったです。 全部読み終わって現実と異世界が結びついた。
1投稿日: 2014.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい! でも梨木さんの本は好きだからこの物語にある生命の連続のメッセージも読み取れる日が来ると願って、また再読したい。 主な物語と並行していた、個のない僕らの物語はなんだったんだろう。細胞のなかの話なのかなー?って思ってみたり。
1投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床の怪異から物語がこんな風に転んでいくとは。菌の話だけでも、その多様さが興味深かったけれど、さらに、男性性・女性性のこと、生命の源泉とつながり、深いなぁ。深すぎて少し、あっぷあっぷ。少し時間を空けて、もう一度、この深みに入ってみよう。
2投稿日: 2014.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013/12/21 再読 性別とは何か。自分と他者との個体差とは何か(自分探しということではなく、相対ではなくオリジナルといえる根拠)。そういったことに対しての細胞とか酵母とか、限りなくミクロな世界からのアプローチなのかなと思った。 同じ著者の他の小説だとストーリーの根底にあるものが、ダイレクトに面にでている印象だ。小説だけれど、エッセイを読んだ時に近い後味というか。 前半のぬか床から湧いてくる人たちや系譜を辿る話はこの作家さんらしいと感じた。 挿入されている「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」はどうとらえるべきか、自分で自分の腑に落ちる結論がでず、誰かと話したいと思った。
1投稿日: 2013.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな小説も書けるんだとびっくり。 通俗的なこと、科学的なこと、哲学的なこと、宗教的なこと、色々な要素が見事につまって、でもバラバラにではなく一つの方向へ結実している稀有な本。菌類がすごく気になってきた。 循環と更新、生と死といったテーマは作品が違っても通奏低音のように流れていて、この著者の作品を短期間のうちに読んでるからこそ感じられるものだなぁと思った。集中して一人の作家を掘り下げていくのも、やはり面白い。
2投稿日: 2013.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ生殖に対して積極的になれない人たちがそのことを見直す物語 か?? よく分からなかったけれど前半のぬか床に支配されたような生活のあたりは好き。 後半は世界の終わりとハードボイルドワンダーランドみたいな
1投稿日: 2013.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん。私にはわかりにくかったです。 「かつて風に靡く白銀の草原があったシマの話」が挿入されていなければ、美しく、素敵で感動的なお話で納得したかもしれませんが、内容が壮大すぎました。 前に「出来そこないの男たち」(福岡伸一)を読んでいたので辛うじて理解できた感じです。
1投稿日: 2013.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログとりあえず光彦めっちゃかわいい。 光彦絡みで何度か泣きました。 全体的には、専門的な内容をスッと理解しにくかったという点に阻まれて十分に味わい切らなかった感じがしています。またいつか、きっと改めて読み直したいです。
1投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
太古に最初に生れた原生命から、菌類を経て現在にまで続いていく壮大なスケールの物語。それでいて、「あはれ」な感覚もひしひしと伝わってくる。文体上は4種類の「語り」を複合させた実験的な試みがなされていて、これも効果的に機能している。まだ『家守奇譚』や『りかさん』などが未読なのだが、これまでに読んだ梨木作品の中では最高傑作か。
1投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこれが女性の視点で描く男女の関係なんだなと思いました。 比較することでもありませんが、でも池澤夏樹さんが描く男女の関係とは明らかにポイントが違う。 なるほどなあ…。
1投稿日: 2013.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログぬ…ぬかどこ…? はじめはぬかどこにまつわる不思議な話かなぁ、なんて思いながら(だってぬかどこから卵が出てきて更にそこから男の子が出てきたり)読んでいましたが予想以上に深い。 ぬかどこを掻き回す女たち 生命の終わりと始まり 一族 菌 島 沼地 生々しいのが半分空想的なのが半分… うーん、うまく感想が書けない
1投稿日: 2013.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
全ては、細胞の見た夢。 遺伝子を運ぶ船、種が生き残るための戦略の一つ。 それよりもっとスケールの大きいはなし。 今生きていること全てが、最初の1つが望んだことの結果かもしれない。 それは、ある意味では「私」の「生」自体を揺るがすような事実かもしれない。 なのに、語られているのは、絶望でもなく虚無感でもなく、希望だ。 孤独は、他を求めることの原動力。 孤独は、他への愛の原動力。 そのことは、私だって知ってるんだ。 まだ、全てを飲み込むには未熟だ。 時間をおいて、全てを飲み込んでみたい。
2投稿日: 2013.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ生命の起源と根源を描く。次第に広がる世界観の壮大さにひれふすような思いだ。生物学のアポリアを文学に昇華させた傑作。どれほどの探究と創造が必要だったか。想像を絶する。
1投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ微生物の話から始まってこの世の最初の命とは?という問に対する答えを巡る壮大な話。 最後の方で主人公が導き出した答えはなんかなるほどそういう考え方もあるかって思いましたね。 途中に挿入されるシマの話は抽象的で色々な捉え方ができるようになっていて思わず考え込んでしまいます。
1投稿日: 2013.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語は、たかが台所の隅に置いてあるようなぬか床から始まるくせに(とはいえ、普通のぬか床ではないのだが)テーマが壮大で、視野の狭い私にはうまく消化できない。 物語の途中に突然入り込んでくる不思議なシマの世界や、ぬか床自体も色々なものにシンボライズできそうで、あれこれぼんやり考えていると散漫になって、感想を書こうにもまとまらない。 生命の営み、 宇宙のはじまり、 破壊と誕生の輪廻、 自我というもの、 自生や寄生について、 進化、など。 何年後かにもう一度読み返したら新たな発見があるのかも・・・。
2投稿日: 2013.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ深淵な物語で、腰を据えて読みました。 女というのは・・・嫌なものですね。。。 ところどころで、『裏庭』との共通点を感じます。
1投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が生まれてくる場所をぬか床と例えるあたりが奇抜すぎる。 前半はそこから生まれた人との関わりの話かと思い、わくわくしていたが、どうも違う。もっと重いテーマであった。 ぬか床、フリオ、カッサンドラン、女っぽい同僚… それぞれの設定にきちんと理由があり、上手くできた設定だった。 ただ、少々長めなのと酵母の話がつまらないのでとばしとばしで、 話がこんがらがったりしてしまった。 もう一度丁寧に読んだほうがいいかな(覚悟はいるけど長いので)
1投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床の中では何が起こっているのか、菌の不思議な世界が、ぬか床の持ち主を巻き込んで、哲学的に展開して行く。これを読んでぬか床が作りたくなる人は稀かな。私はぬか床を作ってみたくなった。『もやしもん』という漫画にもあるように、菌の世界は奥深く、我々人間や植物からは理解できない世界を持つ。その生命の在り方は、やはり同じように生命を持つものとして興味深い。 挿入される話は、恐らく菌の世界の話なのだろう。菌の世界の在り方を、物語に落とし込もうとしたのは凄い。
1投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床と微生物と生殖のおはなし。 急死した叔母から受け継いだぬか床はしゃべる上に卵を産む・・・!? 奇妙なぬか床を元の場所に還すため、主人公は古い島へと向かう。 「生」と「死」、「個」と「他」というものに関連した作者の考えが、不思議な雰囲気とともに表現されている作品。 事の真相の方もそれなりに楽しめた。 抽象的な描写からなる話が挿入されており、思いを馳せるのが好きな人は向いているかも。 コレを読んだ人がどんな解釈をするのか、聞いてみたくなる。
1投稿日: 2013.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床から生まれるって発想がすごい。 が、読んでた時に別の衝撃的なことを体験したせいでなかみの印象が薄い。また読もう。
1投稿日: 2013.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界はたった一つの細胞から始まって、その細胞はずっと夢を見てる。 未来永劫、自分がずっと在り続ける夢。それを、色んな風に枝分かれした菌たちが叶えようとする。元の菌は一つだから。 菌の、壮大すぎる冒険って感じ。 最終的には受精の話なのかな。 あんたは変わってる、と言われた「僕」っていうのは…そういう事か。 読んですぐ、ストンと落ちて来る話ではなく、時間をかけ、あるいは読み返して落ちて来る話だと思う。
1投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログぬか床から始まる物語。そこからまさか、微生物レベルの話になるとは思わなかった。 そもそもぬか床を話の主柱に置いた話に出会うのが初めてかもしれない。 「おなじぬか床はふたつとない。しかもそれは変わりつづける。あとから少しづつ違うものが加わることで、オリジナリティが更新されていく。」というのが良い。人や個、も同じ。 私は父の繰り返しでも、母の繰り返しでもない。 私たちにまとわりつく「孤」の原点は宇宙で初めて現れた細胞の持っていた孤独。ひとつのものから分裂して出来たそれぞれの個も、少し離れてみるとすべては大きく、緩やかにひとつのものとして考えられる。 かなり壮大な物言いにも思われるけれど、この解釈はなんだか好きだ。 自分というものをポイ、と呑気に手離してしまえるような気持ちになる。 フリオが自らを沼の人ではないか、と言い出すシーンと、 島の村に向かう車中でのシーンが特にすき。 だんだんと増殖する細胞のように、 広がりをみせる久美の物語に ぐっと引き込まれる。 そこまで甘すぎず、ファンタジック過ぎない本作、梨木さんの作品の中でも特にお気に入り。
2投稿日: 2013.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログでも、佳子姉さん。 私、本当いうと、分からないの。 こんなに酷い世の中に、新しい命が生まれること。 それが本当にいいことなのかどうか。 いいことなのかどうかは誰にも分からない。 でもね……ほら、動いた。
1投稿日: 2012.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮大な連綿と続く生命の繋がりを、酵母菌などといった生化学と融合させたお話。 1つ1つが繰り返しで、けれど1つとて同じものは無く、全てがオリジナル。 圧巻でした。 生きること、生きていることに自信を失くしたとき、きっと心の支えとなってくれる。
5投稿日: 2012.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ着想は梨木さんらしいし、展開もすごいなーと思うのだけど、なぜだか読み進まない、読みにくい小説で、結局、かなり読み飛ばしながら読んでしまいました。 このテーマが、もっと作者の中でこなれたら、また違う形で小説になるかしら? なんて、読み飛ばしたくせに、何様!?という感じの感想ですが。 また、時間を置いて読んでみようかと思います。
1投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前半と後半の印象が違う。 怨念や呪いのような絡みつく繋がりは、それだけでなく暖めも育てもする、ような複雑な成り立ちにそういうものかも、と思う。 最終的な結末が意外であり、物語的にはそうでなくては成らない決められていた結末にもみえる。 前半が好みで、後半はちょっと苦手。 次に読んだときは印象がかわるかもしれない。 再読。 最終的なまとめかたが結局男女だから子孫を残すというのが、新鮮さが足りないと思ってしまったのかも。強引さを感じたのか。 二人の性格が、少し世間と外れているのだから、せっかくだから新しい形の子孫繁栄?がみたかったのかも。
1投稿日: 2012.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いんだけど私には没頭できない。 壮大さが肌に合わない。 もっと身近な描写だけで壮大さをチラリと覗かせるほうが好みだな。 ぬか床、粘菌、島、有性生殖、無性生殖、沢山の叔母 久美が、好きな男の趣味に合わせて興味のない映画に付き合うのは人生のロス、なんて考えるのはもの凄く違和感があった。 久美は人生に有益なことだけを選んで日々暮らしているのか? そんな大げさな…
1投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩でよくある不思議系。急に幻想的な、モヤモヤした現象が起きだしたりする。なんだか、その境目になかなかついてけなくってまごつくこともある。あれ…あれれ?て感じで。この作品では、同時に進行しているもう一つの話が挿入されてる部分、とか。あれは、もっとミクロな、基底の生命の働きの象徴なのかな、と感じた。誰でも一度は想像するような、細胞の中のもう一つの世界、みたいな。でも、「生命」なんてテーマを文学で扱うのであれば、いかに暗示で、読者の中で考えさせるか、ってのが大事なのかもしれない。それに付随して当然いろんなテーマがある。愛とか自己、個、集合とかね。よくこんなものを扱えたなぁと思う。解き放たれてあれ。 374/472/484/509
1投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ私としては少しホラー。 糠床のもとの場所の話。 どのように人が命を受け継いでいくか。 カッサンドラはからし粉で消えた。
1投稿日: 2012.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ代々伝わるぬか床、という設定に記憶がある。割りと好きな作家でもあるし、読んだような気がするなー…と思いつつ、最後までストーリーは思い出せなかった。ここまで忘れるなんて、我ながら、読み方いい加減過ぎだと反省。 負け犬アラフォーは、主人公に共感できる部分多い。カッサンドラのいやらしさも秀逸。
1投稿日: 2012.08.07
