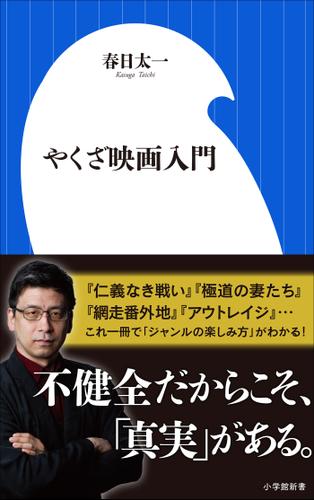
総合評価
(5件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ令和の世にあって、時代劇以上にハードルが高いかもしれない「やくざ映画」について、楽しむための基礎知識を説く。個人的にも「こういう手引き書があれば助かるのになぁ」と思っていたのでドンピシャだった。
0投稿日: 2024.11.27代表作でありながら終止符を打つ作品
1970年市ヶ谷で起きた三島由紀夫の割腹自殺の報に接した時、脚本家の笠原和夫は、衝撃とともにある種の安堵に包まれた。 手がけた任侠映画『総長賭博』に対する三島の熱烈な激賞以来、呪縛に苦しめられていたからだ。 大作家の目を意識するあまり、作品がどんどん観念的な内容に傾き、観客にそっぽを向かれ追いつめられていた。 そんな中での三島の突如の死は、笠原に解放感をもたらす。 深作と組んだ『仁義なき戦い』シリーズが始まるのが1973年。 古典的な様式美は跡形もなく、迸る情念と躍動する無秩序。 三島が生きていたらどう評しただろう。 笠原と深作は『仁義なき戦い』を通じて息の合ったコンビと思われるかもしれないが、実態は違う。 笠原は自身の脚本どおり丁寧にドラマを描き出したいのに、深作の激しいカメラワークで台無しにされたと怒り、深作は深作で笠原のいまだ軍国少年の情念を引きずった脚本に対し、若い観客は求めていないと突っぱねる。 その対立が際立っているのが『広島死闘篇』で、北大路扮する山中に仮託する笠原と、千葉扮する大友に仮託する深作という2人の戦後が作品内でぶつかりあう。 しかしラストの山中の自殺する場面をより悲劇的に描いたのは、深作の方だった。 やくざ映画というのは、任侠映画路線の流れを汲む、一つの型や様式をもったファンタジーであるはずなのに、いまやくざ映画の代表作として主に語られるのは根本となる特長をなす様式やファンタジーを悉く打ち破った『仁義なき戦い』だという皮肉。 その『仁義なき戦い』も、血みどろの抗争に明け暮れたやくざたちの最後にして最大の敵が「市民社会」であったという皮肉。 「秩序の破壊者である暴力団」を辛抱強く追いつめる「健全な秩序を求める市民たち」という構図を見せられた観客は、仮想と現実の境界線の薄さに気づき、それ以来このジャンルは退潮の一途と辿ることになる。 代表作でありながら終止符を打つ作品。 これもまた皮肉だ。
0投稿日: 2024.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログやくざの基本組織図や簡単な用語、有名作品、俳優、考察に筆が及んでおり短い時間でやくざ映画についての知識が得らえれるありがたい本。 現実とは違うという意味では「時代劇」の属するジャンルになるのかもしれない。
0投稿日: 2023.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログかつての隆盛はどこへやら近年は韓国ノワールに押され気味の日本やくざ映画。その歴史を紐解きながら「面白そう!」と思わせてくれる入門書。時代劇研究家でもある著者の「半沢直樹は時代劇よりもやくざ映画に近い。半沢を楽しめた人はやくざ映画も楽しめるのではないか」という導入も巧い。ちなみに私は数年前に酒場で隣の席の男性と東映やくざ映画の話で盛り上がって「お若いのによく知ってますね」とビールを一杯奢ってもらったことがあります。世の中何の知識が役に立つか分かりませんよ?w
1投稿日: 2021.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログコンプライアンス遵守が盛んに叫ばれる現代。かつて全盛を極めた「やくざ映画」の命脈も風前の灯火だ。しかし、その中は「組織論」「義理と人情」など、日本社会の本質を理解するカギがそこかしこに隠されている。 『仁義なき戦い』『人生劇場 飛車角』『博奕打ち 総長賭博』『緋牡丹博徒』『県警対組織暴力』--日本映画史に燦然と輝く名作を紐解きながら、難解と思われがちなこのジャンルの「歴史」「全体像」「楽しみ方」をわかりやすく解説。 なぜやくざ映画は、我々の心を掴んで離さないのか。不健全な作品にしか、救えない魂があるからだ。 あっという間に読み終えた。もう少しボリュームがあっても良かったかも。
1投稿日: 2021.10.09
