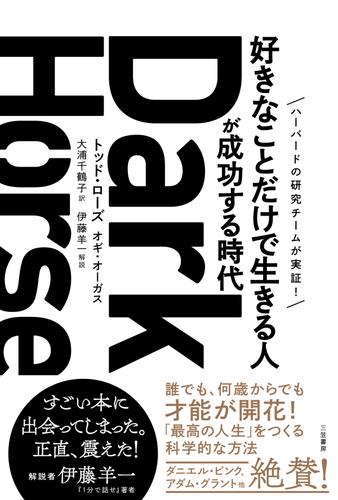
総合評価
(57件)| 13 | ||
| 28 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本を読む人はうまくいくの中で長倉さんが紹介しており、読んだ。 個人の充足感を求めて幸福を手にしたダークホースと呼ばれる成功者たちを紹介しながら好きなことで生きていくことは可能でだと伝えている。 そして充足感に満ちた個人の幸福が、社会全体の幸福に繋がる。 現代の日本でも通用するノウハウが詰め込まれている。 紹介されるダークホースがアメリカ人ばかりで、少しイメージしにくいなと思った。
0投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が肌感覚で親近感を覚える社会環境論と相反する思想のような気がした。 社会の当たり前を疑って異なる道を模索していこう!という意気込みは共感するが、その外縁に立たされている人びとへのリーチが私が今興味あることなので少し個人的な趣向からは外れるな。 とは言っても、こう言ったマインドの人たちが世界を変えていくのだろうという実感はあるのだ。
1投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログピボット、プロティアン、偶発性、冒険する組織とも通ずる。豊富な事例から、丁寧に自己分析の機会を得られる。上述のキーワードに関連する本を読んできたけれど、それでも新しい発見がある。
6投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ目的地を忘れて、充足感を追求しながら、成功に繋がるよう努力すればいい。 これがこの本で言いたいことだと私は理解した。 少し驚いたのは、目的地を忘れてもいいというところ。目指すところをハッキリさせないと成功できないのでは?と思ったのだが、その時気になること、小さなモチベーションを持てることに熱心に取り組み続ければいいようだ。 確かに、その時々の自分自身にとってかけがえのないことに熱心に取り組んでいけば、それが自分にとって本当に大切なことをしていることになる。すんなりと上達できるし、その過程が個性となって自分だけの道となる。 曲がりくねった道でいいし、個人中心でいい。そう言われて、色んなことに興味がありすぎて、もっと一つのことに集中したほうがいいのではと不安を抱えていた私は、とても安心した。 ダークホースと言われる人々は、自分の偏った好みや興味に突き動かされていたらしい。そして、自分の心に火をつけるものに、正直に向き合ってきたようだ。その対象が何であれ…。 他人の目を気にしすぎると、自分が興味を持つことに没頭できなくなることがあるだろう。その対象が一般的でないことだと尚更。そこで、本来の自分を第一に考えられるかが、分かれ目なのだと思う。 他人と違う道、他人から指さされることをするのは怖いと思う。でも、自分の小さなやってみたい!という感情に蓋をするのは、充足感を得るのとは逆方向だ。 周りのことは気にせず、好きなことをしよう。 他人の視線を気にしすぎる私には、強く意識すべきことだと思った。
11投稿日: 2024.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログダークホース、読了。 ●時間は重要ではない ●目的地ではなく目標を持つことの重要性 ●成功ではなく充足 一人一人がかがやける時代にきた。 これを肯定してくれる本。 まじ最高!
1投稿日: 2024.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「標準化の時代」の嫌さを実感して育った身には身につまされることが多く面白かった。 タイトルからはよくある自己啓発本ぽくみえるけど「個性学」という心理学の研究分野のプロジェクトの話でもある。 「標準化の時代」を越えて、個人の充実感が中心に据えられる社会は、今始まろうとしているばかりという見立てで、いろいろな個人の生き方やプロジェクトが紹介されている。 (なぜ今かというと色々な状況が揃ってきている、特にインターネット・テクノロジーが後押ししているという。ちなみに原著刊行は2018年) 最後に紹介される、本書が紹介するダークホースプロジェクト、個性学の主張するところとアメリカ「独立宣言」の目指すところは重なる(同じな)のだ、という主張が面白かった。 「the pursuit of happiness」(幸福の追求)が権利であり義務であるという独立宣言の内容と、「the pursuit of fulfillment」(充実感の追求)が権利かつ義務であるという本書の主張が重ねられている。 独立宣言の場合、迫害対象のインディアンにはその権利は認められませんでしたね… とは思ったが 一方で「幸福の追求」が「生命」「自由」と並ぶほど人生と社会の基盤をなすものであるという独立宣言の主張、それと同じことを本書で言っているのだという主張は力強く心に残った。 そのあたりを踏まえると原題(Dark Horse : Achieving Success through the Pursuit of Fulfillment)が味わい深く感じた。 比べて、邦題(Dark Horse:「好きなことだけで生きる人」が成功する時代)はしょうがないことかと思うけど原題にあった趣がなくなっていてよくある感じのタイトルになってしまっていると思う。 でも内容はタイトルの印象とまたちょっと違う気がするので、「個性学」なるものにピンと来たならタイトルではピンとこない人も試しにちらと見てみるのはいかがでしょうか。
1投稿日: 2024.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「好きなことをして生きていくべし」。この教えは昨今多くのインフルエンサーが口を揃えて主張する。自分もそう思うし、そうしたい。しかし中々実現できずにいる。そのための結論を求めて本書を読んだものの、結局答えは得られなかった。私の問いは、「好きなことだけをして生きて、満足感と豊かな生活を維持するための金銭的な稼ぎを両立するにはどうしたらよいか」である。 社会の標準化に抗い、心の充足感に従えば幸福感を感じられる。その通りである。 心の充足感に従った仕事をすればパフォーマンスが上がる。その通りである。 心の充足感に従って成功した人は大勢いる。その通りである。 本書ではあらゆる視点で、標準化に対抗し、個性を生かして充足感を選択肢の判断基準とすることの意義を漆塗りし、説得力を高める。アメリカの独立宣言まで引用する。 しかし、本書の主張が正しいとすれば、以下の2点のいずれかが前提となってしまう。即ち、 「心が充足していれば稼げなくても大丈夫」という精神論か、「心が充足する選択肢を取れば必ず稼げるようになる」という綺麗ごとである。 例えばサーフィンが心から好きな人がサーフィンに打ち込めば誰もが食っていけるのか。 漫画を読んだり描いたりする人が漫画をひたすら読み描きすれば誰もが食っていけるのか。 世の中には需給もあれば、職業の狭い門というものがある。そうはうまくはいかないだろう。 例えば私は読書が好きである。本を読んでそれが仕事になるのであれば願ったり叶ったりだが、それによって食っていけるかというと、やはり厳しい。AIに聞いても「ライターやブロガー、作家、書店員などがお勧め」のような回答を頂戴する始末である。皆作家やブロガーとして成功できるのなら苦労はしない。 確かに現代は「好きを仕事に」することの制約は減り、実現性は高まった。それに既定のフレームワーク外の、もっと柔軟な働き方、稼ぎ方などはあり得る。 しかし充分な稼ぎを出すには厳然として資本主義という強いルールが立ちはだかる。 このハードルを打ち砕けるだけの主張は、残念ながら本書では見つけられなかった。 とまぁ割と酷評なわけだが、本書の主張には賛同するし、作りも根拠もしっかりしている。例も豊富だし文体も読みやすい。いずれにせよ良書だとは思うので、自分の心の充足感というシグナルにアンテナを立てて、日々の選択にどのような変化を及ぼすか、実践の形で見ていこうと思う。
7投稿日: 2024.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・まず大事な事は「小さなモチベーション」この積み重ねで人は動く。「大きな情熱」「大きなモチベーション」ではなく自分の中にある「、ちょっとやってみるか」程度の「小さなモチベーションがスタートである。
0投稿日: 2024.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ画一的な成功モデルではなく、その人独自の関心や能力を活かした成功(ダークホース)について。これからの社会では世間的な評価ではなく、自分をとことん理解した方が幸せになる。 ダークホース達の4つのルール 1. 自分が好きなことを掘り起こせ 大事なのは大きな情熱ではなく小さなモチベーション 2. 自分に合った道を選択する 一般的なリスクは無視して良い(年齢とか) 3. 独自の戦略を考え出す一見風変わりな方法も自分には正攻法になる 4. 人生の目的地に到達するには、目的地を探してはいけない 目的地のことは忘れて、充足感を今抱いているか自問する ・ダークホースが大切にするのは充足感。 ・最初から目的地を決めるのではなく、都度、その時点での目標を決めて登り続ける。 ・あなたの個性と取り巻く環境が適合するか?=フィット、が大切。
0投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログダークホースのような生き方は理想だけど、がんばってもなかなかフィットを見つけられない人が多いんじゃないかな。 でも、仕事も働き方も多様になったことで、ダークホースが活躍しやすい世の中になったなーとは思う。
1投稿日: 2024.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「標準化されたシステム」を現代のイニシエーションと考えることもできるだろう。つまり、学歴や資格、法人の規模、免許や規制は一種の通過儀礼なのだ。政治・経済のピラミッドシステムに参加する資格が問われるわけだ。それゆえに政治家や社長は二世が優遇される。彼らはいわばサラブレッドであり、生まれつきの「味方」なのだから。 https://sessendo.hatenablog.jp/entry/2024/02/15/220451
0投稿日: 2024.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が本当に好きなこと、夢中になれることを追求して、自分だけの自分らしさ全開の人生を切り拓いてゆくエネルギーをもらえる本。 私も会社員として働く中で、いわゆる世の中や社会人としての常識に当てはめられることに、漠然とした生きづらさを感じていました。 本書は自分の中に眠る小さなモチベーションに従うことや、決められた目標ではなく日々の充足感を大切にすることが書かれています。 会社員の立場だけにとらわれず本当は何をしたいのか、何をしているときが一番楽しいのか本心と向き合いながら、自分自身の情熱と充足感に根差した毎日を送ろうと背中を押してもらえた気がします。
1投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功の追求が充足感につながるのではなく、充足感の追求が成功につながる。 そのために、自分の小さなモチベーションを掘り起こすこと大切。 フラクタル図形の作り方に似たプロセスを感じた。 簡単な規則が、最後に美しい図形につながる。 自分の中の小さなモチベーションを掘り出すための判定ゲームとは、 1、自分が他人をジャッジしている瞬間を意識すること 2、他者を反射的に評価しながら、どういう気持ちが湧いてきたかを見極めること 3、他者に対してなぜそのような気持ちを抱いたのか自問すること
0投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ価値観が多様化し成長に連続性がない現代においてこの本のようなダークホースが輝きを放っていくのは理に適っているし、そうであって欲しいとも思う。裏表紙に書かれた4つのルールの内一つ目の自分が好きなことを掘り起こすことが自分にとってまず重要と感じた。これを定めるには深い自問自答が必要で、ある意味苦しい工程を経なくてはならないが、ダークホースたちはそれをしてきており、自分の充足感を追い求めるのは楽しいことばかりではないのが読後の率直な感想でもある。
1投稿日: 2023.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局人生を豊かにするためには、内省力が大事なのではないか 内省するためには、刺激も必要 外からの刺激に対してどう反応するのかにより自己分析ができる その刺激と柔軟に交わり内省することで自分の進むべき道が見えてくる キャリア研修もそう いろんな人の意見を聞いて終わりでは意味がなく、必ず内省をセットでやることが必要 テクノロジーの力で「あなたに向いてるのはこれ!」と出すのも必要だけど、自分で内省して深掘りしていく過程こそ大事なのでは良いか
1投稿日: 2023.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログダークホースとは、競馬用語で本命ではない「大穴」の馬のこと。 天文学者やオーダーメイド洋裁師、音大講師などさまざまな業界の第一線で活躍される、ダークホース的な型破りの人物と彼らの歩んできた道のりが紹介されている。 ダークホース的な成功過程は以下の通り 1. 自分の中の小さなモチベーションを見つける 2. 一般的なリスクは無視して自分に合った道を選ぶ 3. 自分の強みを自覚した上で独自の戦略を考え出す 4. 目的地のことは忘れて充足感を抱いているか自問する 自分の個性と強み・弱みを活かし、働くことにより充足感が得られる仕事人生って素晴らしいと思うと共に、インタビュー記事だけでなく化学的な根拠や事実、数字に裏付けされた論理的な検証結果などを知りたいと思う。(恐らく、ダークホースの研究が進めば、そういったファクターが徐々に明らかになるとは思うが)
2投稿日: 2023.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が得意なこと、好きなことやこだわりに打ち込むことによって、正規の成功ルートではない道がひらけることがある。そんな人たちの成功例が紹介されています。
0投稿日: 2023.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#Dark Horse(ダークホース) 「好きなことだけで生きる人」が成功する時代』 ほぼ日書評 Day659 普遍的な標準化された成功法などない。一見、いわゆる成功が保証された道から外れたように見えつつも、本人の本当に好きな道を極めることにより、他人には到達できない高みを極めた人々のことを、ダークホースと呼んで、その「成功」の秘訣を探る。 まずは、ちょっと変わった嗜好でも、堂々と好きと認めよう。「なんだかの普遍的な動機によって、意欲をかき立てられるべきだ」という意識から解放されることが最も難しい。 「自分の小さなモチベーションを探り出す」ために、自分の感情の源の奥にあるものを正確に見極めることが必要。 単に「数学が嫌いだ」ではなく、先生の話し方が苦痛…ならば、本に書かれた言葉を読む方が良い。長いこと黙っているのが苦しい…なら、他の人たちと意見を交わしたくなる。こうした細かな問いへの反応が、それぞれに極めて異なる小さなモチベーションの反映。 そうした小さなモチベーションを全て幅広く受け入れた時、世界に向かって「これが本当の私です」と宣言することができる。 「やりたいこと」が見つかったら、ヒッチハイクのように指を立てて待つのではなく、とにかくゴールに向かって歩き始めること。 後にプリンスの録音技師となる女性は、Zepのコンサートに感動し、レコーディングエンジニアを志した。その後の道のりは、多くの幸運に恵まれた側面もありながら、非常に興味深い。Day656の、とにかくRCが清志郎が好きで、彼らに関係する仕事がしたくて…という著者と通ずるものがある。 と、ある程度、法則めいたものを示しつつ、依拠されるのは、あくまでも限定的な事例。 そう、Day657で見たパターンである。 さきに例をひいた、全くの未経験からプリンスの録音技師に上り詰めた彼女も、そんな成功事例が有り余るほどあるわけではないから、サンプルとして有用なのであって、ひいてはダークホースの語源の如く、やはり万馬券に過ぎないのではなかろうか。 終盤にとってつけたように語られる定員や規程カリキュラムを設けない…という極めて耳障りの良い学業システムも、それに奉仕する人手がなければ成り立たないわけで、経済的にその仕組みを回すためには、それこそAIが全ての生産活動を担ってくれるような時代の到来を待たねばならないのではなかろうか。 https://amzn.to/3L5DjIo
0投稿日: 2023.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中の価値観が確実に変わってきているので、こういう本が増えているなぁと言う印象。 自分の好きなこと、充足感を味わえることを見つけるには、まず、自分自身について深く理解する必要があると思った。 自分がどういう人間なのか、何に楽しみを覚えるのか、何に違和感を感じるのか、そういった自分の内面と常に向き合う必要があると思った
1投稿日: 2023.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ【要約】 これまでは富やお金が成功の条件だったが、現在は成功に対する考え方も変わってきた。 成功とは幸福感と達成感が重要だ。 自分のモチベーションの本質を理解し、充足感を得るために不可欠である。 情熱を感じる仕事はいくつもの個人的な欲求を満たす物である。 具体的な目的は持たなくていいから、目の前の充足感を大切にしよう。 【感想】 成功の定義がこれまでと変わってきたのはヒシヒシと感じている。収入地幸福の相関関係はそれほど大きくはないということも知られてきた中で、目の前の充足感を満たす生き方はとても重要になってきたのではないかと感じる。 ダークホースを読んでその考え方の後押しをされた。
0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰もが才能を持っている、個別化の時代へ 充足感があると、幸福になる 自分なんて、と思ってしまうのは今までの時代が関わっている。だよね、と思った。 今までの時代) •標準化時代 生産効率のもと、機械の歯車のように学び、働き、人間の一生のすべてが標準化されてしまった。 •定員主義 定員枠があることで、富裕層が優遇されたり、才能エカント(採用者の偏見)があり、才能は一部の人に見えてしまう。 アメリカ独立宣言は、幸福の追求をうたい、幸福は充足感のことというのも面白かった。 個人の幸せを追求すれば、周りも幸せにできる。 まずは自分の好きなことは何か?洗い出してみよう。 そして、環境を選んだり、戦略を考えてみたい。
0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【「世界に一つだけの花」の歌詞を学術的に詳細に述べたらこうなる】 著者のトッド・ローズが本書で一貫して主張しているのが、学校や会社などの標準化システム(没個性)によって成り立っている既存の組織から脱することがいかに重要であるかということだ。 それは、標準化システム上でのナンバー1ではなく、自分にフィットした居心地のいい環境でのオンリー1を目指そうということであり、まさに世界に一つだけの花の歌詞そのものである。 そして、そのオンリー1を目指す道こそが結局成功への近道になるということを、数々のダークホースたちの事例をあげたり、ときには数学の総合最適化問題における購買上昇法を使って説明している。 たしかに、現代はVUCAの時代と呼ばれて久しく標準化システムの上でのナンバー1になることはかつてよりかなり厳しいものであり、もはやマヤカシのレベルかもしれない気付かされた。
1投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のキャリア形成、仕事に対するモチベ、何か周りと違うなと思っていた矢先に出会った本。 ・自分の小さなモチベの探求 ・自分に合う選択肢の探求 ・目的(金、名声、地位)ではなく、充足感(やってやたぜ!寝る間も惜しい位に楽しい!)の追求 ・キャリア形成に関する既成概念の打破 まさに今の自分の拠り所としている考え方 この本の中に、仲間が居ました
1投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログダークホースと呼ばれる人たちがいかにしてモチベーションを高めているかが分かる。 モチベーションが上がらず悩んでいるならば、まず本書を読んでみるべき。
0投稿日: 2022.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身の幸せのため、目的地を考えず、時間は気にせずなど、フツウのルールとは逆ばかりで驚きはあったものの、 心の平穏を重視していた自分には自然と腑に落ちたし、その裏付けにもなったのでいい体験だった。
0投稿日: 2022.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きなことだけをして成功した人の事例集。成功事例だけでなく、失敗した事例もあげてもらえないと説得力にかけるなと思った。
0投稿日: 2022.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分に合った戦略を見つけ出す。→人それぞれやり方は違う。8人入れば8通りの戦略がある。 成功を掴み取るためには自分の自分だけの方法を見つけださなければいけない。 偶然の出来事をチャンスに変える 自分の強みを自覚する。 マスターソムリエの話は自分の将来の夢にも通ずる考え方があった。 多少文量が多く、読むのが難しかった。 また読み直したい。
0投稿日: 2022.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きなことで生きているのは特殊な人、との考えを検証している本。 大きな目標ではなく小さなモチベーションが大事だったり、全体を通して一般論ではなく独自の視点でものを見ることの重要性がわかる。 いわゆる「叶え組」と言われる、自分にはやりたいことはないと悩んでいたり、やりたいことがある人のサポートをするのが向いているのかも、と思っている人にも読んでほしい。そういう人たちにこそ、希望になったり何かヒントが見つかるかもしれない。
0投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ悪くない本だとは思うけど、ここ最近の「好きなこと礼賛主義」はどうにも嘘くさい。 普通は好きなことなんてないし、やりたいこともない。 存在しないものをあるのが当然の如き論調で埋め尽くした結果、多くの人の逃げ場を潰し、抱えなくてもいいストレスを与えているのだと思う。
0投稿日: 2022.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功に近道はない 近年の成功者は、起業家であれば「ユニコーン」と呼ぶが、この書の言わんとするところは、今までの成功者とは違った「既成概念を超えた人材」が目立ち始め、その信念は「充足感」を満たした延長線に「成功者」となったことである。だが、依然として「成功者」の必然的なものは「好奇心」「情熱」「努力」「奇抜な発想の転換」「行動力」につながると確信する。
4投稿日: 2022.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的なケースは複数ありますが、まとめとして抽象化された部分は完全に解釈できたとは言い難いかも…おそらく次に読んだら別の気付きがポコポコ出てきそうです。 と言っても悪い印象は全くなく、むしろすごく良い本でした。 もとが洋書でボリュームも多い部類だと思いますが、得られるものは多い本だと感じました。
0投稿日: 2022.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界は確実に変わっているので、従来の価値観やレールにした額のではなく、自分の生き方を問い、進んでいくことが大事なんだ。そして紹介された人はそれをした人なんだと思いながら読んだ。とても理解できる反面、親としてまだ学校で学んでいる子供に従来の価値観(勉強や進学)ではなく自分の生き方を自分で選べ。とは言えないなと思いながら読んでいた。 変わった経歴で結果を残す人などが、異色の~という感じで紹介されているが、実際本人は仕事が楽しくて気か付いたら的な発言が多いが、きっと彼らはこのダークホース的な人なんだろうなと思いながら読んた。 そして自分の中でダークホースはある日決断して、大博打を打って成功した人というイメージがあったが、実際は彼らはリスクを取って、失敗したら社会的に抹殺されるようなリスクがあればその選択はしないという話があり。意外だなと感じた。 型破りな成功をしたダークホース達の4つのルール 1.自分の好きなことを掘り起こせ 大事なのは小さなモチベーション 2.自分に合った道を選択する 一般的なリスクは無視していい 3.独自の戦略を考え出す 一風変わった方法も自分には正攻法に成る 4.人生の目的地に到達するには目的地を探してはいけない 目的地を忘れて、充足感を今抱いているのかを自問する 気に入った言葉 ・他人の成功は金や力が要因だが、自身の場合、充足感や達成感が成功の要因(彼らは充足感を何よりも大事にしている。充足感の追及が成功に導いた) ・標準化とは多様性を排除し、生産性の最大化させる
0投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ目標ありきで行動するのではなく、目の前の仕事を楽しめるか、充足できるかを考える。 夢を叶えるには我慢が必要ではない。 ひたすらに熱中できることを選んで、日々全力で楽しんでいくだけ。 気がついた時、大きな成功を成し遂げているはず。
0投稿日: 2022.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言で言えば 選んだ道を正解にしていく ということかな。 ダークホースとは、 今までまで見向きもされなかったのに 突然快進撃をはじめ 勝者となる人を表す言葉 ダークホースの特徴は 充足感をなによりも大切にする。 ダークホース的な成功への過程 1自分の中の小さなモチベーションを見つける 2一般的なリスクを無視して、 自分に合った道を選ぶ 3自分の強みを自覚した上で、 独自の戦略を考え出す 4「目的地」のことを忘れて、 充足感を今抱いているか自問する 2「自分が好きなこと」を掘り起こせ 本当にやりたいことが見つからないのは、 世の中が標準化されているから 小さなモチベーションを見つけることが大事 きめ細かく特定された、 自分自身の(いわは偏った)好みや興味につき動かされてこそ、充足感になる 情熱は多次元的で動的でかつ常に本人の意思で制御されるべきもの 小さなモチベーションを出せたら、 そのモチベーションを様々な組み合わせで活性化できる、様々な機会を得られるため、 あなたの情熱は柔軟性を持つことになる 3「自分に合った道」を選択する 本当の選択権とは、 あなた自身の中にある「好きなこと」「小さなモチベーション」がより多く生かされる機会を見つけて選ぶ権利のこと。 標準化されたシステムでは、選べないものがいくつかある。 (例えば、大企業の中では、 選択肢が上昇するか出ていくかのどちらか) 自分の本当の小さなモチベーションに基づいて 選択をすれば、 最初はほぼ間違いなく良い選択になる。 なぜなら、 ただほんの少しでも自分を理解した上での選択の方が 全く自分を理解してない場合の選択より良い結果を生むから。 また、 はじめのうちは得るものが多く、失うものが少ない。 つまり、 仮に間違った選択をしても、 そのために何かを失う可能性は比較的低い。 4独自の「戦略」を考え出す 唯一最善の方法を見つけるな 自分に合った戦略を見つけよ 5人生の目的地に到達するには、 目的地を探してはいけない 「習得までどのくらい?」は人によって違う。 ダークホースたちは目的地を無視する。 しかし、 目標は無視しない。 目標は ・常に個性から出現 ・能動的は選択から生まれる ・直接的・具体的に達成可能 (⇔目的地 自分以外の誰かが考えた目的に個人が同意し 目指すと決めた地点のこと) 自分にとって最も大切なことで 上達せよ 6誰でも、何歳からでも「才能」は開花する! すべての人間が才能をもっている 一人ひとり能力や環境にばらつきはある。 IQが高い=頭がよい ではなく、多次元的な能力パターンをみるとよい (記号探しが得意、イメージ処理能力が高いなど) WPPSIの知能テストでばらつきがあってよいということ どんな選択をとるかが大事 7世界は確実に変わってきている 平等なフィットのもとでは、 誰もがその個性に応じた最高の機会を 受け取ることができる (フィット⇔確率) 効率性ではなく 適応性が組織に義務付けられる 本物の選択肢を提示されるとき、 あなたは自分の人生を本当にコントロールする権利を手にする。 充足感は個人の権利でもあり市民としての 義務でもある 充足感は獲得するもの
2投稿日: 2022.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん。。人に求められることではなく、個人の好きなことをベースにするのは賛成。 だが、そうするとこの本の事例の大半がそうであるように個人事業になりがちで、安定した収入を得ていくことは難しく、結果人生は不安定になりがち。 サクセスストーリーを並べてあるが、本当に幸せだと感じられるには適度な安定収入は外せないが、この本はそのあたりすっ飛ばしてる印象。 が、常に自分が何が好きか、何が得意かを見極めた上で、戦略的に生きることは大事。人が何に金を払うかはある程度決まっており、競合もたくさんいる中で勝負していく必要。標準ルートも、ダークホースルートもいずれも試行錯誤が必要。でも、ダークホース的ルートで行く方が、その試行錯誤を楽しめるのだろうな。 —- ・個性を生かして、充足感と成功を目指せ ・モチベーションは多岐にわたるコリンが、自分の仕事に情熱を感じるのは、その仕事がいくつもの個人的な欲求を満たすからだ。 ・まだ発見されていないルートを示した広大な地図帳を開く。 ・制約のない達成感と喜びに満ちた社会への扉を開く ・何かに退屈したり、イラついたりしたときに、自分は何を望んでいるのかを見極める。単に数学の授業が嫌いなのではなくて、代わりに何が欲しいのか 例 ・彼女の脳は、高速回転する遠心分離器のようなもので、情報取り込むと、即座に重要なものとそうでないものを選別する ・彼はビジネスに関わる数字が無性に好きで、利益率や諸経費を計算する。仕事に強い関心があった。 ⭐️サミット学習方式
0投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ<成功とは:充足感の追求をし続けること> そのために、何をどうすればいいのか? ・自分の中に小さなモチベーション(複数)を見つけることが大事、情熱は点火剤 ・個別化の時代において、独自の戦略(複数のモチベーション×自分の強み) が必要となる ・やり方は無数にあるので、トライアンドエラーを繰り返し違和感を感じたら 修正して、自分にフィットするやり方を選択すればよい そうすれば、充足感を得ることができるはず ・才能にはばらつきがあるということに注目。時代が変化し、平等なフィット が可能となっている。誰でもやり方次第で、充足感を得る生き方ができる 以上、備忘録まで。ここから感じたことについて、簡単にメモ。上記の考え方でサイクルを回すと成功へのハードルが下がり、かつ自分軸で生きれるので、すごく生きやすくなるのでは。また子育てという視点から考えると、今後、進路や色々なことを選択するにあたり、環境よりもその子にとってのモチベや強みは何かを考えることの重要性に気がつかされた。個性を尊重するということは、そういうことかもしれない。
1投稿日: 2022.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ標準化 に対立軸に ダークホースを定義 標準化は消費期限切れ 個人軸でいいと言っている 標準化された価値観=見えないルール に縛られていないか。 好きなこと、あったことを 自分戦略で 自分に合った戦略: これなら自分にもできるかな という方法 成功が先 充足感が後 ではない 充足感が先 そのあとに成功 まずは充足感重視
0投稿日: 2022.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何かに成功すること」で充足感を得たのではなく、「自分自身にとってかけがえのないことに熱心に取り組むこと」で充足感を得た人が成功している。 ①自分のモチベーションの本質を理解する ②自分のモチベーションがより多く生かされる機会を見つけて選択する ③試行錯誤しながら、自分の強みを生かした戦略を考える
0投稿日: 2022.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私がこの本を一言でまとめると、【偏愛しようぜ!】でした。 1.ちょっとやってみたい!程度な小さなモチベーションを積み重ねる。人生でいちばん、私だけがほしいものは何? 2.一般的なリスクは無視して、自分にあった偏愛の道を選択する。歩き回っていい。平均的でなくていい。 3.自分だけの戦略を考える。強みは、状況によって左右され、動的なもの。唯一の最善の方法は存在しない。決まった道はない。 4.人生の目的地は忘れておくかどこかに置いておいて、いま充足しているかを常に自問自答、改善する。目の前のことに集中する。
0投稿日: 2022.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
まず大事なことは「小さなモチベーション」。この積み重ねで人は動く。「大きな情熱」「大きなモチベーション」ではなく、自分の中にある「おっ、ちょっとやってみるか」程度の「小さなモチベーション」がスタートである。 自分でも「目的地」がどこかを予め想定することは不可能だ。想定するだけ無駄だから、具体的な目的地を考えない。足元の目標を一つひとつクリアしてくのみだ。 「服を仕立てるのに知っておかなければならないことは、まず、顧客1人ひとりの性格、年齢、肌の色合い、職種、ライフスタイル、そして特に、内に秘めた願望だよ」 われわれの場合は、これと決めた仕事で成功して初めて幸福感を得られると思い込んでいる。充足感は目標を達成した見返りなのだ。しかし、あなたの知り合いのなかに、仕事で成功しながらも、不幸な人生を送っている人がどれだけいるか数えてみたらどうだろう。 「充足感」が先。成功は後からついてくる 「人生の選択権は自分にある」 第一線で活躍している人たちは皆、歩いていたのよ。やがて誰かが拾ってくれるまでね。私たちが助けてもらえるのは、歩いている姿が誰かの目に留まるから。誰でも人が前に向かって進んでいるのを見るのは好きだから。だけど待っているだけの人を見るのは 誰も好きじゃないはずよ。 「自分にあった戦略を見つける」ことは、誰か別の人から教えてもらった上達法ではなく、自分の強み(strength)を案内役にして、独学法やトレーニング方法や習得法を探し出すことだ。
0投稿日: 2022.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かっていることではあるがなかなか難しい。 と思うが、そう言っている時点で考えて行動することをやめているんだろうな。 ひたすらトライ&エラーを繰り返して、自分にフィットすることを探す。 そして、自分にとっての天職に出会う。
0投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ継続できる好きなことと小さなモチベーションを見つけ 試行錯誤して自分に合ったやり方、機会を見つけ、次から次へと新たな目標へ向かうべし 才能を発見し、伸ばすべし。 等。 出自や学歴に関係なく、自分の才能を見つけて活かす方法の概念論。 かたや、橘玲氏の無理ゲー社会に描かれてるように知能が高い人にだけ当てはまる論なのか、そうでなくとも個別化したフィットを追求すれば成功(自己肯定感、自己効力感ある人生)が得られるのか気になるところ。
0投稿日: 2022.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局のところ、何でも自分にあった方法で進めていくということが一番という当たり前とも取れる結論だったが、私にとってはとても良い言葉だった。ホントに良い方法論を求め続ける気苦労が少なくなった。
0投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がどういう道を経て今に至るかを振り返る機会になりました。何を基準にそこを選んだのか。本当にやりたいことに没頭していたらまたちがう人生があったかもしれない。そんな事を思わせてくれる良書です。
0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログダークホース。 話題作を読み終えた感想を一言で表すと、 『やりたいことを探し続けろ』という気持ちで腑に落ちました。 たくさんの方々の体験談が聞けたが、 表現の解釈はわからないところが少々あった。 だが、 充足感を求める。 フィットする環境 目的地は忘れろ 自分自身がどういう人間か知る 目的地は無視し、目標は無視しない。 最終的に個人の幸せを追求すれば周りも幸せにできる など。 名言は多く、タメになり。 今後もこれらを意識して生きていこうと思った。
1投稿日: 2022.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ充足感というワードが強く脳裏に残る1冊。自分が充足感を感じる事ができることを探検してもいいんだ!何歳からでも!と思わせてくれました。 これからの人生楽しみになります。
0投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログIntroduction そんな古い「成功法則」をまだ信じているのか 型破りなルートで活躍するようになった「普通の人々」の共通点 「ダークホース的な成功法則」は特殊すぎて真似できない? 仕事で成功したのに不幸な人生を送っている人 1 自分を縛る「見えないルール」に気づくこと―なぜ、「人生が順調」でも満たされないのか? 「他の皆と同じでいい。ただ、他の皆より優秀でいなさい」 「なんか違う」人生への“小さな違和感IIはサイン ダークホースたちの「人生の転機」はいつ、どんな形で訪れた? 北欧に伝わる「ヤンテの掟」 「個性はムダなもの」、世界の価値観が変わった瞬間 ゆりかごから墓場まで「標準化された人生」 「どの高さまで上った?」―“出世の階段"は狭い一方通行 未経験で「人気フラワーデザイナー」になったダークホース スティープ・ジョプズを動かした大学院中退のダークホース シカゴを「緑鮮やかな庭園都市」へと一変させたダークホース “標準化の眼鏡”を外せば「見えなかった道」に気づく! 2 「自分が好きなこと」を掘り起こせ―ルール1 大事なのは、「大きな情熱」よりも「小さなモチベーション」 ”あなたの帆“に最高の風を吹き込むのは何か? なぜ、「本当にやりたいこと」は簡単に見つからないのか アドラー、ユング、フランクル・・・・ 人間を突き動かす「普遍的な欲求」とは? 「自分が好きなこと」を組み合わせれば、可能性は無限大! 「判定ゲーム」で自分の隠れた願望をザクザク掘り起こせ! 「ちょっと変わった嗜好」でも堂々と好きと認めよう 「自らの情熱には従ってはいけない!」その理由 永遠に消えない!「やる気の炎」を燃やし続ける方法 3 「自分に合った道」を選択する―ルール2 一般的なリスクは無視していい なぜ、ダークホースたちは、大胆な行動を取り、困難な道に全力で挑み続けられるのか 「人生の選択権は自分にある」は盛大な勘違い 「どの大学へ行くかj 」—“選択”ではなく”指定“しただけ 「選択のパラドックス」を一瞬で解決する方法 自分の「好き」を羅針盤にして人生を切り開く チャンスは「待つ」ではなく、「歩き回って見つける」 「ダークホース的な生き方」は「博打的な生き方」ではない 「敷かれたレールの上を走る」のは本当に安全か? 未経験からの大転身ーなぜ、彼は自分の成功を確信していたか 「すでに手にしたものを失いたくない」選択に迷うとき 「これが、私の進む道です」 4 独自の「戦略」を考え出す―ルール3 一見風変わりな方法も自分には「正攻法」になる 何かをマスターしたいなら、まず「自分自身についてマスター」せよ! 初心者の常套句「どの戦術が一番良い?」が愚問な理由 自分の「強み」を自覚する 「なんでできないの」あなたの自信と意欲を奪うモノの正体 「あなたはどれくらい上手にカバに乗れるか?」 「盲目の少年」がルーピックキュープを解くために編み出した戦術 「自分の強みに適した戦略」を選べばどんな困難も越えられる 「やり抜く力」を支えるもの 「素晴らしいパフォーマンス」を叶える”最後の鍵II 5 人生の目的地に到達するには、目的地を探してはいけない―ルール4 「目的地」のことは忘れて、充足感を今抱いているか自問する あなたはどこにでも行けるし、何にだってなれる!ただし・・・ スーパーコンピュータが示した「目の前のことに集中する意義」 合う・合わないは当然!「既存の成功」はまるで”既製服“ 「習得までどれくらい?」この質問に疑問を抱かない人は要注意 平均年齢、適齢期・・・「時間」から自由になる考え方 「大人になったら何になりたい?」は呪いの言葉 ”タイガーペアレント"に育てられた優等生ジェニーの物語 「目的地」と「目標」はどう違う? 成功したければ、「最も険しい急斜面」を登って行け! ダークホース的「個人軸の成功」の処方箋220 6 誰でも、何歳からでも「才能」は開花する!―「何かを達成できる機会」は無限にある! 誰もが主役になれる時代。「オ能を伸ばすため」に知っておきたいこと 「私には特別なものはない」と誤解しているあなたヘ われわれの社会を支配する「才能の定員制」 本当に「大学入試は公平で公正なもの」なのか 社会の矛盾をごまかす「才能エカント」という概念 「誰もが才能をもっている」ということを公式化すると IQテストの不都合な真実 「誰もが何かに秀でている」はキレイゴトではない 「選択」ひとつで世界は変わる 7 世界は確実に変わってきている!―「充足感」の追求こそ個人の使命 あなたらしい「最高の人生」へ踏み出そう 「ダークホース的成功」の世界へ! 現在の「能力主義」は「才能の貴族主義」 わずかな勝者と大多数の敗者が生まれる「不公平な人生ゲーム」 「少数が成功する社会」から「万人が成功する社会」へ 私たちには充足感を追求する「権利」だけでなく「義務」がある 「機会均等」から「平等なフィット」へ 組織は「効率性」ではなく「適応性の追求」の責任を負う SFではない!このままでは「超・監視社会」が訪れる 「サミット学習プログラム」ー平等なフィットを提供 「CfA」―学年と単位を廃止。画期的大学プログラム 「NAPo」—定員枠も才能エカントもない組織 あなたは、もはや機械の歯車ではない Conclusion 「個人の幸せ」を追求すれば、周りも幸せにできる 「幸福の追求」は「生存」と「自由」に並ぶ至高の権利 「全能の神ですら、幸福になる必要がある」 なぜ、ダークホースたちは「ギバー(与える人)」になるのか
1投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ【充足感】と言う言葉が印象的で響いた。『自分自身にとってかけがえのないことに熱心に取り組むこと』で充足感を得られる様になりたい。本業の並行して。あくまでも、軸となる仕事は残したい。出来れば定年まで。でもその為には本業でも存在意義が必要。+αを自ら探しながら色々実験中。 後半部分で“育児・子育て”には参考にしたいコレカラの学びや生き方については考えさせられ参考にしたいと思った。
0投稿日: 2022.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の周囲で話題のDark Horse! 目を見開いて驚きの顔で夢中でぐいぐい読みました! 私は「どうなりたいか決めましょう、そしてそこへ向かって進んでいきましょう」という考え方が自分にうまくフィットしなくて、長い間悩んでいたんですけど、この本を読むうちに力強く希望が湧いてきました。 この本に書かれている、「今、この出来事」に対して自分が咄嗟にどんなジャッジをするか自己観察することで自分の心の源に迫っていく自己理解方法は「適応性」上位の私には涙が出そうなほど心の栄養になりました。(@ストレングスファインダーという自己理解ツール:適応性=今にフォーカス) そしてこの本に示されている、「今」小さなモチベーションを感じるものに取り組んでいって、幸福な「今」を積み重ねて常に「充足」を感じていく、という人生の進め方も「えっ!それでいいの?」「いいのね~!!!」状態でして、読んでるそばから実行できまくりまして、この本を読んでから、もう最高に幸福なんです! 価値の力点が「成功→充足」に時代は変化しているという、「天動説→地動説」に匹敵するパラダイムシフト的見地からもゾクゾクしましたが、適応性の私にとっては幸福論というか幸福哲学のようにも感じられました。 幸せはすごく身近で、強みの領域にあった!という、まるで「青い鳥」のようです! 適応性という資質を「強み」としてついに捉えられたので、本書の方法で育てていきます! もう、本当に!読んでよかったです! 適応性資質上位の人に限らず、自分の人生をどこへ向かって進めていくのか決める迷子になっている人、ドリームツリーの作業がしんどい人、ダークホースおすすめです! 今「小さなモチベーション」を燃やせることを積み重ねていきませんか? 私の場合、それは、今とか今日の「これがしたい」です~。(笑) でも、ゴロゴロしたい、とかではないです。それだと、小さくすら燃えていませんので。 少しでも良い未来につながる、今(今日)心からの小さな「これがしたい」「これをしよう」。 今まで「したいことは?」と問いかけてもらったとき、私が「思い浮かべなきゃ」とブレインロックがかかっていたのは、遠くにあって大きな、旅路の果てに向かって多くのリソースをつぎこまなければならないもの、だったんです。 でもダークホースでブレインロックが外れて、そのときどきの状況にフィットしながら「今したいこと」「今のワクワク」を行動し続けていったら、標準化されていない型破りなルートで人生ものすごく最高なところに連れて行ってもらえるんだ!と希望や安心、そしてドキドキや幸福感など、ごちゃまぜな沢山のポジティブな感覚に包まれることができました。 私はもう「したいこと探し」しません(笑) 「したいことを見つける作業」から解放されました! 多くの人のブックレビューや読書会イベントが本書を読むきっかけとなりました。 感動の輪を広げてくださりありがとうございます! 積ん読本は沢山あるのに、ごぼう抜きであえて読むに至ったこの偶然と選択! 本書の目次にもあるように、本当に「選択ひとつで世界は変わる!」を実感しています。 私も本書の感動や素晴らしさを循環・還元させていければいいな、と思います。ありがとうございました!
0投稿日: 2022.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のキャリアだけでなく、親としても考えさせられる本。 大きくなるにつれ、テストや受験の機会を迎えるであろう息子。結果がどうであれ、それらはあくまで才能の一部を評価しただけにすぎず、誰もが秀でた才能を持っていることを忘れず息子を見守りたい。
0投稿日: 2022.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書では標準化という言葉になっているが、コモディティ化した人材のままでよいか。 「標準化」から抜け出し、ダークホースとなりたいか。 その選択をせよというのが本書である。 選択して成功した人たちの体験記のまとめである。 まずは、標準化した世界が縛るルールに気が付くこと。 次に、自分が好きなことを掘り起こすこと。 見つけた好きなことを選択すること。 そして目的地を定めずに突き進むこと。 全部が全部、本書がその通りとは思わないし、自分もやってみようという動機付けにはならなかった。 成功体験ばかり陳列されると違和感がある。
0投稿日: 2021.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログスタンダードな成功法則=モーツアルト、バフェット、タイガーウッズなど。 それに対して、好きなことだけで生きる人が成功する。 「充足感の追求」を続けることで、ダークホースになれる。 標準的な成功では、努力を重ねたのちに充足感を得る。ダークホースでは、充足感を求めていると成功する。 将来の充足感を求めて、一つに努力するのではなく、充足感を追求して最高の人生を歩むことを目指すべき。 最初は人生に対する違和感=本来の自分を求める。 既存のルール「ヤンテの掟」を拒否する。 自制心、決意、不屈の精神、熱意、グリッド、などは「個性は重要ではなく、努力だけが必要」と言っている。しかし実際は個性にマッチした充足感を求めるほうが成功する。 「小さなモチベーション」を見つける。 自分の好きなこと、を組み合わせる。 「判定ゲーム」=他人を見て、自分が他人の立場だったらどういう気持ちになるか、うれしいか、わくわくするか、いやか、など。=モデルケースを探す。 小さな好きなこと、モチベーションをたくさん探す。 人生は選択というより、指定しているだけ。提示された中から選んでいるだけ。本当の選択権は、好きなこと、小さなモチベーションが生かされる選択。 とにかく目的地に向かって歩く。そうすると誰かが拾ってくれる。歩いている姿が誰かの目に留まる。 成功の確率(選択側から見た倍率)は関係ない。リスクは倍率ではなく、フィットすることが多ければリスクは少なくなる。 なにかを失いたくない、と思うと、自分に合った選択をする、ことが難しくなる。 小さなモチベーションと目の前のチャンスがフィットするか、だけを考えて選択する。 標準化したシステムからは標準化した成功しか生まれない。 小さなモチベーションは進化し続ける。進化したら、既存の失うものを気にせずに、チャンスに従う。 既存の教育システムは、才能を開発しているのではなく才能を選別しているだけ。能力主義ではなく定員主義。ネガティブサムゲーム。定員より多い人数が、才能を生かすチャンスが失われる。 アメリカの独立宣言に、個人の充足感が謳われている。 「幸福追求」「生存」「自由」。充足感の追求が社会によって守られる個人の権利であることが書いてある。
0投稿日: 2021.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の仕事が自分に合っていないかも? と、思った時や、 就職前に自分のやりたい事が見つからない といった時に手に取ると良いと思います。 本書で紹介されている小さなモチベーションを理解し、自分の小さなモチベーションを探す事で自己理解が深まります。 自己理解が深まることで、確度の高い、より自分に合った仕事探しに繋がることでしょう。 本書では、ダークホース的な生き方の事例を中心に書かれていて、多少クドイところもありますが、自分探しのきっかけを作ってくれた良書です。 一読される事をオススメします。
0投稿日: 2021.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「さすがにそろそろ仕事せなあかんかな」と思っているときに読むと、「いやいや好きなことやればええねん」、と言ってくれる本。 ただ自分の充足感を求めて行動すれば、結果は後からついてくるし、結果的に幸せになれる、ということらしい。 言ってることは分かるけど、やっぱり厳密な自己分析と行動力は必須だと思った。
0投稿日: 2021.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログルールに縛られない個人の充足感の追求が、個人に成功をもたらし、それこそが個人の幸福の追求であり、ひいては社会全体に良い影響を与えるというのが、私にとっての本書の概要です。 充足感の追求が偉大な成功をあげた実例が紹介されておりますが、標準化されたレールの上での成功者は充足感を追求していなかったのでしょうか。また全ての人が個人の充足感のみ追求した結果、その社会は社会としての仕組みを果たせるのか等の疑問が残りました。 自分が感じる充足感をモチベーションにすることで、良いパフォーマンスと幸福の追求につながる事には共感し、今後の私の選択に活かしていきたいと思います。
0投稿日: 2021.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて https://ameblo.jp/w92-3/entry-12705534357.html
0投稿日: 2021.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代に合った生き方のヒントが得られる本 標準化の仕組みに自分がどれだけ影響されているかを見直すいいきっかけになった。「個を尊重」して生きる、そんな生き方をしたいと思わせてくれます。
1投稿日: 2021.09.29
