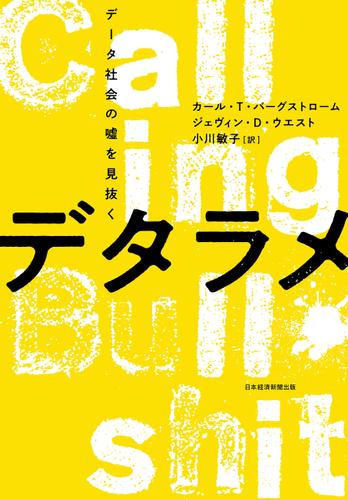
総合評価
(9件)| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題は「ブルシット摘発」Calling Bullshitなのね。ネットのあれこれや定量的ブルシットに重点がおかれていてそこそこおもしろい。
0投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本のここがオススメ 「(1)デタラメをつくるのは、デタラメを退治するよりもはるかに簡単。(2)頭をたくさん使うのは、デタラメをつくる時より退治する時。(3)デタラメ退治はデタラメのスピードには追いつかない」
0投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「数字は嘘をつかない」のではなく「嘘つきは数字を使う」ことを見にしみて理解できる本でした。よくある宣伝広告に書かれた数字の嘘から話は始まりますが、そこまではまあわかる話です。でも本書がすごいのは、そこから機械学習などの最新テクノロジーや、科学論文という「さすがに信じてよいのでは?」と思えるものにまで話が進むことです。普段、専門家の見せる研究結果や「学術論文によると・・」などといった言葉を見てある程度盲目的に数字を信じてしまうことがありましたが、実はその科学というものがいかに怪しいかを教えられました。 論文を読んで内容をまとめる系のYouTuberがよく「科学的に正しい」なんてことをサムネイルに載せたりしていますが、全くもって眉唾です。本書を読んでP値ハッキングの実情を知れば、特定の論文に依拠して科学的に正しいと言い切ることがいかに間違っているかが分かります。正確には「科学的に正しい可能性がある結果が出ている」くらいに捉えるべきだということが分かります。 本書には数字のデタラメを見抜くテクニックがいくつか紹介されていて、すぐ実生活に応用できます。でも個人的に最も響いたのは、「科学」というものは1つの成果で判断するのではなく、その分野の数多くの研究の総体として蓋然的に理解しないといけない、という科学に対する見方を教えてくれるところです。
0投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や、社会には“デタラメ”――事実ではない情報があふれている。その中で真実を見抜くには、どうすればよいのか?人々を惑わせるデタラメの特徴、そして騙されない方法を説く書籍。 デタラメは広まりやすく、正すのが難しい。 例えば「ワクチンが自閉症の原因になる」というデマがある。その信憑性は、後の調査で完全に否定されたが、デマは今もはびこっている。 因果関係がないのに、因果関係を示唆するデタラメがある。 例えば、マシュマロ実験という社会心理学の研究では、マシュマロを食べるのを長時間我慢できた4歳児は、成長してからの学業成績がよかった。この自制心と成績は、因果関係ではないが、自制心が人生で成功をもたらすとメディアは報じた。 デタラメを見破るには、例えば、次のような点に注意する。 ■情報源に疑問を持つ: 「誰が私にこれを伝えているのか?」「その人はどうやってそれを知ったのか?」「その人は何を売り込もうとしているのか?」を自分に問う。 ■この比較は正しいのか: 「空港の手荷物用トレーには、トイレよりも多くの細菌がついている」との論文がある。だが調べたのは呼吸器ウイルスだけ。人はめったに便座に向けて咳せきをしないから、トレーの方が多くても不思議はない。 ■うますぎる話、ひどすぎる話ではないか: うますぎる話(あるいは、ひどすぎる話)は、たぶんデタラメである。 ■数字の桁は間違っていないか: デタラメは底が浅いため、おかしいとすぐわかる、数字の誤りを犯すことがある。 オンラインのデタラメを見抜くには、次のようなことを行う。 ・知らない情報源からの情報は、検索エンジンで確認する。 ・画像を使って検索する。 ・ファクトチェックを行うウェブサイトで確認する。
0投稿日: 2023.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の社会は情報が豊かであるが故に,正しくない情報=デタラメも溢れています。よく行われる手法や人が騙されやすいポイントやなど,何を知ってどこに注目すればデタラメを見破ることができるのか,そのスキルをぜひこの本で獲得してください。きっと一生使えますよ。
0投稿日: 2023.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログパオロ・マッツァリーノの反社会学講座を思い出した。 目新しい主張は少なめ。よくある統計のトリック話。 AIの学習方法は面白かった。
0投稿日: 2022.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログロシアの件でフェイクニュースに騙されないようにと図書館からきていいタイミングだなぁと思ってたけど現実の方が動きが早すぎる。。。
0投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて https://ameblo.jp/w92-3/entry-12717713809.html
0投稿日: 2021.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#デタラメ』 ほぼ日書評 Day503 引っ越しで時間を取られ、久々の書評アップ。 さてさて、原題は "Calling Bullshit: The Art of Skeptism in a Data-Driven World"。まずは、これをこの邦題に訳した才能は素晴らしいとしか言いようがない。 内容的には、読み手をミスリードするグラフや図表等を多くの具体例を挙げて解説するもの。ひとつひとつ丹念に見ていくべき内容ではないが、そうしたトラップにハマらないために、さらっておくことには意味があるだろう。 興味深かったデータ分析例をひとつ。 見た目の良い相手は性格が悪く、性格の良い相手は見た目がイマイチ…という「負の相関関係」に関する説明。 本来、実際に全数の分布を見ればそんな事実はない。しかしながら、実際にそうした「現実」が発生する仕組みは以下の通り。まず、見た目も性格も好ましくない(デートしたくない)相手を全数から消去する。次に「あなたのことを歯牙にも掛けてくれない(雲の上の存在)」相手を消去する。消去から残った集団は、見事に先の負の相関分布にプロットされるというのだ。 https://amzn.to/32lozRL
0投稿日: 2021.11.23
