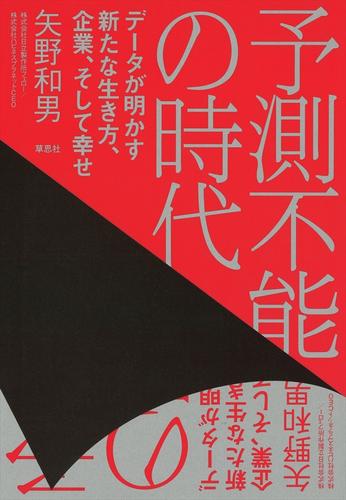
総合評価
(27件)| 11 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ予測不可能な未来を、データを元に、少しでも良いものにしようという取り組みの解説。人々が心地よいと感じる状況を細かく分析できたのは、データが取れたからであり、それはそれで説得力があるのだが、最終的にはデータとは関係ない「易」に帰結するということで、「易」を学んだ方が良さそうです。
0投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい内容だった。 未来は予想できない 但し対応はできるはず 予測不能な時代の幸せな生き方、企業、社会とはどのようなものかを問う われわれは未来について、二つのことしか知らない。一つは、未来は知りえない、二つは、未来は、今日存在するものとも今日予測するものとも違う(ドラッカー) 第1章 予測不可能な変化に立ち向かう 今はドラッカーと真反対、ある程度は、未来は知り得る。だから既に知っている情報やデータを的確に使えば予測や計画が可能である、という前提になっている 変化への適応を阻む構造、「ルール」という罠、「計画」という罠、「標準化と横展開」という罠、「内部統制」という罠、変化する状況を考慮することが大事だと共有が必要 生産性向上が重要だが、行き詰まっている 多様性と変化に対応するための4原則 第1の原則 実験と学習を繰り返す 日々ルールや計画と闘うこと 第2の原則 目的にこだわり、手段にはこだわらない 手段にこだわると、変化に対して弱くなる 第3の原則 自己完結的な機動力を持たせる 出島という第3形態 第4の原則 「自律的で前向きな人」づくりに投資する これが大変 第2章 新たな幸せの姿 幸せだから、仕事がうまくいく、幸せだと、病気になりにくく、なっても治りやすい つながりに格差や孤立がない 短い会話の頻度が高い、人と人の会話においては、大は小を兼ねない 幸せな組織では、会話中に身体が互いによく動く 幸せは会話中の身体の動きから生まれるのでる メンタルヘルスを脅かす方法は、相手との会話のときに、身体を動かさないこと 幸せで生産性の高い組織をつくる4条件 第1の条件 組織図にとらわれずにつながりあう 第2の条件 予定表にとらわれないタイミングで会話しあう 第3の条件 立場の違いにとらわれずに会話を身体で盛り上げる 第4の条件 役職や権限にとらわれずに発言しあう 心理的安全性の確保がマネジメントの基本 第3章 幸せは天下のまわりもの 組織の幸せは、メンバーが周囲を元気に明るくしているかで決まる 幸せは天下のまわりものというのがデータからも読み取れた あなたの幸せは、自分一人では生み出せない、あなたの幸せは、自分が関わる周囲の人たちから与えられるもの 第4章 幸せとはスキルである 幸せを高める能力「心の資本=HERO」 第1の力 ホープ(Hope) 自ら進む道を見つける力 第2の力 エフィカシー(Efficacy) 現実を受け止めて行動を起こす力 第3の力 レジリエンス(Resilience) 困難に立ち向かう力 第4の力 オプティミズム(Optimsm) 前向きな物語を生み出す力 為せばなるの精神を 第5章 変化に向き合うマネジメント 組織版ウェルビーイングケアがまだ無い。 人的資本マップを使えば可能 孤立とは、人との接点がないことではない。人が孤立を最も感じるのは、むしろ人と一緒にいるときなのである。人と一緒なのに、自分に関心を持たれず、応援されず、信頼されず、元気を奪われるような反応ばかりを受けることによって我々は孤立を感じる リモートワークでも会話時はお互いに顔を見せて、動きが分かるように少し大袈裟に動くのが大事 雑談用のネタをアプリを使って1日1分で入力してもらい、みんなで共有するのが良い 会議前後の雑談大事 第6章 変化にデータで向き合う データは常に過去のものであり、未来のデータは存在しないからだ 教師あり学習は統計学をベース 統計学は予測不能な未来を見ることはできない 新しいデータ解析の原則 第1原則 予測不可能性の原則 未来は予測不能に変化し続ける 第2原則 データ能動獲得の原則 データは、能動的に獲得し続ける 第3原則 実験と学習の原則 データを活用し、実験と学習を繰り返して目的を追求し続ける 「し続ける」ということが大変重要 PPPサイクル 実戦はとても難しい 第1の過程 プレディクト=予測 過去データを用いて過去の延長ではどうなるかを予測する 第2の過程 パシーブ=気づき 過去の延長と現実との重要な乖離を特定する 第3の過程 プライオリタイズ=優先化 乖離が起きている対象に対し優先的に行動を起こす 科学は、速さ、長さ、多さの変化と、その変化をもたらすもの(これを力と呼ぶ)に注目する。法則性は「力」と「変化」の関係にこそある。多様な世界に、普遍的、統一的な法則性を見出していくのが科学。変化を定量的に取り扱うための道具が「微分」。新型コロナウィルス感染症で「実行再生算数」はまさに変化率(あるいは微分)を捉えた指標 データとAIが可能にするのは、予測ではない。私たちの行動を支援するもの これからは未来開拓型AIが目指すもの AlphaGoやAlphaZeroはこれをやっている 第7章 格差の本質 勝者優遇のルールが格差を拡大させる エントロピーの増大 平等は自然には現れず、意識的にしかつくれない 格差回避の本丸、教育 格差とは量子効果だ 経済を基本から理解するには、物理学が必要 分野の垣根という人為的な分類に惑わされず、本質を探究する人を増やすことが大事 「自由」と「平等」を両立させることは、原理的にできない。常にトレードオフの関係にある 第8章 予測不能な人生を生きる 幸せとは状態ではなく行為である 予測不能と向き合う最古の方法『易』 中心テーマは、変化であり、変化への向き合い方である 64個のパターン分類は、二進法の仕組みによって、数学的に定義されている 二進法、6ビットの体系で変化の状況をパターン分類し、陰と陽という2状態の組み合わせで変化を表現する。陰=0、陽=1 64×64=4096個という多数の変化を表現できる 変化に立ち向かう力を高める方法 (1)毎朝、コイン投げ他の方法によって、16のうちから1つの視点(訓練項目)を得る。 (2)その視点に対応する本書末尾の記述を読む。 (3)その意味を、その日の仕事や状況にあてはめて、自分なりに解釈する。 (4)この解釈を、その日の仕事や人生における実践で意識し活用する。 (5)翌朝、昨日どうだったかを振り返り、(1)に戻る。 16の変化に立ち向かう視点 ・受け止める(Mindfulness)「0000」〈素直にやるべきことを実行する〉 ・覚悟する(Resolution)「0100」〈矛盾を引き受けることを覚悟する〉 ・求める(Quest)「0001」〈先走らず、今の一歩に集中する〉 ・立ち向かう(Challenge)「0101」〈困難に立ち向かい、今日を最高の学びの日にする〉 ・始める(Begin)「1000」〈次のステージに向け、最初の一文字を書き始める〉 ・やってみる(Passion)「1100」〈力を蓄え、次の伸びしろが見えたら全身全霊で飛び移る〉 ・交わる(Curiosity)「1001」〈制約の中だからこそ、内なる原理に従う〉 ・踏み出す(Adventure)「1101」〈人が集まり、知恵が交わる機会を活かす〉 ・信頼する(Trust)「0010」〈旅の落ちつかなさを楽しむ〉 ・教わる(Update)「0110」〈心を開いて、異質な事物と交わる〉 ・心開く(Diversity)「0011」〈積極的な意味で、一旦引く〉 ・感謝する(Synergy)「0111」〈成長のための困難に感謝し、立ち向かう〉 ・結束する(Relationship)「1010」〈心配し、そして笑い飛ばす〉 ・強調する(Partnership)「1110」〈活躍できる状況に我欲を超えた行動を貫く〉 ・対等になる(Inclusion)「1011」〈制約に従い、工夫する〉 ・協創する(Resonance)「1111」〈緊張する状況でもぶれずに前に進む〉 あとがき 日本が世界に誇るべき概念「道」
0投稿日: 2025.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ・世界が予測不能であることを正しく前提としていれば、最も気にすべきは、「現実と合わなくなった計画にアクションを起こしているか」だ。にもかかわらず、計画通りであることが良いことで、そうでないのは悪い事のように誤って方向づけしてしまうのだ ・変化が起きたときにうまくいかなくなるのは、変化する前の状況に適合していた「手段」にこだわっている場合だ。変化を前にしても影響を受けないのは、簡単には変わらない「目的」の達成にコミットしており、手段については柔軟性を持っている場合だ。 ・MID:マーケティングとは顧客が誰で、顧客の価値は何かを見出すこと。イノベーションとは、答えられていない顧客の要求に答える手段を確立すること。デリバリーとは、これを納期や品質やコストなどを適切にして顧客に届けることである。加えて、顧客からのフィードバックに対し、これを再度マーケティング、イノベーション、デリバリーに反映することである。予測不能に変化する状況では、いくら調査や研究をしても、顧客に提供してみないとその真価はわからないことが多い。 ・幸せな組織の特徴 Flat : 人と人とのつながりが特定の人に偏らず均等である Improvised (即興的) : 5分から10分の短い会話が高頻度で行われている ノンバーバル:非言語的 会話中に身体が同調してよく動く イコール:平等 発言権が平等である ・組織の能力を高めるには、チームメンバーの気持ちが分かる人やそれを考慮した発言が会議でデキる人を育てることのほうがよほど大事なのである。 ・組織の幸せは、メンバーが周囲を元気に明るくしているかで決まる ・人を明るく元気にし、ポジティブな影響を与える動きは、集団の中で循環するのである。その意味で、「幸せは天下のまわりもの」である。 ・あなたが幸せになるための法則は「人に元気を与え、そして人から元気を貰える人になること」であり、それは、「人を応援し、そして応援される人になること」とも言える ・心の資本 Hope : 自ら進む道を見つける力 Efficacy : 現実を受け止めて行動を起こす力 Resilience : 困難に立ち向かう力 Optimism : 前向きな物語を生み出す力 ・「仕事とは決められた職能とその責任を果たすこと」という認識から、「仕事とは成功に必要なことは何でもやること」という認識への変化 ・現在のデータの活用もAIの活用も、まさに「過去の経験をまねする」ことだけを行っている。これにより、新しいことをやらなくなり、変化に弱くなる ・新しいデータ解析が前提とすべき原則 第1原則:予測不能性の原則 未来は予測不能に変化し続ける 第2原則:データ能動獲得の原則 データは、能動的に獲得し続ける 第3原則:実験と学習の原則 データを活用し、実験と学習を繰り返して目的を追求し続ける ・速さ、長さ、多さの変化と、その変化をもたらすものに注目するのが科学。法則性は「力」と「変化」の関係にこそあるのである ・多くの場合、専門分野の知識を持っている人ほど、その特定分野の知識に囚われて本質が見えなくなってしまう。現実における本物の問題やデータを扱うときには、分野の壁を超えて、このような物事の本質を理解しているかどうかが大事なポイントになる。 ・江戸明治の知識人にとって「学問を修める」とは、「道のどんな状況になっても、ブレずに正しい態度で向き合える人になる」ということだった。 ・味方に柔軟性が失われた状態を「ペシミズム」と呼び、指向に柔軟性を持っていることをオプティミズムと呼ぶ。これこそが、変化に立ち向かう最も重要な能力なのだ。 ・前向きな精神は、ことを始めることによって生まれる。やり始めることで次第に集中が生まれるのである。 ・人と信頼を作る人生という旅をため向きに楽しむ境地になることこそ、動的な意味で幸せである
0投稿日: 2024.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し読んでは考え、少し読んでは考えることがある本でした。 良いチームを作りたい方、予測できない世界を生きることに 不安を感じている方におすすめです。 とても良い本だったので長めの紹介文になっています。 科学、特に統計学は人々に予測する力を与えてくれました。 深層学習は過去のデータから最適な組み合わせを見つけてくれます。 幸せに働く人が多いチームでは売上が良いことを示しつつ、 幸せに働くチームが"どのような行動をしているか"を、 ウェアラブルデバイスから得られたデータを基に分析します。 一方で私たちを取り巻く環境は、大きな技術の切り替わりだけでなく、 ほんの小さなきっかけですらSNSで共有され、不連続な予測不能の未来を 紡いでいきます。 このような予測不能の世界では、急峻なニーズの変化、 企業の部門撤退や倒産に翻弄され不幸を感じる境遇に 直面することも少なくないと思います。 こんな予測できない時代に私たちはどう生きるのか。 そのヒントが3000年以上前に体系立てられた易経にあると筆者は言います。 易経はごく最近まで広く学ばれ、先の見えない世界を駆け抜けた明治時代にも 重宝されていた考え方です。 変化を多角的な視点で受け止め、行動し、学び続ける方法を示してくれる易経は、 本来、日本人が一生をかけて鍛錬した"道"は学び続ける精神(武道、茶道など)として 根付いてきた考え方だと言います。 変化とうまく付き合い、幸せに生きるコツを教えてもらえる1冊でした。
0投稿日: 2023.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の講演を聞いて手にした本です。お話も平明で力強かったですが、文章で読むとさらにその印象は強まりました。理系研究者の語る「幸福論」は、まるで方程式を立てて、それを解いているような気持ち良さがあります。また、それが抽象論ではなく徹底して具体であるのは、実証実験とデータを重ねて行くスタイルにもあると思います。読みながら4年前にに読んだアレックス・ペントランドの「ソーシャル物理学」を思い出しました。本書は「ソーシャル物理学」の半径を身の回り3メートルにメッシュした、いわば「ハピネス物理学」です。しかし、著者の論理的な主張のその手前で、アメリカの下院議員ジョン・ルイスの「民主主義とは状態ではない。民主主義とは行為である。」という言葉から語る「幸せとは状態ではない。幸せとは行為である。」という力強いアンセムがなによりも刺さりました。Happinessという状態からHappingという動詞へ。ってことは「Happing物理学」か…。FINE、HOPE、だけでなく、とにかくいっぱいフレーズ、メモしました。
0投稿日: 2023.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ1〜2週間に1冊は本を読みたいと思っているが、この本はやたらと時間がかかった。小さい文字で324ページはなかなかヘビー。内容的にも「ウェアラブル端末やスマホの登場で、幸せを科学的に測定可能になった」ということをベースにその結果を説明してくれればよいものを、自己の研究成果や上記と直接関係のない思いが散りばめられており、読みにくかった。
0投稿日: 2023.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログあ、面白かったです。たくさん、思うところがあり、付箋を沢山つけました。もう一度読みたいです。タイムリーに出会えたかもしれません。
0投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ相変わらず、抽象的なネタを定量的に分析されていて、まず視点が従来にない、という点が痛快に面白い。 そういった意味では、前作ほどのインパクトはなく、ただただ「あぁ、ブラッシュアップされてるなー」と感心するにとどまる。 途中、教育にまで話が発散していくが「結果による処遇の不平等」に関する論は非常に興味深い。エントロピー増大を当てはめるアプローチは、著者らしいアナロジーの提示だったと思い、ワクワクしながら読むことが出来た。 ただ、個人的には最後の1/3くらいは不要かな、と思った。が、本書の意図からすると必要だったのでしょう。
0投稿日: 2023.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯多くの企業では、以下の4つの統制を導入してきた。 (1) 計画に従ってPDCAをまわす (2) 仕事を標準化し、横展開する (3) 当事者が誤った判断を下すことを内部統制により防止する (4) 従順な人を安く雇い、設備に投資する (49p) ◯今日のオペレーションに、明日のための的確なデータ創生の視点を入れなければいけない(202p) ◯ここで一番だめなのは「私はブランコ屋なのに、鉄棒をやらされて困っている」と過去を引きずることだ。(219p) ◯変化を機会に変える行為が「幸せ」である(276p) ★「実験と学習」という、デザイン思考とか、アジャイルの考え方が見直されているが、これまでの、効率しか考えない、非効率が罪のような考え方の方が、特殊な、高度成長期の成功体験に引きずられた、一過性のものだったのかもしれない。 ★今でも「標準化と横展開」が有効であることは言うまでもない。ただそれを盲信して思考停止になるのは避けたい。深化と探索、Googleの20%ルール。 ★この本が独特なのは、変化に対応するために「幸せ」を追求している点。幸せは状態でなく行為なのだ。意識的に共感と敬意を示そう、楽観的なものの見方は鍛えられる、という提案に共感した。
1投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ未来は予測できるものではなく、変化は起きるものとしてその変化を機会に変えられるよう柔軟な生き方を身に着けたいよね、というお話。 著者の過去の取り組み事例などは本書の主題とは異なるがデータの取り方や扱い方の参考になった。 他人にいい影響を与えながら生きたいなぁ。
0投稿日: 2022.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ淡々とした論説の流れだったから、あまり感情も起伏せずに読み進め、データに裏付けされた組織論、あるいは自己啓発本程度に思ったが間違い。いや、そう言えば口絵のライフタペストリやコミニケーションソーシャルグラフで予感はあった。久々に読む最強の本、と稚拙に一言で表現するが、まさにそう。 アリストテレスを引き「幸せ」を定義した後、幸せな組織をウェアラブル端末で分析し、組織論を解説する。フロー状態を体系化したチクセントミハイ教授との共同研究との事、先ずこの導入で一気に引き込まれてしまう。 幸せな組織とは。①人と人とのつながりが均等であり特定の人に集中していないこと② 5分間会話が多いこと③会話中に体がよく動くこと④発言権が平等であること、こうした事がデータで裏付けられていく。 同じように、個人の知的能力を測るIQに対し、集団的知能の概念について。集団的知能が高いグループには①他者の感情を汲み取る能力が高い人が多いと集団レベルに影響②チーム内の会話における発言間の平等性③女性比率の高さ、等も解説される。しかも、ここまでいっておいて更に、データなど過去の事と更に先にいく。秀逸なのは、読者を全く置き去りにしない事。それなのに、どんどん飛躍する。 心の資本ヒーローと言う考え方。HEROという、ホープ、エフィカシー、レジリエンス、オプティミズム、これらが重要となる事。エフェクチュエーションとコーゼーション。サラリーマンはコーゼーションで理屈から。成功した起業家は、許容できる損失からスタートする。自らが持つ資源が増えれば行動できる範囲も変わる。行動しなければわからないことが多い不確実な状況で行動すれば、新たな人とのつながり情報や知識や経験が得られるから。最近、酒の席で友人とまさにこの話をしていた。AI化が進めば、コーゼーション的思考は無用化する。主張が、よく分かる。 平等論について。格差のある状態は何の理由もなくごくありふれた自然の結果だと言うこと。全く同額の所持金からスタートし、配分のためのルールも平等なシミュレーションで、結果として大きな不平等が生じる。その後、エントロピー増大の法則を解説。 極め付けは、易経。2000年以上前に書かれたこの古典は、変化の書であり、64個の極めて体系的に構成されたパターンによって、二進法の基礎になったと。易とコンピュータ両方に二進法が使われているのは偶然ではなく、17世紀に中国に渡った宣教師がこの書物を持ち帰り、当時、二進法を独自に考えていたライプニッツの目に留まることになった。ライプニッツにより二進法は体系化され、コンピュータや情報技術の発展になくてはならないものになっていった。咸臨丸。咸は001 110 臨は110 000 易では陰0陽1により、二進法を表現する。咸臨丸は、このパターン言語を使っていた。面白い。 これでも十分だが、最後の最後に、憲法草案まで書いている。一体何者?論理と知識が同時に満たされる読書体験。
0投稿日: 2022.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前読んだ「データの見えざる手」がとてもよかったので、こちらの本も手に取ってみました。 こちらの本も期待通り、最高です。 ※データの見えざる手: ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則 https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4794220685#comment 本の前半は、「幸せ」を科学するというか、 数値化して、データで分析するという内容。 どうすれば、組織の人間が幸せになるのかについて書かれており、 組織に所属するあらゆる人に示唆がある内容。 例えば、「だから僕たちは、組織を変えていける」などで紹介された 成功循環モデルのファーストステップ「関係性の質」を高める具体策が書かれています。 ※だから僕たちは、組織を変えていける https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4295406252#comment 後半もとても面白かったです。 特に、AIのあるべき姿として、過去のデータから統計的に 決まりやルールを導き出すだけではダメで、 ポジティブな外れ値を見つけて、 未来の兆しを見つけるのがあるべき姿だという著者の主張は、 とても説得力があり、参考になりました。 これからの時代に必須の一冊だと思います。
8投稿日: 2022.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ【どんなことが起きても対応できる】 示唆に富んだ内容でした。 PDCAを否定し、標準化、ルール化を否定しているところがすばらしいです。 確かに、PDCAは計画したことが未来で起きると想定しています。標準化、ルール化も過去の状況に基づいて決定されます。 しかし、過去をどれほど研究しても過去にうまく行ったことしか見つけだせません。 未来を予測することは不可能です。 先人がうまくできたことの焼き直しで、うまく行く時代は終わりを告げています。 情報は一瞬にして世界全体へ伝わる時代です。世の中、全体が常に最先端な状態なのです。 つまり、これから先に起きることは全て未知との遭遇となります。 情報が瞬時に伝わらない時代であれば、ある場所で起きた情報が瞬時には世界全体に伝わらず、場所によってはまだ知らない状態が存在していました。 しかし、今はみんなが最新の情報を知っているのです。 さらに、同じことは二度と起きないと仮定すると、過去のデータに基づいて判断したことは間違っていることになります。 判断基準がないので、過去に起きたことに近い判断は正しい判断に思えるのですが、二度と起きないのであれば、100%間違った判断になります。 ― 未来は何が起きるか予測不能 ー 未来は予測不能であるという心構えでいれば、何が起きても驚くことはなくなります。 しかし、予測不可能だから、ノーガードで殴られっぱなしでは意味がないと思います。 ストレートが来るのか、ボディブローか、膝蹴りか、ローキックなのか、それだけではなく、背後からか、はたまた頭上からなのか何が来ても驚かず対応できる構えは必要です。 ウイルス、戦争、巨大地震、隕石衝突、AI暴走、薬、魔の炭水化物、魔族襲来、エスパー登場、グール、クローン、メタバース、世界線の崩壊などこれぐらいなら予測範囲です。 しかし、実際は想像ができないことが起きるのです。想像もできないので書くこともできません。
4投稿日: 2022.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログビッグデータとか、その解析。果たしてどのようなデータが揃ったところで、この世界は予測不能。データ解析的な話というよりも中盤からはメンタル的な部分に振れていきます。実際、タイトルにも幸せってワードがありますので、データ解析の学習的な本ではないとは思っていましたが、結構、「道」と言うようなまさに思想にたどり着くという構成です。確かに突き詰めるとそう考えることも必要なのかな。でももう少しデータ分析という物に頼りたいという思いもあります。予測が不能でも反応をできるだけ速やかにするためにも。
0投稿日: 2022.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織作りの時に考えていることを色々と体系化してくれていた本。予測不能な社会になった理由や、その中での個人や組織のあり方を綺麗に整理している良本。
0投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
変化と幸福がテーマ。幸福な人は面倒なことにも積極的に取り組み、幸福な人が多い職場は生産性が高いことが研究によって示されている。 幸福で生産性の高い職場の特徴はFINE ・Flat、職場での人間関係に偏りがなく、横や斜めの関係もある。 ・improvised、即興的、5分ー10分の短い会話が多い ・Non verbal、会話の中で共感や同意を示す身体動作が多い ・Equal、平等、会議などで発言権が平等にある。 変化に立ち向かい幸福であるために重要な心の資本はHERO ・Hope 、自らが進むべき道を見つける力 ・Efficacy、自己効力感、自分の能力に対する自信 ・Resilience、困難に立ち向かう力 ・Optimism、楽観性、物事の明るい面を見る前向きさ FINEやHEROを導き出すために行われた著者独自の研究がウェアラブルデバイスと質問表による調査。リストバンド型や首から下げる名札型のデバイスを用いて、身体活動や人との接触を記録。この研究の中でも面白かったのが、動きを1、静止を0として身体活動の配列を作成、その配列のパターンと幸福度に強い相関があったこと。このためスマホさえあれば身体活動からその人の幸福度がわかる。 変化に立ち向かう学問としての易。これは読みたい。
0投稿日: 2022.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の幸福論は、データと帰納によるアプローチ。生産性が高いから幸福なんじゃなくて、幸福だから生産性が高いんだ、というのはかなり芯を食ってるんじゃないかしら。 世に蔓延る不機嫌の拡大再生産をやめれば、自ずと健やかな社会が実現できるのかも、とりあえず、人に優しくニコニコしていよう。
0投稿日: 2021.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日立製作所の半導体技術者であり、幸福の定量化に取り組んでいる矢野和男氏の最新所ということで興味を持ち購入。 VUCAと言われて久しい社会の中で、いかに個人と組織が「幸せ」を目指して現状に向き合うかその指針を示している。 【本書から学んだこと】 ・幸せである組織の特徴 FINE F=Flat, I=Improvised, N=Non-verbal, E=Equal ・「あなたの幸せは、自分一人では生み出せない」、「あなたの幸せは、自分が関わる周囲の人たちから与えられる」 ・筆者がやってきた半導体は簡単に衰退してしまった。その答えとして、半導体は手段であったからだと分析している。状況が変わっても強いのは真の目的であり、それが人の幸せであり最上位の目的である。 単に幸せを目指すための組織の在り方を述べるだけではなく、経営の戦略や経営理念にどう反映させていくかまで考えられていると感じた。新しく組織を運営していく方やマネジメントの勉強をする方に勧めたい一冊。
0投稿日: 2021.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著作の『データの見えざる手』から7年、その間にウェアラブル活動計などからのデータと幸福に関する研究成果を元にハピネスプラネットという会社を立ち上げた著者による新作。本作を貫くのは”予測不能”というキーワードである。 前作が上梓された2014年以降、AIの社会実装は確実に進んできているわけだが、現状のAIのほとんどが過去のデータに基づき学習をさせる以上、それは予測可能な現象にしか適用できず、むしろ予測不能な現代においては”実験と学習”というアプローチに転換する必要がある、というのがこのキーワードによって導かれるテーマである。とはいえ、では”実験と学習”が実際に何を意味するのかというと、真っ先に強化学習のようなものをイメージしてしまうが、そうではないとされ、具体的に何をイメージすれば良いのかが、正直判然としなかった。 本書はテーマが前作に比べて飛躍的に壮大になっており、一種の自己啓発書のような雰囲気すら感じさせる部分がある。一読しただけで正直あまり全体像が理解できていないというのが正直なところでもあるのだが、非常に壮大な問題系に取り組もうとしている、という点だけは間違いなく理解できる。
0投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の思いの丈が詰まっているように思う。 テクニカルな話は期待していたが、無い。 ・予測不能な時代には、計画よりもまず実践しながら学習する ・スピード感を持つためには、個人個人がしっかり幸せや、大目的を把握していることが重要 ・では、幸せとは?スキルで対応出来る。 ・データで変化に向き合って幸せをもたらすためには、乖離を検知して対処すること ・乖離すること、格差が出来ることは自然なこと。それを特別にとらえてはいけない。 ・幸せは状態でなく「行為」のこと。変化に立ち向かう力を高める行為が重要。
0投稿日: 2021.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ幸せな組織の特徴 flat 均等 人と人とのつながりが特定の人に偏らず均等である improvised 即興的 5分から10分の短い会話が高頻度で行われている 1時間の定例以外の会話がある Non-verbal 非言語的 会話中に身体が同調してよく動く equal 平等 発言権が平等である
2投稿日: 2021.08.27幸せは、自分ひとりでは生み出せない
前著『データの見えざる手』では、時間の効率化や行動の最適化に焦点が当てられていたが、今回はより強く幸福化の追求に意識が移った印象。 生化学的な反応の検出装置として、独自にウエアラブル端末を開発してデータ処理していたのが、現在では各人が身につけているスマホに計測用アプリを入れるだけで簡単に取得できるようになったこととも関係しているのかもしれない。 もともと半導体というモノづくりの現場にいた人が、ITサービス、そしてユーザー価値へと、時代の変化に翻弄されつつも、揺るがない究極の上位目的を志向した結果ということらしい。 表からは見えない生化学的な反応や、身体の無意識の動きをシグナルとして計測することで、集団や組織にとっての普遍的な法則が導き出せるというコンセプトに共感して前著を読んだ身としては、「仕事がうまくいくから幸せになるのではない、幸せだから仕事がうまくいくのだ」とか、「幸せにより生産性が高まり、病気も治りやすい」といった本作の書き出しに、正直ちょっと戸惑いを覚えた。 ただ今回も、データから導き出される組織マネジメントの鉄則は傾聴すべきものがある。 まず必要なのは、つながりの総量ではなく、多様性や偏りのなさ。 リモートワークが進めば、必然的に一対一のつながりが増えるため、かえって幸せ度が落ちる。 「孤立とは、人との接点がないことではない。人が孤立を最も感じるのは、むしろ人と一緒にいるときなのである。人と一緒なのに、自分に関心を持たれず、応援されず、信頼されず、元気を奪われるような反応ばかり受けることによって我々は孤立を感じる。まわりに関わる人が多ければ多いほど、このような反応を感じたときの孤立は深まる」。 しかも孤立は「組織の病」でもあるので、孤立した人がいるような状況では、全員のパフォーマンスも低下するのだ。 長話や会議より、日々の短い会話が効果的で、会話中の身体の同調表現は積極的に奨励すべし。 この意味でチーム作りにおいては、知的能力だけでなく、社交性も加味して進めるべき。 面白いのは、幸福度の低い組織とは、メンバーの幸福度がおしなべて低いわけではないというところ。 中には幸福度の高い人もいるのだが、彼らと話をしているのは極端に幸福度の低い人たちで、このような幸せのばらつきや格差が、幸福度の平均値を押し下げている。 逆に幸福度の高い組織とは、メンバーがそれぞれ周囲の人たちを励まし合い、元気づけ、明るくすることで全体の幸福度を高めている。 確かに、古今東西の宗教の教義や古典でも、書かれているのは「汝の隣人を愛せ」など周囲を幸せにする教えで、「自分の幸せを追求せよ」などとは書かれていない。 データが導き出した結論も、「あたなの幸せは、周囲の人たちから与えられるもので、自分ひとりでは生み出せない」ということ。
0投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織(会社)の構成員の幸せを考える上で大変参考になった。大量の実証データをもとに幸せな組織の条件を明らかにし、科学的根拠も示してくれる。自らの経験則からも納得がいく中身であり、組織メンバーと是非シェアしていきたいと感じた。日立の半導体研究者から「幸せ」を研究するに至った著者の思考や経緯も興味深い。最近注目度が高まっているウェルビーイングに少しでも関心のある人は是非手に取るべき書籍。
0投稿日: 2021.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中、中だるみしちゃったけど読破。 著者さんの考えが凝縮しているのは最後の章で、勇気づけられます。前の本と合わせて、個人的には何よりも自分自身を奮い立たせてくれる本です。
0投稿日: 2021.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人においても集団においても「幸せ」の要因として少なからず「身体運動」が関わっているというのがビッグデータによって読み取れるというのは非常に面白い。 この本では最初にドラッカーの言葉を引用している。 『われわれは未来について、二つのことしか知らない。一つは、未来は知りえない。二つは、未来は、今日存在するものとも今日予測するものと違う』 今の時代、数年後どころか数週間後の未来すら何が起きるかわからない。 そんな時代を生き抜く為の知恵が詰め込まれた本です。 著者の視点や洞察力がとても面白く、格差の本質については衝撃的とも言える内容でした。 非常に濃密な内容の本です。 面白かったです。
0投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ◾️概要 予測不能な時代に、データが導き出す幸せな生き方とは何かを知るため、読みました。最も印象的だったのは、「変化を機会に変える行為が幸せである。幸せは状態でなく、行為だ。」です。また、組織の幸せは、メンバーが周囲を元気に明るくしているかで決まるということも、エビデンスとともに述べられています。 ◾️所感 長らく経験則で語られ、捉え所のなかった「幸せ」にデータという物差しをあて解き明かしていく様は圧巻の一言です。研究という枠に収まらず、ドラッカーの述べた21世紀の偉業と言えるでしょう。分野の壁を越え、あらゆる角度から本質に迫り議論を展開しています。まさに、目的の達成のために手段を選ばず果敢に取り組むべき、という主張を体現していると感じました。
1投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも未来とは予測不能である。 AIが進歩したとしても、未来が予測不能であるという前提の前ではなんの意味もない。 今の日本の組織の多くは、ルールに縛られ、標準化や横展開、内部統制によって画一的になっている。しかしこれでは変化には対応できない。 変化に対応するには ①実験と学習→とりあえずやってみて試す ②上位目的へのこだわり→組織の目的にコミットし、その時々で最善の手段を採る ③自己完結的な機動力→縦割りの動きづらい組織ではなく、自己完結的な権力も持った独立組織が理想 ④前向きな人づくりへの投資→可視化しづらい人への投資を惜しまない が必要である。 幸せな組織の4つの特徴 ①flat 人と人の繋がりに偏りがなく均等である ②improvised 5分間会話が高頻度 ③non-verbal 会話中に体がよく動く ④equal 発言権が平等である 個人としてできるのは、人に幸せを与えること。 会話中の同調動作であったり相槌を打つことで幸せを人に与える。そうすればその人から連鎖的に幸せは広がり組織全体に幸せがまわる。 結果として自分も幸せになれる。 幸せとは決して自己完結的なものではなく人に与え与えられるものである。 幸せを高める4つの能力 ①hope 自ら進む道を見つける力 ②エフィカシー 現実を受け止めて行動を起こす力 ③レジリエンス 困難に立ち向かう力 ④オプティミズム 前向きな物語を生み出す力
0投稿日: 2021.05.15
