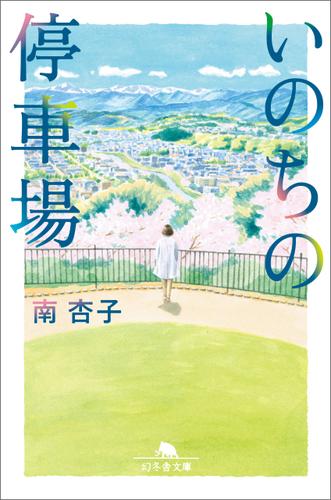
総合評価
(167件)| 66 | ||
| 70 | ||
| 17 | ||
| 2 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ生と死を、側でたくさん見つめてきた著者だからこそ、描ける物語だな、と思った。 張り詰めた高度救命救急の現場から、在宅医療へ。 生きるための治療を行う患者から、生活の中の医療、同時に、死と向き合う過程へ。 「人間には、誰もが自分の人生を自由に創ることが認められている。そうであれば、人生の最後の局面をどのように迎え、どのように死を創るかーーこれについても、同様であるはずだ。その正当性を、すべての人に理解してもらいたい」 生きる、ことに向き合える一冊。
1投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅看護のお話です。知らない事、知らない世界が沢山書かれていました。とても勉強になりました。映画化されているようなので、そちらもみたいと思います。
1投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ大きな救急センターを離れ、 故郷の在宅医療を担うことになった 佐和子 麻世や野呂、仙川先生といった 温かい周りの人 章ごとに違う患者が抱える 老老介護、ゴミ屋敷、先端医療、 小児癌といった現在の問題の中にある 生きる尊厳 最後の章は、実父の死ぬ尊厳 一貫して生きるってどういう状態なのか ということ… お父さんの 「自分で死ぬ力すら残っていない」 「痛みに終わりがあると決めることによって、死はむしろ生きる希望にすらなりうる」 自分や自分の親、家族がこうなった時 自分はどうすればいいのか 考えても想像つかない せめて自分にも他人にも寄り添える心を持とう
1投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
患者と家族の思いを引き出す佐和子医師達の仕事には温かみが感じられた。 そのサポートがあってこそ患者と家族は互いに歩み寄ることができたのだと思う。
0投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ初作家さん。全体的に心が温かくなるお話しばかりでとても満足です。 医療系といえば病院がメインにストーリーが展開されていきますが、在宅医療にスポットを当てた物語は初読みだったので現場での仕事を知ったり、読んでていろいろ考えさせられました。 第五章「人魚の願い」は辛かった…萌ちゃん自身も辛いがご両親のことを思うと…涙腺が崩壊してしまった… すごく気になる所で終わったのですがこれは続編があるのか??
34投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の死に向き合うって辛いしいやだし自分の大切な人が亡くなっちゃうことなんて考えたくもないことだったけど、死に向き合うこと、どう死にたいか一緒に考えること、その人の天寿を全うさせてあげることはすごくすごく尊いことだなって思った。 自分が死を迎えるのは年齢だけでみたらまだまだ先なはずだけど、そのときどう向き合うんだろう、でも少しだけ怖くなくなった気がする。
1投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログおそらく数ヶ月前にKindle unlimitedで借りた本。 なんとなく読もうと思って読んでみた。 なんだろうこの本は。 今の私にピッタリ過ぎてびっくりだ。 救急から地域の訪問医になった医師の話。 勝手が違い過ぎて困惑しながらも、目の前の患者や家族のために、奔走する。 胃ろう、中心静脈栄養、誤嚥性肺炎。 あらゆる手を尽くして、少しでも長く生きて欲しいと願う家族と、穏やかに最後を迎えたい患者。 その時々で感情が揺れ動く。 悩み、苦しみ、いろんな葛藤があり、最後には受け入れる。 私は今現在、入院している。 検査で誤嚥して、誤嚥性肺炎になったから。 今回の入院をきっかけに、車椅子生活から、完全な寝たきりになってしまった。 1年半前に、胃ろう造設をした。 去年の秋、ポートを入れた。 今回の入院では、中心静脈栄養がメインになっている。 これから、訪問医のお世話になろうとしている。 まだ、訪問医に会ったことはないけど、咲和子のような医師にめぐり逢えたらいいな。 自分のこれからの生活を、予行演習しているような気分になった。
1投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日経新聞のコラムが読みやすかったので、この方の作品を手に取りました。在宅介護の話ですが、いろんなタイプの患者と家族が描かれていて非常におもしろかった。あとで映画化されてることを知りました。医療の現場を知る人が作家さんなのは、ありがたいと思います。
0投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ古本屋にて、表紙が隠されている状態で購入。 普段なら絶対に手に取らないジャンルの本であったため、読むことができて良かったと思える作品だった。 医療とは対病気や怪我だけでなく、対人だということを認識でき、医療のあり方についても深く考えさせられた。
0投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ診察する側とされる側(看取られる側)との様々な触れ合いの中で、お互いで気づきがあり、化学反応があり、成長していく様はほんとに心地いいものでした。最後は非常に難しい問題なので、『もし同じ立場なら?』と深く考えさせられました。ほんといい本でした。
0投稿日: 2025.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療に携わる訪問診療の物語。 都内に住んでいるため、訪問医療というのはあまり耳にする機会がない。そう考えると交通の便が多く便利な点なのか。しかしながら亡くなってしまった祖母のことを思い出した。ベットの上から動けなくなってからはお医者さんがきていたのは記憶ある。 内容は個々の登場人物の心の動きが繊細に描写されており、その人その人が頭の中で想像でき動き出すくらいにはリアルに感じた。 その結果なのか、章毎に泣くということが起こった笑 在宅医療、人間の心など様々なことを考えさせられた。
17投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ訪問診療は自分にとって全く知らない世界だった。患者の家族が死を受け入れる体制を整え、患者自身が望む最期のあり方に最大限沿う仕事。医療行為はもちろんあるが、患者、家族双方の心に寄り添い、生活をサポートする訪問診療はものすごい仕事だなと今回初めて知りました。 特に小児がんの女の子のストーリーが素晴らしいです。死ぬ前に海を見たい、次は人魚に生まれ変われるよう、海にお願いしたいという少女の切実な願いと、それを叶えるために全力を尽くすまほろば診療所スタッフの想い。涙が止まりませんでした。
0投稿日: 2025.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的に好きな医療分野の作品。在宅医療に関わる医師、スタッフ、患者、家族の想い、葛藤が伝わってきます。南先生の作品は初めてですが、他も読まないと。萌ちゃんの健気さに号泣しました。
4投稿日: 2025.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
積極的安楽死や在宅での看取りの仕方、肉親の死を看取る… 考えさせられる内容でした。 特に並木さんの話では老々介護の話題を取り上げており、今後加速していく超高齢社会ではこの問題がより浮き彫りになると痛感しました。
0投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ異色の経歴の南杏子さん 女子大卒→編集者→お医者さん→作家 すごすぎる、人生1周目なのか? 作者に信頼感が産まれるのはプロローグの文章で現場の明瞭な表現から(早い) 終末医療、人生観、死生観 誰にでも共通して考えることを専門的かつ人間的に描かれていて、いろんな角度があって、、 私は萌ちゃんの話でめちゃくちゃ泣いちゃった こんなに自然と号泣するとは思ってなかった。素晴らしい作品だと思います
0投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
積極的安楽死を どう考えるか? って話。 患者本人ができるだけ安楽に最期を迎えられるのが一番だ〜って話。
0投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
在宅医療を通して、人がどう命を全うするか描かれていました。 在宅医療に関わる医師やスタッフ、人の気持ちに寄り添う優しさや熱い思いが伝わってきて、何度も心が震えて泣きました。 父と娘の関係、金沢の長閑な風景が描写されていて優しい気持ちになれました。 自分の命を大切に使えてるか、後悔のないよう生きれてるか考えさせられました。
0投稿日: 2025.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログエンド・オブ・ライフのような内容と思っていたら解説でもしっかり書かれていた。 医療費問題や尊厳死安楽死の話もあり、色々と考えさせられる内容だった。
14投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログその結末は「あなたはこの続きをどう考えますか?」と読者に問いかけてくる。 超高齢多死社会を迎えたこの国で、終末期医療のあり方についての議論を「これ以上先送りにするのは、よそうよ」という著者からのメッセージが込められているようにも感じる。 在宅医療の現場を舞台にした医療小説ではあるが、医療者や患者よりも「患者家族」の心情や揺らぎがよく描かれていると感じた。 施設名は架空のものですが、金沢市内に実在する川や橋、地名がたくさん出てくるので、土地勘のある人は実際の風景を想像しながら読むのも楽しいです。
0投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京の救命救急センターで働いていた、六十二歳の医師・咲和子は、故郷の金沢に戻り「まほろば診療所」で訪問診療医になる。命を送る現場は戸惑う事ばかりだが、老老介護、四肢麻痺のIT社長、小児癌の少女……様々な涙や喜びを通して在宅医療を学んでいく。一方、家庭では、脳卒中後疼痛に苦しむ父親から積極的安楽死を強く望まれ……。 終末期医療専門病院の内科医さんだから書ける内容だなぁと思った。 そして、こんなに個人に寄り添った医療を受けることが出来た患者さんは幸せだなと思う。 定期通院をしていていつも思うのは お医者さんの大半は検査の数値を見て薬を処方するだけの人やな…ってこと… その資格があるだけでも凄いことだとは思うけど そのお医者さんの力量ってあんまり感じない。 私の近所には専門医がいなくて 1番近いと思われるクリニックに通院している。診てもらえるだけ有難いと思っているけど 流れ作業的な感じは拭えない。 尊厳死や安楽死についての是非は難しいと思うし 私も咲和子の父親と同じ立場なら同じような気持ちになるかもしれないけど 自分が頼まれたら出来るのか?っていつも考えてしまう…とてもじゃないけど出来ないと思う。 お互いに医師免許を持っていて 苦しんでる身内がいたら また違う考えになるだろうか?
7投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ3人に1人が高齢者、2人に1人が癌患者という時代に、生きることと死に向き合うことをじっくり考えさせられた本だった。野呂くんの今後に期待したいし、周りの人達との関わりも含めて続編が楽しみだ。
0投稿日: 2024.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公が60代女性医師というのがなんというのか逆に新鮮で良かったです。 急性期からの在宅医療は同じ医療でも全然位置づけや役割が違うことがわかりやすく書かれていました。スピーディーに治すことから生命維持や病を持ちながらののQOLの維持、向上。 どの話も感動的で面白かったです。家の女の子の話も涙してしまいましたが、在宅医療は患者家族が密接に関わるところなので患者の想いだけでなく家族の想いも合わさると色々難しそうだと感じました。ただただちょっくら面会に行くだけの関わりではなくせいかつを共にする(主となり介護を担う)家族の巻き込み方も重要ポイントに感じました。 最後は主人公の親の積極的安楽死の話へいき一気に重たくなりますが、最後の一文には鳥肌が立ちました。
6投稿日: 2024.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本のおかげで、これまであまり考えることのなかった「在宅医療」について知ることができ、人間の最後つまりどう死ぬかということについて考えさせられた。 バリバリの救急医が故郷の金沢に戻って在宅医になるというお話。 街の風景が多々描かれていること、周囲の個性的かつ温かい人々、そして医療系…と少し前に読んだ『スピノザの診察室』を彷彿とさせる内容(『いのちの停車場』の方が出版は先)。 一つひとつのエピソードが出来すぎていて作り物感は否めないけど(現実はそう上手くいかないでしょと心の中で突っ込みつつ)、思わずぐっとくる場面もあった。 再生医療の江ノ原のエピソードだけはこれからっていうところで気になる終わり方…。 咲和子が医者としての自分、娘としての自分の間で揺れ動くところでは、医療に正解はないんだろうなと感じた。 終盤は咲和子の葛藤が痛いほど伝わってきて一気読みだった。
2投稿日: 2024.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログフォロワーさん達のレビューを拝読し、いつか読まねばと思っていた一冊。ようやく図書館の予約が回ってきた。 まず、表紙の絵を見て背筋を正す。高台から望む金沢の町と白山、青空に満開の桜。美しくも、儚さを予感させる。 テレビで在宅医療のドキュメンタリーは何度か見たことがあるが、家事をしながら中途半端に見たり、途中でチャンネルを変えてしまったりしていた。キチンと向き合ってこなかった言い訳だろう。 この本では、患者・家族・医師の描写が詳細に書かれており、ゆっくり丁寧に読んでみたのだが、序盤から何度か目頭を押さえてしまう場面もあった。 この本の特徴として、患者本人だけでなく、そばにいる家族や、疎遠になった家族にもフォーカスをあてていると感じた。特に、残される家族に対する「死を受け容れる授業」は印象的である。 人生で数多くは無い肉親との別れ。見送る側は「初心者」で当然。だからこそ、読者としても、この本から少しだけ疑似体験をして、来たる将来に愛する人を見送る時を意識して、日々の幸せを噛みしめることが出来る。家族が元気で居てくれるなら、多少のハードな経験は大したことがない。自分が辛い時はこの本を思い出そう。
29投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ医師としての、在宅医療のお話。 どうしても自分の経験と重ねてしまう。母を在宅で看取って、もう19年も経つんだなぁ。。そんなに前なのに、この本で言う最先端の在宅医療を受けていたことに気付く。最期を迎えるまでの変化も教えてもらい、母の最後の願いをスタッフ総出で叶えてもらった4日後の朝、眠るように旅立ったこと。ずっと思い出して当時のクリニックの皆さんに改めて感謝しながら読みました。 最後のシーンは衝撃的だった。積極的安楽死、あってもいいと思っていたけど、とても難しい。 ◇モンゴルの格言◇ 思って行けば実現する、ゆっくり行けば到着する ※佐和子が『苦しくてどうしようもないとき、マスターならどうする?』と聞いた時のマスターからのこたえ
5投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療の話。とてもハードウォーミングな内容。最後は娘と医師としての決断を迫られ、家族への愛、医師としての責任感を深く考えさせられる。
2投稿日: 2024.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ文中のモンゴルの格言。 苦しくてどうしようもない時どうするのか? 思って行けば実現する、ゆっくり行けば到着する。 小さな女の子の話しはずるい。 号泣してしまいました。 吉永さゆりさんをイメージしてしょうがありません。映画を見て観ます。
14投稿日: 2024.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログさまざまな死の向かいかた。 知っているようで知らなかった最期を丁寧な形で描いた作品でした。 在宅医療という切り口だからこそ見えた自分の知らない親しい人との別れかたは、大切な人との別れ、自分の最期の少し前にもう一度読みたいと思いました。
1投稿日: 2024.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログサイレンを掻き鳴らし 赤信号に突っ込んで、 ときに車線を逆走して、 一分一秒を争いながら 病院を目指す救急車。 必死に命をつなごうと する医療スタッフ。 そして救おうとしても 手からこぼれてく命─ 結局すべては諸行無常 なのかもしれません。 でも、そうやって達観 したところで、 心が満たされることは ありませんよね。 小児がんの少女が最期 に望んだのは海に行く ことでした。 酸素ボンベや点滴台を 取り付けた車椅子で、 大人達に守られながら 辿り着いた遠浅の海に、 もう体力のない小さな 体から歓声をあげます。 父親に抱かれ生まれて はじめて海に足をつけ、 とろける笑顔を見せて ・・・ そして数日後に天使に なった少女─ よくあるお涙頂戴的な 話なのかもしれません。 でも、そうやって斜に 構えてたら、 とんでもない落し物を してる気がします。 嗚咽しながらなんとか 読み終えました。 鏡を覗いたら目の周り が真っ赤でびっくり! 文句なしの星五つです。
140投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.4.23 咲和子の患者さんに対する一生懸命さと命との向き合い方、医師として、娘としての姿勢にぐっときました。 老老介護、四肢麻痺の社長、小児がんの少女、そして脳卒中後疼痛に苦しむ父親からの積極的安楽死の提案。 ・生命活動を終えようとするとき、胃腸の動きが止まっていくため食べなくなっていく。 ・セルフネグレクトとは、別名自己放任。介護医療サービスの利用を拒否するなどにより社会から孤立し、生活行為や心身の健康維持ができなくなっている状態。生活環境や栄養状態が悪化しているのにあ、改善の気力を失い、周囲に助けを求めない。ゴミ屋敷や孤立死の原因とも言われる。セルフネグレクト状態にある高齢者は、認知症のほか、精神疾患・障害、アルコール関連の問題を有すると思われるものも多い。 ・在宅医療とは、最後の日までいかにその人らしく生きるか、そうした毎日を支える存在になろうと、皆がそれぞれに考えている。 ・すべての患者と家族は、命を救うことを求め、咲和子はそれに応えて生かすことだけを考えて生きてきた。死なせる方法など、考えたことはなかった。
4投稿日: 2024.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が、NHK俳句のゲストで登場した際に内科医であり小説家であることを知りました。実体験をもとに、読者が「終末期医療」について考えるきっかけとなればとの思いで執筆されていることに共感し、父の病気のこともあって読んでみました。 病院医療と在宅医療とを対比させながら、主人公の苦悩と成長、医療現場の実態、病人と家族との関係性がいくつかのストーリーで描かれています。病気とどう向き合っていけばいいのか、最後をどう迎えたらいいのか、色々と考えさせられ著者の思惑通り、在宅医療、終末期医療の実態を垣間見ることができ、大変勉強になりました。映画もぜひ観てみたいです。
15投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ04月-03。3.5点。 東京の大学病院で救急センター長を務める、女医の主人公。トラブルの責任をとり、故郷金沢で友人の診療所を手伝う。在宅診療専門の診療所で、いろんな人間模様が。 面白い。ぐっとっくる話の連作短編。次作もあるので、期待。
0投稿日: 2024.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療を行うものとして読み進めさせていただきました。 どの場面もよく出会い、毎回悩んでいることばかりでした。 これだけ、個別化した関わり 出来たら良いなぁ。
1投稿日: 2024.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ南 杏子のいのちの停車場を読みました。 主人公の咲和子は都会の救急医療センターから、実家の金沢に戻り在宅医療を手伝うことになりました。 救急医療の経験を活かせば簡単にこなせると思ったのですが、実際携わってみると、その大変さに気づきました。 色々な人がいて、父親の介護も重なりやるせない思いが伝わってきます。 私の父親も96歳なので思いつまされることが多いです 切ない気持ちにもなってきます
12投稿日: 2024.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ死と言う概念を前向きに考えられる一冊でした。読了してから何日か経過しましたが「息子さんが見えましたよ」というシーンは非常に胸が熱くなったのを未だに思い出します。心に寄り添う温かさを感じて思わずホロリ。
3投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ都内大学病院救急センターで働く咲和子が地元金沢に戻り、在宅医療に携わる日々が描かれている。心温まる感動系。 延命治療をすることが必ずしも正解ではなく、場合によっては患者の意志を尊重したり、緩和ケアに移行することも大切だと感じた。在宅医療は病状だけではなく、患者を取り巻く生活環境や支える家族のケアまで多岐に渡ることを学んだ。 咲和子が父の最期を迎えるまでの心情、迎えた後に自分の使命を果たそうと決意する姿に感動。 父と咲和子のやり取りを読んで、積極的安楽死について考えさせられた。
3投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京の救急救命センターで働いていた62歳の医師の咲和子は故郷の金沢に戻り、「まほろぼ診療所」で訪問診療の仕事を始める。 末期がんで命の尽きつつある患者たちに寄り添う葛藤や医師としての限界、そして、医師もひとりの人間として悲しむことある。そんなことを感じた一冊でした。 子どもの死は特に感じるものがあるし、すべての在宅患者やその家族も死を受け入れている訳ではない。それでも生きている限りは、いつかは自分にも起こりえる現実として受け入れる必要があると思いました。 いつでも会えるから、いつまでも元気という訳ではないから、会いたい時にできるだけ、会えるようにしたいなと感じました。
2投稿日: 2023.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ死とは、温かいものなのだろうか ただ今ワタクシ21歳、本書の中の人物の死を通して自分の生死を考えるきっかけになりました。 . 救急救命センターで世代交代の時期を薄々感じながら働いていた白石先生は、ある時小さなミスを犯し、その責任を取るために辞職した。その後故郷にもどってひょんなことから昔の恩人と出会い、在宅医療を行っていく物語。 私は白石先生を追って金沢まで来た野呂くんに感情移入してしまい、、。なんて真っ直ぐで染まりやすく柔軟な子なのだろう。小児癌の子とのやりとりで思ったのは、在宅の患者さんにとっては、目の前にいる人が資格を持っているかではなく、いかに自分に寄り添ってくれるのかが大切なのだということ。 資格がないからこそ出来ること、気づけることも、もしかしたらあるのかもしれない。 看護師さんが手が冷たいと言われた時、次会う時にホッカイロで手を温めて患者さんに触れたりとか 患者さんからの「ありがとう」を待つのではなく、目の前にある問題に気づいて、それを改善していく。そういう、少しのことに気づけて行動に移せるプロでありたいと思った。 また、本書は「医者である私」と「父の前では娘である私」の心情の葛藤も描かれている。 頭では分かっているはずなのに、感情に揺さぶられて分からなくなってしまう。死とはそれほどまでに患者さんの周りの人の感情を大きく揺るがす出来事なのだ。本人と同じくらい御家族へのケアが欠かせないのは、そういうことなのだ。 残していく方と、残される方。 生きる時間が長くなるほど後者の立場が増えていく。 その葛藤に耐えながら、それでも生きていくのだ。 私も、最期は自宅で迎えたい。 それを叶えられるかどうかは、結局は家族の理解があるか否かなのだね 死とは怖くない、温かいものなんだね
0投稿日: 2023.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ合うよ。最初から読みやすくて自分でも不思議だけど、こんな事あるんだね、だんだんと作風に馴染んで行くけど、初めてなのに初めてじゃないみたいで、4日で読み終えたけど、どのタイミングでも行けるって事。吉永小百合さんの凄く見たかったけどコロナでねコロナ野郎のせいでね。とにかく開拓したよ、直ぐに南杏子さん行きます。人魚の萌の回が一番 泣けたかな、生まれ変わった萌ヘの手紙がグッとくる。先生死ぬの痛いの〜痛くないよ。
18投稿日: 2023.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ心にずしーんと来る話しだった。救急医療センターから、1日に3件を診る在宅医療へ転職。最後の終わり方、ちょっと辛かった。日本も尊厳死が認められる国になったらいいけど、本人じゃなくて家族の立場になると、感情じゃすまない所もあって。色々と考えされられた。
5投稿日: 2023.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ豪華キャストの映画化も気になって、手に取った一冊。同じ作者のディアペイシェントが面白かったけど、今回は自分にとってすこし期待外れだった。 何人かの患者さんを通じて、訪問診療の持つ、生活に寄り添う力みたいな感覚を、丁寧に描いている流れは温かくとても良かった。 ただ、いざ父親が入院すると、主人公は訪問診療を選ぶことにかなりの抵抗を持っているように感じ、訪問診療を選ぶこと=諦めること、という構図が主人公の奥底にはあるのかなと感じたのが、なんだか少し残念だった。 バー店主の、近すぎないけど、そこにいてくれる第三者の存在に救われました。
0投稿日: 2023.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療についてのストーリーで感動を受けた。また医療従事者の1人として心動かされるエピソードが多々あった。 映画の大ヒットニュースから知ったこちらの小説。映画の方もぜひ観てみたい。 また南杏子さんの小説を出逢って、これから読ませてもらいたい。
19投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京の救命救急センターで働いていた、六十二歳の医師・咲和子は、故郷の金沢に戻り「まほろば診療所」で訪問診療医になる。命を送る現場は戸惑う事ばかりだが、老老介護、四肢麻痺のIT社長、小児癌の少女……様々な涙や喜びを通して在宅医療を学んでいく。一方、家庭では、脳卒中後疼痛に苦しむ父親から積極的安楽死を強く望まれ……。 こんな在宅医の元で最後を過ごせたら・・・と思うけど、私も親も・・・誰もかも現実は病院のベットで独り逝くんだろうと思うと淋しい。
3投稿日: 2023.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療のあり方。 積極的安楽死の是非。 かなり深く考えさせられた。 物語として、都合良く展開する場面は多かったが、充分に楽しめた。
10投稿日: 2023.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「いのちの十字路」と読む順番が逆になってしまった この作品も6篇の短篇 「いのちの十字路」同様、それぞれの命の重さが心に染み込んでくる
0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
金沢が舞台ということで風景もイメージしやすく、親しみやすい内容で、文章に寄り道がなく、集中しやすいものだった。 重い話なので読み進めていくと気分が沈んでいくこともあったが、自分が死に対しての理解や覚悟がないことを痛感した。幸いにも両親も健在で、身近な人間の死に立ち合ったことがないが、そういう場面が訪れた時の心構えを学ぶことができた。 安楽死=尊厳死と勘違いしていたが、自分としては長期間痛みや苦しみが続くなら積極的安楽死を望むと思うので、筆者の考え?には賛成。 生かす為の治療をしてきた咲和子が、命を絶つ治療を決断して最後にとった行動には驚き!
2投稿日: 2023.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ大切な家族が治らない病で、耐え難い痛みに苦しんでるってなったら、早く楽にしてあげたいって思うけど、いざとなったら頑張って少しでも長く生きてて思ってしまうものなのかな。
11投稿日: 2023.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞での連載を先に読んでしまったが、ぜひ読みたいと思っていた作品。訪問医療のいろいろなケースがリアルに描かれている。
0投稿日: 2023.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ死というゴールが見えている患者を、在宅医療で支える医師の立場、見守る家族の立場でいろいろ考えさせられる。患者が高齢なのか若年なのかによってもこれまた全然違うが、悔いの残らない看取りとは何なのか。 以下抜粋 物を食べる生き物だけが生きる。食べる行為は、命を長らえる行為。それが自然の姿。 苦しくてどうしようもないときは、思って行けば実現する。ゆっくり行けば到着する。モンゴルの格言。
3投稿日: 2023.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと医療小説は好きなのだが、医師によって書かれた本書はとてもいい本だった。たくさんのこと、特に自宅での家族の看取りについて考えさせられた。 都心の緊急医として働いてきた佐和子は、部下の責任をとって辞職する。故郷の金沢に帰り、そこで在宅訪問医療に携わることになる。いろいろな患者がいるが、病状が重い人もいて、患者とその家族の苦しみに寄り添う医療を目指す。 数年前に書かれた本書では最先端の再生医療についても知ることができ、興味深かった。また、医師としての立場だけでなく、佐和子の父(元神経系医師)が病み、患者の家族としての心の揺れ動きが非常にリアルに描かれていた。何もしてあげられない焦り、親を亡くした人には少なからず共感できるところがあると思う。もし自分が死に瀕したら、看取ってくれる人がいるなら、そして周囲に迷惑でなければ、病院でなくて自宅で一生を終えたいと思った。 神経症の痛みの壮絶さも本書で初めて知った。医師だからこそ見込みがないことを知っており、「楽にさせてくれ」と哀願する父。読んでいるだけで苦しくなった。 南杏子さんの著作をもっと読んでみたいと思う。
3投稿日: 2023.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なかなか重たかったなあ…。 命をどう終えるか、どう看取るか、どう支えるか。いつかは直面するだろうこと。100歳が珍しくなくなっていくだろうこれから、積極的安楽死などもっと議論されなくてはならないんだと思います。 そりゃ、自分は咲和子の父のように「一思いに、スパッと」と望むけど、なかなか家族は割り切れないよなあ!尊厳死、とも言うけど、自分で自分の人生の幕引きを選びたいけど、自殺と何が違うの、と言われると難しい…。 「スケッチブックの道標」「人魚の願い」で涙。
1投稿日: 2023.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学病院の救命救急で副センター長だった主人公の女性。そこから、金沢の在宅医療を行う診療所での勤務を通して、様々な患者さんと時を共にし、在宅医療の在り方を考えながら診療していく。 最後の終わり方は、想像していなかった。 あれが最善だったと思うけど、別の選択肢もあったとも思う。。 闘病している本人と看取る家族の間に、治療方針の違いはあると思う。 看取る家族は、どんな形でも生きていてほしいと願うし、でも、本人は早く楽になりたいと願う。 人生の終わりをどのように迎えたいか、どこでどんな風に過ごしたいのか考える時、闘病中の場合は選択肢は多くはない。 在宅医療でも何かのきっかけで病状が好転することもあるし、逆に人生の終わりを見据えて在宅医療を選ぶこともある。 救命救急と在宅医療では、医者も看護師も取り組む姿勢や内容が違うのだということがとてもよく分かる内容であり、かつ、家族がもし家で人生を終わりたい場合の心構えみたいな事も教えてもらった気がする。 …自分が患者の場合はどうだろう。。 考えておく必要があるかもしれない。
9投稿日: 2023.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療、終末期医療がテーマ。 医師・患者本人・周りの人たち、それぞれの視点で命への向き合い方を描いている。 「生き方」と「死に方」。この本を読むと医療というのは、延命だけが目的ではないことがよく分かる。その人らしい生き方があるように「その人らしい死に方」もある。 苦しくても生きていてくれるだけでいいと願うのは、家族のエゴなのだろうか。尊厳を守るとは何か。分からない。考えても答えは出なかった。
11投稿日: 2023.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
お父さんの話は興味深かった。 正直な話在宅で看取りをする覚悟など わたしにはないと思う。 点滴、胃瘻、酸素マスク、それをつけて 延命できるのであれば1日でも長く生きて欲しいと わたしも必ず思ってしまうと思う。 でもお父さんの場合は起きている時間に 体が炎に焼かれるような痛みが走る。 布団が少しズレるだけで激痛が走る。 こんなのだと本人は死を選びたくなるよなと。 点滴、胃瘻、酸素マスクなどしなくていいから 早く痛みから解放してくれ(死なせてくれ) って気持ちになるんだろうなと思った。 いまの日本は積極的安楽死は認められてないけど このような人達には必要は処置だと思う。 治る見込みない中死ぬまで痛みと戦うなんて 地獄のようでしかないからわたしたちが 高齢者になる時までには積極的安楽死が 日本でも認められるといいなと思った。
1投稿日: 2023.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ死を扱っている部分話も何話かあるので、ズシッと重く心に刺さるし、涙が止まらなかった。でも、目が話せない。 病気を治す、命を助ける、だけが医者の仕事ではないことを思い知らされた本。在宅医療の大変さも知れたし、終末医療についても考えさせられた。そろそろ、両親も年老いて最後を考える年になり、病気だった場合の終末は延命か緩和か。とても考えさせられた。子としてはどんな形でも長く生きていてほしいと思う反面、両親が苦痛を味わうならば延命はエゴなのかな…とも思う。この本はそんなことを考えさせられた。どんな人にもおすすめできる本。ぜひ一度読んでほしい。
11投稿日: 2023.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ父が在宅介護だったので思い出しながら読みました。 人生の最期をどのように迎えるのか…何をしてあげるのか…
3投稿日: 2023.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日 naonaonao16gさんと、自分の父の最期を語ったばかりだったが、タイムリーにこの本を読んでいた。 たまたまフォロワーさんの評価が高かったので、Amazonでポチっておいた作品だった。 東京の救急センターで働いていた60代の女性医師は、自らの判断で大規模な交通事故の患者を引き受けられるだけ引き受けた。 その中で、医師免許が無い者までが必死になって救命の為尽力したのだが、その後それが問題となり、責任を取る形で退職。 実家のある金沢に帰郷し、診療所で在宅医として働き始める。 彼女を尊敬していた、医師免許の無かった彼が、自分の為に先生が病院を去ったことを知り、彼女を追ってくる。 ↓この先ネタバレ有りです。 在宅医の仕事は軌道に乗ってくるのだが、自分の父親が大腿骨を骨折。そこから入院となり、みるみる病状が悪くなっていく。 最期は痛みとの戦いとなる父親に、鎮痛剤を投与するよう求められる。 家族としては少しでも長く生きてほしい。 しかし当人は生きているということだけで、地獄のような痛みに耐え続けなければいけない。。。 家族の気持ちの葛藤などがリアルに描かれている作品だった。 以前読んだサイレントブレスと雰囲気が似ている作品だった。 助手の子や看護師さんなどの雰囲気が(^_^) 読みやすい作品で、1日で読了。
105投稿日: 2023.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療、終末期医療、積極的安楽死について考えさせられる物語。 胸に刺さる物語です。 映画にもなったということですので、映画も見てみたい。 東京の救命救急医療センターで働いていた62歳の医師の咲和子。重症患者の受け入れで現場の責任を取り辞職。故郷の金沢の「まほろば診療所」で訪問診療医となります。 なにがなんでも命を救うという救命救急医師から、在宅での終末医療の現場へ。 戸惑いながらも患者に向き合っていく咲和子。 6編の在宅医療の現場を通して、在宅終末医療について、これでもか、と説いてきます。そして、考えさせられます。 最終章では、積極的安楽死... 第一章は老々介護。まさに今、世の中でいたるところにある問題だと思います。 第二章は先端医療。在宅医療でそんなことできるの?って思ってしまいます。 第三章はゴミ屋敷の中での在宅医療。 第四章は高級官僚の在宅での看取り。家族の気持ちが心を熱くします。 第五章は小児がんに侵された6歳の女児とその家族。これはだめです。涙腺崩壊。現実を受け入れられない親の気持ち。一方で、自身の死を受け入れている娘。これは辛い。涙なくては読み進められない。 そして、第六章は咲和子の父親の積極的安楽死について。中山七里の「ドクターデスの遺産」を思い出しました。 特に第六章の積極的安楽死については、作者の気持ちも強くメッセージとして感じました。 映画みたい。 とってもお勧め
89投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ医療関係のことは難しいし、この本を読んでわかったこともあるけど、やっぱり私にはわからないことだらけ。 でも、人を助けるため、人を幸せにするために奮闘するこの人達を見て、医学って素晴らしいんだな、と思いました。 油断するとちょっと泣きそう^^;
3投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログKindleにて読了。 医師である佐和子は大学病院の救命救急センターから在宅医療へと真逆とも思われる転職をする。 この物語には…在宅の難しさ、老老介護の問題、終末期介護の問題と…盛りだくさんに描かれている。 素晴らしかった。 ぜひ映画も見てみたいです。
3投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすいし面白かった 在宅医療について色々知ることができた。 主人公で医者のさわこがいろんな患者の家に赴くんだけどその患者ごとにストーリーがあって何度もうるうるした 父の積極的安楽死についても感慨深く、読みやすいけど印象に残る内容だった 人は死ぬ8時間前くらいから下顎呼吸といわれる呼吸に切り替わり苦しそうに見えるけど、本人は苦しくない、その間は意識があるみたいなので声がけをするといいとかためになることが色々書いてあった
2投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ南杏子さんの本を読むのは二冊目。一冊目に読んだサイレントブレスと同じで終末期医療が題材。今回は特にメッセージが強く、ラストは積極的安楽死について読者そして社会に対して問いかけるような終わり方であった。あと将棋がすきな僕に個人的に刺さったのが文中に出てきた菊池寛の「人生は一局の棋なり、差し直す能わず。」って言う言葉でした。 医者としてこう言う本はもっと読むべきだと思った。あと川崎協同病院の安楽死事件の本も読んでみようと思った。映画化してるらしいから見よう。
1投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ介護している私はなんだかザワザワしながら不安を感じながら一気に読み上げた。 いのちの大切さ、在宅… 私には在宅介護をする自信がない。これは親不孝になるのかな… 最後はやっぱり家に帰りたい思いになるのかな。 一人暮らしが心配で施設をすすめようとしている私は親不孝なのかもしれない…と思った。
2投稿日: 2023.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰にでもいつかはかならずやってくる"死"について、自分や家族が終末期にどうしたいのか、何が出来るのか、ふだん考える事を避けてしまいがちなことについて考えるきっかけとなった。 考えてもなかなか答えは出ないし、そのときになって心が揺らぐだろうけどこんなふうに心に寄り添ってくれる医療従事者の方々がそばにいてくれたらいいと思った。
5投稿日: 2023.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログタブー視されてきた「いかに死ぬか」というテーマについて、在宅医療を通じて語っている。 身近な人がもう絶対に助からない状態で、痛みに苦しんで「死なせてほしい」と頼まれたとしたらどうするか…。 逆に自分の死期が近づいているとしたら、どう死にたいか。 深く考えさせられた。
1投稿日: 2022.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きているうちにずっと続く死への恐怖と悲痛が、終わりがあると、終わらせることができる選択肢があることによって、死は生きる希望になる。自分の人生の始めを創ることはできないけど、終わりを創ることはできる。
3投稿日: 2022.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を原作にした映画に「感涙」との謳い文句があり、まずは小説をと手に取りましたが、予想外に現代の医療問題をベースにした社会派小説でした。4章とラスト5章のギャップに驚きますが、5章はこれから一層注目される問題です。医療の仕事や医療問題に重きを置いて読む本です。
3投稿日: 2022.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分に近い人間がもし、楽な死に方を求めてきたら、、どうするだろうか 在宅医療、というここ最近ではよく目にする言葉 その現場で働いてる人たちの姿、思いを汲み取れるようなお話でした。 5章の女の子の話、思わず涙が出てきた、、
4投稿日: 2022.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ南杏子さんの本を読むのは3冊目。1冊目のサイレント・ブレスにいたく感動して、すぐに他の本も図書館で予約した。この「いのちの停車場」は、予約待ちの数がエグくて(映画化されるほど人気だったそう)、やっと先日来ました…。 安楽死、私もしたい…。 第四章に出てきた、元高級官僚の言葉。 生涯医療費のうち、終末期にかかる医療費は約半分。この医学的な処置に意味があるのか…。財政問題では常に頭を悩ませてきたが、私が国のために最後にできるのは、『無駄な延命治療で若い人の税金を使わないこと』だろうな。 いや…まじで。私がそういうことになったら、苦しみを長引かせるだけの延命治療にお金を使わずに、もっとハッピーなことに使って欲しい…と思う。
3投稿日: 2022.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ介護問題に関することを書いた本。 いつか自分も体験するかもしれない。仕事と親の介護のどちらを両立するか。終末医療に対してどういった考え方を持つのがいいか。尊厳死をどう考えるか。死にたいと思う人たちに対してどういう風にしたらいいのかこれはめちゃくちゃ難しい。そういったものを考えさせられる小説。
2投稿日: 2022.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療のお話。 主人公の咲和子は、救命救急の現場で命を救うこと、治すことに専念してきたベテラン医師。そんな彼女が在宅医療に従事することになり、全く異なる医療のあり方を模索していきます。在宅は多くが終末期の患者さんの看取りになるのですが、死に至るまでの患者やその家族の心の移り変わり、彼らに寄り添う医療者の姿が描かれており、心を揺さぶられました。積極的安楽死についても考えさせられました。 金沢に住んでたことがあるのですが、金沢の美しい情景も描かれていて懐かしかったです。
5投稿日: 2022.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ白石咲和子62歳。生え抜きの救急救命医の職を、自ら辞任するところから物語が始まります。 父が一人で暮らす故郷の小さな診療所で訪問診療を始めると同時に、別の〝闘い〟が始まります。これまでの病院勤務では見えなかった、「患者と家族の真実」が見えてくるのでした。 咲和子の、様々な状況下の患者と家族に真摯に寄り添う流儀と信条が患者の心に届き、その描写が読者の胸を打ちます。 父の病状悪化と並行して、各章ごとに様々な在宅看護事例・患者と関わることで、物語に変化と抑揚がもたらされ、内容にも深みが出ています。 大学病院勤務経験のある著者ならではの知識も散りばめられ、「レスパイト・ケア」(在宅介護家族の疲れ解消の取組)など、参考になることも多かったです。 物語の最後は、尊厳死とは別の(積極的)安楽死の是非、大きな課題を読者に投げかけているようです。将来、他人事ではないなと考えさせられました。
35投稿日: 2022.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ訪問診療訪問介護が多いこの時代にみんなが読んだ方がいい本だと思う。あと、金沢の良さがところどころ描かれていて嬉しい
1投稿日: 2022.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ患者のそばに家族がいる、このとこがこの物語においてとても大きいことのように感じました。 懸命に介護を行い、家族を支えるのだという強い覚悟を持つ家族。少しでも良くなって欲しいと回復を期待する家族。一方で親子間で確執のある家族。 長い時間を過ごしてきたその時間のなかにはその家族の生活史があり、医療者では医療を通じ、その生活の中へ入って関係性を築いていくのだなと感じました。
6投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ若い頃、海堂尊にはまった。野心的な外科医の世界。痛快なストーリーも純粋に楽しめたけど、どこか現実感のない、白い巨塔的な小説だった。 本作は在宅医療の話。在宅医療=終末医療のイメージだったが、それだけではない医療の姿があった。また、物語の舞台が自宅という事もあり、家族との関係性がリアルに描かれていて、身近に感じる話もあった。 年齢なのか、生死を考えることも増えた。しかもお盆を迎えるこの時期はなおさらだ。そして、80を超えた両親との別れも、そう遠くない将来に必ず来る。何をしても悔いはあると思うけど、少しでも楽しい思い出をつくっておきたい。
2投稿日: 2022.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東京の救急医から金沢の家庭医への転身。都落ち、凋落と捉えるも徐々に魅力を感じてゆく。過剰な小説、医療問題をありたけ詰め込んだという様相。再生医療の話は必要だろうか?父への積極的安楽死などテーマの大きさの割に結論が早い様にも感じる。論点も少なそう。医療小説の導入編には良いかもしれないが、僕にはここまでの初歩的な解説は不要。 大病院勤務の医師をやたら悪様に記すのも苦手。 金沢を片田舎の様に書くが果たしてそうだろうか。或いはもっと僻地では物語が成り立たないかもしれない。
0投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画化されている有名な小説。 大学病院勤務のキャリア女医が故郷の金沢に戻り在宅医療の医師になり終末期医療と向き合う話。 医療をマクロな視点とミクロな視点で見ることは今後の日本に欠かせないと思う。 医療の崩壊というマクロな問題を現場のスタッフというミクロに持ち込んでも解決しない。 人生100年時代と言われる現代。 長生きは必ずしも良いことばかりではないと気付かされる。 主人公が父を看取る場面では自分が娘だったら妻だったら,父本人だったらどうするだろうかと考えさせられた。 ましてその道のエキスパートである医師までもが自分ごとになると慌てふためくというから,正解がない問題であると改めて気付かされる。 前作もそうだったが診療所のスタッフのやりとりがほのぼのとしていて和む。 それにしても石川県金沢に嫁に行くのは大変そう‥。
2投稿日: 2022.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ安楽死という重いテーマながら読後感の良い作品でした。 誰もが辿る老いや死という道に希望を見いだします。
7投稿日: 2022.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療、終末医療について考えさせられる本でした。特に、第5章の小児がんの子どものお話は辛かったです。本来ならもっと生きられるはずの命が…と思いました。が、何年生きたとしても、死の瞬間は等しく訪れます。その時に、本人だけでなくそれを支える家族も納得できるよう、様々な選択肢を医療側が提供できる体制になってほしいと強く思いました。
5投稿日: 2022.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
病院で人が亡くなるのは都合がよいけど、一般の人がどんどん死というものから乖離してしまって、より死が恐怖の対象になってしまうから、死に向かう人が在宅で息を引き取るというのは合理的な気がすると思った。 映画を先に観たけど、やはり萌ちゃんの件は涙なしには読めなかった。 私は佐和子先生の選択は間違ってないし、出頭したとしても不起訴になると思う。 映画はラストなんだか煙に巻かれて終わったけど、原作はきっちり描かれていたので小説読んでよかった。
5投稿日: 2022.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ第五章の6才の娘が末期ガンで打つ手がない話。十分頑張った子供に、「もっと頑張れ、まだ頑張れ」とムチを打つ両親。親の無理解にイラッとするところだけど、子供が死んでしまう事を受け入れられない親の狼狽も痛いほど分かる。無条件で代わってあげたいのにそれは出来ない。 読み進めるのが辛かった。 第一章の魚屋の夫婦のシズが最後を迎える話。徳三郎が感じる、身内が亡くなろうとしている怖さと悲しさと寂しさ。その感情をコントロール出来ない様が手に取るように感じられた。 こういう事は経験を積むことは難しい。だからたくさん本を読む。そういう状況をシミュレーションする。それで疑似の経験を積む。そういう状況に耐えられるように。 それでも子供が絡むことは慣れることは出来ない。実際に体験した方々の悲痛は、はかり知ることが出来ない。
94投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい作品でした。 もっと生きたいのに生きることができない幼い子ども、苦しみに耐えるなら死んだほうがマシだという父。在宅医療が抱える様々な問題や、在宅医療だからこそ出来るケアに考えさせられる思いでした。 私は映画を観てから小説を読みました。 映画では理解できなかった部分も理解でき、『いのちの停車場』は本当に素晴らしい作品だと思います。
15投稿日: 2022.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
それなりに面白くはあったのだけど、お父さんの安楽死の話なくても良かったような・・・・。全ての患者さんのその後を書く必要は無かったのかもしれないけど、IT社長はどうなったんだろうなぁ。。。と。
2投稿日: 2022.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第一話 スケッチブックの道標 #死を学ぶ授業 ①睡眠時間の増加 ②せん妄(夢と現実を行き来する) ③危篤状態(下顎呼吸になる) 第二話 フォワードの挑戦 #先端医療 #再生医療 #治療効果(コストパーベネフィット) 第三話 ゴミ屋敷のオアシス #セルフ・ネグレクト #もらい湯 第四話 プラレールの日々 #レスパイトケア #帰巣本能 #人生は一局の将棋なり 指し直すに能わず #明日できることはきょうするな 第五話 人魚の願い #千里浜なぎさドライブウェイ #癌の子でごめんね #両親は子どもの希望より1日でも長く生きて欲しくなるものなのか 第六話 父の決心 #神経因性疼痛 #脳梗塞の後遺症 #思って行けば実現する、ゆっくり行けば到着する #積極的安楽死 #この痛みに終わりがあると決めることによって、死はむしろ生きる希望にすらなりうる
5投稿日: 2022.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療、終末期医療を題材とした作品。 お話はフィクションだけど、超高齢化社会が進むこの国で既に問題視されている無視出来ないテーマだ。 誰にでも訪れる死。 その最期をどう迎えるか、また看取る側はどう向き合うか、問われる。 答えは簡単には出せない。。
4投稿日: 2022.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療を通じて、死を見つめながら、生きるとは何かを考えさせられる。金沢の情緒漂う風景や、主人公の颯爽とした仕事ぶりも楽しい。
5投稿日: 2022.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログおそらく医療者ではなくても、簡単に読み進められるような書き方だと思います。 まだ想像するしか出来ない両親の最期は、やはり主人公と同じく、苦痛がないようにしてあげたいなと思いました。
4投稿日: 2022.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ実録っぽい作風で物語性は低いのだが、終末医療がテーマなだけに状況を想像しただけで泣いてしまう。 我ながら年取ったなぁ…こういうのに弱いなぁ。
1投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰もが迎える最後を小説として読める。 在宅医療の難しさは医療だけではなく本人と家族の気持ちにも向き合わないといけない事、互いの気持ちを理解し合う難しさに現実の厳しさを知る。 最後に医師がとる行動に救われる人は沢山いるのではないかと思う。ただそれは医師の立場をかけての行為になってしまうのだけれど。
15投稿日: 2022.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療そしてもちろん現在の日本では許されていない医療行為ではあるけれど『積極的安楽死』問題を考えさせられる1冊。
7投稿日: 2022.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ年40兆円の医療費、その半分は終末医療に使われている もう全員が病院で最期を迎える予算はない 自分や家族がどんな最期を迎えることになるのだろう、ということ重ねて考えさせられた もう死ぬことが近いことがわかっている、治療法がない、そんな時どうやって過ごすのか ただの骨折をきっかけに、肺炎を起こして弱っていくとか、癌だとある時を境に急に悪くなっていく描写だとか、救急病院とは対照的にじわじわ死んでいく描写がリアルだった 在宅医療という分野をよく知らなかったが、患者だけでなく介護者の家族との関係づくりや説得が大変そうだと思った
1投稿日: 2022.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
すきま時間でゆっくり読み進めました。 読み進めやすく、非常にわかりやすい文章でした。 決して わかりやすさ=話の軽さ ではなく"実家のこと""診療所のこと""訪問先患者のこと"という形で場面ごとの意図がはっきりしていることがそう感じた理由だったのかなと。 医療用語への解説も適切な量でした。 普段から複雑な文章を読み慣れている人には物足りなく感じるかもしれないですが、人におすすめしやすい医療小説だと思います。
2投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
病院系は悲しく、切なくなることが多いので あまり手に取らないジャンルでしたが こちらの本と出会えて 良かったなぁと思っています。 作中、医療用語が所々に出てきますが きちんと説明があるので読みやすく勉強になる事がたくさんあります。 スケッチブックの道標は本当に、本当に勉強になりました(笑) プロローグから話の展開がはやく 心つかまれあっという間に読み終えてしまいました。 切なくなる場面もありましたが どのお話も最終的には人の温かさに 触れたような心温まる話だったと思います。 咲和子と父のやり取りでは、何歳になっても 親子は親子…医師という立場はあっても 親子という繋がりを超えていくのは難しいことがわかった気がします。
13投稿日: 2022.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
救命救急で働いていた主人公が、故郷金沢に戻り、訪問介護を経て、医療を見つめ直すというストーリー。 全体としては面白かったけど、患者一人一人の結末をもう少し詳しく書いて欲しかったかなぁ。 萌ちゃんの話の回も、どこかで聞いたような、ありがち感が拭えない。
4投稿日: 2022.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とてもいい作品。 でも、実際の心情を考えるととても難しい。 生きている限り誰もが経験すること、と頭ではわかっているのだが。 6編あり、 老老介護、先端医療、自己放任、緩和ケア、小児ガン、積極的安楽死をテーマに、家族の「受容」や在宅医療チームの「かかわり方」が書かれている。 自分に置き換えると、いつの時点・瞬間から、世話・介護から「死の受け入れ」へと切り替えるのか、難しい。 それを助けてくれているのが、医師や看護師なので、頭が下がる思い。 読み終えて、 「自分も逃げてばかりいられないな」 と感じた。 著者・南杏子さんにも、この本をレビューされていたフォロワーさんにもお礼が言いたい。 ありがとうございます。
16投稿日: 2022.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
60を超えてもなお大学病院の救命救急センターで働く女医が、ふとしたミスで故郷金沢に帰り、在宅医療で働くことになる。自宅で逝くこと、看取ること。一方で生き生き暮らす人。他人事でない近い未来自分に起きることだし、考えさせられる。小児がん患者の子の話はとにかく泣けた。それだけでなく、最後はお父さんの死にも向き合わなくてはならず、元気なお父さんが...と、ショックな思い。でも最期の最後に娘を思ったお父さんに泣ける。そして結末は世に問題提起して終わる。
5投稿日: 2022.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅での終末期医療… とても考えさせられるテーマです。 その人らしい生き方があり その人らしい死に方がある
11投稿日: 2022.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ訪問看護でいろいろな人の人生の終末を見ていく主人公が自分の父親の終わりにどのような決断をするかがとても真に迫っている。 自然と涙が出てきました。
2投稿日: 2022.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙が止まりませんでした……! いろんな視点から「死」を見れる作品でした。 楽しくて笑ったり、切なくて泣いたりと、自分の感情揺さぶられまくって心にじーんと染み入る素敵なお話でした。
4投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役医師による医療小説。 密度が違う。 自分や家族に重ね合わせながら 読みました。 折に触れて、何度も読み返したい作品です。
5投稿日: 2022.02.10
