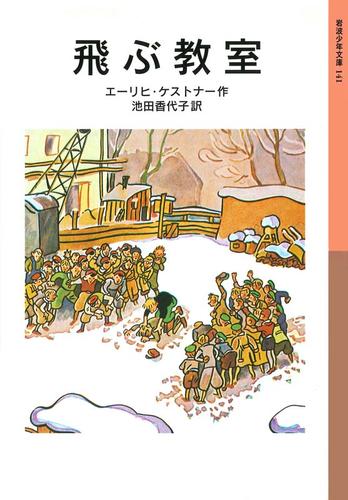
総合評価
(116件)| 50 | ||
| 27 | ||
| 21 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログナチスドイツ時代に描かれた小説。筆者の理想を描くとともに時代への警鐘を鳴らした作品。 平和を乱すことがなされたなら、それをしたものだけでなく、止めなかった者にも責任がある。 世界の歴史には、賢くない人々が勇気を持ち、賢い人々が臆病だった時代がいくらでもあった。これは正しいことではなかった。
0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
明るく飄々としたまえがきから、どんな話が始まるんだろうとわくわく。 ギムナジウムというドイツの寄宿学校での、クリスマス休暇までの出来事。 序盤は登場人物に苦戦しましたが(マルティンとマティアス!)生徒も先生もキャラクターがハッキリしているのですぐに区別できるようになりました。 大人手前の子供たちによるドタバタ、遠い家族への想い、臆病な自分を変えようともがく姿や尊敬できる大人の存在など、思春期ならではの感覚も追体験した感じ。 ケストナーの文体の明るさと当時のドイツの状況が重なって、なんとも言えない気持ちになります。
7投稿日: 2025.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ名取佐和子さんの『図書室のはこぶね』を読んで、こちらの本が登場していたところから気になり読了! 児童書だった(^_^*) 小学4・5向きなのね。 多感な少年たちの仲間愛と葛藤のお話。 読んでいて、最初、東京リベンジャーズをイメージしてしまった。 人質を救うために、仲間を集め救出したり。ちょっと、小学生に読ませるには、過激な暴力もありましたが。 寄宿舎にいる先生も子供の気持ちをよく理解できる大人で、自分の子供の頃の辛い出来事を、絶対に今の子達にはさせないという思いが伝わり感動した。 それぞれ、寄宿舎にいる子達の生活環境にも辛さ感じた。お金がなく、クリスマスの日に自分の家に帰れず過ごす子。 クリスマスに家族と過ごせない。 寄宿舎の先生は優しく寄り添ってくれる。 読み手も心温まる内容が満載でした。 あとがきも読んで、飛ぶ教室の意味も書かれており、納得! 勝手に、主役の子達の将来がビックになっていたらなぁとを想像して楽しみ読めました^_^
13投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ大人になって読んでも充分に楽しめるし、先生側の立場で考えると、自分もこんな大人でいたいなあという場面がたくさん。 冬のドイツの情景や、クリスマスの雰囲気にわくわくしつつも、色んな境遇にいる子供たちが描かれていて、奥の深い話だった。結末まで素敵だったな〜。 決して模範的ないい子ちゃんばかりではないけど、個性豊かな子どもたちが可愛らしい。
0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログケストナー作品を初めて読んだ。 ギムナジウムを舞台にした少年たちの楽しい日々…的な作品かな?くらいに思って読み始めたら、あまりの素晴らしさに号泣しながら読み終えた…。 まえがきから作者の愛と信念が痛いほど伝わってくる。それぞれにいろんな事情を抱えた少年たちの優しさ、強さ、気高さとそしてなによりも厚い友情。大人である先生たちの大きな愛。 なにもかも本当に本当に素晴らしかった!!!
1投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでに読んだいろいろな本に引用されていたので気になっていた本。子どもの頃に出会っていたらきっとずっと大人になるまで心の支えになって寄り添っていてくれる本になっただろうなぁと思う。 岩波少年文庫の本は名作と言われるものばかり何となく敬遠していたので、大人になった今からでも少しずつ読みたい。 今回は図書館本だったので手元に置きたいな
8投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『図書室のはこぶね』がケストナーの『飛ぶ教室』をオマージュしていたので、再読。 ケストナーはやはり素晴らしいね。 ユーモアと勇気、そして思いやり。 永遠の青春小説。 訳者のあとがきもよかった。
1投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
悲しんでいる子どもたちに、気づいてくれるおとながいて、本当によかった。クリスマス時期にまた読み返したい。
1投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔どっかでオススメされたのか、読みたいに追加されていたらしい。けど今回springを読んでいたら七瀬とハルちゃんがバレエを作るのに悩んだ題目のうちの一つとのことで参考文献として読んでみる。 児童小説とのことで今まで読んだことなかった。
0投稿日: 2025.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログクリスマスの物語ということで、この時期まで取って置いた、タイトルだけは若い頃から知る本書を読み、改めてケストナーはいつだって子どもたちの味方だということを、強く実感することができ、それは彼に対する紛れもない信頼度の高さを裏付けるには、充分過ぎる程のものを私に残してくれた。 その根拠の一つに、普段は飄々とした感のある「まえがき」から、既に熱いケストナー節を感じられたことがあり、それは大人も子どもの頃を経て大人になっているはずなのに、時に子どもだからといった見做し方をしてしまう、そんな大人に対する嘆きは言い換えれば、大人と子どもの間に境界線など存在しない平等性なのだと思い、それは本編の登場人物にケストナーが語らせた、『子どものころのことを忘れないでほしい』というメッセージにもよく表れていて、ケストナーの児童書が子どもだけではなく大人が読んでもハッとさせられるのは、そうした忘れかけたものを思い出させてくれるからだと、私は思う。 また、それを裏付けるものとして、『子どもの涙はおとなの涙よりちいさいなんてことはない』や、『生きることのきびしさは、お金をかせぐようになると始まるのではない』があり、子どもだって何も考えず、ただ日々を楽しく生きているわけではないし、寧ろ、大人以上に繊細で脆い部分も併せ持った複雑な一面もあることを、ケストナーは本書の主要キャラクターである五人の少年たちに投影させているのである。 例えば、将来はプロボクサー志望の、喧嘩なら誰にも負けない自信のあるマティアスでも、涙を堪えきれないときがあるということ。 例えば、普段は真っ直ぐな性格のウーリが、時に理解を超えるような行動に出ることだってあるということ。 例えば、頭の切れる皮肉屋で、どこか他人を見下したような態度を見せるゼバスティアーンにだって、内心は異なる気持ちを持つことだってあるということ。 例えば、母親に出て行かれた父親に厄介払いされたジョニーにだって、知識欲や将来の夢があるということ。 例えば、成績が最も良く正義漢も強くて頼りになる、非の打ち所の無さそうなマルティンであっても、決してそうではないということ。 といったように、子どもというのは、時にどうしようもなくなる瞬間が訪れるときもあって、そんな時に寄り添える人が、もしいてくれればという願いを物語の中で具現化しているのは、単なるケストナーの優しさだけではなく、それがそのまま彼自身が過去に体験した学校での辛い思い出とも重なっているからであり、そうした納得できない過去に対して何とかしたいと人一倍思う、彼の願いがそれだけに留まらないのは、本書を執筆した時代とも大きく関係しているからだと思う。 その1933年という年が、訳者の池田香代子さんのあとがきによると、ドイツがナチス政権の手に落ちた年であることを知ることで、ケストナーがまえがきに書いた、『勇気ある人びとがかしこく、かしこい人びとが勇気をもつようになってはじめて、人類も進歩したなと実感されるのだろう』という言葉が腑に落ちるようでありながら、おそらくそう思った根拠は、『平和を乱すことがなされたら、それをした者だけではなく、止めなかった者にも責任はある』に表れているようで、そこにはまさに当時の現場で体験した、ケストナー自身の率直でやるせない悲しみや怒りが色濃く滲み出ていながらも、実際に彼の本が燃やされた出来事を物語に反映させていることには、彼のユーモラスで強かな反骨精神が表れているようで、私は心から尊敬の念を覚える。 そして、その最たるものとして、おそらく他の作品のレビューでも書いたのかもしれないが、そうしたナチス政権化の時代に執筆したとは到底思えない、子どもたちにささやかな幸せを運んでくれるような牧歌的で明るい雰囲気が、彼の作品中には始終漂っていることがあり、この人は作家という仕事に、どこまでも忠実で正直で、そして堂々と絶望的な時代に立ち向かっていたのだということが、ありありと目に浮かぶようで、それは本編でも、自然と私の頬を涙が伝い落ちていく場面を何度も見せてくれたように、子どもたちの心からの叫びを伴った痛みに比べれば、彼のそれなんてと思わせる程の、彼自身の人の良さが何よりも物語っていながら、そうした純粋な気持ちというのは、たとえどれだけ時を隔てようが確実に物語から伝わってくるからこそ、こうして私も何とかして、彼の作品の素晴らしさを伝えたくなるのである。
76投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログケストナーの書いた少年たちのいきいきとした様子が目に浮かんで、彼らの喜怒哀楽が全て詰まってて最高だった! 正義さんと禁煙さんという大人も凄くいい。 ヨーロッパの人にとってクリスマスって凄く特別のものなんだな〜。 幸せな気持ちになれた。
5投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ舞台はクリスマス間近の男子寄宿学校。わんぱくで個性ある少年達が、様々な出来事に直面しながら友情を交わしていく。その目一杯、懸命な日々が眩しく、切なく、愛しい物語。 子どもも大人も変わらず、本気で悩み、怒り、悲しみ、思いやり、喜び、感動し、そうして成長していくのだ。
0投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ主に、子どもたちとかつて子どもだった大人たちの、ある年のクリスマスまでの数日間の話。少年たちだって、それぞれ悩みや悲しみを抱えていて、それを仲間達には見せないように強がってたりするんだよなぁと思う。仲間との絆とか、大人よりよっぽど強いんじゃないかとすら思うよ。あと、理解ある大人が近くにいる大切さも痛感するな。 私は子どもの頃にこの本を知らないでいたのだけど、大人になってから読むのでも響く言葉は色々あった。 ナチス政権下の時代に書かれた作品と聞くと、作家の非常に強い意思を感じたりもした。
2投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしいの一言。ケストナーの他の作品も読み返す。ハンブルク、ベルリン、のワードにキュンとする。映画も観てみたい。夏休みに岩波少年文庫を読むのっていいな。当時の気持ちに戻りつつ、視点はどちらかと言えば、先生方の方が近いっていう感じ。全く新しい物語を読んでいるような気がした。
2投稿日: 2024.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんな方のオススメで出てくるし、雑誌の名前にもなってることから一度は読まねばと思い購入。 ファンタジーと思って読んだら違った。寄宿学校の中で少年達が自分の持つ問題や傷と共に大きく成長していく話。 仲間や先生との雑だけど愛があるそんな関わり方を現代で経験出来るだろうか、夢物語ではないのか、でも確かにあったし今もあるのだと思う。本当は無いものだと諦めてはいけないようにも思う。 こういう事を知ることができるのがまさに児童文学であると思った。
0投稿日: 2024.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなつかしーね。小学校の時好きでよく読んでた。お父さんに買ってもらった。これで読書感想文書けって。感想文は上手く書けなかったけど。青春って感じ。クリスマスっていいよな。
0投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ独特の言い回しがちょっとくどい気がしてたんだけど、 話はいいねー 「平和を乱すことがなされたら、それをした者だけでなく 止めなかった者のも責任はある」 ちょうど、ナチスが政権をとった年に書かれたんだとか。 時代を超えて伝えたいメッセージがあるから、いつまでも読まれる古典なんだろう。
0投稿日: 2024.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
恥ずかしながらこの本を全く知らずにおりました。せめて思春期に読んでいたら…と思いましたが、いやいや、あの頃の私では読了すらしなかったのではとも思います。それくらい入り口はよく分からないまま読み進めました。 しかし本文。 心に沁みる名言の数々と魅力的な登場人物。 とりわけ正義さんことベク先生の人柄たるや。説教臭くないのも素晴らしい。 生徒達もイタズラや喧嘩をすれど、その後にちゃんと反省する機会があり、さらにそこに素直さがあるところが非常に好ましくとても気持ち良く読み終えました。 そしてあとがき。 ナチス政権を背景に言論の自由を押さえつけられながらも書き上げたとの説明に、思い返す名言が一層深く沁みました。 今読めて良かったと尚感じます。
1投稿日: 2024.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
冒頭はケストナーのエッセイ、そして少年たちの物語へ。 ギムナジウム5年生の少年たちがクリスマスを迎えるまでの物語…というと萩尾望都的美少年が出てきそうだが、1933年に出版された本作はまったくそんな内容ではない。背景にナチス政権の暗い世相を感じさせつつ、物語は少年たちの争い、友情、見栄、大人(先生)との関係を描く。 私は女で、子供も娘しかいない。もし私に息子がいたら、この話はもっと自分に近寄せて読めたのかもしれない。それでも読後感は心がほんわか温かくなった。いい話だった。 最後に、もしかしたら「私」の母親は、ジョニーの船長の姉かもしれない、と思ったのだがどうだろう。
1投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログわー、子どもの頃に読めばよかった! でも男子の学園物語だから、女子的にはいまいちだったかな? とりあえず面白かった、少年たちの友情や、喧嘩や、よくわからん意地の張り合い、周りの大人たちの温かな目線。昔のお話だからテンポは速くないけど、その方が心地よいよねー
0投稿日: 2024.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1760407091808977083?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2024.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の中高男子校時代を思い出しながら読みました。 この物語に出てくる生徒たちはお互いの性格とか境遇とかをなんとなく理解し合いながら学生生活を送っている。その一方で自分の中高時代は、仲の良い親友とか仲間とかはいたけど、ここまでお互いを思いやる関係だったかというと、そこまでではなかった気がする。その違いはなんだろうと思った。笑いのツボが合うとか、趣味が合うとか、一緒にいるとなんだか楽しいとか、そういうことが仲間となる要素だったように思うけど、その友が何を頑張っていて何に悩んでいるかとかは気にしたことがなかった。ちょっとしたこととか特に理由がない「なんとなく」で仲間の関係が出来たり解消されたりする程度の弱い連帯で、この物語の彼らのように相手の幸せを思うほどの絆は少なくとも当時は意識していなかったように思う。部活でも大学受験でも一緒に頑張って当時はかけがえのない仲間だと思っていたけど、過ぎてしまえばさっぱり会わなくなる関係がほとんどだ。それって自分の時代だからなのかなとか、日本はそうなのかなとか、はたまた自分だけなのかな、とか思った。必ずしも自分の中高時代が不毛だったとは思わないけど、もう少し相手の目線を持って学生生活を送っていたら違った人生もあったかもしれないなと思う。 それと、池田香代子さんという訳者、どこかで聞いたことのある名前だなと思ったら、新訳版「夜と霧」と同じ訳者さんだった。どなたの翻訳かを意識してみるのも面白いかもと思った。
1投稿日: 2024.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツのクリスマスの話 五人の子どもたちの仲間を思いやる気持ち、家族への思い、大人への思い たくさんの思いがこの本にぎっしりつまっています どの時期も大切ですが、思春期を迎えはじめる時期というのは、かけがえのない時期です 周りの大人がどう導いていけるのか 子どもは何を学んでいくのか 大切なことが、厳しくも優しい言葉で書かれています この本を読むときは、書かれた時代を思い浮かべながら読むことをお勧めします
0投稿日: 2023.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ勇気とかしこさについての物語 寄宿学校で生活する個性豊かな少年たちのクリスマスのお話。悲しみを抱えながら一生懸命生きている少年たちや、彼らに寄り添う素敵な大人たちに出会えます。先生は「正義さん(ベク先生)」が好きで好きでたまりません。作家ケストナーの熱の込もった珠玉の言葉の数々も心の奥底を響かせます。何度読んでも味わい深い、先生の大好きな本です。 「人生、なにを悲しむかではなく、どれくらい深く悲しむかが重要なのだ。誓ってもいいが、子どもの涙はおとなの涙よりちいさいなんてことはない。」 ーーーーーーーーーーーーーーー 友達を救出するために「無断外出」した少年たちに正義さんが話をする場面、ウーリが名誉のために飛び降りる場面、正義さんと禁煙さんが再会をする場面、きっぷ代がなくクリスマスに帰省できないマルティンに正義さんが手を差し伸べる場面、そしてマルティンが家の呼び鈴を鳴らし両親に会う場面など、いくつもの大好きな場面がある。 登場人物もみんな魅力的。粗暴に見えて、ウーリをいつも気にかけているマッツは優しい心根をもっているし、正義先生の話を聞いて心を打たれたかっこつけテーオドールなんか、物語の序盤は憎いやつだったのに、後半はすごく可愛く思えた。不幸な境遇にいるはずのジョニーが「心配するな。ぼくはすごくしあわせってわけじゃない。そんなこと言ったらうそになる。でも、すごくふしあわせってわけでもないんだ」と言って、マルティンを安心させられるのはすごい。尊敬する。家に帰ったマルティンが両親に真っ先に言った言葉「帰りのきっぷ代ももってるよ」には、じーんとした。 大人も最高。正義さんみたいに信頼できる大人になりたいと思うし、禁煙さんみたいに「正義さんには言いづらいけど、禁煙さんには言える」と思われるような大人にもなりたい。司書としては、禁煙さん的な存在を目指したい。最近は、そんなふうに、先生に言えない話や相談をしてくる子もちらほら現れるようになってくれて、少し緊張するがうれしい。 ケストナーの心のこもったメッセージもたくさん入っていて、少し教訓的で苦手な人もいるかもだけど、自分は好き。この物語の大きな魅力だと思う。ケストナーは、「子どもたちに届けたいメッセージ」をストレートに伝えてくれる大人で、それを楽しい物語の中に散りばめることができる稀有な存在だ。ナチスの時代に書かれたという背景を知って、その思いがさらに強まった。本当にすごい。 大学生のときに初めて読んで以来何度も読んでいるが、そのたびに心が揺さぶられる。クリスマスのたびに読みたいと思える作品。
1投稿日: 2023.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログなんでもっと早く読んでいなかったのだろう。 登場人物が素晴らしい。熱くてあたたかい。 人は誰かのために生きることに喜びをもつ生き物だったから進化してきた。と思い出した。最後は涙が溢れた。本を閉じて拍手をしたい気持ちだった。
1投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツの青春小説 クリスマス時期のドイツの寄宿学校の話。 少年期やその時代に想いを持つ人の気持ちを味わえて、名作と言われるのも納得。 ナチス政権時代に書かれたということに驚くとともに、作家魂に感動する。
1投稿日: 2023.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の読み始めはよく分からなかったけど、素敵な大人がいっぱい出てきて、世の中捨てたもんじゃないなと、読後感がとにかく幸福だった✨ あとがきを読むと、一種の作者の理想、憧れではあるみたいだけど。。また時を置いて読み直すと感想が変わるかも。やっぱり岩波少年文庫は良い。
2投稿日: 2023.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ毎年クリスマスの時期になると読みたくなります! 子どもだろうが大人だろうが、抱える悩みや苦しみに小さいも大きいもない。というケストナーさんの考え方に読み返す度心が暖かくなります。 生活を送る中で直面する様々な問題に、自分で考えたり周りと議論したり、皆で協力して乗り越えたり時には大人の力を借りたり…沢山頭を悩ませたりしながらも健全に成長していく様子が読んでいてとても眩しく素敵で思わず笑顔になる場面が多かったです。 メインの5人も他の登場人物達も、きっとこれからも逞しく生きていくんだろうな。
2投稿日: 2022.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章が好き ◯ 作品全体の雰囲気が好き ◯ 内容結末に納得がいった ◯ また読みたい その他 図書館の「クリスマス」の本のスペースにおいてありました。 何冊も並ぶ薄い本の中に、このハードカバーの『飛ぶ教室』だけがやけに分厚くて、ほうっておけず、ついつい手に取ることに。 男の子の親という立場から、日々奮闘するこどもたちを応援したくなります。 ともだち同士や先生に対しては大人ぶる男の子たちが、両親を前にするとすっかりこどもにもどるあたりが、しんみりします。 息子も、こういう「世界」にいるのかしら。 よみつがれる名作ってやっぱりいい。
1投稿日: 2022.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ不朽の名作 小学生の冬休みの読書感想文で読んで以来、ずっと心に残ってる作品。 ナチス政権下で出版を禁じられても子供達のために小説を書き続けたケストナー。 子供達にどんなメッセージを伝えたくてこの物語を書いたのか、 大人になってあらためて買って読んでみると、胸に込み上げてくるものがある。 誰か映画化してください。 (ケストナーの) クリスマスが近づくとまた今年も読みたくなる。
6投稿日: 2022.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログかしこさと勇気を両立して育んでいくことは、難しい。結局のところ、大人になる前に、どれだけたくさん大人たちに迷惑をかけて、それに真摯に付き合ってくれる大人たちと出会えるか。 お互いが、迷惑をかける/かけられる存在であることを認め合えることが、成長には大切なのだろう。
2投稿日: 2022.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生が人間であるという事、生徒も人間であるという事。この時代にこういう先生や生徒が沢山いたとは思えませんが、だからこそ物語にして理想郷ともいえる世界観を作り出したことに意義があるのかなと。今は先生も生徒も人間である以前にルールを順守する事を厳重に求められる組織人としての素養を求められます。なので分かりやすいドロップアウト風味は今は流行らない。でもいじめやパワハラは形を変えて水面下へ。そのような世界に生きているとこの生き生きした物語が、胸にしみますね。
7投稿日: 2022.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ大戦以前の幸福なドイツの一教室が舞台の児童文学。 子どもたちはジムナジウムという宿舎付き学校に友人たちと一緒に暮らしながら学んでいる。 幼い彼らの生活の中にも様々な事件が起こる。 それは小さな出来事であったり、他校との小競り合いだったりするのだが、それらの日々を通して子供たちは逞しく成長していく。 そして話の最後は幸せなクリスマスを迎えて終わる。 戦前のドイツと言えば、ナチス台頭や戦争の足音が近づくなど暗いイメージが多いのであるが、この本は子供たちの健全な成長がほほえましく読めて良かった。 特に出てくる大人が魅力的で、ベク先生と禁煙さんの子供への向き合い方、掛ける言葉を見ていると、果たして自分はこのような大人になり得ているのかと自問したくなる。 良い本でした。
2投稿日: 2022.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供が図書館から借りてきていたのを、そう言えば『飛ぶ教室』は未読だったなと思って手に取る。児童書のオールタイムベストに数えられる作品で、こういう良質な青春群像小説が「児童書」扱いされて(ベク先生や禁煙さんのような)大人の手に届かないことがあるとすれば、まったく残念なことだ。ふと、「ここはグリーンウッド」を読み返したくなるなど。
3投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生の頃、実家に置いてあった。あの頃にこの本を手に取ったが、魅力をあまり感じること無く、20~30ページ読んで、退屈になり諦めた記憶がある。単なるやんちゃな男の子達の学校生活を描いたものとしか受け止めていなかった。 今回はしっかり読んで、ようやくこの本の魅力を堪能することができた。 確かに冒頭は場面が変わり、状況がつかめず、どこから教室が飛ぶのか、予想できなかった。他学校とのトラブルにケリをつけていくあたりから、「そうか、これは教室が飛ぶ話ではなくて、ギムナジウムに通う少年たちの成長の物語なのか」と、遅ればせながら理解した。ページを重ねて海外文学特有の訳文に慣れてきたこともあり、読むスピードが上がった。 表裏が無くて純粋な少年たち(5人組)が、体を張った無謀なチャレンジを繰り返しながら大人になっていく過程を思い出した。主人公マルティンの両親や、ギムナジウムの友人、先生達など、決して物質的に豊かではないが愛にあふれている環境だと思う。私自身も、酸っぱい、そして恥ずかしい思い出のある中高時代の学校行事を思い出した。終盤、先生からの次の言葉が印象的だった。「若い時の思い出を忘れてはいけない」とのこと。かっこ悪くても泥臭く全力で過ごした少年時代の思い出は、大人になった今を精一杯明るく生きるためのエネルギーになる。 本書が出版された当時のドイツは、第一次大戦の敗戦後の混乱からナチスの政権掌握、そして第二次大戦へと向かう、歴史上最も過酷な時代であった。その中で「平和で明るい未来」を次世代の児童達に訴えた、90年前の筆者の「勇気」に思いを馳せてみると、ボケーっと無難に生きていて良いのかと考えさせられる。例えば、マルティンの描いた「10年後の家族の絵」に関する描写があるが、この絵の発想は称賛すべきものだと思う。大人たちが政治的判断を誤っている一方で、これだけ聡明な10代前半の少年が沢山いることを、筆者は訴えたかったのかも知れない。まさにこの本は「90年前から飛んできた教室」なんだと思う。
20投稿日: 2022.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生くらいで読んだときにはあまりピンとこなかったが、大人になってから読むと本当に沁みる… 皆それぞれにプライドがあり、情があり、それを見守る大人たちも元は同じ少年たちだったということ…
2投稿日: 2022.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に登場する先生に自分も教えてもらいたいと思いました。 自分に自信をもって生きていくことの大切さに気付かされました。 また子どもがときに不幸になることを忘れずに生きていきたいと思いました。
2投稿日: 2022.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログSL 2022.1.14-2022.1.16 読後のあとがきで時代背景を知るとまたズンと胸に響く。 これも子ども向けながら大人こそ読んでほしい児童書の良書。
1投稿日: 2022.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに海外文学読んだ。好きなんだけど、名前と人物像がどうにも一致しなくて何度も何度も読み返しちゃう~笑 でも海外の学校の寄宿舎生活とかクリスマス時期の日常とか、子どもらしくわかりやすく描かれてたから、気分を味わうのに最適☆
1投稿日: 2021.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初はあんまり面白くないかなーと思ったけど、読み終わってみたらすごくいい話だった。 この物語を読み終えたあとは人に優しくなれる気がする。 毎年クリスマスに読み返したい。
1投稿日: 2021.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツの作家ケストナーの代表作です。寄宿学校に通う生徒たちの楽しげな日常や心の葛藤が描かれています。ケストナーは、子どもには大人に勝るとも劣らないような悲しみや涙があると言います。大人になった今だからこそ読み返す価値のある本だと思います。
1投稿日: 2021.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ大まかに説明すると、 「同じ寄宿舎に住む5人の仲良し少年達。彼らの学校では様々な事件が起こる。それを通して成長していく少年達の姿を描いた作品。」 というところです。 児童文学ですが、大人が読んでもかなり楽しめる作品です。むしろ、大人の方が作品の魅力を堪能できるんじゃないかなぁ・・・と思ってます。 少年達の考えと行動には 「くすっ」っとなる微笑ましいものがありましたし、「えっ!」っと驚かされるようなこともありました。 「親が子供から目を離せない感覚」に近いです。それがこの作品にはありました。
1投稿日: 2021.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ名作として有名な本だが、子どもの頃、途中で読むのを断念した本書。大人になって再度読んでみた。子どもの頃、なぜ、途中で読むのをやめたのか、改めて納得した。今は、もっとワクワクさせ、楽しい本は、他にもいっぱいあるからでしょうね。
1投稿日: 2021.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ3度目の読了です。ブクログには記録がなかったので、改めて記します。 3度目ですが、読み終えて、胸がいっぱいです。 健全で、まっとうで。いい人しかいなくて。 2度目の時は、訳者の池田香代子さんの後書きがすごくいいな、と思ったのですが、今回は?と思いました。文学を色々な文脈で解釈することは自由ですが、矮小化だけはしたくないとおもいました。
1投稿日: 2021.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログさまざまな子どもたちが、学校や学校の外でいろんなことを学び、成長していく作品. 中でも「禁煙さん」と呼ばれる登場人物の言葉は飾り気がなく、大人の素直な思いを伝えているので面白い. 作品の中で作者と直接語りあうような描写が、さらに物語を深めてくれている. 「ただ、誤魔化さないで欲しい.そして誤魔化されないで欲しい.不運はしっかり目を開いて見つめることを学んで欲しい.うまくいかないことがあってもオタオタしないで欲しい.しくじっても、しゅんとならないで欲しい. 出だしさえ凌げれば、もう勝負は半分こっちのものだ.なせなら、一発お見舞いされても落ち着いてさえいられれば、あの二つの性質、つまり勇気と賢さを発揮できるからだ. 賢さを伴わない勇気は、乱暴でしかないし、勇気を伴わない賢さは屁のようなものなんだよ.世界の歴史には賢くない人々が勇気を持ち、賢い人々が臆病な時代が幾らもあった.これは正しいことではなかった・ 勇気ある人々が賢く、賢い人々が勇気を持って初めて人類も進歩したなと実感するのだろう.」 またこの作品には子どもたち向けだけでなく、教員自身に向けたメッセージも書かれている. 「教師ってものにはな、変化する能力を維持するすごく重い義務と責任があるんだ.さもなきゃ、生徒は朝はベドに寝転がってて、授業はレコードにやらせればいいってことになるんじゃないのかな.違うよ、僕らに必要なのは、教師っていいう人間だ.歩く缶詰じゃないんだ.僕らを成長させたいんなら、自分も成長しないではいられない教師が必要なんだよ.」 これは、2021年の今でなお大事にされていることである. 今問題となっているいじめ問題にも触れられており、「平和を乱されることがなされたら、止めなかったものにも責任はある.」 大人にとっても子供にとっても大切なことは何かを真っ直ぐに伝えてくれる作品.
1投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログまず“飛ぶ教室”という題名と、挿し絵に魅かれた。 はじめのうちは文章がスッと入ってこなかった。地名や登場人物がなかなか一致しなかったが、段々とキャラクターの特徴がつかめてきてから一気に面白くなった。 登場人物1人1人の気持ちが眩しい。子どもの頃に感じたこと、空気、匂いを忘れかけていることに気づいた。 この本に出会えて良かった。
1投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと早く読めばよかった。でも読めてよかった。ドイツのギムナジウム(寄宿舎のある9年制の男子校)を舞台にした少年たちの物語。主人公は5人。彼らは高等科一年、日本で言えば中学2年生くらいか。貧しい家庭だが首席で絵も上手いマルチン、親に捨てられた孤児のヨーニー、ボクサー志望のマチアス、貴族の家の子ウリー、利口なゼバスチアンと個性的な仲間だ。彼らを見守る正義先生と禁煙先生。子ども向けに書かれているけれど、素敵な大人たちの言葉は読む人の心を打つ。 「おこなわれたいっさいの不当なことにたいして、それをおかしたもの罪があるばかりでなく、それをとめなかったものにも罪がある。」 正義先生に憧れる生徒たちの素直さ、友だちの哀しみを理解する繊細さなどとあわせて、大人になってから読んだからこそわかるところも感涙もので、何度でも読み返したくなる物語。そして、まえがきとあとがきをぜひ読んでほしい。 私も子牛のエドアルトに優しくつついてもらいたいなぁ。 1962年の高橋健二訳で読了したが、新訳も読んでみたい。名前の読みが今風とか。
2投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年読んだ本の中で、最も感銘を受けたかもしれない。 ケストナーが前書きで書いているように、大人になるとどうしても子ども時代の記憶を美化して、子どもたちみんなが楽しく過ごしているに違いないという幻想を抱いてしまいがちになる。 ケストナーは、子どもと大人との間にことさら境界線を引かず、同じ人間として描いているように感じる。 また、『エーミールと探偵たち』もそうだったが、親子の深い愛情を、よく表現しているなぁと感じた。マルティンと両親とが会話をする場面や、マルティンが自らの感情を必死で抑えようとする場面など、本当に豊かに表現していると思った。 前書きや本文中で、意味ありげな表現が用いられているのは、訳者あとがきで書かれている通り、おそらく偶然ではないだろう。戦中のドイツで、自らの作品が焚書の対象となってしまったケストナーが、なんとか子どもたちにメッセージを残そう、勇気を与えようという気持ちを必死で表現しているのがわかる。そして、それは現代に生きる人々にも当時と同じ温度感で伝わるような内容になっている。特に前書きに込められたケストナーの情熱は、読んでいて胸が震えるようだった。 以下に、特に気に入った本文中の表現を記載しておく。 「世界の歴史には、賢くない人々が勇気を持ち、賢い人々が臆病だった時代がいくらもあった。これは正しいことではなかった」 「どうしておとなは自分の子どものころをすっかり忘れてしまい、子どもたちにはときには悲しいことやみじめなことだってあるということを、ある日とつぜん、まったく理解できなくなってしまうのだろう」 「教師ってものにはな、変化する能力を維持するすごく重い義務と責任があるんだ」 「平和を乱すことがなされたら、それをした者だけでなく、止めなかった者にも責任はある。」 「世間にはぼくみたいな生き方の人間がすくなすぎるんだよ。ぼくが願っているのは、なにがたいせつかということに思いをめぐらす時間をもつ人間が、もっと増えるといいということだ。」 「わたしたちは年をとった。でも、若さは失っていない。」
2投稿日: 2021.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ少年たちの変化や成長を通して、作者が子どもたちへのメッセージを、説教くさくならず伝えてくれるお話。まえがきにキーワードが書いてあって、物語でそれを説明してくれる感じ。 いちばん心に留めておきたいと思ったのは、実業学校とのケンカでの台詞。「ぼくらは、約束を破るようなやつらとは、これからはぜったい戦わない。軽蔑するだけだ」 むやみやたらにケンカしていたわけじゃないんだ、と少し驚いた。その発想はなかったというか、まっとうな人間でなければ戦う価値もないということなんだな、と。
1投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログクリスマス間近の寄宿学校が舞台の5人の少年たちの物語。それぞれが抱える思いが交差する笑いあり涙ありのお話です。
1投稿日: 2020.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ児童文学でありながら大人こそ読むべき本。 学校の先生や近所に住む大人、寄宿舎に子どもを預ける親の気持ちが切実に伝わってくる。 そして彼らがとても魅力的に見える。
1投稿日: 2020.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ生い立ちも性格もちがう生徒が暮らすようすは学校と重なる。みんなめざすところは違うから、劣等感や傲慢な気持ちをもつことなく、自分なりの目標に向かってすすむ前向きさをもってほしい
1投稿日: 2020.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいる間 小学校の図書室にいる気持ちでいた 海外の寄宿学校の生活 ユーモアの散りばめられたお洒落な会話 そして 人物はみな思慮深く 愛情にあふれ 時に自分の感情に支配されながら 前に進む 憧れの気持ちを創造力で膨らませて チャイムがなるまで夢中でページをめくった 子どもの頃の心を豊かにしてくれたお話に 大人になってから再会する これもステキな体験だ
1投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館にて。 ずっと昔、子供の頃に母にお薦めの本として教えてもらっていた本。 その頃はなんだか読む気がしなくて未読、すうじゅうねんたった今になってやっと読めた。 素晴らしかった。 教師だった母の原点だったのかもしれない。 子供の頃読んでいたら、堅物と思っていた母の見方が変わったかも。 もう一冊、お薦めの「点子ちゃんとアントン」も早速読むとしよう。
2投稿日: 2020.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログNHKのげんちゃんの現代国語を聞いて読むに至った。 なぜ今までケストナーを避けてきたんだろう。ってくらい、子供の成長の一瞬が眩しい。傍観者も悪事を働く人と同罪的な訓話も改めてそうだよなと。 理想の先生がここにはいるから、教職目指す人には読んで欲しい。
2投稿日: 2020.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログNHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」をよく聴いています。 そんなご縁から来年還暦になるオヤジが岩波少年文庫(小学校4.5年以上)を手にしました。 この小説に子供時代に出会うことのできた少年少女たちは、それだけで宝箱にしまっておくプレゼントをひとつ手にできたのではないか、子供の頃外遊び専門で読書体験の少なかった私にとっては、そんなふうに羨ましくも思える素敵な物語りでした。 ギムナジウムで寄宿生活を送る少年たちの物語り。 それぞれの家庭の事情や充たされぬ悩みや将来への希望など色々な重荷を未熟な肩に背負いながらも、友情を育みつつ知恵と勇気で葛藤を乗り越えて成長していく少年たちの姿と、彼らを厳しくも温かく見守る大人たちの眼差し。こんな眼差しの大人に見守られる子供たちは本当に幸せだと思うし、個性豊かで見どころのある子供たちに信頼され、その成長を見守ることのできる大人は子供より何倍も幸せかも知れない。 私はこんな眼差しの大人になれただろうか。 ちょっと切なくて、とっても幸せな気持ちになれる物語りです。
4投稿日: 2020.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログだいぶ前に読み終わったのを思い出しながら描くのでいろいろおぼろげなのですが、子どもながらの世界でもいろいろあって奮闘する少年たちの姿には勇気を分けてもらえた気がする。そしてその少年たちを見守る大人の姿がとてもかっこよくて見習いたく、距離感がとてもよかった。人生で大切なことがこの本に書かれてると感じた。生きていく上で辛い時や行き詰まった時はこの本を読みたいなぁと思いました。
1投稿日: 2020.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本が売り切れだったので、久々にKindleで読んでみた。(この緊急事態宣言で本を勧めるコーナーがラジオで多くなったが、偶然にも違う方がそれぞれに一押ししていたので読んでみた。高橋源一郎さんなんか自分のラジオ番組のタイトルにしてしまっている) サクッと読めていったのだけど、後半近くなって、クリスマスに親元に帰れないマルチンの姿が、自分の小さい時の記憶と同じだったのでひどく感動していたら、それは私の経験の記憶ではなく、過去にこの本を読んだ記憶がすり替わって自分が経験したものと思い込んでいたのだ。自分はキリスト教徒ではないし、学校の寮にも入っていなかった。 ということは遠い昔に読んでいて、自分がひどく、感じ入ったことが自分の記憶に置き換わっていたのだろう。(本当に失礼なヤツだ。
3投稿日: 2020.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族との関係は様々だけど、同じギムナジウムの子供たちは固い友情で結ばれている。やがて大人になれば、禁煙さんと正義さんのような人になるのでしょうか。 登場する子供たち皆が幸せに、そして素敵な大人になっていくと良いですね。
1投稿日: 2020.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログケストナーがこの本を書いたのは、1933年。ドイツはナチス政権となり、ケストナーは、好ましくない作家のため この本も含めナチスに燃やされた可能性がある。世相を感じるためか。所々に強いメッセージを感じる言葉が出て来る。平和を乱すことが為されたならそれをした者だけで無く止めなかった者にも責任はある。 世界の歴史にはかしこくない人びとが勇気を持ち、かしこい人びとが臆病だった時代がいくらもあった。これは正しいことでは無かった。 作品は、少年期の挫折感不安感を描きながらも暗くて沈んだものだけにはなっていない。メルヘンではなくシリアスな物語に共感が持てる。
2投稿日: 2020.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログヒトラ-が政権を握った1933年に出版された【エ-リッヒ・ケストナ-】の本書は、ギムナジウムに学ぶ児童や生徒たちと担当教師たちとの交流をとおして、人間の良心を高らかに謳いあげた感動の児童文学です。親元から離れて寄宿舎生活を送る子ども達が多い中で、二親に見放され育てられた子供、親の仕送り不足ためクリスマス休暇に帰省できずにいる子供、そんな彼らを見守る教師は、懐に深く包み込むのでした。子ども達は先生の深い愛情に目覚め、人との繋がりの大切さを学んでいくのでした。ナチス・ドイツの悪夢から生き永らえた人間賛歌です。
2投稿日: 2020.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
久々に児童書を読んで、語り口などの工夫も楽しく、目新しく読めた。 海外の話ということもあり、外国の名前などが覚えにくいのがちょっと読みづらかったが、読んでいくうちにそれぞれの個性がわかってきた。日本人向けには、適度な注釈や予備知識があった方が読みやすそう。 大人になって読んだからだと思うが、先生ふたりの友情がいいなあと思った。幼き頃、一時心を通わせた友人への哀愁がぐっとわいてきて、感慨深かった。 寮生活など、ハリーポッターみたい、と思ったが、解説を読んで著者がドイツに生きた人であることを知り、また違う文化圏なのだなあと思う。 勇気がテーマということだが、そのような背景を知らなければ、いろいろに読める物語だと感じた。 解説では、壊れゆくドイツを見ながら、それでもここで生きていくと決めた著者の果敢さに鳥肌が立つ思いがした。 誰もが素朴に思っている不安や恐怖を克服すること、それが戦争を止めるための有益な一歩なのだろうと思う。のびのびと若者が自由を謳歌でき、かつ、若くない人も若い心を持ち続けられるような社会が願われる。
1投稿日: 2019.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ大人になってからの再読。色褪せない力と優しさを感じる物語。少年達皆が愛おしい。 次の世代の人にも読んで欲しい名著。
1投稿日: 2019.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分がかって子供であったことを忘れないように… 『おこなわれた一切の不当なことに対して、それをおかしたものに罪があるばかりでなく、それを止めなかったものにも罪があります。』 この言葉は幼い日にも、そして年経た今も…心に深く刺さる言葉です。
1投稿日: 2019.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログじつは読んだことがなかったケストナー。 こういう児童文学はやっぱり子供のときに読んでおくべきでしたね! クリスマスの話なので12月になるのを待って読みました。 あこがれの寄宿舎生活! 彼らの合言葉「あったりまえ!」がうらやましい。 「ギムナジウム」ってだけでときめいてしまうのは『トーマの心臓』や『11月のギムナジウム』の幻想だと思う。 実際には辛いことももちろんあるはずで、ケストナーは子供時代は楽しくて幸せなことばかりじゃなくて悲しいことやみじめなこともあるんだとまえがきで訴えつつ、楽しい学園生活を描き、少年時代を忘れるなと禁煙さんに言わせている。辛い人生を救うのは幸せな記憶なのだ。 優等生のマルティンやまっすぐなマティアスよりも自分の非を認められるゼバスティアーンやかっこつけテーオドールに惹かれます。 「ただ、ごまかさないでほしい、そして、ごまかされないでほしいのだ。不運はしっかり目をひらいて見つめることを、学んでほしい。うまくいかないことがあっても、おたおたしないでほしい。しくじっても、しゅんとならないでほしい。へこたれないでくれ! くじけない心をもってくれ!」 「ボクシングで言えば、ガードをかたくしなければならない。そして、パンチはもちこたえるものだってことを学ばなければならない。さもないと、人生がくらわす最初の一撃で、グロッキーになってしまう。人生ときたら、まったくいやになるほどでっかいグローブをはめているからね!」 「かしこさをともわない勇気は乱暴でしかないし、勇気をともわないかしこさは屁のようなものなんだよ! 世界の歴史には、かしこくない人びとが勇気をもち、かしこい人びとが臆病だった時代がいくらもあった。これは正しいことではなかった。」 「平和を乱すことがなされたら、それをした者だけでなく、止めなかった者にも責任はある」 「ねえ、ぼくに勇気があるかなんて、考えたことがある? ぼくが不安がってるなんて、気がついたことがある? ここだけの話、ぼくはすごく気がちいさいんだ。でも、ぼくは要領がいいんでね、気づかれないようにしてるんだ。自分がいくじなしだってことは、そんなに気にしてない。いくじなしだってことを、恥ずかしいとも思ってない。それもやっぱり、ぼくが要領がいいからだ。欠点や弱みは、だれにだってあると思うよ。問題は、それをごまかすかどうかってことだ」 「ぼくが願っているのは、なにがたいせつかということに思いをめぐらす時間をもつ人間が、もっとふえるといいということだ。金も地位も名声も、しょせん子どもじみたことだ。おもちゃだ。それ以上じゃない。ほんもののおとななら、そんなことは意に介さないはずだ」
1投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
少年時代の友情や半目、誇りと自己嫌悪、など、そういう揺れ動く気持ちがまるで自分の身の回りで起こってることのように、感じられます。国も時代も違うけど、いつの時代も子供たちが通る道なんだな、と愛おしいような気持ちになる。そういう心を持ったまま大人になったような正義さんと禁煙さんの再開と友情は、ある種のファンタジーなんだけど、物語の中でくらい、そういうことがあっていいよね、と思う。 というのは、大筋の解説でしかなくて、本当は、出てくるエピソード一つ一つが面白いので、ただただ登場人物の仲間になったつもりで楽しむのがよいと思う。というのを登場する子供たちに聞かせたら、「そんなのあったりまえ!」って言うかな?
1投稿日: 2017.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったー!クリスマス前の寄宿学校での日々。どの子たちも可愛くて、ぎゅってしたくなる。小学生くらいに読んだらもっと楽しめたかも。
1投稿日: 2017.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どものころにも読みましたし、その後も繰り返し読む大好きな本です。マルチンもヨナタンも正義先生も、登場する人々それぞれが好きです。少々内容的には古いかもしれませんが、内面の輝くような精神は時代が変わっても変わらないと思います。
1投稿日: 2017.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
有名どころ、クリスマスで季節ものなので、購入して読んだ。 ヨーハン・ジギスムント・ギムナジウムのおはなし。 寄宿生五年生のマッツ、マルティン、ウーリ、ジョニー、ゼバスティアーンは、クリスマス集会で『飛ぶ教室』という劇をする。 作文を燃やされたくだり、違和感はあったけれど、ナチスの焚書と関係してるのか……全然気づかなかった。 実業学校生との抗争あり、先生との信頼関係あり、それぞれの悩みあり……。 悩みは、すぐに解決するものじゃない。 なんとか抱えているものなのかも。 子どもは天真爛漫で、いつもきらきらしている、と思いがちだった。 キリスト教徒ではないので、クリスマスがどれほどのものなのかは分からないけれど、最後はよかったなぁと思った。 このおはなし自体が『飛ぶ教室』かな?
1投稿日: 2016.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログあいつにもこいつにも素敵なことが起こるよ、だってクリスマスだからね!という文化を持たない私を置いてきぼりにしない優しくてセンチメンタルで勇敢なギムナジウム小説。 物語全体の構成も大変にエンターテインメントで小説数冊分のわくわくが贅沢に詰め込まれている。うーんケストナーってすごい。 話自体も身につまされ、なぜか懐かしい気持ちにもなるから不思議。どれも体験したことがないどころか見たことも聞いたことも無いようなその親近感にぞっとさえした。 本編始まっての十数ページは登場人物がばんばん出てくるしいちいち名前長いしなんだったら名前似通ってるし大分面食らったけど、始まってみれば主要登場人物は両手で収まる程度なので最初の、十数ページだけ!頑張って読んで欲しい。まあ児童書を読む年齢の少年少女たちは頭も柔らかく困ることなどないのかも知れないけど。
2投稿日: 2016.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ主な5人の登場人物をのみこむまで時間がかかった。 ヨナタンだったり、ジョニーだったり、呼び方も変わるので。 中盤から、俄然、おもしろくなる。 マルティンにも素敵なクリスマスプレゼントがあって、本当に良かった。 エピローグもよかったし、もう一度初めから読んでしまった。
1投稿日: 2016.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこれが、かの名作トーマの心臓のベースとなった作品…とふんふんしながら手に取りました。 家族と友情がテーマです。 寄宿学校で暮らすこどもたち。 クリスマスに、帰る場所がある子とない子。 なんだかこどもって尊いなあ。こどもはみんな宝物。
1投稿日: 2016.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ池田香代子訳で再読。 禁煙さんと正義さんは今の自分と同年代。経た。 こうなったら映画も観なきゃ!
1投稿日: 2015.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ大昔に読んだ本を池田香代子さんの訳で再読。 「世界の歴史には、かしこくない人びとが勇気を持ち、かしこい人が臆病だった時代がいくらもあった。これは正しいことではなかった。」 ケストナーは過去のこととして書いているが、目の前で起こっていることへの必死の警告と心の底からの怒りや悲しみが込められている。(あとがきより) 「平和を乱すことがなされたら、それをしたものだけでなく止めなかった者にも責任はある」と諭すクロイツカム先生の言葉は現政権を目の当たりにして強く心に響く。 「なにがたいせつかということに思いをめぐらす時間を持つ人間がもっとふえるといい」本当にその通りだ。
1投稿日: 2015.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツ寄宿学校での、クリスマスの季節の物語。 ケストナーから勇気ある強い言葉のプレゼントをもらった気がした。 「平和を乱すことがなされたら、それをした者だけでなく、止めなかった者にも責任はある」 書かれたのは1933年。ドイツがナチス政権の手に落ちた年。すでに言論の自由が奪われつつあったまさにその時に書いたということにただ驚き、ケストナーがどうしても伝えたかった強いメッセージが物語に込められている。
1投稿日: 2015.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツの本が読みたくなり図書館で手に取った一冊。 小学5年生から高校3年生までが寄宿舎で一緒に過ごす学校の、中学2年生の5人の友情物語。 物語の最初の1/3は、第2次世界大戦前のドイツの時代背景や、寄宿舎の様子がよくわからず、時間がかかってしまったが、その後、登場人物がつながり、ある事件が起きてからはあっという間に読み進むことができた。 子供はこうあるべき、大人はこうあるべき、ということがとてもわかりやすく語られているので、気持ちよく読めた。
2投稿日: 2015.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ実は今更すぎる初読。子ども心に何となくピンとこなかったのですよこのタイトルが。しかし良いお話でした。ギムナジウムに通う少年たちにとっては、生きるすべての場所が教室なんだな、と思いながら読んだ。
2投稿日: 2015.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書のまえがきを読むと著者の人生と正義に関する読者への痛切なメッセージがあり、何かただならないものを感じる人も少なくないと思います。 それはこの本が書かれた時代を反映しています。 それは、著者の母国ドイツでナチスが台頭し、世界中が人類史上最悪の戦争に向かっていた時代です。 著者はナチスに迫害されながらもドイツに留まり続け、次世代を担う子供たちの為に、メッセージを送り続けていたのです。 元気の良い男子寄宿学生たちが繰り広げる物語。 読み終わって感じたのは、懐かしさでした。 昔の子供達ってこんな感じだったよなとしみじみ感じました。 様々な背景を持った少年たちが一緒に喜んだり悲しんだり、時にケンカもあったりで、ちっともじっとしていない。 生命力にあふれた少年たちの物語は、クリスマス集会での「飛ぶ教室」という題の劇の上演に向けて集束してゆく。 彼らは、様々な経験をし、また人生の師とも呼べるような大人たちとの出会い等を通して人として成長してゆく。 物語のエンディングはクリスマスにふさわしい素晴らしいもので、図らずも少しほろりとしてしまいました。
1投稿日: 2015.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこどもたちと、ときどき大人のクリスマスのお話。それぞれに悩んで、精一杯の気持ちで迎えるクリスマス。作者がこどもに向ける視線がとてもあたたかい。
1投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさんのすてきな大人が出てきます。ケストナーが時代と格闘しながら書いたことがわかる言葉もたくさん出てきます。 ぜひ、書きぬきながら読みたい本。 子どもだけではなく、大人も読むべき本
1投稿日: 2014.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔は岩波の高橋健二訳のしかなかったが、(あれはあれで大好き。「○○してくれたまえ」とか言葉遣いが素敵。)今は様々な出版社からいろんな訳で出ている。名作だから、訳はどれでもいいのかもしれないが、絵はトリアーじゃなきゃ、駄目!絶対!!というわけで、池田香代子の新訳の岩波少年文庫で読みなおす。 まずヨーニーがジョニーになったことに軽く驚く。いや、アメリカ人とのハーフだもん、ジョニーと呼ぶのが正解よね、と納得。美少年テオドルもかっこつけテーオドールになっている。こっちの方が彼の性格がわかってよい。他もウリーがウーリとか若干違う。正義先生は「正義さん」、禁煙先生も「禁煙さん」になっている。これは、昔の方がよかったな。確かに禁煙先生は学校の先生じゃないから(はじめは)、先生というのは変なんだけど、子どもたちの敬意が感じられるもの。 でも、名作が今の子どもたちにも読みやすくなったのは喜ばしい。 マッチョなところは今の眼で読むと気にならなくもないが、戦前だからな。 子どのもころには正義先生がすごく立派な大人に思えたが、今読むと、先生、30代か、もしかしたら20代でもおかしくないかも。 昔の大人は、本当に大人だったね。
5投稿日: 2013.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログジュブナイル。 レビューどうこうよりもまずボクの先入観が激しく間違ってて、 うまく入り込めないまま読み終わってしまった。 タイトルから勝手に、楳図かずお先生の『漂流教室』的なSF系なのかなーなんて…。 よし、お詫びに(何の?)別作品も読むぞ。
1投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
恐らく KiKi が初めてこの物語を読んだのは小学校の低学年から中学年にさしかかる(2年生か3年生)頃だったと思います。 当時の KiKi には正直なところこの物語のよさがさっぱりわかりませんでした。 と言うのも、舞台は男の子ばかりが暮らすドイツのギムナジウムです。 しかも物語の冒頭で印象的に(?)登場する男の子は大食らいときています。 挙句ギムナジウムに通う男の子が実業学校に通う男の子たちに拉致され、それを助けにギムナジウム組が殴り込み・・・・・ ^^; 寮生活の何たるかも知らなければ、男だけの世界に流れる流儀みたいなものにも疎く、ついでに「暴れん坊」が苦手だった当時の KiKi にしてみれば「なんじゃ、こりゃ?」の世界だったのです。 でもね、もう少し成長して小学校を卒業するちょっと前ぐらいのタイミングで読んだときにはこの同じ物語がスッと心に沁みこんできたんですよね~。 これは小学校生活の中で男の子っていうのはどういう生き物なのか、その行動原理にどんな気持ちがあるのかということが何となく理解できるようになってきていたということもあっただろうし、初読の際には読み飛ばしていた大食らいの男の子の将来の夢がボクサーであることもちゃんと理解できていたからだと思うんですよね。 実業学校の子供たちが別の学校の子供を拉致するという設定にはリアリティは感じられなかったけれど、協力して仲間を助けるという義侠心とか、伝統的な対立意識とか、勇気ある行動に憧れる気持ちといったものがある程度身近なものに感じられる年齢になっていたからだと思います。 狭い世界で暮らしている少年たちが見せるある種の純粋さはキラキラと眩しかったし、どんなに仲間が大勢いてそれが素晴らしい仲間だったとしても、その中の個人には何かしらの問題・悩みのようなものがあって、その何かに時に押しつぶされそうになったり、抗ったりするわけだけど、その時は結局1人ぼっちなんだよなぁということも考えさせられました。 ただ、その決着をつける過程で、あるいは何らかのしっぺ返しを食らったときには周りには誰かがいてくれるのがいい。 それは仲間であることもあれば、この物語に出てくる2人の魅力的な大人、「正義さん」と「禁煙さん」のような「子供の心を忘れてはいないけれど、そこにホンモノの知恵も身につけた懐の広い大人だったりもすれば最高です。 そして思ったものでした。 「私もこういう本当の意味で良識のある大人になりたい。」と・・・・・。 さて、今回本当に久々にこの物語に手を出してみたわけですが、今回の読書では KiKi は又全く違うことを考えていました。 それはね、そもそもの事件(ギムナジウム組 vs. 実業学校組の喧嘩)に関してです。 この拉致事件のきっかけとなったのは「ギムナジウム組が実業学校組の旗を盗んで返そうとしなかったうえに、ようやく返されたその旗が破れていた」という子供らしいイタズラと呼んでもいいような些細な出来事なんですけど、その根っこにはもっと根深いものが潜んでいました。 事件のあらましを禁煙さんに語る子供曰く 実業学校の生徒とぼくらは、言ってみれば有史以前から対立しています。 十年前から、もうこんな状態だったそうです。 これは学校どうしのけんかで、生徒の誰かが誰かといがみ合っているとか、そういうことではありません。 生徒は、それまでの学校の歴史をひきつぐだけです。 これってものすご~く単純に言い切ってしまうなら、世界各国から決してなくなることのない「民族問題」の小型版じゃありませんか! 彼らはそんな「学校の歴史を引き継ぐ」ことに使命感にも似たようなものを持っていることがありありと感じられます。 そしてそんな使命感に燃え「それまでの学校の歴史を引き継いだ」子供たちは、相手側の1人を拉致・監禁し、挙句その人質に10分ごとに6発も暴行を働き、ギムナジウム組の子供たちの所有物である書き取りノートを焼いちゃうなんていう暴挙にまで及んでいます。 そして最悪なのはそれらの行動に何ら罪悪感を抱いていないということです。 子供の世界のいたづらにしては度が過ぎていると考えるのは、ひょっとしたら平和ボケした日本人だから・・・・・なのかもしれません。 ケストナーがこの物語を書いたのが1933年。 ナチス・ドイツが台頭してきたまさにその年です。 そしてナチス・ドイツが誕生する背景には第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約下の天文学的数字とまで言われたドイツに課せられた戦争賠償責任があり、終戦後のドイツ国民の窮乏があったことを忘れてはいけないと思うんですよね。 恐らくドイツ国内には「歴史的な屈辱」という意識は蔓延していただろうし、それこそ「歴史を引き継ぐ使命」みたいな意識は通奏低音みたいに流れていたんじゃないかと思うんですよ。 これはパレスチナ vs. イスラエル然り。 ボスニア・ヘルツェゴビナ然り。 モンゴル vs. 中国然り。 etc. etc. そしてケストナーはそんな人間の心に潜む対立感情をギムナジウム vs. 実業学校という比較的こじんまりした世界に再現してはいるものの、決してそれを甘受せず、「正義さん」や「禁煙さん」や別の先生の口を借りて、やんわりと諭しているかのようです。 曰く 平和を乱すことがなされたら、それをした者だけではなく、止めなかった者にも責任はある。 ぼくが願っているのは、何が大切かということに思いをめぐらす時間をもつ人間が、もっとふえるといいということだ。 金も地位も名声も、しょせん子供じみたことだ。 おもちゃだ。 それ以上じゃない。 ほんものの大人なら、そんなことは意に介さないはずだ。 そして物語同様に素晴らしいまえがきの中でケストナーは彼自身の言葉としてこんなことも言っています。 世界の歴史には、賢くない人々が勇気を持ち、賢い人々が臆病だった時代がいくらもあった。 これは正しいことではなかった。 勇気ある人々が賢く、賢い人々が勇気を持つようになってはじめて、人類も進歩したなと実感されるのだろう。 何を人類の進歩と言うか、これまではともすると誤解されてきたのだ。 この物語、児童文学の体裁をとっているし、実際小学校高学年から中学校低学年ぐらいまでの読み物としては素晴らしいと思うけど、案外、大人にこそ読んでもらいたい読み物なのかもしれません。 ま、ちょっと直球勝負すぎて白々しいと感じちゃうところもあるかもしれないけれど・・・・・。 でもね、寺田寅彦先生名付けるところの「国民的健忘症」の日本人、せめて本の中でぐらい「理想論かもしれないけど、やっぱりこういうことって大事だよね。 ちゃんと考えないと・・・・・。」と思う時間も大切なんだと思います。 最後に・・・・ この本の宮崎駿さんの推薦文は以下のとおりです。 子供の時、ぼくはこの本にとても感動しました。 キラキラした夢のような世界でした。 この本の少年たちや大人たちのように、勇気や誇りや公正さを持てたら、どんなに素晴らしいかと。 残念ながら、ぼくは勇気を発揮するチャンスを何度も逃し、傷つきやすく臆病な少年時代を過ごしてしまいました。 読み直して、勇気や誇りを持つことに、自分がどれほどあこがれていたのかを思い出します。 ぼくには少年時代も大人の時代もやり直すことはできません。 でも・・・・・と思います。 ちゃんとした老人になら、まだチャンスはあるかもしれないって・・・・・・。 KiKi も「ちゃんとした老人」を目指したいものです。
2投稿日: 2013.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログクリスマス前のギムナジウムの様子を切り取った物語。 五年生の少年たちを中心に起こる出来事は、ささやかだけど間違いなく幸せを感じる。 寄宿学校という舞台の割に、閉塞感は感じない。むしろ、伸びやか。 新聞の書評でみかけて読んでみた。 書評には登場人物の誰かに似ている自分を見つけるはず、と書いてあったとおり。
1投稿日: 2013.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「心配するな。ぼくはすごくしあわせってわけじゃない。そんなこと言ったらうそになる。でも、すごくふしあわせってわけでもないんだ」この言葉に何もかもが詰まってる気がする
2投稿日: 2013.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ立派な大人たちの物語。教育だの何だのいう以前に、こんな大人になりたい、と思わせる大人であることが、子供にとってなによりの道しるべなんだと思う。子供が好きだというのなら、まず立派な大人にならなくちゃ。
2投稿日: 2011.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログクリスマスにぴったりな一冊。 出てくる男の子たちがみんな可愛い! 男の友情っていいよねー。 前書きのケストナーの言葉に、励まされます!
1投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ『点子ちゃんとアントン』が面白かったので、読みました。子供たちはみんな、やんちゃで勇敢で素直で、大人たちもみな子供のことを思いやって温かいのが、すごく素敵だと思いました。冬のお話ですが、温かいね。 他の学校の子と、本気で戦いをしているところ、戦いにおいて敵との話し合いもなされているところに、子どもの世界の筋の通ったところが感じられて、読んでいて気持ちがよかったです。 挿絵が子供たちの活動的な様子や、先生たちの優しい様子などを表わしていて、とっても良かった。 ちょっと日本語が古い感じがしたけれど、そこもまた味です。
1投稿日: 2011.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログどの物語だって手作りだけど、特にこの作品は手作りな感じがする。贈り手が、ページの向こう側にいるような。
1投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ岩波少年文庫は、本当に素晴らしい作品ばかりだ。 そして、とても注釈が分かりやすいので大好きだ。 この作品も、訳者のあとがきを読むのと 読まないのでは、全然作品の重みが違う。 訳者のあとがきによるとこの作品は ヒトラーが政権を持った1933年に書かれたそうだ。 そういう背景を知ると、この作品のセリフに ケストナーの強い思いを感じ取ることができる。
4投稿日: 2011.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
クリスマスを前にしたドイツのギムナジウムの数日間の話。 かけねなしの名作だと思います。 そして今、読んでもめちゃくちゃ面白い。 小学生高学年の男子には絶対におすすめの内容です。 ここで描かれている生きていくうえでの“尊いこと”は 人間であるかぎり、時代、人種を超える普遍的なものだと思います。 ただ、訳者があとがきで書いてあるように、“男性的”であることへのこだわりについて、 現代の女性読者は違和感を抱くことがあるかもししれません。 ただ、その時代で書かれているものは、時代を超える部分もありますが その時代に縛られていることもあります。 それもその時代に生きたケストナーの個性だと思います。 そういったことも踏まえて 本当にすばらしい小説だと思います。 ちなみにケストナーはユダヤ系ドイツ人でナチスが政権をとった後も 亡命をこばみ、スイスの出版社を通して作家活動を続けたそうです。 この本が書かれたのは1933年、ドイツがナチス政権下にあった時代です。 あとがきでも触れられていますが、この本の有名なことばがあります。 「世界の歴史には、かしこくない人々が勇気をもち、かしこい人々が臆病だった時代がいくらもあった。これは正しいことではなかった」 ナチス政権下でこれだけのことを書いて発表したケストナーの心意気には 感嘆するしかありません。
2投稿日: 2011.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツの学校小説についてのレポートのための参考文献のひとつとして読了。全寮制の学校って厳しそうでもあるけどちょっと憧れたりもする、こういうとこにこそ本当の友情が生まれそう。
1投稿日: 2011.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ正義さんと車に住んでるひと(だれだっけ)ラブラブ!大人になってもこの本を読んで泣けたらいいと思うはなし
1投稿日: 2011.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さい頃からくり返し読んだ児童小説。映画も見た。”ギムナジウム好き”になった原点かも。今読んでも楽しめる良作。
1投稿日: 2011.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログボクサー志望のマッツ、貧しくも秀才のマルティン、臆病なウーリ、詩人ジョニー、クールなゼバスティアーン。個性豊かな少年たちそれぞれの悩み、悲しみ、そして憧れ。寄宿学校に涙と笑いのクリスマスがやってきます。
1投稿日: 2011.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国文学読むのはやっぱり苦手・・・ なかなか入りこめなかったけど後半になってからようやく よさがわかってきた。
1投稿日: 2011.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツの児童文学者、エーリッヒ・ケストナーの代表作。 寄宿学校の少年たちの友情と成長を描く。 この本の面白いところは、子どもを決して子ども扱いしない、心ある大人たちが出てくるところ。 なんといっても素敵なのはこの物語がナチス政権下で書かれたということ。 人間の想像力って、こういうことに使われてほしいですね。
4投稿日: 2011.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「良い話」の教科書を読んでるみたいでした。訳者解説を読みつつ、色々考えさせれたり。「良い話」でした。がーっと読めてスカっとした。こどもが主役の物語で大人がよく書けている作品にハズレはなかなか無いのだと思います。色々思い出させてくれて感謝。言葉の端々の、詩とメッセージが渾然一体となっている様が美しかったです。
1投稿日: 2010.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログみんな忘れてしまうけれど、大人はかつて子どもだったのだ。 理不尽な仕打ちにもまっすぐぶつかっていく、彼らのように。
1投稿日: 2010.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔からタイトルだけは知っておりました。 何で子供のころに読まなかったんだろう?と地団太を踏みたいぐらい良いお話でした。もちろん今読んでも面白いけどこれはやっぱりケストナーが少年少女の為に折角書いたのだから少女のうちに読んでおけばよかった…。 子供時代は幸せなだけだなんて嘘っぱちを書く児童作家…確かに居るいる(笑)。子供だって色々辛いことがあり、真剣に悩むことがあり、胃が痛くなるほどの心配事だってある。そんなことを忘れてしまう大人になっては確かにダメですね。 正義さんや禁煙さんみたいな大人になりたいなあ~と子供のころは思うのに何でそうはなれないのかな。少し自分の人生を反省してみたいです。
1投稿日: 2010.12.07
