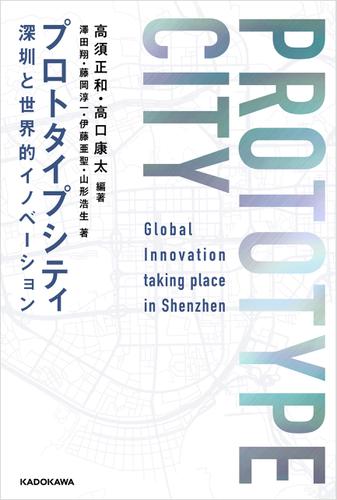
総合評価
(9件)| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
視点が広がるという意味で興味深かったですね。 こんな見たことのない世界があるということ。 そして新たなものを作る形式にも 様々なものがあるということ。 もともとある通販を使っているので この地域の店舗はよく見かけるんですよね。 ああ、なるほどと思いました。 (ただし私が求めていたある情報は本の数行のみ) きっと時代はこの形式になるのでしょう。 悲しいけれどもね。 それを受け入れないといけないのだと思います。
0投稿日: 2023.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログプロトタイプといえば深圳、というのは界隈の人では非常に有名ではあるが 世界的なプロトタイプへの位置付け、潮流などを網羅的にまとめてくれている本 巻末には対談も記載されていて、その内容も非常に面白い 特に目新しい内容はなかったが、興味がある人、深圳とは?、プロトタイプとは?ということを理解したい人は一読する価値はあると思う
0投稿日: 2021.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログトライアンドエラーを繰り返す土壌ができた深セン、 品質テストを実施して品質担保してから出荷する日本では スタートアップのスピード感が異なる。 「製品の新機能が正しく動くよりも、その機能が受け入れられるかを見るほうが大切」 深センはサプライヤーも集結しているので、 低価格の部品がすぐ手に入りやすく低ロットでのモノ作りにコストや時間がかからない。 手を動かすことでトライアンドエラーを繰り返し、コミュニティが形成されていったことで深センはテクノロジー都市になっていった。 元々深センは工業都市で、サムスンやフォックスコンなどの外資の下請工場が存在していた。 下請製造で得た知識で大手の模倣品を作り低価格で売り出すことで利益を得て成長していった。 底辺から1発当ててやろうという野心のある企業家や技術者が集まり今の深センが形作られた。 ソフトウェアはオープンソースの物も増えているので、新興国先進国関係なく同じレベルの物を享受できる。 ソフトウェアの分野は今後も各国で熾烈な争いを繰り広げるのだろうという気がしました。
0投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国やアメリカの力強さの根源がよくわかる。コロナという一大事件があったが人の本質は変わらないと思うし、今後数十年はこの主流が続いて行くと思えるので安心して中国とアメリカに投資を続けようと思えた。 また、日本に向けてアドバイスも書いてるが個人的に思うに、日本は中国とアメリカと同じような場所で戦うのを目指すべきではないと思う。 そもそも、社会の仕組みや気質その他諸々が向いてない。 コロナ後で半導体に投資するといったニュースをみたが、他の国に比べたらえ?これっぽっちっていう金額しか出せない。 戦う場所を間違えてる気がする。今のままの状態で、技術の進歩により日本語の鉄壁ガードを取り除かれたらどうなるか戦々恐々である。
0投稿日: 2021.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国深センを中心に、今のビジネスを考察している本 深センには多くの日本企業が進出している が、なぜ日本企業は変化していると言い難いのか? 知りたいな〜
0投稿日: 2021.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
色んな人がそれぞれ、深センのすごさについて語った文章・対談を集めたもので重複が多かったり全般に読みにくい。 ・伊藤穰一は、二〇一四年のTEDで「革新的になりたいなら、ナウイストになろう」というテーマで講演した。インターネットにより、社会は複雑で予測不可能になった。予測不可能だから、計画を立てるコストはどんどん上がっているにもかかわらず、計画そのものの有効性は下がっている。そのような時代に対応するために、計画でなく、手を動かし、コミュニティを作りながら進むことが大事だと説く。彼は「今に集中して手を動かすことが最も大事。未来予測家でなく実践しよう、フューチャーリストでなくナウイストになろう」と結論づけている。
0投稿日: 2021.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ深圳なのか?という説明に期待したが、そこはまだはっきりとしていないのかな? 街の二重構造性(中心地と郊外の関係)、戸籍の得やすさ(中国は戸籍変更がかなり難しい)等、面白い点もあったが、後はどこにでもあるような内容。
0投稿日: 2020.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国の深圳がどのように発展していったのかを知りたくて、この本を読み始めた 頭でっかちな計画を立てるよりも、手を動かしていく中で正解を探していくプロトタイプ駆動。そのプロトタイプ駆動をより正確に行うために必要なコミュニティが、新興国などの新たな都市に芽生えている。プロトタイプ駆動とその実践の場、すなわちプロトタイプシティの新たな時代が始まっている まず世界経済はこの30年間で大きく成長した。アメリカのGDPは1990年の6兆ドルから、2017年には19.3兆ドルと3倍強にまで成長しているのに対し、日本のGDPは3.13兆ドルから4.87兆ドルへと1.5倍にしか増えておらず、中国やベトナムは30倍の成長を遂げている。 その中でも外資系企業の工場から始まった深圳という街は、たった40年間で大きく進歩し、今ではイノベーションを生み出す、テクノロジーの最先端を行く街へと進化している。 日本のような連続的価値創造のビジネスではなく、非連続的価値創造のビジネスを行う、小産小死型で、計画を深く練ってリスクを回避するよりも、まずは手を動かして、市場にサービスをリリースし、改善点があれば後から手を加えていく。このやり方で成長を続けた。 他にも深圳にはスタートアップの企業が物づくりをしやすい環境が整っていて、小ロットからの発注が、他よりも安くできたり、様々な関連企業が集結しているため、スピーディーにアイデアを形にできるという点が強みであることが分かった。 今後もドローンなどの技術で先頭を走ることになるであろう深圳に、注目していきたいと思った。
0投稿日: 2020.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ自著で、「メイカーズのエコシステム」から5年経っていろいろアップデートされている。 個人的に「メイカーズのエコシステム」との間で順位や優劣はつけられないのだけど、同人誌&現場ルポ的な「メイカーズのエコシステム」に対して、「プロトタイプシティ」はプロ編集者の高口さんを中心に、ライブ感を残したままうまく体系化・抽象化に成功しているように思う。 僕としても、「高口さんがまとめるに足る本を作る」というのが一つのテーマで、全体としてバンドっぽいデキになったとおもう。
0投稿日: 2020.08.09
