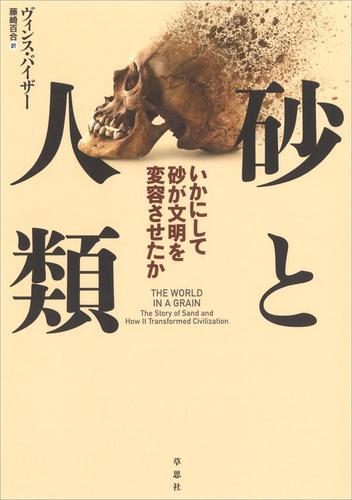
総合評価
(9件)| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
砂のマルサス
大部な著書であるが、砂の歴史的な位置づけ 利用方法から説き起こして、多くの資源と同様に砂でさえも枯渇し始めている という、言説には大変に説得力がある。ありきたりの環境活動家とは異なり、現代の先進国の人々の快適な生活が、砂を始めとした資源の上に成り立っている ということも繰り返し述べている。それだけに発展途上国の多くの人々が、先進国と同様の快適な生活をおくるための資源の問題は 用意には解決策が見つからない課題である。 しかし、この本を読むまで、砂まで枯渇しているとは全く思わなかった。そして砂漠の砂がコンクリートに使えないことも知らなかった。
0投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログここ最近で一番良かった本の一つ。あまり普段焦点が当てられない観点に対して、新しい世界の見方を提供してくれた一冊。永遠だと思われていたコンクリートで一時凌ぎの不完全な世界を作り上げてきてしまった人類は、これから砂不足と需要増加、大規模な立て直しの必要性といった問題に直面していくだろう。アメリカのシェール革命を推し進めたフラっキングという観点は新鮮だったし、ヨーロッパがアジアよりも早くにガラスを取り入れて文明化していたことも驚くに値する。ガラスを文明化したことで、ヨーロッパは望遠鏡や顕微鏡を生み出し、眼鏡を通して学術研究を推し進めたという観点は、今まで持ったことがなかった。
0投稿日: 2025.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ砂丘が好きだから気になって読んでみた。生活の中で原料として砂が使われてることを意識してないだけで砂は意外と身近な存在なんだなと思った。
1投稿日: 2023.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ我々の暮らしが,いかに砂に依存しているか? を一般向けに解説する. コンクリート,ガラス,チップ用のシリコン,シェールオイル/ガスの採掘,ビーチの養浜..... 砂がなければ,いずれも成り立たない. 砂漠の砂が,このどれにも役に立たないというのがショック.
2投稿日: 2022.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「砂」をテーマにしたノンフィクション。 現代文明に砂は欠かせない基本的な物質である。コンクリートやガラス等様々な構造物に使用されているが、土木建築が大量に作られる時代になって、大量の砂が採掘、消費されて地球上から砂が減りつつある。(ここで言う砂とは活用できる地層、河川や海の砂を言う。砂漠の砂は使えないらしい)この状態が続けば、今後の人類の活動に大きな影響が出て来そうで、対策が急がれるがなかなか良い代用品が無い。 砂はお金になる。世間では砂は当たり前に存在する物質という感覚だが、これも水や石油と同様の資源であり、利権をめぐって世界中で紛争の元になっていることを認識しておかなくてはいけない。結局、カネの問題なのかな。
1投稿日: 2020.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白い。 当たり前のように存在する砂について深く知ることもなかなかないので、全く見当違いの分野に触れることができると言う読書らしい読書でよかった。 内容も面白く我々が普段砂の使い道だろうと考えているコンクリートや建築物そして半導体、意外なところではシェールオイルのフラッキング、他にも様々なところで利用されている。しかもそれが有限で枯渇しかけていると言う。 これだけ地球上、土と砂だらけなのに! お勧めできる本だと思います。
1投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ砂と人類 ヴィンス・バイザー著 都市化と欲望の行き着く所 2020/5/16付 日本経済新聞 朝刊 環境の変化や生活圏の拡大によって、野生生物を宿主として突如人間にうつる人獣共通感染症が報告されるようになった。このたびのパンデミックも、急速な都市化が背景にあるといわれる。 では都市化とは何か。その歴史と今を見渡す優れたノンフィクションが刊行された。何千年にもわたる砂と人類の関わりから現代の砂採掘現場まで、「砂」をテーマに世界各地で取材を行い、文明の変容を描き切った大作だ。 古代ローマの建築材に使われた砂と砂利を原料とするコンクリートが都市の土台となったのは19世紀、鉄筋コンクリートの登場を起点とする。砂浜や湖で採取した砂はビルの建築資材となり、道路を覆い、人や物の流れを変えた。 砂はガラスの主原料として科学革命も牽引(けんいん)した。顕微鏡や望遠鏡、デジタル社会に欠かせない光ファイバーやシリコンチップ、スマホの画面も砂でできている。 良質の砂が眠る川や湖、海では争奪戦が繰り広げられている。インドネシアでは24の島が消え、ベトナムのメコンデルタは今世紀中に半分消滅するといわれる。 近年、砂の需要が増すのはシェール石油の採掘場だ。岩盤を裂く際に必要な砂の採掘が進む米ウィスコンシン州チペワ郡では、地下水と鱒(ます)が壊滅的な影響を受け、反対運動が起きた。「未来の世代に対する犯罪だよ」と住民は嘆く。 著者はバランス感覚の優れた取材者で、砂で利益を得る者を糾弾するわけではない。だが隠蔽体質の強い企業や殺人も犯す砂マフィアと対峙する際は、地球の守護者にならざるを得ない。その姿から浮かび上がるのは砂を求めた人間の底なしの欲望の歴史である。 目下、世界最大の砂消費国は中国だ。気候変動で砂漠化が進み、内陸から多くが都市に移住した。今や100万人都市は220超、都市人口は60年前の3倍だ。生態系への影響を顧みない開発で自然破壊が進んでいる。コロナ禍は起こるべくして起きたと思わされた。 全世界が米国並みの暮らしをするには地球4個半が必要で、砂の枯渇は時間の問題だという。コンクリートやガラスの代替物はなく、消費量を減らすしか道はない。国際的な連携は急務であり、本書は議論に必要な材料をふんだんに提供してくれるだろう。 《評》ノンフィクションライター 最相 葉月 原題=The World in a Grain(藤崎百合訳、草思社・2400円) ▼著者は米国在住のジャーナリスト。ニューヨーク・タイムズ紙などに寄稿。
1投稿日: 2020.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類は砂を取り合って殺し合いを起こすようになるだろう。我々の周りは砂から作られたもので溢れている。だから奪い合うであろう。 良い本である。ツイッターで良いと言われていたが、良かった。こういうの読みたかった。砂が人類を支えているという事実をきちんと表すというのが大事。2000年代はただ環境にやさしく!を脅迫するだけのものばかりだけだったからね。 こういう人類に多大な影響を与えたマテリアルっていっぱいあるだろうけれど、こういうのをきちんと学んでで行くのがも面白いんじゃあ。 こういう知識を知ると世の中の見え方変わる。普段歩いているアスファルトの上にいるだけで世界を感じちゃうよね。こういうのが「教養」と呼ばれるものなんだろうけれど、教養、ついちゃうよね。この本。
1投稿日: 2020.04.09ドキュメンタリー風
セメントになったり、セメントと混ざってコンクリートになった、ガラスになったり、シリコンチップになったり、水と一緒に地下深くに撃ち込まれたりと現代文明のあちこちで不可欠な働きをしている砂。一方で用途が広すぎて資源として枯渇が危惧されたり、採掘による周辺環境への影響が取り沙汰されている。著者はジャーナリストで、本書もインタビューや調査を元にしたドキュメンタリーを思わせる構成となっている。科学や歴史の啓蒙書というよりは、砂にまつわる問題を知らしめることを目的として書かれているように思われる。 科学的な典拠となっているのが、ポピュラー・サイエンス(一般向け自然科学啓蒙書)だったり、修士論文だったりで、信頼性に欠けるとまでは言わないものの、もうちょっと頑張ろ?ちゃんと専門書に当たろ?という不満が残るものの、読みやすく分かりやすいので、まあ、許容範囲か。
0投稿日: 2020.04.08
