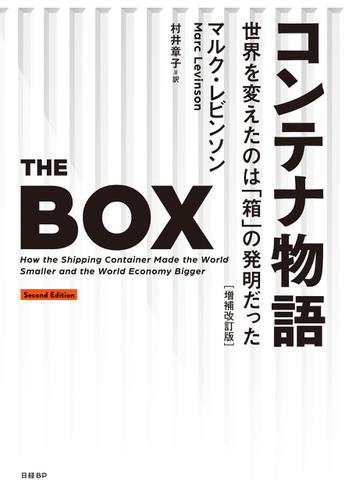
総合評価
(81件)| 23 | ||
| 29 | ||
| 18 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ===== 二〇世紀後半、あるイノベーションが誕生し、全世界でビジネスのやり方を変えた。ソフトウェア産業の話ではない。それが起きたのは、海運業だ。おそらく大方の人があまり考えたことのないようなそのイノベーションは、あの輸送用のコンテナである。コンテナは、この夏私が読んだ最高におもしろい本『コンテナ物語』の主役を務めている。コンテナが世界を変えていく物語はじつに魅力的で、それだけでもこの本を読む十分な理由になる。そのうえこの本は、それと気づかないうちに、事業経営やイノベーションの役割についての固定観念に活を入れてくれるのである。 by ビル・ゲイツ =====
0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ1956年に初めてコンテナ輸送を手がけた輸送業のマルコムマクリーン、ニューヨーク市とニューャージー州の埠頭、港湾労働者の組合運動、ベトナム戦争におけるコンテナ輸送、鉄道とターミナルオペレーション。コンテナは国際物流のコストを劇的に変え、グローバルな生産分担を可能にした。 今では普通になった、コンテナという規格が行き渡るまでの経緯。コンテナがなかった時代は、まだ人々の記憶にある。規格化したらコストダウンできることって、他にもいっぱいあるのに。
0投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナというイノベーションがいかに生まれ、誰にどんな影響をもたらしたのか詳しく書かれていて学びになった
0投稿日: 2025.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナの歴史がわかる本。1つの発明が思いがけないところまで影響を及ぼすことってありますよね。コンテナできたから荷物がたくさん運べるようになってよかったね、ではもちろん止まらない様子がとても面白かったです。 経済的な面でいえば、輸送コストの減少によって、世界の色々な場所でそれぞれ部品を作って、最後に合わせて完成品にするというスキームが成り立ったというところが衝撃的でした。つまりは、人件費や土地の安いところで部品を生産することにメリットが生まれたということでもあり、これって今も社会問題ですから。 ただ、当時、産業が全くなく、衰退していた状況であった地域からすると、そういった大規模資本の投入はポジティブだったんだと思います。時代が変わっただけですね。 あとは、人的問題。コンテナによる効率化によって雇用が減るわけです。このあたりの人間描写もかなり細かくて面白かったのでおすすめポイント。旧態依然とした邪魔してくるやつとか出てきます。 そして、最後にコンテナという頑丈で中身の見えない大量のモノを運ぶことによる危険性。爆弾が入っていたり、移民が入っていたりすることもあるようです。 この全てが変わっているインパクトの大きさこそ、まさしくイノベーションという感じです。
42投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログまえがきと第一章:コンテナ輸送の黎明、アイデアルX号の航海 本書は、長らく注目されてこなかったコンテナの歴史を紐解き、その発明と普及が世界経済に与えた революция的な影響を明らかにします。1956年、マルコム・マクリーンのアイデアにより、老朽化したタンカー「アイデアルX号」が最初のコンテナ船としてニューヨークからヒューストンへ向けて出航し、現代の巨大コンテナ港へと繋がる第一歩を踏み出しました。 第二章:独特な波止場の文化とコンテナ化による変革 本書は、コンテナリゼーション以前の港湾労働が不安定で労働集約的であったこと、そして沖仲仕の賃金が輸送コストの大部分を占めていた状況を描写します。その後、コンテナ化が港湾労働にもたらした劇的な変化、労働組合との交渉、そしてニューヨーク港の衰退といった、波止場を取り巻く文化と産業構造の変遷を分析します。 第七章と第十一章:初期のコンテナ普及とゆるやかな影響 コンテナ輸送の初期の普及状況は緩やかであり、1962年時点でも貨物取扱量に占める割合はわずかでした。しかし、ゲートウェイシティ号やハワイアンシチズン号といった初期のコンテナ船がその効率性を示し始め、1965年から1966年にかけてコンテナ貨物量が急増、多くの海運会社が参入し、国際航路への拡大が進みました。 ベトナム戦争の影響:軍事物資輸送とコンテナ化の加速 ベトナム戦争における物資補給の混乱が、コンテナ輸送の導入を国防総省に迫る要因となりました。シーランド社は積極的に軍事物資輸送に協力し、大幅なコスト削減を実現しました。この出来事が、コンテナリゼーションの世界的な普及を加速させる大きな契機となりました。 物流とジャストインタイム:効率化の追求 コンテナ輸送は、必要な時に必要な数だけ生産し配送するジャストインタイム方式を可能にし、メーカーや小売業における在庫コストの大幅な削減に貢献しました。輸送コストと在庫コストの削減により、リードタイムの制約が緩和され、グローバルなサプライチェーンの構築が促進されました。 港湾の効率と競争力:グローバル市場での生き残り 港湾の効率性が低い国や巨大船が寄港しない国は、ロジスティクスがグローバル市場での競争力を阻害する要因となりました。世界銀行の事例を挙げ、港湾整備が貿易量に与える影響を示唆します。巨大コンテナ船の登場による輸送コストの削減も解説され、港湾ビジネスにおける付加価値の重要性が強調されます。 鉄道の対応、マクリーンの挑戦、そしてコンテナ革命の成就 貨物輸送でトラックとの競争に直面した鉄道会社が、トレーラー輸送という形でコンテナ輸送に参入した動きを紹介します。マクリーンの先見の明と、既成概念を打ち破る「箱」(コンテナ)という革新的なアイデアが、海運業界に革命をもたらし、シーランド社の劇的な成長、そして世界的なコンテナ輸送網の確立へと繋がった過程を描きます。
0投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ物流の話。 コンテナをここまで深く掘り下げたのはすごいと思うけど、いかんせん自分の仕事(医業)とはかけ離れていたので、読むのを途中で辞めた。 岡田斗司夫先生がほめていたけど、万人向けではない。
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログビルゲイツのおすすめ本。 一見地味な輸送用コンテナの発明が、グローバルな分業体制の確立に決定的な影響を与え、世界の経済発展に大きく寄与した。 コンテナが世界に普及するまでの紆余曲折がかなり詳細に記述されており、その分野以外の人間にはやや退屈。
0投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナの歴史がわかる 効率化のために導入された 既得権益者の反発で時間がかかる 船関連だけでなく鉄道、トラック、世界の流通に革命が起きた
0投稿日: 2025.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったけど長い... コンテナの話でもありアメリカ労働者の話でもあり。 規格あわせるってかなり大事だなぁ。
0投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナ開発者の話とコンテナ開発によって世界の物流がどう変わったのか・単純な発想が世界を変えた一例が書かれた本。 アメリカ労働者の権利の強さ、既得権益を壊すことの大変さ、規格統一化の重要さ・大変さがよく分かった。
0投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コンテナのおかげでニューヨークとリバプールは凋落した。 釜山やシアトルが世界のトップになった。 コンテナは労働者にメリットもデメリットももたらした。労働環境は改善したが待遇改善に終止符が打たれた。 海上貨物運賃は、輸出輸入の10%以上を占めていた。関税以上に強力な参入障壁だった。 積み出しと荷揚げに費用がかかる。コンテナで削減できないか。しかし貿易に与えた影響は軽微だった可能性もある。 エジソンの白熱電球は20年後でも普及率は3%。普及には発明だけでなくイノベーションが必要。コンテナも同じで普及には時間がかかった。 コンテナの規格は紆余曲折を経た。鉄道、トラックなどと合わせる。 マルコム・パーセル・マクリーンが改革してコンテナを普及させた。運送業者から身をおこし、旺盛な事業拡大意欲で事業を拡大。海運業に全財産をつぎ込む。 トラックに箱ごと積み下ろしする。 ニューヨーク対ニュージャージー。ニューヨークは古くからの港で設備が老朽化、ニュージャージーがコンテナ化した。 コンテナの規格は鉄道のように、自然には定まらない。高さは8フィートまたは8フィート6インチ、長さは20フィートから40フィートまで。幅は早くから8フィートと決まった。航空便のコンテナは別仕様になった。荷重の問題。 コンテナ輸送は過当競争を呼ぶ。荷揚げ設備が必要なので寄港地は削減し、その間をトラック鉄道輸送がまかなう。クレーンと巨大なコンテナヤードが必要。 その結果。ロッテルダムが世界最大のコンテナ港になった。 マクリーンのシーランドは、たばこ会社のレイノルズに売却された。巨額の投資が必要になった。安価な石油価格を背景に高速船を建造。エレクトロニクスメーカーにコンテナは活用された。 コンテナは、スタートから大規模にやる必要がある。在来船は荷物を求めてあちこちに寄港したが、コンテナは定期航路、高頻度サービスで大量に持つをさばく必要がある。その結果供給過剰になる。 コンテナ船はランニングコストがかかるから、船を休止させておけない。 オイルショックの原油高で、荷物の量が減る。 高速船は燃費が悪く使えない。マクリーンの高速船は海軍に引き取られた。 レイノルズは海運事業を売却。景気に左右されやすい。海運業者が売るのはコモディティと同じ。 マクリーンは、従来のライバルユナイテッドステーツ海運を買収。超大型船で低燃費の船を建造。速度が落ちたため、流線型にしないで荷物を大量に詰める形。 パナマ運河を運航できる最大舟型=パナマックス級。さらにオーバーパナマックス級も建造された。限られた港を往復する。シンガポール~ロッテルダムなど。 寄港地は少なくなる。日本からサンフランシスコ行きの荷物はシアトルで下ろされる。 サッチャー首相は港湾施設に多額の投資が必要なことに嫌気を刺し、21の港を売却した。他の国も追従。 原油価格の下落で産油国向けの荷物が減少し、ユナイテッドステート海運は倒産。 コンテナによって巨額の費用が必要となり、生き残った海運会社はわずか。 船の速度は、原油価格に左右された。 コンテナは動く倉庫。保管費用が削減された。 混載船の時代は荷主は力が無いが、コンテナになると荷主がまとまれば海運会社を左右した。オーストラリアの輸出農家の例。 公定運賃は力を失う。コンテナは世界経済の規模を大きくした。 バービー人形は1959年の時点で、生産を日本で行うことにしていた。当初から世界のサプライチェーンを使っていた。 製造業は当初、垂直統合を目指した。運賃が安くなるとサプライチェーンを作るようになった。 世界のコンテナの20%は空。 コンテナによって反映する場所と不利な場所ができた。 アントワープ、ドバイなどコンテナによって都市化した都市ができた。 かつてはパナマ運河、今はマラッカ海峡で船のサイズを決める。マラッカマックス。さらに船が大きくなるか。
0投稿日: 2024.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01427566
0投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナについてほとんど全てのことがわかる本。コンテナのことはわかったんでもういいです〜ってなるぐらいの情報量なので、少し物流や貿易をかじりました程度の人にとってはボリューム的に若干苦痛かも。ただこれって日本のことを考えるきっかけにはなっていて、港で見かけるどでかいコンテナをJR貨物に積み替える作業ってどこでやってんだろうね?それとも基本はトラック?ググったりYouTubeだったり調べればそこら辺いくらでも分かるだろうから、知的好奇心がある人の知りたい欲をかきたてる一冊には間違いなくなると思う。あと港町特有の気性の荒さの理由が少しわかった気がする
0投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナがシームレスに運ばれること、規格化に伴い大量に輸送できることで、世界的なサプライチェーンを可能にしたんだね。
0投稿日: 2024.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナが普及していく過程と影響の一端を知ることが出来て勉強になった。 トラック運送会社、鉄道会社や船会社などを巻き込んだコンテナの導入・規格化は世界の物流を効率化させ、結果的にグローバル化を推し進めた。 港での荷揚荷卸をはじめとした物流費用が低下したことで、企業にとっては生産地と消費地の距離という制約から自由になり、労務費の低い場所でモノを製造することがトータルコストを押し下げることとなった。
0投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。コンテナの導入によるグローバルなサプライチェーン革命の話は刺激的だ。かつて在来船が主流の時代は輸送効率、荷役効率が悪く、企業の生産拠点も港の近くに設置せざるを得なかった。コンテナの導入により、生産に必要な部材の調達が低コストかつ計画的に行うことができるようになり、生産拠点は港から離れた、土地や税金が安い場所へと移ることも可能となった。在来船の頃は航海中のコストよりも、埠頭に到着している間に発生する荷役等のコストの方が全体の大半を占めたそうだ。コンテナ化によって荷役のスピードは格段に上がり、品質も担保され盗難の恐れもなくなった。そして大幅なコスト削減が実現した。当然ながらコンテナ導入時には沖仲仕や労働組合の猛反発があったそうだが、時代の流れには逆らうことができない。コンテナ化によって誰も想像できなかったレベルでの港湾の合理化が進み、かつて沖仲仕、港湾労働者で溢れていた港から人々が去り、今では最新鋭の設備とコンピュータシステムによる荷役作業が主流となってきている。
0投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナ内の点検はむずい →麻薬とか爆弾とか移民とか運べちゃう 1.輸送技術の進化 2.イノベーションの重要性 今日重要なのは →イノベーションに、よって資本や労働者をどれほど効率的に使い、より多くのものやサービスを生み出せるか」 →イノベーションは最終的に最も適した用途に応用されるにしても、初期段階ではうまく適用できないことが多い →→新技術は最初金にならない 発明の経済効果を生み出すもの →発明そのものではなく、それを実用化するイノベーション →組織や制度の変革 →→エジソンが電球を発明して20年後でも一般家庭での普及率は3%だった ■埠頭 サンフランシスコ、モントリーオール、ハンブルク、ロンドン、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス 一航海にかかる総費用の半分は沖仲仕への賃金だった →人力だからダメ
0投稿日: 2023.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカ牛を日本ですき焼きにするのも 仏デザイナーがベトナムで服を縫製させるのも トヨタのjust in time方式も 日本家電がアメリカを席巻したのも コンテナのおかげ。 こんな話知らなかった、面白かったー!
0投稿日: 2023.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナにまつわる物語。良書。 港湾における労使紛争。起業家マクリーンによるコンテナによる物流改革。改革に対する反対勢力との攻防。コンテナリゼーションによる運輸業界の変遷。 歴史は参加者の想定を超えて動いていく。
0投稿日: 2023.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションの物語なのに、輝かしい閃きではない事にフォーカスしていたのがイイ。 誰も革命的なことの最中にいることすら理解せず、コンテナの革命は一歩ずつ進んだのが良く分かる。 トラックと鉄道と船をひと繋ぎにすることで、今の世界の流通システムが成り立っている。大袈裟に言うと、それが資本主義の根幹なんだと理解できる。 数々の課題を統一していく過程が良い。 大きさの規格、連結金具の開発、ライバルである鉄道会社の取り込み、港湾の荷揚げシステム、大量のコンテナBOXや船舶のリースシステム、トラックやトラーラーのボックス化。 それ以上に多様化し対立化する、ギャングや政治家の対処や、労働組合やライバル会社などへの折衝、資金調達から新しい企業買収方法など、まさに多岐へ話題が散りばめられていて、ページを捲る手が止まらなかった。 コンテナそのものは統一規格化されても、まだまだ効率化の余地があって、AI港湾への進化、パナマ運河やマラッカ海峡の幅問題をクリアーする大型輸送の実現と港湾の革新などが進むのだろうと思った。 まさに、「ロジスティックを制する」ことが、今後も世界経済を制するんだと深く感じた時間になりました!
0投稿日: 2023.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログバラ積み混載中心だった運送が、コンテナの導入でどう変わったのか、手に汗握る産業発展の歴史 252ページまで読んだ
0投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバリゼーションのきっかけとして、物流コストの低下があげられるが、その一躍を担ったのがコンテナで、コンテナ事態は箱にすぎないが、その規格化を通して、陸運と海運をシームレスで一体化させて、各工程の最大コストの積荷の費用と時間を大幅に削減したことが大きな要因として挙げられる。またコンテナの積荷に対応した港湾の設備通しや戦略で、現在の各都市の港湾の明暗が別れたと考えられる!
0投稿日: 2023.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログここ数年、天候不順や感染症の蔓延を発端に不安定な物流の現状を目の当たりにしている。特に、海運におけるコンテナ不足はたびたび問題となっている。今や当たり前に活用しているコンテナ、コンテナの歴史を見つめ直し、その将来を考察している本書は、物流との関係を断ち切れない現代人は必読だと感じた。 マルコム・マクリーンの優れた先見性は、あの時代に海運業を貨物を運ぶ産業と認識していたことと筆者は述べている。何かを発明することの重要性が注目されがちだが、埋もれた発明品を適応させるため、現状の制度を変えるマクリーンのパワフルさこそがコンテナの導入に繋がったのだろう。 本書の中で最も印象に残ってるのは7章の規格である。規格化は国際コンテナ輸送の実現に不可欠なピースであった。技術的また政治的な様々な問題に折り合いをつけながら、コンテナのサイズ、素材そして隅金具と規格化に翻弄した人々の苦労が伝わってきた。技術の過渡期における統一規格の作成は、不確定な技術革新に理解を示し挑戦決断することができてこそ果たすことができるのだろうと考えた。
1投稿日: 2023.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ6年くらい前にビルゲイツがお勧めしてるからぜひ読みなよと同僚からお勧めされた本にやっと手を伸ばすことができました。 単なる箱に過ぎないコンテナは、いかに世界の物流に影響を与えたかが時系列でよくまとめられています。海運送業にもたらした構造変革(前時代の港における荷役による積み下ろしから工場からラストワンマイルまでの直輸送)の大きさを理解することができます。 【コンテナ輸送のポイント】 ・如何に多くのコンテナを効率的に運送し、行き帰りで積載量を最大に近づけることができるか ・コンテナ輸送には特別な技術的ハードルもないため、先行者利益が小さく、完成したシステムを大規模に展開できるか →現在繁栄しているコンテナ港でも後発新興国の脅威から逃れるためには追加の投資が不可欠。そのために、「財務管理」と「経営手腕」がモノを言う。 前半~中盤は正直に言ってかなり眠たくなる内容も多く、読み飛ばした部分もありました。しかし、第13章「荷主」からの内容は読みごたえもあり面白かったです。 序盤で躓いてしまった方は何とか13章までたどり着いてほしいなと感じた一冊でした。
0投稿日: 2023.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナが物流をどのように変えたか、業界がどのように変わっていったか詳述した一冊。 物流を通じて物を運んでいる方々にとっては興味深い一冊。現在にも通じるボラティリティの高い業界の一端を垣間見ることができる。 ちなみにKindleで購入したのだが、ページ数が多いため読破に難儀した。
1投稿日: 2023.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログThe BOX コンテナ物語 本書の構成 コンテナの影響が最初に述べられ、普及した背景が述べられていく。そして、現在起こったことに対する見解が述べられる。 経緯に対しての感想 システムの開発から統一までの経緯が本書には詰まっていた。 マクリーンのアイデアの影響範囲を広く捉えるという視点は良いと思った。(コンテナなら、自社コスト削減どころか、海運のシステムを変えられるなど。) また自社だけだと資産や影響力に限りがあるので、以下に他社を巻き込みチャンスを掴むのかのが大切かもわかった。(軍しかり、投資家しかり。)さらに普及の過程では、totalで仕事の生産性は増すとしても(理解している人も少ないかも)、雇用の安定性、競合他社自身の利益など、普及の阻害要因は沢山出てくることがわかった。しかし、現代社会においては技術の進展による解雇は経営者側が有利と思われる。特に日本だとストライキも起こらないので。 いかに先駆者利益を勝ち取るかという点においては、港の設置はプラットフォームビジネスだなと思った。さらにそこで差別化や付加価値の提供が出来ると強いor 必須。 現状(&結果)に対しての感想 コンテナ化により、運賃コストは下がり、輸送の信頼性、安定性は向上した。 規模の経済を拡大させていくと、格差は広がるなと感じた。安いところは悪循環で発展しにくい。しかし、成功者もまた拡大にはリスクを抱えている。やがて生き残るものは少なくなる。 物流の進化により、市場のグローバル化が加速したのは間違いないと思った。海外品が入ってきて、価格競争に嫌でも巻き込まれる。また逆に自社は海外に拡大できる。 第1章 最初の航海 物体の価値は使われ方にある。最小限のコストで貨物を運ぶ高度に自動化されたシステム。その主役がコンテナ。 コンテナにより、工場の位置が都心から地方に変わり、グローバル化も進んだ。(勝手にもう巻き込まれる) コンテナ港は、ほとんどコンピューターにより制御されている。人為的ミスが入り込む余地がない。 輸送費は今では本当にわずか。 本書では3つの研究テーマを重ね合わせた。「輸送技術の変化がもたらした影響」「イノベーションの重要性」「輸送コストと経済地理学との関連性」 第2章 埠頭 コンテナ登場以前は、港の荷役作業は危険で労働集約型だった。 トラック対抗のため導入されたコンテナだが、初期は相変わらず沖仲仕がいり、コスト節減には繋がらなかった。 第3章 トラック野郎 マクリーンは最初トラック輸送業者から始まる。ルートの認可よりも借りると言う発想で、ICC(利益よりも安定を優先の州際交通委員会)の規制を回避。会社を成長させ、高速の渋滞回避を考えていた時に海上輸送の方法を考える。ターミナル用地はちょうどよく見つかる。トラック運送会社が船会社はできないので、別の会社に資産を移し、その後アメリカ初のLBO(レバレッジバイアウト)を行う。LBO後は、不要資産の整理も行なった。 そして、さらに大胆なコンテナのアイデアを思いつく。スペースが無駄だからトラックから車輪を取ればいい。 マクリーンは輸送コストの圧縮に必要なのは、単に金属の箱ではなく、貨物を扱う新しいシステムだと理解していた。港、船、クレーン、倉庫、トラック、鉄道、そして海運業そのものだと。 第4章 システム セルとクレーンの改良。 続いて、物理学者によるアプローチの紹介。コンピューターのシミュレーションを用いて、コスト削減などの計算をしている。またコンテナの寸法(作業時間と無駄なスペースの関係から)も決めている。クレーンは岸側に設置。 マクリーンはプエルトリコの航路を独占。その過程で、現地を支援する子会社を設立したり、政府重役への配慮を行なったり抜かりない。またすっかり大企業になっても、コスト意識は相変わらず高く、またビジネスマンとしての言動・行動も伴っている。 第5章 ニューヨークvs ニュージャージー ニューヨーク港 vs ニュージャージー港でニューヨーク港が時代の流れに背き、衰退していく様子が書かれている。 ニューヨーク港は、1950年代前半には栄えていたが、内陸輸送費、ストライキ、犯罪、施設老朽化により衰退の一途。ニュージャージーは、港湾局に、マクリーンも巻き込めた。 コンテナは職業や工場立地に大きな影響。 第6章 労働組合 沖仲仕の労働組合は、機械化により仕事が減るのではないと懸念。さらに、機械化による恩恵を還元しろと要求。結局海運側は、雇用保証などお金を払うこととなる。ただ、それ以上に機械化の利益はあった。ただ、このように機械化の恩恵を、経営側と労働側で分かち合うのは珍しい例だった。 第7章 規格 各社コンテナのサイズが色々あったが、これではコンテナにあった船やクレーンがいることになり、非効率である。しかし、コンテナの規格化は、各社の最適解があったり、鉄道などの影響が及ぶ範囲も広く難易度が高い。 まず、長さは複数出すことにした。そして、組み合わせがいいよう長さはに10、20、30、40フィートとした。さらにISOにより、欧州側で主だった小型も追加される。なお、コンテナの先駆者のパンアトランティック海運とマトソン海運のコンテナはいずれも規格外になった。ただ、後に綺麗な数字よりも市場で役立つ数字ということで追加された。また固定具などの問題は有用なもので統一された。最適といかないまでも、コンテナ普及のために妥協して決定されていった。 第8章 飛躍 マークリンはお金がないが船が欲しかった。そこで、お金があり造船技術も持っている会社とうまく提携して、船を確保した。(これまでは、新たに船を作るよりも中古の軍用の船などを安く買っていたほうがコスト的によく市場にはコンテナ非対応の船が多かった。)そして、実績を出し普及。 しかし、アメリカの鉄道会社は、現状うまく行っている有蓋貨車を守るため、コンテナの設備投資を回避するために、非協力的なままだった。 第9章 ベトナム 当時兵站が課題であった。ベトナムの港は数も少ない上に、整備もされていなかった。 そこに、業界を革命していたマクリーンが呼ばれて、さらにコンテナアイデアを大将に直訴して、結果で認めさせた。軍は最大の支援者になった。 第10章 港湾 コンテナの普及により海運会社にとって、どの港にも立ち寄る時代は終わろうとしていた。建造にカネがかかり、必然的に効率を命とするコンテナ船は、大量の貨物を高速で運ばなければ利益が出ない。したがって、大量の貨物が確保でき、スムーズな荷役な補償される港でなければコールする価値がなかった。つまり、コンテナ輸送が盛んになる程、海運は少数の大型港に集中し、港は生き残りをかけて競走する必要が出てくる。 西海岸は、もともと地理的要因から冴えない状況が続いていて、コンテナの可能性にいち早く気づいた。(当時、貿易はヨーロッパ中心で、アジアは戦争や政情不安、内陸の需要も西海岸は薄い。)コンテナ以前は、健全な地方経済を支えるのは製造業だというのが常識だった。一方、港の価値は輸送需要の大きい製造業が近くに立地するかで決まっていた。ところが、コンテナの出現により、「もはや物流は、生産と消費を結びつけるだけの他業種に依存した産業ではない。独立した産業として逆に生産と消費のあり方を決めるのが、物流である。」とされた。また「市内の産業と港との距離が近いことは、もはやさしたるメリットではない」とも言われた。 一方、東海岸では、労働組合と予算の観点からコンテナ普及が遅れた。(ニューヨークでは年間所得保障と引き換えにギャングの人数削減を労使が合意している。)。そしてコンテナ輸送萌芽期中に、出遅れた港はフィーダー港(支船港)になった。 コンテナ化の流れは海外でも起こり、欧州全体やイギリスでも大きく勢力図が変わった。シンガポールも力をつけた。 第11章 浮沈 1966年の春に国際コンテナ輸送が始まり、1968年には、ロッテルダム(オランダ)、ブレーメン(ドイツ)、アントワープ(ベルギー)、フェリスクストウ(イギリス)、グラスゴー(イギリス)、モントリオール(カナダ)、横浜、神戸、サイゴン(ベトナム)にはコンテナの設備が整った。 設備投資にお金が必要な中、アメリカにはコングロマリット(巨大企業がいた)という味方がいた。マクリーンは、公定運賃ならば集荷で差をつけるのはスピードとして、船の建設に力を入れる。そして、地元のよしみもあるタバコ会社に身売りして、お金を調達することに。 同時に世界では船の建設ラッシュが起こるが、供給過剰に陥る。すると、値下げ競争という苦痛に満ちた局面に突入することになる。しかも、設備投資のための借金を抱えながら。運賃体系が崩壊すると、船会社の利益は当然減り、業界再編が起こった。また競走の制限とちう解決策にたどり着いた。しかし、景気低迷や供給過剰になれば必ず再発すると考えられ、運賃は輸送コストギリギリまで下がるだろう。すると、ローコスト体質の企業の方が生き残れる可能性は高く「もっと大きくもっと速く」というプレッシャーが企業にかかるようになった。 しかし、オイルショックにより燃料費が高く取られる船はかえって不利になった。マクリーンは、運輸業は資本集約型で景気やライバルなどの外的要因を受けやすいとして、タバコ会社からスピンオフされた。独自技術から次々にヒット商品を生み出し数十年にわたって高利益を上げ続けるのは難しい。 第12章 巨大化 船が大きくなり、港も巨大化する必要が出てきた。港の、問題はサイズであり、立地でなくなった。かつては、貨物を一旦そこで堰き止め、改めて送り出すことで繁栄していた。港の背後に控える内陸部と経済的に密接に結びついていた。しかし、コンテナ時代には、ごく少数の港に立ち寄るのみ。荷主は始点から終点までにかかるトータルコストが一番安いルートを選ぶようになった。 またリスクを背負いながら借金を払い続けることが負担になった政府は、民間に売り渡された。この頃(1980年代初頭)には、民間も資本を調達できるようになっていた マクリーンはスピードが遅く(オイルショックの反省から)巨大な船を注文するようになる。しかし、1980年代石油価格は大幅に下落し船は場違いに。負債も溜まり、ついにユナイテッドステイツ海運の持ち株会社(マクリーンの会社)は破産する。ついに、マクリーンはこの破産に耐えられなくなり公から姿を消した。しかし、彼への敬意は皆忘れていない。 第13章 荷主 コンテナの影響を最初に受けたのは、海運業界(船主、港、港湾労働者など)。コンテナ革命の最も重大な影響が現れたのはもっと後。何をどこで作ってどこで売るか、何かを輸出または輸入した時に割りに合うかを考える時に、運賃が非常に重要な要素だった。この重みを変えた時、世界経済を様変わりさせた。 コンテナの影響を考えるには、海上運賃の他、陸上運賃、梱包、倉庫、港湾使用料、保険などさまざまに考えなくてはならない。陸上運賃以外はコンテナ化により確実に削減された。 またコスト削減に寄与しているのは、荷主の存在もある。盟外会社が行き交うようになったこと、また運輸業の規制が緩和されたことで、荷主の力が強まった。 そして、こうしたコスト減少の結果、消費者は多大な恩恵を被った。 第14章 ジャストインタイム ジャストインタイムに代表される定時輸送は、コンテナの存在が大きかった。貨物を1個1個人力で運び、港に何日も停泊し、船からトラックへ、トラックから鉄道へま、受け渡しに煩雑な手順を要する時代では、「いつ着くか」を予想することは至難の業であった。よって、生産ラインを安定化させるには、在庫をたくさん抱える必要があった。 輸送の安定性・信頼性が増加すると、企業は人件費の安い海外に拠点を移すようになり、労働集約的な作業は人件費の安い国で行うようになった。しかし、サプライチェーンに組み込まれるためには港が必要。アフリカは人件費は安くても港がなく普及してこなかった。 コンテナ革命は1980年代前半で終わったが、その余波は30年経っても続いている。欧州でも日本でもアメリカでも、安価な輸入品が高価な国産品を押し除けるようになった。先進国で物価が下がった。 旧態依然の港や非効率な港に呪われた国は、グローバル経済で躍進を遂げようにも致命的な障害を抱えることになる。 巨大化もデメリットはある。建造に巨額の融資を伴うため、十分集荷できないと採算が合わない。またコール回数が減り、港のインフラが放置されることもある。 最近では自動化の進展がめざましい。 第15章 付加価値 港の選ばれ方は、トータルで見たコストや所要時間が他のルートより有利だからという理由に尽きる。だから港は、貨物の通過を円滑化・迅速化することで存在理由を強化しなければならない。アントワープら、艀輸送サービスの拡充で港としての魅力を高めた。 コンテナが引き起こす3つの社会問題。① 放置された大量のコンテナ ② ディーゼル燃料で動くコンテナ船やトラックなどの排気ガス ③ 公安当局の頭痛の種(テロ・コンテナ、人間コンテナなど)
0投稿日: 2023.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950〜2000年代にかけてコンテナリゼーションの変遷を学ぶことができました。コストがかかる海上輸送において、より効率的なコンテナ輸送を実現することで世界的に経済発展を促し、埠頭での雇用や設備環境を大きく変えてしまったのは非常に面白かった。ベトナム戦争を皮切りに、コンテナ活用の押し上げ、日本を経由することで空のコンテナの有効活用、ジャストインタイムによるグローバルサプライチェーンの実現など多様な歴史を知ることができました。付加価値をつけながら次なるフェーズへの発展という点では、多くの企業が学ぶべきステップアップだと感じました。
0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この書籍は、世界中でコンテナ輸送が成り立つまでの道のりが記されています。 コンテナが発明される前は荷物を船内に秩序なく詰め込み、沖仲仕が人力で運び出すというスタイルであった。 人力では効率も悪く、人件費もかかるということで、トラック運送業者のマルコム・マクリーンがコンテナを発明。 しかし、発明当時は受け入れられなかった。コンテナのサイズ、船までの輸送、港湾の整備に問題があるからだ。 コンテナの規格化、港湾整備、ガントリークレーンの建設等、現在では当たり前となった設備が開発、運用されるまでの物語である。 まさに、「箱」の発明が世界を変えたのである。 コンテナ、海運業界に従事し、興味ある方は必読です。
0投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界を繋げたのは、箱でした。 インターネットで情報は繋がった。 飛行機や電車、車で人は繋がった。 そして、物が規格化されたコンテナで繋がった。 コンテナで繫がることで、生産地から加工地、消費地とシームレスに繋がることになった。 まさに、世界経済圏。 コンテナで繋がることで、世界の港と世界がどう変わったのか。 そして、古い海運と新しい海運の闘い。 私の頭の中にある、港で船乗り海運世界はずーっと前になくなってたんだと世界をアップデートできました。 港を見に行きたくなりました。
0投稿日: 2023.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ船の物流にかかせないコンテナについての歴史本。 評判がやけにいいので読んでみたのだけど、ただコンテナについての歴史を書かれてあるだけなので、自分はちょっとささらなかった。 物流のイノベーションの物語ではあったのだけど、特に技術的に目新しい感じではなかったし。 せめて、もうちょっと写真や図がほしかったなと思う。 コンテナの歴史を語るうえで、「マルコム・マクリーン」という方が重要だということがよく分かった。まあ、コンテナという概念自体は前からあったようなので、この人がいなくても近いうちに誰かがコンテナ船を作っていたとは思うけど。 とにかく、マクリーンの功績によって、船による物流コストがかなり下がったらしい。海外から港から港へ運ぶより、内陸部へトラックで運ぶ場合のほうが高くつくこともあるよう。まあ、トラックだと量が少なくなるしね。 ただ、この分野については無知ということもあって、いろいろ意味がよく分からない言葉も多かった。「艀」ってどういう意味でいったい何と読むのかとか。調べてみると「はしけ」と読むらしく、大型船がとおれない浅い水面で貨物を運べることができる船らしい。いろいろ工夫はされてたんだなぁ。 最初は機械化に反対していた組合が、機械化が進むと楽になるからと「早く機械化を進めろ」と言い出したという話にちょっと笑った。ただ、それは残った組合の人がクビにならなかったからだとは思う。 日本についての話もいくつか書いてあって、1970年前後には、横浜は神戸でコンテナターミナルが建設されて、アメリカ西海岸までの定期輸送が開始されたのだとか。そのころは日本は高度成長期で、着眼点も良かったんだろうと思った。 他に、日本の話だと、初期のバービー人形は日本製だったとか。それがリカちゃん人形に繋がったりしたのだろうか。 あまりアフリカについての話がでてこなかったけど、アフリカにも早くからコンテナ対応の港ができてたら、もっと発展してたのかなと思った。これから増えていくのかな。
0投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナ船を発明したトラック運送業者マルコム・マクリーンの果敢な挑戦を軸に、世界経済を一変させた知られざる物流の歴史を描く。 図書館スタッフ
1投稿日: 2022.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログひろゆき一推しということで購入。 いかに既得権益が存在している中で革命を起こすのが難しいか、革命が始まると一瞬で世界が変わること、コンテナが当たり前の時代になり、市場がコンテナで溢れかえると逆に低価格化競争によって利益が生まれにくくなること、輸送費が下がったことでものづくりが現地生産では無くなったこと、成功には運も必要なことなど、学ぶことが多くおもしろかった。 また、非常に学術的にまとめあげた筆者に拍手をおくりたい。
0投稿日: 2022.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論としてはタイトルに全てがあるのだろうなと思っている。「The BOX」。結局はモジュール化するという事が様々な効率を最大限に上げるという事なんだよ。単位を統一する事で全てがそれに則って動けるようになるんだよ。めちゃくちゃ哲学的に深いのではないのかこの結論は?応用がありとあらゆるところに効く。本当にコンテナ輸送を考えた人は天才だったな。途中なかなか読み進められないので何故だ?と思っていたのだが半分読んだところで、この物語がアメリカ国内ベースだからだなと気がついた。そこが発端でそこは他の多くの国の港に通じるだろう事はわかるけれど個人的にはその辺は端折って世界レベルでの話で読みたいのだなとわかった。 考えてみれば当たり前なんだけれどパナマックスと呼ばれる巨大コンテナ船が出てきたのはここ数十年の話だし、コンテナ輸送自体も歴史的には60年程しかないという事実にあらためてなんかびっくりしていた。本の最初1/3はアメリカでコンテナ輸送が始まってから現状を維持しようとする勢力とのすったもんだが主だったのもあり、個人的にはラストの様々な港の名前が出てきた現在の話のところが面白かった。結局ユニット単位で物事を捉えるというのが物流の今の流れだし、ユニット単位にすると言う事は世界標準が必要とされるという事だし、標準が発生するという事はその標準を最も効率よく維持できるところに全てが集中するという事なんだよな。 コンテナだけの話としてではなく現代の物や情報の流れとしても非常に示唆的でよかった。
1投稿日: 2022.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の物流と小売業を大きく変えた陰の立役者であるコンテナの発展の歴史に触れた著。非常に専門的であり、日の目を見ない役割であるコンテナに見事に日を当てている一冊だった。
0投稿日: 2022.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「現代のワールドサプライチェーンを作ったのは紛れもなくコンテナである」 マルコムマクリーン=トラック野郎が時代を先取りしまくっていく様子が痛快に記されている。 「コンテナより、コンテナで輸送する仕組みこそがイノベーション。」 「発明はされていても、それが使われるようになるまで時間がかかる。」 ビジネスの根幹を思い出させるフレーズも登場する。 コンテナ普及までの困難は以下の通り。 ・沖中士組合との対立 ・規格化:コンテナサイズから荷役機器、金具に及ぶ ・ICCの妨害 ・鉄道輸送との対立 ・ベトナム戦争 ・供給過多 ・規模の経済を活かすためのコンテナ船巨大化 ・バービーちゃんはコンテナがもたらした産物 中でも14章ジャストインタイム、15章付加価値の内容は一番面白い。コンテナが世界の製造業、貿易を変えたことを確信させてくれる。 コンテナに関わる方、すなわち全世界の消費者にとって価値ある1冊。
0投稿日: 2022.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ箱が世界を変えた。 いまや当たり前のように物流でなんでも届けられるが 鉄道、トラック、船と、コンテナと共に輸送量を上げてきた歴史が分かる。 400ページ越えでボリュームあり読みきれないのが残念
0投稿日: 2022.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
マクリーンの発想をきっかけに、労組との対立、凝り固まった慣習、業界内外からの反発等々を乗り越え、運賃の価格破壊や軍需、規制緩和による自由競争を経てこんにちの物流網・供給網、経済構造はコンテナによって形作られた。 最近はサプライチェーンマネジメントが~なんてよく言われるが、そもそもサプライチェーンという発想自体がコンテナによる物流網の確変が無ければ存在し得なかったという事実を忘れないようにしておきたい。
1投稿日: 2022.08.20否応なく放り込まれた競争の荒波
読んでて遠い目になるというか、何とも途方もないスケールで、マラッカマックスという世界最大のコンテナ船になると、全長400m・幅60m・喫水18mの鋼鉄の塊が海に浮かんでるそうな。 とてもじゃないが想像を超えているし、ちょいちょい映像があればもっと楽しめるだろうなと感じる部分があって、BS海外ドキュメンタリーかディスカバリー・チャンネルにないか探してみたい。 こんな船が万一沈没したら20億ドルものの損害らしくエゲつないよな。 "じゃあ、コンテナの中身は何?"というと、実は世界の海を運ばれるコンテナの約20%は空だったりする。 残り8割のコンテナにしても、その中身は完成品なんてほとんど入っていない。 バービー人形の髪の毛だったり、ネジやレバーだったりと、次の処理を必要とする仕掛品がほとんどらしく、開封してもガッカリするだけかもしれない。 ただ、開けてみるまで何も分からないという意味では、コンテナは「核物質、麻薬、テロ用の爆弾から不法移民にいたるまで、不正な品物を忍び込ませる格好の手段」になっているとも言える。 将来、ニュートリノ探知機が配備されて鋼鉄の中までスキャンできる新技術が開発されるまでは、書類上の確認だけで済ませるしかない。 全長がサッカーコートを何面も並べたよりも長い、フルコンテナ船に乗船している人数は、驚くほど少ない。 人件費という点では、乗組員だけでなく、港湾労働者にかかる費用も激減した。 盗難や破損も少ないから保険料も安くなったし、その他諸々の費用も切り詰められた。 コンテナの導入で、この荷役コストが大幅に削減されたにもかかわらず、実は当初、輸送コスト全体の大幅削減にはつながらなかった。 なぜかというと、コンテナ輸送のカギを握るのは、量だからである。 量が多ければ多いほど、1個当たりの輸送コストは下がる。 貨物がいっぱいに詰まった35トン・コンテナ1個の運賃は、「ファーストクラスの航空券1枚よりも安い」のだが、大型コンテナをいっぱいにするだけの貨物はなかなか集まらなかった。1960年代のほとんどのメーカーは、コンテナをいっぱいにできるような生産方式をとっておらず、だいたいは注文を受けてから生産し、そのたびに送るというやり方だった。このように、コンテナのメリットや可能性を生かす態勢が、海運業者だけでなく輸送業界全体、ひいては荷主まで含めて、整備されるまではずいぶんと時間がかかったのである。 「荷主が出荷する段階でコンテナをいっぱいにし、そのまま荷受人の元まで運ばれてはじめて経済効果が最大化される」のだ。 ただ大きな箱を船に詰め込んだだけでは、ほとんど意味がない。 海運輸送だけでなく、内陸輸送のコストも合わせて引き下がらないと駄目で、そういう意味で、港・船・クレーン・倉庫・トラック・鉄道など、すべての要素が変わらなければ輸送コストの圧縮につながらなかった。 「コンテナリゼーションはシステムである。コンテナの全面活用を念頭において設計されたロジスティクス・システムで使われてはじめて、効果は最大化される」 コンテナリゼーションは世界経済を様変わりさせた。 ただの「箱」が国際貿易量の増加に果たした役割は徒法もなく大きいし、地理的条件の意味合いも一変させている。 輸送費が取るに足らないコストとなると、サプライチェーンはいくら延びてもかまわないことになる。 積出港は必ずしも人口が多く、後背の工場と近接している必要はなくなった。 地理的条件に縛られなければ、コストは安い方がいいに決まっている。 アジア各国が「世界の工場」となった理由もここにあった。 ただ、人件費が安いのはアジアだけではない。 なぜアフリカやその他で繁栄しなかったのか? この答えも、コンテナリゼーションが地理に与えたもう1つの影響にある。 というのも、荷主の立地によって、輸送コストが大幅に下がる場合と、そうでない場合が出てきたのだ。 内陸で経済規模が小さくコンテナ輸送に見合うだけの輸送需要を持たない地域は、混載貨物時代よりも厳しい状況に追い込まれようになった。 また、港湾の近代化を怠った所も、貿易量が減るだけでなく、主要港から外され、2流の扱いを受け、ひいてはすべてのものが割高についてくる。 ただの箱が、一国の経済をグローバル・サプライチェーンに結ぶ媒介役を果たしているのである。
0投稿日: 2022.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほどそれでうまくいくわけか! と膝を打って納得できない仕組みの部分は自らの知識の無さと頭の回転の遅さと恥じる。
0投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションというと、ついGoogleやAppleなどのビックテックを想像してしまうけど、本当の意味でのイノベーションは人々の生活を変えるためにエコノミクスが合うように社会実装する事を指すのではないかと気付かされた
0投稿日: 2022.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログロジの大切さがよくわかる。マルコム・マクリーンという天才について知ることができたのも収穫だった。なぜドバイが急に発展したかも腑に落ちた。
1投稿日: 2022.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。 リアルガチのイノベーションの本。 物心ついたころ最寄駅には、コンテナを乗せた貨車が無造作に停めてあった。コンテナは大昔からあると思い込んでいたが、商用化されてから70年ほどの歴史。
1投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナがいかに世界の経済を変えたかが感じた。 日本が貿易に強くなり始めたのもコンテナのおかげだった。もう少し背景をなぜ?と考えられるようにしておきたいと思った。 詳しくはメモ欄に 今各地で自動化AI化の動きが出てきている。 ここからは考察だが、GPSのチップみたいなものを使用してより効率的になるではと思う。
0投稿日: 2022.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大量のコンテナが積まれた風景というのは、幼少の砌より馴染み深いものだった。 自分にとって当たり前だった風景がその技術が生まれたときには決してそうではなかったこと、そしてその技術が文字通り世界を変えてしまったことがひしひしと伝わってくる。 規制業界における変革の難しさ、それ以上に回り始めた弾み車を止めることの不可能さ。政治的なダイナミズムについても考えさせられる、実にエキサイティングな一冊だ。
0投稿日: 2022.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナという規格が世の中に普及されていくかが丁寧に描かれた物語。長い歴史をコンテナを取り巻く海運を中心に陸海、港湾、政治家、規格者、荷主さまざまな立場で描いている。 単に規格の話に小さくまとめず、丁寧に外部環境を描いたひとつのマーケティング歴史書といった感じ
0投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さな箱の発明が、世界の物流を激変させ、やがてグローバル・サプライチェーンを生み出すに至るまでを記した物語。 イノベーションが生まれて世の中を変えていくまでの様子が克明かつ、ナラティブに描かれていて面白い。個人的にはコンテナ生みの親・マクリーン氏の生涯に興味を持った。映画化したらいいのに!
0投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ箱の歴史一つから得られる教訓は非常に多く、非常に興味深い内容だった。 本当の環境変化は、イノベーションそれ自体ではなく、それを受け入れる"人"によって形成される。そのキーになるが金(=コスト)であり、それを阻害するキーになるのも金(=賃金・雇用)である。 先見の明のある人間の奮闘により、壁(=地理的条件、慣習、既得権益等)にぶち当たりながらそのイノベーションを活かせる全体的な"システム"が形成されていく。そしてそれが機能することが証明されると、そこに生まれるコストメリットが顕在化し世の中は一気に変わる。 著者は外交問題評議会出身の肩書きの通りグローバリズムに肯定的なバイアスはあるが、今のこの生活があるのは、民間のビジネスマンの儲けたいという野望がコンテナリゼーションをもたらしたことにあることは間違いない。そこで、既得権益集団は反発を繰り返しながらも、その変化に乗り遅れる危機感を感じた時から徐々に受け入れていくわけである。しかし、この反発によりラディカルな雇用崩壊を防いでいる面もあるわけで秩序維持には必要な役割である。 人の生き方といった哲学的思考がシュリンクした中で進むAI化、機械化は、ビジネスメリット(=コストメリット)だけが追い求められる懸念がある。 そこで、国や中間共同体が既得権益(=人々の生活)を守るためにある種の抵抗をしながらアウフヘーベンしていくことが、少しづつの進歩、少しでも"マシ"な世の中を形作っていくために必要なことだと感じる。 "効率"を求めるイノベーターと"秩序"を求める既得権益者のぶつかり合いは必要不可欠であり、そのパワーバランスをいかに良い塩梅で進めるかがこれからの世の中のキーになると感じた。 その他、戦争の影響力、国際規格の無力さ、有能性のわな、門外漢の参入による破壊、自由主義の功罪、かつての日本の存在感、コンテナの抱える課題など、様々な観点で得るもののある良書であった。
0投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の仕事に大きく関わる内容なので前から興味があった。物流業界で働く中で感じてた事(不確実性の極み)など、すごく共感できることもあったし、サーチャージ徴収の話とか今も昔もかわらないんだなっと思った。コンテナという世界標準規格が出来たことによる世界経済への貢献は計り知れない。今の海運混乱の状況も考えながら読むとより面白い。標準化の影響で、他航路の問題が全世界に影響を及ぼすほど、海運は全世界の公共インフラとして重要な位置づけにあると実感した。
0投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログビックリした。「箱」がこんなにも世界を変えているのか、と。 箱だけでこんなに話が深くなるとは。箱が既存の仕事を奪ったり、経済に影響を与えたり、歴史を変えたり。 長編なので読むのに時間はかかるが、時間がある時にもう一度読み直したい一冊。
0投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろなところで、読むべきビジネス本として挙げられている本。 小さな運送会社を起業したマルコム・マクレーンが、海運業に進出し、コンテナが世界の海運業を変えていく時期を、アメリカの国内事情から世界情勢まで含めて描写している。 印象的なのは、トラックだろうと船だろうと、運ぶものは同じというマルコムの思いが、業界を変えたということ。その考え方自体は昔からあったとも言われているが、実際にビジネスを変えるきっかけになったのは彼だと言ってもいいだろう。硬直化した業界を変えたのは、異業種からの参入だったこと。そして他社買収から巨大企業への会社売却、その後の破産から再び業界へ参入するというマルコムの起業家精神。 星一つ減としたのは、すでに世界の経済情勢の変遷と同時に内容が古くなりつつあるからだ。何しろ原書の発行が2006年、改訂版は2016年発行(私が読んだのは改訂版)。前からこの本の存在を知っていたにもかかわらず、実際に読む段階までたどり着けなかった。2026年には再度改訂版が出るだろうか。
0投稿日: 2022.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ1 なんで読んだの? (1) 友人の勧め (2) 新しい興味、読書力向上 (3) カテゴリー本のレベルを理解し次の選書に活か せる状態 2 どんな本? 全15章構成でただの箱の生い立ちから始まり付加 価値で終わる。コンテナがいかにして世界を変貌さ せたかを綴っている本 3 問題提起 問題提起してない。 4 命題に至った理由 書いてない。 5 著者の解 解無し 6 重要な語句 (1) 沖仲仕 (2) コンテナ (3) ILU、ILWU (4) ロジスティックス (5) ジャストインタイム 7 感 想 単純にこれを面白いと思える人はとても頭が良い と思う。理解しやすい文章で分かりやすいが面白い 事ではないので、海運や経済に興味がある人で無け れば面白いと思えるものではない。斜め読みとか出 来なかったけど初めてチャレンジできたのが収穫。 内容的には勉強にはなった。人にお勧めはしませ ん。賢い人には勧めたいけど、賢なひとにお勧め聞 かれる事は無いと思う。 8 todo この手の本に出会ったら斜め読み。
0投稿日: 2021.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログまず全体の感想 これを「面白い」と断言できる人は物流システム(特に海運)好きか、IQが高く論理的思考の人だと思う、ということは最初に言っておこう。 自分はというと、示唆に溢れていて面白く感じる部分もあったがレビューや評判程には楽しめず。大量のデータや資料にも関わらず読みやすく仕立てているのには感嘆するが、マルコム・マクリーンの人間性以外に面白味は感じず、数字を読み解いてふむふむと楽しむ迄には至らず、どうやらIQが追いついていないらしい。読み切った達成感は得られたのと、時代の流れやシステムの変化に柔軟に対応しようという気持ちにさせてくれたのでやや高評価に。 新たなシステム(コンテナ)によるグローバル化。コンテナ運輸の躍進により海上輸送コストが急落。コストがもっとも安いところ(国)を選んで発注発送できるようになった。 コンテナに仕事を奪われた港湾で働く人々は、まるで現在のITやAIやグローバル化に仕事を奪われる様にとても似ている。システム化を市場に問えば自然とお役御免になるだろう。それから、マルコム・マクリーン氏。彼の自伝でも出たら読みたいほど魅力的。野心的でバイタルが溢れ先見性が凄い。海運を船を行き来させるという業界の当たり前の感覚から、海運を物流のシステムの一つとして新しい捉え方と当時としては当たり前ではない考え方、それをすぐさまコストとふるいにかけて実行する行動力。組合や様々な規制に、変えられる物は変え、変えられない物は柔軟さとアイディアで乗り切る様は凄まじいものがあった。 もしもマクリーン氏がベトナム戦争当時の輸送ビジネスで日本に寄港することを考えなければその後1970〜のジャパンイズナンバーワンはなかったかもしれない(エレクトロニクス品は荷分時よく盗難にあうし輸出コストが高かった)。
0投稿日: 2021.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログー 「コンテナは単なる輸送手段の一種と考えるべきではない」とベッソンは1970年に議会で力説している。「コンテナリゼーションはシステムである。コンテナの全面活用を念頭において設計されたロジスティクス・システムで使われてはじめて、コンテナの効果は最大化される」。これは、民間の荷主がようやく気づき始めた事実であった。 ー すごく自明で当たり前のことが、当たり前と受け入れられるようになるまでの物語。これは小説にしても面白いけど、これでも十分に面白い。港、港湾のお仕事、船、海上輸送、コンテナリゼーションの歴史がよく分かる作品。
1投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ単純化・規格化する事で世界が変わったっていう本。 楽になるしコストも下がると解っていても、既得権益、先行投資、タイミング等、諸々の事情で簡単には前には進まない。 「海外からの荷物が何でこんなに安いんだろう」と漠然と思ってた疑問に過去の膨大なデータを元に答えてくれる本で読んで良かった本ではあったんだけど、途中から前に書いてあった話の繰り返しが気になった。 あと、この本ではあまり言及されてないけど、自分も輸送コストが下がった事で日々の恩恵を受けている事を自覚しつつ、それがもっと長い目で見た時に人類や地球全体にとって「コンテナの発明」は良かった事なのか、という点が気になってしまった。
0投稿日: 2021.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナの歴史およびその普及が与えた経済的影響をデータを元に解説している本。 AIやITの発展によって刻一刻と産業構造が変化している昨今において、この書籍が与える規格化の重要性に関する知見は、ビジネスパーソンや就活生に対して有用ではないかと感じた。
0投稿日: 2021.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界中のコンテナが揃って同じような見た目とサイズである事実を、今まで一切気にしたことがなかった。最初から各国仲良く揃えたのではなく、長い歴史と苦悩の間に世界で統一されるようになったのだ。となると他のものはどうなのか気になってくる。例えば飛行機も世界中で同じような見た目とサイズが採用されているが、これにもコンテナのような葛藤と改革があったのだろうと思うと感慨深い。
8投稿日: 2021.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代後半から起きた、コンテナ普及による物流の革新について触れた本……と書くと本書が物流分野のビジネス書で、物流の仕事をしている人以外には関係がないように思うかもしれない。ただ、その先入観でこの傑作を読み逃すのは、あまりにもったいない。 コンテナ物流が普及する前は、海運は小口の荷物をバラバラに積んでいたため、非効率な輸送手段だった。とにかく時間がかかる港での積み卸し作業(大型船だと、数日かかる場合も!)、揺れによる積荷の破損、仕事をしてくれない港湾労働者(組合が強い港では、労働時間の半分が休憩時間ということも)。海運業界自体がカルテルと政府からの補助がベースの、文字通り護送船団方式で、改善の兆しもなかった。 それが「規格化されたコンテナにあらかじめ荷を入れて、コンテナごと目的地まで運ぶ」という方法の普及によって、様変わりした。まず、船への荷の積載量が増えた。積卸作業はクレーンとコンピュータで効率化・自動化された。荷を港で保管するときも、倉庫などを必要とせず、そのまま積んでおけば良い。積荷の破損も少ない。何より、大量の貨物を一度に大型コンテナ船で運送し、港でトラックや鉄道にコンテナを機械で乗せ替え、そのまま目的地に運搬できるようになったことがメリットだった。コンテナのおかげで、物流が世界規模で規格化され、時間やコストが正確に計算ができるようになったのだ。これは、工場の立地を考えるうえで、大きなインパクトがある。それまでは、工場は消費地の近く、または原材料の生産地の近くに立地することが多かったが、コスト計算をして予算に見合うのであれば、世界中のどこに立地してもよくなったからだ。グローバリゼーションが、「人・物・金」の国際的な横断であると考えると、コンテナが「物」のグローバリゼーションの大きなきっかけとなった言えるだろう。 コンテナによって、船や港も姿を変えた。船は積載量を増やすために大型化が進み、それを建造できる船社も限られるようになる。かつては国家との結びつきが強かった船社が、国際的な合併が進んで、いまやグローバルな巨大企業しか生き延びていけない。港も大型のコンテナ船が寄港できるような、巨額の設備投資が必要となる。一方で、船の積載量が増えるということは、寄港回数自体は減少するということでもある。港にとっては、設備投資をいかに回収していくかということも争点になってくる。これらは、都市計画にも大きな影響を与える。もっとも顕著な成功例は、シンガポールや釜山である。ここ20年で、アジアの物流拠点として、国際物流に欠かせない存在となった。 一方、本書は、コンテナというイノベーションが、どのように社会に実装されていったか、その苦難の歴史を追った本でもある。コンテナによる労働者削減を阻もうとする労働組合との交渉、コンテナの統一規格化、港湾当局との調整――。どれも一筋縄ではいかないものであり、コンテナを普及させようとする船社のもくろみは、常に想定外の事態に転がっていく。この様子が、とにかく読み物としておもしろい。「イノベーション」というとスマートな響きだが、社会に実装するには関係者との利害調整や、場合によっては妨害を排除するといった泥臭い過程が必要である。本書を読むと、そのことが嫌というほどよくわかるのだ。
0投稿日: 2021.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読了!超長かったけど超面白かった。コンテナなんて当たり前の物だと思ってたけど実はインターネット並みの大発明だった。自分の仕事にはなんの関係もないけど、こういう発想がいい参考になる。読んで良かった!!
0投稿日: 2021.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログニューヨークを拠点にした、ギャングの起源を知ることができる。なるほどそういうことか!そして、偉大なイノベーションを、もたらした、マルコムマクレーン。全く知らなかった…。今なお、物流業界は変化しつつある。
0投稿日: 2021.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ書店で購入し、読了。イノベーションのきっかけや生み出し方が知りたくて読み始めた。ビルゲイツやひろゆきなどもこの本を称賛しておりそれも読もうと思ったきっかけのひとつ。 この本の主題は「コンテナという一つのただの箱が世界を変えている」ということだ。この箱をきっかけに、コスト削減、時間短縮、生産性の効率化、ひいてはグローバリゼーションを育んだ。 特に印象に残ったのはマルコム・マクリーンというコンテナ輸送の父と呼ばれる人物だ。22歳で運送会社を正式に設立し、徹底的なコスト意識とマネジメント力で会社を成長させていった。またこの会社の成功に留まることなく、海運業界にも参入し、グローバリゼーションの流れを担った。そして財務に精通していたマクリーンはアメリカ初のLBOも行った。また彼は海運業界に参入する際、資産を全て注ぎ込んだ。「本気で取り組むには退路を断たなければならない」というマインドがあったからだ。起業家にとって、このマインドは一番大切だと感じた。 電球という発明は実用化までに数十年かかった。発明の経済効果を生み出すのは発明そのものではない。「それを実用化するイノベーションなのである、もっと厳密には、組織制度の変革が必要なのである。」自分は後者を生み出せるような人物になりたいと思った。 コンテナのおかげでベトナム戦争などで物資の供給を可能にしたし、日本の輸出力が高まり経済成長につながった。 「大事を成し遂げるには退路を断つ」 「自分の成るべき姿は発明家ではなく、それを実用化させるイノベーターになること」 この二つを学んだ。輸送の歴史を学びたくなったらもう一度この本を読もうと思う。
0投稿日: 2021.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 2020年の夏ごろから、コンテナ船の運賃が徐々に上がっている。 原因の1つ目はコロナによる物流の停滞だ。本書でも述べられているとおり、コンテナがもたらした革命は箱そのものにあるのではなく、供給者から消費者までの間のサプライチェーンを効率的に融合させたことにある。 コンテナといえば船輸を思い浮かべがちだが、海上移動は運送全体の一部分でしかない。実際には荷主による出荷、トラック・鉄道会社による運送を経て船に積まれ、海上を運ばれる。揚げた先で更に陸路輸送を行い、やっと消費者のもとに届けられる。 この「陸路輸送」の部分が、コロナで停滞した。港にはコンテナの積み下ろし待ちの船が増えていき、遅延がひどく発生するようになったのだ。 原因の2つ目は、単純に需要が増加したからだ。コロナによる巣ごもり需要で、家具や家電を中心にモノの需要が上がった。需要に対して供給元はコロナで歯止めを食らったままであったが、世界の工場である中国のコロナ回復が予想以上に早かった。供給元が息を吹き返すことはできたものの、中国の取引相手である欧米の物流はストップしたままである。これが世界全体に波及し、運賃の上昇が起こった。 ちなみに、コンテナ船業界は赤字が常態化しているという。 2018年には、川崎汽船、商船三井、日本郵船の海運大手三社が定期コンテナ船事業を統合し、「ONE」を設立する。しかし収益の改善は厳しく、その後、海運業界の国際カルテルである「ザ・アライアンス」に参加。業界の再編によりなんとか生きながらえている状態だ。 コロナにより需要がいったん増加したものの、業界全体が回復できるかは分からない。まさに今潮目にいると言っていいだろう。 現状、商船の収益性を向上するためには、「積載量を増やす」か「価格を安くする」の2択であり、過当競争が避けられない。ここから収益性を改善するべくイノベーションを起こせるか。 今や、マクリーンが起こしたような「革命」を、海運業界は再び欲している。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【まとめ】 1 コンテナはいかにして世界を変えたか?(概要版) コンテナが出現する前の世界では、モノを輸送するのは実にカネのかかることだった。輸送費があまりに高くつくせいで、地球の裏側に送るのはもちろん、アメリカの東海岸から中西部に送るだけでも経費倒れになりかねなかった。 コンテナの登場で、モノの輸送は大幅に安くなった。そして輸送費の下落が、世界の経済を大きく変えたのである。 まず、輸送にかかるコストが大幅に安くなることは、輸出品と輸入品の増加を促す。港における作業時間も圧倒的に短くなり、取引のスパンが細かくなる。巨大なコンテナ専用船の荷役は、小さな在来船と比べ、人手も時間も60分の1で済むからだ。 変わったのはモノの値段だけではない。経済のありかたも変わった。 消費地に近いことだけが取り柄の高コスト体質のメーカーを、グローバリゼーションの競争市場に巻き込んだ。地場産業をアウトソーシングに切り替えさせ、世界経済の統合を促したのである。 おそろしいスピードで進行する港での作業によって、コンテナ貨物は全世界をカバーするシームレスな輸送システムを移動していく。1日800キロ移動し、貨物がいっぱいに詰まった35トンコンテナ1個の運賃は、ファーストクラスの航空券1枚よりも安い。港でかかるコスト――貨物を一つひとつ揚げ積みするのにかかる人件費や係船料が切り詰められたおかげで、商品価格に輸送費が上乗せされすぎることが無くなったのだ。 また、時間の節約と正確性の向上も実現する。コンテナとコンピュータの組み合わせによって荷役の時間が驚異的に短縮され、保管の手間がかからなくなった。ジャストインタイム方式で、顧客が必要なときに生産し、コンテナに収めて指定時刻に納品する、ということが可能になった。これによってメーカーは在庫を大量に抱える必要がなくなり、サプライチェーンの信頼性が高まったのである。 2 昔ながらのふ頭 かつて港湾作業が労働集約型産業であったころ、海上貨物輸送にかかる経費の60~70%は、船が海にいる間ではなく、波止場にいる場合に発生していた。そうなると、港湾設備の改善や大型船の建造に投資するのはほとんど意味を成さない。人力で荷役をする限り、作業時間を短縮し港と船を効率よく使うことは到底望めなかった。コンテナが登場してからも、しばらくの間は在来方式よりメリットがあると思われていなかった。 3 マクリーンの登場 海運業の改革は、トラック一台から財を成したマルコム・パーセル・マクリーンの登場によって始まる。 1953年、すでに運送業界のトップランナーとして活躍していたマクリーンはとあるアイデアを思いつく。混雑した沿岸道路を走るぐらいなら、トレーラーごと船に乗せて運べばいい。荷揚げ港には別のトラックが迎えに来て、トレーラーだけをピックアップすれば事足りる。また、トレーラーから車輪を取っ払ってただの箱にすれば、段積みが可能となり、より省スペースで輸送できる。 積み下ろしの際には、船に据え付けられている専用のウインチを取っ払い、ふ頭側にクレーンを設置すればよい。コンテナにスプレッダーを取りつけてウインチで吊り揚げれば、沖仲仕がコンテナの屋根によじ登ってクレーンのフックを固定する必要はない。 なによりコストが低いのだ。中型の貨物船に一般貨物を積み込む場合、56年当時はトン当たり5.83ドルかかったが、マクリーンの船ではトン当たり15.8セントしかかからなかった。 輸送コストの圧縮に必要なのは単なる金属製の箱ではなく、「貨物を扱う新しいシステム」なのだということを、マクリーンは理解していた。 ガンは「海運業界の意識」である。船よろしく変化の遅い環境に慣れきっており、潤沢な補助金のもとで経営をしているため、イノベーションを産もうという土壌もない。マクリーンは海運業界に革命を起こしてやろうと決意したのだった。 4 ニューヨーク港の没落 コンテナリゼーションは、ふ頭に勤める労働者と、ふ頭以外で運輸業に携わる労働者にも多大な影響を与える。港に近いというメリットが用をなさなくなったのだ。ニューヨーク側のふ頭を利用する船の数は減り、トラックの数も減っていく。輸送コスト構造の変化は製造業全体にも波及し、工場が一斉にニューヨークから郊外に移転し始めたのである。 5 規格 米海自管理局は、サイズがバラバラのコンテナ開発に規制をかける。高さに関しては8フィートで各船会社から合意を得たが、幅と長さ、積載量については紛糾する。誰もが自社の流通経路に合うよう、自社製造コンテナのサイズを最適化していたからだ。 その後、長さ10、20、30、40フィートコンテナが米国規格から国際規格になったにもかかわらず、規格外のコンテナは堂々と流通していた。 1965年までは、バラバラのサイズ、バラバラの金具がコンテナリゼーションの発展を妨げていたが、1966年にサイズと隅金具が定まり、国際コンテナ輸送の見通しが立ってきたのである。 6 ベトナム戦争 1965年冬。アメリカ政府はベトナムへの緊急増派を開始し、たちまち物資補給の混乱が始まる。これを解決したのがコンテナリゼーションだった。 当初、ベトナムに積み荷を安全に下すのはほとんど不可能だった。水深が浅すぎて外航船は桟橋に近づくことさえできず、かつ米軍は16種類もの補給方式を運用していたにもかかわらず、中央管理システムの類は一切存在しなかった。港は船でパンク状態になり、ふ頭に揚げられた貨物が何日も野ざらしになっていることも少なくなかった。そして、荷の大半が混載状態だったのだ。 この事態に手を挙げたのが、マクリーンが創設した海運企業「シーランド」だ。突貫工事によりカムラン港を大型コンテナ港に生まれ変わらせ、大型コンテナ船が一週おきにコンテナ600個を規則正しく運ぶようになった。こうして、コンテナリゼーションが兵站改革の一端を担うようになったのである。 7 他国の台頭 コンテナ・ブームの第二幕が繰り広げられたのは太平洋だった。 マクリーンはベトナム戦争からの戻り船を横浜と神戸に寄港していた。この間、日本とカリフォルニアの間を行き交うコンテナ貨物の量は、重量ベースで北大西洋全体の2/3に達している。わずか3年足らずで、日本からアメリカに送られる輸出貨物の1/3がコンテナ化されたのだ。 コンテナのメリットを最初に実感したのはエレクトロニクス・メーカーであり、日本製品はアメリカ市場を、続いてヨーロッパ市場を席巻するようになる。日本以外では香港・台湾・シンガポールといったアジアの国が好調であり、コンテナ供給量はどんどん拡大していった。 そして、需要以上に供給の拡大が続いた結果、貨物の争奪戦が起こり、運賃は下がっていく。コンテナはバラ積み船に比べて建造費用が3倍もかかり、かつコンテナを港から港まで運ぶだけなので、ビジネスモデルに差がつかず、価格競争が起きやすい。そうなると有利なのは物価の安いアジア周辺国家だった。 マクリーンが持ち株を売却しR・Jレイノルズの取締役会をひっそりと去って行ったのは、1977年2月のことだった。 8 巨大化 船は大型化の一途を辿っていく。コンテナ輸送における規模の経済の効果は大きく、しかもはっきりしていたからだ。 1966年に大西洋を横断した最初のコンテナ船、シーランドの「フェアランド号」は全長140メートルにすぎなかったが、1988年になるとパナマ運河を航行できないほどの大型船も発注されるようになっていた。 これに合わせて港も大型化していく。大きい港は道路や鉄道の便もよいため貨物が滞留することがなく、処理能力が高いほどコストは下がっていくからだ。 9 これからのコンテナ 市場は何度もまちがいを犯し、民間部門も政府部門も何度も判断を誤った。そのたびにコンテナリゼーションは足を引っ張られたが、ついに「貨物を箱に入れて運ぶ」メリットと劇的なコスト削減効果が威力を発揮し、コンテナリゼーションは世界を席巻した。 今やこの箱は、ひどく厄介な社会問題を引き起こすようにもなっている。 ①大量のコンテナが放置されるようになった ②ディーゼル燃料で動くコンテナ船やトラックなどの排気ガスが深刻な環境汚染を引き起こしている ③コンテナがテロに使われるようになり、公安局がセキュリティ強化に頭を抱えている
14投稿日: 2021.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見、金属で作られた単なる”ハコ”として極めて無機質なコンテナ。この一見何気ないように見える”ハコ”が実は国際物流のコストを劇的に下げ、そしてその結果として原材料産出・中間製造・最終製造といった各プロセスごとに最も地の利がある場所を選定することができ、それはグローバリゼーションという形で結実することになる。 本書はそうしたコンテナがいかに登場し、国際物流の極めて多岐に渡るステークホルダーの中で物流を、そして世界を変えていくかを描いたノンフィクション作品である。既にサプライチェーンという言葉が経営の世界で戦略的な重要性を持って語られるようになって久しく、サプライチェーンという概念のない企業活動というのは想像すらしにくい。 しかし、本書を読むと、国際物流というのは極めてムダと不合理に溢れ、サプライチェーンを構成する様々なプレーヤーが低コストな物流によってシームレスにつながっているというのはかつては想像すらできなかった、ということがよくわかる。コンテナという”ハコ”を船・トラック・列車といった様々なモビリティで共通的に運べるようにするという相違工夫がなければ、そのような世界はいまだに実現していなかったのかもしれない。 単なる”ハコ”に過ぎないコンテナが、当初の想定を超えて広く世界を変えていくという様は極めてエキサイティングであり、示唆に富む一冊。
0投稿日: 2021.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ物流の勉強のために読み始めました。 海洋物流や国際物流は普段の生活では意識することはなかったですが、実はものすごい勢いで世界を変えたのは、コンピュータとインターネットだけではなかったということがわかります。
0投稿日: 2021.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ物を作って運んで売る。半世紀ちょっと前の世界を想像するところから、話は始まる。 出来上がった製品は箱詰めされて、トラックや鉄道で港のそばの倉庫に運ばれる。中身はバラされて、検品される。船が着くまで留め置かれるが、船がいつ着くのかは分からない。船がついたら倉庫から運び出されて、クレーンで吊るされて船に乗せられる。船倉内では、航海中に荷物が崩れないように、手作業で積みつけられる。 港には荷物が滞留するので倉庫が要る。荷役は全て手作業なので人手がいる。荷物が動けば傷むこともあるし、所々で盗まれることもある。荷物の保険料も高くなる。荷の積み降ろしには時間がかかり、その間船は当然停まったまま。 それが今は、製品が工場から出荷され、港まで運ばれ、そのままの姿で留め置かれ、船が着けばクレーンで積み込まれる。 買主の下に届くまで誰も荷物に触らないので、荷役の人手は減るし、荷物が傷んだり盗まれたりする事もない、保険料も軽くなる。船や港は巨大化・効率化され、運賃の単価も下げられた。 なんでそんなことができるようになったのか、それはコンテナが生まれたからだ、という話。 物流にかかる巨大で広範なインフラが整備されそこにフィットする構成要素としてコンテナが生まれたのではなく、コンテナがまず規定されてそれに合せてより大規模な船や港が規定されたという順番なのが興味深い。 そして、規格化された箱に荷物を収めるというブレークスルーが物流の諸課題を一挙に解決していく話かと思いきや、そうではないというのが本題。 既存の海運業者はコンテナ化などうまくいくはずがないと高を括った、港の労組は雇用不安から抵抗する、勝者総取りのゲームの中で港湾では投資が過熱する、鉄道・トラック輸送とは時に争い時に手を結ぶ、規格化を巡る交渉、原油価格と荷量という2つの外部要因により業況が大きく変動する、荷役という仕事には劇的な変化が起こる。 箱によるイノベーションは、一筋縄では行かなかったり、あるいは時に想像以上の変化・影響を与えたりしながら、船と荷物が世界を結んで行く、世界はもっと複雑になる。
0投稿日: 2021.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ物心ついたときに当たり前のようにあったコンテナ。一人の起業家の一途な信念から生まれ発展を遂げます。数々の困難を乗り越えて現在に至るまでのストーリーは秀逸です。
0投稿日: 2021.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いんですけど、多過ぎるのと、冗長な表現が多い アメリカの著者っぽいなーと思うけど、どうでしょう ちょっと金太郎飴感を感じてしまい、全部読み切るにはしんどいと思ってしまった 頭と末だけ読みました
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログビルゲイツが絶賛した本書ですが、めちゃくちゃ面白かったです。 コンテナ「箱」が、陸(トラック、鉄道)、海(港湾、船)、空(飛行機)、組合、荷主、消費者、戦争までも変えた!!という歴史です。 コンテナの歴史について、めちゃくちゃ調べて描かれているので、こういう本は本当に安く感じます❕ コンテナリゼーションの流れは、一度動き出すと止まらない❕いくら労働組合や反対組織が反対しても止まらない❕ 現代の流れと、とても似ているように感じました。 何か参考になるものがあると思います。 ぜひぜひ読んでみてください
8投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログアジア諸国での生産が安いのは人件費もあるだろうけど、このコンテナがあることでの輸送コストの大幅削減の恩恵を現代は受けているということ。 知らない世界をまた知れた、そんな本でした。 先日の座礁事故は気になりますが。
1投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段は余り気にしない、よく普通にみるコンテナですが、実はそのコンテナの発明と普及が、世界の物流を根本的に大きく変えたという事実に驚きました。 規格の統一により船便と陸便の相互行き来を簡易にし、自動化を可能にし、物流の大きな発展につながったそうです。現在世界中の製品が手に入る便利な世の中になったのも、実はコンテナの発明が大きく寄与していたという事実に感嘆を覚えました。
1投稿日: 2021.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「エバーグリーン」出てきたとこで、「あ、コンテナ見たことある」って思った。コンテナ岸壁、遠目でしか見たことないので、見学してみたい。コンピュータと同じ時期に発展してきたと思うんだけど、だいぶ違うなと興味深い内容だった。
0投稿日: 2021.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログビル・ゲイツ推薦本。さすがに!かなり面白かった。物流革命が世界を変えたって話はタイトルのままなのだけど、この面白さこそ、物流のダイナミズムよ!長編だけど、まったく飽きない。最後はグローバル・サプライチェーンマネジメントの話なんかもでてきてお勉強にもなりました。良書。
2投稿日: 2021.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃ面白かった!!当たり前に目にしているコンテナが、どのようにして世界経済を変えたかの仔細な物語。 荷物を箱に大量に詰め、大量に運べるコンテナ船で大量に荷物を捌けるコンテナ港に荷上げする。その箱をシームレスに鉄道、トラックで運ぶ国際輸送システムが出来上がったおかげで輸送コストが劇的に下がった。 メーカーは輸送コストをあまり気にせずに中間材を作るメーカーを選べるようになり、我々はインドの綿花で作られた生地に、マレーシアの合成樹脂で作られたボタンを中国の工場で付けたシャツを安価に着ることができる。 そんな状況は当たり前のように知っているけど、それは「コンテナ」という金属の箱が生まれたから実現したんだという驚きが味わえた。 荷上げの機械化に反対する労働組合と経営者の対決、コンテナの国際規格を決めるときのいざこざなど、色々な立場から語られる各章のストーリーも実に面白かった。
0投稿日: 2021.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナとパレットで世界は貧乏になった 2021年3月5日に日本でレビュー済み なぜ外国製の物の方が安くなるのだろうか? つい僕らは人件費が安いからと答えがちだ、 しかし、実際にはそこが重要ではない 国内のトラック運賃より、 外国からの船賃の方がずっと安いのである。 まさにグローバル経済の始まりは この船賃の激安化によって作られていると 言える。 しかしそれを発見し、推し進めた先人が 全てを見通して突き進んだかと言うとそうでは無い その複雑で、劇的で、激早な2つの発明の物語を ご覧あれ。
0投稿日: 2021.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログマルク・レビンソン「コンテナ物語」読了。ただの運送用の箱というコンテナのイメージが本書を読んで根本から覆った。既存の港湾の仕事を破壊するだけでなく、世界の物流を変えていった事は、インターネットのインパクトに匹敵かそれ以上に衝撃的だった。イノベーションによる不測の事態を考える上でとても役立つと思う。
2投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナの発明により輸送費が劇的に下がったという話だが、実際にはそんな単純で簡単な話ではない。 コンテナ船が運行をはじめた1965年からたった半世紀でどれほど世界の輸送に影響を与えたか。 船会社側、沖仲仕、国側それぞれの思惑。その時代時代の学者がコンテナリゼージョン後の世界をどのように想像し、全く検討外れであったか。船–トラック–鉄道各社の思惑。コンテナとグローバルサプライチェーンの関わり。各国のコンテナリゼーションへの考え、取り組みによる盛衰。コンテナによる社会問題。そしてコンテナほ今後の展望。 と非常に壮大な興味深い内容だった。 コンテナだけの力でグローバル化が進んだわけではないが、いかにコンテナが寄与してるかが分かる。 コンテナリゼーションを推進するため各時代、異なる立場(価値観)の人を同じ方向へ導くための駆け引き、現代の世界の海運会社の多くは比較的参入が遅いという事実から浮かび上がる事業を成功させる秘訣など物流以外のビジネス全般に関わる考え方も学ぶ事ができる内容と思う。
0投稿日: 2021.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2ちゃんねるの人始め、いろんな人が絶賛してる。確かにおもろい。コンテナがたった20年かそこらで世界を変えていく。エコノミストや業界の経営者たちは「コンテナなんか主流になるわけ無い」「儲かるはずがない」と思い込み、何度も何度も間違えた。コンテナはますます主流になって、ますます儲かった。儲かっている。
0投稿日: 2020.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950年代に始まったコンテナリゼーションの本。 以前は物流にかかるコストが大きくものづくりが局所的に行われていたが、現代はコンテナにより物流のコストが下がったため、グローバルに製品や材料が行き交うようになった。 この本ではコンテナの発明が港湾や船舶、貿易を始め世界の物流にどのように影響を及ぼしていったのか、膨大な資料を元に論じられている。当事者である海運業界の中で、誰もコンテナによってこのような社会になることは予想できていなかった、と書いてあったのが興味深い。過去に起きたゲームチェンジについて書いてあり非常に勉強になる一冊である。
0投稿日: 2020.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログビルゲイツの言う通り、全世界のビジネスのやり方に通じる話。 加えて、自分にとっては、物流の仕事を始めたところなので、さらに面白く読めた。 イノベーションを完成させる為の、必要なアイテム、越えなければならない障壁、共に戦う仲間、そして味方となる考え方、これらがコンテナリゼーションを題材に学ぶ事が出来ると思う。 イノベートのキッカケはよそ者から生まれ、最初は様々な抵抗勢力と戦い、見方を増やして、時代の流れに乗り、世の中の役に立ち、常にイノベートし続ける事。
0投稿日: 2020.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログビル・ゲイツの推薦本、20世紀後半の海運業のイノベーションといわれる「コンテナ」の発明物語(ストーリー部分は370ページくらいで残りは参考文献紹介)。主人公はコンテナを発明したといわれるマルコム・マクリーンで、コンテナ業界がブルーオーシャンからレッドオーシャンへ至る過程や、コンテナの機能上昇、コンテナにより各国の湾岸が整備され輸送・貿易の歴史が変わっていく状況がつぶさに描かれる。基本的に買収・合併で大きくなっていく「コンテナ」業界の歴史は現在のIT業界の状況にそっくりだと感じた。
0投稿日: 2020.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白い。 システムとしてのコンテナの発明とその発展の歴史その世界に与えた影響が描かれている。 箱としてのコンテナの発送は昔からあったようだがそれをシステムとして構築したのは本書にもあるマルコムマクリーン。 しかしその新しいシステムに対する既得権益の抵抗と規制が強く残りなかなか効率化できない。 しかし最終的にそれが取り払われたおかげで物価が下がり効率的になり世界が変わった。 これだけ革命的なのにあまり光が当たっていなかったのは驚き。
0投稿日: 2020.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログコンテナ物語 世界を変えたのは「箱」の発明だった THE BOX 増補改訂版 著作者:マイク・レビンソン 日経BP ビル・ゲイツの推薦 コンテナが世界を変えていく物語は実に魅力的 圧倒的に面白い海のイノベーションの物語で待望の改訂版。 タイムライン https://booklog.jp/timeline/users/collabo39698
1投稿日: 2019.10.24
