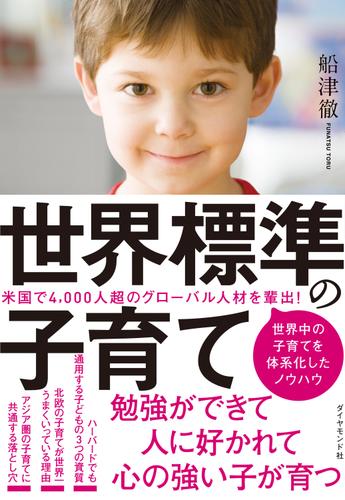
総合評価
(69件)| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の子育てもいいところがたくさんあると思うけれどグローバル化が進む中、世界と日本の子育ての違いを知りグローバルな視点をもって子育てをすることは今後ますます必要になってくるだろう。この本は年齢ごとに3つのステージに分け、それぞれのステージで何をすべきか具体的に書かれているので実践しやすい。大事なのは「自信」「考える力」「コミュニケーション力」の3つ。そして日本式の教育に囚われず、おおらかに子育てすることを心がけること。物申したいところもいくつかあったけれどよくまとまっていて、手元において読み返したい良書。
0投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログデータが古い。2017年刊行なので当たり前ですが✨ 2010年〜2015年のデータが多いが、ここ10年の変容は激しいので、AIが台頭してきた現代にアップデートした最新刊を期待。 ※時間のない方は、巻末の一問一答から入って気になる部分の本文を読むのも良いかもしれません! 子供の年代別の接し方をまとめてくださっているので、その時々で必要な部分を中心に前後の年代を読めます。
0投稿日: 2025.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ各年齢ごとにポイントがまとめられている 0-18歳まで幅広くあるので、教科書的な感じで 各年齢ごとに繰り返し読みたい本
2投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ育児本て知育に偏りがちなイメージがあったけど、これは科学的根拠や他国の事例もあり、ストイックにやらなくても日常に組み込んでいける事例もあってよかった。一方で学習習慣は就学前に終えるべし、とか英語学習の仕方など、やっぱり家でできることはちゃんとやりたいなという気持ちにさせてもらえたので満点
0投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「子供に幸せになってほしい」と願う親の全員に読んでほしい良書。やってはいけない子育ての理由が子供視点で的確に指摘されており、「子育ての前に、まず親自身が育たなくてはならない」と気付かされた。 自立性、協調性、最終学歴、自尊心、考える力、など、どの国がどんな教育を重視しているかを比較する章は面白い。一方、各国で共通している「英語によるコミュニケーション」は日本“だけ”遅れており、これはマズいとの危機感も明確になった。
6投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本と海外の子育ての違いをまとめてある。それをもとに時期に応じた子育ての方法が知識から実践編まであり、とてもためになる本です。時期ごとに再度読み直したいです。
0投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ子育ての心構えとして、読んでおいて良かった!と思った本。 以下は、本からの子育てに取り入れたい事項の抜粋 欧米では子育ては18歳まで。伝えるべき愛情はすべて伝え、伝えるべき技能はすべて伝え、共有できる時間があればともに過ごす。 子供には、「自信」「考える力」「コミュニケーション力」 自分の意志で行動出来た時に褒める。 具体的に褒める。 親は、努力することに意義がある態度をとり、結果に寛容であること。 13歳からはコンフォートゾーンから脱出させよ 習い事を10年継続させて、「特技」 までひきえげる 10歳からはノンフィクションへと読書の幅を広げる。自伝。偉人伝。歴史。政治。社会問題。 新聞記事を読むことを日課にする。 市町村の国際交流イベントを調べてみる 交換留学プログラムを調べる とびたて UWCという非営利のインターナショナルスクール 観光ボランティアやゲストハウスのイベント ホームステイ 子どもの人生は子どものもの
1投稿日: 2024.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
諸外国と比較した際の日本の教育の問題点や、年齢別の子どもへの接し方が具体的に書かれており参考になった。 まずは0歳〜3歳の部分を重点的に読んだため、子どもが大きくなるにつれ該当箇所を読み返したい。
1投稿日: 2024.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界標準の子育ては自信を育てること。 根拠のない自信と根拠のある自信。 この自信を育てる子育てはぜひ実践したい。 子供がもう少し大きくなったらもう一度読みたい。
1投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログややビジネス書的なアプローチで子育について解説している。世界的に見て、評価されている子育ての理論はどういったものなのか?がテーマ。0〜6歳は、子供が「根拠のない自身」を身につけることが、その後のチャレンジ機会を最大化するために必要。そのためには何かときちんと褒めてあげることが必要と。 自分がされた教育とはだいぶ違うけど、しっくり来るな。
0投稿日: 2024.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログとても参考になり、私は数年に1回、読み返しています。 さまざまな国の子育てに精通した著者が、各国のよい点を盛り込んだ教育法を紹介してくれています。 日本の子育てと海外の子育ての比較があったあり、内容も面白いです。 取り入れポイントはたくさんありますが、この本がきっかけで子供の習い事をスタート。10年以上続けて自信になってくれることを願います。
1投稿日: 2024.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから必要な「自信」「考える力」「コミュニケーション」の3つをいかに育てるか、子どもの年齢ごとに指南した本。この3要素はまさに私のコンプレックスであり、国際人となるために必要だと痛感しているところ。子ども時代に培えなかったと感じていて、いかに後天的に身につけるか苦労したところでもある。今も苦手意識がある。これらに苦労しなくなった子どもはどこまで可能性が生まれるだろうか?とても楽しみだし、子どもが自分を超えていくために必要なことだと思う。ひとつだけ気になったのは、男女の役割分担については少し考えが古く、うちの家庭には合わないのではないかという点。科学的根拠はあるのかな?
0投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先に読んだ本と比べると内容がざっくりとしていて子細まで述べられてはいないが、簡単に実践できるものもあり参考になる。 特に子ども(幼児期)の情緒は安定と不安定な状態に揺れ動いているものであり、不安定な状態のときに何か言って聞かそうとしても無理だということ。まずはスキンシップを十分に取って安心させたうえでないと、落ち着いて話をすることはできない。だから例えイヤイヤや癇癪で泣いて困ったとしても、その状態ですぐ話をするのではなくまずぎゅっとしてあげること。これは信頼関係を築くためにもとても大切。 日本人はおしなべてスキンシップが充分でないので、親から積極的にスキンシップをとること。幼児期になり肌の触れ合いが減ってくるので、意識してちゃんと向き合う。 また、小学校にあがるまでに学習環境を整えてあげることも必要だと知った。読み書きや集中して取り組む姿勢など、勉強が始まる前に土台を作ってあげるのは家庭の役割。生活習慣に加えて、早期教育も必要とあり、特に読書習慣や算数の先取りはさせてあげたい。学校任せではいけないのだと痛感した。
0投稿日: 2023.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的には欧州とアジアを比べた比較における意見が書かれています。が、著者の経歴を見れば当たり前のこと。世界標準というとまるで全世界を網羅した本なのではと思いがちですが、 日本育ち、ハワイ在住の実績を収めている教育者が書いた本であるという前提の上読み進めると、違和感なく受け入れやすいのではないかと思います。 「当たり前だよなぁ」と素直に思える内容。 それでいて目から鱗な内容。 なぜかと言うと育児に忙殺されている中で、気をつけていても無意識に陥りがちな日本人特有のNG行動と対処方法が分かりやすく紹介されているから。 以下、特に心に留めたいと感じたメモと感想。 ⭐︎子育て3つの条件「自信、考える力、コミニュケーション力」 ⭐︎日本人が間違う落とし穴 ◽︎他人に迷惑をかけない子育てで自尊心の低い子に。→92%の高校生が自分には価値が無いと感じている。親の仕事は他人の目を気にすること?皆んなの目の前で怒って躾してますアピールすること?問題行動があったらその場から離して(公開処刑を避ける)一体1で説明、納得してもらえばよい。何より自尊感情を守ること。 ◽︎愛情のすれ違いで臆病、シャイな子に。→もっとスキンシップを。 ◽︎否定命令ケナシ言葉でキレる子に。→子どもは文字通り受け取ってしまう。 ◽︎せきたてことばで諦めやすい子に。 ◽︎学校任せで勉強嫌いな子に。→学習態度は親が育てるもの ◽︎身内への悪口謙遜で友達が出来ない子に。→ママはなんも分かってないねとか言いがち。
0投稿日: 2023.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこの方の英語力の育て方の本は、家庭での英語学習のバイブルのように何度も読み返しているのですが、こちらの著書はあまり目新しい情報もなく、ピンときませんでした。。 (自分の子が未就学児だからかな…?) 子供が小学生以降になったら参考になりそうな情報はたくさん。
0投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ乳幼児からティーンエイジャーまでの関わり方をまとめた子育て本はあまり多くないので貴重。むやみに自己肯定感が高いのも困るが、逆境で折れないレジリエンスは必要。 「強い心」は後天的な資質 過干渉は子どもからやる気を奪い、自信を減退させる 自分でやってみたいという気持ちを尊重し、成長の機会を奪わないこと 人前で叱らないのはプライドを潰さないための配慮 兄弟平等は上の子にとって不平等。上の子を中心に育てること。下の子は生まれたときから上の子がいるので、多少の愛情不足は問題ない。 勉強ができる子に共通する資質は知的な才能ではなく、諦めない、自制心がある聞く力がある、チャレンジを恐れないといった「学習態度」である 勉強で獲得した自信は脆く壊れやすい。勉強以外のことで根拠のある自信をつけるのがよい。 知性を褒めると「自分を賢く見せること」を優先するが、努力を褒めると「チャレンジし続けること」を優先する 「一度やめるとやめることが習慣になる。だから決してやめてはいけない」ーマイケル・ジョーダン 男の子はおだてて育てる。女の子には手本やルールを示して育てる コミュニケーション力を伸ばすことを考えたら、「集団で行う活動」に参加させること 演劇経験者は、英語の習得が早い 小学校低学年のときにはプラス暗示が効果的→大器晩成、遅ざき、将来大物になる、将来すごい人になる、世界で活躍できる人になる→なにかのきっかけで成功体験をしたとき、実感する
0投稿日: 2023.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ・自信 スキンシップを取る 上の子優先 お手伝いで成功体験 強みに合った習い事をさせる(10年は続ける) 困難な方を選択する ・考える力 読み聞かせ(質問しながら) 多読 算数は三学年先 選択させる練習 議論練習 ・コミュニケーション力 ごっこ遊び 笑わせる 急かさず話を聞く 読み聞かせ中にコミュニケーション 集団活動の習い事 演劇 国際交流 ホームステイ 留学
3投稿日: 2023.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ父親と母親の役割などジェンダーバイアスが強くある点が気になりましたが、他の本でも書いてあるようなことがまとまっているので、あまり教育論を読んでいないかたはこの本のまとめページだけざっと読むだけでも意味はあるかなと思います。
0投稿日: 2023.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自信、考える力、コミュニケーション この3つを育ててあげることが大切 自信にはダメや急かすこと禁物。自立心育むために自分でやらせ具体的に褒めスキンシップ多くとる。 自信は0から6歳 根拠ない自信をつけさせる・・受け入れる、スキンシップとる 7歳からは根拠のある自信をつけさせる・・少しだけ難しい課題にとりくませ小さい成功を積ませる、継続させる 考える力は「なぜ、どうやって」を会話に折り込む機会を増やす=考える機会増える。 コミュニケーションは集団、年齢違いの環境へ入れる。その前提として自己肯定感を上げてあげる、自分の価値を認識させる。 子育ては0〜6歳まで母親が与える影響が多い→ 父親は母親が気持ちよく子育てできるようにすることが子育て。 父親が子育てするのは母親がより良く子育てするため、休憩や気分転換のため。 父親の最善子育ての法則 父親 → 赤ちゃん でははなく 父親 → (赤ちゃん→)母親 → 赤ちゃん 母親のストレスが赤ちゃんに行かないように父親がする子育ては母親のスキンシップ時間を確保すること 赤ちゃんは自立と不安が交互 愚図りをもそのサイン 6歳までは根拠のない自信をつけさせる 方法は母親のスキンシップで
0投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて育児ノウハウの本を読んだが、とてもためになった。自信、考える力、コミュニケーション能力の3点を、早い時期から伸ばしていってあげたい。 繰り返し読み返して忘れないようにしていきたい。
0投稿日: 2022.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は海外で幼児教育プログラム施設を運営している方の様で、欧米中心ながら海外の子育ての仕方が随所に紹介されており、まさに「世界標準の子育て」が学べる本でした。アジア諸国の偏差値主義な育て方ではなく、欧米のソフトスキル(リーダーシップ、協調性など)を伸ばす子育てが重要であり、海外有名大学でも勉強+αとして求められる要素であることを再認識させられました。 自信、考える力、コミュニケーションを伸ばすことが重要、ということで、これらの伸ばし方について年齢層別に書かれており我が子にすぐ実践出来る内容になっています。 特に参考になったのが、勉強以外の習い事をさせる事(出来れば集団でできるもの)、それを10年単位で継続出来る様に親がサポートしましょう、という箇所でした。確かに、海外有名大学を出ている人は勉強一辺倒でなく音楽だったり、スポーツだったりで実績を残している人が多い気がします。
0投稿日: 2022.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカ、上海で英語学校を経営する著者による、世界の子育てから基準を体系化して紹介した本。 「自信」「考える力」「コミュニケーション」の3つを伸ばすことが大切。
0投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
図書館で借りて読みました。 当方、2歳と1歳の子供がいる新米母です。 子育てをしていると、よく悩んでYahoo!知恵袋とか見てしまうのですが、 人によって意見が違うので、なんとなく自分の都合のいい意見を参考にしていました。 しかし、この本では「子育てには明確な答えがある」として、様々な疑問の答えが記されていました。 世界各国の育児事情と、そこで育った子供たちの能力を統計的に見て「こんな子育てをすればこうなりやすい」といったことが記されています。 個人差があるとは思いますが、こうもはっきりと子育ての指針を示してくれると、新米母としては助かります。 実行したいと思ったことは下記です。 -誉めるときはよい部分を具体的に誉める -本の読み聞かせをする -習い事を10年間継続させる(花形でなく、スキマを狙うのも有効) -家中の物に名前カードを貼る -「ごっこ遊び」に付き合う -こどもをいっぱい笑わせる -海外留学のチャンスを与える -こどもがしようとしていることは最後までやらせる -学校を調べる -楽しく食事をする もしこれが正解でなくても、親子で幸せになれるようなことが多いので、実行しようと思えることばかりでした。 年齢別に18歳までまとめてあるので、また読み直したいと思います。
2投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生100年といわれる中で18年ほどしかない 子育てをより良いものとするためのレシピが書かれた本! 具体的な例をあげて説明してくれているのですごくわかりやすい!全てを覚えて実践しなくても一度読んで章ごとのポイントを押さえていけば親としても子育てに自信を持てそうな気がした。 子育てをする事で大人も学ぶことがあるってよく言うけど子育て本を読むことで大人として生きていく中で大事なことも学べる。
9投稿日: 2022.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ父親の役割 母親の役割とでてくる点が少し引っかかるが、その点を除くと書いてあることは参考になることがたくさんあった。 実践できそうなこと、頑張らないとできなそうなこと、自分にはなかった新しい視点からのアプローチ方、色々あった。 関わり方に意図を持つことで子どもの力を伸ばす手助けになる、と感じた。 うちの子は今は幼児だが、思春期に入る頃また読み直したい。手元に置こうかなと思った一冊。
2投稿日: 2021.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログR3.4.28再読。 改めて意識しないといけないこと ◆否定ダメばかりは反抗心の強い子になってまう ◆せきたて言葉(早く、急いで、ちゃんとして)は失敗を恐れる消極的な子に。 ◆命令、比較、突き放し(もう知らん、勝手にして、いい加減にして)はNG! ◆シャイの原因は愛情不足。もっとスキンシップ! 『反抗の原因は自立心と、母親から離れる寂しさの葛藤』→心当たりがありすぎて、息子の気持ちを思うと涙が出そうになった。余裕がなくなり、突き放してしまう事もあり反省。思い切り受け入れてあげないとな。 ◆人から感謝される喜びと快感をたくさん経験した子どもは前向き積極的で開放的な人柄に ◆諦めぐせの解決法 自身不足→手出し口出しせず見守る 成功体験不足→子どもの意思で選ばせる ルーティン欠如→日々の繰り返しを重視し、生活習慣の改善 ◆言語力を育てる→本の読み聞かせ 3歳からは質問しながら。その際、親の意見も述べる。ママはこうだけど、〇〇ちゃんはどう? ◆しつけ=皆んなと楽しく快適に過ごす方法を伝えること。行動の意味を教える。 ◆プラス暗示。あなたら大物になるよ。世界で活躍できる人になるよ。大器晩成だよ、 ◆質問、尋問、命令になっていないか?1人の人間として雑談 ◆食事は楽しく。小言ばかりを言わない。
2投稿日: 2021.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ子供が2歳なので、対象となる内容をざっと2時間ほどで。 全体的に筆者の主張の根拠が示されていないことが多かった。筆者の経験的にな内容が多い。科学的な内容はあまり期待しない方がよい。(説明していないだけで根拠はあるのかもしれないが) また特に序盤だが、国ごとの教育の違いなど、だからなんなのだ、という内容もあり少々冗長な部分がある。 内容としては、これといって目新しい内容はないが、0歳〜16歳くらいまでの子育て方がまとまっており、長く使えるものにはなっている。
1投稿日: 2021.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分ガ受けた教育を反面教師として、 子どもには自己肯定感をつけさせ、 自分のことは自分で決められる子になって欲しいと思っていた。 子育てに必要なのは 1.自信 2.考える力 3.コミュニケーション力 とあって、 やっぱりそうだよね!!!と頷いてしまった。 低年齢なので役に立つところとしては ▪️根拠のない自信をつける 自分でやりたいを大事にする イヤイヤは自立と母子分離不安の葛藤なので受け入れる ただ禁止命令ではなく理由を伝える、考えさせる スキンシップで愛情確認 お手伝いで成功体験を積ませる(感謝される、思考力や集中力、コミュ力など身につく) →いま超お手伝いブームが来ていて 片付けや調理洗濯たたみ園の支度など色々やらせている。 本人はノリノリで、これは親の空気を読ませているのかと不安だったが ちょうどいいらしいと知って安心した。 飽きるまで色々手伝ってもらうことにする。 ▪️女の子の育て方 手本やルールを提示する まねさせる 努力を褒める(結果は問わない →まさにお手伝いがこのフローだった。女の子との親和性が高いのか? ▪️考える力 絵本の読み聞かせで想像力を育てる どれ読むか自分で選ばせる 3歳からは質問する(親の意見も添える 5歳から文字を日常に取り入れてゲーム感覚で遊ぶ 覚えたら簡単な絵本を自分で読ませる →質問やってる!リアクション良いんだもん。同じ本でも質問変えると飽きなくて楽しいよね。 ▪️コミュニケーション力 ごっこ遊びにとことん付き合う(ちょっと考えさせる質問も交えて たくさん笑わせて感情表現豊かに 聞く力が育つと勉強が得意でコミュ力も増す そのためにはまずは本人にたくさん話させる 小受も中受もしない、中流オブ中流共働き家庭だけど この本に書いてある内容は そこまでお金をかけずに取り入れられるものばかり。 楽しみながらまた年齢が上がったら読み返して実践したい。
3投稿日: 2021.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の教職の授業で先生に勧められ、読んでみた。 かなり基本的な内容で、子育て経験がない私にも理解できた。また、私の母が自分に施してくれた子育てに似ている部分が多々あり、改めて母の教育方針に感謝したくなった。身近に子育てのロールモデルがいるというのは非常に心強い。
0投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ二人目育休中に読了 年齢別にステージが分かれて書かれており、とても読みやすいと感じた。 まだ子供が幼いので、ステージが変わったら、読み返そうと思う。 NGフレーズは、普段よく使う言葉だったので、猛省。しかし、ワーママの身としては、日々、本当に時間がなく、よくせきたててしまってました。いけないことだけど、難しい。。。
1投稿日: 2020.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ言われてみれば、当たり前の内容ばかりだが、実践出来ていないことが多い。 子育てに行き詰まった時に、また読み返したい。
0投稿日: 2020.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログそんなに目新しい内容はなかった。年齢毎に合わて意識すべきことをまとめているところは読み易い。昔ながらの日本の教育を否定するほどの内容でもないかな。大事にしていきたいことも書いてはある。子育てに迷った時にもう一度見返したい。
0投稿日: 2020.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2020/09 図書館 「母親はいつもニコニコ笑顔でいること」 これを実現するためには、やっぱり主人の協力が必要不可欠。今からでも間に合うかな?? 「お願いする→感謝する→おおげさに褒める」 子育てしながら主人も育てる…なかなかハードだなぁ〜…。 自信・考える力・コミュニケーション力 今2歳の娘。 取りあえず褒めて、あまり手出しや口出しをしない。 テレビは一日一時間。 絵本をたくさん読む。 いっぱい笑って過ごせるように…☆ 今後、様々なコミュニティーに参加できるように、今のうちに私自身も土台づくりをしておきたいと思います。 娘が小学生になる頃に、もう一度読み直したい1冊です。
0投稿日: 2020.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ息子0歳8か月。今出会えて良かった本でした。 筆者の言う通り、自信、考えるちから、コミュニケーション能力は確かに生きていく上で大切だと思います。多国籍の職場で働いているいま、強く実感しています。 それらを子どもに身につけるために親としてどうすべきか分かりやすく一気に読めました。 忙しい育児のあいまにも意識して子どもとかかわっていきたいと思いました。
2投稿日: 2020.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
環境や時代の変化に負けないたくましい子供を育てる方法、世界で行われている子育てや研究、成功例・失敗例をもとにノウハウを体系化しようを目的としている本。 学校教育で数値化出来る知識・技術(ハードスキル)より、論理的思考や問題解決力・分析力などのソフトスキルが教育の主流に移行 海外の子育て ・スウェーデンでは父親の育休取得率が80%、日本はたった2%。母親の心の余裕こそが子供の人格を育てる ・「学歴信仰」の韓国は挫折やドロップアウトが44% ・一人っ子同士の夫婦が一人っ子を育てる中国は、愛情たっぷり受けて育ち自尊心が強い反面、プレッシャーが過大で潰れる子供も多い ・「理数系」のインドは機械的に公式を暗記するのではなくHOW/どうしたら?の頭の使い方が上手い 子供の頭脳は6歳までに90%が完成する、本の読み聞かせは0歳から始めるべき。 キーワードは「自信」「考える力」「コミュニケーション力」。年齢別・男女別で分かりやすく書かれています。 重要な事は“どれだけ頭が良いかではない。どのように頭が良いかなのだ”が印象的でした。
1投稿日: 2020.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い本。 子供の幸せを願う人全てに呼んでほしい本。 子育て以外にも、部下の育成などに 共通する部分もある。
1投稿日: 2020.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の上司から頂いて読み込み。 内容は普段意識していることが多かったが、子供を他の大人達がいるコミニティーに参加させてれいないと感じたことが一点課題と感じた。 広い年齢での指南があるので、もしまた少し、子育てに悩んだ際には読み返してみようと思う。
0投稿日: 2020.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
年齢のステージ別での接し方や対処法が書かれており、今の年齢に照らし合わせて読めました。 父親育休多いスゥエーデン 自立のために褒めるアメリカ 理数に強いインド 留学が多い韓国 アジアのようなハードスキルだけでなく欧米のような学力とソフトスキルが必要性 色々忘れちゃうのでまたそのステージが来たら読みたい 自信をつけさせる 成功体験をさせる 手出し口出ししない 考える力 ソフトスキル、分析力、批判的試行、問題発見力など コミュニケーション力 相手の目を見る 親がよい手本を見せる 自分の意思でできたことを褒める 具体的に褒める しつけには理由を あきらめず、自制心、人のはなし聞く、柔軟思考、正確、チャレンジ心 6歳までの習慣 読書、プリント、子供とのコミュニケーション スキンシップ お手伝い成功体験 聞く力はまず親が聞く、聞き上手になる
1投稿日: 2019.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもに教えるために、まず親自身から この本を読もうとする人は、自分の育てられ方に疑問を持っているのでは? 私の感想 これを読んでいて、意識的に何かしら子どもに教えたい人が読む本か それとも親として何が用意できるかの参考書として読むか 読んでいる自分はどちらだろうと、気持ちが揺らぐ時間になりました。 教える、伝わるの本質は、意識的に何かをやらせる、こうやって伝える。 ではない。 知っていることすら忘れている領域がコピーされる。 それだけだと確信した。 ジョハリの窓よろしく 知らないことすら知らない領域のことは認知できない。 それと対偶の、当たり前すぎて気にすることもない知識。 その当然だと思っている知識こそ、伝えるよりも自然に同期する。
1投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「幸せ」とはなんなのでしょうか? * 精神的にも物質的にも豊かな人生を送ってもらいたい * 社会の役に立つような人間に育ってもらいたい * 人にやさしく、たくましく生きてほしい 情報が氾濫している時代 日本もこれまで以上にグローバル化の波に飲み込まれていく 変化に適応できる人とできない人の間で「格差」が生まれます。 明治維新から現在まで、日本の教育観は変わっていません。 思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力といった総合的な学び 誰もが一度は「競争の壁」に阻まれ、挫折や自信喪失を経験していきます。 その時に支えになるのが、困難に負けない「強い心」です。 幼児期(0〜6歳) 小学生(7〜12歳) 中高生(13〜18歳) 世界標準の子育ての根幹となる3つの条件 1. 自信 2. 考える力 3. コミュニケーション力 子育ての90%は、自信を育てられるかにかかっている。 自信の源泉は、子どもが自分の意思でものごとに取り組んだ時に「自分の力でできた!」という成功体験にもとづいて生まれるものです。 しかし、他人に迷惑をかけないこと、集団のルールを守ることを重んじる日本の子育てでは、子どものやりたいことを自由にやらせるよりも、子どもの行動を制限しようとする場面が多い。 過干渉は必ず子どもからやる気を奪い、自信を減退させる。 親は「手出し、口出し」したい気持ちをグッと堪えて、子どもを見守ることが大切です。 「自由と制限」をバランス良く与える子育ての実践。 欧米社会では、幼い子どもでも「1人の人格者」として扱います。 人前で叱らないのは、子どものプライドをつぶさないための配慮です。 情報を見極める力、常識を疑う力、未来を予測する力、多面的に考える力、自分の思考を検討する力。 子供たちは、これまでの常識や価値観の中で生きるのではなく、自分の人生を自分の力で開拓しなければならないのです。 答えのある問題ではなく、答えのない問題が極めて重要 ハードスキルとソフトスキル ーー 認知能力と非認知能力にも通じる。 ーー 今世界の学校の主流は「ソフトスキル」に移行しつつある。答えのない問題にどう取り組むべきか、考える技術を教えることが、学校の役割。 コミュニケーション力がなければ、意思疎通ができない、人間関係をつくれない、仕事がスムーズにいかないなど、多くの障害が生まれてきます。 相手の目を見て、笑顔で挨拶する コミュニケーションの基本 相手の目を見て話をする、自分の考えを正確に伝える、人の話を最後まで聞くなど、そうした人付き合いのルールを教えるのは親の役割です。子どもは親のマネをして成長します。 父親の育児参加 父親が子育てに参加することで母親の育児負担が減り、ストレスが減り、結果として「子育てしやすい国」になっている。 スウェーデン、フィンランド、ノルウェー 母親の心の余裕こそが、子どもの人格を育てる。0歳から4歳くらいまでにかけては、子どもと密接に関わる機会は母親のほうが多く、母子関係によって子どもの精神面・人格面の土台がつくられていきます。 子どもが心の土台(情緒や性格の方向性)を形成する6歳までは、子育ての主役は母親になります。 母親でなくてもできる家事の雑用は、父親ができる限りサポートしてあげてください。 成長期に父親と多くの時間を過ごした子どもは知能指数が高く、社交性があり、より高いキャリアを得る アメリカ人の子育ては「自立心を育てる」目的が根底にあります。 アメリカ人は、自分の意思で行動できた→褒める=自立を促す 日本人は、言うことを聞けた→褒める=従順を促す 子どもの小さな成長を見つけた時には「自分でできたね!、すごいね!」ともっと大げさに褒めてあげてください。 レベルの高い教育も大切なことですが、何よりもベースとなる心を育てておかなければ、いつか経験する挫折に耐えられないのです。 中国では、「子育ては祖父母の仕事」 2005年にアメリカの大学に通う中国人留学生は6万人でしたが、2015年には30万人を超えている。 インド人の理数系頭脳を支えているのが「暗算教育」で暗記ではなく、「いかに工夫して暗算するか」という思考習慣であること。 機械的に公式を暗記するのではなく、Howどうしたら?という頭の使い方を身につけさせることが「理数系頭脳」の土台となっているのです。 将来の方向が文系であるとしても、「考える力」は必要不可欠な要素です。各家庭で「覚える学習」から「考える力を伸ばす学習」にシフトしていくことで、思考力のベースをつくっていくことが重要になります。 アジアは偏差値主義、欧米は総合力主義 〜勉強ができるだけではダメが世界標準 家庭における「ハードスキル偏重教育」の結果 アメリカの大学入試では、テストの点数は学生を評価する一つの基準に過ぎず、テスト成績に加えて、リーダーシップ、社会性、協調性、創造力、問題解決力など「考える力」と「コミュニケーション力」を総合的に評価して合否を決定する。 ガードナー博士 「多重知能」 アジア諸国の子育てはハードスキル(知識)に偏っている。世界のトレンドは学力+ソフトスキル 日本の子どもは、アジアの中でも飛び抜けて「自尊感情が低すぎる」のです。7.5% 集団における調和を何よりも大切にする日本人 もう少し子どもの自発的な行動を周囲の大人がおおらかな目で見守ってほしい、ということです。「まわりに迷惑をかけて成長する」 自尊感情は、変化する時代に対応していくための「チャレンジ精神」、「楽観性」、「立ち上がる力」の源になります。 親から愛され、受け入れられているという「実感不足」もっとも重要なのが、「スキンシップ」で「肌と肌のふれあい」が親の愛情を効果的に伝える手段なのです。 チック症状 「しつけ」を重視する日本人は「ああしなさい」「こうしなさい」「ダメ!」と子どもの自主的な行動を言葉で抑えつけようとする傾向があります。しかし、これはNG。命令・否定言葉は子どもの心に欲求不満を植え付けます。 「根拠のない自信」は100%親から与えられるものです。子ども時代に親から可愛がられ、大切にされ、愛情をたっぷりもらうことでのみ得られる自信です。 手伝いとは、いわば社会経験の第一歩です。 「根拠のある自信」は親から受け取るものではなく、子どもが自分の努力によって獲得していく能動的なものです。 →継続と競争によって育てられる。 競争を通して自分の「強み」に気づかせるため。子どもの特性に合わない習い事をやらせたり、親の希望で習い事を選んだりするのはやめましょう。 勉強で獲得した「自信」はもろく、崩れやすい チームスポーツでリーダーシップを学ぶ。 もうやりたくない、やめたい!は「うまくできないから」 1番を目指して、物事を真剣に続けるということがメンタルタフネスを養います。 両親が子どもの練習に協力して、周囲より少しだけ能力を伸ばしてあげると、子どもは「自分はできる!」という自信を持ちます。すると、もっと上手くなりたい!と自分から練習に励むようになるのです。 子どもたちが自分で「強み」に気づくことはできません。最初は親や周囲の人が見つけて「あなたはここがすごいよ」と教えてあげることが大切なのです。 居心地が良いのは、成長が止まっているサイン。 少し厳しい環境、今よりもレベルが高い環境に子どもをチャレンジさせることによって「成長を止めない」ようにすることが、「根拠のある自信」をより強く、確信に変えていくために必要です。 ーー 地方レベル→県レベル→全国レベル→世界レベル ーー Comfort Zone 子どもを新しい環境にチャレンジさせるときのポイントは「手の届く範囲」であること。 人は誰もが「ラクな道」「甘い水」を選びたくなるもので、だからこそ居心地の良い環境から外に踏み出すときは親が背中を押してあげることが必要です。 子どもが環境の変化を嫌がるのは「失敗を恐れるから」です。 サマーキャンプ 親元を離れ、身の回りのことを全て自分で行う経験は、子どもの自立を促し「自信」と「責任感」を大きくしてくれます。 テレビもゲームもインターネットもない環境 努力を継続してきた子どもは、他のことも継続できる「粘り強い精神」を身につけることができる。 マイケル・ジョーダン 「一度やめると、やめることが習慣になる。だから、決してやめてはいけない」 やり抜く習慣 日々のささいな積み重ねが大きな自信をつくる。多くの人はその時々の「選択」によって人生が決まると考えていますが、本当に人生を決定づけているのは「日々のささいな積み重ね」です。 男の子はおだてて育てる 女の子は手本(型)を示して育てる 母親の働きかけによって子どもの言葉の力には大きな差が生じることを知りましょう。 頭脳の配線工事は「6歳まで」に90%が完成する。手のかからない赤ちゃんほど言葉の発達が遅れる危険がある。 機械音では赤ちゃんの言葉は育ちません。子どもが言葉を最初に身につける時は信頼できる相手とのコミュニケーションが必要なのです。 「母親語」で絵本を読むと、赤ちゃんは普通に読んだ時よりも2倍の注目を向け、情緒的な反応をより高く示す。 日本国内で育てる場合には、英語を早く覚えさせても日本語がおかしくなることはありません。 第一言語の発達には「信頼できる人とのコミュニケーション」が必要ですが、第二言語に関しては「機械音」でも育てることができます。 6歳までに本好きな子どもに育てることができれば、子どもの言語教育はほぼ成功と言って良いでしょう。 特に現代社会は子どもの周囲に映像メディアが氾濫しています。想像力をつける前に映像メディアに慣れてしまうと、想像力を使ってものごとを考えるのが「めんどう」だと感じるようになる。 絵本の読み聞かせは0歳から始める。 日本むかしばなし グリム童話 アンデルセン童話 文字読み指導はゲーム感覚で遊びながらが基本。文字を覚えるのは「ママと遊ぶ楽しい時間」と子どもが感じている状態が理想です。 欧米では、「9歳」が読書力を身につけるクリティカルピリオド(臨界期)だと考えられている。 小学校低学年の時期は、少なくとも月に4-5冊は本を読むように子どもを励まし、導いてください。 チャプターブック アンパンマン、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、かいけつゾロリ 子どもが読む本は「おもしろさ」や「日常性」や「親しみやすさ」がポイント。 小学校低学年は、本を読ませて活字に対する抵抗感をなくすことに重点を置きます。 10歳からはノンフィクションへと読書の幅を広げる。 「考える力」は、人と意見を交換することによって効果的に身につけることができる、ということを家庭で教えてあげてください。 算数は「3学年先」を目指し、論理的思考力を育てる。 算数も読書指導と同様に、慣れさせることによって抵抗感を取り除くことができます。だからこそ、毎日練習することが大切なのです。 ーー 羽生さんの詰将棋の日課にも似ている。 ーー 8+7=15 慣れによる賜物で、単なる丸暗記。重要なのはその先です。基礎計算→論理的に考える力 シンガポールマス ◻︎ ◻︎◻︎◻︎ =36 二つの数字の合計は36です。大きい数字は小さい数字の3倍です。二つの数字は何? 毎日コツコツと辛抱強く算数に取り組んでいると、必ず飛躍するタイミングが訪れます。 選択させ、説明させ、明晰に思考する習慣をつける。 「和」を大切にする日本では、あいまいな表現が好まれます。あいまいな表現に慣れてしまうと、思考もあいまいになってしまう。 欧米の学校では、イエス・ノーを明確にすること、自分の考えを表現することが常に要求されます。 選択することによって、自分のことがよくわかるようになり「好き嫌い」や「イエスノー」をはっきり表現できるように育つ。 YES or NO. It's up to you. 人間は一人ひとりが「違う人格」であるという前提です。 親が分からないフリをして聞き直さないと子どもは自分の思考のあいまいさに気づくことができないのです。 小学校高学年からは、言葉ゲームで考える力を鍛える。 もし〜だったらなど。 自分にとって良い選択は何か?という問いを常に心に留めて生活するように子どもにアドバイスして下さい。 ディベート教育で学力世界一になったフィンランド 議論をし、なぜ?を考える力をつける。 欧米では、ディベートは学校教育の一部となっています。意見交換をすることで、自分の思考の偏りや思い込みに気づき、世の中には多様な考えがあるんだということを実感できる。つまり、考える力と相手を受け入れる力、この2つを学ぶことができる。 母親との関係が子どもの一生のコミュニケーション力を左右すると言っても過言ではありません。 言葉が話せるようになったら「ごっこ遊び」で能力を刺激する。 たくさん笑わせて、感情表現が豊かな子にする。人間は感情表現が豊かな子に親しみを感じる。 母親の表情は、必ず子どもにうつります。子どもはお母さんとそっくりな表情をするのです。 子どもをいっぱい笑わせて育てると社交的になる。家庭内に笑顔とユーモアをまき散らす。にらめっこ 6歳までに「共感して聞く力」を育てる。聞く力が育つと、勉強が得意な子になります。 子どもの話を聞く時のポイントは、目線を合わせることです。話の内容よりも「子どもの心に共感すること」を意識する。 親が「聞き上手」になると、子どもの側からどんどん話をするようになります。 ーー 立腰、姿勢 ーー 習い事はコミュニケーション力を育ててくれる場。「集団行動」に参加させることが一番です。 学校だけでなく、習い事を通して幅広い人間関係が、将来の子どものコミュニケーション力に大きな影響を与えます。 子どもを「子ども扱い」するのは、「子どもを自分の分身」だと考えているからです。 指示や命令を極力辞める。 子どもを大人の集まりに連れていく。 引きこもりの原因のほとんどは「人間関係」 下級生の面倒を見るBuggy System イギリスでは必修科目となっている「演劇」 人前で堂々と話す技術、表情、身ぶり手ぶりを使って意思疎通する方法、相手に伝わりやすい発声・発音の方法、相手に親しみを与える話術 グローバル感覚とは、国籍、文化、価値観、宗教の違いなどに関わらず、あらゆる人々がお互いを尊重し合う、多様性を尊重する意識であり、態度です。 →外国人と友達になり、語り合う経験 外国人とのコミュニケーション3つの基本 1. アイコンタクト 2. 笑顔をつくって挨拶 3. リアクションは2倍大げさに 日本を一歩出ると「思考スイッチ」が切り替わる。海外留学やホームステイ。観光ボランティアやゲストハウスのイベントなど。 海外で一定期間生活し、異なる文化と価値観を持つ人に囲まれて過ごすことで、初めて自分の(日本の)思考の偏りに気づくことができます。同時に、日本の文化、伝統、歴史、価値観の素晴らしさも理解できるようになる。 同じアジアでも、国が違えば言葉も価値観も文化も違う。 魔の2歳児を上手に乗り切る方法 子どもと目線とあわせて、なぜ行動を変更しなければいけないのか、理由をわかりやすい言葉で教えてあげて下さい。 最終手段は、こちょこちょして笑わせてください。2-3歳の子どもは言葉が足らずに自分の気持ちをうまく表現することができません。言葉を覚えると情緒安定する。 新しい環境に子どもを入れる時は、かなら前もってどこに行き、何をするのか、また何をしてはいけないのかを言葉で説明してあげてください。 しつけの目的は、「みんなと楽しく快適に過ごす方法」を伝えることです。 家庭では親が率先して「笑顔であいさつ」を実践してください。子どもも自然とあいさつができるように育ちます。 心を満たすには、添い寝をしたり、一緒にお風呂に入ったり、抱っこしたり、肌と肌とのふれあいを増やすことが一番です。 勉強でつまづいているときはどうすればいい? 小学校低学年の時には、「プラス暗示」が効果的です。結局、勉強ができる子とできない子の差は「継続するか、しないか」だけなのです。 小学校高学年の子どもが勉強で苦労している場合、得意科目、比較的成績が良い科目「集中的に学習させて自信を大きくすることに取り組んでください。 食事中に楽しい会話を心がけるのは「世界標準」のマナー。 パソコン、スマホ、ゲームは与えるべきか否か? 現代の子どもたちの周囲にはテクノロジーとメディアがあふれています。 →「親子会議」で話し合います。同時にルールを守らなかった時の罰則を決めましょう。 プログラミングは問題発見能力、問題解決脳裏、論理的思考力を伸ばしてくれる素晴らしい教材。これからの時代を生きる子どもにとってコンピュータは必須の技能。 * 親が子どもと一緒のことをする時間を持つ * 指示、命令、小言、説教をやめて人間同士のコミュニケーションを心がける * 子どもの強みや好きなことを見つけて親が応援する 勉強ばかりに気を取られていると、子どもの「強み」を伸ばすことを忘れてしまいます。 母親のストレスは父親が解決すべき課題。 スマホばかりという子どもにはなおさら親子の対話が必要です。 基礎学力と学習習慣をつけて学科に送り込んであげることが必要です。 受験のための詰め込み教育は偏った人格形成につながるのでやめましょう。 大学で多様な人と触れ合う経験は声優を目指す場合でも必ず助けになります。
1投稿日: 2019.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の教育本に比べて、 ああしなさい、こうしなさい、 っていう感じじゃないところが 読みやすい。 0〜6歳、7〜12歳、13〜18歳と ステップに分かれて、 アドバイスが記載されています。 ざっくりと印象に残ったところ ・習い事はすぐやめさせない! ・兄弟平等は不平等 →今まで自分だけでママ100%だったのに、 いきなり50%には出来ない。 2人目産まれる前にこの考え方にも 出逢えてよかった。 0〜18歳まで網羅していて、 長く使える本なのでよきでした◎
1投稿日: 2019.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い子育ての条件 ・自身 ・考える力 ・コミュニケーション力 自身を育てる ・0〜6歳 根拠のない自信を育てる ・無条件に受け入れる ・スキンシップ量を増やす ・お手伝いで成功体験させる ・7〜12歳 根拠のある自信を育てる ・競争に参加させる ・強みを伸ばす習い事をさせる ・習い事を10年継続させ特技に昇華させる ・13〜18歳 自信を確信にする ・未知の世界にチャレンジさせる ・長期休みには旅をさせる ・継続してやり抜く力を育てる 考える力を育てる ・0〜6歳 言葉の力を育てる ・子供の頭脳は90%が6歳までに完成する ・絵本の読み聞かせで本好きに育てる ・6歳までに文字を教え、読書力をつける ・7〜12歳 自分で考える力を育てる ・読書ジャンルを広げ意見を持つ訓練 ・算数は3年先を目指し、論理思考を育てる ・選択、説明させ、思考する習慣をつける ・13〜18歳 選択する力を育てる ・自分と向き合う経験を持たせる ・議論をし、なぜを考える力をつける コミュニケーション力を育てる ・0〜6歳 人と関わる力を育てる ・ごっこ遊びで能力を刺激する ・沢山笑わせて感情表現豊かにする ・共感して聞く力を育てる ・7〜12歳 人間関係の幅を広げる ・集団活動に参加させて幅を増やす ・大人に混ざって会話交流させる ・演劇はコミュ力を伸ばす最高のツール ・13〜18歳 世界標準にする ・家族で国際交流して海外文化に触れる ・ホームステイを受け入れる ・留学のチャンスを与える
1投稿日: 2019.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログP51 機械的に公式を暗記するのではなく、 「HOW?/どうしたら」という頭の使い方を 身に着けさせることが「理数系頭脳」の土台 p77 勉強ができる子の資質 ・諦めない子 ・自制心のある子 ・人の話を聞ける子 ・柔軟に思考できる子 ・正確さを追求できる子 ・チャレンジを恐れない子 p111 勉強以外に「根拠のある自信」をつける p113 チームで行うスポーツ ・コツコツ努力する根気強さ ・失敗を恐れずにチャレンジする精神 ・仲間と助け合う心 ・最後まであきらめない忍耐力 ・プレッシャーに負けない精神力 ・チームの一員としての責任感 ・コーチやサポートしてくれる 人たちへの感謝の心や尊敬の心などを得る →これらの精神は、世界の企業が求める リーダー像そのもの。 スポーツは子どもの自信を育て、 助け合いの精神を育て、 リーダーシップを育成してくれる 勉強と並行してスポーツを真剣に続けてきた子供には 「粘り強さ」や「立ち直る力」が身についている 少々の挫折や失敗を経験しても、 気を取り直して再び努力する力を 継続していくことができる。 p119 居心地がいいのは、成長が止まっているサイン p122 子育てにおいては、 「結果主義」ではなく、「努力主義」 大切なのは、親が「結果に寛容」であること。 結果よりも「努力することに意義がある」という 態度を保つ。 p128 継続の大切さ マイケルジョーダンに学ぶ。 ・一度やめると、やめることが習慣になる。 だから決してやめてはいけない。 決して諦めない、 やるべきことをコツコツとやり続ける、 壁にぶつかったら他の方法でやり続ける。 それでもダメなら、また方法を変えてやり続ける。 このような「やり抜く習慣」が極めて重要。 p132 子育ての基本 ・男の子は、おだてて育てる ・女の子は、手本(型)を示して育てる p164 算数は3年先を目指すが、 焦って難しすぎる内容をやらせるのは 挫折の元 p168 親子の会話では、空気を読まないようにする 子どもがあいまいな言葉を使った時は、 分からないフリをして「質問返し」をする 小学生高学年からは、言葉ゲームで考える力を鍛える ・もし~だったらゲーム ・究極の選択ゲーム ・あなたならどうするゲーム p177 強みや長所 子どもに、「強み」や「長所」を伝え、 子どもが自分の個性を活かすために どうしたらいいのかを考えさせる。 自分らしい人生を自分の意思で選択するには 子どもの中に、 ・自分はどんな人間で ・どんな人生を歩みたいのか を、認識してもらうことが大切。 p214 英語経験 ・交換留学プログラムや助成金 AFS https://www.afs.or.jp/ YFU http://yfu.or.jp/host/ P238 いい親子関係を構築する雑談ルール ・子どもに話させようとせず自分から話題をふる ・子どもが話題に乗ってきたら見逃さず話題を広げる ・話を遮ったり、せかしたり、否定したりせずに 最後まで聞く ・上から目線で話をしない ・話しやすい環境を作る P250 選択に迷っているときは、難しい道をアドバイス
1投稿日: 2019.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ参考になる事が具体的に書いてある。自信、考える力、コミュニケーション能力が幸せ人生を送るために必要という考え。子どもが中学生になる頃にもう一度読みたい。
1投稿日: 2019.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【全般】 6歳までは根拠のない自信を育てることが最も大事。そのためには「自分は親から愛されている。自分は価値のある人間だ」と思い込ませることが大事。褒めるときは具体的に褒めよう。子供の長所に気づき子供に教えてあげよう。叱る時はしっかりと叱る理由を言葉で説明して叱ることで子供の自己肯定感は育つ。また、母親のスキンシップが最も子供の情緒を安定させる。母親が笑顔で子供に接せられるよう父親は家事をサポートしよう。 6歳までの子育ての目標は ・根拠のない自信が身についていること ・文字に親しんでいること。本を1人で楽しんで読めるようになっていること。 ・英語の発音が頭の中に入っていること。 ・絶対音感が身についていること ①長女(3歳) ・文字に親しみを覚えさせよう。カタカナやアルファベットも遊び感覚で覚えさせよう。文字を書くことに慣れさせよう。6歳までに自分で本が読めるようになることが目標。 ・ごっこ遊びをして、コミュニケーション力、考える力、言語力を身につけさせよう。「このお店は体に良い食べ物はありますか?」などちょっと考えさせる質問をしてあげる。 ・子供が話をしているときはちゃんと聞いてあげる。聞く姿勢の手本を見せ子供の聞く力を育てよう。 ・子供に「もしも」の質問をして想像力を育ててあげよう。 ①もしXXだったら ②XXとYYだったらどっちがいい ③こういう場面があったら、あなたならどうする? ・本を読む時に質問して考える力をつけさせよう。「私はxxが好きだけど、yyちゃんは誰が好き?」など、自分の意見を言ってから聞こう ②次女(一歳) ・まだ言葉がわからなくてもしっかり話しかけよう。ちゃんと話してあげることで言葉が出てくるようになる。
1投稿日: 2019.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の中でかなり子育てに関する発見が多かった。 例えば我が子の部屋を作ろうかどうしようかと悩んでいたけど、まだまだ早いなぁと考えた。字を覚えるタイミングなんかは、長女は早かったが、この著書と一緒だったので安心した。 そんな風に全てが刺さらないけれど、どれかは自分の子育てに響くところがあるんじゃないかな。 そんな一冊です。 標準としているところから、詳しく細かい事例まではわからなかったので、本来はもっとその部分が知りたいなとも思った。
1投稿日: 2019.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分で決めさせるなど、確かになと思う部分と有益だと感じるところがあるものの、なにはダメ、どうするみたいなことが確信的に書かれている背景がよくわからなかった。子育ての解はない中で、この変化の速い時代に確信を持てるのか疑問が残る。
0投稿日: 2019.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これからの時代の子育て。3つの要件。 ・自信を育てる ・考える力を育てる ・コミュニケーション力を育てる ・抜粋(自信について) 過干渉は必ず子どもからやる気を奪い、自信を減退させます。親は「手出し・口出し」したい気持ちをグッとこらえて、子どもを見守ることが大切です。 人前で叱らないのは子供のプライドをつぶさないための配慮です。 赤ちゃん返りは母親の気を引くため 下の子は生まれたときから上の子がおり、「親の愛情は100%独り占めできないもの」「愛情は兄弟姉妹分け合うもの」という前提で生まれてくるので、下の子は少々愛情不足になっても問題がないのです。兄弟は上の子を中心に。 ・気になった部分要旨(考える力について) 学校任せでは子どもは勉強嫌いになる。勉強ができる子に共通する資質は、能力ではなく態度。その資質とは以下。 1.あきらめない 2.自制心がある 3.人の話を聞ける 4.柔軟に思考できる 5.正確さを追求する 6.チャレンジを恐れない つまり、キーは学習態度。6歳までに学習態度を身につけられるように親がそっとサポート。 子どもを育てるコミュニティ ・要旨 子どもを育てるのに大切はなのはコミュニティ。一つのコミュニティで辛くなっても違うところへ行ける。一つのコミュニティの中で、ある人に言われたら素直に聞けなくても、違う人に言われたら素直に聞けるということもあるから。 ・感想 部活の先生や尊敬する先輩に言われたことは正解だと思えるとか、小学校は嫌いだけど塾は好きで楽しいとか、上の考え方は私も正しいと思う。そういう環境を作ってあげたい。
0投稿日: 2019.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ妻が買っていたものをふと読んで見たところ、目からウロコの内容でした。 子育ての方法が非常に論理的に解説されており、ウンウンと納得しながら読んでしまいました。 非常に読みやすく、内容もしっかりしているので、何度も読んで実践していこうとおもいます。
1投稿日: 2019.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログどうしたら子供にやる気を与えられるのか、悩んでいた時に読みました。自分があまりよろしくない教育の例のほうでやっていたというのもいくつかあり、考えを改めなおそうと感じることが多かったです。
1投稿日: 2019.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の主観や経験による子育て論です。 「学力の経済学」を読んで以降、データを示さない主観や経験による子育て論は興味無くなりましたが、この本もそんな本です。 タイトルに世界標準と書いてますが、何が世界標準なのかよくわかりません。 海外留学に地方自治体からの補助金があるのは初耳だった。
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強ではなく、「自信」、「考える力」、「コミュニケーション力」が必要という考え方がとても為になった。また、子供の成長をサポートしていくという考え方もとても重要な事を知った。
1投稿日: 2018.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログそれなりに調べているっぽいところもあるけれど、だいたいは根拠を示さずに適当なこと言っている。特に最後のQ&Aはひどい。
1投稿日: 2018.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ子育て初心者にはとても参考になった。 実践的な内容も示してありながら、その目的が一貫しているので、なるほど、と思える。 いいな!と思えるところを取り入れていきたい。 娘の成長に合わせて、また読んでみようと思う。 絵本を読んでいる時に、どこが面白かった?なんで〜が好きなの?と質問をしながら読むの、楽しそうだなと思った。娘とこれからもたくさんコミュニケーションを取って短くも長い子育てを楽しんでいきたいなぁ〜とワクワク。 どんな大人になるのか、今から楽しみ。
1投稿日: 2018.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ思ったより内容は薄くタイトル負けしているが大事なことがきちんと書かれている。 育てるべきはは自信、考える力、コミュニケーション力。 特に自信のところは「根拠のない自信」を育てること、そのためには親がたっぷり愛情を注ぐことが大切で、それにより子どもは根拠のない自信を得て、それがすべての土台になるというところが印象に残った。 考える力やコミュニケーション力では親子の会話、絵本の読み聞かせの重要が語られる。 どれも基本的なことのように思えるが、その基本を身に付けさえるのが一番大事なんだと教えられた。
0投稿日: 2018.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ千差万別の「子育て」の標準なんて意味あるのか?と思いつつもなかなか面白く読めました。自信、考える力、コミュニケーション力の習得は必須だと思います。逆にいえば、それ以外は各家庭の好きにすれば良いとも言えます。
1投稿日: 2018.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人も、根拠のない自信がある。お母さんが育ててくれたのだとわかった。彼は三男だから、良い意味で、イイ感じに放っておいてもらったのも絶対良い点。主人はできることとできなさそうなことの線引きも上手い。「自分の身の程をよくわかってる」とよくパパは言うけれど、根拠のある自信もちゃんと自分で育てたのね。 インドの数学も印象的。How?で楽しく学べそう。息子に豆知識として教えてあげたい。武井壮も、もし子供いたらインドで数学勉強できる環境にしてあげたい的なこと言ってたのとリンクした。「ママのインド数学の勉強、助けてくれる??」とか絶対言わなきゃ! 中学から高校までの夏休みは6回しかありません。は、わかってたつもりだけど、ショック!そうだった忘れてた。今年長だから、高校までは…あと13回か!!少な! ブルーノマーズの練習法も参考になる。ブルーノマーズ、カッコイイよね、息子も踊るよ。まさか子育て本にブルーノマーズ出てくると思わなかった。船津先生も聴くのかな。先生のブログ最初から読まなきゃ。 息子もマイクラやる時、ヒカキンやカズさんのモノマネしてるからもっと持ち上げようと思う。
1投稿日: 2018.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書評だったか、広告だったかで目にした本書。売れているそうなので、読んでみました。 特別、目新しいことが書かれているわけじゃないと思います。けれど、多くの子育てパパママには、参考になると思います。 こちらに書かれている「自信」「考える力」「コミュニケーション力」を養うことは、私も同感です。 どんなに学業ができても、自分で考え、応用が利く人間でなければ、社会では役に立ちません。 これらを完全に身につけるのは確かに難しいですが、これらの力を伸ばそうと心がけながら子どもとの会話を10年も続けていれば、自然に自立していくと思います。 小学校を卒業するぐらいには、いつの間にか自分で考え、行動できるようになっているのではないでしょうか。 すごく当たり前のことが、書かれています。
1投稿日: 2018.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://www.diamond.co.jp/book/9784478102794.html , http://www.tlcforkidsusa.com/ , https://ameblo.jp/tlcforkids
0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ次の3つが大事 * 自信 * 考える力 * コミュニケーション力 自身の子育ての参考になった。
0投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログハーバードでも通用する子どもの3つの資質。北欧の子育てが世界一うまくいっている理由。アジア圏の子育てに共通する落とし穴…環境や時代の変化に負けない、たくましい子どもを育てる方法。(Amazon紹介より) 大袈裟なタイトルですが、書いてあることは至極当然な内容です。と同時に、子どもが人として成長する上で最も大切なことだと思いました。その大切な3つの要素が「自信」「考える力」「コミュニケーション力」だと本書は説いています。 私自身か子育てをするにあたり大切にしたいと考えることと、本書で説かれている内容が非常に近く、しかも具体的に書かれており、読んでいて今後の子育てのイメージが湧きました。また、自分の考えがある程度間違ってはいないと自信を持てました。
1投稿日: 2018.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・「自信」、「考える力」、「コミュニケーション力」が重要 ・過干渉は子供からやる気を奪う(P20) ・良い部分を具体的にほめる(P27) ・愛情たっぷり甘やかされると、やる気が育つ(P45) ・周りの目を気にしすぎる子育てが自尊感情をつぶす(P59) ・せきたて言葉でプレッシャーに弱い子に(P70) ・勉強ができるこの資質(あきらめない、自制心がある、人の話を聞く、柔軟な思考ができる、正確さを追求、チャレンジを恐れない)(P77) ・お手伝いで成功体験を積ませる(P97) ・習い事を10年継続させて「特技」まで引き上げる(P114) ・Comfort Zoneから出る(P119) ・長期休みには旅をさせる(P124) ・継続して「やりぬく」力を育てる(P129) ・
1投稿日: 2018.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログルーティーンを守ることが「継続」につながる。「指示、命令をしない」というのは『考える力の育て方』にも書いてあったなぁ。アドラーにも通じる? インド人が工夫して「楽して」計算するという話で同じだなと思ったこと。私はいつも何かに25を掛けるときに25メートルプールを思い浮かべて100掛けて4で割る。
1投稿日: 2018.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバル企業などで世界を股にかけて活躍する人になってほしいというのは、現在の親の共通の希望だろう。 著者は4000人の子供の教育を通じて、重要な3つの点を中心に紹介している。 彼の教え子の中で世界で活躍する人も、最初から優秀だったわけではなく、誰もが一度は「競争の壁」に阻まれて挫折や自信喪失を経験している。 その時支えとなるものが、困難に負けない「強い心」であり、その強い心は育てからによって身につく後天的な資質と言っている。 世界標準の子育て、3つの条件 自信:自分の力でできたという成功体験が重要。過干渉は子供のやる気を奪う 考える力:自分の判断で人生を切り開くための力 コミュニケーション力:多様性の世界を生きるには不可欠な力 その中で、自分が子供に対して行った事で反省する事は、褒めるとき、しつけのために褒めてしまったケースが多かったように感じる。またそのようなときは命令や否定の言葉を使って怒っていたと思う。 もっと早くこの本を読んでおけばよかったと思った。 勉強ができる子の資質 諦めない 自制心がある 人の話を聞ける 柔軟に思考できる 正確さを追求する チャレンジを恐れない 本書で横浜国際交流ラウンジの存在を知ったので、 機会があったら子供に紹介したい。
0投稿日: 2017.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
子育てに関する本は数多く読んでいるが、本書はその中でも良くまとまっており、特に年齢を大きく3段階(幼児期、小学校、中高)に分けて、親と子供の関係性からどのように子供に接するべきかを説いている。 子供の自主性を尊重する、親は子供の鏡、子供を大人と同様に対応に扱う、子供の強みを見つけて伸ばしてあげる、といった点を気を付けていきたい。 【はじめに】 ・自信の源泉は、子供が自分の意志で物事に取り組んだときに「自分の力でできた!」という成功体験にもとづいて生まれるものです。つまり、子どもの自主性を尊重して、子どもがやりたがっていることをやらせてあげなければならないのです。しかし、「他人へ迷惑をかけないこと」「集団のルールを守ること」を重んじる日本の子育てでは、子どものやりたいことを自由にやらせるよりも、子どもの行動を制限しようとする場面が多いのです。子どもの行動をコントロールできる(=きちんとしつけている)親が「良い親」であり、集団のルールを守れる子が「良い子」である。そんな文化が社会の根底にあり、親子に無言のプレッツャーを与えています。もちろん、公共の場や集団でのルールを教えることは大切です。しかし、親が過剰に周囲の目を気にして「あれしちゃダメ!」「これしちゃダメ!」と子どもの行動を制限していると「自信育て」においてまずい結果を招くことになるのです。 ・過干渉は必ず子どもからやる気を奪い、自信を減退させます。「人の手を借りずに自分でやってみたい」「自分で試してみたい」というのは人間の自然な欲求なのです。それを「危ないから」「汚すから」「時間がかかるから」と親が横どうしてしまうと、子どもの成長機会を奪ってしまいます。これは、子どもが何歳になっても同じです。親は、「手出し・口出し」したい気持ちをグッとこらえて、子どもを見守ることが大切です。 ・もちろんほったらかしなのではなく、一人の人格者としてマナー、エチケットなど、社会的責任を伴うことも厳しく指導します。子どもが公共の場所で騒いだりすれば、親は即座に子どもをその場から連れ出し、毅然とした態度で行動を非難します。人前で叱らないのは子どものブライドをつぶさないための配慮です。 ・日本の学校教育のように数値で評価できる知識や技術をへハードスキル」と言います。一方で明確に数値化できない技術や能力を「ソフトスキル」と言います。すなわち、論理的思考カ、分析力、批判的思考力、問題発見力、問題解決力など、「〇×式テスト」で評価することが難しいスキルのことです。今、世界の学校教育の主流は「ソフトスキル」に移行しつつあります。教科書を読めばわかる知識を教えることよりも、答えのない問題にどう取り組むべきか、考える技術を教えることが、学校の役割だと考えられているのです。 【6歳まで】 ・子どもは親のマネをして成長します。親子を観察すると、表情、しぐさ、話し方、身ぶり手ぶりがそっくりなことがわかります。つまり、親が良い手本を示せば、子どもにも良いコミュニケーションが身につくのです。 ・0歳から4歳くらいまでにかけては、子どもと密接に関わる機会は母親のほうが多く、母子関係によって子どもの精神面・人格面の土台がつくられていきます。父親は母親をサポートして母親の育児ストレスを軽減することが必要です。 ・まず、子どもが心の土台(情緒や性格の方向性)を形成する6歳までは、子育ての主役は母親になります。 ・イギリスのニューキャッスル大学の「育児における父親の役割」調査によると、成長期に父親と多くの時間を過ごした子どもは知能指数が高く、社交性があり、より高いキャリアを得ることが報告されています。 ・最近は日本でも「褒める子育て」が定着してきているようです。ただし、日本人が形だけアメリカをマネて子どもを「えらいね」と褒めていると、ちょっとちではぐなことになるのです。アメリカ人は「自分の意思で行動できた→褒める=自立を促す」なのです。一方、日本人の子育ては「協調性のある子に育てる」「行儀のいい子に育てる」という「しつけ」目的が根底にあります。だから子どもを褒める時も「言うことを聞けてえらいね」「がまんできてえらいね」というように、「指示やルールに従えたこと」を褒めるケースが多いのです。日本人は「言うことを聞けた→褒める=従順を促す」です。 ・成長を認められ、褒められて育っと、自発的な「やる気」も強くなり、勉強も習い事も意欲を持つてチャレンジするようになります。子どもの成長を褒める機会を増やしたければ、子どもの意思を尊重して、やりたいことをやらせてあげればいいのです。 ・アメリカ人の「褒める子育て」を観察しくいると、もう一つ特徴が見えてきます。それが「良い部分を具体的に褒める」こと。 ・私は「甘やかし」自体はさほど悪いことだとは思いません。多少わがままでも自己中心的でも、愛情をたっぷり受けて育った子どもは自尊心が強く「やる気」があり、社会でもまれていく中で成長していける資質を持っているからです。 ・アメリカの大学は「多様性が新たな価値を創造する」ことを信念としているので、人種・学カ・個性・才能のバランスを考慮して合否を決定しようとします。異なる価値観や文化を持っ人たちを集めて意見を闘わせることで、人間的な成長が生まれ、優れたリーダーが育成されることを、大学の長い歴史の中で学んできたからです。 ・母親の表情は、必ず子どもにうつります。何千人もの親子を見てきましたが、子どもはお母さんとそっくりな表情をするのです。もちろん、父親も笑顔になることで、「笑顔になりゃすい家庭環境」になるので、意識して表情を明るくしていきましよう。 ・大人を相手に聞く時とまったく同じです。くれぐれもせかしたり、否定したり、話をさえぎったりしないでください。子どもの話を聞く時は、話の内容よりも「子どもの心に共感すること」を意識しましょう。親が「聞き上手」になると、子どもの側からどんどん話をするようになります。 【7~12歳まで】 ・私は世界中の子育てを見てきましたが、日本の子どもたちの自尊感情が低い原因が「人に迷惑をかけない子育て」、「他人の目を気にしすぎる子育て」にあるように思えてなりません。集団における調和を何よりも大切にする日本人は、世界から見ると「人の目を気にしすぎる」のです。今のままで日本人は十分「人に迷惑をかけない国民」です。 ・自尊感情は、変化する時代に対応していくための「チャレンジ精神」、「楽観性」、「立ち上がるカ」の源となります。謙遜を美徳とする日本には「うぬぼれ」や「自意識過剰」は悪いことであるという考えがあります。しかし、子どもが自分のことを好きになれなければ、自分を大切にすることも、他人を大切にすることもできません。大きな挫折を経験した時、子どもの心を支えるのは「あなたが大切な存在である」「あなたには価値がある」「あなたはあなたのままでいい」という、親からもらってきたメッセージです。失敗しても、欠点があっても、トラブルを起こしても、「決してあなたを見放さない」というスタンスが、子どもをタフにします。 ・日本人の場合は親から子供への愛情が足りないことが多いのです。親は十分だと思っていても、子どもには不十分であるケースがほとんどです。この「愛情のすれ違い」に一刻も早く気づかねばなりません。もっとも重要なのが「スキンシップ」で、「肌と肌のふれあい」が親の愛情を効果的に伝える手段なのです。言葉でいくら伝えても愛情を実感することはできません。 ・常に子供を急かせる焦りの子育ては必ず失敗します。反対に、親が寛大な態度でいると、子どもは気楽になり、それまでできなかったことがウソのようにうまくできるようになります。そして成功体験を積み重ねていけば、子どもの自信は復活します。 ・身内(パートナーや友人等)への悪口は世界ではほとんど見ることのない日本の悪しき習慣です。欧米社会では身内の悪口は御法度であり、身内を悪く言う人は、ひるがえれば自分の恥や価値観の狭さを世間にさらしているようなものなのです。 ・子どもを「子ども扱い」するのは、「子どもを自分の分身」だと考えているからです。そのため、平気で命令や指示言葉を使ってしまいます(相手が他人の子だったら「ああしなさい」「こうしなさい」「ダメ」と頭ごなしに言いませんよね)。親子の甘えた会話から大人同士の会話へとコミュニケーションカを向上させるには「指示」「命令」を極力やめることです。大人同士が話をするように子どもと会話をしましよう。 ・演劇が教育の場で人気なのは、コミュニケーションカを高めてくれるからです。人前で堂々と話す技術、表情、身ぶり手ぷりを使って意思疎通する方法、相手に伝わりやすい発声・発音の方法、相手に親しみを与える話術など、コミュニケーションスキルのすべてが演劇を通して身につくのです。 ・かんしゃくを起こす子どもは欲求不満状態です。親が過度に子どもの行動に干渉していると子どもはストレスが溜まってかんしゃくを起こします。子どもが自分の意思でしようとしていることを親が先取りしていませんか?しばらく手出し口出しをせずに子どもを見守りましよう。親が気長に待つことでかんしゃくは滅っていきます。 ・子どもがウソをつくりは何かを訴えたい(たいていは寂しい思い)気持ちを無視されたという不満が一番多いのです。「なんでウソばかりつくの」と叱るのではなく、子どもがウソをつかなければならなくしてしまった自分たちの子育てを見直すことが先です。多くの場合、親がロやかましく、ガミガミ・ネチネチしていると子どもはウソつきになります。一方的に叱りつけるのはやめて、親子のスキンシップと対話を増やしましょう。良き親子関係が構築できればウソをつく必要などなくなります。 【13歳~18歳まで】 ・子どもを競争に参加させる目的は大きく2つ。ーつは、競争を通して自分の「強み」に気づかせるためです。自分の「強み」を知り、強み」に磨きをかける。それを自覚させるためには競争が必要なのです。2つ目は、困難に立ち向かうカ、敗北から立ち上がるカ、プレッシャーの中で実力を発揮する力など、「たくましい心」を育てるためです。もちろん競争すれば、敗者になることもあります。陸上競技で負ければ、「自分は足が遅い」という現実を突きつけられるでしょう。しかし、それも子どもにとって必要なことなのです。「自分は足が遅い、だから他の分野でがんばろう」と思考を転換するきっかけになります。自分の「強み」も「弱み」もよくわからないまま大人になってしまうと、進学や就職で失敗することにつながります。 ・次の3つの組み合わせを分析すると、子どもにとってべストな習い事や将来の学校選択・職業選択の方向性が浮かび上がってきます。 1.性格・人柄・対人関係(優しい、人なつこい、気長、気強い、繊細、外交的など) 2.興味・関心(動物が好き、機械が好き、美術や造形が好き、音楽や踊りが好きなど) 3.運動能力・身体的特徴(身体が大きい、カが強い、すぱしつこい、持久力があるなど) これらについて、子供の強みと思えることを、あまり深く考えず頭にパッと思い浮かぶことを書き込んでください。そして、子どもの「強み」を伸ばすことができる習い事やアクティビティは何か、夫婦で話し合う機会を持ちましょう。理想は子どもの適性に合ったことで、かつ親がサポートできるものです。子どもの特性に合わない習い事をやらせたり、親の希望で習い事を選んだりするのはやめましょう。子どもに強制するのはダメですが、習い事を選定するポイントとしては「親が経験したもの」あるいは「親が知っているもの」をおすすめします。親が経験していれば初歩の技術を教えることができます。また、うまくなるためにどれだけの努力が必要なのか、自分の経験を子どもと共有することができます。その結果、子どもは回り道なく技能を向上させていくことができるのです。 ・特にチームで行なうスポーツの場合には、コツコツ努力する根気強さ、失敗を恐れずチャレンジする精神、仲間と助け合う心、最後まであきらめない忍耐力、プレッシャーに負けない精神力、チームの一員としての責任感、コーチやサポートしてくれる人たちへの感謝の心や尊敬の心などを得ることができます。これらの精神は、世界の企業が求めるリーダー像そのものです。スポーツは子どもの自信を育て、助け合いの精神を育て、リーダーシップを育成してくれる。だから子どものスポーツ参加が重視きれるのです。 ・子どもたちが自分で「強み」に気づくことはできません。最初は親や周囲の人が見つけて「あなたはここがすごいよ」と教一えてあげることが大切なのです。子どもが自分の「強み」を意識し、その部分を伸ばすことに集中すると「特技」へと速いスピードでレべルアップできます。なお、習い事を特技に引き上げる一つの方法が「すきま狙い」です。ごく普通の才能や体格の持ち主の子どもであれぱ「すきま狙い」にターゲットを切り替ると、成功する確率がグンと高まります。 ・「自分が一番」という状態よりも、さらに自分よりも優秀な人がいるレべルの高い環境にチャレンジしたほうが大きく成長できます。人は、あえて居心地が悪い場所へ行くことで、知識や技能を向上させられるのです。少し難しい環境、今よりもレべルが高い環境に子どもをチャレンジさせることによって「成長を止めない」ようにすることが、「根拠のある自信」をより強く、確信に変えていくために必要です。 ・べストな選択は、実力よりも少し高いレべルの学校です。間違いなく合格できる学校、実力よりも低いレべルの学校に入っても、入学した後の成長が小さくなってしまいます。少し上のレべルの環境に身を置くと、まわりの生徒から多くの刺激を受けます。そして「自分も負けないようにがんばろう」と学業や課外活動にさらに努力するようになります。そして学生時代を通して成長を続けられるようになるのです。 ・子どもが失敗を恐れるのは自然なことです。しかし、失敗を恐れて挑戦しないと、そこで成長が止まってしまいます。大切なのは親が「結果に寛容」であること。結果よりも「努力することに意義がある」という態度を保ちましょう。失敗してもいいからチャレンジを続ける、居心地の良い場所から外に出る。そんな態度を身につけた子どもは目標に向かって一直線に歩んでいけるようになります。 ・女の子は、親(特に母親)が「手本やルールを提示してあげる」のが基本です。女の子は男の子よりも人間への関心が強く、人を観察する力が鋭いのです。子どもが最初に他者と出会うのは母親。すなわち、母親が子どもと信頼関係を築き、人生の先輩として立ち居ふるまい、礼儀作法、コミュニケーションの手本を示してあげると、そのとおりにマネしてくれます。お母さんがいつも笑顔で、明るく、礼儀正しく、人に優しくふるまっていれば、子どももそのとおりに育つのです。女の子は「ルール/集団の調和をもたらす決まりごと」を好む傾向があるので、「手本を示す」→「マネさせる」→「努力を褒める」を繰り返していくと、しつける勉強も習い事もどんどん成長していきます。 ・ティーンエイジャーに「考えるカ」の重要性を伝えるキーワードが「選択」です。選択することによって、自分のことがよくわかるようになり「好き・嫌い」や「イエス・ノー」をはっきり表現できるように育つわけです。日本人の子育てでは、幼い子どもに選択させることはほとんどありません。食べ物も洋服も、靴も、カバンも親が選んで与えるのが一般的です。親からすれば、子どものためにより良いものを選んであげくいるわけですが、その一方で、子どもが選択する機会や「僕はこれが好き」と意思表現するチャンスを奪っているとも言えます。子どもは自分で選ぶことによって自分の好き嫌いを認識できます。またモノを大切に扱うようになります。 ・留学先は欧米に限らずアジア諸国でも十分です。重要なのは期間で、2週間くらいではダメです。その国の人たちと、その国の言葉でコミュニケーションをとれるまで、最低でも半年はかかります。海外で異文化の人と接することで、ところ変われば見方が変わる、世界には異なる価値観があるというグローバルな視野を身につけることができます。 ・子どもがあまり話をしなくなったら、子どもにかけている言葉が「質問」「尋問」「命令」ばかりになっていないか、自分を見直してみてください。そして子どもを一人前扱いして、他人と接する時と同じょうに敬意を持って丁寧な言葉で接してください。 ・欧米では子どもがテイーンエイジャーになると「Keep kids busy/忙しくさせておく」ことを心がけます。部活、塾、趣味、ボランティア、アルバイトなど、多くの活動に参加させて、多様な人付き合いをしているとイライラが分散するのです。また忙しければ、無用なトラブルに巻き込まれることも少なくなります。また、もう一つの対策として「タイムマネジメント/時間管理」を教えてください。自分のスケジュールを自分で管理できるように導くのです。なぜスケジュール管理が重要かというと、子どもがスケジニール管理をできなければ、親が「宿題やりなさい」「早くしなさい」と言わなければならず、親子の衝突が絶えなくなるからです。 ・算数の問題でケアレスミスを繰り返す。やり方がわかつているのに見直しができずにテストで悪い点をとってしまう。この問題は子ども自身が「正確さを追求するクセ」を身につけなければ解決しません。親や先生からいくら言われても子どもが自分で直そうと本気にならなければダメなのです。算数の計算でミスそしたら、ほったらかしにせず、正しい答えがわかるまでやり直させてください。間違った回答は消しゴムで消さないこと。間違った回答の横に正しい答えを書かせましよう。一度間違いを消してしまうと同じミスを何度も繰り返します。自分のケアレスミスを認識させるために、わざと間違った答えを残しておくのです。「正確さを追求するクセ」を身につけるには長い時間がかかります。ご両親は根気づよく子どもの勉強(大切なのがミスを直す作業)に付き合ってあげてください。
1投稿日: 2017.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ将来の変革の時代に柔軟に対応できるようになるために、自信、考える力、コミュニケーション力をつけるような子育ての方法が述べられている。この3つの条件にまとめられているのがとても分かりやすくて良かった。 人生100年の時代に、子育ては18年。あっという間に過ぎ去るのでこの18年は子供にしっかりと注ぎ込みたいと思えた一冊。
1投稿日: 2017.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に標準って?と言い出せば切りがないのでしょうけれど,客観的に感じるととても参考になることがたくさんです。 どんどん親も子供もチャレンジしてみたくなりますよ。
1投稿日: 2017.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【子育て・教育】世界標準の子育て / 船津徹 / 20170928 (75/671) < 303/84219> ◆きっかけ ・日経広告 ◆感想 ・そもそも子育てに世界標準なんてあるのか?というツッコミはしたくなるが、3つの条件は至ってシンプル。 1) 困難に負けない「自信」 2) 人生を自分で決めていくための「考える力」 3) 人に愛される「コミュニケーション力」 ・今迄の子育て方針とは違ってないが、他方でいずれも十分でないと思う。やはりtop priorityは自信を付けるということだと思う。積み重ねてきた実績を伴った自信も結構だが、それをレバレッジにして根拠のない自信も大いに身に着けてほしいものだ。このあたりは、別の書籍等でもう少し深堀していきたい。 ・「高校受験、大学受験、就職、結婚、転職、独立。人間はいくつもの『大きな選択』をして成長していきます。多くの人はその時々の『選択』によって人生が決まると考えていますが、本当に人生を決定づけているのは『日々のささいな積み重ね』です。 (中略)何か一つ、コツコツと10年継続することができれば、子どもは大きな自信を得ることができます。」 ◆引用 ・世界標準の子育ての3つの条件 -自信:干渉を減らして、成功体験を積ませる -考える力:答えの問題(ハードスキル:計算問題)ではなく、答えのない問題(ソフトスキル:論理力)が重要 -コミュニケーション力 ・母親の心の余裕こそ、子供の人格を育てる。そのために夫が妻を支えること。 ・日米のほめ方の違い -アメリカ人:自分の意思で行動できた=>褒める=自立を促す -日本人:言うこと聞けた=>褒める=従順を促す ・良い部分を具体的に褒める ・多少わがままでも、愛情たっぷり受けて育った子供は自尊心が高く、やる気があり、社会でもまれていく中で、成長していける資質を持っている。 ・覚える学習から考える学習へ ・命令・否定言葉を使っていると、キレやすい子になる。親のイライラは伝染する ・兄弟は上の子中心でいい。下の子は生まれた時から上がおり、親を100%独り占めできない、兄弟で分け合うものと分かっている。上はそうではない。 ・勉強が出来る子の資質 -あきらめない -自制心がある -人の話を聞ける -柔軟に思考できる -正確さを追求する -チャレンジを恐れない ・学習態度を決定するのは6歳までの習慣つくり ・自信を育てるには -スキンシップで愛情を伝える -お手伝い等で成功体験を積ませる -下の子の面倒を上の子に頼むと兄弟の仲が良くなる -小学校に入ったら競争に参加させる(競争を通じて自分の強みに気付かせる) ・強みの見つけ方 -性格、人柄、対人関係 -興味、関心 -運動能力、身体的特徴 ・勉強で獲得した自信はもろく、崩れやすい ・習い事を10年継続させて、特技まで引き上げる。根拠のある自信を大きくしてくれるのが継続。 ・花形よりも競争の少ないすきまが狙い目 ・あきらめ癖の原因と解決法 -自信不足=>手だし口出しせず見守る -成功体験の不足=>子供の意思で選ばせる -ルーティーンの欠如=>日々の繰り返しを重視し生活習慣を改善する ・男の子はおだてて育てる。女の子は手本を示して育てる ・考える力の土台になるのが育てる力 ・本読み;質問をしながら読み聞かせる。感想も(パパはここが面白かったけど、どこがおもしろかった?) ・計算プリントに取り組ませて数字への抵抗感を取り除く ・間違っても消しゴムで消さず、残しておき、空欄に書きなおさせる。 ・NET シンガポールマス ・子供に選らばせる。選ぶことによって好き嫌いを認識できる。モノを大切に扱うようになる。選択を意識できると、人に流されなくなる。 ・もし~だったらゲーム(もしどこでもドアがあったら・・・) ・父親は人生の先輩としてのアドバイザー、母親は子供 の体調や精神管理をするサポーター ・たくさん笑わせて、感情表現が豊かな子にする。そのためには、子供の気持ちに親が共感することが大切。 ・大人に混ざって、会話・交流させる ・小学校低学年まではプラス暗示が特に効く(お前はできる等) ・ティーンエイジャーに暇させてはいけない。タイムマネイジメントを教える。欧米ではkeep kids busyを心がける ・母親のストレスは父親が解決すべき課題
0投稿日: 2017.10.04子育ては親が問われる
4歳と1歳の娘を育てているが、 本書にあるような「自立心を育てるために褒める」をしたいと思いつつ、「従順に対して褒める」をついついしがちであることに反省させられた。 「女の子の子育ては手本を示す」というのもなるほどと思った。実践してみよう。ちなみに男の子は、「おだてて育てる」。まあこれは、なんとなく納得。 子育ては親自身の真価が問われるものだと意識するために、時折この本に立ち返ろうと思う。良書です。
0投稿日: 2017.08.01
