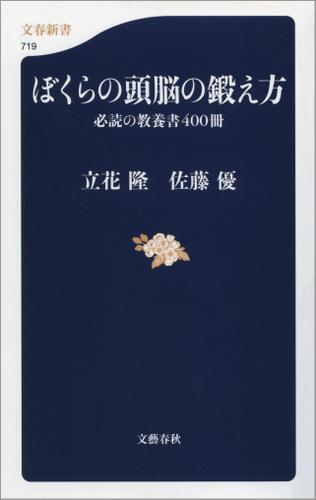
総合評価
(157件)| 35 | ||
| 59 | ||
| 35 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ激しい知的興奮を感じたとても刺激的な一冊! 圧倒的な読書量を誇るお二人だけあって、名著にまつわる対話を聞いているだけで教養が身に付いた気がしてしまいます。 特に第三章「ニセものに騙されないために」と第四章「真の教養は解毒剤になる」は面白かった。 興味深いポイントを何点か列記すると… ・日本人に欠けている最大の教養はゲオポリティクス(地政学)であり、これが分からぬゆえ、大戦中に「欧州の天地は複雑怪奇」ということで総理が辞職してしまう。 ・人間のダークサイドに関する情報が現代の教養教育に徹底的に欠けている。虚偽とは何か、詭弁とは何かについて学んでおくべき。 ・いざ大変なことが起こると、日本の官僚組織では、ただ「うまくやれ」というとんでもない指示が上から来る。最終的に失敗したら、「何できちんと報告しないんだ」と部下に責任を押しつける。 ・ニセ科学の破壊力はかつてないほど大きくなっている。検証すべき情報が厖大であると、とりあえず識者が言っていることを事実として受け止めてしまう。テレビのコメンテーターが説明していることを確かだろうと受け入れる。これが怖い。 ・教養の定義は「人間活動全般を含むこの世界の全体像についての幅の広い知識」というようなことになる。 などなど… お二人は200冊ずつ計400冊を本書の中で紹介していますが、単なるブックガイドにとどまらず、読み物としてもとても深い内容の一冊でした。 脳に刺激の欲しい方に強くオススメします。
0投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優さんの選書は難しいなぁ。 気になった本は次のとおり。 「影を裁く日」高柳芳夫(講談社文庫) 「人間の條件」五味川純平(岩波現代文庫) 「たのしい・わるくち」酒井順子(文春文庫)
0投稿日: 2025.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ対談と本の紹介の2部構成。 紹介されている本も刺激的だったが、対談もすごく刺激があり、あっという間に読み終わりました。 本を読む習慣が出来たのは、ここ数年なので、知らない本や著者が多く、今後本を選ぶ際の参考になりそうです。 実際、この本を読んだ後、本屋や図書館に行ったら、目につく本のバリエーションが増えました。
0投稿日: 2024.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養の定義とは、 人間活動全般を含むこの世界の全体像について幅広い知識。 その人の精神的自己形成に役立つすべてのもの
0投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ正月の夕べに知的な刺激に浸ろうと本書を手繰ると、古典の読み方から戦争論やインテリジェンス、勉強法まで、知の巨人と知の怪物が繰り広げる縦横無尽の語り合いが、やはり面白かった。 知の全体像を掴むために、巨大書店の書棚をすべて隅から隅まで見て回るのは、本書で立花隆氏が言及したのを読んだのがきっかけで、もう10年前続く私の小さな習慣になっている。 立花隆氏が冒頭に挙げた「東大教師が新入生にすすめる本」と「教養のためのブックガイド」にも、今年は目を通しておきたい。
1投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ第五章が面白い。 日本人に欠けている最大の教養アイテムはゲオポリティクスだと思います。という立花隆の言葉が印象的。
1投稿日: 2022.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ新緑の中に身を置くと心も体もピッカピカ。今の季節は何処に行っても気持ちいい。静かだとなお良い。 最近は静かなのが心地よい。自宅では意識してテレビを消す様にしている。音を伴う映像を見ると疲れを感じるのはやはり歳のせいか。 なので、本を読む時間が自然と増えてきた。小説が多いけど、ノンフィクションもたまに読む。 小説以外の本を読む時は、適当に選ぶと当たり外れが大きいので、立花隆や佐藤優の書評を参考にすることが多い。 すると、この2人が対談している新書を偶々見つけたので早速読んでみた。知性の塊りみたいな2人だがユーモアがあるし、人間味の温かさも感じて昔からファンだ。 立花隆の書斎「猫ビル」が近隣にあって、ジョギングでよく脇を通った。生前、本人を見かけたこともあるが、家族らしき人の肩に手をかけてゆっくり歩いていた。 佐藤優は著作を読むと超ストイックな印象だが、メタボっぽいし、声のトーンも高くて可愛い感じ。ただ、最近はかなり痩せてきた。遂にダイエットに成功したのかもしれない。 今回読んだ新書「ぼくらの頭脳の鍛え方」は、2人合計で400冊の本を勧めているが、歯応えの強そうな本が多く、全部読みこなすのはかなりしんどそう。 紹介された本は歴史、哲学物が多い印象だが、柔らかい本もある。しかしなんと言っても2人の対談内容がバツグンに面白く、それだけでも読む価値ありと思った。 マルクスやフロイトなど、2人の評価がけっこう違う本も多いし、著作に関するエピソード、コメントが楽しい。立花隆の学生時代の話や、佐藤優の外交官時代の話、刑務所にいた時の話など大変興味深い。 常に傍に置いて、次に読む本の手引き書みたいに使うことにしよう。
5投稿日: 2022.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ぼくらの頭脳の鍛え方 必読の教養書400冊 立花隆氏と佐藤優氏による対談集。 電子版2017年6月20日発行 底本2009年10月20日刊行 2009年の対談集なのでやや時代を感じる所もある。 ただ異常な知的欲求者達の対談集といった所。 一般人は真似できない。 いくつかを時間をかけて読んでいく。 地道に自分の血肉にしていくことだろう。 佐藤優氏も池上彰氏との対談本と違い、立花隆に圧倒されてる感あり。 個人的には日露戦争の乃木希典の評価で全く異なる立場になった箇所は興味深い。 ただ日露戦争時から兵士の命を軽く考えていた事、 やみくもな特攻精神といったものは203高地の戦闘で 悪い意味で伝説化してしまった所はあると思うので ここは立花隆氏の言うように乃木希典は愚将であると思う。 印象に残った部分 立花隆による「実践」に役立つ14か条 (あくまで仕事と一般教養のための読書について、趣味のための読書についてではない) (1)金を惜しまず本を買え。本が高くなったといわれるが、基本的に本は安い。一冊の本に含まれている情報を他の 手段で入手しようとしたら、その何十倍、何百倍のコストがかかる。 (2)1つのテーマについて、1冊の本で満足せず、必ず類書を何冊か求めよ。類書を読んでみてはじめて、その本の長所が明らかになる。そのテーマに関して健全なパースペクティブを得ることができる。 パースペクティブ【perspective】. の解説 · 1 遠近法。透視図法 2 見取り図。 · 3 将来の見通し。展望。 (3)選択の失敗を恐れるな。失敗なしには選択能力が身につかない。選択の失敗も、選択能力を養うための授業料だと思えば安いもの。 (4)自分の水準に合わないものは、無理して読むな。水準が低すぎるものも水準が高すぎるものも、読むだけ時間のムダである。時は金なりと考えて、高価な本であっても、読みさしでやめるべし。 (5)読みさしでやめることを決意した本についても、一応終わりまで1ページ、1ページ繰ってみよ。意外な発見をすることがある。 (6)速読術を身につけよ。できるだけ短時間のうちに、できるだけ大量の資料を渉猟するためには速読以外にない。 (7)本を読みながらノートを取るな。どうしてもノートを取りたいときには本を読み終わってから、ノートを取るためにもう一度読み直したほうがはるかに時間の経済になる。ノートを取りながら一冊の本を読む間に五冊の類書を読むことができる。たいていは、後者のほうが時間の有効利用になる。 (8)人の意見や、ブックガイドのたぐいに惑わされるな。最近、ブックガイドが流行になっているが、お粗末なものが多い。 (9)注釈を読み飛ばすな。注釈には、しばしば本文以上の情報が含まれている。 (10)本を読む時には、猜疑心を忘れるな。活字になっていると、何でももっともらしく見えるが、世評が高い本にもウソ、デタラメはいくらでもある。 (11)オヤと思う個所(いい意味でも、悪い意味でも)に出合ったら、必ず、この著者はこの情報をいかにして得たか、あるいは、この著者のこの判断の根拠はどこにあるのかと考えてみよ。それがいい加減である場合には、デタラメの場合が多い。 (12)何かに疑いを持ったら、おつでもオリジナルデータ、生のファクトにぶちあたるまで疑いをおしすすめよ。 (13)翻訳は誤訳、悪訳がきわめて多い。翻訳書でよくわからない部分に出合ったら自分の頭を疑うより、誤訳ではないかとまず疑ってみよ。 (14)大学で得た知識など、いかほどのものでもない。社会人になってから獲得し、蓄積していく知識の量と質、特に、20代、30代のそれが、その人のその後の人生にとって決定的に重要である。若い時は、何をさしおいても本を読む時間をつくれ。 (朝日ジャーナル 1982/5//7初出 「ぼくはこんな本を読んできた」文春文庫収録) 今、教養という言葉は死語になりつつある。また万巻の書を読み尽くせる人はいません。 結局は、人生の残り時間を確認しながら、最大の成果を得られるように計画を作るしかない。そのとき、知識の系統樹が頭に入っていることが大切です。 読者にお勧めなのは、巨大書店の書棚をすべて隅から隅まで見て回ることです。 すべて見るのが大変なら、文庫と新書コーナーだけでもいい。 現代社会の知の全体像が大雑把でもつかめると思います。 Amazonもいいけど、書店の棚にはやはり全体像がある。 頭が悪くなる勉強法(佐藤優) 国家公務員一種とか、司法試験を3回も4回も受けたらいけないんです。 一定の時間、机に座って、記憶したことを一定の時間に紙の上に再現する記憶と条件反射しか使いません。 それを一つの分野でやりすぎると頭が悪くなる。 受験勉強に時間をかけすぎると、頭が悪くなって、 その枠組みから抜けられなくなるんです。 だから、外務省の中でも苦節4年とか、苦節5年で入ってきた外交官で使い物になるやつは一人もいない。 東大の大学院は東大の学部よりレベルが低いと言われています。 大学院入試の語学試験というのは明らかに大学よりレベルが低くなっている。 (立花)ホリエモンというのは、ときどき面白いこともいうけれど、 ときどきアタマおかしいんじゃないかと思うようなことも言う。 これもアタマおかしいほうの発言ですね。 ゲノム解読で死なない人間ができるなんてことはありえません。さまざまの病気が解明されて、寿命が長くなるということはあるでしょうが、生命現象が解明されればされるほど生命現象に永遠の継続がないということがわかりつつある。 生命現象の本質の中に死というものがある。 生きているということはいずれ死ぬということです。 100 %当たる細木数子 (佐藤)あともう一つ心配しているのは、占いブーム。 細木数子さんの占いというのは100%当たる占いなんです。 例えば「このままの姿勢だったら、来月の5月、文春新書はスッテンテンになって、文春新書の編集長は地獄に落ちるわよ」と、こういう予言なんですね。 (立花)そう、そう。 (佐藤)来年の5月、編集長を更迭になっていたら、予言が当たったんです。 ところが、編集長に留まり、文春新書が当たっていたら、「私が言ったとおりに心を入れ替えたから、当たった」ということになって、やっぱり当たるんです(笑)。 これは論理学で言う所のトートロジー(恒真命題。 「AはAはである」というような常に成り立つ命題」ですよね。 彼女はトートロジーを作る天才なんですよ。 「明日の天気は雨か、雨以外のいずれかです」という天気予報をしているようなものです。 だから、彼女の占いは100%当たる。 こういうトートロジーに対する耐性がヨーロッパやアメリカにはあるから、もし政治家や占い師がトートロジーを唱えると 「ふざけるな、おまえ」という話になります。 ところが日本はそうならない。イラクへの自衛隊派遣の是非をめぐる小泉首相(当時)の国会答弁を日本人はおかしいと思わないでしょう。 「戦闘地域とはどこですか」 「それは自衛隊が出動していない所です」(小泉) 「じゃあ、自衛隊はどこに出動しているんですか?」 「非戦闘地域です」(小泉) 「じゃあ、非戦闘地域とは何ですか?」 「自衛隊が出動している所です」(小泉) こんな国会答弁にも関わらず、国会が止まらない。 総理大臣に対して不信任案も出されない。 それはトートロジーという絶対に勝つ論理を使ってもいいんだという、 他の世界とは違うゲームのルールが、この国にはあるからなんです。 (2021年11月8日に細木数子が亡くなった。TV出演が多かった2005年のレイザーラモンHGとの対決くらいしか印象が無かったもののトートロジーという手法をうまく使っていたという佐藤優氏の指摘にはうなずける所が多い。今後トートロジーを使うものが再び表れた時に厳しく指摘していく必要があろう】 (立花)要するにホロコーストを進める時の、上司の指示の出し方が 「うまくやれ」なんです。それを現場が忖度して、ホロコーストを実行する。 そうすると、ホロコーストがいかに行われたのかについて証拠を探そうとしても、きちんとした命令があるわけではないから、あちこちの証拠が抜けている。その抜けている部分の証拠だけをつないで論を立てると、ホロコーストはなかった、という証明になってしまう。 (佐藤)「うまくやれ」という言葉の中に、ものすごい暴力性があるんですよ。 (佐藤)嘘をつく部下がいると、傷口が広がって取り返しがつかなくなることがあるんです。 だから私は、嘘をつかない限り部下のどんなトラブルに対しても、絶対に叱らなかった。 どんなトラブルがあっても、私に申告してくれば、上司との関係においてもトラブルを起こした奴の味方をした。 そうすれば私のところに相談に来ますから。 (立花)大学の教養課程でも「暗黒社会論」「悪の現象学」的なコースを設けるべき。悪徳政治家、悪徳企業の嘘を見破る技法、メディアに騙されない技法を教えることが現代の教養には欠かせません。 (立花)人間のダークサイドに関する情報が、現代の教養教育には決定的に欠けていますね。この社会には、人を脅したり、騙したりするテクニックが沢山ある。それは年々発達しているから、警戒感を持って、自己防衛しないと、簡単に餌食になってしまう。 虚偽とは何か、詭弁とは何かについて学んでおくべきですね。 (佐藤)権力党員である条件は、権力の一番の中心には入らない。 堺屋太一さんのように閣僚になるとか、あるいは政府の諮問委員になってしまうと権力党員からは脱落する危険性がある(笑) 権力は、いつかどこかで入れ代わりますから。 権力に批判的な姿勢を取りながら、必ず権力の内側にいる。 これが権力党員のコツですから、常に建設的批判者でなければならないんです。 建設的批判者だといっても、反体制的、左翼的にはならないんです。 私の考えでは、ニュースキャスターで評論家でもある田原総一朗さんはホンモノの権力党員なんです。 私は田原さんを大変に尊敬しているんです。 なぜかというと、独特の技法を持っていないと権力党員の党籍を維持できないからです。これは皮肉で言っているのではありません。 メディアと政治をつなぐ回路として権力党員はとても重要です。 しかし、立花さんは田原さんとは決定的に違う。権力党員ではなくインテリゲンツィアなんです。 インテリゲンツィア・・権力にとって都合の悪い存在 (立花)客がそれぞれ孤立していますよね。いかにも陰謀ができそうな喫茶店というのは、いつ頃東京からなくなったのかしら? (佐藤)バブル期でしょうね。喫茶店が地上げの対象になってなくなっていった。 (佐藤)中略 ところでソ連時代のモスクワには喫茶店がほとんどありませんでした。 あと、酒場や一杯飲み屋もほとんどなかった。 とにかく喫茶店といっても大衆食堂型で、客に食わせたら、すぐ外に出してしまう。30分いられる喫茶店がないんです。 スターリンが政策としてそういうふうにしたんです。 (佐藤)中略 人間というのは環境に順応する力がすごく高いんです。 ポイントは途中で保釈されないこと。保釈されると、娑婆に戻って他の人と話をすることで現実を取り戻す。しかし一切保釈なしで面会も認められず、取調官と裁判所のあの閉鎖空間の中に入ってしまうと、やっぱり独自の世界観ができて、迎合してしまう。 (立花)佐藤さんがギリギリの所でこらえることができたのは、やっぱり読書体験があるからですか。一種の疑似体験というか。 (佐藤)そうです。読書による疑似体験の力はものすごく強い。 あの檻の中で耐えられたのは、ソ連崩壊の時にいろんな人間模様を見た経験と読書による疑似体験、その2つがあったおかげです。 (立花)僕は、203高地の勝利で、日本人は悪いことを学習してしまったと思っているんです。 殺されても殺されても、鉢巻き締めて、突撃していくわけですから、あれぐらい馬鹿げた戦法はない。 乃木希典は日本を誤らせた最初の人間だと思う。バカの一つ覚えのような決死隊の突撃を繰り返させた乃木は部下の大量殺戮者ですよ。 あの乃木を朝野をあげてほめたたえたところから、日本人の戦争観は狂ったものになってしまった。 太平洋戦争末期にバンザイ突撃による玉砕戦法がくり返された愚も、みんなあの乃木のバカをほめたたえてそれを陸軍の伝統にしてしまった所から来ている。乃木は自分の過ちを知っていて、天皇の赤子を殺して申し訳ないという気持ちで明治天皇崩御の直後に自決したんです。 (佐藤)中略 戦争にはその国の知力が結集されます。だから軍事にはその国の民族的な性格が表れる。そこが教養としての軍事モノの面白さの一つですね。 (立花)中略 狂った政治思想はみなユートピア思想から生まれている。 政治の基本は、ユートピアなんてものはないし、作ろうと思えば逆ユートピアを生むだけだったという歴史の現実を直視するレアリズムの認識から出発すべきです。 (立花)中略 歴史は常に反復するということを教養として知っておくべきなんです。 あの戦争を起こした右翼の連中が狂っていたように、戦後史においても連合赤軍のような極左過激派の思想や、オウム真理教のような宗教にまで、狂った思想がたびたびあらわれた。同時代の歴史だけを記憶していては、危険な歴史が反復しうることを見破れない。 (立花)中略 あのころの右翼は、みな現体制をテロ、クーデターなどの強硬手段でぶっつぶす所までは真剣に考え、ある程度実行にも移したが、その後どうするかは真剣に考えていない。近代をつぶせば理想の天皇と結びついた古代理想国家が再生すると根拠もなく信じていた。 一種のユートピア思想なんです。 (立花)中略 人間にはもともと読書をする遺伝子は備わってはいない。 実際、人類において書き言葉の歴史より話し言葉の歴史の方がはるかに長いんです。 要するに、本の世界以前に、音声による伝承の世界がある。 伝承文化が積み重なった結果として、文字文化が生まれるわけです。 だから、文字を読む、本を読むための脳回路は親と教師が育てる必要があります。 (立花)脳と読書・識字の相関は脳科学の世界では常識です。 日本語の場合、平仮名があって、片仮名があって、漢字がある。 それで音と文字と意味とがそれぞれ微妙にずれている。脳はこうしたずれがあればあるほど、その複雑さに順応するために高次の発達をとげるんです。 だから日本人の脳はすごくいい脳になった。 かつて日本語をローマ字にしてしまえとか、志賀直哉が「日本語を廃止して、フランス語を採用せよ」なんて言いましたが、とんでもない話です。 (立花)中略 人間がどの言語世界で育ってどのような文字を読んでいるかで、脳が全然違ってくる、と今読んでいる 「プルーストとイカ」(M・ウルフ著 インターシフト)という脳科学の本に書かれている。日本語で育つか、中国語で育つか、英語で育つかによって脳が変わってくる。 「知」の世界への入場券 (佐藤)立花さん、蔵書数はどれくらいあるんですか? (立花)地下一階、地上三階のビルを仕事場にしていますが、十年ほど前に数えた時には、約3万5千冊でした。 (佐藤)ビルの外装がネコの顔になっている「ネコビル」ですね。 (立花)ええ。舞台装置家の妹尾河童さんに描いてもらった。 ネコビル近辺にも本の置き場があります。現在の正確な蔵書数はわかりませんが、十年で倍ぐらいになっているとして、7、8万冊でしょうか。佐藤さんはいかがですか? (佐藤)約1万5千冊です。最近、箱根に二番目の仕事場をつくり、思想・哲学系の本は都内の仕事場からそちらに移しました。 立花さんは毎月、本代にはどれくらい費やしていますか? (立花)これも正確には把握していません。医学書や理系の専門書を大量に買うときは、50万円くらい使う時もありました。しかし、それほど高くない本なら、両手で持てる重さの限界が、だいたい3、4万円でしょう。月に4回それくらいの買い出しをするとして十数万円じゃないですか。 (佐藤)私は約20万円です。サラリーマン(外交官)時代も月10万円が本代で消えていました。 (この蔵書数、書籍代の話は異常で一般人には真似できない。池上彰氏もそうだが・・。書籍を置く場所の問題は切実だ。一般人はKindleなどの電子書籍で保有するのが良い) 2021/11/14(日)記述
0投稿日: 2021.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養をつけたいのと立花隆の推薦に興味があり購入。実利的には佐藤優推薦の方が良いかも。少しずつ血肉にする。
0投稿日: 2021.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆氏が亡くなったので、私が普段よくその著作を読む佐藤優氏の対談集をなんの気無しに読んで見た。 立花氏の著作を読むのは、学生時代に読んだ「日本共産党の研究」以来だ。 紹介された計400冊のうち読んだことあるのが8冊程度だった。気になる書籍は時間がある時にでも読んでみよう。お二人がすすめる書籍の購入には、転勤族で家も狭く荷物にもなり、少し抵抗があるので図書を利用するが… 戦争もの、軍事ものが意外に数多く紹介されており、二人とも根は男の子なんだなと笑えた。
0投稿日: 2021.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大学の教養課程でも、暗黒社会論、悪の現象学的なコースを設けるべき。悪徳政治家、悪徳企業のウソを見破る技法、メディアに騙されない情報を教えることが現代の教養には欠かせません ガンにも個性があって、どれ1つ同じガンはないということが次第にわかってきました 日本共産党と言う組織は、マルクス主義の特約にやられた、宗教団体なんですよ 人間の認識と言うのは、すべてが経験・感覚入力の基盤の上に成立するものであって、もし、感覚入力を全て取り去ったら、認識能力そのものが崩壊してしまうと言うことを、たくさんの感覚遮断実験が証明しています 現代語訳般若心経 玄侑宗久
0投稿日: 2021.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいて楽しくなった。旧制高校時代と比べ今のエリートは確実に教養に欠ける。自分自身も高校、大学時代の読書量は少なく、殆どの時間を意味のない暗記に費やしてしまった。これから死ぬまで読書を重ね少しでも失われた時間を取り戻したい。 立花さんのご冥福を心よりお祈りします。
0投稿日: 2021.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館にて借りた本。 立花隆さんと佐藤優さんが対談形式で本を紹介する話。 自分は今まで、漫画→小説→ビジネス書→歴史関連ときているが、その次は哲学や教養書になりそうだ。 そうならないといけないと思わせる本だった。 教養とは、「未知の問題に対して、そういうことをテキストから読み取る力」と紹介している。 最後に立花隆さんが本の読み方14箇条を挙げている。 参考になりそうなものを抜粋していく。 「命を惜しまず本を買え。」 「必ず一冊で満足せず類書を読め。」 「速く読め。」 「疑いながら読め。名作ほど間違いはある。」 「並行して5冊読め。」 !若いうちは、何を差し置いても本を読む時間を作れ! 5冊は物理的に重くなってしまうので、3冊くらいで並行読みしていきたい。 まだ私のレベルでは難しい本を多く紹介されていたので、成熟していったら読んでいきたい。
1投稿日: 2021.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りたはいいが、最後まで読み切ることが出来ず、改めて借りてしっかりと読みたい本。 2人の話は自分にとってちんぷんかんぷんなことが多く、 立花さんが本書で述べている通り、自分の水準に合ってない本なんだろうな、と。 おすすめの本は全てピックアップしたので、 自分の読みたい本と合わせてゆっくり読んでいこうと思う。 そしてまた、自分が読書好きと言えるようになるくらい、読書を進めた先に、改めて読みたい一冊。
1投稿日: 2020.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ぼくらの頭脳の鍛え方 (文春新書 719) (和書)2010年02月07日 23:22 立花 隆・佐藤 優 文藝春秋 2009年10月17日 参考になったよ。 メモしていきたい本が何冊かあった。 「外国語上達法」千野栄一著 「デュシャンは語る」マルセル・デュシャン著 いろいろあって400冊は多い。僕の読書能力ではまともに読んだら5年はかかるだろう。
0投稿日: 2020.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「知の巨人」立花隆氏と「知の怪物」佐藤優氏の必読教養書400冊 対談形式である ブク友さんのレビューをみて気になったのだが… 読む前から圧倒されてしまう 果たして自分が読んでも良いものか、と恐れ多くなるが、怖いもの見たさ的な好奇心から読んでみた 蔵書数ももちろん驚愕なのだが、お二人とも毎月の本代は十数万〜二十万円とのこと(ひぇ〜) 実際読んでみて、(想定内の)知らない本だらけ、対話の内容も、お手上げの内容も多い しかし、グイグイ引き込まれて読めてしまう 揺るがない確固たる自分を持っている方の底力というのはこういうものか、と、ひたすら圧倒されるのだが、お二人のそれぞれの考え方がそれぞれで面白い(もちろん、それはちょっと…と受け入れがたいものもあったが) そいういう見方があるのか…とかね 例えば 「カラマーゾフの兄弟」実は神を信じていないドストエフスキーの本心が透けて見える とし、ドストエフスキーの小説が流行するような社会は「病んでいる」と考える佐藤氏 また「蟹工船」は労働問題をカリカチュア化されてしまっている とご立腹な佐藤氏 政治や外務省、外交秘話的な話も面白い 大物政治家や、著名人の知られざる一面 凡人には刺激的だ 本を紹介しながら時代背景も対談してくださる 例えば コーヒー・ハウスが政治的陰謀の場に… それを把握していたスターリンはソ連全土から無くさせた! ちなみにロンドンにもあったが、この当時はインド植民地化の前のため、コーヒー文化があったそうだ コーヒーハウスは喫茶店の原型 現代のスターバックスでは、人に話しかけたりはしない(笑、確かに) ニセものに騙されないために スパイ小説でダークサイドを探れ 週刊誌の俗悪記事をたくさん読んでいる人の方が知恵がつく 現代の教養教育に人間のダークサイドに関する情報が欠けている 人を脅したり騙したりするテクニックが発達している世の中 → なかなかダークサイドを知る勇気が出ない つい目を背けてしまう 家人の本棚にある「ルポ西成」「売春島」とか、どうも手が伸びないが… 佐藤氏とロシアつながりの米原万里氏の本が、2冊ほどピックアップされていた 「オリガ・モリソヴナの反語法」については、ロシア人がいかに友情を大切にするか、スターリン主義が何であったか、反語法を学ぶための最良のテキストとしている(ふふ今は本棚で崇めているので読むのが楽しみである) また優れが書評集とし「打ちのめされるようなすごい本」も紹介されていた シュライエルマッハーのように「直観と感情」で読んでいるとなかなか褒めておられる(米原さんは佐藤氏の書評で手厳しいことを述べられていたが…(笑)) ■立花氏の「教養」の定義 ・人間活動全般を含むこの世界の全体像についての幅広い知識 ・その人の精神的自己形成に役立つすべてのもの ・現代社会を支えている諸理念の総体 ・知っていないと恥ずかしい知識の総体 ・各界で教養人とみなされている人々と恥ずかしくない会話を持続的にかわせるだけの知的能力 → なるほど 一生かかっても教養人にはなれない… でも教養は年齢に関係なくいくつになっても、いつでも必要だからこそ、これからも学び続けよう! ■立花氏の「実戦」に役立つ十四カ条の抜粋 ・金を惜しまず本を買え→はいそうします ・一つのテーマについて必ず類書を何冊か求めよ→只今実践中です ・自分の水準に合ったものを読め(高くても低くても時間の無駄)→それが理想だが、合った本を見つけるのが至難 ・本を読みながらノートを取るな、どうしてもノートを取りたいときは、読み終わってからノートを取るためにもう一度読み直せ ノートを取りながら一冊読むより、五冊の類書を読む方が効率的→これは難しいのです せめて各章ごとではダメですかね… ・注釈は半分以上の情報が含まれることが有→最近はほぼ目を通します ・本を読むときは猜疑心を忘れるな 嘘、デタラメはいくらでもある→気を付けます! ・何かに疑いをもったら、オリジナルデータ、生のファクトにぶち当たるまで疑いをおしすすめよ→できる範囲で… ・大学で得た知識などいかほどのものでもない 社会人になってから獲得し、蓄積していく知識の量と質がその後の人生に決定的に重要→量も質も向上させたいものだ ◎今後ぜひ読みたい本リスト ■「二重らせん」ジェームズ・D・ワトソン ■「古代文明と気候大変動」B・フェイガン ■「嫉妬の世界史」山内昌之 ■「不思議の国サウジアラビア パラドクス・パラダイス」竹下節子 ■「『相対性理論』を楽しむ本 よくわかゆアインシュタインの不思議な世界」佐藤勝彦 ■「明治十年 丁丑公論・瘠我慢の説」福澤諭吉 うーん 正直生きている世界が違いすぎるため、あまり読みたい本は増えなかった(汗) しかしながら、こちらの知識が乏しくても、対談式のため読みやすく、また知らない世界を知ることができ好奇心が満たされる ためになることも、意外と失礼ながら下らないこともあったりと読み物として楽しめた
28投稿日: 2020.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと早く、大学一年生くらいの時期にこの本に出会っていれば良かった…読書を楽しむためではなく、あくまで社会に対しての態度を養うための教養を身につけるための最高のブックガイド。今からでも一冊でも多くキャッチアップしようというモチベーションになる。
1投稿日: 2020.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「教養とは何か?」がよくわかる本である。たしかにネットで情報収集しようとしても、基礎的知識がなければ検索ワードさえ思い浮かばない。本書は「知の世界」に入るためにはどのようにすればよいのかのパスポートのように思えた。 小生は立花隆氏の「中核vs革マル」と「天皇と東大」を数十年の時をへだてて読んだが、読後ともに興奮した記憶がある。 立花隆氏はだいぶ前から「知の巨人」と言われていた。そして今、佐藤優氏も同じ評価を得ているが、新旧の「知の巨人」の対談は実に興味深かった。 本書の内容は、マルクスからナウシカまで多岐にわたっている。立花隆氏が「風の谷のナウシカ」を映画版ではなくコミック版を押しているのは面白い。漫画の完全版と比べて映画版は「小指の爪だ!」との評価には思わず笑ってしまった。たしかにコミック版には深い思想性があった。 また立花隆氏の「日本の教育はガタガタで、経済的破綻の根っこには知的な破綻がある」との言葉にはズシンとした重みを感じる。せめてこの二人の著書を読むことにより足下に少しでも近づきたいものだと思った。
1投稿日: 2020.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆さんと佐藤優さんが400冊の愛読書を紹介しながら、「教養」をテーマに歴史や政治、科学などについて語った本。 読書という行為は、本の内容を覚えることをいうのではなく、本を通して自分の頭で物事を考えることをいいます。本書を読むと、そのことを強く感じます。
0投稿日: 2020.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ対談本。知の巨人と佐藤優で対談してるのにも関わらず、佐藤優の希有な経歴から来る話題に立花氏は引っ張られてしまうような場面もあった。これは佐藤優氏の話題が良いのか、立花氏の好奇心が強いのか。ロシアのエリートについてはもう少し聞きたかった。 当たり前だが一冊一冊に対してのコメントが少なく、ポンポンと出てくるのでもう少し深掘りして欲しかった。
0投稿日: 2020.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者両氏が、様々な分野から200冊ずつ本を集めて紹介する。 両氏の教養の幅広さと深さに改めて舌を巻く。 教養の全体図を把握するための一助になりそう。
0投稿日: 2020.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にレベルの高い対談をベースに展開していきます。 紹介された本が読みたくなります。 で、自分の教養のなさにショックを受けます
0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログジャーナリストでサイエンス・ライターの立花隆と、元外交官で作家の佐藤優が、合計二百冊の本を紹介しています。また、二人の対談では、いわゆるアカデミズムに限定されることのない幅広い知と教養のありかたとその意義について両者の考えが語られています。 たんなる読書家というだけでは終わらない二人の推薦する本という印象です。歴史や宗教についてすでに読んだことのある本についても、そうした視点からとらえることができるということに改めて気づかされたという意味で、興味深く読みました。
0投稿日: 2019.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ蔵書数が1.5万冊の佐藤優と7~8万冊の立花隆という化物二人の書評を元にした対談集かな。 なんかまさに知の巨人といった感じ。 これ位の教養があると世の中の見え方が全く違うんだろうな。 二人の知識の深さと幅広さに終始圧倒されます。 400冊の本を紹介しているけど、歴史、政治哲学方面が多いかな。 ちなみに自分はこの中に紹介されている本を一冊も手にとったことがありません…苦笑 ただ二人共古典を大事にされているそうで、紹介される本も名前くらいは聞いたことがあるような物がよく出てきます。 そういや社会の時間に習ったよなぁ、と思い出しながら楽しく読めました。 やはり古典にも目を向けないと駄目よね。。。 【メモ】 毛沢東は文化大革命のときに、民衆を愚民化して操りやすくするためにはリテラシー、読書能力を落とせば良いと考えた。本を読めば読むほど人間は愚劣になる、余計なことは考えるな、まずは行動せよ、と過去の論文を取り出して説いたのです。 →こういう考えのもと「書物主義に反する」という本が生まれたらしい。 恐ろしいと思うと同時に凄く理にかなっていると思った。独裁者が知識人を真っ先に虐殺し・書籍を処分するというのはよく聞くことだけに、読書の大切さを痛感させられる様な気がした。。。
0投稿日: 2019.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識の系統樹を頭に入れておくことは重要。 知の果てを見に行く。 果てが見える地点に立つ。 時間は有限であり その限られた中でいかに読書を楽しみ成長を楽しむか。 人生は面白い。
1投稿日: 2019.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ知の巨人と知の怪物が400冊の本を紹介する。対談形式で作られた本になる。 400冊となると、さすがに新書では触りしか紹介できず、水面を見ただけという印象。紹介する本が10冊ずつになると、話は濃密になるが編集者の企画力と編集力が問われるので、400冊にして二人に投げてパパッと纏めた感じだった。企画としては面白いが、やっつけ感があり勿体ない企画だった。そして、二人の意見はガッチリと噛み合うわけではなく、相手の反論をして別の事を質問して躱していることが多く見られた。実際にはもう少し話していて、清々しく討論をしていたのかもしれないが、時間も限られているだろうし、ページ数も限りがあるから、全体的にしょうがないのかな。 二人の解説を読みながら惹かれた本も数冊あったが、なかなか歯ごたえのある本ばかりが並んでいる。本書のような紹介本の中から選んで、本当に読書をする人はいるのだろうか。もしかして、みんな格好つけたいだけとか、紹介を見て読んだ気になりたいだけなんでしょう。その気持ちは非常にわかる。いつか読みたいと思っている、ヘーゲル、カント、シェリングは、思うだけで読めていない。
0投稿日: 2019.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログVol.59 400冊のブックガイド、知の巨人VS知の怪物編。 http://www.shirayu.com/letter/2010/000112.html
0投稿日: 2018.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治、宗教、国際情勢など多面的に、本を紹介してくれている。この世界について、そして自分について理解を深めたい人には面白い書。 最初の、佐藤優氏が1万五千冊くらい、立花氏が4万冊以上は本を持っているなど、二人の学びや読書へのスタンスが秀逸であり、刺激的。 佐藤優氏が、何度も、共産主義、マルクス主義、革命、小泉元総理などを批判しているのだが、なぜそれらについて否定的スタンスをとるのか、その論理を深く知りたいと思った。
0投稿日: 2018.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆さんと佐藤優さんの本をめぐる対談本。それぞれ推薦する100冊について論じ合っている。読む本に困ったら、ここに戻ってくるかなというところ。タイトルを眺める限り、ピンこないので、合わないのかも。成毛さんとホリエモンの対談本のほうがピンとくる。立花さんは、ホリエモンや勝間和代は好みではないようなので、好みが違うのであろう。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ"立花隆さんと佐藤優さんの「必読の教養書」、ブックガイドです。文藝春秋でも掲載されていたものを新書化したもの。この二人のインプット量が半端ではない。世の中をいろいろな視点から見つめて自ら考え続けるためには、こんな本を読んできたという体験談ともいえる。付録として立花隆さんの実践で役立つ14条というものがあるので、抜粋しておく。 1.金を惜しまず本を買え。本が高くなったといわれるが、基本的には本は安い。一冊の本に含まれている情報を他の手段で入手しようと思ったら、その何十倍、何百倍のコストがかかる。 2.一つのテーマについて、一冊の本で満足せず、必ず類書を何冊か求めよ。類書を読んでみてはじめて、その本の長所が明らかになる。そのテーマに関して健全なパースペクティブを得ることができる。 3.選択の失敗を恐れるな。失敗なしには、選択能力が身につかない。選択の失敗も、選択能力を養うための授業料と思えば安いもの。 4.自分の水準に合わないものは、無理して読むな。水準が低すぎるものも、水準が高すぎるものも、読むだけ時間のムダである。時は金なりと考えて、高価な本であっても、読みさしでやめるべし。 5.読みさしでやめることを決意した本についても、一応終わりまで一ページ、一ページ繰ってみよ。意外な発見をすることがある。 6.速読術を身につけよ。できるだけ短時間のうちに、できるだけ大量の資料を渉猟するためには、速読以外にない。 7.本を読みながらノートを取るな。どうしてもノートを取りたいときには、本を読み終わってから、ノートを取るためにもう一度読み直したほうが、はるかに時間の経済になる。ノートを取りながら一冊の本を読む間に、五冊の類書を読むことができる。たいていは、後者のほうが時間の有効利用になる。 8.人の意見や、ブックガイドのたぐいに惑わされるな。最近、ブックガイドが流行になっているが、お粗末なものが多い。 9.注釈を読みとばすな。注釈には、しばしば本文以上の情報が含まれている。 10.本を読むときには、懐疑心を忘れるな。活字になっていると、何でももっともらしく見えるが、世評が高い本にもウソ、デタラメはいくらもある。 11.オヤと思う個所を(いい意味でも、悪い意味でも)に出合ったら、必ず、この著者はこの情報をいかにして得たか、あるいは、この著者のこの判断の根拠はどこにあるのかと考えてみよ。それがいいかげんである場合には、デタラメの場合が多い。 12.何かに疑いを持ったら、いつでもオリジナル・データ、生のファクトにぶちあたるまで疑いをおしすすめよ。 13.翻訳は誤訳、悪訳がきわめて多い。翻訳書でよくわからない部分に出合ったら、自分の頭を疑うより、誤訳ではないかとまず疑ってみよ。 14.大学で得た知識など、いかほどのものでもない。社会人になってから獲得し、蓄積していく知識の量と質、特に、二十代、三十代のそれが、その人のその後の人生にとって決定的に重要である。若いときは、何をさいおいても本を読む時間をつくれ。 何回も読み返しながら、気になる本から類書を含めて探索するべし。 ただし、目的意識がないと続かないので、ご注意を。"
1投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年10月20日 初版 サブタイトルは「必読の教養書400冊」 立花氏と佐藤氏がそれぞれ200冊ずつ「教養」を身につけるために読んでおくべき本を紹介している。 これを読むと、いかに自分が本を読んでいないのか、が痛烈に感じられる。目の痛い一冊。 基本的に最新の本を読みあさる前に、古典にあたるべきというのは納得できる。ウェブのブックレビューは新刊をフォローする事が多いのだが、こういう本の案内所はこれからの社会人にとって実はかなり有益であろう。 実際「何を読むか」というのはなかなか難しい問題なのだ、まったく。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優が書店に並んでいるのをよく見るが、今まで手に取ったことはなかった。しかし、立花隆との対談であり、書籍の推薦書ということでどんな本を推薦しているのだろうという関心もあり、読んでみた。 立花隆と同レベルの会話ができているし、進めている書物から推察するに、古典や歴史等に詳しい人なのかと思いきや、実務家だったからか、勝間和代や藤原正彦を進めているのには驚いた。立花氏が言うように、俗物過ぎ、他の推薦書と比べると明らかに温度差がある。しかし、氏が薦めるということで、ちょっと読んでみたくなってしまった。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「知の巨人」立花隆氏と、「知の怪物」佐藤優氏の対談本。 サブタイトルとして「必読の教養書400冊」と書かれている。つまり、「知の巨人」と「知の怪物」が、読むべき本としてセレクトした濃厚な400冊が紹介されているのですね。 正直、これだけ「知」を極めつくしたこの二人が対談をするとなると、両者一歩も引くことなく、壮絶な知的バトルが展開されて、収拾がつかないほどの喧嘩になっちゃうんじゃないかと心配でした。 ところがどっこいそんな心配は無用で、このお二方は、とても仲良く対談を楽しんでおられたのでした。 お互いの知を認め合いつつ、むしろこの機会こそ高質の知を相手から得られるチャンスとばかりに、自身の知らない部分はどんどん聞き出し、未知の世界へ食いついていき、そして自身の知との核融合させ、結果として自身の知も相手の知も増幅させるという相乗効果を生み出すことに互いに成功しているように感じました。 もちろん、ここで繰り広げられている対話のレベルは非常に高く、私にとってはむしろ空中で展開されているようにさえ感じました。正直のところ、ここでご紹介いただいた400冊のほとんどは、今さら自分には必要ないと感じています。また、これからの自身の人生において、これらを読むことが役立つかというとそうも感じられませんでした。 読みたいと思った本は、多少本棚に登録はしたものの、それほど増えませんでした。ここでお二方がリストアップされた本は、どちらかというと巨人や怪物にとっての最高の知のエッセンスなのだろうと思います。そこに至るまでに、もっと雑多な中間的な読書を多く経られたのだろう思います。従って、そういう中間的な読書もままならない者にとっては、いきなりこんなのを読んでもまだピンとこないだろうなと思います。 だけど、この本では、それらのエッセンスについて語り合われています。初耳のテーマや聞きなれないキーワードなんかも続出ですが、やはり頭のいい人たちが語ると、難しいこともなんとなくわかるように話してくれるし面白い。ニュアンスが伝わるというか、なんとなく分かったような気にさせてくれる(笑)。ですので、本書を読んだことは無駄ではなく、むしろ有効だったと感じます。
9投稿日: 2018.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく恐ろしいほど多くの本を読んでいる二人によるブックガイド。326頁のうちほぼ3分の1を占める124頁がブックリストに充てられ、両名が200冊ずつ(蔵書から100冊、文庫・新書から100冊)計400冊を紹介している。 と言っても本書で面白いのは対談形式をとって綴られる二人の読書ガイド。多少、二人の読書歴・知識自慢トーク合戦に見えなくもないが、佐藤氏の外交官時代の体験談は興味深い。 数えてみると、400冊のうち私が既読なのは15冊、読みかけて挫折したものが2冊でした。全部読もうとは思いませんが、面白そうな本を探すネタにしようと思います。
0投稿日: 2017.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
多少考え方に偏りがあり、受け入れ難い部分もありますが あらゆる分野に精通している教養の塊のような二人の対談で 自分がいかに無知なのかを思い知らされます。 歴史・政治・哲学・科学どれ一つとっても自分の教養が不足していることを 思い知らせてくれるのでここに挙げられている400冊を少しずつでも 読んでいかなければなぁと思います。 この本で取り上げられた400冊で読んだことがあるのは 「細胞の分子生物学」「100万回生きた猫」「沈黙」の3冊くらいですからね。 ただ、この本も2009年に発行されたものであり既にそれから8年近くもの 歳月が経っているんですよね。さらに沢山の本が発行されているわけで その中には当然読むべき本や読みたい本も沢山あるわけで そういうことを考えているとちょっと途方に暮れてしまいます。 そうは言いつつも千里の道は一歩からくらいのつもりで 気になった本をリストアップして読んで行きたいと思います。 でも1番魅力的に思えたのは最後の付録として挙げられている 立花隆選・セックスの神秘を探る十冊だったりします。
0投稿日: 2017.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログおおお...そういうこと知らないと 単に本読んでも理解できないのね。 なるへそ。 ...と思うが、別にそういう本読みたいとは思わないので 私にとって、まるっきし役にたたない退屈な本でした。
0投稿日: 2017.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が何を知らないかが解る本。 専門分野について門外漢であると、まず何が解らないかが解らない、何を読めばいいかも解らなくなってしまう。 本書では、分野ごとに本が選ばれ解説も載っているので、自分が興味を惹かれた本・必要だと思う本をピックアップしやすいのがいいと思った。 また、佐藤氏と立花氏のレビューの書き方がそれぞれ個性が出ているのが面白い。 佐藤氏は200冊全ての本について、3行~5行でレビューをまとめているのに対し、立花氏は何冊かまとめて一行でレビューを書いているものもあれば、何ページにも渡ってレビューを書いてある本もあるといった調子だ。 佐藤氏の方は「この本はどんな本?」と迷うことがなく、何故選んだのか根拠が全ての本において解り易いと思った。 対して、立花氏の方は、文章の量や論調で、彼のその本に対する感情や息遣いが感じられるようだった。 この400冊のレビューを読むだけでも、かなり読みごたえがあり、何冊か本を読んだような読後感と知識を得られると思う。 レビューの中で、知らない分野について見て行くのも勿論だが、自分の専門分野でどの本が選ばれ、専門外の知識人からどのように評価されているのか見るのもまた興味深かった。そのような見方をするのもまた一つの楽しみ方だと思う。 本書では、本についての両氏の対談も載せられているが、こちらも非常に刺激的で面白いので一見の価値あり。 ただ一方で、ここに紹介されている400冊を全て読んだとしても、両氏のようになれるわけではないのだろうな、と当たり前のことながら思う。 読書にプラスαして体験なりがないと、ここまで真に迫った喋りは出来ないよなあ、と思った。 以下、自分が読むべきと思った本を列挙しておく。読みたいと思った本は山程あるので割愛する。 ①自分が読むべき(自分に必要と思った)本:立花氏選 立-20「死ぬ瞬間」キューブラー・ロス→人間の死について 立-25「ヒトの変異」アルマン・マリー・ルロワ→人間の奇形について 立-26「心の先史時代」スティーヴン・ミズン→人間精神の起源について ②自分が読むべき(自分に必要と思った)本:佐藤氏選 佐-23「負け犬の遠吠え」酒井順子→同一律・矛盾律・排中律を見事に駆使して完璧な論理を打ち立てているらしい。佐藤氏にここまで言わせるとは凄い。 佐-118「ウィトゲンシュタイン」藤本隆志→現代の優れた知性の持ち主は、一人の例外もなくウィトゲンシュタインの影響下にあるとのこと。 ◎佐-119「精神分析入門(上・下)」フロイト 高橋義孝・下坂幸三訳→確か読みかけで本棚の中にある。 ◎佐-188「入門!論理学」野矢茂樹→対談で出て来ていた論理用語が全く解らず絶望(佐-23の3つの単語も何のことか解ってない)。これは必ず読みたい。
0投稿日: 2017.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2009年刊行。◆サイエンス関連の厚みが全く違う(立花氏>佐藤氏)一方、宗教関連の厚みが全く違う(佐藤氏>立花氏)というのが第一印象。とはいえ、博覧強記の2人が対談すれば、同機や対立という意味のみならず、相乗効果という意味でも面白いものができるんだなぁと。◇また、新書でも良書を選べば、十分知的興奮を味わえるのだなぁということを感じさせる一書でもある。◆ただし、2人の本意か否かは別として、セレクションにおける文春贔屓は顕著に伺える。
0投稿日: 2017.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり難しい内容でしたσ^_^; ただ小説も読まなあかんねんなあと思いました。 自分としては濫読を続けてるので知識としては一本スジが通ってきたように思います。 最近は佐藤優さんを中心に紹介されてる本を読んでるような感じです。 前は大前研一さんが中心やったんですがσ^_^;
0投稿日: 2016.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養とは、「知っていないと恥ずかしい知識の総体」とのこと。 著者の推薦本はすべて読むことは、(趣味嗜好もあるので)不可能だが、なるべく読んでいきたい。 「大学で得た知識など、いかほどのものでもない。社会人になってから獲得し、蓄積していく知識の量と質、特に、二十代、三十代のそれが、その人のその後の人生にとって決定的に重要である。若いときは、何をさしおいても本を読む時間をつくれ。」 胸に刺さる言葉であった。
0投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ二人とも、読書量とか知識量が化け物かと思う。ブックガイドという体裁を取った、知識の披露し合い本。二人の火花の散らし合いがけっこう面白かったり。
0投稿日: 2015.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015.7.4 読書についての本を読んでいます。 人類の中でも、おそらく最も多くの本を読んでいるのではないかと思われるお二方の、おすすめ本は見ておかなくては、ということで。 ちなみに恥ずかしながらどちらの方の著作も読んだことはないです。 教養のための読書、というテーマで選んだ本についての対談。 言っていることの意味は2割ぐらいしか分からないけど、めっちゃ面白かった!(←教養というか語彙のなさ) 「日本語の文法的には意味が分かる」ぐらいの感じなので、どちらかというとフィクションを読む面白さに近いかも(笑) 文庫は2009年に出版されていて(もともと文庫なのかしら?)ちょっと内容は古いんですけど、次読みたくなったら買おう、と思いました。(図書館で借りました)
0投稿日: 2015.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ癖のある2巨塔?の癖のあるおすすめ本紹介書。本の紹介部よりも、対談部の方が圧倒的におもしろい。歴史観の違いから、歴史の理解がすすむような感がある。とにかくなんにも知らない、ということを思い知らされたので、おすすめ書(にかかわらず)からまずは歴史関係書を読みたい。特に20世紀史は日本、世界史ともに激動の100年で、かつ飽きのこない濃い100年。しっかりとした知識を得たい。 それと良い工学書も。サイエンスというくくりでいくつかの書が紹介されたが、工学書こそもっと出てきて欲しい。今後とても重要な位置を占めるはずなので、もっと両巨塔には取り上げてもらいたい。分野まるごと。
0投稿日: 2015.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ"頭脳を鍛える方法=読書をすることと言っても言い過ぎでない。 本書は数多ある読書本の一つである。なぜこの本を薦めるかというと,学生時代の読書目標となる丁度良い数の本が紹介されているからである。学生時代には本を乱読し読書によって血沸き肉躍るという体験をしてほしい。本書はその助けとなるであろう。" *推薦者(図職)H.N *所蔵情報 https://opac.lib.utsunomiya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=BB00298163&initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
0投稿日: 2015.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「知の巨人」立花隆と「知の怪物」佐藤優が空前絶後のブックリストを作りあげたという帯のキャッチコピーに魅かれて読み始めましたが、まさに二人は「知の巨人」や「知の怪物」というよりむしろ「知の狂人」です。 2人共に本代に月々10数万~20万円位使っており、蔵書は立花隆は7万冊、佐藤優は1万5千冊。因みに司馬遼太郎記念館には「蔵書のうちの2万冊」とあります。全体では5万冊程度あるようです。 佐藤優が立花隆にチクリと「今日の対談にも、立花さんはかなりの本を持ってこられたのですが、私はほとんど何も持っていないのは、情報屋の感覚がまだ残っているからなんです。情報の世界で最後に勝負するときには、紙も何も持っていないですから」と言うのも面白い。 古い本や1冊のボリュームがある本が多く、ここに上げられた400冊を読むのは不可能です。私が読みたい(既読は除く)と思ったのは、新書・文庫中心に以下のものです。 立花隆選 ・ベスト&ブライテスト:ハルバースタム 朝日文庫 ・回想十年:吉田茂 中公文庫 ・松尾芭蕉から1冊 ・風の谷のナウシカ:宮崎駿 徳間書店 ・大日本帝国の興亡①~⑤:ジョン・トーランド ハヤカワ文庫NF ・ハル回顧録:コーデル・ハル 中公文庫BIBLIO ・文化大革命十年史(上・中・下):厳家祺 岩波現代文庫 ・安田講堂1968-1969:島泰三 中公新書 佐藤優選 ・日露戦争史 20世紀最初の大国間戦争:横手真二 中公新書 ・歴史と外交 靖国・アジア・東京裁判:東郷和彦 講談社現代新書 ・戦前の思考:柄谷行人 講談社学術文庫 ・CIA失敗の研究:落合浩太郎 文春新書 ・日本解体「真相箱」に見るアメリカ(GHQ)の洗脳工作:保坂正康 扶桑社文庫 ・不思議の国サウジアラビア:竹下節子 文春新書 ・米軍再編 日米「秘密交渉」で何があったか:久江雅彦 講談社現代新書 ・テロルの決算:沢木耕太郎 文春文庫
0投稿日: 2015.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆と佐藤優という2人の知の巨人たちの対話。彼らは知識人同士の対話だと少し本気を出すので、知識がない分野では内容についていけない。まあ、もちろん一般読者向けには配慮してはいるのだとは思うが、知識のなさが実感させられる。特に、哲学とか、安保抗争の話が個人的にはよくわからなかった。
0投稿日: 2014.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆と佐藤優、この二人の読書量がハンバなく多くて付いていけません。どうやったらそこまで読めるのだろうか? この本に挙げられている本を読みたいんだけど、時間とお金が足りないんだよな〜。テレビのグルメ番組を観るけど実際には食べられない感じな気分。
0投稿日: 2014.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆の頭の中のほんの端っこでもいい、覗けるかな。ブックリストを片っ端から読んでみるか。時間がいくらあっても足りないな。あとお金もね(苦笑)。
0投稿日: 2014.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ軍隊、国家、官僚は苗字しかない。下の名前なんてわからない。覚えない。 イスラエルの情報屋も戦争がゲームになるのではないか、と危惧している。 ソ連では喫茶店に30分いられなかった、陰謀の場になってしまうから。 読書人階級を復活させなければならない。本を読むのは1つの階級だから。 東ドイツの短編小説にはナチスの残党が多数登場してくるから面白い。 モサドやMI6は明らかにインテリジェンスを芸術して見ている。芸術的な感覚がないと政治も外交もわからない。インテリジェンスの問題に従事できる人間は天才でないといけない。余人をもって代え難しなので、情報の神様みたいな人が生まれてくる。
0投稿日: 2014.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「知の巨人」立花隆と「知の怪物」というよりは外務省のラスプーチンの通り名の方が有名な佐藤優の読書対談とお勧めの教養書400冊。蔵書はそれぞれ7〜8万冊と1万5千冊。毎月の本代が十数万〜20万円だそうだ。これだけ有ると100冊選ぶのが大変でむしろ1000冊にするか3〜5にするかの方が選びやすいとそれぞれの書棚からの200冊と新書・文庫から200冊を推薦している。 立花氏は「東大教師が新入生にすすめる本」と「教養のためのブックガイド」をたたき台におそらく大学生ぐらいを想定して選び、佐藤氏は40〜50歳くらいの教育現場に携わる人を思い浮かべて選んだそうだ。また、立花氏は全部読み通さなくても必要なときに資料としてみれば良い本を、佐藤氏は気合いでなんとかよ見通せる本を基準にしたといずれも教育現場のことを考えての選書の様だ。新書・文庫は書店に今並んでいる(2009年頃)というのが条件でこれは新書が定期刊行物化しているのと売れないとすぐなくなるからで佐藤氏は今度はに20〜30代ののビジネスパーソン向けに役に立つという観点で選んでいる。 対談はいきなり「ソクラテスは読書を否定した」から始まり一番最後にショウペンハウエルの『読書について 他二篇」にある読書と言うのは他人の頭で考えることだから、あまり本を読みすぎると頭が悪くなるという警告で締めくくられている。(笑)記憶と条件反射だけを鍛える受験勉強も頭を悪くするらしい。 立花の書棚からは自然科学16、人文12、歴史11、古典10、数学&哲学11、政治・法学10、思想9、文学15にファンタジー・SF・まんがから6(読んだのはどうやら2冊のみ) 佐藤の書棚からは宗教・哲学32、政治・国家23、社会・経済9、文学20、歴史16とくくり方が少しちがっている。(こちらも2冊、読みかけのローマ人の物語を1冊と数えるのは・・・) 二人が挙げているのが聖書、職業としての政治、オイディプス王の3冊で全般に題名は知ってる有名な本が多い。ちょっと硬めで手が伸ばしにくいが中には風の谷のナウシカ(立花)や花と蛇(佐藤)なんかもあり硬い一方ではない。 佐藤の新書は思想・哲学・宗教が29、戦争・歴史・天皇17、国家・政治・社会24、文学・物語8、マルクスと資本主義9、仕事術13、最近のベストセラーもあったが1冊も読んでいない。 立花の新書はあの戦争&ファシズム18、近代日本&現代史12、アメリカ7、軍事&憲法6、経済&マルクス4、戦後日本&全共闘6、世界史7、サイエンス17・・・と細分化されておりなぜかおまけにセックスの神秘が10冊。 こちらは1冊のみでした、読んでない本が多いということはガイドブックとしてはいいのか。自分の興味のままに色々読んでみれば良しとしよう。 付録には立花による役立つ14か条。①金を惜しまず②1テーマで類書を読む③失敗しないと選択力が身につかない④水準に合わないものは無理して読むな⑤読みさしで止める場合も一応さらっと最後までめくる⑥速読術⑦読みながらノートを取るな、たいていはノートを取る間に類書を読んだ方が良い⑧ブックガイドに惑わされるな(笑)⑨注釈もよめ⑩懐疑心を忘れるな⑪オヤと思ったらどこから情報を得たか、また判断の根拠を考えてみる⑫疑いを持ったら生のデーターにぶち当たるまで疑え⑬翻訳を疑え、誤訳もままある⑭大学で得た知識などいかほどのものでもない。社会人になってから獲得し、蓄積していく知識の量と質が重要。特に若いうちは。 対談中にも大学院のレベルが同じ大学の学部よりレベルが落ちているだの、中学英語が簡単すぎるのに高校で習う英語が難し過ぎる(完璧にマスターし語彙が3000増えれば以前の外交官試験、今の外務省の専門職試験に十分合格できるのだと)とか寄り道が面白い。佐藤氏は同志社大学3年時に教養向けの授業で先生の代わりに講義をしたことがあるそうだ。さすが怪人。
0投稿日: 2014.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中にはこんな人がいるのか、と頭を殴られたような衝撃が何度も何度も走る。 紹介されている本は面白そうなものばかりだけれど、読み切れないだろうなあ、この二人みたいに本の内容を血肉にするなんてできるのかなあ、とくらくら。 非常に刺激的な本。
0投稿日: 2014.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ某所の指摘で、佐藤優の"知性"が怪しいという話があり、指摘内容がもっともであったため、佐藤優の著書については途中で読むのをやめてしまった。
0投稿日: 2014.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2人とも読書量が膨大だな。 どちらかというと人物臨終図鑑とかを書いてくる立花氏の著書セレクトのほうが私の好みには合ってました。
0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優の自身の立ち位置をクリアに明かしてから、論評に入るスタイルには、安心感すら感じるのは何故だろう。難しいこと考えずに、この本でリストアップされていた本から自分が読みたいなと思った本を買って読んでみよう。
0投稿日: 2014.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に濃い中身のブックガイド。自分がどれほど無知か思い知った。長期休暇の度、どれだけ読めるか挑戦したくなる。
0投稿日: 2014.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ知の巨人 立花隆氏と知の怪物 佐藤優氏のブックガイド 文庫新書から200冊、書斎から200冊と、 文学、社会、政治、科学、宗教などあらゆるジャンルの幅広い本が選ばれています。 正直、お二方化け物です。 読書上級者にお勧めです。
0投稿日: 2014.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書とは疑似体験であり、着想の助力であり、詰まる所は、ただの言葉である。読み終えた後、何に感銘を受け、どれだけの言葉を拾ったか。ふと判断に迷う時、その言葉を引用できるか。あるいは、感覚として刷り込まれ、受肉されたか。本著はテーマが多岐に渡り、放たれた言葉は多い。しかし、それらを身につけるには至難である。 何気ない会話を記憶しているか。友人の発言で容易に生き方を変えられるか。映画を見たからといって、その体験がリアルに生活へ反映されるか。感受性の強弱はあるにせよ、身につくのは知識であり、知識は暗記であり、着想のヒントとし、知恵と変えるには、反復や咀嚼が必要だろう。 立花隆と佐藤勝、一級の知識人の知的刺激溢れる一冊。同じ情報に触れた二人でも、理解の異なる箇所があり、それが面白い。答えなどなく、ただ、物差しがあるのだ。
7投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ何の為に読書をするのか? その答えの一つが載っています。 本書は立花隆氏と佐藤優氏が教養書を400冊選 び出し、それについて意見を交わしたものです。 佐藤氏は、2002年に鈴木宗男事件に絡む背任容疑で逮捕され、512日間を獄中で過ごしたのですが、ギリギリのところで耐えることができたのは、読書のお陰だったそうです。 「読書による疑似体験の力はものすごく強い。あの檻の中で耐えられたのは、ソ連崩壊のときにいろんな人間関係を見た経験と読書による疑似体験、その二つがあったおかげです。既視感があったんです。」(p.130) 乱暴な表現ですが、読書することで、予習ができるんですね。 予習しておけば、いざとなった時に対策を取りやすい。 最近流行りの企業小説も、なぜ流行るかというと、疑似体験の側面が強いからでしょうか。 読書で多くの体験を学び、行動に繋げたいですね。
2投稿日: 2013.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏と立花隆氏が対談の形式を取って「読むべき本」の評を展開してます。2人とも、人によってかなり好き嫌いが分かれる方々だと思いますが、個人的には佐藤氏の論は分かりやすいので好きです。立花氏は好きでも嫌いでもなく、という感じ(笑) 前半では両氏が100冊ずつ、推薦書を挙げてます。が、絶版だったりやたらに高価だったりする本も含まれているようなので、参考までに、という感じで捉えました。 後半では新書に絞り、同様に両氏が100冊ずつを紹介しています。こちらは大きな本屋に行けばほぼ間違いなく並んでいるだろうな、というラインナップ。が、面白そうな本が多いのはやっぱり前半の方ですね。良書と出合うのはそれだけ難しい、ということなのでしょう。 佐藤氏の背景及び関心領域がキリスト教とロシア(ソ連)、それに外交なので、彼が紹介する本はそのあたりに根差したものがやはり多いです。対する立花氏は、第二次世界大戦を巡る世界情勢を含めた近代政治や科学に関する本の紹介が多い。前提として娯楽として読む本はほとんど紹介されていないので、その辺は割り切って読むべきです(立花氏は谷川俊太郎など詩人の作品も紹介してますが、ごくごく一部)。 ☆が3つと少なめな理由として、そもそも一般ウケするような本を紹介してない(笑)というのが一つ。これを本にして売った文春はスゲェな、と思いました。 あと、書評を集めてると言いつつ、実は立花氏が結構サボってる(笑)というのがあります。佐藤氏は、自分が紹介する全200冊を結構丁寧に紹介していて、読むべき理由や背景についても簡潔に触れてるんですが、立花氏は例えば第二次大戦に関する本を数冊並べたあと、「最低限これぐらいは読んでおくべき」ぐらいで終わらせてます。どんな内容なのかをざっくりであっても紹介するというのが書評の基本だと思うんですが、根こそぎひっくり返されたなーという印象です。まぁ、立花氏に言わせたら、この程度は四の五の言わずに読め、ということなのでしょうが。 いろいろ書きましたが、ちょっとカタめの領域に関する本を読みたい人なら、参考になる書評集だとは思います。
0投稿日: 2013.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「結局は、人生の残り時間を確認しながら、最大の成果を得られるように計画を作るしかない」につきるのだと思う。 文学嫌いの科学志向で無神論者の立花氏と正反対の佐藤氏だが、流石にこのレベルになると双方への興味関心なのか、通常は中身がない事になりがちな対談本だが面白く読める。佐藤氏はベストセラーもリストアップしており、その辺は読書に対する偏見がないなと思う。自分はどちらかと言えば佐藤支持かな。 教養とは社会で生き残っていくための「知」であるが、上澄みだけでなく俗悪なものにも触れる必要があり、その方が知恵がつくってところが印象的。まあこの世は俗悪だからね。が、それじゃいくら時間があっても足りなそうだが。 ちなみに最近はやりの刑務所読書だが、佐藤氏は512日で220冊。読書には最適な環境との事。やっぱ家にいたらPCあるしダメかな。刑務所はアレとしても図書館に篭るぐらいしないと。
0投稿日: 2013.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ必読の教養書400冊 ― http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784166607198
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ400冊も本が紹介されているのに、実際に自分が読んでた本がモモとナウシカぐらいだというのはどういうことなのか?
0投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「知の巨人」立花隆と「知の怪人」佐藤優による、対談形式で知性の磨き方の指南書。 必読の教養書として合計400冊が紹介されています。 この本を読んで確かに、これだけの読書量・知識量(教養)は驚嘆すべきことだとは思いますが、すべての国民がこれだけの教養を身につけていたとしたら違う世界になるかもと思いつつも、果たしてそんなことが可能なのかと感じてしまいます。 少なくとも、私には無理です。ここまで求めようとしたら、時間がいくらあっても足りません。 私にできることは、その見極めです。一体自分にとって今必要な情報・知識は何か、ということ。 それが明確になったときに、その分野のキュレーターを探すこと。 そのキュレーターが今回の著書でいうところの、立花氏かもしれないし、佐藤氏かもしれない。 (でも、今までこのお二方の著書をちゃんと読んでいないので、私にはまだ早いということでしょうか) 今回紹介されている400冊は確かにすごいとは思いますので、自分が興味を持った分野と合致した場合は参考にしたいと思います。 立花隆により「実戦」に役立つ十四カ条 (1)金を惜しまず本を買え。本が高くなったといわれるが、基本的に本は安い。一冊の本に含まれている情報を他の手段で入手しようと思ったら、その何十倍、何百倍のコストがかかる。 (2)一つのテーマについて、一冊の本で満足せず、必ず類書を何冊か求めよ。類書を読んでみてはじめて、その本の長所が明らかになる。そのテーマに関して健全なパースペクティブを得ることができる。 (3)選択の失敗を恐れるな。失敗なしには、選択能力は身につかない。選択の失敗も、選択能力を養うための授業料と思えば安いもの。 (4)自分の水準に合わないものは、無理して読むな。水準が低すぎるものも、水準が高すぎるものも、読むだけ時間のムダである。時は金なりと考えて、高価な本であっても、読みさしでやめるべし。 (5)読みさしでやめることを決意した本についても、一応終わりまで一ページ、一ページ操ってみよ。意外な発見をすることがある。 (6)速読術を身につけよ。できるだけ短時間のうちに、できるだけ大量の資料を渉猟するためには、速読以外にない。 (7)本を読みながらノートを取るな。どうしてもノートを取りたいときには、本を読み終わってから、ノートを取るためにもう一度読み直したほうが、はるかに時間の経済になる。ノートを取りながら一冊の本を読む間に、五冊の類書を読むことができる。たいていは、後者のほうが時間の有効利用になる。 (8)人の意見や、ブックガイドのたぐいに惑わされるな。最近、ブックガイドが流行になっているが、お粗末なものが多い。 (9)注釈を読み飛ばすな。注釈には、しばしば本文以上の情報が含まれている。 (10)本を読むときには、懐疑心を忘れるな。活字になっていると、何でももっともらしく見えるが、世評が高い本にもウソ、デタラメはいくらもある。 (11)オヤと思う箇所(いい意味でも、悪い意味でも)に出合ったら、必ず、この著者はこの情報をいかにして得たか、あるいは、この著者のこの判断の根拠はどこにあるのかと考えてみよ。それがいいかげんである場合には、デタラメの場合が多い。 (12)何かに疑いを持ったら、いつでもオリジナル・データ、生のファクトにぶちあたるまで疑いをおしすすめよ。 (13)翻訳は誤訳、悪役がきわめて多い。翻訳書でよくわからない部分に出合ったら、自分の頭を疑うより、誤訳ではないかとまず疑ってみよ。 (14)大学で得た知識など、いかほどのものでもない。社会人になってから獲得し、蓄積していく知識の量と質、特に、二十代、三十代のそれが、その人のその後の人生にとって決定的に重要である。若いときは、何をさしおいても本を読む時間をつくれ。 <この本から得られた気づきとアクション> ・読書の力はすごい ・自分の興味と方向性にあったキュレーターが大事 <目次> 第1章 読書が人類の脳を発達させた―狂気の思想、神は存在するか、禅の講話 ブックリスト1 知的欲望に満ちた社会人へ―書斎の本棚から二百冊 第2章 二十世紀とは何だったのか―戦争論、アメリカの無知、スターリンの粛清 第3章 ニセものに騙されないために―小沢一郎、官僚は無能だ、ヒトゲノム 第4章 真の教養は解毒剤になる―マルクス、貧困とロスジェネ、勝間和代 第5章 知の全体像をつかむには―東大生・立花隆、神学生・佐藤優、実践読書術十四カ条 ブックリスト2 すぐ役に立つ、すぐ買える―文庫&新書二百冊
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログよく,「何を読んだらいいのかわからない」という人がいるが, そのような人は,本書を読んでみてはいかがでしょうか? 世界の全体図が見えた方がいいとは思うけど, そんなに片意地を張らずに,興味が湧いた本から 順次,読み進めていけばいいと思う。 本書のような,道先案内本(ブックガイド)を参考にすると 効率はいいとは思うけど, 効率を重視すると,読書が酷くつまらなくなってしまう。 二人の読書量,知識量に勝てる気が全くしない(汗)。
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ"知の巨人"と"知の怪物"の対談はまさに次元が違う。頭脳を鍛えるために読書が果たす役割が大きいということなのだろう。文中で二人とも高校で哲学を教えるほうがいいと言っていたが、恥ずかしながら哲学をよくわかっていないのでブックリストを参考に勉強しようと思いました。
0投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ポパー「究極の真理は理性によって到達しえない」p41 インターネットの場合、バーッと流して見ていって、探している単語なりが引っかかったらそれでいいわけです。インプットではなくてスループットの検索。p56 シュライエルマッヘル『宗教論』「宗教の本質は直観と感情である」と定義することによって、神の場を、形而上学的な天から心の中に転換した近代の思想的起源を画する書。p82 【ヘーゲルの考えた枠組み】p180 矛盾、対立、差異 資本家と労働者の間に矛盾があっても、協同組合をつくることで、資本家と労働者の転換が可能になる。だから矛盾は解消できる。 対立は、一方がもう一方を完全に絶滅することで解消できる。 ところが差異は解消不能である。たとえば議論する相手から、「これは趣味だよ」と言われたら、もうその先には介入できない。趣味は差異だから。差異は解消できない以上、どうしても自分の立場を決めなければならない。だから、どっちの立場に立つかによって、世界は違ってみえる。 マルクス『ユダヤ人問題によせて』「宗教は人民のアヘンである」p263
0投稿日: 2013.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
発行された当時に購入して読んだ(2010年1月15日に読了)。その際には、「現代における教養の全体像を理解するにはよい。ブックリストも使えそう!」と感想を書いていた。 今回、3年ぶりに改めて読み直してみた。 立花隆氏と佐藤優氏の対談はいろいろな話に展開し、改めて知的な刺激を受けた。会話の内容が高尚であり、書いてある語句を電子辞書で調べながら理解を補った。両氏は単純に記憶しているだけでなくて、自分の知識として消化していることが伺える。 例えば歴史についても、「○○年に△△があった」、と受験勉強のようにひたすら暗記するだけでなく、その出来事が起こった際の社会背景や当時の人々達の心理的なものを徹底的に理解しようとする姿勢には影響を受ける。知的好奇心が旺盛で本当の教養の楽しさを知っている。 ブックリストについては、立花氏より佐藤氏の方が丁寧な紹介をされている印象がある。 ここに紹介されている400冊(両氏200冊ずつを紹介)の中で、読んだことがある、手元にあるものはわずか7冊しかない。 過去に小林秀雄氏と岡潔氏の「人間の建設」という対談本を読んだが、それの現代版という感じもする。 決してまねは出来ないが、たまには、このような高尚な対談を読むことで自らに刺激を与え続け、教養を身につける原動力とする努力は必要だと思った。
0投稿日: 2013.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ人に言われた本を読んで賢くなるならしめたものであるが、そうは問屋が卸さないのである。 2009年10月の本なので、文庫&新書ガイドが少し古くなっている可能性がある。古本屋で本を探すタイプなら気にならないかもしれない。私は、この本をそもそも古本屋で買った。 印象に残ったことは、昔『僕はこんな本を読んできた』読んだ時と同じで、「立花隆による「実践」に役立つ14ヵ条」に尽きる。 紹介されている本については、作者名とタイトルにひととおり目を通しておけば、書店や何かで目についた時に、ふと思い出して本を手に取るきっかけになってくれるかもしれない程度の付き合い方で良いかと思う。本書を片手に、ネットで本を買って片端から読むという実践は、相当しんどいだろう。 手広く読書していると、ある程度評価されている本は自然と分かってくるものかと思う。「これ聞いたことあるぞ」という経験を増やすための伏線の一つとして、本書のような本を読むという方法も無いではないが、趣味の読書の範囲であれば、その時間は好きな本を読むことに使った方がよいだろう。 ブックガイドを利用すると自分では読まない本を読むきっかけになる。一方で、人が良いと言うからという理由で、安易に本を受けいれてしまう可能性もある。 結局、どのように頭脳を鍛えていくのが良いのか、人によって答えが異なるであろうことは、うすうす誰でも分かっているわけであるが、本書のような本は、イチローがどうやって野球がうまくなったかということを知るのに近い楽しみがあろう。お二方のファンなら読んでみても良いかも知れない。
0投稿日: 2013.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ何故この本のレビューを書いたかというと、この本を批判したくてしょうがないからだ。先日『読書の技法』のレビューでも書いた(この『ぼくらの頭脳の鍛え方』を先に読了していた)が、著者の一人である佐藤という男は、とにかく「自分はこんなに物知ってるんだよ」「こんなことも知らないの」「こんなに本読んでるからね」っていうことを自慢したくてしょうがない男なのである。好きな人は好きなんだろうけど、こういう「物知り自慢」の人の本は、肌が合わないのである。 この人たちは「すごいよな、こんなに本読んで」とは思うけど、「だから何?」って思っちゃう。 (フランスの)ポスト・モダン以降の哲学、デリダとかバタイユとかフーコーとかは、この佐藤と立花の対談同様、読書自慢しかしていない。特に哲学はその学問上含有している問題があって、Aという人が100の本を読んで主張する思想・言説に対抗するために、Bという人間はAが読んだ100の本プラスアルファが必要となる。このBに対抗するCはBが読んだ100プラスアルファプラスベータを読む必要がある。そしてDは・・・、このイタチごっこが永遠に続くのが、現代哲学の孕む問題点だと思っている。これでは読書競争に他ならない。 僕はハイデガー・サルトルを好む実存主義者だが、彼らは確かに先人達の著作をたくさん読んでいたに違いないが、しかし、それ以上に思索においてオリジナリティ(ハイデガーの「死の現存在分析」はその白眉であろう)があったし、読書で得た知識を発展させようという意図がある。 でもメルロ・ポンティ以降のポストモダンや、この佐藤・立花みたいに 「Aという本ではこうこう書いてありますよね」 「いやいやでもBと言う本ではああも言ってますよ」 「Bと言う本に関連して言えば、Cという本では・・・」 という読書感想会であって、何の主張もない。 「Aという本では・・・書いてある。でも私は・・・であると考える」という思考をするべきではないか。知識人と言われる人は、もしこういう主張をすると「Bという本では・・・と書いてあったけど」と反論されるのが怖いから、何かを主張をするために何百冊も本を読む。僕に言わせれば本末転倒だと思う。 こういう人達って、思想・思索の中だけで満足してしまうんだろうなって思っちゃう。僕がサルトルを好きなのは、彼は思索に留まらず、(デモ)行動をして時には逮捕された事もあるくらいだ。「文学は飢えた子供の前で何ができのか?」は有名だが、サルトルが生きていたフランスは、何かあるとサルトルがどういう行動をとるか注目していた。愚直にもフランス共産党を支援したその行動の政治的是非は分かれるかもしれないが、それでも彼は行動した「最後の知識人」だし、そういう所に僕は惹かれる(ノーベル文学賞を拒否するなんて!)。知識人であるならば、蓄えた知識を現実にフィードバックする必要があるのではと、僕は思う。 また佐藤の『読書の技法』では「メモをとって本を読め」と主張するが、この本のもう一人の著者立花は「メモなんかとる時間があったら、その時間で別の本を読め」という。読書に対するスタンスも正反対だ。対談が噛み合うはずもない。 対談形式でこの本は書かれているが、概ね立花の発言に対し、佐藤が「AやBやCの本を僕は読んだけど、その中では・・・と書いてありましたよ」なんて、サラッと読書量自慢をする形式の対談で、噛み合っていないこと著しいです。そういう佐藤の嫌味な会話を僕は楽しみました。 この本は ①まず佐藤の嫌味を楽しむ ②佐藤と立花が読んだ本のリスト及びその感想があるので、これから読む本のガイドブックとして使用する と言う点で有用だと思いますので★一つにしました。
0投稿日: 2012.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に本マニアなんだなあと、対談を読んでいて思う。対談は途中でギブ。でもブックリストは参考になる。何冊か、速攻で図書館に予約入れたった。
0投稿日: 2012.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書量が多いことで自他共に認める二人の著者が、大学生からビジネスマンを対象に、教養として読んでおくべき本を紹介し語り合ったという内容である。したがって、古典、哲学、歴史、などがほとんどで、最近の小説は出てこない。二人の得意な分野はけっこうオーバーラップしているためか、お互いが読んでいる本も多く、それらを語り合う場面でのやりとりもおもしろい。多くの本が紹介されているので、今後読んでみようと思わせる本もいくつか出てくる。特に佐藤優氏は、すべての紹介本を数行で紹介しており、それがとても参考になる。この本は、著者や彼らの考えに対する好悪は横に置いておいても、教養のためのガイドブックとしてそのリストだけでも役に立つと思う。
0投稿日: 2012.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ二人の知識の量に脱帽。勝間氏を尊敬されていたのは、驚愕。 読みたいと思える本は少ないけど、それを読んでみて、視野を広げていきたい。
0投稿日: 2012.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆と佐藤優によるブックガイド。紹介されている本は400冊に上る。哲学、経済学、戦争論、科学、仕事術など様々なジャンルの本が掲載されている。確かにここに掲載されている本を全て読破出来れば、かなり教養が深まると思われる。
0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自称読書家なので、勇んで挑戦! しかし、ながら自分の読んできた分野の狭さに落胆し、 更に自身の読解力の低さを思い知らされた。 ここに載っている400冊ぐらい、軽く内容の把握はしたいし、 自分自身がこうして選出できるレベルに到達したい↑ 今後の本を読む指針、また動機付けとして、 読書家のあなたに贈りたい一冊。
0投稿日: 2012.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
知の巨人と、知の怪物による「学び方」を学ぶブックガイド。 哲学・化学・思想・歴史…まだまだ学びたい事は山ほど在ることに気付かせてくれた一冊。 入手しやすい新書が多く抽出されている事で実用も高い。 実用的ではない、『教養』を蓄積し、総合知を高める。 読んだ内容について熟慮すること。 読書による疑似体験でイマジネーションを高める。 読書人階級 ゲオポリティクス 権力党員
0投稿日: 2012.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆、佐藤優の圧倒的な読書量とその記憶力に感動。難解な内容が多く流し読み。読書ガイドブックとなる。
0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
蔵書数、7万冊と1万5千冊の両氏がセレクトした400冊を対談形式で紹介している本です。 読んでいるだけでなく、内容を専門用語を含めてしっかり覚えているというのがすごいなぁと圧倒されながら読みました。 気になった本は、柴山 全慶の『無門関講話』ですが、ちょっと難しそうなので無門関の入門書を読んでみようかなと思いました。 ★★★ 公理が必要とする佐藤と、そう考えてしまうと公理が存在することが前提とされて思考が閉じ込められてしまうことを危惧し「確実と思われる体験事実を積み上げていくことで世界認識を深めるべき」とする立花とのディスカッション(224~227ページ)が面白かったです。 上記に関して、ヴィーコの『新しい学』を読まなきゃなと、、、こんな感じに読まなきゃリストが増えてしまった本なのでしたー。
0投稿日: 2012.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段から本代に月に10万円以上使うという、立花隆・佐藤優の本の紹介の対談集。佐藤氏は給料もそれほど高くなかったサラリーマン時代からそれぐらい使っていたというし、立花氏の書庫は約8万冊もあるというから驚きだ。私を本好きにさせてくれた、とてもオススメの一冊。
0投稿日: 2012.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的な知識と教養を兼ねそなえた二人の会話に知的好奇心が刺激されること間違いなし。難しい話も多いので、興味ある箇所だけ拾い読みでもいいかな。読書好きなら、二人が薦める書籍リストだけでも価値ありだ。
2投稿日: 2012.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆先生と元外交官で作家の佐藤優さんが選ぶ400冊です。まともにここに上げられている本を読破するのはおそらく普通の人だったら一生かかってもできるかどうかわからないラインナップだと思います。 「知の巨人」立花隆と「知の怪物」佐藤優が贈る「濃ゆい」ブックリストと本にまつわる対談です。ここにあがっているリストをもしすべてつぶそうと思うのならば、文字通り「すべてをなげうって」読み込んでいくか、もしくは、彼らのように「職業」としてやっていくしかないんじゃないか?と思えるような、内容と量です。 文芸評論もやっている立花隆先生はともかくとして、モスクワ大学や東京大学で教鞭をとっていたにせよ、外務官僚としてあれだけ忙しく国事に奔走していた佐藤優さんが仕事の合間を縫ってよくもこれだけの本たとえば日本の古典『御伽草子』や『雨月物語』も入っているのは本当に驚きました。佐藤優さんは確か、同志社大学の神学部の大学院出身で組織神学という本人の著書いわく、ほかの宗教とキリスト教とを比較して、キリスト教がいかに優れているかということを相手に納得させるかということをやってきた方なのでやはり、ロシアの一筋縄ではいかない連中とやり合っていくには日本の古典も必要だったのではないか、と個人的には思っています。 一方の立花隆先生は膨大な読書遍歴の中から選んだものは古典はもちろんのこと、宇宙に関するものや、中には漫画版の『風の谷のナウシカ』が選ばれていたことには『あぁ、なるほどなぁ』と何か感慨深い気持ちにさせられました。そして、最後のほうに立花隆先生が選んだ『セックスの神秘を探る十冊』という箇所には正直言ってここで触れることをはばかられるような内容の本が挙げられていて、立花先生の別な部分が垣間見えるとともに、僕もここを最優先にして、どれだけかかるかはわかりませんが、できたら死ぬまでにここに挙げられている本を制覇できればと思っています。
5投稿日: 2012.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆と佐藤優が対談形式でお勧めの本を紹介していくという形の書評。佐藤優との対談だけあって、宗教色の強いものも多い。ビジネス系は極端に紹介が少ないのは、両者ともあまり得意でないからか。立花隆は理系的要素が強いものも多く紹介している気がする。 第二次世界大戦当時のことについて書かれた本が比較的多かった気がする。 文庫、新書のみで各100冊紹介しているのは買いやすいという点で親切。
0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時代の先端を行く作家で論客の二人、立花隆さんと佐藤優さんが、必読の教養書400冊について語り、紹介した新書にしてはぶ厚い一冊。 因みに立花さんで蔵書が3万5千冊を越してるそうです。 400冊を紹介してるので説明が薄くなるのは仕方ないですね。ただ、ジャンルごとに紹介してくれたり、本屋で現在売ってるものからチョイスしたりと、分かり易くはなっています。 挙げられたら本を片っ端から読破なんて到底無理なので(それぞれがヘビー)二人の語る教養を少しでも理解し、今後の読書参考にしたいと思いました。 教養を育てたい人にはお勧めの一冊!
0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「必読の教養書400冊」と副題がついていますが、 いわゆる初心者をていねいに導くガイドブックの類ではありません。 二人の「知の巨人」がいかに思想を形成してきたか、おびただしい書物を列挙しつつ、対談形式で語っています。 二人の膨大な読書量にも圧倒されますが、 むしろ独特な読み解き方にハッとさせられることが多かったです。 立花隆さんは「結局は、人生の残り時間を確認しながら、最大の成果を得られるように計画を作るしかない」と本書を締めくくっています。 残り時間といえば、私もボケッとしてはいられません。 今、この時代に自分には何が必要なのか、これを契機に頭を冷やしてよく考えてみよう。 そして本当に読みたい本、読むべき本を厳選しよう。
0投稿日: 2012.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログすごかった。とにかく二人の知識量と読書量に圧倒される。 政治、戦争、経済、宗教、哲学、思想、科学、歴史… ありとあらゆるジャンルをテーマに対談を進めながら、書籍の紹介をしていく。 この2人がいかに知識・教養を重要視しているかを見ると、自分も読書欲を刺激される。 「読者にお勧めなのは、巨大書店の書棚をすべて隅から隅まで見て回ることです。現代社会の知の全体像か大ざっぱでもつかめると思います。」 ----- p24 国體の本義 p39 マルクス p42 キリスト教 p113 戦争 p120 アメリカ p138 ロシア p141 ゲオポリティクス(地政学) p150 自民党戦国時代(三角大福中) p167 社会のダークサイドを知る p175 血液型占い=ナチズム p197 新左翼、ロスジェネ、東大紛争 p211 教養とは p219 古典を読む必要性について
0投稿日: 2012.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ所謂『知の巨人』こと立花隆氏と『知の怪物』こと佐藤優氏が各自200冊お勧め本リストを作り、互いのリストを見ながら対談するという趣向。リストにざっと目を通すと既読が30冊、読みたいのも30冊。打率1割5分だから書評として役に立ったかと言われると微妙なところ。お二人とも当代きっての読み手なので一介の活字中毒者が手を出しても消化不良を起こしそうな本も多い。従って書評ではなく知的対談として読んだ。意外だったのは佐藤氏が理科本には弱く立花氏と噛み合わなかったこと。巨人はど真ん中直球、怪物は変化球という感じか。^^;
0投稿日: 2012.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
紹介されてる本が難しそうな古典ばっかり。教養のために昔こんな事があったことは知るべきとしての古典も多い。けど、読む気にならねぇ(笑)体の仕組みを知るのも教養、手元に置いておこう聖書、英語も必要上達本、もちろん哲学も資本論、戦争も知ろう軍事本と言った感じ。リストの中のナウシカと100万回生きた猫は読んだことがある。20代30代に読んでもらう為のリストらしいが、固そうなものばかり。
0投稿日: 2012.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2人で400冊もおすすめ書籍が挙げられてる。 書斎の本棚から100冊、文庫&新書から100冊、それを2人分で200冊。 で、そこに対談で彩りがつけられてる。 佐藤さんは紹介文がほぼ均等の量。立花さんは歴史書の本文を長く引用したり、反対に解説はないけどサイエンスの本を何冊もバンバンあげたり、それだけ見ても個性があっておもしろい。 生き字引みたいな2人のお話を見て、自分なんて少しも教養がないから「すごくレベルの高そうな会話が繰り広げられてるように見える」ぐらいにしか思えないけど、でももっと読書したいと思わせてくれる本でした。 個人的には新書と文庫の紹介の方が好きです。 お金とスペースがない僕みたいな人のために作ってくれたコーナーですよね。ありがとうございます。 数学、論理学、交渉学の新書は早速買ったので読む。 ちなみに最後はまさかのネタで締められててびっくりしました。食いついたのは言うまでもないw
0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤氏はいらなかったんじゃないだろうか。 せっかく面白い話になりそうなのに変な方向に逸らされてイライラする所がいくつか。 拘置所の隣人とか興味深い話もあったけど。
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆と佐藤優がそれぞれ書斎から100冊・新書から100冊ずつ系400冊のブックリストを作りそれをもとに知識・教養・歴史・政治・科学・文学と語る本。 それらの話はとても面白いのだが、一番面白かったのは佐藤優の大学時代の話。 神学教授に可愛がられて、同志社大1年生のときからマンツーマンで指導を受け、2年生のときに大学院までの課程を全部終わらせて3年生のときには時々大学で教えていたという・・・ 言語も英語ドイツ語に加えて、「ちょっと余力があるようだから、ギリシア語とヘブライ語とラテン語をやれ。ギリシア語は二つやれ。あとチェコについて勉強したいんならロシア語もやってこい」とまで。 立花隆もそうだが、ここまで必死でやらないと彼らくらいの力は身に付かないのだろう。 様々な分野で一流の人は、若いうちに並々ならぬ努力や打ち込みをした結果であることが多い。 同じ努力の量でも、後で頑張るよりも初めに一気に頑張った方がいいのは確か。 人生も後半で本気を出しても、それによって人生が劇的に変わる可能性は低いし、力がついてもデキる人モードで過ごす時間ももうたいして残っていない。 早くに必死で頑張ると、それによって上のステージに行け、そこで貴重な体験をすることによってさらにどんどんレベルアップしていく。 出世街道とかもそんな感じかな? ということを思いました。 でも遊びも、若いうちにしか経験できないことがいっぱいある。 そっちもやっておかなきゃ! と思ったらどうすればいいのでしょう。 両立はできるのか、どっちか犠牲にするしかないのか・・・ とりあえずエネルギッシュな人を目指せばいいのか!?
0投稿日: 2012.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人たちの脳みそはどうなっているのだろう… 読書量もさることながら、一冊一冊の内容をしっかりと把握し、意見を述べている。脳みそのつくりが違うんじゃなかろうかと思ってしまいます。 理解できる内容もあれば、終始首をかしげてしまう内容も。 もっと成長して100%理解、自分の意見を述べれるようになりたいです
0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆と佐藤優が対談形式で、本を紹介。 自分の教養のなさを思い知った。二人の話の内容がさっぱり分からない。 どういった視点で本を読めばいいか、著者がそう書いた背景など、ただ本を読むだけでなく、そこから自分なりに考える事が重要であることを改めて考えさせられた。 佐藤氏の本の紹介文が4~5行にも関わらず、すごくわかりやすく、読んでみたいと思わせる。 趣味の読書だけではなく、教養を身につける読書を増やしたい。 本を読む視点が変わります。おすすめ。
0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代を代表する2人の知識人による読書ガイド。 読みたくなる本、読むべき本がいっぱい紹介されていますが、サラリーマン生活の中ではなかなか手がでないなあ・・・。
0投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮大な知的好奇心の熱さに打たれる本。 政治・経済・哲学・科学とその話題の矛先はとどまることをしらない。 本書で語られる読書術は、完全に実学よりの読書術。 膨大な情報を収集、蓄積、解釈、出力するためとんでもない量の読書(人間技じゃない)するお二方の真似は到底できないが、その技術、情熱の一端を授かることができる。 真の教養人へGO!
2投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 難しいかと思ったが、難しい本についてもなぜそれが大切なのか、なぜ必要なのかを、二人掛かりで教えてくれる感じ。 両人ともあまり良い印象はなかったが(失礼)、これを読んで特に佐藤優氏の印象は変わりました。 興味のあるものから読んで行きたいと思います。
0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ全ての思考や行動のベースになる教養を鍛えるためのブックガイド。 これを全部読んだらすごいだろうなぁ。
0投稿日: 2011.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ知の巨人と知の怪物と呼ばれる知識人2名による推薦書が紹介されてます。さすがに学生中に全部読むことはできないだろうな。
0投稿日: 2011.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかくたくさんの本を読む人たちだ。そして、よく理解できていると思う。 予測できる人になりたければ、基礎数学論を学べ。特にゲーデルの不完全性定理。隈部正博氏の著作がよい。 迷ったら捨てよ。 上昇志向に気をつけよ。小さな人間になることも大切。 いやな相手にも挨拶など、最低限の大人の対応をせよ。 不の感情で連帯するのは偽りの連帯。皆、自分のことしか考えていない。 人々への報復制裁は考えないこと。 人間は無意識に物語を作る。 五味川純平の本読め。人間の条件など。 宮台真司・日本の難点、野間宏・真空地帯よめ 大正・昭和期の小説を読め。
1投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ対談本ですが、お二人の知識につけていけず 何を話しているのかちんぷんかんぷん。 自分の知識のなさを痛感した一冊。 400冊のお二人のオススメ本が紹介されており 参考にして、気に入ったのがあったら購入して 少し教養をつけたいと思う。
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読めるというのは、賢いということを意味するのだと思わされた本。 対談形式なので、気軽に読んでも面白い。
1投稿日: 2011.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書初心者向けガイドとして読む動機付けを用意してくれたあたりが素敵。私の頭はどうしたら働いてくれるの?に答えてくれる可能性のある一冊。
0投稿日: 2011.11.09
