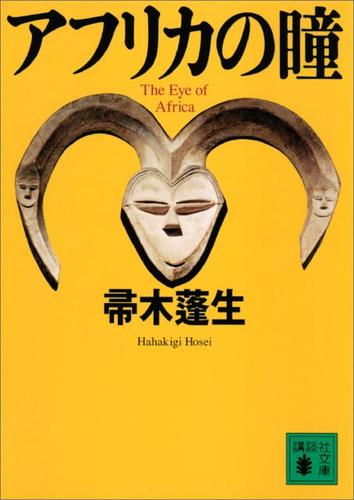
総合評価
(34件)| 12 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカの貧困、はびこるエイズ、利権を守りたい政府、製薬会社の非合法な治験。と考えさせられるテーマ。ある新薬Xを従来の薬よりも良く見せる宣伝の仕方について何通りも示してくれたので、「あ、物事の本質ってこんなにも簡単に隠せてしまえるんだなぁ」と思った。
0投稿日: 2021.02.06私の人生を変えた本
私が高校の図書館で借りて、それ以来何十回も読み込んだ本です。アフリカの蹄の続編にあたります。 私自身、抗生物質に重度のアレルギーがあり、諦めざるを得ませんでしたが、発展途上国の支援に携わりたい、と強く思わされた作品です。 外国への興味、支援、医療に携わる人なら是非読むべき1冊だと思います。
1投稿日: 2017.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ十人に一人がHIVに感染している国南アフリカ。かつて白人極右組織による黒人抹殺の陰謀を打ち砕いた日本人医師・作田信はいま、新たな敵エイズと戦っていた。民主化後も貧しい人々は満足な治療も受けられず、欧米の製薬会社による新薬開発の人体実験場と化していたのだ。命の重さを問う感動の長編小説。
0投稿日: 2017.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ『アフリカの蹄』の姉妹編。 白人極右組織による黒人抹殺の陰謀を書いている『アフリカの蹄』の後、南アフリカは黒人政権の国となったのだが、貧困は変わらず、そのうえエイズが国中に蔓延して、希望を失った人々はアルコールに依存したりするのだった。 出口の見えない南アフリカの現実。 白人は高価なエイズの治療薬を使うことができるが、黒人は病院にかかるお金も病院へ行く交通費もないのに、エイズの治療薬なんて買えるわけがない。 経済的に豊かな国が、企業が、個人が、ほんの少しのお金をエイズ撲滅のために使ってくれたら。 “要するに、アフリカの貧困とエイズから日本が学ぶことは多々あるのに、日本の眼はアフリカには向けられていない。日本がいつも視野からはずさないでいるのは合衆国であり、時々横目で見ているのが欧州、そして終始見下しているのがアジアなのだ。” アフリカの女性は、人種差別の他に性差別も受けながら、それでも生きるために身を粉にして働く。 畑をつくったり、水を運んだりするのはいつも女性だ。 “負け続ける戦だと分かっていながら倒れるまで闘うしか、道は残されていない。広大な砂漠に井戸がひとつあるのとないのとでは大違いだ。砂漠全体の緑化は及びもつかないが、井戸さえあれば周辺の住民に水を与えられる。その井戸は枯らしてはならない。” 主人公の作田は外科医なのであるが、市立病院での勤務が終わった後、民間の診療所でボランティア医師として働いている。 ある日運び込まれた患者は、別の診療所でエイズの薬をもらっているという。 エイズの治療薬はとても高価なはずなのに、その診療所ではただで薬をくれるばかりか日当までくれるという。 しかしその薬の副作用ではないかと思われる症状で死んでいく人も多発している。 この薬は一体なんなのか。 また、特別よく効くわけではないが、それなりの効果があると言われるエイズ治療薬ヴィロディン。 安いので、外国産の薬を買うことができない国民は、この薬を使うしかない。 そして、出産時に母から子どもへの感染が多くを占めるこの国のエイズ患者のために、妊婦と新生児には無料で与えられている。 ところが、この薬を服用しているのにもかかわらず、新生児がエイズで死んでいく。 この薬は本当に効き目があるのか。 これらのことを作田を中心として、医師や患者たちが、また作田の妻のパメラから公衆衛生や女性問題などを教わっている人々が、患者に聞き取り調査などして問題を解明していく。 命を狙われたり誘拐されたりと、その調査が妨害される中、どうやって彼らは問題を公にしていくのか。 ミステリとして読んでもとてもスリリングで面白いのだが、南アフリカの現状が、虐げられている人からとことん搾取していくそのシステムが、システムの底辺にいる女性や子どもたちの苦しい息遣いが、ものすごく胸に迫ってきた。 作田の仲間たちが、この国の未来となるべき姿を芝居にして上演する。 その芝居のタイトルが「アフリカの瞳」 “この国はアフリカの中でも特殊です。いろんな問題がこの国に集約されています。この国にいるとアフリカがよく見える。いやアフリカだけでなく、世界がよく見える。その意味で、この国は世界の瞳です。人間がどう動いているか、見据えている瞳がこの国にあるんです”
2投稿日: 2015.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログとても賢くなったような気分になる作品でした。 南アフリカでHIV感染治療に取り組む日本人医師作田信さんのお話です。 貧困社会の医療、政治、援助など色々な事が詰まっています フィクションなのかノンフィクションなのか分からなくなります ラストは感動します!
0投稿日: 2015.01.07アフリカ、HIV、日本人医師
ある意味ショックだった。 HIVについてあまりにも無関心というか、本の中にもあったように対岸の火事のような認識しかなかった。 読み終えた今でもそうかも知れないが、読んでよかった。
0投稿日: 2014.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ蹄の方が面白かったけど、こちらもやっぱり終盤は感動。 ただ金銭や物資、人間を送って援助するだけでは問題解決にはならず、場合によってはかえってその国の力を弱めてしまうということは、正直あまり考えたことがなかった。
0投稿日: 2014.04.26アフリカの未来に光明を灯す日本人医師に脱帽
HIV感染・教育インフラの不備・貧困の悪循環と10年前に書かれたこの本の内容は、今でもアフリカの現状と変わらないと思う。無能な政治、巨大製薬会社の闇など外部に原因を求めるのは簡単だが(これはこれで痛切なしっぺ返しがあるが)、まず身近でできることから始めようという作田医師夫妻に頭が下がる。併せて、女性の地位向上と教育、これがいかに重要かが切実に理解できる。帚木文学の中でも一二位に挙げられる一冊だと思う。是非とも皆さんに読んでほしい。
0投稿日: 2014.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログHIV感染者とエイズ患者の違いを知らずにいました。援助することは大事だけれど、その結果に思いを寄せることも大事なんですね。さらに 国の施策を盲信しないことも必要だと思いました。疑問に思ったら追求するエネルギーを持っていたいものです。
0投稿日: 2014.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでが真実でどこまでがフィクションなのかわからないが、医者としての叫びのような作品。 インフラや食糧や衣料のやみくもの援助すらも生活を破壊していく。10人に1人がHIVに感染している国。民主化後も貧しい人々は正しい知識も知らされず、満足な治療は受けられず、欧米の製薬会社による新薬開発の人体実験場と化していた。エイズを通してアフリカのかかえる様々な問題が書かれている。 「アフリカの蹄」という作品が前篇として対になっているらしいが、これだけでも十分な完結したメッセージ小説となっている。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ南アフリカを舞台にした医療小説です。アパルトヘイト崩壊後の南アにてエイズが非常に流行っており、政府が私利私欲のために効果のない抗HIV薬を無料配布したり、アフリカが製薬会社の人体実験場と化している現状が描かれている。南アフリカは世界情勢を見つめるアフリカの瞳だという一説はささりました。
0投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカにある某国でエイズ勢力が跋扈している。アパルトヘイトから解放された矢先のエイズ禍。低所得者層では、効果的な抗エイズ薬は買えない。彼らは製薬会社から人体実験のモルモットにされ、黒人政府には踏み台にされていた。そんな所に日本人医師・作田が多くの人達と共にエイズと戦う。 興味深く読むことができた。すんごい感動した。難しい本読むよりこういう小説絡みで読んで勉強できるんだから、もっと本を読もうと、読まないといけないと思った。力を合わせるって素敵な事、作田も皆もすっごい良い人。これは泣けるぞ。 さて、これは差別・エイズを問題にしたものだ。日本に住んでてエイズを心配したことがあったろうか。小中高と性教育が設けられているが、どこかよそよそしい。エイズのことだって、これ読んでちゃんと危険な病気なんだと分かった。軽視してた。 どっかの発展途上国に蔓延してる病気でしょ?薬あるんでしょ? いや、他人事で片付けてはいけない。今アフリカでのエイズ感染者は減少を見せているが、反対に中央アジアなどで増加しているのが現状だ。楽観視は禁物。 援助の話も出たが、これも印象的だった。医師を派遣して病人の治療、食糧難なら食糧をあげればいいと単純に思ってた。大間違い‼自分も政府となんら変わらんじゃないかと落胆した。必要なのは育成。自分たちで生きていける力。現地の医師を育て、農業のやり方を指導する。自分の足で立てるようにすることこそが正しい。 今こんなことに気づくとは…情けない。色々勉強になる。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカの蹄に続く姉妹作。 前作未読だがとても引き込まれた。 重いテーマだが、読後感は爽やかで、アフリカのみならず、人間の未来を感じさせる終わりだった。
0投稿日: 2012.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログノンフィクションなのではないか? と思わせるほどの小説でした。 アフリカに蔓延るエイズ、そのエイズと政府に立ち向かっていく日本人医師と彼の仲間たちの様子を描いた物です。 世界各国でエイズは今も蔓延しています。圧倒的に多いのはアフリカですが、日本でもエイズ患者は多くいます。決して他人事ではないのだと、この本を読んで思いました。
0投稿日: 2011.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ十人に一人がHIVに感染している国南アフリカ。かつて白人極右組織による黒人抹殺の陰謀を打ち砕いた日本人医師・作田信はいま、新たな敵エイズと戦っていた。民主化後も貧しい人々は満足な治療も受けられず、欧米の製薬会社による新薬開発の人体実験場と化していたのだ。命の重さを問う感動の長編小説(amazonより抜粋)
0投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカの蹄を読んでいないのですが読みました。南アフリカ、そしてはびこるエイズの現実。。何も分からずに死にいく人々。何もならないけど、それでも村の診療所で孤軍奮闘する医師。大国のエゴ。当事者の意識の欠落。どこかで起きている現実に、目の前のことから一歩ずつと思います。生きるということは力強くあること。
0投稿日: 2011.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠いアフリカで何が行われているかを知ることができる本。日本人が無関心な大陸で、日本はじめ先進国の施しが国の自立を妨げている現実を著者は厳しく指摘している。
1投稿日: 2010.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から読みたいと思っていて、ラオスで出会ったJICA職員の方から頂いた(奪った?笑)一冊。 アフリカの現状についてとてもよく調べられているというのが、節々で感じられた。所々に織り交ぜてあるたとえ話(たばこ一箱で子どもの一日分の蛋白質が奪われるとか、高速道路5kmの費用=アフリカ人100人の1年の食費とか)が、自分の中でイメージを想起しやすくてよかった。 誘拐事件のくだりからスピード感は出てきたけど、現実感ないし、何事もうまいこといきすぎやし、ちょっとだれてきたのは否めないな。 ただ、ラストは感動的やし、締めとしてふさわしいラストやし、自分の好きな一冊。 HIV感染の問題について、何も知識がない状態だったので、ここまで大きな問題だと知って、衝撃やった。 また勉強せなあかんことが増えたなー。。。。
0投稿日: 2010.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログHIVをめぐるアフリカの問題・・・全然知らなかったなぁ。薬のことが1番びっくりしました。。後半になって、一気に話が進んであっという間にラスト。ラストの劇の場面が好きでした。
0投稿日: 2010.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ心臓移植の知識を得るために留学先のアフリカへ渡った医師作田。アパルトヘイト政策のために黒人は虐げられている現実があった。そこに黒人の子供を中心として、絶滅したはずの天然痘が発生し続々と死んでいく。白人優位主義の極右組織の影が見えていた。 天然痘の発生が極右組織の仕業とわかったり、話がスムーズにしすぎているきらいはあった。でも少しずつでも地位向上を目指そうとする黒人の団結心は現実のままだと思った。
0投稿日: 2010.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログある意味ショックだった。HIVについてあまりにも無関心というか、本の中にもあったように対岸の火事のような認識しかなかった。読み終えた今でもそうかも知れないが、読んでよかった。
0投稿日: 2010.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログいや、おもしろかった。HIV薬害(と呼んでいいと思う)について内面から真っ向固く書き連ねているにもかかわらず、ストーリー展開もキャラ立ちも極上の筆力でああっという間に読める。私はまだ前作「アフリカの蹄」を読んでいないのだが、ぜひとも読まなければ、という気にさせられた。 それにしてもキャラたちのすべて魅力的なことよ! 悪者がまったく出てこない(出てきてもそれは深く書かれない)のは物足りない気もするが、テーマがはっきり浮かび上がって、むしろマンガ的にはしない、読者に「こう感じて欲しい」という作者の狙いが前面に出ていて、ドキドキはするが、エンタティンメントというよりは実録ものをどう面白く読んでもらえるか、作戦勝ちなのだろう。 前半もおもしろく読めたが、後半のスピード感はまさに圧巻。展開としては特にひねったところはないだけに、本当に筆力の強大さなのだろう。
0投稿日: 2010.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ南アフリカ共和国らしき国のエイズ感染者を救おうとする日本人医師のお話、不正をただし悪を許さない姿は現代のヒローなのか。家族を巻き込んでのエイズに絡む事件の告発は危険だった。結果は万々歳で世界を大きく動かすほどの展開になる。アフリカのエイズの現状を知る上では参考になる本だ。
0投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカの蹄の続編ともいえる。 アパルトヘイトに撤廃を成し遂げるが、貧富の差がなかなか埋まらない。貧しさに黒人たちがまだ喘いでいる。 やがてエイズ感染が広がる。 世界のエイズ感染者の60%の地域。 感染からどのように救い出すのか。 HIV感染者からエイズへ。 小説を読んで、日本ではどうなのだろうかと思ってしまう。 HIVとは、エイズとは、小説を通して正確な知識を持って欲しい。 著者の弱者に対する暖かな眼差しを感じる。 著者には一貫してこうした弱者に対する視線があり、ホッとする。
0投稿日: 2009.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれもウガンダで一気に読んだ一冊。 アフリカをディープに読みたいなら、これ!! クライマックスも感動しますよ!
0投稿日: 2009.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ『アフリカの蹄』から続けて読むと、ちょっと二番煎じ、パターン化といった感じが否めなかった。しかも金の亡者より、自分の信念をつらぬく者たち(それが間違った考え方だとしても)を描いた『アフリカの蹄』のほうが、腹立つのは同じでも理解できる部分があって面白みが深かった。・・・とはいえ、内容がつまらなかった訳ではない。
0投稿日: 2009.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ天然痘と闘った「アフリカの蹄」から、約12年。 作田先生が帰ってきました。 今度の敵はエイズ。 HIVウイルスに有効とされた薬を飲んで、副作用を起こして亡くなる者、薬を飲んでいたはずなのに、母子感染して、発症した我が子を見守るしかない母親。 本当にHIVウイルスに有効な薬を投与されているのか? 再び、作田が政府相手に立ち向かう。 作田の周りにいる黒人たちの力強い生き方に励まされる一作。
0投稿日: 2009.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカの人種差別がテーマの小説。 NHKでドラマ化されていたけれど、 あまり見ていなかったからそれなりに新鮮に読む。 面白いが、 主人公があまりに立派で現実とのギャップを感じ、 それと同時に人種差別をする側の思考も理解しがたく、 なんとなくずっと悶々としながら読み進める。
0投稿日: 2009.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の傲慢は、知らない内に黒く広がっていくものなんだと思います。 けど、それに立ち向かっている人もいる。 見習えるとは思わないけど、尊敬します。
0投稿日: 2009.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ知らなければいけない現実。 見ようとしなければ見えない現実。 それは、事実に裏付けられた物語だからこそ、力がある。 病気で苦しむのも人間であるし、状況をさらに過酷にするのも人間。 でも、希望を見いだすとすれば、それもまた人間の中にしかない。 ペシミストでないかぎり、人は生き続けようとすることにこそ希望を見いだす。 その希望から見放された人間、それがHIV感染ということなのだろうか。 スケールが大きく、しっかりと練られた物語。 山崎豊子を受け継ぐのは、この方なのだと思う。
0投稿日: 2008.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人のストーリー構成って一種独特のものがある。映画化されると面白いような構成と言えばいいのか・・。
0投稿日: 2008.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「アフリカの蹄」続編。天然痘、アパルトヘイトからHIV、民族の自立へとテーマが以降。ラストがなんか都合良すぎるのは物語だからいいのか。現実もっと救いがないですし。国際援助とかエイズ問題とか、どう向き合って行くべきかをちゃんと語ってくれます。
0投稿日: 2007.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「アフリカの蹄」の続編。 作者が本当の医師だけあって、医術に関連する表現が丁寧に書かれていることで、作品に重厚さを出している。 前作がNHKでドラマ化されたので、ぜひともこちらもドラマ化してもらいたい。 ラスト、バスの中で読んでいて号泣。
0投稿日: 2007.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリーはなかなか面白いのですが、冗長すぎます。1/3くらいは削りたいかな。あるいは、その代わりに農村再生の動きをもっと書き込むか。そうすれば、全体に締まった感じになったろうと残念です。 しかし、エイズに実情、政府援助がもたらす問題、アフリカの貧困の実情などを描き、社会に対する警句としてはなかなか良く出来た作品と言えるかもしれません。 気になったのは、欧米の製薬会社はアフリカに無料でエイズ治療薬を配布すべきだという説が随所に出てくることです。会社勤めの人間としては、会社と言うのは営利団体であり、そこまで要求するのは酷な気がします。この薬で欧米では十分に利益を出しているのだからという根拠ですが、新薬開発は非常に多くの投資を必要とし、しかも全てが成功するわけではないのですから。むしろそうした要求は社会に対し行うべきでしょう。
0投稿日: 2007.07.24
