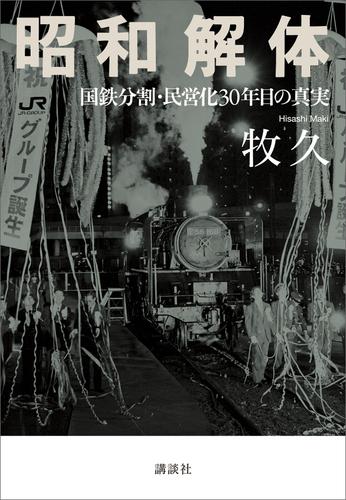
総合評価
(17件)| 11 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄は戦後も公共企業体として再出発しながらも政治との蜜月が続き、利権化されていた。さらには戦後の民主化政策で労働組合が力を増し、五十五年体制を作り上げる。国鉄はまさに昭和の腐敗した歴史の象徴であり、それが解体していく様は圧巻。 また、中曽根首相の先見の明、断固とした決意、圧倒的な政治感覚には目を見張るものがある。 以前読んだ国鉄改革の本は、葛西の視点によっており重視しているポイントも違うように感じたので、そちらも改めて読み直し比較してみたいと思った。
0投稿日: 2020.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄栄枯の歴史を国鉄内部の目線で描いたルポ。 鉄道ファン向けに描かれるような東海道新幹線開通や世間の様子ではなく、国鉄がJRへ解体されるまでの組織と政治の話に特化していて、その人間の織り成すドラマはあまりにも金と欲にまみれて重苦しい。 変わり続ける政治家、利権をむさぼる労働者、不明瞭な責任の中で愛されなかった国鉄という組織が、国鉄三羽ガラスと言われる井出、松田、葛西の三人の官僚を中心に終息を迎える。 筆者はベテランなだけあり、(ドラマ的な描き方をしている部分もあったが)可能な限り事実を書こうとしていたように思われる。 心底悔やまれるのが、福知山線事故の責任を感じた井出が国鉄改革回想録2000ページをお蔵入りさせたという話。 本書はこちらも参考にされているとのことから、他の国鉄関連書籍を読んだ上で再読したいと思った。
0投稿日: 2020.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄が労使対立と巨額の債務のなかで迷走を続け、分割民営化されるまでのドキュメント。親方日の丸で統制の取れない職場の実態が生々しい。
0投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本来は、国鉄の解体が昭和の解体であるということを、すぐに分からなければならないのでした。 いや、本当に勉強になりました。
0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日読んだ同著者の「暴君:新左翼・松崎明に支配されたJR秘史」が裏の歴史だとすると、先に書かれた本書は国鉄改革の表の歴史である。 国鉄分割最後まで分割・民営化に反対した国労の歴史は戦後まで遡る。 シベリア抑留から帰国した、田中角栄の戦友、細井宗一から国労の歴史が語られる。 機関助士廃止反対運動、マル生粉砕、スト権スト。 国鉄当局と国労との泥仕合の中で分離した動労など、労使関係は累積赤字とともに悪化の一途をたどる。 そして国鉄再建の道として示されたのが分割・民営化案だった。 しかし、審議される頃には国鉄総裁はレームダック、運輸省と国鉄上層部は分割・民営化案を潰しにかかる。 手を結んだのは、国鉄若手官僚と政府だった。 これは国鉄解体にとどまらない。 昭和62年4月1日にJRとして新しく発足したその日は、昭和の解体と言っていいほどの意味を持っていた。 これが国鉄解体、表の歴史である。
0投稿日: 2020.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和の一大事件である国鉄分割・民営化に関わったさまざまな人物の証言を元に再検証する500ページ超の大著。改革派・国体護持派それぞれの思惑が交錯する様はまさにスペクタクルで読み応え抜群!タイトルが「国鉄解体」ではないのも、読み終えればこれしかないと思えるのにも驚いた。
0投稿日: 2019.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ半強制的に組合に入らされている若手や中堅に、昔はこんなことがあったと知る意味でおすすめ。信じられないようなことがあったんだなと、驚くと思う。
0投稿日: 2019.05.19昔は良かったわけではない
国鉄は明治39年以来国家の事業として日本経済の基盤を支えてきた。しかし昭和39年の新幹線開業と同時に赤字となると最終的には鉄建公団や年金を含めると37兆円の累積赤字に至った。田中角栄は47年度末に8千億の累積赤字となった国鉄を日本列島改造論でこう書いている。赤字線の撤去によって地域の産業が衰え人口が年に流出すれば鉄道の赤字額を超える国家の損失を招く怖れがあると。 昭和42年国鉄の職員数は47万人、翌年のダイヤ改正では増発などで3万人が必要で、石炭時代の名残の機関助士を中心に5万人の合理化を計画していた。2014年の東洋経済の記事では世界最大のウォルマートが220万人、2位のマクドナルドが44万人だ。国鉄の巨大さがよくわかる。ちなみに現在では6社+貨物の本体で12万人ほどだ。国鉄の分割・民営化は巨大赤字企業の再建を図るとともに、国鉄労働組合(国労)ー総評ー社会党の解体を目的とした戦後最大の政治経済事件でもあった。労使共にいずれは国がなんとかしてくれると親方日の丸意識に安住し、労使の対立、派閥抗争、組合同士の争いに明け暮れ政治家に利用された。井手正敬、松田昌士、葛西敬之の「三人組」を中心とした若手キャリアの改革派が立ち上がり、中曽根内閣の土光臨調では行財政改革の目玉として国鉄解体と民営化による再建を手がけた。現在単体の営業利益は北海道と四国を除けば黒字化し合計では1兆円を超える。 国鉄迷走の原因となったのが昭和43年に国労、機関士・運転士が中心の動労が勝ち取った現場協議制度だった。石炭をくべるため2人乗車だったのを1人乗車にして合理化をはかる当局に対し、反対した組合が代償として現場での団交権を手に入れたのだ。裏で絵を描いたのは国労中央執行委員の細井宗一、スト権の無い国鉄では違法ストを実施すると処罰が待っている。そこで「定められた運行手順を、ゆっくりと時間をかけて完全に実施する」順法闘争というサボタージュ戦術を編み出した国労きっての理論家だ。細井は国鉄は多少の赤字がいい、10万人きっても年間4千億、1兆円の赤字の有効打にはならないと語っている。同じようなことを言った田中角栄は同郷で満州へ赴任した騎兵連隊では士官候補生の細井が新兵の田中をかわいがると言う関係だった。 国鉄は国家独占資本主義の機構で、労働者を搾取し国民から収奪している。その利益の源泉が現場だ。現場が止まるのが一番怖い当局に対し、現場が団結することで組合は力を持つ。この細井の理論は結果的には現場協議を駅長や助役を吊るし上げる場に変え、職場は荒廃した。例えば昭和57年に朝日がスクープしたブルートレインのカラ出張は組合員ののタレコミによるのだが、その内容は外から見れば非常識そのものだ。毎日故障は発生しないと合理化のため降ろされた設備要員に既得権として手当の継続があったが「手当を支給しておいて、さらに合理化を強行するというのはどういうことか」とタレ込んだのだ。 国鉄当局の方も問題が多い。職場の管理権を取り戻そうと始めた生産性向上運動、略してマル生は労使協調して成果は配分されると言うものだ。しかしこの本では生産性向上の具体的な中身はない。マル生運動の実態は当局に賛同する組合員を取り込み組合を弱体化させるのが目的だったからだ。実際に国労からは1年半で5万人の組合員が脱退している。マル生に対するマスコミの風当たりも強く、昭和46年10月に不当労働行為の証拠テープが流れた。「いま騒がれているのは組合切り崩しの不当労働行為だ。しかし、やむにやまれずこれはやらなきゃいかん。知恵を絞った不当労働行為をやっていくというのだということがあるわけです。」 昭和47年沖縄返還協定発効後に佐藤首相が6月に退陣を発表、その3日後に田中角栄の日本列島改造論が発刊された。目玉は全国新幹線網の整備であり国鉄の赤字は拡大する。マル生に勝利した組合は増長し、順法闘争がきっかけとなる乗客の暴動が同時多発的に発生した。昭和50年組合はスト権の奪回を目指しゼネストに突入するがトラック輸送が普及した結果国鉄離れが進んでいた。国鉄の運行はマヒしたが国民生活はマヒしなかった。そしてスト権問題を協議していた専門委員会はスト権を認めないのみならず国鉄分割・民営化にまで言及していた。 この後政府、政治家、労使ともに権力闘争と一体となった国鉄対策が続く。成果は出た、今や日本の新幹線といえば定時運行、事故の少なさともに世界最高水準だろう。そこに向けた努力の積み重ねは評価すべきだが、国鉄を含め解体された昭和の世の中が今より良かったとはとても思えない。
0投稿日: 2019.02.04正に昭和の歴史
ヤクザ映画紛いの組合対会社には驚かされる。 健忘術数を尽くした男たちの戦いは映画にもなりそう。 人事労政担当者必読書だ。
0投稿日: 2018.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄解体の正史 関わる人達の営みはドラマチック トップ中曽根総理の覚悟 それにしてもよくあれだけの改革が出来た あれがあったから日本航空 日本郵政はまだ容易だったのだろう 前例主義 現代は「社会保障」誰も手がつけられず、財政と国家の破綻を座して待つばかり 本当に安倍首相は時代認識も、歴史的使命観も持ち合わせていない 不思議 東條首相と似ているかもしれない 日本は時代の転換期に人を得ない国 国鉄解体は壮大なドラマであるが、歴史的には必然 それでも山あり谷あり、筋書きは読めない 3人組ほかブレナイ人々 「私」のない人
0投稿日: 2018.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄分割民営化に関して、出来事や関わった人の心中が詳細に記されています。 自分が生まれる前に日本で何が起こっていたのか、また、今のジェイアールの労使関係のルーツがよくわかりました。 非常に丁寧に取材、調査されており、かつ分かりやすく書かれた素晴らしい本だと思います。
0投稿日: 2018.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく詳しい。一度読み返さないと消化しきれない。組合幹部は何がしたかったのだろうか。いやはや。3人組のうち、東日本は動労に屈し、西日本は尼崎をやり、東海だけはまだ大きな失敗をしていないが、はたして葛西は無事一生を終えるのだろうか。あそこが1番危なそうなものだが… すごい時代だけど、そんなに昔のことでもなく、今でも過激にストが打たれたら、怒り狂った民衆が駅員に襲いかかることができるのだろうか。
1投稿日: 2018.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長かったけど面白かった。知らなかったことがたくさん。国労の人の意見も聞いてみたい。最高裁までの過程もきちんと読んでおきたいと思った。
0投稿日: 2017.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは本当にすごい本、というか凄すぎる内容の本だった。 明治国家の西洋化の象徴として新橋ー横浜間の鉄道が最初に通され、終戦直後には復員兵を数十万単位で引き受け、64年の東京五輪では新幹線を通したが為に赤字転落をした国鉄は最終的には、職員27万人、累積赤字37兆円(!)となり、複雑な労使関係、より複雑な労労関係、そして半国家組織であるが故の絶え間ない政治の介入により1980年代初頭には瀕死の重体となっていた。この国鉄を「分割民営化」して再生させるという1点に執念を燃やした国鉄キャリヤ組の井出、松田、葛西の"改革3人組"と脆弱な党内基盤ながらも抜群の政治センスを発揮して"戦後政治の総決算"を特に国鉄民営化において実現しようとする政治家、中曽根康弘らが主役のこの物語(まぎれもない実話だが)は、様々な困難で複雑な状況を乗り越えながら、最初の検討(第二臨調)から6年越しで分割民営化を成し遂げていく、それはすなわち国鉄の巨大な労働組合(国労、動労など)を分割することであり、それは全国的な労働組合連合である総評の中核を消滅させることにつながり、最終的には総評を基盤とした左派政党である日本社会党を減退、変容させることにつながった。つまり国鉄の分割民営化は昭和日本国家の解体へとつながった訳である。 内容の詳細は省略するが、読み終わって思うことは、"これこそが政治である"ということである。職員25万人、国民の足を担う巨大組織の大改革には策謀と裏切り、変節、保身、増悪、執念などの様々な情念が宿り、さらに利権や選挙、組織の存亡など具体的事象も絡まり最終的には労組同士の殺し合いにまで展開してく、まさに人間世界の悲劇、喜劇のすべてがそこに表出されているように思える。この組織の人間の情念をすべて賭けたすさまじい権力闘争に比べれば、いまの政治状況などはすべて児戯に等しく思えてしまうのである。 なお、「凄すぎる内容の本である」と評したが、このものすごく複雑で経過年数も長大な大河ドラマの詳細を調べつくし、かつ読者を迷わせることなく理解させる筆者の構成力、筆力も驚かざるを得ない本であった。とても分かりやすく淡々と事実を構成して語ってくれているのだが、これほど凄みのを感じる本も本当に珍しいと思う。 前回読んだ「愛国とノーサイド」に続き、私が生まれる少し前、私が全然知らない日本がそこにあったことだけは間違いない。うーん凄すぎる。
3投稿日: 2017.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄がいかに腐敗していたか、そしてJRに転換することが必然だったかよくわかる一冊。 今のビジネスマインドでは通用しない事がまかり通る時代だったんだと。
1投稿日: 2017.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ1987年4月1日は国鉄が民営化され、JR各社が発足した日にあたり、今年は民営化から30年という節目となる。30年が経過したものの、民営化の際に議論された問題は全てが解決したわけではなく、むしろJR北海道の経営問題のように、深刻さを増すものもある中、日経新聞の記者であった著者が、民営化時の首相であった中曽根康弘をはじめとする政治家、国鉄職員として民営化をリードした若手職員、日本最大の労働組合として強い影響力を持ちながらも、その闘争戦術の拙さから崩壊の一途を辿った労働組合幹部らなどへのインタビュー、膨大な一次資料に基づき、民営化に至った歴史をまとめた一冊。 読み終えて思うのは、この国鉄民営化という出来事が、経済学的な側面から見れば、当時の先進国がこぞって志向していた「小さな政府」を民営化という形で具現化したものであるのは当然のこととして、国内の政治情勢の観点から見ると、国鉄労組の動員力を背景につけた社会党の勢力を弱め、自民党による「55年体制」を終焉させる(そしてそれとほぼ時を同じくして昭和も終焉する)という中曽根康弘の強い意志に表れであったということである。当時の政治的な権謀術数は、当時官房長官を務めていた後藤田正晴の「情と理」にも詳しく、それと重ねて読むと、その凄まじさと、「かつての日本の内閣は、沖縄返還(佐藤栄作)や国鉄民営化(中曽根康弘)など、ある特定の政治的命題を遂げるのだという強い意志を持っていた」という同士の評をよく理解することができる。
0投稿日: 2017.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ国鉄改革の裏舞台を、政治、国鉄当局、労働組合、それぞれの立場から詳細に記録したもの。 「未完の国鉄改革」「国鉄改革の真実」にも、触れていないことが多く、語られている。
0投稿日: 2017.03.20
