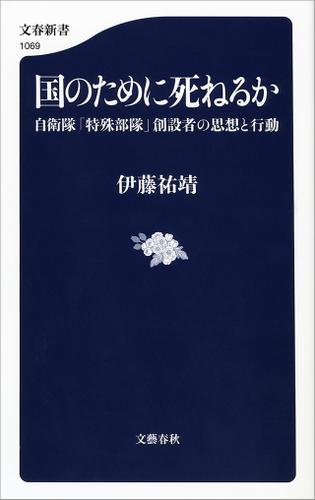
総合評価
(64件)| 14 | ||
| 24 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きることが保障されており、個人としてどう生きるかに目が向いてきた人生だったので,新しい視点をたくさん得られた 国という概念はまるで酸素のようで意識したことなかったが、アイデンティティになっていた潜在意識を呼び起こす名著でした
1投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログおすすめ。 #興味深い #過酷 #考えさせられる #国防 書評 https://naniwoyomu.com/31930/
1投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル的にもっと堅い内容を想像していたが、良い意味で雑な感じ。 国を思う心を正直に吐露したらこうなりました、みたいな本。
0投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ不審船追跡をきっかけに自衛隊の特殊部隊創設に関わった人の本。 練習のための練習ではダメで、本番を想定したトレーニングをしなさい、というのは一般的な事柄にも通用する。 とは言え、明らかに支持にはないような指導を防大生にするのは、気持ちわかるが、ちょっとやり過ぎかなぁと思った。 個人でできることはいっぱいいっぱいには取り組まれた人だと思う。それ以上やるには、組織の上から動かすような政治力いるんだろうなぁ。
0投稿日: 2023.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感する箇所もあれば、しない箇所もあります。 でも、問われているテーマそのものは、今の日本で生きている国民全員が、それぞれの立場で考えなければならないテーマだと思います。
0投稿日: 2023.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
伊藤祐靖著「自衛隊失格」(2018.6)の読後感はよくなかったですが、次に手にしたのが「国のために死ねるか」(2016.7)です。著者は自衛隊とか公務員とかには向いていないと思ってましたが、「はじめに」を読んだだけで同様の感が。バランス感覚の欠如、遵法精神なし、強烈な自己主張・・・。さっと斜め読み。自衛隊へのカンフル剤のつもりでしょうけど。国のため云々より、1人で道を究めてゆく武道家、武術家としての道が合ってると思いました。失礼しました。
0投稿日: 2023.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログラジオ出演した方の著作を読むということが多いが、本書もその一つ。著者は60年代生まれの同世代だが、陸軍中野学校出身の父に育てられた稀有な経歴を持つ。本書を読み進める中、『兵士に聞け』を読み始めたが、自衛隊、自衛官を見る目線はやはり違った。海自特殊部隊創設に携わったが、その完成を見る前に艦船勤務に戻され、退官を決意。「平時と非常時」に対する見解は同感だ。しかし、常に非常時で生きるミンダナオ島での弟子である女性の話は、殺すか殺されるかという極限では野生の本能剥き出しでなければ生きられない悲しさを感じた。
0投稿日: 2021.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
陸上特待生で日体大入学。父は陸軍中野出身。 体育教師が決まっていたが海上自衛隊入隊。 江田島で訓練。防大卒とは違い二等兵から。 1999/3イージス艦で富山へ。不審船発見。 船員と目が合った。自分と同じ仕事していた。 距離50mで威嚇射撃命じられる。その距離だと不審船は沈没。拉致被害者がいたら死んでしまう。 乗船を命じられた隊員は自爆されたら死んでしまうのを承知していた。防弾服がないので漫画週刊誌を体にまいていた。手旗信号係りは夜で見えないのだから行く必要はないのでは?と聞かれた。 海上保安庁の船が近づくと不審船が動き出した。 追いつけず逃してしまう。特殊部隊の必要性を感じた。外国の軍隊にトレーニングへ。あるレベルから機密保持で入れない。米軍に参加。黒人将校と仲良くなる。インディアン兵士から、黒人と一緒にいるのを問われる。黒人は元奴隷。黒人は戦わなかった インディアンは戦って1000万人殺させた。日本は戦って、原爆二発落とされた。なのに黒人と仲良くするのか?
0投稿日: 2021.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログレビュー評価高い書籍。 自衛隊特殊部隊創設時の隊長で、世界で様々なバトルサバイバル術を身に着けていく。 普通の人が知らない世界、筆者の個性が色濃い本。
0投稿日: 2021.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ元々軍隊ものが好きだったが、組織を作った人の作品を読んだのは初めて。 書名がとてもインパクトがあるため、なかなか手に取りづらいかとは思うが、現代日本に生きる概ね高校生くらいからであれば読んでおいて一つの価値判断の基準と出来るのかと思う。 太平洋戦争と言うとよく知りもしないで拒否反応を示す人が多いかとは思うし、自分もまだまだ勉強不足ではあるけれども何故当時の人達があそこまで滅私奉公をし、国に殉ずる事が出来たのか、そして現代の私たちが何故国と言うものに対していまいち「愛国心」を持てていないのかなどが理解できた。 使命感とは何か、について考える一助にもなるだろう。
0投稿日: 2021.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはすごいな。 タイトルがあんまり良くないんだけど。 戦うこととはどういうことか。 生きることとはどういうことか。 軍人はなぜ戦うのか。 国とは何か。 色んなことに著者自身も迷いながら、多分完全な答えはないが、一つ一つの少なくともその場での納得を見せている。 軍が必要悪というなら少なくとも、悪だという自覚を持てと言った、大学時代の後輩がいる。 そんな奴には生涯何に守られているか理解できないだろう。 つか、立憲民主党、これ読め。
0投稿日: 2021.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本で実務の現場を生きてこられた方の本。 拉致されている日本人が運ばれているかもしれない北朝鮮工作船との遭遇。 フィリピンミンダナオ島の女性兵士との話。 伊藤さんのお父様、お祖母様のお話。 太平洋沿岸数カ国の海軍の合同演習での、黒人とネイティブアメリカンとのお話。 有名なアメリカ銃器メーカーの社長とのお話。 韓国とラオスでの日本人のお話。 等々 色々と感じさせられて、考えさせられる内容の本でした。 私は日本のために少しでも優れた兵士になっていこうと思いました。
0投稿日: 2021.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容(「BOOK」データベースより) 新安保法制が施行され、「自衛隊員の戦死」が現実味を帯びてきた。しかし、今の日本という国家に、「死ね」と命じる資格はあるのだろうか。自衛隊でも、もっとも死ぬ確率が高い特殊部隊の創設者が、自分の経験をもとに「国のために死ぬ」ことを、とことん突き詰めて考えた衝撃の手記!
1投稿日: 2021.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日読んだ著者の小説『邦人奪還』がリアル過ぎてある種衝撃を受けたため、本書を手にした次第。 海上自衛隊に特殊部隊を創設した張本人の体験談、自衛隊退職した後のお話、何れも凄すぎるエピソード。センセーショナルなタイトルだけど、帯にあるように右でもなければ左でもない、危険な政治思想とも関係ない。 著者のストイックな思想とそれを実現した生き方が抑えられた文体で語られる。 だからなのか心の奥深くを抉られるような衝撃を今回も受けてしまった。
2投稿日: 2020.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ自衛隊を辞めてからの訓練が激しすぎて、別の世界の出来事としか思えない。 そこでのトレーニングパートナーから発せられた我が国を守ること、国民のあり方についての根本的な疑問に、著者は答えられるのか。 我々も国としての答えを持てるのか。
0投稿日: 2020.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年45冊目。満足度★★★★☆ 本書の感想を一言で表すなら「凄みのある一冊」。「生と死」について考えさせられました。
1投稿日: 2020.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ実は今年の1冊目に読んだのが、この本だった。 めちゃくちゃ過激なタイトルなんだけど、自衛隊の「特殊部隊」創設のことが知りたくて。 帯に「右でも左でもない」ってあるんだけど、私もそうです。と最初に言っておきますw 最近では映画でもドラマでも、警察や自衛隊の「特殊部隊」が普通に登場してくるけど、どんな理由でできたのか、そもそもいつからあったの?って思ってた。 能登半島沖不審船事件をきっかけに、海上自衛隊に設立された「特別警備隊」。 冒頭は不審船事件の模様が、その現場にいた筆者の目線で描かれていて、その臨場感たるやいきなりクライマックスのよう。 手に汗握り心震わせながらページをめくった。 その時その場所にその人がいてくれてよかった。 その後、「特殊部隊」創設にあたっては、いろいろなしがらみもあり、紆余曲折がある。どこにでもそれはあるのだが、レベルがちがうんだろうなと思う。 後半は著者の自衛隊を退役してからのお話。 この方は本当にストイックだし、信念をもって生きているのだなって思う。 ~作品紹介・あらすじ~ これは愛国心か、それとも危険思想か――。 自衛隊初の特殊部隊、海上自衛隊「特別警備隊」の創設者が語る「国のために死ぬ」ことの意味。 新安保法制が施行され、自衛官の「戦死」が現実味を帯びてきた。とくに特殊部隊員は明日にでも国のために死ななくてはならない。 だから、「他国とのお付き合い」で戦争するなんてまっぴら御免。 この国には命を捧げる価値があってほしい。 死と背中合わせで生きてきた男の誓いと祈りがここにある。 彼らは命令があれば命をもかける。 命令をするのは国である。 国とは、私たち国民ひとりひとりのはずなのだ。 「なぜ先祖が子孫のために残した掟を捨てて、他人が作った掟を大切にしているの?」 日本人ではない弟子の言葉が響いた。
1投稿日: 2019.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は元自衛官で民間の軍事関連アドバイザー 多少バイアス(盛っている?)はあるものの、自衛隊の状況や、世界の中でみた軍事面での日本の状況が伺えて興味深い
0投稿日: 2019.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ平和な国に暮らす一般市民が持ち合わせないような経験や感覚が語られており、一読に値すると思う 日本という国家そのものの意志や方向性はどうなっているのか、国民の意識にも一石を投じる主張であるが、これはプーチン大統領をはじめ、国内外の各方面から指摘されている内容だと感じた。 あらゆる暴力が否定され、電子化された情報で瞬く間に拡散・共有される今の時代には、ミンダナオの戦士は古典的な騎士道に近いものを感じたが、世の中で一国だけが平和憲法をうたったところで世界平和が訪れるわけでないのは人類の低俗性を象徴しているかもしれない ただ筆者のような人物がいなければ国も民族も消え去ってしまうこともあるだろうし、尊敬されるべきだと思う
1投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ弟子のラレインが海底60メートルで拾ったのは額入りの「国民精神作興ニ関スル詔書」であった。。「関東大震災などによる社会的な混乱を鎮(しず)めるために大正天皇が発したもの」と書かれているが、社会的な混乱とは「民本主義や社会主義などの思想」を指す(小学館 日本大百科全書〈ニッポニカ〉)。 https://sessendo.blogspot.com/2019/01/blog-post_28.html
1投稿日: 2019.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書っぽくない内容。この人の考えに共感できる部分は少ないが、一人の男の生き様を書いた本としては興味深く読んだ。自衛隊に対する考え方もすこし改めなければならないだろう。
0投稿日: 2019.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は自衛隊の組織の話で、そういうのに興味のない私は少々退屈だったけど、後半はおもしろかった! 自分やその仲間たちを守るために戦うということがどういうことなのか、本気で考えてきた人だから非常に説得力がる。 日本がいかに自立していないかがよくわかった。 改憲を望む立場の人たちの気持ちもわかった。
0投稿日: 2019.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ任務として「死を覚悟する」驚きを隠せないがよく考えると軍人の覚悟として必須 われわれは平和憲法ぼけしてしまっていて、自分の国家を守る意識すら失っている 現世利益の最大化に品性が堕してしまい、国家の勢いを失いつつある 根本の理念の構築が不可欠という指摘はその通り 問題はいかに達成するか 安倍政権の愛国心は頷けるが、利益誘導はあってはいけなかった 利権屋に墜ちる 愛国心は国家を形成する人間社会に不可欠なもの 戦後忌み嫌われているが再構築が必要 そのためには民主主義社会が確立していなければならない 天皇への愛国心から卒業 愛国心があり、国家意志のもと、死をも辞さぬ兵士を必要とするのが国家 公務と軍務の決定的な違い 部下を死地へ送る決断を背負う指揮官の責務は重い 「統御」をもっとシンプルに素直に受け止めるべき⇒「覚悟」だと思う 2-1 特殊部隊創設 海軍と陸軍の違い (1)意思疎通の手法 通信システム 任務分析(権限委譲) (2)意思決定のシステム 艦長ただ一人 一人ひとりの自己判断で引き金 特殊部隊は陸軍型 全体情報に関心を持ち、各々が判断して戦闘する 教育 難しいことをいかに簡単に理解させるか 3-1 戦いの本質 実践的であれ 訓練はともすれば形式を重視される 平時の思考 戦時の思考・判断・行動とは距離がある ex頑張っていることが評価される 4-1 この国のかたち 「群のために自ら犠牲になる覚悟の個体が存在する」 情があっても、その時には対応できる ⇒この国にそれだけの価値があって欲しい 自分の命を捧げるに値する、崇高な理想を目指す国家であって欲しい
1投稿日: 2018.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ海上自衛隊の特殊部隊である特別警備隊の創設にかかわった元自衛官の自伝的な本。 続きはこちら↓ https://flying-bookjunkie.blogspot.com/2018/08/blog-post_9.html Amazon↓ https://amzn.to/2OqGcnd
1投稿日: 2018.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自衛隊特殊部隊を創設し、海外での実践もあるとのことで、気構えや考え方などなるほどと思うところが多々ありいの、でも文書は変な誇張や脚色がなく、タイトな感じで読みやすい。平成の葉隠とレビューしてる人がいたが言い得て妙です。
1投稿日: 2018.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織を守るのは本能。そういう本能を持った人がいる。 天皇はエンペラーではなく、部族長だった。 日本民族は変わったのか?変わったのだとしたら、それはなぜ?どのように? といった筆者の心情が書いてある。 エピソードが全部ぶっ飛んでいて全然共感できる内容ではないが、すごい人もいるもんだと思って読んだ。 国家というものがもつ最後の手段としての暴力を、その最前線で犠牲になる人がどう見ているのか、というのの一端が垣間見れた。
1投稿日: 2018.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ一気に読了。自衛隊ではないが、似たような組織に身を置く者にとって、同感できる点多数。どんな組織も多かれ少なかれこんなもんなのだろう。その中で、自分がどのようにふるまうべきか考えさせられた。国家も個人も、譲れない矜持というものは大切なのだろう。
1投稿日: 2018.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ●→本文引用 ●普通の人生観を持つ者でも突入だけならできるが、特別な人生観の持ち主でなければ、その任務を完遂することはできない。特殊部隊員に必要なのは、覚悟でも犠牲的精神でもない。任務完遂に己の命より大切なものを感じ、そこに喜びを見いだせる人生観だ。 ●私に欠落していたのは、リアリズムの追及であった。(略)いつの間にか、実際に遭遇する環境よりも、訓練しやすい環境を優先していた。無意識のうちにである。(略)実戦経験の有無によるものではないかと言う人もいるがあまり関係ないと思う。(略)経験があるというだけで自然にリアリズムを追求できるわけではないし、経験がなくても、周到な準備をすればできないことではない。(略)要は訓練への向き合い方の問題なのである。 ●戦いとは、戦闘能力の競技会ではない。(略)自分が能力を発揮できる環境ではなく、自分も発揮しにくいが、相手がさらに発揮しにくい環境を創出すべきなのである。なぜなら、相手の方が戦闘能力が高くとも、それを発揮しづらい状況に引きずり込んでしまえば勝てるからだ。
0投稿日: 2018.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ元自衛官の自伝。 体育教師予定から自衛隊幹部になり、特殊部隊創設に関わった後、退役しフィリピンへ。 かなり熱い方なのだろうと思われます。 本番を想定した訓練の難しさを感じました。
1投稿日: 2017.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ能登沖に北朝鮮の不審船が現れ、当時海上自衛官である、後に自衛隊初の特殊部隊を創設する事になった方の著書。 読んでいると、この国に対してまた考え直すきっかけになった本であった。 今の日本は命を賭けてでも守るべき国なのか、他国に決められた憲法を未だに守り続けている国。 ぜひ若い世代に読んで欲しい本
1投稿日: 2017.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ平成11年3月におきた能登半島沖不審船事件。北朝鮮の不審船による日本領海侵犯事件だが、なぜか、というより当然のように詳細は報道されていない。その時現場はどうなっていたのか。 当時、不審船を発見・追尾したイージス艦みょうこうの航海長であった著者が振り返る。 船には拉致された日本人がいると思われていた。 しかしみょうこうとともに不審船を追っていた海上保安庁巡視船は、なんと残存燃料に不安ありと途中「ありがとうございました」と言い残して引き返していった。 残されたのは工作船に乗り込み立入検査する権利のない自衛官だけ。 初の海上警備行動が発令し、立入検査を自衛官が行えるようになったが、誰も停止した不審船への立入検査のやり方を知らなかった。 しかも、不審船に乗り込む下士官が持つのは触ったことも撃ったことすらもない拳銃。 防弾ベストは装備になく、代替のように少年週刊誌をガムテープで胴体に巻き付ける始末。不審船は重火器で武装し、必ず自爆装置を備えている。 検査隊員たちは、不審船に立ち入った瞬間、全滅確実だったのだ。 開いた口が塞がらない、の一言に尽きる。これが国防の最前線での話である。日本という国の状況が凝縮されたエピソードだ。 しかし本書のテーマはもっと別のところにあるので、ぜひ手に取って一度読んでみていただきたい。 「国のために死ねるか」というこのタイトルの裏には、おそらく『この国は命を懸けて守るに値するか』『命を懸けて守るに値する国民か』という、有事の際には国と国民を守るために戦わなければならない、真摯に働く自衛官たちの問いと、国の在り方、国民の在り方に対するわたしたち、「平和主義」という言葉を、そこに含まれる本当の意味も知らずに使っている人々への問いが存在している。
1投稿日: 2017.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル買いしちゃったんだけどね、この本。どこかで見た名前だなと 思ったら、2012年8月19日の日本人活動家尖閣諸島上陸事件の時に、 魚釣島に日の丸を掲げた人だったわ。 元々は海上自衛官であり、自衛隊初の特殊部隊である海上自衛隊の 特別警備隊発足に係わっている。 意に沿わぬ異動命令をよしとせずに、退官後にはフィリピン・ミンダナオ 島に渡り、実戦的な格闘訓練を積み、現在は現役の警察官や自衛隊員 を指導する私塾を開いている特異な経歴の持ち主である。 冒頭の1999年の能登半島沖不審船事件の記述から既に映画のような ストーリーである。この事件をきっかけに著者は特殊部隊の必要性を 実感するのだけれど、どうもしょぱなから違和感を持ってしまったのだ。 著者の考え方に大きな影響を及ぼしたのは彼の父親の存在である。 陸軍中野学校で蒋介石暗殺を命じられ、戦後になっても「命令は解かれ ていない」として射撃訓練を続けた人物。 子供の頃は父の話が分からなかったという著者だが、確実にその影響は 受けていると思うんだ。特にミンダナオ島でのトレーニング・パートナーで あった女性との会話の中で彼女が日本国憲法を「他から押し付けられた 掟」と言った時に、きちんと反論できていないのだもの。 著者は自身の価値観をきっちりと持っている人なのだと思う。それを貫こう との姿勢には共感は出来るのだが、結局のところ、突き詰めて行くと憲法 改正をして、自衛隊を軍隊としたいと思っているのではないのかな。 現行の日本国憲法が他から押し付けられた掟だというのであれば、自衛 隊だってアメリカの希望で誕生したものなんだけれどね。 警察や海上保安庁同様に、自衛隊も私は感謝をしている。それは主に、 大災害が発生した時の自衛隊の機動力に対してである。だから、今まで と同じように自衛隊員に戦場で命を落とすような事態にないって欲しくない し、他国の人に銃を向けて欲しくはない。 「君達は自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく 自衛隊を終わるかもしれない。 きっと非難とか叱咤ばかりの一生かもしれ ない。御苦労だと思う。 しかし自衛隊が国民から歓迎されちやほやされる事態とは、 外国から攻 撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し国家が混 乱に直面している時だけなのだ。 言葉を換えれば、君達が日陰者である時のほうが、国民や日本は幸せな のだ。 どうか、耐えてもらいたい。」 防衛大学の第1回卒業式で、時の首相・吉田茂は式辞でこう述べた。比べ てみて欲しい。先の国会での所信表明演説で安倍晋三は海上保安庁、警 察、自衛隊を称えて拍手を促した。 本書を読んでいて、安倍晋三の所信表明演説に通じる危うさを感じたのは 私の考え過ぎなのだろうか。 生まれ育った国だから守りたい。それは私も思う。でも、「国のために死ね るか」と問われたら、そこには大きな疑問点がついちゃうんだけどね。 タイトルで勘違いしちゃんただよな。自衛隊出身であるからこそ、隊員を死と 隣り合わせの場所へ送り込みたくはないというお話かと思ったんだ。失敗。
0投稿日: 2017.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ元特殊部隊自衛官の方が愛国心、憲法論などについて かたい感じで語られた本なのかと思って読み始めたが ハードボイルド小説みたいなところもあって読みやすい。 自衛隊は命を懸けた仕事なんだと改めて感じました。 ミンダナオ島でのラレインとのやり取りがもっと詳しく 書かれてました。 おすすめ↓ http://www.yobieki-br.jp/opinion/sukeyasu/Mindanao1.html
1投稿日: 2017.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログすごくおもしろかった。読んでて夢中になりました。 伊藤さんの思想にはとても共感するけれど、「右でもなければ、左でもない」と帯にもあるように、その思想や信条を読む人に押し付けていないのがいい。 多くの人に読んでほしいですね。
1投稿日: 2017.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ元海上自衛隊の自衛官で、特殊部隊の創設チームだった、伊藤氏による硬派な本。著者は、目の前で北朝鮮の不審船に何もできなかった後悔から、また心の準備ができていない自衛隊員に命の危険を冒させることへの疑問から、非常時の戦闘を目的とした特殊部隊を海上自衛隊の中に作ろうとした。 理路整然と書いてあるので、一般人にもわかりやすい。自衛隊という特殊な組織の強みや弱みも見つめている。 自分の命と引き換えにしても守りたいものがある。それが日本という国である人が特殊部隊の隊員である。死にたいわけではない。著者は、日本という国が、命を懸けて守に値する国であってほしいと願っている。「国のために死ねるか」というタイトルは彼が答えを追い求める、人生をかけた問いである。 自衛隊に入る人は正義感が強いだけでなく、純粋で、筋を通すことを好む人たちだと思った。著者は、特殊部隊員はたまたまそういう資質を持って生まれただけなので感謝する必要はないというが、一般の日本人は、こういう人たちに日々の安全を守られているのだと感じた。
1投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1999年の能登沖不審船事件をきっかけに創設された自衛隊初めての特殊部隊「特別警備隊」の先任小隊長として、足掛け8年にわたって部隊を率い、国防のまさに最前線にいた筆者が、「国のために死ぬこと」の意味をとことん突きつめた一冊。 なかなかに衝撃的かつ大胆な本です。日本の防衛最前線にいた筆者の迷いや信念が伝わってきて、生半可な気持ちで見て見ぬふりをする自分を含めた日本人って情けないなと思う。第9条云々が話題となっている近年ですが、現実を目の前にしてどれだけ本気で国を愛している国民がいるのだろう、と考えさせられる。ラレインという女性の話、生き方は自分が生涯出会うことのないものでひたすらすごいなとしか言えない。どれだけのんきに自分が生きているか、そしてそれは誰かの覚悟や思いで成り立つ平和であることを心に刻む。
1投稿日: 2017.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人は平和ボケしていると言われている昨今、著者のような危機感を持つ人は希有だろう。 彼の言う事はある意味正論ではあるだろうし、理解はしたいと思うが、共感までは難しい。
0投稿日: 2017.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本初の自衛隊特殊部隊の創立メンバーである伊藤祐靖氏の著書。 特殊部隊創立のきっかけとなったのは、1999年に起きた北朝鮮による能登半島沖不審船事件なのである。なんとなく大昔から自衛隊には特殊部隊があるものだと、勝手に勘違いしていた自分には少し意外だった。作品の中では、伊藤氏が創立メンバーとして経験した厳しい訓練の様子や、退官後に渡航したミンダナオ島でのエピソードなどが紹介されている。 伊藤氏によると特殊部隊の隊員になるためには、生まれ持った資質のようなものが必要なのだそうだ。体が丈夫なのはもちろんだが、その資質とは相手の心情を察する能力であり、いざという時には自分が犠牲になるという、伊藤氏の言葉を借りれば「特異な本能」なのである。 自分には特異な本能もなく全く別世界のお話しなのだが、せめて特殊部隊の隊員が命を賭して助けるにふさわしい人間でありたいなと思った。
1投稿日: 2017.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ能登半島沖不審船事案をきっかけに創設された特警隊。その創設者の一人による、普通に生きている私たちにとってはあまりにも壮絶な問いかけ。 冒頭が、不審船を追跡するみょうこうの場面から始まって、最初からクライマックス状態。読み物として非常に面白い。著者のお父さんの話とか、ミンダナオ島で出会った弟子の話なんかはフィクション入りまくってる気はするが、いちから特殊部隊作っちゃう人のことだから、本当のところはわからないね。 憲法がどうとか、思想的な話も若干無いではないが、この本の本質は、自分が理想とする生き方をどんな代償を払っても貫きたいか、という、右とか左とかとは無関係の、人間の生き方についての問いかけである。 自分自身、公共心が高い人種とは思わないが、それでも多くの人が小さく憧れのように持っている「人の役に立ちたい」という気持ちを、偽善と貶す訳でもなく、偉いと褒めるわけでもなく、そういうものだと肯定してくれる本にあまり出会ったことがなかったので、とても新鮮だったし、この部分はすっと心に入ってきた。
1投稿日: 2017.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段なら手に取らないハードなタイトル・・・僕は死ねま千円。普段知らない世界を垣間見れて結構面白かった。
0投稿日: 2017.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ命を賭してでも、やり抜かなければならないことがある。守り抜かなければならないことがある。確かにあるはずだと思う。そのためには高尚な理念が必要だ。全くその通りだと思った。でも何を守るのだ? 私はただの技術者だが、絶対に譲れないことはなんだ?そのために命を賭して立ち向かっているのか?そう問われている気がした。 今の日本は守り抜かなければならないものなのか?確かに日本は守っていく必要があると思うが、もっと広い視点で守っていくべきものがあるような気がした。
1投稿日: 2017.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ北朝鮮による能登半島沖不審船事件を契機として、海上自衛隊に設立された「特別警備隊」。この設立に一自衛官として関わった著者が、不審船事件の生々しい模様や、「特別警備隊」の激しい訓練の様子を題材としながら、「論理を超えた世界で、生命を賭す」ということが、どのようなことかを伝える。 もちろん、本書の冒頭に描かれる不審船事件のドキュメントや、自衛官の職を辞した後にミンダナオ島で20歳そこそこの女性海洋民族と常軌を逸したようにも見える激しいトレーニングを繰り広げるさまなどは、読み物として息を付かせぬ勢いでこちらに迫ってきて、大変面白い。 その面白さとは別に、「特別警備隊」の隊員たちが自らの生命を賭して任務にあたる様子からは、我々の日常的な生活には存在しないような論理を超えた深淵が見える。自衛隊という存在に対して、政治的な評価はカッコに入れた上で、この深淵の一端に書籍を通して触れられるのは貴重な体験のように思える。
2投稿日: 2017.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、富山沖のシーンは臨場感あふれて当事者のみにしか書けない心情がとてもよく書かれていたのだけど、進むに従い感動は薄れていった。オレ感が強すぎるというか… 粉骨砕身して創設した特殊部隊の成果が書かれてないので、結局意義があったのかが分からない。 ラレインの強烈な生存競争への執着は何から来てたんだろうか?出自なのかな。 命を懸けて守ろうとしている「国」には価値を持っていてほしい、という気持ちには全く同感です。
1投稿日: 2017.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログとても熱い人が真剣に考えを吐露した本で、生ぬるい自分の気持ちが引き締まる思いと、もっと広い視野或いは別の視点があってもいいのではないか、との両方の感想を持った。 作者は、陸軍中野学校出身の父親の影響をいつのまにか受けて海自に入り、やがて北朝鮮不審船事件に現場で遭遇することで本物の戦闘を知り、特殊部隊創設、自衛隊退職後のフィリピンでの訓練などを通し、自分の生命を賭して国を守ることを考えてきた。 頭で考えた理屈ではなく、生死の境を見るような訓練や現場を通しての思想なので、実に厳しい。しかし、そこには本当に国や国民を想う心があるので、説得力が増す。学者や評論家の意見ばかりではなく、時には本書のような現場を知る人の考えも聞くべきであると思う。
2投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 私も知らなかった……不審船事件を目の当たりにし、これをきっかけに自衛隊特殊部隊の創設に関わった著者による、「闘争とは何か」さらには「日本という国は何か」を問う本。 著者の父を通して、太平洋戦争中の”軍人/兵士”が何を考えていたのか――を垣間見、ミンダナオ島の女性から闘争の本質を見る。 己の身体の一部を犠牲にしてでも、確実に相手を殺す―― どんな大義名分も無い。純粋に「生か 死か」の二択に研ぎ澄まされた世界だった。 日本の戦後反省や戦争論――国家間など様々な利害の駆け引き――はこの本には無い。ただ、戦うと決めた人間たちが、どう行動するのかを、著者の経験からひも解いていく。 日本の自衛隊についても言及。 陸・海・空の発想の違いなど。 米軍とも比較し、彼らは、‘兵員の業務を分割し、個人の負担を小さくして、それをシステマティックに動かすことで強大な力を作り出す仕組み’と、的確で詳しい。 そのうえで、自衛隊には質の高い人間が揃っている事を伺わせるが、実際の戦闘になったとき、臨機応変さに欠ける――マニュアル化しているため――ような事を仄めかしている。 日本は戦争をする気がないと考えるのは、短絡的かもしれない。 少数精鋭の傾向のある自衛隊は、有事の時に犠牲を抑えて戦えるのか? ともすれば、再び”カミカゼ”をしてしまうのか、それは真に勝利へ結びつくのか―― しかし、この本を読み進めていくと、覚悟を持った人たちに、この疑問は無意味なのかもしれない。 本の後半、情についての言及もあったが、情が覚悟を邪魔することは一切なかったという。
1投稿日: 2016.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自衛隊に存在しなかった特殊部隊設立に関わった著者の、その原動力となった事件。 拳銃も撃ったことのない隊員を、北朝鮮の工作船に乗り込ませなければならないという場面。 大変緊迫感がある。 だがその緊迫感は長くは続かない。防衛省は、「頑張った」ということで評価を受けようとする役所らしい。特殊部隊創設中に著者も異動になってしまい、退職する。 僕は国のために死にたくないし、著者も、この国に生命を賭して守るものがあるのか、その答を出せていないが、それでも守りたいし、守るに値するような国であって欲しいと語る。 いやあ別世界だなあ〜。 国のために死ねるか、というのは普遍的なテーマだと思っていた。「日本」が強調されると話がおかしくなるのでは、と。けれど、やはり特殊部隊がなかった自衛隊、というところがスタートなので、日本の話になっちゃうのだ。ただ他国のこともよく知らないし、この本だけ読んでも、結局のところ僕には何もわからない。水中格闘の話なんかも出てきて、面白いには面白いが…とここまで書いて、サブタイトルに目が止まった。「自衛隊特殊部隊創設者の思想と行動」。ああ、それなら理解した。こっちがメインだ。
0投稿日: 2016.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
海上自衛隊の特殊部隊設立の経緯、その後の筆者の海外での訓練生活を踏まえた日本への考えがつづられた1冊。 格闘訓練や避難訓練の箇所を読み、平時に非常時をシミュレーションしていないことにハッとさせられる。
0投稿日: 2016.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ元自衛隊の猛者が語る本当に国家と公のあり方とはという話し。8割は著者の経験談で、暗殺者だった父の訓練、自衛隊に入隊し、北朝鮮の拉致の現場と遭遇し、特殊部隊を創設に走る、自衛隊の組織と自分の国家認識への疑問を感じミンダナオ島で自活する、という普通じゃない人生とサバイバルを語り、最後に(これが言いたかったであろう)日本という国は借り物の憲法のもとではあるが必死に経済成長をさせてきた。じゃあそこからどうする?という問いかけをする。
1投稿日: 2016.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルからするとかなり右に振り切れていそうな感じを受けるが、読んでみるとそこまでではなく、どちらかといえば筆者の思想について非常に落ち着いた筆致で描かれている。 序盤二章は、自衛隊での経験や自衛隊初の特殊部隊創設に至るまでの過程を、自分の思いや出会いを絡めながら語っている。 陸と海の思想の違いや、自衛隊の特殊性など、経験した方でないと書けない話が非常に興味深い。 後半二章は、話としてどこまで真実かは置いといて、いろいろと考えさせられるエピソードが多かった。 敵との戦い方(どこまで自分の体をさらせるのか)ということや、日米の関係、そして戦争相手のアメリカに従属する日本人への黒人とネイティブアメリカンの思いなど。 また、自衛隊員となり「国のため」に働くことからスタートした筆者の思いが、幾多の経験を経て、日本人とは何なのか、この国は本当に守るべき国なのか、迷った末にもう一度「国のため」に動く(ただし、迷いを抱えつつ)ことにする最後がとても心打たれた。
1投稿日: 2016.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
海上自衛隊に存在する特殊部隊を設立した方の本。どのような経緯で特殊部隊が設立され、その設立に携わったかが、中の人ならではの視点から書かれている。 …のと著者のなかなか香ばしい軍人っぷりが読んでいてときに胸が熱くなり、ときに吹き出してしまう。 まず北朝鮮の不審船を発見し追跡するあたりからもうこの人は完全な軍人なんだなぁと思わせる。帰投しようとする海上保安庁に対して「逃げるくらいなら自決しろ!もしくは本艦を沈めてくださいといえ!」ってあたりもう面白すぎるし「大丈夫かよオイ…」と変に不安になる。面白いけど。 そもそも自衛隊のことを「軍隊」といって憚らない。海自に入隊するときも「海軍に行きます」だもん。そして退役後はガチの海外に行って戦い方を学びなおす毎日。熱いです。でも不安になります。 でも実際本当に国を守るために死ねる、、つまり本書に出てくる「死ぬのはまぁ仕方ないが任務はどうやって完遂するかなぁ」と考えられる人間がいないと多分戦争って勝てなくってこの人を始め一般常識から見るとあっぶねぇなぁと思っちゃう人たちのお陰で今日もカタカタ本の感想なんかかけているのかなぁと思ったりしました。
1投稿日: 2016.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすく、分かりやすいリアルスパイもの。こういう人に自衛隊員やってほしいが、そうとばかりも言えないのよね…組織内の軋轢なんかについても描いて欲しかった
1投稿日: 2016.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ1993年日本海で北朝鮮の不審船と自衛隊イージス艦「みょうこう」とが遭遇した時、艦橋に航海長として任務に就いていた著者が自衛隊や、軍事行動の本質について述べる本。タイトルからはちょっと過激な思想の本かという印象を受けますが、それはいい意味で完全に裏切られます。 自衛隊は軍隊ではないとか、スーダンは戦地ではないとか、建前論に終始する政治家の言葉とは異なり、自衛隊や軍事行動の本質を単刀直入に切り込みます。著者が自衛隊は戦闘行動を目的とした組織である事を認めた上で述べる次の一文は建前論ではなく、すっと腑に落ちました。「軍事行動とはあらゆる解決策を模索し、懸命に和解を企図したにも関わらず、万策尽きてなお、国家としてどうしても譲れないと判断した事柄についてのみ発動されるもの。どんなに美しい言葉で飾ったところで、国家がその権力を発動し国民たる自衛官に殺害を命じ、同時に殺害されることをも許容させる行為。ゆえに権力発動の理由が『他国とのおつきあい』や『〇〇大統領に言われたから』などというものであってはならず、日本の国家理念に基づくものでなければならない」 部下の隊員の命を預かる幹部自衛官の心得を垣間見ることができる本でした。 冒頭に触れた北朝鮮不審船事件の際の艦橋内における緊迫のやり取りを収録した本書前半部も読み応え十分です。
3投稿日: 2016.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
米軍 兵員の業務を分割し個人能力に頼らずシステマティクに動かす。交代要員を量産できる。 特殊部隊 不平不満を感じても、その場で何とかする。 任務分析 通信ができないときの意思疎通の手段。 上級指揮官の存在意義 それは戦闘前にある。 始まってしまったら現場指揮官に専念させる環境を整えるのが仕事。 戦争 各国の底辺と底辺が勝負するようなもの。 エース同士の戦いではない。 最高の軍隊 アメリカの将軍、ドイツの将校、日本の下士官。 自分の何を失ってでもやる価値があるか? 成功の確実性が変わらずに自分のダメージがより少ない方法を模索する。 アメリカ人 おなかいっぱいになっても、食べるのをやめない。 日本人 空腹時は凄いが、ちょっと満ち足りるとやめてしまう。 日本人の危うい行動美学 我慢の限界を超え堪忍袋の緒が切れたときの感情的な敵対行動。
1投稿日: 2016.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ文春新書のデザインのせいもあって、このタイトルがよりキツく迫ってくる感じがしますね(笑 センセーショナルなタイトルですが、別にイデオロギー的なイロモノ本ではなく、著者の経験を元にちゃんとパッケージングしたらまぁこうなるか、という感じです。読めばわかるんだけど、タイトルで敬遠する人はいるかも。 とっても良い本でした。 事前に想像していた流れは、自衛隊的なエピソードが並んだ後に、今の日本人はだらしない!的な展開で、一方的に扇動されるかなと思ってたらさにあらず。 序盤は確かに自衛隊のエピソードで、圧倒的なスピード感に引き込まれて感情的にも高ぶったものの予想通り。でも、そこから先の広がりは予想外で、お父さんのエピソードも効果的に作用してる印象。ミンダナオ以降はゾッとするほどエッジが立ってて、日本人論的なくだりも刺さりました。(経験と自覚があるだけに。。 色々面白かったくだりはあるのですが、絞るなら、優先順位と絞り込みのくだり、常識を捨てる話、そして、日本人の「3回目には皆殺し」のくだりと、感情を押し殺さないこと。 あとがきもメッセージ性があって、なんか一貫してるなぁという印象。敢えて避けずに通ったのは素晴らしいのでは。
1投稿日: 2016.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本、思考方法以前に思想で受け付けられない人もたくさんいるのでは? 第一優先以外を捨てられると、ある意味生きやすそう…
0投稿日: 2016.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ真剣に戦うことを考えてた人の話で、全部に頷けるかは別として面白い。 戦闘にあたっての陸海の文化の違い(ビークルかインディビジュアルか)、レンジャーでの経験、ミンダナオ島での生活、防大での指導経験にあった非常時においての常識に囚われた判断の弊害など、改めて戦闘に全ての基準を置くことの重要性を感じた。
1投稿日: 2016.09.14不審船は止まっちまった、そこへお前は「ですよね」で行ってしまうのか
ほぼ同年代ながら価値観にだいぶ差がある。それでも読んで損はない。非武装平和主義で自衛隊を認めない人にとってもそうだと思う。 1999年3月自衛隊の最新鋭イージス鑑「みょうこう」は北朝鮮の不審船を発見した。追いついた海上保安庁の巡視船はパラパラと上空に向けて威嚇にならない威嚇射撃をした後帰投する燃料に不安があると引き上げて行った。逃げる不審船に対しみょうこうは127ミリ炸裂砲弾を着弾点を近づけながら威嚇射撃を繰り返し前方50mで船橋窓ガラスが吹き飛んだがそれでも船は止まらない。船を飛び越えて100m先の弾着でようやく船が止まる。 「止まっちまった」拉致された日本人を発見したら、是が非でも救出しなければならない。だが、無理だ。なぜなら、1回も訓練をしたことがない。防弾チョッキもなく、立入検査隊員達は拳銃を握ったこともない。船が自爆すれば隊員達は全滅する。闇夜の中で行く意味が有るのか尋ねる手旗要員に航海長だった伊藤氏が答える。「つべこべ言うな。今、日本は国家としての意思を示そうとしている。あの船には、拉致された日本人のいる可能性がある。国家はその人たちを何が何でも取り返そうとしている。だから、我々が行く。国家がその意思を発揮する時、誰かが犠牲にならなければならないのなら、それは我々がやることになっている。その時のために自衛官の生命は存在する。行って、できることをやれ」「ですよね、そうですよね。わかりました。」これには伊藤氏の方がめんくらってしまう。それでいいのか?私に反論しないのか?お前は、「ですよね」で行ってしまうのか・・・ 彼らを政治家なんぞの命令で行かせたくない。そしてもう一つ「彼らは向いていない」向いている者はほかにいる。世の中には、「まあ、死ぬのはしょうがないとして、いかに任務を達成するか考えよう」と言う者がいる。向いていない者にこの厳しい任務を強いるのは、日本国として、これを最後にしなければならない。これが伊藤氏が特殊部隊の創設に関わるきっかけだった。 伊藤氏が自衛隊に入ったのはバブル前、自衛隊はまともな奴のいくところだとは思われていなかった。確かに防衛大学に入れば学費はいらないとか、夜明けの新宿を歩いていると声をかけて来るのが自衛隊の勧誘だとかそんな話はあった。ではそんな自衛隊の実力はどうか。兵力の比較はよく知られているが組織戦闘力の強弱については「バックに国家があるか」「生命を失う気があるか」で比較されることが多い。よく言われるのは生命を失う覚悟がなく、法的な根拠に弱さがある自衛隊の実力は4段階で下から2番目の弱い方だ。上から順に特殊部隊、自爆テロ、通常の軍隊で一番下は海賊。しかし伊藤氏は日本の特殊性により違うと言う。 日本はトップレベルに特出したものがないが、ボトムのレベルが非常に高い。優秀じゃない人が極端に少ない。モラルのない人がほとんどいない。一般的な傾向として軍隊にはその国の底辺の人材が集まる。だから戦争とは国の底辺通しの戦いなのでボトムのレベルが極めて重要になる。部隊の大多数を占める下士官が優秀な日本は他国の将校からは非常に優秀に写る。アメリカはその逆で下士官はだnめで、特殊部隊の技量も低いと言う。その米軍がが世界最強な理由は兵員の役割を分担して負担を軽くし、システマチックに運用することで交代要員を量産できることだ。 伊藤氏が自衛隊を止めるきっかけが、特殊部隊創立以来の各国とのコネクションを維持し、そこから得る技術や知識を日本で必要とする後輩に伝えるためだった。そのためには身寄りがない場所で「撃てて、潜れて、平和ボケしない緊張感」が必須だった。そこで知り会って弟子の-本当は師匠のような-若い女性にこう言われて窮する。「あなたの国はおかしい」「掟というのはこの土地で本気で生きる者のために、この土地で本気で生きた祖先が残してくれたもの」「あなたの国の掟は誰が作ったの」「他人が作った掟に従って生きていくような者がこの土地に生きることを、誰も絶対に許しはしないわ。12時間以内にあなたは生き物じゃなくなるわよ」殺害予告だ。「祖先の残してくれた掟を捨てて、他人が作った掟を大事にするような人を、あなたは、なぜ助けたいの?そんな人たちが住んでいる国の何がいいの?ここで生きればいいじゃない。」 守る価値のある国であって欲しいと言うのが伊藤氏の願いだが、価値観は人それぞれだ。昔から日本は掟や言葉を海外から取り入れて来た。押し付けられた掟だろうが残るものは残り、なくなるものは何れなくなるだろうよ。
2投稿日: 2016.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の同僚の方のお薦めで、お借りして読んでみました。 著者の伊藤祐靖氏は元海自特殊部隊の小隊長。自らの実体験を踏まえての記述は、その主義主張の立ち位置如何に関わらずいろいろな面で興味深い内容でした。根っこの考え方の部分では、私として明確に共感しかねるところがあるのですが、それでも著者のメッセージの真剣さは十分伝わってきます。 予想外に面白い気付きをたくさん得ることができる面白い本でしたね。
1投稿日: 2016.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ海上自衛隊創設者の日本への強烈なメッセージ。「なぜ先祖が子孫のために残した掟を捨てて、他人が作った掟を大切にしているのか?」この問いに答えられる奴はいるのか?
2投稿日: 2016.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ特殊部隊創設者によるエッセイ。なぜ特殊部隊が必要だったか、どのような考えをもって立ち上げたのかがよくわかる。筆者の自衛隊の評価も問題点も、率直に語っており、強烈な軍国主義者ではなさそうである。そして、ミンダナオでの修行が強烈だ。常に実戦を意識している海洋民族の弟子と死ぬ寸前まで訓練をする。軍人とは何か、を考えるうえで非常に参考になる一冊だ。
2投稿日: 2016.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルや帯の内容からは国粋主義的な偏った内容の展開かと思ったが、そういう単純な思想の左右の話ではなく、一般人向けに書かれた軍務に携わる人間の世界のリアリティから読者に考えさせるテーマを投げかけてくる、そういう凄みのあるものであった。あまりなじみのない自衛隊について、様々な見方ができ、勉強になった。最近のニュースもまた違った視点で見ることができるかもしれない。
2投稿日: 2016.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ陸軍と海軍の意思疏通の方法の違いが面白かった。 「海軍型意思疎通」 ・・・ 船全体で生死をともにし、船内における意志疎通は比較的簡単、よって船長が判断し、各部署は船長の判断の材料となる情報をあげるに留める。 船長が何を考えているかは、あまり推察しない。言われたことをやる。他の部署の仕事には興味なし。 「陸軍型意思疎通」 ・・・ 作戦が始まってしまえば、隊員同士の意思疎通はほぼ出来ない。 よって隊員は隊長が当初作戦の目的として提示した任務遂行のためには自分は何をすべきか考えて、事態が想定どおり行かない場合でも任務遂行のために自分は何をすべきかを自問し作戦行動に移す。(或いは事前に不測の事態が生じた場合の対策も共有する) 作者は海軍型が、渋谷のハチ公前に何時に集合と指示があった場合、携帯電話をもって行き連絡を取りあい不測の事態に備えるような方式であるのに対して、 陸軍型は、渋谷のハチ公前に何時に集合と指示があった場合もし○○分遅れた場合は、△△に移動し、◇◇まで待つ。それでも会えない場合は、XXに移動し■■まで待つ、と言った具合に予め綿密に行動計画を立てて意志疎通の出来ない状態でも行動することだと言う。
1投稿日: 2016.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ永野修身 戦うも亡国、戦わざるも亡国。戦わずしての亡国は、魂までも喪失する民族永遠の亡国なり。たとえ一旦、亡国となろうとも、最後の一兵まで戦い抜けば、我らの子孫は祖国護持の精神を受け継いで、必ずや再起三起するであろう 日本という国は、何に関してもトップのレベルに特出したものがない。ところが、どういうわけか、ボトムのレベルが他国に比べると非常に高い。優秀な人が多いのではなく、優秀じゃない人が極端に少ないのだ。日本人はモラルが高いと言われるが、それは、モラルの高い人が多いのではなくて、モラルのない人がほとんどいないということである 軍隊にはその国の底辺に近いものが多く集まっている。要するに軍隊はその国の底辺と底辺が勝負するものなのである 現に、自衛隊が他国と共同訓練すると、「なんて優秀な兵隊なんだ。こんな国と戦争したら絶対に負ける」と、毎回必ずいわれる ミンダナオ島 フィリピン南部 フィリピンの1/3 ミンダナオ島だけは、島民の激しい抵抗により植民地化が進まず、古くから定着していたイスラム教が勢力を保ち続けた 自分が大切だと決めたもののために何かを諦める 殺し、殺されながら共存している そのためのルールがある 全部を生き残させようとしたら全滅する 必要以上に殺してしまえば、自分が飢える ドイツの名将ロンメルは、「訓練死のない訓練は、戦死のない戦闘と同じで、芝居と同様である」
2投稿日: 2016.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ【海自特殊部隊創設者が語る「国ために死ぬ」ことの意味的組織論】数々の実戦を経験した海上自衛隊特殊部隊創設者が語る「国のために死ぬ」ことの意味と、「兵士を死なせる」国家への願い。
2投稿日: 2016.07.01
